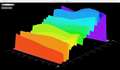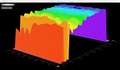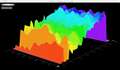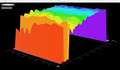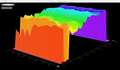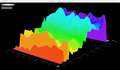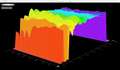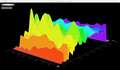SC-LX83
第4世代「ダイレクトエナジーHDアンプ」や「Home Media Gallery」機能などを搭載した7.1ch AVマルチチャンネルアンプ
友人より、この製品を安く譲ってもらい使用していますが、残念なことに電源がストレートにコンセントに刺さっています。
電源タップの購入を考えていますが、このクラスのアンプに見合う、またはおすすめでこれ使ってますとかありましたら教えてもらえないでしょうか?
私の電源タップに対する感覚は、\15000〜25000くらいかなぁと思っています。壁にアース付の3ピンコンセントはあります。
書込番号:13230853
![]() 0点
0点
延長や分配が必要ならば、百円ショップやホームセンターで売っているテーブルタップが良いです。ちょっと高くても良いのならばコンビニという手もあります。
書込番号:13231229
![]() 2点
2点
少し高価になりますが、クリプトンのPB-200がお勧めです。 もう少し安価なものではオヤイデのOCB-1 SXが良いと思います。
私は自作の電源タップ(材料費5万円)を使っています。
良質な電源タップを経由することで、音質は大きく向上します。 5千円のラジカセ並みのオーディオシステムでは効果は感じにくいでしょうけど。
書込番号:13231755
![]() 3点
3点
SC-LX82に、PS Audioのこれ使ってます。
http://www.kanjitsu.com/ps_audio/quintetnew.php
コンビニやホームセンターに売ってるようなものから買い替えました。
違いは分かると思います。
ケーブルはOrtofonのPSC-4500XG Silverを使ってます。
http://www.ortofon.jp/product/cables/index.html
予算に収まらないの紹介してすいません。
書込番号:13232023
![]() 2点
2点
貴方はオカルトが好きですか?
好きなら何十万円でもだして高価なタップを買ってください。
そうでないなら、簡単に手に入れられる範囲で自分が納得のいく値段のものを買いましょう。
物理的に違いはありません。
100歩譲って万が一にも違いがあったとしても、値段と音のよさに因果関係はありません。
書込番号:13235269
![]() 2点
2点
意見ありがとうございます。
たまに仕事でEMC試験やらノイズフィルタやら触れる機会があるためか、電源ラインは綺麗にしておきたいんですよねぇー。
Minerva2000さんのオヤイデか、手ごろなところのオーディオテクニカあたりにしておこうかと思います。
書込番号:13235446
![]() 1点
1点
なんにせよ試すのは悪くないと思います。
私もオーディオタップに興味があったのですが、普通のタップより高額で試せずにいたのです。
そんな時に偶然ジョーシンが特売をやっていまして、オーディオテクニカの5000円程のノイズフィルタータップが500円だったので、二つ買ってしまいました。
オーディオといいましてもオンキヨーで高額な製品ではなかったのですが、聴き疲れがまったくなくなりました。
数時間聴いていられなかったのに、一日聴いていても平気になったのです。
ちなみにPSオーディオのノイズハーベスターも買いましたが、私の環境と耳では変化を感じとれませんでした。
趣味なので後悔はしていませんし、中には変化を感じている人もいるのだろうと考えています。
何もしないで決め付けるよりは試して体験した事が経験になりますし、良い方にも悪い方にも「変化」したり、変化しなぃ事もあります。
良い方に変化する事を祈ります。
長文失礼しました。
書込番号:13235558
![]() 2点
2点
自己満足な世界ですので納得の行くレベルで行きましょう。
書込番号:13235642
![]() 1点
1点
25000円の予算なら、専用回路を引いてもらえば良いのではないでしょうか?
間取り、どの程度までするか(専用の分電盤を付けるのか、既存の分電盤から引くのか)などで工事代は変わってきますが、その予算内で収まるかもしれませんので。
書込番号:13241264
![]() 0点
0点
10キロ先の車のクラクションが聞こえる方には効果があるのかもしれませんね。
オーディオ先輩風吹かしている方ほど、冷静に音を聞けていないのでしょう。
「安いシステムでは違いがわからない」「訓練された私の耳では違いがわかる」
よく耳にするこのような発言、先輩風吹かしている人の特徴ですね。
書込番号:13241418
![]() 3点
3点
電源タップや電源ケーブルで音が変わることは、オーディオ機器やAV機器メーカーの設計者が認めていることです。もちろん、オーディオ評論家やAV機器評論家は全員、音が変わると認めていますね。
彼等が揃いも揃って、10キロ先の車のクラクションが聞こえたり、冷静に音を聞けていないとは考えにくいですね。
逆に、そんなもので音が変わる訳がないと主張されている方は、オーディオにもAVにも全くの素人で、また電源ケーブルも電源タップも自分で買って試したことがこれまで一度も無く、単なる個人的な思い込みで主張されているのが特徴ですね。
書込番号:13243380
![]() 5点
5点
遠くの音が良く聞こえるとかの聴力と、音の善し悪しを聴き分ける能力は一緒ですか?
いつもですが、オカルト説派やオーディオ後輩風を吹かしている人の風力のほうが大きいですよ。
書込番号:13243461
![]() 2点
2点
くろりんくさん
>>遠くの音が良く聞こえるとかの聴力と、音の善し悪しを聴き分ける能力は一緒ですか?
すいません。そんなこと私言っていません。
Minerva2000さん
>>電源タップや電源ケーブルで音が変わることは、オーディオ機器やAV機器メーカーの設計者が認めていることです。
だ か ら
これはオーディオのみを扱っていて大手ではない会社が言っていることです。
これがそもそも問題なのです。あなたが彼らの言う無根拠のキャッチフレーズに洗脳されていると言いたいのです。
評論家の言うことなんて論外。定量的に違いを示した評論家の科学的なデータ、もしくはダブルブラインドテストの結果
示してください。
>>逆に、そんなもので音が変わる訳がないと主張されている方は、オーディオにもAVにも全くの素人で、また電源ケーブルも電源タップも自分で買って試したことがこれまで一度も無く、単なる個人的な思い込みで主張されているのが特徴ですね。
でましたね!先輩風の呪文
私は無知な時代散々試しましたよ。
(型番などは忘れましたが)
とにかく一度ダブルブラインドテストしましょうよ。
否定せずに試しましょうよ。
ちなみに私はケーブル類の肯定派と議論したくコメントしたのではなく、
ここを見たオーディオ初心者が「ケーブルって音変わるんだ」と洗脳されないように、反対意見(事実)を書き込み、そして判断して欲しかった為です。
書込番号:13243992
![]() 1点
1点
>10キロ先の車のクラクションが聞こえる方には効果があるのかもしれませんね。
言ってるじゃないですか?
違うのならこれの意味は?どのコメントに対しての意見ですか?
書込番号:13244010
![]() 2点
2点
くろりんくさん
よく読みましょう
>>遠くの音が良く聞こえるとかの聴力と、音の善し悪しを聴き分ける能力は一緒ですか?
遠くの音が聞こえるとは言いましたが
音の善し悪しウンヌンは言っていませんが。。。
意味は
10キロ先の音が聞こえる超超超人なら
ケーブルの違いを聞き分けられるかも
という意味です。
書込番号:13244022
![]() 1点
1点
>意味は
10キロ先の音が聞こえる超超超人なら
ケーブルの違いを聞き分けられるかも
俺の解釈との違いが判りません。
書込番号:13244033
![]() 1点
1点
Minerva2000 さん、メーカーの設計者や評論家はプロではないですよ。
メーカーの設計者は設計のプロであって音のプロではありません。
それで飯は食っていません。
プロであるなら製品の優劣はわかるはずですが、誰一人として他社の製品の方が優れているとは言いませんよね。
すべてのメーカーがNo.1なんですか?
ありえませんよね?
求めているのは音の良し悪しではなく、メーカーの利益です。
オーディオやAV機器の評論家もプロではありません。この方たちはメーカーの太鼓持ちです。
オーディオやAV機器の自称評論家が、ここがいいとか、あそこが優れているとか褒めるのはよく見ますけど
この製品はまったくもって良くないとか、こことここが駄目だなどと製品を批評しますか?
少なくとも私は見たことがありません。
評論家なら良い点だけでなく、悪い点をきっちり示してほしいものですね。
どうせ主観なんですから。
科学的な根拠がなく、聴感だけの主観で発言している人達なんですから当然プロではありませんね。
個人的な思い込みで強く主張していた人達が評論家になるんです。
プロというなら利益関係無しに、その分野の研究をしている人でしょう。
この人達は、物理的に変わることはないと断言していますね。
Minerva2000 さんは、単なる個人的な思い込みで主張されていますからひょっとして
オーディオ評論家やAV機器評論家なんじゃないですか?
書込番号:13244127
![]() 4点
4点
どうぞ Valentine vs Valensia さんにお聞きください。
私は、自分で考え理解しました。
私の主観による解釈ですのでValentine vs Valensia さんの考えとは違うかもしれませんが、
同じだとは思いませんけど。
書込番号:13244131
![]() 3点
3点
成功への さん への助言として
違うという意見は多いですが、科学的な根拠は一切ございません。
あくまでも主観によるものです。
ただ、AVは自己満足な世界です。
メーカー純正でついてきたじょぼい物では気分が良くないのもわかります。
効果を感じられなかった場合、幾等ぐらいなら納得できるかで決めるのがいいでしょう。
それで、効果を感じ取れる感性なら高額な投資をしても良いと思います。
私は、10年以上前にオヤイデの物を使いましたがまったく違いはわかりませんでした。
アンプが10数万円で、スピーカーも2本セットで10数万円の安物でしたのでわからなかったのかもしれませんけどね。
書込番号:13244138
![]() 2点
2点
ハイエンドの米国製パワーアンプを買った方が、付属されているしょぼい電源ケーブルを見て、さすが米国のハイエンドメーカー、こんなしょぼい電源ケーブルでも良い音が出るという自信を持っているのだな、と感心していました。
実際は、「高級な電源ケーブルを付属してもユーザーは自分の好みの電源ケーブルをつなぐのだから、すぐゴミ箱行きになるものにコストをかけるのは無駄。」としてパソコンショップで3ドルで買える電源ケーブルを、初期動作確認用に付属していたのでした。(笑)
書込番号:13244376
![]() 2点
2点
10年以上前のオヤイデの物って大したことないですね。違いが判らないのも仕方ないです。
書込番号:13244387
![]() 1点
1点
>メーカー純正でついてきたじょぼい物では気分が良くないのもわかります。
もともと電源タップの話なんで、純正ではついてきませんよ。
書込番号:13244496
![]() 1点
1点
>電源コード
何でも良いんです。でもそー言っちゃ オーディオ評論家もマニアも立つ瀬が無いから。個人の自由で良いんじゃないですか。神社のお守り札も、桐箱入りで5万円位ので祈祷をお願いすると、、、家内安全、志望校合格間違い、、ない、、かも、、保証はしないけど。
ちなみに、高級と言われる物ほど、大手に少量発注したOEMだったりする。生産現場を知っているものから見れば、大手の量産品の方が品質管理が行き届いているんだけどね。
OEMだと相手の仕様書の範囲であれば、テキトーな製品が流れたりする。それで偏った音が出るのを良いアジダナァ、、(微笑)
書込番号:13244915
![]() 4点
4点
笑っちゃうよさん
全くその通りだと思います!
Minerva2000 さん
雑誌は本当にいい加減なことばかりですよ。特にこういった中毒性の高い趣味の専門誌ほど。
是非一度ダブルブラインドテストをしてみて下さい。
聴こえる音というのは、音以外の情報(見た目、事前情報など)がとても多く影響を与えている。
それが一瞬にして解りますよ。
☆カローラの親父★さん
そうですね、私も高級ケーブルはお札的な物かと思います。
精神安定剤的なことかもしれませんね。
私は高級ケーブルの全てを否定はしません。
音は違わないですが
ルックス耐久性等を気に入ったら、多少高いお金は払います。
書込番号:13245373
![]() 2点
2点
私は過去に、電源ケーブルでアンプの周波数特性が変わることを客観的に証明する実験を行いました。
これで電源ケーブルによる音の変化が、私の気のせいやプラシーボ効果なのでは無く、実際に変わっていることが客観的に証明されましたので、満足しています。
書込番号:13246116
![]() 2点
2点
Minerva2000さん
どのような計測方法だったでしょうか?
F特、
顕微鏡でみなければわからないような計測結果は意味がないと思います。
そもそもアナログですし、同じシステムでも温度が違ったらそれこそ音変わりますよ。
そのような重箱の隅をつつかず
ダブルブラインドテスト是非実践してください。(かたくなにこれは触れませんね)
書込番号:13246137
![]() 1点
1点
気楽に「ダブルブラインドテストを実践して。」と言われますが、ダブルブラインドテストでは、電源ケーブルを交換した人も何から何に替えたのか分からないようにしなければなりません。手袋をして目隠ししてもまだ不十分です。 ケーブルの重さや曲がりやすさ具合で、何のケーブルか分かってしまう可能性があります。
厳密にやるなら、電源ケーブル交換ロボットを自作してそれを乱数でコントロールして交換させねばなりません。そんなことをする暇も金もありませんし、やる意味も感じないのでやりません。
私の確認方法は下記のとおりです。
テスト日時:2008年8月15日19時〜24時
テスト機材:AVアンプ ヤマハDSP-AX4600
スピーカ ダイヤトーン DS-1000(27cm 3way 密閉型)
スピーカケーブル AET 6N14G (チャンネル当り2本使用)
電源タップ 自作(R-1コンセント2個使用、ケーブルはTunami Nigo 3m)
電源ケーブル 標準添付のケーブル(A)とオヤイデ PA-23FX(1.3m)(B)
テスト方法:さいころを振り、偶数であればオヤイデを、奇数であれば標準添付品の
ケーブルに交換。同じものが続く場合は、一度抜いて再度差込。
ケーブル差込後、電源を入れYPAOでフロントスピーカのサイズ判定を実施。
備考:AVアンプは開放型ラックに収納され、その横に電源タップを設置。
電源ケーブルは、AVアンプと電源タップ間に使用。ケーブル交換は、ラック、アンプ、
タップとも移動することなく実施。抜いたケーブルは、常にラックの後ろに置き、
ルームアコースティックの影響を排除。
テスト結果
回数 さいころ ケーブル サイズ判定結果
1回目 4 B 大
2回目 6 B 大
3回目 6 B 大
4回目 3 A 小
5回目 1 A 小
6回目 1 A 小
7回目 6 B 大
8回目 2 B 大
9回目 5 A 小
10回目 3 A 小
11回目 1 A 小
12回目 2 B 大
13回目 3 A 小
14回目 2 B 大
15回目 2 B 大
16回目 1 A 小
17回目 2 B 大
18回目 4 B 大
19回目 2 B 大
20回目 5 A 小
上記の結果は、電源ケーブルの交換で、スピーカから出る音のバランスが変化していること
を示しています。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:13246970
![]() 1点
1点
電源ケーブルや電源タップなどの議論になると必ずこうなりますよね。
自分は音質、画質に関わらずケーブル等替えたい派なの何ですが
AV REVIEWの4月号 読者のお悩み相談室コーナーの投稿に同じようにブラインドテストをしてください、という質問がありました。
その回答として、料理の例でいえば「値段」「見栄え」「おなかのすき具合」におもいますよっても味が変わるし視覚要素も判断基準になると書いています。
まさにその通りだなと思います。
オーディオは趣味的要素が大きいもので、自分なんかはケーブルの色がかっこいいなぁとか、電源タップの質感がいいなとか、そんなので喜んでるやつです。
実際音質はケーブルや、インシュレーターなどで良くにしろ悪くにしろ変わっちゃいましたね自分的には
書込番号:13247160
![]() 0点
0点
こんばんは。
AVアンプでも良いのだと反応あるのですね。
私のDENON AVC-4310だとほとんど反応しません。(汗
私にとっては初めての定量風なデータを提示いただきありがとうございました。
YSPの測定結果に文句つける人もいますかね?
ご存知かも知れませんが、バリバリの肯定派です。
書込番号:13247235
![]() 1点
1点
Minerva2000さん
資料ありがとうございます。
出していただいたこと、感謝しております。
内容に関してなんですが、、、
あまり言いたくはありませんが
実験方法に関して、これは実験と呼べるものではありません。
ダブルブラインドテストに関して、
たしかに電源ケーブルやSPケーブルは一人では厳しいですね。
どなたかにお手伝いしてもらえば?
ダブルブラインドテスト、お金と暇がないとおっしゃいますが、
実験結果でケーブルの違いがなかった場合、これ以上ケーブルにお金をかけずにすむのでむしろ安い実験だと思うのですが。いかがでしょうか?
書込番号:13247267
![]() 0点
0点
オーディオには門外漢に近いですが、一言だけ。
>ハイエンドの米国製パワーアンプを買った方が、付属されているしょぼい電源ケーブルを見て、
さすが米国のハイエンドメーカー、こんなしょぼい電源ケーブルでも良い音が出るという自信
を持っているのだな、と感心していました。
これこそ、正しい考え方だと思います。
理想のアンプは、理想の電源を搭載しているべきだと思うからです。
電流容量が足りない、細い細いケーブルではダメでしょうが、十分な容量があり、負荷変動
で電圧ドロップしない電源系であれば、ACラインが多少汚れていようと、完璧に安定した
DCを内部回路に供給できる電源であるべきです。
何十万もするアンプが、AC電源の微小な条件変化で音が変わるなんて・・・
それが事実であれば、それは、プアな電源を平気で搭載するアンプメーカーの怠慢でしょう。
真空管アンプ以外の高級アンプで、もし、音が変わってしまうなら、それを許している評論家は、
メーカーに甘い人たちなのだと私は思います。
書込番号:13247621
![]() 0点
0点
Minerva2000さんの [13246970] の実験は、以前、
[8213066] http://bbs.kakaku.com/bbs/20435010179/SortID=8176401/#8213066
で紹介されているものです。
それに対する私の見解もそこで述べてありますが、ここに抜粋を再掲します。(言葉は言い直していますが趣旨は変わりません。)
まず、[8217354] に書いたように、疑問点は主に2点あります。
(1) 実験に使っているスピーカーの大きさが大きいことから考えて、電源ケーブルに関わらず、本来すべて「大」と判定されるべきではないか?「小」と判定されることがあるのは、実験になにか根本的な問題があることを示唆するものではないか?
(2) そもそも電源ケーブルで音が変わるという実験にはなっていない。電源ケーブルでYPAOの測定結果が変わるという実験にすぎない。
そして、[8279258] に書いたように、これだけ大きな疑問が投げ掛けられているのにもかかわらず、Minerva2000さんからはこれを覆す反論がありません。まず、これがそもそもおかしいのです。そして、私が追試や再現と言っているのは、もしも追試や再現があれば、Minerva2000さんから反論がなくても、少しは考える余地があるかもしれないという意味で言っているだけです。追試や再現がどうこう以前に、疑問を覆す反論がMinerva2000さんから出されていない時点でそもそもおかしいのです。なお、私はすでに実験に疑問を投げ掛けていますから、私が追試や再現をする必要はありません。
書込番号:13247660
![]() 3点
3点
議論は苦手なので続けませんが、YPAOの測定結果だけが変化するのでなく、スピーカーの音が変化し結果として測定結果も変化すると思います。
試験者の主観ではなくマイクによる客観と思います。
と言って逃走。(笑
書込番号:13247721
![]() 0点
0点
Minerva2000 さんのように、意味のない間違いでもかまいません。
誰でもいいから早く変わることの証明をしてください。
書込番号:13247749
![]() 0点
0点
>ダブルブラインドテストに関して、たしかに電源ケーブルやSPケーブルは一人では厳しいですね。
>どなたかにお手伝いしてもらえば?
ダブルブラインドテストの意味を勉強して下さいね。電源ケーブルを何から何に替えたか分からないロボットに手伝わせる必要があるのですが。
シングルブラインドテストなら妻に手伝ってもらって、百発百中で3種の電源ケーブルの銘柄を当てましたが。
書込番号:13248049
![]() 1点
1点
>実験になにか根本的な問題があることを示唆するものではないか?
実験に何も問題は無いと考えていますが、何か問題がありますか?
>電源ケーブルでYPAOの測定結果が変わるという実験にすぎない。
測定結果が変わるのは、測定回路を含め、アンプ回路が電源ケーブルの大きな影響を受けているからです。電源ケーブルで何も変わらないなら、測定結果も変わりません。
書込番号:13248067
![]() 1点
1点
>>ダブルブラインドテストの意味を勉強して下さいね。電源ケーブルを何から何に替えたか分からないロボットに手伝わせる必要があるのですが。
いやいやいや。
薬の二重盲検ではないのですから、別にロボットまで出さなくても。。。。
奥さんにサイコロか何かをふってもらい、偶数奇数でA、Bの電源ケーブル交換で良いのですよ。ロボットがいなくてもちゃんとできますよ。
ちなみに結果はどうでもよいです
ここまであなたがキリキリしてると、このような掲示板では信憑性に欠けますからね。
(ようは負けたくない一心で捏造しかねないから)
私は、肯定派がダブルブラインドテストをやってくれればそれでよいのです。
書込番号:13248699
![]() 0点
0点
Minervaさんの環境では、電源ケーブルの交換で、YPAOが変化をとらえたということは、紛れも無い事実として受け止められると思います。
一方、困ったキリがないさん(←ハイエンドユーザ)の
>私のDENON AVC-4310だとほとんど反応しません。(汗
という事実もあります。
初心者の方が高価な電源ケーブルや電源ボックスに手を出しても、音が良くなるかも知れないし、変化が無いかもしれない、やってみないと分からないという世界です。これが結論ではないでしょうか?
ちなみに私の環境では電源ケーブルや電源ボックスの交換で音は変わりますが、他の要素(アンプ、スピーカなど)の方がずっと大きいので、特に意見なしです。
書込番号:13250020
![]() 0点
0点
>奥さんにサイコロか何かをふってもらい、偶数奇数でA、Bの電源ケーブル交換で良いのですよ。
>ロボットがいなくてもちゃんとできますよ。
これでは、ダブルブラインドテストにはなっていないとツッコミを入れる方が、おそらく1名はおられます。
その方によれば、奥さんが無意識のうちに微妙な合図(目付き、声音)を送っているのを被験者が感じ取ったり、仮に別の部屋で交換するように段取りしていても、ケーブル接続時にどのケーブルか知っている奥さんの何らかの意図により、しっかり押し込んだり、いい加減に押し込んだりすることで、ケーブル本来の音質の違いではない、接触抵抗変化による音質変化が起こるかもしれない、ということです。
書込番号:13251066
![]() 1点
1点
そして何も聞こえなくなったさんのご投稿 [13250020] について、思ったことを書きます。
>Minervaさんの環境では、電源ケーブルの交換で、YPAOが変化をとらえたということは、紛れも無い事実として受け止められると思います。
ばうさんも指摘されていますが、Minerva2000さんの実験で使用されているスピーカー (DS-1000) はウーファーの口径が27cmあり、そこそこ大きなスピーカーです。この時代のダイヤトーンは低音の量感が控えめとの印象はあるものの、それでもサイズが「小」と判定されるのは不自然ではないでしょうか。実験になにか問題がありそうな気がします。
>ちなみに私の環境では電源ケーブルや電源ボックスの交換で音は変わりますが、他の要素(アンプ、スピーカなど)の方がずっと大きいので、
「他の要素」の中に、「心理的要素」が挙げられていないことが気になりました。電源ケーブルや電源ボックスの交換による音の変化よりは心理的な影響のほうがよほど大きいような気がします。つまり、正しく記述すれば「電源ケーブルや電源ボックスの交換で音が変わる気がするが、気のせいかも知れない」ではないでしょうか。
書込番号:13251139
![]() 3点
3点
忘れようにも憶えられないさん、久しぶりです。音大生活は? もう18歳通り越して20歳くらい? ヨーロッパに留学とかの話はないですか?
>実験になにか問題がありそうな気がします。
私は使ったAVアンプかも?と思います。
このヤマハのAVアンプは画質にこだわりさんの家でも聴きましたが・・・
AVアンプも最新型は性能が進んでいるので、電源ケーブルやタップ交換に影響されない安定な音を出してくれるかもしれません。これもやってみないと・・・の世界ですが。
どなたか、Minervaさんと同じテストをされたらおもしろいですが。
うちはAVアンプのSP判定機能ないので無理です。
書込番号:13252029
![]() 0点
0点
議論なんかせずに試せばいいのに・・・。
否定した時点で発展なし。
音なんて試してみないとわからない世界の最も足るものですから、
自室機材で使用して初めて価値が出るもんです。
その音を聞いてもらわないとほかの人は評価すらできないわけで・・・。
Marinco 5266BL〜富士電線VCT 2.0SQ*3〜Marinco 5269BL+LEVITON 699で非メッキ簡易延長タップ作れますよ。
延長の必要がないなら699だけで事足りますが・・・。
書込番号:13254363
![]() 3点
3点
DSP-Z11で11.1chを楽しんでいる者です。突然、脳に「2種類の電源ケーブルを使ってYPAOするのじやゃ〜〜」と電波が走り、普段Z11に繋いでいるハーモニックスX-DC15SM1.5m(以下H)と、シマムセン特製6N電源ケーブル1.5m(以下S)とを繋ぎ換えて、どのような変化があるか調べてみました。Z11付属ケーブルは未使用で繋いだことがなく、会社の倉庫の元箱に入っているのでご勘弁を。
フロント/TB2 センター/TB2C サラウンド/FB1 サラウンドバック&フロントプレゼンス&リアプレゼンス/Radius90 サブウーファー/YST-SW1000
結論から先に書きますと、小宅ではサラウンドバックの「大きさ判定」に「大」「小」のバラつきが出ました。他のスピーカーは7回ともすべて「大」の判定(プレゼンスは判定されません)。なぜサラウンドバックだけなのか、電源ケーブルの影響なのか、原因は分かりません。
1回目H「小」、2回目S「大」、3回目H「小」、4回目S「小」、換えずに5回目S「小」、6回目H「大」、換えずに7回目H「大」
書込番号:13254824
![]() 3点
3点
連投します。「周波数補正」にも僅かな差異があります。
そして師匠、Minerva2000さん、皆さん、喜んで頂けましたか(^^;)
書込番号:13254886
![]() 3点
3点
MUSTANG-Dさん、
電源ケーブル交換によるYPAOへの影響実験、ありがとうございます。
YPAOは別に「目」でウーファサイズを見てスピーカーの「大・小」を判断しているのではなく、マイクで「聞いて」判断しているのですが、かなり微妙な判断をしているとは言えそうですね。
DS-1000は27cmウーファですが、非力なアンプだと低域の量感が出ません。馬力のあるアンプだと強力な低音が出てきます。 私の場合、電源ケーブル交換で、YPAOの「小」判定から「大」判定に変わったのですが、これは聴感と完全に一致しており、力強い量感ある低音が出るようになりました。
高級なアンプだと電源ケーブルの影響を受けないと勘違いされている方もいますが、高級なアンプほど電源ケーブルに敏感です。高級アンプに1本30万円の電源ケーブルを使ってみたところ、その音の圧倒的な良さに感激し、結局10本購入された方もいます。ちなみにその方はスピーカーには、2千万円のアヴァンギャルドや、マッキントッシュの高級スピーカーを使われています。
書込番号:13255343
![]() 2点
2点
Mustang-Dさん、実験ありがとうございました。
電源ケーブル交換で違った判断が出たものもあった、ということは分かりました。
本当は1本は家電量販店で売ってる普及品にするとよかったかもしれません(両方とも高級ケーブルなので)
しかし途中で結果がひっくり返りましたね。バーンインの進行もあるのでしょうか?
しかしフロント、リアなど主要なスピーカは、変わらないことが分かりました。
この結果をもって、なんともいえませんが、一応テストをやってもらったので、感謝します。
書込番号:13255849
![]() 1点
1点
拙者、ホームセンターでケーブルに目覚めました。
ホームセンターにも良い物売ってるよ。
書込番号:13256083
![]() 2点
2点
こんばんは。Z11は3年で3回しかYPAOしておらず、そろそろやらねば〜と思っておりました。サラウンドバックはヤマハNS-10MMからRadius90にしても、必ず「小」判定でした。シマムセンのケーブルに交換したら「大」になり、そのあとは「大」で落ち着いております。Radius90は鳴りっぷりがいいので「大」「小」境界線にあるのかも知れません。電源ケーブルを換えたり、もっと回数を重ねたりしても、やはりサラウンドバックしか変わらないと思いますし、27cmウーファーのDS-1000の判定が、ケーブルで「大」と「小」切り換わる理由とは関係なさそうです。
実は、元々フロントスピーカーはトールボーイのFB1でした。先代Z9では「大」だったのが、Z11では必ず「小」に判定されるようになってしまい、聴感上はコントロールされた質のよい低音なのですが、Z11のマイクでは控えめに拾われてしまうようです。サラウンドに使っていたTB2は常に「大」判定でしたので、フロント3chを揃えたい気持ちもあって今年から前後入れ換えたのです。もっとハイグレードなシステムなら参考にして頂けたと思いますが、その場合はマイクの性能がついていけるのか心配になってきます。YPAOって意外と気まぐれなのかも知れません。
私も「変わる派」なのでケーブルやインシュレーター、消磁器などアクセサリーも使います。五感が健常なら、誰でも思い込みやプラシーボからは逃れられないと、それらも含めて堂々と受け入れています。普段の人間関係、食生活なども同じです(^^;)仕事や子育てならともかく、趣味道楽に対して、私にはMinerva2000さんや、ばうさんのような信念はありません。でも信念のない私でも、楽しめていることは確かですし、ケーブルなどで音が変わって聴こえるうちは、なるべく疑心暗鬼にならず、楽しんでいきたいと思っています。失礼いたしました。
書込番号:13258032
![]() 3点
3点
私の場合、経験と知識の蓄積によって、信念を形成してきております。
そこが、それら抜きで信念を先行させている方との根本的な違いですね。(笑)
書込番号:13258805
![]() 3点
3点
Mustang-Dさん、
>趣味道楽に対して、私にはMinerva2000さんや、ばうさんのような信念はありません。
わたしもそれに習えです。(小さい声で−−アクセサリ)
FB1を「小」判定するとはヤマハさん、どんなソフトなんでしょうね。メーカーとしては低域豊かな、ふくよかなサウンドを想定しているのでしょうか。カッチリとした音が好きな人はどうすればよいでしょうか? うちはいつもダイレクトモードにしているから良いですが。−−脱線気味になりました。
書込番号:13259113
![]() 1点
1点
電源ケーブルで音が変わるというのなら、ケーブル毎にアンプの出力をオシロで測定すればいいんですよ。マイクでスピーカーの出す音を測定するのは他の要因で変化する可能性があるからダメです。部屋にいる人が立っているか座っているかだけでも変化する可能性があります。その他、温度、湿度等・・・
仕事上、いろいろなセンサ類+それに対応するアンプを扱いますが、もし電源ケーブルで測定データが変化してもらったら非常に困ります。そんな欠陥品を掴まされたらメーカーへ突き返します。幸いにもそんな経験は無いですけどね。
書込番号:13264385
![]() 2点
2点
オシロで観測したアンプ出力端子の電圧変動が仮に全く同じであったとしても、「アンプの電源ケーブルを変えても音は変わらない」ことを証明したことにはなりませんよ。
音が変わるかどうかは、スピーカーから実際に出た音を計測して判断しなければなりません。
私のつたない実験では、YPAO測定時に私の姿勢や位置による影響が出ないよう、同じにしていましたし、サイコロの目に合わせて瞬時に温湿度が変わる精妙な空調装置も使っていませんでした。
大体、アンプと計測器は全く別物で、計測器はその測定結果を数十ワットの出力変動を伴いながら結果表示していません。
書込番号:13265044
![]() 1点
1点
>オシロで観測したアンプ出力端子の電圧変動が仮に全く同じであったとしても、
>「アンプの電源ケーブルを変えても音は変わらない」ことを証明したことにはなりませんよ。
>音が変わるかどうかは、スピーカーから実際に出た音を計測して判断しなければなりません。
言っている意味がわかりません。電源ケーブルがアンプのスピーカー出力以降に影響を与えるってどういう理論?教えていただきたいです。
アンプからの出力が同じで、スピーカーから出た音を記録した結果が違うのならそれは、アンプ〜音声記録間で受けた影響によるものであって、電源ケーブルの影響とは考えられないと思いますが。
>大体、アンプと計測器は全く別物で、計測器はその測定結果を数十ワットの出力変動を伴いながら結果表示していません。
えーっと・・・電源ケーブルの違いがアンプの出力変動にどのように影響する想定しておられるのか良くわからないのですが・・・
書込番号:13267656
![]() 0点
0点
>アンプからの出力が同じで、スピーカーから出た音を記録した結果が違うのならそれは、アンプ〜
>音声記録間で受けた影響によるものであって、電源ケーブルの影響とは考えられないと思いますが。
アンプがスピーカーから出る音に及ぼす影響は、アンプのスピーカー端子出力電圧のみであってアンプの他の内部要因によるものは無いということは自明ではないので、そのこと(電源ケーブルの影響が無いことも含め)を確認することが必要です。
前段をもう少し分かりやすく言うと、「アンプのスピーカー端子出力電圧の波形が同じなら」スピーカーから出る音は、全く違うアンプであっても全く同じになることは、必ずしも自明では無いということです。
>えーっと・・・電源ケーブルの違いがアンプの出力変動にどのように影響する想定しておられるのか
電源ケーブルの違いがアンプの出力(変動)に影響すると想定していますが、ここでは「どのように」影響するかは議論していません。
書込番号:13267790
![]() 1点
1点
Minerva2000さんは承知の上かもしれませんが。
某氏に、何を言っても無駄だと思いますよ。
書込番号:13267806
![]() 1点
1点
くろりんくさん、
ご忠告ありがとうございます。その懸念はうすうす感じていたのですが、ついつい書き込みに反応してしまう性格でして。
もう止めます。議論しても収束しませんので。
書込番号:13267822
![]() 1点
1点
Minerva2000さん、こんにちは。
以前に紹介していただいた三菱の電源ケーブル、PC−1、中々調子が良いですよ。バイオリンのストリングスの余韻が見事に再現されるようになりました。これが再現されないとCDを聴いた気がしません。ケーブル類を間違えて選択すると不自然な余韻が残り音の解像度に影響します。PC−1の余韻は透明感の中にある余韻ですから生、そのものの音です。[SYLVAN]との相性も抜群です。
書込番号:13268042
![]() 1点
1点
画質にこだわりさん、こんにちは。
三菱の電源ケーブル、PC−1の調子が良いとのことで何よりです。
これに使われている三菱電線工業開発のDUCC導体は評判が大変良くて、最近はアクロリンクも導体として採用しているとのことです。
書込番号:13268195
![]() 1点
1点
まだ研究中ですが、マスタリング用の業務用ソフトで音質変化をテストしています。
ソフトウエアはCDマスタリングでも実績のあるSteinbergのWave Lab 7です。
現状、PC/Macをトランスポートに仕立てた際のプレイヤー・エンジンとしても屈指のアイテムだと思います。
DAWのデファクト、ProToolsと連携して制作されたCDソフトを多くの皆さんが楽しまれているはずです。
お題はアンプやCDPのライン出力をDAWにA/D変換して取り込んで機材のキャラクターを確認できないか?です。
機材が介在するほかD/A変換→A/D変換が必要なので単純に元ファイルとの比較ができないことと、
実際にテストに使う音声ファイルはどんなものが良いかにまだまだ研究の余地がありますが、
テスト途中の状態でもなかなか面白い現象が確認できます。
テストソースはフルレンジのホワイトノイズ、基本的に業務機器をマスタークロックで制御してテストしてます。
MacからDDC/DACへ送りプリアンプ経由でADCを経てDAWに取り込んでみました。
グラフ縦軸は出力レベルですが、解析(1)はdB、解析(2)はLINERで視覚化したものです。
同一ファイルを使ってプリアンプの電源ケーブルだけ代えてみて周波数分布に変化がないか見ています。
3D解析した画像が添付の写真です。
書込番号:13269016
![]() 4点
4点
こんばんは。
低音の劣化が大きいと解釈して良いのですか?
書込番号:13269082
![]() 0点
0点
携帯だとグラフが良く見えないのでPCで見ました。
各帯域でギザギザに変化しているので、
ケーブルによる変化をグラフ上で確認するの難しそうですね。(汗)
でも、純正ではないケーブルでのグラフ見てみたいですね。
ところで、
never forgetさんは、
忘れようにも憶えられないさんの分身ですか?
書込番号:13269225
![]() 0点
0点
続けて市販ケーブルを使用した場合の画像です。
オヤイデのTUNAMI-GPX、三菱のPC-1です。
書込番号:13269301
![]() 5点
5点
とりあえず本日最後の画像です。
三菱PC-1使用のままプリアンプのトーンのLOWを全開+10dBまでブーストした状態です。
途中のケーブルの周波数分布と比較してどの位の差異があるか視覚化してみました。
アンプのトーン・コントロールの変化量に対してケーブルでの変化量を比較してみて下さい。
書込番号:13269355
![]() 3点
3点
redさん
グラフありがとうございます。
げげっ、使われたプリ場合、
純正ケーブルお方がグラフ上はよさそうですね。(滝汗)
聴かれた感じはどうでしたか?
書込番号:13269473
![]() 0点
0点
元画像のサイズが大きすぎたのでブラウザ上で縮小表示されてつぶれ見にくくなってしまいました。
カラー・チャートはオクターブ相当でグラデーションされています。
解析(1)dBはアベレージなので時間軸方向も揃って見えますがLINEARをみると随分動きがあります。
周波数帯域のアップ・ダウンがそこそこありこの辺りがケーブルのキャラクターじゃないでしょうか。
テスト・ファイルは2分位のものが必要だなと思っています。
今回はファイルが短すぎたのでDAWに取り込んでから倍の長さに引っ張りました。
実際にはピークとデップはもっと先鋭になっています。
サンプリング・レートは16bit44.1kHz、音声そのものは20Hzから20kHzと一般的なCDのレンジなんですが、
元ファイルが24BitらしくAPOGEE UV22でデコードされていて可聴範囲外にもウェーヴが確認できます。
ディザ合成されるとこういう部分に波形が立つことは初めて知りました。
ちなみに機材ですが・・・
Mac+Wave Lab7 →Hiface EVO(スーパークロック同期DDC)→Lavry DA11(DAC)→
CLASEE CP35(プリアンプ)→Sonic Solutions ADC→Mac+ProTools
DDC/DAC/ADCはMutech iCLOCK マスタークロック・ジェンネレータで同期させ、
プリアンプ、ADCへのアナログ信号はXLR出入力で接続しています。
各々の出入力が管理できる様にデジタル・アッテネータ式の機材を使用しました。
書込番号:13269552
![]() 3点
3点
困ったさん、こんばんは。
>純正ケーブルお方がグラフ上はよさそうですね。(滝汗)
意外でしょ?
ホワイトノイズなので聴いてどれが気持ちよいということもなかったですけど(苦笑)
驚いたのは経由する機器で元ファイルとはかけ離れちゃうことですね。
こんなに変容しちゃうのかと・・・
とりあえずこの場は電源ケーブル1本でもそなりに変化があるとボールを投げ帰せれば役目は終了でしょう。
もうちょっと機材の標準化が必要みたいですしテスト・ファイルも熟慮しないといけない感じです。
今日はここまでにしておきますが、今回は別の機会の伏線です。
オシロスコープはもちろん、S/N、定位なども測定できるんですが、
純正ケーブルここで随分違いが出てしまって脱落します。
それとノイズ・フィルターやクリーン電源系を使うとこのグラフがあっ!と驚く変貌を遂げます。
テストしてみてそして何も聞こえなくなった師匠が電源に拘る理由が理解できました。
書込番号:13269687
![]() 4点
4点
Redfoderaさん、テストお疲れ様です。
なかなかここまでされる方はいませんので、大変貴重です。
しかし正直いって分かりにくいグラフですわあ
時間軸の動きはいらないので、一定の時間にわたって平均をとれば、平面二軸のグラフにできます。そうして比較すればどうでしょうか?
書込番号:13270668
![]() 0点
0点
忘れようにも憶えられないさん、こんにちは。
>電源ケーブルや電源ボックスの交換による音の変化よりは心理的な影響のほうがよほど大きいような気がします。
クラシックの弦楽奏者でしたら、お分かりになると思いますが、バイオリンのフェザータッチの音、弦楽器群が同期してハモッタ音、それがホールに吸い込まれる音などは素晴らしく、奏者でなくても陶酔させられるところです。これは心理的なものではなく、ハッキリ見分けがつきます。これを再現するにはSPケーブルや電源ケーブルで調整するしかないのです。これが実現しますと比較的静かになるシンフォニーの第二楽章を聴く楽しみが出来ます。コンサートマスターの技量が良く分かるのです。
書込番号:13270960
![]() 1点
1点
redfoderaさん、こんばんは。
興味深い実験結果ですね。参考になります。
もし可能ならで結構ですが、スピーカーから出た音をマイクで拾ってそれを表示していただけるとうれしいのですが。
またプリアンプだけでなく、プレーヤーやパワーアンプで、電源ケーブルを替えた時の差も関心があります。
人により、電源ケーブルの交換による音の差が最も顕著に現れるのは、プレーヤーという方もいれば、パワーアンプと仰る方もおられます。
また機器を変えた時の差とそれに繋がれている電源ケーブルを変えた時の差で、どれくらい違うのかも興味があるところです。
redfoderaさんのことですから、実験条件(機器やケーブルでの十分な通電時間を取るなど)を合わせたり、同一条件で複数のトライはされていることと思いますが、それらも明記された方が良いでしょう。
話は変わりますが、測定結果で最初、低音のレベルが落ちているように見えるのは、低音から高音まで均等に位相が遅れているからでしょうか? これを補正して見ることは可能でしょうか?
書込番号:13272552
![]() 0点
0点
こんばんはです。
redさんがこちらですごい実験をされていると聴いてふらりと立ち寄らせてもらいました(笑)
私も今現在アップされているグラフはちょっと見にくいと感じました(よくよく見れば違いがわかりますが)。
クリーン電源での変貌グラフにするとどれだけ違うのかすごく気になります。私もCSEのクリーン電源を購入したときに今までのはなんだったんだといいたくなるぐらい豊かな低音が出てきて驚きました。もちろん電気工事後も凄まじい変化です(今もなお進化し続けています)。
こういうモニタリング環境を整えればおのずと一番良いケーブルの組み合わせが音だけではなく目で見極めることが出来るようになるのでこれはかなり効果的な実験方法かもしれませんね。
redさんの実験方法参考に自分もやってみようかな……機材が無いですが(汗)
書込番号:13272606
![]() 1点
1点
Minerva2000さん、こんばんは。
まだトライアルというべき状態でテスト方法の標準化で試行錯誤しつつ、
Wabe Lab7の習熟度アップを計っているというのが現状です。
機器のキャラクター、電源ケーブル、ライン(&デジタル)ケーブル、その他アクセサリー類も、
対象に加えられる様にテスト方法を標準化できれば理想ですね。
時間のある時に少しづつトライアルして手法を洗練させたいと思っています。
今回のトライアルでもオクターブバンド、スイープ、220Hz正弦波&三角波を使ってみましたが、
電源ケーブルを入れ替えてテストしなかったので物の比較はできてません。
>スピーカーから出た音をマイクで拾ってそれを表示していただけるとうれしいのですが。
これが一番難しいテストになると思います。
いわばアコースティック楽器をレコーディングするのとほぼ同じ感覚ですね。
スタジオ(理想は無響室?)を数日押さえ機材全てをセッティングしたままテストを行う必要があります。
会社に無響室はありませんし、職権乱用してスタジオを押さえるのマズいですね。
ちょっと実現は困難かと(汗)
>プレーヤーやパワーアンプで、電源ケーブルを替えた時の差も関心があります。
元ファイルでいくつかのDACでダイレクト出力をトライアルしてみましたが、
やはり電源ケーブルの入れ替えを行っておらずテスト方法を試してみたレベルです。
CDPもテストソースをCD-Rで用意すればベンチマークできますね。
パワー・アンプは直接的にテストするとなると方法で悩むところですが、
スピーカー出力をハイインピーダンスで受けラインレベルに変換する手法で擬似的にテストできます。
どしても信号のコンバートが必要なのでコンバートに伴う変容を折込まなければいけませんが、
ここを勘案した比較なら電源ケーブル、SPケーブルもテストすることができます。
例えばLuxmanあたりでもカーオーディオ用にトランスフォーマーが販売されています。
ただこれのために出費するかどうかはいまのところ考えていません。
ご了解下さい。
http://www.luxman.co.jp/product/cc_xat1000.html
>同一条件で複数のトライはされていることと思いますが、それらも明記された方が良いでしょう。
今後、周辺環境の標準化は課題ですが、今回は以下の状態でトライアルしています。
機材は前夜から10時間程度通電だけしてます。
テスト作業中はほぼ連続してますから多少条件にバラツキがありますね。
電源ケーブルは起動した複数のMacに指したまま2時間ほどウォームアップしています。
Mac以外はアメリカン電機の壁コンセント・ハイパーシリーズ4口からダイレクトに接続してますが、
暫定的にMITのコンディショナーに繋ぎ変えてトライアルを別途行っています。
Macはコトベールのサージ・フィルター付きのタップ経由で給電してました。
電源ケーブルはMacを含めて藤倉CV-S 2(1.5m)にHubbel+Shelterでテスト用に新規10本を作成しました。
XLRケーブルはアビーロード・リファレンスを2組、USBはフルテック、
デジタル・ケーブルはXLR/BNCともGothamで統一してます。
そして何も聞こえなくなったさん、天地創造さん
グラフについてはどんなタイプで表現するのが良いか思案しています。
Wabe Lab7の習熟度アップにともなって見せ方や切り口は改善できるかもしれません。
スペアナないし折れ線で周波数帯域をグラフにすることももちろん可能です。
ただ今回のトライアルで気がついたことがとても重要なポイントになりそうなんです。
時間経過にともなってそこそこ大きな周波数のレベル変動があったことです。
解析(2)LINEARではエンペロープを表現してますから特に顕著ですよね。
実はコンディショナーの有無で比較するとかなり興味深い変化がおこりますので楽しみにしていて下さい。
もう少しテスト手法が洗練されてから改めてお見せしたいと思っています。
書込番号:13273148
![]() 3点
3点
みなさまこんばんは。憶えられない@プラハ留学中 です(うそ)。
聞こえなくなった師匠、コメントをありがとうございます。
画質にこだわりさん、ご意見ありがとうございます。変わる派のご意見として拝聴しました。
さて、redさんのグラフですが、わかりづらいというより、ここからどんな情報を汲み取れるのかがよくわかりません。そもそも縦軸に目盛りがない…ので、バスブーストの波形から類推すると、時間軸方向に数dBとかの、オリジナルには無い山谷ができているってことですよね?
とすると、 D/A → アンプ → A/D → FFT(?) のようなプロセストの中に、なんらかの不具合とかノイズとか、少なくとも時間的な不安定さ、があって、それを見ていると考えるのが自然な気がします。そうした中で、ケーブル間の、恐らくとても微妙な差を論ずることができるのかというと疑問だと思いました。再現性も不明ですし。
上記によって「電源ケーブルで音は変わらない」と主張するわけではありません。とかく思い込みや早とちりをしがちな案件なので(特にredさん)、落ちついて考えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:13273175
![]() 0点
0点
redfoderaさん
はじめまして。
データ拝見いたしました。
リクエストがあります。(すいませんずうずうしくて。。。。)
計測回数を3サンプルだとどうでしょうか?
グラフを見た限り、そうとうシビアなグラフでしたので(おそらく室温が1度変わるだけで顕著な差がでそうなグラフ)
ぜひとも同条件でのサンプル回数を増やしていただきたいです。
書込番号:13273566
![]() 0点
0点
忘れようにも憶えられないさん、こんばんは。
オリジナルの波形はMac内でデータから音声の周波数分布をシュミレートした状態ですが、
それ以外は機器なりコンバートなりを経て行き着いた状態ですから同一とは言えませんよね。
ただし機器を固定して条件を標準化するとそのシステムの音としては比較できる状態になります。
かなりおこがましいがスタジオの常設機器で収録編集を行う様なもんです。
ワインのテイスティングするにもISO(国際基準協会)No.3591準拠のグラスを使用しますでしょ。
平たく言うと比較する時の条件を脳内システムではなくて自家システムにしてしまうってことです。
一部の条件を変える(例えば電源ケーブル)ことで変化が確認できればそれも有りでしょう。
極端な話が、自分のオーディオ・システムのCDプレイヤーを入れ替えるのと同じ行為ですから。
蛇足ですが今回トライアルを始めたのは自前サイトに比較用の音声ファイルを置くための準備行動です。
以前、検討していたことを少し前に進めようと思っています。
>そうした中で、ケーブル間の、恐らくとても微妙な差を論ずることができるのかというと疑問だと思いました。
縦軸にメモリがないのはたしかにWave Lab7、とても不親切ですね。
そして何も聞こえなくなったさんのお話の通りスペアナで時間軸輪切りにした方がわかり易かったかも。
ただしそれで見えるは周波数の分布と出力レベルだけです。
これで満足頂けるなら比較用のグラフを今度ご用意しておきます。
むしろ忘れようにも憶えられないさんがお詳しい範囲かなと思うんですが・・・
もし本当に音大生さんならですが。あ)
ちなみに解析(2)は縦軸が周波数帯域別のLINEARつまりエンペロープです。
解析(1)のゲイン・レベルに相当するdBとは意味がまるで違います。
共振の状況によってピークとデップが変化するってのが音声(波形)の面白いところですし、
音程、音量、倍音比率とならんでエンペロープは「固有の音」を作る重要な要因ですよね。
画質にこだわりさんが都合良くヴァイオリンのお話を引き合いに出してくれていますが、
同音のアップ・ボウ、ダウン・ボウの違いって何でしょう?
エンペロープが変化するってことは人間の聴覚にとっては「音が変わる」ということです。
> D/A → アンプ → A/D → FFT(?) のようなプロセストの中に、なんらかの不具合とかノイズとか、
>少なくとも時間的な不安定さ、があって、それを見ていると考えるのが自然な気がします
ご指摘の通り、不安定さがあります。
安定感を増す方法、実は電源です。
交流電源から直接引き込んでいるとエンペロープの傾向は残しているかもわからないほど変化しますし、
今回はテストソースが短か過ぎて時間軸をストレッチしてアベレージで評価するのも気が引けるほどです。
ここにコンディショナー入れると状況が随分違ってきてエンペロープからして安定します。
近いうちに手法をもう少し練って画像を用意するつもりです。
書込番号:13273608
![]() 2点
2点
Valentine vs Valensiaさん、はじめまして。
テスト環境を標準化していく上で難しいものひとつが空気だったりします。
本来、空気を媒介して聴くものですからファクターとしては査証すべきなんですが、
毎度毎度、条件が変わり過ぎるのであえて各種変換を経る信号レベルで検証しようと考えました。
スピーカー再生しているものを同一条件で収録するのは自宅レベルでは困難ですし(汗)
計測回数の増加については私も考えていますし定位やオシロスコープなど他の測定項目も加えるつもりでいます。
いくつかの違う角度と視点で比較できる方が現象を把握しやすいかなぁと思ってます。
書込番号:13273667
![]() 2点
2点
連レス続きで申し訳ありません。
Minerva2000さん
>測定結果で最初、低音のレベルが落ちているように見えるのは、
>低音から高音まで均等に位相が遅れているからでしょうか?
エディターの視点で20Hz以下のエンペロープをみるならご指摘の通りでしょう。
単純に波形としては位相の遅れが出ていると思います。
ハード・ウエアのことを考え合わせて推測するなら、
20Hz以下の音声再生が能力的に追いつかない感じもします。
可聴範囲以下は極端に能率のカーブが低くく、
ロールオフが大きいんじゃないでしょうか。
CLASSE CP35の再生周波数、スペックが20Hz(-5dB)です。
ハードウエアの再生能力に係わらずMac内ではデータそのものの波形解析されてます。
実機の実効値とギャップがあるのはある種当然だろうと理解しています。
>これを補正して見ることは可能でしょうか?
位相を補正すると収録したデータを意図的に編集加工することになります。
マスタリング用に波形編集を行うソフトウエアですから補正は可能ですが、
テスト・測定という視点からは改ざんすることに当たりますね。
入れ物(機材環境)を固定して標準化する上ではハード選定に検討の余地有りですね。
ちなみに解析する再生帯域を20Hz〜20KHzにすることはできます。
書込番号:13275914
![]() 3点
3点
redさん、ノリすぎ。たとえば、
>>測定結果で最初、低音のレベルが落ちているように見えるのは、
>>低音から高音まで均等に位相が遅れているからでしょうか?
>
>エディターの視点で20Hz以下のエンペロープをみるならご指摘の通りでしょう。
>単純に波形としては位相の遅れが出ていると思います。
といったやりとりは、一見双方識者風ですが、きちんと意味を理解できる人はいないはずです。redさんも意味をわかって答えてないでしょ?「エディターの視点」で位相遅れを語るっていったい…(←ちびまる子ちゃん風)。
昨日は柔らかめに書きましたが、お話を聞く限りでは、検証系の再現性という基本中の基本が確認されていないようですし、ケーブルを替えても替えなくても測定ごとになんらかの相違は出そうに思えます。よくわからない不安定性を「ケーブルの違い」と早とちりするかたもいそうですし、風呂敷をひろげる前に熟成が必要なような。
書込番号:13277410
![]() 3点
3点
鉄塔直マイ変電所の天地さんが
ケーブルごときで変わらないと言われれば信じて良いですが、
機器も環境も揃えず口先否定はスルー。と言って逃走。(笑)
書込番号:13277613
![]() 0点
0点
困ったさん
未熟者な私の名前を出さないでくださいよ……恥ずかしい(->_<-)
あとまだマイ変電所は工場です。オーディオ専用棟はまだはるか先のお話です(^_^;)
年齢も経験も若輩者の私の言葉なんて参考にしちゃダメですよ( ̄∀ ̄;)
私のレポは基本的に主観による感想です。深く考えずに感じたことをそのまま言っているので理論も根拠もありません。
データなどの視覚的に判断できちゃんとした根拠があるようなものでないと納得されない方には私のレポなんて妄言にしか聞こえないと思います。
実際PCオーディオシステムからどこかひとつだけケーブル変えても正直変化はわかりません。
音楽聞くのに理論とか根拠とか考え出したら疲れるだけで音楽が楽しめませんよ(-_-#)
そんな中でも今までの経験から一つ言えるのはやるなら中途半端にせず最初から徹底的にやってしまったほうが変化がわかりやすいことかなと。電源まわりで言えば電源タップだけ電源ケーブルだけとやっていると変化が微量すぎてわかりません。
一気に専用分電盤を取り付けてクリーン電源いれてできたら電源ケーブルも……ぐらいまでやってしまわないと変化はわかりにくいものです。
お金が凄くかかりますがどうでしょう?私はこれでかなり変化を感じ取ることができました。
長々と失礼しました(^_^;)
若造がなんか言っとると聞き流してもらって結構です。
書込番号:13277723
![]() 0点
0点
忘れようにも憶えられないさん
ノラな過ぎ(汗)
というより検証が未熟でノレませんか(困った)
>きちんと意味を理解できる人はいないはずです。
少なくとも忘れようにも憶えられないさんは読み取れないってことですか?
オリジナルと比べて他3点共通に2Hz周辺と6Hzの対比はとってもわかりやすいですよ。
ヴァイオリンのアップ・ボウ、ロウ・ボウの音の違いがイメージできる方なら理解できると思うんだけど・・・
>ケーブルを替えても替えなくても測定ごとになんらかの相違は出そうに思えます。
安定感と再現性を高める必要性は私も感じていますし、それも改善しないと説得力が増しませんよね。
ただトライアルが少ないなかでも不安定な部分と安定している部分がはっきりしているんですよ。
皮肉なことにアンプが苦手にしていそうな2Hz周辺、再現性ともどもとっても安定しています。
不安定にみえるところ、実は0.5秒という時間内で不規則に変動していることを拾えているってことじゃないでしょうか。
書込番号:13277953
![]() 5点
5点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「パイオニア > SC-LX83」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 3 | 2016/01/11 20:43:51 | |
| 6 | 2012/07/08 20:24:30 | |
| 2 | 2012/05/25 23:37:56 | |
| 6 | 2012/03/11 17:21:53 | |
| 0 | 2012/01/06 21:53:00 | |
| 7 | 2011/11/03 18:35:46 | |
| 3 | 2011/10/10 0:20:39 | |
| 3 | 2011/11/05 0:45:05 | |
| 2 | 2011/09/10 22:00:18 | |
| 3 | 2011/08/17 11:09:41 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
-
【欲しいものリスト】PC構成20251031
-
【欲しいものリスト】メインPC再構成
-
【Myコレクション】自作構成
-
【欲しいものリスト】pcケース
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
AVアンプ
(最近3年以内の発売・登録)