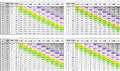�F����A�����́B
�@�������ʐ^���n�߂����A�J�����G���Ŋy���݂ɂ��Ă����̂̓��[�U���e�̃t�H�g�R���e�X�g�̃R�[�i�[�ł����B���{�J�����̌���t�H�g�R���e�X�g�ł́A���m�N���E�J���[�v�����g�A���o�[�T���ȂǕ��傪������Ă��܂������A���ł����o�[�T�����傪��Ԍ�����������ہB�u���Ɣ��i��J���Ă�����ǂ������v�Ƃ��u��ʒ[�Ɏʂ荞��XX���c�O�v�݂Ȃ��Ȃ̂������āu���o�[�T�����ƎB�e���ɂ����܂Ŕ��f���Ȃ�������Ȃ��̂��v�Ɨ������������̂ł��B���ۃX���C�h�f�ʋ@�ŕ\������ۂ̓g���~���O���I�o����ł��܂���A�B�e�����u�Ԃ�36×24mm�̃t�B������ɍ�i�Ƃ��Ċ�������Ă��邱�Ƃ��d�v�������킯�ł��B
�@AF�������A�ʂ����������b���R�}�����������A���ԁE��Ԃ̐���A�I�o�E�t�H�[�J�[�X�̌���͑S�ăJ�����}���̗͗ʂɔC����Ă���A�ʐ^�Ƃ�����̖ʔ����Ƃ́A�|�p�ʈȊO�ɂ��B�e���̙��߂Ɂu�J�����}���̃C���[�W����f���������ɓI�m�Ƀt�B�����ɘI�������邩�v�Ƃ����X�̋Z�p�������v�f���A����Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����傫�������Ǝv���܂��B
�@����A���������C���Ƃ��Ă������m�N���v�����g�ł́A����������掆��ʐ^�p�l���̃A�X�y�N�g�䂪3:2�ł͂Ȃ��̂Ńg���~���O���ӎ����ĎB�e�i���o�[�T���قǂ̌������͖����j�B�����Ă���Ă����݂ɂ��摜�̉��H��������O�B����ɎB�e�ȑO�ɁA�t�B�����͒����̃��[���ōw�����ċ�̃p�g���[�l�Ɏ����Ŋ����č��A�B�e��̓t�B���������E��掆�ւ̘I���E�������S�������ł�������̂ł��B������������A�̎�Ԃ̂�����v���Z�X���܂߂�"�ʐ^�Ƃ����"���y����ł��܂����B
�@���̍��Ɣ�ׂ�ƁA�J�����̐��\���A�b�v�����������Ńs���{�P��I�o�̎��s����͂قډ������܂����B��Ԃ̂������Ă���������PC��ōs����悤�ɂȂ����̂͑�i���ł��B�����ɎB�e�ƍ�i�n��Ɋ������Ԃ��������̂͊�������Ƃł����A�t�Ɏ₵����������������邱�Ƃł��傤�B���L���@�ŘI��������掆�������t�������g���[�ɓ���Ē|���݂ł���瓮�����c���b��ɑ��������܂łْ̋����Ǝv���ʂ�̊G�������o�����̊�т͑��ɑウ���������̂�����܂��B
�@������ƌ����āu�̂͗ǂ������v�Ƃ͌����܂��B�]���ł̓��ԎB�e�ł��s���g�o�b�`���A������莝�����Y��Ɏʂ���悤�ɂȂ������ƂŎB�e�ł����т͑����܂������A���s���ĉ������v��������̂��������͎̂����B�������y���݂̑��ɐV�����y���݂��m���ɑ����Ă��܂��B
�@�ƁA�O�u���������Ȃ�܂������A��q�̂悤�ɋZ�p�̐i���ɂ��ʐ^�Ƃ�����̊y���ݕ����ς���Ă��Ă���Ɗ����Ă��܂��B����A�Z�p������ɐi�����Ă��Ă����ƁA���̊y���ݕ��Ƃ͂܂�������ʐ^�Ƃ�����̊y���ݕ������܂�Ă���Ǝv���܂��B10�N��A20�N��A�����50�N��Ɏʐ^�Ƃ�����͂ǂ�Ȋy���ݕ��Ȃ̂��낤�H�B���Ƒ債�ĕς��Ȃ��A����Ƃ���Ƃ��Đ��ނ��Ă���B���⍡�Ƃ͑S���قȂ�y���ݕ������Ă���̂��B�����z�����Ă݂܂��傤�B
�@�z�����邾���Ȃ�^�_�ł��B����A���̂R�A�x�ɂȂ̂ł���Ȃ���ŃX���𗧂ĂĂ݂܂���(^^;
���t��������������K���ł��B
�����ԍ��F21962655
![]() 8�_
8�_
�ʐ^�����g�߂ɂȂ����Ǝv���B
���ɃX�}�z�̕��y�ŁA�C�y�ɋC�y�Ɏ�y�Ɂc�G���L�I�ȗv�f�����܂����悤�Ɏv���B
���ʁA�B�e���̈�u�̗����I�v�l���K�v�Ȏ���ɂȂ������ȁH
�ܘ_�A�A�b�v���[�h���B
�J�ƐH���A���ł��B
�s����s���������������X�A���߂�Ȃ����B
�����ԍ��F21962694�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�����Ƒ債�ĕς��Ȃ��A����Ƃ���Ƃ��Đ��ނ��Ă���B
�ʐ^�Ƃ������f�����������̂��y���ލs�ׂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�����v�����g�A�E�g���掆�ɏĂ��t����Ƃ��������Ƃ͖����Ȃ��ă}�C�N���`�b�v�݂����Ȕ��ɃR���p�N�g�Ȕ}�̂ɕۑ����ăX�}�z���i�������悤�Ȓ[���Ŋy���ނ悤�ɂȂ��Ȃ����Ǝv���܂��B
�J�����@�ނ͋K�i������č��̎ʃ����ł��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�ł�����e���[�J�[�Ő��\�������Ƃ������������y���݂��Ȃ��Ȃ��āi�J�����@�ނ��j�����Ƃ��y�����Ƃ����L�~�݂����Ȃ��̂͊��Ɏ���x��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21962799
![]() 2�_
2�_
�����i�e������
���ʐ^�����g�߂ɂȂ����Ǝv���B
�����ɃX�}�z�̕��y�ŁA�C�y�ɋC�y�Ɏ�y�Ɂc�G���L�I�ȗv�f�����܂����悤�Ɏv���B
�@�X�}�z����͎ʐ^���R�~���j�P�[�V������i�Ƃ��Ċ��p���Ă��܂���ˁB�C���X�^�f���Ƃ������t�����܂�邭�炢�ʐ^�ł̏��`�B�E���L�͈�ʉ��܂������A�ނ�E�ޏ���ɂ�"�ʐ^���"�Ƃ����ӎ��͑S�������ł��傤�B�����܂Ō��t�ł͓`������Ȃ�����⑫���邷�邽�߂̎�i�ł����Č����Ďʐ^����ł͖����B��������Ƃ��ĎB�e�����ʐ^�������b�̉����ŎB�e�����ʐ^�̕�������ې[�����Ă��Ƃ����X���肻���c
�@
�@�ʐ^����ʉ����Ĕ×����Ă��錻�݁A"�ʐ^���"�ƌ������Ă���l�̎ʐ^�ƁA�����łȂ��l�̎ʐ^�̍��͂Ȃ�Ȃ�ł��傤�B"�|�p��i"���ӎ����Ȃ���ʃ��[�U�[���i�`�������ɎB�e����ʐ^�̕������͌|�p���������Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����A����"�ʐ^���"�̉�X�̑��݈Ӌ`�͂ǂ��ɂ���̂��H
�@����"�ʐ^���"�𖼏��Ȃ獡�܂ňȏ�Ɍ|�p�I�Z���X���v������邩������܂���ˁB
�����ԍ��F21962843
![]() 4�_
4�_
�����i�����_����
�����͎ʐ^�B�e������ɂȂ��čs���Ǝv���B
�������ڐ����������A��ʊE�[�x�ڐ���������J�������×����Ă܂��B
����ł͏��S�҂��A�ǂ�����Ă���ɋC�t���̂��H
���{�� �Â��ʂ镔�����J�����̃R���s���[�^�[���A����ɖ��邭�ʂ��Ă��܂��B
����ł́A����ɋC���t���Ȃ��āA���p�������Ȃ��Ȃ�B
���ʐ^������ɒʂ��K�����������B
�ʊE������͏��i�Ɣ��鎖�ƃZ�b�g��
�B�e�Z�p��`�������B
�D���
�������Y�킳
�N�y�҂قǎ�����肢�B
�N��n�K�L���݂�Έ�ڗđR�B
����͑���c��w�ł�
���w�Z3�N���݂����ȕ����B
�J�b�^�[�i�C�t�ʼn��M���̂����ē������B
�����ԍ��F21962882�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�@�����̐��E�C��茵���ɂ͎��Ȗ����Ŏʐ^���B���Ă���̂ŁC�܂������������Ƃ͂ǂ��ł��ǂ��悤�ȁD�ʐ^�����߂��瑼�̎��Ȗ����ł����ɂ͂܂��Ă���ł��傤�D
�@
�@�J�������i�����鎖�͊��}���Ă��܂����C������Ƃ����đf���炵���ʐ^���B����ł�����܂���D�܂��Ă�C10�N���20�N��͎���ł邩���m��܂��C�����܂őz������K�v���Ȃ��悤�Ɏv���܂��D
�����ԍ��F21962908
![]() 3�_
3�_
1.4�̃����Y�Ń{�P���Ȃ�Ă̂��Ȃ��Ȃ邾�낤��
�X�}�z�J�������Εӕ����Ⴀ���
�����Ԃ̎����^�]�F���Z�p�ŗ��̔F���ł���̂�
���z��ʊE�[�x�ʂ肵�ă{�J���Ȃ�ĊȒP���낤��
�����ԍ��F21962926
![]() 3�_
3�_
�f�W�^�����ŕ\���ʂł͐i�������Ǝv���Ă܂�
�t�B��������A�J���[�ł̓��m�N���قǃv�����g���ɂ�����Ȃ������ł���
�t�H�g�V���b�v�Ƃ��g���ĊȒP�Ƀ��^�b�`�ł���悤�ɂȂ����̂͂������i����
�����ԍ��F21963502
![]() 3�_
3�_
���R���B��Ƃ��ِ����B��Ƃ������������ȗ������B��Ƃ����낢��Ȕ�ʑ̂�����܂�����ǁA���̏�ɂ����Ă������o���Ȃ����⎞�Ԃ�ۑ������i�ȂǂƂ��ăJ�������g���B
���������ۂɎ����̋L���̂܂܂��B��Ƃ��A�|�p�I�ȍ�i��n��Ƃ��A�����Ő�ɔ[���ł���ʐ^�͂Ȃ��Ȃ��B��Ȃ��̂ŁA���ł���������A���x�������^��A�����\������Ă��炤���߂ɑ����Ȃ�Ƃ��w�͂��邱�Ƃ���Ȃ̂ł͂Ǝv���B
�����������R���ِ����������s�ςł͂Ȃ��̂ł�����A���̏�ł����ʐ^���B���J�������ł����Ƃ��Ă��A���̎ʐ^�̎��̂����Ƃ����ʐ^���B���\���͂ł�ł��傤���A�����ǂ����߂�̂���ƌ�����ł��傤�B
���Ǖ��}�ł��邪�䂦�ɁA�O���邩���߂邩�ǂ����őË�����Ƃ����߂�����Ƃ����Ȃ����葱����Ȃ��B
�����ԍ��F21963564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���͂悤�������܂��B
�����Ȃ蓊�����ςȂ��ł͉��ł�����A�܂��̓X���傪�\�z���Ă݂܂��B
�i�R�����g�ɑ��邨�Ԏ��͂܂��ʂŏ����܂��ˁj
�P�D�_�C�i�~�b�N�����W�̊g��
�@�V���i���o�邽�тɉ�f���̑����A�Ï��掿�̌��オ�b��ɂȂ�܂����A�_�C�i�~�b�N�����W�ɂ��Ă͒u������ɂ���Ă�����������܂��B���A�ɘI�o�����킹��Γ����͘I�o�I�[�o�[�A�t��������B�J�����}���͂ǂ���ɘI�o�����킹�邩�B�e���ɑI���𔗂��܂��iHDR���������邯�ǁj�B�_�C�i�~�b�N�����W���g��i±2EV�����炢�H�j���Ă����A�B�e���̓I�[�g�ɔC���ĉƂɋA���Ă��猻�����ɓ��A���A�������A���邢��HDR������I�ׂΗǂ��킯�ł��B����ɂ�14bit�L�^�ł�����Ȃ��ł��傤����20bit�Ƃ��L�^�t�H�[�}�b�g�⌻���\�t�g�̑Ή����K�v�ɂȂ�܂����A�\�t�g���̑Ή��͕ʂɓ���Ȃ��ł��傤�B
�@�_�C�i�~�b�N�����W�̊g����ɂ��Ă݂܂������A�J�����i���̏ꍇ�̓Z���T�[�j�̐i���ɂ��A�B�e���ɋL�^�ł����g�偨�ʐ^�\���͎B�e��ɉƂƂ��ł������莎�s���낵�čl����Ηǂ��B�ʐ^�Ƃ�����̊y���ݕ��͂��������`�ɏ��X�ɕς���Ă����Ɨ\�z���܂��B�B�e���ȒP�ɂȂ邱�ƂŎʐ^���܂�Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��A�B�e���Ɍ��߂Ă������ڂ����ɉ����Ă���̂ł��B����͊��Ɏʐ^�Ƃ�����ł͂Ȃ��ƍl��������o�Ă��邩������܂��c
�Q�D�ȍ~�͂܂��ʓr�l���Ă݂܂��B
�����ԍ��F21963821
![]() 4�_
4�_
���i�����_����
�����X����B
���i�e������
�n�G�g���O�T�̓n�G��߂�̎ʐ^�ł����A�n�G�ł͂Ȃ��ăn�`�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F21964154
![]() 3�_
3�_
VR�ʐ^�W��肽���I
�����ԍ��F21964430�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�������삤�낤�낳��
���I�m���ɁI
�n�G�ɂ�����j�O��Ǝv���Ă���ł�( *´䇁M)
�����ԍ��F21964777�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���肵�����Ȃ̂ŃA�u���ۂ������c
�A�u�Ȃ�n�G�ځA�n�G���ڂ܂ł̓n�G�Ɠ������ނȂ̂Ńn�G�Ƃ͐e�ʂ݂����Ȃ��ˁi�j
�����ԍ��F21964826
![]() 3�_
3�_
�ZJTB48����
���ʐ^�Ƃ������f�����������̂��y���ލs�ׂ͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�����v�����g�A�E�g���掆�ɏĂ��t����Ƃ��������Ƃ͖����Ȃ��ă}�C�N���`�b�v�݂����Ȕ��ɃR���p�N�g�Ȕ}�̂ɕۑ����ăX�}�z���i�������悤�Ȓ[���Ŋy���ނ悤�ɂȂ��Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�J�������ǂ�ǂ�y�ɂȂ��Ă����悤�ɁA�\���f�o�C�X���V���v�����y�ʂɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B�������C���[�W���Ă���͎̂������^�̓d�q�y�[�p�[�i�������J���[�j�B���d�̓��C�����X�ōs���̂ŏ[�d���s�v�B�d���͓����Ȃ̂ő��K���X�ɓ\��t���Ă��ǂ��B�ǎ���e�[�u���N���X�ɂ��ċC�ɓ������ʐ^�����C�A�E�g����̂��ǂ��ł��傤�B�B�e�����ł͂Ȃ��ӏ܂̎d������莩�R�x�������Ȃ��Ă����Ɨ\�z���܂��B
�Z��̎ʐ^�Ƃ���
�������͎ʐ^�B�e������ɂȂ��čs���Ǝv���B
�@�����A�����Ă��郉���[�J�[��]���B�e���ăW���X�s���̎ʐ^���B��Ă��N���J�߂Ă���Ȃ��ł��傤�B�����������Ă��u�����܂�͂ǂꂭ�炢�H�v�Ƃ�(^^;�B�Z�p���i�����������Ől�Ԃ̔\�͂��މ�����Ƃ����͎̂d���̂Ȃ����Ƃł��B�ł�����̐l�Ԃ��̂����̔\�͂�����Ă����Ƃ��Ă��A����͒P���ɑމ��Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B����ɔ_�ƂȂLj��肵�ĐH���������ł���\�͂��擾���Ă���̂ł�����B
�@
�@�ʐ^�����l�A�B�e�Z�p�������ʐ^�̏�肢����̑S�Ăł͂���܂���B�f���ʼn�����`�������Ƃ����z���������Ɏ�������̂����ʐ^�Ƃ�������Ƃ�����A�B�e�Z�p�̓J�����ɗ����ċL�^���ꂽ�L��]����̒����玩���Ȃ�ł͂̕\�����o���\�͂��Ƃ����̂��ߖ����� "�ʐ^�Ƃ����" �ɂȂ�̂�������܂���B�@�B���l�Ԃ̑���ɂ���Ă���邱�Ƃ����������A�@�B�ł͂ł��Ȃ��l�Ԃ̊��������ƂɎ��Ԃ�������]�T���ł���Ȃ�A������܂��ʐ^�̐i���ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F21964882
![]() 2�_
2�_
VR�ʐ^�W�����ł��ˁI
�I�����C���ʐ^�W�����B
�����ԍ��F21965017
![]() 2�_
2�_
�������v�����g�A�E�g���掆�ɏĂ��t����Ƃ��������Ƃ͖����Ȃ��ă}�C�N���`�b�v�݂����Ȕ��ɃR���p�N�g�Ȕ}�̂ɕۑ����ăX�}�z���i�������悤�Ȓ[���Ŋy���ނ悤�ɂȂ��Ȃ����Ǝv���܂��B
�Ђ�����y�ȕ��ɗ���ė��Ă�J������ŁA�|�p���Ƃ��ē��݂Ƃǂ܂�邩�ǂ��������́A�Ō�̉�邶��Ȃ����Ǝv���B
�v�����g����ƌ����͎̂B�e�҂ɂƂ��Ă̍ŏI�����B��̎�i���Ǝv���B
VR���̓d�q�f�o�C�X�Ŏ��R���݂ɉ摜�𑀂�̂��ǂ����u���Ⴀ�A�I���W�i���͂ǂ�H�v���ĕ����ꂽ�瓚�����Ȃ����̂͂ǂ����Ǝv���B
�����u���̋K�i�͌��ݑΉ����Ă���܂���v�@�@�u���̃T�[�r�X�͏I�����܂����v
���ĂȂ�̂�������Ȃ����̂ɔ��\�̎�i�������ɐ悪����悤�ɂ͎v���Ȃ��B
�����ԍ��F21966580
![]() 5�_
5�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
����Ƃ̈Ⴂ�͖��Â��u�Ԃő����鎖 |
�B�e�҂̋Z�ʂ�₤�J�������\�ɂ͌��E�������Ă��� |
�B�e�҂����̏u�Ԃ��G�ɂ������Ɖ]���ӎv�����͕₦�� |
����Ő�o���Ă��I�ԏœ_�����ƃA���O���A�\�}�͊e�X�̚n�D |
�����i�����_����
�����͊����̃J�����V�X�e����
���E�͌����Ă�Ɗ����Ă܂�
�t�@�C���_�[�A�Z���T�[�A�A�ʁAAF���\
���X�ɂ������サ�Ȃ���ł͖����ł��傤���H
�����ƈႤ�f�o�C�X�����܂��\���͗L��܂���
�ʐ^���̂��̂�
�G��̕��ʁA�͕�Ɏn�܂�\����]��
��l���m�A�g���̃R�~���j�e�B�ł̔�I���]����
SNS�ł̋��L�Ɖ]���R�~���j�P�[�V�����̗̈���L����c�[���ɕς��L��܂�
���Ȍ����~���[�����Ƃ����ړI�����͕ς��Ȃ��ł�����(��)
��Ƃ��Ă͍L�����Ă͂���Ǝv���܂���
��������^�p�̈�͋≖����ł��傤����
���̗���͕ς��Ȃ��A�����̃J�����E�G�̉��l�ς�
���X�ɕς���čs���ł��傤
���ׂ��炭������ˣ�̐���
���܂邾������ʔ����Ȃ��ł�����
���ǁA���\�҂���݂��Ă������͕ς��Ȃ��ł��傤
�B��Z�p��茩�đI�肷�鎖�����\�҂̊�ł�����
AI�����ꂷ���s����̂Ȃ�
�����A��ł͂Ȃ���ƂɈׂ�ł��傤
�����ԍ��F21966684�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
2018/07/16 12:24�i1�N�ȏ�O�j
���v�����g����ƌ����͎̂B�e�҂ɂƂ��Ă̍ŏI�����B��̎�i���Ǝv���B
�f����i�≹�y���́A�����O����ŏI���f�W�^���f�[�^�Ȃ̂���ʓI���Ǝv���܂����A�����͌|�p�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H�@��̂Ȃ���Ȃ̂ł��傤���H
���Ƃ��N���V�b�N���y���i���ʂɂ���Ďc����Ă�����́j�́A����Ӗ��u�y�T�v�Ƃ����K�i�Ɋ�ċL�^���ꂽ�u�f�[�^�v�Ȃ킯�ł����A�����V�傳��̉��߂ł́A����Ȃ��̂͌|�p�ł͂Ȃ��ƁB�i�j
�����ԍ��F21966916�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 7�_
7�_
�����܂���A�ɂƂ����ԐM���ǂ����Ă��܂��A��������̕��������X�����܂��̂ł��������B
����삳��
�@����10�N��A20�N����ʐ^�Ƃ�����͑����Ă���Ǝv���̂ł��������������Ƃ������ƂŁc(^^;
���Ђ�N�Ђ�N����
���X�}�z�J�������Εӕ����Ⴀ���
�������Ԃ̎����^�]�F���Z�p�ŗ��̔F���ł���̂�
�����z��ʊE�[�x�ʂ肵�ă{�J���Ȃ�ĊȒP���낤��
�����A�����������X��҂��Ă܂����A����ɏ�������邱�Ƃɂ��܂��B
�����\�z�̂��̂Q�ł��B
�Q�D�f���̂R�c�L�^����ʉ�����
�@����ł͏c���Q�����ł̋L�^�ł����A����ɋ���������Ɨ\�z���܂��B���̋Z�p�Ɋւ��Ă͎����^�]�Z�p����̗��p�����҂���܂��B��Ԃ��肻���Ȃ̂͂Ђ�N�Ђ�N�������ꂽ�X�e���I�J�����ɂ�鑪���A���ƈÏ��Ȃ烌�[�_�[�g�ɂ�鑪���A�y�т��̃n�C�u���b�h�B���Ɖߓn�I�ɂ̓p�i���i�߂Ă���4K�t�H�g�����p�����t�H�[�J�X�Z���N�g�̋Z�p���L�p�ł��傤�B
�@�僌���Y�̗��e�A��cm���ꂽ�ʒu�ɑ����p�̃����Y��z�u���āA�B�e���̓s�N�Z���P�ʂɔ�ʑ̂̋������L�^���܂��B�����Č������ɂ̓��C���Ƃ����ʑ̂�I���������͍i��l�������\�t�g��őI���i�X�}�z�p�\�t�g�Ȃ�"�{�P�"�Ƃ����X���C�_�[���ȁj����ƁA�V�~�����[�V�����ŋ����ɉ������{�P��������B
�@����Ȃ�AF1.4�Ƃ��̖��邢�E�傫���E�d���E�����ȃ����Y���w�����Ȃ��Ă��A�p���t�H�[�J�X�ŎB�e���Čォ��V�~�����[�V�����Ń{�J���Ηǂ��B�X�}�z�ł�F1.4��F1.0�̃{�P���������ꂽ�|�[�g���[�g�B�e���\�ɂȂ�܂��B�v����ɍi��̑I�����������ɍs�����オ������͗��邾�낤�Ƃ������Ƃł��B����͎ʐ^�Ƃ�����̐i���A����Ƃ��މ��ǂ���ł��傤���H
�����ԍ��F21967194
![]() 1�_
1�_
����ɊG��c�ł��A���ʁE���ʁE���n�c���낢�날��܂���ˁB
����Ɍ����Ɍ���L���L���I
�ʐ^�������ł���( *´䇁M)
�B�e�@�ނ�f�[�^�����낢�날���Ă��A�B���̈ӎ����悾���A���͂�����Ύ���蓾�܂��B
���A�n�G�g���O�T���̂����̂̓A�u�ł�(´��`; �O ;´��`)
�����ԍ��F21967798�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�Ȃɂ͂Ƃ�����
���̓X�e�L�Ȏ��ォ�Ǝv���܂��B
�≖����f�W�^���ɂȂ��Ă�
�s���s�ł��ˁB
�����ԍ��F21968277
![]() 1�_
1�_
����ł͏c���Q�����ł̋L�^�ł����A����ɋ���������Ɨ\�z���܂��B���̋Z�p�Ɋւ��Ă͎����^�]�Z�p����̗��p�����҂���܂��B��Ԃ��肻���Ȃ̂͂Ђ�N�Ђ�N�������ꂽ�X�e���I�J�����ɂ�鑪���A���ƈÏ��Ȃ烌�[�_�[�g�ɂ�鑪���A�y�т��̃n�C�u���b�h�B���Ɖߓn�I�ɂ̓p�i���i�߂Ă���4K�t�H�g�����p�����t�H�[�J�X�Z���N�g�̋Z�p���L�p�ł��傤�B
-----
��ʉ��͂܂������ǁA���i���͊��ɂ���Ă��ˁB
�v����ɍi��̑I�����������ɍs�����オ������͗��邾�낤�Ƃ������Ƃł��B����͎ʐ^�Ƃ�����̐i���A����Ƃ��މ��ǂ���ł��傤���H
------
�J�����̐i���ł����Ďʐ^�̐i���ł͖����ł��ˁB
�������މ��ł������B�Ⴆ���̋�������[�x�V�~�����[�V������g�ݑւ��āA�u���ɂ�����������O�̕��Ɠ����ʒu�Ɍ�����v�Ƃ��o������ʐ^�̐i���ƌ����邩���B
�������͎��Ԃɂ���Đ[�x��s���g�ʒu���ς�葱���āA�Î~��Ȃ̂ɓ��I�ȍ�i�ɂ���Ƃ��B
�[�x�V�~�����[�V������������Ȃ���SS�V�~�����[�V�����Ƃ����o����Ǝv���Ȃ��B
��̐i���Ƃ����̂͂悭������܂���ˁB
���ہA���܂ł��������v�����g���o�����ŁA�I�������L�������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21969059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����́B
�Z���ӂ�ׂȂƁ`�邳��
���t�H�g�V���b�v�Ƃ��g���ĊȒP�Ƀ��^�b�`�ł���悤�ɂȂ����̂͂������i����
�@�l�ɂ���Đ������͂��낢��ł��傤���ǁA�d������������ʂ��ĂȂ�����lj�������A�G�撲�ɂ�����Ɖ��ł�����߂��ċ≖����̐l�Ԃ��ƍŏ��͌˘f���܂����B�ł��̂����d�I���Ƃ����Ă����A���͎������B�e�����摜�f�ނ��g���Ȃ�n�j���ăX�^���X�ł��B�ꎞ���n�}�����V�C�����̉��H�ʐ^��\��܂��B����܂ʼnߓx�ȉ��H�͔ے�h�ł��������\�y���������̂ō��͗e�F�h�ł��B
�Z�h�m�[�}���E�J�X�^������
�������������R���ِ����������s�ςł͂Ȃ��̂ł�����A���̏�ł����ʐ^���B���J�������ł����Ƃ��Ă��A���̎ʐ^�̎��̂����Ƃ����ʐ^���B���\���͂ł�ł��傤���A�����ǂ����߂�̂���ƌ�����ł��傤�B
�@�J�����̐i���ɂ�胏���`�����Ō��삪�B���\�����������Ƃ��Ă��A���x�����n�ɑ����^��Ƃ��B�e�@��𑝂₷�J�͂�ɂ��܂Ȃ���A���ꂪ����邱�Ƃ������Ƃ���B���ɐ��ʂ��o�Ȃ������Ƃ��Ă�������Ђ�����߂Ď�Ƃ��Ċy���߂������Ă��Ƃł��ˁB
�Z�����삤�낤�낳��A��
�n�`�֘A�l�^�̓X�L�b�v�I
�i�C���t���Ȃ������j
�~�b�R������ւ̕ԐM�������Ȃ肻���Ȃ̂ň�U��܂��B
�����ԍ��F21970187
![]() 0�_
0�_
�����i�����_����
�l�I�ɂ͂����܂ł͑z�肵�Ă��Ȃ���
���m�N���v�����g�ł̏Ă����݂╢���Ă�����J���[�ł͓�������̂Łc
�����������x���̉��H�����R�ɂł��邾���ł������i���Ǝv���Ă܂���
�����ԍ��F21970203
![]() 1�_
1�_
�~�b�R������A�Q���܂Ƃ߃��X���܂��B
��VR�ʐ^�W��肽���I
�@VR�͎�������������܂��B�Ⴆ�Εx�m�R�̎R���ŏ����̏o��VR�ŎB�e�B�������n���Ɗ���̕\���������o�R�ҒB�A����U������Ƃ܂����Â����F�̋�B���������ʐ^�������B���Ă݂����ł��ˁB
�@�A�N�V�����J���n�ł̓{�`�{�`�o�Ă��Ă͂��܂����A�{�i�I�ȃX�`���B�e�ł͂܂��܂��L�����m�����̊�������̂����y�͂܂��܂�����Ċ����Ȃ̂��c�O�ł��B
�R�c�L�^�ɂ���
����ʉ��͂܂������ǁA���i���͊��ɂ���Ă��ˁB
�@����͒m��܂���ł����B�܂��f�l�������v�������Ƃł�������Ɏ�������Ă��Ă��s�v�c�ł͂���܂���ˁB
���������މ��ł������B�Ⴆ���̋�������[�x�V�~�����[�V������g�ݑւ��āA�u���ɂ�����������O�̕��Ɠ����ʒu�Ɍ�����v�Ƃ��o������ʐ^�̐i���ƌ����邩���B
�@�p�i�̃t�H�[�J�X�Z���N�g�Ȃ�A�Ԃ̐ڎʂƂ��ʼnԕق̈�ԉ������O�܂ŁA�{���Ȃ�ق�̐�mm�����Ȃ���ʊE�[�x�̒P�Ƃ̉摜���������ĉԑS�̂ɍ��ł������̂悤�ȉ摜���ł��Ȃ��̂��ȁH�i�����܂ł͂܂������ł��������j
�@���ƁA�ŋߗ��s��̓�AF�ɂ��Ă��A�Жڂ����łȂ��قȂ�t�H�[�J�X�̗��ڂɂ̓W���X�s���ő��̓{�J�����ċZ�@���\�ɂȂ�܂��B�P���̉摜�̒��ŕ����̃t�H�[�J�X�|�C���g�����݂����邱�Ƃ��ł���Ȃ�A�V�����ʐ^�\���������邱�Ƃł��傤�B
�����ԍ��F21970333
![]() 0�_
0�_
�����i�����_����
>VR�ʐ^�W
�Ⴆ�A�O�����h�L���j�I���Ƃ��Ƀh�[���Ǝ����̍�i������Ƃ��A�L���ʐ^��3D�������w�i�ɏ���Ƃ��A��ɓW���ꏊ�̍H�v�A�����Ǝ��R�ň����ŃR���e���c�Ƃ��Ėʔ����ʐ^�W����肽���ł��B
>�P���̉摜�̒��ŕ����̃t�H�[�J�X�|�C���g�����݂�����
�ǂ��ł��ˁI�ʔ����I
���f�[�^����Q�œ_�摜����鎖�ɖʔ���������܂��ˁB
�����ԍ��F21970490�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Z�����V�傳��
���v�����g����ƌ����͎̂B�e�҂ɂƂ��Ă̍ŏI�����B��̎�i���Ǝv���B
�@�v�����g���ƍ�i�ɂ���āA����I�Ԃ��������I�Ԃ����\�������ł̑I�����ɂȂ�܂��B���t�`��t���邩�t�`�Ȃ��ɂ��邩�B���ی������̈�ۂ��傫���ς��܂��B���Ƃ������T�C�Y���d�v�ł��B�Z��E�l�E���̂ǂ�ɂ��邩�B�G�悾�Ƃق�̐�cm�p�̍�i������ΕLj�ʂ̑�������B�T�C�Y���̂��\���̈�v�f�Ȃ�ł���ˁB�������ʐ^�����������́A�m���ɂ������ӎ����č�i������Ă܂����B
�@�|���č����ƁA������i���X�}�z�Ō���l������A��Ђ̈����m�[�gPC�̉t���Ō���l������B�L�����u���[�V�������L�b�`���s�������j�^�Ō���l������A50�C���`������4K�e���r�Ō���l�����邩������܂���i���Ƃ��Ă���������829����f�j�B�\���T�C�Y��f�B�X�v���C�̉掿�����鑤�̊��Ɋۓ������Ă��錻����āA���鑤�̎��R�x�͑��������ǁA��҂��`�������Ӑ}�̉������{���ɓ`����Ă��邱�Ƃ��B
�@�������������Ӗ��ł͎^���A�ł�VR���v�����g����o�J�o�J�����͏�̔�ł͂���܂���̂ŕ����I�ɂ͎^���ł��܂����A����ȊO�͓��ӂł��܂���B
�����ԍ��F21972378
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
> �|�������
�����́A�m���ɁA�\���̕������ɂ���ẮA�p���āA�s���R�ɂȂ����������Ǝv���܂��B
�����悤�Ȃ��Ƃ́A�����e�L�X�g�ɂ������āA�t�H���g���������ǂ��܂ŋK��ł��邩�A�Ƃ����̂�����܂��B
���̕ӂ��ɘa���鎎�݂̈�Ƃ��āA�f�[�^���g���A�\�����Ƃ���肵�āA�ł��\���Ӑ}�Ɋ����������_�����O������悤�Ȏ葱���i�v���O�����j��\�ߎd���ށA�Ƃ����l����������܂��B
�摜�f�[�^�ɂ��Ă��A�ǂ�����ꂽ���A������i�����āA�\���f�o�C�X�Ƀx�X�g�G�t�H�[�g��������A�ǂ�����Ă���ɍ���Ȃ��Ȃ�\������邱�Ƃ����ۂ���j�@�\������Ɨǂ��ł��ˁB
�����V�傳�Ꭶ���ꂽ�AVR�́A���鑤�Ɏ�̓I�ȃi�r�Q�[�V���������߂�̂ŁA�摜�i�ʐ^�j�ł��f���i����j�ł��Ȃ����̂��Ǝv���܂��B�����̎ʐ^�̂悤�ɁA�\���Ƃ��Ă̌|�p�����A�܂��H�A�F�߂��Ă��Ȃ����́B�Ȃ̂ŁA�I���W�i�������A�ʐ^�Ƃ͈قȂ�Ǝv���܂��B
���ꂪ�\���Ƃ��Ċm������ɂ́A�����̃u���[�N�X���[���K�v�ŁA����͂܂��o���Ă��Ȃ��A�Ƃ������ێ��̂��肩�ł͂Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21972444�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�Z�����̓���
�����X�ɂ������サ�Ȃ���ł͖����ł��傤���H
�@�Ȃ̂Őݒ��10�N��A20�N��A�����50�N��ɂ��Ă݂܂����B���܂Ŏ������������\�z��10����20�N�キ�炢��z�肵�Ă��܂��B
����Ƃ��Ă͍L�����Ă͂���Ǝv���܂���
�@������Ă��邱�ƂƎ�|�͈Ⴄ��������܂��A�����̏ꍇ�͓���ł����ǃc�@�C�X��Touit12mm�̍���UP������{���҂�8���͊C�O���[�U�[�ł����B���������̂��Đ����e���V�����オ��܂��B�����̍�i�������܂�������킯�ł��Ȃ��̂ɊC�O�ł��C�y�Ɍ��Ă��炦��A���邢�͂��̋t���Ă��Ƃ�����ŋN����̂ł�����A��Ƃ��Ă̊y���ݕ����L�����Ă���Ǝv���܂��B
��AI�����ꂷ���s����̂Ȃ�
�������A��ł͂Ȃ���ƂɈׂ�ł��傤
�@�J�����⌻���\�t�g���v���̎B�e�Z�p�E�����Z�p��AI�ő�s���Ă���鎞��͂�����K���ł��傤�B���[�U�[�̓v���J�����}���s���ĎB�e���ꂽ���̂悤�ȍŏ㋉�̍�i�����܂��B
�@PC�u�ޏ�������H�R�����Y�E�R�I�M�E�쑺����A�S�b�z�A���̑��e�C�X�g�ō�i�����Ă݂܂����B�v�A���i�u15�Ԗڂ̐X�R�哹���C�C�ˁA���ꃊ�r���O�ɏ��낤�B�ł��ޏ��ɑ���̂͏H�R�����Y�e�C�X�g�̂ŁB�v�݂����Ȗ����c
�@���͂�ʐ^�Ƃ�����͐�ŁH�`�F�X��AI�ɕ����Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ�����ʐ^�ł��N����̂��Ƃ�����A���̂����Ɏʐ^���y����ł������Ƃɂ��܂��傤(^^)
�����ԍ��F21974409
![]() 0�_
0�_
�ʐ^���X�g���[�g�Ɏʐ^�Ƃ��Ă̂ݐ����c���Ă��鐢�E�͑��ΓI�ɂ����͂��ŁA�����Q���̂������̂��Ƃ������B�l�͌�҂ł��B
���������A�ʐ^���|�p�ɗ^�����ő�̉e���́u���[�e�N���A�A�}�`���A���v�ł��B�܂�A�H�Ƌ@�B�Ƃ͊y����ׁA��������}��ׂ̕��ł���A���ꂪ�|�p�Ɉ�����ݓ��ꂽ�i�F�߂�ꂽ�j���A�|�p��i�ɂ�����Z�p�͂̔ے�ƂȂ�����ł��B
�|�p�ʐ^�o��ȍ~�Ɏc�����̂́u�V�����\�����ǂ����v�Ƃ������l�ςŁA�܂肻��͌|�p�ʐ^���̂��⏬����\���ł��镨�ł��������A���������͐i��ōs���ł��傤�B
�܂��A�P���Șb�A������ł��R�s�[�ł���ʐ^�Łu��_���v���������̂��������b�ł��B
��������A���ׂȗ��j���Y��Ȃ����E�i�u���O�R��AYouTube�R��j�ƂȂ������A���̕\���̐�i���͗��j������ɏؖ����Ă�����ŁA�ӏ܊��ł̍Č����]�X�͂ǂ��ł��ǂ��ł��傤�B
�������A�\���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���Ƃ��Ă̈����͏�L�̏Ƃ͕ʂɍ��܂�̂ł͖������Ǝv���܂��B
�܂�A�B�ꖳ��Ȃ͕̂��̂Ƃ��Ă̖ڂ̑O�Ɍ�������ʐ^�i�ʐ^��������ꂽ���j���̂��̂ł����āA�R���e���c�Ƃ��Ă̎ʐ^�ł͖����Ƃ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21975016�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�A���S�����I
�X�g���[�g�Ȏʐ^�\�����⏬������͔̂������Ȃ��^���ƕ��������Ƃ��Ă��A�ʂɔߒQ�������ł������āA���ꂩ�當�́A���͂���{�A�ƌ����悤�ɑS�̂Ƃ��ĉ�����\���ł���A����͂����Ɓu��_���v�Ƃ��đ��݂ł��܂��B
�H��܂̃j���[�X�ł��b��ɂȂ��Ă܂����A���ꎩ�́A���ׂȖ��ł��B���Ǒ��̂Ƃ��ėD��Ă��Ȃ���Ε]������Ȃ���ł����B
�t�ɁA�R���e���c�Ƃ��Ă̎ʐ^����_���Ƃ��ď��L�����咣�ł����Ƃ��āA���y�Ō���JASRAC�݂����Ȗ��H�͗ǂ����������B�|�p�Ƃ͐��n�ŗǂ���ˁ[���H�Ǝv���܂����A�D�ꂽ�C���[�W���[�J�[�Ƃ��Ă͂�����ł��d���͂���Ǝv���܂����ˁB
�����ԍ��F21975030�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���~�b�R������
> �S�̂Ƃ��ĉ�����\���ł���A����͂����Ɓu��_���v�Ƃ��đ��݂ł��܂��B
����́u�����v�͈̔͂Ɉ˂�Ǝv���܂��B
�Ꭶ���ꂽ�u�{�v�ɂ��Ă��A���{�ꓙ�ł́A�c�����Ɖ������������āA�R���e���c�̃��C�A�E�g�Ƃ��āA�c��������i�������\���s�j�݂����Ȑ�������ґ����t����ꍇ������܂��B
�������݂��ƁA�e���r�����́u�Ґ����v�Ƃ��ł��ˁB
�X���傳��i�Ƃ��������H�j�́A�ʐ^�i�摜�f�[�^�j�̕\���ɂ����āA�u�����v���甲�������镔���́u���l�v���Ă��Ă���悤�Ɋ����܂����B
�����ԍ��F21975200�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
>����́u�����v�͈̔͂Ɉ˂�Ǝv���܂��B
�ǁ[��[���ł��傤�H
>�u�����v���甲�������镔���́u���l�v���Ă��Ă���悤�Ɋ����܂����B
���\�Ȏ��������Ȃ�u����͊��Ⴂ����v�Ƃ������������̘b�ł��B
�l�̋��D�Ȃ�S�������ē��������ǂ���͎������鉿�l�ɑ��ē����Ɋ����郂�m�ł����āA�ʐ^�Ƃ����\���}�̂ՓI�ɘ_���Ă���Ȃ�A�ʐ^���|�p�ɂ����炵���j�A�|�p�Ƃ��Ă̎ʐ^�ɂ������炳�ꂽ�̂͊��ɉߋ��̎����Ȃ킯�ł�����A���̍�p���̂��ʐ^�̉��l���낤�ƌ������B
�`���I�ȍ��x�ɐ������ꂽ���p�I�|�p���A�J�����Ƃ����H�Ƌ@�B���ȒP�ɕ`�ʗ͂ŏ����āA����͑債���P�����Ȃ��o����悤�ɂȂ����B���̎ʐ^���܂��A���x�ɐ������ꂽ���p�̂悤�ɐU�镑�������Ă̂́A�\�����`�[������Ƃ��̂���ł���A�ʐ^�̕��ՓI�ȉ��l�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21976152�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���~�b�R������
> >����́u�����v�͈̔͂Ɉ˂�Ǝv���܂��B
>
> �ǁ[��[���ł��傤�H
���镨���I�ȕ\���t�H�[�}�b�g��O��ɂ����u��i�v�Ƃ����l���Ă݂�Ƃ킩��Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A�P�[�^�C�����Ƃ��ł��B�����PC�̑傫�ȉ�ʂŌ�����A�c�ȑ㕨�����o���Ǝv���̂ł����A�W�������Ƃ��Ċm�����܂����B
�o�ŎЂ̐l�B�́A�P���ɁA�A�ڏ����̒P�s�{���̂悤�Ȋ��o�Ŏ�舵�����Ƃ��āA���̎苭���ɋC�Â����悤�ł��B�܂�A�����R�[�h��Ƃ��Ẵe�L�X�g�݂̂́A�u�����v�����������Ă����킯�ł��B
���������u�����v�̉��l�̂��Ƃł��B
> ���̎ʐ^���܂��A���x�ɐ������ꂽ���p�̂悤�ɐU�镑�������Ă̂́A�\�����`�[������Ƃ��̂���ł���
�l�I�ȉ����Ƃ��ẮA�f�B�W�^���ɂȂ��ĉ����ς�������Ƃ����ƁA�u�f�ށv�Ɓu��i�v�̋��E�������āA��蓮�I�ɂȂ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�܂�A�f�[�^�Ƃ��ė��Ƃ��������̂��̂̑f�ސ����≖���͂邩�ɋ����Ȃ�A���̑��^����������]�n������ɍL�������A�Ǝv���܂��B������A�u�\���̌`�[���v�Ɗ���̂��K�����A�Ƃ����̂����̊�������a���ł��B
�u�f�ށv�Ɓu��i�v�ƌ����A���y�̊y���Ȃ��A�����ȑO�́A���C�u���t���S�Ăł���A�u�f�ށv�Ɓu��i�v�͖������������ƌ����܂��B�������w�Ƃ��̕������̊W���B
�y�������邱�ƂŁA�u�f�ށv�Ɓu��i�v���A���߂��ꂽ�Ǝv���܂��B�u�y���v�̉��t�́A����Ӗ��ŃR�s�[��������܂��A�y�����̕��̏��ʂƂ͈Ⴄ�Ӗ�������Ǝv���܂��B
�摜�ł��f�B�W�^�������ꂽ���f�[�^�Ƃ����\�����邱�Ƃ́A�y���Ɖ��t�Ɠ����悤�ȊW���Ǝv���܂��B
P.S.
�]�k���]�k�ł���
�Ñ�M���V���̘b�ł��B
�ŋ߂̘A���͕����ɋL�����Ƃ����ɖv�����āA�{���̌����̖L������Y��Ă���A�Q���킵���A�ƋL�����i������c���Ă���c�j�l�����邻���ł��B
> �l�̋��D�Ȃ�S�������ē��������ǂ���͎������鉿�l�ɑ��ē����Ɋ����郂�m�ł�����
��ǂ�ŁA���̈�b���v���o���܂��� (^_^;)
�����ԍ��F21976577�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����܂���A�܂��ŐV�̃��X�ǂ��t���܂����ԂƂ������ƂŁB
�Z�n�C�f�B�h�D���f�B�f�B����
�@�I�[�f�B�I�̐��E���ƁA�|�P�b�g���W�I�̃��m�����̏��^�X�s�[�J�[�ʼn��y�����Ƃ�����A�����܂œO��I�Ƀ`���[�j���O���ꂽ���Ő����t�ɋ߂������Œ����l������B����ŁA�Đ����ɒቹ���ɒ[�Ƀu�[�X�g����Ƃ��A�I���W�i���ɒ����łȂ��Ă��y���߂��OK���Ă����Đ����������ɍ��t���Ă���Ǝv���܂��B�y�����f�W�^���f�[�^�ł����A�w���҂�t�҂Ȃ�ł͂̕\��������邱�Ƃ����e����Ă��܂����A�������͂��ꎩ�̂��y����ł��܂���ˁB
�@�����������ʂŁA�f�W�^������̎ʐ^�͂܂��\�����@�E�]�����@�ɂ��āA��҂��ӏ܂��鑤���͍������Ċ��������܂��B�����V�傳��̂��ӌ������̍l����100%��v������̂ł͂���܂��A�S�ے肷����̂ł͂Ȃ��Ǝ��܂����B
�����ԍ��F21976675
![]() 1�_
1�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
�������肪�Ƃ��������܂��B�ǂ�������b�ł��ˁB
���p�A�O�����p�ɑς������i�Ƃ��č�Ƃ��l����ׂ��ƌ������ʂ�����܂����A���p�A�O�����p�����o������Ƃ̖��Ǝv���Ă܂��B
�܂��A�ł��A���́u�z��O�v�͗�R�Ƒ��݂��邯�ǂ��\���҂Ɗӏ҂̃M���b�v�Ȃ�Ă̂͂����ē�����O�̕��Ȃ̂ŁA����Ȃ͎̂ʐ^�ł킴�킴�����b�ł͖����Ɩl�͎v���Ă܂��B
�l�ԊW�Ƃ͑z��O�ƌ���̘A���ł��[��(^^;)
���C�u�ŁA�A���[�i�ȂƓ�K�O�K�Ȃ̃M���b�v�Ȃ�Ęb��ɂ�����܂���ˁB
������O������B
�������A�������悤�Ƃ���ӎu���̂͑��d���܂��B
�Ɩ���ӏ܋����̓v�����g���Ă��ӏ҂Ɉς˂����ŁA�u�v�����g���ŏI�v���Ă̂͌l�̂������ł���A���ߑ��Ȃ�����߂ł�����Ǝv���܂��B
�����i�����_����
�������̃y�[�X�Ł�
�����ԍ��F21977162�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���͂悤�������܂��B
��������ċx�݂ł��炭�s�݂ɂȂ�̂ł�����Ƌ삯���ŁB
�o��ł��������烌�X���܂��ˁB
�Z���i�e������
���B�e�@�ނ�f�[�^�����낢�날���Ă��A�B���̈ӎ����悾���A���͂�����Ύ���蓾�܂��B
�@������̒ʂ肾�Ǝv����ł����A�ŋ߂ӂƋ^��Ɏv���悤�ɂȂ����̂ł��B
�������N���A�ޏ��ɂ���5100�킹�A�ό��n�ɍs�����Ƃ��ȂLjꏏ�Ɏʐ^���B���Ă܂����B���i���A�����̃X�i�b�v�ʐ^���B���āAiPad�ɓ]�����Ċӏ܂���̂ł����c
�u���̎ʐ^�ǂ������B���������H�v
�@�ꏏ�ɕ����ē����ꏊ�ł����˂Ǝv�����V�[�����B��̂Ŏ����Ⴄ�͎̂d�����Ȃ��B���������X�Z���X�ŕ�����(^^;�B�����͎�ŎB���Ă�����肾���ǔޏ����Y�킾����B���Ă邾���B�ł����ʕ��͎�����������i�P�Ɏ���������Ȃ����ƌ���ꂽ��g���W������܂��j�B����Ă邱�Ƃ����ʕ��������ŕЕ��͎�ŕЕ��͎����Ȃ��A�����̂���Ă邱�Ƃ͖{���Ɏ�Ȃ낤���ƁH
�@�ꉞ���ʐ^���Ƃ��āA12mm�̒��L�p�ŎB������F1.4�Ŕw�i���ڂ������肵�āu����̓L�b�g�����Y����B��Ȃ����낤�v�Ɗ撣���Ă݂͂�̂ł����A����͏�肢����̖{������Ȃ����A���̂����X�}�z�ł������̂��̂��ʂ���悤�ɂȂ邾�낤�ƍl����Ƌ������Ȃ邾����B
�@�J�������i������قlj���Ȑl�̌��g�������Ȃ����A����Ȃ��Ƃ𐁂�����悤�ȃ��N���N����悤�Ȑi�����Ȃ����̂��H�B�Ƃ����̂����̃X���𗧂Ă����R�̂ЂƂł��B
�����ԍ��F21977381
![]() 1�_
1�_
���~�b�R������
> �u�v�����g���ŏI�v���Ă̂͌l�̂������ł���A���ߑ��Ȃ�����߂ł�����Ǝv���܂��B
�m���ɁA �u�v�����g���ŏI�v�Ƃ����̂́A�X�y�N�g���̏�̜��ӓI�Ɍ��߂��ꏊ�ɃN���A�J�b�g�ȁu���l�{�[�_�[���C���v��ݒ肷��s�ׂȂ̂ł����A�P���ɁA�����o�����Ƃ��A�X�y�N�g���̑��ݎ��̂��y�����邱�ƂɂȂ�Ƃ���A�Ȃ��Ȃ��A�Ǝv���܂��B
���l�{�[�_�[���C���i�Ɍ�������́j��ݒ肷��l�́A���i�̑��݁j���̂𗝉����Ă��Ȃ��̂��A�n���̖��̌��_�Ȃ̂��A�Ƃ����̂�����Ƃ͎v���܂���(^_^;)
> �����i�����_����
> �������̃y�[�X�Ł�
���Ȃ����ł��B
�����ԍ��F21977416�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���~�b�R������
> �|�p��i�ɂ�����Z�p�͂̔ے�ƂȂ�����ł��B
���́u�Z�p�́v�Ƃ����̂́A�i��j���s�����Ȃ��Z�p�͂̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H
���s�����Ȃ�����������A�ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����H
�������A���s����w�ԁA�Ƃ����̂͂����āA���s�̌J��Ԃ����琶�܂ꂽ�i�����j�Öْm�I�Ȃ��́i�o���l�j�������̌��ɂȂ邱�Ƃ�����Ƃ͎v���܂��B
���s���ɂ����Ȃ������ƂɈ��Z���Ă͂����Ȃ��킯�ŁA���̌��ʂ��A�u�V�����\�����ǂ����v�Ɍ��������̂��Ǝv���܂��B������u�⏬���v�Ƒ�����̂��낤���A�Ƃ������܂����B
P.S.
�|�p�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł����c
�Ȃ��A�����̎ʐ^�Z�p�Ȃ�āA�s���肩���p�\�Ȕ͈͂͞����������Ƃ���ŁA�m�����̂��߂ɂ́A��Ƃ̕����d�ꂽ�悤�ł��B�T���Ƃ��ł��B
�����̊G��������ł́A���p�I�Ȋϓ_���猩���Ă���Ǝv���܂��B
�l�I�Ȍo�����ƁA�O���I�ɂ́A�f�W�J���͈Ï��Ɏア����c�A�Ƃ������ƂŁA�≖�J�����������ďo�Ă܂����B���������A���ŎB���R�}���������Ă������B���ʁA�����܂�͋≖�̕����ǂ��������������܂����B
�����ԍ��F21977614�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
>�P���ɁA�����o�����Ƃ��A�X�y�N�g���̑��ݎ��̂��y�����邱�ƂɂȂ�Ƃ���A�Ȃ��Ȃ��A�Ǝv���܂��B
����A���߂�Ȃ����A�o���Ă͖�����ł��B
�l�̋C�����ƁA�ʐ^�_�̖{���̓Y���Ă��āA�C�����Ƃ��Ă͕����邯�ǁA��ʉ�����ƊԈႢ���Ƃ����w�E�ł��B
�l���v�����g���ꂽ�ʐ^���D�������ǁA����͌l�̎���Ǝv���܂��B���ɃE�F�b�g�v���Z�X�Œ��J�Ƀv�����g���ꂽ�ʐ^�̓R���e���c�Ƃ��Ă����u�㎿�ȕ��v�Ƃ��đf�G�ł��B
>���́u�Z�p�́v�Ƃ����̂́A�i��j���s�����Ȃ��Z�p�͂̂��Ƃł͂Ȃ��ł��傤���H
����͂���Ŗʔ����b�����ǁA�l���������̂͂����ƕ`���Z�p�Ƃ������ۓI�ȈӖ��ł��B
�܂�A�|�p�ʐ^�o��ȑO�̊G��ɂ́A�^���ł��Ȃ��I�����I�̑啔���ŁA�M�̃^�b�`�Ƃ��̍�Ƃ̋Z�p���x���Ă��B�ł��ʐ^���Ɠ�����ʑ̂��l�������`�ʗ͂ŎB����ŁA�����B�����̂��H���̎B�����̂��H�ŁA�]��������ł��B�����������l�ς��|�p�ʐ^���|�p�Ɏ��������ʂƂ��āA�����Z�p�������Ƃ����̃r�b�N���l�ԂƂ��X�|�[�c�Ɠ��������ŁA�|�p�Ƃ��Ă͕]���Ώۂ���O�ꂽ�Ƃ������ƁB
�����ԍ��F21978048�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�J���ɉi���ɒǂ��t���Ȃ��E�T�M�̋C���ł��B
�Zhirappa����
"�s���s"���Č��t�A���߂Ēm��܂����B
�I�[�f�B�I���J�������A�A�i���O����f�W�^���ɕω�������������A���^�C���Ɍo���ł������Ă����̂̓��b�L�[�Ȃ��ƂȂ̂�������܂���ˁB
�Z�~�b�R������
���Ⴆ�A�O�����h�L���j�I���Ƃ��Ƀh�[���Ǝ����̍�i������Ƃ��A�L���ʐ^��3D�������w�i�ɏ���Ƃ��A��ɓW���ꏊ�̍H�v�A�����Ǝ��R�ň����ŃR���e���c�Ƃ��Ėʔ����ʐ^�W����肽���ł��B
�@���������C���[�W�ł������B�����h�[���̓V����X�N���[���ɂ��Ęf���T���D���B�e�����ΐ���y����������i����I�ɂ��ĈӖ��j�ŕ\������Ƃ��y�������ł��B
�@VR�Ƃ����A���Z���̍�360�x�S���̎ʐ^���B���āA�v�����g�����ʐ^���Z���e�[�v�Ōq�����킹�čŌ�͉~����i�摜�͓����j�ɂ��Ċ����B���ɓ���˂������VR�V�сi�������̌��t�͂���܂���ł������j�����Ă܂����B�Ȃ̂Ŏ����ɂƂ���VR���Ă���قǖڐV�����Z�p�ł͂Ȃ���ł��B���������ʓ|���������Ƃ��ȒP�ɂȂ��������̑��݁B���̕ӂ������V�傳��Ƃ̊��o�̃Y���Ɍq�������̂��Ǝv���܂��B
�����f�[�^����Q�œ_�摜����鎖�ɖʔ���������܂��ˁB
�@�Z�@�Ƃ��Ă͌Â����炠�鑽�d�I���ł����A�b���\�R�}�̍����A�ʂł̎B�e�Ȃ�AF���[�h�F���i���ځj�Ȃ�Ă����ł������B����Ƀt�H�[�J�X�|�C���g�𑝂₵�āA���f������̕@���玨�܂ł����ł����w�i��F1.4�J���Ƃ��A1���̉摜�ɕ����̔�ʊE�[�x�����݂�����\�����\�Ȃ͂��B
�����߂���
���[�x�V�~�����[�V������������Ȃ���SS�V�~�����[�V�����Ƃ����o����Ǝv���Ȃ��B
�@�d�q�V���b�^�[���嗬�ɂȂ�ł��傤���獂��SS�Ő��b�ԘA���B�e���ďu�Ԃ��o�����悵�A���ɂȂт�����\�����邽�߂ɂP�b�Ƃ��̃X���[�V���b�^�[�i���\���琔�S���̉摜�������j���B�e��ɑI�Ԃ��Ƃ�4K�t�H�g�̉����Z�p�ʼn\�ɂȂ�Ǝv���܂��B���̍ۂ��ڂ�����SS1/1000�Ŕ��͂P�b�Ƃ��A������SS���P���̉摜�ɍ��݂�����\���Z�@���A���ł��傤�B����̓J�����̐i���{�ʐ^�̐i���Ƃ�����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F21978115
![]() 1�_
1�_
���~�b�R������
> ��ʉ�����ƊԈႢ���Ƃ����w�E�ł��B
�����͗����ł��B
�≖����ɂ́A���o�[�T��vs�l�K�v�����g�_���Ƃ����̂������������ŁA���̃T�C�g�ł��A���o�[�T���]�X�����������ɏo�����������܂����܂��B�s�ސT�Ȃ���A�v�킸�����Ă��܂��̂ł����c�B
�ł��A�����l���Ă݂�ƁA���Ȃ�傫�Ȗ��ɂ��āA���̕��Ȃ�̈ӌ����q�ׂĂ���ꂽ�̂��ȁA�Ƃ������S�Ƃ����������݂����Ȃ��̂ł��B
> �^���ł��Ȃ��I�����I�̑啔���ŁA�M�̃^�b�`�Ƃ��̍�Ƃ̋Z�p���x���Ă��B
�ʐ^�ƊG��̑��l���̌�����̈Ⴂ�̘b�ł��ˁB�������A�l�I�ɂ́A�S�������Ă���Ƃ���ł��B^_^;
�v����ɁA�����̈Ⴂ�ł����āA������ǂ����������̘b���Ǝv���܂��B�����Ɂu�⏬���v�݂����ȁi�����ȂׂĂ̗D����܂ށj�ϓ_���������ނ��Ƃɂ́A�ǂ����Ă��A��a���������Ă��܂��܂��B���t�K�ɓ˂����ނ悤�ł����c(^_^;)
�ςȘb�A�u�Ȃ�ł��Ӓ�c�v�Ɏʐ^���o�i���ꂽ�Ƃ��āA���̐^��̃`�F�b�N�|�C���g�́A�G��Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�͂��ł��B�g��ꂽ�@�ނƂ��`���ꂽ�i�ʂ荞�j���m�̃A���o�C�Ƃ��ގ��̗̂悤�Ȃ��̂͋��ʐ�������Ƃ��āA�G��ł悭����u�������G�ł��ˁB���܂�ɂ������v�݂����Ȃ̂́A�Ȃ����낤�ȁA�Ƃ������Ƃł��B��{�I�Ɂu�����B�����̂��H���̎B�����̂��H�v�ŁA�^�䔻�肪�����Ǝv���܂��B�u�����搶�Ȃ�A����������u���͂Ȃ��v�A�݂����Ȃ��Ƃ́A�����A�Ȃ��Ǝv���܂��B�^��ɂ͈Ⴂ���ǁA�Ԉ���Ďc�����{�c��i�̉\�����ے�ł��Ȃ��̂ŁB
���ǁA�����������́A�Ƃ��đ����邵���Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂��B
P.S.
�e�L�X�g�i���́j�̑��l���A�Ƃ����̂͂悭�m���Ă���Ǝv���܂����A�r�{�i�V�i���I�j�ɂȂ�ƁA�������a�炮�̂ŁA�t�F�[�Y�������Ȃ����S���M���A����Ȃ�ɁA�ł��邻���ł��i�v���b�g�Ƃ����C���L���X�g�̐ݒ�́A�\�߁A����Ƃ��āj�B�G��Ǝʐ^�̊W���A�ǂ����A�����悤�Ɋ����܂��B
�������A�m�x���C�Y����Ȃ�A�b�͕ʂ������ł��B(^_^;)
�����ԍ��F21978146�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
�⏬���Ƃ����Č��t�̎g�����ɂ́A���ӂ��K�v�ł��ˁB
�v�́A���ω��Ƃ��A�W�����Ƃ��A�L�����Ƃ��A�����������ł��B
�ꖇ�̎ʐ^�̉��l�͌���Ȃ������Ȃ邯�Ǎ\���v�f�Ƃ��Ă͂����Ɩ������ʂ������K�v�s���ɂȂ�悤�Ȏg�����B
����Ō����u���v�Ɓu��v�͂ǂ������D��Ă��邩�H�݂����Ȗڐ��Ȃ�Ė����B�ł������Ɂw�u���v�肪�Ƃ��x�Ƃ��w���߁u��v�x�Ƃ������͂����Ƒ��݂���B
����ւ����Ȃ��B�u��肪�Ƃ��v�u���߂��v���Ⴀ�Ӗ��𐬂��Ȃ��B
���������������������킯�ł��B
��������u���v���u���e�f�`!!�v�Ƃ��u���A�A�A�v�Ƃ��L�邯�ǂˁB
���̑S�̂ʼn�����\������ׂɁA�ꖇ�̉��l���Ⴍ�Ȃ鎖���⏬���ƌ����܂����B�n���ɂ��Ă�킯�ł͖�����ł���B
�����ԍ��F21978441�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�F����A�����́B
�ċx�݂̗��s����A���Ă����̂ő����܂��B
�@���̓~�b�R�����u�⏬���v�Ə����ꂽ���X�̓��e���ǂ������ł��ĂȂ������̂ł����A���̌�̂��ꂱ��ǂꂳ��Ƃ̂�����ǂ�ł��������Ɏ�|�������ł��܂����i���Ԃ�j�B����l�ƍl�����Ⴄ�̂��ȂƂ�������������܂����A�܂��͐�o���ĕԐM����`�ł͂Ȃ��A�ߖ����̗\�z�Ƃ����{�X���̎�|�ɉ����ď����Ă݂܂��B
���f�B�X�v���C�̕\���\�͂��Z���T�[�̋L�^�\�͂ɒǂ��t���i�܂��͒�����j
�@����͎B�e�\�͂ƕ\���\�͂����܂�ɂ��A���o�����X���Ǝv���܂��B�Z���T�[�̉𑜓x�̓f�W�J���n������QV-10��VGA�����A������PC���j�^��CRT���嗬�ł������A�Ⴆ��Nanao��17�C���`CRT T560i�̉𑜓x�A�掿�Ɣ�ׂăf�W�J�����̉𑜓x�E�掿�͈��|�I�ɗ���Ă��܂����B
�@���̌�A�Z���T�[�̉𑜓x�E�掿�̓C�P�C�P�h���h���Ői�����Ă����ƌ����Ԃɋt�]���āA����𑜓x�Ȃ�Q�疜��f�z���͓�����O�A�����@�Ȃ�S�疜��f�I�[�o�[�Ƃ�������ɂȂ�܂����B����f�B�X�v���C�̕��͂Ƃ����ƁA�X���ł�HD(216����f)��4K(829����f)�����X���x�H�B�𑜓x�Ɋւ��Ă͋L�^�\�͂ɑ��ĕ\���\�͂�1/10�ȉ��Ƃ��ɒ[�ɒႢ�Ƃ������тȎ��ゾ�ƌ����܂��B
�@�e���r���ɂ���Ƃ킩��₷���Ǝv���܂����A�̂�SD�掿�̃\�[�X��HD�𑜓x�̃e���r�Ō������u�̂͂���Ȃɉ掿�����������̂��v���������Ƃł��傤�B�܂�HD�����4K���j�^�Ō����Ⴄ�ƁuHD�掿�͍ŏ��͐����Ǝv��������4K�掿��m�����Ⴄ�Ƃ����߂�Ȃ��ȁv�ƂȂ�܂��B
�@���l�ɃJ�����̉掿�𐳓��ɕ]��������ɂ́u�L�^�\�́��\���\�́v�ł���K�v������̂��Ǝ����͍l���܂��B����́u�L�^�\��>>�\���\�́v�ł���ˁB����ȏł́u�X�}�z��D850�̉掿���債�ĕς��Ȃ��A�X�}�z�ŏ\�����ˁB�v�Ƃ����ӌ����������Ƃ��B
�@�����S�疜��f�I�[�o�[�������ƃs�N�Z�����{�ŕ\���ł���f�B�v���C������Ȃ�A���Ƃ�30�C���`���x�������Ƃ��Ă�D850�ŎB�����ʐ^�́u��̂ǂ��܂ōׂ����ʂ��Ă���̂��ꂪ�m��Ȃ��v�Ɗ����ł���ł��傤���A�X�}�z�̎ʐ^���Ɓu�p�b�ƌ����Y�킾���Ƃ�����Ƌ߂Â��Č�����N�������ŕ`�����G�݂����A����σf�W�C�`�͐����v�Ɛ����ɕ]�������Ǝv���܂��B
�@�f�W�J�����嗬�ɂȂ��Ă܂�10���N���炸�B����ł̓Z���T�[���̐i���������ł����A����͎ʐ^�̃f�W�^�����̉ߓn���ł����āA���㐔�\�N���x���ł͕\�����̐��\���L�^���ɒǂ��t���A�ǂ��z�����������Ɨ\�z���܂��i���̌��ɂ��Ă͊�]�̔�d���傫���ł����ǁj�B
�@���̑O��Ń~�b�R������A���ꂱ��ǂꂳ��̃��X�ɕԐM�������ł��B�ł́A�����̂Ƃ���͂��x�݂Ȃ����B
�����ԍ��F21990022
![]() 1�_
1�_
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�������悤�Ȃ��Ƃ́A�����e�L�X�g�ɂ������āA�t�H���g���������ǂ��܂ŋK��ł��邩�A�Ƃ����̂�����܂��B
�@�E�B���h�E�T�C�Y��t�H���g�T�C�Y�Ȃǂ����鑤�̊��ɍ��킹�Ď��R�ɑI�ׂ邱�Ƃ����������̑傫�Ȑi���ł����A������̂悤�Ƀt�H���g�̑I����C�A�E�g�ȂǁA�f�U�C�i�[�̈Ӑ}�荞�ނ��Ɓi�Č������邱�Ɓj������ɂȂ��Ă��܂����B�����b�g�����_�ɂ��Ȃ��Ă��܂����킯�ł��B
�@�y�[�W�f�U�C��������Ȃ����m�ɓ`����Z�p�Ƃ��Ă͊��ɃA�N���o�b�g������܂����A�ʏ��Web�u���E�U�ŃR���e���c�����邱�ƂɊ���Ă��܂�����ł́A�Ԃ��Ď��R�x���Ⴗ���Ėʓ|�Ƃ�����ۂ�������܂���B
�@�ŁA�ʐ^�����l�Ȃ�������ׂ��A���ꂪ�f�W�^������̎ʐ^�Ƃ������̂Ȃ̂��B�Ƃ����l���ɂ͎^�������˂܂��B�O���X�ŏ������ʂ�A����̉摜�\���Z�p���Ⴗ���邾���ł܂����_���o���ɂ͑����Ƃ����̂������̍l���B
�����̕ӂ��ɘa���鎎�݂̈�Ƃ��āA�f�[�^���g���A�\�����Ƃ���肵�āA�ł��\���Ӑ}�Ɋ����������_�����O������悤�Ȏ葱���i�v���O�����j��\�ߎd���ށA�Ƃ����l����������܂��B
�@�Ⴆ�Ύ����\���B�I�����C���V���b�s���O�ŏ��i��������Ō������Ƃ��Ă��A����̃u���E�U�ł͂ł��Ȃ��B�����}�ӁE�쒹�}�ӂ����Ď�����Ō��Ă݂������Ď��v���Ⴍ�Ȃ��ł��傤�B�F����͂����v�������Ƃ͂Ȃ��ł����H�B����Ȃ̏œ_�����E�B�e�����E�Z���T�𑜓x(dpi)�A�f�B�X�v���C�̉𑜓x(dpi)�̂S�̃p�����[�^������Ύ����ł���͂��BAdobe������J�������[�J�ɓ��������ċK�i�����āA���ł�Web�u���E�U������Ă���Ȃ����낤���B
�@���ꂪ�����ł���Ȃ�A�ʐ^�̊�]�ӏ܃T�C�Y���摜�ɖ��ߍ��ނ��Ƃ��\�ɂȂ�܂��B��掆����̗ǂ����f�W�^������ł����߂����߂̋Z�p�v�V�������Ă��ǂ��Ǝv���܂��B�ʐ^�̃f�W�^�����̎���͂܂��n�܂�������ŁA����̐i���ɂ��ʐ^���̂��̂̊T�O���Ƃ��Ă̊y���ݕ����ς���Ă�����̂Ɨ\�z���܂��B
�����ԍ��F21993794
![]() 0�_
0�_
���\���\�͂�1/10�ȉ���
����̕���\����A����\�x�[�X��4K�ɂȂ�����͈ӊO�Ə��Ȃ��ł��B
���Ƀe���r�����ł���A����\�x�[�X�ł�2K�ł���ӊO�ɒB��������炢�ł��B
�܂��A�≖�ʐ^�̎���͏o�͂̎嗬���≖�̃v�����g�ł������A�啔����L���ȂǃT�[�r�X�T�C�Y�ł�����A�ӏ܋����Ɗӏ܃T�C�Y�̊W�ŁA100~200���h�b�g(����f�ł͂���܂���)�������ȁH�ƁB
�����ԍ��F21994763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2018/07/28 23:27�i1�N�ȏ�O�j
����̕���\�̊ϓ_�ł�4K�͕K�v�Ȃ���������܂��A�s�N�Z������������Ζʐς�����̃_�C�i�~�b�N�����W��������̂ŁA���o�I�ɂ͂��Ȃ�̍����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Ƃ��f�W�^���T�E���h�ň�ʓI�ȃ_�C�i�~�b�N�����W16bit�́A�ʏ�̉��ʂł͖�肠��܂��A���ɏ����ȉ��ʂɂȂ�ƁA�l�Ԃ̊��o�̊��x�̂ق��������ĉ����̍r���ڗ��悤�ɂȂ�܂��B
���o�̏ꍇ���A�摜���̈Â������𒍎����铙����ƁA�͂����荷���o��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F21994819�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2018/07/28 23:29�i1�N�ȏ�O�j
���݂܂���A�_�C�i�~�b�N�����W��������Ƃ��������A�K����������Ƃ����ׂ��ł����ˁB
�����ԍ��F21994827�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���摜���̈Â������𒍎����铙����ƁA�͂����荷���o��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̃f�W�C�`�̍L���f�ł��犴�x�I�ɉ������ł����A
�L�^�Đ��K�i�ɂ����Ă��A����ł́u�K���L�^�̃P�A�v������܂���ˁB
Jpeg�ɋ߂��g�������RAW�����Ԉ�ʂ̎嗬�ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A�Õ��K���̂��߂̐�ΓI�Ȋ��x�s���̖��͉i���c�肻���H
�����ԍ��F21994870�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��
Jpeg�ɋ߂��g�������RAW
��
Jpeg�ɋ߂��g������Ŋ��uRAW�̐��f�[�^�ɋ߂��_�C�i�~�b�N�����W���ێ��ł���v�L�^�K�i
�����ԍ��F21994878�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����i�����_����
�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���ڂ̓��ɂȂ��Ă��邩�́A�H�Ȃ̂ł����c(^_^;)
�l����ׂ����ƂƂ��āA���̕�����w�E�̂���A����̉𑜓x�i�̌��E�j�Ƃ���������܂��B�A�b�v���̃��`�i�f�B�X�v���C�́A�܂��ɁA���������Ӗ��̃l�[�~���O�ł��B
�����Ȃ�Əo�Ă���̂��A�≖�v�����g����ł����������Ƃ��Ƃ͎v���܂����A��ڂł킩����́A�����ɒ��ڂ��ď��߂Ă킩����́A�̏����ł��B
�f�B�X�v���C�ƂȂ�ƁA�P���ɖڂ��߂Â��āA�Ƃ͍s���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�i��ʂɃi�r�Q�[�V�����ƌĂ��j�\���f�o�C�X���삪�K�v�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ��A�ʐ^�̊ӏ܁E�]���Ɂi�s�t�I�ȁj�ω��������炷�̂ł��傤���H
�ω��������炷�Ȃ�A���́A�v�����g���e�Ɍ����Ă���炵���A�t�H�g�R���ɂ��A�t�@�C�����e�̃J�e�S���[���݂����邩������܂���i�j
���邢�́A�X���傳�l���Ă�����悤�ɁH�A��҂��]�ފӏ܃X�^�C����\���f�o�C�X�ɋ�����������A�嗬�ɂȂ邩������܂���B
�Ȃ��A���p�I�L�^�Ƃ������Ƃ��ƁA�œ_�ʒu�̈ړ��Ƃ�8K�R���e���c�Ƃ��́A�܂��ɁA�i�r�Q�[�V�������肫�̂悤�ł��B
8K����̎g�����Ƃ��āA�B��Ă���f�w��������A�Ƃ��A����Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F21995426�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂��B
���̂��͒�̃����e���ő��X�ɐQ�Ă��܂����̂ő��N�����Ẵ��X�ł��B
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�����ڂ̓��ɂȂ��Ă��邩�́A�H�Ȃ̂ł����c(^_^;)
�@�����܂���A�����\���̘b�ւ̎����čs�����������߂��܂����B���ꂱ��ǂꂳ�����ꂽ�̂̓X�^�C���V�[�g�̋Z�p���g�����ĕ\�����ɉ����ē��I�Ƀ^�C�|�O���t�B�i���C�A�E�g���܂ށj�𐧌䂷��悤�ȃC���[�W���Ă��Ƃō����Ă�ł��傤���H�B�����\���͂�����t��Ɏ���āA���I����Ŋ��ɂ�炸�Œ�T�C�Y�ŕ\�����邱�Ƃ��\���낤�Ƃ����A�C�f�A�ł����B
���l����ׂ����ƂƂ��āA���̕�����w�E�̂���A����̉𑜓x�i�̌��E�j�Ƃ���������܂��B�A�b�v���̃��`�i�f�B�X�v���C�́A�܂��ɁA���������Ӗ��̃l�[�~���O�ł��B
����ɂ��Ă͈�U�߂�܂��B
�Z���肪�Ƃ��A���E����
�@������Ă��邱�Ƃ͈�ʘ_�Ƃ��Đ������̂ł��傤�B�Ƃł�55�C���`�̃e���r�Œn�f�W��u���[���C�ʼnf��Ƃ����܂����A�𑜊��ɂ��Ă͑S���s���͂���܂���B������PC�Ŏʐ^�Ƃ�������ꍇ�͕s���Ȃ�ł��i�������h�̂悤�ł����j�B���N31.5�C���`��4K�f�B�X�v���C�����܂������A����܂�26�C���`��HD�f�B�X�v���C�Ɣ�ׂĉ𑜊��͈��|�I�ɏオ���Ċ����B����HD�ɂ͖߂�܂���B
�@����ł���6500��24M�����8M�Ƀ_�E���R���o�[�g���ĕ\�����Ă���킯�ŁA�u�����L�^���ꂽ�����s�N�Z�����{�Ńg���~���O�����Ŋӏ܂ł����炠�ƂR�{�͊����ł���H�v�݂����Ȋ����ł��B�܂��A�����8K�����y���Ă����ΊT�ˉ����ł����A�]�ރ��[�U�[�����Ȃ��̂ł���Ύ��Ԃ������肻���ł��B
�@�ʐ^�Ɖf��̊ӏ܂̎d���͑S�R����āA�f�悾�Ɗ�{����Ĉ�苗���Ŋӏ܁B�ʐ^�͊G��Ɠ��l�A����đS�̂����遨�߂Â��ăf�B�e�[���������肵�܂��B���̎��A��f�������Ă��܂��̂͘_�O�A�ΐ��ɃA���`�G�C���A�X���������ă{�P���\���ɂȂ��Ă���̂��������Ⴄ�̂��C���B����Ċg�債�Č���Ηǂ��Ƃ����͕̂�����܂����A�ǂ����f�W�^������̕\���f�o�C�X�Ƃ̕t���������ɓ���߂Ă��Ȃ��悤�ł�(^^;
�@�܂��܂�������Ă��܂��A���̕ӂŁB
�����ԍ��F21997304
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
���f�B�X�v���C�ƂȂ�ƁA�P���ɖڂ��߂Â��āA�Ƃ͍s���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�i��ʂɃi�r�Q�[�V�����ƌĂ��j�\���f�o�C�X���삪�K�v�ɂȂ�܂��B���̂��Ƃ��A�ʐ^�̊ӏ܁E�]���Ɂi�s�t�I�ȁj�ω��������炷�̂ł��傤���H
�ȉ��̃��|�[�g���������A4000����f�N���X�̉摜�f�[�^��31.5�C���`��8K�f�B�X�v���C�ŕҏW������x�ł���A���ʂȃi�r�Q�[�V���������ł����p�ɂȂ�悤�ł��B
https://www.sankeibiz.jp/business/news/171212/bsb1712121100003-n1.htm
-----�L��������p��������-----
�Ⴆ���掿�̐l���ʐ^���k�����ĕ\������ƁA�ׂ����s���g�܂Ŋm�F�ł����A���{�ŕ\������Ɗ�̔����Ȃǂ̈ꕔ�����\�����ꂸ�ɑS�̂̍\�}�����߂Ȃ��B�k���Ɗg����J��Ԃ��Ȃ����Ƃ�����Ǝ��Ԃ��������ɁA�s���ڂ��ɋC�t���Ȃ��Ŕ[�i����~�X��U�����Ă��܂��B
-----�L��������p�����܂�-----
�@�����\�}�̎ʐ^���������B���Ĕ��u����������̂Ă悤�Ȃ�ĂƂ��������Ƃ����܂����A�ق�̏\�������`�F�b�N���邾���ł��ʓ|�Ō��ɂȂ�܂��B�v���Ȃ炱��𐔕S���A���疇�̉摜�ɑ��čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł������ςł��B��Ȃ̂ł��̍�Ƃ̌y���̂��߂�50���͏o���܂��A���𑜓x�ŎB�e�����摜��f�̂܂ܕ\���ł��郂�j�^�͂���ς薣�͓I�B���ƂQ-�R�N�����20���~�䂭�炢�܂ʼn������Ă���邩�ȁH�B���ꂭ�炢�Ȃ琥�������ł��B
�����܂���A�~�b�R�����������܂܂ł����܂��b�̗���Ő�ɂ�������B
�Z�n�C�f�B�h�D���f�B�f�B����
������̕���\�̊ϓ_�ł�4K�͕K�v�Ȃ���������܂��A�s�N�Z������������Ζʐς�����̃_�C�i�~�b�N�����W��������̂ŁA���o�I�ɂ͂��Ȃ�̍����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����݂܂���A�_�C�i�~�b�N�����W��������Ƃ��������A�K����������Ƃ����ׂ��ł����ˁB
�@���F�ł��ȃ��x���ł̃f�B�U�����O���\���Ă��Ƃł���ˁB�R�X�g�ƃ��\�[�X�̖�肪������Γ���̕���\���邱�Ƃ��A�����Ǝv���Ă܂��B���ς���Ɠ����F�ł��ψ�Ȃ̂Ə����m�C�Y������������̂ł͈�ۂ��ς��܂����A�s�N�Z���������Ă��܂��悤�ȃm�C�Y�͂��Ƃł�����Ӗ��͂��邩������܂���B���ƁA�v�����g�̌��ڎd�グ��������Ƃ��B�~�N�������x���ł̃f�R�{�R���V�~�����[�V�������ĉ摜�ɉA�e�������邱�Ƃŗ������������͋C���o���Ȃ�Ă��Ƃ��ł������B�f�o�C�X�̐i���ō�ƌ��������łȂ��\���̕����L����Ȃ炻����y���݂ł��B
�����ԍ��F21999292
![]() 0�_
0�_
��������PC�Ŏʐ^�Ƃ�������ꍇ�͕s���Ȃ�ł��i�������h�̂悤�ł����j�B���N31.5�C���`��4K�f�B�X�v���C�����܂���
�ߋ����ł�4K��8K�̏����ɂ͂Ȃ�܂��B
(�Y�t�摜�Ɛ}���̎��Q��)
��ʂ�31.5�^�̂Ƃ��A
�ӏ܋�������31.5cm(0.315m)�ł�����A����1.0��8K�����̂悤�ł��B
�����ԍ��F21999538�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���͂Ƃ��������܂��B
�Z���肪�Ƃ��A���E����
�@�������肪�Ƃ��������܂����B�����Ă݂��玩���̎������́A55�C���`�̃e���r�����鎞��2m�A31.5�C���`��PC�f�B�X�v���C�ʼn�ʑS�̂����鎞��60cm�A�e�L�X�g��ǂނƂ���40cm�A�摜�̃f�B�e�B�[�������鎞��30-20cm���炢�ł����B�����̊��o�͓��ʂ��������͖����悤�ň��S���܂����B
�Z�~�b�R������
�@�������ĂȂ���������܂��c
���|�p�ʐ^�o��ȍ~�Ɏc�����̂́u�V�����\�����ǂ����v�Ƃ������l�ςŁA�܂肻��͌|�p�ʐ^���̂��⏬����\���ł��镨�ł��������A���������͐i��ōs���ł��傤�B
�@�L���Ȋό��n�ɍs���Ďʐ^���B��Ƃ��i�Ⴆ�Δ����r�Ńp���t���b�g�ɂ��肪���ȌΖʂɎR�X���f�����ʐ^�Ƃ��j�A�u������B��Ӗ�������낤���H�v�Ǝv�����Ƃ���������܂��B����ȂƂ�"�V�����\��"��͍������肵�܂����A��������牽���Ƃ����l���������\�N���ςݏd�˂Ă����ƁA���Ǖ\���̃p�^�[���͏o�s�����Ă��܂��ł��傤�B
�Ƃ������Ƃ��w���Ă���A�ō����Ă܂����H(^^;
�ǂ��������y�U�ŋc�_�ł��铪��������Ă��Ȃ��悤�ł��������͈ꎞ�̒p�Ƃ������ƂŁB
�����ԍ��F22001199
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
> �ȉ��̃��|�[�g���������
���Љ�肪�Ƃ��������܂��B
���i�Ǝ��́H�j�������A�ڂ��Â炷���ƂőΏ��\�A�Ƃ������Ƃł��ˁB
8K�Ƃ����ƁA����̃C���[�W�ŁA�~�߂Ċg�債�Ĕ����A�݂����ȃC���[�W�����������̂ŁA�Î~��ł��A�i�r�Q�[�V�����K�{�A�Ȃ̂��ȁA�Ǝv���Ă��܂����B
���[�J�[�̕����A���������Ƃ���ɑi�����Ă��銴���Ȃ̂Łc^_^;
�����ԍ��F22001372�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
>�@�L���Ȋό��n�ɍs���Ďʐ^���B��Ƃ��i�Ⴆ�Δ����r�Ńp���t���b�g�ɂ��肪���ȌΖʂɎR�X���f�����ʐ^�Ƃ��j�A�u������B��Ӗ�������낤���H�v�Ǝv�����Ƃ���������܂��B����ȂƂ�"�V�����\��"��͍������肵�܂����A��������牽���Ƃ����l���������\�N���ςݏd�˂Ă����ƁA���Ǖ\���̃p�^�[���͏o�s�����Ă��܂��ł��傤�B
>�Ƃ������Ƃ��w���Ă���A�ō����Ă܂����H(^^;
�����Ă��܂��B�����Ă��܂����A�⏬���͉ߒ��ł����āA�ړI�ł͂Ȃ��ł���ˁB
�|�p�ł͖����ł����p���t���b�g���܂��ɂ��̌`�ŁA�ʐ^�ƕ��͂̑g�ݍ��킹�ň�̕\���`�ԂɂȂ��Ă��܂��ˁB
�ꖇ�̎ʐ^���f���炵�����ǂ����ł͂Ȃ��āA��i�S�̂̈ꕔ�Ƃ��Ăǂ��@�\���邩�H�Ƃ��������Ǝv���܂��B
��Ō����A�p�^�[�����o�s��������ł��p���t���b�g�ɂ͂��́u�炵���ʐ^�v���K�v�Ȗ�ł��B
�����ԍ��F22001494�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���~�b�R������
���ł��߂�Ȃ����c
> ��Ō����A�p�^�[�����o�s��������ł��p���t���b�g�ɂ͂��́u�炵���ʐ^�v���K�v�Ȗ�ł��B
����ŁA�p���t���b�g�̍쐬�́A���[�`�����[�N�I�Ȃ��̂ɂȂ�̂��A�⏬���A�Ƃ��������ŗǂ��ł����H
�ŁA�o�s�������u�͂��v�̐V�p�^�[����ǂ����߂�̂��A�n���ҁH
���̃R�R���́A
������āA�ʐ^�Ɍ��������Ƃ��ȁH�A�Ƃ����̂�����̂Łc(^_^;)
�����ԍ��F22001530�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
>����ŁA�p���t���b�g�̍쐬�́A���[�`�����[�N�I�Ȃ��̂ɂȂ�̂��A�⏬���A�Ƃ��������ŗǂ��ł����H
�Ⴂ�܂��B
���̈ꖇ�̎ʐ^�����C���ł͂Ȃ����A�ʐ^�̃v�����g�̐��x���K�{�ł͂Ȃ��A�����Ɍi���n���{�݂�炪�ʂ��Ă���Ƃ���������ł���A�p���t���b�g�̒��ŋ@�\����ƌ������Ƃł��B
>�ŁA�o�s�������u�͂��v�̐V�p�^�[����ǂ����߂�̂��A�n���ҁH
�R�����Ԉ����������O��Ƃ�������Ȃ̂ŁA�Ⴂ�܂��B
���A���������Č��t�����݂�ΐ������ᖳ���ł����ˁH
�l�͑n���҂̐��������Ă�����ł͖����̂ň������炸�B
�����ԍ��F22001989�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���~�b�R������
> �Ⴂ�܂��B
�����̓N���A�ɗ����ł����A�Ǝv���܂��B(^_^;)
���肪�Ƃ��������܂��B
�Ȃ��A�p�^�[�����o�s�������Ƃ��u�⏬���i�̃v���Z�X�j�v�Ȃ̂��H�A����͂Ȃ�ƂȂ��킩��Ƃ��āA�Ȃ��ʐ^�|�p�Ȃ̂��i�G�Ƃ����y�Ƃ����͂ł͂����Ȃ��̂��A�ǂ����H�j�A�́A�܂��A��`���������邽�߂ɁA�ق��Č��Ă��邱�Ƃɂ��܂��B
�����ԍ��F22002041�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ꂱ��ǂꂳ��
�Ƃ肠�����ǂ������ł�(^^;)
�ʐ^���ᖳ���Ă��ǂ��͍̂����ʐ^�ȍ~�̐��E������ł���B
���̐��E�̖�����������ŁA�ʐ^��������c�A�肷��̂͋�����Ȃ���Ȃ����ȁB
�������A�A�A�̌��t�I�т��܂��ꗂޗ\��w
�Љ�I�ɗe�F�����A�������A�̈Ӗ��ł��B
�����ԍ��F22002074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���b�̍���܂��Ă��݂܂���A�|�p�Ƃ͖����̎҂������̂��Ȃ�ł����A
�A�[�g�̐��E�̓u���b�N�z�[���̗l�ɐl�̎v�l�̖����̉\���������܂�(=^�E^=)�A
���̎���j���{�Ɏs���͗l�̉��G�����R�ƌ���A�����̕�����������ꂽ���ɋ������ւ����܂���A
�@�ނ��i������̂̓A�[�`�X�g�ɂƂ��ĕ����ȊO�̉����ł��Ȃ������ł�(*�E�ցE)(*-��-)(*�E�ցE)(*-��-)�A
�ŏI�I�ɋ@�ނ͗ǂ��M�̗l�ɁA�\���̂��߂̓���ł���l�̊������镨�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����ł�����B
�����ԍ��F22003801
![]() 2�_
2�_
������
�𑜓x�̘b�����������B
�@DELL��31.5�C���`8K���j�^�̉𑜓x��280dpi�A�ŋ߂̃X�}�z����200dpi�z�����������Ȃ��ł�����\���f�o�C�X�̍��𑜓x���͂��͂����H���B�����Ȃ�ƍŏ��ɂ��̉��b����̂͏o�ŁE���ŋƊE�ł��傤�B�G���ȂǂŎg����I�t�Z�b�g�����175��(�P�C���`��175�{�̐����`����)�Ȃ̂ň�����̉𑜓x���̂܂܂ŕ\���ł���350dpi�̃��j�^���܂����y����Ɨ\�z�BA4���J���������\�����ĉ𑜓x�͓����A���ҏW�\�t�g�̃p���b�g�ނ�\�������Ă�25�C���`���炢����Ώ\���B�����̉掿�������ʼn�ʂŊm�F�ł���̂ł�����A���͂�Z���̂��߂̈���͕s�v�ɂȂ�܂��B
�@����ȃv���̐��E�ɂ��܂�ĕi���̍��܂������j�^���A���y���i�ň�ʃ��[�U�ɒ����̂͂�����10�N�キ�炢�ł��傤���H�B���̉��b�͈�ʃ��[�U�[�ɂ�����͂��B�v�����g����ہA���ʎ��ƃC���N�W�F�b�g���̃C���N�̏������ɂ��掿�̍��A�t�H�g�y�[�p�[�̃����N�����E������̈Ⴂ�ɂ�鍷�Ȃǂ��v�����g�O�̃v���r���[�Ŋm�F�ł��܂��B�����������琡�~�߂Ŏ��ۂɂ̓v�����g�����Ɂu�Z�Z���[�J�[�̍ō����v�����g�y�[�p�[�́����d�グ�ŃV�~�����[�V���������摜�f�[�^�������i�v�݂����Ȋy���ݕ������܂�邩������܂���ˁB
�@���ꂪ���̋ߖ����\�z�ɂ��Ă̋�̓I�ȃC���[�W�ł��B
�����f�B�X�v���C�̕\���\�͂��Z���T�[�̋L�^�\�͂ɒǂ��t���i�܂��͒�����j
�����ԍ��F22004535
![]() 1�_
1�_
����_����Ƃ�[������
>�ŏI�I�ɋ@�ނ͗ǂ��M�̗l�ɁA�\���̂��߂̓���ł���l�̊������镨�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����ł�����B
�Ⴆ�A���C�J��135mm�ŋ@���͂āA�X�i�b�v�����̕���������L������A�j���[�J���[�͒������O�r�ɐ����u���ăX�i�b�v�������Ƃ�������A��������������Ă̕\���̕ω��Ƃ������j�I�����͂���킯�ł����A���̕ӂ̎��͂ǂ��l���܂����H
�@�ނ̐i������s���ď��߂Đ��܂ꂽ�\���͐l�̊������Ă����Ƃ͌����܂��H
�l�I�ɂ́u�e�N�m���W�[�Ɛl�v�u����Ɛl�v�݂����ȑΗ��\���ł͖����Ɗ����܂��B�e�N�m���W�[��������l����邱�ƂȂ̂ŁA�����ɐi�������Ȃ����ȂƁB
�����ԍ��F22004546�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
������
�Z��_����Ƃ�[������
���ɐ����ς���ĐQ�������O�Ȃ̂ŕԐM�͖��������܂��ˁB
�Z�~�b�R������
�i�ނǂ��납�P���ߖ߂��Ď���B
�����������A�ʐ^���|�p�ɗ^�����ő�̉e���́u���[�e�N���A�A�}�`���A���v�ł��B�܂�A�H�Ƌ@�B�Ƃ͊y����ׁA��������}��ׂ̕��ł���A���ꂪ�|�p�Ɉ�����ݓ��ꂽ�i�F�߂�ꂽ�j���A�|�p��i�ɂ�����Z�p�͂̔ے�ƂȂ�����ł��B
�@�����Ō��� "�Z�p��" �Ƃ� "�f�����g���Ď��o�I�ɐl�̐S�ɑi���������i��n��Z�p��" �̂��Ƃł���ˁB�Ⴆ�A���ꂽ���ɐV�q�R��Ԍ����ɍs���ĕx�m�R�ƎO�d���ƍ����t���[�����Ɏ��߂��ʐ^���B������F�����悤���Y��ȍ�i���ł��܂������ʂȋZ�p�͕s�v�A�X�}�z�ł��\���A�p���������ăt�H�g�R���ɂ��o���܂���B�������A���̐��Ɏʐ^�����݂��Ȃ������Ƃ��āA�K�C�h�u�b�N�������ɂ��̏ꏊ�������ŒT���o���A���ʂƂ��ł��̕��i��`������i���������Ƃ�����A�����"�|�p��i"�ɂȂ蓾���͂��ł��B�����������Ӗ��Ŏʐ^�͌|�p��N�H�����̂�������܂���B
�@�����A�����̍l����@"�ʐ^�̌|�p��"�@�͂��Ԃ̑����̕��Ƃ͈Ⴂ�܂��B�`���ɂ������܂������A�Ƃ���ꏊ��360�x�̉�p�A���b���琔���ԑ��݂������ŁA�J�����}�������߂��u�ԂƋ�Ԃ����B�I�o��t�H�[�J�[�X���J�����}���̈ӎu�Ō��߂�B���̏ꏊ�̎��ԁE��Ԃ̒��ɑ��݂���L��]��f�����̒�����A�������\�������������������c���A���̏����킬�����i�����ď��ʂ��ɒ[�ɐ�������j���ƂŁA���N���Ɏ���`����Z�p�B�e�L�X�g�̕����ɗႦ��Ɣo��݂����Ȃ��̂ł��傤���B
�@���̏ꏊ�ɍs�������]����V��܂ő҂Ƃ��̘J�͂�^�A��p��I�o�̑I���A������Ӑ}�����ʂ�L�^����Z�p�͂��Ђ�����߂������Ŏʐ^�Ƃ����̂͌|�p���肤��ƍl���Ă��܂��B�ʐ^�͍ŏI���ʂ����ł͂Ȃ���i�Ɏ���܂ł̃v���Z�X���܂߂ĕ]�������ׂ��Ƃ����̂����_�ł��B
�����ԍ��F22006505
![]() 1�_
1�_
���~�b�R������
���̗l�Ȗ}�l�����������̂͂������܂��Ǝv���̂ł����A
���I�ɃJ�����͂����܂ł�����Ǝv���Ă���܂��̂ŁA�l�Ɏg���Ă����Ǝv���܂��A
�X���^�C�̗l�ɃJ�������i�����鎖�ɂ���Ď��̗l�Ȏ҂ł��ʐ^���y���߂�悤�ɂȂ����A�̂��Ǝv���܂��A
�ʐ^���������ꂽ�����́A���ꂱ������M���ł�������Ύ�Ŏʐ^�ȂǎB��Ȃ��l�ł������A
�����ʐ^���B���ċ������X���f�W�J���������獘���������ł���( ´䇁M)�A
�����̎ʐ^�p�ƌ���ꂽ�Z�p�I�Ȏ��ƁA�����͕ʕ��Ƃ͎v���܂����A�A
����Ӗ��ŁA�g���Ղ��ǂ��J�����ƌ������A����l�̊�����{���Ă���ƌ����ʂ��L�邩���ł��ˁB
�����ԍ��F22006882
![]() 2�_
2�_
��ɏ����܂��T���������Ėڂ��o�߂܂����B
�Z��_����Ƃ�[������
�����̎���j���{�Ɏs���͗l�̉��G�����R�ƌ���A�����̕�����������ꂽ���ɋ������ւ����܂���A
�p�������Ȃ���j���{�̎s���͗l�̂��Ƃ͏��߂Ēm��܂����B
�����Ă������_���Ȃ�ł����u�{���Ȃ������̂��ȁH�v�Ƃ����̂������(^^;
���ŏI�I�ɋ@�ނ͗ǂ��M�̗l�ɁA�\���̂��߂̓���ł���l�̊������镨�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����ł�����B
�@����́A�����i�������ł����ė~�����Ƃ�����]�����ӎ��������Ƃ��Ă��܂܂�Ă���̂ł́H
�ߔN�ł̓h���[���ɂ���B���f�l�ɂ���y�ɂȂ������Ƃ������I�ɂ̓C���p�N�g���傫���ł��B�����h���[���̋L�����o�Ă܂�����ˁA�J�����̐i�����Ă͉̂𑜓x��Ï����\��UP�����ł͂Ȃ��A�B�e�G���A�̊g����Ă����v�f���������̂��Ƌ������ւ����܂���B
�@�₪�āAgoogle�Ƃ��ƘA�g���ċ�B��C���̂����߃X�|�b�g�Ƀh���[�����^��ŁA�h���[���ł����B��Ȃ��_�C�������h�x�m�Ⓙ�����[�C�̐����Ƃ����B�e�ł��鎞�オ����ł��傤�B�ł�����͖{���Ɏ����̍�i�ƌ�����̂��^��ł��B����ẴJ�������i��������̓J�����������̊������Ďʐ^���B��A�摜�f���Ɏ�����UP���Ă���āA���łɂ���̃R�����g��t���Ă���鎞�オ���邩���B��l�̃J�����}�����S���Ȃ��Ă������[�d���Đ��O�̎�l�D�݂̎ʐ^���B�葱���Ă��ꂽ�肵��(^^;�B�܂��A����͂���ōK���Ȃ��Ƃ�������܂��ǁc
�����ԍ��F22009173
![]() 1�_
1�_
���Q�D�f���̂R�c�L�^����ʉ�����
���@����ł͏c���Q�����ł̋L�^�ł����A����ɋ���������Ɨ\�z���܂��B���̋Z�p�Ɋւ��Ă͎����^�]�Z�p����̗��p�����҂���܂��B
���̎����^�]�p�̎B�e���f�q�ɂ����āA
�B�e�f�q�̃g�b�v���[�J�[�ł���\�j�[�́A�K�������������Ȃ������H
(���L�����N�Ŗ������Ă��Ȃ������A��������܂���(^^;)
http://biz-journal.jp/i/2018/08/post_24285.html
��
�R�y�[�W�ڂ́A�u���̎��^��������
���L���̎�|�͂Ȃ��Ȃ��Q�l�ɂȂ�Ƃ��낪����܂��B
(�u���҂������ŋ�����̂́A���X�C�ɂȂ�Ƃ���ł͂��邯���)
���������ނ́uF�^�[���v�ɎB���f�q�̑����֘A���������悤�Ɏv���܂��̂ŁA
��L�̍u���҂�����Ă��Ȃ������ŁA��ЂƂ��Ă̓P�A���Ă��邩������܂���̂ŁA�C�ɂȂ���͒��ׂĂ݂Ă��������B
�Ƃ���ŁA
�ÓT�I�ȁu���̎B�e�v�͉��x���Ǐ��I�u�[��������A���܂ł̓t�B�����J��������f��A
�f�W�J����r�f�I�J�����ɂ�����A
�e���r��r�f�I�J�����̋K�i�ɂ��Ȃ�܂������A�u���Ƃ̎��v�ɂ����ĕK�v�ȗ��v�̌p���v���o�����Ƀ|�V�����Ă��܂����͎̂��m�̒ʂ�ł��B
��L�̃����N�̎�|�ɂ��ւ��܂����A
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
���C�m�x�[�V�����Ƃ́A�u�����I�ɕ��y�����Z�p�A���i�A�T�[�r�X�v�ł���B
�����̋Z�p��i���A�����\�A���@�\�A���i���ł��邩�ǂ����͈�؊W�Ȃ��B
���u�����I�ɕ��y�������ǂ����v���d�v�Ȃ̂��B
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
��
��Ƃ��Ă̈Ӗ��Ȃǂɂ����Ă͑傫�Ȗ��ł����A
�y�u�����I�ɕ��y�������ǂ����v���d�v�z
�Ƃ́A���X�Â��̓r�f�I�f�b�L�́u�x�[�^�v�uVHS�v�A
�J�����I�ɂ͌ÓT�l�^�́A�u�����Ȃ�35mm���ȑO�̑傫�ȃJ�����K�i �v�u���C�J��(135)��35mm���v
�Ȃǂ��l������ƁA
�����̋Z�p��i���A�����\�A���@�\�A���i���ł��邩�ǂ�����
�y�x�z�I�ł́A�����z
�Ƃ͎v���܂����A�ނ���y�������Ă��Ȃ����z���傫�ȉe����^����悤�ł��B
���̂悤�Ȍo�܂��v���N�����ƁA
�����^�]�Z�p����̔h���͈ӊO�ɓ�Y�H
(�����^�]�֘A�́A�B���f�q�����łȂ��A�����B���f�q����́y���̓����Ə����Ɗ��p�z���ŏd�v�����H)
���u�����Ȃ�35mm���ȑO�̑傫�ȃJ�����K�i �v�u���C�J��(135)��35mm���v
���C�J��35mm���ȑO�ɁA35mm���Ɠ����܂��͂�菬�������i�͓o�ꂵ�Ă����悤�ł����A�������[�J�[���̗p����u�K�i�v�܂��͋K�i�ɋ߂��ł��������̂́A�����I�ɉe���͂����������Ɖ���́u�v�B
�����ԍ��F22009678�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����肪�Ƃ��A���E����
> ���̎����^�]�p�̎B�e���f�q�ɂ����āA
> �B�e�f�q�̃g�b�v���[�J�[�ł���\�j�[�́A�K�������������Ȃ������H
���͂����v���܂��B
���ہA���̕��ɒ����Ă��܂��B
�����ԂŎv�킵���Ȃ��Ƃ��낪�J���������ɖڂ������Ă����ۂ�����܂��BTowersemiconductor�Ƃ��ł��ˁB
�\�j�[���g�����Z�̊J�������Ŕ����̃Z�O�����g�������Ă��܂��B
����͒u���Ƃ���
���̎ʐ^�́A�ʂ��Ă�����̂ƊςĂ���l�̊W���̐��䂪����Ȃ̂ŁA���̂܂�܂ł͕��y���Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂��B
���ʂȂ�A�ǂ����猩�Ă����������ŃJ�����̑��݂���x�藣���������ɂȂ�̂ł����A���̉摜�Ƃ��f���͔�ʑ́A�J�����A�ς�l�A�Ƃ����W�����c���Ċς�ʒu�ɂ���Č��������傫���ς��܂��B
�������t��Ɏ���ăS�[�O���O��Ȃ炠�邩���H
�����^�]�̏ꍇ�́A���A���^�C�����䂠�肫���Ǝv���̂ŁA��������A�\���A�̃l�^�������o���͓̂���悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F22009736�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
> �ł�����͖{���Ɏ����̍�i�ƌ�����̂��^��ł��B
����́A�o�����摜�ɑΛ�����p�����悾�Ǝv���܂��B��{�I�ɂ́A�Ԃ̑��l�Ȃ胍�{�b�g�Ȃ肪�B�����摜�ł��A�W�ߕ��ɂ���ẮA�����̎ʐ^�i��i�j�ɂȂ蓾��Ǝv���Ă��܂��B
�A���\���W�[�̍�҂͒N�H�A�Ƃ�����܂��ˁB
> �J�����������̊������Ďʐ^���B��
���������摜���ǂ������̒��Ɏ�荞�ށi��荞�߂�j���A�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����̐L�ё�i������j�݂����Ȋ����ł��B
P.S.
�X���傳��́A�{��w�i�ʐ^�Ƃ̕��j�́A�����̓��A�������m�ł����H
�����B�e�œ���ꂽ�ʐ^���W�߂���i�ł��B
http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320092228
�����ԍ��F22009917�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���X�A���肪�Ƃ��������܂�(^^)
���̃��X�ƁA
��̃����N��R�y�[�W�ڂɂ���
���Ȃ��ł��H�@�v���Z�b�T��CIS�̉摜�f�[�^���g����h�̂ł���B
��
���ꂩ��`���b�g�u�ϑz�v���Ă݂܂�(^^;
(���̕���̐��m���͊F���ɓ������̂ŁA�}�g���Ɋw�p���x��~�Y�ƃ��x���ł̐��m����L���Ă�����̃��X����������̂ł���(^^;)
���āA
�q�g�Ɖ摜������̋��ʊT�O�̍ŏ��v�f�ɁA
���ʉ摜�ɑ��Ắu��f�v������܂��ˁB
�����W�Ŏ��߂����Ƃ��\�ł��B
���̂ɑ��Ă͎O�������W�ł��������킯�ł����A
�����^�]�ȍ~�ɂȂ�ΑΌ��ԂȂǂ́u��Ƃ��ē����v�킯�ł�����A
�O�������W�f�[�^���T���v�����O�̃^�C�~���O���Ɉ����Ă��邾���ł̓_���Ȃ̂�������܂���B
�}���s�\�ł����Ă��A���z�f�[�^����(���ʂ̕\����������������ǂ��A�F����Q�̂�����f�ȑ��ݔ����Ɏ��l(^^;)�ɂ����ẮA�������x������Ύ��Ԏ������܂߂��u�ŏ��\���v�f�v�ɂ���č\�������u���m�v���������Ƃ��o����̂ł��傤�B
�]���̉摜�F���Z�p�������ł́A�Ⴆ�A�ԑ��������Ă���l�Ɖԕ��̃v�����g�V���c�𒅂Ă���l�̋�ʂ��t���Ȃ����Ƃ����邩������܂���(^^;
���A���A�߂���P�[�X�ł����A�s�X�g���̊G���v�����g�̃V���c�𒅂Ă���l���A�e�����X�g���s�X�g���������Ă�����̂ƌ�F����āA�U���^AI�h���[���ɂ���ĎE�Q����Ă��܂��Ƃ�(TT)
�u����ȏꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂��H�v�ƍl����ƁA�X���Ⴂ���r�������Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�u�ϑz�v�͂��̂ւ�ɂ��܂�(^^;
�����ԍ��F22009928�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���Ԃ̑��l�Ȃ胍�{�b�g�Ȃ肪�B�����摜�ł��A�W�ߕ��ɂ���ẮA�����̎ʐ^�i��i�j�ɂȂ蓾��
���쌠��͂����Ȃ肻��~���̂悤�ł��B
�������Agoogle�ȂǂŏE���Ă����摜���A�ʂɋ����������ł́A�݂菈������Έ��p�Ȃ�Љ�A
�݂菈���Ă�������̃��m���Ƃ���Γ��p�ɉ߂��Ȃ��ł��傤�����(^^;
�����ԍ��F22009939�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����肪�Ƃ��A���E����
> �݂菈���Ă�������̃��m���Ƃ���Γ��p�ɉ߂��Ȃ��ł��傤�����(^^;
���́u���܂�ɂ��L�}�b�Ă���i����Ӗ��Ō�����Ă���j�v���p�̎�舵�����Ǝv���܂��B�p���f�B�ٔ��̘_�_�������H
�����ԍ��F22009967�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
�ʐ^�̌|�p���ƁA�|�p���ʐ^�ł��鎖�Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���܂����A���i�����_���l����Ǝ����_�Ƃ��Ă̌|�p���Ƃ������ߕt���Ȃ�A�Ȃ�قǁA�Ƃ����������ł��B
�����܂Ŏj���Ƃ��ĉߋ��Ɏw�E���ꂽ�b�ł��B
�l�̋C�t���ł������A�^�V�����b�ł������ł��B
�����ԍ��F22010020�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����_����Ƃ�[������
�l�I�ɂ͎B���Ă鎞�̊y�������d�v�ŁA�y���������Ȃ�ʐ^���~�߂܂��B
�Ȃ̂Ŏg���Ċy�����@�ނ��ō��ł��B������O�ł����ǂ�(^^;)
������O�ł����ǁA�l�I�ɂ͓���I�тɍł���ɂ��Ă��鎋�_�ł��B
�����ԍ��F22010058�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���p���f�B�ٔ��̘_�_�������H
�u�p���f�B�ٔ��v���{���ŁA�_�_�́u�����߂̎�i�v�����������H
�֑�
�p���f�B�Ƃ����킯�ł͂���܂��A
�A�}�{�N�̌��̉�ƁA
�T���O���X�������Ă���Ƃ��̃f�M���E�\�h�E�U�r��
�ŋ߂̎��I�ȁu������āA�p���f�B�H(^o^)�H�v�������肵�܂�(^^;
���ʔ�G�Ŏg�������ȁH
����A�u�̌����ڂ͂Ƃ������A�K�����������ăZ���t�����Ƃ�(^^;
�����ԍ��F22010243�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����܂���A����ς�~�b�R������̏����ꂽ���Ƃ������Ɨ����ł��Ă��Ȃ������悤�ł��B
���ꁫ�ɂ��ċ������킢�Ă����̂ł����A�l�b�g��Ɂu�����ǂނƂ킩���v�݂����ȃy�[�W����������Љ���Ȃ��ł��傤���B�Ȃ���Ώ��Ђł��B
�������܂Ŏj���Ƃ��ĉߋ��Ɏw�E���ꂽ�b�ł��B
�����ԍ��F22010350
![]() 1�_
1�_
�����肪�Ƃ��A���E����
> �]���̉摜�F���Z�p�������ł́A�Ⴆ�A�ԑ��������Ă���l�Ɖԕ��̃v�����g�V���c�𒅂Ă���l�̋�ʂ��t���Ȃ����Ƃ����邩������܂���(^^;
�ĊO�A�u�i�V���c�́j�����v�̈Ⴂ���环�ʂł���悤�ȋC�����܂��B
> ���A���A�߂���P�[�X�ł����A�s�X�g���̊G���v�����g�̃V���c�𒅂Ă���l���A�e�����X�g���s�X�g���������Ă�����̂ƌ�F����āA�U���^AI�h���[���ɂ���ĎE�Q����Ă��܂��Ƃ�(TT)
��˖h�~�Ɣ������x�̃g���[�h�I�t�ł͂Ȃ��ł��傤���H
��˂Ŕ���Q�i�G���W��[��������������������W�v���p�K���_���u�s�X�g���̊G���v�����g�̃V���c�𒅂Ă���v���i�l�Ԃ̏��j�Ɍ��f����Ė��p�ɒe��Q�����j�ƁA�h���[�������������̊��ĂƂ������Ƃł��B
�����ԍ��F22010410�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�Z���肪�Ƃ��A���E����
�@�����N��ǂ݂܂����B�g���j�g�������ߐM���ĉt���s�u�̕��y��ǂ߂Ȃ������\�j�[�A�E�H�[�N�}���ŊJ���s���iPod�{iTunes�ɂ�������D��ꂽ�\�j�[�B���ꂩ����J��Ԃ������ł��ˁB�����A�����^�]�Z�p�ɂ��Ă̓\�j�[���_�����Ă��������{�͊C�O���ɂ͎��������Ȃ��ł��傤�i�C�O���ƌR���ړI�̔�d���傫�����Ȃ̂Łj�B
�@�h���[���ł�����ɔ�s���Ȃ��烊�A���^�C����3D�}�b�v�����ď�Q��������Ȃ����s���鎞��B�Ԃł̕��y�������ł��傤�B�����A�Ԃ��Ǝ���͏�Q�����炯�ł�����A�h���[���ƈ���ĒP�Ƃł�3D�}�b�v�̐����ɂ͌��E������܂��B�M���@�E�d���E�X���Ȃǂɕt����ꂽ�J�����⑼�Ԃ̃J�����ƃ����N���āA���Ԓ��̎Ԃ̌��Ԃ����яo���l�Ԃ��@�m�ł���V�X�e�����₪�Ď��p�������ł��傤�B���{�����������Ă��������������s�s��p�ӂ��ĊJ����i�߂�Ώ��@�͂��邩������܂��A�v�������瑦���s���Ă��܂�������A�����J�ɂ͂���ς�G��Ȃ����ȁc
�@�J�����̘b�ɖ߂��ƁA3D�}�b�v�̐����Z�p�͎B�e�ɂ��L�p�Ȃ͂��ł��B�J�����P�Ƃł͂Ȃ����̋@��i�X�}�z�Ƃ��𗘗p�����T�u�J������T�e���C�g�J�����j�ƘA�g���āA�ʒu���͌덷��cm��GPS�����p�B�J�����}�����w�肵���^�[�Q�b�g�����A���^�C���ɒǏ]���ăt�H�[�J�V���O�Ȃǂɗ��p����B����AF�͔�ʑ̂��t���[�����ɓ����Ă��邱�Ƃ��O��ł����A�t���[���O�̔�ʑ̂̈ʒu���E�ړ��\�����O���@�킩�����ł���t���[�����ɓ��������_�Ŋ��ɍ��ł��Ă���Ȃ�Ă��Ƃ������ł���Ǝv���܂��B
�@�^�[�Q�b�g��j��E������E�B�e����B�ړI�͈Ⴆ�ǕK�v�ȋZ�p�͋��ʂł������ԊJ���X�s�[�h���������Ȏ����^�]����̗��p���������낤�Ƃ����̂������̗\�z�ł��B
�@���ƁA�����̃C���[�W����3D�L�^�ɂ��Ă͂����܂ŋL�^�܂łł����āA�\���ɂ��Ă͍��㐔�\�N���x���ł�2D���嗬���낤�Ǝv���Ă܂��B�\�������ʐ^�ɉ��s�����������Ƃ��āA��O�̉Ԃ��^�b�`����Ƃ��̉ԂɃt�H�[�J�X���āA���̐l���╗�i�Ƀ^�b�`����Ƃ�����Ƀt�H�[�J�X���ړ�����A����Ȏʐ^�̌������ł���悤�ɂȂ�Ɨ\�z���Ă��܂��B
�����ԍ��F22010490
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
> ����AF�͔�ʑ̂��t���[�����ɓ����Ă��邱�Ƃ��O��ł����A�t���[���O�̔�ʑ̂̈ʒu���E�ړ��\�����O���@�킩�����ł���t���[�����ɓ��������_�Ŋ��ɍ��ł��Ă���Ȃ�Ă��Ƃ������ł���Ǝv���܂��B
��p��B�e�����ɐ������|���ėǂ���A������A�����W�t�@�C���_�[�̏o��ڂ͂���Ǝv���܂��B
�B�e�p�J�����ł��A�m���A����p���Ƃ��������i���m�ɂ͗p�i�j���������悤�ȁH
���ʂ�CM�B��ɓ��������悤�Ȑ��i��������i�B
�����ԍ��F22010519�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�����������摜���ǂ������̒��Ɏ�荞�ށi��荞�߂�j���A�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�����̐L�ё�i������j�݂����Ȋ����ł��B
�@�����̊���������ɒǂ��t���Ď���邱�Ƃ��ł����Ȃ�A����͎����̍�i���肤����Ă��Ƃł��ˁB�@������͎̂����A�B�e�`�����X��^�����̂������ŎB�e���ʂ�F�߂��Ȃ�I�b�P�[���ė��_���ȁB
�����߂���
���ŁA�o�s�������u�͂��v�̐V�p�^�[����ǂ����߂�̂��A�n���ҁH
�@�ʐ^�Ɍ��炸�A���y�E�o��Ƃ��ł����ʂ̔Y�݂�����Ă������ł��B100�N��A�l�Ԃ��S�n�ǂ��Ɗ����郁���f�B�[��̎����o�s�����Ă��邩������Ȃ��B575�ŕ\���ł���S�Ă̕\�������݂��ĐV�����o��͐��ݏo���Ȃ���������Ȃ��B����A�����ł͖����ƐM�������ł��ˁB����H�A�܂��Y��������(^^;
������Ƙb��ς��܂��B
�@�s�v�c�Ȃ͎̂ʐ^�ɂ͓���ł�YouTube�݂����ȂP���̃T�[�r�X�����݂��Ȃ����ƁB����ł̓\�j�[�Ȃ烿�J�t�F�A�����[�J�[�����l�̃T�C�g������܂����A���icom�f���ɂ���R�̍��X�������݂��܂����A�͂����肢���ăo���o���̏�ԁB����r�b�O�f�[�^�̎���A�ގ������f�[�^�f�ނ݂͌��Ɉ����ꂠ���āA�o���o���������ʐ^�̃f�[�^��YouTube�̂悤�ɂP�̃T�[�r�X�ɏW�܂�n�߂�Ɨ\�z���܂��B
�@�B�e�����ʐ^�͎�����PC�ł͂Ȃ��C���X�^�ł��Ȃ��A���̎ʐ^�X�g���[�W�T�[�r�X��UP����̂��f�t�H���g�ƂȂ�B�����ł̓J���I�P�̎����̓_�̂悤�Ɏʐ^�ւ̕]���������B�u�J���Z�~���_�C�r���O���ď����𑨂���u�Ԃ̎ʐ^�B�\�}70�_�A�u�Ԃ̐���80�_�A�������ގ�������i������15���_���݂��܂��v�B��ҁu�K�r�[���I�v�݂����ȁB
�@�G��̂悤�ȍ�ғƓ��̕\�����@�ō����o���ɂ����ʐ^�̐��E�ł́A�V�����\���̑�������������������"�|�p�ʐ^��"�̑��_�ɂȂ邩���B�u���̏ꏊ�ł̂��̕\���͂��Ȃ��̍�i�����E�ŏ��߂Ăł��B�v�ƕ]�����ꂽ�Ȃ炻�̓��͏j�t�B�������������������Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22010587
![]() 0�_
0�_
�����i�����_����
> �s�v�c�Ȃ͎̂ʐ^�ɂ͓���ł�YouTube�݂����ȂP���̃T�[�r�X�����݂��Ȃ����ƁB
�Î~��ɑ�����v����������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�ȑO��Flickr���������̂ł����A���́A��������ł���Ǝv���܂��B���{��Ή����Ȃ��̂ŁA���{�ł̒m���x�͒Ⴂ�Ǝv���܂����B
Flickr���ƁA������A�u���̖��p�t�v�N���X�́A�S���S�����Ă��܂��i�j�B
�ǂ������ƌ����ƁA�d���̃I�t�@�[�҂��̐l���W�܂��Ă��銴���ł��B
> �u���̏ꏊ�ł̂��̕\���͂��Ȃ��̍�i�����E�ŏ��߂Ăł��B�v�ƕ]�����ꂽ�Ȃ炻�̓��͏j�t�B�������������������Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
���������̂́A�m���ɁA�A�����Ǝv���܂��B�R�����u�X�̗��x�������ƃ|�C���g�������A�Ƃ��ł��ˁ�
�����ԍ��F22010645�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
2018/08/05 19:43�i1�N�ȏ�O�j
�V�����\���Ƃ����̂́A���X�ɂ��Ċ����̊��������l��������������Ƃ��납�琶�܂�Ă����ł���ˁB
���i�R���̊F������A��x�����������Ȏʐ^�\�������ʂ肩�v�������ׂČ��Ă��������B�����Ƃ��̒��ɁA�����̃g�����h�ƂȂ�悤�ȕ\��������܂���B�i�j
�����ԍ��F22010666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����i�����_����
>�����܂���A����ς�~�b�R������̏����ꂽ���Ƃ������Ɨ����ł��Ă��Ȃ������悤�ł��B
�ӂ��ł��������A�������̐������肪�傫���ł��B
�l�b�g�ł͖����Đ\�����ł����A�A�A��
https://www.amazon.co.jp/%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE%E7%90%86%E8%AB%96-%E7%94%B2%E6%96%90-%E7%BE%A9%E6%98%8E/dp/4865030514
�l�����������͂܂�o�Ă܂��B�����Ƃ����Ȏ��ɐG����Ă��܂��B
���A����ڂ��̂��A�l�̗���͕s���Ȃ̂��A�ǂ݂Â炢�b�X(^^;)
�|�p�ƌ|�p�I���Čꊴ�������������Ă�Ǝv����ł���ˁB
�����I�����I�A���[�W���O�I�݂����ȂƂ���̓G���^����G���^�������ꂽ������W�������̕����D��Ă���Ǝv���܂��B�T�b�J�[�I��Ƃ��o�X�P�b�g�I��Ƃ��싅�I��Ƃ��G���^�������ꂽ�X�|�[�c�̐_���������v���[���u�|�p�I�v�Ƃ��]���Ă����{��I�ɂ͈�a�������ł���ˁB
���̌|�p�͂������i�����j���ʂ̓G���^���ɔC���Ă��܂��Ă���Ǝv���܂��B��G�c�Ȏ�������������ʐ^���Ăэ��ω����Ǝv���܂��B
���ʓI�ɂ����ƓN�w�Ƃ��w��Ƃ��u�i����炵���Ӗ��Łj���̒��̖��ɗ����Ȃ��v���m�ɂȂ邱�ƂŁA��菃���Ɍ|�p�ł��鎖��ڎw���Ă���C�����Ă��܂��B
�����܂Ō��t�̈Ӗ��Ƃ��Ăł��B
�Ⴆ�A�N�w�͖��ɗ��������ł����ǁA���ꂪ�N���̏����p����@�_�̌�돂�ɂȂ�Ȃ�A����͎v�z�ƂȂ���ɗ��Ƃ����悤�Ȏ��ł��B���ɗ����͓N�w�ɂƂ��Ăǂ��ł��ǂ����Ƃ������B
�|�p�Ō��o���ꂽ�V���ȕ��@�_�≿�l�ς��A�r�W�l�X��f�U�C����ʐ^�́u�A�C�f�A�̎�v�ɂȂ邱�Ƃ͂���ł��傤���ǁA�����ƌ|�p�͖��W�ɑ��݂��悤�Ƃ���Ƃ������ł��B
�܂�A�u�ʐ^�̌|�p���v�Ɓu�|�p�ʐ^�v�͊��ɑS���Ⴄ���m�ɂȂ�������Ă�ƌ������ƂŁA�u�ʐ^�̌|�p���v�Ɓu�|�p�I�v���[�v�͓����l�ȁu�^���̈��v���Ǝv���܂����A�Ⴂ�܂����H
>�@���̏ꏊ�ɍs�������]����V��܂ő҂Ƃ��̘J�͂�^�A��p��I�o�̑I���A������Ӑ}�����ʂ�L�^����Z�p�͂��Ђ�����߂������Ŏʐ^�Ƃ����̂͌|�p���肤��ƍl���Ă��܂��B
�u�|�p�Ƃ́����ł���v�����m�ȏ�ł́u�|�p���v�Ƃ����\�����Ƃ���ƁA�w�͂��^���|�p�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�M�����u���i�^�j��_�Ɓi�V��ƘJ�́j���|�p���H�Ƃ������ɁB
�Ȃ̂ŁA�����Ɍ|�p����]�����|�p�I��|�p���Ƃ������t�ł͂Ȃ��A�l�̗��z�I�ʐ^������铹������|�p�Ƃ������t�I�т����ꂽ�����ŁA���́u�|�p�v�Ǝʐ^���Z�H�����u�|�p�v�͕ʃ��m�ł��B
����܂���B
���܂�N�h�N�h���������炵���ŁA���������ł��ˁB
�ނނ��B
�����ԍ��F22011861�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�j�R���̓v����������ُ픽��(������)��F�����Ă��邪
3D�F������Λ����̒i���܂ŃJ�������c�����邩��
�䂪�q����Y��ȕەꂳ��ɘI�o��s���������������
�����ԍ��F22013169
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
���J�����������̊������Ďʐ^���B��A�摜�f���Ɏ�����UP���Ă���āA���łɂ���̃R�����g��t���Ă���鎞�オ���邩��
����Ȏ��オ�����Ƃ���A�l�Ԃ̓T�C�{�[�O�����@�B�ƗZ�����ċ��邩���ł���(-_-;)�A
�j���{�̎s���͗l�̉��A����L��܂����琥��������������������A
���R�ƗZ�����ׂ����Ă��A�ɗ͒��ȂNjȂ������܂܂Ŏ���|�����������������Ȃ������⒃���̒��ŁA
���ʂɍl����ΐ^�t�ȕ��������ɒ��a���Ȃ���S�̂��������āA�K�x�ȋْ������������܂����B
�A
���~�b�R������
�����ł��A��̐��E�ł͊y�����̏��������ł���(=^�E^=)�A
�J�����̃X�^�C���ł����A����̃f�U�C���͂��̌`�ɕK�R��������̂�����������ł���(=^�E^=)�A�A
����Ȃ�ɏd��������A�A�N�Z�T���[�ɂ͕s�����Ǝv���܂��̂ŁA�A
�J�b�R�ǂ��č����I�A���R���̌`�ɋ@�\����������ċ��Ȃ���Β����ɖO���邩���ł�( ´䇁M)�B
�A
�����ԍ��F22013426
![]() 1�_
1�_
���n�C�f�B�h�D���f�B�f�B����
>�V�����\���Ƃ����̂́A���X�ɂ��Ċ����̊��������l��������������Ƃ��납�琶�܂�Ă����ł���ˁB
�l�̗����ł͏����\�����قȂ��Ă��āA�V�����\���́u�V�����ƋC�t���v�K�v������킯�ł����A����ɂ͋C�t���ׂ̓��ݑ䂪�K�v�Ȃ�ł��B
���̓��ݑ�Ƃ́u���݂̕\���v�ł��B
�u���݂̕\���̔ے�v���u�����̌��݂̕\���̑g�ݍ��킹�v���B
�O�҂ł�����w�E�̒ʂ�}�W�����e�B����̌����Ƃ�������������܂��������Ƀ}�C�m���e�B����̔M��Ȏx���Ɏx�����܂��B��҂ł���������ƐZ������ł��傤�B
�r�����m�ȑS���V�����\���́u�V�����\���v�Ƃ͋C�t���ꂸ�ɏI���܂��B�l�̈ӎ��͈ꑫ��тɂ͐i�����Ȃ����A�����炱�����̒ʂ�u���݂̕\���v�ɒ��ӂ����͂ƂĂ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F22013613�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�l�����������̂ڂ��ăR�����g�A�����܂���B
> �ł�����͖{���Ɏ����̍�i�ƌ�����̂��^��ł��B
���ꂱ��ǂꂳ��������Ă�����p���ɒʂ��܂����A����������̍�i�ƌĂׂȂ������͉����H�Ƃ��������ɂ��āB
��͒��쌠�Ƃ������_�B
�l�I�ɂ���Ȃ��̂͗��v�▼���̊m�ۈȊO�̈Ӗ��͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���A�R�������R���̂悤�Ɋ����Ă��܂��Ă���\���ł��B�l��A�}�`���A�͎����̍�i�ŐH�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�������͖����킯�ŁA�u�ǂ��ł��ǂ��v�ƋC�t���ċ��݂ɂ��ׂ��Ɗ����܂��B�v���ɑ���A�h�o���e�[�W�ł���A�v���̐^����������K�v�͂���܂���B
������͂��̍�i�͒N����̂��Ƃ������_�B
��i����������ł���悤�ȏꍇ�A�����̍�i�ƌ����ėǂ����ǂ����B�v���x�̎��ӎ������鐅�������Ă��Ȃ��\���ł��B
�Ⴆ�A�������q���l�V���������������A�݂����Ȏ����ȁB������̂͋{��H����I�I�Ȃ�(�P�ށP)
�ŏI�I�ɁA�N����������H���Ď��͂ǂ��ł��ǂ��Ǝv���܂��B
�������q�������ƂƂ��ĕ]������Ă��邵�A�l�V���������z���������g�͍������E�ŌẨ�ЂƂ��đ������Ă܂��B
AI����i���B�����Ƃ��Ă�����ȑf���炵���摜�����W�ł���AI��������l�́A���ɂ��f���炵��AI�����邾�낤���B
�܂�A��i=��ƂƂ����Z�b�g�ŕ]�������K�v�͕K������������ł���ˁH�V�����C���[�W�V�����V�X�e���V������i�ޗ͂�����Έ��̍�i�ɌŎ�����K�v�͖����A�V�����ސl�Ƃ��Ă�����ł����̐l���g�Ɏ��v������܂��B��ŁA��i�͎�����Ďc���čs���B
���̂悤�ɍl����ƁA������������ƌ����Ȃ����R�ƌ����͍̂��i�����_����̌���ꂽ�l�ȁu�v���Z�X���d�v�v�ŁA�����Ɏ������g���[��������������Ƃ������ł͂Ȃ����ȂƁB
�����B�e�̐���Ȃǂ́A�u�������B���ĂȂ��v�ƕ]�����邩�u���������ݏo�����A�C�f�A���v�ƕ]�����邩�ŁA�[�����͈قȂ�ł��傤�B
�b������܂����A�l�͌|�p�����\�ȒP�ŋC�y�ȃ��m�ƍl���Ă��܂��B�����Ƃ�ł��Ȃ���������x�Ȏ��Ƃ��������A�u����Ȃ̂���Ă݂���A�ǂ��H�v�݂����ȍ�Ƃ̖₢�������y���ރ��m�ł͂Ȃ����ȂƁB
�T�����[�}������Ƃ����C���[�W�ɋ߂��ł�(^^;)
���t����Ȃ����番����ɂ������ǂˁB
�Ȃ�قǁI��肢�I�݂����Ȋ����B
�����ԍ��F22013638�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
�~�b�R������A�{�|�`��܂����B�Љ�肪�Ƃ��������܂����B
��͊y���ҏ����A�����������v���܂��B
�ŏ��ɏ������ʂ�A�z�����邾���Ȃ�^�_�ł��B����������ɂƂ��Ďʐ^�Ƃ�����̈��.�B
�����2700�~������������(^^;
���X�͂܂��ʓr�����܂��ˁB
�����ԍ��F22013666
![]() 0�_
0�_
�����i�����_����
���~�b�R������
> �~�b�R������A�{�|�`��܂����B�Љ�肪�Ƃ��������܂����B
�������ł�(^^)/
Kindle�ł��Ȃ��̂��c�O�c�B
������Ԃ̋ɂ͍S��l�Ȃ̂Łi�j�B
���̊��ɂ́A�J�����c�i�����j
�����ԍ��F22013908�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�����i�����_����
�����ꂱ��ǂꂳ��
>�{�|�`��܂����B
>�������ł�(^^)/
�����I
�y���݂ł��B
���������ǂ������ȁB�B�B��ɂ�����w
�����ԍ��F22013914�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���n�C�f�B�h�D���f�B�f�B����
> �����������Ȏʐ^�\��
�ǂ����u�����v�������ł��Ȃ��ʐ^�\���c^_^;
�����̌��E����邩��B�ʐ^���ς�u�ځv�́A�ʐ^���B��u�ځv�ł�����܂���ˁH
�����A���̎ʐ^����B��v���Z�X�ɂ��鍢����Ď��邩��u�����v�Ƃ����̂́A�|�p�\���Ƃ��Ė{���ɐ����̂��H�A�Ƃ����ƁA�l�I�ɂ́u�Ⴄ�v�ƌ��������Ƃ���ł��B
�Ⴆ�A���H����ȑf�ނ����Ƃ��˂������č��ꂽ�����͋M�d�ȕ����Ǝv���܂����A���ꂾ���Łu�|�p��i�v�Ƃ��Ẳ��l���������ƌ����ƁH
�ł��A���ʂȂ�̂Ă��镔���̉��l�������o�����A�Ƃ����A���܂�ɂ��L���ȁu���v
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%A0%E7%8E%89%E7%99%BD%E8%8F%9C
�́c�H
�Ƃ͌����A�������̂�3D�v�����^�[�ŁA��̐F�t���i�V�ō������ǂ��ł��傤���H
3D�v�����^�[�̋Z�p�J���Ƃ��Ă͐����͂��ł����A��i�H�Ƃ��ẮH
�����ԍ��F22014146�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
���X���傳��́A�{��w�i�ʐ^�Ƃ̕��j�́A�����̓��A�������m�ł����H
�������B�e�œ���ꂽ�ʐ^���W�߂���i�ł��B
�m��܂���ł����A�}���قŒT���Ă݂܂��ˁB1976�N���ă��C���_�[����ʓI�ł͂Ȃ���������A���l�B�e����ɂ͑����ȍH�v�Ɠw�͂��K�v�������Ǝv���܂��B�����B�e�̏ꍇ�A��Ԏז��Ȃ̂͐l�Ԃł�����A�ߖ����̓����B�e��AI���ڂ̃h���[���i��s�^�E�������s�^�E�����^�j���g�p���邱�Ǝ嗬�ɂȂ邩������܂���B�J�C�c�u����J���Z�~�������ŋ���ߐH����u�ԂƂ����A�A�}�`���A���[�U�[�i���w�������R�����Ƃ��ł��j�B�e�ł��鎞�オ����Ƃ����炻��͑f���炵�����Ƃł��B
�Z���肪�Ƃ��A���E����
���]���̉摜�F���Z�p�������ł́A�Ⴆ�A�ԑ��������Ă���l�Ɖԕ��̃v�����g�V���c�𒅂Ă���l�̋�ʂ��t���Ȃ����Ƃ����邩������܂���(^^;
�����A���A�߂���P�[�X�ł����A�s�X�g���̊G���v�����g�̃V���c�𒅂Ă���l���A�e�����X�g���s�X�g���������Ă�����̂ƌ�F����āA�U���^AI�h���[���ɂ���ĎE�Q����Ă��܂��Ƃ�(TT)
�@����͐l�ԂȂ�e�ՂɎ��ʂł��܂���ˁB�Ώە������ʂȂ̂����̕��Ȃ̂��A���Ƃ͎���̏i�V���c�ƔF���������ɂ���A��Ŏ����Ă���j�Ƃ��B������Ă�G�N�X�g���C���̃v���p�C���b�g���ƁA�P��O���o�C�N�ł��̑O���ԂƂ����ŁA�o�C�N�����݂��Ȃ����̂悤�ɎԊԂ��l�ߎn�߂��̂ŋ����ăv���p�C���b�g��������Ƃ�����܂��B������ĒP��Ȃ̂Ƒ����p�̃��[�_�[���g���ĂȂ��̂Ńo�C�N���O�Ԃɗn������ł��܂����̂������ƍl���Ă��܂��B��F���Ȃ����߂ɂ͋������̎擾�◧�̎�����Z�p���Œ���K�v�Ȃ̂��Ɗ����܂����B
�Z�~�b�R������
�@��ЋA��ɓd�Ԃœǂ�ł܂����ʔ������Ǔ���B�R��ȏ�ǂݕԂ��Ȃ��Ɨ����ł��Ȃ������ł��B
�����ԍ��F22019353
![]() 1�_
1�_
���͂▢���\�z�ƑS�R�W�����b�ŋ��k�ł����c
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�@�����o���������łɒm���Ă���}���قQ�����ɍs���Ă݂܂��������܂������u�����̓��v�̑����͖����B�ŁA�������l�b�g�Ō��������Ƃ��댩�������̂Ŗ�����ɍs�����Ƃɂ��܂����B�����A����Ɂu�l�͓����J�����}���v�{�� �w/���Ƃ����{���B�ǂ݂₷���{�������̂Ŏ肸�ɂ��̏�œǂ�ł��܂����B
http://www.owlet.net/hon/doubutucameraman/
�@���̒��Łu�����̓��v�̎B�e���̋�J�ɂ��Ă��q�ׂ��Ă��܂����B�����ʐ^�Ƃ�����̐ԊO���Z���T�[�Ń����[�Y���鑕�u���g���ĎB�e���Ă������Ƃ��Q�l�ɂ��āA���N�������Ė쐶�����p�̎B�e�@�ނ����삵���b�Ƃ��A���ɓǂ݂�����������܂����B�Ō�̕��ŁA�����̂��Ƃ��|�p�ƂƌĂԐl�����邪�A�����ł͂����v�������Ƃ͂Ȃ��B�����A����̂܂܂̎��R���B�e���邱�Ƃɐ���t�ŁA�|�p�Ȃ�čl����]�T�Ȃ�ĂȂ��B�����A�����ł����Ă����̎��R�̌��Č|�p�Ɗ�����Ȃ炻��͂��̐l�̒��ɂ���̂��낤�i���͂̍Č���20%���x�j�B�Ƃ������t����ۓI�ł����B�Ƃɂ��������ʐ^�ɑ���M�ӂ͔��[�����āA�����y���ĎB�e���邱�Ƃ������ɂȂ�������p��������������قǂł����B�쒹�ȂǓ����ʐ^���D���ȕ��ɂ͐���Ƃ������߂������{�ł��B
�����ԍ��F22024497
![]() 1�_
1�_
�Z�~�b�R������
�����A����ڂ��̂��A�l�̗���͕s���Ȃ̂��A�ǂ݂Â炢�b�X(^^;)
���������S�R�ǂݐi�߂��Ȃ���ł��B�u����͉��������Ă���낤�H�v�ƂR�s�ǂ�Q�s�߂�̌J��Ԃ��B���ɂȂ��ă����_���Ƀy�[�W��i�߂ė����ł������ȕ�����T���Q�[���݂����ɂȂ��Ă܂���(^^;
���u�|�p�Ƃ́����ł���v�����m�ȏ�ł́u�|�p���v�Ƃ����\�����Ƃ���ƁA�w�͂��^���|�p�̈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�M�����u���i�^�j��_�Ɓi�V��ƘJ�́j���|�p���H�Ƃ������ɁB
�@�����͎��������܂������ł��Ă��Ȃ��Ǝv���̂ł����A�ʐ^�̌|�p���Ƃ́u���R�⎖�ۂ����v���Ƃɂ���ƍl���Ă���̂ł��B���ԁE��ԁE�F�ʂ��i�荞�ލ�Ƃ���P�Ȃ郊�A���ł͂Ȃ��V�����f���ݏo�����Ƃ��ł���A�݂����ȁB�Ώۂ����݂��Ȃ��Ă��C�}�W�l�[�V���������ŕ`����G��ƈ���āA���Ȃ��Ƃ���ʑ̂����݂��Ȃ���Ύʐ^�ɂ͂Ȃ�܂���B�Ȃ̂ŃJ�����}�����C���[�W�����ʑ̂邽�߂̉^��J�͂���Ƃ̃C�}�W�l�[�V�����ɑ�����̂ł���Ȃ�A������|�p�̈ꕔ�ł����ėǂ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ƁB�����܂Ŏ��_�ŊF�������l����ׂ��Ƃ܂ł͎v���Ă܂���B�Ȃ̂ł��݂�����ȏ�@�艺���鉿�l�͖����ł��傤�B
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�@�����������R��܂����B���̒��ŁA�������B�e���Ă���Ƒ��肪������J�������ӎ����Ă���̂��킩��A���̂����ł��̎ʐ^���̂��̂��s���R�ɂȂ��Ă��܂��ƁB���ꂪ��̖��l�B�e�ɂȂ����Ă����̂��Ƃ��Ǝv���܂����A���A���Ȏ��R���B�e���悤�Ƃ���B�e�҂ƃJ�����̑��݂����̍�i��s���R�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��B���Ƃ�����Ȃ��̂ł��B�������\�z�����h���[�����g�����B�e���s���ɂ��Ă��A���̃h���[������A���ɋ[�Ԃ���ȂǍH�v���K�v�����ł��B
��������Ɨ\�z��������(^^)
�����ԍ��F22024568
![]() 1�_
1�_
���i�����_����
���������\�z�����h���[�����g�����B�e���s���ɂ��Ă��A���̃h���[������A���ɋ[�Ԃ���ȂǍH�v���K�v�����ł��B
�h���[�����ƁA���邳�����ĕq���ȓ����B�e�ɂ͓���Ǝv���܂��B
���R�̒��Ńh���[�����g���̂͂��邳���Č����ł��B
�����ԍ��F22025017
![]() 1�_
1�_
���͂悤�������܂�
�������삤�낤�낳��
���h���[�����ƁA���邳�����ĕq���ȓ����B�e�ɂ͓���Ǝv���܂��B
�@���̃h���[�����Ɩ����ł���ˁB����Łu�ߖ����̓����B�e�́v�Ƃ��܂����B�Ⴆ�g���{�݂����ɐÂ��ɔ�s������@�i�����ȏ��^�y�ʉ����K�v�ł����j���J�������A����Ɍx�����ꂸ�ɎB�e����Ƃ��\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�Ȃ��A�����̓h���[�����uAI���ڂ̖��l�@�v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���܂����B����������Ə��^���{�b�g�B�ړI�͖쐶�����ɐl�Ԃ�J�������ӎ��������Ɂi�X�g���X��^�����Ɂj���̐��Ԃ��B�e���邱�Ƃł��B�@��}�i�[�̖����o��ł��傤����A�q�������R�����łƂ������܂������A�����ɂ͒N�ł��ǂ��ł��g������Ă��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@�{��w���̖{�ɂ��ƁA���l�B�e�ł͂��炩���ߖɃJ�������Œ肵�A�����̒ʂ蓹�ɐԊO���Z���T���Z�b�g�B���䃆�j�b�g�͖ڗ����Ȃ��悤�ɓy�ɖ��߂��肵�������ł����A���T�T�r�^�C�v�̃h���[�����o�����Ƃ���A�����Ŗɓo���ĎB�e�ʒu���m�ۂ�����ɉ����Ĉʒu���ړ������邱�Ƃ��ł��܂��B�B�e��͗��ꂽ�ꏊ�ɂ���l�Ԃ̌��ɔ��ŕԂ��Ă���ƁB����Ȕ�s�{���s�^�̃h���[�����o����~�����ł��B
�����ԍ��F22025278
![]() 2�_
2�_
���i�����_����
���Ⴆ�g���{�݂����ɐÂ��ɔ�s������@���J�������A����Ɍx�����ꂸ�ɎB�e����Ƃ��\�ɂȂ�Ǝv���܂��B
����Ȃ�ʔ������ł��ˁB
�h���[���Ńg���{��ǂ�������B�e�Ƃ�����Ă݂����ł��I
�A���Ɠ����傫���ŁA�A���̑����ɓ����Ă����Ƃ��B
����ōl���Ă��������ł͖ʔ������͎̂B��܂���ˁB
���肪�Ƃ��������܂��B
�{��w����̖{�����Ă���͂��ł��E�E�E�B
�����ԍ��F22025729
![]() 2�_
2�_
�Z�����삤�낤�낳��
���A���Ɠ����傫���ŁA�A���̑����ɓ����Ă����Ƃ��B
�@VR�̃S�[�O���t���ĒT���ł�����Ǝv���ƃ��N���N���܂��ˁB���ɃZ���T�[�T�C�Y��1mm�p�Ƃ��āA24M�̃�6500�Ɠ����h�b�g�s�b�`���Ƃ���Ɖ𑜓x��250×250�ƕ�����Ȃ��B�ł��A�X�}�z���Ɠ����Z���T�[��2,000����f�Ƃ�����܂����獡�̋Z�p�ł�1000×1000���炢�̓C�P�����B�ۑ�͑������A�N�`���G�[�^�ƃo�b�e���ł��ˁB���̐������ƒ������ŏ��ɍ�肻���ȗ\���B�����ă��V�A���ÎE�p�ɗ��p����Ƃ�(^^;
�����ԍ��F22029181
![]() 1�_
1�_
�������삤�낤�낳��
�����i�����_����
�� �A���Ɠ����傫���ŁA�A���̑����ɓ����Ă����Ƃ��B
�������Ƃ̂ł��郌���Y�͂���܂��B
�ꉞ�́Aconsumer grade�i���[�Y�i�u���j�������ł��B
https://www.canonrumors.com/venus-optics-officially-announces-the-laowa-24mm-f-14-2x-macro-probe-lens-a-weird-but-revolutionary-lens-for-macro-videography/
����́A�ꌩ�̉��l����ł��B
�����ԍ��F22029200�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����i�����_����
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�������ă��V�A���ÎE�p�ɗ��p����Ƃ�(^^;
�͂͂́A���V�A�ł����B
���V�A�l�l�͐e�ōD���Ȃ̂ł����E�E�E�B
�ł��A�K�X�ǘR�ꌟ�����{�b�g�ȂǂňĊO�������p������邩���B
�����ꂱ��ǂꂳ��
���̃����Y�m���Ă܂����A����܂ł͒m��܂���ł����̂ŁA���肪�Ƃ��������܂��B
���挩�܂����A�������낢�ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���̃����Y�ł͂���܂��ALAOWA �̕ϑԃ����Y�����B�e�Ɏg���Ă��܂��B
�����ԍ��F22029833
![]() 1�_
1�_
�B�e���������m�ł���A�ʒu����܂�Ă���B
�]���̎ʐ^�ȏ�̊y���݂���������悤�ɂ��v���܂��B
�����ԍ��F22030145�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�Z���ꂱ��ǂꂳ��
�@�ʔ��������Y�̏Љ�肪�Ƃ��������܂��B���t�@�C�o�[�ʼn������Ȃ��Ă�����Ȃɒ����L�p�����Y��������Ă��Ƃɋ����܂����B���̃����Y1�{�����t���č����ʐ^�̗��ɏo��Ƃ��y������(^^)�B���{�ł��I�����p�X�Ȃ���邩�ȁH
�Z�����삤�낤�낳��
�@�����T�C�Y�̃h���[�������p�����ꂽ��A�ŏ��Ɏg���Ă��炢�����̂͏��E���w�Z�Ƃ��̋��猻��B�����≮�O��VR�S�[�O����t���ċa��I�ƍs�������ɂ��A���̎Љ�����w�ѐl�ԎЉ�Ɣ�r����J���L�������Ƃ��ł������B�̂̃T�C�Y������Ă��Љ�̒��Ő������i��J�j��m��A�������琶�������ɂ��悤�Ƃ����C���������܂��ΐ������ȁB�{��w���̏��ł��������ʐ^��ʂ��Ėҋחނ݂����ɔɐB�͂̎ア�������ɂ���Ƃ��P�Ȃ�ӏܗp�̓����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�������Ƃ��đ�Ɏv���Ă��炦��悤�ȗ͂ɂȂ肽���A�I�Ȃ��Ƃ�������Ă��Ċ������܂����B
�Z���[���[�������
���B�e���������m�ł���A�ʒu����܂�Ă���B
���]���̎ʐ^�ȏ�̊y���݂���������悤�ɂ��v���܂��B
�@���̂悤�ȃ��^�f�[�^�i�t�я��j�͂ǂ�ǂ��Ă����ł��傤�B�����A�B�e��̉摜�͂��ă^�O�Ȃǂ�t���Ă����Z�p�͂܂��܂����p���̓r���̂悤�ł��B
https://wired.jp/2018/01/18/gorillas-and-google-photos/
�@���^�f�[�^�̕t���͌�t�����B�e���̕�����萸�x�������܂�����A�B�e���̏������i�C�ۏ��Ƃ��j���ʑ̂̏��Ȃǁi���O�o�^�ς̉Ƒ���F�l�̃v���t�B�[���j���L�^����Ƃ��BGPS���瓾����B�e�ʒu�Ȃnjl���̗ނ͌�������J�ɂȂ�ɂ��Ă��A�Ӑ}�I�ɎB�e���ԁE�ʒu�̌��J�������邱�ƂŁA�u�������k�C�����s�ŎR�ɓo���Ă铯���ԑтɗF�B�`�͓c���ň���ł��v�Ƃ��A�u�����͎B�葹�˂����Ǔ����ꏊ�E���ԑтł���ȕ��i�����ꂽ�̂��v�Ǝ����������˂��E�B�蓦�����f���i�̌��j��Ǐ]���Ċy���߂�\�����߂Ă��܂��B
�@�ʐ^�Ƃ͂���P�̂������ȊO�ɂ��A�����L�^���ꂽ���^�f�[�^���g���ėl�X�Ȋϓ_����ގ��摜���ĂяW�߂Ċy���ގ��オ����̂��Ɨ\�z���܂��B
�����ԍ��F22031726
![]() 0�_
0�_
50�N��̎ʐ^�̊y���ݕ��́A�����炭�A���߂��y���ޕ����ɂ����Ⴄ��납�B
�B�����f�[�^���ω���������A�L�����y���ޓ���ɂȂ�A�C������B
�B�����Q�̎ʐ^��2����ɉԊJ���A�炢�Ă����Ԃ��͂��B
�Ȃ������v�������Ƃ����ƁA6���ɎB�����f�[�^��HD���������ł�(��)
�����ς����Ԃ����āA�����ȂƂ���ɍs���āA��������B������ł����ǁA���������A�Ȃ����X�b�L������(��)
�܂��A�O����n�߂܂���
�����ԍ��F22031817
![]() 2�_
2�_
�Z���肱�[����
���B�����f�[�^���ω���������A�L�����y���ޓ���ɂȂ�A�C������B
���B�����Q�̎ʐ^��2����ɉԊJ���A�炢�Ă����Ԃ��͂��B
�@�C�C�ł��ˁA�v���[���g�p�Ƃ��Ă������������B50�N��Ȃ�J���[�ō��掿�̓d�q�y�[�p�[������ł��傤����A���̉Ԃ̎ʐ^�����Ƃ��ɏ����ē��X�y���ނ��Ƃ��ł���ł��傤�B�Î~��̂悤�ł��Ċ�����̂悤�ɂ��U�����A�ʐ^�Ɠ���̋��E�������܂��ɂȂ��Ă����\�������܂��B�Ⴆ�ΉԂ̖����z�����߂ɒ����~�܂��Ă���ʐ^������A�Y�킾�ȂƎv���ċ߂��Ɋ��ƒ��������Ă��܂��B����Ȋώ@���̓K�ȋ������̍Č����܂߂� "�^�����L�^����̂��ʐ^�ł���" �Ȃ�Ď咣����l���o�Ă��邩���B
�����ԍ��F22033977
![]() 1�_
1�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�f�W�^�����J�����v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 7 | 2025/10/12 15:12:56 | |
| 7 | 2025/10/12 12:02:48 | |
| 12 | 2025/10/12 15:17:27 | |
| 21 | 2025/10/12 12:56:21 | |
| 4 | 2025/10/12 11:01:13 | |
| 0 | 2025/10/11 16:39:39 | |
| 5 | 2025/10/12 8:45:14 | |
| 5 | 2025/10/11 17:35:51 | |
| 6 | 2025/10/11 10:28:12 | |
| 7 | 2025/10/11 19:02:40 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zA20?
-
�yMy�R���N�V�����z30���\��
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j