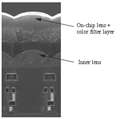D3 �{�f�B
�^�C�v�F���t ��f���F1287����f(����f)/1210����f(�L����f) �B���f�q�F�t���T�C�Y/36mm×23.9mm/CMOS �d�ʁF1240g
![]()

-
- �f�W�^�����J���� -��
- ���t�J���� -��
D3 �{�f�B�j�R��
�ň����i(�ō�)�F���i���̓o�^������܂��� �������F2007�N11��30��
�f�W�^�����J���� > �j�R�� > D3 �{�f�B
35mm�t���T�C�Y�ŗL��2481����f�ƍ����ǂݏo��������
�f�W�^�����t�J��������CMOS�C���[�W�Z���T�[ �J��
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200801/08-010/index.html
�������ł��B�j�R��D3X�̃Z���T�[�ɂ܂��ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F7316075
![]() 2�_
2�_
�����A����ᐦ���ł��ˁA��肪�Ƃ��������܂��B
���E�S��f�ǂݏo���@6.3frame/s�i12�r�b�g�j
2400����f�ŕb6�R�}�������Ⴂ�܂����A�o�b�t�@�������[��������Ԃ��ȁH
���E���ǂݏo��
������ăN���b�v�ł�����Ă��Ƃł����ˁB
������ɂ��Ă��A���悢�挻���������тĂ��܂����̂Ŋy���݂ł��B
�������A�����͂��ɂȂ��H
�����ԍ��F7316118
![]() 0�_
0�_
���R�A���Ђ̃A���t�@�ɂ��g���̂ł��傤�ˁB
�܂����A�j�R���ɓŌ������āE�E�E�i�H�j
�����ԍ��F7316132
![]() 0�_
0�_
�@�\�j�[�P�Ƃ̊J���ł��傤���H
�����ԍ��F7316201
![]() 1�_
1�_
���Ŕ��\����������̂��낤�H
�����ԍ��F7316359
![]() 0�_
0�_
�J����A/D��12bit�A6.3fps�ł����B�������ɂ������D300�̂悤��14bit�ŁA�Ƃ͂����܂���ˁB1.5fps�ł͂�����ƁBD3X�͑䐔���o��Ƃ��v���Ȃ��̂ł���Ɍ��܂�ł����ˁH
�����ԍ��F7316367
![]() 0�_
0�_
�����Ŕ��\����������̂��낤�H
�@�N�x���Ɍ����Ă���Ȃ��ł����H
�����ԍ��F7316425
![]() 1�_
1�_
D3��CMOS�́A�j�R���v�A�\�j�[�����ł������A����͐v��
�\�j�[�Ƃ������ł����ˁB
���ꂪD3X�ɍڂ�Ƃ�����ACMOS�̐v�͎��ۂ̂Ƃ���A�ǂ���
����Ă���̂�������Ȃ��Ƃ������E�E�E
���ǁA�v�͂ǂ�������Ă��W�Ȃ���������܂���� (^^;
�����ԍ��F7316519
![]() 0�_
0�_
�\�j�[�̃t���b�O�V�b�v�@�ɂ��̗p������ł��傤�ˁB�c�@�C�X�P�����Y�Ƃ��̂b�l�n�r�������琦���掿�ɂȂ肻���ł��B�c�R�w�͈�̂�������ʂɂȂ��ł��傤�B
�e�w�����łɂ͍ڂ肻�����Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F7316638
![]() 0�_
0�_
�h�{�N���ɗʎY�h�Ƃ��Ă���܂�����AD3X�̏��Ȃ��Ƃ��N�������͉\�̂悤�ł��ˁi�O�O
�����ԍ��F7316647
![]() 0�_
0�_
�B���f�q�̎���i���o������{�f�B�Ƃ̗Z�������Ɉ�̂ǂ̈ʎ��Ԃ�v������̂Ȃ̂ł��傤��(^^�U
�X�Ȃ�t���T�C�Y�f�W�J���̓o�ꂪ�y���݂ł���(^^
�����ԍ��F7316657
![]() 0�_
0�_
����͊�{�I�ɂ̓�900�p�̑f�q�ł���ˁB
���̓j�R�����g���̂��A�g���Ƃ�����c3�w�������e�w�Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃł����ˁB
�܂��g���Ƃ������Ƃ�O��ɂ���Ȃ�A�ǂ���ɍڂ��Ă���̂ł��傤�B
�c3�w���L�͂ƌ��Ă���l���������ł����A
���܂Ńj�R���̃n�C�G���h�̑f�q�͑��@��Ƃ̋��p���������Ƃ�����܂���B
�����12bitRAW�Ƃ����̂��D�ɗ����܂���B
�܂�����Ȕ��\�����邩��ɂ́A���Ђɂ�����u�ėp�v�f�q�Ȃ͂��ŁA�T���v�����i�����\����邾�낤���A
�܂���900�̉��i�͉���܂��A30�`40���������ꍇ�ɂ̓j�R�����c3�w��60���̒l��t����̂�
����Ȃ�܂��ˁB�i���l�̋@��Ɠ����f�q�ł́H�H�j
��������łe�w�@�̑f�q�Ƃ��Ă͍���f�ɐU�肷���Ȋ�������܂��B
�����Y�ւ̗v�����������ł��傤���A�t�@�C���T�C�Y�I�ɂ������ɂ������m�ɂȂ�܂��ˁB
�i�l�I�ɂ́j����ł������炪�{���ƌ��܂����A�ǂ��ł��傤���H
�����ԍ��F7316671
![]() 5�_
5�_
NIKON D3�AD300
PENTAX K20D
OLYMPUS E-3
�Ɗe�Ђ̃t���O�V�b�v�@����������ĊԂ��Ȃ����̎����ɔ��\����Ƃ́E�E�E
SONY���Ȃ��Ȃ������ł��ˁI
�����ԍ��F7316686
![]() 0�_
0�_
�c�R�O�O�̑f�q��SONY���ł���
�c�R�̑f�q��SONY���ł͂Ȃ��Ƃ̉\�ł��B�i�����Ȃ�Ƃc�R�w�̖ڂ��Ȃ��j
�j�R�����c�R�p�ɔ����Ă����Ǝv���ĊJ����i�߂���
�����Ă��炦�Ȃ������̂ŊO�̂����̂���
�i�̗p���ꂽ��Ɛ�_�����낤�Ɂj
�@
�����ԍ��F7316886
![]() 5�_
5�_
������ɂ��Ă��L���m������ɂƂ��Ă͋��Ђł��傤�B
�X�O���~��1Ds3������Ȃ��Ȃ����Ⴄ�����ˁB
�����ԍ��F7316907
![]() 1�_
1�_
���悢��\�j�[���t���T�C�Y�ł��ˁ`�I
2400����f�Ƃ������ƂŁA���܂ł̃f�W�^�����ł̓g�b�v�ɂȂ�̂ł��傤���B
�y���݂ł���^^
�����ԍ��F7316926
![]() 0�_
0�_
��f�������������Ⴂ�܂����l�i�H�j
�l�^�o���V�����Ƃ������́A�ĊO�A���������肵�āE�E�E�I�H�i^^�G�j
�����ԍ��F7316956
![]() 0�_
0�_
����12�r�b�g�Ȃ̂��A����14�r�b�g�ɂ��Ȃ������̂��B���̃Z���T�[�ŃL���m���Ƀ\�j�[�������ł�����̂����Ȃ�^��������܂��B12�r�b�g�̂܂܂Ȃ獂��f��D3�ɂ͓��ڂ���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�܂��l�i�������Ȃ��̂ɂȂ邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�܂��܂��f�W�^�����t�̃��C���i�b�v���s�\���ȃ\�j�[���j�R����L���m���ɐ^��������R���邩�ǂ������^�₾�Ǝv���܂��B
���̏�Ԃ��ƃ\�j�[�����̃Z���T�[�Ńt���O�V�b�v���o�����Ƃ��Ă��A�{�f�B�̓o�b�e���[��̌^�̓o��ƂȂ苎�N�Q�l�o�W���ꂽ�t���O�V�b�v�̂��̂Ƃ͑啪�Ⴄ���̂ƂȂ邩������܂��A����������������Εs�H�ȃ��f���̃J�������C���[�W���Ă��܂������ł��B������ɂ���A�Z���T�[������Ȃ�������̘b�肾���ŏI�肻���ȋC�����܂��B
�����ԍ��F7317552
![]() 2�_
2�_
���ɂ́A12bit��14bit����������Ō��������ł́A���f�����Ȃ��̂ł���
����قlj掿�ɈႢ������܂��ł��傤���H
���^�b�`�������́A�Ȃ߂炩�����Ⴄ�ƌ������Ƃ͗����ł��܂�����
14bit���Ɩ��b��R�}�������ł����A���i�ʐ^�Ƃ╨�B��p�r�ł�
����܂�W�Ȃ��ł����
�Ȃ�ł����@�\�ɋl�ߍ���ŁA�����ɂȂ���
�Õ��ʐ^�ɓ����������̂ŁA�Q�O���~���炢�ŏo��Ƃ����ł��˂�
�蓮�����グ����́A�b��R�}�ł��ʂɂ��̑���Ȃ��Ǝv��Ȃ��ł�
�����ԍ��F7317700
![]() 1�_
1�_
�Ձ[����ł��B����A�����́B
��肪�Ƃ��������܂��B
�Q�S�W�P����f�̂b�l�n�r�A�y���݂ł��ˁB
���X�O�O�����ł͊J�����ݔ����������ł��܂���A�j�R���ɂ������Ƃ����͍̂l�����܂��B
�c�Rx�̃Z���T�[�͂���Ō��܂肩�ȁB
�����ԍ��F7317703
![]() 0�_
0�_
�\�j�[���Ƃ��Ƃ��t���T�C�Y�ł��ˁB
�W�Ȃ��ł����A�t���T�C�Y�ł��{�f�B����u������ė����̂ł��傤���H
�����ԍ��F7317988
![]() 0�_
0�_
>14bit���Ɩ��b��R�}�������ł����A���i�ʐ^�Ƃ╨�B��p�r�ł�
>����܂�W�Ȃ��ł����
raw 14�r�b�g��1��/�b�̓j�R���ł͂Ȃ��ł����A���̋@��Ɗ��Ⴂ����Ă��܂��H
�����ԍ��F7318027
![]() 0�_
0�_
atos�p�p����A�����́B
>���ɂ́A12bit��14bit����������Ō��������ł́A���f�����Ȃ��̂ł���
>����قlj掿�ɈႢ������܂��ł��傤���H
�����ł��B���ɂ͑S�����f�ł��܂���B
�����A���ꂩ�烂�j�^�[�̐��\���オ���Ă����ƈႢ���������Ă��邱�Ƃ͏[���l�����܂��B
�X���傳��̃����N����Q�Ƃ���ƁA�Z�p�Ƃ��Ă͂c�R�O�O�A���V�O�O�̑f�q�̃t���T���Y��
�̂悤�Ȋ����ł��ˁB
���̑f�q�ɂ��c�R�O�O�̂悤�ɁA�P�S�r�b�g�ɑΉ����邱�Ƃ͏[���l������ƌ��Ă܂��B
�Ƃ���ŁAatos�p�p����I�I
>14bit���Ɩ��b��R�}�������ł����A
���̏��͂ǂ����痈���̂ł����I�H
�����ԍ��F7318053
![]() 0�_
0�_
>�Ƃ���ŁAatos�p�p����I�I
>>14bit���Ɩ��b��R�}�������ł����A
>���̏��͂ǂ����痈���̂ł����I�H
atos�p�p����A�ł͂���܂��B
�J����A/D��1bit�AA/D��bit�����オ��A����N���b�N����������A�ǂݏo�����x��
�����ɂȂ�܂��B
����āA12bit��14bit��A/D��bit����2bit�オ��Γǂݏo�����x��1/4�ɂȂ�܂��B
�܂�A12bit�Ŗ�6fps�œǂݏo����Ȃ�A14bit�Ȃ�1/4�̖�1.5fps�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F7318286
![]() 4�_
4�_
�@������ɂ��Ă��A��������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�t���T�C�Y�̎B���f�q�����}�U�[�}�V�[�����H��̃��C���ɏ�����Ƃ������Ƃ́A3�N��ʂɂ́A�ǂ̉�f���̗����ł�20���~���̂͗e�Ղɑz���o����̂Łi�}�U�[�}�V�[���̌������p��2���Ȑ��I�ɐi�ނ̂ŁA�����ɃI�������G�L�X�g���`���[�W�͌��I�Ɍ����Ă����ׁj
�@�j�R���́AFX�͍���f�łƒ��f�����x�ϐ��̃}���`�}�E���g�ADX���A����f�łƒ��f�����x�ϐ��̃��C���A�b�v�Ƃ����Ƃ����Ȃ��Ƃ������܂��B
�@���Ɖ𑜓x�̒Ⴂ���̍L�p�`�W���̒P�œ_�����Y�̃��j���[�A�����E�E�E
�����ԍ��F7318294
![]() 0�_
0�_
> �S��f�ǂݏo���@6.3frame/s�i12�r�b�g�j
FX�t�H�[�}�b�g����6�R�}�^�b�ADX�t�H�[�}�b�g�i12M�s�N�Z���j����11�R�}�^�b�B�ꂽ�肷��Ɛ������ł��ˁB
�����ԍ��F7318320
![]() 0�_
0�_
2008/01/30 22:26�i1�N�ȏ�O�j
>���ɂ́A12bit��14bit����������Ō��������ł́A���f�����Ȃ��̂ł�������قlj掿�ɈႢ������܂��ł��傤���H
������8bit�̉摜�ł킩��͂�����܂���B
RAW�����Ł{3EV�܂ŏグ�Ă��r��Ȃ����ƂȂǂʼn��b���܂��B
���ƁA12bit�ɗ}������Ȃ������̂́A�J����A/D�ɍS��������ł��ˁB
�ł����A���̃N���X�ɂȂ�ƃJ����A/D�̃����b�g�������Ă��Ȃ��c
�����ԍ��F7318328
![]() 1�_
1�_
�����Ȕ��\�ł��ˁ`�B�f���Ɋ�ׂ܂��B
�Ȃ��Ȃ������FX�@���o���ĂT�c�R�Ƃ��邱�Ƃ̂ق����}�����Ǝv���܂���
��Ԑl���吨������Ǝv���܂��B
���̑f�q�ŗ����ō������c�R�w�͂ǂ��Ȃ�́H���Ă��ƂɂȂ邵�B
�����ŗp�ł͉�f�����������Ǝv���܂����B
�j�R���̃��C���i�b�v�͂T�c�R�@����ɂȂ��Ă����̂ł��傤���ˁB
��ɑ��������̂͂R�O���~�ȉ���FX�@��1500����f�O��B
mash76����ɂP�[�I�ł����ǁB
����ς��f�����炱�̑f�q�̗����ł͂��肦�Ȃ����ȁB
�����ԍ��F7318382
![]() 0�_
0�_
�܂�.����>
�����肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F7318464
![]() 0�_
0�_
�ǂ��Ȃ��ł����ˁA�j�R��������CMOS���̗p�����ł��傩�B
�j�R���͉��ʋ@�킪��f���ŏ�ʋ@�����邱�Ƃ��ߋ��ɂ�����܂�����A
�����D300�̃{�f�B�ɍڂ��Ă�����ʔ����Ǝv���̂ł����B
�����ԍ��F7318514
![]() 2�_
2�_
�����A���̃t���T�C�Y�Z���T�[���A���̂܂܃j�R���̃t���b�O�V�b�v�ɓ��ڂ����Ƃ͍l�����Ȃ��Ǝv���܂��B
���܂ł̌o�܂����Ԃ�A��{�x�[�X�͂��̃Z���T�[�������Ƃ��Ă��A
�j�R���I���W�i���ȕ����𓋍ڂ����A�ʃZ���T�[�Ƃ��ă����[�X���Ă���Ǝv���܂��B
����ɁA�j�R���Ƃ��Ă��A
�t���b�O�V�b�v�@�ɁA�R���y�`�^�[�Ɠ����Z���T�[�𓋍ڂ���Ȃ�āA
���蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ɍl����A2600����f�Ƃ�3000����f�Ƃ��A
���|�I�ȍ���f�@���A�t���b�O�V�b�v�Ƃ��ă����[�X���Ă���Ǝv���Ă��܂��B
����ɉ����āA����f�@�Ɂux�v��t���ă����[�X���邱�Ƃɂ��^��������Ă܂��B
D40x�̐��Y���~�߂āAD40�̍���f�@�Ƃ�������J�����ɁuD60�v�ƌ�������t���Ă������ƁA
D200x��D80x�AD50x�������[�X���Ȃ��������Ƃ��l�����킹��ƁA
D3X�ł͂Ȃ��AD4�Ƃ��A���̔ԍ���t���ă����[�X���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���܂ł̗�����l����ƁA
����f�@��D4�Ƃ��āA�t���T�C�Y�̗����@��D400�Ɩ��t���Ă������ȋC�����Ă��܂��B
�����܂ŁA�����ł����B
�����ԍ��F7318657
![]() 2�_
2�_
����������f�@�́A�uF�V�v�ŁI�I
�����ԍ��F7318667
![]() 1�_
1�_
�Ձ[����ł�����
�����́B��肪�Ƃ��������܂��I
���ɗ��܂������I�������Ă��܂����I
mash76����
�R�����g��ώQ�l�ɂȂ�܂����I
�����ԍ��F7318749
![]() 0�_
0�_
������ɂ��o�Ă��܂��B
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080130AT1D3008G30012008.html
�����ԍ��F7319214
![]() 0�_
0�_
�\�j�[��Exmor�́AD/A�R���o�[�W������bit�����t���L�V�u���ɘM���ᖳ�������ł��������H�H
EX-F1��10bit���[�h��12bit���[�h������܂��B
D300��12bit���[�h��14bit���[�h������܂��B
�e�X�A�t���[�����[�g��1/4�ɗ����܂����B
�i���ɍ���̑f�q��14bit�o�͂��ƁA1.6fps�ł����E�E�E�E�����f�W�J���Ǝv���Ή䖝�ł���H�H�j
�����ԍ��F7319639
![]() 0�_
0�_
�l�I�ɂ�D300��14bit 2.5fps�ӂ肪�䖝�̌��E���Ǝv���̂ł����c1.6fps�͂�����Ɓc
����Ə�̕��ŁA�J����A/D�́AA/D2bit�オ��Ɠǂݏo�����x��1/4�ɂȂ�A�Ə����Ă܂����A�ǂݏo�����Ԃ�4�{������̂ŁA�R�}����1/4�ɂȂ�A�ł��ˁB���炵�܂����B
�����ԍ��F7320079
![]() 0�_
0�_
> �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����
> RAW�����Ł{3EV�܂ŏグ�Ă��r��Ȃ����ƂȂǂʼn��b���܂��B
�Ȃ�قǁA�Ԃꂽ�Õ��Ȃǂ������グ�鎞�ɗL�������ł���
���́A�R���g���X�g�͋�������ǂ��A���肬��K�����c���Ă���Ƃ���
�掿���D���Ȃ̂ŁA�ǂ������ł���
�y���^�b�N�X�����肪�A645�f�W������ɍ̗p���Ă�����
�����Y�Q�����ʂɂȂ�Ȃ��Ă����̂ł���
�����ԍ��F7321107
![]() 0�_
0�_
[7317552] �n�[�h���b�N��t�@������H��:
> ����12�r�b�g�Ȃ̂��A����14�r�b�g�ɂ��Ȃ������̂��B���̃Z���T�[��
> �L���m���Ƀ\�j�[�������ł�����̂����Ȃ�^��������܂��B
���̃Z���T�[�̉�f�T�C�Y(5.94�~�N�����p)�ł́A�Z���T�[�ɓ��˂�����q��d�q�ɕϊ�����ʎq������50%�Ƃ��āA�ʏ�̎B�e�ł͊e��f���ɖ�4000�̌��d�q�����������Ȃ��v�Z�ɂȂ�܂��B(���ʂ̋��Ԃ̖��邳�̖�100���N�X�̏Ɠx���Ń����o�[�g�I�g�U���̂�ISO100���x�����Af/1.4�̃����Y�ŃV���b�^�[�X�s�[�h1/100s�ŎB�e�����ꍇ�̌v�Z�ł��B)
�v����Ɋe��f����̏o�͐M���͘A���I�ȕ��ł͂Ȃ��A�~�ς��ꂽ��4000�̓d�q�̐��ɔ�Ⴗ�闣�U�I�Ȓl�ƂȂ�̂ŁA����ɉ��Z�����m�C�Y�����l�����12bit�ȏ�ɐ����鐸�x���グ�Ă����܂�Ӗ��̖����Ɖ]�����ł��B
�����ԍ��F7323164
![]() 0�_
0�_
2008/02/01 00:15�i1�N�ȏ�O�j
���V���b�g�m�C�Y�Ƃ����z�ł��ˁB
�����x���Ńf�W�^���A���v���g���̂͂��̂��߂ł����A�ኴ�x���ɂ�14bit�̉��b�͏\������Ƃ������Ƃ��m�F���Ă��܂��B
�����ԍ��F7323507
![]() 2�_
2�_
> �ኴ�x���ɂ�14bit�̉��b�͏\������Ƃ������Ƃ��m�F���Ă��܂��B
���Y��f�T�C�Y�ł͒ʏ�̎B�e��4000�ʂ̓d�q���������Ȃ��ꍇ�A14bit����(16384�X�e�b�v�j�̗L���i�m�C�Y�ł͂Ȃ��j�f�[�^��ׂɂ͖�16000�̓d�q�A�܂�ʏ�̂S�{�̘I�����Z���T�[�ɗ^���Ȃ���Ȃ�܂���B
�����l�ȉ�f�T�C�Y�̃Z���T�[�𓋍ڂ����L���m��1DsMarkIII�̗�����ƁA�Z���T�[�̊ISO�Ƃ���Ă���ISO100�ł͂Ȃ��AISO25�����ŎB�e���Ȃ���Ȃ�܂���B
���̗l�ȃJ�����̎g���������Ă���l�͖w�NJF���ł��̂ŁA14bit�̉��b���Ă���Ǝv���Ă��郆�[�U�[�͑��̏ꍇ�A���������o���Ă��邾���ł��傤�B
�����ԍ��F7323897
![]() 1�_
1�_
���˂�����q�̐���4000�� 12bit �������Ƃ��Ă��A�������d�q�̃G�l���M�[���ʂ͈��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���q�̕��͌��F�t�B���^�[�Ńt�B���^�����O����Ă���̂ŁA�܂���̐U�����i�ˁj���ŁAh�� �̕��� 0 �` 4000h�� �̃����W�ŗ��U�I�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F7324039
![]() 0�_
0�_
�@�j�R���͂�������D3�Ńt���T�C�Y�Z���T�[�����ЊJ�������̂�����A����̓t���T�C�Y�Z���T�[�͎��А��AAPS-C�T�C�Y�̓\�j�[���c�Ƃ�������ɂȂ肻���ȋC�����܂����ǂ��ł��傤�H
http://www.capacamera.net/pma08/index.php?page=1&id=11
�@�c�c�Ă��\�j�[�̃t���T�C�Y�@�͎�U���@�\���ڂɂȂ�悤�ł��ˁB
�����ԍ��F7324171
![]() 0�_
0�_
�\�j�[���A�N���Ƀt���T�C�Y�@�u���v�̔����\�����悤�ł��ˁB
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/other/2008/02/01/7877.html
������\����CMOS�Z���T�[���g���悤�ŁB
�����Ȃ�ƁA���̃Z���T�[�����̂܂g���āA
�j�R����D3�̌�p�@�������[�X����\���͌���Ȃ��������Ȃ����悤�Ɏv���܂��B
����ς�A�I���W�i���Z���T�[���ڂŁAD4�������[�X����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
D3�����@�i����D400�ƋL���Ă����܂��j�ɂ��A
���Ђ̃t���b�O�V�b�v�Ɠ����Z���T�[�𓋍ڂ���Ƃ͍l���ɂ����ł��ˁB
D400�ɂ��A�V�J���̃Z���T�[�𓋍ڂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�J�����ǂ��܂Ői��ł���̂��A
�j�R���̐헪�A���[�h�}�b�v���ǂ��Ȃ��Ă���̂��A
�j�R���W�҂ł͂Ȃ����ɂ͂킩�肩�˂܂����A
���Ȃ��Ƃ��܂��A�d�l��\�z���Đ���オ�ꂻ���ł��ˁB
���ڊW�Ȃ��ł����A
D3�A�g���Ύg���قǁA�C�C�J�����Ǝ����ł��܂��ˁB
CF�ւ̓]�����x�ƌ����A�V���b�^�[���痈��U���ƌ����A
�g���Ă��ăz���g�y�����J�����ł��B
�ŁA�t���T�C�Y�̉��b�i�w�i�̃{�P�j�́A�≖�ȗ��v�X�Ɋ������Ă��܂��܂����B
����ς�A�t���T�C�Y�̊y�������ĔF�����Ă��܂��ƁA
�����t���T�C�Y�@���~�����Ȃ�܂��ˁB
�����AD400���y���݂ł��B
�����ԍ��F7324210
![]() 0�_
0�_
2008/02/01 08:55�i1�N�ȏ�O�j
���̓̓ɂ���
�ኴ�x����14bit�̌��ʂɂ��ẮA���ۂ�RAW��+3EV�ȂǑ������Ă݂�q�X�g�O�����̌`�ł͂����荷���o�܂��B
�P�Ɍ��q���x�̖�肾���ł͂Ȃ��A�㏈���̗]�T�x���܂߂čl�����Ȃ��ƃ_���ł��B
�����ԍ��F7324382
![]() 0�_
0�_
> ���˂�����q�̐���4000�� 12bit �������Ƃ��Ă��A�������
> �d�q�̃G�l���M�[���ʂ͈��ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���˂�����q�̐��͖�8000�A�ʎq������50%�Ŕ���������d�q����4000�ƌv�Z���Ă��܂��B
�Z���T�[�͊�{�I�ɂ͂��̔��������d�ׁiq�N�[�����j��(���V)�L���p�V�^c����d���iv�{���g�j�ɕϊ�������A�A���v�ő������ďo�͂��܂��B
���d�q�̃G�l���M�[���ʁi�^���G�l���M�[���܂ށj�ƃL���p�V�^���̓d�q�̃G�l���M�[���ʂ̍��̓t�H�m���i���M�j�Ƃ��Ċg�U���܂�(�G�l���M�[�ۑ��̖@��)�B
����āA�o�͂����M���͒P�ɃL���p�V�^�ɗ��܂����d�q�̐��ɔ�Ⴕ�iv=q/c�j�A���R���U�I�ɂȂ�܂��B
>> 14bit�̉��b���Ă���Ǝv���Ă��郆�[�U�[�͑��̏ꍇ�A
>> ���������o���Ă��邾���ł��傤�B
>
> ���ˁA���̃f�W�^�����������Ă��郆�[�U����M���Č����Ă���̂ł����H
> �z�����S�������ˁB�ŒႾ��
�Ӂ`��B
����@�B�̎��ۂ̉^�p��ʂƎg�p���@�ɂ��Ă͍l�@�����A�J�^���O�X�y�b�N�������ɂȂ����[�U�[�����������w�E����̂͐l���u��M�v���鎖�ɂȂ�̂ł����B�M���̗l�Ȕ���������l�͂�����Ȃ��v���C�h���������Ȃ��A�ɂ߂ĕ\�w�I�Ȑl�Ԃɂ��������Ȃ��̂ł����B
�܂��A���m�Ȓf���v�����݂��I����҂ɑ��Ď��͊m���Ɏ茵�����ł����A�}�i�[�]�X�����ɂ��銄�ɂ̓X�e�n���ł͂Ȃ����i�̃n���h���l�[���œ��e�����������������A��Ȃ��ԓx�̒N��������͂܂��}�V���Ǝv���܂��B
> RAW��+3EV�ȂǑ������Ă݂�q�X�g�O�����̌`�ł͂����荷���o�܂��B
���M���̗��U�I�ȓd�ׂ̐����l�������A���g���X�y�N�g�����ł��Ȃ��G�l���M�[���z�i�q�X�g�O�����j�����������ŔC�ӂ̃r�b�g���ł̃m�C�Y�����ƗL���M������ʏo����炵���M���́u�����v�ł���...
�����ԍ��F7327214
![]() 2�_
2�_
>�ኴ�x����14bit�̌��ʂɂ��ẮA���ۂ�RAW��+3EV�ȂǑ������Ă݂��
>�q�X�g�O�����̌`�ł͂����荷���o�܂��B
�������������I�ɂ��肻���ȃV�i���I�ō����킩��Ⴊ�Ȃ��ł����ˁB
�����i�K��+3EV���邱�Ƃ��ĕ��i�̎B�e�ł���܂����H
�����ԍ��F7327733
![]() 1�_
1�_
���̌�y�ɂ͂��ׂĂP�U���������[�h�ʼn^�p����V�炪���܂��B
�����ԍ��F7327888
![]() 0�_
0�_
���̓̓ɂ���
�������̌��͋�������̂ł����A�[���ł��邾���̒m���������͎������킹�Ă���܂���B
>���˂�����q�̐��͖�8000�A�ʎq������50%�Ŕ���������d�q����4000�ƌv�Z���Ă��܂��B
���ˌ��̐���8000�Ȃ�ł��ˁB
>�Z���T�[�͊�{�I�ɂ͂��̔��������d�ׁiq�N�[�����j��(���V)�L���p�V�^c����d���iv�{���g�j�ɕϊ�������A�A���v�ő������ďo�͂��܂��B
����͂����ł����B
>���d�q�̃G�l���M�[���ʁi�^���G�l���M�[���܂ށj�ƃL���p�V�^���̓d�q�̃G�l���M�[���ʂ̍��̓t�H�m���i���M�j�Ƃ��Ċg�U���܂�(�G�l���M�[�ۑ��̖@��)�B
���������Ă���̂͌��d�q�̃G�l���M�[���ʂł͂Ȃ��A�u�d�q�v�̃G�l���M�[���ʂł��B
���ɋ����O�ɔ�яo���ĐÎ~���Ă���Ƃ��̃G�l���M�[���ʂ� 0�A���݂̓d�q�̃G�l���M�[���ʂ� -W �Ƃ��āA���d�q�ɂ���ɂ� W �ȏ�̌��G�l���M�[���K�v�ł����A���� W �Ƀo���c�L�������Ȃ��ł����A�ƁB
���A������l�����āu�ʎq������50%�v�Ƃ̂��Ƃł����ˁH
�����ԍ��F7329946
![]() 0�_
0�_
���̓̓ɂ���
VTZ250�Ƃ����܂��B���i�R���ւ͏��̏������݂ł��B��낵�����肢���܂��B
�ʎq�͊w�I�ȓ���c�_�͂Ƃ������A
���̓̓ɂ���̋c�_�ɂ͉�������������悤�ȋC�����܂��B
���Ƃł͂Ȃ��̂őf�l�̈ӌ��Ƃ��Ă��������������B
�܂��A���q���J�E���g����Ƃ��̎B�e�����ł����A�ʏ�̏����łȂ�
�t�H�g�_�C�I�[�h�����傤�ǖO�a��������ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ƃ���ƁA�����ƌ��q�������Ȃ�C�����܂��B
���ꂩ��A�S�O�O�O������P�Q�r�b�g�ł悢�Ƃ̘b�ł����A
���̏ꍇ�A�`�c�̂k�r�a�𐳊m�Ɍ��q�P���̓d���ɂ��킹�Ȃ���
�`�c�̏o�͂��s���m�H�ɂȂ镔�����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�ȏ�̂��Ƃ��l����ƁB�P�S�r�b�g�����Ȃ������Ӗ��ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂����B�B
�����ԍ��F7330148
![]() 0�_
0�_
2008/02/02 13:49�i1�N�ȏ�O�j
���ƁA���q��4000�̎��ɁA�f�W�^���I��12bit���������U���Ȃ��Ƃ͍l�����܂���ˁB
�m���_�I�ɂ����R�_�I�ɂ��A�����f�ɂ�11bit���̕��z�A�����f�ɂ�13bit���̕��z�Ȃǃ����_���Ȋg����ł���A���̃��x�����z���r�b�g���������悤�Ȕ�A���̋��`�ɂȂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�A���g�`�ł���Ɨ\�z���t���܂��B
�ŁA�J��Ԃ��悤�Ɍ㏈���̃K���}���F��}�b�s���O�A�I�o��̂��Ƃ��l���Ă�12bit�ł͉����M���M���A14bit����܂��]�T�����邩�ȂƂ����̂��������Ă���Ƃ���ł��B
�����ԍ��F7330198
![]() 0�_
0�_
�� ���q��4000�̎��ɁA�f�W�^���I��12bit���������U���Ȃ��Ƃ͍l�����܂���ˁB
������ā����ǁA�w�m�C�Y�̐U���ŐM�����h���Ԃ�ꂽ��I�H�x ���Ęb�ł����H�i^^�G�j
�����ԍ��F7330648
![]() 0�_
0�_
8000�������� 13bit �ł��ˁB
���ɉ����̃G�l���M�[�̓����W�Ƃ��Ă�(�g������� 400nm - 800nm ������)���X��{�� 1bit�B���Ƃ͂��͈̔͂��ǂꂾ���ׂ����T���v�����O���邩�ł����A���X�O���F�Ƀt�B���^�����O����Ă���̂ŁA�����̃r�b�g�͂���Ȃ��̂�������܂���ˁB�u������ G �̉�f�v���Ă̂͂킩���Ă��邵�A�u�Z�߂̔g���� G �̉�f�v�Ƃ������Ƃ��ĕK�v�Ƃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��傤����B
�����ԍ��F7330672
![]() 0�_
0�_
���������b�l�n�r�̃o�P�c�͌��q�P����ϑ��ł�����H�@
�P�̃G�l���M�[���m�C�Y�������ďؖ�����������ĂȂ�����
�i4000���x�̓��˂����Ȃ����Ƃ�
�@�P�ȉ��͘_���I�ɖ�����邱�Ɓ@�@�@�͎��������ǁj
�����ԍ��F7330843
![]() 0�_
0�_
2008/02/02 16:49�i1�N�ȏ�O�j
>������ā����ǁA�w�m�C�Y�̐U���ŐM�����h���Ԃ�ꂽ��I�H�x ���Ęb�ł����H�i^^�G�j
�������ł��B
LSB�t�߂ł̓t�H�g�_�C�I�[�h��d�C��H�̃m�C�Y�͖����ł��܂��A�����̓A�i���O�̋ɂ߂Ċ��炩�ōׂ��ȐU���ł��B
��f���̊��x������12bit�P�ʈȉ��ł��傤�B
�ł�����A���ɂ҂�����4000�̌��q���ł��A14bit�ɂ������Ȃ�̊K���͕K���t���܂��B
���ƈ�̖��́A�����S�������Ă��Ă��Ȃ��ꍇ�̃O�����h�m�C�Y�i�d�C�I�m�C�Y�j���S���l������Ă��܂���B
����͏��Ȃ���Ώ��Ȃ��قǗǂ��̂͌����܂ł�����܂���B
��i�̈Õ��A���邢�͕��ʂ̎ʐ^�ł��A���������̃m�C�Y���ȂǂɕK���e�����܂��B
�����ԍ��F7330893
![]() 1�_
1�_
2008/02/02 16:52�i1�N�ȏ�O�j
�܂�A4000�̌��q�Ɠ����K������A/D����Ɓu�ǂݗ��Ƃ��v���o�邱�Ƃ̕������ł��B
1�̌��q���ǂ���̃f�[�^�ɂ��邩�A���E�̔����ȃ��x���ɂ���Ƃ���Ƃ����ŊK����т��������܂��B
�ɂ߂Ċ�{�I�Ȃ��ƂȂ̂ŁA�z���ł������Ȃ��̂ł����B
�����ԍ��F7330909
![]() 2�_
2�_
[7329946] �u���s�̂�������v����H��:
>>���d�q�̃G�l���M�[���ʁi�^���G�l���M�[���܂ށj�ƃL���p�V�^���̓d�q��
>>�G�l���M�[���ʂ̍��̓t�H�m���i���M�j�Ƃ��Ċg�U���܂�(�G�l���M�[�ۑ��̖@��)�B
>
>���������Ă���̂͌��d�q�̃G�l���M�[���ʂł͂Ȃ��A�u�d�q�v�̃G�l���M�[���ʂł��B
>���ɋ����O�ɔ�яo���ĐÎ~���Ă���Ƃ��̃G�l���M�[���ʂ� 0�A���݂̓d�q�̃G�l���M�[
>���ʂ� -W �Ƃ��āA���d�q�ɂ���ɂ� W �ȏ�̌��G�l���M�[���K�v�ł����A���� W
>�Ƀo���c�L�������Ȃ��ł����A�ƁB
�V���R���̎d���� W �͑��4.5�d�q�{���g(eV)�ł��B�ΐF�̔g��555nm�̌��q�̃G�l���M�[ h�� �͖�2.2eV�ł��̂ŁA���������d�q�͊�{�I�ɂ͌��������яo���܂���B�܂��A���ɃZ���T�[���яo�����d�q���L���Ă��A�����͖ܘ_���o�ł��܂���̂ŎB���ւ̉e���͍����ł͖������܂��B
�����̊E�ʂ����яo���Ȃ��d�q�Ɂu���d�q�v���Ɖ]�����̂��g���ׂ����͖������̂ł����A�ȉ��̎O��ނ̓d�q����ʂ���ׂɁA�����Ďg�p�����Ă��������܂����B
(1) �V���R���̉��d�q�т̓d�q
(2) �V���R���̃o���h�M���b�v�i��1.1eV�j�ȏ�̃G�l���M�[ h�� �̌��q�ɗ�N����A�`���ѓ����ړ�����u���d�q�v
(3) �d���o�p�̃L���p�V�^�ɗ��܂����d�q
���˂������g�� �� �̌��q�ɗ�N����A���������ړ�����^�C�v(2)�́u���d�q�v�̃G�l���M�[���ʂ͖w�ǘA���I�Ȓl���Ƃ�܂��̂Łi�o���c�L�j�A���̒i�K�Łu���d�q�v�̃G�l���M�[����������s����A12�r�b�g�ȏ�̑��萸�x�͈�����x�̈Ӗ�������������܂���B
�A������͌��́u���ÁE���x�v�ł͂Ȃ��A����F�̃x�C���[�t�B���^�[�߂��Ă������q�́u�g���E�F�v���ԐړI�ɍēx���肷��A���X���㉮�I�Ȃ��̂ɂȂ�܂��� (^^;
���ۂ̃Z���T�[���ł͂��̃o���c�L�̂���G�l���M�[�́u���d�q�v�͌��o�L���p�V�^�̕��ɓ�����A���������i�K�ł��̃o���c�L�͔M�Ƃ��Ċg�U���A���Ƃ��Ă͏��ł��܂��B����āA�M���̑���̓L���p���ɗ��܂����d�ׂ𐔂��邾���ɗ��܂�̂ŁA���Ǘ��U�I�Ȃ��̂ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F7331786
![]() 3�_
3�_
[7330148] VTZ250����H��:
> ���̓̓ɂ���̋c�_�ɂ͉�������������悤�ȋC�����܂��B
> �܂��A���q���J�E���g����Ƃ��̎B�e�����ł����A�ʏ�̏����łȂ�
> �t�H�g�_�C�I�[�h�����傤�ǖO�a��������ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���H
�m����14bit�݂����ȑ傫�ȃ_�C�i�~�b�N�����W��L���Ɏg���ɂ͏o���邾���O�a�ɋ߂����G�l���M�[����f�ɏƎ˂��������]�܂����ł��B�������A�ȑO���y�����l�ɁA����͒ʏ�̘I�o�v�ɋL�����I���l�̐��{�ɂȂ�̂ŁA���̗l�Ȕ�ʑ̂���̕��˃G�l���M�[�ƃZ���T�[�������l�������ʓ|�ȃJ�����̎g����������l�͂��Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B
> ���ꂩ��A�S�O�O�O������P�Q�r�b�g�ł悢�Ƃ̘b�ł����A
> ���̏ꍇ�A�`�c�̂k�r�a�𐳊m�Ɍ��q�P���̓d���ɂ��킹�Ȃ���
> �`�c�̏o�͂��s���m�H�ɂȂ镔�����o�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�������Ƃ���ł��B�������A�s��Ɏ������掿��B������ׂɁA�d���o�p�̃L���p�V�^���܂߁A�摜�Z���T�[�̊e��f�Ԃ̓����̃o���c�L�͋ɗ͉��������Ă���ƍl�����܂��B
�܂��A�e��f�R�����ɐڑ�����Ă���A/D�ϊ���H�̃Q�C���ALSB���̓�������f���瑗���Ă���M���d���̃����W�ɍœK�����ꂽ�v�ɓ��R�Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7331819
![]() 1�_
1�_
[7330198] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H��:
> ���ƁA���q��4000�̎��ɁA�f�W�^���I��12bit���������U���Ȃ��Ƃ͍l�����܂���ˁB
�����o�[�g�g�U���̖̂O�a�ɋ߂��n�C���C�g(100���N�X���ł̗��_�I��ISO100�ŕK�v�ȘI����8�{�A����+3EV)�Ō��q�̐��͖�W�O�O�O�A��������d�q�͖�4000�ƌv�Z���Ă��܂��B4000�𐔂���ɂ�12bit(�S�O�X�U�X�e�b�v)�͏[���Ȑ��x�ł��B
> �m���_�I�ɂ����R�_�I�ɂ��A�����f�ɂ�11bit���̕��z�A�����f�ɂ�13bit����
> ���z�Ȃǃ����_���Ȋg����ł���A���̃��x�����z���r�b�g���������悤�Ȕ�A����
> ���`�ɂȂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�A���g�`�ł���Ɨ\�z���t���܂��B
���������n�C�G�X�g���C�g�ɋ߂����ϒl��8000���������鐔�̌��q����������A�Ɍ���ꂽ���̉�f���Ŕ�������d�q�����m�ɃJ�E���g���鐸�x�i�Ⴆ��13bit�����j���K�v���́A���͋^�킵���Ǝv���܂��B
�e��f�ɓ��B������q���͗��U�I�ŁA���R��f�Ԃł̓|�A�\�����z�ƂȂ�܂��B
���̃����_���Ȋg����̒��x���v�Z����ƁA���ϒl8000�̃|�A�\�����z�̏ꍇ�A2400�����̉�f�̒���8480�ȏ�̌��q�����������f���u��������v�m���̕����u���Ȃ��Ƃ���L��v�m�����傫���ł��B
�܂�A�n�C���C�g���ł͌��q�̗h�炬�Ɉ��铝�v�I�ȕ��U�͈ĊO�����A�v�����x�̃r�b�g���𑝂₷�����_���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ɖ]�����ł��B
�܂��A�V���h�[���ł͓��R��������d�q�̐������Ȃ��̂ŁA12bit�̃J�E���^�[�̐��x�ł��S�����͗L��܂���B
�d���o�p�̃L���p�V�^���瓾��ꂽ�M���ɉ��Z�����l�X�ȃm�C�Y�i�O�����h�m�C�Y�̔M�d�q���j�͗��U�I�ȓd�ׂƂ��č������Ă���̂ŁA��������A/D�̐��x���グ�Ă��M���ƃm�C�Y�̐U������ʏo�����ł͗L��܂���B
> �ŁA�J��Ԃ��悤�Ɍ㏈���̃K���}���F��}�b�s���O�A�I�o��̂��Ƃ��l���Ă�12bit
> �ł͉����M���M���A14bit����܂��]�T�����邩�ȂƂ����̂��������Ă���Ƃ���ł��B
���f�[�^�̐��x�ƁA����������f���U�C�N�A�K���}�������̉��Z�X�e�b�v�ł̐��x�͕����čl���Ȃ���Ȃ�܂���B���Z�͊ۂߌ덷���̔����Ɗg�U��h���ׁA�ܘ_�A���f�[�^��荂�����x�i�Ⴆ��16bit�j�ōs���̂��]�܂����ł��傤�B
�����ԍ��F7331882
![]() 1�_
1�_
���̓̓ɂ���
���J�ȉ��肪�Ƃ��������܂��B
�܂������ł��Ȃ��Ƃ��낪����܂��̂ŁA�^����Ԃ������Ă��������B
�܂��A���q�W�O�O�O�̏����ɂ��Ăł����A
�u���ʂ̋��Ԃ̖��邳�̖�100���N�X�̏Ɠx���Ń����o�[�g�I�g�U���̂�ISO100���x�����Af/1.4�̃����Y�ŃV���b�^�[�X�s�[�h1/100s�ŎB�e�����ꍇ�̌v�Z�ł��v
�Ƃ������̂ŁA�K���I�o�ł̌v�Z���Ǝv���t�H�g�_�C�I�[�h�̖O�a�̘b���o�����̂ł����A
�u�����o�[�g�g�U���̖̂O�a�ɋ߂��n�C���C�g(100���N�X���ł̗��_�I��ISO100�ŕK�v�ȘI����8�{�A����+3EV)�Ō��q�̐��͖�W�O�O�O�A��������d�q�͖�4000�ƌv�Z���Ă��܂��B�v
�Ƃ���̂ŁA�{�R�d�u�̘b�������̂ł��ˁB���Ⴂ���Ă��܂����B
�����ł܂��^��Ȃ̂ł����A�{�R�d�u�܂ł����������Ȃ��Ƃ���ƁA
�{���̃_�C�i�~�b�N�����W���{�R�d�u�܂łɐ�������邱�ƂɂȂ�Ȃ��ł��傤���H
�f�W�J���G���Ȃǂ�ǂނƃf�W�P�̃_�C�i�~�b�N�����W�͂W�d�u�قǂ���A
�v���X���ɂS�d�u���炢�Ȃ��Ƃ��܂�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
���ƁA���̋c�_�ł͂W�O�O�O���d�v�Ȑ����Ȃ̂ŁA�\�ł�����
�v�Z���������Ă��炦�Ȃ��ł��傤���H�����v�Z�Ƀg���C���Ă݂����ł��B
�`�c�R���o�[�^�̃r�b�g���Ɋւ��Ăł����A
���̓̓ɂ���̂��������Ƃ���œK���͂���Ă���Ǝv���܂����A
����̓[���ɂ͂Ȃ�܂����ˁH���K���z�ł��傤���B
�m���ɂS�O�O�O�𐔂���Ȃ�S�O�X�U�́u�J�E���^�v�ŏ\���ł����A
�S�O�O�O�̗��U�l���P�Q�r�b�g�̂`�c�R���o�[�^�ł͂���ɂ�
�d�q�P���̓d���Ƃk�r�a�̂̍����P�^�W�O�O�O�ȉ��ɂ��Ȃ���
�`�c�̏o�͂̂ǂ����ɃW�����v����������Ƃ������܂��B
�P�^�W�O�O�O�ȉ��̂���͌������C�����܂��B
�P�S�r�b�g�����ʂ��ǂ����ł����A����̎��̋C������
�u�P�Q�r�b�g�ŏ\�������ǁA�P�S�r�b�g�ł����Ɨǂ��Ȃ�C������v
�Ƃ����������ł��B
���̓̓ɂ���̗��_���������Ƃ���ƁA�P�Q�O�O����f�̃R���p�N�g�f�W�J���ł�
���q���P�O�O�O�ȉ��ɂȂ肻���ł��ˁB
�Ƃ���Ƃh�r�n�S�O�O�Ō��q���Q�T�O�B�B�W�r�b�g�ŏ\���H�I
�����ԍ��F7333066
![]() 0�_
0�_
2008/02/03 00:42�i1�N�ȏ�O�j
���̓̓ɂ���
14bit�ŗʎq�������摜�f�[�^�́A�m�C�Y�ɂ܂݂�Ȃ������͂�14bit���̏��ʂ������Ă��܂��B
�i�A�i���O�m�C�Y�ɂ܂݂ꂽ���̃f�B�U�����O���ʂ�����B�����Č��q���x��12bit�����������ɂ��挳�̌����ʂɑ����Ă��邱�Ƃ͂܂������j
�܂��A�A�i���O�I�ȃm�C�Y��A/D�O�ʼn��Ƀ[���Ƃ��Ă��A���m��LSB���x������v���Ȃ��ƁA���Ȃ�̊m���Ń~�X�J�E���g���܂��B
�����ɑ��ė]�T�����̃T���v�����O�͕K�������ʂ����܂��B
�I�[�f�B�I�ł��A�ړI�̃p�b�P�[�W���i��16bit��CD������Ƃ�����16bit�Ŏ��^����^���X�^�W�I�͂���܂���B
�܂��A�����S������Ȃ��ꍇ�i���q�ʃ[���j�A12bit����S/N�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́ARAW�����ŘI�o���v���X����Ȃǂ̍ۂɈÕ��̃O�����h�m�C�Y�ł��Ȃ�s���ɂȂ�ł��傤�B
���j�A�f�[�^����1/2.2�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ňÕ����v�Z���Ă݂�Έ�ڗđR�ł��B
�ȏ�̂��ƂɊւ��āA���̓̓ɂ���̐��������12bit�ŏ\���ł���Ƃ������Ƃ̐��������������܂���B
�����ԍ��F7333402
![]() 2�_
2�_
�@�R�A�Șb���i��ł��܂����A
�@�v�́A�u�B�e���ɓK���I�o�ŎB��A12�r�b�g��14�r�b�g���S����薳���v�Ƃ������Ƃł��ˁH���b����̂́A�u�P�x���̂��܂�ɂ�������������̂��ʂ����Ƃ��ɁA�ڂŌ����������o���邾�������ɍČ����悤�Ƃ����Ƃ��ɗD�ʍ����o�Ă���v���Ƃł��ˁH
�@�E�E�E�I�o�̏C�s�ɖ��������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7334170
![]() 1�_
1�_
[7333402] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H���F
> ���j�A�f�[�^����1/2.2�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ňÕ����v�Z���Ă݂�Έ�ڗđR�ł��B
�܂����Ă��K���}�̌v�Z���̒��ԃX�e�b�v�ł́u���Z���x�v�Ɓu���̃f�[�^�̐��x�v���������Ă��܂��ˁB�����ł��m�C�Y���̃f�W�^�����l�f�[�^�����̌o�����L��B�ɊȒP�ɗ����o���锤�̋�ʂȂ̂ł����B
���ꂩ��A��ʓI�Ɏg���Ă���sRGB�AAdobeRGB���̋K�i�ł́u�ňÕ��v�̓��j�A�f�[�^�ł���A1/2.2��݂����ȃK���}���ǂ����A���������K�p���Ă��܂���B
> ���̓̓ɂ���̐��������12bit�ŏ\���ł���Ƃ������Ƃ̐��������������܂���B
�ʏ�ő��4000�̗��U�I�d�ׂɍ��X���̗��U�I�m�C�Y�d�ׂ���������d�ׂ̑����̏��G���g���s�[��\���ɂ�12bit�̃J�E���^�[�͏\���ł���Ƃ͋M���̓��ŗ�������͖̂����ł��B
�܂��A�J�E���^�[��12bit�ɂ��鎖�ɂɊւ��Ă͓��Y�Z���T�[��v�����A���̓��̃v���ł��낤�\�j�[�̋Z�p�ҒB�͎��Ƒ�̓������_�Ɏ������݂����ł����B
���v�E���w�A���w�A�M�������A�����́A�f�W�^����H�v�̋Ɋ�{�I�ȕ���ł��A���ۂ̌o���Ɩ{���̒m���������Ă��Ȃ��̂͋M���̂���܂ł̓��e��ǂ߂Ζ��炩�ł��B
�܂��A���g�̖����A�m�������Ԃ肵���\�̂Ȃ��M���͎����̎v�l�\�͂̂Ԃ��������Ă���ǂ̑��݂������F���o���Ă��܂���B���͂��̒��x�̃��x���̐l��z�肵�ĉ�������Ă����ł͗L��܂���̂ŁA�������炸�B
�����ԍ��F7338920
![]() 2�_
2�_
[7333066] VTZ250����H��:
> ���̋c�_�ł͂W�O�O�O���d�v�Ȑ����Ȃ̂ŁA�\�ł�����
> �v�Z���������Ă��炦�Ȃ��ł��傤���H�����v�Z�Ƀg���C���Ă݂����ł��B
�ӏ������X�^�C���Ŏ��炵�܂��B
�ʐ�1�������[�g���́A���ˌ���100%���˂����闝�z�I�����o�[�g���́i�����g�U�݂����Ȃ��̂ł��j������Ƃ���B
���N�X�̒�`�ɂ��A�P���N�X�̏Ɠx�ł͂��̕��̂�1/683���b�g�̃p���[�˂��鎖�ɂȂ�B
100���N�X�̏Ɠx���ł͂��̕��̂́A�J�����̃V���b�^�[���J���Ă���1/100�b�̊ԁA1/683�W���[�� �̃G�l���M�[����˂������ɂȂ�B
�����o�[�g���̂�5.94�~�N�����p�̃p�b�`��1/683 * 5.94 10^-6 * 5.94 10^-6 J����˂���B
�����ŁA�@���Ȃ郌���Y���g�����Ƃ��A�B���ʂœ�����P�x�͔�ʑ̂̋P�x���鎖�͖����Ɖ]������O���ɒu���K�v������B
���̃p�b�`����̊g�U���˂́@2�X�e���W�A��(sr)�@�̗����p���̑S�Ă̕����ɋψ�ɃG�l���M�[����˂���B
�i��l N �̃����Y�̊J�������p�͋ɍ��W�n���̐��`�p�x�G�������g�Y���ʊp�x�̓�d�ϕ����s������
2��(1 - 2N / ��(4*N*N+1))sr�@�Ɠ��o�����B
����āAN=1.4 �`= ��2 �̃����Y�̏ꍇ�A�����o�[�g���̂���2��sr���ɕ��˂����G�l���M�[�̖�5.7191%��f/1.4�̃����Y�ɓ��˂��鎖�ɂȂ�B
���ɁA�B�e�����Y�̓��ߗ�����������B
�T�^�I�ȂU�S�V���\����50mm f/1.4�̕W�������Y�����グ��B
�}���`�R�[�g���ꂽ�����Y�Ƌ�C�̋��E�ʖ���0.3%�̔��˃��X��������Ƃ���B
���̏ꍇ�A���ߗ��͖�96.46%�ƂȂ�B
�̃x�C���[�t�B���^�[���̉�f���l����B
�ΐF�������l�����ꍇ�A�Ⴆ��555nm�̔g���ł͌��q1�̃G�l���M�[ h�� �͖� 3.578 10^-19J �ł���B
�����o�[�g���̂�5.94�~�N�����p�̃p�b�`������˂��ꂽ�G�l���M�[���S�ėΐF�ł������ꍇ�A�����5.7191% * 96.46%�������Y��ʂ��ĉ�f�ɓ��B���镽�σG�l���M�[�ƂȂ�B
���̏ꍇ�A����͖�7964.74 h�ˁ@�`= 8000�̌��q�����̃G�l���M�[�ƂȂ�B
���˗�100%�̕��̂͏����ł���B�I���̊�Ƃ�����ʑ̂̔��˗���12�`18�p�[�Z���g�ł���B�I�o�v�ő������ꍇ�A���̕��̂̐����V���b�^�[�X�s�[�h�͂��̍l�@�ō̗p����1/100s�ł͂Ȃ��A1/833s �` 1/556s �ƂȂ�ł��낤�B
����1/100s�ł� 3.059EV�`2.474EV�ʂ̃v���X�����̘I�o����s���Ă���Ɖ]�����ł���B
����ISO�K�i�ł̈���Ɠx���ł̒��ԃO���[�闝�_�I�o�l�� 2^EV = ���N�X*ISO/12.5 �ł���B
���̏ꍇ�AEV0 = ISO100�A�i��f/1.0�A�V���b�^�[�X�s�[�h�P�b�ł���B
ISO100�A100���N�X��EV9.644�����ŁA�i��f/1.4�A�V���b�^�[�X�s�[�h1/800s�ɊY������B
�܂��L�̃n�C���C�g�������グ��1/100s�̃`���b�^�[�X�s�[�h��ISO�K�i�ɑ��Ē��x+3EV�̘I�o����������ɂȂ�B
> �d�q�P���̓d���Ƃk�r�a�̂̍����P�^�W�O�O�O�ȉ��ɂ��Ȃ���
> �`�c�̏o�͂̂ǂ����ɃW�����v����������Ƃ������܂��B
> �P�^�W�O�O�O�ȉ��̂���͌������C�����܂��B
�����@�̎B���Z���T�[�ł͂���قǂ̐��x��K�v�Ƃ��Ȃ��̂ŁAA/D�X�e�[�W���o����f�Ԃ̂���͎��ۂɂ�2�`3%�ʂł͂Ȃ��ł��傤���B���̒��x�̃R�����Ԃ̂��(Fixed�@Pattern�@Noise)�͉摜�����v���Z�b�T�[�ŕ�o���܂����B
12bit�̐��x�̐��l�Ɋ�����̔�A�����͓��R��������ł��傤�B�������A����ȏ�̐��l�̔�A�������Ⴆ�J���[�}�l�[�W�����g�̃L�����u���[�V������Ƀf�B�X�v���[�ƃR���s���[�^�[�Ԃ̃g�[���J�[�u�}�b�s���O��8bit�e�[�u���̊Ԉ��������Ŕ������܂��B
12bit�̉𑜓x�������o���܂ł��Ȃ��A8bit�̃f�[�^�ł����A���l�̔�A�������m�o�\���x���ȉ��ɗ��܂鎖���[������܂��B
�����ԍ��F7338992
![]() 1�_
1�_
[7334170] ridinghorse����H��:
> �E�E�E�I�o�̏C�s�ɖ��������������Ǝv���܂��B
D3�̃Z���T�[�̉�f�̓\�j�[�̍��\����FF�Z���T�[�̂���̔{�̖ʐςȂ̂ŁA�ʏ�B�e�ł�13bit�����̓d�א��̃G���g���s�[�͓�����ł��傤�B�܂��A�P�i�蕪�ʌ����B�e�����14bit���[���˒����ł��傤�B
�A���Z���E�A�_���X�̃]�[���V�X�e����낵���A�X�|�b�g���[�^�[�ŎB�e��������ʂ̗l�X�ȕ����̋P�x�𑪒肵�A�@���ɂ�����Z���T�[�̃_�C�i�~�b�N�����W�ɓ��Ă邩���l����̂��ʔ�����������܂���B
�����ԍ��F7339010
![]() 0�_
0�_
2008/02/04 01:09�i1�N�ȏ�O�j
���̓̓ɂ���
>��ʓI�Ɏg���Ă���sRGB�AAdobeRGB���̋K�i�ł́u�ňÕ��v�̓��j�A�f�[�^�ł���A1/2.2��݂����ȃK���}���ǂ����A���������K�p���Ă��܂���B
�܂����Ă����������Ȃ��Ƃ��������ł��ˁB
sRGB�̍ňÕ��͋�Ƃ��肠�镔���܂ł̓K���}�J�[�u�ł͂Ȃ����钼���̌X���AAdobeRGB�̋K�i�͏����ȃK���}2.2�i�J�����K���}��1/2.2�j�ł��B
���Җ��m�ɈႢ�܂��B
������x�K�i�ׂĂ��������B
�����A���̌��������Ɗ�{�K���}�������݂��Ȃ��ƕ������Ă��܂��܂����A�܂������̈Ӗ��ł͂Ȃ��ł���ˁH
�ŁA�ǂ���ɂ��Ă��ňÕ��̗������Ƃ���isRGB�ł�4�{���x�ł������j�v���X3EV�܂ő����ł���RAW�����\�t�g�ł́A���ˌ��[�����̃o�b�N�O�����h�m�C�Y�̗ʂ�����Ă��܂��B
������Ԗ₢�����A���̐���������܂���B
�܂��A�ǂ̂悤�ȃ��x���̐l�Ԃɑ���������Ƃ��Ă��i���Ȃ����m���̂���l�ł��j��������������e�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�t�ɁA�N�ɂł��[���o����悤�Ȑ����i�܂��͗Ⴆ�j���o���Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�G���W�j�A�̋Z�ʂƂ��Ă͑債�����ƂȂ��̂ł͎v���܂��B
�����ԍ��F7339594
![]() 4�_
4�_
2008/02/04 01:22�i1�N�ȏ�O�j
>�܂��A�J�E���^�[��12bit�ɂ��鎖�ɂɊւ��Ă͓��Y�Z���T�[��v�����A���̓��̃v���ł��낤�\�j�[�̋Z�p�ҒB�͎��Ƒ�̓������_�Ɏ������݂����ł����B
�P�ɃJ����A/D��CMOS���ƁA14bit�ɂ����ꍇ�ɒ[�ɘA�ʑ��x�������邩��ł��傤�B
�\�j�[�̃r�f�I�J������14bit���̗p���Ă��܂���B
http://www.ecat.sony.co.jp/business/dvcam_vtr/products/index.cfm?PD=28234&KM=F23
�����ԍ��F7339649
![]() 3�_
3�_
�b��������Ă悭�����Ƃ��̂ł����A���̘b�Ƀf�W�^�������i�����j��
�b�����荞�ޗ]�n�͂Ȃ��̂ł��傤���H�@�����x�B�e��RAW�ŋL�^�������A
�����̃X�e�b�v���i�������ȊK�����j���K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H
�������A�����łǂꂾ���ׂ̍������K�v���A���ׂ̍������@�\����̂�
�̘b�ƂȂ��ł����E�E�E�B
------------------
������
�b�̍���܂��Ă�悤�Ȃ�A�������ė����Ă������� m(_ _)m�i^^�U�j
�����ԍ��F7339708
![]() 1�_
1�_
>�����x�B�e��RAW�ŋL�^�������A
�u���X�̌��q�̃G�l���M�[�� 12bit �����~���������̂�����A����ȏ�̃r�b�g�͕K�v�����v
�Ƃ�������
�u���X 12bit ���������Ƃ��A�I�[�o�[�T���v�����O�̈Ӗ��͂���v
�Ƃ������������Ă���Ǝv���܂���A���́B
�����x�B�e�̓A���v�������邾���ŁA���q�̐��� 12bit ���瑝����킯�ł͂���܂���B
���q��̓m�C�Y(�Ód��)�ɖ������̂��A���邢�͈Ód���ɏ�悹�����̂��A���͂킩��Ȃ��̂ł����A
���̓̓ɂ��� �� [7331819] ��ǂނƁu��f���ƂɈÓd�����r�b�g 0 (�l 0�j �ɐݒ肷��v�����H�H�H ���̕ӂ����͂ǂ������͂킩��Ȃ��̂ŁA����Ă��炲�߂�Ȃ����B
�ł� ���̓̓ɂ��� �̂��b�ׂ͈ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F7339863
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������A�ǁ[���ł��i^^�G�j
�G���W�j�A�̋Z�ʂ����������������̎��_�̈Ⴂ�͉��ƂȂ������Ă܂������i�j�A
�����A�m�C�Y�ɖ�����鎖���A12�r�b�g�ȏ�K�v�Ȃ����̏ɂȂ�̂����A�ǁ[��
�X�b�L�����Ȃ��ł��i^^�G�j
�m�C�Y�ɖ������Ƃ����Ă��M���I�ɂ͉��Z�����킯�ł����E�E�E�H
���������Ă��Ȃ����_�𑪒肷��A���O�Ƀm�C�Y���𑫐�
�i���O�����h���x���̊m��j���o�����Ⴄ�ł��傤���E�E�E�H
�m�C�Y�t���A���ǂ��m�肷�邩�Ŏ��_���Q�ɕ����ꂿ�Ⴄ�悤�ȁE�E�E�H�H
�i���O�ɋK�肵���d���l�Ŋm�肷��̂��A�t���A�����̓s�x���肷��̂��E�E�E�B�j
�����ԍ��F7339922
![]() 1�_
1�_
���̓̓ɂ���̎��_
���q�P�̑��݂ɒ��ڂ��A�B���f�q������������M���̊K�����E�̘b�����Ă���B
�v����ɁA�T���v�����O�̕K�v���E�̘b�ɏœ_�ĂĂ���B
�����I�ɂ́A�m�C�Y�t���A�����炩�̎�@�ɂ����āA���̓s�x�A���O�Ɋm�肵��
�������̂Ƃ���B�i�`�c�ϊ����ɑ���Ɠ�������Ă��܂��B�j
---------------------
�\�^�R�~����̎��_
�B���f�q�̐����M���ɂ����āA�T���v�����O�̕K�v���E���P�Q�r�b�g�ł������Ƃ��Ă��A
���̊O���ʼn��Z�����d�C�I�ȃm�C�Y���A�i�����K���́j�A�i���O�ʂł������A�`�c
�ϊ��i�T���v�����O�j�O�̐M���������K�������i�����K���I�ɗ��U����j���ƂɂȂ�
�̂ŁA�P�Q�r�b�g����T���v�����O�͖��ʂɂȂ炸�A�K�v�����炠��Ƃ��Ă���B
---------------------
�Ƃ������ł�낵���̂ł��傤���l�H
�����ԍ��F7339958
![]() 1�_
1�_
�����Y�̃e�X�g�B�e���Ă����炱��Ȃɒx���Ȃ����Ⴂ�܂����B�e�X�g�B�e���ē���ł��B
���̂����u�f�W�^�����t���ׂāv�ŃX�����Ă��邩������܂���̂ŁA���̎��͌��Ă���������Ƃ��ꂵ���ł� �� ���낱���p���_����@
�ŁA�r�b�g�̉��̕����d�v�Ș_�_�ɂȂ��Ă�Ǝv���̂ł����A���ۂ͏�̕����Ɍ��߂��ł���ˁH
�f�q�̖O�a�d���i�H�j�ӂ���t���r�b�g�ɓ��ĂāA���̎����̕��͂ǂ��܂ŐL�тĂ�A�Ƃ����̂��Ɨ������Ă��܂������B
�f�q���Ƃ̊��x�̃o���c�L��m�C�Y�̃o���c�L�܂߂āA�����r�b�g�ɗ]�T�������������悢�悤�ɂ͎v���̂ł����B����Ƃ� A/D �̑O�Ƀo���c�L�����̂��iD3 �̓J����AD�Ȃ̂Řb�͈Ⴄ��������܂���)�B
��̓I�v�`�J���u���b�N�ł����B
���̕ӂ̂Ƃ���͎��ۂ̂Ƃ���ǂ��������Ƀr�b�g�����蓖�Ă�̂��A�f�l�ɂ͑z�����t���܂���B
�����ԍ��F7339960
![]() 1�_
1�_
�ǂ���ɂ��Ă��u�����x�B�e�ƌ��������āA���̕��͏��ʃX�J�X�J�ɂȂ��Ă�摜�����Ă�ȁv���Ă��Ƃ��킩��܂������A�ƂĂ��������낢�ł��B
�ł�����A���܂肢���݂���Ȃ��ł���Ă�����������Ǝv���܂� m(_ _)m
�����ԍ��F7339964
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������A�����ł��B
����b�ɂ͂��čs���܂��A�������������Ȃ�C���ĉ������i*_*�j���_�i^^�G�j
�����ԍ��F7339969
![]() 0�_
0�_
2008/02/04 09:59�i1�N�ȏ�O�j
��������̑��������킩��Ȃ����ԑт̂���l����i�j
>���q��̓m�C�Y(�Ód��)�ɖ������̂��A���邢�͈Ód���ɏ�悹�����̂��A���͂킩��Ȃ��̂ł����A
�������d�v�ł��B
�Ód���m�C�Y��LSB�ɑ��ď\�������ł���قǏ������A��肭1/8000�ȓ��Ƀ��x���������~�X�J�E���g�͖����ł��傤�B
�������A�m�C�Y�͋ɂ߂ă����_����LSB�ɑ��Ė����ł��Ȃ��U���ω�������܂��B
���̎��g�����S��Ƀ����_���ł����A���ɒ���g���тŖ��ɂȂ�܂��B
�i���̐��̓e���r�ł��̂ŁA���������ɘA���T���v�����O�Ƃ����l�������������Ă��܂����A����f�o�C�X��CCD��CMOS�ł��B�o���I�ɂ��ϑ����Ă݂�Γ������Ƃł��j
�摜�̂���̈�ł͐���J�E���g�A���̂���̈�ł͑����ă~�X�J�E���g�Ƃ������Ƃ��N���蓾�܂��B��T���v�����O�̕��������ڂɂ��Õ��̃m�C�Y���q���e���Ȃ邱�Ƃ��o�����Ă��܂��B
��ʑS�̂�ϕ��I�ɕ��ς�����̓̓ɂ���̎咣�͓����邩���m��܂��A��������������Ζ��炩�ɈႢ�܂��B
���������̓̓ɂ���̎咣�A���q���̉e���͈ӊO�ɑ����̂��Ƃ������Ƃ��悭�F�����Ă��܂��B
NHK�����L���Ă���悤�Ȓʏ�̐��S�{�̊��x�����������x�J�����i�A�i���O�����j�́ACCD��CMOS�Ƃ͑S���Ⴄ���d�ϊ��i�n�[�v�R���Ȃǁj���̗p���Ă��܂����A���̍����x�̈�ɂȂ�ƌ��̗��q�͗L�����ł���Ƃ������Ƃ��͂�����F���ł��܂��B
�i�������p�ꂩ�m��܂��A�ʏ́u���V���b�g�m�C�Y�v�ƌ����Ă��܂��j
���̌�ɔ�������d�C�I�ȃm�C�Y�͂������ꡂ��ɏ��Ȃ����Ƃ͗\�ߊm�肵�Ă��邩��ł��B
�i�����Y�L���b�v�A�v����Ɋ��S�ȎՌ������ăm�C�Y�ϑ�����킩�邱�Ƃł��j
��sRGB��AdobeRGB�̃K���}�J�[�u�̈Ⴂ�ɂ��āB
sRGB�̏ꍇ��ITU-R BT.709�ɏ������Ă��܂��B
ITU-R BT.709 �́A
0.0 �` 1.0 �̓��� x �ɑ��āA
x >= 0.018 �̎��A1.099(x^0.45) - 0.099
x < 0.018 �̎��A4.5x
�� x^0.45 �́Ax �� 4.5 ��������܂��B
�܂�A�ňÕ���4.5�{�ɂȂ�܂��B
�iAdobeRGB�̏����ȃK���}��2.2�Ƃ������Ƃɂ��Ă͎������o�Ă��܂��A�s�색�{���g���[�̃G���W�j�A�ɂ��R�����g�ł�����ԈႢ�͂Ȃ��ł��傤�j
�������猻���\�t�g��3EV�������邱�Ƃ�����i3bit������j�A�ړI�F��̃}�b�s���O�������Ă����ꍇ���A12bit�ł͏\���łȂ����Ƃ�������܂��B
�i���ɈÕ���S/N�͌��������Ă��Ȃ���Ԃ������Ă���̂�����A���q�ʂ͊W�Ȃ��j
>�܂����Ă��K���}�̌v�Z���̒��ԃX�e�b�v�ł́u���Z���x�v�Ɓu���̃f�[�^�̐��x�v���������Ă��܂��ˁB
�Ƃ����R�����g�́A���[�U�[�͌��ʂ������܂���̂őÓ��ł͂Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F7340350
![]() 2�_
2�_
2008/02/04 10:22�i1�N�ȏ�O�j
���������K���łȂ��������ߒ������܂��B
>�摜�̂���̈�ł͐���J�E���g�A���̂���̈�ł͑����ă~�X�J�E���g�Ƃ������Ƃ��N���蓾�܂��B
���F�摜�̂���̈�ł͊ۂߌ덷�͖����ł��Ă��A���̂���̈�ł͖����ł��Ȃ��ۂߌ덷�������Ĕ����Ƃ������Ƃ��N����܂��B
�����ԍ��F7340411
![]() 0�_
0�_
�u���[�~���O�ƃX�~�A�����J���Ă���
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/index.html
�̒��́u�C���[�W�Z���T�̘b�v�ł́A�Â�KODAK��35mm�t���T�C�Y1100����f�̖O�a�d�חʂ����p����Ă܂��ˁB
�ŁA����ȊO�̃C���[�W�Z���T�ŖO�a�d�חʂ��킩��Ȃ����Ƃ�����̂ł����A���ꂪ�[�������ĘI���𑝂₷(�����ԂɂȂ�c�܂�ISO���x��������)�̂����p�ɂȂ�̂ł����14bitAD�ŗǂ����Ă���(�[���Ӗ�������)�ŗǂ��ł����H
14bit���Ӗ��̂���C���[�W�Z���T�����҂������̂�2400����f�̓p�X�������ł��ˁB
���x���グ���ꍇ�ɂ��Ăǂ��Ȃ邩�ɂ��čl����Ɓc
�����ԍ��F7341626
![]() 1�_
1�_
[7339649] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H��:
>> �܂��A�J�E���^�[��12bit�ɂ��鎖�ɂɊւ��Ă͓��Y�Z���T�[��v�����A���̓���
>> �v���ł��낤�\�j�[�̋Z�p�ҒB�͎��Ƒ�̓������_�Ɏ������݂����ł����B
>
> �P�ɃJ����A/D��CMOS���ƁA14bit�ɂ����ꍇ�ɒ[�ɘA�ʑ��x�������邩��ł��傤�B
> �\�j�[�̃r�f�I�J������14bit���̗p���Ă��܂���B
> http://www.ecat.sony.co.jp/business/dvcam_vtr/products/index.cfm?PD=28234&KM=F23
�����2/3"��CCD�Z���T�[�Ȃ̂ŁA�C���[�W�T�[�N���̒��a��12mm�A�𑜓x��1920x1080�A�����`�̉�f�̏ꍇ�A���̃T�C�Y��5.45�~�N�����p�ƂȂ�B
���̃Z���T�[�̗ʎq�����ɂ��čl����B
CCD�Ȃ̂ŁACMOS��f�ƈႢ�A�X�C�b�`���O����A���v�̃g�����W�X�^���`������K�v�������B
����āACMOS�Ɠ���f�s�b�`�ł��ACCD�ł̓t�H�g�_�C�I�[�h(PD)�̖ʐς���傫���ł���ƍl������B
�ʐς̍L��PD�̒f�ʂ́A�����������ł������L�����A�A�X�y�N�g�䂪����ɂȂ�B�c����PD�ɔ�ׁA�߂ɓ��˂������q���d�q�ɋz�������O��PD�̑��ʂ���o�čs���Ă��܂������͌���Ǝv����B
����ėʎq������CMOS�ɔ�ׂĎ�L���ɂȂ�Ǝv����B
1000���~����3���Ɩ��p�r�f�I�J�����̃Z���T�[�ł���A���R�x�C���[�t�B���^�[�����ڂ��Ă��Ȃ��B
�t�B���^�[�̌��ݕ��A�}�C�N�������Y��PD�̊Ԋu�����߂��鎖�ɂȂ�B
�������a�̃}�C�N�������Y�̏ꍇ�A�œ_�������Z���Ȃ�Γ��R f�l ���������Ȃ�B
�܂�A���邢�}�C�N�������Y�ƂȂ�A�W�������オ��̂ŗʎq�������オ��B
�Y�t�̉摜�Ń}�C�N�������Y�̉��Ɉʒu����J���[�t�B���^�[�w�̑�̂̌��݂��c���o����B
�܂��A�t�B���^�[�w����菜�����ɂ��A�}�C�N�������Y��PD�̊Ԋu�͌��\�߂���̂�����B
����āACMOS�̉�f�̗ʎq������50%�Ƃ����ꍇ�A���̃J���[�t�B���^�[�w�����́A�A�X�y�N�g�䂪�L���ƍl������CCD�̉�f�̗ʎq������60%�ɒB����\�����[������B
�X�`�[���J������5.94�~�N�����p��CMOS��f�A�P�O�O���N�X�A�i��f/1.4�A�V���b�^�[1/100s�ł́A���ϖ�@7964.74�@�̌��q����f�ɏƎ˂����B
### CMOS�̗ʎq������50%�̏ꍇ�A�@��4000�̓d�q�@����������B
���Y�r�f�I�J�����̃J�^���O�ɋL�ڂ���Ă���2000���N�X�AT10 ~= f/10�A23.98�R�}�^�b�̊���x�ł́A�V���b�^�[�X�s�[�h��1/23.98s�Ƃ���ƁA�e��f�ɕ��ρ@12634.89�@�̌��q���Ǝ˂���鎖�ƂȂ�B
### CCD�̗ʎq������60%�Ƃ����ꍇ�A ��7580�̓d�q�@���������鎖�ƂȂ�B
����CCD�Z���T�[�̏ꍇ�A13bit�J�E���^�[���K�v�ɂȂ�Ƃ͏[���l������B
���ƁA���̃r�f�I�J�����́u�N�C�b�N���[�V�����v�B�e�@�\�𓋍ڂ��Ă���B
�Ⴆ�Έ�b�Ԃ�24�R�}�ł͂Ȃ��A12�R�}�A8�R�}���̂Q�{���A�R�{���ŎB�e�o����B��R�}�̘I�����Ԃ������Ȃ镪�A�I�o�̕���K�v�ɂȂ�ƍl������B
��f�̐Ód�e�ʂ�ADC�̃����W���O�a���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�d�q�I�ɃQ�C���R���g���[�����s�����Œʏ�B�e�ƃN�C�b�N���[�V�����B�e�Ԃ̘I�o�����Ȃ�����B�������AADC���O�a�����ꍇ�ɂ̓N�C�b�N���[�V�����̑��x�{����ɍ��킹�ĎB�e�����Y�̃A�C���X�ŘI�o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�B�e���ɃA�C���X������̂̓J�����I�y���[�^�[�̕��S�ɂȂ�B
����āA�O�a���ɂ���ADC�𓋍ڂ�������]�܂����B14bit�̃_�C�i�~�b�N�����W��ADC�̏ꍇ�A�R�{���̃N�C�b�N���[�V�����B�e���ł������Q�C���R���g���[���Œʏ푬�x�B�e�̃V�[�N�G���X�ƘI�o�����킹����\�����L��B
����āA���������\�����p�r���ႤCMOS��CCD�Z���T�[��ADC�̃r�b�g���͓����ł����Ă����������Ƙ_����\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^���́A�����P�H�I���Ǝv����B
�����ԍ��F7343787
![]() 1�_
1�_
[7339594] �\�j�[�^�������R�j�J�~�m���^����H��:
> �v���X3EV�܂ő����ł���RAW�����\�t�g�ł́A���ˌ��[������
> �o�b�N�O�����h�m�C�Y�̗ʂ�����Ă��܂��B
> ������Ԗ₢�����A���̐���������܂���B
RAW�����\�t�g�̓J��������̃f�[�^�i�ʏ�12bit�̃R���|�[�l���g�j����Ƀf���U�C�N�A�g�[���}�b�s���O���Z�����s���B
12bit�̌��f�[�^�ł��A������C���v�b�g�Ƃ��鉉�Z�͊ۂߌ덷���̔����Ɗg�U��h���ׂ�16bit�A32bit���̐��x�ōs���̂����ʂł���B
�l�X�ȉ��Z�X�e�b�v���o�Č����\�t�g����������JPEG�ATIFF�t�@�C������16bit�̃R���|�[�l���g�̉��ʃr�b�g�������_���Ƀ[���ł͂Ȃ�����ƌ����āA���ꂪ�Z���T�[�f�[�^��12bit�ȏ�̏��G���g���s�[�i�d�ׂ̒[���j���L���������ƌ��������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�J��Ԃ��Č������A���q�ɔ���������ꂽ�d�q�̐��͗��U�I�ł���A���o�p�L���p�V�^�̓d���͗��܂����d�ׂɔ�Ⴕ�A���U�I�ł���B
�܂��A�o�b�N�O���E���h�m�C�Y�̌��ł���M�ɗ�N���ꂽ�d�q�̓d�ׂ��A���q�ɗ�N������ꂽ�d�q�̓d�ׂ��S������ŁA�ʎq�͊w�I�ȁu�d�C�f�ʁv�Ȃ̂ł���B�܂�A��̓d�q��菬�����d�ׂ͑��݂��Ȃ��Ɖ]�����ł���B
����āAADC�̐��x���グ�Ă��A�S�����d�ׂ̔M�d�q�i�܂�o�b�N�O���E���h�m�C�Y�j�ƌ��d�q�i�܂�M���j�̋�ʓ��ł��锤�������̂ł���B
���l�̑傫�������{�ɂ��悤�Ƃ��A�Ⴆ�t�[���G��͂œ�����m�C�Y�ƐM���̎��g�����z�A�܂��͕��l��͂œ�����G�l���M�[���U�̎w�W���́u�S���v�ς��Ȃ��̂ł���B
�ܘ_�AADC�̃r�b�g�����グ�ē����鉼�z�I�ȓd�ׂ́u�[���v�������I�ɂ͈Ӗ��̖������Ȃ̂ł���B
�d�v�Ȃ̂͌��f�[�^�Ɋ܂܂�Ă�����G���g���s�[�ʂ𒆊ԉ��Z�X�e�b�v�Ŕ�������ۂߌ덷�Śʑ����Ȃ����Ȃ̂ł���B
����������͉��Z�X�e�b�v�̃r�b�g���x�̖��ł���A����ADC�̃r�b�g���Ƃ͖ܘ_�S���W�������̂ł���B
�����ԍ��F7343798
![]() 0�_
0�_
2008/02/05 00:44�i1�N�ȏ�O�j
���̓̓ɂ���
�r�f�I�J�����̌��͎����ŒZ���I�Ǝv���܂����B
���炵�܂����B
�ق��̌����قڔ[�����܂����B
���J�Ȑ������肪�Ƃ��������܂��B
���āA�ł͑f�p�ȋ^�₪����܂��B
���̓̓ɂ���̂悤�ȕ����ǂ̂悤�ȉ�����̂��A����͐̂�����ɋ���������܂����B
�b�����Ȃ��т܂����A�I�[�f�B�I�ɏڂ����ł����H
�����̘b
�����ɤ40�N�O�̍ŐV�Z�p�Ŏ��^�����I�[�v�����[���̃A�i���O�e�[�v������܂��B
���̃e�[�v�f�ނ�S/N�𑪒肵����-48dB��������܂���ł����B
���_�I�ɂ�8�r�b�gA/D��S/N���قƂ�Ǘ����Ȃ��Ńf�W�^�����o����͂��ł��B
�i���ۂɂ̓A�i���O�e�[�v�ɂ͑傫�ȃw�b�h�}�[�W��������܂����A�����ł͘b�̓s���㖳�����܂��j
���̃e�[�v��16bit�Ńf�W�^��������̂́A�����I�Ȃ��Ƃ��܂߂ĈӖ��������ł��傤���H
����́A�A�i���O�f�ށi���^�@�ނ����ׂăA�i���O�j�̃r�f�I�e�[�v���f�W�^��������ɂ��A���l�I�ɂقړ��Ă͂܂�܂��B
�܂��A��L�̓��e�Ƃ��֘A���܂��B
��낵�������痝�_�I�Ȉӌ��������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F7344209
![]() 1�_
1�_
���̓̓ɂ���
�z�����͂邩�ɏ��钚�J�ȕԓ��A��ϋ��k�ł��B
��������ϕ�����₷���A�v�Z���Ă݂��̂ł����A
�Ō�̍Ō�Ŕj�]���Ă��܂��܂����B�B
�ł�����`�F�b�N�����肢�������̂ł����B�B�B
��قǂ̃\�j�[����ւ̕ԓ��ł�����ƋC�ɂȂ����_������܂����̂ŁA
�����܂����Ă��������B
�b�l�n�r�̗ʎq�������T�O���ŁA�b�b�c�̗ʎq�������U�O���ɂȂ肤��B
�Ƃ������ƂŁA�b�b�c�͂P�R�r�b�g�ł��ǂ��Ƃ��Ă��܂����A
��������ƁA�b�l�n�r�̗ʎq�����͂Ȃ��T�O���Ȃ̂��A
�U�O���̉\���͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��^��ɂȂ��Ă��܂��B
�b�l�n�r�̗ʎq�������T�O���ȉ��ł��邱�Ƃ��ؖ����Ȃ�����A
�P�Q�r�b�g�ŏ\���ƒf���ł��鍪���͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����������@�ȉ��v�Z�ł��B��������������
�u2^EV = ���N�X*ISO/12.5�v�̒�`�ɏ]����
2~EV = 100*100/12.5 = 800
����͍i��f/1.0�̂Ƃ���1/800s�Ƃ������Ƃł���ˁH
�Ƃ������Ƃ�f/1.4�̎���1/400s�ł��ˁH�H�i���M�Ȃ��B�B�j
���Ɉ��f�ւ̏Ǝ˃G�l���M�[�̌v�Z�ł����A
�u�����o�[�g���̂�5.94�~�N�����p�̃p�b�`��1/683 * 5.94 10^-6 * 5.94 10^-6 J����˂���B�v
������āA�ȉ��̓���O��ɂȂ�܂���ˁH
�@�����Y�̎B���f�q�̔��Α��ɎB���f�q�Ɠ��������i�œ_�����j�̈ʒu�ɔ�ʑ̂�����Ƃ����{�ɂȂ�B
�A���f�ɓ�����̃G�l���M�[�͔�ʑ̂̋����ɂ��Ȃ��B
�@�͌����Ă݂�Ȃ�قǂƎv���A�ڂ��炤�낱�������܂����B�ʐ^�ɏڂ����F����ɂ�
������O�Ȃ̂�������܂��A���ɂƂ��Ă͑�ςȐV�����m���ł��B
�A�͋�����������A����ȋC�����܂��B�i�������Ɓ��Ƃł����B�B�j
�@�߂��ꍇ�͂悭�킩��܂���B�����܂���B
�Ƃ�����A5.94um������̌����l����悢�Ƃ������Ƃ�
1/683 * 5.94 10^-6 * 5.94 10^-6 = 5.166 10^-14 W�ƂȂ�܂����B
���ɂ��̂��������������Y��ʂ��ē����Ă��邩�ł����A
������ƃX�e���W�A���̒�`��������Ȃ������̂ŁA
���ׂ��Ƃ��닅�̔��a���A���̏�̂��镔�H�̖ʐς����Ƃ������A���^���O�Q
�Ƃ���܂����B��d�ϕ��Ƀg���C���悤�Ǝv�����̂ł����A
�����ł������ɖ����̂ŁA�Ƃ肠�����ȈՓI��
���a�P��̋���z�肵�Af/1.4�̖ʐς���×1/1.4×1/1.4×1/4�i���O�Q���j
�Ƃ��Ă݂�ƁA0.4007�X�e���W�A���ƂȂ�܂����B
���Ȃ݂Ƀ��̓̓ɂ���ɋ����Ă�����������2��(1 - 2N / ��(4*N*N+1))�ł�0.3660
�����炸�Ƃ������炸�B�B�������l�ł���0.3660���g���܂��B
0.3660/2��= .05826�@�E�E�E
���̓̓ɂ���̌v�Z�l5.7191���Ƃт݂�[�ɂ���Ă��܂��܂����B�B
�C�ɂ��������܂��B
5.166 10^-14 W×.05826 = 3.0096 10^-15 W�@�����f�ւ̃G�l���M�[�ƂȂ�܂����B
�����Y�̓��ߗ��̘b�͌덷���x�Ȃ̂ŁA�͂����܂��B�����܂���B
�i�ʎq��������������T�O���ɂ��Ă��܂����A�����ł���ˁB�B�j
�u�̃x�C���[�t�B���^�[���̉�f���l����B
�ΐF�������l�����ꍇ�A�Ⴆ��555nm�̔g���ł͌��q1�̃G�l���M�[ h�� �͖� 3.578 10^-19J �ł���B�v
����͗̒P����Ƃ̉���Ȃ̂ŁA����Ӗ��ň������ł��ˁB
�`�c��I�ԂƂ��̓I�[�o�[�t���[���Ȃ��悤�ɑI�ԂƎv���̂ŁA�K�ȉ��肾�Ǝv���܂��B
�i�Ƃ������P�^683�Ƃ������Z��555nm���O��Ȃ�ł��ˁB�v�������Ō����܂����B�j
h = 6.625 10^-34 J�Es
��= 299,792,458 m/s / 555 10^-9
h��= 3.5786 10^-19 J�@���̓̓ɂ���̌v�Z�l�ǂ���ł��B
�Ƃ������ƂŌ��q�̐��ł����A
1/100s�̏ꍇ�A3.0096 10^-15 / 100 / 3.5786 10^-19 = 84 �B�B�B
�����������������ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�P�O�O�Ŋ�������܂����̂ł��傤���B�B
�����ԍ��F7344439
![]() 0�_
0�_
�u�s�y�Q�T�O�̓Ƃ茾�ł��B
�݂Ȃ���i�������ĂȂ���������܂��B�B�j
�h�r�n�P�O�O�ł̓d�q���S�O�O�O�ɂ���
�^��Ɏv���Ă��Ȃ��悤�ł����A
���́i�������H�j�^��������܂��B
���̐����c�R�ɂƂ��Ăǂ̂悤�ȈӖ����l���Ă݂��
�c�R��T�c�̏ꍇ�P��f�̖ʐς���Q�{�ɂȂ�܂��̂ŁA
�h�r�n�P�O�O�ł͂W�O�O�O�ł��B�P�R�r�b�g�����ł��ˁB
�h�r�n�Q�O�O�ł͂S�O�O�O�A
�h�r�n�S�O�O�ł͂Q�O�O�O�A
�h�r�n�W�O�O�ł͂P�O�O�O�A
�h�r�n�P�U�O�O�ł͂T�O�O�A
�h�r�n�R�Q�O�O�ł͂Q�T�O�A
�h�r�n�U�S�O�O�ł͂P�Q�T�A�Ȃ�ƂV�r�b�g�����łi�o�d�f�ɂ�����Ȃ��f�[�^�ł��B
�h�r�n�Q�T�U�O�O�ł͂R�P�A�T�r�b�g�����B�B
����̂c�R�̂h�r�n�U�S�O�O�̉摜���V�r�b�g�̃f�[�^�������Ă���Ȃ�āB
�����̊ԈႢ�A�Ƃ������ԈႢ�ł����ė~�����I�i������̋��сj
�ȏ�u�s�y�Q�T�O�̓Ƃ茾�ł��B
�����ԍ��F7347902
![]() 0�_
0�_
>[7347902]
�@��������ꂽ�B
1pixel������d�q 4,000�͏��Ȃ����܂��� (2^12=4,096�B12bit��
����Ă��܂��̂ŁA14bit�̈Ӗ����Ȃ��j
�@����ɁA�����d�q 1�P�ʂ̓d�������o�ł���Ƃ͎v���Ȃ��̂ł���?
�����ԍ��F7348331
![]() 0�_
0�_
2008/02/06 00:38�i1�N�ȏ�O�j
�ʂ̌��n����A����ɂ��n���Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂����B
�t�B�����̂��Ƃł��B
�t�B�����̗��q��̑傫���́ACMOS��CCD�̉�f���y���ɏ���������A����q���͂����Ə��Ȃ��͂��ł��ˁB
��������ƁA���q���͔��ɑe���~�������������Ă��Ȃ��āA�f�B�U�����O�I�ɖʐς��g�����~����\�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂�C���N�W�F�b�g�v�����^�̕\�����@�Ɠ����ł��B
�܂�A�u�t�B�������~�����L���ŐF�ʖL�x�A�ƂĂ��f�W�^���J�����͋y�Ȃ��v���Č����Ă���l�̊�͐ߌ����Ƃ������ƁH
��ώQ�l�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F7348904
![]() 1�_
1�_
2008/02/06 01:09�i1�N�ȏ�O�j
>����̂c�R�̂h�r�n�U�S�O�O�̉摜���V�r�b�g�̃f�[�^�������Ă���Ȃ�āB
���q���̂��Ƃ��l����܂ł��Ȃ��A���d�C�I�Ȍ��n������߂����̂�����܂��B
D3���ǂ̃|�C���g����f�W�^���A���v���g���Ă��邩�킩��܂��A�����x��̓f�W�^���A���v�Ƃ����̂����Ώ펯�ł�����ˁB
D3�́A�͂�����ISO��������f�W�^���A���v�Ȃ��A�m��R������܂��B
�����ԍ��F7349030
![]() 0�_
0�_
���x���グ���ꍇ�Ƃ����̂͂ǂ��Ȃ�̂��H���Ă����^��͂��łɓ��������Ă���܂���ˁB
�����ԍ��F7349070
![]() 0�_
0�_
�l���Ă͂��܂��B
kuma_san_A1���� �������ꂽ�����N��
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/ccd/ccd.html
�����́u�R�D�V���b�g�m�C�Y�v�ȉ��͓��e�I�ɔ���Ă܂��ˁB���p����
>Kodak��35mm�t���T�C�Y1100����fCCD�̃X�y�b�N�ׂĂ݂܂����B�O�a�d�חʂ�6���G���N�g�������d�q6���ƂȂ��Ă��܂��B
�ł����AYahoo �ŁuKODAK Full Size sensor�v�ő������q�b�g���܂��B�ȑO�����N�������Ƃ����邩�Ǝv���܂����A
http://www.kodak.com/ezpres/business/ccd/global/plugins/acrobat/en/datasheet/fullframe/KAF-10500LongSpec.pdf#search='KODAK Full Size sensor'
���ꂪ�����ł��傤�ˁB
�����4�y�[�W�ڂ́uSummary Specification�v�ɕ\������܂����A���̒���
Saturation Signal�@60ke
�Ƃ����̂�����ł��傤�B
���Z���x�̕����ōl�@���܂����B
�܂����q��̃G�l���M�[�����߂Ă݂܂��B
�v�����N�萔 h : 6.6 * 10^(-34) Js
���̔g�� �� : 500 * 10^(-9) m
���� c : 3 * 10^8 m/s
�Ƃ��āA��� ch/�� = 4 * 10^(-19) J �ł��B
����� 60,000���̃G�l���M�[�͒P���� 60,000 �������� 2.4 * 10^(-14) J �ł��B
�d�C�f�� q : 1.6 * 10^(-19) C
��p���āA��������d�� = (2.4*10^(-14)) / (1.6*10^(-19)) �� 1.5 * 10^5 V �ł����E�E�E 150 kV�A���Ȃ킿�P�T�O�L���{���g�H
�O�a�d���͂������� 1000mV�A���Ȃ킿 1V ���x���Ǝv���Ă��̂ł����A���͂܂�����ɂ������ĂȂ��悤�ł�(4000�Ƃ��Ă��Aqv/2 �Ƃ��Ă��卷����)�B
�܂����p����
>���[�J�̃X�y�b�N�V�[�g�ŖO�a�d�חʂ��m�F���悤�Ƃ��Ă��A�قƂ�ǂ��O�a�ʂ��C���[�W�Z���T�̍ő�o�͓d���Ƃ��Ă��������Ă��܂���B�d�ׂ��o�͓d���ɕϊ�����Ƃ��̏o�͊��x���d�l�ɏ�����Ă���A��������v�Z���ċ��߂邱�Ƃ��ł���̂ł���
���ꂪ�u�o�͊��x�v�Ȃ̂ł����B
����
>APS-C�T�C�Y��600����f��z�u�����C���[�W�Z���T�̏ꍇ�A1��f������̖ʐς͖�6.1×10-11�������[�g���Ȃ̂ŁA���q�̐���14���ɂȂ�܂��B
���̌v�Z���킩��Ȃ��̂ł����ǁB
(2.3×10^15) / (6.1×10^-11) = 3,770 �ŁA��4000�ł���ˁH
�Ȃ��珑���Ă���lj��������݂������݂����Řb�̗���Ƃ��Ă͂���ł��傤���B
���������͎̂����ŕ����ׂ����̂Ȃ̂ł��傤���ǂˁB
�����ԍ��F7349134
![]() 0�_
0�_
�ȂB�O�a�d����o�͊��x�ɂ��Ă��R�_�b�N�� pdf �ɂ͏����Ă���܂��ˁB
12�y�[�W�� Specification �̕\����
Saturation Signal Nom. 1500 Units mV �ł�����A�O�a�d���� 1500mV�B
Output Sensitivity Nom. 25 Units ��V/e �ł�����A�d�q��ӂ�̏o�͊��x�� 25��V �ŁA�d�q�̌� 60,000 ������ɂ�����ƁA�m���ɖO�a�d���� 1500mV �������܂��B
���l�I�ɂ͂���ł����̂ł����A�u�o�͊��x�v���ĉ������I
1.5 * 1.6 * 10^(-19) = 2.4 * 10^(-19) J
����A��ɋ��߂����q 60,000�̃G�l���M�[�� 2.4 * 10^(-14) J �ŁA10���{���̍�������܂��B����͑S���M�ɂȂ�H
�����ԍ��F7349223
![]() 0�_
0�_
�M�ɂȂ���Đ���������܂�����B
�ŁA�d���͓d�ׂ߂�L���p�V�^�̗e�ʎ���(CCD�͓d�ׂ�]���H���g���ĉ^��ł�������)�B
�ŁACMOS�C���[�W�Z���T�̏ꍇ�̓Z�����ɓd���ϊ����Ƃ�����PGA�������ł���ˁc�B
�������Ȃ��ꍇ(�悤����ɃL���p�V�^�ɂ���ēd����ǂ�)�͊m���̖��ɂ��뗣�U�I�Ƃ��������́u�������v�Ƃ��v����̂ł����APGA���������ꍇ�A�����ɂ��m��������H�̂ŁA���߂���̂��H�ƁA�������������������]�ł͏������i�݂܂���(�Ƃ������v�Z�͔C���܂�)�B
�����ԍ��F7349264
![]() 0�_
0�_
�����X���炵�܂��B
�V���ɃX�����Ă���̎��ł��Ȃ��̂ŁB
����̎B���f�q��D3X�Ɏg���Ȃ�A���i��D3�Ɠ����ɂ���Ζ��Ȃ����Ǝv���܂����B
���炭��900�͂��Ȃ�}����ꂽ���i�ɂȂ�ł��傤����A�f�q��V���ɊJ�����Ă�1Ds3���݂̉��i�ł͏o���ɂ����ł��傤���B
����12bit 6fps�ł�D3�̃{�f�B�ł̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł��傤����A�N���b�v1000����f���ɗ̓ǂݏo����f����2/3�ɂȂ邱�Ƃ��A�R�}��3/2�{�A9fps���x�Ɍ��т��鎖���B���f�q�̋@�\�Ƃ��ĉ\�łȂ��ƃ_���ł����B
14bit 1.5fps���[�h�����B��p�ɗL���Ă������ł��傤�B
�ǂ����炵�܂����B
�����ԍ��F7349722
![]() 0�_
0�_
2008/02/06 09:48�i1�N�ȏ�O�j
�t�B�������u�f�W�^�������f�q�v�Ȃ̂��A�Ƃ������ƂŎ��̓��͂܂Ƃ܂�܂���(*^_^*)
�����ԍ��F7349855
![]() 0�_
0�_
������
�w�g�[���W�����v�����邮�炢�Ȃ�E�E�E�x ���Ă����܂Ƃ܂���ł��傤���H�i^^�G�j
�����ԍ��F7351111
![]() 0�_
0�_
2008/02/06 17:23�i1�N�ȏ�O�j
�w�g�[���W�����v�����邮�炢�Ȃ�E�E�E�x
�����͂Ƃ������AA/D�̃r�b�g�����҂��i�����G�e���ʂł��j�q�X�g�O�����͎������ɂȂ�܂���B
�i��ʑS�̂��Ȃ炵���\���@�\�ł�����j
����ŗǂ���ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F7351283
![]() 1�_
1�_
�\�^�R�~����Ǝ��̍l�����͎��Ă�悤�ł��ˁB
�����Ƃ��A���̏ꍇ�A�w���������炠�����ɍs���Ȃ������ł����E�E�E�i^^�G�G�j
�����ԍ��F7351294
![]() 0�_
0�_
>>APS-C�T�C�Y��600����f��z�u�����C���[�W�Z���T�̏ꍇ�A1��f������̖ʐς͖�6.1×10-11�������[�g���Ȃ̂ŁA���q�̐���14���ɂȂ�܂��B
>
>���̌v�Z���킩��Ȃ��̂ł����ǁB
>(2.3×10^15) / (6.1×10^-11) = 3,770 �ŁA��4000�ł���ˁH
�����Ăǂ������B�����Ȃ���ʖڂł��B
��Z����� APS-C 600����f�ł̌��q�̐��͂����Ɓu14����/��f�v�ƂȂ�܂��B
���l�� ISO100 �ł̍ő�P�x���̃t���T�C�Y(36×24mm)�u�S�́v����(555��m �̔g���̌���)���q����
1.9872 × 10^12
�}���u2���v�ł��B
��̃R�_�b�N�̃Z���T�[�� 11Mpixel �ł�����A���q���́u��18����/��f�v�ł��B
�X�y�b�N�V�[�g�ł́u6���v�ł�����A�S�̂� 2/3 �͗ʎq���������}�C�N�������Y�̎�������̒Ⴓ(���˂���H)�����Ŏ������ł��傤���ˁB
���l�ɃX���^�C�̃\�j�[�̃Z���T�[�̏ꍇ�A���q���́u��8����/��f�v�ł��B
�������R�_�b�N�ɂȂ���� 1/3 �Ƃ���A��2��7���(14bit�ȏ�)�̌v�Z�ɂȂ�܂��ˁB
�Ƃ��������ōl�������Ă݂ẮH
���� ���̓̓ɂ��� �̏������݂�ǂݒ����Ă݂܂���(�O�͗����ł��Ȃ��������Ƃ��A���͏����͗����ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����̂�)�B
�����ԍ��F7351705
![]() 0�_
0�_
2008/02/06 19:45�i1�N�ȏ�O�j
�L����ʑS��ɍ~�蒍�����q�̐��͖c��ł��ˁB
�i�܂�S�̂Ō���Ζ����Ƃ��������~�����j
���Ȃ��r�b�g���Ń��~�b�g����ƁA�S�f�q���ŋς��Ă��A�Ⴆ���𑜓xGIF�摜�̃q�X�g�O����������Ε�����悤�Ɏ�������Ԃ͕ς��܂���B
�i��ʑS�̂Ŗ����~���Ȃ̂ɁA���̎������H�j
���͂��̊ϓ_�����14bit�͗L�p���ƌ����l���ł��B
���͂��̍l���́A��̃A�i���O�I�[�f�B�I�̃f�W�^�����Ɏ��Ă��܂��B
S/N-48dB�̃A�i���O�I�[�f�B�I�\�[�X��8bit�̃T���v�����O�ŏ\�����Ƃ����l����������܂����8bit�̉����Ă݂�ΒN�������Ƃ͎��Ď����ʍ��������Ǝ������܂��B
�i����ǂ��납�A�A�i���O�I�[�f�B�I�\�[�X�̃f�W�^������16bit����24bit�̕������炩�ɗǎ��ɂȂ�Ƃ����Տ��I�Ȏ���������A�^���ƊE�ł��펯�����Ă���j
���ꂪ���̂��Ƃ��������́A���̃X���ʼn��x���\���܂����B
�����ԍ��F7351753
![]() 1�_
1�_
���s�̂��������
�L��������܂����B�Ƃ肠�����A���̐S�͋~���܂����B
���S���āA�c�R�ɂ�������Ă������Ǝv���܂��B�i�����Ȃ����ǁB�B�j
�����A���s�̂��������̌v�Z�͖O�a�d�חʂ���A
���̓̓ɂ���̌v�Z�͘I�o���痈�Ă���̂ŁA
�I�o����̌v�Z�������悤�ȃI�[�_�[�ɂȂ�Ƃ���Ɉ��S�ł���̂ł����B�B
���s�̂��������̕������Ă����ȉ��̖����H�ɂ��Ăł����A
�u����� 60,000���̃G�l���M�[�͒P���� 60,000 �������� 2.4 * 10^(-14) J �ł��B
�d�C�f�� q : 1.6 * 10^(-19) C
��p���āA��������d�� = (2.4*10^(-14)) / (1.6*10^(-19)) �� 1.5 * 10^5 V �ł����E�E�E 150 kV�A���Ȃ킿�P�T�O�L���{���g�H�v
���̌v�Z�͂U�O�O�O�O���̃G�l���M�[���P�̑f�d�ׂŊ����Ă���̂ŁA
�傫�Ȓl�ɂȂ��Ă���C�����܂��B���̕��@�Ōv�Z����Ȃ�A�U�O�O�O�O���̓d�ׂ�
�������ق����A��萳�����d���ɂȂ�C�����܂��B�����A��������d����
�U�O�O�O�O�̓d�ׂ��L���p�V�^�i�t�H�g�_�C�I�[�h�j�ɏ[�d�����ƍl����悢�̂ŁA
�p���b�u����A�f�d��×�U�O�O�O�O�^�b�Ōv�Z����悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�Ƃ���ƁA�o�͊��x���đf�d�ׁ^�b�H�H
�M�Ɋւ��Ăł����A���œd�q����N�����Ƃ��ɕK�v�ȃG�l���M�[�i�r���Ȃ��P�u���炢�j�ɑ��ė]�������������̂̊i�q�U�����M�ɂȂ�Ƃ������Ƃ������Ǝv���܂��B
�w������̉����̂ɏK�������ƂȂ̂ł���o���ł����B�B
�����ԍ��F7352207
![]() 0�_
0�_
���s�̂��������
�����܂���A�I�o�̘b���͂����Ă��܂��ˁB
�c�R�ق����ł��I
�����ԍ��F7352391
![]() 0�_
0�_
���������BPC ���s���ŋ}篌Â� PC (�ڒ��ڒ��x���I�j����������o�����̂ł����A���X�ƕԐM�������āu���e���m�F����v�{�^������������u���O�C�����Ă��������v���āA�S�ď����Ă��܂��܂����B�u���E�U�̖߂�{�^���ł����͕͂������Ȃ����B�F�����ӁB
�����������͂͏����܂��A���Ƃ��Č��ł���悤�撣��܂��B
VTZ250����
���̈ӌ��̓R�_�b�N�� pdf ��
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/ccd/ccd.html
�����́u�� ���q���̌v�Z���@�v����������̂܂ܗp���������ł��BCIPA �̊��x�K����m��܂����N�X��[�����������̋L�q�����̂܂܍̗p���܂����B�Ȃ̂ŊF������l���Ă݂Ă��������B
�����̌�A�𐳂��Ă����܂��B
>�t�Z����ƍő�P�x�i�O�a�j���̘I���ʂ�0.1/0.18��0.56���N�X�b�ł��B
�������́u�I���ʂ�1/0.18��0.56���N�X�b�v�ł��B
�����̃y�[�W�́u���q�̐���2.3×1015�ł��v���g���A�t���T�C�Y�Z���T�[�� ISO100 �̍ő�P�x���̌��q���� 2���Ƃ��o�܂���BAPS-C �Ȃ炻��� 1.53^2 �Ŋ���Ƃ��B����ň��f������ł�����P���ɉ�f���Ŋ���ƁB
��������ƃR�_�b�N�� 18���Ȃ̂ł����A�X�y�b�N�V�[�g��ł� 6���ƁB�������S�Ă̌�������킯�ł͂Ȃ��̂�(�����ɉ��ǂ̗]�n�����邩��)�B
>�܂����q��̃G�l���M�[�����߂Ă݂܂��B
�@�E�E�E�E�E
>�Ƃ��āA��� ch/�� = 4 * 10^(-19) J �ł��B
����͂��̃����N�ɂ��u555nm�̔g���̌��q1�����G�l���M3.58×10-19�W���[���v�Ƃ���܂��ˁB�g���� 500nm �ɂ��Čv�Z���������ŁB
>����� 60,000���̃G�l���M�[�͒P���� 60,000 �������� 2.4 * 10^(-14) J �ł��B
���ꂪ�u���f���O�a���Ɍ��q�����S�G�l���M�[�v�ł����A555nm ��p���� 2.148 * 10^(-14) J �ɕς��܂��B
>�d�C�f�� q : 1.6 * 10^(-19) C
>��p���āA��������d�� = (2.4*10^(-14)) / (1.6*10^(-19)) �� 1.5 * 10^5 V �ł����E�E�E 150 kV�A���Ȃ킿�P�T�O�L���{���g�H
���ꂨ�������ł��ˁB
[7349264]
>�ŁA�d���͓d�ׂ߂�L���p�V�^�̗e�ʎ���(CCD�͓d�ׂ�]���H���g���ĉ^��ł�������)�B
�d�� V ���X�y�b�N�V�[�g����u1.5�v�ƋK�肵�āA�ނ���L���p�V�^ C �����߂�ׂ��Ȃ̂ł��傤�B�����ēd�חʂ� Q �N�[�����Ƃ��܂��B
���f�̃G�l���M�[�F2.148*10^(-14) = (C(V^2)) / 2 = (QV) / 2
��Ԗڂ̎��� C �͋��܂�܂����A�����ł͂ނ����Ԗڂ̎��ɒ��ڂ��āA
Q = (2*(2.148*10^(-14)))/1.5 = 2.864 * 10^(-14) �N�[����
�����d�C�f�� 1.6 * 10^(-19) �Ŋ���ƁA���P�ʂ̓d�q���uN�v�����܂�A
N = 1.79 * 10^5
�ŁAN �͖� 18���ł��B
���� N ����ɋ��߂��u�R�_�b�N�� 18���Łv�ƈ�v����̂͋��R�ł��傤���H
���āA���R�ł��傤�ˁB
���Ԃ� 6���Ƃ̍��ŁA2/3 �̃G�l���M�[���M�Ƃ��Ď�����̂ł��傤(���M����)�B
���Ɓu�o�͊��x�v�͒P���Ɂu�d�q��̏o�͓d���v�ł����Ǝv���܂���B���q������������(�d�q���G�l���M�[���������)���ꂾ���̓d��������ƁB�O�a���ɂ� 6���S����������邩��A60000 ���|����ƖO�a�d���� 1.5V ���o�܂��B
�Ō�Ɏ֑��B
�O�a�d���̓L���p�V�^�e�ʂŌ��܂���Ƃ��Ă����܂��B
�f�q�̐����A�v�ɂ����ďo�͊��x�����������邱�Ƃ��\�Ȃ̂��͒m��܂��A�����\�ł����(ISO���x�͒Ⴍ�Ȃ邩������܂���)�O�a�d�חʂ𑽂����邱�Ƃ��o����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�܂�A�_�C�i�~�b�N"�����W"���g�傷��(18���ɋ߂Â���)���Ƃ��o����̂ł́H �Ƃ̖ϑz���B
�������o�͊��x��������(���U��������)����̂ŁAA/D �I�ɂ͐��x���������Ȃ�ł��傤���B
�����ԍ��F7353738
![]() 0�_
0�_
>���f�̃G�l���M�[�F2.148*10^(-14) = (C(V^2)) / 2 = (QV) / 2
>
>��Ԗڂ̎��� C �͋��܂�܂����A�����ł͂ނ����Ԗڂ̎��ɒ��ڂ��āA
>
>Q = (2*(2.148*10^(-14)))/1.5 = 2.864 * 10^(-14) �N�[����
Q' = Q/3
�Ƃ����B
��ԖڂƎO�Ԗڂ̎����(�ƌ������R���f���T�[�̎����)�A
C = Q' / V
�Ƃ��� C (�t�@���b�h) �͋��߂�ׂ��ł��傤�ˁB2/3 �͔M�Ƃ��Ď�����̂�����B
�����ԍ��F7353749
![]() 0�_
0�_
>���X�ƕԐM�������āu���e���m�F����v�{�^������������u���O�C�����Ă��������v���āA
>�S�ď����Ă��܂��܂����B�u���E�U�̖߂�{�^���ł����͕͂������Ȃ����B�F�����ӁB
�@���C�������@�����܂��B�������x�����̗J���ڂɉ�܂����̂ŁA�A�N�Z�T���[�̃������͒����̎��͌������Ȃ��ł��B
�E�E�E�F�l�A�J�J�N�R���^�C�}�[���������A��p�S���E�E�E
�����ԍ��F7354838
![]() 0�_
0�_
>�t�Z����ƍő�P�x�i�O�a�j���̘I���ʂ�0.1/0.18��0.56���N�X�b�ł��B
�����A����Ȃ��ł��B�{�P�Ă܂��ˁA�����܂���B
�d�v�Ȃ̂�
>CIPA�i�J�����f���@��H�Ɖ�K�i�j�ł́A�摜��RGB�f�[�^��118�ƂȂ�Ƃ��A�C���[�W�Z���T�̘I���ʂ�0.1���N�X�b�ƂȂ�̂�ISO100�Ƃ��Ă��܂��B
���̂�����ł����A�o�T�������܂����B
http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/cipa-kikaku_list.html
��������̃����N��
http://www.cipa.jp/hyoujunka/kikaku/pdf/DC-004_JP.pdf
����� 19�y�[�W�ڂɂ���
�uS = 10 / Hm�v
�Ƃ����̂�����ł��B
���������œ��������̂ł͂Ȃ��̂ŁA�����͖��m�F�ƌ������[�����Ă���킯�ł͂���܂���(�I�o�̊T�O�́H�Ȃ�)�B
���̓̓ɂ��� �� [7338992] �̏������݂������͂܂������ł��Ă��܂���B
�����ԍ��F7357738
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�j�R�� > D3 �{�f�B�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 6 | 2025/02/22 17:02:47 | |
| 9 | 2024/12/02 20:30:05 | |
| 15 | 2023/05/20 14:10:11 | |
| 4 | 2023/03/19 19:26:53 | |
| 21 | 2023/02/23 20:29:09 | |
| 11 | 2022/12/01 7:51:19 | |
| 11 | 2022/10/08 20:42:36 | |
| 6 | 2022/07/18 7:31:22 | |
| 9 | 2022/10/10 15:21:26 | |
| 13 | 2022/04/22 17:46:15 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zA20?
-
�yMy�R���N�V�����z30���\��
-
�y�~�������̃��X�g�z�T�[�o�[�p����PC �\����
-
�y�~�������̃��X�g�z10��7��
-
�y�~�������̃��X�g�z�����Y
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- TVS REGZA�̂������߃e���r5�I �L�@EL��mini LED�����掿�I�y2025�N9���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- �H��ߖ�̐�D�I �X�[�p�[�ł��g�N�ȍŋ��N���W�b�g�J�[�h7�I �y2025�N9���z

�N���W�b�g�J�[�h
- ����ł��������I 4���~�ȉ��̍��R�X�p�X�}�z�uOPPO Reno13 A�v

�X�}�[�g�t�H��
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j