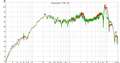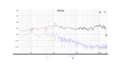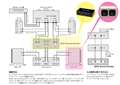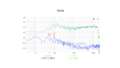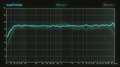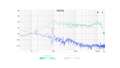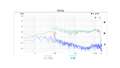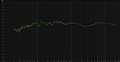�̔������K���}�C�N���������̂ŁA�����ɏ��߂ăX�s�[�J�[���肵�Ă݂܂����Ƃ���A��肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA�X�s�[�J�[����o���҂̕����܂����狳���Ă��������B
������@��
�}�C�N/ROLAND CS-15
�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6
����\�t�g/REW
�X�s�[�J�[/707S2
PC/win11
��/�����̑���摜
�E/�l�b�g�ɂ���������摜
REW���C���X�g�[���A�Z�b�e�B���O���đ���܂ł͂ł��܂������A�v���������̎��g�������̃O���t�ɂȂ�܂���ł����B
���������ł��傤���H
�����ԍ��F25388370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
����肭����ł��Ă�̂�������Ȃ������̂ŁA
�������ΐ��ɂȂ��ĂȂ��̂ŁA�Ԉ���Ă����ł���
�����ł悭�g���̂�MySpeaker
�ȒP�Ȃ̂�
����X�^�[�g
SP����X�C�\�v��
�}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H
�����ԍ��F25388409�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���G���[�S������
iPad mini��ETNiRTA�A�v�������đ��肵�����ʂł��B
�X�s�[�J�[��KEF iQ70�ł��B���X�j���O�|�C���g�ł̑���ł��B
�}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H
�����ԍ��F25388578
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
��Minerva2000����
���}�C�N�ŏE����PC�ɃO���t�\���ł��傤���H
�����ł��ˁB
����ʂ���܂������B
https://audio-seion.com/rew-install/
���}�C�N�̓X�s�[�J�[�����Ɍ����Ă��܂����H
���X�j���O�|�C���g�Ō����Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25388736
![]() 2�_
2�_
��Minerva2000����
�������ɂ悵����
����Ȃ�o�܂����B
�A�v��/spectroid
���X�j���O�|�W�V����
�����ԍ��F25389216�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�A�v��/audacity
PC/win11
���X�j���O�|�W�V����
PC�̕����Ƃ��܂����܂�����ł��ĂȂ��悤�ł��B�B�B
�����ԍ��F25389218
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
�X�}�z�A�v���̕����ȒP�̂悤�ł���
������̌f���ł݂������̂�
�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����
�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����
�A�v����spectroid�Ǝ����悤�Ȋ���
�X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�
���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���
�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H
��ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������
(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)
�����ԍ��F25390019�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�������ɂ悵����
���x���肪�Ƃ��������܂��B
��������̌f���ł݂������̂�
�A�v��Sound Analyzer�Ńs�\�N�z�[���h����
�ቹ���獂���܂ŃX�C�\�v���𗬂�����
������������Ă݂܂��B
���X�}�z�}�C�N�̓����̓t���b�g�ł͂Ȃ������Ȃ̂�
���E��SP�������悤�ɖ��Ă���m�F���x���ł���
�����Ă����OK�Ƃ���Ă͂������ł��傤���H
�����ł��ˁB
�X�}�z�}�C�N���Ƃ��܂ЂƂȊ��������܂����A������x�̊m�F�p�Ƃ��Ƃ��܂��B
����ݔg�m�F���ƁA����p�}�C�N���ق�������
(�����Ȃ̂�EMC8000�A5��~���炢)
�x�����K�[�̓R�X�p�����݂����Ȃ̂ŁA���S�ғI�ɂ͏�����܂��B
UM2 U-PHORIA�̒��Âƍ��킹��1�����炢�Ȃ̂ŁA�|�`�낤���������ł��B
���ɂ��C���^�[�t�F�C�X�ł����̂���Ό����������ł��ˁB
������
BEHRINGER/UM2 U-PHORIA
Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)
���Ȃ݂ɐ̔������AEDIROL/UA-20�̓h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł����i��
������������ASOUND BLASTER G6�̃}�C�N���́iASIO�j���������Ă�̂��B�B�B�䂪�c��܂��B
REW���̂͂��������@�\�ȑ���\�t�g�Ȃ̂łȂ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�ł��B
�������傢�����Ă݂܂��B
�����ԍ��F25390051
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
��EDIROL�h���C�o���Ή����Ă��炸�g���܂���ł���
�h���C�o�[���v���p�e�B�ŊJ��
XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��
����Ă͂������ł��傤���A��������
�����͒�ݔg�����邭�炢�Ȃ̂ŁA
���p��(�ۋ��Ȃ�)�̂܂g���Ă܂��B
�����ԍ��F24077278
�ቹ�ʼn�����������g��������
�����Ɗi�i�ɃX���[�Y�ɂȂ�܂���
����ƋC�Â����Ƃ��A���낢��o�Ă��܂��B
��REW�͑��@�\�Ȃ�Ƃ��g�����Ȃ������Ƃ�
�悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�
��������g�����Ȃ������悳�����ł��B
�����ԍ��F25390285�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
���x�ǂ����B
��2ch�ł�����𐮂���̂��d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B������AV�A���v�̕���ʂłƂ�ł��Ȃ��ቹ�ʉ��ɋC���t���APC�̃w�b�h�z���p�O�t��DAC�ɂ��܂���MIC���͂��������̂�ECM-8000(4��~�}�C�N�j�ƃt���[�\�t�g��F�����肵����A��ݔg�ɋC���t�����S�Ƃ͂����Ȃ��܂ł��Z�b�e�B���O�őēd�C����܂����B
�܂��ɂ���ł��ˁB
��XP�Ƃ��Â�OS�̌݊����[�h�ŃC���X�g�[��
����Ă͂������ł��傤���A��������
�����Ă݂܂��B
��肭�s���A�C���^�[�t�F�C�X��V�K�w������K�v�͂Ȃ��Ȃ�܂��ˁB
���悢�\�t�g�̂悤�ł��ˁA���ꂩ��Ȃ�
��������g�����Ȃ������悳�����ł��B
���Ȃ݂�REW�i�����j�́A���[���`���[�j���O�@�\������݂����ł��B
https://m.youtube.com/watch?v=78qQph0jet4
�Ƃ���ŁA�ʃX���̌��ǂ��ł��傤��?
��������m�F���Ă��炦��Ə�����܂��B
���V�����삵�܂����i��
�����ԍ��F25387497
�����ԍ��F25390379�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
�����V�����]�l�[�^�[�A�ǂ̂ւ�ɐݒu����̂����ʍ����ł���?
�����Ƃ��Ă܂����A���݂܂���
���_�N�g�̉�����̕ǖʂɁA
�ǂ�ɂ߂Ȃ��e�\�v�Ŏ��t����
�������ł��傤��
SP�̗����̕ǂɃv���[�g��\������
�悭�Ȃ����Ƌ��Ă���
���˂�蒼�ډ����o���Ă�_�N�g��
�G�l���M�[���傫���Ǝv���܂����B
���]�l�[�^�[�ŏ�����v���[�g��
�O���邩��(����)
���]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��
�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��
�z�����ʂ����肻���ł��B
�ʎY���Ď���SP�ɕ��荞��ł܂���
�z���ނȂ��Ő����L���L�����˂��锠��
���]�l�[�^�[�𐔌���邾����
���������������A
�z���ނŋl�܂��Ă�������
�z���ނ𔖂��\�邾���ł悭�Ȃ��Ă܂��B
�����ԍ��F25390419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
�����]�l�[�^�[�̓L�b�`���y�[�p�[��
�g�߂ŁA�ׂ�Ă��߂�̂ň����₷��
�z�����ʂ����肻���ł��B
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
���́A�����ɓV�Ղ玆�ō��܂����B
������T�E���h�o�[�̃E�[�t�@�[����1�Âݒu���ėl�q�݂Ă܂��B
�����A�L�b�`���y�[�p�[�ł����삵�Ă���A�ʎY���Ă݂悤�Ǝv���܂��B
��ɑ��肵�Ă���A��ݔg������Ŗ������邩�ǂ����ł��ˁB
���ƁA�O�ׁ̈A�m�F�ł����AECM8000������Ƃ��ŕϊ�����G6�ɐڑ����Ă��g���܂�����?
https://www.monotaro.com/g/05296435/?t.q=xlr%20%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
���̃}�C�N���P��w�����Ȃ̂ŁA���ꂪ�������Ă��̂��B�B�B
��薳����A����p�}�C�N������ɍw�����悤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25390442�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���G���[�S������
����ɂ��́B
����͊y�������ȃX���A�Q�l�ɂ����Ă��������܂�^^
�O���t�̏c���͏㉺50db�͈̔͂ő�����̂���{�`�炵���ł��B
�����ԍ��F25390464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
��ECM8000������Ƃ��ŕϊ�����
G6�ɐڑ����Ă��g���܂���?
�c�O�Ȃ���g���܂���
G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p
ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B
PC�p�ŊO�t����USB DAC������
DTM�p�r�ŃR���f���T�[�}�C�N���͂�
�t���Ă�����ł��B
�����ԍ��F25390484�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
��G6�̓_�C�i�~�b�N�}�C�N�p
ECM8000�̓R���f���T�[�}�C�N�ł��B
�Ȃ�قǁB
�ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?
������@��
�}�C�N/ROLAND CS-15�i�R���f���T�[�}�C�N�j
�C���^�[�t�F�C�X/Sound Blaster G6�i�_�C�i�~�b�N�j
����\�t�g/REW
�X�s�[�J�[/707S2
PC/win11
ROLAND CS-15
https://www.roland.com/jp/products/cs-15/
���Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X�����Ƃ������������ł����ˁB
XLR�ڑ��ł���^�C�v
���������C���^�[�t�F�C�X
BEHRINGER/UM2 U-PHORIA
Focusrite/Scarlett Solo (3rd Gen)
������}�C�N
ECM8000
���������A�X�s�[�J�[����̐��������������Ă��Ȃ��̂ł��݂܂���B
�����ԍ��F25390536�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
���ƂȂ�ƁA����������肭����o���Ȃ����̂́A�}�C�N�������ł�����?
���̂悤�ł��ˁB
�R���f���T�[�}�C�N�́A
�d���������ł���}�C�N�[�q���K�v
�����Ⴀ����ɁA���̕ӂ̃C���^�[�t�F�C�X
�R���f���T�[�}�C�N�p�A48V�t�@���^���d����
�t���Ă���Ύg����ł��傤�B
�����ԍ��F25390619�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
���肪�Ƃ��������܂�!
�䂪�����܂���!
�߂��Ꮥ����܂����B
����p�}�C�N�i�S�w�����R���f���T�[�j�ł����ƌv�����āA��肭�����������Ă݂܂��B
�����ԍ��F25390664�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ƍŋߋC�Â��܂������A�X�s�[�J�[�͔����܂ł��y�����ł����A�����Ă���̕�������Ɋy�����ł��ˁB
�X�s�[�J�[�̐��\���ǂ��܂ň����o���邩�A�Ȃ����Ɏ��Ă�ȁB
https://ordinarysound.com/measurement-basic/
�����ԍ��F25390700�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
���X�s�[�J�[�͔����Ă���̕���
����Ɋy����
�����v���܂��B���ƒP���Œu������
�����ʒu�ł����F���ω�����̂�
�����w�W���Ȃ��ƁA
�Ƃ�悪��̌��I�ȉ��ɂȂ���
���܂����O������܂��B
���肷��Ə��͂߂�̂�
�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�
���������₷���Ȃ�܂��B
�����ԍ��F25390846�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���A�v��/spectroid
��������g���Ă܂��B���������B
�����������̎��g�����特�o�Ă܂��ˁA�X�s�[�J�[�ɋ߂����炩�ȁB
�ݒ�ς�������ƍׂ����\���ł��܂���B���ꂾ��1������5db���݂ł����B
�����ԍ��F25391090�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
�����肷��Ə��͂߂�̂�
�傫���O���͓̂��ݎ~�܂�
���������₷���Ȃ�܂��B
�ЂƂ܂��A���E��ʁX�Ɍv���������܂����B
���̃A�v������Ԏg���₷�������B
�v���C���[/audacity
�v���A�v��/spectroid
���X�j���O�|�W�V����
L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H
�P�O�OHz�O��Ƀf�B�b�v�i��ݔg�j�����銴���ł����ˁB
���̕ӂ����V�Ńt���b�g�ɂł��邩�A�����A�����Ă݂܂��B
�����ԍ��F25391322
![]() 2�_
2�_
CD�������Ă���Ɖ��y�V�F�ЁASTEREO�t�^�u���ɂ̃I�[�f�B�I�`�F�b�NCD 2013�v������܂����B
FM�t�@�����A�����S�j���ďC�̓����悤�ȕt�^���������i�s���s���ł����j
�������C�����̕x�m���K��̐��\�������Ă܂����i�֒e�C�̔��ˉ��j�A���C�@�֎Ԃ̏d�A�Ƃ�
�����ԍ��F25391363
![]() 2�_
2�_
��ݔg�̓f�B�b�v�ł͂Ȃ��s�[�N�ł��ˁB110Hz������ɂ���܂��B
�����ԍ��F25391410
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
��L/R�̃o�����X�I�ɂ͂ǂ��ł��傤���H
�����Ă܂��ˁA����Ȃ�
���̂܂܂ł��悳�����ł���
�\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��
�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H
(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A
���炷�����Œ���������ł�)
110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���
�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�
�f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I
���߂ŕ����̂�
���E�̍����A�����̉e�����A
���Ȃ��̂ł��傤�B
�����ԍ��F25391477�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�X�����قƂ�ǒǂ��Ă��Ȃ��Ă��݂܂��A25391322 �̃O���t�A������ߋ����Ƃ͌����ɒ�� 3Hz �܂łقڃt���b�g�ɏo�Ă���͕̂ςł��ˁB
���g���̃A�v���ɕs�ڂł����A���炭���ł�FFT�̃T���v����������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��i�J�N�J�N���Ă��܂���ˁj�B�����g�X�C�[�v�^�s�[�N�z�[���h�ő����Ă���Ȃ�X�C�[�v���������ɂ���A���邢�͒�퐳���g�ő���ƁA�܂������Ⴄ���ʂɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB
��� 6kHz �ȏ�̍���ɋ����������鏊�� B&W ���ۂ��ł����ˁB
�����ԍ��F25391542
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
�݂Ȃ���
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
���\�t�g�ɕt���Ă�C�R���C�U�\��
�D�݂ɒ��������Ղ��̂ł́H
(�C�R���C�U�[�͂Ȃ�ׂ��A
���炷�����Œ���������ł�)
G6��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂������炵�Ă݂܂��i��
��110Hz��Minerva2000����̋�Ƃ���
�s�\�N�ł����A���͈͓̔��ɂ������܂�
���܂�t���b�g�ɂ��������B&W�̌������Ȃ�ƁADENON�̔����������Ă܂����ˁB
�����������͕������Ă��܂��B
���f�B�X�N�g�b�v�̃I�\�f�B�I
���߂ŕ����̂�
���E�̍����A�����̉e�����A
���Ȃ��̂ł��傤�B
L���̔��˂������Ƃ��邩�Ǝv���܂������z���ށi�L�����v�}�b�g�j�𑤖ʂɒ������̂����ʂ������̂���ł��ˁB
REW�̃��[���V�~�����[�V�����O�O���t�Ƃ͑S�R�Ⴂ�܂����i��
�����������悭������܂��A�Ƃɂ������o���ł���ƃX�b�L�����Ă����ł��ˁB
����}�C�N�����Ă���܂����肵�Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�܂��Ⴄ���ʂɂȂ邩������܂���B
�����ԍ��F25391563
![]() 2�_
2�_
���Ȃ݂ɐ���A�d���R���Z���g�H��/3�������������܂����̂ŁA�����G�[�W���O���Ă�����ʂ��o�邩���m�F�������Ƃ���ł��ˁB
�ЂƂ܂��A�I�[�f�B�I���S�҂����鎖�͂����������I���������ł��ˁB
��́A���z�A�[�X�A���V�����]�l�[�^�[�A�V���[�}�����g���炢�ł��傤���i��
�ǂ��[�[�[�i��
�����ԍ��F25391569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
�O���t�����̔����A�����F��
�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���
�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B
���莞�̉��ʂ��グ���
�����Ă��邩������܂���
�ł��A�ʉ����Ղ�100�|20kHz��
�悭�����Ă���̂�
�������v���Ǝv���܂��B
��������������
��JAZZ���[�h�J�X�^�}�C�Y���Ē����Ă܂�
�����̓G���[�S�����C�����悭�����邱��
�H��͑听���A���������鉻���Ċm�F�ς�
���Ƃ́A���y���݂̎��Ԃ���Ȃ��ł��傤��
���łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB
�����ԍ��F25391582�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
���O���t�����̔����A�����F��
�Ñ������x���̏オ��100Hz�ȉ���
�Q�l�̌����ɂȂ�܂��B
�Ñ����Ƃ����̂͏��߂Ēm��܂����B
������I�[�f�B�I/�X�s�[�J�[�ɉe����^�����ł��ˁB
�����łɃJ�X�^�}�C�Y����Ă܂��ˁB
�����ł��ˁB
PC���璮���ꍇ�́ADAC�ōׂ����J�X�^�}�C�Y�ł��܂����APOWERNODE EGGE���璮���ꍇ�́A�����܂ŃJ�X�^�}�C�Y�o���Ȃ��̂Ŏg�������Ă܂��B
�T�E���h�o�[������o�͂ł��܂����A�܂����ł��A����Ԃł��i��
�Ƃ���ŁA�x�����K�[�̃T�|�[�g�ɖ₢���킹����A�ȉ��̉����܂����B
Behringer UM2��USB�N���X�R���v���C�A���g�f�o�C�X�̂��߁A��{�I�ɂ̓h���C�o�̕K�v�Ȃ������v���܂��B
�����p���������\�t�g�E�F�A��ASIO�h���C�o�Ȃǂ̃h���C�o��K�v�Ƃ���ꍇ��ASIO4ALL�Ƃ����ėp�h���C�o�̎g�p�𐄏����Ă���܂��B
�������Ȃ���AASIO4ALL�̓T�[�h�p�[�e�B���̃\�t�g�E�F�A�ł���AWindows11�𐳎��ɃT�|�[�g���Ă���܂��߁A���q�l���ɉ����Đ���ɓ��삷�邩�ǂ����Ƃ����_�Ɋւ��܂��ĕ��Ђł͖��m�Ȃ���v�����˂܂��B
�x�����K�[/UM2�́AASIO�h���C�o�Ȃ������Ȃ̂�windows�ł͕s����炢�����ł��B
https://music-thcreate.com/behringer-um2/
���Ȃ݂ɂ����ɂ悵����́AECM8000�ő��肷��ꍇ�́A�ǂ̃��^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?
PC��Mac�ł���?
�����ԍ��F25391714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�G���[�S������
��ECM8000�ő��肷��ꍇ�́A
�ǂ̂悤�ȃC���^�[�t�F�[�X�g���Ă܂���?
PC��Mac�ł���?
����PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)
�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B
PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��
����������ւ��Ă����̂ł���
RME�������ƕ����A
�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���
(DTM�p�Ȃ̂œ�����O�Ȃ̂ł��傤)
��������������āA���ǎU���ł����B
������6ch�o�͂�3way�X�e���I��
�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������
(�`�����f�o�\�t�g2���~)
�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B
�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������
�����ԍ��F25392239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
������PC��Win11(XP���疳��UG�̌J��Ԃ�)
�ƌÂ�fireface���g���Ă܂��B
PC�̓m�C�Y���ۂ��āA2�A3���̃J�\�h��
����������ւ��Ă����̂ł���
RME�������ƕ����A
�����Ɣ����Ă݂���m�C�Y�͉���
��͂�ARME�ł����B
��������G6�����Ă݂܂������A���ɕ�����Ȃ������Ă��܂��B
�C���^�[�t�F�[�X�͂�͂胁�W���[�Ȃ̂��A���芴�A�𑜊������ėǂ������ł��ˁB
win11�C���^�[�t�F�[�X�ŐV���
https://oto-money.com/dtmnews-windows11/
��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��
�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������
(�`�����f�o�\�t�g2���~)
�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B
���̗̈�͂܂��ڂ���������܂��A�v�����Ȃ���DSP�AEQ�ׂ�����������ł���悤�ł��ˁB
YOUTUBE�Ō������B
�ŏ��́ADAC�Ƃ���ADI-2 Pro FS R�����X�g�A�b�v���Ă܂������A�}�C�N�v���͌��\�d�v�Ȃ̂ŁARME/Fireface UCX II�����肪�������ȂƎv���͂��߂Ă��܂��B
�R�n�͈ȉ�
MOTU/M2
Steinberg/UR22C
Focusrite/Scalett Solo gen3
�P���Ƀ}�C�N�v�������Ȃ炱��ł��悳�����ł����B
M-AUDIO /M-Track Solo
�Ƃɂ����AWIN�̏ꍇ�̓h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�ł��ˁB
���̓_�AMac�͗D�ʂł����ˁB
�́AUA-20�g���Ă����́AMac�������̂ŁB
�������\�z���I������A�ӏ܃��[�h����܂��B
�����ԍ��F25392294�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������ɂ悵����
��������6ch�o�͂�3way�X�e���I��
�}���`�A���v�̃`�����f�o�Ɏg������
(�`�����f�o�\�t�g2���~)
�}�C�N�[�q�ʼn��������A���\�V�ׂ܂��B
�v���@�͂��邳���l�Œb�����A������������
�`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���?
https://procable.jp/dividers_dac/cx2310.html
�g�����悭�������Ă��܂��A�x�����K�[�͈ٗl�Ɉ����ł��ˁB
�T�u�E�[�n�[�ƈ����A���v�����āA�Q���ɂ�2.1 ch�������́ASONY�̓V��X�s�[�J�[���������Ɏ����Ă��āA4.1ch�g�߂Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B
POEWRNODE EGGE�́A2.1 ch�����E�ōׂ������o���Ȃ��̂ŁB
���r���OAV�̕��́A�t�����g�������鎞�ɁA�T���E���hSP��V��ɍĔz�u�\��ł��B
�����ԍ��F25392559�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���h���C�o���Ή����ĂȂ��Ǝg���Ȃ��̂��l�b�N�AMac�͗D�ʂł�����
RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B
Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�
�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA
�Ȃ��Win�ł����̂ł́H
���`�����f�o���Ƃ���Ƃ��ǂ��ł���
�ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B
�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v
(LE�łȂ�)���g���Ղ�����
AV�͉����̒��(�����ƕ���)�̍Č�����������
�傫���e�����܂��B
�Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA
���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����
�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����
������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����
�������Ă��܂��܂��B
https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html
3way�X�s�\�J�\�Ƃ������ɃN���X���g��������
�ʑ��̂��ꂪ�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȃ̂ō��̓t�������W�ɋ߂��A
�S�ш���o���鍂���\�X�s�\�J�\��
����Ƃ���������L���c�B�[�^�[
�̃^�C�v��������
B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������
������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B
(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A
���������ɂȂ�̂ł��傤)
707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F25392635�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��RME�Ƃ��Ɩ��p�̓h���C�o�[�Ή����邵�A�����������B
Mac�͓���ŗV�тɕs�����A���킩���Ă���̂�
�u�[�g�L�����v������Win�Ή����Ă�����Ȃ̂ŁA
�Ȃ��Win�ł����̂ł́H
�Ȃ�قǁB
�v���O�C���������Ƃ��ł����ˁB
midi�ݒ�Ƃ�����mac�̕����ȒP�݂����ł����B
https://youtu.be/nml6Ve5km0o
�����܂Ŏg���p�r�͍��̂Ƃ��떳���̂ŁAWIN�ł������ȁB
����PC�����ւ�����macmini��WIN�nminiPC�����������ׁ̈B
���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B
�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v
(LE�łȂ�)���g���Ղ�����
�t���o���h�E�t�F�C�Y�R���g���[�������[���ł��ˁB
AV�A���v���Ǝ����ŕ���Ă܂����A2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?
�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B
��B&W�̒��j�ƂȂ郆�j�b�g�̐��\������
������́A�����ɍ����Ă�Ǝv���܂��B
(���C���i�b�v�̓R���e�B��A�X����A
���������ɂȂ�̂ł��傤)
707�̓}���`�ɂ���K�v�Ȃ��̂ł́H
707�n�̏ꍇ�́A���ʂ�2ch�Œ����Ƃ��Ηǂ��Ƃ����Ӗ��ł��傤��?
�ЂƂ܂��A�Q���̓s���A2ch��AV�p�T�E���h�o�[3.0.2�Ŏg�������đ�����X�}�z�ł͐������܂������A�T�E���h�o�[�̃T���E���h���Ɖ����̃V���{�����@������Ȃ������͂���܂��ˁB
���r���O��AV�����́A�ЂƂ܂����̂܂܈�ʃR���V���[�}�[�p�r�B
�Q���̉����́A����������Ɠ��ݍ���ŋƖ��p���x���ŗV�т��������ł��ˁi��
�����ԍ��F25392671�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�G���[�S������
��2ch�̏ꍇ�̈ʑ��Y���͂ǂ�������ł��傤��?
�����������̃Y���𑪒肷����@��������܂���B
PC���特�g���X�^�[�g�A
�E�\�t�@�\�̉��g���}�C�N�Ŏ����PC�\��
�X�^�[�g����E�\�t�@�\�̉��g�܂ł̎��Ԃ�ǂݎ��
�c�B�[�^�[�ł��A�������Ƃ����A�ǂݎ��
�f�W�^���`�����f�o�̓��j�b�g����
�^�C���f�B���C��ms�P�ʂœ������
�x����(���E�[�t�@�\)�ɍ��킹��
�������Ƀf�B���C
�g�`�̓��B���Ԃ���v�����܂��B
������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{
�����ԍ��F24543267
�[��łƂĂ��Â��Ȏ���
�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����
�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���
�傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA
�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�
1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�
���A�������ʎ����̉��ł��B
�����ԍ��F25392738�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��������̕��̓��}�n��3way�Ŏ��{
�����ԍ��F24543267
��肪�Ƃ��������܂��B
���R�A�ȃX���ł��ˁi��
���[��łƂĂ��Â��Ȏ���
�ʑ�����̂Ȃ��t�������WSP����
�L��ŃN���A�ȉ��ꂪ�L����܂���
GENELEC�ЂŎ����������ɂ��̊��o��̌����܂����̂ŁA������ڎw�������~���͂���܂��ˁB
���傫�ȃ}���`�E�F�CSP�ŁA
�ʑ������킹��ƒቹ���獂���܂�
1�_���特���o�Ă��銴���ɂȂ�
���A�������ʎ����̉��ł��B
�Q����GENELEC�̃t�������W�X�s�[�J�[5.1ch�\�z������܂����A�R�X�p�������Ȃ̂ŁA�o�����b&w707S2��4.1ch�}���`�`�����l���|�}���`�A���v�V�X�e����g��ł݂����ł��ˁB�i�ʂɃ��A���Ȃ�2.1ch�ł������ł����A�Ȃ��������v���������̂Łj
�悸�́A���̕ӂ��Q�l�ɂ��Ȃ���C���ɐi�߂Ă������Ǝv���܂��B
���ŏ㗬��Windows11/PC���ɂ�����S��ASIO�\���ɂ�� I/O�̊m��
���f�W�^�� I/O �ɂ��\�t�g�E�F�A�N���X�I�[�o�[�i�\�t�g�`�����f�o�j�̓K�Ȑݒ�
���x���A���C�e���V�[�A�`�����l���ԓ����̊m���Ȑݒ�ƍ\��
���ʑ����̓K�ȉ�������ѐݒ�
���}�X�^�[�{�����[������ƃ`�����l���ԑ��Q�C���ݒ�^������A�ǂ��łǂ̂悤�ɍs����
���̑O�ɑ���}�C�N�V�X�e���̍w�����Ȃ��Ɓi��
�܂����t�����x���ł����A���~�b�^�[�J�b�g����撣��܂��B
�����ԍ��F25392899�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���C���ɐi�߂Ă�������
�^���ł��A��͋��ɁA�ɂԂ��B
�����ԍ��F25392921�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
�����ARME Fireface UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?
DIGICheck
�EVector Audio Scope/�ʑ��`�F�b�N
�ESurround Audio Scope/�T���E���h����
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1287777.html
���ʑ������Ƀf�W�^���`�����f�o���g���Ă܂��B
�x�����K�[����DCX2496��PC�ɂȂ�����^�C�v
���ƁADCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?
���Ⴆ�ΒP���̏e�e�̂悤�ɁA
���ꉹ�����甭�˂��ꂽ����
�����ƒቹ�̓��B���Ԃ��ꂪ�����
������������āA�ɂ���Ńs���ڂ��A���A����
�������Ă��܂��܂��B
https://jp.pioneer-audiovisual.com/components/avamp/sp/tech/03.html
�Ⴆ�A�ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?
�������AGENELEC�ЂŃC�}�[�V�u�����������́AMarantz av10����X�s�[�J�[�v���A�E�g���Ă܂������A�ǂ�����DSP����䂵�Ă����̂��Y��܂����B
��\�t�g���ĐF�X�����āA���������̂��悭�������Ă��܂���i��
MCACC
DILAC
GLM
DIGICheck
�����ԍ��F25393307�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
��UCX II�����ł����A���̋@�\�͎g���Ă܂���?
�g���Ă܂���A���\�`���[�u�̃C���z���p�A
�Ƃ��ǂ��X�s�[�J�[
�����̂�UC�A�`���{�^�����[�q�������ʒu
���f�������������̂ŁA�Ƃ�ł��Ȃ��Â�����
�������AWin2000�̍��������悤�ȁB
�Ɩ��p�Ȃ̂�����������ڂ��ς�܂���B
�g�p���A�P�Ȃ�d��
��DCX2496��WIN11�Ŏg���ꍇ�A�h���C�o�͂ǂ�ň��蓮�삵�Ă܂���?
DCX2496�AUC�Ƃ��ŏ��Ƀ\�t�g�����
���������A�h���C�o�[�œ����Ȃ��b�����Ȃ��ł��B
Win11�Ȃ�\�t�g��XP�݊��œ����̂���
���ʑ������ꍇ�APIONEER��LX805�̎�������/Advanced MCACC�ōs���ꍇ�ƁAFireface UCX II/DCX2496��g�ݍ��킹�čs�����ꍇ�Ƃł́A��������Ă����ł��傤��?
LX87�F�X�s�[�J�[���̂܂܁A
������LC�l�b�g���\�N��ʂ����܂܈ʑ��
��͎���
DCX2496�Fch���ƂɃf�B���C�̕t�����`�����f�o�@
LC�l�b�g���\�N���O���A�A���v����SP���j�b�g�֒���
��̓t���[�\�t�g�̑g�ݍ��킹�Ńf�B���C�l����
�����g�`��`��
���R�[�h�\�t�g��
Lch���o����Rch�}�C�N�����^��
Rch�̓`�����f�o�A�A���v�ASP�A�}�C�N�Ȃ̂Œx��
�^���g�`����LchRch�̎��Ԃ���ǂ݁A
SP���j�b�g�̃f�B���C�l���`�����f�o�ɓ����B
UC�FDCX2496�̑���Ƀ\�t�g�`�����f�o
������EKIO�E�E�E2ch�X�e���I(�܂�4ch�܂ł͂������t���[)����ȏ�ch���₷�͉̂ۋ�2���~���炢�B
��MCACC�ƁAUCX II/DCX2496�ł�
��������Ă����ł��傤��?
��������Ɛl�́B
LC�l�b�g���\�N���L��Ɩ����B
LC�l�b�g���\�N��ʂ��ĕ�ł���
MCACC�͍��x�ȋZ�p
�}���`�A���v���̓x�^�Ȃ���
���̓}���`�A���v
(LC�l�b�g���\�N���X)
�����ԍ��F25393992�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�ڂ���������肪�Ƃ��������܂��B
RME,�AUCX2496���ɑ��v�����ł��ˁB
���Ȃ݂ɁAEDIROL UA-20�͌݊����[�h�ł��_���ł����B
RME�ADCX2496�͗��N�܂łɔ������Ǝv���Ă܂����A�Ƃ肠���������ɁA���̕t�^��2WAY�o�X�`�����f�o�Ŏ����I�ɂ���Ă݂悤���Ǝv���Ă܂����ǂ��ł��傤��?
�����p�^�[��1
pc/win11
�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II
�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002
����X�s�[�J�[/707S2
���X�s�[�J�[/SONY SS-J90AV(�����p)
����A���v/POWERNODE EGGE
���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)
�����p�^�[��2
pc/win11
�C���^�[�t�F�[�X/RME Fireface UCX II
�o�X�`�����f�o/FOSTEX STDV-002
����X�s�[�J�[/707S2
���X�s�[�J�[/polk es10/707S2/607S2/707S3
����A���v/POWERNODE EGGE
���A���v/Nobsound NS-01G Pro(�����p)
���m�F�_
�A���v�ƃX�s�[�J�[�͓��ꂵ���������ʂ������̂�?
���⑫
�����p�^�[��2�̃X�s�[�J�[�́A�����p�^�[��1������������s���z��
��悪�o�₷���X�s�[�J�[��I��\��
�����I�ɂ́A���A���v�ƃ`�����f�o��DCX2496�ɃA�b�v�O���[�h
���Q�l
�u�ቹ�Ɏn�܂�ቹ�ɏI���v�o�X�`�����f�o
https://m.youtube.com/watch?v=O9fVHHiGpA4
�u���܁A�Ăт́g�o�X�`�����f�o�h�v
https://stereo.jp/?p=4662
�����ԍ��F25394051
![]() 0�_
0�_
���ƁA���̃��[�J�[�̑���}�C�N��DSP��g�ݍ��킹��A���g�������A�ʑ���ADILAC LIVE���܂Ƃ߂ďo����悤�ł��B
�ǂ̑����V�X�e�������������܂��ˁB
����}�C�N/miniDSP
DSP/miniDSP 2×4 HD
����\�t�g/REW�ADILAC�i�I�v�V�����j
���Q�l
https://minidsp.jtesori.com/products/minidsp-2x4-hd/
https://www.phileweb.com/sp/news/audio/202308/23/24584.html
�����ԍ��F25394058
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B
�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A
SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���
�����ቺ���Ă��܂��܂��B
FOSTEX STDV-002��SW�̍���J�b�g�̂�
�X���[�v�\12dB/oct�ł́A��邢�̂�
���Ȃ�Ⴂ���g���łȂ���707S2�Ɗ���
�����ቺ���Ă��܂��܂��B
��������707S2�Ɍ������悤��
SW�͍���J�b�g�͕t���Ă���ł��傤�B
�܂�A�`�����f�o��艹��
�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�
707S2�Ɍ������悤��SW����
DILAC�ŃC���p���X�����
DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�
�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������
���҂ɂȂ�܂��B
RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���
�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H
�����ԍ��F25394269�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��707S2�͎旧�ĂČ��_����������Ȃ�SP�ł��B
�ቹ��45Hz�^-6dB�܂ŏo�Ă���A
SW�����Ⴂ���g�����o�鐫�\�̍������̂łȂ���
�����ቺ���Ă��܂��܂��B
�Ȃ�قǁA�Ȃ�ł������f�o���Ă��_���Ȃ�ł��ˁB
��Ȃ������Ƃ���ł����i��
���܂�A�`�����f�o��艹��
�ʑ����C�ɂȂ�̂Ȃ�
707S2�Ɍ������悤��SW����
DILAC�ŃC���p���X�����
DILAC�͎g�������Ƃ��Ȃ��̂�
�ڂ����Ȃ��A�G���[�S������
���҂ɂȂ�܂��B
DIRAC����AV�A���v�ł����g���Ȃ��̂��Ǝv���Ă܂������AREW���܂߂�miniDSP�̑���V�X�e�������̓_�A�����I�ŗǂ������ȋC�͂��Ă��܂��B
����}�C�N��USB�Ńh���C�o���X�Ȃ̂ŁA������Ō������Ă݂܂��B
�܂��A�C�ɂȂ�Ƃ������P�Ȃ�D��S�ł��낢�뎎���ėV�т��������ł����i��
��RME�͏����̉�������̒�グ�Ƃ���
�ʘg�ōl����ꂽ�炢�����ł��傤���H
�����ł��ˁB
�C���^�[�t�F�C�X��DAC�Ƃ��Ďg�����A������DAC�Ƃ��Ďg�����ɂ���Ĕ����@����v�����ł��ˁB
���̂Ƃ���z�肵�Ă�̂́A�ȉ����炢�ł��ˁB
PC��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[
�I�[�f�B�I�pNAS��RME���A���v�i�A�L���t�F�[�Y,SOULNOTE,XLR�ڑ��ł���^�C�v�j���X�s�[�J�[
���Ƃ͒��ځA�l�b�g���[�N�v���C���[����ӏ܂��Ă�̂ŁA�����I�ȃV�X�e����グ�p�i�n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�V�X�e��2024�j�ɍl���܂��B
�Ƃɂ����A���낢��A�h�o�C�X������Ϗ�����܂����B
�����ԍ��F25394316
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
�ȉ��̃p�^�[�������ꂼ�ꑪ���r���܂����B
�m�[�}��
���V���i�Б�2�Â|�[�g���ɐݒu�j
�X�|���W�L��iB&W�����j
������V�X�e��
�v���A�v��/spectroid
���X�j���O�|�W�V����
���⑫
�X�|���W�L�肾�ƒ��}���C���B
�m�[�}���ƌ��V�͂��܂�ς��Ȃ��݂����ł����A���V�̕������}���āA������k�P���ǂ��̂��H
�ǂ����͂��܂����H
�����ԍ��F25395840
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���ǂ����͂��܂����H
�X�|���W�͖��炩�ɒቹ����
�o�X���t��薧�ɋ߂Â��������}�V�Ƃ�
�ቹ�ŕs��������l�����Ȃ̂ł��傤
���V�ƃm�\�}���̍��͌���ꂸ
2�ł͏��Ȃ��̂���
��v�̓x�������炷���
����͏�肭�����Ă���
���ΓI�Ȕ�r���ł������ł�
�������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���
����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����
�D�݂Œ������悢�̂ł́H
�����ԍ��F25396690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
���������������A��{�I�ȕ����͏o���Ă���
����ȏ�̓C�R���C�U�[�Ƃ��g����
�D�݂Œ������悢�̂ł́H
���x���肪�Ƃ��������܂��B
�X�}�z�A�v�����\�A���x�����݂����ł��ˁB
���V�͂���������Ƒ��₵�Ă݂܂��B
��́A�R�[�i�[���^���L�̑f�ނ��Ă����̂ŁA���삵�Ă���܂��v�����悤���Ǝv���܂��i��
�p�b�V�u����DAC���A���v�A��������miniDSP�̃C�R���C�U�[�g�������Ȃ��悤�ł��ˁB
���Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[�����ł��B
�������߂Ēm��܂������AGENERIC�����R�X�p�����āA�}�C�N���t���ĂĐ��\���ǂ������ł����ǂ��ł��傤��?
�ȉ��R�s�y
���������𐳊m�ɍČ�
iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ������̂ŁA�f�B�[�v�ȃL�b�N�A�x�[�X���܂~�b�N�X���A�P�̂ōs�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�����̃n�C�p�X�E�t�B���^�[���g�p���邱�ƂŁA�T�u�E�E�[�t�@�[��g�ݍ��킹���V�X�e���̍\�z���e�Ղł��B
������_���璮������ MTM �f�U�C��
�ŏ�ʋ@��Ƃ��ėp�ӂ��ꂽ iLoud Precision MTM �́A�n�C�t�@�C�E�I�[�f�B�I�̐��E�Łu���z�����v�ƌĂ�� MTM�i�~�b�h�E�E�[�t�@�[�A�c�C�[�^�[�A�~�b�h�E�E�[�t�@�[�j�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A��萸�x�̍����������������܂��B���̌��ʂ����炳���̂́A�X�s�[�J�[�E�L���r�l�b�g�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/318037/
�p�b�V�u�X�s�[�J�[�V�X�e���ƃA�N�e�B�u�X�s�[�J�[�V�X�e���̃n�C�u���b�g�ŗV�т����ł��ˁB
�����ԍ��F25396768�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ǂ����A100��Hz�[200kHz������̓ʉ��̓f�X�N�̔����݂����ł��ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=cUj6Scx-iro
�����ԍ��F25396964
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
��iLoud Precision �ɂ� ARC �L�����u���[�V���������s����ƁA30 Hz �܂Ŋg�����ꂽ�ቹ���u�[�~�[�ɂȂ邱�ƂȂ����m�ɍĐ�
���ŏ�ʋ@��iLoud Precision MTM �́u���z�����v�ƌĂ�� MTM�z�u�ɂ��A�����c�C�[�^�[�̈�_���璮�����A�X�s�[�J�[�̑��݂������A���y�����̂܂܂̌`�Œ�������A���R�Ő����͂ɖ������T�E���h�ł��B
30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�
�d�C�Ńu�\�X�g�ł���Ȃ�A�傫��SP�͐�łł��傤
�l�Ԃ͍��E�̈ʒu�Ɖ��s�������̊��x�͍�������Ǐ㉺�͓݂��ł��A�O�p�������鎨�����E�ɕt���Ă���̂�
���ʂ̍����ቹSP�ł��N���X���}�s�ō����肪���Ȃ�
�Đ����Ă�����g����1����o�Ă��1�_���畷�����܂��B
�����ቹ�̎��t���ʒu�ɂ��A
�����𗣂��K�v�͂���܂���
���z������2�̃��j�b�g���瓯�����g�����o���̂�
�㉺�̒��S����O�ꂽ�����ŕ����ꍇ��
���������Ȃ��ƁA1�_����ł͂Ȃ�
����ƂȂ��Ă��܂��܂��B
�����Ȃ݂ɂ��̃��[�J�[����
�ǂ��ł��傤��?
�l�b�g�ł͂Ȃ��������������Ȃ��ƁA���Ƃ��������ł��B
RME�Ŋ������̂́A�����ƌ����Ă�̂�
���R������ȂƎv���܂����B
707S2�͂ǂ��ł������Hgenelec����������Ă܂���ˁH
�����ԍ��F25397359�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
��30 Hz���o����SP�͂��Ȃ�傫���Ȃ�܂�
���ʂ̍����ቹSP�ł��N���X���}�s�ō����肪���Ȃ��Đ����Ă�����g����1����o�Ă��1�_���畷�����܂��B
�F�X���C���i�b�v����݂����ŁA���ʃ��f����iLoud Precision 5��2way�ŃR���p�N�g�ł��ˁB
KEF��GENELEC�̓����͒�����������܂��̂ŁA�ǂ����������̂��́A���̋@����Ă��画�f�ł����ˁB
�X�s�[�J�[�����߂Ĕ������Ƃ��Ă�4�����AKEF��LSX�n���1���ōl���Ă��܂����B
�A�N�e�B�u����AIRPULSE�n�����A���ł����B
��RME�Ŋ������̂́A�����ƌ����Ă�̂�
���R������ȂƎv���܂����B
707S2�͂ǂ��ł������Hgenelec����������Ă܂���ˁH
RME���܂��l�b�g����ł����A����DAC�Ƃ��͎������Ȃ��Ńl�b�g�Ń|�`�鎞��ł�����ˁA�߂����i�������o������������̖ڐ������Ĕ����Ă܂��ˁB�i�l�i�ɂ��
707S2�͎��@���������A707S3���������Ă��炠����x�o�N�`�Ŕ����܂������A�[���̉����ł��ˁB
100kHz�t�߂̓ʉ��ȊO�͂قڃt���b�g�ł����A��Ȃ��ł��̉����Ȃ�o�����X�������ȂƊ����Ă��܂��B
�~�������Βቹ�͂����Ɨ~�����Ƃ���ł����A�j�A�t�B�[���h�ł͏\�����ȁB
genelec�̎����ł́Ax 8331A�A2 x 8341A�A2 x 8351B�����ɒ����܂������Ax 8331A����ԃo�����X�ǂ��������܂����B
�傫���Ȃ�ƒቹ���_�u���đ����ۂ������܂����B
���Â�ɂ��Ă��A�X�s�[�J�[�L�����u���[�V�����V�X�e������̂ɂȂ��Ă���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�́A�Z�b�e�B���O���y�ŁA�\�t�g�ōׂ����X�s�[�J�[����ł��郁���b�g�ɖ��͂������Ă��܂��B
YAMAHA�̃A���v����@�\���ė����̂ŁA����������������Ă܂����A�A�N�e�B�u�̕����\�t�g�i���������C���[�W�B
���ꂼ��̖ړI���Ⴄ�͕̂������Ă܂����A�X�s�[�J�[�V�X�e�����Ă����ȃp�^�[��������ȂƓ��X�����B
��YAMAHA
R-N1000A(198,000�~)
R-N2000A(429,000�~)
��IK MULTIMEDIA
iLoud Precision 5 (143,550�~)1�{
iLoud Precision MTM(191,400�~)1�{
���݁A���[�J�[�Ɏ����₢���킹���ł��B
�����ԍ��F25397432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����z����SP�AAV�̃t�����g�n�C�g�Ŏg�p��
���Ȃ݂ɂ�����͂ǂ��Ŏ������ꂽ��ł���?
�����ԍ��F25397445�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
�����Ȃ݂ɂ�����͂ǂ��Ŏ������ꂽ��ł���?
�n�C�G���h�V���[�A�������͕̂��ʂ�2way�^�C�v
�l�i�̓n�C�G���h�ł͂Ȃ������̂Ŏ����ɍw���ł�
���X�s�[�J�[�L�����u���[�V�����V�X�e������̂ɂȂ��Ă���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�́A�A�N�e�B�u�̕����\�t�g�i���������C���[�W�B
���̓f�W�^���A���vIC�������A�f�B���C��������
�ȒP�ɓ�����܂��BLC�l�b�g���\�N�̂Ȃ�
�I�\���C�������̃}���`�A���v�X�s�[�J�[�Ȃ̂�
����Ȃ�̉��͏o�Ă��܂��B
�̂Ȃ���̂������Ȃ���A
�A�N�e�B�u���g���Ղ���������܂���
�����ԍ��F25397709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
���n�C�G���h�V���[�A�������͕̂��ʂ�2way�^�C�v
�l�i�̓n�C�G���h�ł͂Ȃ������̂Ŏ����ɍw���ł�
�����ł��ˁB
�܂����A�n�C�g�X�s�[�J�[�ł��g���Ƃ́A�������}�j�A�ł��ˁB
���̂Ȃ���̂������Ȃ���A
�A�N�e�B�u���g���Ղ���������܂���
�����ł��ˁB
���ɂ�����肠�����薳��������Ȃ̂ŁA�����̕����܂܂ɁB
�o�C�N�ł����ƁA����Ȋ����ł��ˁB
AKIRA�d���o�C�N=�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[
�n�[���[�_�r�b�g�\��=�p�b�V�u�X�s�[�J�[
�ǂ������D���Ȃ�Łi��
�����ԍ��F25397727�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
USB���z�A�[�X�̎���@���������܂����̂ő����APC��USB�ڑ��Ŏ����Ă݂܂����B
���V�X�e��
PC��G6��POWERNODE EGGE��707S2
PC��G6��707S2
������
AMAZON MUSIC/�_�C�A�i�E�N���[�N/24bit/96
AMAZON MUSIC/�_�C�A�i�E�N���[�N/24bit/48
������
USB���z�A�[�X�ɂ��ẮA�S�̓I��S/N�����サ���𑜓x�ɉ����A�O�ɑO�ɏo�Ă��邳�܂����ĂƂ�A���s�����A���̊��������ق��A������̉��A�]�C�ɗD����ہB
���Ƀw�b�h�t�H���ł́A���ꂪ�����Ɋ�����ꂽ�B
���ǂ���������X�ɗǂ��Ȃ�\�������肻���ł��B
�����g������
���z�A�[�X�̗L�薳���ł́A���ɑ傫�ȍ��͖��������B
�����ԍ��F25398295�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
�X�s�[�J�[���̑�g�������܂�
���Ԃ̊y���݃A�N�Z�T���[��������Ă܂���
����Ă݂�ƃI�J���g�����\��������
���_�I�ɐ������t�����A
���ʖ����͊�{�I��
�O���X�^���X���悢��������܂���B
�����ԍ��F25398493�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��ςƋq�ς�D������Ȃ���A�I�[�f�B�I���C�t�i���Ă���܂��i��
�x�e�I�������A�T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h��DIY���s���\��ł��B
TBC
�����ԍ��F25398533�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�G���[�S������
���T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h��DIY���s���\��
�T���E���h�͐l���ʂ�ڐG����
�����̃��X�N������A
�X�s�[�J�[��ێ�����A���炩��
���S�z�������Ă����ƁA�悢����
DIY�̓J�X�^�����ȒP�ł��B
�����ԍ��F25398558�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
����͂܂��Ɠ��ȃf�U�C���ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���r���O�̃��[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C���͂���Ȋ����ł��ˁB
�T���E���h�X�^���h�́A��C����@�Ɖ���������Ɏ��[�ł���悤�ɂ��Ďg���������o�������ŁA�C���e���A�f�U�C���Ƃ̗Z����}��܂��B
���̌�A�e���r�{�[�h���lj����삵�A�������グ�ĉ��Ƀv���C���[�ނ����[�ł���悤�ɂ��悤�Ǝv���܂��B
�܂��܂���͒����ł��B
���Ȃ݂ɁA�����ɂ悵�����AV�V�X�e���̍\���Ɣz�u�͂ǂ�Ȋ����ł���?
�����ԍ��F25399679�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�⑫
�T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h�́A�ɍ��킹�O��ړ��ł���d�l�B
�����ԍ��F25399683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����̃X�P�W���[��
2023.09/�T���E���h�X�s�[�J�[����
2023.10/�e���r�{�[�h����
2023.12/�t�����g�X�s�[�J�[����
2024.01/�v���C���[����
2027.01/�A���v����
�����ԍ��F25399702�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���T���E���h�X�s�[�J�[�X�^���h�́A
�ɍ��킹�O��ړ�
�������\�肪����A
SP�̓X�^���h�Œ肪�悢�ł��傤�A�����h�~
�@�햢��Ȃ�A�ג��߃o���h�͂������ł��傤��
�X�^���h���E�ɃX���b�g���J����
�������ɂ悵�����
AV�V�X�e���̍\���Ɣz�u�͂ǂ�Ȋ���?
�����́A�������TV�ɌÂ����}�n��AV�A���v
�ꉞ�v���W�F�N�^�[�������悤�ɂ��Ă��܂��B
SP�̓Z���^�[�Ȃ��́A4.0.6�\���ł��B
(�����̂œV�䑤����)
�����ԍ��F25399786�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�Ȃ�قǁB
������Aklipsh�̔w�ʂɂ̓l�W������̂ŁAL�^����Œ���ł��܂��ˁB
�����A��������Ɣ����Ȋp�x�������o���Ȃ��Ȃ�܂��ˁB
�܂��A�o���h�Œ��߂�������R�x�������B
�ŋ߁A�n�k�����Ȃ��̂Ŋ��S���f���[�h�ł����B
��4.0.6
�Ƃ������́A�T���E���h�X�s�[�J�[�́AJBL con pro��iLoud Precision MTM�̍\���ł���?
���̒��̃X�s�[�J�[�C�ɂȂ�܂��B
�����̊����ƁA�����I�ɒlj��ł���̂̓n�C�g���炢�ł��ˁB
�A�g���X�̈ړ������~�����Ƃ���ł����A�n�C�g�ƃg�b�v�~�h�������Ō��ʂ���܂�?
���ꂩ�v�����āA�t�����g2ch��iLoud Precision MTM�ɂ��āA�T���E���h��iLoud Precision 5�ő����āA4.1.4�\�z�B
GENELEC������R�X�g�n�C�p���[�C�}�[�V�u�V�X�e�����o�������ȋC�����Ă܂�(��
�����ԍ��F25399839�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���T���E���h�X�s�[�J�[�́AJBL con pro
��iLoud Precision MTM�̍\���ł���?
����Ȃɂ��������Ȃ̎g���Ă܂���
�V��6�{�́A�t�����g�n�C�g2�{�����z����(��̃X���ʐ^)
4�{��Control 1pro
(�v�`�����i)
https://s.kakaku.com/review/K0000505666/ReviewCD=1421534/
��4�{�̓T���E���h2�{��BOSE�̃t�������W�����i
�����ԍ��F23376005
�t�����g2�{�͒��j�ċx�ݎ���i
���A�g���X�̈ړ������~�����Ƃ���A4.1.4�\�z
�ړ����͓V��4�{���f�t�H
2�{��4�{�ɕύX����b���͂悭�����܂��B
AV�A���v��3D��̋@���
SP�̕��������������A���v�ɓ���
��������̉����v�Z���ďo���̂�
�K��͈͂ɓ���Ă�A���ƗZ�ʂ������悤�ł��B
�����ԍ��F25400263�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
����A���[�J�[����A������A�֓����Ƃ����Ŏ����ł���悤�ł��B
https://www.miroc.co.jp/rock-on/rock-on-shibuya-dolby-atmos/
���ƁA����ȃC�x���g������悤�Ȃ̂ő̌��������ɂ������Ǝv���܂��B
https://www.snrec.jp/entry/news/srfes2023_ik_ua
���ړ����͓V��4�{���f�t�H
2�{��4�{�ɕύX����b���͂悭�����܂��B
AV�A���v��3D��̋@���
SP�̕��������������A���v�ɓ���
��������̉����v�Z���ďo���̂�
�����L����܂���(��
���̃Z�b�g����100���ȓ��ŁA7.1.4�g�߂����ł��B
�A���v/lx805
�X�s�[�J�[/ iLoud MTM11�{�Z�b�g
�ϑz��
�����ԍ��F25400289�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
https://www.digimart.net/cat17/shop1484/DS07921139/
�����ԍ��F25400292�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ȃ݂ɁA���V�����ǔł��������܂����B
��قǁA���r���[���܂�(��
�����ԍ��F25400322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���茋��
�m�[�}��
���V���i�Б�4�Â|�[�g���ɐݒu�j
USB���z�A�[�X�iPC���ɐڑ��j
������V�X�e��
�v���A�v��/spectroid
���X�j���O�|�W�V����
���⑫
���z�A�[�X�͌��V���ɒlj�������Ԃő���
�����ԍ��F25400593
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����
���̒��ɓ����̂Ɠ������ʂɂ���ɂ�
�����T�C�Y���ƍL���ʐς�
�傫�����K�v��������܂���
���A���v/lx805
���X�s�[�J�[/ iLoud MTM11�{�Z�b�g
�ǂ����DSP�̃^�C���A���C�����g���
�@�\�����̂ł�
�����Ńt�����g�̃^�C���A���C�����g���
�f�B���C�ł��A
�����ʒu�ʼn��̓��B���Ԃ𑵂�������
LX87��MCACC���������
��O�ł��ʑ�����
�^�������ŁA�ʑ���]�Ȃ��A��l���炸�ł����B
(������O�ʼn�ʃL���v�`���[����)
�����ԍ��F25400919�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�����V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����
�����ł��ˁB
�T�C�Y�傫�����Ă����܂�ς��Ȃ��悤�ł��ˁB
���^���L�̗��_�ł́A�g�U�Ƌz���̃~�b�N�X���x�X�g�̂悤�Ȃ̂ŁA�V��l���ɃR�[�i�[���^���L����(�z����)������������đ��肵�Ă݂܂��B
���ǂ����DSP�̃^�C���A���C�����g���
�@�\�����̂ł�
�I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŁA���̕ӂ͗ǂ��������Ă���܂���B
�ڂ����A�h�o�C�X���炦��Ə�����܂��B
���̔F���͈ȉ��ł��B
���������V�X�e��1
AV�A���v/LX805
�t�����g�X�s�[�J�[/klipsh R-50M
�T���E���h/klipsh theater pack
���������V�X�e��2
AV�A���v/LX805
�t�����g�X�s�[�J�[/iLoud MTM11�{�Z�b�g
�T���E���h�X�s�[�J�[/iLoud MTM11�{�Z�b�g
���m�F�_
�E�������V�X�e��1�̎��������́A�A���v����MCACC��DIRAC LIVE�ōs���悢�F��
�������A�X�s�[�J�[���ׂ̂̍��Z�b�e�B���O�͏o���Ȃ�
�E�������V�X�e��2�̎��������́A�X�s�[�J�[����ARC�V�X�e���ōs���悢�F��(PC�Ɛڑ�)
�X�s�[�J�[���ׂ̂̍��Z�b�e�B���O���lj������\
�EGENELEC�Ђ̃C�}�[�V�u�V�X�e���́AAV10����11ch�v���A�E�g���Ă��܂����B
������GENELEC�X�s�[�J�[���Ő��䂵�Ă����Ƃ����������Ă��܂����B
�EDENON�̔����̘b�ł́A�f�m�}��AV�A���v�̉��ꎩ����́A�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�ɂ��L���ƌ����Ă܂����̂ŁA�ǂ��炩�̋@�\���g���Ύ���������F���B(PIONEER���i�ł������F��)
�E���Â�̃V�X�e���ł��A�v���C���[����AV�A���v����DSP�ŁA�����t�H�[�}�b�g�ƃT�E���h���[�h�����R�ɑI���\�B
���⑫
�����I�ȃ��r���OAV�V�X�e���̃O���[�h�A�b�v���\�z��
�p�b�V�u�X�s�[�J�[�V�X�e�����A�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�V�X�e�����̂ǂ��炪�œK��������
���Â�ɂ��Ă��A���r���O���ɍ������R���p�N�g�������x�ȃV�X�e�������z�I
�����ԍ��F25401126�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
����DSP�̃^�C���A���C�����g��ŋ@�\�����̂�
���I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŁA�ڂ���
���ŏd�v�x�̍������2��
�@���g�������E�E�E�h���~���Ȃ߂炩�łȂ��s�A�m�Ŗ����t�͕s�\
�A�ʑ��Y���E�E�E�����ቹ�̃X�^�[�g�s��v�͉����s�N��
DSP�ŕ���܂����A�Ⴆ��AV�A���v�����̃p�C�I�j�A��
SP������GENELEC�ł́A�@�A��̋@�\���_�u���ē���邱�ƂɂȂ�Ӗ��ł��B
���I�ɂ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ�����A�X�s�[�J�[�����^�C�v���L������
�Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��
��cL���炵����A�ׂ�������10m�ȏ�
�����悭���悤��SP�P�[�u����0.5m�Z���Ƃ��A�܂��܂����v���Ă�����ł��B
L�͐M����1/4�g���x��AC�͐i�݂܂��A�ш���ɋ}���Ɉʑ����ꔭ��
�p�C�I�j�A��AV�A���v�Ń^�C���A���C�����g�������A�������オ�傫�������ł�
���̏�ŁAGENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B
�����ԍ��F25401587
![]()
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
���@���g�������E�E�E�h���~���Ȃ߂炩�łȂ��s�A�m�Ŗ����t�͕s�\
�A�ʑ��Y���E�E�E�����ቹ�̃X�^�[�g�s��v�͉����s�N��
��DSP�ŕ���܂����A�Ⴆ��AV�A���v�����̃p�C�I�j�A��SP������GENELEC�ł́A�@�A��̋@�\���_�u���ē���邱�ƂɂȂ�Ӗ��ł��B
���I�ɂ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ�����A�X�s�[�J�[�����^�C�v���L������
���̕ӂ͗����ł��܂��B
�A�N�e�B�u�X�s�[�J�[�̕����A���g�������̃L�����u���[�V�����\�t�g���D�G�BGENELEC�Ђő̌��ς݁B
LX805/KLIPSH��DILAC��TEAC��/OTOTEN�����ő̌��ς݁B
�����A���ۂɎg�����������̂Ŕ�r�͏o���܂��B
���ǂǂ��炩��DSP���g���Ζ��Ȃ����낤�Ƃ����F���ł��B
���Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��
��cL���炵����A�ׂ�������10m�ȏ�
�����悭���悤��SP�P�[�u����0.5m�Z���Ƃ��A�܂��܂����v���Ă�����ł��B
���̕ӂ͂悭������܂��A707S2�p�b�V�u�ł����g�������̒����ɋ�킵�Ă�̂ŁA�l�̓A�i���O�̌��E�������܂���(��
�������ʔ����̂�������܂��A�ʓ|�͖ʓ|�ł��ˁB
���V����������āA�Q���Ńs�[�[�[�[�������x���J��Ԃ��ĉƑ��ɉ����Ă�̂��ĉ����܂�܂����B
��L�͐M����1/4�g���x��AC�͐i�݂܂��A�ш���ɋ}���Ɉʑ����ꔭ��
�p�C�I�j�A��AV�A���v�Ń^�C���A���C�����g�������A�������オ�傫�������ł�
���̏�ŁAGENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B
���̕ӂ́A�I�[�f�B�I���S�҂Ȃ̂ŗ������ǂ����܂���B
�Ƃ�DENON�A���v�ɂ���ȋ@�\����܂������A�܂��g�������Ȃ��ł���(��
�����ԍ��F25401666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
�����Ⴂ���g���N���X�ɂȂ�Ƒ傫��LC���K�v�A�U���ʼn������₷��
�����̕ӂ͂悭������܂��A
B&W�@LC�l�b�g���\�N
�Ō�������ƁA�敥���b���͌��\�݂���܂��B�Ⴆ��
https://www.kurizz-labo.com/old_hp/Users_Report-18.html
707�́A�t�������W�{�c�B�[�^�\�̍\���ɋ߂�
�����ŃN���X�ALC�̗e�ʂ��������e���͏��Ȃ�����
�����ԍ��F25402052�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
��B&W�@LC�l�b�g���\�N
�Ō�������ƁA�敥���b���͌��\�݂���܂��B�Ⴆ��
�Ȃ�قǁB
���X�̃��~�b�^�[�J�b�g�ł��ˁB
�́A�A�����J���o�C�N�̃V���[�V����J�X�^�}�C�Y����������܂����A����ɋ߂��ł��ˁB
���_�̓~�j�l��ł���(��
��707�́A�t�������W�{�c�B�[�^�\�̍\���ɋ߂�
�����ŃN���X�ALC�̗e�ʂ��������e���͏��Ȃ�����
����������Ɛl�́B
LC�l�b�g���\�N���L��Ɩ����B
LC�l�b�g���\�N��ʂ��ĕ�ł���
MCACC�͍��x�ȋZ�p
�}���`�A���v���̓x�^�Ȃ���
���̓}���`�A���v
(LC�l�b�g���\�N���X)
GENELEC�Ƃ�LC�l�b�g���[�N���Ȃ��̂ŁA�����悭�ē�����O��������܂���B
����ƌ����Ă���Ӗ��������ł��܂���(��
�m���������ƃ}���`�A���v�͓�������Ȃ̂ŁA�����������Ӗ��ł́A�A���v������LC�����̃A�N�e�B�u���D�ʂ��Ď��ł��ˁB
�܂��A���̕ӂ̃V�X�e���\����iLoud Precision MTM�̌��C�x���g�ŒT�낤�Ǝv���Ă��܂��B
���������A������Ɗӏ܊��ō\�����Ⴄ�̂�������܂���̂ŁB
�ȉ��A�R�s�y�B
�T�E���h���[���ł́AminiDSP�Ђ̑g���p�{�[�h���̗p���A12ch����DSP�ƃo�����X�A���v��g�ݍ�������DSP�{�b�N�X�삷�邱�ƂŁA�R�X�g�p�t�H�[�}���X�̍���DSP�������������Ă��܂��B ����̃V�X�e���ł́AFIR�Ɋւ��Ă͊O���̃A�v���Ńt�B���^��v���邱�ƂɂȂ�܂����A����Ɋւ��ẮuFIR Designer�v�Ƃ����D�G�ȃA�v���ŏڍׂ�FIR�t�B���^�̐v���s���Ă��܂��B�܂��A�e�`�����l���̃��x���A�f�B���C�AEQ�iIIR�j�Ȃǂ́AminiDSP�̃R���g���[���A�v���ŗ��p�\�ƂȂ��Ă���A���������[��EQ�p�Ƃ��ė��p���Ă��܂��B���̂悤�ɁA�����ł́A�N���X�I�[�o���烋�[��EQ�܂ł̑S�Ă̏�����miniDSP�ŏ������Ă��܂��B
https://www.capcom.co.jp/sound/topics/dynamic_mixing_room/
���Ƃ́A�l�̓��[���A�R�[�X�e�B�b�N/��ݔg�̑�́A�F�X�����[�����Ȃ̂Ŏ�T��Œ����|�C���������邵���Ȃ��݂����ł���(��
�����/�v���V���[�}�[
http://www.salogic.com/home-select.files/home-145.htm
�ӏ܊�/�R���V���[�}�[
https://www.audifill.com/essay/eng/0_16.html
���ɓI�ɂ͕����̖͗l�ւ����������ł��B
�����ԍ��F25402092�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���}���`�A���v�͓�������A�����������Ӗ��ł́A�A���v������LC�����̃A�N�e�B�u���D�ʂ��Ď��ł��ˁB
�͂��A�D�ʂ��Ǝv���܂��B
�i�K�ŏ�����
1�D�v�����C���A���v
2�D�Z�p���[�g�A���v
3�D2�{����(DG68�A�g���m�t�Ȃ�)
4�D3�{�`�����f�o�{�}���`�A���v
2�A3�A4�Ƌ��z�A��x���オ��܂��B
4��LC�O���A���v������
����(���[�J�[�⏞�Ȃ����X�N)
�ɂȂ��Ă���̂ŁA���_�I�ɂ�
�n�[�h���������ł��B
genelec�͎���4�ɃW�����v
����X�s�[�J�[���[�J�[����
�X�}�[�g���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25402564�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
����ɂ���
�����玸�炵�܂��B
�S�͂܂��@���ʂ������ł��ˁB
���G���[�S������
�e�Ȃ��牞�������Ă��������Ă���܂��B
�撣���Ă��������B
�����ԍ��F25402572
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
��2�A3�A4�Ƌ��z�A��x���オ��܂��B
4��LC�O���A���v������
����(���[�J�[�⏞�Ȃ����X�N)
�ɂȂ��Ă���̂ŁA���_�I�ɂ�
�n�[�h���������ł��B
4�́A�o�R�Ō����ƌ��x�N���X�ł���(��
�`�r�������ł��B
��genelec�͎���4�ɃW�����v
����X�s�[�J�[���[�J�[����
�X�}�[�g���Ǝv���܂��B
������́A�S���h���g���Ē���܂ōs���Ă��܂������ł��ˁB
�悸�́A707S2�̃Z�b�e�B���O�����x���߂āA���r���O�T���E���h�ł��炭�V��ł���A��ɔ��������Ǝv���܂��B
TBC
�����ԍ��F25402657�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
>���V���A���g���I�ɂ͌����Ă��܂����
���̒��ɓ����̂Ɠ������ʂɂ���ɂ�
������A������Ԃ̐Q����������Ă݂܂����B
�����̌���Ǒ��i�ׂ��L�b�`���j/50Hz���ڗ���
���X�j���O�|�W�V����/100Hz���ڗ���
�L�b�`���①�ɑO/50Hz.100Hz���ڗ���
���������āA���ꂪ��ݔg�̌�������Ȃ��ł��傤���H
�L�b�`���①�ɂ̃��[�^�[�����������Ă�悤�ȋC�����܂��ˁB
�����ԍ��F25403006
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
��ݔg�́A�������̐��@�Ŋ�����
���g���Ŕ������܂��B
1�����傫���A2�A3���Ō����čs���܂���
�ꍇ�ɂ�肯��ł��B
���L�b�`���①�ɑO/50Hz.100Hz���ڗ���
�m�C�Y���x���Ɖ������x�����߂��A
�ቹ�͑��萸�x���o�ĂȂ������ł��B
�����AV�A���v�̉����ŏo�Ă��鉹�ʂ��炢
(���Ȃ�剹��)��ڈ��ɂ���Ă͂������ł��傤��
�����ԍ��F25403239�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�m�F���肪�Ƃ��������܂��B
�������AV�A���v�̉����ŏo�Ă��鉹�ʂ��炢
(���Ȃ�剹��)��ڈ��ɂ���Ă͂������ł��傤��
�Ȃ�قǁB
��������傫�����đ���ł��ˁB
10db�ȏ�łقږ����ł���Ƃ���̂ŁA�����Ă݂܂��B
����ł���肠��A�R�[�i�[���^���L�ƌ��V���ōđ��肵�Ă݂܂��B
�ȉ��R�s�y�B
�Ñ����Ƒ���Ώۂ̉��������������قlje���͑傫���A10db�ȏ�łقږ����ł���
��ʓI�ɈÑ����̉e���́A����ΏۂƂ̉�������10db���x����Ζ����ł���Ƃ���Ă��܂��B����͂��Ƃ��A�剹�ʂʼn��y������Ă��钆�ł͉�b��������A���肪�Â��ȋ�Ԃ��ƃX���[�Y�ɉ�b���o����̂Ɠ����d�g�݂ł��B����̉��A���Ȃ킿�Ñ������傫���Ȃ�قǑ���Ώۂ̑����𐳊m�ɑ��肷��͓̂���Ȃ�܂��B���������Ė{���������������ꍇ�͏\���ɈÑ����Ƒ���Ώۂ̉�����������ő��������̂��]�܂�����������ł��B
https://www.skklab.com/%E9%A8%92%E9%9F%B3%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E6%99%82%E3%81%AE%E9%9B%91%E9%9F%B3%EF%BC%88%E6%9A%97%E9%A8%92%E9%9F%B3%EF%BC%89%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%89%B1%E3%81%84%E3%80%81
�����ԍ��F25403307�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����
�ЂƂ܂��A�R�[�i�[���^���L����ł��������܂����B
���ʂ͂����ɁB
�����ԍ��F25403709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������ɂ悵����
����Ȃ�o�܂����B
���茋��
������V�X�e��
�v���A�v��/spectroid
���X�j���O�|�W�V����
�z����/�R�[�i�[���^���L�i�t�����g�V��Q�ӏ��ݒu�j
�z����/���V���i�o�X���t�Б��R�Âݒu�j
���⑫
���ʃA�b�v������Ԃ�4��
500Hz�t�߂Ƀf�B�b�v������
�X�}�z�A�v���ł̑���͂���ɂďI�����܂��B
��
�����ԍ��F25404138
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
���₷���Ȃ�܂�����
��ݔg���
����÷���g���ŕ����̏c�������Ɗ֘A�t��
�������Ă�������̊Ԃł̔��˂����������܂��B
�V��1.9m�A��3.5m�A�c4.3m�Ƃ����������ł��傤���H
�����ʒu��ς��Ă����݃��x�����ω����܂��B
�����ԍ��F25404355�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
���V��1.9m�A��3.5m�A�c4.3m�Ƃ����������ł��傤���H
��ݔg/���[���A�R�[�X�e�B�b�N�͉��[���ł��ˁB
���X�j���O�|�W�V�����ŕς��̂ŁA�F�X�T���Ă݂悤�Ǝv���Ă܂��B
�悸�́A�������c���ł͂Ȃ��A�����Ɏg�������Ō������ł��B
https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1405932.html
���z�́A�������X�s�[�J�[�𗼃T�C�h�����ăZ�b�e�B���O�o��������ł����A�悸�͉����ɂ��Ăǂ��Ȃ邩�B
�C���ɂ����߂܂��B
���[���A�R�[�X�e�B�b�N�́A�F�X�A�m�����[�܂��Ėʔ����ł��B
��������Ȃ�Ă����̂ŁA���������̃��m�͎���o�������ȋC�����Ă��܂�(��
�����ԍ��F25404446�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
�ǂ����A���^���L��V��ɐݒu����ƁA����/500hz�t�߂��z�����Ă��܂��悤�ł��ˁB
�I�[�f�B�I�V���b�v�̓X���ɂ��A���^���L�������o�X���t���ɔz�u����Ƃ��������Ƃ̎��B
���Ƃ́A���ꂪ���ʍ��������ł��B
�ȉ��A�R�s�y�B
���X�j���O���[���̂悤�ȏ����ȕ�Ԃł́A�ቹ��ŕ����̐��@�ɉ�������ݔg���N����܂��B������w������x�ƌĂ�錻�ۂł��B����"����"�̈�����A�u�[�~�[�ȉ���A���������Ɠ��̕NJ��́A���̒�ݔg�̉e���ɂ����̂ł��B����A�X�̒��͕�����Ă��Ȃ���Ԃł��邪�䂦�A��悪���z�I��"����"�A��Ԃ̋����������܂���BAGS�́A�����������̒��ł�"������"�����������Ȃ�"����"�̗ǂ��ቹ�Đ��������炵�A�X�̂悤�ȊJ���I�ȉ�����������܂��B
AGS�ɂ���ݔg�̊ɘa����
����܂ł̒�ݔg��́A�����̋��Ȃǂɋz���̂�ݒu���铙�̎�@����ʓI�ł����B�������A���ۂɂ͒��ɑ��Ă͂��܂���ʂ��Ȃ�������A���̉���S�n�悢�����ɊW���钆���悪�ߏ�ɋz������Ă��܂��A�Ƃ�����肪����܂����BAGS�ł́A���̂悤�ȃf�����b�g�����ƂȂ��A���̉�����P���ł��邱�Ƃ������ł��B
��ݔg�ɂ�鉹���̃s�[�N��f�B�b�v�́A���X�j���O�ʒu�ɂ���Ē��̕����������傫���قȂ邾���łȂ��A�����ꏊ�ŕ����Ă��Ă����g���ɂ���ĕ��������ɑ傫�ȍ��������܂��B�Ⴆ�A�x�[�X�̂��鉹�����傫���������邩�Ǝv���ƁA�ʂ̉������قƂ�Ǖ������Ȃ��A�Ƃ������o�����X�̈�������ɂȂ�܂��B�����ł͖͌^�����̌��ʂ�p���āAAGS�̌��ʂ�����������܂��B
https://www.noe.co.jp/business/architectural-acoustics/own-products/ags/lineup/sylvan.html
����ł��邩�ȁB
���ƁADG68�̘b�����܂������A����̓I���`�����ƌ����Ă܂����B
�Ȃ�EQ��͎ד��̂悤�Șb�Ԃ�ł����B
�����ԍ��F25404900�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
���삵�܂�����B
�O��ނ̑����̖_�g�ݍ��킹�Ă��܂��B
�����ԍ��F25404990�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]()
![]() 1�_
1�_
https://www.sonarworks.com/soundid-reference
�Ń_�E�����[�h�\��Sonarworks SoundID Reference for Speakers�̃g���C�A���ł������Ă݂��B
�X�s�[�J�[�́APolk Reserve R600�B
��O�́A50Hz���炢��+15dB���炢�̃s�[�N�����邪�A����+3dB�ȓ��Ɏ��܂��Ă���悤���B
���̉��́A��O��35Hz�`120Hz���炢�ɂ����ݔg�ɂ��ቹ�u�[�X�g�̉��Ɋ���Ă��܂��Ă���̂ŁA������ƕ�����Ȃ���������B
�����ԍ��F25405089
![]() 1�_
1�_
���G���[�S������
�ގ��͞w�ł��B�^�����ߏ��̃z�[���Z���^�[�ɖ��������̂ŁB
�����ԍ��F25405111
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�I�[�f�B�I�I�ɞw�ƃ^���̈Ⴂ�͉��ł��傤��?
�_�͎����ʼn��H���ꂽ��ł���?
���H���ȒP�Ȃ玩�삵�����ł��ˁB
�����ԍ��F25405150�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
����������Ȃ�Ă����̂ŁA���������̃��m�͎���o�������ȋC��
�������킩��A����͉\�����L����܂���
�C�R���C�U�[�͖��\�ł͂���܂���A±3dB���x��������x
�d�C�ł����琷���Ă���ݔg�̐[���J�͎����オ��܂���
�傫�ȕ����̓Z�b�e�B���O�Ő����A
�C�R���C�U�[�ׂ͍��ȓʉ��������Ŏg���܂��B
���I�[�f�B�I�V���b�v�̓X���ɂ���
��DG68�̘b�����܂������A����̓I���`������
��̓���́A������I���`���ł���
�}�C�N�œ�������Ȃ���A�p���C�R�ŎR��Q(�s��)�ƃ��x����ς���
�}�j���A���������������Ƃ�����܂�����ςł����B
�}�C�N�Ŏ��������I�[�g�}�͂ƂĂ��֗����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25405158
![]() 0�_
0�_
���G���[�S������
�^���̕������x�������ėǂ��ł��傤�BAGS���^�����g���Ă��܂��B
�ۖ_�ł�����K�v�Ȓ����ɐ邾���ł��B
�����ԍ��F25405207
![]() 0�_
0�_
��Minerva2000����
�Ȃ�قǁB
�w�̕��������݂����Ȃ̂Şw�ł��ǂ������ł��ˁB
�ЂƂ܂��v���Ă݂܂��B
�����ԍ��F25405306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������ɂ悵����
���傫�ȕ����̓Z�b�e�B���O�Ő����A
�C�R���C�U�[�ׂ͍��ȓʉ��������Ŏg���܂��B
�������܂����B
���}�C�N�œ�������Ȃ���A�p���C�R�ŎR��Q�}�C�N�Ŏ��������I�[�g�}�͂ƂĂ��֗����Ǝv���܂��B
�ł���ˁB
�����Ȃ�ƁA�ȉ��̋@���DSP�Ɋւ��ẮA���i���̉��l�����邩�ǂ����ɂȂ�܂����ADG68�ɂ��ꂾ���̒l�ł��������ł��傤��?
DG68/\890000/sharc/SHARC ADSP-21489/ES9028PRO
LX805/\423720/Cirrus Logic�����TI DSP/ES9026Pro
miniDSP2x4 HD/\44000(�}�C�N�ʔ���/\26800)/SHARC ADSP-21489/DAC�s��
LX805�́Asharc����Ȃ��Ƃ����̂������������Ă܂��B
�P��EQ����邾���Ȃ�AminiDSP2x4 HD����ԃR�X�p�������ȂƎv���Ă܂��B
�v�́A�Z�b�e�B���O�Ǝ����������o�����X�ǂ��g���āA������D������Ȃ���R�X�p���������Ŋy���߂����ɂ��������͂Ȃ����Ȃ�(��
��{�S���A�I���`���Ȃ�ŁB
�����ԍ��F25405337�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������ɂ��܂��Ă��A�X�s�[�J�[������̃��b�N�ɐݒu�����ׂ�TV���Ԃɓ��������ŁA������ʂ��ڂ₯�Ă��܂��������ő�̌��O�_�ł��B
����͕����̔z�u���������ɂ��āA�X�s�[�J�[�Z�b�e�B���O�ʼn������邵���Ȃ����ȂƎv���Ă��܂��B
��ݔg
�������
�Z�b�e�B���O
�L�����u���[�V�������Ђ�����߂����[���A�R�[�X�e�B�b�N
�����ԍ��F25405349�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ȉ��A�R�s�y
������ł́AAltitude 32��4�E�F�C�E�A�N�e�B�u�N���X�I�[�o�[�@�\�����p���āACH Precision�̃X�e���I�A���v�uA1�v�uM1�v��Е�ch������1�䂸�g�ݍ��킹�AVIVID Audio�̃X�s�[�J�[�uGIYA G1 SPIRIT�v��4�E�F�C�E�}���`�A���v�쓮���邷��Ƃ����V�X�e���Ńf�������{�B�I�v�e�B�}�C�U�[�@�\����уA�N�e�B�u�N���X�I�[�o�[�̐��\���A�s�[�������B
Altitude 32��CH Precision�̃X�e���I�E�p���[�A���v 4���g�ݍ��킹�āA4�E�F�C�쓮���s����
Atitude 32�̔w�ʒ[�q���B��ch������4�n���̏o�͂�p����4�E�F�C�E�}���`�A���v�쓮�����{
�X�e���̉�ł��鐼��p�͎��́A�n�C�G���h�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�̓C�R���C�W���O��������������������A����Ř^������ł̓f�W�^���̃C�R���C�W���O����g����Ă���Ǝw�E�B�u�g���m�t�ɂ��ẮA�N�x���オ�邱�Ƃ͂����Ă��A�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���В����Ċm���߂Ăق����v�ƌ���Ă����B
https://www.phileweb.com/sp/news/audio/201704/17/18568.html
���n�C�G���h�I�[�f�B�I�̃��[�U�[�̓C�R���C�W���O��������������������A����Ř^������ł̓f�W�^���̃C�R���C�W���O����g����Ă���Ǝw�E�B
�Ƃ������́A�I�[�f�B�I�V���b�v�X���́A������EQ���ے肵�Ă��ƌ��������ȁB
�����ԍ��F25405874�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����
Behringer ECM8000���������܂����B
�ЂƂ܂����̃V�X�e���ő��肵�Ă���ADEQ2496�w����EQ����悤���ƂȎv���Ă��܂��B
http://blog.livedoor.jp/loghouse1jp/archives/52305630.html
DCX2496/DEQ2496�̈Ⴂ���A���܂ЂƂ������Ă��܂��A���̕ӂ̓g���C�A���h�G���[�ł����ˁB
https://www.craft-design.yokohama/electric-hobby/dcx2496/
���̌�A�莝����DAC��EQ����܂����Ƃ���A���Ȃ�ǍD�ł��B
�Տꊴ�������A�����m�[�}���ɂ͖߂�Ȃ������ł��B
�����ԍ��F25408567�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�NjL
�R�[�i�[���^���L�ƌ��V������������āA���S�m�[�}���ȏ�ԂŃX�}�z���瑪�肵�܂������A����/500hz�t�߂Ƀf�B�b�v���ς�炸����܂����B
���^���L�����ɒu������F�X�����܂������A�������ʂł����B
�l�I���_
�X�}�z�}�C�N���̂̐��x�s����
�����ԍ��F25408617�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���茋��
�}�C�N/ECM8000
�C���^�[�t�F�[�X/M-TRACK SOLO
����\�t�g/Room EQ Wizard
��\�t�g/Equalizer APO
PC/win11
DAC/g6
AMP/POWERNODE EGGE
���A�l�ŁA�}�C�N����ɐ��������悤�ł��B
�X�}�z����̎��̂悤�ȁA500�t�߂̃f�B�b�v�͖����Ȃ�܂����B
���z���ނ̏ꏊ��ς��Ȃ��瑪�肵�Ă݂܂������A�����ȈႢ������ł��Ă�悤�ł��B
EQ�����������ł����o���܂����̂ŁA����X�ɍׂ������������Ă�����Ǝv���Ă��܂��B
�����z
�ǂ����ɂ́u�����ėǂ��Ɗ����鉹�v�Ɓu�����Ɠ������v��2������̂����m��܂���B
�������@��͖w�ǖ����̂ŁA��ʓI�Ɍ�����ǂ����͑O�҂́u�����ėǂ��Ɗ����鉹�v�ł���A�l�ɂ���ĈقȂ�Ǝv���܂��B����āA���l���ǂ��ƌ����Ă�����́A�����ɂƂ��Ă͓��ĂɂȂ�Ȃ����Ȃ̂����m��܂���B
����ARoom EQ Wizard�́u�����Ɠ������v��ڎw���c�[���ł��B������REW����������TSP(Time Stretched Pulse)�M���ł��B���̐M���̓t���b�g�Ȏ��g�������̐M���Ȃ̂ŁA����̍Đ����ʂ��t���b�g�ɂȂ�悤�ɒ�������A�u�����Ɠ������v�������܂��B
�A���A���ۂ͕����̉e����X�s�[�J�̉��������̉e���ŁA�����Ɠ����ɂ͂Ȃ�܂���B
�Ȃ̂ŁA�����̗ǂ��X�s�[�J�ƒ�ݔg�̏��Ȃ������ɂ��邽�߂ɁA�z���ނ�C�A�E�g�Ȃǂ̉��P���K�v���Ǝv���܂��B�܂��A���̒��x���ƑĂ����ʂ�EQ����ɂ͊����Ȃ���������Ȃ��ł����B
�܂��A�~�L�V���O�X�^�W�I�̉������t���b�g�ȓ����łȂ���A�Đ������t���b�g�ȓ����ɂ��Ă������ɂ͂Ȃ�܂���̂ŁA�������������Ǝv���A����ŗǂ��̂ł��傤�B���͊�{�t���b�g����ɂ��Ă��܂��B
�܂��APC�ōĐ����Ȃ��\�[�X�A���Ƀl�b�g���[�N�v���C���[�Ȃǂ̃X�g���[�~���O�\�[�X�́A�ʓrDSP�ŕ����K�v������܂��B
���̂Ƃ���A�ȉ��̋@��ł�������x��DSP����ł���Ǝv���܂����A��t���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[������̂łǂ���̃V�X�e���������ɍ����Ă���̂��͗v�����ł��ˁB
��DSP�����@��
�p�C�I�j�A�A�I���L���[��AV�A���v���A�荠�ȉ��i��Dirac�Ή����Ă��܂��B
LX805
TX-RZ70
TX-RZ50
���ꂩ��͂�A�s���A�����Ŏg���̂ł���AminiDSP���育��ȋC�����܂��B
miniDSP SHD
https://minidsp.jtesori.com/products/shd/
�x�����K�[�œ��ꂷ��Ȃ炱�����݂����ł����A���荢��̂悤�ł��B
DEQ2496
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/19062/?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAsQjTCjUWf6TtnqPevCP1CzjI4hFNA5l0aQy408vhYswo_I1S9U67EaAs9QEALw_wcB
����t���A�N�e�B�u�X�s�[�J�[
���l�i���߂ł����ƊE�W��
GENERIC
iLoud Precision
�R�X�p���߂̃j���[�J�}�[/�X�^�W�I�E���j�^�[�̍Ē�`
https://hookup.co.jp/products/ik-multimedia/iloud-precision
����[����ɂ��Ă������܂ŗ���̂ɂ��Ȃ莞�Ԃ��������ȁB�B
����ꃂ�[�h�Ȃ̂ŁA����͓������x�݂ł��B
��
�����ԍ��F25409909
![]() 0�_
0�_
�G���[�S������
��DCX2496/DEQ2496�̈Ⴂ���A
���܂ЂƂ������Ă��܂���
D�f�W�^��CX�`�����l���N���X�I�[�o�[24bit96kHz
DEQ2496��EQ�C�R���C�U�[�ɑ���܂��B
�Ⴂ
DCX2496�A6ch(3way�X�e���I�\)
3���9way�X�e���I�Ƃ��A���\
�p�\�R����ʂŃR���g���[���\(RS232C)
�ƂĂ����Ղ�
�e�X�̃X�s�[�J�[���j�b�g�ɑ�
�N���X���g���A�������x���A
�C�R���C�U�[�A�^�C���f�B���C
�p�r�̓o���o���̋Ɩ��@���
����Ƃ��z�[���̉����ݔ�����
���ӓ_
�Ɩ��p�Ȃ̂ŃL���m���R�l�N�^�[
11�{���g�Ńt���r�b�g
�����p��1V�ł̓t���r�b�g�ɂȂ炸
�����������m�C�Y�ŕs��
���x�����̓I�V��������Ή����\
LE�̓p�\�R���ɂȂ��炸�A�R�X�g�_�E����
DEQ2496
�C�R���C�U�[
�}�C�NEMC8000�ʼn����\
�����p��1V�������̐�ւ��{�^���őΉ�
�I�N��2���~�O��
DEQ2496��1.8���ł������V�i���l
�O�I�[�i�[�A1���J���ĂȂ��Ƃ̎�
DCX2496���C�R���C�U�[���t���Ă���̂�
�p�\�R���Ń}�C�N��SP��F���݂Ȃ���A
�������傫��EQ�̎R�J�Ă�
�����͉\
DCX2496�͏����^�����Ղ������悤��
�������T�E���h�n�E�X�Ŕ�����
�����N���[���������Ă܂��B
����^�̓m�C�Y��œd�����V�[���h����
���ʂ͏��������ǖ������x���ł��m�C�Y�͂��Ȃ�
������܂����B����^�Ȃ���Ȃ����͕s��
�f�W�^�����͂ɂ��������������Ă����̂�
(�z�\�P����A�P�����b�N)�f�W�^���œ��o�͂����܂���
DCX�͒P�Ȃ�v�Z�@
�ǎ��̊O�t��A/D��DAC�ōX�ɉ���������\
��H�}���l�b�g�ɂ�������A���C����
�ł��A�₽�牽�ł�����Ȃ̂ŁA��
�������A�S�[���������Ȃ��A�w�͂ƍ������Ώ��ł���
�f�B���b�N�̊C
����o���Ȃ�
�܂�DEQ2496�Ō��Ȃ炵���悢��������܂���A
�_���Ȃ�I�N�ŏ����ŁA�_���[�W�͑�����������
�����ԍ��F25409977�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ɂ悵����
������肪�Ƃ��������܂��B
���I�N��2���~�O��
DEQ2496��1.8���ł������V�i���l
�O�I�[�i�[�A1���J���ĂȂ��Ƃ̎�
�T�E���h�n�E�X�������݂����ŃI�N�ɂ������ł��ˁB
���������A�S�[���������Ȃ��A�w�͂ƍ������Ώ��ł���f�B���b�N�̊C����o���Ȃ�
�܂�DEQ2496�Ō��Ȃ炵���悢��������܂���A
�܂��ADEQ2496�̕��������o�͂��t���Ă�̂ʼn����ƕ֗������ł��ˁB
�ЂƂ܂��A�n�C�u���b�g�l�b�g���[�N�V�X�e���\���͂���Ȋ������C���[�W�B
�V�X�e���\��2/�l�b�g���[�N�v���C���[�o�R�Ŏg���邩��B
���Q���V�X�e���\��1/PC
PC/WIN11
DDC/G6
DSP/DEQ2496(���f�W�^��)
MIC/ECM8000
DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(���f�W�^��)
AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)
SP/707S2
���Q���V�X�e���\��2/�l�b�g���[�N�v���C���[
NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)
DSP/DEQ2496(���f�W�^��)
MIC/ECM8000
DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)
AMP/SOUL NOTE A1(XLR)
SP/707S2
��AV�V�X�e���\��3/�l�b�g���[�N�v���C���[�}���`�`�����l��
NP/Ever solo DMP-A6(HDMI)
BP/ZR1(HDMI)
DSP/DIRAC
MIC/DIRAC
AMP/LX805(HDMI)
SP/KLIPSH
AV��EQ���DIRAC
Ever solo DMP-A6
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0C55KFZQN/ref=ox_sc_act_image_4?smid=A86UQ26AD5A0N&psc=1
�����ԍ��F25411048�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Q���V�X�e���\��4/PC
PC/WIN11
DSP/miniDSP SHD(USB)
MIC/UMIK-1(USB)
AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)
SP/707S2
���Q���V�X�e���\��5/PC
PC/WIN11
DSP/miniDSP SHD(USB)
MIC/UMIK-1(USB)
AMP/SOUL NOTE A1(XLR)
SP/707S2
miniDSP SHD���ƃI�[���C�������Ȃ̂ł��Ȃ�y�����B
https://minidsp.jtesori.com/products/shd/
�}�C�NEMC8000���g���ꍇ�́A�ʃC���^�[�t�F�[�X������́B
�����ԍ��F25411115�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ǂ����ADAC�������f��������͗l�B
https://minidsp.jtesori.com/products/shd-studio/
�����ԍ��F25411125�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Q���V�X�e���\��6/PC
PC/WIN11
DSP/miniDSP STUDIO(USB)
MIC/UMIK-1(USB)
DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)
AMP/SOUL NOTE A1(XLR)
SP/707S2
���Q���V�X�e���\��7/PC
PC/WIN11
DSP/miniDSP STUDIO(USB)
MIC/UMIK-1(USB)
AMP/POWER NODE EGGE(���f�W�^��)
SP/707S2
���Q���V�X�e���\��8/�l�b�g���[�N�v���C���[
NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)
DSP/miniDSP STUDIO(���f�W�^��)
MIC/UMIK-1(USB)
DAC/RME ADI-2/4 Pro SE(XLR)
AMP/SOUL NOTE A1(XLR)
SP/707S2
���Q���V�X�e���\��9/�l�b�g���[�N�v���C���[
NP/Ever solo DMP-A6(���f�W�^��)
DSP/miniDSP STUDIO(���f�W�^��)
MIC/UMIK-1(USB)
AMP/POWERNODE EGGE(���f�W�^��)
SP/707S2
DAC���������F�X�ȃp�^�[�����z��ł������ł��B
miniDSP�́ADIRAC�Ή��Ȃ̂�EQ���\���A�x�����K�[�����������ł��B
�����ԍ��F25411153�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���[���A�R�[�X�e�B�b�N�ɂ���
GENELEC�ЂŎg���Ă����̂́A�ǂ���炱�̃��[�J�[�̂悤�ł��B
https://youtube.com/watch?v=ukp3Jo2yWK4&si=VRUTbKzvlzBKuh8J
�����ԍ��F25422944�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Q�����[���A�R�[�X�e�B�b�N�f�U�C��
�����C���[�W
�����ԍ��F25423005�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�X�s�[�J�[�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2026/02/11 10:17:41 | |
| 16 | 2026/02/11 17:53:42 | |
| 5 | 2026/02/05 15:41:47 | |
| 3 | 2026/02/02 12:47:32 | |
| 13 | 2026/02/03 6:52:58 | |
| 4 | 2026/02/01 8:20:56 | |
| 2 | 2026/01/28 0:02:05 | |
| 2 | 2026/01/26 8:41:26 | |
| 3 | 2026/01/26 11:59:46 | |
| 1 | 2026/01/31 11:02:54 |
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�X�s�[�J�[]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�������߃��X�g�z���X1440���Q�[������l����
-
�y�������߃��X�g�z���X�X���p
-
�y�~�������̃��X�g�z�V�Z�p�������@�̎���PC
-
�y�~�������̃��X�g�zDDR4�őË��\��
-
�y�~�������̃��X�g�zAM5
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N2���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2026�N1���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2026�N2���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�Ɠd�j
�X�s�[�J�[
�i�ŋ�5�N�ȓ��̔����E�o�^�j