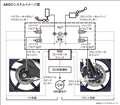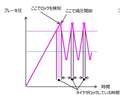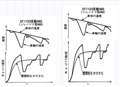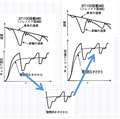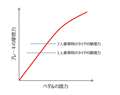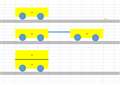����1
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/
����2
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/
��Ԑl���������Ă����������͓���
�Ƃ������Ƃ��ǂȂ��ł�������悤�ɐ������鎎�݂ł��B
����1�̃X���蓮��
96km/h����t���u���[�L�B
1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B
https://youtu.be/MRxr757Q9nk?t=211
�u���[�L���ݗʂ����ɂ���JAF�̃e�X�g����B
1����Ԃɔ�ׂĒ����Ԃ͐����������L�т�B
https://www.youtube.com/watch?v=-dw1avumTpI
�����d���Ŋm�F�ł��Ȃ��ԂɑO�X����200���܂œ��B���Ă��܂��܂����B
���������������X�͈�����Ȃ̂ł����A���ɂƂ��Ă͋����̓��e�łǂ����Ă��������������̂ŁA���������Ƃ͏d�X���m�̏�ł���1��X�����Ă����Ă��炢�܂��B
�����ԍ��F25938419�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����@���������ς��@���]��Ȃ�@�\���̂킩��@�͎��}�@���炢�ڂ��Ă�������
�����ԍ��F25938428
![]() 3�_
3�_
���i�C�g�G���W�F������
��https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937648
��ABS�́A�ݒ肳�ꂽ���̋����Ńp�b�h�������t���A���b�N������A�ɂ߁A���b�N������A�܂����������Ńp�b�h�������t����Ƃ���������u���ɌJ��Ԃ��Ă���Ă���Ɨ������Ă��܂����A
�Ȃ�قǁB�i�C�g�G���W�F�������Fig. A�̂悤�ɂ��l���ɂȂ����Ƃ������Ƃł��ˁB
�������̔��z�͂���܂���ł����B
����܂ł̐����ŁA���͏��Ȃ��Ƃ�Fig. B �̂悤�ɓ`����Ă��邾�낤�Ǝv������ł��܂����B
��https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937875
���P�A�`�a�r�쓮���ɃV�X�e�����u���[�L����ς��Ă���Ƃ��������́H
���ۂɂ́AFig. C�̂悤�Ȑ���ƂȂ�܂��B
���̗��R��2�Ő�������Ƃ��āA�˂��݂���B����̃����N��ɂ����� �}10�͂܂��ɂ��̂悤�Ȑ��}�ƂȂ��Ă��܂��B
https://www.honda.co.jp/factbook/motor/technology/19950900/006.html
Honda T.R.-C.ABS�EM.A.-C.ABS �����䐫/�^���̂��߂̋�̉��Z�p �}10
ABS�������Ă���Œ��ɂ��A�����J�n/�����J�n����u���[�L�����L�����p�t�����ׂ����ϓ����Ă��邱�Ƃ��������肢�������܂��ł��傤���B
ABS���^�C�����b�N�Ō������A���b�N�������������̂͂������̂Ƃ���ł��B���̂��߁AABS�ɂ͐l���y�_�����͂����ABS���g������/�����������͂�m�邽�߂̉t���Z���T�����ڂ���Ă��܂��B
Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō������J�n����悤�Ȑ���ɂ��Ă��܂��ƁA���̃u���[�L���͍ő�ύڗʂ�z�肵�����͂ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ邽�߁iFig. A-1�j�A�ԏd���y�����ɂ̓^�C�����b�N���琧��J�n�i�����J�n�j�܂ł̎��Ԃ������Ȃ�܂��iFig. A-2�j�B
���̂��߁A�^�C�����b�N���Ă��鎞�Ԃ������Ȃ�A�y�����̕������������͐L�тĂ��܂��܂��B
�܂��A���x�������Ă���悤�ɁAABS���쓮�J�n����i1��ڂ̃^�C�����b�N�j�܂ł̃u���[�L���͐l���y�_���ވ��͂ł��B
��舳�͂܂œ��B���Ȃ����茸�����n�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�ԏd���y�����ɂ́A�^�C�����b�N������ɂ���Ƀy�_���ݍ��܂Ȃ�����A��������ABS���쓮���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
���Q�A�܂��A�ǂ̂悤�Ȑ���Ńu���[�L����ς��Ă���̂������������������B
1�ŏ������悤�ɁA�ԗ֑��Z���T�Ɖt���Z���T��p�����t�B�[�h�o�b�N���䂪��{�ƂȂ�܂��B
��������Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō���/��������̂ł���A�ԗ֑��Z���T�͕K�v����܂���B
Fig. C �̂悤�Ȑ���ł́AABS�̓^�C���̃��b�N�����m����ƁA���b�N���������Ⴂ�u���[�L���܂Ō������܂��B
��������Ăщ������n�߁A�܂����b�N����ƁA���x�͐�قǂ�菭�����������u���[�L���܂Ō������܂��B
��������Ăщ������n�߁c�A�ƌJ��Ԃ����ƂŁA�u���[�L�������b�N���E�ɋ߂Â��Ă����܂��B
�����ԍ��F25938433�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���Ђ�N�Ђ�N����
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/#25931647
�͂��B�͎��}�ł��B
�����ԍ��F25938435�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������ā@�\����R�����Ɓ@��3�Ɂ@�ς������@�Ȃ���?�@�@������m������
�����ԍ��F25938445
![]() 0�_
0�_
�f�B�X�N�u���[�L�͈ꌩ��₱���������Ɍ����邪
�ԗւƃf�B�X�N�a�̔䗦�͉ςł��Ȃ��̂�
�d�Ԃ̃v���X�u���[�L�Ɠ���
�Ȃ�Ȃ�@���[���������t����@�g���b�R�u���[�L�Ƃ�������
��3 �Ɠ����Ƃ������܂�
�����ԍ��F25938451
![]() 0�_
0�_
���Ђ�N�Ђ�N����
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937527
��3�͂�����ł��ˁB
�͂��B�����v���܂��B
�Ђ�N�Ђ�N����ɂ͂����ƃ��X�ł����\����܂���ł������A���ɊԈ���Ă������ȂƂ��������܂���ł����̂ŁB
�����ԍ��F25938454�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��3�̏o��Ł@�Y���ǁ@�{���͎��R��Ԃ̎��ʂ́@M�[m �ɂ��邩�Y�݂܂���
���̂ق��������G���K���g�ɂȂ邩�Ȃ�
�����ԍ��F25938460
![]() 0�_
0�_
���Ƃ́@ABS �͖��@���O�~�@�ł͂Ȃ�
�쓮�����̐����͂����邱�Ƃɂ��
�ő�Î~���C�͂��@�쓮�ƃT�C�h�t�H�[�X�ɐU�蕪����@�������锭���ł�
�����ԍ��F25938469
![]() 0�_
0�_
�O�̃��X�ɑ����ۂ�
�ꕔ�̕��X��
����Ȃ��Ƃ����ȁ@�ł����炢����
�Ł@�����̍\���v�������Ă���ׂ��Ă���̂Ł@�����@�b�͔��U����̂���
�����ԍ��F25938476
![]() 0�_
0�_
ABS�@�n�C�h�����j�b�g�̍\���}�ł́@�����Z���T�[�̂����͋H�ł���
�Ƃ������@�����܂Őf��V�X�e���́@���̃��[�J�[�̔���Ȃ���
�����ԍ��F25938541
![]() 1�_
1�_
�����������Ȃ̂Ł@�s���m��������܂���
�ʏ푖�s�����@�p���x�@�p�����x�@�����o����
���e����郍�b�N���i�p�����x�̍ő�l�j���w�K���邱�Ƃɂ��
ABS�������̌��o���x�����߂Ă���ƕ����܂��B
�i�ā@�~�@�^�C���̓�����O��ٌa���w�K�j
�����ԍ��F25938552
![]() 0�_
0�_
���������@�����}�@�����p�ӂ��������@�\����Ȃ��̂ł���
���b�N���o��
�}���Ȋp���x�����@�Ɓ@���p���x�@���画�肵�Ă��܂��̂�
���������܂����ʒu�Ō��o���Ă�킯�ł͂Ȃ��̂ł�
�Ǝv���܂��B
���ʂƂ��ā@���Z�ʒu�ɂ͐����ł���
�����ԍ��F25938574
![]() 1�_
1�_
���Ђ�N�Ђ�N����
�������܂Őf��V�X�e���́@���̃��[�J�[�̔���Ȃ���
�����Ȃ�ł��ˁB
ABS�̐��䃍�W�b�N�̕ϑJ�͑��������Ȃ��̂ł����A���̓ǂ����ɂ͂��łɖ�����f�Ă�����̂��ڂ��Ă��܂����B
�i�������͖Y��܂����j
���͂����������̕�����ʓI�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��B
���ʏ푖�s�����@�p���x�@�p�����x�@�����o����
�����e����郍�b�N���i�p�����x�̍ő�l�j���w�K
�����b�N���o��
���}���Ȋp���x�����@�Ɓ@���p���x�@���画��
�����������܂����ʒu�Ō��o���Ă�킯�ł͂Ȃ�
�͂��B�������̔F���ł��B
�����\������ɂ́A
�@ �����Ɏ��ԁ\�c���Ɍ��������x�iG�Z���T�l�j
�A �����Ɏ��ԁ\�c���Ɏԗ֑��Z���T�l
�B �����Ɏ��ԁ\�c���Ƀu���[�L���i�����Z���T�l�j
���c�ɂȂ�ׂ�ׂ��Ȃ�ł����A����͇B�������ڂ������߁A���b�N�����m���邽�߂̃��W�b�N���\���ł��Ă��܂���B
���b�N���E���班�����Ԍo�߂����Ƃ���Ƀ��b�N���m�̓_������̂́A�@�ƇA���烍�b�N�����m���Ă��邽�߂ł��B
�����ԍ��F25938637�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�Ȃ̂Ł@�z���_�̎������@
�ԑ��i���H���͂ǂ��Ȃ�@�@�l�ւ̕��ϒl���j�Ɓ@
����Ώ֑ۗ��x�@��
�����Ԏ��s�h�l�d�@�ɖ������f������
�K�v���������̂��Ǝv���܂��B
���̓Z���T�[��
���t�����l�����\�ԁ@�Ȃ�@����ɂȂ邩������܂���
�܂�����@�R�ꂽ�肷��@�v�f�ɂȂ�܂��̂�
���̂������Ă�@���������Ԃł͐f�����ƂȂ��ł��B
�@
�����ԍ��F25938654
![]() 0�_
0�_
�Z�p������ǂޏ�Œ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂�
�����̓��e�́@
�t�ɓ����Ǝ҂��@�܂���ʂɍs���Ă��Ȃ��@�Ƃ������Ƃł�
�L���Ȃǂɑ����@���Ђ̔�����S���Ă�����̂�
�v���ӂ��Ǝv���܂��B
����������Ɓ@���艟�����I�ȓ����o���
�R�X�g�@��@�M�����i�̏ᗦ�͕��i�ׂ̂���ɂȂ�j������
���o��i�i�Z���T�[�j�@��@�����i�i����o���u�j��
������ł��\���}�ɐ��荞���{��ɂȂ����肵�܂��B
�i�������́@�����̑_�����������肵�܂����j�@
�����ԍ��F25938661
![]() 0�_
0�_
���̗F�l�E���畷�����b�ł�
ABS���䃆�j�b�g�́@�QCPU�Ł@���݂����Ď����������Ƃ��Œ���K�v
�ƕ������̂ł����@�����������L�q�̎����͌������Ƃ�����܂���
����������Ɖߋ��̋Z�p�Ȃ̂�������܂���
�i�Q�T�N�o��������@�܂��������j
�����ԍ��F25938666
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
���ɕ�����₷���O���t�����肪�Ƃ��������܂�
�i�C�g�G���W�F������̎咣�ł���AFig.A�ł����Ƃ���̍ő�̃u���[�L�����ǂ�Ȏ������Ƃ����̂͐v�Ƃ��Ė�肠��܂���Ƃ����猾�t�Ő������Ă����������������܂���ł����̂�
�Ƃ���ŁAFig.A�̍ő�̃u���[�L�����w�ő�ύڗʂ�z�肵�����́x�Ɖ��ɂ�����܂������A�������Ƃ��Ă͎ԑ��A�^�C���̃O���b�v�͂�H�ʏA���z�ȂǂłƂĂ����炩���߈�Ɍ��߂������̂ł͂Ȃ��ł����
���ꂾ���炱���A
> 1�ŏ������悤�ɁA�ԗ֑��Z���T�Ɖt���Z���T��p�����t�B�[�h�o�b�N���䂪��{�ƂȂ�܂��B
> ��������Fig. A�̂悤�ɏ�Ɍ��܂����u���[�L���Ō���/��������̂ł���A�ԗ֑��Z���T�͕K�v����܂���B
�Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ��������ł�
�����ԍ��F25938829
![]() 2�_
2�_
������ABS �͐�]���Ă܂��@���������A���^�C���ɏ�ق����Ƃ͎v���܂���
������̓T�X�y���V�����X�g���[�N�ʂ���@�p���ω��ɔ����^�C�����̉����͂ق����Ǝv�����肵�܂�
�����ԍ��F25938903
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
�l���܂��ɂ��̂悤�ȃC���[�W�}���������Ǝv���Ă����Ƃ���ł��A���肪�Ƃ��������܂��B
�l�̃C���[�W�͂��̐}�̂悤�ɍl���Ă��܂��B
D�_�܂ł́A���ʂ̃u���[�L���O�Ńh���C�o�[�̓��ݗ͂ɔ�Ⴕ�āA�����͂��オ���Ă����܂��B
�Ă�D�_�Ńp�j�b�N�u���[�L(�}�u���[�L)���V�X�e�������m�����A�_�Ő����͈͂��(���̎Ԃ̎��u���[�L�̍ő吧����)�ƂȂ�A���̐����͂Ń��b�N��h��ABS�������Ƃ����C���[�W�ŁA��Ԑl���̈Ⴂ�ɂ͊W�Ȃ������͂�C�̂܂܂���Ȃ����Ȃ��āB
�����A�ԏd�̈Ⴂ��ABS�����삷��܂ł�A�_����B�_�܂ł̒����̈Ⴂ�͂��邾�낤���ǁB
�ł�����ԏd�ɂ����C�_�̈ʒu�͕ς��Ȃ����낤���l�̍l���ł��B
�ŁA�O�X���ł������܂������A�ԏd��C�_���ς��Ƃ��������Ȃ�A���̍�����,�ǂ�Ȑ���ł��������Ă���̂����������Ă��܂��B
�����ԍ��F25939003�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���ԏd��C�_���ς��Ƃ��������Ȃ�A���̍���
�ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�
�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�
�Ƃ������Ƃ���͂育�������������Ȃ��̂ł��ˁB
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937400
���ł͂���ȏ�̐������ł��܂���B
�\�������܂���B
�����ԍ��F25939022�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������������炢�ł�����
���Ƃ���ŁAFig.A�̍ő�̃u���[�L�����w�ő�ύڗʂ�z�肵�����́x�Ɖ��ɂ�����܂������A�������Ƃ��Ă͎ԑ��A�^�C���̃O���b�v�͂�H�ʏA���z�ȂǂłƂĂ����炩���߈�Ɍ��߂������̂ł͂Ȃ��ł����
�����ł��B
�����̃��b�N���E���ǂ��܂ʼn�����̂��A�Ԃ����̃��b�N���E���ǂ��܂ŏオ��̂��A���ׂĂ�z�肵�Č������J�n���鈳�͂ƍēx�������J�n���鈳�͂����߂�K�v������܂��B
������Ǝg�����̂ɂȂ�Ȃ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25939023�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ђ�N�Ђ�N����
��������ABS �͐�]���Ă܂��@���������A���^�C���ɏ�ق����Ƃ͎v���܂���
��������̓T�X�y���V�����X�g���[�N�ʂ���@�p���ω��ɔ����^�C�����̉����͂ق����Ǝv�����肵�܂�
�����ł��ˁB
Fig. B�̂悤�Ȑ���ł���A�^�C�����b�N���m�����m������ABS�̃��[�^�[�d���l��ς��邾���Ȃ̂ŁA�t���Z���T���Ȃ��Ă��ł���Ǝv���܂��B
Fig. C�̂悤�Ȑ��䂪�ł��邩�ǂ����͂�����Ƃ悭������܂���B
�t���Z���T���Ȃ��ƁA�l���r���œ��ݑ������肵���Ƃ��ɑΉ��ł��Ȃ��C�����܂��B
�ԗ����Ń^�C���̐ڒn�����v������̂́AF1�̂悤�Ɍ���ꂽ�ō����x�ȋ�C���Z���T������Ή\��������܂��A�ʎY�Ԃ�TPMS�ł͓���ł��傤�ˁB
G�Z���T�̒l���g���Đ����͔z���̌v�Z������\�������l���g���Ă���Ǝv���܂��B
https://www.eureka-moments-blog.com/entry/2019/12/29/202215
�����ԍ��F25939029�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ƂЂƂA�ԏd�ɂ���ĕς��̂͂��̃C���[�W�}�̓��ݗ͂ɂ�鐧���͂̎ΐ��̌X���͕ς�邯�ǁA�ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F25939038
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���ԏd�ɂ���ĕς��̂͂��̃C���[�W�}�̓��ݗ͂ɂ�鐧���͂̎ΐ��̌X���͕ς�邯�ǁA�ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H
�������h���C�o�[�̃u���[�L���ݗ�
�c�����p�b�h�̉����t����
�ł���ˁB
�X�����ς��Ƃ������Ƃ́A
�{�͑��u�̔{�͂��ς��A�}�X�^�[�V�����_�[�̌a�ƃL�����p�s�X�g���̌a�̔䂪�ς��A�y�_���䂪�ς��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F25939059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
���ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�
���^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�
����͎ԏd���قȂ鎞�̒ʏ�̃u���[�L�ōő吧���͂b�ɓ��B����܂ł̒ʏ�u���[�L�ł���������������̂ł́H
�ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H
�����p�j�b�N�u���[�L�̎������d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H
�`�a�r�Ŏ�̍���������A�p�j�b�N�u���[�L�ł������悤�ɏd�ʂɂ�萧���������ς��̂����ʂȂ�Ȃ��́H
���X�����ς��Ƃ������Ƃ́A
���{�͑��u�̔{�͂��ς��A�}�X�^�[�V�����_�[�̌a�ƃL�����p�s�X�g���̌a�̔䂪�ς��A�y�_���䂪�ς��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�������͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��ł��傤�B
�����ł����ˁB
����͊��Ⴂ�ł����A���炵�܂����B
�����ԍ��F25939088
![]() 0�_
0�_
>�t���Z���T���Ȃ��ƁA�l���r���œ��ݑ������肵���Ƃ��ɑΉ��ł��Ȃ��C�����܂��B
����܂�W�Ȃ���Ȃ����ȁ@
�������������t�[���h�̓u���[�L�y�_�����ɂ��ǂ���
�l�Ԃ������Ă���킯�Ł@�i�Ȃ̂ő��ɃK�N�K�N������j
�������Ɛl�Ԃ����ݍ��߂��������ł�����
���̐}�ɂ���悤�Ɂ@�ȈՃ��U�[�o�͂����
�S�n���͓Ɨ����Ă܂��̂Ł@�n�����̑��ʂ͌���Ȃ��킯�ł�����
�����ԍ��F25939103
![]() 1�_
1�_
�ԗ�������\������@�^�C���ւ̉��́@�́@
�T�X�y���V�����̒��ݍ��݂Ɓ@�ɂ����ƌ����Ǝv���܂��B
�����@�^�C���̐ڒn�ʂ̑����͓ǂ߂Ȃ��ł��傤��
��C���͋}���ɂ͕ς��Ȃ��̂�
���푖�s���̃X���b�v������w�K���Ȃ�
�����ԍ��F25939110
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
������͎ԏd���قȂ鎞�̒ʏ�̃u���[�L�ōő吧���͂b�ɓ��B����܂ł̒ʏ�u���[�L�ł���������������̂ł́H
�͂��B�����ł��B
���ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H
���������͂ł���A�����������ς��
�����͂�ς���A�����������ɂł���
�Ƃ������Ƃł��B
�ʏ�u���[�L�ł��낤�ƃp�j�b�N�u���[�L�ł��낤�Ɠ����ł��B
���d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H
�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����ő吧���͂ł��B
[1] �ԏd��������A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�
[2] �^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��傫���Ȃ�A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�
[3] �ő喀�C�͂���u���[�L�����傫���Ȃ�A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����傫���Ȃ�
[1]����[3]���Ȃ��ĊԂ��Ȃ��A
�ԏd��������A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L�����傫���Ȃ�
�ƂȂ�܂��B
�܂�A�ԏd�𑪒肵�Ȃ��Ă��A�^�C�����b�N�����m���邱�ƂŁA�ő喀�C�͂�������u���[�L����������Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F25939117�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���ō��_�̂b�_�͕ς��Ȃ��̂ł́H
���̂b�_�Ƃ́A�u���[�L�����b�N���鐡�O�̐����́i���C�́j�ŁA�����ɂ�炸���MAX����������ƌ������ł��傤���H
���������Ƃ���A�J�̓���C�_�͂ǂ��Ȃ�܂����H
�オ��܂����A������܂����H
�����ԍ��F25939123
![]() 1�_
1�_
���Ђ�N�Ђ�N����
ABS���g�������������͂����A�������͐l������ł��鈳�͂��債�ĕς��Ȃ���A���݂̈��́����݂�ABS�̃��[�^�[�d���ŁA���݂��d���𑝂₵���茸�炵���肷�������ł����B
�r���Ől�����ݑ�������A�͂����肵�Ă��܂��ƁA���͂Ɠd���̊W�l��������Ă��܂��̂ŁA����ς舳�̓Z���T�������������ȒP���낤�ȁB
�Ƃ����z���ł��B
�����ԍ��F25939133�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���ʏ�u���[�L�ł͓��������͂����������A�ԏd�̈Ⴂ�ŁA�����������ς��̂ɁA�ǂ����ăp�j�b�N�u���[�L�ł́A���������͂b�������Ă���̂ɁA�d�ʂ��ς���Ă����������������Ȃ�ł��傤���H
�����͂b�͓����ł͂Ȃ��ԏd�ŕς��A�ƌ����Ă�̂ɂ܂��J��Ԃ��B
�������p�j�b�N�u���[�L�̎������d���ɂ���čő吧���͂�ς��Ă���Ȃ�A���������������ɂȂ�̂͗����ł��邯�ǁA�ǂ�����čő吧���͂��d�ʂɂ���ĕς��Ă���̂ł��傤���H
�u�ő吧���́v�̈Ӗ����s���ł����A�u�����́v�̓^�C���̃X���b�v�����o���ĕς��Ă���A�ƌ����Ă���̂ɌJ��Ԃ��B
�����ԍ��F25939143
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
�����ł��ˁB
�A�b�v���ꂽ�C���[�W�}�@�e�����@�b�@�ŏd�ʂɂ��ő�u���[�L�͂̕ω��́A����Ɨ����ł����悤�ȁB
�m���Ɍy���ق��������u���[�L�͂ł̓��b�N���₷���̂�������O�ł���ˁB
���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25939167
![]() 2�_
2�_
��use_dakaetu_saherok����
�ς݂܂���A���̂Q���I����Ă��܂��܂����̂ŁA���̂R�ʼn��܂��B
��͂�A���������_�ł����ˁB
�ԏd�̕ω��́A���������ɑ傫���e����^���܂��B
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
���̎��́A�傫������Ă��镔��������܂��B
�Ƃ����̂́A�d�͉����xg���g�p���Ă��邩��ł��B
���X�d�͉����xg���g�p���Ă���̂ɂ͋^�₪����܂������A�@������d�C�ł͈ړ������x��d�q�^���ȊO�Ŏg�p���Ȃ����̂ŁA�m�F�̂��ߏ������Ԃ�v���Ă��܂��܂��B
�d�͉����xg�́A�����ɂ�����^����\���Ƃ��Ɏg�p������̂ł���A�ᖀ�C�ʼn�]����^�C���A�ԗւ��g�p���������^���ɂ͕s�K�ł��B
�����ɂ��d����W(run)�ł���A�����ɂ��d����W(brake)�ł����āA�����ɂ��i�܂��͗������~�߂�j�d��W(fall)�ł͂���܂���B
W(run) = (1/2) m v^2
W(brake) = Fb d = �� m d
W(fall) = Fg d = g m d
�܂��^�C���́A�H�ʂƂ̐ڐG�ʂ���]�ɂ��ω�����̂ŁA���͂ɂ���ăg���b�h�ʂ��ό`���ڒn���E�����Ă����̐ڒn�ʂֈڂ�ς�邽�߁A�X���b�v�����X�������ɂ����@�\�ł��B
�����H�ʂƂ̖��C�Ŏԗ��d�ʂ��ړ����Ă���d���ƕ\���Ă��鎖�ɁA������������������̂ł��B
�d��x�{�̉����x�́A
�� = Fb / (x m)
�����ƒ��ڂ̔��͂łȂ��u���[�L������Fb�͂��̂܂܂ŕ\���A
�d�ʑ�x�{�́A
(1/2) x m v^2 = Fb d
= x m �� d
= x m {Fb / (x m)} d
d = x m v^2 / Fb
�ƂȂ��āA�ԗ��d�ʂ��d�ʑ������Ɏc��܂��B
�܂��A�\��t���Ē�����ABS�̑���������猩�āA�Ђ����ڂ����O���Ă������[�X�����������쎞�̈��͂͂قڈ��ł��B
�܂蕽�ς���A�u�i���쎞�{�����[�X���j/2 �v�͈��ł��B
�����ԍ��F25939201
![]() 1�_
1�_
�d���́@���ʂł����ā@�d�͉����x����Ȃ�
ABS�͓����C�W���̂悤�Ɂ@�Ö��C�W����������i�^�C���̃X���b�v���ŏ��ɂ���j
���̂悤�Ŗ��ł͂Ȃ��@�����̔����ł��B
�����ԍ��F25939232
![]() 0�_
0�_
������ā[�ƁA����ς�G�l���M�[�Œǂ��ƁA����ς肍�ɔ�Ⴕ�Đ��������͐L�т���Ă��Ƃł����ˁH
�����ԍ��F25939234
![]() 0�_
0�_
���Ă�D�_�Ńp�j�b�N�u���[�L(�}�u���[�L)���V�X�e�������m�����A�_�Ő����͈͂��
��(���̎Ԃ̎��u���[�L���̍ő吧����)�ƂȂ�A���̐����͂Ń��b�N��h��ABS������
���Ƃ����C���[�W�ŁA��Ԑl���̈Ⴂ�ɂ͊W�Ȃ������͂�C�̂܂܂���Ȃ����Ȃ��āB
�����ǂނƁA�i�C�g�G���W�F������̍l����ABS�́A�u�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ń��b�N��h���悤�ɓ����v�Ƃ��ǂݎ��܂��B
ABS����ׂ̍����H�v�͈�U�u���Ă����āA�����̓^�C���̉�]���Z���T�[�Ō��Ă��āA�}���ɉ�]��������������u���[�L����߂�v�ł��B���b�N�������͂���ɋ߂���Ԃ����o���ꂽ�爳����߂�̂ł����āA�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ŏ�߂��ł͂���܂���B
�����ԍ��F25939255
![]() 3�_
3�_
��cbr_600f����
�G�l���M�[�Ŕ�r����ƁA
�d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A
�y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B
�Ƃ����ABS�ׂ̍�������͒u���Ƃ��āAA>B�Ȃ���A�ő吧���͂����Ȃ��~���Ԃ̒��Z�Ő��������̕ω����o�邯�ǁA�ő吧���͂��ω�����Ȃ�A�d�ʕω��ɂ��A���������̕ω����P���ł͂Ȃ��悤�ȁB
�����ԍ��F25939310�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937527
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937541
���傤���Ȃ��ȁ[�[ �������킹���邩
�Ȃ��d�͉����x�͂��Ƃ���
��P
�k�P*��*�l�����P�^�Q*�l*V*V
�k�P���P�^�Q*�l*V*V/�i��*�l���j���P�^�Q*V*V/�i��*���j
��Q
�k�Q*��*�Q�l�����P�^�Q*�Q�l*V*V
�k�Q���P�^�Q*�Q�l*V*V/�i��*�Q�l���j���P�^�Q*V*V/�i��*���j
�̗��K���Q��܂���
��S
�k�S*�ʁf*�l�����P�^�Q*�l*V*V
�k�S���P�^�Q*�l*V*V/�i�ʁf*�l���j���P�^�Q*V*V/�i�ʁf*���j
��T
�k�T*�ʁf*�Q�l�����P�^�Q*�Q�l*V*V
�k�T���P�^�Q*�Q�l*V*V/�i�ʁf*�Q�l���j���P�^�Q*V*V/�i�ʁf*���j
�k�P���k�Q�@�k�S���k�T
���@�H�ʖ��C�W�����{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�ԗ��d�ʑ����ɂ�銊�������̕ω��͂Ȃ�
�����ԍ��F25939341
![]() 0�_
0�_
��R
�k�R*��*�������P�^�Q*�i�l�{���j*V*V
�k�R���P�^�Q*�i�l�{���j*V*V�^��*����
�@�@���P�^�Q*V*V�i�i�l�{���j�^���j�^��*��
�����萧�����u�̔\�͂��{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�ԗ��d�ʑ����ɂ�芊�������͑�������
�����ԍ��F25939342
![]() 0�_
0�_
���G�����J����
Fb = ��b�EB�ES
�̎���ő�l��
Fb(max) = (R / r)�EFt
�ł��B
Fb > (R / r)�EFt
�ɂȂ�^�C�������b�N����Ƃ������Ƃł��B
����A�^�C�����~�܂��Ă����
Ft(stop) = ��t�Em�Eg
�ƂȂ邱�Ƃ͖����ł����A�^�C�����]�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H
���������悤�ȃ^�C���̕ό`�ɂ���Ď~�܂��Ă��鎞�Ɖ���Ă��鎞�ƂŃ^�C���ƒn�ʂ̐ڐG�ʐς��Ⴄ����ł����H
�e�����Ȃ��Ƃ͌����܂��A�傫���͂���܂���̂ŁA�����ł͏ȗ����č��Z������F=��N�ōl���Ă��܂��B
���C�͂͌������̐ڐG�ʐςɈˑ����Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��Ă����A����Ă��鎞�ɂ͏d�͂̉e�����Ȃ��Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂��A�����R�͂̕������ς��킯�ł�����܂���A�^�C��������Ă��鎞�̖��C�͂�
Ft(roll) = ��t�E(mg)
�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�ׂ����Ƃ���ł����A��t�Em�Eg �ł͂Ȃ��A��t�E(mg) �ƋL�ڂ��Ă���̂́Am�����ʁAg���d�͉����x�ƃo���o���ɍl����̂ł͂Ȃ��A(mg)�Ƃ����͂̑傫���Ƃ��đ����Ă�������������������ł��B
�Ƃ������ƂŁA�ő吧���͂�
Fb(max) = (R / r)�EFt(roll)
�̎��ɓ����܂�����A
R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES
�ƂȂ�킯�ł��B
��d = x m v^2 / Fb
���ƂȂ��āA�ԗ��d�ʂ��d�ʑ������Ɏc��܂��B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955#25931647
��d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�E��b�EB�ES) �c(4)
�ƂȂɂ��Ⴂ�܂����H
�d�ʂ�x�{�ɂȂ�A�ő吧���͂�
R�E��t�Ex�E(mg) = r�E��b�Ex�EB�ES
�ƂȂ邾���ł́B
���\��t���Ē�����ABS�̑���������猩�āA�Ђ����ڂ����O���Ă������[�X�����������쎞�̈��͂͂قڈ��ł��B
������͂ǂ����w���Ă���������Ă���̂�������܂���ł����B
Honda�̃O���t�͏d�ʍ���\���Ă͂��܂��B
�����ԍ��F25939399�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���G�l���M�[�Ŕ�r����ƁA
���d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A
���y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B
�G�l���M�[�Ȃ�A�u������ × �ړ������v�̐ϕ��ɂȂ�܂��B
�����͂����Ȃ�A�u������ × ���������v�ł��B
�������u�ő�v�����܂����A�u���[�L�̍ő�Ȃ̂��^�C���̍ő�Ȃ̂����A������ƒ�`���Ă��������B
�����ԍ��F25939413
![]() 0�_
0�_
�������Ƃ���
���Ȃ��̍D���Ȃ悤�ɍl���Ă���B
�������������������Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F25939420�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������Ƃ���
���Ɛ\���Ȃ����ǁA�l�ɁA���܂Ƃ�Ȃ��ŁB
���i�R���̋֎~�����̂悤�ȁB
�M���Ƌc�_�������Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F25939431�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
���̓W�J�̂Ȃ��ŁA�d�ʂ͏�����̂Ő��������ɏd�ʂ͊W�Ȃ��Ƃ������߂ŗǂ낵���̂ł��傤���H
�����ԍ��F25939438�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���܂Ƃ��Ƃ͎���ȁI�I
�Ԉ���Ă��邩��w�E���Ă��邾���ł����B
�����ԍ��F25939449
![]() 3�_
3�_
���i�C�g�G���W�F������
���d���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��A
���y���Ԃł̍ő吧���� × ��������(��~�܂ł̎���)��B
���m�Ɍ����ƁA�����Ƃ���̂��������悤�ɁA
�G�l���M�[�͐����͂Ǝ��Ԃ̊|���Z�ł͂Ȃ��A�����͂𐧓������Őϕ��������̂ɂȂ�܂��B
�d���Ԃł̍ő吧���́��y���Ԃł̍ő吧���͂ł���A�X����̒ʂ萧�������͓����ł��̂ŁA���R�G�l���M�[�͑O�҂̕����傫���Ȃ�܂��B
���Ȃ݂ɁA�����x�����x�͑O�҂̕����傫���Ȃ�A�������Ԃ͂قړ������߁A��L�̎����A���������Ƃ��� A��B �ƂȂ�܂��B
�����̓W�J�̂Ȃ��ŁA�d�ʂ͏�����̂Ő��������ɏd�ʂ͊W�Ȃ��Ƃ������߂ŗǂ낵���̂ł��傤���H
�͂��B�����ł��B
�����ԍ��F25939464�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�G�����J����́A
>�ԏd�̕ω��́A���������ɑ傫���e����^���܂�
use_dakaetu_saherok����́A
�d�ʕω��́A�e�����Ȃ��̂��咣�B
���[��A�l�����̃w�b�h�ł́A������܂ւ�B
�����ԍ��F25939478�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�R���̋֎~�����r�炵�̒��ɁA����̐l���ɂ��܂Ƃ��s�ׂ�����B
�����ԍ��F25939492�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���[��@�����������悤�Ƃ��Ȃ��l�́@������Ȃ�����
����܂�@�������@�Ǝv����
������������^�]�҂݂����ɂȂ�ł���
�����܂Ŏw������ӔC���Ȃ��̂��Ȃ�
������@
�ሳ�z�ǒf�M�@�̖��Ӗ����������
���f���@�̖��p�����L�߂���@���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ͑�������
�����ԍ��F25939554
![]() 2�_
2�_
�Ȃ�قǁA�t���܂Ƃ��Ǝ���Ă��܂��̂ł��ˁB�����͐l���ꂼ��ł��̂ł���͑��d�������Ǝv���܂��B
�������Ƃ��āA�����̗v��������Ƃ��́u�ł��e����������͉̂����H�v�u�����ȗ����Ċ�{�����Ƃ��邩�v�Ƃ�����͂Ȃ蔻�f�̐ςݏグ��������̂Ǝv���܂��B
���x���o�Ă����b�ł����A���̃X���̏d�ʑ��Ɛ��������Ɋւ��ẮA
�E�u���[�L���ア�͂œ���ł���Ƃ��́A�u���[�L�̖��C�͂��x�z�I�ɂȂ�̂Ő����������L�т�
�E�u���[�L�����ɒ����قǓ���ł���Ƃ��́A�^�C���̖��C�͂��x�z�I�ɂȂ�̂Ő��������͐L�тȂ�
�E�����Ɍ����A�H�ʂ̏�������d�ʔz����d�S�ʒu�A�^�C���̕ό`��ABS�̓���Ȃǂ����G�ɗ���Ō��ʂɕω���������\��������
�Ƃ������Ƃ��Ǝv���̂ł����A���������Ȃ��ň���I�Ɂu���̎�������v�Ȃǂƒf�����Ă��܂��̂͂�����ƕs�e�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ͎v���܂��B
�����ԍ��F25939672
![]() 3�_
3�_
���Ԃ�A�ŏ��ɁA�������������A�Ƃ��A�^���G�l���M�[�����������Ə�����`���āA�W�J������E�E�E
�P���������Ƃ��A�ŏI�I�ɁE�E�E
�u���[�L�p�b�h���f�B�X�N�������͂ƁA�^�C�����n�ʂ������͂��A���W�Ƃ��Ďc��E�E�E
����������E�E�E���Č����܂���
���x���Ⴍ�āA���݂܂���E�E�E
�����ԍ��F25939971�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������߂悤�Ǝv�������ǁA���ƈ���A�l�̍l���ĕ��������܂��B
�}�̐����ł��B
�}1�̂悤�ɒʏ�̃u���[�L�ł�B�_�Ő����͍͂ő��A�ƂȂ�A���ł��ɂȂ�܂��B
�}�����ł́A�ő吧����A����ABS�̓���ƂȂ�}2�A3�̂悤�ɂȂ�A�m�R�M���g�̃g�b�v(�ő吧����)�͏d�ʕω��ł͕ς�炸�A �u���[�L���Ԃ�C�AD�̂悤�ɁA�ς��낤�ƁB
����ŁA���̃u���[�L���Ԃ̐ώZ���A�ԏd�ω��ɂ���ĕω�������A�����������ω����邾�낤�ƁB
���ꂪ�ŏ����猾�������������ƁB
�����ԍ��F25940082�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��U
����M�̗��z�I���R��Ԃ�
���ʃu���[�L���������Ă���@���C�W����
�A�[����P�F�P�̃��o�[�ł����̗͂ʃu���[�L�Ɉ��͂���������̂Ƃ���
���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��
���������@L6�����߂�
��V
����M�̗��z�I���R��Ԃ�
�g���b�R���u���[�L������������@���C�W����
�A�[����P�F�P�̃��o�[�ł����̗͂��g���b�R���u���[�L�Ɉ��͂���������̂Ƃ���
���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��
���������@L�V�����߂�
��W
���ʁiM-���j�̗��z�I���R��Ԃ�
�R�Œ������ꂽ���ʂ��̕��̂��ԑ̂̉��ɂ���
���ʓ����C�W���ʁ@�d�͉����x�͂��Ƃ���
���R��Ԃɏ���V��^�����ꍇ��
���������@L�W�����߂�
�����ԍ��F25940138
![]() 0�_
0�_
����ɂ��Ắ@�z���_�̎����������ł��傤
�ʏ�ABS�u���[�L�����̐}�ł�
�E�̐}�͎ԏd���d���ꍇ�Ł@
�}�X�^�[�o�b�N���̔{�͑��u���D�G�ȏꍇ�i�H�ʃʂ��{�g���l�b�N�ɂȂ�ꍇ�j
�������̐}���d�ʑ����������c�ɉ�����
�ԑ̂̑��x�ቺ�̌����x�́@�قړ����ɂȂ�܂�
�����̗����オ�蕔���͌����ɂ͓����ł͂���܂���
�茸�����n�܂�����Ԃł̌����x�͓����Ƃ����Ӗ��ł�
�����ԍ��F25940151
![]() 2�_
2�_
���Ȃ݂Ɂ@�t�[���h�����オ��������@ABS���쓮����̂ł͂Ȃ�
�ԗւ̑��x���O�i���m�ɂ͊p�����x���X���b�v�w�K�l������j
�ɂȂ������Ƃɂ��ABS�͍쓮���܂�
�ԗ��d�ʂ��y���ꍇ�Əd���ꍇ
�t�[���h���͈���Ă��܂�
�����ԍ��F25940162
![]() 1�_
1�_
���Ȃ݂Ɂ@�X����ʂ��ā@�݂Ȃ���@�u���[�L�̓��ݎn�߂��[�[�[
�ƍl���Ă���܂���
�c�_�̖ړI�͊��������ł��̂�
�ɒ[�Șb�@����V�@�̏�Ԃ���@
���łɃu���[�L���������Ă���@�Ƃ��Ė�肠��܂���B
�����̋����͂S�ււ̕����i�I���t�F�X�j�����Ƃ�₱�����Ȃ�܂�
�����ԍ��F25940166
![]() 1�_
1�_
���߂�@ABS�����\���m�C�h�̔\�͂܂ŏc�ɉ������Ⴂ����̂�
�������͍��̖����������Ԃ����ق��������ł���
�����ԍ��F25940183
![]() 2�_
2�_
���Ђ�N�Ђ�N����
���x�����킩�����C�����Ă����A���肪�Ƃ��B
�l�̐}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu���ԏd�ɂ���ĕς��Ƃ������Ƃł��ˁB
������}�u���[�L�����A�d���ɂ���ĈقȂ�L�����p�[�t����ABS�����삷��Ƃ������ƂˁB
�ŁA�d���ɊW�Ȃ���������������Ƃ������Ƃ́A���_�I�ɂ́A�}�������A�d���ɊW�Ȃ����������͓����Ƃ������Ƃł��傤���ˁB
�����ԍ��F25940222�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
������ŁA���̃u���[�L���Ԃ̐ώZ���A�ԏd�ω��ɂ���ĕω�������A�����������ω����邾�낤�ƁB
C�̘a�AD�̘a���������Ԃł͂Ȃ��A�ԗ�����~����܂Łi�O���t�̒[����[�܂Łj�̎��Ԃ��������Ԃł��B
����܂Ő������Ă����O������ɂ����ẮA�ԏd���ω����Ă������������ω����Ȃ��̂Ɠ����悤�ɁA�ԏd���ω����Ă��������Ԃ͂قƂ�Ǖω����܂���B
����A�����G�l���M�[�ōl���Ă݂܂��B
�G�l���M�[�͎��Ԑϕ��ł͂Ȃ������ϕ��ł��̂ŁA�{���͉����ɋ����A�c���ɗ͂̃O���t�ōl����ׂ��ł����A���������Ԃł��C���[�W�͂ł��܂��B
C�̕����̖ʐς����AD�̕����̖ʐς����̘a�������G�l���M�[�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�}-2�A�}-3�̐��}��艺�̕������ׂĂ̖ʐς������G�l���M�[�ɂȂ�܂��B
�����āA�}-3��A�͐}-2��A��荂���ʒu�ɂȂ�܂��B
�i�ԏd��������A�^�C�������b�N���鐡�O�̃u���[�L���͑傫���Ȃ�j
��������ƁA�}-2�̖ʐς��A�}-3�̖ʐς̕����傫���Ȃ�܂��B
����͌y���Ԃ��d���Ԃ̕����傫�Ȑ����G�l���M�[��K�v�Ƃ��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B
�������������ł����Ă��A���傫�������͂���������A���傫�������G�l���M�[��������
�Ƃ������܂����A
�������������ŁA���傫�������G�l���M�[�邽�߂ɂ́A���傫�������͂��K�v
�Ƃ������܂����A
���傫�������͂���������A���傫�������G�l���M�[�������邽�߁A�����������ɂ��邱�Ƃ��\
�Ƃ������܂��B
�����ԍ��F25940223�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���͂����ƁA
�G�����J����E�R�s�^�X�t�O����E�R�}���^���u�u�u�[���炲�w�E���������Ă���
�w�����͂͂ǂ��ւ������x
���C�ɂȂ��Ă����̂ŁA���߂ĉ^����������W�J���Ă݂܂����B
���ʁA
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955#25931647
��d = v0^2 / (2�E��t�Eg) �c(9')
������̎��͕ς��܂���ł������A
��d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�E��b�EB�ES) �c(4)
������̎��͊Ԉ���Ă���܂����B
�������ɃX�}�z�ŏ����ɂ͌��E�������̂ŁA�摜�œY�t���܂��B
���낢��ƌ������@��ƂȂ�A�X�����Ă��ėǂ������ł��B
���w�E���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25940247�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
����O�i���߂łƂ��������܂�
> �l�̐}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu���ԏd�ɂ���ĕς��Ƃ������Ƃł��ˁB
ABS�̂Ȃ��w�}1�̓��ł��ɂȂ�ʒu�x�Ƃ͉��ł��傤���H
�u���[�L�ޗ͂𑝂₵�Ă��p�b�h�����t���͂�����ȏ�͏オ��Ȃ������[�t�o���u�I�Ȃ��̂����邩�̂悤�ȓ���ł����A
���̂悤�ȋ@�\�͎��ۂɂ͂Ȃ��A�K�v������܂���
�����ԍ��F25940256
![]() 0�_
0�_
�ԏd�ɉ������@���ł������������Ƃ����̂́@���̂��Ƃł��B
ABS�n�C�h�����j�b�g���ɂ͌����\���m�C�h������܂��B
�����ԍ��F25940270
![]() 1�_
1�_
���Ђ�N�Ђ�N����
���������ʂ�ł��B
���̐}�ŗǂ��킩��܂��B
�����ԍ��F25940302�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
ABS�́@���炭
�����I�����[�t�o���u�ł͎����ł��Ȃ��@���ł����Ȃ������ł�����
�ԑ��Z���T�[��ABS-ECU���Z���j�b�g�ɂ�錸���o���u�������Ƃ���
�L����ʂɗp������@�\�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F25940315
![]() 0�_
0�_
�z���_����
�u�c�_�̖ړI�͊��������ł��̂�
�@�ɒ[�Șb�@����V�@�̏�Ԃ���@
�@���łɃu���[�L���������Ă���@�Ƃ��Ė�肠��܂���B�v
���@���i�O�O�G�j
�����ԍ��F25940341
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�����͂Ə����ƃ^�C���̖��C�͍��݂ɂȂ��č�������̂ŁA�u���[�L�̖��C�͂Ə����܂����B
���������Ńu���[�L���|����������łȂ���A�}�u���[�L���ɕ��M�̌��E�]�X�͍l���Ȃ��Ă����̂��Ǝv���܂��B
���ɋ������߂y�_�����o�[�����Ȃ�����z�[�X���c��肵�āA�}�̂悤�Ȕ���`�ȓ����ɂȂ�A�Ō�͏��ɒ����Ă���ȏ㓥�߂Ȃ��Ȃ��ł����A���Ȃ��Ƃ��^�C���̖��C�͂���Ƃ���܂ł͖O�a�Ȃǂ����ɏオ���ł��B
�����ԍ��F25940381
![]() 0�_
0�_
���A�l�ŁA�X�b�L�����܂����B
�F���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F25940387�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���Ђ�N�Ђ�N����
�}�P��ABS�Ȃ��Ƃ����ݒ�Ȃ�ł�����
����Ƃ��납���̓u���[�L�y�_���������瓥��ł��p�b�h�����t���͂������Ȃ��Ƃ���
�ł�cbr_600f�����܂��t�H���[���Ă��������ĕ��������ꂽ�悤�Ȃ̂ŁA�����ǂ��Ƃ��܂��傤
�����ԍ��F25940542
![]() 0�_
0�_
�����������ʂ�ł��B
�����̐}�ŗǂ��킩��܂��B
���{�l���@�}�P����@�Q�C�R�֓W�J�����ł�
�����F�߂��Ă���̂�
�@�u�}�P���v�@�ɍS���ă}�E���g��邱�Ɓ@�K�v�ł����H
�����ԍ��F25940550
![]() 0�_
0�_
> ���{�l���@�}�P����@�Q�C�R�֓W�J�����ł�
> �����F�߂��Ă���̂�
�͂��A���{�l�̌���͉������Ă�̂ł�����ł���
> �u�}�P���v�@�ɍS���ă}�E���g��邱�Ɓ@�K�v�ł����H
�i�C�g�G���W�F������ւ̃}�E���g�͂������܂���
�����A�Ђ�N�Ђ�N����̂킽�����̎���ɑ����������߂��w�E���Ă����������������ł�
�����ԍ��F25940635
![]() 0�_
0�_
����́@���Ȃ����@�����̐^�ӂ�ǂ݂Ƃ�ĂȂ�����ł͂���܂���
���́@����Ȓp���炵�ȓ��e���w�E���Ȃ��Ă������悤��
�i�C�g�G���W�F������@�ɍčl�@�𑣂��܂�����
��������Ɏw�E���Ă������������Ȃ�@�w�E���Ă����܂��傤�B
�����ԍ��F25940642
![]() 0�_
0�_
�@��use_dakaetu_saherok����
���^�C�����]�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��̂͂Ȃ��ł��傤���H
�v���Ă��Ȃ��̂́Ause_dakaetu_saherok����̕��ł���B
��Ft(stop) = ��t�Em�Eg
�����use_dakaetu_saherok����̍l����\�������̂ł���A�d�͉����x�Ɩ��C���g�p���Ă��鎞�_�ŁA�^�C���͉�]�������C����������Ĉړ����Ă���O��̍l���ƂȂ��Ă��܂��B
�������R�͂̕������ς��킯�ł�����܂���A�^�C��������Ă��鎞�̖��C�͂�
��Ft(roll) = ��t�E(mg)
���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�^�C���̉�]�͂Əd�͂ɂ�門�C�Ƃ́A�S�R�ʂ̂��̂ł��B
���C�Œ�~�����Ă���̂ł͂Ȃ��A���C�͒P�ɗ͂̓`�B�Ɏg�p����Ă��邾���ł��B
�܂�A�g���R���Ƃ�CVT�Ƃ��Ɠ����ł��B
���̋@�\�̎d���̌��̓G���W���Ȃ̂ŁA����Ɠ����l���ƂȂ�A�����Ɏg�p�����d���̋@�\�̓u���[�L�ł��B
�����`�B����̂��^�C���ł����āA�H�ʖ��C������ɉe�����A���C���傫����u���[�L�̎d���͓I�m�ɐ����֗��p����A���C���Ⴏ��X���b�v����Ƃ����������ł��B
�܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B
���̕⊮��������G�l���M�[�Ƃ��Ă��邩�炱���A���ƂȂ�̂ł��B
�����ԍ��F25940768
![]() 1�_
1�_
�����l����\��������
���W�J�͌ÓT�����w�����������̂Ŏv�z�ł͂���܂���B
�����d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ�����
�d��[J]����[N]×�ړ�����[m]���Ă킩���Ă܂���
ABS��
�^�C���̉�]�����o��i����
�^�C���ƘH�ʂ̐Î~���C�W��������X���b�v�������o��i��
����������i�Ɩ�����[��i��p���邱�Ƃɂ��
��X���b�v��Ԃ��@�������Ԃɂ킽���Ĉێ�����
�����̓R���g���[�����u�ł��B
�ȑO�͖��@���O�~�Ǝv��ꂽ�Z�p�ł͂���܂���
���݂ł́@�Î~���C�W�����C�W���̂悤�Ɉ�����
��ʓI�Z�p�ł��B
�i�n���h��������ꍇ�@�����͂ƃR�[�i�����O�t�H�[�X�̃x�N�g���a�ƂȂ�j
�����ԍ��F25940795
![]() 1�_
1�_
�����C�Œ�~�����Ă���̂ł͂Ȃ��A���C�͒P�ɗ͂̓`�B�Ɏg�p����Ă��邾���ł��B
�͂��B
����͂��̒ʂ肾�Ǝv���܂����A���̑傫���� ��t�E(mg) �łȂ���Ή����Ƃ��������̂ł��傤���H
�]���钼�O�܂ł� ��t�E(mg) �ł��邱�Ƃ͓��ӂ��������܂���ˁH
�]����n�߂��r�[�ɂ����ł͂Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł����H
A�Ƃ����͂C�œ`�B�����͂�B�Ƃ���Ȃ�AB=��A �ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
���[�X�p�^�C���̂悤�ɔS���͂ŃO���b�v���Ă���悤�Ȏ���ł����Ă��A�d�Ԃ̂悤�ȓS�̎ԗւł����Ă��A���b�N���Ԃ̏��]����s�j�I�����Ԃł����Ă��A �_�E���t�H�[�X�̂悤�Ȏ��d�ȏ�ɉ����t����͂��Ȃ����� ��t�E(mg) �ł��邱�Ƃɕς��Ȃ��ł��傤�B
���܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B
�����̕⊮��������G�l���M�[�Ƃ��Ă��邩�炱���A���ƂȂ�̂ł��B
�����͂Ɛ����͂̊W��Fig. E��(8)���ɋL�ڂ��܂����B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25938419#25940247
�����͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��������̂ł���G�����J����̂��l���ɂȂ�W�����Ă��������B
�����ԍ��F25940834�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���G�����J����
���܂�d���݂̒荇���́A�����͂Ɛ����͂ł����āA�H�ʖ��C��d�͉����x�͕⊮�����ƂȂ�܂��B
�t���u���[�L�̐����͂����߂�Ƃ��ɁA�H�ʖ��C�Əd�͉����x���W���Ă��܂��B
�^�C�����X���b�v�����ɉ�]���Ă��鎞�́A�^�C���͎d�������Ă��Ȃ��̂ŃG�l���M�[������܂���B
�^�C�������b�N���ăX���b�v���Ă��鎞�́A�^�C���͓����C�͂ɉ������G�l���M�[������܂��B
�^�C�����X���b�v���Ȃ��M���M���̂Ƃ��������͂̍ő�l�ł����A�^�C���͎d�����Ȃ��̂ŃG�l���M�[������܂���B
�������A���̐����͂́A�^�C������]�����Î~���Ă���Ƃ��̐Ö��C�́i��t�Em�Eg�j�ɓ������̂ł��B
�����ԍ��F25940951
![]() 0�_
0�_
ABS�Ȃ��̎ԂŁA�^�C���������b�N���Ă��܂��A�u���[�L�̖��C�ŏ���Ă����G�l���M�[���A����Ƀ^�C���ƘH�ʂ̊Ԃŏ������ł���ˁB�^�C���͐₦�������Ă��āA�u���[�L�̓���ɉ����Ďd���������Ă���Ǝv���̂ł����B
�ǂ�ȍ����\�ȃu���[�L���g�����Ƃ���Ń^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂��鐧���͓͂����Ȃ���ŁA�}�u���[�L���̐��������̘b��ɑ��āA�^�C���̖��C�͂���ł͂Ȃ��⊮�����Ƃ��A���ƒf�����Ă��܂�������قǁu�v�z�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F25940963
![]() 0�_
0�_
�v���������ǁA�����͂Ɠ��������͂ŎԂ��~�܂�Ƃ�����A
�d���Ԃ̊����͂�FA�A�d����MA�A
�y���Ԃ̊����͂�FB�A�d����MB�A
�����x����(m/s2)�Ƃ����
FA��MA��
FB��MB��
�ƂȂ蓯�����x�̔�r�Ȃ烿�͓����Ȃ̂Ŋ����͂́A�P�ɏd���ɔ�Ⴕ���l�ƂȂ�A���̊����͂Ɠ��������͂Ŏ~�߂���̂ł́B
�ŁA���ǁAFA�AFB�A����قǂ̓��ł�(�ő吧����)�Ȃ̂��Ȃ��āB
�����ԍ��F25940968�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����@ABS���ԗ���T���̂��������
�Î~���C�W���@�Ɓ@�����C�W�������藐����
�݂Ȃ�������̂ł��傤��
�Î~�܂ł̊����������ÓT�͊w�ŋ��߂�̂�
�������܂���
�����ǂ̑��x�܂ŋ�����邩��
���a�ƐÎ~���C�W���ŕ\���v�Z�ł�
�ԗ��d�ʂ�M�������܂��B
���̂��Ƃ𗝉��ł����
�����ł�M�������邱�Ƃ������ł����Ȃ��ł�����
�����ԍ��F25941001
![]() 0�_
0�_
�����͂������̂́@�ϑ��҂����n�ɂ���ꍇ�ł�
�����ԍ��F25941006
![]() 0�_
0�_
�Î~���C�W���ʁ@�d�͉����x��
�ő�R�[�i�����O�t�H�[�X�@�ʂ���
���S��F�@���@������/��
������/�����ʂ���
�������[�g�i�ʂ����j
����ā@�ő���x�́@�ԗ��d�ʂɂ͉e������Ȃ�
�����ԍ��F25941011
![]() 0�_
0�_
���ό`�����Ȃ�@���̌���i�A�v���[�`�j���l�����ق��������ł��傤
����V�ʼn����o�������@ABS��������������Ԃ��@L�@����������̂Ƃ���
���̏ꍇ�@�����Ԃ���A�������ꍇ������������^�����ꍇ
��͂�@�����́@�k�@�ƂȂ�
����̓^�C���̐������Ⴄ�����ʓ�{�̑�Ԃ��������ʼn����o�����ƂƓ����ł���
�����ԍ��F25941015
![]() 0�_
0�_
�����������
������
���̂��j���[�g���̉^���������ɏ]���ĉ^������̂́A���̕��̂������n���猩���ꍇ�����ł���B�ϑ��҂����n�ɂ���ꍇ�A���Ȃ킿�ϑ��҂������n�ɑ��ĉ����������͉�]�������͂��̗��������Ă���ꍇ�ɂ́A�����n����ϑ������ꍇ�Ɍ�����͂̑��ɁA�ϑ��҂̉^���Ɉˑ��������|����̗͂������B���̌��|���̗́i�p: fictitious force�j�������́i�p: inertial force�j�Ƃ���
�����ԍ��F25941031
![]() 0�_
0�_
���[��@�����@
�u�d�����̂�ς�ł���Ǝ��@��@�J�̓��@�͋C�����悤�ˁB�v
�Ł@������Ȃ�����
���W�J�Ɋ��ꂽ�l�́@���ϓI�ȓ��e�Ƃɍ��ق������Ă�
�u���͐���������v�@�Ɓ@���ʂ�����邪
���W�J�Ɋ���ĂȂ��l��
���������@���̐��m����M���ĂȂ��悤�Ɂ@�v���܂��B
�i���ł͐�������Ȃ��j
����͐����O�̉^���G�l���M��
�d���Ɋ����邾���̊ȒP�ȓ����Ȃ킯��
���̎����o���Ȃ���������Ƃ����āA
�^���ʁ@�Ƃ��@�����́@�Ɓ@���������̂�
����ɂȂ��ĒT���l������Ȃ�ā@
���́@�z�������ĂȂ��������Ƃ��m��ā@�������납�����ł��B
ABS�́@�Ƃ��@�p�b�h�̖ʁ@�Ƃ��@�^�C���̃^���~�@�Ƃ�
�{���͖������Ċȗ�����������b��
�@��N�����ā@�����Ł@��蕶�G�ɂ��Ă������̂Ȃ�ł��ˁ@
�ŋc�_�̖{�����������Ă����B
�����ԍ��F25941120
![]() 0�_
0�_
������Ə�̂ق��ŁA�Ђ�N�Ђ�N���A�b�v���ꂽ�A�����͂Ǝ��Ԃ̃O���t�ŁA�d���̈Ⴄ��̐����͂�ABS�V�X�e���̌����ɂ�肻�ꂼ��s�[�N�����͂����Ȃ��Ȃ��Ă邯�ǁA���̏��Ȃ��Ȃ�����d�������A�y�������A�قړ������Ƃ�����A�d���̈Ⴂ�ł̃^�C���̖��C�͊W�Ȃ���������Ȃ��悤�ȁB
�����ԍ��F25941152�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�������@�ԗ����d�ʂ��@�Q�{�Ƃ��@�R�{�ɂȂ��
�u�����[�����@�����@�P���Ɉ����L�������v�Ƃ͎����v���܂���B
��Ԓ���͈͂��炢�̑����́@���W�J��M��������@�Ǝv���Ă����̂ł��傤�B
�z���_��new-ABS�̐����ɂ́@
�u�����[���x�@�����[�����@�̃O���t�v���K�������K�v�Ƃ͎v���܂���
�����Ǝҁi�ԗ��vABS�S���j�ł�
�c�_��s�����ɂ�
�u�����[���x�@�����[�����@�̃O���t�v���K�{�ł���Ǝv���Ă���̂ł��傤�B
�@
�����ԍ��F25941167
![]() 1�_
1�_
>������Ə�̂ق��ŁA�Ђ�N�Ђ�N���A�b�v���ꂽ�A�����͂Ǝ��Ԃ̃O���t�ŁA�d���̈Ⴄ��̐����͂�ABS�V�X�e���̌����ɂ�肻�ꂼ��s�[�N�����͂����Ȃ��Ȃ��Ă邯�ǁA���̐����͂̌����̓x�����͘H�ʂ̃ʂɂ����́A���Ƃ������Ƃ͊m���̂悤�Ɏv���B
�����ԍ��F25941531�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̎��ǂ���������G�����J����ɓ`������̂��ȂƁA�ӂƎv���o���A������������������Ă݂܂����B
���̃��[�^�[�͎ԗցA�E�̃��[�^�[�͘H�ʂ�͂��Ă��āA���E�ǂ���̃��[�^�[����]���Ă���ƍl���Ă��������B
�u���[�L��������Ƃ�������͍��̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł����A�����Ƃ����͉̂E�̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł��B
���̃��[�^�[��N�Ƃ����͂ʼnE�̃��[�^�[�ɉ����t�����Ă���Ƃ��A�E�̃��[�^�[���~�߂�����ɓ����͂̍ő�l�̓�N�ƂȂ�܂��B
�i�ʁF���[�^�[�Ԃ̖��C�W���j
����܂ł̐����ł́A���̍ő�l���ő吧���͂ƌ����Ă��܂��B
�������͂ō��̃��[�^�[�Ƀu���[�L��������ƁA���̃��[�^�[�͎~�܂�܂����A�E�̃��[�^�[�͊����Ă��炭��葱���܂��B
���ꂪ�^�C�������b�N����Ƃ�����Ԃł��B
�d�͂����邽�߂Ƀ��[�^�[�����ɂȂ�ׂ܂������A���[�^�[�������t����͂����d�݂̂ł���A�ő吧���͂̓ʁE(mg)�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F25964117�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
���̍����i�쓮���j�̐}�̕��͕�����܂����A�������̕���������ƁB
�}�������e�[�}�ł����琧�����͋쓮�͖͂����i���ۂɂ̓A�C�h�����O���������邩������Ȃ����ǁA���̍ۂ͖����Ƃ��āj�̂ŁA�}�������|�������_�Ŋ����œ����Ă���Ԃ��ǂ̂悤�Ɏ~�߂�̂��Ƃ������Ƃł���ˁB
�ŁA�l�����Ƃ��āA�}�������������_�̉^���G�l���M�[ �A�P/�Q���u2�̔M�ʂ��u���[�L�p�b�h�ƃu���[�L���[�^�[�̊Ԃ̖��C�M�ŏ�������Ƃ������ƂŁA
�P�A�p�b�h�̃��[�^�[�ւ̉�������
�Q�A���[�^�[�̉�]���y�ю��ʁi�Ԃ̊����͂̂悤�Ȃ��́j
�R�A�p�b�h�̖��C�W��
�S�A�p�b�h�̃��[�^�[�Ƃ̐ڐG�ʐ�
�Ȃǂ����ƂɃu���[�L�p�b�h�ƃ��[�^�[�Ƃ̖��C�M���ǂ����Œǂ��ق���������Ղ��悤�ȁB
�ŁA�p�b�h�̉������͂��������ă��[�^�[���~�߂Ă��܂������̓��b�N���Ă�̂Ńu���[�L�̖��C�͂̓[���Ȃ̂Ńu���[�L�͌����Ȃ��āA���b�N���̐����͂̓^�C���ƘH�ʂ̖��C�݂̂Ƃ������Ƃł���ˁB
���Ƃ����Ď����ɂ͕��G�ōׂ����v�Z�͂ł��܂��ǁB
�����ԍ��F25964245
![]() 0�_
0�_
�u���[�L�p�b�h�̏d�S�ɑ���@���a�����́@�Œ�Ȃ̂Ł@�����̃^�C�����a�Ƃ̉�]�䗦�͕ω����܂���
���a�䗦���܂߂ā@�ϐ���'�Ƃ��ā@�܂Ƃ߂Čv�Z(��������)�̂���ԊȒP�ł���
�����ԍ��F25964273
![]() 0�_
0�_
���u���[�L��������Ƃ�������͍��̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^���ł����A�����Ƃ����͉̂E�̃��[�^�[���~�߂悤�Ƃ���^��
�����͂�����킷�̂ɏd�͉����x���܂܂�邱�Ƃ����������������Ȃ������̂ŁA�����̐��������̂��߂ɍ�����͎��}�ł��B
������u���[�L�̃ʂ�����킵���͎��}�͂�����B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25938419#25940247
�����ԍ��F25964498�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���Ƌ}�������̘H�ʂƃ^�C���̖��C�M�����ǁA
1�A�^�C�������b�N���Ă鎞�̓u���[�L�M�͔��������A�����͂Ƃ��Ă̓^�C���X���b�v�ɂ��H�ʂƃ^�C���̖��C�M�̂݁B
2�A�u���[�L�������ău���[�L�����M���Ă��錸�����́A�^�C���͉�]���Ă�̂ŁA�^�C���O���b�v��������������Ă���A�قڃX���b�v�͖����̂ŁA�^�C���ƘH�ʂ̖��C�M�́A�قڔ��������B
�Ƃ���A
�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA���������Ƃ��~�܂�܂ł̐������ԂƂ��ɂ́A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂͊W�Ȃ��悤�ɂ��v���܂��ˁB
�����ԍ��F25965110�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ł��B
>�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA���������Ƃ��~�܂�܂ł̐������ԂƂ��ɂ́A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂͊W�Ȃ��悤�ɂ��v���܂��ˁB
�ԈႢ�܂����A����͊W����܂��ˁB
�}�����ł�ABS�̓����Ń^�C�����b�N�́A�قږ����̂ŁA�Ԃ��~�߂邽�߂̐����͂̓u���[�L���M�����ƂȂ�A�H�ʂƃ^�C���̖��C�͊W�Ȃ��悤�Ɏv���܂��ˁB
�ł����B
���炵�܂����B
�����ԍ��F25965120�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��cbr_600f����
>ABS����ׂ̍����H�v�͈�U�u���Ă����āA�����̓^�C���̉�]���Z���T�[�Ō��Ă��āA�}���ɉ�]��������������u���[�L����߂�v�ł��B���b�N�������͂���ɋ߂���Ԃ����o���ꂽ�爳����߂�̂ł����āA�u���[�L�̖��C�͂��ő�ɂȂ�t�߂Ŏ�߂��ł͂���܂���B
�����ł��ˁAABS���쒆�́A�Z���T�[���Ԃ̈ړ����x�ƃ^�C����]�����r���āA���x�ɑ���^�C����]����������Ƃł��s���Ƃ݂�A�X���b�v�������Ă�(���b�N�������Ă�)�Ɣ��f���Ĉ�����߂��ł��傤�ˁB
�ŁA���x�ƃ^�C����]������v������܂��������߂�B
���̌J��Ԃ���f��������Ă����ł��傤�ˁB
�ł�����ABS�͎����I�Ƀ��b�N���O�̍ő吧����(�u���[�L�̍ő喀�C��)�ɂȂ�悤�ȃu���[�L��������Ă���Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB
�����ԍ��F25966932�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�����ԁi�{�́j�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2025/11/18 0:38:32 | |
| 3 | 2025/11/18 0:13:26 | |
| 1 | 2025/11/17 23:31:06 | |
| 0 | 2025/11/17 22:12:41 | |
| 0 | 2025/11/17 21:34:55 | |
| 4 | 2025/11/17 21:46:09 | |
| 3 | 2025/11/18 1:04:02 | |
| 4 | 2025/11/17 22:33:39 | |
| 2 | 2025/11/17 20:54:00 | |
| 2 | 2025/11/17 21:15:37 |
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�����ԁj
�����ԁi�{�́j
�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j