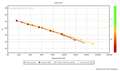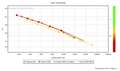�Z���JGT-Four-A�Ɛ\���܂��B
���̖��O�̒ʂ�AST185�̂��̎Ԃ�����Ȃ�������҂ł��B
���N�O����f�W�J�������������A�����́AE-30��D300���g�p���Ă��܂��B
����D300�蕥��D700�̃t���T�C�Y�Ɉڍs���āA�t�H�[�T�[�Y��
�t���T�C�Y�̃_�u���}�E���g�̐��Ɉڍs���邩�ǂ����Y��ł���܂��B
�ł��A�t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̉掿�͂ǂꂭ�炢�Ⴄ�̂ł��傤���B
����ȂɌ��I�ɈႤ�̂ł��傤���B���ꂪ���i.COM�̌f������������
���������ł����B
�ŋ߂悭�A�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�͂Q�i�Â��v�u�Â�����掿�������v
�Ƃ����咣������A����ɑ��ċc�_���������邱�Ƃ�ڂɂ��Ă���܂����A
���̎咣������Ă�����̐����͈ꌩ�����Ƃ��炵���̂ł����A���̌��ł�
���̍����������Ȃ��̂ŁA�ƂĂ������������܂��B�܂��A���̈ӌ���
�^������Ă������������݂����ł��̂ŁA�S���ԈႢ���咣����Ă���
��ł��Ȃ��̂ł��傤�B���̕��X�̐����͎��̂悤�ȌÂ��Ԃ�����Ċy�����
����悤�Ȃ��₶�ɂ͑S��������܂���B�ނ��딽�_����Ă�����̐�
�̕��������o����l�Ɋ����Ă��܂��B
���̕��X�̎咣�ł̓t�H�[�T�[�Y�����łȂ��AFX�t�H�[�}�b�g�̃����Y��
DX�t�H�[�}�b�g�̃J�����ɑ�������ƈÂ��掿�������Ȃ鎖�ɂȂ�悤�ŁA
�����{���Ȃ獂���������o����FX�t�H�[�}�b�g�̃����Y���w������DX�t�H�[
�}�b�g�̃J�����𗘗p���Ă���NikonD300���[�U�́ANikon�ɊŔɋU�肠���
���������Ȃ�܂��B����́A�����ł��܂��A�����牽�ł����{�̉�Ђ�
����Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�Ǝv���̂ł����ǂ����Ă��D�ɗ����܂���B
���̎咣�͖{���Ȃ̂ł��傤���B�ł���߂��Ƃ������������̂ł����A
���_����Ă��咣���J��Ԃ����̂́A�P�Ȃ�l�K�e�B�u�L�����y�[���ł�
�����A��������������悤�ɂ��v���Ă��܂��B���̘b��́A������������
�̂ł��̂悤�ȃX���b�h�𗧂��グ�邱�Ƃ��S�O�����̂ł����A�ނ���
���̔Ŏv�������c�_���Ă��������Č��\�ł��̂Łu�t�H�[�T�[�Y��
DX�t�H�[�}�b�g�AEF-S�t�H�[�}�b�g�̃����Y�����i�Â��v���R�m��
���Ă��������Ȃ��ł��傤���B
�����A�c�_�����Ƃ��́A�����Y�̓����Ɍ��肵�ĉ������B�t�H�[�}�b�g��
�ʐς̘b���ɂ͉�p�����߂�Ƃ��ɐG���K�v������悤�ł����A����
���Ȃ��Ă��m�C�Y���S���������Ȃ����z�I�ȎB���f�q�Ƃ����O��ł��˂���
���܂��B�����ɁA�B���f�q�̓�������V���b�g�m�C�Y�̘b�����o�Ă����
�c�_���������邾���ł��B�������l���Ȃ��̂ł���A�����Y�͈Â��Ȃ�Ȃ��A
�掿�������Ȃ�킯�ł͂Ȃ��Ƃ������_�ł��ǂ��Ǝv���܂��B�ǂ����Ă��f�q
�̓��������l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̗��R���͂�����ƋL�q���Ă���
����Ə�����܂��B
�����c�_�����M��������ƁA����I�Ȉӌ�����ь������Ǝv���܂���
��l�̑Ή��ŗ�Âɋc�_�����肢���܂��B
�܂��A����܂ŎU�X�c�_�������Ă܂����Ă�K�v������̂��Ƃ�������
�����鎖�Ƒ����܂��B�����A���̋c�_�����̃X���ɏW���Α���
�X���ł̋c�_�������Ȃ邩�Ǝv���܂��̂ŁA���̃X���̈Ӗ��������
���l��������K���ł��B
�����ԍ��F10141193
![]() 7�_
7�_
�t�H�[�T�[�Y���Â��Ƃ����咣�͐������Ƃ������܂����A�����s���ł��B
��ʓI�ɂ͖��邳�Ɋւ��Ă̓t�H�[�}�b�g�ɊW�Ȃ��������邳�ł��B
���̌��ł��̔͂܂��܂����M���Ă���Ǝv���܂����A����E30�p����D700���w�����邱�Ƃ������߂��܂��B
�����}�E���g�Ń����Y�����ʂł����AD700�͎�ɍL�p�n���g���AD300�͖]���n�Ƃ��邱�ƂŁA�����Y�����̎�Ԃ̏Ȃ���@���������܂�܂��B
�����ԍ��F10141259
![]() 3�_
3�_
FX/DX/m43���g���Ă��܂����A�������������悤�ł��B�����Y�̖��邳�̓t�H�[�}�b�g�Ƃ͖��W�ł��B
�P�Ƀt�H�[�}�b�g�ɂ��B���f�q�T�C�Y���̈Ⴂ����A
�m�C�Y���閾�邳�����i���eISO�l�j������Ă��܂��Ƃ����b���Ǝv���܂��B
FX D3/D700�ł�ISO6400�܂ʼn䖝���Ďg���܂��B
���l��DX CMos�@D300/D90/D5000�ł�ISO3200�ACCD�@��D40��ISO1600�AD60/D3000��ISO800-1600�B
m43 Pana G1�ł�ISO800�Ƃ������Ƃ��낪�ꕔ���L�@����̊��z�ł��B
FX��m43�ł͎O�i���̊J���ł��B
�����ԍ��F10141349
![]() 4�_
4�_
�����n����
�����̂��L���������܂��B
��͂蕁�ʂɍl�����E-30�p�ł����ˁE�E�B�ł��A����ς�S�~��肪
����̂ŁA�t�H�[�T�[�Y��������C�ɂȂ�Ȃ���ł��B�F�l��D700�����
E-30�Ƌ��ɎB�e���ɂ��������Ƃ�����̂ł����A�A���Ă��Ă���A�O��
�����Y��������D700�ŎB�e�����ʐ^�ɂ�������͂�����S�~���ʂ��Ă��āA
�S�~��������ςł����B�F�l�ɂ́A�u�O�Ń����Y��������̂��ԈႢ���v��
����ꂽ�̂ł����A���t�̊y���݂��Ă����ȃ����Y���g��
���Ƃł�����A�����ɐ�����̂��ǂ����Ă��[���ł��Ȃ���ł��B
�܂��A�m����D300���g���Ƃ��̓����Y�������ɗ͂������Ă����ł����ǂˁE�E�B
�Q��Ԃ牺���Ă����ĊO�ł̃����Y�������ɗ͔�����Ƃ����̂�
��̎肩�Ǝv���܂����A���ꂾ�ƂQ��ނ����g���Ȃ��ł���ˁE�E�B
D700�̃S�~��肪�I�����p�X���݂ɗD��Ă���������͂Ȃ����������m���
���E�E�B
�ƁA�Y��ł��܂��B
�܂��A�Z�����Ԃł̔�r�ł����AD700��E-30���g�������Ă݂āA���̎B�e�Ώ�
�ł͂��قlj掿�̍��������Ȃ������m���Ȃ̂ŁA�������̂���E-3�̌�p�@�킪
�ǂ���t�Ƀt�H�[�T�[�Y�ɏW�Ă��܂��Ƃ����������邩�ȂƎv����
���܂��BFotopus�ł݂�t�H�[�T�[�Y��150mm F2.0�̎ʐ^�ɂق�ڂꂵ�Ă��āA
�����͂��̃����Y�Ƃ����z���������ł��B
����I���ł��B�u���������Ƃ��I�I�v�Ƃ���������������S�R�S�z�Ȃ��̂ł����E�E
�����炱���A�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���Ăǂ��Ȃ̂��Ă�`�H�v�Ƃ�����
�������Ƃ����킯�Ȃ�ł��B
������ς�A�r���ł��傤���E�E�E�B
���݂Ȃ���A��ÂɁE�E
�����ԍ��F10141393
![]() 5�_
5�_
���u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�͂Q�i�Â��v�u�Â�����掿�������v
�����Ă�{�l�B���@�����Y���Â��Ƃ͎v���Ė����ł��傤�ˁH
�������Z�œ_�����Ȃ��2�i�i�������̃{�P���������Ȃ����𝈝����ď�������ł邾�����Ɛ������܂��B
���̕��X�@���Ɉꖼ�̕��́A�掿���{�P�ł�����R���@�ɂ���K�v�͖����Ǝv���܂��B�t���T�C�Y�@���g���či��J���ł����ʂ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă܂����A���ۃt���T�C�Y�@�������Ă��邩���������s���ł��B
�����ԍ��F10141416
![]() 17�_
17�_
������l�b�g����
���ԐM�L���������܂��B
�͂��A����͂ƂĂ��悭�킩��A���ł����ɗ��������Ă��܂��B
�ł��A�ǂ���炻�������b���ł͂Ȃ��悤�Ȃ̂Ŏ��ɂ͂���Ղ�Ղ�
�Ȃ�ł���ˁB
�����ԍ��F10141430
![]() 0�_
0�_
�ǂ��ǂ܂��ɂ�����ڂ��Șb�Ŏ��炵�܂����B��i�������{��ł��ˁB
�����ԍ��F10141527
![]() 0�_
0�_
���ۂɂ������Ȃ�A������g�������z�������ł���B
�����ԍ��F10141573
![]() 11�_
11�_
������l�b�g����
���炵�܂����B������ƌ��t���炸�ŁA�����̕ԓ��ł�����������
����������������m��܂���̂ŕ⑫���܂��B
�b��������Ղ�Ƃ����̂́A������˂��Ƃ��܂̏������݂ł�
�Ȃ��ȑO���瑱���Ă���u�Q�i�Â��v�̋c�_�̂��Ƃł��B���̈Ӗ�
�����Ȃ̂��X�b�L�������肽���Ǝv���Ă��܂��B�������X�b�L��
���Ȃ��̂ŁA�V�X�e���ڍs����̂��A�c���̂����f���ɂԂ��Ă���
��ł��E�E�B�i����́A�����P�Ɏ��̖��ł����E�E�j
����������������悤�ł������ώ��炵�܂����B
��܂����낤����
�����ł���ˁB���ۂɊ����邱�Ƃ��S�Ă��Ƃ������Ƃŗǂ��̂����m��܂���ˁB
�����ԍ��F10141642
![]() 0�_
0�_
����ɂ���
�{��Ɋւ���
�����������_����̂�����̂ŃX���[���Ă��܂��������܂ɂ͖������w�E�������Ƃ�����܂��B
�����̕��͂���Ȃ��Ƃ�����͂��͂Ȃ��Ɠǂ݂Ƃ��Ă����Ǝv���܂����A
��͂����⍬���������Ă���̂��ȂƎv���A�c�O�ł��B
�t�H�[�}�b�g�̑傫���ɂ���đ�����ʂ��قȂ邱�Ƃ��A�����Y�̖��邳�ɂ���ւ�����_�ł��B
�ȑO�A�ȉ��̂悤�Ȏw�E�����܂������A������Ƃ����邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B
�y35mm�������܂��܊�ɂ���悤�ł��ˁB����Ȃ�f���܂��B
�����ގ��i�ɋ߂��j��ISO 100�̃t�B�������x�[�X�Ƃ���������r��̕ϓ��v�f�����Ȃ��ł��傤�B
�i�f�W�^���ł̓t�H�[�}�b�g���Ƃɉ\�Ȍ��葍���I�ɍœK�������X��������j
�唻�̃V�m�S(4×5�j��35mm���̖ʐς̔{15�{�ƂȂ�܂����A�z����́u���ZF�l�v�͂ǂ̂悤�ɂȂ�܂����B�z
�_�u���}�E���g�Ƃɂ���
��{�I�Ɏ^���ł��B4/3�i�܂�m4/3�j�ƃt���T�C�Y�p���܂����A���݂ɕ⊮�ł�����̂Ǝv���܂��B
�ꎞ�I��APS-C���g�p���܂������A�ܒ��I�Ȃ��̂Ŏg�������̃����n�������ɂ����悤�Ɏv���܂��B
���ݕ⊮�̈Ӗ��͎�Ƃ��Ĕ�ʊE�[�x�̎g�������ł��B
�ق����~�����Ƃ��̓t���A�[���ق����~�����Ƃ���4/3�Ƃ����悤�Ȋ����ł��B
m4/3�ōۗ����Ă��܂������g�ѐ��Ƌ@���́A����ɗ^����ْ����̒Ⴓ�Ȃǂ̃����b�g���傫���ł��B
�t���T�C�Y�ł̒��L�p�ɑ��z�̎����𓊓����Ă���p�Ό��ʂ��Ⴛ�����Ƃ������Ƃł��͈̔͂́A�y�����̖��͂��܂�m4/3�ւ�������ڍs���܂����B
�j�R��FX�ɂ��Ă͍����ȃi�j�N��12-24mm�̑I����������܂��ˁB�`�ʂ̒��x�͂܂��ǂ��m��܂���B
�����x������5D��E-P1�Δ�ł�1�`1.5�i�قǂ̍��ł��傤���B�i���G�͌l��������ł��傤�j
�v�́A�g�ѐ���[�x�ȂǂL����������Ɗ����ȃV�X�e���͑��݂��Ȃ��̂ŁA�����Ƃ��������Ă����Ȃ��Ă͂Ƃ����Ƃ���ł��B
�����ԍ��F10141672
![]() 13�_
13�_
�u��i�Â��v�Ƃ����͖̂����ł����Ǝv���܂��B4/3����i�Â��̂Ȃ�A�R���f�W�͐^���Âł��B
�����ԍ��F10142121
![]() 34�_
34�_
�Z���JGT-Four-A����͂��߂܂���
�t�H�[�T�[�Y�̃����Y��2�i�Â��Ƃ̍����́A�o���オ��̎ʐ^�̏œ_�[�x���l������ƁA
�t�H�[�T�|�Y�̃V�X�e���Ŏʂ����ʐ^�Ɠ��������t���T�C�Y�ŎB��ɂ́A�{�̏œ_������
�����Y���g�p�����i���2�i�i���Ďʂ����ʐ^�Ƃقړ����ɂȂ�A�ƌ����_�ɗL��܂��B
�܂�A�t�H�[�T�[�Y�͏œ_�[�x���[���Ȃ�ƌ����Ă���̂ɉ߂��Ȃ��̂ł��B
�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���t�H�[�T�[�Y�̃{�f�B�[�Ŏg�p�������́AF2��F2�̖��邳�ł��B
�ςȋ�_�ɘf�킳��邱�ƂȂ��A�������C�ɓ����������g�p����̂���Ԃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10142295
![]() 16�_
16�_
���ԓ��������F�l�A�ǂ����L���������܂��B
����ς肻���ł���ˁB�������ꉞ���n�̐l�ԂȂ̂�F�l���ʊE�[�x�Ȃ�
Wikipedia���݂��肵�Ē��ׂĂ݂��̂ł����A�o�Ă��錋�_�͊F�l�Ɠ���
�ł����B���M�����c�_�̒��ł́A���l�̈ӌ��Ŗ₢���킹���N����̂ł����A
�������ʂ̃L�[���[�h���g���āA�����̓����̂��ƂƈႤ�l�Ȉӌ���
�o�Ă��܂��B
�u�t�H�[�T�[�Y150mm F2.0�̓t���T�C�Y���Z�łǂ��Ȃ�̂��v�Ƃ����₢
�ɑ��ẮA�u�t���T�C�Y300mm�����̉�p�Ŗ��邳��F2.0�v�Ƃ����̂�
�������Ǝv���̂ł����A�u��p�ɉ����ăt���T�C�Y�������邳F4.0�ɂȂ�v
�Ƃ����̂��s���Ɨ��܂���B�����P�ɔ�ʊE�[�x���t���T�C�Y��F4.0������
�Ȃ邾�����Ǝv���̂ł����A���̂悤�Ȏ咣�ɂ͎v�����A�ނނނށE�E�E�ƁA
���f�������ł��B
�u�t�H�[�T�[�Y������Ȑ����������Ă���̂Ȃ瑼�ЂɈڍs���������ǂ�
�̂��ȁE�E�v�Ƃ������������悬���Ă���̂ł����A����͎v���ڂ�
�������ƂȂ̂ł��傤���B�t�H�[�T�[�Y�͐F�X�ƌ��_�����邯��ǁA��肭
�g���Ă��A��ԑ����C�ɓ������ʐ^���B���̂Ō��\�C�ɓ����Ă����
�ł�����ǂ��E�E�E�B
�����ԍ��F10142609
![]() 2�_
2�_
�u��ʊE�[�x���ς��v�̂ƁA�uF�l���ς��v�̂́A���`�B
�t�Ɍ����AF�l���ς��Ȃ���A��ʊE�[�x�͕ς��Ȃ��B
�ł́A�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̏œ_�����i��p�j���Ɂi���������͊��Z�j�����Ƃ��A�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�Δ�Łu��ʊE�[�x����i�[���Ȃ�v�Ƃ́A�ǂ������Ӗ��H
�l���Ă݂āB
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�́uF2.0�v���A�����uF2.0�v�̘I�o�l�Ƃ��Ďg����̂́A�M���̑����l��ς��Ă��邩��B
�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�Δ�ŁA��2�i���̃Q�C���E�A�b�v�B���ꂪ�掿�i�m�C�Y�j�̍��Ɍ����B
�����ԍ��F10142797
![]() 4�_
4�_
�F�l����A���܂�C�ɂ���K�v�͂Ȃ��Ƃ����R�����g���A�������S
���܂����B�掿�ɂ��Ă��A���Ȃ��Ƃ����̎�ςł�D300��E-30�̔�r
�ł́AA3�܂ł̃v�����g�ł͗��ҁA���F������܂���B�s�N�Z�����{��
�����Ɍ��Ă݂�ƁAD300�ł͊J���ł͎��ӂ�������ƊÂ��Ȃ�悤�Ȉ�
�ۂ�����܂����A�����i��������������܂��BE-30�ł͊J���ł�
�Â���������ꂸ�������Ă��܂�
�Â���ʑ̂ɑ��ẮAD300�Ɣ�ׂ��E-30�̎ʐ^�̈Õ����������
������l�ȋC�����܂����A�t�ɊK�����c���Ă���ꍇ�������āA
����̓Z���T�̌��E�����邯��ǁA�G���̃|���V�̈Ⴂ���ȂƎv����
���܂��B�����Ƃ��Ƃ��Ă��ǂ��J�����ł��B�������A�t���T�C�Y�Ƃ���
�̂��C�ɂȂ��Ă���̂������ŁA������Ƃӂ�ӂ炵�Ă�����Ă���
�Ƃ���ł��B
�ȑO�A�F�l��ōs����BBQ�̎��ɗF�l������D700�{24-70mm F2.8�ƁA
E-30+14-35 F2.0�ŁA70mm��ł��ꂼ��̊J���ŎB���ׂ��Ă݂܂����B
PC��̃s�N�Z�����{�Ō��Ă��ǂ�������ꂢ�Ɍ�����̂ŁA���̗F�l��
���L����G�v�\����PX-5800��A2�Ńv�����g���Č���ׂ��̂ł����A
��ʊE�[�x�̈ȊO��������ȊO�́A�D��������������̂ł����B�����ɁA
�j�R���̕���F4.0�ɍi���Ĕ�ʊE�[�x���ɂ������̂ƌ���ׂ�ƁA
�{���ɂǂ��炪�ǂ���Ȃ̂�������܂���ł����BBBQ���I����Ė�������
���邻�̏�ɂ����ʂ̗F�l�����Ɂu�ǂ��炩���ꂢ�Ǝv������I��ł���v��
�����Ăǂ��炩��I���Ă��A�����ɕʂ�܂����B�v��A2���x�Ȃ猀�I�ȍ���
����킯�ł͖����A����ς������Ċӏ܂�����A�ǂ�����u���ꂢ�v����
�������Ƃ��킩��܂����B
�t�H�[�T�[�Y�̔�ʊE�[�x���[�����Ƃ����_���Ƃ����咣�������̂ł����A
�F�l�Ɏ肽D700�ʼnԂ�l���̃|�[�g���[�g���B�e�����Ƃ��ł��A�t���T�C�Y
�̊J���ł́A��ʊE�[�x�����ĖڂɃt�H�[�J�X�����킹�Ă��@�ɂ͂�����
���Ȃ������肷��̂ŁA��͂�Q�i�ʂ͍i�邱�Ƃ��������ǂڂ��̗ʂ��t�H�[
�T�[�Y�Ɠ����悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B
�t���T�C�Y�����g���̕��́A�J���ŎB�邱�Ƃ��d������Ă���̂��Ǝv����
�ł����A�����ɂ́A�����܂Ő�ʊE�[�x�͕K�v�Ȃ������ł��B�������
D300�ł͂���������ʊE�[�x���[�����o�I�ɂ̓t�H�[�T�[�Y�ƂقƂ�Ǖς�
��Ȃ��Ȃ̂ŁA���������Ӗ��ł͎g�����������₷�������ł��B
����ŁA�t���T�C�Y�͈Â��Ƃ���ɋ����Ƃ����̂͗F�l�̃J�����Ŏ���
�ł��܂����BISO 3200��6400�������ʂ͂ɂ̓t���T�C�Y�łȂ�
��Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���A����ȊO�̏�ʂł͉掿�̈Ⴂ�͊�������
����ł����B
�����Ƒ傫���L���ƕς��̂����m��܂��AA2�ȏ�̑傫����
�v�����g�����i���Ȃ��̂ʼn掿�I�ɂ́AE-30�ł��K�v�[�����Ǝv����
���܂��B�����̂悤�ȃ��[�U�ł���A�킴�킴�t���T�C�Y�Ɏ���o���Ȃ�
�ł��ǂ��ƌ������Ƃł��傤���ˁB
�����ԍ��F10142909
![]() 9�_
9�_
�ǂ����ł��B
���S�҃}�[�N���t���Ă܂����A�A�A^^;
�����Y�̘b�Ɍ���Ƃ���ƁA���鐯���߂炳��͏o�Ă��Ȃ���Ȃ��낤���A�Ǝv���܂��B
����ŁA�܂����ɕʂ̃X���Łu�Â��v�Ə������ށB
������A�F�X�o�債��^^;���̌���͊O�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B
���Ȃ̖��ł͖����A���ȋ����@�̖�肾�Ǝv����ł���ˁB
�����ԍ��F10142925
![]() 2�_
2�_
�������������Ȃ�قǁA�����o��B
���̍���r��H�v�Ŗ��߂��鎩�M������Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y���g����B
�t�Ɍ����A�t���T�C�Y�͏��S�Ҍ����B
�������A�㋉�҂��g���A�S�ɋ��_�����B
�����ԍ��F10142969
![]() 4�_
4�_
�{�X�g�[�NT-233����
>�u��ʊE�[�x���ς��v�̂ƁA�uF�l���ς��v�̂́A���`�B
���`�ł͖����ł���B�œ_�������ς���Ă���ʊE�[�x�͕ς��܂��B
��ʊE�[�x�́A���a�Ɣ�ʑ̂܂ł̋����Ɖ�ʏ�Ńs���g�������Ă���Ƃ݂Ȃ���傫���ōl����̂����ʂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10142977
![]() 6�_
6�_
�������A�œ_�����������ꍇ�̘b�B
�������A�s���g�����킹��ʒu�������ꍇ�̘b�B
�X���傳�g���A�t�H�[�T�[�Y��150mm���t���T�C�Y��300mm�Ɋ��Z����i�œ_�������ɂ���j�b�����Ă���B
F�l��傫������ƁA��ʊE�[�x���[���Ȃ�B
��ʊE�[�x��[������ɂ́AF�l��傫������B
���̎d�g�݂�ے肷��l�͂��Ȃ��Ǝv���B
�����ԍ��F10143025
![]() 1�_
1�_
�����ł��˂��B
>F�l��傫������ƁA��ʊE�[�x���[���Ȃ�B
>��ʊE�[�x��[������ɂ́AF�l��傫������B
>���̎d�g�݂�ے肷��l�͂��Ȃ��Ǝv���B
���̃X���̗����������͂�����u�Â��v�ƌ������ۂ��A�Ƃ����Ƃ���ł��B[10141193]�Ƃ��A[10142609]�Ƃ��Ō��y����Ă��܂��B
�u�Â��v�̂łȂ���Ε���������l�����Ȃ��낤�Ǝv���܂��B�i����������l�͏œ_���������Z���邱�Ƃɕ���������l�ł��ˁj
�Ƃ������Ƃ���ŁB
�����ԍ��F10143144
![]() 2�_
2�_
�b��B���Ȃ܂܊g�傷��̂ł킩��ɂ����Ȃ�̂ł��B
�[�x��F�l�͑��ւ��܂����A�����Y�̖��邳�̊T�O�͂�����Ɛ蕪���Đ����������������ł��B
������B��������Ƃ���ɋ�_�����܂�Ă���̂ł��B
����p�������ł����4/3��25mmF1.4�̐[�x�̓t����50mmF2.8�Ɠ����Ƃ����Ƃ���͊m��B
�Ƃ��낪�A���邳��4/3F1.4�͕s�ρA�s�ςȂƂ����F2.8�ւ���ւ��悤�Ƃ����_�ł��B
�[�x�Ɩ��邳��蕪���Ă����Ό���������邱�Ƃ͂���܂���B
��ɏ������悤��35mm����菬�����Ȃ���������l������_�ł��B
35mm�����傫���Ȃ�ꍇ�̌�������Ă��炸�A�����Ƃ��Đ��藧���Ȃ��b�ł��B
�����ԍ��F10143187
![]() 11�_
11�_
�X���傳�܁B
�u�t�H�[�T�[�Y�͂Q�i�Â��v�̘b�͂����ɏ������܂ꂽ������
�قƂ�ǂ�����������Ă���悤�ɒP�Ȃ����ł�����A�S�z
����K�v�͂���܂���B
�J�����ɂ͂��ꂼ��p�r������A�p�r���ƂɓK�s�K������܂��B
�t�B��������ɔ|�������o��厖�ɂ������l�ɂƂ��Ă̓t���T�C�Y
�͕֗��ł��傤�B���ɒ��]���ł̉�p�ƃ{�P�Ɣ�ʑ̂Ƃ̋����Ƃ�
�▭�ȃo�����X�ɂ��Ă����́A���Ƃ��Ɖf��t�B�����̂Q�R�}��
�ނ����R�}�Ɏg�����Ƃ�����R�����������̃t�H�[�}�b�g���A
�ǂ����Ă����܂Ńn�C���x���ȃo�����X���������Ă���̂��A����
���R�̔z�܂Ɋ��т𑗂肽�����炢�ł��B
���łɂ����Ή�f�̑傫���̓_�ł̗D�ʂ�����̂Œ������x��
���g�����ɂȂ�A�Ƃ����̂�����p�r�ł͗��_�ł��傤�B
�t�H�[�T�[�Y�̓f�W�^��������l���Ĉꂩ��K�i��������_�ŗ��z
�I�ȃV�X�e�����Ǝv���܂��B�t�H�[�T�[�Y���̌��w���\�̃����Y��
�t���T�C�Y�p�ɍ������A���̂������傫����d���E���i�ɂȂ�܂��B
�ł��t���T�C�Y�ɂ́A�t�H�[�}�b�g���傫�����߂Ɍ��w�I�Ɂg���e�h
�ɂȂ�܂�����i�t�H�[�T�[�Y�͎B���f�q�����������߂Ɍ��w�I�ɂ�
�Q�{�V�r�A�j�A���ʓI�ɂ��܂������Ă��܂��ꍇ������܂��B
����Ȃ킯�ŁA����i�ɂ����ăt���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̋�ʂ�
�������������A�Ƃ����̂͂���Ӗ��Ó��Ȍ��_�ł��B
�������A���̗��҂��������邽�߂ɓ�������镨�ʂ̓t���T�C�Y�̕���
ꡂ��ɑ傫���Ȃ�킯�ł�����A�t�H�[�T�[�Y�̂ق����V�X�e���Ƃ���
�����I�A�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�܂��B
���Ⴀ�`�o�r�|�b�́A�Ƃ����ƁA�t���T�C�Y�������悻1.41�{���w�I
�ɃV�r�A�Ȃ͂��Ȃ̂ŁA�����փt���T�C�Y�p�̃����Y��p����Ȃ�掿
�I�ɂ͕s���ɂȂ�܂��B�܂�A�t���T�C�Y�����t�H�[�T�[�Y����
�s���A�Ƃ������Ƃł��B
�ł͂`�o�r�|�b�ɗ��_���Ȃ����Ƃ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��āA�t���T�C
�Y�p�̖L�x�ȃ����Y�����i���Ƃɖc��ȒP�œ_�j�����p�ł���A�Ƃ���
���Ƃɂ́A�傢�ɗ��v������܂��B
����ȂƂ�����l����A�ꂩ��V�X�e�������Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y��
�œK�Ȃ�Ȃ����ƁA���͎v���܂��B���邢�̓t���T�C�Y�ƃt�H�[�T
�[�Y�̓��Ăł������B�������͂������Ă��܂��B�t���T�C�Y�ɂ��o
�Ԃ��Ȃ��킯�ł͂���܂��A���܂�X���ȏ�̃J�b�g���t�H�[�T�[
�Y�ŎB���Ă��܂��B�唻�i�`�P�m�r�j�Ƀv�����g���Ă��\���g�����ɂ�
��܂��B��L���Ɏア�ȂǂƂ����l�����܂����A���ɂ͂����͎v����
����B�ق�Ƃ��Ɍo�����Č����Ă���̂��^��ł����A�v�����^������
���v�����g���w�^�Ȃ�����������܂���B
�����ԍ��F10143211
![]() 16�_
16�_
>���̎咣�͖{���Ȃ̂ł��傤���B�ł���߂��Ƃ������������̂ł����A
>���_����Ă��咣���J��Ԃ����̂́A�P�Ȃ�l�K�e�B�u�L�����y�[���ł�
>�����A��������������悤�ɂ��v���Ă��܂��B
�ȒP�ɔ��ʂ�����@������܂��B
�������L��Ȃ�A�������炻�̍������Ђ��炩�����ł��B
���ۂɂ́A�����o�Ă��Ă���܂���B
�����̎^���҂Ƃ����̂��A���̂̂��镨�ł���A�l����������Ȃ����炻�̂����̒N������́A����̈���A��������Q�ƌ��̈���A�o�Ă��Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
���x�A�u�c�_�H�v���J��Ԃ���悤�Ƃ��A�N��l�A���̂悤�ȍs���ɂ͏o�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł͑�ϓ������Ƃ�Ă��܂��B
���ꂪ�u�M����ɑ���s���v�Ǝv���邩�ǂ������|�C���g�ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F10143278
![]() 13�_
13�_
�Z���JGT-Four-A����
�ƂĂ��ǂ��X���b�h�𗧂��グ�ĉ������܂����B
������ł́A�X���傳�܂ɂ͑�ϐ\����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����A�Ƃ�ł��Ȃ����_�H���ӂ肩�����A�����̐l�����������锭���𑱂��邨�悻�Q���̕��ɁA�Ƃ��Ƃt���������悤�Ǝv���܂����A
�Ƃ��낪�v���̂ق����������Ă��܂��A�ǂ��������̂��Ǝv���Ă����Ƃ���ł����B
���܋�̓I�Ȃ�����������l���炨�҂����Ă���̂ł����A���āA�ǂ��Ȃ邱�Ƃł��傤���B
������ł͑����̕����A���łɖ����Ȃ��������Ă���������悤�ł��ˁB
���܂��玄���Ƃ����������ގ��͂Ȃ��悤�ł��B�ƂĂ����S���܂����B
�����ԍ��F10143352
![]() 6�_
6�_
�Z���JGT-Four-A����
�����́B
�Z���JGT-Four-A���܂̍����͂������Ƃ����Ǝv���܂��B�������̋c�_�ɋ^��������āA���ʂƂ��Ď��ƈႤ���e�ŁA���̃X���b�h�����ʂƂ��čr�炵�Ă��܂��܂����B�������݂𑱂��邱�ƂŁA���炻�̃X���b�h���r�炷���Ƃɂ��Ȃ肻���������̂ŁA���̌�̋c�_�ւ̏������݂͍T���܂������A���̎咣�͉��������Ă���̂������Ȃ�ɏ������������ʎ��͎����Ŕ[���o���铚�����o���܂����B�ł��t���n�I�ȕ��̌��ʂł��̂ŊԈ���Ă��邩���m��܂��A���̎��͂��e�͉������B�܂��A���Ƃ̕�������ꂽ����ɂ��Ă��w�E������K���ł��B
�܂��ŏ��ɁA�ŏ��Ƀ����Y�̓����ׂ邽�߂ɉ����ǂ̂悤�ɕ�����Ηǂ��̂��ׂ��̂ł����A���w�ɂ͊��w�Ƃ��g�����w�Ƃ��F��ȕ��삪����悤�ł��B�����Y�̏����̐v�ɂ͊��w���g����悤�ł����A�ʂ̌����x�Ȃǂ���͂���ɂ͔g�̓������l�������g�����w�Ȃǂ�m��K�v������悤�ł��B�܂��͊ȒP�ȂƂ��납����w������ĎB���ʂ̃T�C�Y��œ_�����A��p�Ƃ������̂����Ȃ̂���c�����܂����B�����āA�t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̌��w�n��P���ɍl���Đ}�ɏ����Č���ׂ��Ƃ���A���Ȃ�Ɍ��_���o�܂����B���炭�A�Y�t�����}�����Ė�����痝�n�̕��Ȃ炷��������Ǝv���܂��B���w���x���̐��w��m���Ă���Ώ[���ɗ����o���錋�_�ɒB���܂����B
�ȒP�ɂ܂Ƃ߂�ƁA�ȉ��̒ʂ�ł��B
���t�H�[�T�[�Y�̌��w�n�́A35mm�̌��w�a���̃X�P�[���Ŕ�����
�@�k���������̂ł���B
���t�H�[�T�[�Y�̌��w�a��35mm���Z����Ƃ����͉̂����Ƃ����̂́A
�@�����P�ɒP�ʌn���Q�{�ɂ���ƌ������ƁB
�u�t�H�[�T�[�Y��150mm F2.0�́A�t���T�C�Y��300mm�̃����Y�̉�p�Ɠ����ŁAF�l�͓����v�Ɗm�M�����Ă�悤�ɂȂ�܂����B�^���̎咣�ł́A�t���T�C�Y���Z�ŏœ_�����ƎB���f�q�T�C�Y�͔{�ōl���邪�A���a�͂����Ȃ��ƌ����Č��ʂ����Ȃ��Ǝ咣����Ă��܂������A�}�ł�������悤�Ƀt���T�C�Y���Z����ꍇ�ɂ͌��a�����Z���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B�܂�A1mm��2mm�ƍl����ΊȒP�ɂ��̊��w�a���t���T�C�Y�̌��w�a�ɕϊ��ł��܂��B���ꂪ�A�u���Z�v�ł���u�����v�Ȃ̂ł��B
�ł́A�u�t�H�[�T�[�Y�͌��ʂ����Ȃ��Ȃ��̂��v�Ƃ����ƁA����͌��Ńt�H�[�T�[�Y�̌��w�a�ʼn摜����邽�߂ɗ��p�������ʂ́A�����Ȍ��w�a�ɂ����Ă�͂�1/4�ł��B�ł́A�u��͂�掿�������́H�v�Ƃ����₢�ɑ��ẮA�uNo�v�ƂȂ�܂��B
�m�C�Y����l�œ���������\�������̋ɂ߂ė��z�I�ȎB���f�q��z�肵�āA�^����ꂽ���ɑ��Ă�����Ƌ@�\������̂ƍl���܂��B�摜�͌��̑��Ƃ��Ē��i���Ă���ƍl����ƁA�K�v�Ȃ̂͒P�ʖʐς�����̌��Ɠ_��_�Ƃ��āA�����Y���ǂ��܂ōׂ����\���ł��邩�Ƃ����������ƂɂȂ낤���Ǝv���܂��B����́A�G�̋�ƕM�̑傫�����l����Ηǂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ��ƁA�������������Ǝv���܂��B
���̗ʁF�F�G�̋�̗�
�����Y�̕���\�F�F�M�̑傫��
�B���f�q�F�F�L�����o�X
�t�H�[�T�[�Y��A4���Ƃ���ƁA�t���T�C�Y��A2�̃T�C�Y�ɂȂ�܂��B����ɗ^����ꂽ�G�̋���g���āA�����G��`�����Ƃ��l���Č��܂��B�t���T�C�Y��4���b�g���̊G�̋�K�v���Ƃ���ƁA�t�H�[�T�[�Y��1���b�g���̊G�̋���^�����܂���B�G��`�����߂̕M�́A�t���T�C�Y�͒��a�S�~���ŁA�t�H�[�T�[�Y�͂P�~���ł��B�G��`���E�l����͓����\�͂������Ă���Ƃ���ƁA�ł��������Ă����G�͂S�{�̍�������܂��B�������AA4�ɏ����ꂽ�G���k���ő@�ׂɕ`����Ă��܂��B�������傫���ɂȂ�悤�Ȋӏ܋����ł݂�Ƃǂ��Ȃ�ł��傤���B
�܂�AA4�̊G��1m�͂Ȃꂽ�Ƃ��납��ŁAA2��2m���ꂽ�Ƃ��납��ł��B�ǂ����āAA4�̃L�����p�X��1mm�̕M��������̂��Ƃ����^���������邱�ƂƎv���܂��B����̓t�H�[�T�[�Y�̃����Y�̐v����݂Ă݂�Ƃ킩�邩�Ǝv���܂��B�t�H�[�T�[�Y�̃����Y��MTF������60/20�{�Őv����Ă��āA�t���T�C�Y�̃����Y��30/10�{�̔{�̋�Ԏ��g�������������Ă��܂��B�܂�{�̕���\�����邱�Ƃ�\��������ł��B�ȑO����ǂ����Ă���Ȃɔ{�̋�Ԏ��g�������Őv���Ă���̂��낤�Ǝv���Ă����̂ł����A�܂�͂������Ȍ��w�n�ł��A�������35mm�̉掿�����o�����߂ɐv����Ă����̂��ƌ������Ƃ𗝉������킯�ł��B
�����A���̍l�������ԈႦ�Ă����炲�w�E������ƍK���ł��B
�܂萮�������
�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�̌��w�n��1/2�ɂȂ�悤�ɐv����Ă��āA�����Y�̕���\�����̂��߂ɔ{�̊�Őv����Ă���B�v�Ƃ������Ƃł��ˁB����ς�I�����p�X�͌��w�̉�ЂȂȂ��ƍĔF�����܂����B
����Ȏ��͌��w�̐��Ƃ��Ə펯�Ȃ̂ł��傤�ˁB�܂��A�t�H�[�T�[�Y�̎d�l���ɂ͂��̂悤�Ȏ������ɏ�����Ă���̂����m��܂���B�����A����́A�I�Ȗʂł��������Ă��Ȃ��̂ŁA�����o���Ă��Ȃ��Ƃ�����܂��܂����肻���ł��B���w�̕��̗ǂ��@��ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F10143379
![]() 10�_
10�_
�V���v���Ƀs���z�[���J�����ōl���܂���B
�ʐς̈قȂ��̃t�B�������g���ăs���z�[���J�����Ŏʐ^���B�e����Ƃ��܂��ˁB
������t�B�����܂ł̋����ƃt�B�������x�������Ȃ�A�t�B�����̖ʐςɊW�Ȃ������V���b�^�[���x�ɂȂ邵�A������p��Ȃ�傫�Ȗʐς̃t�B�����͌�����ʐς̕������{�i���̕\���A�������ł����H�j�����Ȃ�A�����̓��i�Ƃ������ʐρj�{�ŃV���b�^�[���x���x���Ȃ�܂��B
���̃s���z�[���A������t�B�����܂ł̋������u�œ_�����v�ŁA�œ_���������̒��a�Ŋ������������uF�l�v�ł��B
�����ăt�B�����̏ꍇ�A�t�B�����̖ʐςƗ��q�̐��͔�Ⴗ�邩��A�傫�ȃt�B��������荂�掿�ɂ��₷���A�������ꂾ���ł��B
�f�W�^���ł́A�B���f�q�̖ʐςƉ掿�͓����ł͂���܂���B���łɂ����Ȃ�A�掿�Ǝʐ^�̉��l�������ł͂Ȃ��ł��B
�t�H�[�}�b�g�ŃJ������I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A�����̋��߂�ʐ^�i�����j�ɖ]�܂����p�b�P�[�W�̃J������I�ׂΗǂ��̂ł��B
�Ƃ������ƂŁA���l�̐��������ȂNjC�ɂ����A���R�Ɏʐ^��������čs���܂��傤�B
�����ԍ��F10143743
![]() 6�_
6�_
����H
�摜���Y�t�ł��Ă��܂���ł����B�ă`�������W���܂��B
�ȒP�Ɍ����Ƒ����`�Ƃ��čl����Ηǂ��������Ƃ������Ă��܂��B
�����ԍ��F10143926
![]() 0�_
0�_
�����܂���A����A�b�v�����摜�͈�ԉ��̃t���[���T�C�Y�̂Ƃ��낪�ԈႦ�Ă��܂����B�t�H�[�T�C�Y��z�肵��0.5���|����̂�Y��Ă��܂����̂ŏC���ł��T�C�h�A�b�v�����ĉ������B
�O�̋L���͍폜�o���Ȃ��̂ł��傤���E�E�B
�����ԍ��F10144002
![]() 1�_
1�_
������
�����̗ʁF�F�G�̋�̗�
�������Y�̕���\�F�F�M�̑傫��
���B���f�q�F�F�L�����o�X
���̕M�̑����ƃt�����W�o�b�N�̒��������ւ��ăR���p�N�g�^�̂悤�ȑf�q�ɂ��ז��ȕ`�ʂ��\�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͗������܂��B
�����A�G�̋�̗ʂ̂Ƃ���́A����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���������A���̋�_���o�Ă����w�i�Ƃ��āA�[�xF�l���Z�����邳�ɓ]�������w�i�ɁA����ʐϔ��_�����ɂ���̂ł��B
�n�[�t�T�C�Y�͎���ʐς������Ȃ�����ۂ͈Â��킯�ł���Ƃ�����̘b�̓W�J�ł��B
�����I�ȊG�̋�̎g�p�ʂ̗Ⴆ�ł́A����ʐϔ��_�Ǝ����悤�Șb�ŁA����������₷���b�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�R���p�N�g�^��35mm���ɔ�G�̋�̎g�p�ʂ��ɂ߂ď��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B
����Ɋӏ܊g�嗦�������Ȃ�X�����班�Ȃ��G�̋����ɔ��܂��Ă��܂����̌����^���₷���Ǝv���̂ł��B
�����Y���𑜂��Ă���O��ł͑f�q�̑召�ɂ�����炸�e�f�q��������RGB�f�[�^�́A�f�[�^�Ƃ��ĕێ������̂ŁA
�����܂ł��f�[�^�Ƃ��ĂƂ炦�A���ʂ̑召�E�����ɒu�������Ȃ������킩��₷���̂ł��B
���Ƃ��ƁA�P���Ȗʐϔ��_�͏�L�����Ă��܂����A����Ɍ����Ɗӏ܃T�C�Y�̂����Ȃ����Ƃ��ɉ��������L���@��PC���j�^�[�̃o�b�N���C�g�Ȃǂ̌ォ��t�������G�l���M�[�ʂ��܂������l�����Ă��܂���B
�����ԍ��F10144094
![]() 1�_
1�_
�䂽����
�P���ɑ����`�ōl����ƃ_���ł���B
���͔g�Ȃ�ŁA�g���܂œ����䗦�Ŋg�債�Ȃ��Ƃ�����Ƃ������ۂ�����Ȃ���ł��B
�ǂ���������������Ă����ƁA
��ʏ�ɃV�}�V�}���悭�Ƃ��āA��~��������Ɉ�������̐��ɂ͌��E������A�����F�l�Ō��܂�܂��B
����F�l���ƈ�~��������̐��̐��̌��E�̓t���T�C�Y�ł��t�H�[�T�[�Y�ł������ɂȂ�܂��B�܂�A�t���T�C�Y�̕�����ʑS�̂łQ�{���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�����A30M��f�t���T�C�Y�̃J�����Ƃ��A���̂����ɔ��������Ǝv���܂����A�t�H�[�T�[�Y�ł͂��̂悤�ȍ���f�J�����͎����ł��܂���B
�ނ������b�͌����Â�܂� ^^;
�����ԍ��F10144247
![]() 1�_
1�_
�ʉ�y����
�L���������܂��B
�Ȃ�قǁA���ɂȂ�܂��B
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̊W�ɂ����ẮA���������ƍl���܂������A��肿�����ȃR���f�W�Ȃǂɂ����ẮA���������ɂ����ł��ˁBWeb�Œ��ׂ����ɂ������ʂ̌����x�Ɋւ��ẮA���w�ł͐������s�\���ƂȂ�A�g�����w�̍l�������K�v�Ƃ������Ƃ�m��܂����B���w�����藧�����ł͗ǂ��̂ł������̋��E�̈悪�悭�킩���Ă��܂���B�������Ă��Ȃ��̂ɏ������ނȂƌ����邩�Ǝv���܂����A���̕��ɁA�����_��������������ƌ����Â��l��������܂����B
�܂��܂����s���̂悤�ł��B���͔g�̐���������̂Œ��i������������ōl���邱�Ƃ͖������N�����\�������邾�낤�ȂƂ͎v���Ă��܂������A���w�E���Ȃ���Ή������ȗ��_�̕Ж_��S���ł��܂��\��������܂����B���w�E�����A��Ϗ�����܂����B
���a�̑O�̃����Y�̑召�ɂ���ē�������ʂ̈Ⴂ�́A���̊��w�I�ȍl���ł��_�����̐���������Ƃ������ƂŖ��邳�������邱�Ƃ͕\���ł���Ǝv���̂ł����A�W���͂������Ă��Ȃ��P�ʖʐς�����̌��ʂ𑝂��邱�ƂƂȂ�Ȃ��̂��������o���Ă��܂���ł����B�܂�A�܂��܂����ʂ̖{���I�ȍl�����������o���Ă��Ȃ��̂ł��傤�ˁB
�Ƃ����킯�ŁA�㔼�̊G�̋�̗ʂɂ��Ă͊ԈႢ�̉\����Ƃ������Ƃł������������B�܂��A�����s�\���ȊԈ����������������ł��܂��Ă��邱�Ƃ����l�т��܂����݂Ȃ���
����̈ꌏ�ŁA������ƌ��w�Ƃ������̂�����Ă݂悤�Ƃ����C�ɂȂ�AAmazon�ʼn������{���Ă݂܂����B�����A�z���\��ƃ��[�������܂����B�������y�Ԃ��ǂ���������܂��A�ʐ^�𗝉����邽�߂ɂ��A�����������Ƃ������̂�����Ă݂悤�Ǝv���܂��B�����̕��Ȃǂ������܂����炲�w��������ƍK���ł��B
�����n�̂������ۏo���ł��ˁB�܂��A����������炵���ėǂ������Ǝv���Ă��܂��B�i�j
�����ԍ��F10144254
![]() 0�_
0�_
�@�Z���JGT-Four-A ����A�݂Ȃ���A�����́B
�����Ȃ�̉��߂��܂Ƃ߂Ă݂܂����B
�ԈႢ�����邩������܂��A�����̃q���g�ɂȂ�K���ł��B
�������Y�̓����Ɍ��肵�ĉ������B�t�H�[�}�b�g��
�ʐς̘b���ɂ͉�p�����߂�Ƃ��ɐG���K�v������悤�ł����A����
���Ȃ��Ă��m�C�Y���S���������Ȃ����z�I�ȎB���f�q�Ƃ����O��ł��˂���
���܂��B
�@���̑O��́u���ZF�l�v��������鎞�ɂ͂̂߂Ȃ��ł��傤�B
�����Y�Ɖ摜�f�q�̖ʐςƂ��̌��ʂ̎ʐ^�̊W������Ă��邩��ł��B
�����̎咣������Ă�����̐����͈ꌩ�����Ƃ��炵���̂ł����A���̌��ł�
���̍����������Ȃ��̂�
���̎咣�����Ȃ�ɈӖĂ݂�ƁA
�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʂ������ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
�Ƃ��������Ǝv���܂��B
���ۂ̗�ɓ��Ă͂߂Ă݂܂��B
(�T�Z�Ȃ̂ōׂ����덷�͂����ق��E�E�E�{���I�ȂƂ��낾�������Ă��������B�j
�@�܂��A�Z���T�[�̉�f���������ŁA�ʐς��Ⴄ�ꍇ�B�@E-30��D700�̏ꍇ�i�P�Q�O�O����f�A�ʐϔ�S�{�j�ł��B
�uE-30�Ł@50mm F2�AISO 800�ŎB������́AD700�Ł@100mm F4�AISO 3200�ŎB�������
��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʂ������ɂȂ�B�v
�i���ۂɂ́@�����Y�̂ڂ����̈Ⴂ�A�@JPEG�摜����鎞�̃K���}�J�[�u��V���[�v�l�X�Ȃǂ̃p�����[�^�A�m�C�Y���_�N�V�����̗��������ȂǂɈႢ������Ǝv���܂����A��x������Ă݂Ă͂������ł��傤���H�j
�@E-30�̃Z���T�[�̂P��f������̖ʐς�D700�̂��̂�1/4�ɂȂ�̂Ŋ��x��1/4�ɂȂ�܂��B
�i���ۂɂ́A�ގ��̓���������J�����̈Ⴂ�͗L��܂����A����ɂ��Ắu�ǂ��炩��������Ă���B�v�A�u�Z�p�̍��Ō덷����v�Ƃ������ƂŐ�������Ă��܂��B�j
���̂܂܂��ƁAE-30��ISO�����W��D700�Ɣ�ׂ�ƂQ�i�Ⴂ���ɃV�t�g���Ă��܂��܂��B
�����ŁAA/D�ϊ��̑O�ɂQ�i���i�S�{�j��������D700��ISO�����W�𑵂��Ă��܂��B�i����ɂ��Ă͐v�҂ł͂Ȃ��������ɂƂ��Ă̓u���b�N�{�b�N�X�Ȃ̂őz���ł����A���̗l�ɍl����Ƃ��܂͍����܂��B�j
���̂��߁A���ۂƂ��Ă͓���F�l�̃����Y�ŎB�e����ƁAJPEG�Ȃǂ̏o�̖͂��邳�͓����ɂȂ�܂����m�C�Y�̗ʂ͂Q�i�������Ă��܂��B
�����E���邽�߂�E-30�łQ�iF�l���������AISO���Q�i�Ⴍ���܂��B
�o��f�s�b�`��1/4�ɂȂ�����@�@�Q�i�����x���Ⴍ�Ȃ�@�������́@�Q�i���m�C�Y��������p
�@�ł͎��ɉ�f�s�b�`�������ŃZ���T�[�̖ʐς��Ⴄ�ꍇ�A�≖�t�C�����œ������܂��g���ăt�H�[�}�b�g�T�C�Y���Ⴄ�ꍇ�Ƃ��A�Ⴆ�� (�t�H�[�T�[�Y, 500����f�j��(�t���T�C�Y�A�@2000����f�j�̏ꍇ�ł��B
�@(��̓I�ɂ́@D100 ��D700 �A OLYMPUS E-1�@�� EOS 5Dmark2�A D300 ��D3x�@�Ȃ�Ă����g�ݍ��킹������܂����A�����l�i�ɂ����Ԃ�J��������̂Ł@���ۂ̖��Ƃ��Ắu������v��u�Z�p�̍��v�͑傫���Ǝv���܂��B�j
���̏ꍇ�́A���x�͓����Ȃ̂Ō��ۂƂ��ẮA
����F�l�̃����Y�̏ꍇ�AFT�̕��́@�������邳�@�������@1/2�̉𑜓x�̉悪�B��܂��B
�܂�u��f����1/4 �ɂȂ�����𑜓x�i�������A�c�����@���ꂼ��j��1/2�ɂȂ�B�v�Ƃ������Ƃ������܂��B
�����Ŏ��ɂ���FT�̉��2�{�̉𑜓x�����t���T�C�Y�̉悪�����l�Ɍ�����������l���Ă݂܂��B
�L�^����Ă��Ȃ��������o�����Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA���̓���ɂ���ɂ̓t���T�C�Y�̉�̉𑜓x��1/2�ɗ��Ƃ����ɂȂ�̂ł����A
�l�̉�f�����̉�f����鎞�Ƀm�C�Y���_�N�V���������2�i���m�C�Y�����点�܂��B
���̂��Ƃ��A���ΓI�ɂ����邱�Ƃ́A
�o��f����1/4 �ɂȂ�����@�𑜓x��1/2�ɂȂ�@�������́@�m�C�Y��2�i�������p
�Ƃ������Ƃł��B
�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʂ������ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
�@���̎咣�����p�I�ȈӖ�������O��Ƃ��āA�e�����Y��J�����Ɋւ���Z�p�̍����قډ����т̌덷�͈̔͂ł���Ƃ������Ƃ�����܂����A���ꂪ�N���A�ɂȂ�A
�o��f�s�b�`��1/4�ɂȂ�����@�@�Q�i�����x���Ⴍ�Ȃ�@�������́@�Q�i���m�C�Y��������p
�o��f����1/4 �ɂȂ�����@�𑜓x��1/2�ɂȂ�@�������́@�m�C�Y��2�i�������p
�@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i��f�s�b�`��1/2 �A��f����1/2�̎��������v�̂ł��j
�@�O������ɓ��ӏo���邩�ǂ����́@�܂��ʂ̖��ł����A�l�����Ƃ��Ėʔ������A��ł͌����ƈ�v���Ă���悤�ȋC�����܂��B�iISO100-400�ʂ���PC�̃��j�^�[��A3���炢�̃v�����g�ł͂��̍��͕�����Â炢�ł����B�j
�����ԍ��F10144284
![]() 2�_
2�_
�͂炽����
���w�E�L���������܂��B
����������Ă��邱�Ƃ́A���m�ɗ����o���Ă��܂��A���w�E����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͂悭�킩��܂��B
���w�ōl������Ƃ��낪�ǂ��܂łȂ̂��Ƃ����A���E�̈悪�������Ă��Ȃ��̂Ŕg�Ƃ��Ă̊��̉e�����o�Ă���̈��A���ʂ̌v�Z�̂Ƃ���Ŗ������N�����̂��낤�ȂƂ����\���͂���̂ł����[���ɗ������o���Ă��܂���B
���Ƃ������̂͏�X�s�v�c�Ȑ����������Ă���Ȃ��Ɗ��o�I�ɗ������Ă��܂������A���O�ł����肱��܂ł��܂�����悤�Ƃ����C�ɂȂ�܂���ł����B����̈ꌏ�ł�����Ɩ����𗝉��o���Ȃ��������������āA�����������Ƃ����z���������̏������݂ł������܂������A���̂����菭���^�ʖڂɕ����Ă݂悤�Ǝv���Ă��܂��B����Ȍf���ŋc�_����ׂ�������Ȃ��̂����m��܂��A�l�I�ɂ́A�F�X�Ƃ�����������ƗL���v���Ă��܂��B
����b�����ȒP�ȗ�ɒu�������āA�V���v���ɘb�����o����l�����D�G�ȋZ�p�҂��Ǝ��Љ�ł͏�X�����Ă��܂��B�t�ɓ�������A�m�����ӂ�����āA�����o���Ă��Ȃ����炱���X�ɓ�������������đ�������������A������̉ʂĂɗ����o���Ȃ����Ƃ��o�J�ɂ���悤�ȋZ�p�҂قǖ{���͎g���Ȃ��Ƃ������Ƃ����Љ�Ő������݂ė��܂����B���Љ�ł́A�O�҂̋Z�p�҂�ڎw���Ă���̂ł����Ȃ��Ȃ�����Ə�X�����Ă��܂��B�݂Ȃ���̂��w�E�Ȃǂ͂ƂĂ��Q�l�ɂȂ�܂��B
�L���������܂����B
�����ԍ��F10144315
![]() 1�_
1�_
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
E-3 / 150mmF2.0�@�i��F2.0 |
E-3 / 150mmF2.0�@�i��F2.0�@�g���~���O |
E-3 / 150mmF2.0 / EC-14�@�i��F2.8 |
E-3 / 150mmF2.0 / EC-20�@�i��F8.0�@�g���~���O |
�Z���JGT-Four-A����A�����́B
��Fotopus�ł݂�t�H�[�T�[�Y��150mm F2.0�̎ʐ^�ɂق�ڂꂵ�Ă��āA
�������͂��̃����Y�Ƃ����z���������ł��B
�Ƃ̘b�ɔ������ďo�Ă��Ă��܂��܂���^^�@�ǂ������Y�ł���ˁB
150mmF2.0���āA���̎�̘b�ł������������ɏo����Ē@�����s���ȃ����Y���Ǝv���܂��E�E�E�B
���͋Z�p���ł����ł������̂ŁA���w�I�Ȃ��Ƃɂ͏ڂ�������܂���B
����Ȉ�ʐl�ł���ԗ������₷���b���Ǝv���̂́u�Ⴆ�A�j�R����300mmF2.8��D700��E-3�ɕt������ǂ��Ȃ́H�v���Ęb���Ǝv���܂��B
���_�Ƃ��Ă͂����Ȃ�܂���ˁH���i�O�҂�D700�ɑ������E��҂�E-3�ɑ������j
�@�œ_�����@�@�@�@�@�@300mm�@�@�E�@300mm
�A��p�@�@�@�@�@�@�@�@8.2�x�@�@�E�@4.1�x
�B�J���ł̔�ʊE�[�x�@300mmF2.8�E�@300mmF2.8
�C�V���b�^�[���x�@�@�@���Ґݒ肪�����Ȃ瓯��
�܂�E-3�Ƀj�R��300mmF2.8�������ꍇ�A�w�t�B�����Ŋ��Z600mm�����̉�p��F2.8�x�Ƃ����̂͊ԈႢ�Ȃ����Ƃł͂���܂��H�Ǝ��͎v���܂��B
�V���b�^�[���x�������Ȏ��_�ŁAF2.8��F2.8�ȊO�̉��҂ł��Ȃ��ł��B
�����Y�̌`���f�q�̃t�H�[�}�b�g�ɂ���ď���ɕό`����킯�ł��Ȃ��̂ɁA�Â��Ȃ�͂�����܂����ˁB��ʊE�[�x�����āA�t�B�����ŁiD700�j�Ɖ���ς���ĂȂ����Ⴀ��܂��B�ς�����̂́w��p�x�݂̂ł���ˁB
�Z���JGT-Four-A��������y����Ă��܂����A�|�[�g���[�g���ʖт����Ƀs���g�����킹��Ƃ��Ȃ�Ƃ������A�����ƕ��ʂ̎g�����Ȃ�t�H�[�T�[�Y�̃{�P�ŏ\�����ȂƎ��͊����Ă��܂��B�u�w�i���ڂ������ʐ^���B�肽���̂Ȃ�t�H�[�T�[�Y�̓{�c�v�Ƃ����b���ǂ��o�܂����A�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�g���ă{�P�ʂ�����Ȃ����炢�̍�i���B���Ă�������ăA�}�`���A�łǂꂭ�炢����̂��ȁH�Ə����ɒm�肽���ł��B���͂���Ȏʐ^�����̌f���Ō������܂��E�E�E�B
�ǂ���������������ŁA���ۂɃJ�����������ĊO�ɏo�����Ă���l�����Ȃ��C�����ĂȂ�܂���B�g���Ε�����͂��Ȃ̂ɁA�c�O�ł��ˁB��Ȃ̂́w�����ɂƂ��Ė{���ɕK�v�Ȕ�ʊE�[�x�͂ǂꂭ�炢���H�x�ł����āA�ςȐl�����Ɏg���������Ɂu�t�H�[�T�[�Y�̓{�P�������Â��v�ƕs�v�c���_������������͂���܂���B
�Ō�ɁA�ق��ł���150mmF2.0�ŎB�e�����ʐ^��\�点�Ă��������܂��B
�����A�J���i�肾�ƃ{�P�����Ď��̘r�ł͈�������Ȃ����Ƃ����邭�炢�A��������Ƃڂ��܂��B150mm�Ƃ��Ă͈ٗl�ɏd���C�����܂����A�`�ʂ�����Δ[���̑f���炵�������Y�ł��̂ł����g���ė~�����ȂƎv���܂��B
�����ԍ��F10144323
![]() 9�_
9�_
>�����A30M��f�t���T�C�Y�̃J�����Ƃ��A���̂����ɔ��������Ǝv���܂����A�t�H�[�T�[�Y�ł͂��̂悤�ȍ���f�J�����͎����ł��܂���B
���݂܂���A�v�Z���Ă݂���A���E�̐�����������ƈႢ�܂����B
�����͐�Βl�ł͂Ȃ��u�t�H�[�T�[�Y�̕����𑜂̌��E�͒Ⴂ�v�Ɠǂ�ł��������Bm(_ _)m
�����ԍ��F10144341
![]() 0�_
0�_
�䂽����
�������������Ă���Ԃɓ��e���A�A�A�Q��܂���(^^;
���J�ɂ��݂܂���B�������Ă���Ƃ́i�����j�v���Ă܂����� ^^;
���œǂl�����Ⴂ���Ă�����̂ŁA���ߓ���Ă݂܂����B
�킽���Ȃ����n�I�^�N�Ȃ�ŁA���������݂����Ă��܂��܂��B^^;
�d���͌��w�Ƃ͑S�R�ʂ̕���ŁA�܂����ꂱ���u��v�̐��E�ł��ˁB
���w�̐��̐l��������₷�������Ă����Ɩ{���͗ǂ���ł��傤���A�d���Ō��w������Ă���l�͂ǂ����Ă�����b�ɂȂ��Ă��܂��C�����܂��B
����ς�w�Z�̐搶�͏�肢�l�������Ǝv���܂��B�i��肭�Ȃ��l�����č��邱�Ƃ�����悤�ł��� ^^;�j
�����ԍ��F10144393
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���
���L���������܂��I�I
�����́A����āA������Ɨ����o���Ă��܂��A���������悭�ǂ�ŁA
�����Ȃ�ɗ������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�t�H�[�T�[�Y�͎B���f�q������������掿�������Ǝv��ꂪ���Ȃ̂ł����A
�������Ă��[���掿���ǂ��Ȃ�悤�Ɋ撣���Ă���Ƃ������Ƃ�������܂����B
�܂�A�����ē���ۑ�ɒ��킵�Ă���Ƃ������܂��ˁB���ꂱ���A
���{�̕����ł��B�I�����p�X�͂Ƃɂ��������܂��߂ȉ�Ђ��ƌ������
�ł����A�u��邶��Ȃ����A�t�H�[�T�[�Y�I�I�v�Ɖ����������Ȃ�܂��ˁB
�����܂ŁA�^�ʖڂɃf�W�^��1��̊���������ƍ��o���Ă���̂�����
�����ƕ]��������Ă��ǂ��悤�Ɏv���̂ł����E�E�B
�����́AMF��OM���g���AAF�����Nikon���g���Ă��܂����B�̂�Nikkor�̃����Y
�����{�������Ă����̂ŁA���̗����D300�֎��R�Ɨ��ꂽ�킯�ł��B
�I�����p�X�����ɂ͂������̂ł����AAF�����܂�ǂ��Ȃ��Ɗ����Č�₩��
�O�����̂ł����AD300�̃S�~����̌�����ɂ��A�I�����p�X�́A���͂�
�S�~��葕�u������A���[�U�̓S�~����S���ӎ����Ă��Ȃ��ƌ������Ƃ�
�m��A���������������܂����B����ɁA��Ԃ̌��_���Ǝv���Ă���AF��
E-3��AF�̕]�����������ŁA��x�́A�g���Ă݂悤�Ǝv���n�߂��킯�ł��B
����ɁA�A�[�g�t�B���^���ʔ��������ƌ������ƂŁA�}�N���̈��
�I�����p�X�ł���Ă݂邩�Ǝv���A50mm �}�N����E-30�̍w���Ɏv����
�܂����B���R�A���̎���Nikon�̃����Y���Ηǂ������Ǝv�����̂ł���
OM�͑�D���������̂ŁA�I�����p�X��DSLR����x�����Ă݂����Ƃ����z����
���������Ă��܂����̂ł��B
�g���Č���A�掿�������Ƃ����̂͞X�J�ł������Ɗ����Ă��܂��B
���̌�A14-35mm F2.0���v�����Ĕ��������Č��݂Ɏ����Ă��܂��B
�������A�t���T�C�Y�̃����Y���g���ƃ����Y�̐^���g����̂ł��ꂢ
�Ɏʂ���Ƃ������Ƃ������Ă��܂������A�����Ē�����MTF�̓����̗ǂ�
�Ƃ���Ǝ����̏��Ȃ��Ƃ�����g���Ă��邾���ŁAFX�t�H�[�}�b�g�̃����Y
��D300�ɑ������Ă��𑜓x�̖ʂł͕s���Ȃ��Ƃ͕ς��Ȃ��Ƃ������ƂȂ�
�ł��ˁBDX�t�H�[�}�b�g�����Y�Ƃ����ƁAMTF������1.5�{�ɂȂ��Ă���̂�
�Ǝv�����̂ł��������ł��Ȃ������ł��B
�ł�APS�ł����ꂢ�Ȏʐ^���Ƃ�܂���ˁB�������s�v�c�Ȋ����ł��B�v�́A
�t���T�C�Y�́A�B���f�q�������Y�̐��\���E�܂Ŏg�����Ă��āAAPS��
�t�H�[�T�[�Y�̓����Y�̐��\�̕����܂������Ă���Ƃ������Ƃł��傤���B
���A�l�ŁA�����̊��o��M���Ďg���Ă����Ă��A���v�������Ƃ�����������
������܂����B�L���������܂��B
�ǐL�F
150mm�̎ʐ^�L���������܂��B����Ȃ̂��݂�Ƃ܂��܂����ꂪ�����Ȃ���
���܂��܂��B�����ł���˂��E�E�B���̃����Y���g���邾���ł��t�H�[�T�[�Y
���g�����l�������Ȃ����Ǝv���Ă�����ł��E�E�B
�����ԍ��F10145287
![]() 4�_
4�_
��ʊE�[�x�������[���Ȃ��āA���邳�͕ς��Ȃ��ȂǂƂ����s���̂����V�X�e���́A���蓾�Ȃ��B
�{���ɂ����������̂����݂���ƐM����̂́A�e�l�̎��R�����B
F�l��傫������ƁA��ʊE�[�x���[���Ȃ�B
��ʊE�[�x��[������ɂ́AF�l��傫������B
�ʐ^�̐��E�ł́AF�l�����������Ƃ��u���邢�v�ƌ����AF�l���傫�����Ƃ��u�Â��v�ƌ����B
���̂ق��̌������́A���������Ƃ��Ȃ��B
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̖ʐϔ�́A��4�B���Z���̌W���́A���̕������ł����2�B
�t���T�C�Y��4×5���̖ʐϔ�́A��14�B���Z���̌W���́A���̕������ł����3.73�B
�����������킩��A�傫�������킩��B�傫�������킩��A�����������킩��B
�t�B�����̏ꍇ�A���x�������Ȃ�A�t�H�[�}�b�g���傫���Ȃ�A�𑜓x���オ��B
�f�W�^���������i�f�W�^���̏ꍇ�́A�u�𑜓x���グ����v�j�B
�Ⴄ�t�H�[�}�b�g���m�ŁA�u�����������x�v�u�����𑜓x�v�̎����͗����s�B
�𑜓x���ɂ��悤�Ƃ���A�������x�������邵���Ȃ��B
���x�\�����ɂ��悤�Ƃ���A�Q�C���E�A�b�v���邵���Ȃ��B
�������A�e�Г����Z�p�����ɂ���Ƃ����O��B
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y���ׂ�̂́A�e�����Ƒ������r����悤�Ȃ��́B
�e�������������A�����n�������A�����͈قȂ�B
�������قȂ邱�ƂƁA�u�e�����ɂ����@�L��△����v�́A�܂������ʂ̖��B
�B�l�Ƒf�l���������A�e�����ł��\�����Ă邾�낤�B
�u�����͗��h������D�����v�Ƃ����l������A�u�����͑�U�������猙�����v�Ƃ����l�����邾�낤�B
�����ԍ��F10145411
![]() 3�_
3�_
�݂Ȃ���
�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��͂����肵�Ă���
�����B�䂽���璸���������́A�u�G�̋�̗ʁv�܂�A���ʂ�
��`�ɂ́A�܂��A�s�����������邯��ǂ���p�ƃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�A
�œ_�����̊W�ɂ����đ����`������A���Z�Ƃ����̂������̕ϊ���
�l����Ηǂ��Ƃ������Ƃ́A��ς悭�킩��܂����B�܂��A�œ_������
���a�ɂ����F�l�����肳���ŁA�����̒P�ʂ�ϊ����čl����A
�u�t�H�[�T�[�Y150mm�́A�t���T�C�Y�̉�p��300mm�Ɠ������B�������A
�@150mm F2.0�͂����܂ł��œ_����150mm�ł���A�����I��300mm�̏œ_
�@�����ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�����Ƃ����\�����̕ϊ��ƒ�`����ƁA
�@���̃����Y�́A�t���T�C�Y300mm F2.0 �w�����x�ɂȂ�B�v
�Ƃ������Ƃł��ˁB���̂悤�ȗ����Ő������ł��傤���B���Z�̊��
�ړx�͐F��Ȍ���������܂����A�����̒P�ʂ�ϊ����邱�Ƃ��P����
������₷���A����������悤�ɂ��v���܂���B
1-300���܂��������ɂȂ��Ă��邪�A�^���̎咣�̖{���ł���悤�ȋC��
���ė��܂����B���ϓI�ɂ́A�����Ȗʐςʼn摜����邱�Ƃ��s���ł���
���Ƃ́A�t�B��������̃u���[�j�[�A35mm�A110�̔�r�ŗe�Ղɗ����o��
�܂��B�t�H�[�T�[�Y�͂��̕s���Ȗʂ������ł��������ׂ��A�Ƃɂ��������Y
���撣�点��Ƃ����v�ɂȂ��Ă���Ɓi���́j�����ł��܂����B
ISO���x�̖ʂ����̒ʂ肾�Ǝv���܂��B�̂̋≖�ōl���āA�uISO400��35mm
�t�B������ISO100��110�t�B�����ɒu��������ƁA�t���T�C�Y��ISO400��35mm
�t�B�����ŁA�t�H�[�T�[�Y��ISO100��100�t�B�����ł���B�ǂ�����AISO400��
�B�e�����āA110�̃t�B�����͌�������ISO400�ɑ�������B�v�Ƃ������Ƃ���
�ł��傤���B
�^���̎咣��P�ӓI�ɉ��߂��Ă݂�ƁA1-300���܂��������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�
�قƂ�Ǖς��Ȃ��l�ȋC�����܂��B���̂悤�ɕ�����₷�������͂���܂���
�ł������E�E
�͂炽����̃R�����g�ł�������Ă��܂������A�ǂ����A���ꂩ��
��̋c�_�ɂ̓����Y�����̋c�_�Ƃ���������O���������ǂ������ł��ˁB
���̌�́A�B���f�q���܂߂āA�t�H�[�T�[�Y�V�X�e���S�̂ŁA������������
�ƍK���ł��B
�����ԍ��F10145613
![]() 1�_
1�_
�ǂ����Ă�F�l���T���̂Ȃ�AF�l�ɂ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�t�H�[�T�[�Y�́A�����I�Ƀt���T�C�Y��1/4�̌��ʂōςނ̂�����A�t���T�C�Y��1/4�̌��ʂ�����荞�܂Ȃ������Y���g���Ă���ƍl����悢�B
������u�Â��v�ƌ����l�́A�����������낤�B
�Â��ď\��������A�Â������Y���g���Ă���B
�t�H�[�T�[�Y�ŁA�t���T�C�Y�Ɠ������ʂ���荞�ރ����Y�����̂́A���ʂ������Ƃ��낾�B
�������A��ʊE�[�x���ɂ��悤�Ƃ���A��������K�v�����邪�A�����Ă����܂ł���̂Ȃ�A�t���T�C�Y���g���悢�����̘b�B
�����ԍ��F10145732
![]() 5�_
5�_
1-300����
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̃m�C�Y�̈Ⴂ�̗��R����f�s�b�`�ł���Ȃ�A����́u���ZF�l���_�v�ł͂���܂���B
���ZF�l���_�̏ꍇ�A��ʃT�C�Y�����Z���܂��̂ŁA��f�T�C�Y�́u���Z���T�C�Y�v�ɂȂ�܂��B
���Z���T�C�Y�̉�f�Ŋ��ZF�l���Q�{�Ȃ̂Ńm�C�Y���Q�i�������o��̂��A���ZF�l���_�̃L�����Ǝv���܂��B
�㔼�ł́A�ꌩ��f�s�b�`�𑵂��Ĕ�r���Ă���悤�ł����A��f�������s�Ȃ����ƂŁA�����I�ɉ�f���𑵂��Ă����r���Ă��܂��̂ŁA�O���Ɠ��l�ł��B
�܂�1-300�����̒��ɕ`���Ă���`���͊��ZF�l���_�ł͂Ȃ���ł��B
���̃X�e�b�v�ׂ̈ɁA���ZF�l�����ɗ����Ȃ���ʂ���グ�Ă����܂��B
50mmF2.0��100mmF2.0�̃����Y���ǂ�����t���T�C�Y�J�����ɂ��܂��B�ǂ��炪���邢���A�ƍl����Ƃ��ɓ�����O�ł����A���ZF�l�͖��ɗ����܂���B
���ʂ�F�l�ƃZ���T�[�T�C�Y�ɕ����čl�����ق����A�ȒP�œK�p�͈͂��L���A���ۂ�f���ɕ\���Ă���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10146283
![]() 2�_
2�_
��50mmF2.0��100mmF2.0�̃����Y���ǂ�����t���T�C�Y�J�����ɂ��܂��B�ǂ��炪���邢���A�ƍl����Ƃ��ɓ�����O�ł����A���ZF�l�͖��ɗ����܂���B
���Z����K�v���Ȃ���ʂȂ̂ŁA���ɗ��Ƃ��A�����Ȃ��Ƃ��̖��ł͂Ȃ��B
50mmF2.0�̉�p��100mm�Ɠ����ɂȂ�悤�Ƀg���~���O����A100mmF4.0�̃����Y���g���Ă���̂Ɠ����A�Ƃ������Z�Ȃ�\�����B
�Z���T�[�̋Z�p�������ŁA�t���T�C�Y��2000����f�A�t�H�[�T�[�Y��500����f�Ȃ�A�P���ȗ����̏�ł̃m�C�Y���x���͓����ɂȂ�B�������x�������ɂȂ�B
�����A���̓�̃J�����̂ǂ����I�Ԃ��A�^���ɔ�r��������l�͏��Ȃ����낤�B
�������A���̘b�́A���ZF�l�̘b�Ƃ͈Ⴄ�B�������A�܂��������W�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�ǂ�����t�H�[�}�b�g�̑傫�����痈��b�Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F10146837
![]() 2�_
2�_
�X���傳�܂͂���߂đ����Ŕ[�����Ă�����悤�ł�����A������
�����܂ł��Ȃ��b�Ȃ̂ł����B
�e�l�̘b�Ǝ��ʊE�[�x�̘b�͕ʂ̘b�ł��B
�����œ_�����W�O�~���̃����Y�łR�T�~���t�B�����̂e�Q�ƂU�S�T�̂e�Q
�ł͉�p���Ⴂ�܂��B������������B��U�S�T�̂ق����L���ʂ�܂��B
���̉�ʂ���g���~���O�����ꍇ�A�R�T�~���t�B�����Ɠ����͈͂��g���~
���O������͈̔͂ł̎��ʊE�[�x����p������ɂȂ�ł��傤�B�ł��A
�U�S�T�̃����Y�̕����𑜓x�͒Ⴂ�ł�����A���Ƃ��ƂR�T�~���t�B����
�p�̃����Y�ŎB�����ʐ^�̕��������s�Ȃ͂��ł��B
���̂Q�̃t�H�[�}�b�g�œ�����p�ɂȂ郌���Y��p�ӂ���Ȃ�A�U�S�T
�̂ق����œ_���������������Y�ɂȂ�܂��B���������e�l�̃����Y��p��
�ł���Ȃ�A�J���ŎB���ׂ�U�S�T�̂ق������ʊE�[�x�͐ł��B
�ł��A�ǂ���������e�l�ł��ˁB
���R�A�����e�l�œ������ނł���A�V���b�^�[�X�s�[�h�����ɂ��ēK��
�I�o�ł��B����ł��ʐς��R�{��������܂�����A�����Y��ʂ��Ă���
���̗ʂ͂U�S�T�̂��̂̂ق����R�{���������͂��ł��B����ł������
�u�e�l���傫���v�Ƃ͌����܂���B������O�ł��B
�t�B�������ƃN���A�ɗ����ł��邱�Ƃł�����A���ꂪ�b�b�c���̎B��
�f�q�ɂȂ����Ƃ���Řb�͕ς��܂���B�����t�B�����̘b�ł������ł�
�Ȃ��Ƃ����̂ł���A����͂��̐l�̗���̘͂b�ł����āA�t�H�[�T�[
�Y�Ƃ����K�i�����r�̖��ł͂���܂���B
�����ԍ��F10147517
![]() 5�_
5�_
�{�X�g�[�NT-233����
���݂܂���B���̃X�����o�����o�܂�m��Ȃ��l�ɂ͕�����Ȃ��������݂ł����B
��ʊE�[�x��{�P�ׂ̈�F�l�����Z����̂́A�܂��ǂ��Ƃ��āA����́u�Â��v�Ƃ����\���ɒl���邩�B
�Ƃ����̂��Ƃ肠�����̖��ł��B
F�l�͖��邳�̖{���ł͂Ȃ��A���ZF�l�i���a�j�������{���ł���B�Ƃ����������݂����������߁A�������܂����B�i���̌�ǂ����邩������܂��j
���ZF�l�i���a�j�őS�Ă��ȒP�ɐ����ł���B�Ƃ����_���ł����̂ŁA�����Łu���ʂ̗����̕����ȒP�ŕ֗�����v�Ə����Ă݂܂����B
�����ԍ��F10147608
![]() 3�_
3�_
�u35mm����菬�����Ȃ���������l������_�ł��v�Ƒ������Ă����l�́A�傫�����̓�������������A�ǂ����ɏ����Ă��܂����B
�����̃����c����邽�߂ɉ�����̂��������ӂȐl�����̈ӌ����A���ꂩ��^�ʖڂɎʐ^������悤�Ǝv���Ă���l�������L�ۂ݂ɂ�����ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ́A�l�������Ȃ��̂��낤�ȁB
���������l�́A���̒��A�{���ɑ����B
�����ԍ��F10148416
![]() 4�_
4�_
>�傫�����̓�������������A�ǂ����ɏ����Ă��܂����B
�����ɓ���������܂����B������Ɖ��Ă��������B
��N��������͈ȉ��̂Ƃ���B
���y35mm�������܂��܊�ɂ���悤�ł��ˁB����Ȃ�f���܂��B
�����ގ��i�ɋ߂��j��ISO 100�̃t�B�������x�[�X�Ƃ���������r��̕ϓ��v�f�����Ȃ��ł��傤�B
�i�f�W�^���ł̓t�H�[�}�b�g���Ƃɉ\�Ȍ��葍���I�ɍœK�������X��������j
�唻�̃V�m�S(4×5�j��35mm���̖ʐς̔{15�{�ƂȂ�܂����A�z����́u���ZF�l�v�͂ǂ̂悤�ɂȂ�܂����z
�����ԍ��F10148484
![]() 2�_
2�_
[10145411]�ŏ��������Ɓi�ȉ��A3�s�j
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̖ʐϔ�́A��4�B���Z���̌W���́A���̕������ł����2�B
�t���T�C�Y��4×5���̖ʐϔ�́A��14�B���Z���̌W���́A���̕������ł����3.73�B
�����������킩��A�傫�������킩��B�傫�������킩��A�����������킩��B
����́A
35mm���@24×36mm=864mm2
4×5���@99×122mm=12,078mm2
�ʐϔ�13.97916666�E�E�E��14
���̕�����3.7388723�E�E�E��4��
�������ގ��i�ɋ߂��j��ISO 100�̃t�B�������x�[�X�Ƃ���������r��̕ϓ��v�f�����Ȃ��ł��傤�B
�i�f�W�^���ł̓t�H�[�}�b�g���Ƃɉ\�Ȍ��葍���I�ɍœK�������X��������j
�����́A�Ӗ����悭�͂߂Ȃ������B
�f�W�^���ł͂Ȃ��āA�t�B�����ōl����A�Ƃ������Ƃ��B
�����������Ƃ���A���ʂ͓����Ȃ̂ŁA���̕K�v�������Ȃ��B
�����ԍ��F10148584
![]() 2�_
2�_
���݂܂���A������Ɖ����玸�炵�܂��B
���ʂ̒�`�ʼn���������܂��ɂȂ��Ă���Ƃ��낪����悤�Ȃ̂ŏ�������Ō��܂����B
�����Y�Ƃ����̂͂����_���甭�U���������œ_�ʂɌ�����������ʂ�����܂��B
���̈�_����ł�����ǂ̂��炢�W���ł��邩�Ƃ������\���������̂������Y�̊J�����i�m�`�j�ł���A�������ł͂m�`�A�J�����ł͂e�l�A�]�����ł͌��a�ɒu�������Ďg���܂��B
���̂e�l�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�i���C���[�W�T�[�N���j�Ƃ͑S���W����܂���B
���ʂ̒�`�Ō����A�e�l�œ����閾�邳�́u�Ɠx�i���N�X�j�v�A�C���[�W�T�[�N���S�̖̂��邳�̓����Y���̂������Ƃ���u�����i���[�����j�v�ƌ��Ȃ��čl���������Ȃ����Ǝv���܂��B
�i�����Y����o�Ă�����������d���ɒu��������A�œ_�ʂŏƂ炳��Ă���P�ʖʐς�����̌��ʂ��Ɠx�ŁA�����Y����o�Ă�����̑��ʂ������ł��j
�Ⴆ�Γ����e�l�̑唻�����Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̃����Y������Ƃ���ƁA������ʑ̂������������Ƃ��̏Ɠx�͑S�������ł����A�����͑唻�����Y�̕������{���傫���A�Ƃ������Ƃł��B
���邢�A�Â��Ƃ����̂͂��̂ǂ���̒�`���g�����ňقȂ�܂��B
�ʐ^�̏ꍇ�A���邢�A�Â��̘b�������ŋc�_���邱�Ƃ͂܂��Ȃ��ł��傤�B
�ԈႢ������w�E���肢���܂��B
�����ԍ��F10148682
![]() 10�_
10�_
���͌v�Z�����̂����킯�ł͂���܂���B
�ʐϔ��F�l�ɂ��肩����A���̂��߂̕X�I�v�Z���Ȃ�N�ł��v�����ł��傤�B
���̌v�Z�����͕̂����Ƃ��Đ������Ƃ��Ă��A��_���̂��̂����������Ƃ̏ؖ��ɂ͂Ȃ�܂���B
�����̂��Ƃł��B
35mm��F4�Ɍ������V�m�S�̑z����̊��ZF�l�͂����ɂȂ�܂����B�iISO100�͋��ʁj
�����̂ݏ����Ă��������B
�����ԍ��F10148762
![]() 9�_
9�_
�����̂e�l�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�i���C���[�W�T�[�N���j�Ƃ͑S���W����܂���B
���̂Ƃ���B
������W�����悤�Ƃ���A���Z�̘b���o�ė���B
���̘b�ɂȂ����ȏ�A���Z�ɂ���Ă��荇�킹��F�l���m���ׂāA�u���邢�v�Ƃ��u�Â��v�Ƃ������b�ɂȂ�B
�ʐ^�̗p��ł́AF�l�̂Ƃ��́A�u���邢�v�u�Â��v���g���B
�u�ʂɂ��̘b�͂��Ȃ��Ă��悢�v�Ƃ�������́A�������B
�����A�m���Ă����đ��͂Ȃ��Ǝv���B
�Ɠx�͘I�o�̘b�Ɍq����A�����͉𑜓x�̘b�Ɍq����B
�����ԍ��F10148769
![]() 2�_
2�_
��35mm��F4�Ɍ������V�m�S�̑z����̊��ZF�l�͂����ɂȂ�܂����B
�������ɂ��ꂮ�炢�́A�����ōl���ė~�����B
�����ԍ��F10148790
![]() 1�_
1�_
��͂�A���݂��Ȃ��悤��F�l�������Ȃ��ł��傤�B�O��_�ł�����B
�H�Ɛ��i�ɖ��L�����F�l�ƈقȂ鍪���s����F�l�����s���Ă������������邾���ł��B
���͍T���߂ɏ����Ă��܂����@�V�m�S���傫�ȃt�H�[�}�b�g�����݂���킯�ł���B�i��
�����ԍ��F10148881
![]() 12�_
12�_
�͂炽 ����A�݂Ȃ���A�����́B
���t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̃m�C�Y�̈Ⴂ�̗��R����f�s�b�`�ł���Ȃ�A����́u���ZF�l���_�v�ł͂���܂���B
���܂�1-300�����̒��ɕ`���Ă���`���͊��ZF�l���_�ł͂Ȃ���ł��B
�@���������Ȃ̂ł���A������Ǝc�O�ł����B�i�������݂��܂Ƃ߂�̂ɁA�����������\���ڂ�܂����B�Ȃ�Ƃ��N�C�Y�ŕs�����ɂȂ����悤�ȋC���ł��B�j
�ǂ����������ňႤ�ƌ����Ă���̂��A�������Ȍ��ɏ����Ă�����Ă��܂����A
�܂��A�c�O�Ȏ��ɗ��n�I�^�N�ł͂Ȃ����ɂ͊Ȍ������ė����ł��܂���B
�������炷��ƁA�u���ZF�l���_�v�����Ȃ̂���������Ă���悤�ł����A
�����A�����Ԃ̂��鎞�ł��������ł�����A���̐��������킹�Ă�������������Ă���������Ƃ��肪�����ł��B
��50mmF2.0��100mmF2.0�̃����Y���ǂ�����t���T�C�Y�J�����ɂ��܂��B�ǂ��炪���邢���A�ƍl����Ƃ��ɓ�����O�ł����A���ZF�l�͖��ɗ����܂���B
�@�T�ⓚ�̂悤�Őݖ�̈Ӑ}��������܂���B
�@�܂������̉��߂��Ԉ���Ă���Ƃ������o�������̂ŁA������Ɠقǒlj����Ă����܂��B�@�u�E�E�E�E�𑜓x�A�傫���@�������ʐ^���E�E�E�E�v
�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
�i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
�@�Ԉ���Ă��Ⴞ�߂����ǁA���̊W����������i���ɂ́j���������֗��Ȃ�ł���B
�����ԍ��F10149055
![]() 0�_
0�_
�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
�i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v
�������i��f�������A�Z�p���x�������A�̑O��Łj�B
1-300����́A���Z�̍l������������Ɨ������Ă���i�ȂǂƏ����̂́A�G�z������ǂ��j�B
�킩��ƁA�u�֗��v�B
�����ԍ��F10149137
![]() 2�_
2�_
�@
�@�ʉ�y ����A�����́B
�����炷�݂܂���A�uF�P�S�v�ł��B
���Č�������{��܂��H
�@�{�X�g�[�NT-233 ����A
������A�����ł����H
�����ԍ��F10149247
![]() 2�_
2�_
�����́A�ʂɂ�����͂��܂��E�E�E
�P���ɖʐϔ��F�l�Ɍ��т�����_�i�����ɂ�����i�K�ŒN�����̐��������ؖ����Ă��Ȃ��j
�ɂ��܂ł��t�������C�͂���܂���B
�b�͐U��o���ɖ߂��������ł��B
����35mm������Ƃ��ĕX�I�Ɂi�����j�ʐ�16�{�̃t�H�[�}�b�g�iISO100�͋��ʁj������Ƃ��āA
���̑z����̊��ZF�l�́A
35mm����F�l���4�i���邢�Ƃ����咣�ł͂Ȃ������ł����B
�i1/4��2�i�Â��Ȃ�j
F14�Ƃ������Ƃ͋�_�Ƃ͕ʂ̌����ł���Ƃ������Ƃł��傤���B
�����ԍ��F10149496
![]() 6�_
6�_
�������ɂ���o���Ă݂���c
��̓�l�͂��Ȃ����ǁA����ς��l���܂����ˁ`�B
�f�W�^���]�̂��o�J���c�B
�t�B�����ł͂ǂ�����ăQ�C���A�b�v���Ă��ł����ˁ`�H
6×7�A6×6�A6×4.5�B
�����t�B�������g���ē����I���������܂����B
���������瓯���I�o�ł����B
�f�W�^���ł͕s�v�c�Ȏ�������Ă��ł��ˁ`�B
>�ʉ�y����
�����Ɓc8×10���ƁA������F0.�����ɂȂ��Ȃ��ł����H
�����v�Z�ł��Ȃ��ł��i�j
�����ԍ��F10149692
![]() 4�_
4�_
����H�ԈႦ���I�t�ł����B
�Â��Ȃ��ł����ˁi�����j
F45�H�i�����ł��������H�j
���`�A��₱����(*_*;
�����ԍ��F10149741
![]() 3�_
3�_
1-300����A�����́B
> �c�uF�P�S�v�ł�
�Ȃt�ɍs����������݂����ł��ˁB���ꂾ��4×5����35�~���T�C�Y���u3�D5�i�Â��v���ƂɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
����͂Ƃ������A�f�p�Ȏ��₪����܂��B
> �u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
�i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
��G�c�ɂ͊m���ɂ��̒ʂ肾�Ƃ͎v���܂����A
���ꂪ�ǂ�Ȏ��Ɂu�֗��v�Ȃ̂��A���ɗ��̂��A�z�������܂���B��낵��������ĉ������B
�{�X�g�[�NT-233����ɂ���������ł��B
���ɁA��ŏ�����Ă��܂���
> ���ꂩ��^�ʖڂɎʐ^������悤�Ǝv���Ă���l����[10148416]
�ɂƂ��āA���邢�́A�ʐ^��J�����̏��S�҂ɂƂ��āA
�ǂ��֗��Ȃ̂��A�ǂ����ɗ��̂��A�����ĉ������B
�����ԍ��F10149753
![]() 2�_
2�_
1-300����
>�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
>�i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
�͂��A�����ł��B���������܂���B
1/4�̃Z���T�[�T�C�Y�̃t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y�Ɠ������o�ň������Ƃ���ƁAF�l��2�i���ɂȂ�܂��ˁB
���Ȃ̂́u�����Ȃ闝�R�v���l����Ƃ��ł��B
�m�C�Y�̌������u��f�T�C�Y��1/4�v������A�Ƃ����ۂɂ́A�t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y�̖ʐς�1/4�̃Z���T�[�T�C�Y�ŁA�܂芷�Z���Ȃ��ōl���Ă��܂��B�����������ŁA�Â��Ȃ�܂���B
���鐯���߂炳��̏������݂́u�����Ȃ闝�R�v���l���鎞�܂Ŋ��Z���Ă���悤�ɓǂ߂܂��B
���̕ӂ��A1-300����Ƃ��鐯���߂炳��̈Ⴂ�ł���A���鐯���߂炳��̏����݂����̐l��蕴�����錴�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10150069
![]() 2�_
2�_
�ʉ�y ����A����͎��炵�܂����B�����Ȃ�Ȃꂵ�߂������ȂƎv���܂��B
�@���̃X���b�h��ǂݕԂ��Ă݂��̂ł����A���������u��_�v�̋�̓I���e�����������邱�Ƃ��o���܂���ł����B
�������A���Ԃ�u��_�v�Ǝ��̌����Ă��鎖�A
�@�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10141193/#10144284
����͓��������Ǝv���̂ŁA����ɓ��Ă͂߂ď����Ă݂܂��B
�@�@�@35mm���@24×36mm=864mm2
�@�@�@4×5���@99×122mm=12,078mm2
�@�@�@�ʐϔ�13.97916666
�@�@�@���̕�����3.7388723
�u�V�m�S��35mm������
3.7�{�̏œ_�����̃����Y��3.7�iF�l��傫�����ĎB�e���A3.7�i���̑��������������
�i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���B�v�@
F4����3.7�i�i����F14�A
�@�@
�����ɓ��Ă͂߂�Ƃ����������ƂɂȂ�܂��B
�������@3.7�i�̑����������ăR���g���X�g�͍d���Ȃ邾�낤���A���q���̕ω���������f�W�J���̍����x�m�C�Y�Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ���낤�Ǝv���܂��B
���ۂɂ́u������v�u�Z�p�̍��Ō덷����v�̃��x���ł͂Ȃ��ł��ˁB
�t�C������ISO1250�̕��ɕς��������܂��悢��������܂���ˁB�i���������`�F�X�^�[�ɓ��������ǁj
�@��̓I�ɍl���Ă����Ƃ��̗����i�u��_�v�̕��ƌ������@�������߂������ł����j��
�t�C�����̑������̓f�W�J���ƈ���āA�Q�C���ƃm�C�Y�����łȂ������������Ȑ��̕ω����̂ŁA
���ɃT�C�Y�̑傫���قȂ�t�C�����t�H�[�}�b�g�Ԃɂ͂��܂�K�p���Ȃ������悢�l�ȋC�����Ă��܂����B
�@���̗����̓Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴄ�����̃J�����̃g�[�����ʊE�[�x�𑵂����肷�鎞�̂�������Ƃ����ڈ���̂Ɍ��\�֗����Ǝv���Ă���̂ł����B
�����������ʂ���l���Ă��A35mm���ƃV�m�S�œ����ʐ^���B���V���`�G�[�V�����������Ă���Ƃ����N�ł��m���Ă��邱�Ƃ�����@���̗����ɂ͂�����Ȃ��Ώۂł��ˁB
��{�A�u35mm���ŃV�m�S�Ɠ����ʐ^�͎B��Ȃ��v�@������O�̎��ł����B
�@���̂�����̂��Ƃ͂�����x�悭�l���Ă݂܂��B
�@�J���N��������� ����A
�@
�u�t�H�[�T�[�Y�V�X�e���͓������邳�ŁA������p�̃����Y��1/2�̑傫���ō���i�t���T�C�Y�j�v�Ƃ����A
�܂��A�����������������Z�[���X�g�[�N�Ƃ��Ă͗L��̂�������Ȃ����ǁA�܂�ŘB���p�̂悤�Ȃ��̌��t�����Ŕ[�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ��A
�u�ł��A�����g���[�h�I�t�Ŏ����Ă�����͖̂������ȁH�v�ƍl�����肷�鎞�ɂ��֗��Ƃ������q���g�ɂȂ�悤�ȋC�����܂��B
���ۂɂ����ȋ@�ނ��g������ł���l�͂����������_�������Ă��A�o���I�ɒm���Ă��鎖���ł��傤���ǁB
�@�͂炽 ����A�܂���X�������Ă��܂��܂����B
�@���鐯���߂炳��́u�Â��v�u���邢�v�ӂ��̓��{��Ŏg����Ӗ������ł͎��܂肫��Ȃ��̂ŁA����ł��B
�����ԍ��F10150514
![]() 2�_
2�_
�g���[�h�I�t�B�����Ȃ�ł���ˁB�Ȃɂɂ���A��������̂Ǝ�������
������B
�œ_�����Q���̂P�Ōy���Ĉ����Ď��ӌ��ʂ��o�b�`���o��t�H�[�T�[�Y��
�u�{�P�Ȃ��v�Ƃ����u�����v������i�|���ł���A��A����Ȃ���)�B
�܂�A�{�P�Ȃ��ƍ���l�ɂƂ��Ắu���v�����ǁA�{�P�Ȃ����������l
�ɂƂ��Ắu���v�Ȃ�ł��B
�u�掿�������v�͂��̃V�m�S���g���Ă���l�����Ȃ��̂��A�u���v������
�u���v�����邩��ŁA�������Ƃ̓t���T�C�Y�ɂ�������킯�ł��B
�����ԍ��F10150668
![]() 10�_
10�_
�ׂ�������� �~�C����肪�~�C���ɂȂ��Ă܂���B
�����Ԉ���Ă܂������A�u�Q�C���A�b�v�v�͎��̖{���ł͂���܂���B
�t�H�[�T�[�Y 500����f 150mm F2.0�A�t���T�C�Y 2000����f 300mm F4.0 �́A
���m�ɂ�
�u�t���T�C�Y�̂ق����A�t�H�[�T�[�Y 500����f 150mm F2.0 �����v
�ł��ˁB
�����͑��ΓI�Ȃ̂ł��B���������t���T�C�Y��ɂȂȂ�Ȃ��B
���̓_�ł̓t�H�[�T�[�Y���[�U�[�̕��X���u�t���T�C�Y����ɂ���ȁv�ƌ����Ă邱�Ƃ͌��ʓI�ɐ������ł��B
���̏ꍇ�̐����́u�t���T�C�Y�͓�i���邢�v�Ȃ̂ł��B
����ł����ΓI�Ƀt�H�[�T�[�Y����i�Â����Ƃ͕ς��Ȃ��킯�ŁB�܂��Ƃ肠�����́u�t���T�C�Y�� 300mm F4.0 �ɑ�������v�Ƃ��Ƃ��Ă�������Ȃ��ł����B
�����ԍ��F10150790
![]() 1�_
1�_
���������ōl���Ă��Ӌ`�͔����Ǝv���܂��B
����50mmF1.4�ł��`�ʂ��Ⴂ�܂�����ˁB
��p�Ɣ�ʊE�[�x�𑵂���ΈႤ�����Y�Łu�����ʐ^�v���B����Ȃ����B
�i������C��������Ă�l�͓�������p�̃����Y��F�X�������肷��w�j
�܂��ʐ^�o�J�i�܂ގ����j�̑唼�́A���t�␔���ł͕\���Ȃ����̂�����
�Ǝv���Ă邩��ʐ^�B���Ă��ł����B
�����ԍ��F10150813
![]() 8�_
8�_
����ɂ���
�V�m�S�̘b�́A�P���Ȗʐϔ��e�l���Z�_�i�������_�ƌ����Ă��܂��j�̖������m�F���������߂Ɏ����o�������̂ŁA
�P�ɖʐρi������ʁj���傫���Ȃ�������Ƃ����āA�z����̊��Z�e�l���������Ȃ���̂ł͂Ȃ��ł��傤�Ƃ����b�ł��B
���̌��ł���ɓ˂�����ŋc�_�������͂���܂���B���������炩�ɂȂ����̂ł���ŏ[���ł��B
���u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
��1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ���ĎB�e����ƁA
���i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł���
���Z�e�l�_���ʌ����������t�̂悤�ȕ����ɂȂ��Ă������Ƃ͌��\�Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂��B
�������A�ˑR�Ƃ��Ĕ[�����Ă���킯�ł͂���܂���B
���ɁA��ʊE�[�x���ނ�ɗ��߂�̂Řb�����G�����Ă���Ǝv���܂��B
���Z�e�l�_�̔��Ď҂͂���𗍂߂�i���p����j���Ƃŗ����𑣂������Ƃ����ӂ�������܂����A���炩�ɁA�蕪����������������Ȃ��b���������₷���Ȃ�܂��B
���Ƃ��Ɛ[�x�͕ʌɃR���g���[�����\�ł����āA�e�l�Ƃ̑��ւ͐[�����̂́A�ʒu�W��œ_�����ȂǕʂ̗v�f�����ނ̂œƎ��ɉ^�p����悢�b�Ȃ̂ł��B
��_�ƈقȂ�A�[�x�̈Ⴂ�ɂ��Ă͂��łɕ��L���F�m����Ă��܂��B
�𑜓x���ʂ̗v�f�Ȃ̂ł����A�����֎������ވӐ}���瓪�������ȂƎv�����ʁA�_�̌��E�������Ă��܂��܂��B
�͂����Ă��ς�����悤�Ș_�ł���Ƃ����ł��ˁB
�m�C�Y�̃Q�C���A�b�v�̘b�͂��̏ڍׂȒ��x�͂킩��܂���B�s���ȗv�f�R�ƌ��_�I�Șb�ɗ��߂�͍̂���܂��B
�m�C�Y�̏o���͎��ۖ��Ƃ��ĎB�e���Ɍʂ̃R���g���[�����l����悢�����ł��B
�t�H�[�T�[�Y�ɏڂ����l�͒m���Ă��邱�Ƃł����A�R�_�b�N�t���t���[��CCD����LMOS������܂ŁA��ʓI��CMOS����������������̂ł��B
�S�̂�����͒��ׂĂ݂Ă��������B
�t���T�C�Y24���K���Ɋ����Ċ��Z×1.5�̂`�o�r�|�b��12���K�ڂ��ē����G���W���ŏ�������Ί��Z�e�l�Ȃ�Ĕ��z�͏o�Ă��Ȃ��킯�ł��傤�B
�[�x�͐�ɏ������悤�ɐ蕪���^�p����Ζ��������B
�����ԍ��F10150823
![]() 6�_
6�_
���s�̂�������
�݂Ȃ���
���͂悤�������܂��B
������̃X���b�h�͎��Ɠ��l�u���ZF�l�v�_�ɋ^��������ꂽ�������Ă��X���b�h�Ȃ̂�
�����������݂������Ă��������Ă��܂��B
�����ʉ�y����Ɠ��ӌ��ł��B
���s�̂�������́u��_�v�ƌ���ꂽ���Ƃɑ���
>�{���ɃC���[�Ȋ����̐l�ł��ˁB���S�҃X���Łu��_�v�����āB
�Ƃ��Ԃ��ɂȂ��Ă�������Ⴂ�܂����A
������̃X���ł������ł�����������悤�ɑ��l�̔����ɂ͌h�ӂ������đΉ����܂��傤��B
>���͂��Ȃ��ɑ��A�u�����ɑ��Đ^���ȑԓx�ŗՂނ��Ɓv����]���܂��B
�ƁA���ɂ�����������ł͂Ȃ��ł����B���͂��̊�]�ɂ������������Ǝv���Ă���܂��B
�������Ȃ��ɑ��A�u�����ɑ��Đ^���ȑԓx�ŗՂނ��Ɓv����]���܂��B
�u��_�v�ł͂Ȃ��Ƃ��������̂ł���A���l��̂ނ̂ł͂Ȃ�
��̓I�ɒN�ɂł������o����悤�Ȍ��t�ł������̈ӌ����������ɂȂ�܂��B
������̃X���Ŏ���
�u�g���Z�œ_�����h�͕����ʂł͂Ȃ��B�����ʂł���Ȃ瑪����@�������Ăق����v
�Ƃ��������܂�����
>�u���Z�œ_�����͕����ʂ���Ȃ��v���āA���Ȃ���l�B�̍H�v��n���ɂ��Ă܂��ˁB
�Ƃ̂������ŏI����Ă��܂��c�O�ł����B���������͒P�Ȃ�u�C�`��������Y�v�������ŁB
���炽�߂ĕ����ʂł���Ƃ��������Ȃ�A�킩��₷���������ĉ������܂����H
���܂Łu���Z�œ_�����v�������ʂ��Ƃ������͕��������Ƃ�����܂���̂ŁB
�܂��A�u���Z�œ_�����v�̒�`�́A���̌�ǂ��Ȃ�܂������H
���̎w�E���������ɂ��Ă��������������܂����H
����������������A�L�Ӌ`�ȋc�_���W�J�o����Ǝv���̂ł����B
���́A���̂��̋c�_�����������܂ŕ�������̂����炩�ɂ������̂ł��B
���������u���Z�œ_�����v�Ƃ��u���ZF�l�v�Ȃǂ̍l�������A�{���͕K�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
���������l�������̍���ɂ���܂��B
���ꂩ�狞�s�̂�������
����a�]�������C���̂����ŕ���\���\�������o���Ȃ����Ƃ��������ł����A
���ږ{�_�ƊW����܂���̂ŁA�������ڂ������m��ɂȂ肽�����
�V�̖]�����̌f���̕��ł������ɂȂ����炢�����ł��傤���B
�܂��A�����V����ɂ͓V���w��V�̊ϑ��ɂ��Ĉ�ʂ���̎���ɓ����镔��������܂���B
�܂��A�e�n�̌��J�V����Ȃǂɂ��₢���킹�ɂȂ��Ă���낵�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10151248
![]() 10�_
10�_
����H
���s�̂�������̑O�̏������݂������Ă��܂��܂����ˁc
�����ԍ��F10151258
![]() 1�_
1�_
�@���̗��_�A�Ȃ��������Ă邾���ŕ��������Ă���l��K�v�Ȃ��Ƃ����l����R����悤�ł��B�i�ƌ������A�قƂ�ǂ̐l�������݂����ł����j
����͂��ꂼ��̊������Ȃ̂łǂ����悤���Ȃ����͂���܂����B
���������u�H�v�̕����͂���܂����@
���������m�ōl�����y��ł��Ȃ��̂��A��͂肱�̗��_���ԈႢ�Ȃ̂��A���邢�́A�V���ȃp�����[�^����������肷��ΐ�������̂��A�E�E�E�E�E�܂��悭������܂���B
�������A���f�Łu�g���ł����_�v�ƕЕt���邱�Ƃ��ł��Ȃ����͂ƌ������A�ʔ������������ɂ͋����܂���B
�@�������m����o���̖L�x�ȕ��X�̈ӌ�������������̂����������b��̖ʔ����Ƃ���ł�����܂��B
�@�܂��A���F�f���̏������݂ŁA�������A�����Ɨ��������Ŏ��ۂ̎ʐ^�͎B��Ȃ����ǁA
�����ɖʔ����A�����[���ł��B
����ɁA�召�̃t�H�[�}�b�g�łǂ�����i��Δ�ʊE�[�x���������������Ă��܂��l���ӊO�Ƌ���悤�����A���ꂼ��̑��ւ̊�{�������������i��R�̃p�����[�^������ł��������ʔ����j�͂����Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���s�̂������� ����A
�{�l�������Ƃ���ŁA���̉��߂͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�H
�@http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10141193/#10144284
����̓I�ɒN�ɂł������o����悤�Ȍ��t�ł������̈ӌ����������ɂȂ�܂��B
�ܘ_�@�����ł��l���Ă݂܂����A�������肢�������ł��B�@���Ԃ��̐l�̎v���Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���ꂩ��A���炭�̊ԁ@�l�b�g���̖����Ƃ���ɍs�����ƂɂȂ�̂Ł@���������邱�Ƃ��������ނ��Ƃ��o���Ȃ��Ȃ�܂����A�܂����x�����Ƃ��ɂ͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�H�E�E�E
�����ԍ��F10151571
![]() 1�_
1�_
�X���傳��
E-30�������ł��ˁH
���͂��܂��G���g���[�@1����E-300�ł��B
�S�~���t���܂���ˁB�I���́B
�掿����肠��܂��A�����Y�̓I�����p�X���͋����قǗD�G�ł���B
�����͐���傫�����Č��������ł��B
�≖������唻�A�����A���C�J����
�D�G�ȃ����Y��t�B�������J������Ȃ���嗬������ς���Ă����܂����ˁB
�f�W�^���ł�����͓����ŁA����̗���̒��ɃI�����p�X�͂���̂��ȁH
���̓����͍��͒N���킩��܂��E�E�E�B
�t���T�C�Y��ے肵�܂��A�����35�~������̃V�X�e�����d���������̂ł���A
�����]�ސl���g�������ɉ��l���ł�̂ł��傤�ˁB
�����S�~�̖��̓X�g���X�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F10152396
![]() 5�_
5�_
1-300����@����××�́B
�����l�b�g���O��������܂���
�����̂܂�Ȃ�����ɓ����Ă����������肪�Ƃ��������܂����B
�܂�Ȃ�����A�Ƃ����̂́A���Ƃł��l���Ă݂�ƁA
���u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɑ���
��1/2�̏œ_�����̃����Y��2�iF�l�����������ăJ�����ɕ\�����Ă���ISO���x��2�i�Ⴍ
���ĎB�e����ƁA
���i��p�A��ʊE�[�x�A���邳�A�m�C�Y�̗ʁA�𑜓x�A�傫���@���j�����ʐ^���B�邱
�Ƃ��ł���
����͊m���Ɂu���ZF�l���_�v���瓱���o���邱�Ƃ��Ǝv���܂����A�ʂɁu���ZF�l��
�_�v���Ȃ��Ƃ��o�Ă��邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv��������ł��B����������A�u���ZF�l��
�_�v�̃L���ǂ���ł͂Ȃ��Ǝv��������ł��B
������
�u���ZF�l���_�v�Ɋւ��ẮA�͂炽�������Ă�����悤�ɁA
��͂�i���ł����j�u�t�H�[�T�[�Y�i�̃����Y�j��2�i�Â��v�Ƃ�
�������������e���邩�ǂ������L�����Ǝv���܂��B
�ŁA�l�I�ɂ́A�G���̌��o����u���̃^�C�g���Ƃ��ẮA�܂�b�̓�����Ƃ��Ă�
�u������Ɩʔ����v����ǂ��A�b�̏o�������̂܂܁u�t�H�[�T�[�Y�i�̃����Y�j��2�i��
���v�ł́A���܂�ɋ�a�Ŗ��Ӗ��ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
����ƁA�u���ZF�l���_�v�ł́u���邢�E�Â��v�̒�`���A
�]���̃J�����ʐ^��@�̒�`�Ƃ͈Ⴄ�悤�ł���
�u�t�H�[�T�[�Y��2�i�Â��v���A�]���̒�`�ʼn��߂��Ă��܂��l�����R�o�Ă��܂�����A
������Ɩ��ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����̂��l�̊��G�ł��B
�œ_�����ɂ���AF�l�ɂ���AISO���x�ɂ���A���Z�������l�͂�������̂ł́B
�����ԍ��F10153029
![]() 4�_
4�_
�t�H�[�T�[�Y�@�̍����x�̉掿�̓t���T�C�Y�@�����ł��B�i���Z�j
���ZF�l���g���ƃZ���T�[�T�C�Y���t���T�C�Y�Ɋ��Z�����̂ō����x�̉掿���t���T�C�Y�@�Ɠ����ɂȂ�܂��B
�R�A�S���~���甃����t�H�[�T�[�Y�@�͊��Z����ƃt���T�C�Y�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�i�����������t���T�C�Y�B�j
�{�f�B���̐��\���Q�i�グ�A�����Y���̐��\���Q�i�����銷�Z�����ĈÂ��Ƃ����̂͌������\�����Ǝv���܂��B
�t���T�C�Y�@�̍����x�̉掿�̓t�H�[�T�[�Y�@�����ł��B�i���Z�j
�����Y�͂Q�i���邭�Ȃ�܂��B
�t���T�C�Y��F4.0�̃����Y���t�H�[�T�[�Y��F2.0�ɑ�������i�t�H�[�T�[�Y�Ɋ��Z�j�Ƃ����Ƃ��͋t�ɃZ���T�[�T�C�Y
���t�H�[�T�[�Y�ɂȂ��Ă�̂ō����x�̉掿�̓t�H�[�T�[�Y�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�i�����������t�H�[�T�[�Y�B�j
150mmF2��300mmF2�Ɗ��Z����Ƃ��́A�C���[�W�Z���T�[�̓t�H�[�T�[�Y�̂܂܂ł��B
150mmF2��300mmF4�Ɗ��Z����Ƃ��́A�C���[�W�Z���T�[�̓t���T�C�Y�ɂȂ��Ă��܂��B
�ݒ�ł��銴�x�̖��͂���܂����A����ȍl����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F10153112
![]() 3�_
3�_
���ꂼ��̃t�H�[�}�b�g�������i�𗝉����邱�ƂŁA�J���������[���g�����Ȃ���悤�ɂȂ�B
���ꂼ��̃t�H�[�}�b�g�������i�𗝉�����Ƃ��ɁA�����������Ƃ������I�ɔc���ł���t�H�[�}�b�g����ɒu���Ċ��Z���邱�ƂŁA�X���[�Y�ȗ������\�ɂȂ�B
���ꂪ�A��Ԃ́u�֗��v�������b�g���Ǝv���B
�t���T�C�Y�ɑ��āA������唻�̃J�������u���邢�t�H�[�}�b�g�v�Ƃ͌ĂȂ��悤�ɁA�t���T�C�Y�ɑ���t�H�[�T�[�Y���u�Â��t�H�[�}�b�g�v�ƌĂԕK�v�͂Ȃ��B
����A�t���T�C�Y�������邢�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���o�ꂷ��\�����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B
�����A���s�̐��i���C���A�b�v������ƁA�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�́A���Z���F�l���A���N���X�̃t���T�C�Y�̃����Y�ɑ��āA�傫���i�Â��j�B
����́A�ʂɁA�t�H�[�T�[�Y�̌��_�����r�Ȃ̂ł͂Ȃ��B
���������A���������`�ɍœK�����ꂽ�t�H�[�}�b�g�Ȃ̂�����B
�V�m�S�ƃt���T�C�Y���r���邱�ƂɈӖ����Ȃ��̂Ɠ����ŁA���ZF�l�ɂ��ė������A����Ɋ�Â��Ċe�t�H�[�}�b�g�̐��i�𗝉�����A�t���T�C�Y�EAPS-C�E�t�H�[�T�[�Y�̗D��_�́A�s�т��Ƃ킩��B
�������������̂́A���ꂾ���B
�����ԍ��F10153319
![]() 8�_
8�_
�����ł���͂�X���傳���u������ɂȂ��Ă��܂��āA���͎v��������Ж_��S���ł���̂ő�ϐ\����Ȃ��v���Ă܂��B
�Ȃ�ł����A�ǂ�������ς菑���Ă��܂��܂��B^^;
1-300����
���͂���ς�A�̉��̕��ɏ����������������Ă��銴�������܂��B
F�l2�i���_�͂���ʂŁA�t���T�C�Y�̎��͂�Ⴍ�݂Ă��܂����ƂɂȂ�ł͂Ȃ����A�ƑO��i��j�̃X���̓r���Ŏv���Ă����̂ł��B
�u�ȁ`�A�t���T�C�Y���č��X�����x�m�C�Y���ǂ��������v
�ƁA���܂��܃X����ǂ��S�҂��v������A�C�}�C�`�A�Ȋ����ł��B
���鐯���߂炳��Ƃ����s�̂����������Ă���咣���u�Z���T�[���鑍���ʂʼn掿�����܂�v�ƁA�f���ɓǂނƂ����Ȃ����Ⴂ�܂��B
�u�Z���T�[�T�C�Y���������ꍇ�A�I�����Ԃ������Γ����v
�Ȃ킯������ł����B1-300����̐����ł��A���l�̖��ɂȂ�\����������������Ǝv���܂��B
����������ׂɂ́A����ς蒷�X�Ɛ������K�v�ɂȂ��āA�A�A
�ƁA�Ȃ��Ȃ�����ł��ˁB
�����ԍ��F10153361
![]() 0�_
0�_
���߂܂���
�܂����₱�̋c�_���n�܂�܂���
�����Œ�Ăł�
�t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�ŁA���ґ������������
������ʑ̂��B�e���������F�Ŏ������܂��傤
�F�ō����o���A��������Ǝv���̂ł�
����E-3���������Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ��ɂ��Ȃ�܂���
���͂�������ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂�
�����ԍ��F10153684
![]() 4�_
4�_
�͂炽����A
���̃X���𗧂��グ�����_�ŁA�����͂�����x�͊o�債�Ă��܂��̂ŁA
���̍ۂł�����A�O��I�ɂ���Ē����Ă����\�ł���B�X������C����
�K�v�͂���܂���B�����A���̃��[�h�ɂȂ�ƑS�Ăɂ��Ԏ����o���Ȃ�
�̂ł��e�͉������B�����A�݂Ȃ��܊���I�ȉ��V�͍T���ĉ������ˁB
���āA���̋c�_��������߂Ă��܂����B���̘b�肪�{���ɐF�X�ȂƂ����
�J��Ԃ���Ă������Ƃ��m�F���܂������A�قƂ�ǂ��I�����p�X�̃X���b�h
�ł��ˁB�L���m���̃X���b�h�ł��uAPS-C�̃����Y�͈Â��̂��v�Ƃ����₢
���������̂ŁA�L���Ȗ^�����o�ꂵ�Ă���̂��Ǝv������A�ꌾ����������
�ł��܂���B�ǂ����L���m���̃X���b�h�ɂ͂��������Ȃ��悤�ł��B����
������ƁA����ς�P�Ȃ�l�K�L�����������������̐l�������悤����
�����v�����m�M�ɋ߂Â��Ă��܂����B�����͏����ł��M�������Ƃ����|�W
�e�B�u�ȍl���ł������A������Ƃ��낭�������ꂽ�C�����ɂȂ��ė��܂���
�̂��c�O�ł��B
1-300����A
���̗��_���Ȃ��������Ă��邾���ŕ��������Ă��邩�Ƃ����l����������
�����ƁA�ŏI�I�ɖ�����掿�������ƌ����Ƃ���Ɏ����čs�����Ƃ���
���邩��Ȃ̂��Ǝv���܂��B����ɔ��_����l�ɑ��āA�Ȃ�ӂ�\�킸�A
�u�����������������v�Ƃ����������������A�I�����p�X�t�@���łȂ���
�����Ȉ�ۂ������c�邩��ł��傤�B
����܂ŁA�����F�X�Ȉӌ������Ă��āA���������͈͂ň�x���������Ē���
���Ƃɂ��܂��B
�����Z�e�l
���ZF�l�́A�B���f�q�̓����܂Ŋ܂n���l�������̂ł���A�t���T�C�Y��
�B���f�q�T�C�Y����Ƃ��čl����B�t���T�C�Y�̊��Z�W���͂P�ł���A
�������Ȃ�ɂ�ČW���͑傫���Ȃ�A�T�C�Y���傫���Ȃ�ƌW���͏�����
�Ȃ�B�܂�A���̌��w�n�������I�o�ŎB�e����ۂɕK�v�ȑ����ʂ̑召��
�ړx��\�������̂ŁA���ۂ̎ʐ^�B�e�Ƃ͒��ڊW�Ȃ��B
�i���Z�e�l�Ȃ�Č���Ȃ��Ō��w�n�����ʓx�f�i���ɈӖ��͖���F�̎��j��
�ł���`������������������Ă悢�����m��܂���B�j�����A����́A
�S�̈�̉掿���v��ړx�ɂ��Ȃ�Ȃ����A�I�o�ɂ��e�����Ȃ��̂ŁA
������ɂ��Ă��債���Ӗ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
��S/N��
���̖��Â�\������̂�S/N����g���̂́A�B���f�q�Ōv�����ꂽ���ʂ̓d�C
�M���Ƃ��čl���邩��ł���B�m�C�Y�����͐M����Ɣ�Ⴕ�đ�������̂�
����Ζ��邢�Ƃ��납��Â��Ƃ���܂Ńm�C�Y�ʂ����ƂȂ邱�Ƃ��l����
��邪���ۂ̎ʐ^�ɂ����ẮA���邢�Ƃ���ł̓m�C�Y�ʂ͌������Ă���A
�Â����ł̓m�C�Y�ʂ����傷��B���̌��ۂ���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�▾�x��
����đ��������A�P��ʐς�����̃m�C�Y�̗ʂ����ƍl���Ă��悢
�i���ۂɂ͗l�X�ȃm�C�Y������Ǝv���܂����E�E�j�Ƃ��������������܂��B
���̎��A���R�B���f�q�̓m�C�Y���x��M�����x�ɔ�ׂď[���������Ȃ�悤
�Ɋ撣���Đv���Ă��邪�A���ɂ��M�����x���キ�Ȃ�̈�ɂ����āA
�B�����̖ʐϔ�ɂ��S/N��̍��͖ڗ����Ă���B�܂�A��Ɠx�ɂ�����
�̓t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y��1/4�̌��ʂł��邱�Ƃ��A���������ɂ��
���������Ă���̂ŁAISO���x�̑����̓m�C�Y����������ĕs���ł���B
���̂��߁A�t���T�C�Y��ISO6400�����ʂɎg����悤�ɂ���Z�p���t�H�[�T�[�Y
�ɓK�p���Ă��AISO1600�����E�ƂȂ�B
�������AS/N�䂪�[���Ɏ��钆���Ɠx�ɂ����ẮA���̌��ʂ̍��ɂ��
�掿�̉e���͏������B�܂�A�J���i��ł��A��Ԃꂪ��������悤��
�V���b�^�[�X�s�[�h�̈�ɂ����Ă͎B���f�q�̑傫���ɂ��e�����o�ė���
���A�\���Ȉ����ʂ�������̈�ł͎B���f�q�̑傫���̈Ⴂ�ɂ��S/N��
�̈Ⴂ�͉掿�ɑ傫�ȉe����^���Ȃ��B
���掿
���a���掿�����߂�Ƃ����ӌ������邪�A�\���Ȍ��ʂ�����ꍇ�͎�����
���ӌ����A�𑜓x�Ȃǂ̕����掿�����肷��傫�ȗv���ƂȂ�B�B���f�q
��S/N��͒�Ɠx�ɂ����Ă��e�����傫���Ȃ�A�m�C�Y�������`�ʂ���
�掿�������Ȃ�B���̗̈�͉掿�͌��ʂɍł��ˑ�����B
�]���āA�t���T�C�Y�Ɣ�r���ď������ʐς̉e���ɂ���ĉ掿�������Ȃ�
�ƌ����̂͒�Ɠx�̎��ƌ��肷��ׂ��ł���B
�ƌ������Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B�F�X�����܂������A�����炭
----
�t�H�[�T�[�Y�́A�B���f�q�����������ăV�X�e���S�̂����^�����邱�Ƃ�
�ڎw�����V�X�e���ł���B���̂��߁A���w�n�S�̂ł͌��ʂ����Ȃ��Ă�
�≖35�~���Ɠ����̉掿�ŎB�e�o����悤�ɁA�����Y�̉𑜓x���グ��
�H�v���Ȃ���Ă��邪�A�B���f�q�̃T�C�Y���������������Ƃɂ��f��
���b�g�����邱�Ƃ��m���ł���B
�Ⴆ�Γ���f���̃t���T�C�Y�t�H�[�}�b�g�Ɣ�r�����1��f�̎�u�ʐ�
���t���T�C�Y��1/4�̑傫���ƂȂ邽�߁AS/N�䂪�����Ȃ鐫�������A
���Ɠx�ł́A�m�C�Y�ɑ��Č��ʂ��[���ɑ傫���̂�S/N��͖���
�Ȃ�Ȃ����A��Ɠx�ɂ����Ă̓m�C�Y�ʂ��掿�ɉe�����y�ڂ��B����́A
���ۂ̗��p�ʂɂ����āA�t�H�[�T�[�Y�̊��x�̏���ݒ�̓t���T�C�Y��
2�i���x�Ⴂ�̂��Ƃ����������B
----
�ȂǂƂ��������Ȃ�A���ۂ̌��ۂƍ����Ă���̂Ŕ[����������������
�ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�A���ʂ����Ȃ��Ƃ����������A�������ł�
�掿�������Ƃ����Ƃ���Ɏ����čs�������Ƃ����Ӑ}�������B�ꂷ��̂ŁA
�I�����p�X���[�U�Ȃ炸�Ƃ��A�ꌾ���������Ȃ�̂ł��傤�ˁB
�掿�������Ƃ�������������߂ċc�_���Ă݂邱�ƂŁA�����ƌ��ݓI��
�c�_�����܂��l�ȋC�����Ă��܂����B�{�X�g�[�NT-233����
�������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�ꌾ�Ō����Ƃ����������Ƃ���Ȃ��̂ł��傤���B
�����ԍ��F10155353
![]() 15�_
15�_
���R�Ȋw�I�Ȏ��_�Ō����A
�u�����𗧂Ă��҂ɂ͂�����ؖ�����ӔC������v��ł����ǂˁB
�N������͂����������Ă��邩��A���X�M�p����Ȃ���ł��B
�i�ܘ_�A���̗��_�Ǝ����ɑ��Ă͔��؎��������錠���͒N�ɂł�����܂��B�j
�����ԍ��F10155918
![]() 10�_
10�_
Tranquility����
�C���ƌ��a�Ɖ掿�̊W�ɂ��ẮA���Ȃ������g���u���_�I�ɐ����ł���B���Ԃ�����ΐ�������v�Ə������̂ł��B�����ŗ��_�I�ɐ������܂��傤�B�����ł��Ȃ��̂Ȃ甭����P�܂��傤�B
���ZF�l�ɂ��Ắu�B���O�i�L�^�O�j�v�Ɓu�B����i�L�^��j�v�̘b�͎�قȂ�܂��B����͂킯�čl�������������ł��B[10150790] �ŏ��������Ƃ͎B����B
����Ɣh���X���Ȃ�����h�����X���������N���Ȃ���ʖڂł���B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041115/SortID=10101952/
�ŁA�X���b�h�ɎQ������ȏ�A�S���̃��X���e�ׂɓǂނׂ��Ȃ̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����͂ł��܂���B����͐\����Ȃ��Ƃ͎v���܂��i�������l�ԓI�ɍŒ�Ȑl�X������������̂ŁA�ǂނƋC�������Ȃ郌�X�������ł����ˁj�B
1-300���� ��
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10141193/#10144284
�ɂ��Ắu�̌��������ۂ𗝋��Ő������悤�Ƃ��Ă���v�Ƃ����_�Łu�B����̐����v�ƌ����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041115/SortID=10101952/#10144465
����̌㔼��
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041115/SortID=10101952/#10150097
������B����̐����B
�������͐F�X����܂����A��`�����Ă����Ȓ�`�̎d��������B���ɒ�`�͉ߋ��X���ʼn��x�����Ă���͂��ł��B
�B���O�ɂ��čl����̂����{�ł��傤�ˁB
�u�����Y���̉��l�Ƃ́H�v�ɂ��čl����̂��悢�ł��傤�B
���̒��̎ʐ^�p�����Y�́u�P�œ_�����Y�v�Ɓu�Y�[�������Y�i�o���t�H�[�J�������Y�j�v�̓�ɑ�ʂł��܂��B
���̂����Y�[�������Y�ɂ��āB
�u�Y�[������ƃ����Y���͉����ς��́H�v�u�ǂ��ς��́H�v�u�Y�[���O�ƃY�[����Ń����Y���̉��l�͂ǂ��炪��Ȃ́H�v
�Ȃǂɂ��čl���Ă݂�̂��{���I�ł��B
���̍ۂ͔�ʊE�[�x�̉e�����Ȃ����ʃ`���[�g�Ȃǂŕ]������̂��悢�ł��傤�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8512335/ImageID=139927/
����Ă݂�킩��܂����i�u����Ă݂�v�Ƃ������_�Łu�B����v�̘b�ƂȂ��Ă��܂��܂����j�A�Y�[�����邱�ƂŁu�𑜓x�v�uS/N��v�̗����Ƃ�����Y�[�������Y�Ȃ�āA��{�I�ɂ͂���܂���i�����I�ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��j�B
�����ɂ͑��݂��邱�Ƃ�����ł��傤���A����ȃY�[�������Y�̃e�����͎g�����l�i���݉��l�j������܂���ˁB
�u���ZF�l���_�v�Ƃ́u�����Y���̉��l�����Z�œ_�����Ɗ��ZF�l�Łi��{��������Łj�\������v�ƌ��������ł���A�Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F10156078
![]() 0�_
0�_
���� Tranquility����
���̃X���ł��Ȃ��Ƙb�������C�͂���܂���̂ŁA���������������B
�h�����̃X���Řb�������܂��傤�B�u������ł͂ł��Ȃ��v�ƌ����Ȃ�A���Ȃ��͌��X���������~���������ł��B
�����ԍ��F10156099
![]() 0�_
0�_
���Ƃ�����J��Ԃ�������邱�Ƃł����A
>�u�����𗧂Ă��҂ɂ͂�����ؖ�����ӔC������v��ł����ǂˁB
�����𗧂ĂĂ��܂����H
�V�������������͉������Ă��܂���B
���ƃg���~���O�Y�[���ƌ��w�Y�[���̔�r���ʂ͏o���Ă��܂��B
�����ԍ��F10156132
![]() 0�_
0�_
���s�̂������� ����
�݂Ȃ���
����ɂ��́B
>�C���ƌ��a�Ɖ掿�̊W�ɂ��ẮA���Ȃ������g���u���_�I�ɐ����ł���B���Ԃ�����ΐ�������v�Ə������̂ł��B�����ŗ��_�I�ɐ������܂��傤�B�����ł��Ȃ��̂Ȃ甭����P�܂��傤�B
���̌��ɂ��Ă�[10144616]�Ő��������Ă��������܂����B
������P��C�͂���܂��A�킩��Â炩�����Ƃ�����A���������肾�����̂�������܂���B�\���킯����܂���B
������ɂ���A���̃X���b�h�̎��Ƃ͈Ⴄ�b�Ȃ̂ŁA�������ڂ������m��ɂȂ肽���悤�ł�����ʂ̏��ŁA�Ə����܂����B�V�̖]�����̌f�������܂ɔ`���܂��̂ŁA������Ŏ��₵�Ă�����������炽�߂Ă������������܂��B�����������Ə��ɓ����ĉ������������������ł��傤�B
���s�̂�������͂����Ŏ��Ƃ͘b���C���Ȃ������Ŏc�O�Ȃ�ł����A���Ƃ��Ƃ�����̃X���b�h�́u�I�����p�X�ɂ����邢�p���P�[�L�����Y���o���Ăق����v�Ƃ����b��ł����B�����������Łu�t�H�[�T�[�Y�͈Â��v�Ƃ������b���o���̂ŁA����͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����A�Ə������݂������Ă��������܂����B
�u���ZF�l�v��u���Z�œ_�����v�̘b�����Ă����̂́A�������݂����Ȃ�����\����Ȃ��Ǝv���Ă���܂����B
�����ɂ��̘b��͈Ⴄ���ő����܂��傤�A�Ƃ�������Ă����ĉ��������̂��Z���JGT-Four-A����ł��B���X�̎�肪�Ⴄ���ŃY�����������݂𑱂���̂��ǂ����Ǝv���܂��̂ŁA���͂����������ɂ͂��̌��ŏ������݂̂͏I���ɂ��܂��ƌ����܂����B���肪�������ƂɁu���̍ۂł�����A�O��I�ɂ���Ē����Ă����\�ł���B�X������C�����K�v�͂���܂���B�v�Ƃ���������Ă��������Ă��܂��B
���āA���s�̂�����������������u���Z�œ_�����v�̒�`�ł����A
>�u��p�s�ς̂܂܁g���̑傫���h���t���T�C�Y�Ɠ������Ȃ�悤�Ɋg�k�����Ƃ��̉��z�I�ȏœ_�����v[10144465]
�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B
���͂��̕\���ł͗ǂ��킩��Ȃ������̂ŁA
�u�t���T�C�Y���Z�œ_�����Ƃ́A�C�ӂ̃t�H�[�}�b�g�ɂ����ĉ�p�s�ς̂܂܁g���̑傫���h���t���T�C�Y�Ɠ������Ȃ�悤�Ɋg�k�����Ƃ��̉��z�I�ȏœ_�����v�Ǝ����Ȃ�ɕ⑫����������
�u��p�s�ςő��̑傫�����ɕۂ����܂܂ł̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y��ς��鎖�͕s�\�Ȃ̂ł͂���܂��H�v
�Ƃ������˂��܂����B
���̕⑫���߂��Ă��邽�߂�������܂��A���炽�߂āA�ǂ��������Ƃ������Ă��������܂��H
�܂��A
>�V�������������͉������Ă��܂���B
�������ł����A�u�g���Z�œ_�����h�͕����ʂł���v�Ƃ��������͏��߂ċ��s�̂������畷���܂����B
����ɂ��Ă��u������@�v�����u�˂��܂������A���X���ł�������ł����������������Ă���܂���B
�u�����ŗ��_�I�ɐ������܂��傤�B�����ł��Ȃ��̂Ȃ甭����P�܂��傤�B�v�ł��B
����ɍ���
>�u�Y�[������ƃ����Y���͉����ς��́H�v�u�ǂ��ς��́H�v�u�Y�[���O�ƃY�[����Ń����Y���̉��l�͂ǂ��炪��Ȃ́H�v
�Ȃǂɂ��čl���Ă݂�̂��{���I�ł��B
�Ə�����Ă����܂����A�V���ȋ^�₪�������܂����B
�u���̉��l�v�Ƃ͉��̂��Ƃł����H
������u���ZF�l���_�v�͒P�œ_�����Y�ƃY�[�������Y�ňႤ�̂ł����H
�Y�[�������Y�̃Y�[���ʒu�ɂ���ĕς��̂ł��傤���H
���Ƃ���ƁA�܂��܂���₱�����Ȃ�܂��ˁB
�������������Ő\����Ȃ��̂ł����A���s�̂�������̂�������邱�Ƃ𗝉����Ȃ����Ƃɂ͐�ɐi�߂܂���B
�����ԍ��F10156604
![]() 10�_
10�_
���s�̂������� ����
���Q�l
http://www.nhao.jp/~tsumu/Research/Intr_atm/atmosph.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8746209/
http://www.astroarts.co.jp/hoshinavi/magazine/shokunin/028/index-j.shtml
���̑��u�V�[�C���O�v�u�V���`���[�V�����v�ȂǂŌ�������A���Ȃ�̏������Ǝv���܂��B
���ɊW�Ȃ��������݂Ő\���킯����܂���B
�����ԍ��F10156817
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
�Z���JGT-Four-A���܂Ƃ߂Ă��܂����ATranquility����u���l�v�ɂ��Ď��₪�o�Ă��܂����A�⑫�Ƃ������A�l�I�����ł��B
>�u���ZF�l���_�v�Ƃ́u�����Y���̉��l�����Z�œ_�����Ɗ��ZF�l�Łi��{��������Łj�\������v�ƌ��������ł���A�Ƃ������Ƃł��B
�u�����Y���̉��l�v���ē���ł��ˁB�œ_������F�l�������ł��������ɂ͂Ȃ�܂���B
�C�ɂȂ�Ȃ��l�ɂ͕�����Ȃ��A�u������Ƃ����Ⴂ�v(���͂���A�U�C�f���̎����ɐF�����A�t���A�Ƀn���ɃS�[�X�g�A���ӌ��ʁA�F�Ƃ��ˁB���͂ł��Ȃ������ł́u��C���v�Ƃ��j���l�ɂ���Ă͑傫�ȈႢ�ɂȂ�܂��B�����ɕ����Ή��́A������Ȃ��l���猩��Δn���݂����ɍ��������肵�܂��B�i�A�}�`���A�̏ꍇ�A�Ɛl�̗�����������ꍇ�̕������Ȃ��Ǝv�� ^^;�j
���s�̂�������ɂ͕�����Ȃ���������܂��u������Ƃ����Ⴂ�v�ɑ喇�@���Ă���l�������ǂ�ł��܂�����A�������݂̍ۂɂ͂����ӂ��������B
�u���l�v�Ƃ͐藣�����c�_�ɂ��Ȃ���A���ZF�l�̘b�͎��܂�܂��A�u���l�v�̘b����������Ί��ZF�l�͌덷�̂����ł��傤�B
�ȉ��A���s�̂�������ȊO�̐l�ɂ�
���Ȃ݂ɁA
�Ƒ��ɃJ�����̃����Y���u����Ȃ̂����̃K���X�ʃW�����v�ƌ���ꂽ������܂��H
���͂���܂��B(>_<)
�����ԍ��F10158488
![]() 3�_
3�_
ZD150mm�̃����Y�̏œ_������150mm
���̉�p���t���T�C�Y�Ɋ��Z������300mm����
F2�Ńt���T�C�Y�Ɠ���ISO���x�ŎB������V���b�^�[�X�s�[�h�͓���
�Ȃ̂Ń����Y�̖��邳�͑̊��I�ɂ͓���
��ʊE�[�x�̓t���T�C�Y�̕����ă{�P��
�t���T�C�Y�g�������Ɩ�����ł����A
�F����̋c�_��ǂ�Ŏ����Ƃ��Ă͂��̂悤�ɉ��߂��܂����B
���̒��̐��������_�Ƃ������̂́A�����V���v���ł킩��₷�������肵�܂��ˁB
�����ԍ��F10158617
![]() 11�_
11�_
���ZF�l�́A
�E���a
�E�œ_����
�E���ʂ̖ʐ�
��3�v�f�݂̂��琬�藧�A�ƂĂ��V���v���Ŕ��������_�B
���߂ė��������Ƃ��́A���̖������ɋ������B
�����ԍ��F10158826
![]() 3�_
3�_
�{�X�g�[�NT-233����
���ZF�l���_�̓V���v���ł����A�A�A
���ZF�l���_�Ő��������͔̂�ʊE�[�x�ƃm�C�Y��2��ނ̌��ۂł��ˁB
��ʊE�[�x�͗ǂ���ł���B���ł����藧����B
�m�C�Y�̕��͂Ƃ����ƁA�����ɁA�ϑ��Ƃ���܂��ˁB
���̃Y�����X�ɗ��_�ŕ������A��ʊE�[�x�܂ł̓K�p�ɗ��߂Ă������������_�̃V���v������ۂ��ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10159010
![]() 6�_
6�_
�͂炽����A���ZF�l���u��ʊE�[�x�v�Ɓu�m�C�Y�v�̘b���Ɨ�������̂́A���������Ȃ���B
���ZF�l�́A���̂������P���Ȃ��Ƃ��������Ă��Ȃ�����ǁA���̕��A�[���B
���ZF�l�́A��ʊE�[�x�ɂ��Ă��A�m�C�Y�ʂɂ��Ă��A�����������Ă��Ȃ����A���͂��ׂĂ����Ɋ܂܂�Ă���B
�u�V���v���Ŕ������v�Ƃ����̂́A�����������Ƃ���B
�ł��A�����͂��Ȃ��B�����ŗ������Ȃ��ƁA�������Ȃ��Ȃ邩��B
SS999����́A�f���炵�����������Ă���B
�����ԍ��F10159200
![]() 1�_
1�_
���Z�e�l���_�������́A
�������̐l���ē����I�o�v�����g�������ƂȂ��`�Ƃ�
TTL�����u�ł��Ȃ��v�t���b�V���������g�������ƂȂ��낤�ȂƂ�
���t���b�N�X�����Y���Ăǂ����Z����H�Ƃ��v���܂����B
�P���Ɂu�����Y��ʉ߂�����̗ʂ��S�{��������掿���Ⴄ�v�̂Ȃ�
35mm����50mmF1.4��ND4�t�B���^�[��������
4/3��25mmF1.4�Ɠ����掿�ɂȂ�낤�ȁ`�Ƃ��A
�n�[�tND�t�B���^�[�g�����猸�����͉掿���K�^�����ɂȂ�̂��ȁH�Ƃ�
�F�X�z�����Ă��܂��܂����i���ۂɂ̓R���g���X�g����������B�j
�����ԍ��F10159276
![]() 13�_
13�_
�}�t��蕥���āA�{�����������悤�B
�����A�{���ɁA���������������ƁA���ꂾ���B
�����ԍ��F10159328
![]() 2�_
2�_
Tranquility����
���Z�œ_�����ɂ��Ă͔h�����X���ł��܂��傤�B���ꂩ�����g�ŃX���b�h�𗧂Ă��邩�B
�C���ɂ��Ă����l�B���������a�Ɖ掿�Ƃ̊W���萫�I�Ɂi�Ⴆ�Ύ���p���āj�����ł���Ƃ����̂ł�����̌���ł͂���܂���B�܂�u�@��������v�Ƃ����̂Ȃ�A����͖����ł��Ȃ����ۂƂ������Ƃł��B
�����������u�����킩��Ȃ��̂��A������͂����ς�킩��Ȃ��v�ł��B
���_����l�͈�l��l�������Ƃ��Ⴄ�B���_����l�̘_�_���܂Ƃ߂Ă��炦��킩�邩������܂��B
���ƁA���_����l�̎咣�i���Ⴀ�A���Ȃ���͂ǂ��l���Ă�́H�Ƃ������Ɓj���킩��Ȃ��B
�u�t�H�[�T�[�Y 150mm F2.0 �́A�t���T�C�Y�� 300mm F2.0 �Ɠ����̉��l������v�ƍl���Ă���̂��B
����Ƃ�
�u�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�͔�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƍl���Ă���̂��B
�ł��u�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�͖��邳�͓����B�ʐς��l�{�Ⴄ�����v���Ă̂͑ʖڂł���B�u�掿�̉��l���r����v���߂ɂ���Ă���̂ł�����A�ʐς����l�ɂǂ����т��̂��H�������Ă����Ȃ��ƁB
�l�I�ɂ́u�����Y���̉��l�v�����ł�����x�����ł���������@���l�����̂ł����A�Ƃ肠���������Y���̉��l�ɂ��čl���ė~�����ł��ˁB
���̗�Ō����Ȃ�
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8512335/ImageID=139915/
������̓Y�[���O�̉摜�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8512335/ImageID=139927/
������͓�{�Y�[�������摜�iF�l���ŏœ_������{�BExif ���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
���摜�Ƃ��s�N�Z�����{�Ő蔲���������ł��B
�摜������Ă���̂Łu�B����v�Ȃ̂ł����A�B���O�̃����Y�����[���I�ɖ͂������̂ɂȂ��Ă��܂��B�Y�[���O�ƃY�[����ł́A�����Y���ɂ��ꂾ���̈Ⴂ������A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���w�Y�[���ƃg���~���O�Y�[���̈Ⴂ���������̖{���i�ւ̗ǂ��q���g��^������́j�Ȃ̂ł����A������Ƃ��܂�ǂ���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ˁB�����͂����܂ł킩���ĎB�e�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁB
�u��܂������܂ōi��v�ƃ����Y�����قڂ��̂܂܌����悤�ɂȂ�̂ł����E�E�E�B
�����ԍ��F10160393
![]() 0�_
0�_
�����Y���̉��l�ƌ������u�����Y���̃N�I���e�B�v�ł��ˁB
���z��Ԃɂ����郌���Y���̃N�I���e�B�Ƃ͉����H
����́u�𑜁v�ł��B
���z��ԂƂ͖����������Y�A�C���Ȃǂ̈��e�����r��������Ԃ̂��ƁB
�𑜂���₱�����̂ł����A�u�𑜓x�v�ł͂���܂���B�P���Ɂu��ʑׂ̂̍����������ǂꂾ���ʂ邩�v�݂����Ȃ��̂ł��B
�Ƃ肠�����𑜈ȊO�̃N�I���e�B�̗v�f���v�����܂���B
�����ԍ��F10160439
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
��������������B
�u�����Y���̃N�I���e�B�v���c�_����Ƃ��ɁA�L���m����j�R���̂悤�ɓ��������Y���N���b�v�Ŏg���Ƃ��ɂ͂Ƃ������A�t�H�[�T�[�Y��135�t���T�C�Y�ł̓����Y���S���Ⴂ�܂���ˁB�i�����`�ł�����܂��E�E�E�j
�������A���z�I�����Y�ɂ����闝�_���f���̂��b������Ă���̂�������܂��A�����͂����Ȃ��Ă��Ȃ��킯�ŁA�t�H�[�T�[�Y�̓����Y���������{�f�B�i�܁D�B���f�q�j������ɒǂ����Ă��Ȃ��A�t���T�C�Y�̓{�f�B�i���j�͂����������Y���ǂ����Ă��Ȃ��i���̂������j�ƌ����邱�Ƃ��悭����܂��B
���ہA�I�����p�X��ZD�����Y�́A�������B���f�q�i������f�s�b�`�j�ɑΉ��ł���悤�v����i���̕������H�쐸�x���v������j�Ă���AMTF�Ȑ�����ʂ̃t���T�C�Y�p�����Y��2�{�ɑ��������Ԏ��g���ŕ`����Ă��܂��B
�i���̈Ӗ��ł́A�����t�H�[�T�[�Y�w�c�ł��V�O�}�ɂ��Ă͂�����ƕʁA�ƌ����ׂ����Ǝv���Ă��܂��B�j
���s�̂�������́A���̓_�͂ǂ̂悤�ɂ��l���ɂȂ��Ă���̂ł��傤���B������������K���ł��B
�����ԍ��F10160617
![]() 4�_
4�_
>������Ƃ��܂�ǂ���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���ˁB
�����͂����Ƃ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ǝv���Ă��܂����A�����ɂ͂ł��Ȃ��̂Ń`���[�g�Ƃ��̎g�p�@�̂݁i���Y�^���˂āj�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502411000/SortID=6606870/
��������̃X���� ���ʂ̓��{�̐l����@�ɂ����������`���[�g�ł��B
http://jpdo.com/ee02/141/img/35.jpg
����� A4 �ɂ��̂܂܈�����܂��i���͕��ʎ��j�ƁA�u1:1.0�v���c�� 20mm �ŁA�u1:2.0�v���c�� 40mm �̕��ň������܂��B
�e�`���[�g�̏c���́u�����C��20�{�A�����C��20�{�A�������킹��40�{�̃��C���v�ō\������܂��B�u1:2.0�v�̃`���[�g���Ɓu40mm �̒��� 40�{�v�Ȃ̂ŁA���C���̕��͔����Ƃ��Ɂu1mm�v�ł��B�u1:1.0�v���Ƃ��̔����́u0.5mm�v�B
�ڂ��������͂��܂��A�u1:1.0�v���u40�s�N�Z�����傤�ǁv�Ɏ��߂�B�e�����i���Y�^�j�B
�f�W�J���̃A�X�y�N�g��� 4:3�A��f���� N�A�t���T�C�Y���Z�œ_������ x [mm] �Ƃ��āA
�B�e����[mm] �� (x * ��N) / (34.6 * ��3)
����
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=9246525/ImageID=278531/
���̉摜�́u1:1.0 �� 40�s�N�Z���v�ɂȂ��Ă��܂��A���ɂ��������B�e������ƁA
��f���́u1463����f�v�A���Z�œ_�����́u28mm�v�Ȃ̂ŁA
�B�e���� �� (28 * ��14630000) / (34.6 * ��3) = 1787 [mm]
���̉Ƃ͋����̂� 1.8���[�g�����B�e��������ꂸ�A���ʁu1:1.2 �� 40�s�N�Z���v�ɂȂ��Ă��܂��܂����Ƃ��B
��ʂɍ���f�E���Z�œ_���������������Y�قǎB�e������K�v�Ƃ��Ă��܂��܂��iA6�v�����g�Ƃ���������B�e���������Ȃ̂��ȁH�j�B
�����ԍ��F10160637
![]() 0�_
0�_
�t���[������
�����Y�̗��_�u�𑜓x�i�{/mm�j�v���E�́u�i���Z�ł͂Ȃ��jF�l�v�Ō��܂�܂��B
�Ⴆ�uF2.8 �̃����Y���ƁA��f�s�b�` 1.9��m �����E�v�Əo�܂��i�����͂�����ƈႢ�܂����j�B
���̐�ɏo���� FX150 �Ƃ����R���f�W�̉摜���g�債���̂�����B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9567565/ImageID=310558/
�x�C���[�z��Ȃ̂ŋU�𑜂��������o�Ă��܂����A���_�𑜌��E�͗]�T�ŏo�Ă܂��i�R���g���X�g�͒Ⴂ���ǁj�B
�u���t�� F2.8 �̃����Y�̉𑜌��E�ȂA����Ă݂Ȃ���킩��Ȃ��v�Ƃ����̂����̍l���ł��B
150�{/mm �Ƃ��Ȃ�Ƃ��A�����ȑ���l���Љ��Ă܂����A���������Y��������R���f�W�̉�f�s�b�`���𑜂��邩������܂��B
�R���f�W�̃Z���T�[�Ɋ����ł���Ύ����ł����ł����ǂˁB
�����ԍ��F10160660
![]() 0�_
0�_
���ƁA�v�����\�͐l�ɂ��Ⴂ�܂��B
���̎��Z�ł̓t�H�[�T�[�Y F2.8 �� 1����f�͉𑜂ł���A�Ɠ���ł��܂��i���a���R���f�W���傫���Ɠ���Ȃ邾�낤���NJ��҂��Ă��܂��j�B
1����f�́A�܂����ɂƂ��ď[���ł��ˁB�R���f�W�̃Z���T�[�� 8�قǕ��ׂ�� 1����f���̂��͉̂��Ƃ������ł��܂��B
�u������F�߂Ȃ��v�ƂȂ�ƁA���������Řb���l���邵���Ȃ��A�𑜂̂߂�ǂ������b�����邵���Ȃ��ł��ˁB
�u�����Y���̃N�I���e�B�͌��a�ɔ�Ⴗ��v
�ŏI�I�ɂ͌����������o������Ȃ���ł��傤���ǁA����ł��Ƃ肠�����͌��������Řb�͂ł��܂��i���{���I�Ƃ������邪�A�b���ʓ|�������Ȃ邾���j�B
�����ԍ��F10160716
![]() 0�_
0�_
���s�̂������� ����
�C���Ɋւ��Ă͏�L�̂Ƃ���ł��B
���X�����������A���̌��Ƃ͊�{�W����܂���̂ŁB
���Ȃ�L���ȏ����������ł��B
�܂��s���_���c��悤�ł�����A�ʂ̃X���b�h�𗧂Ăĉ������܂����B
����ƁA���͎�������܂����B���_�ł͂���܂���B
���炽�߂Ď��₵�܂��B
���ꂪ���s�̂�������̋L�����u���Z�œ_�����v�̒�`�ł��B
>�u��p�s�ς̂܂܁g���̑傫���h���t���T�C�Y�Ɠ������Ȃ�悤�Ɋg�k�����Ƃ��̉��z�I�ȏœ_�����v[10144465]
���̂܂܂ł͈Ӗ����ǂ��킩��Ȃ��̂ŁA�����Ȃ�ɐ���������ɕ⑫���Ă݂܂����B
�����Ƃ肠�����⑫���Ă݂�����
�u�t���T�C�Y���Z�œ_�����Ƃ́A�C�ӂ̃t�H�[�}�b�g�ɂ����ĉ�p�s�ς̂܂܁A�œ_�ʂł́g���̑傫���h���t���T�C�Y�Ɠ������Ȃ�悤�Ɋg�k�����Ƃ��̉��z�I�ȏœ_�����v
����P�F���̕⑫�ł͈Ӗ����ς���Ă��܂��܂����H�@����Ƃ������Ă܂����H
�@�@�@�@�ς���Ă��܂��Ă���ꍇ�́A�����������Ă��������܂����H
����Q�F�������Ƃ�����A����ł͔C�ӂ̃t�H�[�}�b�g���t���T�C�Y�ȊO���蓾�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�@�@�@�@���������āA���͂��̒�`�ɂ͖���������Ǝv���̂ł����A�������ł����H
���́A���s�̂�������́u���Z�œ_�����v�ɂ��Ă̔����ł��B
>���Ɗ��Z�œ_�����ɂ��ĂˁB
>���̍l���銷�Z�œ_�����́u�����ʁv�ł���B�u���~���E���[�g���v�Ƃ��̕����ʂł��B[10138450]
����R�F�u�����ʁv�Ƃ́u����ΏۂɌŗL�ȁA�����n�̐������L�q����A�q�ϓI�ɑ���ł���ʁiWikipedia�j�v
�@�@�@�@�u���Z�œ_�����v���u���z�I�ȏœ_�����v�Ə�L�̒�`�ŏq�ׂĂ��܂����A�������Ă��܂��H
�����ɗ��āA����ɋ^�₪�������܂����B
���ׂċ��s�̂�������̏������݂ł��B
>�u���ZF�l���_�v�Ƃ́u�����Y���̉��l�����Z�œ_�����Ɗ��ZF�l�Łi��{��������Łj�\������v�ƌ��������ł���A�Ƃ������Ƃł��B[10156078]
>�����Y���̉��l�ƌ������u�����Y���̃N�I���e�B�v�ł��ˁB���z��Ԃɂ����郌���Y���̃N�I���e�B�Ƃ͉����H
����́u�𑜁v�ł��B[10160439]
>�����Y�̗��_�u�𑜓x�i�{/mm�j�v���E�́u�i���Z�ł͂Ȃ��jF�l�v�Ō��܂�܂��B[10160660]
����S�F���ǁu���Z�v�͕K�v�Ȃ��̂ł͂���܂��H
�����ԍ��F10160720
![]() 7�_
7�_
�Ⴆ�ASIGMA 30mm F1.4 �̂悤�ȁA
�t�H�[�T�[�Y��������Ȃ���Canon��j�R���ł��g���郌���Y������܂��B
�B�e�f�q�̑傫���ɂ���āA�t�H�[�T�[�Y�K�i�������̃}�E���g�ɔ�ׂāu�Â��v�Ȃ邱�Ƃ͖����Ǝv���܂����B�B�B
���Ԃ����Ȃ瓯���I�o�ő��v�ł���ˁH
�ނ���t�H�[�T�[�Y���ƒ��]����60mm�̉�p��F1.4������A���̋K�i���u���邢�v�̂����H(��)
�����ԍ��F10161224
![]() 7�_
7�_
Tranquility����
���Z�œ_�����ɂ��Ă͌��X���ŁB�����������Ƃ��N���邩��X���b�h�����͊�{�I�ɔ��Ȃ�ł����ˁB
�܂����������̂��Ȃ�Ȃ�Łi�����g���{�X���Ŋ��Z�œ_�����Ƃ������t��p���Ă���̂Łj�����܂����A���̒�`�łقڏ[���ƍl���Ă��܂����B
�����Y�����ĐV���Ȍ��w�n��t�^���邱�ƂŃG�l���M�[���X�����Ɋg��k���ł��܂���ˁi�G�l���M�[���X�����͗��z��ԁj�B�t�@�C���_�[���̊g��Ƃ��k���Ƃ��A�����������Ƃ��q�ׂĂ��܂��B
���z�I�ȏœ_�����ɂ��ẮA��������������Ɋg��k�������ꍇ�Ɂu�œ_�����v���`�ł���̂����͒m��Ȃ����߂ɂ��������܂����B
�܁A�Ԃ����Ⴏ�u�t���T�C�Y�g���ē�����p�̎ʐ^�B�낤�Ƃ���Ɖ��~���ɂȂ�́H�v�Ƃ��������Ƃ������������ł��B
����i�t���T�C�Y�������牽�~���H�j�ɑ��āu���a���Ŋg��k���v�Ƃ���������t�^���������ł��B�ŁA�{�X���ł͍��܂ł̂Ƃ���A���������V���ȏ����͕K�v�����c�_��W�J���Ă��܂��i��`�Ƃ������̂͂��낢�날���ē��R�j�B
�����ʉ]�X�ɂ��Ă͌��X���ŁB
>����S�F���ǁu���Z�v�͕K�v�Ȃ��̂ł͂���܂��H
����ɂ��Ă͌����Ă���Ӗ����킩��܂��B
�����ԍ��F10163508
![]() 0�_
0�_
�{�X�g�[�NT-233����
���݂܂���B���ɂ�����ƕ���܂���B
�r�r�X�X�X����͊��ZF�l���g���Ă܂��B
�V���v�������猾���A���ZF�l�͗v��Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ƃ������A�u���ZF�l�Ő����o����v�Ƃ���������ǂ��ǂނƁA����
���ʂ̖ʐςŐ������Ă����肵�܂����珮�X�ł��B
����������̂������Ȃ��A�����������A�Ƃ����̂ł���A���i.COM
�ł͂Ȃ��A�ʂ̂Ƃ��낪���������悤�ɂ��v���܂��B
�i���ZF�l���g��Ȃ��̂��V���v���Ŕ������Ƃ����I�`�ł͖����ł���� ^^;�j
�����ԍ��F10164016
![]() 7�_
7�_
�ʐ^���猩��AF�l�͊��Z���Ȃ��ƁA�Œ��ꒃ�ɂȂ�܂��B�܂������g���l���Č����炢�����ł��傤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10165231
![]() 0�_
0�_
���̖Œ��ꒃ�ɂȂ����T���v���������Ē��������ł��˂��B
���_�𗠕t���邽�߂́u�������͊ϑ������Ă��Ȃ��v�Ƃ͂ƂĂ��v���܂���̂ŁA
�ǂ�ȕ��@�Ō������̂��A�����Ăق����ł��B
�i���R�A�ǂl���ǎ����ē������ʂ��m�F�ł���悤�ɏ����Ă��炢�����B�j
���̎����ɂ���ă����Y�̂ǂ�ȓ������������āA�ǂ̂悤�ȍl�@�������̂�
�������Ăق����ł��B�ł���@�ނ̃Z�b�e�B���O�̎ʐ^���\���Ă��������B
�u�������Ȃ��Ă��l����Ε�����v���ƃI�J���g�����A
���̃T�C�g�ւ̃����N�\��͖̂{�l�̎咣�Ƃ͌�����̂ŋp�������Ă��������܂��B
�����ԍ��F10165431
![]() 17�_
17�_
���s�̂������܁F
���X���ŋc�_���鎖�́A���Ɨ��ꂪ�c�_�����X�����邱�ƂɂȂ�܂��B�܂��A
���X���ŋc�_���Ă���ƌ����Ă��A�l�X�Șb�肪����ł���̂łǂ̂��Ƃ�
�ƂĂ�������ɂ����̂ŁA�R�s�[���y�[�X�g�ł����Ē������A�v�Ă���
�ő�����ꂽ�����A���̃X���������ɂȂ��Ă������������₷���̂ł�
�Ȃ��ł��傤���B�ʓ|�Ȃ�d������܂��ǂˁB
�݂Ȃ��܂ցF
����܂ł̋c�_�������Ȃ�ɂ܂Ƃ߂�����ł����A����ɂ��ẮA����
�܂ň٘_������w�E����܂���ł����B�܂�́A����܂ł̋c�_�͂���
�������Ƃ��������������Ƃ������Ƃł悢�ł��傤���B
�����ŁA���[�����������邽�߂ɂƂĂ��V���v���Ȏ���������ĉ������B
�t���T�C�Y��50mm F2.0�i�Ⴆ�AOM ZUIKO 50mm F2.0�Ȃǁj�ƁA�t�H�[�T�[�Y
��50mm F2.0���t�H�[�T�[�Y�ɑ��������Ƃ��A�t���T�C�Y��50mm F2.0�́u�Â�
�Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
����܂ł̋c�_�ł́A���a������˂������͑S�ĎB���f�q�ɓ���Ƃ��������
�c�_����Ă��āA�t���T�C�Y�̃����Y�������2�i�Â��Ȃ�Ƃ����c�_��
�s���Ă����Ɨ������Ă��܂��B�i���a�̘b�������ŁA���a���������ꍇ�ɂ́A
�œ_������2�{�ɂȂ�ƎB���ʐς�4�o�C�g�Ȃ�A���ʂ�1/4�Ɍ�������Ƃ���
�b���͂ǂ����ɒǂ�����Ă���悤�ɂ������܂����A����͉��ɒu���Ă���
���Ƃɂ��܂��B�j����2�{�̃����Y�́A���a������25mm�ł��B
���̗������������Ƃ����O��̉��ł́A�t���T�C�Y��50mm F2.0��
�t�H�[�T�[�Y��50mm F2.0���t�H�[�T�[�Y�̃J�����ɑ��������ꍇ
�ɂ͓�����p�i�t���T�C�Y100mm�����̉�p�j�ƂȂ�܂��B�������A
�t���T�C�Y�̃����Y�̓C���[�W�T�[�N���̈ꕔ�����g���Ă��Ȃ���
�������ƂőS�̌��ʂ�1/4�ɂȂ�܂���ˁB
�����ŁA�ȉ��̋^�₪�����т܂����B
�^��P�F����́A�u�Â��v�ƒ�`����̂ł��傤���B
�@�@�@����܂ł̎咣�Ȃ�u�Â��v�ƌ������ƂɂȂ�܂���ˁB
�^��Q�F�{���ɈÂ��ł��傤���B�������Ă��Â��Ȃ�܂���B
�@�@�@�����i��l�A�V���b�^�[�X�s�[�h�Ŏʐ^���B��܂��B
�@�@�@����́A�ǂ����Ăł��傤�B����1/4�̂͂��ł���ˁB
�@�@�@OM-ZUIKO�́A�d�C�M�����������Ă��Ȃ��̂ŏ���ɃQ�C��
�@�@�@�A�b�v�Ȃ�ďo���܂���B
�^��R�F���ZF�l�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤�B
�@�@�@���҂Ƃ������E�E�E�ł����H
���̋^��ɂ������Ƃ�����������ƗL���ł��B
�����ԍ��F10165602
![]() 6�_
6�_
�ꕔ�������܂��B
�u�E�E�E�B���ʐς�4�o�C�g�Ȃ�A�v
��
�u�E�E�E�B���ʐς�4�{�ƂȂ�A�v
�ł��B
�B���f�q��4�o�C�g�ƂȂ�Ƒ�ςł��B�\�������܂���B
�����ԍ��F10165662
![]() 0�_
0�_
�� ���̖Œ��ꒃ�ɂȂ����T���v���������Ē��������ł��˂��B
�ȒP�ł���B���܂ł�F�l�ƏƓx�A���x�̘b�͒P�ʖʐς̍l�@�ŁA
�P�ʖʐϓ��ł�����A�n�[�t�T�C�Y����A�唻�܂őS�ē����ł��B
�ܘ_�����t�B�������g���ē����I�o�A����������掿�������ł��B
�ł����AF�l��I�o�A�g�P�ʖʐς̉掿�h�������ł��A����͒N�ł�������܂����A
�n�[�t�T�C�Y�Ƒ唻�́g�ʐ^�̉掿�h�������Ƃ͒N�������܂���B����͔�펯�ł��B
����ł́A�������`�����X��^���܂�����A�l���Č��܂��H
�����ԍ��F10165668
![]() 1�_
1�_
�Z���JGT-Four-A����
���Ȃ������̃X���𗧂Ă��Ӑ}�͂킩��܂��A���̘b��Ɋւ��Ắu�݂�Ȃ������Ă邱�Ƃ��o���o���v���Ă����̂���Ԃ̖��ŁB���ƌ��������ɂ����Ƃ������ƂȂ�ł����ǂˁB
�܂��A���̕��ɂ��Ă����_���ł܂��Ă���킯�ł͂���܂���B�ł���������x���ނ��邱�Ƃ��ł����Ɗ����Ă��܂��B
��̕��ށB
�E�u�B���O�v�Ɓu�B����v
�E�u���̗��q���v�Ɓu���̔g�����v
��҂ɂ��Ă͒m��������킯�ł͂���܂��A��������ʂ肠��̂Ő������@������ɉ��������̂ɂȂ�܂��i����������Ă����͔̂g�����ł��j�B
�ǂ��̈ʒu�ɗ������b�����Ă���̂��A���ӎ��������������ł��B
�X����� �Z���JGT-Four-A���� ��������o���ꂽ�̂ŁA����ɂ����������Ă݂܂��B
>�t���T�C�Y��50mm F2.0�i�Ⴆ�AOM ZUIKO 50mm F2.0�Ȃǁj�ƁA�t�H�[�T�[�Y
��50mm F2.0���t�H�[�T�[�Y�ɑ��������Ƃ��A�t���T�C�Y��50mm F2.0�́u�Â�
�Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
�u���������Y�̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�v�ł��ˁB���������ꍇ�́u�t���T�C�Y�� 50mm F2.0 �����A�g���~���O�Ɣ�g���~���O�v�Ƃ��Ă��������i���R�͂��������q�ׂ܂��A�l�@���V���v���ɂ��邽�߂ł��j�B
���̃`���[�g�̂悤�ɎB�e�̂悤�ɔ�ʑ̂����肳��A���t�H�[�T�[�Y�̉�ʑS�̂Ɏ��܂�Ƃ��A�u���̓���̔�ʑ̂Ɋւ��Č����Ȃ�ΑS�������v�ł��B
�����Y�����S�������A���g���~���O�ō���Ă��Ȃ����痼�ґS���������̂ł��B
�������ψ�O���[�J�[�h���i�t���T�C�Y�́j��ʑS�̂ɓ���ĎB�e����ꍇ�ȂǁA�u���S�ɋψ�œ���Ȗʂ��B�e����i���S�g�U�ʂƌĂԂ����j�v�ꍇ�́u��ʑS�͓̂�i�Â��v�Ȃ�܂��B�ǂ�����ǂ��܂ł���ʑ̂ȂǂƂ�����ʂ������i�����炱���u��ʑS�̓��m�Ŕ�r����v�Ƃ�����r���@�����藧�j�A�t�H�[�T�[�Y�̑S�̌��ʂ��t���T�C�Y�� 1/4 �ɂȂ邩��ł��B
�������t���T�C�Y�ɂ́u���ӌ����v�������I�ɑ��݂���̂ŁA���S�ɓ�i�̍�������킯�ł͂���܂���B
�Ƃ͌����A�t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̉�p�Ⴂ�́i�����̎���|����Ƃ��Ắj�ǂ���r�ł͂Ȃ��̂ł����ǂˁi�����炱���u�Y�[���̈Ӗ����l���Ă݂Ă��������v�Ə������̂ł����j�B
����t�H�[�}�b�g�ɂ����ăY�[������Ƃ́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�u��ʑ̑��S�̂̌��ʂ�������v���ʂ������炷���A���p�҂���������҂��Ă��邩��ł��B�u�ʂ��Y�[���v�́u�Y�[�~���O�ɔ����A���j�A�ɔ�ʑ̑S�̂̌��ʂ������A��ʑ̉𑜂��������Ɓv���Ӗ����܂��B�������p�ƌ��т��u300mm �̉�p�� F2.8 �͂��ꂾ���̌��ʂƔ�ʑ̉𑜂�������ȁv�Ɗ��҂���킯�ł��B
�����Y���̃N�I���e�B�ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B
�����ԍ��F10165949
![]() 0�_
0�_
>�^��Q�F�{���ɈÂ��ł��傤���B�������Ă��Â��Ȃ�܂���B
����́u�B����v�Łu���̗��q���v�ł��ˁB
���Ȃ��̃f�W�J���ŃO���[�J�[�h���B�e���A�g���~���O�Ɣ�g���~���O�摜�Ŕ�r���Ă݂Ă��������B
��ʒ��S�t�߂̓����͈́i�s�N�Z���������j�ł� S/N��͓����͂��ł��B
��g���~���O�摜��ʐ� 1/4 �ɏk�������摜�ł͉�ʒ��S�t�߂� S/N��͔�g���~���O�摜���Q�{�ł��B��������g���~���O�摜�̎��ӂ͌�������Ă��܂��i���������Ɖ�ʎ��ӂ� S/N�䂪����j�B
>�^��R�F���ZF�l�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤�B
���ZF�l�͊��Z�œ_�����ƃZ�b�g�ōl���܂��B
�t�H�[�T�[�Y�̕��͊��Z���āu100mm F4.0�v�ł��B
�����ԍ��F10165977
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B
���������悤�Ɂu���Z�œ_�����v�ƌ����Ă�����̂�
>�Ԃ����Ⴏ�u�t���T�C�Y�g���ē�����p�̎ʐ^�B�낤�Ƃ���Ɖ��~���ɂȂ�́H�v�Ƃ��������Ƃ����i���͉��H�������H�j���������ł��B[10163508]
�ɂ����܂���ˁB
���ꂾ���̈Ӗ������Ȃ��A���z�����u���Z�œ_�����v���Ӗ�������悤�ɐ����ɓ��Ă͂�
�t�H�[�}�b�g�̑召�ɂ��掿�̍���������悤�Ɗ�Ă����̂Ȃ�ł��傤���c
���ɂ͂��̎����牽�����Ƃ��Ă���̂��A�悭�킩��܂���B
���z�������l�����ɑ}������ƁA���̎��ɈӖ�������悤�Ɋ������܂��ˁB
���������A�����������l�H�𐔎��Ɏg�p�o������̂Ȃ�ł��傤���H
���Z�œ_�������i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×�œ_����
���ZF�l�����Z�œ_����÷�L�����a
�������ł�����
���ZF�l���i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×�œ_����÷�L�����a
�܂�
���ZF�l���i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×F�l
�������Ɏ��ɂ͏����邯�ǁA�����牽�H�Ƃ��������Ȃ�ł����B
�ǂȂ������w�ɋ������A���̎���������ĉ������܂��H
���������t�H�[�}�b�g�̑召�ɂ��掿�̍��́A�����Y�̉𑜗͂̍��̉e��������܂��傤���A
�C���[�W�Z���T�[�Ȃ�t�B�����Ȃ�̐��\�����傫�������Ă�����̂ł��B
�����ȃt�H�[�}�b�g�͊ӏ��ɑ傫���g�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����瓖�R�ł��B
�������A�t�B�����̎�ނɂ���ē����t�H�[�}�b�g�ł��傫�������o��悤��
�f�W�^���ł��C���[�W�Z���T�[�Ɖ摜�����G���W���̔\�͂ɂ���đ傫�������o�܂���ˁB
����͓����t�H�[�T�[�Y�ł��ǂ�ǂ��x�掿���オ���Ă��邱�Ƃł��킩��܂��B
�ł����烌���Y�ƃC���[�W�Z���T�[����̂Ƃ��ĂƂ炦�掿��_����̂́A���{�I�ɖ���������Ǝv���܂��B
���鐯���߂炳��
>�n�[�t�T�C�Y�Ƒ唻�́g�ʐ^�̉掿�h�������Ƃ͒N�������܂���B
���̂Ƃ���ł��B
���l�ɁA�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̉掿�������Ƃ͒N�������Ă܂���B
�������A�ኴ�x�ł͂قƂ�Ǎ����Ȃ��A�����x�ł�����̍��ł����Ȃ��̂�����
�t�H�[�T�[�Y�̋Z�p�҂͂����Ƃ��撣���Ă���ƌ�����̂ł͂���܂��H
����ƁA�n�[�t�T�C�Y�Ƒ唻�ł�����F�l�̃����Y�̖��邳���Ⴄ�Ƃ͒N�������܂���ˁB
�����ԍ��F10166026
![]() 13�_
13�_
���s�̂�������
>�ψ�O���[�J�[�h���i�t���T�C�Y�́j��ʑS�̂ɓ���ĎB�e����ꍇ�ȂǁA
�u���S�ɋψ�œ���Ȗʂ��B�e����v�ꍇ�́u��ʑS�͓̂�i�Â��v�Ȃ�܂��B
�Ȃ�܂����B
>�ʂ��Y�[���̓Y�[�~���O�ɔ������j�A�ɔ�ʑ̑S�̂̌��ʂ�����
�����Ŕ�ʑ̂Ƃ́u��ʑ̂̏œ_���v�̂��Ƃł����H
���Ƃ�������ʂ͑����܂����B
��������Y�������Ă鑤�̔�ʑ̂̌��ʂ������܂���B
�����ԍ��F10166093
![]() 4�_
4�_
����ROM�ꂵ�Ă܂��B
���s�̂�������@
���u���������Y�̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�v�ł��ˁB���������ꍇ�́u�t���T�C�Y�� 50mm F2.0 �����A�g���~���O�Ɣ�g���~���O�v�Ƃ��Ă��������E�E�E
����H�u���������Y�̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�v�ł͖����A�u�����t�H�[�}�b�g�́A�����Y�Ⴂ(�œ_�����Af�l�A���a�������AOM�I�[���h�����Y��ZD�����Y)�v�ł͂���܂��H
�ǂ����O������Ⴂ����Ă���l��...�B
�ł��A���̌��ʂ��ǂ��Ȃ邩�A�ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B(OM�����Y�g���Ă��܂����A2�i�Â��Ȃ����L���������̂ŁB)
�����ԍ��F10166103
![]() 6�_
6�_
���s�̂�������
�ЂƂԎ����Y��܂����B
>>����S�F���ǁu���Z�v�͕K�v�Ȃ��̂ł͂���܂��H
>����ɂ��Ă͌����Ă���Ӗ����킩��܂��B
>�����Y�̗��_�u�𑜓x�i�{/mm�j�v���E�́u�i���Z�ł͂Ȃ��jF�l�v�Ō��܂�܂��B[10160660]
���Ȃ������g���u�����Y���̃N�I���e�B�͊��Z�ł͂Ȃ�F�l�Ō��܂�܂��v�ƌ��_����Ă܂��B
�����ԍ��F10166125
![]() 5�_
5�_
���s�̂�������
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂����B
�����A�ǂ������܂������ł��Ă��܂���B�u�ǂ������Y�Ȃ�A�������x�𑜂ł����v�Ƃ������Ƃ�����������Ă���̂��A����Ƃ�MTF�Ȑ��Ȃ�Ă��܂�Ӗ����Ȃ����Ă��ƂȂ̂��i�������̓_�ɂ͔������炢���ӂ��܂����j�E�E�E
> �u�����Y���̃N�I���e�B�͌��a�ɔ�Ⴗ��v
������āu���̏����������Ȃ�v�Ƃ������Ƃł���ˁB�܂��������Y���̃N�I���e�B�����a�����Ō��܂�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł���ˁB
�u�B���O�v�Ɓu�B����v�̘b���Ă����̂��A����Ղ�Ղ�ł��B
���炭�܂�ROM��ɖ߂��āA�F����̋c�_��ǂ݂Ȃ���A��������l���Ă݂܂��B
�����ԍ��F10166129
![]() 2�_
2�_
���s�̂�������
�܂��V�������邳���o��ł��ˁB
>�u�Y�[�~���O�ɔ����A���j�A�ɔ�ʑ̑S�̂̌��ʂ������A��ʑ̉𑜂��������Ɓv
�����t�H�[�}�b�g��F�l�������Ȃ̂Ɍ��ʂ��ς��܂����B^^;
�u�t�H�[�}�b�g���Ⴄ����F�l�������Ȃ�S�̂̌��̃G�l���M�[���Ⴄ�v�ƌ����̂ł���A�i�掿�ɑ���e���͂Ƃ������j�u�܂��������ˁv�Ƃ����̂����ʂ̔������Ǝv���܂��B�ł��AF�l���t�H�[�}�b�g�������Ȃ̂Ɍ��ʂ�������Ƃ����̂́A�����ł���l�́i���w��������Ă���l�������āj���Ȃ��ł��傤�B^^;
�ǂ�ł��鑤�Ƃ��ẮA���S�҂��悭���ԈႢ�ł���u�����Y�̌a���傫���������邢�v�Ɠ�����ۂ��܂��B
����ƁA�債���b�ł͂Ȃ��ł����A�u���ӌ����v�ƌĂ�錻�ۂ̓t�H�[�T�[�Y�ɂ�����܂���B��Ԃ̉f���ʂɎʂ�����R�T�C���S�摥�̕��͂���܂����A�ώ��ȏƓx�̕��ʂ��ʂ��ꍇ�Ɍ����Ă��A���a�H�������Ƃ����͍̂l���Â炢�ł��ˁB�����A���i���Ƃɔ�ׂ�ƃt�H�[�T�[�Y�p�̃����Y�͌��a�H���������v�ɂȂ��Ă���悤�ł��ˁB
�����ԍ��F10166637
![]() 7�_
7�_
�u���邳�v�Ƃ������t�ɑ��āA
�@����
�A�掿�A�N�I���e�B�[�A�𑜓x
�̓�̈Ӗ����������ċc�_����Ă�̂Řb���܂Ƃ܂�Ȃ��ł��ˁB
�@�́A���ۂ�SIGMA�̂悤�Ƀt���T�C�Y�ł��t�H�[�T�[�Y�ł����ʂ�F�l�Ŏg���郌���Y������Ă郌���Y�x���_�[�����邭�炢�Ȃ̂ŁA
�����v�ō���������Y��F�l���t�H�[�}�b�g�ɂ���Ă����Ƃ͎v���Ȃ��ł��B
�A�ɂ��ẮA�t���T�C�Y�͎B���f�q���傫���ėL���Ȃ���A
�������ɂȂ�Ȃ�قǃt�H�[�T�[�Y���掿���ǂ��ē�����O�ł��ˁB
�������������Ĕ�������A�����łȂ��ƍ���܂��B
��������F�l���掿����Ȃ��Ǝv���̂ŁA���ZF�l���v�Z���ĉ掿��]������͈̂�a������܂��B
F�l���i�����Ƃ��A�[�x���[���Ȃ��Ă��掿���ڂɌ����ė�����̂ł����H
F2.8�̃����Y�́AF1.4�̃����Y���掿������ł��傤���H
�����ԍ��F10166686
![]() 13�_
13�_
����_�w�_���݂����ȗl����悵�Ă��܂����B
�ǂ��l�߂��ĕ⋭�����邽�тɒ������lj������
����悤�Ɏv���̂ł����A���{�l�͂����炭�C�Â�
�Ă��Ȃ��i���邢�́u���̐l�̗���͂̂Ȃ��v��
����Ă���H�j�̂��߈���U���܂��B
�����ԍ��F10166760
![]() 7�_
7�_
Tranquility����
���Ȃ��̌����Ă����u���Z�œ_�����v�̈Ӗ�����Ƃ킩��܂�����B�u�p�x�v��\���A�ƁA����������Ɛ��m�ɏ����Ă��炢���������ł��i�܂��ł킩��Ȃ������j�B
���̒�`�ł������ł���B���������ŋ�������`�́A���X�́u���邳�̒�`�v�ɃC�`���������Ă���l����������l������`�ł�����i�G�l���M�[�ۑ����͂��邯�ǁA�Ɠx�ۑ����͂Ȃ���A�Ƃ������Ɓj�B�ŁA�����ʂł��B���肵�č�}����B
>��������F�l���掿����Ȃ��Ǝv���̂ŁA���ZF�l���v�Z���ĉ掿��]������͈̂�a������܂��B
F�l�͉掿��\���Ă��Ȃ��BF�l���掿��\���悤�ɍ�������_�ł��i��������x���������Ƃ��j�B
���ZF�l�F�u�����YF�l × �t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���v�Œ�`�����l�B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���F�u���Z�Ώۃt�H�[�}�b�g�ł̓����p�������œ_���� �^ ���t�H�[�}�b�g�̏œ_�����v�Œ�`�����l�B
��`�̈��͂��̂悤�ɃV���v���Ȃ��́B
����ɂ��ς̃����Y�̑���
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DMC-FZ1
����́u���Z300mm F2.8�v�̃����Y���͑S���قȂ�܂��B
���ʂ���̂́u�ʏƓx�v�Ɓu��p�v�����ł��B���̂�����p�̓����Y�����̂��̂ł͂���܂���i�t�H�[�}�b�g���݂̊T�O�j�B
�����ԍ��F10166923
![]() 0�_
0�_
�Ƃ肠�����掿���𑜗͂Ɖ��肵���ꍇ�ōl���Č��܂����B
�����������Y�̏ꍇ�A��ʑ̂ɑ��镪��\�̓����Y�̗L�����a�Ō��܂�܂����A�œ_�ʂ̉𑜗͂͏œ_�����ɊW�Ȃ��e�l�����Ō��܂�܂��B
�i���̂ւ���Ȃ�������ɂȂ��Ă����ۂ��܂����j
���������Ė����������Y�ł���A�����e�l�̃����Y���g����������L���{�����������t���T�C�Y�̕����𑜂Ƃ����_�ł͊m���ɗL���ł��B
�������A���t�̃����Y�͍����\�Ȍv���p�Ε������Y��V�̖]�����ȂǂƔ�ׂ�Ǝ��������|�I�Ɉ����A�e�l������������Ƃ����ĉ𑜗͂�������킯�ł͂���܂���B
�C���[�W�T�[�N�����������������Ɏ�����lj��ł���Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y�����Y�̕���\���K�������t���T�C�Y�ɗ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
�i�t���T�C�Y�ōi��J������M���M���ɉ𑜂��郌���Y��������Ȃ�Ȃ��ł��傤���ǁB�j
�t�H�[�T�[�Y���Ă��Ƃ��Ƃ��������l������������Ȃ����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10166955
![]() 4�_
4�_
�u��v����
>����H�u���������Y�̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�v�ł͖����A�u�����t�H�[�}�b�g�́A�����Y�Ⴂ(�œ_�����Af�l�A���a�������AOM�I�[���h�����Y��ZD�����Y)�v�ł͂���܂��H
���A����B�ق�Ƃł��ˁB
����͋^��P�^��Q�Ƃ��u�Â��Ȃ��v�ł��ˁB�^��R�̂ݑO�ɏ������Ƃ���B
�����ԍ��F10166965
![]() 0�_
0�_
>�Ƃ肠�����掿���𑜗͂Ɖ��肵���ꍇ�ōl���Č��܂����B
���z��Ԃ̃����Y���ɂ����āA���͂���ȊO�̉掿�v�f���v�����Ȃ��̂ł��i������O�ɏ����܂����j�B
�����ԍ��F10166971
![]() 0�_
0�_
>�C���[�W�T�[�N�����������������Ɏ�����lj��ł���Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y�����Y�̕���\���K�������t���T�C�Y�ɗ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
>�i�t���T�C�Y�ōi��J������M���M���ɉ𑜂��郌���Y��������Ȃ�Ȃ��ł��傤���ǁB�j
>�t�H�[�T�[�Y���Ă��Ƃ��Ƃ��������l������������Ȃ����Ǝv���܂��B
���z��Ԃ��ĉ��x�������Ă��ł����ǂˁB�����Y����\�̎��Ȃ�@���Ȃ肪���藧�n�ł̘b�B
���̓t�H�[�T�[�Y���ǂ��Ƃ����ċ��������ł��B���������Y�͂��������Y�B����ƃ����Y�X�y�b�N�͕ʁB
�����ԍ��F10166988
![]() 0�_
0�_
���s�̂������� ����
����ɂ��́B
��́u���Z�œ_�����v�ɂ��ď�������ʼn��������̂ł��ˁH
>���Ȃ��̌����Ă����u���Z�œ_�����v�̈Ӗ�����Ƃ킩��܂�����B�u�p�x�v��\���A�ƁA����������Ɛ��m�ɏ����Ă��炢���������ł��i�܂��ł킩��Ȃ������j�B
�ȉ��́A���X���̎��̏������݂̈ꕔ�ł��B
�����̂ڂ��ēǂނ̂͑�ςȂ̂ŁA�R�s�[���Ă����܂��B
-------------------------
�u���Z�œ_�����v�ƕX�I�Ɍ����Ă��邱�Ƃ́A�u����t�H�[�}�b�g�ŔC�ӂ̏œ_�����̃����Y���g�p�������A����Ɠ���̉�p��35mm���œ��邽�߂ɕK�v�ȃ����Y�̏œ_�����v�ł���܂�����A�����āu���Z�œ_�����́���mm�����v�ȂǂƂ����������������ɁA�P���Ɂu�t�H�[�T�[�Y����mm�̉�p��35mm���́���mm�����v�Ɛ������ׂ��ł��B
-------------------------
�����������Z�œ_�����Ƃ�
�u�t�H�[�T�[�Y25mm�����Y�́g��p�h��35mm����50mm�����Y�Ɠ����v
�Ƃ������Ƃ�\�����������ɂ����܂���B
-------------------------
�v����Ɂu���Z�œ_�����v�Ƃ������̂́u��p�v����X�̂Ȃ���35mm���ɂ��Ă͂߂Ă킩��₷���\�����������́A���̂̂Ȃ����l�ɉ߂��܂���B
���̎��̂̂Ȃ����l�����a�Ŋ����ďo�Ă��鐔�ɂ́A�܂��������̈Ӗ��������Ƃ������Ƃł��B
-------------------------
���m�Ɍ����Ɓu���Z�œ_�����v�͊p�x��\���Ă���̂ł͂���܂����B
�ǂ���ǂ�Łu�p�x�v��\���Ɖ��߂��܂����H
>�ŁA�����ʂł��B���肵�č�}����B
�u���z�I�ȏœ_�����v���A�ǂ����肷��̂������������̂ł����H
�Ƃ���ŁA�����O�̏������݂ŏ�������
>���Z�œ_�������i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×�œ_����
>���ZF�l�����Z�œ_����÷�L�����a
>���ZF�l���i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×�œ_����÷�L�����a
>���ZF�l���i�t�H�[�}�b�gA�̑Ίp����÷�t�H�[�}�b�gB�̑Ίp�����j×F�l
�́A���ZF�l���������߂̎��i�H�j�ł����A���s�̂�������̏����Ă邱�ƂƓ����ł���ˁH
>���ZF�l�F�u�����YF�l × �t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���v�Œ�`�����l�B
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���F�u���Z�Ώۃt�H�[�}�b�g�ł̓����p�������œ_���� �^ ���t�H�[�}�b�g�̏œ_�����v�Œ�`�����l�B
�����̎����ǂꂭ�炢�u�H�v�Ȃ��Ƃ������Ă��邩�ƌ����ƁA����Ȋ����Ɍ����Ă���̂Ɠ����ł��B
�킩��₷���t�H�[�T�[�Y��150mmF2.0���ɂ��܂��B
�u�t�H�[�T�[�Y���āA�t���T�C�Y�̔����̑傫�������Ȃ��Z���T�[�T�C�Y����ˁB�������p����l�����150mm�̓t���T�C�Y��300mm���Ă��Ƃł���B
F2.0�ŏœ_������150mm������A���a��75mm����ˁB��������300mm�Ȃ̂Ɍ��a��75mm�����Ȃ�����A300÷75�ŁAF��4.0�ł���B
F2.0���Č��������Ď���F4.0�Ȃ���A�t�H�[�T�[�Y���ĈÂ���ˁB�v
���������̂��u�k�فv�ƌ����܂��B
�ł��A���ZF�l�_�҂́A����̂ǂ����k�قȂ̂��킩��Ȃ��̂ł��傤�˂��B
�����ԍ��F10168397
![]() 16�_
16�_
���s�̂�������
�����܂���uF�l���掿��\���悤�ɍ�������_�v�Ƃ����̂������ł��Ȃ���ł��B
�@>���ZF�l�F�u�����YF�l × �t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���v�Œ�`�����l�B
�@>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���F�u���Z�Ώۃt�H�[�}�b�g�ł̓����p�������œ_���� �^ ���t�H�[�}�b�g�̏œ_�����v�Œ�`�����l�B
�Ƃ������v�Z���������ʂ̐��l�������Ӗ����邩�H
���̌v�Z������Ɖ��Ɋ��p�ł��āA�����������̂��H
������Ǝ��̓����Ƃ��̌f���ł������������Ă������ł��Ȃ����ł��i�j
�������͕s�v�ł��恦
�o���I�ɁA���t�̃T���j�b�p�ŎB�����ʐ^�̕����A
�R���f�W�̃T���j�b�p���掿���ǂ��̂͂킩��܂��B
�����悤�ɁA�t���T�C�Y�̃T���j�b�p�ŎB�����ʐ^�̕����A
�t�H�[�T�[�Y���掿���ǂ��̂��킩��܂��B
�ł�������ĎB���f�q�̑傫�����܂������Ⴄ���瓖�R�̂��Ƃ��v���̂ŁA
�f�l�̎��̓����Y�̊��ZF�l����掿�̕]�������������v�Z����̂͂�߂Ă����܂��ˁB
�����ԍ��F10168404
![]() 10�_
10�_
Tranquility����
�������Ŏ�(�H)�̎g�����������ł��܂����I
����������300mm ×
����������150mm�ł��ˁI
�����ԍ��F10168652
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
�����̖�肪����̂ŁA������Ƃ����������܂��ˁB
�������_��3����܂��B
1. �u�掿�v�̈Ӗ�
2. �u���邳�v�̈Ӗ�
3. �u���ZF�l�v�̈Ӗ�
1. �Ɋւ��Ă͑����̐l�����s�̂�������ƈقȂ�Ӗ��Ɏg�p���Ă���ׂɍ������Ă��܂��ˁB���s�̂�������́u�����̖��������Y�̉𑜓x�v�̈Ӗ��Ɏg�p���A���̐l�́u���܂��܂ȗv�f���g�ݍ��킳�������̉掿�v�̈Ӗ��ɉ����Ă��܂��B
���̖�����������̂͊ȒP�ŁA�ǎ҂��z�N����u���܂��܂ȗv�f���g�ݍ��킳�����掿�v�ƈӖ������Ȃ��P����g�p����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�����߂������P�ꂪ����܂��B
�u�𑜓x�v���Ӗ�����ꍇ�u�𑜓x�v���g�p����Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�𑜓x���p�x�ő���Ό��E�l�͌��a�Ō��܂�A�����Ōv���F�l�Ō��܂�̂́A���ɋc�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�i���g���ˑ��͂���܂����A����͈Öق̗������\�ȍ��ڂ��Ǝv���܂��j
�u�掿�v�Ə����ƍ������������ăX�����L�т܂��B
2.3.�́A�����v��������A�����܂��ˁB^^;
�����ԍ��F10168950
![]() 3�_
3�_
�����͂Ȃ��Ǝv���܂����A�����������A���������ł����珟��ɂ���ėǂ��Ǝv���܂��B
���ʂɊ֘A����掿�ł��̂ŁA�F�����Ƃ��]�v�Ȃ��Ƃ͂���܂���B
���ʂƊ֘A����掿�i���������x�掿�ASNR�j�͒����̊֘A���������āA
�����������A���������������܂��i�m�C�Y �� ����ʁA���� �� �m�C�Y�̕����j�B
���g�Â��h�̒�`�́A���ꎫ���ׂ��炨������Ǝv���܂��B���ʂ͊W������܂����A
��͌��ʂł͂Ȃ��ASNR�ł��i�ǂ������邩�ǂ����j�BSNR�͖{���I�Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F10169884
![]() 0�_
0�_
�� ���l�ɁA�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̉掿�������Ƃ͒N�������Ă܂���B
F�l�������ł��A�Ⴄ�t�H�[�}�b�g�ł͔�r�����Ȃ��A�Ӗ����Ȃ��̂�������܂����ˁB
�� �������A�ኴ�x�ł͂قƂ�Ǎ����Ȃ��A�����x�ł�����̍��ł����Ȃ��̂�����
���������������̂ł�����A�����ō�������͂��Ȃ��Ǝv���܂��B���̍��ł����A
�Z���T�[�ʐς̈Ⴂ�������ŁA���z�͂҂�����ʐϔ�ł���ƕ�����܂��B
���a�𑊓�F�l�ƕ\�����܂����A����F�l����������AF�l�Ɋ֘A����S�Ă̐����������ɂȂ�܂��B
�Z���T�[�ʐς̃g���b�N�́AF�l�ƑS���������ʂ�����A�܂�F�l�ł��̌��ʑł��������Ƃ��ł���ƌ����܂��B
�����ԍ��F10169971
![]() 0�_
0�_
�u��v����A
�j�A�~�X�Ŏ��̃J�L�R�u10169971�v����ł����B�]�v�Ȃ��Ƃ͂��Ēu��
�g�����悭�����Ȃ���ԁh�̈Ӗ��́ASNR���Ⴂ�ł���Ƃ������ʔF�����ł���Ǝv���܂��B
���SNR�ł��B
���Ȃ݂Ɏ����̏ꍇ�ASNR �� 1�`2������͐^���Â̋��E�����Ǝv���܂��B
���ۂ̌��ʂ́A����ƁA�����x�J�����͈Ⴂ�܂����A����SNR �� 2�ł����瓯���Â��ł��B
�܂��A�I�o�s����SNR �� 2�̎ʐ^���摜�ҏW�\�t�g�Ŕ����������Ă������Â��ł��B
�����ԍ��F10170291
![]() 0�_
0�_
�����͂Ȃ�ׂ�������ŃJ�L�R���������Ǝv���܂����A
�吭���^�I�Șb�����ł��Ȃ��̂��A�I�����p�X���[�U�[�ɑ��ĕs���v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10170423
![]() 0�_
0�_
���ꎫ���Łg����h�̈Ӗ��ׂĉ�����
���鐯���߂炳��̗����Ƃ͐����̈Ӗ����L�ڂ���Ă��܂���
�Ȃ����ꂪ�����Ȃ�Ɩ�̂킩��Ȃ����������Ă��܂����̂ł��傤��?
�����ԍ��F10170522
![]() 8�_
8�_
�g�����悭�����Ȃ���ԁh�̈Ӗ��́A��SNR�łȂ��Ǝ咣��������A�������������ł��B
����͎�ϓI�Ȃ��̂ŁA����ɂ����E����܂����A���E����Ȃ��悤�A�_�u���u���C���h�Ƃ�
�Ȋw�I�Ȏ�@������܂��B�\�Z�������Đl���W�߂�A���Ȃ萳�m�Ȍ��ʂ������܂��B
�����ԍ��F10170666
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�ЂƂ��₳���ĉ������B
���鐯���߂炳��ɂƂ��āA�u���ꂽ�n��̒��ԁv�Ɓu���ꂽ�n��̖�v��
�ǂ��炪���邭�Ăǂ��炪�Â��̂ł����H
����Ƃ��������邳�ł����H
�����ԍ��F10170717
![]() 3�_
3�_
�Â��̌����͌��ʂł����A�Â��̊��SNR�ł��B
���ʂ��W�Ȃ��ƌ����Ă܂��A�d�v�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�������A����邩�ǂ����̘b�ɂȂ�܂��ƁA�����SNR�����߂邱�Ƃł��B
�����J�����ł́A���͖��邢�A��͈Â��ɂȂ邩���m��܂��A
19���I�O���̃V���{�C�J�����́A������ӁA6�`8���ԘI�o����K�v������܂����B
���̃J�������猩�������A���̃J������������i�̕����y�ɖ��邢�ł��B
����ɔ�ׂ�A4/3�ƃt���T�C�Y�̍��͓�i�����ł�����A�������ł��ˁB
�����ԍ��F10170792
![]() 0�_
0�_
�����g�Œ��ׂė~�����Ǝv���܂����A���Q�l�܂łł��i����ɏE���܂����j�B
http://contest2.thinkquest.jp/tqj2003/60460/rekisi.htm#5
�����ԍ��F10170815
![]() 0�_
0�_
>>�Ƃ肠�����掿���𑜗͂Ɖ��肵���ꍇ�ōl���Č��܂����B
>
>���z��Ԃ̃����Y���ɂ����āA���͂���ȊO�̉掿�v�f���v�����Ȃ��̂ł��i������O�ɏ����܂����j�B
�����܂���A����������Ă����܂��ˁB
�܂����t�̒�`�Ƃ��� �A�i�X�`�O�}�[�g���� �̏����ꂽ�悤�Ɂu����\�v�ł��B��ʑ̂̓�_������������i�������ă����Y���Ƃł���j���E�́u��ʑ̑��̊p�x�v�ł悢�Ǝv���܂��B
��ʑ̂Ƃ̋�������܂��Ă���Ƃ��́u��ʑ̉𑜓x�i�{�^mm�j�v�Ƃ��������������`�ŋ������Ǝv���܂��B���邢�́u�����A�����v�Ƃ�����ʂm�ɂ��邽�߁A�u�����𑜓x�v�Ƃ������������\�ł��傤�B
�����Y���̃N�I���e�B�́u����\�v�Ɓu�����v�̓���v�f�ł���ƍl���܂��B
�����Ƃ��u���a�v�ň�`�I�ɒ�܂���̂ł����A�Ⴆ�uND�t�B���^�[�Ō�������v�Ȃǂ̏ꍇ�i�ǂȂ����̃A�C�f�B�A�����������܂����j�A���a�͈��Ȃ̂Łu����\���̂܂܌���������v�Ǝv���܂��B�u����\�͕ς��Ȃ����R���g���X�g�͌���B�J�����̏ꍇ�͘I�����ԂŘI���ʂ𑝂₵�ăR���g���X�g���ł���v�ƍl���܂��i���̍����m�F�ł����A�����炭�����ł͂Ȃ��ł��傤���j�B�܂背���Y���ɂ����Č����́u�R���g���X�g�̃p�����[�^�[�v�ƍl���܂��i�B����͂���� S/N �����ށj�B
���ǂ̂Ƃ���u�����Y���̃N�I���e�B�͌��a�ɔ�Ⴗ��i���͌��a�̓��ɔ��j�v�Ƃ����̂����̍l���ł��B
����\�͐������i�ꎟ�������j�݂̂ł����A����̖ԓ_�̂悤�Ȋ����œ��Ŕ�ʑ̉𑜓x���u�ʉ𑜓x�v�Ƃ��Ē�`����A���a�̓��ɔ�Ⴕ�܂��B
���a�̓��ɔ�Ⴕ�āu��ʑ̖ʉ𑜓x�v�Ɓu�����v�̓�Ƃ����サ�܂����A�����͕ʂ̃t�@�N�^�[�ł��傤�ˁB�O�҂͌��̔g�����A��҂͌��̗��q���̌���ł��傤�i�悭�킩��܂��j�B
�����ԍ��F10170823
![]() 0�_
0�_
�ł́A���鐯���߂炳��A
�����J�����ł́u���͖��邢�A��͈Â��v�ł����ł����H
�����ԍ��F10170828
![]() 1�_
1�_
19���I�O���̃V���{�C�J�����̃t�H�[�}�b�g�͂ǂ̂��炢�Ȃ̂ł��傤?
��i�ȏ�Â��Ȃ�Ƃ������Ƃ�FT�����̂��������������Ď��ł����?
�����ԍ��F10170845
![]() 0�_
0�_
�� �����J�����ł́u���͖��邢�A��͈Â��v�ł����ł����H
�ǂ��Ȃ��Ƃ͌����Ă܂����B�S�z�͂���܂���B
SNR�͌��ʂ̉e�����f�g�c�ŁA���̃J�����́A�ō����x�t�߈ȊO�A�w�ǘ_���v�Z�Ɠ����Y��ȊW��ۂ��Ă܂��B
�����ԍ��F10170896
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
���Z�œ_�����ɂ��Ă͂����悢�̂ł͂Ȃ��ł����B
�u��p�v�́u�p�x�v���̂��̂ł��B�p�x�̒P�ʂ͉���ނ�����܂����A�݂��ɕϊ��ł�����̂ł��i�����I�ɂ͖��P�ʂł��邪�⏕�P�ʁj�B
�����g Tranquility���� �̕��͂�ǂݍ��ݑ���Ȃ���������������܂��B
�u���z�I�v���āA�����̃����Y�����z�I�ȏœ_�������Ǝv���܂���B��}���āA�v�Z���ċ��܂�B
��`�Ȃ�ĉ��ʂ肩����̂ł��B���̊��ZF�l�̒�`�ɂ́u���Z�œ_������K�v�Ƃ��Ȃ��v���̂�����܂��B
��ɏ������i���ꕪ�q�ԈႦ�Ă������ǁj
���ZF�l �� ���Z�œ_���� �^ �����Y�L�����a
�́A�u������̂ق���������₷�����ȁH�v�Ǝv���ċ��������̂ɂ����܂���B
���Ɓu�k�فv�Ƃ����̂͑������M���錾�t�ł��B
���̍l�����k�ق́u������x���ړI�ŁA�����ł͉R���Ƃ킩���Ă��邱�Ƃ�Ɍ������Ɓv�ł��B
�k�قƂ͍��{�Ɉ��ӂ�����킯�ł�����A�������̂悤�Ȃ��̂��������炱�̃X�����̂��̂��폜�Ώۂł��傤�i�����Ǘ��҂������爫�ӂ̂���X���͍폜����j�B
�����ԍ��F10170907
![]() 1�_
1�_
>�ǂ��Ȃ��Ƃ͌����Ă܂����B�S�z�͂���܂���B
���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�ł́A�����J�����ł́u���͖��邢�A��͈Â��v�ł����ł��ˁB
����ł́A�Ȃ���͈Â��̂ł����H
�����ԍ��F10170910
![]() 0�_
0�_
�� �Ƃ肠�����掿���𑜗͂Ɖ��肵���ꍇ�ōl���Č��܂����B
����́AF�l�Ɗ֘A�����܃{�P�ł����A����F�l����������A�����𑜂ɂȂ�܂��B
�����𑜂Ƃ́A�ʐ^�Ƃ��Ẳ𑜂ŁA��ʍ��E���E�Ίp���̉����̈�Ƃ��̘b�ł��B
�ǂ�������v�Z���Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F10170915
![]() 0�_
0�_
�� ����ł́A�Ȃ���͈Â��̂ł����H
��������ɕ����ĉ������B
�����ԍ��F10170928
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
�u�掿�̈Ӗ��v�ƌ����܂��Ă��ˁB
�݂�Ȃ� �͂炽���� �̂悤�ɍl���Ă���̂ł�����u�掿�Ƃ������t���g��Ȃ��v�ł������ł����E�E�E�B���łɏq�ׂ��悤�Ɂu����\�v�Ɓu�����v�̓��v�f�ɂ��܂����B������u�掿�̓�v�f�v�Ƃ����A�u��̑���_�v�ł�������ł����E�E�E�B
���ۂɂ͂����Ȑl������̂ł���ˁB���̃X���ł� �r�r�X�X�X���� �́u�掿�������̓�����O�v�݂����Ȃ��Ə����Ă܂����B�ʂ̃X���ł�����Ȋ����̐l�����܂����B
�����ԍ��F10170948
![]() 0�_
0�_
Tranquility����A
�M���̎���ɑ��Ă̓����́A[10170792]�ɏ����Ă���܂��̂ŁA���Q�Ɖ������B
���ʂ͌����ł����Ă��A��ɂȂ�Ȃ��ƌ������P�ł����A�ًc������܂������\���o�������B
�����ԍ��F10170949
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
>���ʂ̉e�����f�g�c
���ꂪ���R�Ŗ�͈Â��A�Ƃ������Ƃ̗����ł����ł����H
�c�O�Ȃ���E�`�̕��͂����S���Ȃ��Ă܂��āA�������Ƃ��o���܂���B
����Ɏ����m�肽���̂́A���鐯�J��������̂��l���ł��B
���s�̂�������
>�����̃����Y�����z�I�ȏœ_�������Ǝv���܂���B��}���āA�v�Z���ċ��܂�B
�Ⴂ�܂���B
�œ_����30cm�̓ʃ����Y�́A���z�����������Y���炿����30cm�̏��ŏœ_�����Ԃł���H
����͕������ő���钷���ł��ˁB���z�I�Ȓ����ł͂���܂���B
���s�̂�������������܂����Ƃ��Ă��Ȃ������̂ł�����A�k�قƂ������t��p�����͎̂��̊ԈႢ�ł����B�\���킯�������܂���B�u�k�فv�Ƃ������t�͓P���Ă��������܂��B
�������A��ɏ������悤�ȁu���z�œ_�����v�u���zF�l�v�̌v�Z�́A�s�����Ő������Ȃ����Ƃɂ͕ς�肠��܂���B
�����ԍ��F10171009
![]() 5�_
5�_
>���̊��ZF�l�̒�`�ɂ́u���Z�œ_������K�v�Ƃ��Ȃ��v���̂�����܂��B
�����܂���A���ǕK�v�Ƃ��܂��B
�ʂɕK�v�����ƌ����Ȃ����Ȃ��ł����A
�i�t���T�C�Y�Ƃ́j�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�� �� �t���T�C�Y�̎B���ʑΊp���� �^ ���t�H�[�}�b�g�̑Ίp����
����łł����ł����E�E�E�B
�t���T�C�Y���Z�œ_���� �� �t�H�[�}�b�g�T�C�Y�� �^ ���t�H�[�}�b�g�̎��œ_����
�Ŋ��Z�œ_��������`�ł����Ⴂ�܂�����B
�ŁA���ǂ������犷�Z�œ_�����ɂ��Ă����ȉ��߂��\�ł��傤���B
�ł����Z�œ_�����̒�`�ɂ��Ă͂Ƃ₩�������قǂ̂��̂ł͂Ȃ��ł��B�����Y���̕���\�ƌ����̓�ɂ��Ă͂��́i���Z�œ_�����́j��`�����ɂ��̌��\���ϑ��ł��܂��i���ꂪ�d�v�I�j�B
�����ԍ��F10171032
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
���݂̃����Y�͕����̃����Y��p���č\������Ă܂���ˁB�u�����͉��z�I�Ȉꖇ�̒P�����Y�ɑ�\�����邱�Ƃ��ł���v�Ƃ����̂����̔F���ł��B
������͐��Ƃł���܂��A������v�Z���ؖ����ł��܂��B
�u�����Y�̎�_�v�ɂ��Ă������ł��傤�B�O����_�E�㑤��_�A�����̓����Y���ɂ���܂���B�ԃ}�W�b�N�ŋ�ԂɋL���Ă�����݂̂��̂ł͂���܂���B�v�Z���č�}���ċ��߂���̂ł��傤�B
�����ԍ��F10171047
![]() 0�_
0�_
>�i�t���T�C�Y�Ƃ́j�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�� �� �t���T�C�Y�̎B���ʑΊp���� �^ ���t�H�[�}�b�g�̑Ίp����
>����łł����ł����E�E�E�B
>
>�t���T�C�Y���Z�œ_���� �� �t�H�[�}�b�g�T�C�Y�� �^ ���t�H�[�}�b�g�̎��œ_����
>
>�Ŋ��Z�œ_��������`�ł����Ⴂ�܂�����B
����Ȃ�����Ȃ��B
�u�t�H�[�}�b�g�T�C�Y��v���Ă����������ŕK�v�H ���Č����ƁA�����͂���u���Z�œ_���������߂邽�߂ɕK�v�v�Ȃ�ł��B
����ȊO�ɂ��t�H�[�}�b�g�T�C�Y��͂������p����܂����B���̓_�ł� F�l�Ɠ����BF�l�͑��ʏƓx���狁�߂��B�ł�F�l�͑��ɂ������p�ł���B
�������傭�u��`�v���Ă̂́u����Ȃ���v�Ȃ�ł��B
�u��`�Ƃ́A������l�����l�̎v�������߂��Ă�����́v�ł��B�u�ŏ��ɈӖ��A�A�C�f�B�A�A�v�z�Ȃǂ��肫�v�ł��B
�����ԍ��F10171074
![]() 0�_
0�_
F�l��A�Ɠx�A�I�o�v�Z�Ȃǂ́A�P�ʖʐς�Ώۂɂ��܂��̂ŁA�ʐ^�Ƃ͊T�O���Ⴂ�܂��B
�ʐ^�͉�ʑS�̂�Ώۂɂ��܂��̂ŁA����̓Z���T�[�S�́A�������͓������̈ꕔ�ł��B
���̓����ʂ��Ȃ��ƍ������܂��̂ł����ӂ���K�v�ł��B
�ʐ^�̎��_����́AF�l��Ɠx�ȂǒP�ʖʐς�Ώۂɂ���̂��͖̂Œ��ꒃ�Ӗ��s���Ȃ��Ƃ�
�����܂������A����͂�����ƍl�����璼��������Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Γ����ꕽ���~���̖ʐςł����A�����4/3��ʂ�0.445%�A35�~����0.116%�ɂȂ�܂��B
�����ꕽ���~���ł͊ԈႢ�܂��A��ʏ�ł́A4/3�̕���4�{���傫���ł��B
35�~�����̎ʐ^�����x��̖ڂ��ʂ����Ƃ���A4/3�ł͔��т�@�̈ꕔ���ʂ��Ă��܂��܂��B
���̓���r���ĉ��̈Ӗ�������ł��傤���H�Œ��ꒃ�ł͂���܂��H
�����ꕽ���~�����r����̂��A�ʐ^�ɂƂ��Ă͖��Ӗ��Ȃ��Ƃ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10171075
![]() 0�_
0�_
Tranquility����A
[10170792]�ł͂͂����肨�������܂����̂ŁA���Ӗ���������b�͂��t�����ł��܂���B
�����ԍ��F10171088
![]() 0�_
0�_
���������A��{�����Ԉ������ʖڂ���B
���a�͂Q�{�Ȃ���4/3��135�Ɠ������ZF�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���̐l�͂����m�̂Ƃ���A
���ZF�l���Ⴄ�t�H�[�}�b�g�œ�����p�Ɣ�ʊE�[�x��������
�i���Z�����j�œ_������F�l�̃Z�b�g�̂�����F�l�ɂ����܂���B
�I�����p�X���g��E-P1�̐�����p.134�ŏ����Ă܂��B
�œ_����
35mm�ŃJ�����Ɠ����œ_�����ɑ��āA�Q�{�����̖]�����ʂ������܂��B
��ʊE�[�x
35mm�ŃJ�����ɑ��āA�Q�{�����̐[���[�x�������܂��B
���Ƃ��AF2.8�̖��邳�̃}�C�N���t�H�[�T�[�Y�V�X�e�������Y�́A
35mm�Ŋ��Z��F5.6�ɑ������܂��B
�����܂��Ȃ��Ƃ͉�������܂���B
�hF5.6�ɑ�������h�@���Â��ƌ������A
���邳�ł͂Ȃ���ʊE�[�x��F5.6�ɑ�������ƌ����Ӗ����A
�Ƃ��邩�̈Ⴂ�ł��B
�����ԍ��F10171101
![]() 7�_
7�_
���s�̂�������
�����Y�̎�_�́A�������Ȉ�͏����Ă܂����݂���_�i�ʒu�Ƃ����Ă��������ȁj�ł���B��}������}�ʂɏ����܂���ˁA���̃����Y�ŗL�̋q�ϓI�ɑ���o����_�Ƃ��āB
���鐯���߂炳��
����ł͘b��i�߂܂��B
���ꂽ��A��ɂ͐���̐�������܂��B���Ԃł����l�ɐ���̐�������܂��B
�قƂ�ǑS���A�ǂ�����z�Ɠ����悤�ȍP���ł��B
�ł������̋�̌����͐���̐��A���Ԃ̌����͐���̐��{���z�P�B�ǂ�����卷�Ȃ������̐��ł��ˁB
���Ƃ���ƁA���X��[10170034]�ł��鐯�J������������Ă���������u���邳�v�̐���
�i�\���킯����܂��u���邳�v�͂�����ł��_�_�̂ЂƂł��̂ŁA������ɏ����܂��j
-------------------------
>100W2�ɏƂ炳�ꂽ�����h�[���̕���100W1�̕������{���邢�B
������O�ł��傤�B��{���邢�ȊO�͉��ł�����܂���B
-------------------------
�̐����ƁA����������ʂ������ŁA�قƂ�Ǔ������邳�ɂȂ�̂ł͂���܂��H
�����ԍ��F10171147
![]() 0�_
0�_
�� ���邳�ł͂Ȃ���ʊE�[�x��F5.6�ɑ�������ƌ����Ӗ���
�܂����͖��邳���Ǝv���܂����A���Ȃ��Ƃ������̓����͖��邳�ł��B
4/3��f/2.8�̃����Y�̖��ẤA35�~������f/5.6�Ɠ����ł���ƌ����܂��B
�ʐ^�̖��Â̒�`�́A��̃J�L�R���Q�Ƃ��ĉ������B
���R���K�R����ŋc�_���ėǂ��ł����A���邳�������̏ꍇ�A��ʊE�[�x�������ɂȂ�܂��B
�����ĉ�܂₻��ɂ��𑜌��E�������ɂȂ�܂��B
�܂�A����F�l�Ƃ́AF�l�Ɋ֘A����S�Ă̐����ƘA�����āA���������߂܂��B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����Y�̐����R�X�g��A�傫���d������v���܂��B
�i4/3�̏ꍇ�g���ӌ����̔��{�I�ȑ�h�ɂ�郌���Y�̌������啝�������܂����j�B
�����ԍ��F10171164
![]() 0�_
0�_
�� �ł������̋�̌����͐���̐��A���Ԃ̌����͐���̐��{���z�P�B
�� �ǂ�����卷�Ȃ������̐��ł��ˁB
���̗����͊ԈႢ�ł��B���炭�o���̘b�𗝉����ĂȂ��Ǝv���܂��B
�� 100W2�ɏƂ炳�ꂽ�����h�[���̕���100W1�̕������{���邢�B
���̎���̖��邳�́A���̏Ɠx�Ǝ����͗������Ă܂��B�������A�ʐ^�Ƃ��Ă͏Ɠx�ł͂Ȃ�
���G�l���M�[�����邳�����߂܂��̂ŁA����͔F���̃Y�����Ǝv���܂��i[10171075]�Q�Ɓj�B
�Ɩ��̈ʒu�ɂ���Ė�1/3�Ƃ������ɓ͂��Ǝv���܂����A���Ƃ̎���ł́A���̔�Ⴊ�Ⴄ��
�����ݒ肪����Ƃ͎v���܂���B��Ⴊ�����ł���A�ʐς��C�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B
�ʐς�Ɠx�����ł���A1/3�̃G�l���M�[���͂��܂��̂ŁA��{����Ƃ������P�ł��B
�����ԍ��F10171205
![]() 0�_
0�_
�����A�c�_�����������Ă��܂����ˁB
���āA���s�̂������܂���A���̃X���𗧂��グ�����R�������˂��
�܂������A���R�͈ȉ���3�ł��ˁB
�i���R�P�j���̃X���𗧂��グ�邫�������ƂȂ����X���b�h�ł͑S������
�@�@�@�@�@�W�Ȃ��b���ʼn��X�������܂�Ă����ԂɂȂ��Ă���A�����
�@�@�@�@�@�������ׂ��ƍl�������B�i�]�v�Ȃ����b���Ǝv���܂������A
�@�@�@�@�@�^���҂������܂����̂ŁA������ƈ��S���܂����B�j
�i���R�Q�j��������X���̐[���Ƃ���ŁA����̐l�X�ʼn��X����Ă��Ă�
�@�@�@�@�@����������̂��Ȃ������ȋC�������̂ŁA�ēx�����̐l�̖ڂ�
�@�@�@�@�@�G��āA�������c�_�����邽�߂̃X���𗧂Ă������悢�ƍl��
�@�@�@�@�@�����ƁB
�i���R3�j�ŏ��̏������݂ɏ������悤�ɁA�l�I�Ƀt���T�C�Y�ɍs���ׂ����A
�@�@�@�@�@�t�H�[�T�[�Y���g�[����ׂ�������Y��ł��钆�ŁA�t���T�C�Y��
�@�@�@�@�@�_���g�c�ɉ掿�i�K���A���A�𑜓x�j���ǂ��Ǝv���Ă������A
�@�@�@�@�@���ۂɗ��Ҏg���킯�Ă݂�ƁA���p��̓t���T�C�Y�̓t�H�[�T�[�Y
�@�@�@�@�@�Ɣ�r���Ă���Ɠx�̔�ʑ̂��B�e����Ƃ��ȊO�́A����قǗD��
�@�@�@�@�@�Ă���Ƃ��v�����A�t�Ƀ����Y�̐��\�̓t�H�[�T�[�Y�̕����ǂ�
�@�@�@�@�@�悤�Ɏ��������B�������A�Â��ĉ掿�������ƐF��ȂƂ���Ő���
�@�@�@�@�@���Ă���l�����āA�{�����Ƌ����Ă��炢�����������ƁB
����ȏ�ł��ȉ��ł�����܂���B�������܂����ł��傤���B
�����ԍ��F10171260
![]() 9�_
9�_
�ȉ������A���炵�܂��B
����܂ł̋c�_�ŁA�����������������Ƃ͊��ɏЉ���Ē����܂����B�ǂ����
����́A���ӂ��Ă���ƍl���Ă��ǂ������ł��ˁB���ǁA���s�̂�������
���ł��咣���ꂽ�����Ƃ́A�u�t�H�[�T�[�Y�̌��w�n�̓t���T�C�Y�̌��w�n
�ɔ�ׂāA�摜����邽�߂̌��ʂ����Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ̂��낤�Ɗ������
�ł�������͂�낵���ł��傤���B���ZF�l�Ƃ������̂����̒��x��\���l��
����Ƃ��������̂Ȃ瓯�ӂ���l���������Ǝv���܂��B
����A���a���掿�i�����A����\�j�����߂�S�Ăł���Ƃ����͉̂ʂ�����
�����Ȃ̂��낤���ƈˑR�Ƃ��ċ^��������܂��B�������A�傫�ȗv�f��
�܂߂�ł��傤���A����ȂɊȒP�Ɍ�����Ȃ��̂ł͂Ǝv���܂��B
���̋^����l�����ނƂ���
>�t���T�C�Y��50mm F2.0�i�Ⴆ�AOM ZUIKO 50mm F2.0�Ȃǁj�ƁA
>�t�H�[�T�[�Y��50mm F2.0���t�H�[�T�[�Y�ɑ��������Ƃ��A�t���T�C�Y
>��50mm F2.0�́u�Â��Ȃ�v�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
�ƌ�������������Ē������̂ł��B
�܂��ŏ���OM-ZUIKO�����čl���܂��B���̃����Y�́A�t���T�C�Y��
�J�����̃~���[�{�b�N�X�Ƀt���T�C�Y�̎B���ʐς������Č��������܂��B
���̂����̒���1/4�̗̈悪�t�H�[�T�[�Y�̎B���f�q�ł��B����́A���s��
�������܂��������ɂȂ��Ă���g���~���O�Y�[���Ɠ����������o���邩��
�m��܂���B
���ɁAZD50mm F2.0�̃����Y�����܂��B���̎��A�t�H�[�T�[�Y�̎B���f�q
�ɑ��Č������܂����A���a������˂������͑S�ăt�H�[�T�[�Y�̎B���f�q��
�Ɍ������Ă���͂��ł��B���҂͎��ۂɎ������Ă݂�Ɠ���F�l�œ����V���b�^�[
�X�s�[�h�ɂȂ�܂��B�܂�́A�B���f�q�ʂ̌��͓����ł��邱�Ƃ��ϑ�����
�Ă���Ɨ����o���܂��B
���s�̂�������̉́AZD50mm F2.0��OM-ZUIKO 50mm F2.0
�͓������邳���Ƃ̉ł����B�i���ۂɂ́u�Â��Ȃ��v�Ƃ����L�q�ł������j
�������A����܂ł̒����������ł̍l����������ƁA�B���f�q�O��3/4���̂Ă�
����̂ňÂ��Ƃ����ɂȂ�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̌��ۂ��ǂ̂悤�ɐ����o����̂����l���Č���ƁA�ȉ��̉�����
����ꂻ���ł��B
----
ZD50mm F2.0�́A��p�ƌ��a�䂩�猩�ăt���T�C�Y�C���[�W�T�[�N��
����邽�ߎ����o����\���ȃT�C�Y�ł��邪�A�B���f�q�ɓ��e������ʂ�
���a����̓��ˌ���1/4�����g���Ă��Ȃ��B
----
����́A�B���f�q�̑傫���Ȃǂ��猩��Ƃǂ���琳�����Ɗ����܂����A
�Ȃ��A���̌��a����̓��ˌ���1/4�����g���Ă��Ȃ��̂��^�₪�����܂��B
�t�ɁA���ˌ���S�ďW������t��4�{�̖��邳�������邩���m��܂���B
�����āA�B���f�q�̃Q�C���������邱�Ƃ�S/N������������邱�Ƃ��o����
�����m��܂���B�ǂ����Ă�������Ȃ��̂����V���ȋ^��ł��B
�������������������Y�̃e���Z���g���b�N�n�̊m�ۂƂ����I�����p�X��
���ɂ�������Ă��鎖�ł͂Ȃ��̂ł��傤���B�܂�A
------
�t���T�C�Y�̃����Y�͎߂ɓ����Ă���������܂߂Č��ʂ��m�ۂ��Ă���
����ŁA�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�͓��ˌ��̒����璼�i�ł�����݂̂�
���ė��p���Ă���B���̌��̗ʂ�1/4�ł���
------
�ƌ������������Ă�ꂻ���ł��B
���̂悤�ȓ����́A���ӌ����̖���e���Z���g���b�N�n�̕K�v���Ȃǂ�
�S�ď����ċc�_������ƁA�t�H�[�T�[�Y�̃����Y��1/4�̌��ʂ����Ȃ���
�������Ƃ����c��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�܂�A�B���f�q�̖ʂ��猩�Ă����ƁA�����������_�ɂȂ�킯�ł����A
����̃����Y�̖ʂ��猩�Ă����ƁA�ȉ��̂悤�Ȍ��������o����̂ł�
�Ȃ��ł��傤���B
------
�t�H�[�T�[�Y�̌��w�n�́A�t���T�C�Y��1/4�̌��ʂʼn摜�̐������\
�ƂȂ�ɂ�������炸�A���a��Ȃǂ̓t���T�C�Y�����A�܂�A�K�v��
���ʂ�4�{���W�߁A�����ɓ��˂���������߂����Ă��郌���Y�ł���B
------
���������������ƁA���L�̉����������邩�Ǝv���܂��B
------
�t���T�C�Y�̃����Y�́A���ˌ���1/4���B���f�q�ɐ����ɓ���A�c��3/4
�́A�߂ɓ��˂��Ă���B���̂��߁A�B���f�q�ɂ���u�ł��Ȃ�������
���ӂɍs���ɂ�đ傫���Ȃ�A���ӌ����̖�肪�傫���B�t���T�C�Y��
�B���f�q�S�̂ɐ����Ɍ�����˂���ɂ͌��a��2�{�ɂ��āA���̂�����1/4
�̓��ˌ��݂̂��g���K�v������B
------
�������A�B���f�q�̏����������痈��S/N�䂪�s���ɂȂ�̂͂��邩��
�v���܂��B�ɂ�������炸�A�ǂ����ăt�H�[�T�[�Y��4/3�C���`�̃T�C�Y��
�I�̂��ƌ������Ƃɂ��ẮA�]����35mm�̃����Y�Ɠ����傫����
�e���Z���g���b�N�n�̌��w�n����邱�Ƃ��d���������ʂȂ̂ł��傤�B
�܂�A
--------
�t�H�[�T�[�Y�͒�Ɠx�̉掿�i�Ɗ����ď����܂��j�̕s�����o�債��
��ŁA�[���Ɍ���������̈�ł̍��掿����ڎw�����d�l�ł���B
--------
�ƌ��_�Â��Ă��ǂ��悤�ȋC�����Ă��܂����B�����̉����ɂ��Ă�
�[���Ɍ��ł��܂��A���ۂ̗��p�ɂ����ẮA�����͖������Ă���Ƃ�
�������܂���B�������ł��傤�A�݂Ȃ��܁B
�������܂Ƃ߂�ƁA�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�͌��X�S���v�z�̈قȂ�
���w�n�ł���A�����P���Ɍ��a�䂾���ŁA�c�_���ĉ掿�Ɍq���Ă����̂́A
�S���Ӗ��������悤�ȋC������̂͏��������ł��傤���B
�����ԍ��F10171269
![]() 14�_
14�_
�� �[���Ɍ���������̈�ł̍��掿����ڎw�����d�l�ł���B
����͈Ⴂ�܂��B�[���Ɍ����������Ԃł��A���掿���͏o���Ă܂���B
�Ȃ��Ȃ�A4/3��ISO100�́A��i����āA�t���T�C�Y��ISO400�����ł�����B
�������A�Â��Ƃ��A��掿�Ƃ��A�Z���T�[�T�C�Y������������d���Ȃ��ł͂���܂���B
��i���邢����a�����Y���������A�Z���T�[�T�C�Y���������ƌ����s��������S�āA
���Ղ��c�����������ł���̂��A�������咣���Ă܂��B
�����ԍ��F10171319
![]() 0�_
0�_
�g�Â��h�Ɗ֘A�������邩���m��܂��A�g�V�͓�^�����h�ƌ������{�������܂��B
�ʐ^�ł́A��̗v�f���A�����ĂāA����グ���瑼�͉�����ƌ����W�����}������܂��B
�Z���T�[�T�C�Y���������Ȃ����炪��ʊE�[�x���[���Ƃ��A�ꌩ�����̌o���ƈႤ������
����悤�Ɍ����A�W�����}���ς����ƈꎞ���o������܂������A����F�l�ōl������A����
���ʂȂ��Ƃ��Ȃ��A��ʊE�[�x���[���Ȃ����̂��A���a�A����F�l���������Ȃ��������ł��B
��͂肽���Ȃ��̂͂Ȃ��A���ł��㏞������ƍĔF�����܂����B���Ȃ݂ɖ�����������
�֎q�Ɉ�N�����܂������A������Ɏ����}�O�c�@�c����l�̎�ԑ㏞������܂����B
��ʖ����ʎE�l�Ƃ��Ǝv���܂��B��͂葍���̈֎q�͂��̈ʂ̒l�i�����邩���m��܂��A
��i����a�����Y�̒l�i���A35�~�������Ȃ��̂ɑ�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10171342
![]() 0�_
0�_
���ӌ����͕ʂ̋@��ŋc�_�������Ǝv���܂����A4/3�̂����͊Ԉ�����Ƃقڒf��ł���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10171345
![]() 0�_
0�_
�F����̃��X�ǂ�łȂ��Đ\����Ȃ��ł����A������Ǝ����ς��āB
�u�t���T�C�Y�̃g���~���O�Ńt�H�[�T�[�Y�̉摜���[���̌��ł���v�����łȂ��A
�u�������t�H�[�}�b�g�ƃY�[�������Y�ő傫���t�H�[�}�b�g���^���̌��ł���v����B
����Ȃ��Ƃ��ƃt�H�[�T�[�Y���[�U�[�̕��ɓ{���邩������܂��E�E�E�B
http://www.imagegateway.net/p?p=DKyLAsEve2e
�ڂ��u�t�H�[�T�[�Y500����f�̃s�N�Z�����{�i�̃g���~���O�B��₱�����I�j�v��͂����摜�ł��B
���o�̉摜�ł����A���o�̃����N��̉摜�ɂ� Exif �������ĂȂ��悤�ł����B���x�͂����� Exif �������Ă��܂��B
�ꖇ�ڂƓڂ̔�r�ł����A�u�𑜓x�����m�C�Y�̈Ⴂ�ɒ��ڂ��Ă��������i�𑜓x��A���̈Ⴂ�̓x�C���[�̊Ԉ����T���v�����O������������j�v�B
2/3 �� 1/4 �ɏk��������t�H�[�T�[�Y�̉摜��������i�������g���~���O�j�B
2/3 �� 1/16 �ɏk��������t���T�C�Y�̉摜�������܂��i�������摜�T�C�Y�͂ƂĂ��������Ȃ�j�B
���ꂪ�t�H�[�}�b�g�̖{���i�̈��j�ł��B
�Ȃ������Ȃ邩�A�l���Ă݂Ă��������B
���ƁA�A���o����̈ꖇ�ڂƓڂ́u�����Ɍ��V���b�g�m�C�Y�������҂������i�̃m�C�Y��v�ł��B���V���b�g�m�C�Y��i�̔䂪���Ȃ��ƌ��邩�����ƌ��邩�͐l���ꂼ��ł����A���ꂪ�܂����������Ȃ̂ł��B
������A�Ȃ������Ȃ邩�l���Ă݂Ă��������B
�����ԍ��F10171348
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
[10170948]�ɑ��郌�X�ł��B
�u�掿�v�Ə����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł���A����Ƃ��u�掿�v�Ə����Ȃ��ŗ~�����ł��ˁB
�r�r�X�X�X����ɂ�
�u�ǂ̂悤�ȃt���T�C�Y300mm F2.8�ł��A�S�Ẵt�H�[�T�[�Y150mm F2.0�����掿���ǂ����v
�Ǝ��₵����Ⴄ�������Ԃ��Ă���Ǝv���܂���B���������r�r�X�X�X����̓���������Ƃ��ꂵ���ł��ˁB
���Ȃ݂Ɏ����t���T�C�Y�p300mm F2.8��v����I�����p�XZD150mm F2.0���掿�������̂͊m���ł��B^^;
�����ԍ��F10171784
![]() 6�_
6�_
F�l�̘b�ł�����AF�l�Ɋ֘A����掿�A�����x�掿���܌��E�Ȃǂ��c�_���Ă�ł��傤�B
ZD150/2.0�́A300/4�����ȃ����Y�ŁA328����i�Â��Ȃ�܂��B
f/2.0�ł���̂́A�ԈႢ�܂��A�B�����ʐ^��������A
35�~������f/4�Ɠ������ʂ��������܂���Af/4�����ƌ����܂��B
�����Y�̐v�ƃR�X�g���A��p�ƌ��a�ɂ���ĕς�܂��B���������ł���Ǝv���܂��B
���ۂ�4/3�����Y�̒l�i�������Ȃ�܂����A���ӌ������A�s��V�F�A�ɂ������̈�����
��������K�v�ŁA���������ł�����A���������Ă��d���Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10172014
![]() 1�_
1�_
���鐯���߂炳��
>���̎���̖��邳�́A���̏Ɠx�Ǝ����͗������Ă܂��B�������A�ʐ^�Ƃ��Ă͏Ɠx�ł͂Ȃ�
���G�l���M�[�����邳�����߂܂��̂ŁA����͔F���̃Y�����Ǝv���܂�
�����̈Ӗ����킩��܂���B���G�l���M�[�Ƃ́H
���G�l���M�[�Ō����A���̒n�����̒n����卷�Ȃ����ƂɂȂ�܂��H
�B�e�ł͏œ_�ʂ̖��邳�i�Ɠx�j���d�v�Ȃ̂ł́H
>�Ɩ��̈ʒu�ɂ���Ė�1/3�Ƃ������ɓ͂��Ǝv���܂����A���Ƃ̎���ł́A���̔�Ⴊ�Ⴄ��
�����ݒ肪����Ƃ͎v���܂���B��Ⴊ�����ł���A�ʐς��C�ɂ��邱�Ƃ͂���܂���B
�ʐς�Ɠx�����ł���A1/3�̃G�l���M�[���͂��܂��̂ŁA��{����Ƃ������P�ł��B
1/3�̃G�l���M�[��2�{���邢�Ƃ́H
�ǂ������Ӗ��ł��傤�H
�����̈ʒu��A���Ƃ̋�����L���Ƃ͊W�Ȃ�����������Ƃ������Ƃł����H
�ł���A�Ȃ��̂��ƒ��̒n�����̒n����卷�Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F10172041
![]() 1�_
1�_
�ʐ^�Ƃ��ẮA�����܂Ō��ʘ_�ŁA�掿�ASNR�������ł���Ηǂ��킯�ł��B
���̉掿�ASNR�́A�I�o�̎��ɗ��܂������̃G�l���M�[�̗ʂɂ�錈�߂��܂��B
���̃G�l���M�[���A�≖�ł͉��w�����A�f�W�^���ł͓d�q�����̂ɕK�v�Ȃ��̂ł��B
���w�����̗ʂ�A������d�q�̐��́A���G�l���M�[�̗ʂɂ���Č��߂��܂��B
�� �����̈ʒu��A���Ƃ̋�����L���Ƃ͊W�Ȃ�����������Ƃ������Ƃł����H
������L���Ƃ͊W������܂���B����͉�p�ł͂���܂��A�p�x���l������ǂ��ł��B
�d�����猩�鏰�̊p�x�������ł�����A�d�������������͓��������ŏ��ɓ͂��܂��B
���ۂɐ��Ƃ͈���ēd���̌�ɔ��˔Ƃ�������܂����A���������ł���\���܂���B
�Ⴆ�Ί�����1/3�̏ꍇ�ł����A��d����1/3���A��̓d����1/3�Ƃ̔�r�ɂȂ�܂��B
����͖ʐςƂ͊W������܂��A�Ɠx�ȂƂ��W������܂���B
��������炤���̊����́A���z��菬�����ł��̂ŁA�d���̗�Ƃ͈Ⴄ�ƋC�t�����Ǝv���܂���
�Ⴊ�ǂ��Ȃ������ł��ˁB�������A�P�ʖʐς̑���͍��܂łƑS���ς�肪�Ȃ����݂��܂��B
�P�ʖʐς̏Ɠx�Ƃ��́A�ʐ^�S�̂𑪂���̂ł͂���܂���A�g���Ȃ������ł��B
���̂܂܂ł͎g���܂��A���Z�͂ł��܂��B���Z���郌�[�g�́A4/3�̏ꍇ��i�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10172144
![]() 0�_
0�_
�� �ł���A�Ȃ��̂��ƒ��̒n�����̒n����卷�Ȃ��̂ł́H
����͎���ł͂Ȃ��A����Tranquility����b�����Ƃ��Ȃ��ƁA�����͗������Ă܂��B
�����ԍ��F10172169
![]() 0�_
0�_
�ǂ݂₷�����͂ł̂��Ԏ��A���肪�Ƃ��������܂��B
>������L���Ƃ͊W������܂���B����͉�p�ł͂���܂��A�p�x���l������ǂ��ł��B
�d�����猩�鏰�̊p�x�������ł�����A�d�������������͓��������ŏ��ɓ͂��܂��B
>��������炤���̊����́A���z��菬�����ł��̂ŁA�d���̗�Ƃ͈Ⴄ�ƋC�t�����Ǝv���܂���
�Ⴊ�ǂ��Ȃ������ł��ˁB
���̓�̕��͖͂������Ă܂��H
�����Â�������̂́A�P���ɉ�������ł��B
�����ԍ��F10172317
![]() 5�_
5�_
���Ȃ݂ɁA�����i�d���E���Ȃǁj�ƁA������n�_�̌��ʁi�d���Ə��̊ԁA���ƒn���̊ԂȂǁj�̊W�́A������2��ɔ���Ⴗ��Ƃ����@��������܂��B
�܂��A�u��ɂ͐���̐�������v�Ə����܂������A����͖ڂɌ����鐯�̐������ł��B
�ڂɂ͌����Ȃ��Â����܂Ő�����ƁA�͂����ĉ����炢�ɂȂ�̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10172366
![]() 3�_
3�_
���s�̂�������
�ꉞ�����Ă����܂����A�t�H�[�T�[�Y�̕����t���T�C�Y�����m�C�Y���������Ƃ�N���^��Ɏv���Ă܂����B
���łɁA������ꉞ�����Ă����܂����A���s�̂�������̃T���v���͌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�������T���v���ł͂Ȃ��ł��ˁB
��f�s�b�`�A�J���[�t�B���^�[�̓��ߗ��A�ʎq�����Ȃnj��V���b�g�m�C�Y�ɉe����^����p�����^�ȊO�͕ύX���Ȃ��T���v�����o���Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�������A�}�`���A�̂ł��邱�Ƃ͌����܂��B��ԊȒP�Ȃ͉̂�f�s�b�`������ς���A�܂�A�t���T�C�Y�̃J�����ƃt�H�[�T�[�Y�̃J�����ʼn�f���ƘI���ʂ𑵂��ē�����ʑ̂��B��悢�ł��傤�B
�m�C�Y�̈Ⴂ�����̈Ⴂ�Ɣ�r���Ėڗ��悤�ɁA���x���グ�ĎB��A����ŏ\���ł��B�Ⴂ���I�o�łQ�i���Ȃ�A���V���b�g�m�C�Y�ȊO�̃m�C�Y�v���͗��҂łقڑł����������Ă���Ǝv���܂��B
������₷���T���v���̓C���^�[�l�b�g��ɂ�����ł�����܂��B�I�����p�XE-30�ƃj�R��D700�Ƃ��B
���̃J�����Ŕ�r����������A�t�H�[�T�[�Y�p�T���v�����g���~���O�摜�Ƃ��āA�t���T�C�Y�p�T���v�������w�Y�[���Ŋg��B�e������ŁARAW�f�[�^����f�����ŏk������Ηǂ��Ǝv���܂��B�k�����̃A���S���Y���͏d�v�ł��B
���̏ꍇ�ł����V���b�g�m�C�Y�̉e������r�I�������ኴ�x�ł͂Ȃ��A�����x�ɐݒ�i�܂�A�I���ʂ����炷�j�����ق����ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10172422
![]() 3�_
3�_
���鐯���߂炳��
����Ȃ�ł����ǁu���鐯���߂炳��v�̒��ň�Ԗ��邢�̂�
�ǂ̃V�X�e���i�{�f�B�[+�����Y�j�ɂȂ��ł����H
645��66�A67�A4×5�@8×10�Ȃǃt�B�����J�������܂߂ċ����Ă��������B
�܂�͂��ꂪ�ō��掿�Ȃ�ł���ˁH
�����ԍ��F10173000
![]() 6�_
6�_
���s�̂�������
�͂炽����
�x���Ȃ�܂������A���w���������̂ł��������܂��B
�P���ɁA�G���̔�r�L������u�t���T�C�Y�@�͂����ȓ_�ň�ԗD��Ă�Ȃ��v�Ɠǂ��x�ł�(��)
�������x�B�e�͖��炩�Ƀt���T�C�Y�̂ق����������ł��B
�ł����̑��́A�������R���f�W������ɔ����������Ƃ��قǂ̈Ⴂ������Ƃ��v���܂���B
�v���̖ڂŌ����画�f�ł���̂�������܂��A
���Ԃ�l�ɂ͖ڂ̑O�ɓ�̎ʐ^����ׂ��Ă��A�ǂ����̎ʐ^���t���T�C�Y�łǂ������t�H�[�T�[�Y�Ȃ̂��͂킩��Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ȃ̂ŁA
�t���T�C�Y�@�̃T���j�b�p�ŎB�����ʐ^�ƁA
�t�H�[�T�[�Y��150mmF2�ŎB�����ʐ^�̂ǂ����̉掿���D��Ă�̂��A���������Ėl�ɂ͂悭�킩��Ȃ��B
���A������̓����ł�(��)
�����܂���B
����Ȋ����ō����E-410�Ƌ��Ɏʐ^���y���݂����Ǝv���܂��B
���������v���܂����I
�����ԍ��F10173646
![]() 8�_
8�_
�t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̉掿�͂ǂꂭ�炢�Ⴄ�̂ł��傤���B
����ȂɌ��I�ɈႤ�̂ł��傤���B���ꂪ���i.COM�̌f������������
���������ł����B
�Ⴂ�Ȃǎ��ɂ́A����܂���A�݂Ȃ���킩���ł����H�ʐ^�́A�����ł́A�B��Ȃ����Ƃ��炢�����ł��܂���ˁH�A�����̍D���ȕ��g���܂��傤�A�i�O���O�j
�����ԍ��F10173993
![]() 6�_
6�_
��ʊE�[�x��F�l�Ō��܂�̂��H
�����̓m�[�ł��B
�����œ_�����A����F�l�A�����V���b�^�[���x�A�����J�����B����ł������Y���Ⴄ�Ɣ�ʊE�[�x�͓����ɂȂ�܂���B
�P�œ_�����Y�ƁA�Y�[�������Y��F�l�Əœ_�����ŎB���ׂĂ݂ĉ������ȁB�@
��ʊE�[�x���Ⴄ����AF�l�Ɋ��Z���ă����Y���Â��H�H�H�@�c���v�ł����H
�����ԍ��F10174359
![]() 5�_
5�_
���ZF�l�i���邢�́A����F�l�j�́A���_�A���Ȃ킿�A���ۂ̐��E�̂��ƂȂ̂����A����������ƁA���̂��Ƃ��痝�����Ă��Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ��낤���B
�������ɁA���������[���Ȏ��Ԃ܂ł͑z�肵�Ă��Ȃ������B
�I舂������B
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�́A���_�l�ł�1.96�i�̊J�������邪�A������r�ŁA���̍���������Əo�邩�ǂ����́A���Ȃ�������B
�����Y��J�����́A�o���c�L�̑傫�Ȋ�B�ł���A����t�H�[�}�b�g�̃����Y���m�ł����A�C���[�W�T�[�N���a���قȂ�̂�������O�������肷��B
�����炱���A���������f�������čl���Ă���̂����B
�����ԍ��F10174494
![]() 0�_
0�_
�� �����Â�������̂́A�P���ɉ�������ł��B
�O�̘b�̂���͏� �� �����Y�̌��a�Ɨ����ł���Ǝv���܂��B
���ۂɃZ���T�[�ɓ͂����́A�����Y�L�����a�ɓ�����̔������ł����A�قڈ��ł���܂��B
��������˂��������A���𒆐S�ɏ��܂ł̋����a�ɂ���360�x���̂̋��ʂ�ʂ�܂����A
�S�Ă̕������ψ�̏ꍇ�A�����珰�ɓ͂����́A���ʐς����̋��̑��\�ʐςŊ��镔���ł��B
�Z���T�[�������̏ꍇ�A���������Ȃ�ɂ�āA�����猩���Z���T�[�̑Ίp���̊p�x��
�������Ȃ�A�܂��A����̋��̂��傫���Ȃ�܂�����A�͂��������Ȃ��Ȃ�܂��B
�����狗���������ł��A�Z���T�[�T�C�Y���傫����A����̋��̖ʐς����ł����A
���q���傫���Ȃ�܂�����͂��������ő����܂��B�������ԓ��͂����G�l���M�[��
�傫����ASNR������A�掿���ǂ��Ȃ�܂��B
�܂��_����A�͂����G�l���M�[��S�̏ꍇ�A�m�C�Y�̗ʂ́�S�ɂȂ�܂��B�ł��̂ŁA
SNR �� S/N �� S/��S �� ��S�ł�����A���G�l���M�[�̗ʂ��掿�����߂܂��B�����
�J�����̊��x�𐧌�����f�g�c��ԑ傫���A�܂��͍����ł��Ȃ��̗v�f�ł��B
���ł͂Ȃ��A�����Y�̊J���̏ꍇ�������ł����A�S�ăC���[�W�T�[�N���ɓ͂����ꍇ�ł�
�Z���T�[�͉~�`�ł͂���܂��瑹��������܂��B���ǖ�Z���̌����Z���T�[�ɓ͂��܂��B
4/3�̖�61%�ɑ��āA3:2�̃J������59%��ɂȂ�܂��B�ʐ^�Ƃ��Ă͖����ł��鍷�ł����A
�������܂��ƁA����F�l�̊��Z�W���́A2�ł͂Ȃ��A1.96�ɂȂ�܂��i�i����1.94�i�ł��j�B
Tranquility�������߂̖��Â̊��o�ƈႤ�Ƌ��܂����A�����Tranquility����̖ڂ́A
4/3�ł��A35�~�����ł��Ȃ��A�_�l�̐v�ō��ꂽ�J�����ł����A�c�O�Ȃ��炻�̃J������
�Z���T�[��ς��邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ�ɂ�閾�Â̕ω���
���邱�Ƃ��ł��܂���B
�����ԍ��F10174543
![]() 0�_
0�_
�r�r�X�X�X����
���萔�����|�����܂��B
>�t���T�C�Y�@�̃T���j�b�p�ŎB�����ʐ^�ƁA
>�t�H�[�T�[�Y��150mmF2�ŎB�����ʐ^�̂ǂ����̉掿���D��Ă�̂��A���������Ėl�ɂ͂悭�킩��Ȃ��B
������������܂��� ^^;
�ƁA�������A�v��ΈႢ�͏o�邾�낤���ǁA�u��̐��E�v�̈Ⴂ���Ǝv���܂��B
�ǂ�����I��ł��\���Y�킾�Ƃ��v���܂��B
�ȉ��A�t�H�[�T�[�Y���u�Â��v�Ƃ�������
�ł��A300mm F4.0 �� 150mm F2.0 �łǂ��炪���邢���A�Ƃ����̂́u��̐��E�v�ł͍ς܂Ȃ��ł��ˁB
������2�{�̃e���R���g��������AF���������ǂ����̋��ڂ����B
�i���̓I�����p�X��AF���Â��Ă�������Ȃ��H�A�Ɣ��_����邩���m��Ȃ��ł����ǂˁB^^;�j
�����ԍ��F10174596
![]() 4�_
4�_
���鐯����ɔ�ׂ���A���̂̓U���I�������B
�ނ́A�{���ɂ悭�l���Ă���B
�����ԍ��F10174668
![]() 1�_
1�_
�u���邳�v�̖��̐������v�������̂ŏ����Ă݂܂��ˁB
�u���邢�d���ɕς����̂ŕ��������邭�Ȃ����v
�Ƃ������{��̕��͂��l���܂��B�����ɂ́u���邳�v��2��ޓo�ꂵ�܂��B
�@�u���邢�d���v
�A�u���������邢�v
���҂ɂ͕����I�ȈႢ������܂����A�ǂ�����u���邢�v�ƕ\������܂��B���{��Ɋ��\�Ȑl�͗��҂̈Ⴂ���g�������܂��B
�@�͌��w�I�Ɍ����u���x�v��\���A�v���̒P�ʂ́u�J���f���v�ɂȂ�܂��B�A�́u�Ɠx�v��\���A�v���̒P�ʂ́u���N�X�v�ɂȂ�܂��B
��ʓI�ȓ��{��̗p�@�Ƃ��܂��āA�@�͎����Ō��郂�m�Ɏg���A�A�͏Ƃ炳��鑤�Ɏg���܂��B
�J�����̏œ_�ʂ̉e���͎����Ō����Ă����ł͂Ȃ��̂ŇA���g���̂����ʂł��B
���{��ɕs���R�Ȑl�́A���̎g�������Ɏ��s���邩������܂���B���̏ꍇ�A��b���������Ȃ��ł��傤�B^^;
�u���x�v�̑ւ��Ɂu�S�����v�A�u�Ɠx�v�̑ւ��Ɂu�����v���g�p���Ă��ǂ��Ǝv���܂��B���̏ꍇ�A���W�n���ɍ��W�n�i�����Y�̏ꍇ�A�~�����W�n�̕����ȒP�ł��傤���j�ɂȂ��Ă���_�ɒ��ӂ���K�v������܂��B
�����w�ɏڂ����l�̃c�b�R�~�͊��}���܂��B^^;
�����ԍ��F10174758
![]() 1�_
1�_
�J�����͐̂���5%�ȓ��̌덷�͖����ł���ƌ����܂��B
�܂�A���엦98%�̃t�@�C���_�[���A100%�Ə����Ă����C�Ȃ̂ł��B
���́g�œ_������F�l����{�����h��������₷���Ǝv���܂��B
1.96�{�����m�ł����A��{�͂����p�I�ł��傤�B�덷��2%��������܂���B
�i�~�����͊������Ă�3.14�ɂ��ė~�����ł����j
���a�����ƌ����Ă�̂ɁA�����Ɍv�Z������A�L�����a��
150/2.0 �� 300/4 �� 75�~���ł͂Ȃ��A300/3.92 �� 76.53�~���Ƌ͂��ɑ傫���Ȃ�܂��B
����́A�A�X�y�N�g��3:2�̃Z���T�[�̌�����������������A��������a���K�v�ł����A
�A�X�y�N�g�䂪�����̏ꍇ�̓p�[�t�F�N�g�ł��B
�Ɩ��̖��ẤA���ۊw�Z��A�H��A���ԏ�ȂǁA�F��ȕW��������܂��B�����͑S��
�l�Ԃ̖ڂ�z�肵���Ɩ��ŁA�L��A����z�肵���킯�ł͂���܂���B�L�������
�q�L�w���ł�����A�l�Ԃ����������Ɠx���Ⴍ�Ȃ��Ă��ǂ������m��܂���B
�l�Ԃ̎q�����Â��ƌ����Ă�����͒m��܂���B�q�L���猩�Ė��邢�ł���Ηǂ��̂ł��B
���Â��������̑O�ɁA�N���猩�����Â�����Ȃ���A�Ӗ����Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F10174974
![]() 0�_
0�_
�� SNR������A�掿���ǂ��Ȃ�܂��B
S��R�͗]�v�ł��ˁB���i�I�j��
�����ԍ��F10175382
![]() 0�_
0�_
>���Â��������̑O�ɁA�N���猩�����Â�����Ȃ���A�Ӗ����Ȃ��̂ł��B
���̒ʂ�ł��ˁB�����̓J�����̌f���Ȃ̂ŁA�J�����B�e�ł̖��Â����܂��傤�B
���鐯���߂炳��
���܂��܂Ƃ�������ɂ����������������肪�Ƃ��������܂����B
���܂ł̏������݂���A�����Ƌ����̊W�𗝉�����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���A���낢�남�������܂����B���炢�����܂����B
�����ł͂Ȃ����Ƃ����̌�̏������݂ł킩��A���S���܂����B
�����Ŗ��Ȃ̂́A�����̕����ł��B
>�����狗���������ł��A�Z���T�[�T�C�Y���傫����A����̋��̖ʐς����ł����A
���q���傫���Ȃ�܂�����͂��������ő����܂��B�������ԓ��͂����G�l���M�[��
�傫����ASNR������A�掿���ǂ��Ȃ�܂��B�@[10174543]
�����ł��������Z���T�[�T�C�Y�Ƃ́A�C���[�W�Z���T�[�̂P��f�̑傫���̂��Ƃł��傤���H
����Ƃ��A���̏W���ł���t�H�[�T�[�Y�Ȃ�t���T�C�Y�Ȃ�̃t�H�[�}�b�g�̑傫���ł��傤���H
>Tranquility����̖ڂ́A
4/3�ł��A35�~�����ł��Ȃ��A�_�l�̐v�ō��ꂽ�J�����ł����A�c�O�Ȃ��炻�̃J������
�Z���T�[��ς��邱�Ƃ��ł��܂���̂ŁA�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ�ɂ�閾�Â̕ω���
���邱�Ƃ��ł��܂���B�@�i������[10174543]�j
�Ƃ���������Ă���̂ŁA�Z���T�[�T�C�Y�Ƃ͌�҂̂��Ƃ���������Ă���̂ł��傤�ˁB
�J�����̏ꍇ�i�l�Ԃ̖ڂ������ł����j�A�œ_�ʂ̊e�P�_�P�_�̌��̋�����A�d�C�M���̑召���邢�͊����ޗ����q�̉��w�ω��̑����ōČ����A�������ׂĉ摜�����Ă����ł��B
�f�W�^���J�����Ȃ�P��f�A�≖�Ȃ�n���Q������Ȃǂ̕��q�̏W���̂����̂P�_�ɂ�����܂��B
�œ_�ʂ̂P�_�P�_�́A���ꂼ��Ɨ��������������A���݂��Ɋ֘A���܂���B
�ł�����A�œ_�ʂɓ͂����̗ʂ��l����Ƃ��́A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�S�̂ɓ�������̑��ʂōl����̂͌��ł��B
�����ԍ��F10175873
![]() 5�_
5�_
Tranquility�����
�≖�̃n�[�t�T�C�Y���A�唻�Ɠ����掿�ł���Əؖ��������̂ł����ˁB
�P�ʖʐς̏Ɠx��掿�͑��_�ł͂���܂���A�x��ŗǂ��Ǝv���܂��B
�����́u10165668�v�u10171075�v�Ȃǂ��Q�Ƃ��ĉ������B
�����ԍ��F10175991
![]() 0�_
0�_
�� �����Ƌ����̊W�𗝉�����Ă��Ȃ��̂��Ǝv���A���낢�남�������܂����B���炢�����܂����B
�������厖�Ȃ��̂�����܂��B
�������߂��ďW���ʐς̏��������̂ƁA�����������ďW���ʐϑ傫�Ȃ��̂��A
�������猩��p�x�̕��������ł���A������ʐρA�����ďƓx������Ă��A
�W�����\�������ł���Ƃ��������Ă������������ł��B
�����ԍ��F10176003
![]() 0�_
0�_
>�������߂��ďW���ʐς̏��������̂ƁA�����������ďW���ʐϑ傫�Ȃ��̂��A
�������猩��p�x�̕��������ł���A������ʐρA�����ďƓx������Ă��A
�W�����\�������ł���Ƃ��������Ă������������ł��B
���ꂪ�P�̉�f�Ȃ炻�̂Ƃ���ł��B
�����ԍ��F10176120
![]() 1�_
1�_
>�≖�̃n�[�t�T�C�Y���A�唻�Ɠ����掿�ł���Əؖ��������̂ł����ˁB
�ǂ����Ă����������߂ɂȂ�̂ł��傤�H
�≖�t�B�����ŗL�̍Č��o������i�K���Ɖ𑜁j�ʂ̑������掿���Ƃ���Ȃ�A�����t�B�����œ��������������ꍇ�A�v�����g�ł̈����L���{���������Ȃ�A�n�[�t�T�C�Y���唻���A�v�����g��̓����ʐςł͓����掿�ł��ˁB
�����ӏ܃T�C�Y�Ɉ����L�����Ȃ�A���R���������{�����n�[�t�T�C�Y�̕����傫���Ȃ�܂�����A������̕����v�����g��̓����ʐςł̉掿�͗��i�t�B�����ł͗��q���r���j���ƂɂȂ�܂��B
����́A���鐯���߂炳��̂��������Ƃ���́u�P�ʖʐς̏Ɠx��掿�iS/N��ł����H�j�v�A�܂�f�W�^���ł͂P�̉�f�A�t�B�����ł͈�_�̊����ޕ��q�̌��ɑ��锽�������ʂ����E���邱�Ƃ̌���ł��B
�����ԍ��F10176166
![]() 3�_
3�_
�͂炽����
>�u�掿�v�Ə����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł���A����Ƃ��u�掿�v�Ə����Ȃ��ŗ~�����ł���
���̌��ɂ��Ă͂��Ȃ��Ɏx������邢���͂���܂���B
�u�m�C�Y���������Ƃ��掿�������v�Ǝ��͌����Ă���B������u�掿�������ƌ����ȁv�ȂǂƂ��Ȃ��Ɏx������邢��ꂪ�����Ƃ������ƁB�u�m�C�Y�͉掿�̏d�v�ȗv�f�v�ł��B
�t�H�[�T�[�Y 150mm F2.0 �� �t���T�C�Y 300mm F2.8 �ł̓m�C�Y�̓_�ł̓t���T�C�Y���掿���ǂ��ł��ˁi����ISO���x�Łj�B
����Ƃ���͌��V���b�g�m�C�Y�̃T���v���Ǝv���Ă܂���B�m���ɊJ�����̓_�ł͌��V���b�g�m�C�Y�ƌ����ɂ͎�肱�ڂ�������ł��傤�B��f�s�b�`��Ɣ�ׂāA�Ƃ���ǂ��뒎�H���T���v�����O�ł��B����������Ȍ����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��Ă��A�Ǝv���܂��ˁB
�A���T���v�����O�ƒ��H���T���v���A�����������Ƃ������J�����B���ꂪ�ǂꂭ�炢�قȂ�܂����H
���H���T���v�����O�ł��������ĕW�������������Ȃ�͓̂����ł��傤�B�U�镑���Ƃ��Ă͓����Ȃ̂ɁA����ȍׂ����Ƃ���������Ă��ȁA�Ǝv���܂��B
�������k���A���S���Y���͏d�v�ł��傤�BRAW �ō�������������萳�m��������܂��ARAW�ō���������@���k���A���S���Y���Ɏx�z����܂��B���Ƃ��Ƃ��ƃJ���[�䂦�̓���͂���܂��ˁB
�ł��u����͌��V���b�g�m�C�Y�̃T���v���ł͂Ȃ��v�Ƃ������̂Ă�A����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł���B�m�C�Y�͌����Ă��܂��BS/N��͏オ���Ă��܂��B���̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�����邩��ł��B
�܂����x���グ����r�ł́A���V���b�g�m�C�Y�ȊO�̃m�C�Y�������Ă��܂��B�����猻���_�ł͑傫���t�H�[�}�b�g�̕����ʐϕ��ǂ��Ȃ邩�ƌ��������ł͂Ȃ��B
Tranquility����
>�����Y�̎�_�́A�������Ȉ�͏����Ă܂����݂���_�i�ʒu�Ƃ����Ă��������ȁj�ł���B��}������}�ʂɏ����܂���ˁA���̃����Y�ŗL�̋q�ϓI�ɑ���o����_�Ƃ��āB
���́u���z�I�ȏœ_�����v�ł́A���̐����͂��Ă��܂��B
�����ԍ��F10176498
![]() 0�_
0�_
>�u�掿�v�Ə����Ȃ��Ă��ǂ��̂ł���A����Ƃ��u�掿�v�Ə����Ȃ��ŗ~�����ł���
���̌��ɂ��ẮA�܂��Ɏ��� ���鐯���߂炳�� �̃��X�ɂ���܂����ˁi�v���Ԃ�Ƀ|�`���܂����j
>�@F�l�̘b�ł�����AF�l�Ɋ֘A����掿�A�����x�掿���܌��E�Ȃǂ��c�_���Ă�ł��傤�B
[10172014]
�͂炽���� ���Ă����������̘b�����Ă�́H
�Ȃt�H�[�T�[�Y�̔��ď�������ł��ă��J�c�N���Ƃ������������ł��B
�����ԍ��F10176517
![]() 0�_
0�_
���ɏd�v�Ȃ��ƂȂ̂ōČf���܂��B
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
http://www.imagegateway.net/p?p=DKyLAsEv
e2e
�ڂ��u�t�H�[�T�[�Y500����f�̃s�N�Z�����{�i�̃g���~���O�B��₱�����I�j�v��͂����摜�ł��B
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�ڂ́u�t���T�C�Y2000����f�̃s�N�Z�����{�� 1/16 �g���~���O�v�ł�����̂ł����B
�ꖇ�ڂƓڂ́A����͂قڏ����ɓ�i�̌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ɂȂ��Ă��܂��B
>�A���T���v�����O�ƒ��H���T���v���A�����������Ƃ������J�����B���ꂪ�ǂꂭ�炢�قȂ�܂����H
�u�����Ƃ������J�����v�Ȃ̂Łu�T���v�����O����ꏊ��������ƈقȂ�v�����ł��B
�T���v�����O����͈͓͂����B�����Ƃ����͈̔͂̒��� 100% �̃T���v�����O���ł���킯�ł͂Ȃ��B
���ꂪ���V���b�g�m�C�Y�̃T���v���łȂ��ĂȂ�ł��傤�H
�Ȃ��A�A���o���̃����N�������킩��܂����A���̍��̔\�͂���
�u�t���T�C�Y����g���~���O���ď������t�H�[�}�b�g�̉摜��v�Ƃ��́u���ZF�l�A���Z�œ_�����A���ZISO���x�̍l�����g���₷���v�B
�u�������t�H�[�}�b�g���X�e�B�b�`���ăt���T�C�Y�̉摜�ɋ߂Â���v�Ƃ��́u����F�l�A���̏œ_�����A����ISO���x�̍l�����g���₷���v�B
����Ȋ����ł��ˁB
������ƌ����āu��_�v�ȂǂƂ����̂͐l�̂������t�ł����B
�����ԍ��F10176556
![]() 0�_
0�_
�͂炽����@
>�u���邳�v�̖��̐������v�������̂ŏ����Ă݂܂��ˁB
�u���x�v�Ɓu�Ɠx�v�͂��̂Ƃ���ł����A
�u�G�l���M�[�ۑ����v�͂���܂����u�Ɠx�ۑ����v�͂���܂���ˁB
�u�Ɠx���ŏ��������v�Ɓu�Ɠx���ő傫�����v�̓������Ƃ��܂��B
�O�҂���҂̃T�C�Y�܂ŃG�l���M�[��ۑ����Ȃ�����w�I�Ɋg�傷��A�O�҂͌�҂��Ɠx�������܂��B
�����ԍ��F10176570
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
���̃A���o�������Ă��������B
�摜�i�ʐ^�j�Ƃ������̂͂��ׂ��炭�u�f�W�^���I�ȃT���v�����O�v�ł��B�A�i���OTV ���A�������͘A���ł����A�c�����ɂ͑�����������B
�������ɏ��������Ƃł����A
�摜�ɂ͉�f���������O��Ƃ���A
�u��f���� 1/n �{�ɂ���AS/N��́�n�{�ɂȂ�v
�u��f���� n �{�ɂ��Ă� S/N��͕ς��Ȃ��v
�Ƃ����A���ɏd�v�Ȗ@�������藧���܂��B
�≖�́u��f���v���u�v�����g�T�C�Y�v�ƒu��������悢�ł��傤�B
�u���̊�v�����g�T�C�Y�v�Ƃ����̂������̂��A���ł����A����̓v�����g�����ۂ̕���\�i�𑜓x�H�j�Ō��߂邵���Ȃ��ł��B
�����ԍ��F10176601
![]() 0�_
0�_
���s�̂��������
���J�c�L�܂����A�A�A�ǂ�����Ηǂ��ł����˂��B
�����A�w���������͖����ł����A�s�v�ɃX���������Ȃ�Ȃ��悤�ɂ���ׂ̒�Ă��炢�Ɏ���Ă��������B
>�t�H�[�T�[�Y 150mm F2.0 �� �t���T�C�Y 300mm F2.8 �ł̓m�C�Y�̓_�ł̓t���T�C�Y���掿���ǂ��ł��ˁi����ISO���x�Łj�B
����̂悤�Ɂu�m�C�Y�̓_�Łv�ƏC������Ă���A�s�v�Ȗ��C�͋N���Ȃ��Ǝv���܂���B
�t���T�C�Y�̕����t�H�[�T�[�Y���m�C�Y�����Ȃ��̂͐������ł��B���E�l�Ƃ��Č��V���b�g�m�C�Y�ōl����̂��ǂ��Ǝv���܂��B�i�T���v��������Ȃ����炢�������Ǝv���܂��B�j
���̓_�͉𑜓x�̌��Ɠ����ŋc�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�X�����L�тĂ��闝�R�́A������u���ZF�l�v�Ő������邩�ۂ��ł��B
�m�C�Y�̐������A��f�T�C�Y�A��ʃT�C�Y�A�I���ʂōs�Ȃ���Ȃ���ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł����A���s�̂��������J���悤�ȏ������݂�����Ǝv���܂��B�i���Ȃ��Ƃ����̏������݂͌���܂� ^^;)
�Ⴆ��
>�O�҂���҂̃T�C�Y�܂ŃG�l���M�[��ۑ����Ȃ�����w�I�Ɋg�傷��A�O�҂͌�҂��Ɠx�������܂��B
�����ŁA���w�I�Ɋg�傷�闝�R���s���ł��B
���������߂��̓_�����邱�Ƃ͔F�߂܂��B
�����A��ʂ��k������ƌ��V���b�g�m�C�Y����Ȃ��Ă��ׂ����͗l�͏����Ă��܂��܂��B
�Ⴂ����ׂɂ͗������K�v�ŁA�������������Ă���T���v���͂���Ȃ����A������������Ȃ��l�Ɍ�����Ȃ�A�������������ɂ��K�v������Ǝv���܂��B
����ƁA�T���v���̏o������������Â炢�Ǝv���܂��B�����ƃt�H�[�T�[�Y�A�t���T�C�Y�Ə����Ă��Ă��āA������2/3�ƃt�H�[�T�[�Y�̔�r�ł��ˁB�ŏ����̓t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�̔�r�Ɗ��Ⴂ���܂����B
�܂��AF�l���̃����Y�ŃY�[������ƌ��ʂ��ς��Ƃ��A�����������Ƃƕ��ׂď������ƐM�ߐ���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10176908
![]() 4�_
4�_
������ƒ������܂��B
>�X�����L�тĂ��闝�R�́A������u���ZF�l�v�Ő������邩�ۂ��ł��B
�X�����L�тĂ��闝�R�́A�������@�A�T�^�I�ɂ́u���ZF�l�v�Ő������邩�ۂ����Ǝv���܂��B
����ƁA����̕����̗��_�ɖڂ��҂�A���_�ɂ��蒍�ڂ��Ă���悤�ɓǂ߂鏑�����݂ɂ́A���̓��J���܂��B
���łɏ����ƁA���ZF�l���_�͊z�ʂǂ���Ɏ��ƁA�t���T�C�Y�̉��l�𗎂Ƃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B���͂�������J���܂��B
����A�ǂ������A�債�����J�c�L�ł͂Ȃ���ł����� ^^;
�����ԍ��F10176943
![]() 2�_
2�_
�͂炽���� �̕��͂�ǂ�ł��āA�����킩��Ȃ��̂��܂��܂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł����B
�S���������Ă���̂ɂ킩��Ȃ��Ə����Ă���悤�ɓǂ߂܂��B
���Ȃ����������Ă��Ȃ��Ǝv�������ɂ��Ă�����ƕ⑫�������܂��B
>>�O�҂���҂̃T�C�Y�܂ŃG�l���M�[��ۑ����Ȃ�����w�I�Ɋg�傷��A�O�҂͌�҂��Ɠx�������܂��B
>
>�����ŁA���w�I�Ɋg�傷�闝�R���s���ł��B
�g�傷��̂ɗ��R�ȂȂ��ł���B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�䂪�Q�̏ꍇ�B
�g�債�Ȃ���ΏƓx�����A�ł����̃T�C�Y���Ⴄ�i����\�� 1/2�j�B
�g�傷��ΏƓx�� 1/4�A���̃T�C�Y�͓����i����\�͒Ⴂ�܂܁j�B
���ꂪ�����Y���̘b�B
150mm F2.0 �� 300mm F2.0 �̃����Y���ɂ͂��̈Ⴂ������B
>�����A��ʂ��k������ƌ��V���b�g�m�C�Y����Ȃ��Ă��ׂ����͗l�͏����Ă��܂��܂��B
����͎B����̘b�B
���摜�i�ʐ^�j�́i���݂̂Ƃ���j�f�W�^���I�i��A���j�ȁu�W�{���v�ł��ˁB
�u���w�I�v�ȑ��̊g��E�k���́u�œ_�����v�ɂ���čs����B
�u�B�����v�̑��i�摜�j�̊g��E�k���́u��f���i�̕������j�v�܂�u�T���v�����O���i�W�{���j�v�ɂ���čs����B
�u�B����v�̉摜�i��f���j�̊g��E�k���́B
�u�g��v�͐V���ȃG�l���M�[��t�^���鏈���B�V�O�i���������邪�m�C�Y��������BS/N��͕ς��Ȃ��B����\���ς��Ȃ��i���̒Ⴂ����\�̂܂܁j�B
�u�k���v�͕����̉�f���܂Ƃ߂āu�ăT���v�����O�i���E�T���v�����O�j�v���鏈���B���f������̌��q�̐��������A���V���b�g�m�C�Y������ S/N��͌��シ��B�摜�Ƃ��Ă͏Ɠx���ɂ��邽�߂ɂ��̌�V�O�i�������炷���A�m�C�Y������̂ŁA���̕����ł� S/N��͕ς��Ȃ��B��f��������̂ŁA�k���O���摜�ɔ�ו���\�͗�����B
�u�B����v�̉摜�̃g���~���O�E�X�e�B�b�`�́E�E�E�B�߂�ǂ��Ȃ̂ł�߂Ă����܂��B
����������Ǝ����ōl���ď������݂��Ă��炢�����Ȃ��B���ZF�l�ɂ��Ă�����͓��l�B
�����������ł��Ȃ�������ăC�`���������Ȃ��łˁB
�����ԍ��F10177086
![]() 0�_
0�_
>�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�͂Q�i�Â��v�u�Â�����掿�������v
>�Ƃ����咣������A����ɑ��ċc�_���������邱�Ƃ�ڂɂ��Ă���܂���
���͋t�ŁA�����̔ł�"�t���T�C�Y�̉掿��̫����ނ�舫��"�ƌ�������ȏ������݂����܂��B
�t���T�C�Y�ɗ��H�H�������H�H
����̉ʂĂɂ̓����Y�̐v�҂̕�����������n��(��)
����F�l�̋c�_�͊y�����q���v���Ă���܂��̂ŁA�������������B
�����ԍ��F10177119
![]() 1�_
1�_
�͂炽����́A���ZF�l���A�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̊W�ɂ����W��Ă���悤�Ɍ�������A�t�H�[�T�[�Y�̃l�K�L�����Ɏg���Ă���悤�Ɍ������肷��̂����Ȃ�Ȃ��̂��ȁB
����ɑz�����āA�\����Ȃ����B
�����ZF�l���_�͊z�ʂǂ���Ɏ��ƁA�t���T�C�Y�̉��l�𗎂Ƃ����Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B
����ł悢�B
�u���l��������v���Ƃ��悢�̂ł͂Ȃ��A���ZF�l��ʂ��čl���邱�Ƃɂ���āA���ׂẴt�H�[�}�b�g�̑��ւ����炩�ɂȂ�A���Ή����Č��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�̂��悢�B
�����ԍ��F10177144
![]() 2�_
2�_
>�����������ł��Ȃ�������ăC�`���������Ȃ��łˁB
�����ŗ����ł��ĂȂ������ɃC�`���������Ȃ��łˁA�ł��B
���Ȃ݂ɍ��C�t���܂������A�X���^�C�́u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�v�ɂ͋��������ł��B���̈Ӗ��ł̓X���Ⴂ�̐l�Ԃł��B
�t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y���ǂ��ł������B�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̑召���掿�ɗ^����e���ɋ��������邾���ł��B
���邢�E�Â��Ɋւ��ẮA���������T�O���ʐ^�ƊE������Ă��Ȃ������߂��ł��傤�ˁB
�u�����Y���̖��邳�̔Z�x�v�݂����Ȋ����Ŗ��t����悢�̂ł���B
�u��p���AF�l��肾�Ə������t�H�[�}�b�g�͑傫���t�H�[�}�b�g��葜�̖��邳�̔Z�x���Ⴂ�v�݂����Ȏg�����ł��B
�����Ƃ�����Ȃ̉��߂Ē�`�����Ƃ��A�u�����v�ő��S�̂́u���邳�v���킩�邩��s�v�Ȃ�ł����ǂˁB
�uF�l�������������Y�𖾂邢�����Y�Ƃ����v�����̌��������߂��̎n�܂�ł��傤�B
�����ԍ��F10177185
![]() 0�_
0�_
���uF�l�������������Y�𖾂邢�����Y�Ƃ����v�����̌��������߂��̎n�܂�ł��傤�B
�܂��A���Z����ΐ������킯�����B
�����ԍ��F10177205
![]() 0�_
0�_
�_�ƌ������̂́A�ʒu�����邪�A�ʐς��Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
�ʐς��Ȃ��ƁA�����ł��܂���̂ŁA���b���邱�Ƃ��ł��܂���B
�Z���T�[����f���ʐς�����܂��B�ǂ������Ƃ炳�ꂽ�g���h�Ƃ��ĂƂ炦�܂��B
��f�̓Z���T�[�̈ꕔ�ł����A�S�Ẳ�f�̑��ʐς̓Z���T�[�ʐςɂȂ�܂��B
�܂��A��f�����ς��Ă��A�m�C�Y�͊��Z�ł��܂��̂ŁA��f���͏d�v�ł͂���܂���B
1200����f�ƁA���f�i�Z���T�[�j�����Z�ł��܂��B
���Z�̂����́A���̉�f����ɓZ�߂�ꍇ SNR �� ��× S ÷ �i�ゎ × N�j�ł���
�� �� 4�̏ꍇ�́ASNR �� ����SNR × 4 ÷ 2 �ɂȂ�܂��̂ŁA2�{�ł��ˁB
�m�C�Y�����{�ł͂Ȃ��A�ゎ�{�ɂȂ錴���́A�ꕔ�v���X�E�}�C�i�X�����E�����̂ł��B
���Z�͂ł��܂����A�b��͈Ⴄ��f���E��f�T�C�Y�ł͂Ȃ��A�Ⴄ�Z���T�[�T�C�Y�̔�r�ł��B
�ʐ^�̎��_�Ƃ����̂́A�Z���T�[�̎��_���Ǝv���܂��B[10171075]�������ĎQ�Ƃ��Ă��������B
�܂��A��U�������I������A�ʐς̎d�����I��܂��B�ʐ^�t�@�C���́A���n�������d�q����
�L�^�����ł��B�ʐϏ���4/3���A35�~�������L�^����K�v������܂���B�Q�l���x��Exif��
�J�����̌^�Ԃ������܂����A���̃f�[�^���Ȃ��Ă��ʐ^�͎ʐ^�ł��B
�܂��l�ɂ���ẮA��f���̊��Z���s����Ȑl�����܂��i����f�������̐l�͂����ł��ˁj
����Ȃ�A������₷���悤�AExif�������ꂽ����1200����f�t�@�C�����r���ėǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10177214
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�����ł��Ă��Ȃ������ɂƌ�����ƁA�����ł��Ă��Ȃ������M���Ȃ��Ȃ�܂��� ^^;
���āA���s�̂�������̏������݂ň�َ��Ȃ��Ƃ�����܂��B���ꂳ��������A�����A�u�������Ă��邩�v�͗������Ă���Ǝv���܂��B�i�����ł��Ȃ��̂́u�Ȃ���������邩�v�ł��B�j
�����َ����Ƃ����ƁA
[10165949]
>����t�H�[�}�b�g�ɂ����ăY�[������Ƃ́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�u��ʑ̑��S�̂̌��ʂ�������v���ʂ������炷���A���p�҂���������҂��Ă��邩��ł��B�u�ʂ��Y�[���v�́u�Y�[�~���O�ɔ����A���j�A�ɔ�ʑ̑S�̂̌��ʂ������A��ʑ̉𑜂��������Ɓv���Ӗ����܂��B
�v����ɁA�t�H�[�}�b�g��F�l���ς��Ȃ��̂ɁA�Y�[���Ō��ʂ�������Ƃ��Ă��܂��B
���āA����ł��B
50mm F2.0 �� 100mm F2.0 �̃����Y���t���T�C�Y�Ŏg�p�����ꍇ�A�Y�[���Ō��ʂ��ς��Ȃ痼�҂̌��ʂ͈قȂ�͂��ł����A�ǂ̂��炢�Ⴄ�̂ł��傤���B
���̎���̓����ŁA���̋��s�̂�������̗��_�ւ̗����͐[�܂邱�Ƃł��傤�B
�����ԍ��F10177499
![]() 2�_
2�_
���݂܂���A���������⑫�ł��B
�Y�[���ɂ��A��ʑ̂̑����傫���Ȃ�܂��͗��̊p���傫���Ȃ�A�Ȃ痝���ł��܂����A���ʂƂ͗����͈̔͂��܂��B
�����ԍ��F10177561
![]() 0�_
0�_
[10177499]�͗��Ɍ��܂肷���ł��ˁB
���������Ƃ��v���܂������A�ӂ邱�Ƃɂ��܂��Bm(_ _)m
�����ԍ��F10177943
![]() 0�_
0�_
���݂܂���B2�_�������Ⴝ���A������Ɖ���ł��B
���s�̂������u�Y�[�~���O�ɔ����A���j�A�ɔ�ʑ̑S�̂̌��ʂ������A��ʑ̉𑜂��������Ɓv�Ə������ꍇ�A�u��ʑ̉𑜁v�͉𑜓x��\���Ă��܂���B
�Ȃ�Ƃ������A�𑜓x�ƃm�C�Y�����ɕ߂炦�Ă��āA�𑜓x��2�����A�M�����x��1������3�����ł��傤���B���邢�͐F����\�Ȃǂ��܂߂Ă����Ǝ������オ�邩������܂���B�傫����\���Ȃ���ς̃C���[�W�ɂȂ�܂����B
���ʂɊւ��ẮA�u��ʑ̑S�̂̌��ʁv�ł��̂ŁA��ʑS�̂̌��ʂł͖����n�Y�B
���ʂ̐l����ʑS�̂̏Ɠx���ς�炸�A��ʑ̖̂ʐϔ䗦�������Ȃ�A�ƃC���[�W���錻�ۂ�ʂ̌��t�ŕ\�����Ă��āA��ʑS�̂̃G�l���M�[���ς��Ȃ��̂Ŕ�ʑ̂�\������ׂ̌��ʂ�������B�Ƃ����������Ǝv���܂��B
�ŁA���ʂ�������Ɣ�ʑ̉𑜂������A�Ƃ����̂́i���a���ꏏ�Ȃ�p�x�ōl���ĉ𑜓x�͕ς��܂���j��ʓI�Ȍ��t�ŕ\���ƁA�u���ʂ�������ƃm�C�Y������A�F����\���オ��i�{�������邩���j�v�Ƃ����咣�ł��傤�A�ƁA�v���܂��B
����Ő����Ȃ�A�A�A�킩�邩�`�I�Ƃ������������܂��B^^;
�����ԍ��F10178550
![]() 0�_
0�_
�x�X�A���݂܂���
�i���a���ꏏ�Ȃ�p�x�ōl���ĉ𑜓x�͕ς��܂���j
�����͌��̏����݂�F�l���Ƃ��Ă��܂�����Y�[���ɂ���Č��a�͑傫���Ȃ�܂��ˁB�𑜓x���p�x�ōl����l�͉𑜓x���オ��܂��B
�ǂ��肪�����ł��Ȃ����Ƃ�����A�ł���A��������������₷�������ė~�����Ǝv���܂��B^^;
�����ԍ��F10178633
![]() 2�_
2�_
����ɂ���
�����Ɏ����āA���ZF�l�_�͂���l�ɂ��o���o���A�܂��Ƀ}�`�}�`�̗l���������Ă��܂����B
���ZF�l�_�́A�ӏ��Ɍォ��t�������G�l���M�[�ʂ̂��Ƃ��܂������l�����Ă��Ȃ��Ƃ����_�ɂ��Ă� 2009/09/13 00:59�@[10144094]�ɂ����Ă��łɎw�E�����Ƃ���ł��B
������ɂȂ��āA�����ɋC�Â��A�l������悤�Șb�ɂȂ��Ă��܂����ˁB
���̓_�ɋC�Â��A��������W�J���ꂽ���邳�Ɋւ���_�̐����͂��ቺ���邱�Ƃ͎��o�ł���ł��傤�B
�_�ɉ𑜂̗v�f�𗍂߂��̂́A1-300���Ǝv���܂��B���Ӑ[���ǂނƉ�f���x�̔�������邽�߂Ɏ������̂ł��傤�B
�_������߂Č��艻����b���ȂƎv���܂������A1-300����͊��ZF�l�_�҂ł͂Ȃ��A�j���[�g�����ȗ��ꂾ�����̂ł��ˁB
�͂炽�����ZF�l�_�ʼn�f�s�b�`�����낦�邱�Ƃւ̖���N��
2009/09/13 14:02�@[10146283]�ł���Ă��܂��ˁB
����U�������I������A�ʐς̎d�����I��܂��B�ʐ^�t�@�C���́A���n�������d�q����
�L�^�����ł��B�ʐϏ���4/3���A35�~�������L�^����K�v������܂���B�Q�l���x��Exif��
�J�����̌^�Ԃ������܂����A���̃f�[�^���Ȃ��Ă��ʐ^�͎ʐ^�ł��B
�����G�̋�_�Ɋւ��āA���ZF�l�_�ւ̔��_�Ƃ��ċL�q�������e�Ƃقړ����b�ł��傤�B�����������Ă��܂����B
�y�����Y���𑜂��Ă���O��ł͑f�q�̑召�ɂ�����炸�e�f�q��������RGB�f�[�^�́A�f�[�^�Ƃ��ĕێ������̂ŁA�����܂ł��f�[�^�Ƃ��ĂƂ炦�A���ʂ̑召�E�����ɒu�������Ȃ������킩��₷���̂ł��B�z
2009/09/13 00:59�@[10144094]
��������̊��ZF�l�_�ł͂��̂�������������ŁA�G�̋�ʂ����ʂ������悤�Ȉ����������Ă����̂ł��B
���āA�ȑO�ɒ�N����
�y�t���T�C�Y24���K���Ɋ����Ċ��Z×1.5�̂`�o�r�|�b��12���K�ڂ��ē����G���W���ŏ�������Ί��Z�e�l�Ȃ�Ĕ��z�͏o�Ă��Ȃ��킯�ł��傤�B�z�ɂ��āA
��L��t�H�[�}�b�g�Ԃʼn�p�����낦�Č����邱�Ƃ͑z��ł���ł��傤�B
�z����̊��ZF�l������Ă���̂ł���Ύ����Ă��������B
���Ȃ��̂ł���Θb�͏I���ł��B
�i�B���f�q�̉𑜗͂��قȂ邱�Ƃ͗������Ă��܂����A�����̈�ʓI�ȃ��[�U�[�̕K�v���̓J�o�[�ł���͈͂��Ǝv���܂��B�j
�����ԍ��F10178661
![]() 0�_
0�_
�����ZF�l�_�́A�ӏ��Ɍォ��t�������G�l���M�[�ʂ̂��Ƃ��܂������l�����Ă��Ȃ�
���邷���郂�j�^�͖ڂ�ɂ߂�̂ŁA�C���������������B
�����ԍ��F10178709
![]() 0�_
0�_
�{�X�g�[�NT-233����
>�͂炽����́A���ZF�l���A�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̊W�ɂ����W��Ă���悤�Ɍ�������A�t�H�[�T�[�Y�̃l�K�L�����Ɏg���Ă���悤�Ɍ������肷��̂����Ȃ�Ȃ��̂��ȁB
���`��A�[�w�S���ɂ͂���Ǝv���܂����A�\�ɏo�Ă��邩�Ȃ��B�Ǝ������ώ@���Ă݂܂��B^^;
���������A�u�t�H�[�T�[�Y�͂Q�i�Â��v�͋��e�ł��܂��A�u�t�H�[�T�[�Y�͂Q�i�A�Â�(���Z�j�v�Ȃ瑽��OK�ł��B
����ł�������́A��������Ǝv���܂��� ^^; �Œ���A���Z���Ă���Ȃ�u�Â��v�����Z����Ă��邱�Ƃ�������悤�ɂ��ė~�����Ǝv���܂��B
���\�P���Ȃ�ł��B^^;
�����ԍ��F10179015
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
�悩�����B
���Z�́A�����̐l�ɂƂ��Ă܂�����݂̏��Ȃ��l����������ǁA�ԈႢ�Ȃ����[�U�[�̗��v�ɂȂ�Ǝv���̂ł��B
�����ԍ��F10179102
![]() 0�_
0�_
�Y�[��(�����Ԃ�Y�[���A�b�v�A�Ƃ������Ƃł��傤)�����
�u��ʑ̑��S�̂̌��ʂ�������v�Ƃ����̂́A����Ⴛ��
�ł��傤�B�A�b�v�ɂȂ�Α��̑傫�����傫���Ȃ�܂��B
���̖ʐς������ĒP�ʖʐς̖��邳���ς��Ȃ��Ȃ�A
���̑����\��������̗ʂ�������͓̂�����O�B
�܂��A�Y�[���A�b�v����A�ו��܂Ō�����悤�ɂȂ��
�ł�������ʂ�������̂�������O�B
�ǂ���������ɂ����b�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���A������ɂ����̂́A�u���ꂪ�ǂ������v�Ƃ����_�B
������O�̕�����₷�����Ƃ��A�킴�킴�i������
��������Ă���̂͂Ȃ��Ȃ̂��A���ꂾ���͂ǂ����Ă�
������܂���B
�����ԍ��F10179145
![]() 5�_
5�_
quagetora ����
>���̖ʐς������ĒP�ʖʐς̖��邳���ς��Ȃ��Ȃ�A
���̑����\��������̗ʂ�������͓̂�����O�B
������ƌ�������������Ȃ̂ŕ⑫�����ĉ������B
�g�Y�[���ɔ����ăC���[�W�T�[�N���̒��a�������{���ŕς��h�Ƃ���Ȃ�A���̃��[�W�T�[�N���S�̂̌��ʂ͂��̂Ƃ���ł��B
���������ۂɎB�e�����̂́A�t���T�C�Y�Ȃ�24mm×36mm�͈̔͂̂݁B�t�H�[�T�[�Y�Ȃ�17.3mm×13.0mm�͈̔͂����ɂȂ�܂��B������F�l�ʂ��̃Y�[�������Y�Ȃ�A�Y�[�����Ă��P�ʖʐϓ���̖��邳�i���ʏƓx�j�͕ς��܂���A�C���[�W�Z���T�[�i�t�B�����ł��j�S�̂̑����ʂ͕ς��܂���B�������P��f����̌��ʂ��ς��܂���B
�i���̏ꍇ�A��ʑ̖̂͗l�ȂNJe���̖��Â͍l���܂���j
�t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�̓Y�[���ɂ���ĕς���ł͂���܂���A������ЂƂ̒P�ʖʐςƂ������Ƃł��B
�܂��A�Y�[���A�b�v����Α��{�����傫���Ȃ�̂Ŕ�ʑׂ̂̍��������܂Ŏʂ���悤�ɂȂ�܂����A���ʂ��C���[�W�Z���T�[�Ɉˑ����܂��̂ŁA���ʂɂ��Ă��Y�[���ɂ���ĕς��Ȃ��ƌ����܂��B
��������ς���Ȃ�A�Y�[���A�b�v����O�͍L���͈͂��ʂ������̏��ʁA�Y�[���A�b�v��ׂ͍����������ʂ�����ʂƂ��������ł��傤���B
�����ԍ��F10179843
![]() 0�_
0�_
�����A���炵�܂����B
�͂炽�����łɓ������Ƃ������Ă����܂����ˁB
�����ԍ��F10180109
![]() 0�_
0�_
����Aquagetora����ɂ͊ȒP��������������܂��A���͈������������Ⴂ�܂��� ^^;
�Ȃ̂�[10166637]�������Ă܂��B
���̓lj�̖͂��ł��傤���˂��B�lj�͂̂Ȃ��l�Ԃ��ǂ�ł܂���ŁA������₷�����肢���܂��Bm(_ _)m �Ђ�ɁB
�����ԍ��F10180205
![]() 0�_
0�_
�� ���K
���̗�ł����A������4:3�̒����`�̎l�p�ɂȂ�悤�l�{�̕��ː����o���āA
���̎l�{�̕��ː����l���Ƃ���4:3�̒����`�́g���h�i�W���ʁj�ł���A
������̋����Ɋւ�炸�A�������ԊԊu���͓������G�l���M�[�������ł��܂��B
���̎��A������̋�����A�W���ʂ̏Ɠx���ǂ��ς낤���S���e��������܂���B
�����C���[�W�ł����A150/2 �� 300/4�̂悤�Ȋ��Z�������ł���Ǝv���܂��B
�� �ʐ^�̏����Ɗӏ܁A�����ĕ��K
�ʐ^�̏�����ӏ܂̘b�ɂȂ�܂��ƁA�ʊy�悳��N���ꂽ���ł����A����͒P����
�g���Â̖{����SNR��h�Ɨ����ł���A���ɂȂ�Ȃ��Ǝv���܂��B
��U�������ł�����i�Q�C����g�[���ȂǏ�����j���d�q����RGB�̒l�Ƃ��ċL�^����܂��B
���̌�ǂ̂悤�ȏ��������Ă��A���̏��ʂ����邱�Ƃ������Ă��A�����邱�Ƃ�����܂���B
�m�C�Y���������������ŁA�𑜂�K��������ȂǑ㏞�Ȃ��ł́ASNR�͌���܂���B
���j�^�[�̃o�b�N���C�g��ῂ������߂��Ă��AISO1600�ŎB�����ʐ^�́AISO200�ŎB�����ʐ^
�ɂ͌����܂���B����͋t�ɁA���Â̖{����SNR�ł���ƍĔF���ł���Ǝv���܂��B
���ẤA�������ꂽ�A�܂��͊ӏ܂��鎞�̖��Âł͂Ȃ��g�����������̖��Áh�ŁA���̐��l��
SNR��ŋt�Z�ł��܂��B�����G�l���M�[�E������ �� �m�C�Y�̕����ƕ������Ă��܂��܂��B
�������ʐϏ�Ȃ���Ό��̏Ɠx�͕�����܂���B�ʐς��傫����ΏƓx���Ⴂ�ł��傤��
�Ɠx�ł͂Ȃ������ʂ������ł���A35�~�����ł��A4/3�ł���ʂ̂��Ȃ������ʐ^���B��܂��B
�����ԍ��F10180365
![]() 0�_
0�_
��قǂ��̃X���������܂����B
����ƑS�Ẵ��X��ǂݏI���܂����̂ŁA�����������݂����Ă��炢�܂��B
�b�����ɖ߂��܂������e�͂��B
�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�́A�t���T�C�Y�̃����Y�ɔ�ׂ�2�i�Â��B�v�Ǝ咣����Ă�����X�ɐ\���グ�܂��B
�u2�i�Â��v�̍����Ƃ��āA
�P�D�t�H�[�T�[�Y�̏œ_�����̓t���T�C�Y�̏œ_�����Ɋ��Z����2�{�ɂȂ�B
�Q�D�œ_������2�{�ɂȂ鎖��F�l��2�{�ɂȂ�B��������ZF�l�������͑���F�l�Ə̂���B
�R�DF�l��2�{�ɂȂ遁2�i�Â��Ȃ�B
�S�D���̂��߃t���T�C�Y�Ɠ����̉摜��ɂ�2�i���邢�����Y���K�v�B
�u�����Y��F�l�������Y�̏œ_����÷�����Y�̗L�����a�v����݂�Έꌩ�܂��Ƃ��Ɍ����܂��ˁB�ł�������Ƒ҂��Ă��������B
��������AF�l����������v���Ƃ��āA�œ_�������傫���Ȃ�i��p�����܂�j�ꍇ�ƁA�L�����a���������Ȃ�i�i��H�����i��A�����Y�̑O�ʂ�����������j�ꍇ������܂��B
��L�P�̎��ۂ́A�O�҂̉�p�����܂邱�Ƃɂ��F�l�̑����ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
����́A�t�H�[�T�[�Y�̃C���[�W�T�[�N���̒��a���A�t���T�C�Y�̃C���[�W�T�[�N���̒��a�̖�2����1�ł��邽�߂ł��B�i��p��2����1�ɂȂ遁�œ_������2�{�ɂȂ�j
�]���āA��L�S�͌��ŁA�������́A
�u�t���T�C�Y�Ɠ����̉摜��ɂ͏œ_������2����1�i��p��2�{�j�ƂȂ郌���Y���K�v�B�v
�ƌ���Ȃ���Ȃ�܂���B
�v�́A�P�`�S�̗��_��F�l�̑����v�����A��p�̋������ƁA�L�����a�̌������������Ă��܂��Ă���̂ł��B
����1�B
��L�S�́A���̂悤�Ɍ����������܂��B
�t���T�C�Y�̃����Y�Ńt�H�[�T�[�Y�Ɠ����̉摜��ɂ́A�J��F�l����2�i�i��Ηǂ��B
������������Șb�ŁA�������́A
�t���T�C�Y�ł́A�t�H�[�T�[�Y�Ɠ����̉摜��ɂ́A�œ_������2�{�̃����Y���g�p����Ηǂ��A�������͉�p�������ɂȂ�悤�ɒ��S�������Ηǂ��A�ƂȂ�܂��B
�㔼�͂܂��ɁA�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�̃J�����Ƀ}�E���g�A�_�v�^���g�p���t���T�C�Y�̃����Y�����t���Ďg�p�����ꍇ�ɊY�����܂��B
�Ȃ��A��L��A�̑O��Ƃ��āA���e�ʂ̖��邳�͒P�ʖʐϓ����蓯���ł��邱�Ƃ��K�v�ł��B
���́u���邳�v�ɂ��Ă��{�X���ł����낢�뒿������ь����Ă���悤�ł��ˁB
�P�ʖʐϓ�����̖��邳���������P�ʖʐϓ�����̏��ʂ������ƌ���������悢�ƍl���܂��B
�ꕔ�̕��X�́A�P�ʖʐς�����̖��邳�ł͂Ȃ��A�����ʂŔ�r���ׂ��Ƃ̈ӌ�������悤�ł����A�S���^���ł��܂���B����ɂ��Ă͎��̃X���ŋc�_�����肢���܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10143992/
�Ō�ɃA���`�t�H�[�T�[�Y�h�̕��X�́A�t�H�[�T�[�Y�Z���T�[�̐��\��A�_�C�i�~�b�N�����W�iSNR�j���t���T�C�Y�ɑ��ė��ƌ�����ł��傤���A�������͔��_�̗]�n�͂���܂���B
�������������Y���\�Ƃ͕ʎ����̂��b�ł�����B
�����ԍ��F10180523
![]() 2�_
2�_
�ʉ�y����̊G�̋�̘b�ɋ߂��ł����A�Ȃ��������������ɈႢ�܂��ˁB
���D�ɕ`�����G��z�����Ă��������B
���D�͖c���ł��܂����A�G�́g�G�̋�x�h�����R���ݕω��ł��܂��B
�܂��A�T�C�Y��g�G�̋�x�h���ς��Ă��A�掿�͓����ŕς�܂���B
�����Ƃ�����蓯�����ł�����B
�������A���D�̑傫�����ς��Ă��A�P�ʖʐς́g�G�̋�x�h����ɂ������������܂��B
����͉����ł��ˁB�P�ʖʐςł͂Ȃ����D�\�ʐς�1%�Ƃ����������ł�����ǂ��ł����A
����́g�ʐ^�̎��_�h�A����A�g���c�̎��_�h�ƌ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10180793
![]() 0�_
0�_
���G�̎��_�ł����A�\�ʐώl�{�c����D�́g�G�̋�x�h�͓�i�����Ȃ�܂��ˁB
�O�Ύ����ł�������ł����A�g�G�̋�x�h���ς�Ȃ��Ƃ����畨�����n������܂��B
�����ŕ`�������ł��B
�����ԍ��F10180832
![]() 0�_
0�_
���G�̗�͍ŏ��́g�G��h�̃X���̑O�ɍl���܂������A�䂽����̂����Ő������邱�Ƃ��ł��܂����B
����𗧑̓I�ɂ��K�p���������A������p�ƌ��a�ŁA�𑜂̈Ⴄ�����Y���g���Áh�Ɋ��Z�������Ǝv���܂��B
���̖��Ấg�掿�̑������_�h�ƌ����B���ȕ\���ł����A�I���t�@�����������������Ă����A
�g�����̃����Y�͈Â����ǁA�����i�����ǂ��A�]�����Ȃ����h�Ƃ����v�]����ꂽ���Ǝv���܂��B
�����ǂ��A�C�f�B�A������܂�����A���Ћ������������B
���Ȃ݂ɕ��G�̗�͋≖�̈����L���Ɠ����ł��B�����L���͋͂��ł��K���掿�̑���������܂���
�≖���܂��Z�����[�X�ł͂Ȃ��S�����D�ɓh�z������A���w�ł͂Ȃ������ň����L���܂��B
�܂��G�̋�ł����A�≖�̏ꍇ�͊����ƌ����ɂ���Ă��̏�ō���܂��B���ꂽ�ʂ́A
�����������G�l���M�[�̗ʂɂ���Č��߂��܂��̂ŁA�����I�Ȍq���肪�������₷���ł��B
�����ԍ��F10181050
![]() 0�_
0�_
�@���Ԃ̂���Ƃ��ɂȂ�܂����E�E�E
�@̫�ϯĂ`�A�`�a�A�`�b �̘b�A�����������ǂ��ł����H
�����ԍ��F10181214
![]() 1�_
1�_
�������ǂ��A�C�f�B�A������܂�����A���Ћ������������B
�t���T�C�Y�̓����Y���邢���ǃV���b�^�[�X�s�[�h���Ȃ����x���B
�����ԍ��F10181372
![]() 0�_
0�_
�r���܂œǂ��A�����Ԃ��炢�炵�Ă����̂ł�����Ə������Ă����������B
�킩��Ȃ��l�́i�܂��͂킩�肽���Ȃ��l���j�܂�������ǂ݂܂��傤�B
http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field
�ł�����������Ɖp����������킩��Ȃ��ꍇ�����邩������Ȃ��̂ŁA�ł��邾���ȒP�ɐ�������ƁA
�t���T�C�Y�@��50mm F2.8�̃����Y����������10���[�g���͂Ȃꂽ�l���B�e�����Ƃ���B����Ɠ�����ʊE�[�x�ƃt���[���邽�߂ɂ́A�t�H�[�T�[�Y�ɂ�50mm F1.4�̃����Y����������20���[�g���͂Ȃ�ĎB�e���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�܂���25mm F1.4�̃����Y���t�H�[�T�[�Y�ɂ͂�������10m�͂Ȃ�ĎB�e���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�܂�
�t���T�C�Y�{50mm F2.8 (10m)= �t�H�[�T�[�Y+50mm F1.4 (20m)= �t�H�[�T�[�Y+25mm F1.4(10m)
����͒P���Ȑ��������甽�_�������Ȃ��B��̌덷�͂��邪�B�R���Ǝv������v�Z���Ă݂Ȃ����B�ł������킩��Ȃ��Ă����ɔ������肵�Ȃ��Ŏ����ŕ����ĂˁB
�ŁA����Ȃ��ł͂ǂꂪ���邢�����Y�Ȃ̂��Ƃ����A�z�Ȏ�������R�\������邩�甃���Ă����ƁA
���邳��F�l���œ_�����^�L�����a
�Ɠ��{��̒�`�Ƃ��Č��܂��Ă���B�����炱��Ȃ��ł�50mm F1.4��25mm F1.4�����邢�B������F1.4�����B���ł��킩��B�ŁA�t���T�C�Y�{50mm F2.8 �Ɠ����摜�邽�߂ɂ̓t�H�[�T�[�Y�ɂ�F1.4���K�v�A�Ƃ������ƂɂȂ�ˁB�܂�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���Â��Ƃ����ZF�l�Ƃ��Ȃ�Ƃ������̂͒P�Ȃ郌�g���b�N�̖�肾���玞�Ԃ����ʂȂ̂ōl����̂͂�߂悤�B���̒��ł͊ȒP�Ȃ��Ƃ����l������n���Ƃ����̂����̐e�̌��Ȃ��������B
���ƃZ���T�[�̊��x�̓����Y�Ƃ͖��W�����炲������ɂ���̂͂�߂悤���B�t�H�[�T�[�Y�̃Z���T�[�̂P�̃s�N�Z���̓t���T�C�Y��菬��������A�����I�ɂ�1�̃s�N�Z���̊��x�̓t�H�[�T�[�Y�͕s���B�����s�N�Z���̊��x�͋Z�p�ɂ���ĈقȂ邾�낤����s�N�Z�������Ƃ������̃T�C�Y�ł��������x�̏ꍇ�͂��蓾��B�]���Ă����͎������Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��A�������B
����ł킩��Ȃ���A�����l���Ȃ�����������Bw
�����ԍ��F10181375
![]() 15�_
15�_
�s�����w����b�͈Ӗ�������܂���i���j�B
�~�X�^�[KEH����̘b���Ӗ�������܂���B
ISO���x�̘b�ł�����A�t���T�C�Y��4/3�͓������x�ݒ�ł͉掿���Ⴂ�܂��̂ŁA
�掿�������ɂ���悤�ݒ肵�Ȃ���ł����A����͓�i�̍��ł��ˁB
������������ւ̓����́A����f/1.4�Ȃ�P�ʖʐςł͓������邢�ł����A
�ʐ^���������邢���ǂ����͕ʂł��B�P�ʖʐςƎʐ^�̊T�O���Ⴂ�܂��B
�J�L�R[10165668]��������Q�Ƃ��Ă��������B
�����ԍ��F10181402
![]() 0�_
0�_
����ڂ�����A����͕ʂɎ���Ȃ��ĂȂ����ǁB�B
�P�ʖʐςƂ��A��`�̕s���Ȏ��ȗ��̕ςȗp��g���Ƃ������Ă킩��Ȃ��Ȃ��B
�������Ă����ƍl���悤�B
�����ԍ��F10181411
![]() 7�_
7�_
��`�͖��邢�ł���B�m�C�Y�Ȃ��ł����́B�m�C�Y�܂݂��4/3�t�@���͋C�ɓ���Ȃ������m��܂��B
�����ԍ��F10181420
![]() 0�_
0�_
����ق�����A�����܂��܂��Ӗ����������ł���[�B
��`�͖��邢�ł���A�m�C�Y�܂݂�Ƃ́A�͂āA�ǂ�ȃg���`�Ȃ̂������B
���ʂɌ���̓��{��ŏ������Ƃ͉\�ł����H
�����ԍ��F10181425
![]() 8�_
8�_
�ʂɕ�����Ȃ��Ă��ǂ��ł͂Ǝv���܂����A�m�肽���ł�����J�L�R[10171075]���Q�Ƃ��Ă��������B
�����ԍ��F10181436
![]() 0�_
0�_
����A�\����Ȃ����ǁA�T���̂߂�ǂ����������߂Ƃ���B
�Ȃ����낢�g���`�Ȃ̂��Ǝv��������������B�B
�����ԍ��F10181439
![]() 5�_
5�_
�܂�ǂ�ł��������Ă��Ȃ��̂ɂł��ˁB������g���`�ł��傤���B
�����ԍ��F10181446
![]() 0�_
0�_
���̂��[�A�ق�Ɛ\����Ȃ����ǁA
���ɔ������肷��̂͂�߂Ă�����āA�O�����ė���ł邶���B
�ق�Ƃ��Ɏ����̎g���Ă錾�t�̒�`��������x�Ċm�F���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂���B
��������Ύ����ʼn������Ă�̂��悭�킩��͂��Ȃ��ǂȂ��[�B
���Ƌq�ϓI�ɂ킩��v�Z�����Ȃŕ\�L���Ă�������ق������͂������ȁA
�g���`�͓���Ă킩��Ȃ���B
�����ԍ��F10181449
![]() 6�_
6�_
�� ̫�ϯĂ`�A�`�a�A�`�b �̘b�A
����F�l����������AF�l�Ɋ֘A���鐫�������ʂ̎ʐ^�������ł�����A�ǂ��ł͂Ǝv���܂��B
�ނ���ʐς𑊓�F�l�ɂ���ւ�����A�t�H�[�}�b�g���ǂ��ł��ǂ����ƂɂȂ�܂����B
4/3�Z���T�[������������ƌ�����_�͂���܂���B���ʏƎ˂ŋɏ���f�ֈ���i�݂܂����B
���邢�����Y������Ηǂ��̂ł��B�������Z���T�[�̕s������a���Ȃ��ł������܂��B
�����ԍ��F10181452
![]() 0�_
0�_
�� �ق�Ƃ��Ɏ����̎g���Ă錾�t�̒�`��������x�Ċm�F���Ă݂邱�Ƃ������߂��܂���B
�����̃J�L�R��ǂ番����Ǝv���܂����A�ǂ��Ƃ��Ȃ�������A�R�����g�����l�ł����B
�����ԍ��F10181460
![]() 0�_
0�_
���́[�A�ׂɂ�������킯����Ȃ����ǁA
��4/3�Z���T�[������������ƌ�����_�͂���܂���B���ʏƎ˂ŋɏ���f�ֈ���i�݂܂����B
�����邢�����Y������Ηǂ��̂ł��B�������Z���T�[�̕s������a���Ȃ��ł������܂��B
�Ⴄ��Ȃ����ȁB�t���T�C�Y�̗��ʏƎ˃Z���T�[���ł��������ς菬���������s������Ȃ��H�����I�ɏ������Z���T�[���s���Ȃ��Ƃ͖��炩�ł��傤�B��߂܂��A���̈������Ƃ������̂́B�B�B
�������ł��������Č����̂́A�����ŏ�����
1-1���O
�Ȃ��ǁi�j
����ق�����͖��邢�����Y�̃����b�g���P�ŏ������Z���T�[�̃f�����b�g��-�P�����Ăǂ������Ӗ��ł����Ă�̂��Ӗ����S��������Ȃ��Ȃ��B
�����������A���邢�����Y�̃����b�g���P�ŏ������Z���T�[�̃f�����b�g��-�Q��������
1-2=-1
�ŁA����ς��s�������B�Ƃ������ƂɂȂ邵�ˁB
��������ق�����̂ق��̃J�L�R���������̂��߂�ǂ��Ȃ̂́A����Ԃ���������肪���邩��ȂB
�ǂ�ł�ƁA���낢��Ԉ���Ă��ł��炢�炵�Ă���B
�����ƍl���悤���Ă����̂͂����������ƂȂ��ǂȂ��B
���������t�H�[�T�[�h�̃����b�g�͉掿����Ȃ��ăT�C�Y�ł��傤�H
�����ԍ��F10181477
![]() 8�_
8�_
�� �����I�ɏ������Z���T�[���s���Ȃ��Ƃ͖��炩�ł��傤�B
���łł����H�E�E�E�������Ă��ꂽ��ʐϔ�̌��_�ɂȂ邵���Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA��߂Ă��ǂ��ł����B
�܂�4/3�͂ǂ�Ȏ���g���Ă��s���������ł��Ȃ��Ƃ����咣�ł��傤���H
�����ԍ��F10181486
![]() 0�_
0�_
�� ���������t�H�[�T�[�h�̃����b�g�͉掿����Ȃ��ăT�C�Y�ł��傤�H
�܂�A���x�̓R���f�W�ɏ����ڂ��Ȃ��Ƃ������_�ɂȂ��ėǂ��ł��ˁH
�����ԍ��F10181489
![]() 0�_
0�_
�ق�ƐH��������Ȃ��A�ɂ����珑�����Ⴄ���ǁA
�ł͂���ق�����Ɍ��J����I
1. �S�^�R��R���f�W�����Ƃ��ǂ�Ȏ���g���Ă��A�t���T�C�Y����������g���A�掿�I�ɂ͕������Ȃ��ł����H
A������
B�����Ȃ�
2. �t���T�C�Y�@�����Ƃ��ǂ�Ȏ���g���Ă��A�S�^�R��R���f�W����������g���A�T�C�Y�I�ɂ͕������Ȃ��ł����H
A������
B�����Ȃ�
�����ԍ��F10181495
![]() 3�_
3�_
C�@���������Ȃ�
�ł������ł����B�B�B
�����ԍ��F10181498
![]() 0�_
0�_
�Ȃ����₷�邩�����ł��܂���B����[10181452]�ɏ����Ă���܂��B
�����ԍ��F10181502
![]() 0�_
0�_
�ق�A����ς蓚�����Ȃ��ł��傤�B
�킴�킴AB�ɂ��ă����N���b�N�œ�������悤�ɂ����̂ɂȂ��[�B
���������킢���������瓦������悤��C�܂ō���ďグ���̂ɁB�B
����ق�����A�ق�ƈ������Ƃ͂���Ȃ�����A
������x�����̎g���Ă�����{����Ē�`�������Ă݂���ǂ��ł��傤���B
�Ӗ��̂Ȃ����t���������܂���B�ŁA�Ԉ���Ă�B
�V���v���ɍl����A�����͂����o��͂��ł���B
�����ԍ��F10181522
![]() 7�_
7�_
���^���̓Z���T�[�T�C�Y�̍�������܂�����A���̕����͎d������܂���B
�}�E���g�͖��邢�����Y���g��Ȃ��ƌ����O��ł�����AE-410�Ɠ����ʏ��^���ł��܂��B
�܂��}�C�N���Ɠ����~���[���X�Ȃ瓯�����ŏ��^���ɂȂ�܂��B
�����Y�͓�����p�A�������a�̂��̂ł�����A�t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ��傫�����قړ����ł��B
4/3�̕���������^�d�ʂɂȂ�܂����iZD35-100/2.0��EF70-200/4L�͋ɒ[�ȗ�̈�j
����͎��ӌ����Ԉ���Č��������Ȃ��������ŁA4/3���L�̌��ۂɉ߂��܂���B
�����ԍ��F10181534
![]() 0�_
0�_
����������œǂ܂Ȃ��̂��A�M���̓`�Ƃ̕ł��傤���B
�����ԍ��F10181541
![]() 0�_
0�_
����A���l�̓`�Ƃ̕Ƃ����킯����Ȃ���B
�_���I�ȕ��͂̏��������������Ȃ���������܂��A
���݁A�A�����J����{�̎��������w�ŋ����Ă�����@�́A
�ŏ��Ɍ��_�������āA�����ė��R�ł��B
����ق�����̏����Ă��邱�Ƃɂ́A�ǂ��ɂ����_���Ȃ��B�B�B
�ǂދC���N���Ȃ��̂͂����肦�ł��傤�B
�������Ƃ����邮�邮�邮�邩���Ă邾���ł���B
����������Ƃ͂����肵����`�ŁA�N�ɂł��킩����{��ŕ\�L������ǂ��ł����H
�ƒ�Ă��Ă���̂ł��B
���Ȃ݂ɓ�����
C
C
�ł����H
���_�������Ă��Ȃ��̂Ŕ��_���ł��܂��B�B�B
�����ԍ��F10181555
![]() 9�_
9�_
������Ƃ́A���̏ꍇ�A������p�œ������a�̈Ӗ����Ǝv���܂����A�ł�����
�������ʂɂȂ�ƌ����Ă܂��ˁB����́A���\����A�傫���d���A�l�i�܂œ����ł�
4/3�̐v�~�X��ʕ��ŏ����ł���Ǝv���܂��B
�܂��AK-m��D40�ƁAE-410��510�AE-620�Ɣ�r���܂��ƁA�{�f�B�T�C�Y�̍��͖w��
�Z���T�[�T�[�Y�̍��Ɠ�����Z���`�ʂŁA�T�C�Y���̔����Ƃ͑S�R�Ⴂ�܂��B
���̈ʂł���ˁB���̈ʂ͋����Ă���������Ǝv���܂��B
������悪�������悤�ɁAAPS-C�@�̃}�E���g�̓t���T�C�Y�̑���a�����Y���l�����v�ŁA
���ʂ�����܂��B4/3�ɍ����āg�Ő�h�v������A�܂��������Ȃ�܂��B
�����ԍ��F10181619
![]() 0�_
0�_
���ς�炸���_������܂��B�B�B
�����������APS�̂��ƂȂb���ĂȂ��̂ɁA
�_�|�ƊW�Ȃ����Ƃ�ˑR�܂������Ă�̂́A
�Ȃ�Ȃ�ł��傤���B�B�B
����ɂ��̓��{�ꂪ�ʂ��Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA
����������ƕςȐl�Ɋւ���Ă�̂��ȁA�Ǝv���n�߂Ă��ł����B
�����ł����H
�������Ă悭�����Ă��������B
���͂ǂ�Ȏ���g���Ă��Ƃ�������ŁA�ׂɉ�p�Ƃ����a���ǂ��̂Ƃ�������ݒ肵�Ă��Ȃ��ł���ˁB���������ǂ��̕����ʼn�p�Ƃ����a�Ƃ������܂��������H
�ǂ����Ă���ȊȒP�Ȃ��Ƃ��킩��Ȃ��̂��A�ق�Ƃ��ɕs�v�c�ł��B
�����ԍ��F10181653
![]() 10�_
10�_
���鐯���߂炳��ɁA�킽����������₪����܂��B
�M�a���ʃX���Ń��X����
> 4/3�ł��A��i���邢�����Y��t���A35�~�����Ɠ����ʐ^���B��܂�
�ɂ��Ăł����A�u��i���邢�����Y�v���ċ�̓I�ɂǂ�����Ηǂ��ł����H
�ꉞ���₷���悤�Ɏ��̑I������p�ӂ��܂����B
A.�L�����a��2�{�̃����Y
B.��p��2�{�̃����Y
C.�L�����a����2�{�ŁA���A��p����2�{�̃����Y
D.���������C���[�W�T�[�N�����قȂ�̂ŁA��i���邢�����Y��t���Ă������ʐ^�͎B��Ȃ�
�����ԍ��F10181809
![]() 1�_
1�_
���炭���̃X�������Ă����̂ł��������ɂ͓�����Ď���ł��܂���ł����B�͂��߂ē��e�������܂��B������������̐����ʼn�p�Ɩ��邳�ƃZ���T�[�T�C�Y�̊W���͂��߂ĂȂ�ƂȂ������ł��܂����B���S�Ɍ�����Ă���܂����B�����O�ɂӂ��킵���ꖡ�̂���ǂ����e�Ǝv���܂����B����ł́B
�����ԍ��F10182057
![]() 4�_
4�_
���݁A���M�N�`�R�~�E����5�ʁI
�Ƃ���ł��鐯���߂炳����ăJ�����������Y�ȂɎg���Ă�́H
�����ԍ��F10182083
![]() 2�_
2�_
�� �u��i���邢�����Y�v���ċ�̓I�ɂǂ�����Ηǂ��ł����H
�g�������邢�h�̂��{���Ȃ��Ƃł��ˁB��p�������A�L�����a�������ł���ł��B
�����ԍ��F10182612
![]() 0�_
0�_
�� ��p�������A�L�����a������
�œ_�����́A35�~�����́������������Ƃ����������́g��p�������h�̈Ⴄ�\���ŁA
F�l�́A35�~������f/���������Ƃ����������́g���a�������h�̈Ⴄ�\���ł��B
�ʐ^�S�́A�Z���T�[�̕��A���A�Ίp���A�ʐς��l�@�����ꍇ�A
��ł����Ⴊ��������Ǝv���܂����A���܂ł����ł���������܂���ˁB
���_�ł���Ȃ�A�r��������Ȃ����P�ł�����A�g�r���͎x���h���Ɨ������Ă܂��B
�����ԍ��F10182683
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
������ƌ��Ȃ��Ԃɗ��ꂪ�ς���Ă�݂����ł����B
>[10177499]�͗��Ɍ��܂肷���ł��ˁB
[10177499] �̂ǂ������܂��Ă���̂��킩��܂��B
[10177499] ����̔����B
>�v����ɁA�t�H�[�}�b�g��F�l���ς��Ȃ��̂ɁA�Y�[���Ō��ʂ�������Ƃ��Ă��܂��B
����́u�����Y���̘b�v�A�܂�u�t�H�[�}�b�g���l���Ȃ��b�v�ł��i�C���[�W�T�[�N�����ɒ[�ɍL����A�t�H�[�}�b�g�͔�ʑ̂���荞�ޔ͈̖͂��j�B
��ʑ̋����i�B�e�����j���ŁA�����ʑ̂��B��B���̔�ʑ̂ɂ��Ă̌��ʂ͑����܂��ˁB
���ʁF���� × ����
�Ⴆ�Ύ��̃A���o���ł́uQuraz�v�̊ŔB�Ɠx���Ŗʐώl�{�B�܂�u�����l�{�v�ł��B���Ԉ��Ȃ̂Ō��ʎl�{�B
F�l��肶��Ȃ��Y�[���ł����ʂ������܂��B�u�œ_������{��F�l��{�v������ȃY�[�������Y���݂��܂���ˁi�������Ƃ��Ă��Y�[���̈Ӗ��������j�B�܁A�u�Y�[���v�̈Ӗ��ɂ����܂����B
�ƌ������A150mm F2.0 �� 300mm F2.0 �́u�����Y�����̂��́v���C���[�W���Ă��������B���̓�̃����Y���������N�I���e�B�Ȃ�āA���т��̂ł���B
>50mm F2.0 �� 100mm F2.0 �̃����Y���t���T�C�Y�Ŏg�p�����ꍇ�A�Y�[���Ō��ʂ��ς��Ȃ痼�҂̌��ʂ͈قȂ�͂��ł����A�ǂ̂��炢�Ⴄ�̂ł��傤���B
���܂��Ă���̂��ƁH
�u�t���T�C�Y�Ŏg�p����v���āA����ȕ��Ƀt�H�[�}�b�g�𐧌������A�����Y�����̂��̂ōl���܂��傤�B
�u�C���[�W�T�[�N������ʑ̂�菬�����ꍇ�v�Ƃ��͔�r�ɂȂ�Ȃ��̂Ř_�O�ł��B
�u�O���[�J�[�h���B��v�Ȃǂ́u�����ʑ̂����݂��Ȃ��i�Ώۂ����S�ψ�ʂ́j�ꍇ�v�ɂ��Ă͂��łɏq�ׂ܂����B�t�H�[�}�b�g��F�l���ʑS�̂̌��ʂ����肵�܂��B
[10178550] �� [10178633] �͂�����Ƃ킩��܂��A���̌����Ă邱�Ƃ͌��ǂ�
�u��ʑ̂̃����Y���̃N�I���e�B�̓����Y���a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v
�Ƃ������Ƃɉ߂��܂���i����̉���݂����Ȃ��́j�B
�����ԍ��F10182854
![]() 0�_
0�_
>�����ZF�l�_�́A�ӏ��Ɍォ��t�������G�l���M�[�ʂ̂��Ƃ��܂������l�����Ă��Ȃ�
>
>���邷���郂�j�^�͖ڂ�ɂ߂�̂ŁA�C���������������B
��k�ŕԂ��Ă�ꍇ����Ȃ��A�u�ォ��t�������G�l���M�[�v�́u�M���̑����v�ł��BS/N��ɂ͖��W�B
�����ԍ��F10182865
![]() 0�_
0�_
quagetora���� �́u�_�w�_���v�Ă�肵���l�ł����H
�S���u������O�̂��Ɓv�Ȃ�ł���B
������O�̐ςݏd�˂ł��ˁB
�����ԍ��F10182875
![]() 1�_
1�_
������u������O�̂��Ɓv�������Ă����܂��i���ɉ��x�������Ă��邱�Ɓj�B
�E��f���𑝂₷�̂́u���Z�œ_�����v��L���̂Ɠ����i���������ZF�l�͑傫���Ȃ�j�B
�ł��t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̉摜�̔�r������Ƃ��ɂ́A���Ǔ��T�C�Y�ɂȂ�悤�Ɂi�傫�������j�k�������Ⴄ����A�N���킴�킴�u��f�����݂̊��Z�œ_�����v���l���悤�Ƃ͎v��Ȃ���ł��傤�ˁB
�Î~��ɂ́u���f���v�����݂��Ȃ��̂����̗��R�B
�����ԍ��F10182896
![]() 0�_
0�_
�ł��悤����Ɓu�����Y�����̂��́v���l���n�߂Ă��ꂽ�݂����ł��ˁB
>�B�u�œ_������{��F�l��{�v������ȃY�[�������Y���݂��܂���ˁi�������Ƃ��Ă��Y�[���̈Ӗ��������j�B�܁A�u�Y�[���v�̈Ӗ��ɂ����܂����B
�u×�Q�{�̃G�N�X�e���_�[�v�Ɓu�ʐ� 1/4 �g���~���O�v�͓������l�ł��B����Łu���ZF�l�v�͂킩��ł��傤�B
�������A
>�E��f���𑝂₷�̂́u���Z�œ_�����v��L���̂Ɠ����i���������ZF�l�͑傫���Ȃ�j�B
�u��f���v���u���Z�œ_�����v�̈�v���ƍl����ƁA
�u×�Q�{�̃G�N�X�e���_�[�v�Ɓu�ʐ� 1/4 �g���~���O�v�͓������l�u�ł͂Ȃ��v�B
�ɂȂ�܂��B
�Ƃ͌����A���̏ꍇ�������YF�l���i��ɍi���āA��܂̉��Ƃ����a����f�s�b�`��啝�ɏ������ꍇ�ɂ́A
�u×�Q�{�̃G�N�X�e���_�[�v�Ɓu�ʐ� 1/4 �g���~���O�v�͓������l�u�ł���v�B
�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10182935
![]() 0�_
0�_
���Љ�̎d�����Z�����āA���܂�A�N�Z�X�o���Ă��Ȃ������ɃX���b�h��
�L�т܂����ˁB�ǂ����A������ƐS�z���Ă����ɂȂ����悤�ł��B
�ʂ̓��e���炿����Ɨ���āA�X����Ƃ��ď����������݂����Ē����܂��B
���ǁA�����Y���ǂ������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�B���f�q���������f�����b�g��
�����Y�̘b���Ƃ��Č���Ă���̂ŁA�������Ă���悤�Ɍ����܂��B
������������A���Z�e�l�ȂǂƂ������̂����Ȃ�Ȃ��ł��傤���B
�B���f�q���������f�����b�g�����ʂ̊ϓ_���猾���̂ł���e�l���̂��̂�
�Ⴄ�Ӗ��ɂȂ��Ă���̂ł��傤����A������ƈႤ���t���g���āA�ϐ���
F�l�������͏œ_�����ƌ��a�Ō��悢�̂ł͂Ǝv���܂��B
�������邾���ŁA�����Ԃ�Ɩ{���ɍi�����c�_���o����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Z�e�l�ȂǂƂe�l�ɍS����������������K�v������̂��^��������܂��B
�c�_�����M���Ă���ƁA����I�ȕ\���̌��t�ɍs�������Ă��܂��܂����A
�f���ł̃R�~���j�P�[�V�����͌��t�ɂ����̂Ȃ̂ŁA���ꂼ��̓`������
���Ƃ�������Ɠ`���Ȃ��\���������ƍl���Ă����ׂ����낤�Ǝv���܂��B
����̊���I�Ȍ��t���X�g���[�g�Ɏ��̂ł͂Ȃ��A������x���������Č���B
�܂��A�����������������Ɠ`���Ȃ����Ƃ̕��������ƍl���Č��t��I�ԁB
���ꂼ�ꂪ������ƈ����ď������߂����ƌ��ݓI�ȋc�_�ɓ`���̂ł͂Ȃ�
�ł��傤���B
����A�V���Ȑ��ɂ��ẮA����ɕ����点��w�͂ɖ��߂�K�v�������
����Ȃ��ł��傤���B�u������Ȃ����܂��������v�Ƃ����̂́A���Ȃ藐�\��
�������ł����āA���������̂ł���u�����𗝉��������Ȃ����������v
�Ƃ����ӌ��̕����A�����E�ł͑����ł��傤�B���Ȃ��Ƃ��A�V�����A�C�f�A��
�������ۂ��������Ƃ��Ă��A��O�҂ɂ���Č�����]������Ȃ���A
�������ƔF�߂��Ȃ��̂����̒��̏�ł��B�w�p�̐��E�ł͂��ꂪ������O��
���傤���A�����̐��E�ł�����𗝉��������Ȃ��ƁA�d�������炦�܂���B
���s�̂�������́A�ʐ^�Ȃǂ��A�b�v����đ�O�҂���������悤�ɓw�߂�
�����A�V���Ɍ��ݓI�ȋc�_�Ɍq�������Ǝv���܂��̂ŁA�X����̗���
�Ƃ��Ă͑�ϊ��ӂ��Ă��܂��B�i�����A�c�O�Ȃ��犷�Z�e�l�Ƃ����l������
�����ɂ�����o�܂͕�����܂������A���̈Ӌ`�ɂ��Ă͂܂��[���ɗ����o��
�Ă��܂���B�j
���t�ł͂Ȃ��Ȃ��`���ɂ����̂ł���A�}�Ȃǂ��g���Đ������Ă݂��
�������Ƃ��L�����Ǝv���܂��B
�����A������ƋC�ɂȂ�̂́u�Ƃ茾�v���Ԃ₢�Ă���l�ł��B
�P�Ȃ�Ƃ茾�������Ă���l�ɁA���J�ɑΉ�����K�v���Ȃ���Ȃ����Ȃ�
�v���܂��B�u�ǂ����āA�j�R����L���m���̃X���b�h�œ����b�����Ȃ��̂��v
�u�咣��������������̂ł���A�Ǝ��ɃX���b�h�����Ăċc�_�����Ȃ��̂��v
�Ƃ�������Ɋւ��Ă͉��Ȃ��A�킴�킴�V�X�e���Ƃ��Ă����Ďg����
����I�����p�X���[�U�����̒��ł������Ȃ��̂��s�v�c�łȂ�܂���B
���ǂ́A�F�X�Ƌc�_�����Ă���l�̋C���Ђ����������߂́u�Ƃ茾�v���Ƃ���
�v���Ȃ��̂ŁA�Ƃ茾�͓Ƃ茾�Ƃ��ĕ����Ă����͈̂�ԗǂ��̂ł͂Ȃ���
���傤���B
�{���A�����̐��������咣����̂ł���A�����g�ŃX�����グ�Đ��X���X��
�c�_�ɗՂނƂ��AWikipedia�ŐV���ȓ��e�����Ƃ��A�V���Ȋw���Ƃ��Ċw�p
�_���\����Ƃ��Ƃ����̂��A�����������ł��傤�B
����Ȑ[���Ȃ�����̃X���̂Ȃ��œ���̐l�Ɍ����Ă��������A���
���ݓI�Ȋ������Ǝv���܂��B
���s�̂������ʐ^���A�b�v���ĉ�����A�l�������q�ׂĒ������Ƃ���
�ɂ͂ƂĂ������������܂����A��͂�AD700��E30���g���������o���ɂ����ẮA
�܂��܂��^�₪��������܂���B���̋^����Ă͏�肭�`������قǍl��
���Z�܂��Ă��Ȃ��̂ŁA���������������Ă��玿�₳���Ă��炨���Ǝv���܂��B
���̘A�x���ɗF�l����D700������邱�ƂɂȂ����̂ŁA���Ԃ�������
E-30�Ƃ��������B���ׂ����āA�����ɂƂ��ăt���T�C�Y�͖{���ɕK�v�Ȃ�
���Ƃ������ɂ��ẮA�������g�ł������Ă݂悤�Ǝv���܂��B
�Ȃ��A���������ł��ˁB�\����܂���B
�����ԍ��F10183035
![]() 4�_
4�_
�� �V���ȓ��e�����Ƃ��A�V���Ȋw���Ƃ��Ċw�p�_���\����Ƃ��Ƃ����̂��A�����������ł��傤�B
�≖�ł��f�W�^���ł����ɐV�������̂ł͂���܂��A���ێg���Ďʐ^���B���Ă�̂�
���r���[�Ŗ{���𗝉��ł����A�l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A��a���ƌ����Ă��Ǝv���܂��B
�܂��A���s�̂�������������f�T�C�Y�ł����A�����������ǂ��ł��傤���A
��f�T�C�Y�͕ʌ��ŁA�g���~���O�����Ďn�߂Ė]���i��p�������Ȃ�j�̘b���ł��܂��B
�g���~���O�Ƃ́A�����ʐς����郏�P�ł�����A����͕ʌ��ł͂Ȃ��{���ł��ˁB
�����ԍ��F10183086
![]() 1�_
1�_
�Ԉ���������闝�R�͂Q��ށB
(�P) ���m�ł���
(�Q) �̈ӂł���@(�Q)�́w�E�\�����ցx�I�ȑP�ӂ̌̈ӂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ӂ̌̈ӂɕ�������B
�^���ɂ���ă_���[�W���鎖�����邪�A���ꂴ��Ȃ��B
��^���̏�ƋC�Â����l�́A���\��܂��͏��Ȃ���ʂ�߂���悢�B
�E�E�E�l���ς��Ɛ^�����ς�邱�Ƃ�����炵���B
���ʁA�����o���鎖�̓M�����ɂȂ�Ȃ�����ǁE�E�E�E�B
�����ԍ��F10183099
![]() 2�_
2�_
�� �Ȃ��A���������ł��ˁB
�����ł��ǂ��ł����A�L�Ӌ`�Șb���������������Ǝv���܂��B
�܂��Ȃ����Z�œ_�����ƁA���ZF�l���K�v���ƌ����܂��ƁA
�� �܂��́A�t�H�[�}�b�g���Ⴄ�ꍇ�A�œ_������F�l�͎B�����ʐ^�̉�p�ƌ��ʂ�����ł��܂���A
�� ���ɁA�≖�̊��o�ɍ��킹�ĕ�����₷���悤�A35�~�������̊��Z�l�ŕ\�����܂��B
35�~���̊��o���Ȃ��l�������̂ɂł����A�o���o���ł͂Ȃ��A���ꂵ����r���₷����Ƃ��Ă��Ӗ�������܂��B
���܂ł̌o���ƑS����a�����Ȃ��A�܂���ʂ̕t���Ȃ����ʂ������܂��̂ŁA����ŗǂ��Ǝv���܂����A
�����œ_�����̘_��������Ȃ�A�����ǂ�ł݂����Ǝv���܂��B�펯�ł���B
�܂��A�J�����ƊE�ł͐̂���N���l�ɗ]�v�Șb�����Ȃ��̂��펯�ł����A
���q���m����Ȃ��̂��A���[�J�[�ɂƂ��ēs���̈������ƂƂ͌���܂���B
�����ԍ��F10183184
![]() 2�_
2�_
�� �^���ɂ���ă_���[�W���鎖�����邪�A���ꂴ��Ȃ��B
�_���[�W�͂Ȃ��Ǝv���܂��B���[�U�[�ɂƂ��Ă͌��X���v������܂���B
�������g�������a�ɂ����珬�����T�C�Y�̕s����ł��������Ƃ��ł���h����������A
����̓}�Y�C�ƌ����Ă����������܂����A���[�U�[�Ɨ��v�����̗���ł��ˁB
�����ԍ��F10183265
![]() 1�_
1�_
�X���傳��A�Ƃ茾���ċ�����Ɛ�����̂��Ƃ��Ǝv����ł����ǁA
�{���ɂ��낻��X���[���Ȃ��ƁA
�X�����ǂ݂ɂ����Ȃ��Ďd�����Ȃ��A�Ǝv���͉̂������H
�܂��A���͑ގU�����A���̃X���炢��B�B�B
�����ԍ��F10183481
![]() 11�_
11�_
���̓[������
>���ʁA�����o���鎖�̓M�����ɂȂ�Ȃ�����ǁE�E�E�E�B
�Ƃ��낪�A�Ȃ�ŋc�_�ɂȂ邩�ƌ�����
������G�c�Ɍ����ƁA���鐯���߂炳��⋞�s�̂�������͎����́u���̂����v��ς��悤�Ƃ��Ă����ł���B
�����܂ł��A���̗����ł����ˁB�����Ԉ�����]���ł͂Ȃ����M�͂���܂��B^^;
��V�Ȏ咣���Ǝv���܂��B
���Ƃ��Ă�F�l�ȊO�������Y�̖��邳�Ƃ��č̗p����ƁA�Ⴆ�ΘI�o�v���ȒP�ɂ͍��Ȃ��Ȃ�(R2-400�����Ɏw�E���Ă��܂��j�̂ŁA�^���͏o���܂���ˁB
�����ԍ��F10183544
![]() 7�_
7�_
���鐯���߂炳��
�������������Ă��܂���B
���Ȃ��́A������������̃��X[10181375]
----�����������X������p
�t���T�C�Y�@��50mm F2.8�̃����Y����������10���[�g���͂Ȃꂽ�l���B�e�����Ƃ���B����Ɠ�����ʊE�[�x�ƃt���[���邽�߂ɂ́A�t�H�[�T�[�Y�ɂ�50mm F1.4�̃����Y����������20���[�g���͂Ȃ�ĎB�e���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�܂���25mm F1.4�̃����Y���t�H�[�T�[�Y�ɂ͂�������10m�͂Ȃ�ĎB�e���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�܂�
�t���T�C�Y�{50mm F2.8 (10m)= �t�H�[�T�[�Y+50mm F1.4 (20m)= �t�H�[�T�[�Y+25mm F1.4(10m)
�i�i�����j�j
���邳��F�l���œ_�����^�L�����a
�Ɠ��{��̒�`�Ƃ��Č��܂��Ă���B�����炱��Ȃ��ł�50mm F1.4��25mm F1.4�����邢�B������F1.4�����B���ł��킩��B�ŁA�t���T�C�Y�{50mm F2.8 �Ɠ����摜�邽�߂ɂ̓t�H�[�T�[�Y�ɂ�F1.4���K�v�A�Ƃ������ƂɂȂ�ˁB�܂�t�H�[�T�[�Y�̃����Y���Â��Ƃ����ZF�l�Ƃ��Ȃ�Ƃ������̂͒P�Ȃ郌�g���b�N�̖�肾���玞�Ԃ����ʂȂ̂ōl����̂͂�߂悤�B���̒��ł͊ȒP�Ȃ��Ƃ����l������n���Ƃ����̂����̐e�̌��Ȃ��������B
----���p�I���
�ɑ��āA[10181402]�ł́A
----���鐯���߂炳�X������p
������������ւ̓����́A����f/1.4�Ȃ�P�ʖʐςł͓������邢�ł����A
�ʐ^���������邢���ǂ����͕ʂł��B�P�ʖʐςƎʐ^�̊T�O���Ⴂ�܂��B
----���p�I���
�Ɖ��Ă��܂��B�Ƃ��낪���鐯���߂炳��̃��X[10182612]�ł�
---���鐯���߂炳�X������p
�g�������邢�h�̂��{���Ȃ��Ƃł��ˁB��p�������A�L�����a�������ł���ł��B
----���p�I���
�Ɖ��Ă��܂��B
�܂��ɖ������������[10181375]�Ɠ������������Ă���̂ł���B
��p�������ŗL�����a�������Ƃ́A
�t���T�C�Y50mm�@F2.8 �́A�t�H�[�T�[�Y 25mm F1.4
�ł͂Ȃ��ł����H
�܂�u�������邳�v��O���Ŕے肵�Ă����Ȃ���A��ɓ������Ƃ��m�肵�Ă��܂��ˁB
�܂��A���鐯���߂炳��̃��X[10182683]�ł́A
----���鐯���߂炳����p
�� ��p�������A�L�����a������
�œ_�����́A35�~�����́������������Ƃ����������́g��p�������h�̈Ⴄ�\���ŁA
F�l�́A35�~������f/���������Ƃ����������́g���a�������h�̈Ⴄ�\���ł��B
�ʐ^�S�́A�Z���T�[�̕��A���A�Ίp���A�ʐς��l�@�����ꍇ�A
��ł����Ⴊ��������Ǝv���܂����A���܂ł����ł���������܂���ˁB
���_�ł���Ȃ�A�r��������Ȃ����P�ł�����A�g�r���͎x���h���Ɨ������Ă܂��B
----���p�I���
�ȂǂƂ��������Ă��܂��B
���������Ĕ��_�������e����ɂȂ��čm�肷��Ƃ́A�ǂ��炪�r���ł����H
���鐯���߂炳��A�{���͕������Ă���̂ł��傤�H
�����ԍ��F10183614
![]() 8�_
8�_
������������
�Ƃ茾�������Ă���l�́A�N�Ƃ͌����Ă��܂��A�킴�킴��������Ă���
����������悤�Ȃ̂ŁA�����g�͎��o������悤�ł��B
�����́A���s�̂�������ƁA���̕��̓X�^���X���������悤�Ɏv����
���܂��B���s�̂�������̓t�H�[�T�[�Y�̎B���f�q���K�v�Ƃ��鑍���ʂ�
���Ȃ����Ƃ�\�����悤�Ƃ��āA�Ꭶ�Ȃǂ��n�߂Ă����܂��B����̕���
���܂Ōo���Ă����t�V�тő�����������������ŁA���s�̂��������
�������݂𗘗p���Ȃ���l�K�L�����Ɏ����Ă����Ă���悤�Ȉ�ۂ��n��
�܂����B
���Ȃ��Ƃ��A�����́u�Ƃ茾�v�ɑ��Ă̓X���[���悤�ƍl���Ă��܂��B
�͂炽����
�������A�ʏ��F�l���l�����ł̕��������Ⴄ�Ƃ������������Ă��܂��B
���������Ⴄ�̂ɂ��ւ�炸�A���Z�e�l�Ƃ������l�Ń����Y�̖��邳��\��
���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A�����������Ă��錴�����Ǝv���܂��B
�]���āA�e�l�Ƃ������t���g�킸�Ƀ����Y�̓�����\��������́iF�l��
���邳�\���Ƃ͈قȂ���́j�Ƃ���Ηǂ���Ȃ��̂Ƃ������Ƃł��B
��������A�ʏ�̂e�l�ƍ������Ȃ��ł悭�Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������A���̒l�͒ʏ�̎B�e�̎��ɂ͑S���ӎ�����K�v�͖����A����܂�
�̘I�o���g���悭�āA���̒l�����ƂȂ�̈�i��Ɠx�H�j�ɂ��������
�̈Ⴂ��\�����邽�߂ɗ��p����悢�ł��傤�Ƃ������Ƃł��B
�����ł����Ȃ��ƁA���܂Ōo���Ă��c�_�������������ɂ���܂���B
�����ԍ��F10183659
![]() 3�_
3�_
�t���T�C�Y�Ɠ����u���邳�v��ɂ̓t�H�[�T�[�Y�ł͓�i���邢�����Y���K�v�̑����ł��B
��������̓Z���T�[��ISO���x�̖��Ȃ̂ł����A
�f�W�J���Z���T�[��ISO���x�ݒ�͒P�ʖʐϓ��������Ƃ��܂��B
�܂�t���T�C�Y�̃Z���T�[�Ō���ISO-200���A�t�H�[�T�[�Y�̃Z���T�[�Ō���ISO-200��
�Z���T�[��ɓ�������ʂ͓���ʐς����蓯����ʂœ���̉摜���L�^�ł���悤�ɃZ���T�[��v���������܂��B�i�d�C�I�ɐM����������A�o�C�A�X�d���������肷��B�j
����͋≖�t�B�����̂��납��ς��܂���B35mm�̋≖�t�B������APS�T�C�Y��110�T�C�Y�ɃJ�b�g���Ă�ISO���x���ς���ł͂Ȃ��̂Ɠ����ł��B
���āA�w�������邳�x�邽�߂ɁA�t�H�[�T�[�Y�ɓ�i���邢�����Y�����t���ĎB�e����ƁA�C���[�W�Z���T�[�̌v�Z������A��i�̘I�o�I�[�o�[�Ƃ��ċL�^����Ă��܂��܂��B
����������ɂ̓V���b�^�[�X�s�[�h�𑁂����邩�AND�t�B���^���g�p���A�����ʂ����炷��������܂���B�i�i��H�����i��Ɣ�ʊE�[�x���ς��̂�NG�j
�ȂƂĂ��ܑ̖����ł���ˁB
���������f�W�J�����[�J�[���A�������ʐςŃt���T�C�Y�Ɠ����̎ʐ^���B���悤�ɃC���[�W�������Ă���Ă���̂ɁA�킴�킴�����������o���āA�������Ďg�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�āB
�Ȃ̂ŁA�f�W�J���̐v��A�t���T�C�Y�Ɓi�Ȃ�ׂ��j�����i�ɋ߂��j�̎ʐ^���B�邽�߂ɂ͓����p�œ���F�l�̃����Y������Ηǂ��悤�ɂȂ��Ă���̂ł��B
�܂�̓t���T�C�Y50mm F2.8 �ɑ��ăt�H�[�T�[�Y�ł� 25mm F2.8 �̃����Y�ŏ[���ƌ������Ƃł��B
�f�W�J���̒��̃v���Z�b�T�́A���̏����ňꐶ�������Z�������Ă���Ă���̂ł��B
�ŁA�ŏI�I�ɂ̓C���[�W�Z���T�[�̐��\�ɍs������ł��B1��f������̃_�C�i�~�b�N�����W�Ƃ��A�m�C�Y�A�Œ�K�v�Ɠx�Ƃ��ˁB�ł��t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y��4����1�̖ʐς����Ȃ��Ƃ��������I����Ȃ̂ŁA�������͂ǂ����悤������܂���B
�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y��4����1�����Z���T�[�ʐς��Ȃ��̂ʼn掿�������A�ƌ�����A���̒ʂ�Ɠ����邵������܂���B
�����ԍ��F10183825
![]() 10�_
10�_
�������E���Ƃ��āA�l�K�e�B�u���[�v�Ɋׂ��Ă���̂œ����̖ړI��
�����Ԃ��Č��邱�Ƃɂ��܂��B���X�́A�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y��
����Ȃɉ掿���Ⴄ�̂��Ƃ������Ƃ��^��̃X�^�[�g�ł����B������
D700(�蕨�ł����E�E)��E-30�������Ď���t�߂��ӂ�ӂ�ƎB�e��
�Ă݂܂����B�@�ނ͈ȉ��̒ʂ�ł��B
E-30+ZUIKO DIGITAL 14-35 F2.0 SWD
D700+AF-S Nikkor 24-70 F2.8G ED
�B�e��AColor Edge CG301W���g���ăs�N�Z�����{�ł������J���܂�
���Ă݂܂����B���܂荷���������Ȃ��Ƃ����̂������Ȉ�ۂł��B
�������A���ꂼ��̉摜�̈�ۂ͈قȂ�܂��B�G���̕�������
�Ⴄ�ƌ������Ƃ�������܂��B�ł��A�m�C�Y���C�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ�
�ǂ���ł��[���g����i�����Ɗ����܂��B
�u�t�H�[�T�[�Y�����Y��2�i�Â��āA�掿�������E�E�v���Ȃ��Ƃ��A
�����̓����ɁA���҂��g���Ă����ł͂���Ȃ��Ƃ��������ʂɂ�
�������܂���ł����B�ǂ�������ʂɂȂ�ƁA����������ł���̂�
���傤���ˁB��͂��Ɠx�̔�ʑ̂ł����H
�����ԍ��F10183884
![]() 12�_
12�_
���A���������O���܂����B�B�B
�ǂ����_�c���ĉ������_�悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�������Ǝ��̂��ړI�̂悤�ł��ˁB
���������̃X���ɓ������Ƃ������܂����Ă��܂����B�B�B
�����͎ʐ^���B���Ă݂��炢���̂ɂƎv���܂��B
���������킯�ōς݂܂���B
���s�̂�������ւ̃��X���������Ȃ����Ƃɂ��܂��B
�ق�Ƃ͂�����̃X���ł������A����I�ɂ�����ŁB
����ł͂��߂������B
�����ԍ��F10183938
![]() 6�_
6�_
������Ƃ����ʂ�܂��˂���A
���������Ȃ�����ł������A���[���������̂ŁA�ǂ�ł��܂����B
������Ƃ���̘b�ɂ́A�����Ԉ���Ă���Ƃ���������ł����ǁA���������H
�܂��A
���t���T�C�Y�Ɓi�Ȃ�ׂ��j�����i�ɋ߂��j�̎ʐ^���B�邽�߂ɂ͓����p�œ���F�l�̃����Y������Ηǂ��悤�Ɂ��Ȃ��Ă���̂ł��B
���܂�̓t���T�C�Y50mm F2.8 �ɑ��ăt�H�[�T�[�Y�ł� 25mm F2.8 �̃����Y�ŏ[���ƌ������Ƃł��B
���f�W�J���̒��̃v���Z�b�T�́A���̏����ňꐶ�������Z�������Ă���Ă���̂ł��B
�ł����A50mm F2.8��25mm F2.8�ł͓����p�ł͂���܂����B��p���Ⴂ�܂���ˁB�����Ăǂ��l��������50mm��25mm�ł�����B���Z��p�Ƃ����Ӗ��Ȃ�ł��傤���A�������������Ɗ��ZF�l�Ɠ����Řb����������̂ŁA��߂����������ł���B
���������t���T�C�Y50mm���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��t����Ɖ�p��25mm�ɂȂ�Ƃ�����������ɑ����悤�����ǁA50mm�͂ǂ�ȃJ�����Ɏ��t���Ă�50mm�Ȃ�ł���B��p�͕ς��Ȃ��B�N���b�v�t�@�N�^�[���ς�邾���Ȃ�ō������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�łȂ��Ƃ����ƌv�Z�ł��Ȃ��ł��傤�B������킩��Ȃ����݂�Ȕn���Ȃ��Ƃ����X�ƌ����o����Ȃ����Ǝv����ł����ǁB
����Ƀt���T�C�Y50mm F2.8 �ƃt�H�[�T�[�Y�ł� 25mm F2.8�ł͔�ʊE�[�x���������܂��B�v�Z���Ă݂܂��傤�B���Ȃ���ʊE�[�x���~�����Ȃ�A25mm F1.4�łȂ��Ɩ����ł���B��ʊE�[�x�͉��Z�����ł��܂���B
���������ʐςŃt���T�C�Y�Ɠ����̎ʐ^���B���悤�ɃC���[�W�������Ă���Ă���̂ɁA
����͂����ԏ��������܂������ȁB���������ʐς�ISO�͊W�Ȃ����āA�����Ō����Ă邶��Ȃ��ł����BISO���x�ƃs�N�Z�����x�A�Z���T�[�ʐς������Ƃ킯�čl���܂��傤�B
��G�c�ɂ����āA
���ۂ̏o�� /�s�N�Z��������ʁ�ISO���x
�ł���ˁB�܂���
���ۂ̏o�́�ISO���xx�s�N�Z���������
�Ƃ�������̂́A���w���ł��킩��B�܂�f�W�^���̏ꍇ�AISO���x�͂����̑������Ȃ�ł���B������ISO�グ��ƃm�C�Y���ӂ���B�����ĕ����I�Ƀs�N�Z������o��m�C�Y�̗ʂ͌��̋����Ɋւ�炸��肾����B�͂��͂��A�����܂ł݂�Ȃ����Ƃ��Ă��Ă邩�Ȃ��H
�ŁA�������ʂ���S�^�R�s�N�Z�����t���T�C�Y�̃s�N�Z���Ɠ����o�͂��o�����߂ɁA���������ǂꂮ�炢�������Ă�̂����Ă����̂̓��[�J�[�����킩��Ȃ��B�������Z���T�[�ɂ���ăs�N�Z���̃m�C�Y���x���͈Ⴄ�B�ŁA�݂�ȃm�C�Y�e�X�g����Ă��Ȃ��H����ł����Ƃ킩���Ă�l�Ԃ�DPREVIEW�Ƃ����āA��������GH1��ISO400�̃m�C�Y���x����5D2��ISOXX00���炢���ȁA�Ƃ��������ɂȂ��Ă�B�ł��m�C�Y���x����Ⴍ�����邽�߂ɁA���[�J�[�����낢��Ƒ��Ȏ���g���āA�f�W�^�������Ńm�C�Y���ڗ����Ȃ��悤�ɂ��Ă邩��A�e�X�g�������Ƃ킩��Ȃ����Ƃ��������ǂˁB�ł��A���ۂɎʐ^���B��f�W�^�������̕���p�͂��Ȃ炸�o�邩�猩��l������킩��B
�ŁA���̌�������t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y��蓯��ISO�ł̓m�C�Y�������B�Ă���������ł����������Ă邯�ǁB�ł��p�i�͂��܂�����Ă�Ƃ͎v����B�f�W�^�������Z�p�͌��\��������Ȃ��ł��傤���ˁB
���t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y��4����1�����Z���T�[�ʐς��Ȃ��̂ʼn掿������
���̂Ƃ���B�����I�ɖ������B�٘_������悤�����ǁi��j
���ǁA�����Y�A�s�N�Z���A�Z���T�[�ʐς������Ⴒ����ɂ��Ȃ��ł킯�čl����A���イ���Ƃł���ˁB
�����ԍ��F10184316
![]() 5�_
5�_
�t���T�C�Y50mm���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��t����Ɖ�p��25mm�ɂȂ�Ƃ������
���̂��ꎄ�ł��B������ƕ֗��ȍl���Ƃ͎v���Ă���܂������A�����l����͈̂ꐶ������߂Ă݂悤�Ƃ������܂��B
�����ԍ��F10184380
![]() 0�_
0�_
�t���T�C�Y50mm���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��t����Ɖ�p��100mm�̊ԈႢ�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���̂ł����B���ӋC�Ȃ悤�Ő\����܂���B
�����ԍ��F10184400
![]() 0�_
0�_
�t���T�C�Y50mm���t�H�[�T�[�Y�ɂ���ƁA�œ_������100mm�A��p��24�x�ɂȂ�܂��E�E�E�ł����?
(�t���T�C�Y100mm�̃����Y���t���T�C�Y�{�f�B�ɂ����Ƃ��Ɠ�����p)
�����ԍ��F10184517
![]() 0�_
0�_
�����ł���ˁB������������͂��������āA��p�Əœ_�����������ԈႦ�Ă�̂��Ƃ��v���Ă���̂ł����B
�����ԍ��F10184541
![]() 0�_
0�_
������������
���낢��Ƃ��w�E���������܂������A���Ȃ����ȑO���X�������e�Ɩ������Ă܂���B
----�ȉ����p
���������t���T�C�Y50mm���t�H�[�T�[�Y�Ɏ��t����Ɖ�p��25mm�ɂȂ�Ƃ�����������ɑ����悤�����ǁA50mm�͂ǂ�ȃJ�����Ɏ��t���Ă� 50mm�Ȃ�ł���B��p�͕ς��Ȃ��B�N���b�v�t�@�N�^�[���ς�邾���Ȃ�ō������Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�łȂ��Ƃ����ƌv�Z�ł��Ȃ��ł��傤�B������킩��Ȃ����݂�Ȕn���Ȃ��Ƃ����X�ƌ����o����Ȃ����Ǝv����ł����ǁB
----���p�I���
�ς��Ȃ��̂͏œ_�����ł��B����͂ǂ�ȃJ�����ɕt���Ă��ς��Ȃ��B
�ς��̂́A�C���[�W�T�[�N���ŁA�t�H�[�T�[�Y�̃C���[�W�T�[�N���̓t���T�C�Y�̖��B
�]���āA��p�������ɂȂ�B
�t���T�C�Y�p�̏œ_����50mm�̃����Y�̉�p�ƁA�t�H�[�T�[�Y�p�̏œ_����25mm�̃����Y�̉�p�͂قړ���ł��B�v�Z���@�̓O�O�b�Ă��������Ƃ��āA�ǂ������46.8�x�ł��B
���������O�̃��X�ň��p�����Ă�������̂ɁA�����g�Ŕے�Ȃ���Ƃ́A�������Ȃ��̂ł��傤���H
�t���T�C�Y�{50mm F2.8 (10m)= �t�H�[�T�[�Y+50mm F1.4 (20m)= �t�H�[�T�[�Y+25mm F1.4(10m)
��L�̓��X[10181375]�Ŗ�����������̏������݂ł���B
���ƁA����F�l�Ƃ��A���ZF�l�͂����ꕔ�̕��X�̊Ԃł̂ݒʗp���鑢��ł����A�u35mm������p�v�͈�ʓI�Ɏg�p����Ă���܂��̂ŁA�������炸���������������B
ISO���x�ɂ��Ă͎��̏��������܂��������Ɣ��Ȃ��Ă��܂��B������������̕\�L�����ɕ�����₷���̂ŗ��p�����Ă���������A
�@���ۂ̏o�́�ISO���xx�P�ʖʐϓ�����̃Z���T�[�������
�Ɨ������Ă���܂��B
�u�P�ʖʐϓ�����v���u�s�N�Z���v�������T�O�ł��ˁB
�����ԍ��F10184645
![]() 2�_
2�_
��ʊE�[�x�ɂ��Ă͖�����������̂��������ʂ�B
�t���T�C�Y��菬���ȃZ���T�[�ŁA�t���T�C�Y�Ɠ�����ʊE�[�x�悤�Ƃ���ƁA�t���T�C�Y�Ɠ����x�̑傫�ȃ����Y���K�v�ƂȂ��Ă��܂��܂��B
���^���Ɏ����������t�H�[�T�[�Y�₻��ȉ��̃R���f�W�ł́A�^����ɂ�����߂���Ȃ��t�@�N�^�[�ł��B
�����ԍ��F10184760
![]() 0�_
0�_
�����i���p���������j
��ł̃��X�A�u��ʊE�[�x��v�Ƃ͂�����ƌ���������܂��ˁB
�t���T�C�Y�Ɠ�����ʊE�[�x�Ɠǂݕς��Ă���������K���ł��B
�߉ނɐ��@��������܂��A�����Y�̗L�����a���������Ȃ�ƁA��ʊE�[�x�͐[���Ȃ�܂��B
�����ԍ��F10185052
![]() 0�_
0�_
�� �u�P�ʖʐϓ�����v���u�s�N�Z���v�������T�O�ł��ˁB
�i�P�j
����1200����f�ł��A4/3��35�~�����̉�f�T�C�Y�͈Ⴂ�܂����A
�P�ʖʐρA�ꕽ���~���Ƃ��́A�ǂ̃t�H�[�}�b�g�ł��ꕽ���~���ł��B
�i�Q�j
�����t�H�[�}�b�g�̏ꍇ�A1200����f���낤���A4800����f���낤���A
��f�Ή�f�̔�r�͈Ⴂ�܂����A�P�ʖʐϑΒP�ʖʐς̔�r�͑����ł��B
�Ⴄ��f�Ԃ̊��Z���ł��܂����A����̓J�L�R[10177214]���Q�Ƃ��Ă��������B
�܂��A�����t�H�[�}�b�g��1200����f�̉�fSNR�� �� 256�̏ꍇ�A
4800����f�̉�f�T�C�Y�͂���1/4��������܂���A�ʐϔ����̏ꍇ�m�C�Y����2�{�A
�܂������ł�����m�C�Y���{�ɂȂ�܂��̂ŁASNR �� 128�ɂȂ�܂��B�܂�
1200����f�ŁA��fSNR �� 256
4800����f�ŁA��fSNR �� 128�ł����A�Z���T�[�S�̂̕i�����l����ꍇ�A
1200����f�̃Z���T�[�S�̉掿�́A�i��1200�j×256 �� 8868�A
4800����f�̃Z���T�[�S�̉掿�́A�i��4800�j×128 �� 8868�A�S�������ɂȂ�܂��B
�i���Z�̐����̓J�L�R[10177214]���Q�Ɓj
�܂��ʑS�́A���f��4/3�@�ƈ��f��35�~�����@���r���ėǂ��ł��B����͑��z�ŁA
��Ŋ����̉�f�ɕ����邩�A����͎��R�ɂ���č\���܂���B
�ł��̂ŁA�Z���T�[�S�̖̂ʐς��������ėǂ��̂ł��B
�i�R�j
��̐����ł́A�ʐς�1/4�Ə���������A�m�C�Y���{�ɂȂ��Ďd���Ȃ��̂ł����A
�ʔ����̂́A����́g���R�h�ɂ��A�i��l�ɂ���ʊE�[�x��A��܂Ȃǂ̕ω���
�҂������v���܂��B
4/3�@�Ɏ����l�̑��ɁA��{�̑����œ_�����A��{�̑���F�l�ƁA��i��������ISO���x������
�����āA�l�ɓn���Ďʐ^���B�点����A�t�@�C���_�[�Ƃ��͂�͂��a��������܂����A
����ȊO�́A35�~�������ݒ�ŎB�����ʐ^�́A��a���Ȃ��{����35�~���J�����ŎB�����ʐ^��
�ׂ����`�F�b�N���Ă���ʂł��Ȃ����̂ɂȂ�܂��B����͑���F�l�̖��͂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10185628
![]() 2�_
2�_
�����◝�������������Ԉ���Ă��邩�͎����Œ��ׂ��܂��B
���łɎ������ʂ������Ă���������܂��B
���t���ς���Ă��܂��܂����B
�݂Ȃ���A���U���܂��H
�����ԍ��F10185773
![]() 2�_
2�_
�� ���łɎ������ʂ������Ă���������܂��B
�ǂ�ł����H
��a��������Ƌ�l�����܂����A�S����a�����Ȃ��A�≖�̐̂���i�ŏ��̒�������j
���̃f�W���R���f�W�܂ŁA�S�Čo���ɂ҂����肷��̂�����F�l�̗ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10185822
![]() 0�_
0�_
[10182896] �̎��̏������݁B
>�E��f���𑝂₷�̂́u���Z�œ_�����v��L���̂Ɠ����i���������ZF�l�͑傫���Ȃ�j�B
����̒����ƌ������⑫�����B
�܂��J�����̏ꍇ��
�E�u�œ_�����v�́u���̑傫���v�Ɓu��p�v�̓�����߂�p�����[�^�[�ł���B
�Ƃ������ƁB[10182896] �̐����ł́u��p�v�̎��_�������Ă��܂��B
�iTranquility����A�ȑO���Ɂu�œ_�����Ƃ́H�v�Ɛu�˂��Ă��܂����ˁB�����͂���ł��j�B
�u�B���O�v�����Y���ɂ����銷�Z�œ_�����̒�`�́i�O�X���̎��̏������݂����p���āj
>�t���T�C�Y���Z�œ_�����̒�`�́A
>�u��p�s�ς̂܂܁g���̑傫���h���t���T�C�Y�Ɠ������Ȃ�悤�Ɋg�k�����Ƃ��̉��z�I�ȏœ_�����v
�ł悢�ł��傤�B�u���̑傫���v�Ɓu��p�v�������Ă��܂��B
�u��f�������Z�œ_�����̗v�f�ɉ�����v�́u�B�����v�̔�ʑ̑��ɂ��Ăł��B
���łɏq�ׂ��悤�Ɂu��f���̊�������v�̂ŁA�u�t���T�C�Y���Z�v�Ȃǂ����u���t�H�[�}�b�g�ł̊��Z�v�̕����֗���������܂���B�v����Ɋe������Ɋ��Z��̊�����悢�Ƃ������ƁB��f����p�������Z�œ_�����̒�`�͏����܂��A
�E���̃t�H�[�}�b�g�ɑ��A��f�s�b�`�� 1/n �ɂ��i��f���𑝂₵����j�A��ʖʐρi�S��f���j�� 1/n^2 �Ƀg���~���O�����Ƃ��A�u���Z�œ_���������̃t�H�[�}�b�g�� n�{�ɂȂ����v�Ƃ����i���ZF�l�� n�{�ɂȂ�j�B
�Ƃ���������������܂��B
�u�B����v�̉摜�ɂ��u���Z�œ_�����v����`�ł��邩�ǂ����͍l���Ă��܂��A����͂��������ł��傤�B
�u���̉�f����葝�₷���Ɓv���g�又���B
�u���̉�f����茸�炷���Ɓv���k�������B
���x���������悤�ɁA�g�又���� S/N��s�ςŔ�ʑ̉𑜓x�i����\�j�s�ρB
�ʐϔ�i��f����j1/n �̏k�������� S/N�䂪��n�{�Ɍ���B����������\�� 1/��n�{�ŗB
�g��E�k���������玟�̒藝�i�H�j�����܂��i��������x�������Ă���͂��j�B
�E���̉�f�����k�����邱�ƂŁA����\�� S/N��ɕϊ��ł���B���̋t�A�uS/N���\�ɕϊ����邱�Ɓv�͂ł��Ȃ��B
�����ԍ��F10186280
![]() 0�_
0�_
�Z���JGT-Four-A����
�u�킩��Ȃ����Ȃ��������v��ł���B
���Ȃ����uF�l�ɂ��Ă킩���Ă���v�̂Ȃ�悢�ł��B���������Ȃ���F�l���킩���Ă��Ȃ��B
���̓f�W�J���n�߂� 2003�N���炸�[���Ɓu��f���v�Ɓu�t�H�[�}�b�g�v�ɂ��čl���A��f���ɂ��Ă͎��������Ă��܂����i�R���f�W 200����f���g���Ă������̂̉�f���R���v���b�N�X�A�t�H�[�}�b�g�R���v���b�N�X���������܂��j�B
�F�X�Ȗ@�������͂Ő��ݏo���܂����B
�ł��u�t�H�[�}�b�g�ƃm�C�Y�̊W�v�ɂ��Ă͂ǂ����Ă����_���Ă邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�ł��l���Ă������炱�� ���鐯���߂炳�� �̂��b�����܂��ܖڂɂ��������ňꔭ�ŗ����ł��܂����ˁB
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=9469167/#9488251
��{�I�Ɋ��ZF�l�ɂ��Ă͂��̎��́i���ZF�l�ɂ��Ă͏��߂Ắj���X�Ős���Ă��܂��B
���ZF�l�́AF�l�o����ۂ�
(�ʏƓx) / (�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W��)^2
�Ƃ������Ƃœ��o�ł��܂��B
�����ԍ��F10186320
![]() 0�_
0�_
�Z���JGT-Four-A����
�����l�ł��B
���̒��ɂ͕ς�����l��������B�Ƃ����̂������Ȋ��z�ł��B
���S�҂̕X�Ƃ��l����ƁA�������������������ǂ����Ǝv���܂����A���x�Ƃ������̂�����܂��ˁB
�I�����p�X�̃J�����ƃ����Y�̉掿�͏\���ɗǂ��̂ŁA���������ɏ������މɂ���������ʐ^���B��(�Ƃ��ʂ̎��j�ɍs���܂��B
�ł́A������U�Ƃ������ŁB
�����ԍ��F10186554
![]() 13�_
13�_
��N�O�̐l�ɑ�n�����`���ƌ����Ă��M���Ȃ������
��n�����`�ł͂Ȃ������ؖ��o���܂���ł����B
�t�B�����J�������������
�n�b�Z���u���[�h(�U×�U)�p�����Y���A�_�v�^�[�Ńj�R���ɕt�����ꍇ
�ʂ�͈͂������Ȃ�܂����K���I�o�͕ς��܂���B
�t�B�����Ɠ����œd�C�I�����f�q�̊��x�̓T�C�Y(�ʐ�)�ɖ��W�ł��B
2009/09/13 01:49�@[10144323]
2009/09/19 16:14�@[10178200] olympus�����ǂ����"�d-�o�P�����܂���^^"
�Ŏ������ʂ�������Ă��܂��B�������"���鐯���߂痝�_"��ے肷����̂ł��B
�Ȋw�͑������ł͂���܂���̂Ŗڂ���E���R�̎������ʂ������
���������̂ł��B
�����ԍ��F10187909
![]() 13�_
13�_
�͂炽����
���̃X���̖������I�����悤�ł��B�ł��A���nj��_���o�Ȃ������̂ŁA�܂��ǂ����ŌJ��Ԃ����̂ł��傤�B���̃X�����A�u�킩��Ȃ����܂��B�������v�ƌ����Ȃ������������搶�̋����̏o�Ȏ҂��ǂ�ǂ�ƌ����Ă���悤�ȏ�悵�Ă����̂ŁA���낻��I��鎞���������悤�ł��B
���s�̂�������
�u�킩��Ȃ����Ȃ��������v�̂ł����B����͂ǂ����\����܂���B�����炭�A�����ł��Ă��Ȃ�������R�����邩�Ǝv���܂����A���̕��X���\���Ă��l�т��܂��B����F�l�����Ă��Ȃ��̂�������ł��ˁB�Ȃ�قǁA���ۂ̑��肪�����Ȃ����ł悭�������܂Œf��o������̂ł��ˁB����͂�A���̊�́A�������ꂵ�܂����B
�����ԍ��F10187924
![]() 10�_
10�_
���āA�����̕����炱�̃X���̎������������Ƃ��w�E����Ă��܂��B���������̌ア����c�_���d�˂Ă����s�����낤�Ɗ����܂��̂ŁA���낻�낱�̃X������鎞���ɗ����Ɗ����Ă��܂��B�����ŁA�X����Ƃ��čŌ�ɂ܂Ƃ߂��������Ƃɂ��܂��B
�y�܂Ƃ߁z
�X���b�h���L�т錴���́A��͂�u���Ƃv�̖�肾�Ǝv���܂��B
�s�l�́A�e�l�ߗ��Ŋ��������̂ł��B�������A����͊��Z�Ȃ�Ƃ��ƌ��킸�AT�l�Ƃ��ďq�ׂ��Ă��܂��B���ZF�l�͏]���̂e�l�̍l�����ɐV���ȍl������lj����Ă���̂�����Ⴄ���t�Ō��Ƃ����̂����R���ƃX����Ƃ��Ă͍l���܂��B�܂��AF�l�͒P���ɏœ_���������a�Ŋ��������̂ł����A����o����܂łɂ͋��ܗ�������̏����ł���A�ő�W���p�Ȃǂ��l��������ŒP�������ꂽ���ƂȂ��Ă���悤�ł��B�܂����邳�ɂ��Ă����̔{���Ȃǂ��l�����ē��o�����悤�ł��B�e�l�͒P�Ɏv���t���ŋK�肳�ꂽ�킯�ł��Ȃ��A�l�X�ȍl�@���d�˂�ꂽ��ŁA���������^�������ʒP�������ꂽ�p�����[�^�̂悤�ł��B�܂�A���ʂ̑傫���Ȃǂ��l�����ꂽ��ŁA�œ_�����ƌ��a�̒P�Ȃ�w�I�䗦�ŊJ���݂̂ɔ����W���\�͂Ȃ̂ŁA���̏�����ω����������̂́A����͊���F�l�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�܂��A�ʐ^�̘I�o�ɂ͒P�ʖʐς�����̌��ʂ��I�o�ɉe������Ǝv���̂ł����A���ʂōl���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ̂��͍Ō�܂ŕ�����܂���ł����B�t�H�[�T�[�Y�Ɏ���ė��p���Ȃ����ʂ�ΏۂƂ��āu�Â��v�Ƃ��A�u�掿�������v�Ƃ��ɂȂ��Ă��܂��B�Â������Ƃ��ăt�H�g���̓��͗ʂ̕����������V���b�g�m�C�Y�ʂł���Ƃ����Ƃ���������Ď咣���J��Ԃ�����ł����A�ʏ�̎ʐ^���B�e����ۂɎB���f�q�ɓ���t�H�g���̗ʂ��A�t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�łǂ�قǕς���Ă���̂��Ƃ������Ƃ��^��Ƃ��Ďc���Ă��܂��B�K�Ȍ��ʂ邽�߂ɃV���b�^�[�X�s�[�h��i���ω��������Ԃɂ����ĎB���f�q����������ʂ͈ꏏ�ł́H�H�Ƃ����^�₪����܂��B��������Ɠx�̎��ɂ́A���̍��͔@���ɕ\���ł��傤�B
��͂�A���̂悤�Ȍf���ŋc�_���鎖�ɂ͌��E������̂ł��傤�ˁB���Ƃ����łȂ��A���̖{����}���Ȃǂ��Ȃ���c�_���o����Α��݂ɗ������[�܂����悤�ɂ��v���܂��B
�����ԍ��F10187993
![]() 6�_
6�_
�܂��A����̉ۑ�ɂ��Ă��L�q�����Ē����܂��B
�y����̉ۑ�z
�t�H�[�T�[�Y�̃J���������Ďg���Ă�������ɂ��Ă͉��̉ۑ�������悤�Ɏv���܂��B�B���f�q�̏������̃f�����b�g������ė��p���Ă���̂Ńt���T�C�Y�Ɣ�ׂăn���f������Ƃ������͏��m�̏�ł��傤�B�܂��A�B���f�q�ɔ�ׂď[���߂���قǑ傫�������Y���A�����̕i���Ƃ��ĂƂĂ��D��Ă���ƌ������Ƃ������b�g�Ƃ��Ď�����Ă���̂��Ǝv���܂��B�t�H�[�T�[�Y�̃��[�U�����҂��Ă���͎̂B���f�q�̐i���ł��傤�B����́A�܂����炭���Ԃ�������̂��낤�Ǝv���܂��B���R�A�t���T�C�Y�̎B���f�q���i������Ǝv���܂����A�ŏI�I�ɂ��̓�͂ǂ̂悤�ɕ������Ă����̂��͒N���\�z�ł��܂���B�������A���̊Ԃɂ��ꂼ����[���Ɋy���߂悢���낤�Ǝv���܂��B
����A�I�����p�X�ȊO�̃��[�U�A���̂悤��D300���[�U�ȂǂɂƂ��Ă͂��̖��̓t�H�[�T�[�Y���[�U�����傫���ƌ����܂��BAPS-C�J�����̃��[�U�͍��掿�����߂ăt���T�C�Y�̃����Y�����Ƃ��܂����A���ꂪ���Z�e�l�Ȃ���̂ňÂ����Ƃ����ɂȂ�̂ł���A�����ȃ����Y���Ă��v��������Ȃ��Ȃ�܂��B���[�U�̃����b�g���l����Ƃ����̂ł���A���s�̂���������\�Ƃ���A���Z�e�l�𗝉������悤�Ƃ������X�������ƌ��ʓI�ɓ����ׂ��ł��傤�B�܂�́A
�u��X�̂悤�ȁw�����o���Ȃ����̈����l�����x���ǂ̂悤�Ɍ��炷���v
�ƌ������Ƃɐs����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�K���ɂ��āA���s�̂�������2003�N���炸���ƌ������Ă������ʂ�����悤�Ȃ̂ŁA���������I�����đ�ʂ̎����f�[�^�����Â����_�Ȃǂ����āA�}���Ȃǂ��Ē����Ȃ�����������̂������Ƃ��K���Ǝv���܂��B���̌��ʁA����܂ł̏펯���V���Ƃ��čL��������邱�ƂɂȂ邩�Ǝv���܂��B
�B���f�q�̏�����������ė��p����Ă���I�����p�X�̃��[�U�̃X���őf�l�i�H�j����ɋc�_����̂ł͂Ȃ��A�����Ɖe�����鑼�Ѓ��[�U�̕��X�̖ڂɐG���l�Ȍ`�Œ�Ă���邽�����]�܂����ł��傤�B
���́A�C���^�[�l�b�g������̂ł����g�̐����L�߂�ɂ�����قǔ�p��������Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃ�������Ƃ��ẮA���̉��i.com�̃f�W�^���J�����S�̂̂Ƃ���ŁA�����g�̃X���𗧂Ăċc�_�ɗՂނƂ������Ƃ��ǂ��Ǝv���܂��BWIkipedia�Ȃǂ�����܂����A�����ŐV���Ƃ��āA�f�l������Ƃ܂ŗ�����[�߂�̂ł���ΐ��̒��͂��̕����ɓ����ł��傤�B
���i.COM�ł́A���̂悤�Ȍ`�ŃX�����L�тČ��ǁA�N���Q���҂����Ȃ��Ȃ�X���͂������ڂɂ��܂��B��������ȏケ�̂悤�ȃX���𑝂₳�Ȃ����߂ɂ��A���̐����咣�������X�ŋc�_�̏������āA�c�_���s�������҂𑝂₷���Ƃ��ő�̉ۑ肩�Ǝv���܂��B�w�p�I�ɉ��l�̂���`�ɂ���̂ł���A�_�����M���ǂ��ł��傤�B�_���Ȃǂł́A�펯�I�Ȏ��ł����Ă��c�_���邽�߂̎��Ƀt�H�[�J�X�����邽�߃C���g���_�N�V�����Ō��m�̎������������ꍇ�������ł��B���炭�A����������Ă��Ȃ��̂͌��m�̉ۑ�ł���̂ł͂Ȃ��A�ۑ�ł͂Ȃ����������͖��m�̎����ł��邱�Ƃ������̂͂��ł��B�_���Ƃ������̂�ǂݏ������ꂽ���Ƃ�������Ȃ�悭���킩��̂��ƂƎv���܂��B
�y�ӎ��z
���̃X���̂��A�ŁA���̋c�_�̖{���𗝉����邱�Ƃ��o���܂����B�܂��A���̌��ʁA�������t���T�C�Y�֍s�����ǂ����̌��f�����邱�Ƃ��ł��܂����B���ۂɎg���Č���ƁA�ʏ�̗��p�ɂ�����2�i�Â����Ƃ��痈��掿�̈���������ꂸ�A���݂̃t���T�C�Y�͎������҂قǂł͂Ȃ��������Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�����f�����オ��A���|�I�ȉ𑜓x��������悤�ɂȂ�܂ł͕s�K�v�Ȃ悤�ł��B
����A�ʏ�̗��p�ɂ����Ă̓t�H�[�T�[�Y���Ȃ��Ȃ��̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ƃ�������������܂����B�����A�t�H�[�T�[�Y���g���Ă��郆�[�U����́A�B���f�q�̃f�����b�g�����邱�Ƃ��[���ɗ���������ŁA����ł�����Ă��g���Ă���Ƃ����Ƃ���ɃX�y�b�N�Ɍ���Ă��Ȃ��������͂�����̂��낤�Ƃ������Ƃ������܂����B�������炭�A���̃V�X�e�����g���Ȃ���\�Z�߂āA���̋@��iD700X?�@or E-3X)���o�ė����Ƃ��ɂǂ����邩�l���Č��悤�Ǝv���܂��B
�Ō�ɁA���̃X���ŋc�_���Ē������F�l�Ɋ��ӂ̌��t���q�ׂ����Ē����āA�I���ɂ����Ē����܂��B
�ǂ����L���������܂����B
�����ԍ��F10188001
![]() 17�_
17�_
�ʏ��ɶ���\��ł�����ڎ�l���̕��X�ɗ��ė~���������Ȃ�܂����
��pCCD��m���Ă���҂��炷��A���鐯���̎咣�́u�펯�v�ł����āA�u�ۑ�v�ł��A�܂��Ă�u���m�̎����v�ł��낤�͂�������܂���B
�@���鐯���̎咣�́A�v�Z���ɂ���A�l���v�Z�ɁA�܂�Ɂオ������x�̂��̂ł��B
�@������A�u�ؖ�����v �Ƃ������l������̂��A�悭������܂���B
�@�v�Z�́A�u���v�́A�E�ƍ��������Ă܂���ˁA�Ƃ��������̘b�Ȃ̂ł���w
�@���̃J�L�R���������Ǝv���܂��B
�@������Ȃ���A������폜�\�����܂��B
�@���̏�ɂQ�s�����J�L�R���������폜�\�����܂��B
�@���̃��X�́A�X���傳��́u���сv�̉��ɁA�u�������A�ʏ��ɏ������ށv �Ə������̂ŁA�������������������ł��B
�@���̍l���́A���炭���Ԃ������āA�ʏ���UP���邱�Ƃɂ��܂��B
�@�Â��� �u�����v ����荇�������v���܂��̂ŁA���̕��������X���呤�̕��X�ɂ́A�Q�����������������������A���肢�\���グ�܂��B
�����ԍ��F10215417
![]() 0�_
0�_
�s�����w����@����ɂ��́B�X���y���݂ɂ��Ă��܂��B
������̃X���ɂ͗�₩�����x�ɏ����������Ȃ̂ł����A
���鐯���߂炳��⋞�s�̂�������@�̂���������Ă��邱�Ƃ�
�F�X�ȃJ�L�R�����āu�������悤�Ƃ��Ă���v�҂ł��B
�Z���JGT-Four-A����
10188001�ȍ~�̃J�L�R���폜����Ă���悤�Ȃ̂ł���
����̓Z���JGT-Four-A���폜�˗����o���Ă���̂ł����H
�X����l���I��肾�Ƃ����Ă���̂ɏ����Ă��邱�Ƃ����R�Ȃ̂ł����ˁH
�����ԍ��F10215467
![]() 0�_
0�_
��R�폜����܂����ˁB�X���傳��͏オ��ƌ����܂������A���ꂪ���̐l�̋c�_�����_����؋֎~�����Ƃ̉��߂ł��傤���B
�펯���{�̂���l�Ԃł�����A���̂悤�ȍ폜�˗��͂��Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10215525
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��̂���������Ă��邱�Ƃ�F�X�ȃX����
�ǂ�ł݂܂����B
�܂��܂����S�ɂ͗������Ă��Ȃ��̂ł�����
�����I�ɂ͂����������Ƃ����������̂��ȁH
�Ǝv�����Ƃ�����܂��B
�X���傳�폜�˗����o���Ă���̂��Ƃ���ƁE�E�E�E
����͂ǂ��Ȃ̂��ȁE�E�Ǝv���ď���������ł��B
�����ȏ������݂⌙���点�̗ނł��Ȃ������悤�Ɏv���܂��̂ŁB
�����ԍ��F10215555
![]() 0�_
0�_
���̃X���ł͋��ʔF���ɓ�������ł����ǂˁB
�u�����Y���̃N�I���e�B�i�����A����\�j�͌��a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v
����Ɓu���Z�œ_�����v�Ƃ̊T�O�����킹��Γ����͏o���������B
�Ȃ̂ɁA�Ȃ����S�Ă��Ȃ������ɂ��Č��̏ꏊ�ɖ߂��ł���ˁA�t�H�[�T�[�Y�̐l�X�́B
�u����̌������Ƃ͗��������B���ǔF�߂��Ȃ��v�����Ȃ�Ƙb�������ł͂���܂���B
�Ȃ��A�u���Z�v�Ƃ������{�ꂪ�����ł��Ȃ��l�������̂ŁA���������������Ă����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041113/SortID=10159202/#10213843
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041113/SortID=10159202/#10213867
�ȂO�X���ł����������悤�Șb���������̂ŁA���͓��{��̖��Ȃ̂��ȁA�ƁB
�����ԍ��F10215568
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������@����ɂ��́B
�l�͊�{�I�ɂ́A���鐯���߂炳��⋞�s�̂����������Ă��邱�Ƃ�
����������Ȃ����H�Ǝv���Ă��܂��B�i�܂������ł��Ă��Ȃ�����j
���Nj����������Ă��������̃J�L�R��ǂނƕ����I�ɂ킩�镔��������܂��B
�����ԍ��F10215603
![]() 0�_
0�_
����E-1�̍w����^���Ɍ����������Ƃ�����܂����AF�l�����Z���Ȃ��ƈ�a���������܂��B
���͕��������̂ŊȒP�ł����A���̈�a��������Ă�܂܁A���N�������ł��܂���ł����B
D3�̔��������������ɂ�����x�l���悤�Ƃ��܂����B���̐����̈ꕔ�͂��̎��̐��ʂł��B
�������A��͂蒼���ł��Y��ɐ����ł��܂���ł����B
���̎��������m���Ǝv���܂����A�ꌩ�Œ��ꒃ�ȊG���A�����������ς��܂��ƁA�ˑR�ς���
���邢�G�������Ă��Ċ��������o��������܂��H����F�l��Z�߂ł������ɂ���ȏ゠��܂����B
���Ȃ݂ɁA���̗��̎����ł������ɖ��邭�����邩�ƌ����܂��ƁA���̎��͍��E�̖ڂ�
�����Ɠx�Ō������m���Ă܂����A���W�ȊG�Ǝv���āA��ɍ������Ȃ�����ł��B
�������A�������̂����Ă�ƕ�����܂��Ɓi���̏ꍇ�x���ꂽ�̂ł����j�A�l�Ԃ͗��Ⴉ��
�������G���������ė��̓I�ȃC���[�W�����܂��B
����̏Ɠx�����������ꂼ��ς�܂��A�ʐς��{�ɂȂ�܂��̂ŁA���������Â̕ω���
��i�ł��낤�Ǝv���܂��i�ڂ��x���ꂽ���ɕ����肭�@�\�����A���邳�̍������̂܂�
�������Ǝv���܂��j�B
�����h�[���܂ł͂����܂��A6���12�������̖��Â̍��������u�Ԃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10215832
![]() 1�_
1�_
�� ���͓��{��̖��Ȃ̂��ȁA�ƁB
������Ƒ�U���ł����A���̖{�̌�̖��ł͂Ȃ��A���̖{�̐S�̖�肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10215938
![]() 0�_
0�_
�d�����}�������āA���炭�A�N�Z�X���Ă��܂���ł����B
�����́A�폜�˗����Ȃɂ����Ă��Ȃ��̂ł����A�Ȃ��폜�����̂ł��傤�B
�m���ɁA�܂Ƃ߂͏����܂������A�X���傪�錾����Ǝ����I�ɍ폜�����d�g�݂Ȃ̂ł��傤���B
����Ƃ��A�K��Ɉᔽ���鏑�����݂Ƃ��������̂ł��傤���H
�������D�ɗ����Ȃ��̂ł����E�E�B
�����ԍ��F10216354
![]() 0�_
0�_
�Z���JGT-Four-A����
�����ł������B
�����^���Đ\����Ȃ������Ǝv���܂��B
�X���傪�폜�ł���@�\������̂��Ǝv���Ē��ׂĂ݂�����
����͂ł��Ȃ�������������ŁA�폜�˗��������̂��Ǝv���Ă��܂����B
�����ԍ��F10216453
![]() 0�_
0�_
���ɋ����[���X���ł��B
�ǂ�ł���i���z�h�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10218682
![]() 0�_
0�_
�Z���JGT-Four-A����
���݂܂���A���ǂ܂��������Ⴂ�܂��B^^;
�s�����w����
�ʐς��������Z���T�[�̃m�C�Y���������Ƃ��A�ʐς̏������Z���T�[���ƃ{�P���������Ȃ邱�Ƃ��_�_�ł͖����Ǝv���܂��B
�P�ɁA�u���邳�Ɖ�f���������Ȃ�A�Z���T�[�������������m�C�Y�������v�Ƃ����咣�Ȃ�A�N�ł��[�����o���܂����A�u��p��F�l�������Ȃ�A�Z���T�[�T�C�Y�������������Â��v�Ƃ����ƁA�������������܂��B
�܂��A�u��p��F�l�������Ȃ�Z���T�[�T�C�Y���������J�����͑傫�ȃJ���������{�P���������v�Ƃ����咣�Ȃ�A�N�ł��[�����o���܂����A�u��p��F�l�������Ȃ�A�Z���T�[�T�C�Y���������J�����̕����Â��v�Ǝ咣�����ƁA�������������܂��B
�X�����L�т闝�R�́A���炩�Ɂu�Â��v�Ƃ������t�̎g�����̖��ł��B
�����ԍ��F10219885
![]() 4�_
4�_
�����͂炽����ɗ���ł��܂��̂ŁA�\����Ȃ��̂����B
�u��p��F�l�������Ȃ�A�Z���T�[�T�C�Y�������������Â��v�Ƃ����Ƃ��ɁA���ꂪ�����ʂ�u�Â��v���Ӗ�����̂��Ɨ�������̂��A���ZF�l�̍l�����̊̂�����A������O���킯�ɂ͂����Ȃ���B
���Ȃ킿�A�u�ʐ^�̉掿�i�𑜓x�A�m�C�Y�ʁj�́A���ʂ���鑍���ʂ����߂�v�Ƃ����l����������B
F�l�ƃV���b�^�[�X�s�[�h�̑g�ݍ��킹�Ɋ�Â����Ái������u�I�o�v�j���܂���`�ŁA����ɖ{���I�Ȃ�����Ƃ��Ă̖��Ái���ʖʐςɋN���j�����݂���A�Ƃ����l����������B
���t�̖��Ƃ����ʂōl����A�u���邢�v�ɏ�Ƀv���X�̉��l���A�u�Â��v�ɏ�Ƀ}�C�i�X�̉��l������U�銴�o���A���Z�b�g���Ă݂�̂�����Ǝv���B
�����ԍ��F10220782
![]() 0�_
0�_
�� �X�����L�т闝�R�́A���炩�Ɂu�Â��v�Ƃ������t�̎g�����̖��ł��B
�Â��ɑ��Ă̗������Ԉ������A�������F����������ǂ��ŁA���͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���ꎫ�����Ԉ�����Ƌ�����A4/3��p�́gE-��h������Ă����v�ł��傤�B
�g�Â��h�̑��Ɂg�W�����\���Ⴂ�h�Ƃ��������͗ǂ��Ǝv���܂��B
4/3�ł͒N�ł��ʐ^���B���Ĕ�r������A�������Ȃ��ƊȒP�Ɋm�F�ł���Ǝv���܂����A
����F�l�́A4/3�����̂��߂ł͂���܂���B
����F�l��˂��~�߂�̂ɁA��ɃL���m���ƃj�R���̈��ƁA�\�j�[�ƃp�i�̃R���f�W��
��r���ĕ�����܂����B�S�Ă��Y��Ɉ꒼���i��Ȑ��j��ɕ��т܂��B����F�l�̐��ł��B
���̌����͋≖�t�B�����ƑS�������A�Z���T�[�̒P�ʖʐς̓d�C���\�͖w�Ǔ����ł��B
�j�R��D3�̃Z���T�[�̒P�ʖʐς̐��\�́A�p�i�̃R���f�WFX100�Ƒ債�ĕς�܂���B
�ς����̂͑��ʐςł��B�P�ʖʐς̓d�C���\�������̏ꍇ�A�S�̂̐��\���W���ʐϔ�ŕς�܂��B
�����ԍ��F10221089
![]() 0�_
0�_
http://kakaku.com/item/00490711093/ �iD3�A2007-11�����j
http://kakaku.com/item/00501911147/ �iFX100�A2007-06�����A�ʐϔ�Ŗ�4.4�i�̍��j
FX100�����Y�́A6.0-21.4mm f/2.8-5.6�ł����A�Ίp��/�ʐϔ�Ŋ��Z���܂��ƁA
28-100mm f/13-26�ɂȂ�܂��B����͑����œ_�����i��p�j�Ƒ���F�l�i���a�j�ł��B
�܂�AD3��28�~���̃����Y��t���āAf/13�̐ݒ�A�����V���b�^�[�Ŏʐ^���B������A
FX100�Ƌ�ʂ��Ȃ��A��������ʐ^�ɂȂ�܂��BISO�l�͋C�ɂ��Ȃ��ėǂ��ł��i�����j�B
�������A��b���x�̐����ŁAFX100�͂��鑬�x���x���V���b�^�[����܂���B
�����V���b�^�[��܂���̂ŁAD3�����̑��x���x���V���b�^�[���g�������r�ł��܂���B
�Ⴄ�p�x����AFX100��ISO100�ł́AD3��ISO2100�����ȉ掿�������܂����i4.4�i�̍��j�A
�����Y��ȐÕ��ʐ^���B�邽�߁AD3��ISO200���4.4�i�Ⴂ���x�i�܂�ISO9.5�j���K�v�ɂȂ�܂��B
�ȏ�A4/3���A�Â����g�킸�앶���Ă݂܂����B
�����ԍ��F10221183
![]() 0�_
0�_
�@���ݎc���Ă���E�E�E
2009/09/26 11:59�@[10215417]
�E�E�E��艺����A���̏�܂ł̊Ԃ��A�ƂĂ��ǂ��܂Ƃ܂��Ă��܂���w
�@���̊Ԃ��Q�Ƃ��邾���ŁA������l�ɂ͏\���������Ă��炦��̂ł͂Ǝv���܂��B
�@���������āAendokatsu���� �ւ̓������A����ōς�ł��܂������ł��B
�@���� �͂炽���� �i10219885�@�u�Â��v�Ƃ������t�̎g�����̖��j �� �{�X�g�[�NT-233���� �i10220782�@�u�Â��v�ɏ�Ƀ}�C�i�X�̉��l������U�銴�o���A���Z�b�g���Ă݂�̂���j �̂��Ƃ�́A���w�c�̎咣�̂܂Ƃ߂ɂȂ��Ă��܂��ˁB�@����͕ۑ����m�ł�w
�@�͂炽���� �Ȃǂ̈ꕔ�̕��́A����藝�����Ă�����悤�ŁA���������悤�ȕ��͂���Ӗ����Ȃ��Ǝv���̂ł��B�@��`���Ⴄ�����ƌ������Ƃ�w
�@�t�H�[�T�[�Y�ł́A���̃J�L�R��l�����́A���s�̂������� �����Ă��E�E�E��
�w���̂��߂�4/3�t�H�[�}�b�g���x�̑����E�E�E�ƌ����X���b�h�ɂ������Ă��Ȃ��n�Y�ł��B
�@���ė~�����Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ă���̂ŁA�咣�������̂��A���t�F�A�Ȃ̂ŁA���ɏ����܂���B�@����������肽���ł��B
�@������肽���̂́A�u���̋c�_�ɕt���Ă����̂ɂ��������v �Ƃ����l�����ւ́A�l�����̒ł��B�@�݂Ȃ���̎咣�̕������Ƃ́A�����Ⴄ��������܂���B
�����ԍ��F10221462
![]() 1�_
1�_
�s�����w���� ����ɂ��́B
���ЃX���b�h�͗��ĂĂ���������
���������Ǝv���܂��B
�u���鐯���߂炳��v��u���s�̂�������v�̂���������Ă��鎖��
�u�Ԉ���Ă��Ȃ����v�Ǝv������A�u���Ȃ����ԈႢ����Ȃ��̂����v
�Ǝv����������낤�낵�Ă���܂��B
�����}�C�N���t�H�[�T�[�Y�������Ă���̂ł���
�ǂ����Ă��t�H�[�T�[�Y�I�[�i�[�̊�����l����ƁA���܂�ʔ����b�ł�
�Ȃ��̂ł����A�����炭�t�H�[�T�[�Y�Ƃ����K�i�𐧒肷��ɓ�����
���x������e�͈Ⴄ�ɂ���A���̂悤�ȋc�_�͏d�˂�ꂽ�̂��Ǝv���܂��B
�ł�����q���ɂ��͑傰���ɂ��Ă��A�N�ɂł��킩��悤��
���������Ă����X���Ő������������Ă݂�����ł��B
�I�����p�X�i�p�i�\�j�b�N�j����Ȃ��Ƃ���ɏ������ق��������̂����m��܂���ˁB
�S�R�W�Ȃ��ł����ǁA���i�R���̃f�W�C�`�����x�����L���O���ăI�����p�X�̃J������
���������N�C�����Ă��܂��ˁB�@�@�@
���r���[�̃R�����g�̒��Ƀt�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`�E���l��
�Ïk����Ă���̂�������܂���B
�����ԍ��F10221801
![]() 0�_
0�_
�ȂA�C���V���^�C���́u���ΐ����_�v�݂����Ŋy�����ł��ˁB
�ŋߓ����g�����Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂����B
�����Ȃ�u���������_�v�ł��傤���E�E�E
�����ԍ��F10221815
![]() 0�_
0�_
��̓I�Ȏd�g�݂͕����̊p�x���牽�x���ڂ������������Ǝv���܂����A
�J�����͎ʐ^���B�铹��ł��̂ŁA�����܂ŎB��ꂽ�ʐ^�Ŕ��f���錋�ʘ_�ł��B
�d�g�݂𗝉��ł��Ȃ����A���ʂƂ��Ă͑S�ē�i�̍��ɂȂ����킯�ł����A
���ʂ����āAF�l�������Ƃ��������Ă��Ӗ�������܂���B
���ʂ͓�i�̍��ł����A����ɑ��Ă̔��f�̓��[�U�[�����ꂼ�ꂵ�܂��B
���͔�ʊE�[�x�s���ɔY�܂���鎞���ǂ�����܂����i�掿�ƃg���[�h�I�t�ł��܂����j
�Y��ɎB�ꂽ�ʐ^�ɂ킴�ƃm�C�Y�����ĕҏW����̂�����܂���B
�����ԍ��F10221874
![]() 0�_
0�_
���u���鐯���߂炳��v��u���s�̂�������v�̂���������Ă��鎖��
�u�Ԉ���Ă��Ȃ����v�Ǝv������A�u���Ȃ����ԈႢ����Ȃ��̂����v
�Ǝv����������낤�낵�Ă���܂��B
���₢��ނ�͕ʂɂ����������Ƃ������Ă͂��܂����B
�ȒP�Ȏ��������ɘb���Ă��邾���Ŏʐ^�p���Ђ˂���Ęb���Ă��邾���ł�����B
������O�̘b���I�ɋ������邩��A
�܂�Ő��I�̑唭���݂����Ȕn���b�ɂȂ�I
�≖�̑唻�ƃ��C�J�����ׂē��������b���ł��܂��ˁH
�ł��t�B��������������Y�ƃt�B�����̐��\�������菬�����t�H�[�}�b�g�̃J���������y�����킯����Ȃ��ł����I
�@
�����ƁA�n�����x�x�����I���Č����Ă����l������ɋ��Ȃ������̂ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10221934
![]() 8�_
8�_
�� ���r���[�̃R�����g�̒��Ƀt�H�[�T�[�Y�̑��݈Ӌ`�E���l��
�� �Ïk����Ă���̂�������܂���B
�������ʘ_�ł����A4/3�̒����̓{�f�B����������������邱�Ƃł��B
�Z���͓������a�̃����Y�́A35�~�����̂��̂���i�傫���d���Ȃ�܂��B
����͑���a�ł��Ȃ������̈�ŁA�o�ϐ����������ቺ���錴���ł�����܂��B
���̌����̌����A�܂�4/3�V�X�e���̖��_�́A�펯����v�ɂ���Ǝv���܂��B
�f�W�^���Ή��̂��߂̔��{�Ă��ȑ�́A�P�Ɋ��Ⴂ�ł����̂��A�����̌����̌����ł��B
�E�E�E
�������Z���T�[���̂́A����قǂ̃f�����b�g���Ȃ��Ɛ��������̂��A����F�l�Ȃ̂ł����B
�����ԍ��F10221959
![]() 0�_
0�_
endokatsu����
���̃����N�C�����Ă���I�����p�X�J�����̍w���w���l���Ă݂Ă��������B
�f�W�^�����t�̓���@�Ȃ̂ŏ��S�҂������ł��B
�R���f�W�ɔ�ׂ�Ζ����x�͍����ł��傤����]���͓��R�オ��܂����A
����Ă���ƐF�X�Ƃ킩���Ă���̂ő��А��i�ɔ��������郆�[�U�[��������ł��B
�w���������Ǝ�������̕]���͈Ⴂ�܂����ˁB
�I�����i���ƂĂ��ǂ���Γ���@���w����A
�����@��t���b�O�V�b�v�ɔ���������Ǝv����ł����قƂ�ǔ���Ă��܂���B
�����ԍ��F10222062
![]() 0�_
0�_
���[�b�A�����ɂ������Ă��܂����ˁI
E�[3�̔ŐK�����Ƃ��čs���܂���ł����H
�����ԍ��F10222129
![]() 4�_
4�_
�{�X�g�[�NT-233����
�����ے���肵�ĐS�ꂵ����ł���
���āA�u�Â��v�̃C���[�W���A�ƌ�����ƁA����ς�Ⴄ�ł��傤�B
���̃X���i�Ƃ������A��A�̃X���j�ɂ͕����́u���邳�v���o�Ă��܂��B�����ƈȉ��̒ʂ�i��肱�ڂ������邩���j
�@ �Ɠx�i�傫���������邢�A�P�ʂ̓��N�X�j
�A F�l�i�������������邢�B�P�ʂ͖����j
�B �Z���T�[�A�܂��̓t�B�����������ʁi�傫���������邢�B�P�ʂ̓��[�����b���G�l���M�[�Ƃ��đ�����Ȃ�W���[�����H�j
�C ���a�i�傫���������邢�B�P�ʂ̓��[�g�������ǁA���ʂ�mm�܂���cm�j
�D ���ZF�l�i�������������邢�B�P�ʂ͖����j
�E �����i�傫���������邢�B�P�ʂ̓��[�����j
�F ��ʑ̂�`�ʂ���̂Ɏg�p����Ă�����ʁi�����������邢�B�P�ʂ�...?�j
�A�𖾂邳�Ƃ��鍪���͇@�ł��̂ŁA�@�ƇA�̍����͂���قǖ��������N���������ł��傤�B�i����ł��u�Ɠx���傫�������{�P��v�Ɗ��Ⴂ����l�����Ȃ��Ƃ�����܂��j
�B�ȉ����ʐ^�̕����Łu���邢�v�Ƃ���p�@�͑����ł͌������Ƃ������̂ŁA�Ȃ��Ȃ��̃I���W�i���e�B���Ɗ��S���܂����A������Ƒ����̈Ӗ��ɓ����P����g�������ł��B
���Ƃ��A�t�H�[�T�[�Y 50mm F2.0�͊��ZF4.0�Ƃ��āA�t���T�C�Y��100mm F2.8�Ɣ�ׂ�ƁA
�u�t�H�[�T�[�Y�̕������邭�i�@�A�j�t���T�C�Y�̕������邢�i�B�C�D�j�v
�ƂȂ�܂��B�u�Ȃ��Ȃ��v�̂悤�ŁA�ǂ�ł��č������Ȃ������s�v�c�ł��B�i�E�F�͊����j
�ʐ^���B�镶���ł͒��N�i�����厖�ł��j�@�܂��͇A���u���邳�v�Ƃ��Ďg���Ă��܂��̂ŁA����ƈقȂ�Ӗ��ł́u���邳�v�͎g�p���Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B�ǂ����Ă��B�C�D�Ɂu���邢�v�Ǝg�p��������A�@�A��ʂ̌��t�Ō����\���K�v������ł��傤�B
�������A�ŏ��ɒ�`�������Ȃ���A�ǂ�ł���l�ɂ͒ʂ��܂��A�r������ǂl����̓N���[�����t�����Ƃ́A�قڊԈႢ����܂���B�ł�����N���[���ɂ��X�����������Ƃ��ړI�Ŗ����ꍇ�A�B�C�D�̕��ɕʂ̕\�������蓖�Ă邱�Ƃ����������߂��܂��B
���āA����Ƃ͕ʂ�
>���Ȃ킿�A�u�ʐ^�̉掿�i�𑜓x�A�m�C�Y�ʁj�́A���ʂ���鑍���ʂ����߂�v�Ƃ����l����������B
�Ƃ����̂ł���A�傫�����̎��͂��ߏ��]�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ȕ��ł��I�����Ԃ�������Ή𑜓x�͉҂��܂����H�����ʂ�������Ή𑜓x���҂���̂ł���Ώ��������̃f�����b�g�͊��x���炢�ɂȂ����Ⴂ�܂��B�ł����_�I�ȉ𑜓x�̌��E�͌��ʂł͌��܂�܂����ˁB
���̑傫���̃|�e���V�������r��������T�C�Y�Ŕ�r����̂������ł��B�Ƃ���������F�l���o���ۂɌv�Z���Ă��邶��Ȃ��ł����B�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�����Q�i�Â��̂ł͂Ȃ��A�u�ʐϖ�1/4�v�܂茾������ς���u�Q�i���������v�Ƃ����̂��t�H�[�T�[�Y�̃|�e���V�����̐����ȕ]�����Ǝv���܂���B�i������O�����Ėʔ����Ȃ��̂�������܂��j
�����Ă��݂܂���B
�����ԍ��F10222160
![]() 4�_
4�_
�u�Â��v�ɂ�����炸�A�{���̗����ɓw�߁A����������I�ɂ܂Ƃ߂������ŗǂ��Ǝv���܂���B
�܂��́u�Â��v���l�K�e�B�u���ƌ��ߕt���Ȃ��Ŗ{���̗����ɓw�߂Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10222171
![]() 3�_
3�_
�t�H�[�T�[�Y�́A�e���Z���g���b�N�����̊m�ۂ��d�����߂����̂ƁA�e������̉e����ጸ�����邽�߁A�}�E���g�a�i�C���[�W�T�[�N���a�j���i�ߏ�Ƃ�������قǁj�傫���������A��萳���`�ɋ߂��A�X�y�N�g����̗p�����肵���B
���̂��߂ɁA�����ăZ���T�[�T�C�Y�������������A�ƌ����Ă�������������Ȃ��i�������A�R�X�g�_�E�����ړI�ɂ������낤���j�B
�����A����炪���ׂĖ��ʂ������Ƃ͎v��Ȃ��B
�Ƃ����̂́A�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�ɂ��āA������͖�2�i�̉掿�����o��͂������A�t�H�[�T�[�Y�͉�ʑS�̂̋ώ����������̂ŁA�ʐ^�S�̂Ƃ��Č����ꍇ�A���\�����Ƃ���܂ōs���i�����l�܂�j�B
����܂ł̃��X�ɂ������A�u�ኴ�x�i���邢�́A�����\���ɉ��j�ł́A�t�H�[�T�[�Y�̉掿�͂����v�Ƃ����咣�́A�����̌��ۂ������ꍇ�A���Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ��B
���邢�́A�t�H�[�T�[�Y�ŎB��ꍇ�Ɠ����̔�ʊE�[�x�E�V���b�^�[�X�s�[�h���m�ۂ��邽�߂ɁA�t���T�C�Y�̊��x��2�i�グ��A�掿�̓C�[�u���ɂȂ�B
�Ƃ������b���A�t�H�[�T�[�Y�E���[�U�[����͗]��o�ė��Ȃ��āA����I�Ȕ����̕������������̂́A���s�v�c�B
�Ȃ��A�͂炽����Ƃ́A�l���Ă��钆�g���̂��̂Ɋu����������Ȃ��̂ŁA���_���Ȃ��B
�����ԍ��F10222254
![]() 4�_
4�_
�F�̓G�l���M�[�ł��̂ŁA�G�l���M�[�̒P�ʂł���Ηǂ��ł��B
�����W���[���ł��傤���A�d�͂̐烏�b�g���ł��\���܂���B
TNT�����ʂ̍l��������́A�G�̋�̎��ʂ����肩���m��܂���B
�����ԍ��F10222356
![]() 0�_
0�_
�����[���X���ł����A�I�����p�X���[�U�[�̕��̏������݂��w�ǂȂ��ł��ˁH�H
���̂��낤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10222617
![]() 0�_
0�_
�� �A�u�ኴ�x�i���邢�́A�����\���ɉ��j�ł́A�t�H�[�T�[�Y�̉掿�͂����v
�� �Ƃ����咣�́A�����̌��ۂ������ꍇ�A���Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ��B
4/3��ISO100�̉掿�́A��i������āA35�~������ISO400�ɑ����ł����A
35�~������ISO400�̉掿���\�������ł�����ˁi�l�ɂ���Ă͈Ⴄ�����m��܂��j�B
�����ԍ��F10222917
![]() 0�_
0�_
���邢���ŎB�������̂ł�����r�ΏۂɂȂ�Ȃ�4/3�͘b�ɂȂ�܂���B
�����B�e�_���_���V�X�e���͏�Q�@�B
�s���̗ǂ��V�[�������̔�r�Ȃ�Ĕ�r����Ȃ��ł��傤��B
���邢�ꏊ�Ő^��������ʂ��ĉ掿�ǂ����������Ă��Ȃ��B
�t���T�C�Y�̃g���~���O�̂ق������������ʂ̌�����ǂ��������˂��B
��ʊE�[�x�͂ǂ�ȃV�X�e���ł��[���o���邯�ǁA
�t�H�[�T�[�Y����F1.4�ȉ��Ȃ�č��Ȃ����疳�������B
�p�i�͗ǂ����ǃI���̓_�����ˁB���x���Ⴗ���B
�I���̓G�̓R���f�W�ł���B�iE-1�̎����R���f�W�Ώۂ̐����������ɂ��j
�����ԍ��F10223470
![]() 1�_
1�_
���N�͓��{�ƒ����𑫂���2�Ŋ����A4/3�̓t���T�C�Y�ƃR���f�W�𑫂���2�Ŋ���b�͕����܂��ˁB
�R���f�W���́A�t���T�C�Y�ɋ߂��Ǝv���܂����B���͓�i�����ł����B
�����ԍ��F10223616
![]() 1�_
1�_
�܂������Ă�����ł��ˁB
�l�܂�Ƃ���A4/3�̃C���[�W�Z���T�[��35mm�t���T�C�Y��1/4�̖ʐς����瓯��F�l�ł��Q�i�Â��Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�������A�͂炽��������Ă���悤�Ɂu�Â��v�Ƃ������t�������Ӗ����Ă���̂��A�����ɂ���ӂ�Ȃ܂܂ł��ˁB
���́u�Â��v������t���邽�߂ɂ��낢��u���Z�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���悤�ł����B
�������A���́u�Q�i���̊��Z�v���@���Ƃ��Đ��藧�Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y�@���i�����d�ˁA����f�����ɂ�������炸�����x�掿�����サ�Ă��邱�Ƃ͂ǂ����������̂ł��傤���H
�܂������t���T�C�Y�ǂ����ł��A���Ƃ���NikonD3��D3x�̉掿�iS/N��j�̈Ⴂ�͂ǂ����������̂ł��傤�H
����A�C���[�W�Z���T�[��摜�����G���W�����i�����d�ˏ����I�Ƀm�C�Y���X���B�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�Z���T�[���ʐς�1/4���Ɓu����F�l�ł��Q�i���Â��v�Ɗ��Z��`�҂͌���������̂ł��傤���H
�����ԍ��F10224131
![]() 1�_
1�_
�s�����w����̃X���Ɋ��҂������B
�����ԍ��F10224277
![]() 0�_
0�_
���x�����������Ǝv���܂����A��i�Â��̌��_�́A��̓I�ȋZ�p�Ɉˑ����܂���B
�≖�ł������ł������A�f�W�^�����{���͕ς�܂���B��f���Ƃ͊W������܂���B
��{�I�Ȃ��̂ł�����B�ܘ_�A��̓I�ȋZ�p�����������邱�Ƃ��ł��܂����B
�W�̂Ȃ���f���ɋC�ɂȂ��Ă�悤�ł�����A�J�L�R[10177214]���Q�Ƃ��Ă��������B
�����ԍ��F10224550
![]() 0�_
0�_
�t�����g�J�Q����
�����́B�R�����g���肪�Ƃ�������܂��B
�~�X�^�[KEH����
�R�����g���肪�Ƃ�������܂��B
����A����ς�u���鐯���߂�v����̌����Ă��邱�Ƃ͓����
�悭�킩��܂���B
�����̒��ɂ������펯�͂����ł̑������ƑS�������ŁA����ɂ��Ă�
���ЂƂ̋^����킫�܂���B
���鐯���߂炳��@�̎咣�𗝉����悤�ƍl����ƁA
�킩��悤�Ȃ킩��Ȃ��悤�ȋC�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ݂Ɂu�Â��v�Ƃ������t�̎g�����Ɋւ��Ă͈�a��������܂��B
�l�̒m��Ȃ����Ƃ��u���鐯���߂炳��B�v�͂����m�Ȃ悤�Ȃ̂�
�₳�����킩��₷�������Ă������������̂ł��B
����Ɂu���������_�v�Ƃ������Ē������Ă�悤�Ő\����܂��A
S/N���m�C�Y�Ɋւ��邨�b���u���������_���v����p�ɂɏo��̂ɑ���
�u�����������_���v����͂��قǏo�Ȃ��̂��q���g�̂悤�ȋC�����Ă܂��B
���������Ƃ��Ă��鑤�ʂ��l���g�ɂ���̂�������܂���B
�u�s�����w����v������X���𗧂ĂĂ��������
�������Ƃ��Ⴄ�������Ő������Ă����Η����ł���̂��ȁH
�Ƃ������҂����Ă��܂��B
�����ԍ��F10224555
![]() 1�_
1�_
�{�X�g�[�NT-233����
�u���_��̌��E���l����Δ����傫�������掿���ǂ��v�Ȃ�Ă̂́A����ς蓖����O�����āA�ʔ����Ȃ��Ǝv���܂���B
���Ƃ��Ắu�����������̂Ɏʂ肪�ǂ��v�t�H�[�T�[�Y���ʔ����Ǝv���܂��B
(�m�C�Y�������Ȑl�Ƒ傫�ȃ{�P���D���Ȑl�ɂ́A�S�������Ȃ��V�X�e���Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂����B^^;)
�ŋ߂̌��t�ł́u�M���b�v�G���v�H���Č�����ł����ˁB ^^;
Tranquility����
�܂��ĊJ�����݂����Ȃ�ŁA�����������̂ł����A�b�͂ǂ����ʕ����i�ނ悤�ł��̂ŁA�܂��ގU�ł��傤���B
>����A�C���[�W�Z���T�[��摜�����G���W�����i�����d�ˏ����I�Ƀm�C�Y���X���B�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�Z���T�[���ʐς�1/4���Ɓu����F�l�ł��Q�i���Â��v�Ɗ��Z��`�҂͌���������̂ł��傤���H
���A����͌����Ǝv���܂��B���V���b�g�m�C�Y�𗝗R�ɋ����Ă��邩��B
�p�i�\�j�b�N�̓����Ɍ��̗��p����������I�ɏグ�Č��V���b�g�m�C�Y�����炷�̂������āihiro_sakae���Љ�Ă��̂Ō����l�������͂��j�A���������̂����p�������A��R�ʔ�����ł����˂��B
�����u�Â��v�ɂ͓B���h���Ă������̂Łu�Ȃ��Ȃ��v�ƌ���ꂽ���Ȃ���A�ʂ̕\���ɂ���ł��傤�B��������A�X���̒����͎��̊��ł�1/4�ɂȂ�A�A�A�������� ^^;
�����ԍ��F10224622
![]() 2�_
2�_
�� �u�Â��v�Ƃ������t�̎g�����Ɋւ��Ă͈�a��������܂��B
���ꎫ�����Ԉ�����Ƌ��܂�����A���ɂł��邱�Ƃ͉�������܂���B
���ꎫ�����������Ƃ���A��i�Â��ȊO�͉�������܂���B
�Ɠx��F�l�́A���ÂƊW�Ȃ����̂ƌ������炻�ꂪ�Ⴂ�܂����A
�����܂Ō����̈�ŁA�����܂ł��������ɓK�p�ł�����̂ł͂���܂���B
�Ɠx��F�l�͖ړI�ł�����܂��A���ʂ�]�����鋤�ʂȊ�ł�����܂���B
���̂��߂̏Ɠx�A���̂��߂�F�l���l���Ȃ���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10224707
![]() 0�_
0�_
�� ���V���b�g�m�C�Y�����炷
���ꂪ�ł�����A�m�[�x���O�N���͊m�����炦��ł��傤�B
�����ԍ��F10224720
![]() 0�_
0�_
>��i�Â��̌��_�́A��̓I�ȋZ�p�Ɉˑ����܂���B
>�≖�ł������ł������A�f�W�^�����{���͕ς�܂���B
>��f���Ƃ͊W������܂���B��{�I�Ȃ��̂ł�����B
�Ƃ������ł���u�Z���T�[���ʐς�1/4�����瑍�����1/4�v�Ƃ����A������O�Ȍ��_�ŏI���ł��ˁB
�������u���邳�Ƃ�S/N��v���Ƃ̐����������ƋL�����Ă��܂����B
�m�C�Y�ʂ̔�r����Ԃ̖��ł͂Ȃ������̂ł����H
���Ȃ݂Ɏ��́u���邳�v�Ƃ́uS/N�v�Ō����Ȃ�uN�v�ɊW�͂Ȃ��uS�v�̗ʂ̑傫���ƔF�����Ă��܂����ǁB
�����ԍ��F10224759
![]() 1�_
1�_
���������������ς蕪����Ȃ������������s��������
��������邱�Ƃ̕З��A�悤�₭���ڂ낰�Ȃ��番������
�����悤�ȋC�����܂��B�i�ȉ��ɏ������Ȃ�̗���������
�����������������������j�B
�܂�A���Z�e�l�Ƃ��������̖̂{���́A�u���̎����ʁv
�݂����Ȃ��̂�\�킷���l�Ȃ�Ȃ��ł��傤���B���Ԃ�
�������u�I�o���Ԃ����Ă��������ł͂Ȃ��A���̎���
���ʁv��\�킻���Ƃ�����̂Ȃ̂ŁA�u�Ȃɂ����e�l�v��
�����\�������Ɓu������₷���v�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�B
�����l����ƁA��f���i����ΐ蕪���̂������j�Ƃ��m�C�Y����
�ٍ̐I�Ƃ��������Ƃ͑S�R�W�Ȃ��b�A�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv����
���B
�����Ă��������l�����ɂ��ꗝ����Ǝv���܂��B
�����āA�����������Z�e�l�Ɋ�Â����f�͐�ΓI�ȏ��ʂ̑��ǂ�
�͂���Ƃ͂����A�J�����V�X�e���Ƃ��Ă̗L�p���Ɋւ��Č�����
�ЂƂ̑��ʂł����āA�V�X�e���̗D��ɂ��āA�ʒi�A�u�f�߁v
���悤�ƂȂ����Ă���킯�ł��Ȃ��̂ł��傤�B�����A�t�H�[�T�[
�Y�t�@���Ƃ��Ắu���Ȃ���Ă���v�悤�ȋC�����Ċ���I�ɔ���
���܂����A����Ɍĉ����Ċ��Z�e�l��������Ă���l���u���茾�t
�ɔ������t�v�ɂȂ��Ă��܂��ăX�����������Ă���A�Ƃ�������
�ȂႠ�Ȃ��ł��傤���B
�@�����āA���̗��_�A�u�������Ă���l�v�ɂƂ��Ă͂����炭
���܂�ɖ����Ȃ̂ŁA������Ȃ��l���{���ɕ�����Ȃ��Ƃ͂ƂĂ�
�M����ꂸ�A���₳��Ă��u�����������t�����Ă���v�悤��
�����v���Ȃ��̂��낤�Ƃ��v���܂��B
�@�����g�͂������蕪�����Ă������肵���C���Ȃ̂ł����A���A
�ق�Ƃɕ������Ă��܂��ł����H
�����ԍ��F10224812
![]() 1�_
1�_
�� �u�I�o���Ԃ����Ă��������ł͂Ȃ��A���̎����ʁv
�����ł͉掿�����߂���̏��ʂƌ������̂́A���G�l���M�[�ł����A�I�o���ԂƂ͊W������܂��ˁB
�V���b�^�[�X�s�[�h�͒����œ����ł���Ǝv���܂��i�Ⴄ�ꍇ�͉��̈Ⴄ�K�v�̐������j�B
�����ԍ��F10224892
![]() 0�_
0�_
�� �m�C�Y�ʂ̔�r����Ԃ̖��ł͂Ȃ������̂ł����H
SNR����f���ƊW�Ȃ����Ƃɂ��ẮA�J�L�R[10177214]�̐������Q�Ƃ��Ă��������B
�����ԍ��F10224922
![]() 0�_
0�_
�ŋ߁A���t�ɋ����������n�߂ď������݃`�F�b�N���Ă��܂����B
����D5000 KISSX3 E-620���������Ă܂������A
������Ƃ��̃X�������Ă������肵�܂����B
�傫�����̂͗ǂ������I�Ȕ��z�͗����ł��܂������A
�ȂA���������̂�n���ɂ�����A�����Ō������������݂����̂��āA
�����܂��B
���������Ƃ����ʓI�Ȕ����Ƃ��͐l�Ƃ��Ăǂ����Ǝv���܂��B
�L���m���Ƃ��j�R���݂����Ƀ��W���[�ȃu�����h�����ƁA
�݂�Ȃ���Ȋ����ɂȂ�̂ł��傤���H
���̃X�������Ċ������̂́A�L���m���A�j�R���͊m���Ɍ�₩��O�ꂽ��
�Ƃ������ƂƁA���t���̂̌������ǂ����ȂƎv���n�߂܂����B
�R���p�N�g�J�����ł������ʐ^�Ƃ��B���Ƃ��v�����A
���Ƃ���������A����σR���p�N�g�J���������Ă�l�Ƃ��A
���Ɍ����Ⴄ�̂��ȂƂ��v���ƁA
���ނ̋C�����Ĉ������Ⴂ�܂��B
�ނ������������͂킩��܂��A�v���݂����ȃJ���������Ȃ�A
�l�ԂƂ��Ă����Ɨ��h�ȑ�l�Ȑl�ł����Ăق����ł��B
���܂ŃJ�����ɏڂ����l���Ă������Ƃ��v���Ă܂������A
�����̏������݂����Ă���ƁA����ςȂ��ȁA�A���Ĉ�ۂ������Ȃ�܂����B
���Ԃ�蓪�������l�������Ƃ͎v���܂����A
���퐶���ŋ߂��ɂ�����A�������I���Ă��ł��B
�����ԍ��F10224972
![]() 17�_
17�_
�� �傫�����̂͗ǂ������I�Ȕ��z�͗����ł��܂������A
4/3�́A35�~�������傫���A�d���āA�������Ă��Ƃ͂����m�ł����H
�Ⴆ�A
ZD35-100/2.0�̏d����1.6�L��������A�l�i��24���~��ł����A����ɑ�������
EF70-200/4LIS�̏d�ʂ͂��̔����A�l�i�͔����ȉ��ł��B
�掿�����Ƃ������ł����AAF�̔�����EF70-200/4LIS�̕����S�R�ǂ��ł��B
�܂��A
ZD150/2�̏d����1.5�L���A�l�i��20�������܂����A����ɑ�������i������p�E���a�j
AF-S300/4�̏d���͓���1.5�L���ł����A�l�i��11���~�ł��B
AF-S300/4�͍i�������A4/3�@�ɕt���Ă��g���₷�����A�����𑜂��֎��ł��܂��B
���̎��́A600/8�����̃����Y�ɂȂ�܂����A�����600/5.6������ZD300/2.8�Ɣ�ׂĂ�
��i�����Â��Ȃ�܂���iZD300/2.8�̒l�i��64���~�ł��j�B
�����ԍ��F10225111
![]() 1�_
1�_
�R���f�W�������ł���B
�u�掿�͔�ʊE�[�x�Ō��܂�v�͐^���ł����A
�掿�̂��߂Ɏʐ^�\�����̂Ă�͖̂{���]�|�B
�u��͏������˂�v�ŁA�傫���t�H�[�}�b�g�ōi��Δ�ʊE�[�x��[���ł��܂����A�����ɂ������̂͂��������B
��ʊE�[�x���[���̂��D���Ȃ�R���f�W�������B
���������̃R���f�W�̐��i�͍Œኴ�x���������Ƃ������_������B�����ƃR���f�W�撣��I
�����ԍ��F10225138
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������A
�R���f�W�͗ǂ������m��܂��A4/3�́u��͏������˂�v�ł��܂����B
������̃����Y
ZD14-35/2.0�̏d����0.9�L���ŁA�l�i��20���~�ł����A���̃����Y����i���邢
AF-S24-70/2.8�̏d���͓���0.9�L���A�l�i��17���~�ł��B�܂��i���Ⴂ�܂����A
���̂悤�Ȉ��������Y������܂��Bhttp://kakaku.com/item/10504510342/�i240�O�����j
�����ԍ��F10225168
![]() 0�_
0�_
��ʊE�[�x����ɃJ�����V�X�e�����l���č��Α唻�A�����A���C�J���i�R�T�~���j�AAPS�A�X�p�C�J�����A���낢��ȃt�H�[�}�b�g�őS�ăV���b�^�[�X�s�[�h�A�i��l�������B�e�̂Ȃ��őS�Ă����܂��ˁB
���ꂱ����ςȎ����Ɣ��f�ł��Ȃ��̂ł��傤���ˁH
����������ʊE�[�x�͌��ʂŌ��܂镨�ł͂Ȃ��̂ňÂ����邢�͂����������ˁB
����̓����Y�ƃJ�����̐v��̖�肾�����͂菬�����傫���̕����Ó��ł��傤�ˁB
���n���n�������b�ɕt�������̂����Ԃ̖��ʁB
�ނ�ڂ�B4����A�Č����a����A�u���O�ɃR�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F10225388
![]() 1�_
1�_
���鐯���߂炳��
2009/09/28 01:27�@[10225111]�ŏ�����Ă��邱�ƂƎ����悤�Ȃ���
��������A"�{���͏d��"�����ł��B
�Ӗ����킩��܂���ł������B
�����ԍ��F10225483
![]() 0�_
0�_
����킱����@
�Ȃ����I�����p�X���[�U�[�͑��А��i���������܂��B
�߂��Ⴍ����ȗ����Ńj�R���E�L���m���E�\�j�[���_�����Ə������݁A
�t�H�[�T�[�Y���������Ōy���ĉ掿���悭�A�m�C�Y���C�ɂ��Ȃ���ō��̃V�X�e�����ƁB
���Ѓt���T�C�Y�͑傫���d�����z�Ŏ��Ӊ掿���_���i�ȒP�Ƀ\�t�g�ŕ�ł���̂Ɂj���ƁB
�v�����g���Ă��鑼�Ћ@�ނ��A���ł����˂Ȃ��t�H�[�}�b�g���g���Ă���Ǒf�l�W�c���A
�������낷�̂��I�����p�X�̓����ł��B
�ϑz�Ȃ̃I�����p�X���[�U�[�i����E-3�j�͘U�������I�^�N�������ăL�����ł���B
�����Ɏʐ^���y����ł郆�[�U�[���z���g�ɏ��Ȃ�����B
�Ȃ̂ŃN�`�R�~�����Ђ̔Ƃ͂�����ƈႢ�܂��ˁB
���А��i�����o�Ă���ƕK�����`�����`���Ə�A�M�҂����n�߂܂��B
�t�Ƀj�R�L���m�\�j�[��4/3�̘b�ɂȂ��Ă��E���E���Ƃ����������ɂ����Ȃ�܂��ǂˁB
���肸�Ƀj�R���E�L���m���̓���@���g���Ă݂ăN�`�R�~�ɎQ���Ȃ����Ă݂Ă��������B
�ʐ^���y�����Ȃ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10225653
![]() 1�_
1�_
�����őf�l�̎���I
�@����d�ׂɕϊ����A�I���̍Œ��͂���߂�킯�ł����E�E�E
�u���̓d�ׂ߂Ă����A�R���f���T�I�ȕ����̗e�ʂ�傫������AISO����������v
�@�E�E�E���Ă��ƂŁA�����Ă܂����H
�@���ꂪ�����Ă��āA�Œኴ�x����100�~�܂�ȋ@�킪�����̂́A������̖�� �iCMOS��CCD�̐��i���i���オ��j �Ȃ̂ł��傤���B
�����������������������@�ȉ��A����ƊW�����肻���ȗ]�k�@����������������������
�@SONY �̃R���f�W�AWX1 ������ł��B�i���j
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX1/
�@���̒��ɁA�u�l���u���y�����[�h�v ���Ă̂�����܂��āE�E�E�i���j
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX1/feature_2.html#L1_150
�@�U���������āA�掿���]���̂Q�{�ɂ���Ƃ����@�\�ł��B
�@�U�����������ʐ^�́A�܂��A�R���f�W�ł���Ȃ�\���Ƃ����ʐ^�ɂȂ�܂�w
�@����ɑ��āA���邢�Ƃ���ŎB�e����A�ʏ�̂P�����̎ʐ^�̓_���_���ł��B
�@���Ȃ킿�A �]���̂Q�{ ÷ �U �� �]���̂R���̂P�@������������ł��܂� orz
�@WX1 �̍Œኴ�x�� ISO 160 �ł��B
�@�d�ׂ߂Ă��������̗e�ʂ�{�ɂ���A�I�����Ԃ�{�ɂł��� �i�����ʂ��{�j�A�Œኴ�x�� ISO 80 ���x�ɂȂ�̂ŁA�\���ɖ��邢�Ƃ���̉掿�����P�ł��邩���I
�@�R���f�W�A�����Ƃ����w
�@�i�����ʂ��{�ɂȂ�ƁA���ʂ��{�ɂȂ��ē]�������ɂȂ�Ƃ��H�j
�@�i���[�����O�V���b�^�[���āA�I�����Ԃ�Z��������͑Ή��ł��Ă��A����������͓���Ƃ��H�j
�����ԍ��F10226708
![]() 1�_
1�_
���邩�߂���̘b���100�{���߂ɂȂ�܂����B
�Â��Ƃ��낪4�{�������I�ǂ�Ȏʐ^�ɂȂ�̂��y���݂ł��ˁB
�����ԍ��F10226768
![]() 3�_
3�_
>�v�����g���Ă��鑼�Ћ@�ނ��A���ł����˂Ȃ��t�H�[�}�b�g���g���Ă���Ǒf�l�W
>�c���A�������낷�̂��I�����p�X�̓����ł�
�����ł����Ȃ��Ǝ���(�{��To)��ۂĂȂ������m��Ȃ��ł���(��)
�����ԍ��F10227354
![]() 1�_
1�_
�͂炽����
�������J�����̖ʔ����Ƃ���Ȃ̂��ȁA�ƁB
�l�̚n�D�́A�����ł͐������Ȃ������������B
����A�������Y��ɐ����������Ƃւ̉����������āA������͂�����ł܂��ʔ����B
���鐯���������A
�u�S�Ă��Y��Ɉ꒼���i��Ȑ��j��ɕ��т܂��B����F�l�̐��ł��B�v
�́A�܂������������Ƃ�������B
�m���ɁA�����P���Ȑ^���ł����Ȃ��̂����i�����āA�����������̂����j�A���̐������������ƂŁA�J�����E�����Y�E�ʐ^�̌������ς�����B
�����ԍ��F10227355
![]() 0�_
0�_
����킱����
����A�����ɂ���l�́i��������܂߂āj���Ȃ����ł�����A����܂��ʉ����Ȃ������ǂ��Ǝv���܂���B^^;
���Ɏʐ^�D���̐l�ƃJ�����D���̐l�͈Ⴂ�܂�����B
���ʂ̎ʐ^�D���̐l�͂����ƕ��ʂł��B
�{�X�g�[�NT-233����
���̐��̓Z���T�[�T�C�Y�ň����Ă��ꏏ�ł���B
���ʂ̍H�w�͈̔͂ŊȒP�ɐ����ł��邱�Ƃ��A�ʂ̕ςȗ��R�Ő��������Ƌ^���Ȋw�̍��肪�Y���o���̂ŁA���������̂ɕq���Ȑl���N���[����t����̂ŃX�����r��܂��B^^;
���p�S���p�S
�����ԍ��F10227503
![]() 6�_
6�_
�����̐��̓Z���T�[�T�C�Y�ň����Ă��ꏏ�ł���B
�������������ł��B����ȊO�ɂ͂Ȃ��Ǝv���B
�����ԍ��F10227552
![]() 1�_
1�_
�݂Ȃ���t�H���[���肪�Ƃ��������܂��B
���ꂩ�炢�낢�돑�����݂�ǂ݂܂������A
��Ԃق̂ڂ̂��Ă���̂��As5pro�̔̂悤�ȋC�����܂��B
�ł��AFUJI�͍ŋߐV���i���o���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA
���������l����ƁA�܂����_�ɂ��ǂ蒅���܂���B
�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ƃ����I����������܂������A
����͈��t�ł͖����Ƃ̏������݂�����A
�T�C�Y�I�ɂ͂��傤�Ǘǂ��̂ł����A������܂����G�ł��B
���N�q�����Y�܂��̂ŁA����܂łɂȂɂ��w���������̂ł����A
�������������܂��A�����e�l���̂ȂɁH���Ċ����Ȃ̂ŁB
�i�������قǂ悭�{�P��ʂ͂킩��܂������B�j
�Ȃ��r��Ă����̂ŁA�ߏ蔽�����Ă����܂���ł����B
�����ԍ��F10228108
![]() 3�_
3�_
�����́I
�����X���炵�܂��B
�f�l�̑f�p�ȋ^��ł����A�I�[�g�t�H�[�J�X�ƃ����Y�̖��邳�͊W����܂����H
������������������K���ł�m(_ _)m
�����ԍ��F10228538
![]() 0�_
0�_
����킱����@
�R�R�ɏ������ރJ�����I�^�N�̃S�^�N�̓L�����ł����A�ʐ^�͊y�����ł��B
�����悤�ȃJ�������������������ʐ^�̋��X�܂ŕ��匾�����肷��z�����ă��_�ˁB
�Ԃ����Ƀt���b�V���͂��@�x�Ȃ̂ŁA
���邢�P�œ_�����Y�ƍ����x�J���������Ă��郁�[�J�[�������߂��܂��B
�j�R���E�L���m���͎����ł��m�[�t���b�V���ł�����̂ŐԂ����B��͗ǂ��ł���B
�t�H�[�T�[�Y�E�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�͎����B��͋��ł��B
�E�`�͕����ʐ^�D���������̂Ŏ����̐Ԃ����̍��̎ʐ^����R����̂ł��肪�����ł��B
���܂�Ă��邨�q����ɂ�������c���Ă����Ă��������ˁB
�����ԍ��F10228915
![]() 0�_
0�_
20D��D70�̎��͌����Ⴄ��20D�̕����ǂ������ł����A����X3��D90�ED5000���ǂ��Ǝv���܂��B
������APS-C�@�̉掿�́A4/3�Ɣ�ׂ���A20D��D70�Ɠ����ʂ�����ȏ�̍�������܂��B
���ɓ�Έʂ܂ł̎q���́A�����Ƃ͌����܂��A���T�B�����ʐ^���Ⴂ�܂��B
��x�ƃ`�����X�����Ȃ��ł��̂ŁA��͂�掿�Ɛ��\�Ή��i���X3���ꉟ�������߂��܂��B
�Ԃ����ł͂Ȃ��A���ʂ̃X�i�b�v��U���ʐ^�ł�����AE-620���AG1���ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10229013
![]() 0�_
0�_
�� �Ԃ����Ƀt���b�V���͂��@�x�Ȃ̂ŁA
���̘b�͂�͂荪�������Ǝv���Ă��A����������ǂ������m��܂��A
�Ԃ����ł��Q�p�Ƃ��F�X����܂��B�ڕ@�����葫�Ȃǃp�[�c�̐ڎʂ�����܂��̂ŁA
��t�i���ăt���b�V����������̂�����܂��B��t�i���Ă�X3���g���������ǂ��ł��B
�Ȃ��Ȃ�A�Œኴ�x��ISO100�ł́AX3����i�掿���ǂ��ł��i�ʐόv�Z�Ə����Ⴂ�܂��j�B
�����ԍ��F10229087
![]() 0�_
0�_
���y�̂��鐯���܂ɂ͑�ϋ��k�ł����A
�t���b�V���̓_���ł��B���ɖڂ́B��w�I�ɂł��B
�����ԍ��F10229112
![]() 0�_
0�_
�� �I�[�g�t�H�[�J�X�ƃ����Y�̖��邳�͊W����܂����H
�ʑ���AF�́A�����Y�̌��a������Ƃ���O�p���ʂł��̂ő���a�̕������x�������ł��B
�R���g���X�gAF�̏ꍇ�A��f���Ƃ����ʂ��Ⴗ����Ɣ������݂��Ȃ��Đ��x�������܂��B
�����ԍ��F10229152
![]() 0�_
0�_
�Ⴆ�Γ������̎��ɐԂ����̊�ɓ����鑾�z���ǂ̈ʋ������l�������Ƃ�����܂����H
���߂͏\�����b�N�X�ƌ����܂����A�Ԃ����̓������͑����������x�����Ǝv���܂��B
���ĉƂ̏Ɩ��͐��S���b�N�X�A���{�̉Ɖ��͐��\���b�N�X�������ł��B
�n�����ɗD�����ł����A�J�����Ɍ������ł��B
�����ԍ��F10229249
![]() 0�_
0�_
���`��B�B�B
�Ԃ����̖ڂ͌`��F���o����͂�����H
�F��F���ł���͍̂X�ɂ�����H
��l�Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA��w�I�ɗǂ�����܂���B
�����ԍ��F10229308
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳�Q�Ƃ���悤�Ɍ������������݂�ǂ�ł��悭�킩��Ȃ��̂ŁA������Ɛ������Ă݂܂��B
�܂��u�掿�v�ł����A�����ł́A��ʑ̂𒉎��ɍČ��o���Ă���摜�قǁu�掿���ǂ��v�ƌ����Ă����Ǝv���܂��B�f�W�^���J�����̉掿��ǂ����邽�߂ɂ́A���������Ȃ��𑜗̗͂D�ꂽ�����Y�ƁA�m�C�Y�̏��Ȃ��ǂ��M�����擾���鎖���K�v�ɂȂ�܂��B
OLYMPUS��ZUIKO DIGITAL�����Y�́A���[�J�[����f�W�^���ɍœK����}���������Y�ƌ����Ă���悤�ɁA�i��J�������ʎ��ӂ܂ň��肵�����������Ă��܂��B�]����35mm�������Y�ɔ�ׂ�ƁA�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̂��ɑ傫���悤�ȋC�����܂����A���\�ɑË������Ȃ��Ƃ����Ƃ���ł̋��e�͈͂̑傫���Ɏ��܂��Ă���Ǝv���܂��B
�t�Ɍ����A�v������鐫�\�����������ŁA�����Y�̃T�C�Y�����e�͈͂Ɏ��߂邽�߂�OLYMPUS���̗p�����t�H�[�}�b�g�T�C�Y���A4/3�������ƌ�����̂�������܂���B
�܂��A�Z���T�[�T�C�Y��������������ŒZ�B�e���������������鎖���o�����悤�ŁAZD14-54mm��ZD12-60mm�Ȃǂ̂悤�ɁA���Ɏ���͈͂̍L�������Y���������Ă��邱�Ƃ�4/3�̃����b�g�ƌ�����ł��傤�B
�����ۂ��A�f�W�^���ʐ^���`������M���ł����A�f�W�^���J�����ł́A�P��f�P��f���瓾����M���̏W���̂Ȃ̂ŁA���̂P��f�̐M���̎��iS/N��ASNR�j�����ł��B
�P��f�̏W���\�͂��傫���قǃm�C�Y�̊��������Ȃ��Ȃ�̂ŁA���ʂ̖R�������ł́A����f���������ꍇ�A�ǂ����Ă��C���[�W�Z���T�[�T�C�Y�̏����ȕ����s���ɂȂ�܂����A�\���Ȗ��邳�̂��鏊�ł̓m�C�Y�̊����������o����قǂɏ��Ȃ��Ȃ�̂ŁA����f���Ȃ�4/3�ł�35mm�t���T�C�Y�@�Ǝ��p��卷�Ȃ��摜�������Ă��܂��B
���鐯���߂炳��͂Ȃ����C���[�W�Z���T�[���ʐς�S/N������߂�ƌ����܂����A���炩�ɊԈႢ�ł��B�Z���T�[���ʐς������ł��A������@�̏ꍇ�A�����炩�ɉ�f�������������m�C�W�[�ȉ摜�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����킩��܂��B����͂P��f�̎���ʐς����������Ƃ������ł��B
�����ANikon D3 �� OLYMPUS E-30 �Ŕ�r�����ꍇ�AISO100�`200���x�ł͂قƂ�nj����������܂��ANikon D3 �� D3x �̍����x�B�e�ł� D3x �̕����m�C�W�[�ł��B
�i�P����4/3��35mm�t���T�C�Y���Q�i���Ɗ��Z�o���鎖�ł͂Ȃ��Ƃ킩��܂��j
�����ŏd�v�ɂȂ�̂��u�����Y�̖��邳�v�ł��B���܌����u���邳�v�Ƃ͎��ۂ́uF�l�v�̂��ƁA���m�ɂ́uT�l�v�ł��B
���ʂ��R�������A���Ƃ���ISO1600��F2.0�^�P�b�I�o���K���ɂȂ�悤�ȏꍇ�ł́AF4.0�ł͂S�b�I�o�œ����I���ʁi�������邳�̉摜�j�ɂȂ�܂��B�������A�I���ʂ������ł�F4.0�̕����S�{�I�o���Ԃ������̂ŁA�I�o���ɔ��������H�m�C�Y�͂S�{�̗ʂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�܂�AF�l�̏����ȁu���邢�v�����Y�́A�f�W�^���J�����ł͎��ۂ�F�l�̒i�����ȏ�ɂ��肪�������݂Ȗ�ł��B
�����������Ƃ������āAOLYMPUS���uSUPER HIGH GRADE�v�����Y��F2.0�̊J��F�l���������u���邢�v�����Y�𓊓����Ă��Ă���̂ł��傤�B
�܂��A����4/3�@�ł��AE-1�̎���ɔ�ׁA�ŐV�̋@��ł͖��炩�ɍ����x�掿�����サ�Ă��Ă��܂��B
����̓m�C�Y�̔����ʂ�}���鎖���o���Ă���̂��A�m�C�Y���������鎖����肭�Ȃ��Ă��Ă���̂����R�Ƃ��܂��i���Ԃ��ł��傤�j�A�����I�ɂ͂܂��܂���m�C�Y���o���邾�낤���Ƃ�\�z�����܂��B�����Ȃ��Ă���A�܂��܂�4/3��35mm�t���T�C�Y�̍��͏k�܂鎖�ł��傤�B
�߂������A�����Ō�����Ⴂ�͔�ʊE�[�x�����ɂȂ��Ă���̂�������܂���B
�����l���Ă݂�ƁA4/3�Ƃ����t�H�[�}�b�g�͒P����35mm�t�B�����J�����ɒu������鎖��_�����Ƃ������ƈȏ�̉\��������悤�ɂ��������܂��B
�ȏ�A�{�X���̃^�C�g���ɉ����čl�@���Ă݂܂����B
�����ԍ��F10229627
![]() 8�_
8�_
>�f�W�^���J�����ł́A�P��f�P��f���瓾����M���̏W���̂Ȃ̂ŁA���̂P��f�̐M���̎��iS/N��ASNR�j�����ł��B
�u�P��f�̐M���̎��v�Ɓu���̗ʁi��f���j�v�� S/N��͌��܂�܂��B
�O��Ƃ��Ắi�X���b�h�̍ŏ��̏������݂����p�����Ă��������āj
>�������Ȃ��Ă��m�C�Y���S���������Ȃ����z�I�ȎB���f�q�Ƃ����O��
�ł����A
�摜������f���� 1/N �ɏk������ƁA�u�P��f�̐M���̎��iS/N��ASNR�j�v�́u��N�{�v�ɂȂ邩��ł��B
�����ԍ��F10229698
![]() 0�_
0�_
�����̉掿�Ƃ͘I�o�ʂɉe�������掿�ŁA��ʓI�Ɏg����g�����x�掿�h�̉掿�Ɠ����ł��B
�����Y�̉𑜂�����͂����m�̒ʂ菬���a�ɂȂ�قǂ��Ղ��ł��B
����̓t�H�[�}�b�g�ɉe������Ȃ��悤�Ɍ����܂����i�R���f�W�̃����Y�̉𑜂������j�A
�ʐϔ�̌v�Z�Ƃ͈���āA�ȒP�Ȍv�Z�Ő����ł����肩�͕�����܂���B
�܂����ł��A4/3�̉掿�������̂��������Z���T�[�̓d�C���\���Ⴂ�Ǝv����������܂���
����͈Ⴂ�܂��B�P�ʖʐς̓d�C���\�́A�R���f�W�ł��AD3�ɕ����Ȃ��قǍ����ł��B
�掿�̈Ⴂ�́A�P�ʖʐς̓d�C���\�ł͂Ȃ��A�P�ɏW���ʐς�����������ł��B
���̃V���b�g�m�C�Y�͘_���I�ɍ����ł��Ȃ����E�ł���A���̑O�ɉ�X�l�Ԃ͖��͂ł��B
����͉i�v�@�ւ�A�����E�G�l���M�[���Ȃ����琶������Ɠ�����Փx�̖�肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10229766
![]() 0�_
0�_
>�u�P��f�̐M���̎��v�Ɓu���̗ʁi��f���j�v�� S/N��͌��܂�܂��B
�Ⴂ�܂��B
�摜���\������P��f���Ƃ�S/N�䂪�ϓ����邱�Ƃɂ���āA���ʂ̖R�������Ńm�C�W�[�ȉ摜�ɂȂ�̂ł��B
>�O��Ƃ��Ắi�X���b�h�̍ŏ��̏������݂����p�����Ă��������āj
>>�������Ȃ��Ă��m�C�Y���S���������Ȃ����z�I�ȎB���f�q�Ƃ����O��
>�ł����A
�m�C�Y���܂������������Ȃ��B���f�q�Ȃ�S/N�����邱�Ƃ͏o���܂���B
>�摜������f���� 1/N �ɏk������ƁA�u�P��f�̐M���̎��iS/N��ASNR�j�v�́u��N�{�v�ɂȂ邩��ł��B
�\���킯����܂��A�{�X���Ńm�C�Y�����̂ɁA�摜�̏k�����l����Ӌ`���킩��܂���B
�����ԍ��F10229772
![]() 2�_
2�_
�� �摜�̏k�����l����Ӌ`���킩��܂���B
��f���̂��W�Ȃ��ł�����ˁB�W������̂���ʑS�̂̃T�C�Y�����ł��B
�����ԍ��F10229800
![]() 0�_
0�_
>�摜���\������P��f���Ƃ�S/N�䂪�ϓ����邱�Ƃɂ���āA���ʂ̖R�������Ńm�C�W�[�ȉ摜�ɂȂ�̂ł��B
�P��f��S/N��Ƃ����Ӗ��ł͂��̂Ƃ���ł��B
>�m�C�Y���܂������������Ȃ��B���f�q�Ȃ�S/N�����邱�Ƃ͏o���܂���B
�f�q�Ƀm�C�Y�������Ƃ��A��̉�f�ɓ��Ă������ǂꂾ�����m�Ɏ������邩�͊m���̐��E�ł���A�i�Ⴆ�� n�̌��q����̉�f�ɓ��Ă��̂ł���j�������鐔�́u���� n�A�W���� ��n�v�̐��K���z�ŕ\����܂��B
>�\���킯����܂��A�{�X���Ńm�C�Y�����̂ɁA�摜�̏k�����l����Ӌ`���킩��܂���B
�Ⴆ�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y�ƑS�������B���ʂ��l�����ׂ����̂Ƃ��܂��B
�t���T�C�Y���k�����Ȃ���A�P��f�� S/N��̓t�H�[�T�[�Y�Ɠ����B��������f���i�摜�T�C�Y�j���S�{�B
�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y�Ɠ����摜�T�C�Y�܂ŏk������A�P��f�� S/N��̓t�H�[�T�[�Y�̓�{�ł��B
�u�Ӌ`�v�ł͂Ȃ��A������������������Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F10229854
![]() 1�_
1�_
>�Ⴆ�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y�ƑS�������B���ʂ��l�����ׂ����̂Ƃ��܂��B
�t���T�C�Y���k�����Ȃ���A�P��f�� S/N��̓t�H�[�T�[�Y�Ɠ����B��������f���i�摜�T�C�Y�j���S�{�B
�t���T�C�Y���t�H�[�T�[�Y�Ɠ����摜�T�C�Y�܂ŏk������A�P��f�� S/N��̓t�H�[�T�[�Y�̓�{�ł��B
�u�Ӌ`�v�ł͂Ȃ��A������������������Ƃ������Ƃł��B
���ǁA�P��f�̎���ʐρi���d�ϊ��̐��\�j���M���̎������߂Ă���Ƃ����̂Ɠ������Ƃ������Ă���̂ł͂���܂��H
�����ԍ��F10229903
![]() 4�_
4�_
��f���������̏ꍇ�͗������₷���Ǝv���܂����A
��f��������Ă���i�̍��͕ς�܂���B��f�P�ʂŌ���K�v������܂���B
�Ⴄ��f���̊��Z�͋��s�̂�������Ǝ����̑O�̃J�L�R���Q�Ƃ��Ă��������B
����ʐςƁA���d�ϊ����\�̊T�O���Ⴂ�܂��̂ŁA�����������l���Ă��������B
�����ԍ��F10229923
![]() 0�_
0�_
�P��f�̎���ʐςƌ������u�P��f�̎���ʁi���q���E�G�l���M�[�j�v�ł��B
������鎞�ԁi�V���b�^�[�X�s�[�h�j���l�{�ɂ��Ă������ł����A
F�l���Ȃ�i���Ԃ͂��̂܂܂Łj����ʐς��l�{�ɂ��Ă������ł��B
���Ԃ̏ꍇ�A����őf�q���O�a���邩�͋Z�p�̖��i�t�H�[�T�[�Y�� ISO25 ����������ȂƎv���܂��j�B
�ʐς̏ꍇ�A����ʐς��l�{�ɂ���̂ƁA�B�e��ɉ摜�T�C�Y 1/2�i�摜�ʐρE��f�� 1/4�j�ɏk������͓̂������Ƃł��B
������ɂ���A���f������̌��q�� N�������̂��u4N�v�ɑ������Ƃ���ƁA
�W������N �ł���Ă����P�x���x�����A�W���� 2*��N �ł���悤�ɂȂ�܂��B
�摜�Ƃ��Ắi���̂܂܂ł͖��邭�Ȃ��Ă��܂��̂Łj1/4�{�ɂ��āA���ʁA���f������u���q�� N�A�W���� (1/2)*��N�v�ƂȂ�A�m�C�Y������̂��킩��܂��B
�ȏ�́u�m�C�Y�̔������Ȃ����z�I�ȑf�q�v�̘b�B�����ɂ͈Ód���m�C�Y�Ƃ�����܂��ˁB
�d�v�Ȃ̂͂����m�C�Y�̐����ł��傤�B
���Ɂu�f�q�̃m�C�Y���f�q�ʐςɔ��v�Ƃ��܂��B�f�q�ʐώl�{�Ȃ����ʎl�{�����m�C�Y���l�{�A�[�����肤��O��ł��傤�i��f���l�{�Ȃ�m�C�Y�l�{�͐��藧���܂��ˁj�B
���̏ꍇ�́u�f�q�̃m�C�Y�Ɋւ��Ă͑傫���t�H�[�}�b�g�̃����b�g�͖����v�ƂȂ�܂��B
�f�q�̃m�C�Y�Ɋւ��đ傫���t�H�[�}�b�g�Ƀ����b�g�͖����Ƃ��A���q�̐��ɉ��������V���b�g�m�C�Y�Ɋւ��Ă͑傫���t�H�[�}�b�g�̃����b�g������Ƃ������Ƃł��B
�ŁA�����ɂ͑f�q�Ƀm�C�Y�͂���܂��B����́u�t���T�C�Y�̓t�H�[�T�[�Y����i���m�C�Y�����Ȃ��v�Ƃ͂Ȃ�܂���B�f�q�Ƀm�C�Y������Ƃ����O��ł̗��_��́u�t�H�[�T�[�Y�� ISO100 �́A�t���T�C�Y�� ISO400 ���m�C�Y�����Ȃ��i����f���Łj�v�ƂȂ�͂��ł��B
�����ԍ��F10229936
![]() 0�_
0�_
���ƁA�������������Ƃ͂��̃X���̍ŏ����炸�[���ƌJ��Ԃ��Ă��܂��B�ł��������x�ǂݕԂ��Ă��炦��Ɗ������ł��B
�Ⴆ��
�u����t�H�[�}�b�g�ʼn�f�����������f�W�J�����w�����g���~���O���邱�Ƃ͑��̊g��Ƃ����Ӗ��Ŗ]����L���̂ƈꏏ�B����ł����ZF�l���傫���Ȃ�̂Ńm�C�Y�͑�����v
�Ƃ��ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9830885/#9846769
����Łu����f�@�̓m�C�Y�������ł��ˁv�Ɠ˂����܂�Ă��܂��i���̒ʂ�I�j�B
http://www.imagegateway.net/p?p=DKyLAsEve2e
���̃A���o���Ō����A�ꖇ�ڂ̓t�H�[�T�[�Y2000����f�@�i��1/16�g���~���O�j�̃s�N�Z�����{�摜�A�ڂ̓t���T�C�Y2000����f�@�i��1/16�g���~���O�j�̃s�N�Z�����{�摜�A���ꂼ��u���̂��́v�ƌ����Ă����ł��B
�E�������t�H�[�}�b�g�ł̃X�e�B�b�`�ő傫���t�H�[�}�b�g�̉摜�͍���B
�ł��B�������L�p�̃p�[�X�͕\���ł����A�p�m���}�݂����ɂȂ����Ⴂ�܂����B
�����ԍ��F10229946
![]() 1�_
1�_
���œǂ�ł���l(���邩�ǂ�������܂��j�ׂ̈ɏ���������Ă݂܂��ˁB
Tranquility����Ƌ��s�̂�������̊Ԃł́u���V���b�g�m�C�Y�v�̈������Ⴂ�܂��B
���s�̂�������͌��V���b�g�m�C�Y���m�C�Y�Ƃ��Ĉ����Ă��܂����ATranquility����̓V�O�i���̕��ɏ悹�Ă��܂��B
S/N��Ƃ������Ƃł���A�m�C�Y�i���V���b�g�m�C�Y�ȊO�j���L���̒l�����ꍇ�A���ʂ������S/N�䂪��������̂͂ǂ�����ς��܂���B���s�̂�������̍l�����ł͕���𑝂₵�ATranquility����̍l�����ł͕��q�����炵�܂��B
���҂̈Ⴂ�m�ɂ���ɂ́A�Z���T�[�̈��f�������q������������ł���悤�ȍ���f�̋Ɍ����l����Ε���Ǝv���܂��B���̏ꍇ�A���V���b�g�m�C�Y�̓m�C�Y�Ƃ͈����Ȃ��ł��傤�B
Tranquility����̍l�����͐M��������ʂɒʗp���A�ėp���������Ǝv���܂��B���Z���T�[�֘A�̘_���Ȃǂ�����ƌ��V���b�g�m�C�Y�̍l���������̕���ł͈�ʂɎg���Ă���悤�Ȃ̂Ō��V���b�g�m�C�Y�̍l�������L���ł���Ǝv���܂��B
�ŁA��낵���ł��傤���A�����l�B
�����ԍ��F10230406
![]() 2�_
2�_
�J�����̍����x�m�C�Y�͊�{�I�ɃV���b�g�m�C�Y�ł��̂��A����͗B��ɋ߂��f�g�c�����ϐ��ł��B
���̂��͉̂e�����Ȃ��킯�ł͂�܂��A�t���T�C�Y����R���f�W�܂ł���قǕς�܂���̂ŁA
�Z�p���i�����Ă��������ʂ��オ�邩�����邩�̘b�ł��ˁB�܂������Ђ��V�����Z�p�i�����ł��Ă��A
���ꂪ�ꎞ�D���ɉ߂��܂��i�L���m�����ǂ��Ⴞ�Ǝv���܂��j�A�ʂ̃t�H�[�}�b�g��
���ꓯ���悤�ȋZ�p���g���܂�����A�W���ʐς����{�̓�i�̍��͉i�v�s�łł��B
�����ԍ��F10230595
![]() 1�_
1�_
�����叫�I
�����ԍ��F10231361
![]() 3�_
3�_
�s�v�c�Ɏv���̂́A���鐯�J�������@�t�H�[�T�[�Y�̔ɗ��Ắ@���ZF�l�̎��_�����ǂ��ǂƏ�����܂����A
�j�R���E�y���^�b�N�X�E�\�j�[�̔Ł@APS�@��F2.8�̃����Y���Ă�F4������1�i�Â������Y�ɂ����ׂ�܂���Ƃ��@�L���m����APS�@��F�ꍇF2.8�̃����Y���Ă�F4����1�i�ȏ�Â������Y�ł���Ɓ@�����Ɠ����l�ɉ��x���N�h�N������Ă�ƈ�a���������̂ł����ˁB
�t�H�[�T�[�Y�̔����ɗ��Ă����������ɏ������ƕЎ藎���̗l�ɂ����v���܂���ˁB
�����ԍ��F10233157
![]() 13�_
13�_
�� APS�@��F2.8�̃����Y���Ă�F4������1�i�Â������Y�ɂ����ׂ�܂���Ƃ��@
APS-C�@��f/2.8�́A35�~������f/4���������Â��ł��ˁB
���̏ꍇ�́Af/4������ZD14-35/2�̕����������邢�ł��B
�����ԍ��F10234055
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �́@2009/09/29 01:14�@[10229627]�@�{�X���̃^�C�g���ɉ����čl�@ �� �ɂ���
�����ʂ��R�������A���Ƃ���ISO1600��F2.0�^�P�b�I�o���K���ɂȂ�悤�ȏꍇ�ł́A
���i�t���T�C�Y�́jF4.0�ł͂S�b�I�o�œ����I���ʁi�������邳�̉摜�j�ɂȂ�܂��B
�@�@��
�@35mm�t���T�C�Y�ł́AISO6400�ŎB�e����A35mm�t���T�C�Y�����P�b�I���ɂȂ��āA�����������Ǝv���܂��B�i������́A���z�I���������낢��ݒ肵�� �u�����v �̏ꍇ�j
�@����ƁA���ۂ̎B�e�ɋ߂��ꍇ�̘b�́ATranquility������V�̂�����Ă���l�����番����Ǝv���܂����A�uCMOS �ŘI�����Ԃ����тĂ��m�C�Y�����܂葝���Ȃ����x�v ��m���Ă���Ǝv���܂��B�@�i35mm�t���T�C�Y���ɗL���ɂȂ�ꍇ�����鎖���������̃n�Y�j
�������I�ɂ͂܂��܂���m�C�Y���o���邾�낤���Ƃ�\�z�����܂��B
�������Ȃ��Ă���A�܂��܂�4/3��35mm�t���T�C�Y�̍��͏k�܂鎖�ł��傤�B
�@���̍��͈ӊO�Ə��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ƃ��A���鐯���߂炳����A���s�̂�������������Ă���Ǝv���܂��B�@�ǂ��炩�Ƃ����ƁA���̃n�[�h���� ���鐯���߂炳�� �̕����Ⴍ�āAISO50 ��B������ΐ��\�ʂł̕���͂Ȃ��Ȃ� �u�n�Y�v �ł�w
�����ԍ��F10234759
![]() 0�_
0�_
���V���b�g�m�C�Y�́u���q�̐U�镑�����m���I�ɂ����킩��Ȃ��v���Ƃ��炭��m�C�Y�ł��B
���H�}����}���āu�����v��}������ƁA�����������q����̉�f�Ɂu�h�X�g���C�N�v�œ����邩�̂悤�Ɏv���Ă��܂��܂����A���ۂɂ͌��q�̓����͂Ă�Ńo���o���B
�f�W�J���ŘI������Ƃ́A��̉�f�ɗ������q�̐��𑪒肷�邱�ƁA�ƌ������Ƃ��ł��܂����A���̌��q�̐����ǂ̉�f�������ł͂Ȃ��A���ς𒆐S�ɂ���Ƃ������Ƃł��B���Ȃ킿���q�̐��͊m���I�ɂ�������ł��Ȃ��i���q��������Ȃ��Ɍ��̏ꍇ�����Č��q��⑫�ł��邩�͊m���ł��j�B
���̌��ʂ͉摜�� RGB���x���̂���ƂȂ��Č���܂��B
�O���[�J�[�h���B�e���Ă��̃q�X�g�O�������z���������Ƃ�����l�́A���̃��x�������ς𒆐S�Ƀc���K�l��ɍL���邱�Ƃ��킩��Ǝv���܂��B�u�m�C�Y�����Ȃ��Ȃ��v�Ǝv������A�c���K�l�̍L��������Ȃ��ł��i�o�����痝�_���w�ԁj�B
���V���b�g�m�C�Y�́u�摜�ւ̃m�C�Y�̌�����v���f�q�̃m�C�Y�Ƃ͂�����ƈႤ�Ǝv���܂��ˁB�O���[�J�[�h����������イ�B�e����A���̊��o�͂킩��Ǝv���̂ł����B
�܂��O���[�J�[�h���k������ƃm�C�Y������iRGB���x���̂��������j�̂��킩��܂��B����ł��m�F�ł��邵�A�q�X�g�O�����\���ł��m�F�ł��܂��B
��{�I�Ɏ��̃A���o���ł̈Ⴂ�͌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ł��B
�����ԍ��F10234832
![]() 0�_
0�_
�s�����w����A�����́B
����F2.0��F4.0�̏ꍇ�̔�r��Ꭶ�����̂́A4/3��35mm�t���T�C�Y�̂�����u���ZF�l�v�̔�r�������̂ł͂���܂���B
�����܂ł��f�W�^���C���[�W���O�ɂ�����uF�l�v�����������Ƃ̗D�ʐ����������Ƃ��������ł��B�ł�����s�����w����̏�L���p�̂悤�Ɂu�t���T�C�Y�́v�Ƃ͏����܂���ł����B
�����Ƃ��A�≖�ʐ^�ɂ����Ă���Ɠx���̑������s�O�̓_�ŏ������i���邢�jF�l�͗L���ɂȂ�܂��̂ŁA����̓f�W�^���ł��≖�ł��ʐ^�B�e�ɂ����Ĉ�ʓI�Ɍ����邱�ƂƎv���܂��B
���������ϓ_���猩�Ă��u���ZF�l�v�Łu���邳�v�����͍̂��������Ȃ��ƍl���܂��B
��p����ʓI�ɗ������₷��35mm���̏œ_�����ɒu��������
�u4/3��25mm�̉�p�́A35mm����50mm�ɑ����v
��ʊE�[�x�l��
�u4/3��F2.0�̔�ʊE�[�x�́A35mm����F4.0�ɑ����v
�Ƃ�����ɕ\������̂́A�܂��d�����Ȃ��Ǝv���܂����A
���̏ꍇ�ł��u���Z�œ_�����v�Ƃ��u���ZF�l�v�Ƃ����\���͌���̌��ɂȂ�̂ŁA
���������\���͗p����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10234936
![]() 4�_
4�_
>�����܂ł��f�W�^���C���[�W���O�ɂ�����uF�l�v�����������Ƃ̗D�ʐ����������Ƃ��������ł��B
�u�D�ʐ����������Ƃ������ǔ��_���ꂽ����A���_�ɑ��锽�_�͂��Ȃ��ŗD�ʂƂ������Ƃɂ��Ă��܂��v
�Ƃ����킯�ł��ˁB
�����ԍ��F10235394
![]() 0�_
0�_
[10215568] ���B
�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E
�Ȃ��A�u���Z�v�Ƃ������{�ꂪ�����ł��Ȃ��l�������̂ŁA���������������Ă����܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041113/So
rtID=10159202/#10213843
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041113/So
rtID=10159202/#10213867
�ȂO�X���ł����������悤�Șb���������̂ŁA���͓��{��̖��Ȃ̂��ȁA�ƁB
�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E
�u���Z�v�Ƃ́u���l�̊Ԃɉ��l�Ɋ�Â�����������������v�Ƃ������ƂƃC�R�[���ł��B
���Z�ł���Γ������������邵�A��������������Ȃ犷�Z�ł���B
Tranquility���� ��������邩�ǂ����͊��Z�ł��邩�Ƃ͖��W�B
>���������ϓ_���猩�Ă��u���ZF�l�v�Łu���邳�v�����͍̂��������Ȃ��ƍl���܂��B
�u���ZF�l�Ŗ��邳�����͍̂��������Ȃ��v�̂ł���A����́u���Z�ł��Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
������ Tranquility���� �����������Ȃ��Ƌ��ق��Ă��邾���ŁA���ۂ́uS/N��v�Ƃ������ʂƂ��Č����Ƃ����Ӗ��ō�����������܂��B
�����ԍ��F10235420
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
�l�̏��������ƁA�����Ɠǂ�ł܂����H
�����ԍ��F10235608
![]() 7�_
7�_
>��ʑ̂𒉎��ɍČ��o���Ă���摜�قǁu�掿���ǂ��v�ƌ����Ă����Ǝv���܂��B
���ꂪ�ړI�Ȃ�A
>�f�W�^���C���[�W���O�ɂ�����uF�l�v�����������Ƃ̗D�ʐ����������Ƃ��������ł��B
���ꂪ��������͓̂���t�H�[�}�b�g�A�����p�ɂ����Ă����ł��傤�B
[10179843] �ł����g�������Ă܂��ˁB
>�Y�[���A�b�v����Α��{�����傫���Ȃ�̂Ŕ�ʑׂ̂̍��������܂Ŏʂ���悤�ɂȂ�܂���
�Y�[���A�b�v����� F�l���傫���Ȃ��Ă���ʑ̂𒉎��ɍČ��ł���悤�ɂȂ�܂��B
�܂��A�������X�ł����������Ă܂��ˁB
>�t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�̓Y�[���ɂ���ĕς���ł͂���܂���A������ЂƂ̒P�ʖʐςƂ������Ƃł��B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�i�t�H�[�}�b�g�ʐρj��P�ʖʐςƂ���悤�ɖʏƓx��ϊ�����Ɓu���ZF�l�v�����܂�܂��B
�����ԍ��F10236830
![]() 0�_
0�_
�œ_��������p���t�H�[�}�b�g���P�̉�f�T�C�Y���W�Ȃ��AF�l�̏����Ȗ��邢�����Y��F�l�̑傫�������Y�ɔ�ׂăm�C�Y�̏��Ȃ��M�����擾����̂ɗL�����ƌ����Ă����̂ł����A�킩��܂���ł������H
���łɁA�≖�ʐ^�ł��������s�O�̓_�ŁA���l�ɗL�����ƌ����܂����B
�O����������x�B
�u�œ_��������p���t�H�[�}�b�g���P�̉�f�T�C�Y���W�Ȃ��v�ł��B
�����ʑ́A����J�����E�����Y�ōi���ς����ꍇ���A���l�ł��ˁB
���̏��������܂��������̂ł��傤���H
�����ԍ��F10237348
![]() 1�_
1�_
�@�������ɍŋߎg��Ȃ��Ȃ�܂������A���̃J�����͂Q�i�ƂS�i�Â���ł�w
�����ԍ��F10237750
![]() 2�_
2�_
��p�ƌ��a�������ł���A�œ_������F�l�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƊW������܂���B
�܂��A�≖�̘I�o�v�Z��̘b�ł����A����̓t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ����Ƃł��ˁB
�����ԍ��F10239100
![]() 1�_
1�_
�@�P�ɁA�t�H�[�T�[�Y�́A����ʐςS���̂P�ƁA�P�U���̂P�̗���o���������������Ȃ̂ł����E�E�E
�@�ʐ^�Q���ڂ́A�Q�^�R ccd �́A�ƶ���� �`�Q�ŁA�����g�����J�����ł��B�@���̃J�����͖��邢�ꏊ�̎ʐ^�ł��s�N�Z�����̃������ڗ����A�s�N�Z���}�b�s���O�ɏo���Ȃ��� �i�C���ɏo���Ȃ��Ɓj �����Ȃ��̂�������܂���B�@�i������͊��S�ɗ]�k�j
�@�ʐ^�R���ڂ́A�P�^�R ccd �i�r�f�I�J�����j �̎ʐ^���ڂ������ł����B
�@���A�{�����̂ɏo�Ă��Ȃ��̂� �iorz�j ����ɕt���Ă��������Y�̂݁A�ʐ^�ɎB��܂����B
�@���̃����Y�A�e�l0.8�ł��B
�@�����ƌ����I�@�Ƃ����A�l�X�̎v����̌����������Y�Ȃ̂�������܂���w
�@�Ȃ��r�f�I�J�����̘b�������ł���̂��Ƃ����ƁA���̑̑��ɂȂ肻���ȃl�^�����邩��ł��B
�@������P�O�N�O�A���q�������Q���b�肾��������̘b�ł��B
�@�����r�f�I�ŎB�낤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���̂悤�Ȏ����A�i�E���X����Ă��܂����B
�@�u���ɏœ_���� �Smm �e1.0 �Ƃ��������Y�ƁA�Wmm �e1.4�Ƃ��������Y���������Ƃ���ƁA��ʓI�ɐ��������ʂ�̂͌�� �i�Wmm �e1.4 �����Y�j�v
�@�Ƃ肠���������܂ł́A�I�����ԁi�ő��1/30�b�܂ŌŒ�j�ɂ��A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ��ւ��Ȃ����ł��B
�@�d�����Z�����Ȃ��ė��Ă��܂����̂ŁA���̘b�A�����ɑ����������邩�A�����ł��邩�A���ɔ����ł��A�X�~�}�Z���B
�����ԍ��F10239400
![]() 0�_
0�_
>�œ_��������p���t�H�[�}�b�g���P�̉�f�T�C�Y���W�Ȃ��AF�l�̏����Ȗ��邢�����Y��F�l�̑傫�������Y�ɔ�ׂăm�C�Y�̏��Ȃ��M�����擾����̂ɗL�����ƌ����Ă����̂ł����A�킩��܂���ł������H
���̂��Ƃ������Ă���̂������ς�킩��Ȃ��̂ł����i�}�W�Łj�B
�u�m�C�Y�̏��Ȃ��M���v���ĉ��ł����H
��������O�Ɏ���
�u�����Y���̃N�I���e�B�̓����Y���a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v
�Ə����܂�����ˁB�����Ă��Ȃ��͂���ɓ��ӂ��ꂽ�B
�������牽�ŁuF�l�̘b�v�ɂ���ւ��̂��A�S�������ł��܂���B
����ƁA�u���ZF�l�v�́u�����Y���̃N�I���e�B�Ɋւ��ăt���T�C�Y�Ɋ��Z����v�Ƃ��������̘b�B�P�Ȃ銷�Z�ł��B
�u�����Y���̃N�I���e�B�̓����Y���a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v������Řb�͐s���Ă�̂ł��i���Ƃ́u���Z�v�Ƃ������{��𗝉����邾���j�B
�����ԍ��F10239806
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �͑O�X���Łu���a�Ō��܂邱�ƂɈ٘_�͖����v�Ə�����܂�����ˁB
���̎��́u����\�����܂�v�Ƃ����b��������������܂��B
�u��ʑ̂̌����v�����a�Ō��܂�܂��B
�u����\�v�Ɓu�����v�B���̓�����l�i����ɉ�����Ȃ�u��ʊE�[�x�v���j�B
�g���l�h�Ɋւ��āuF�l�v�Ƃ����g�ʁh���t���T�C�Y�Ɋ��Z����B���ꂾ���̂��Ƃł��B
�O��Ƃ��āu�œ_�����v�����Z���Ă����˂Ȃ�܂���B
�����ԍ��F10239824
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�u�m�C�Y�̏��Ȃ��M���v���ĉ��ł����H
S/N��̑傫�ȐM���Ƃ����Ӗ��ł��B
�V�O�i���ɔ�ׂăm�C�Y�̊������������Ƃ������Ƃł��B
>��������O�Ɏ���
�u�����Y���̃N�I���e�B�̓����Y���a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v
�Ə����܂�����ˁB�����Ă��Ȃ��͂���ɓ��ӂ��ꂽ�B
�������牽�ŁuF�l�̘b�v�ɂ���ւ��̂��A�S�������ł��܂���B
�����Y�L���a���傫�������W���́E����\�ɗD��Ă��܂��B
������F�l�Ƃ͂܂��ʂ̘b�B�b������ւ��Ă͂��܂����B
F�l�������������Y�́A���邢�œ_�������т܂��B
�����Ō����u���邢�v�Ƃ́A�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ������Ƃ������Ƃł��B
���a���傫���ďW���͂̂��郌���Y�ł��A�œ_������������F�l���傫���Ȃ�Əœ_�����傫���Ȃ��āA���̂Ԃ�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ������Ă��܂��܂��B
�l�Ԃ̖ڂ��A�t�B�������A�f�W�^���̃C���[�W�Z���T�[���A�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ��������Ƃ��u���邢�v�Ɗ����܂��B
�ڂ̎��_�o�A�t�B�����̊����ޕ��q�A�C���[�W�Z���T�[�̃t�H�g�_�C�I�[�h�A�ǂ�������ɓ����������̋����i�ʂ̑����j���傫���قǁA�傫���������邩��ł��B
�����āA�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ������قǁA���ΓI�Ƀm�C�Y�̊��������Ȃ��Ȃ�܂��B
�ł�����A�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L�����Ə����܂����B
�ǂ����킩��܂��H
>�u���ZF�l�v�́u�����Y���̃N�I���e�B�Ɋւ��ăt���T�C�Y�Ɋ��Z����v�Ƃ��������̘b�B�P�Ȃ銷�Z�ł��B�u�����Y���̃N�I���e�B�̓����Y���a�i�̓��j�ɔ�Ⴗ��v������Řb�͐s���Ă�̂ł�
���ꂱ���m�C�Y�̘b�͂ǂ��ɍs���Ă��܂����̂ł��傤�H
�s�����w����
�������낢�b�����ĉ������܂����B
>�u���ɏœ_���� �Smm �e1.0 �Ƃ��������Y�ƁA�Wmm �e1.4�Ƃ��������Y���������Ƃ���ƁA��ʓI�ɐ��������ʂ�̂͌�� �i�Wmm �e1.4 �����Y�j�v
���̂킯�́u�����_����������v�ƁA�Ƃ肠���������Ă��������ł����ł����H
�����ԍ��F10239935
![]() 4�_
4�_
���s�̂�������
���������������Ƃ�����܂����̂Ł@�ˑR�̗�����������������
�@���ZF�l�ׂ̍����b�͘b�͂悢�ł�����
�@�t���T�C�Y�Ƀt���T�C�Y�p50mm F2��t���@�K���I�o�@ISO100�@1/60�@F5.6�̎�
�@�t�H�[�T�C�Y�ɓ��������Y��t�� ISO100�@�P/60 �ɂ����ꍇ F�l�������ɂ���@�K���I�o�������܂����H
�@
�����ԍ��F10239977
![]() 1�_
1�_
�� F�l�������ɂ���@�K���I�o�������܂����H
���l������ISO100�ƌ����Ă��A�掿�͓�i�̍�������܂�����A
F�l�������̏ꍇ�A���ʂ͓�i�̍�������ƕ�����܂��ˁB
���̓�i�̍������邩�̐����́A���{�I�ɖʐς̍������邩��ł����A
���_�Ǝ�����Y��ɍ����܂��B
�B��ꂽ�ʐ^�����āAF�l��ISO�l�Ȃǂ̐��l�����ŗǂ���Ƌ�Ȃ�
������l�̏���ł��傤���b�͈Ⴂ�܂��ˁi�J�����̎ʐ^���B��ȊO�̉��l�̋c�_�H�j
�����ԍ��F10241022
![]() 0�_
0�_
�� ������F�l�̃����Y�̕����L�����Ə����܂����B
����͌��킸�ɂƕ��������������܂��B�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������̏ꍇ�ł��B
�T�C�Y���������P���ɔ�r�ł��܂���B�Z���T�[�̖ʐϔ������Ĕ�r���Ȃ���ł��B
�����ԍ��F10241038
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� �Q����A
�]�k�ł����A���xISO�l���ɓ����̂��{���]�|�ȍl���ł��B
�≖�̎��͋Z�p�̐����Ő�ɓ����K�v������܂����A�{���͂����ł͂���܂���B
�f�W�^���ł͎������x�@�\������܂�����A�}�j���A���ݒ�œK���I�o�̓J������
�C���邱�Ƃ��ǂ�����܂��i�y���^�b�N�X��A�j�R�����g���₷���ł��j�B
�ʐ^�Ƃ��Ă͊��������G�l���M�[�̗ʂ��d�v�ŁA�K���I�o�ׂ͍����Z�p�̖��ł��B
�K���I�o�ł��Ȃ������̂́A���т𐆂����ɏł����Ƃ��Ɠ������x���̘b���ł��B
�����ԍ��F10241087
![]() 0�_
0�_
�@ISO���x�@F�l�@�V���b�^�[�X�s�[�h�́@���˂�������K���I�o�Ɏ����Ă������ł�����
�ʐ^�ɂƂ��Ĉ�ԑ厖�Ȃ��̂Ŗ����̂ł��傤���H
�@�܂��K���I�o�ŎB�������̓��m���r���Ȃ���@�Ⴆ�t�H�[�T�C�Y�ƃt���T�C�X�̔�r���ł��Ȃ��̂ł́H
�����ԍ��F10241098
![]() 4�_
4�_
�� �ʐ^�ɂƂ��Ĉ�ԑ厖�Ȃ��̂Ŗ����̂ł��傤���H
��O�̃J�L�R���Q�Ƃ����炨������Ǝv���܂����A�Ԉ���Ă͂����܂��A��ԑ厖�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
���т𐆂����ɁA���Ă̗ʂɍ����Đ��̗ʂ�����̂����ʂŁA�t�͕��ʂ���Ȃ��ł��傤�B
�掿�A�h�{�������߂�̂��A�܂��͂��Ă̗ʂŁA���̗ʂł͂���܂���B���̗ʂ��Ԉ������
�ł��ĉh�{��������܂��������邱�Ƃ��Ȃ��ł��̂ŁA�ׂ����Z�p���ƕ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10241137
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
>���l������ISO100�ƌ����Ă��A�掿�͓�i�̍�������܂�����A
F�l�������̏ꍇ�A���ʂ͓�i�̍�������ƕ�����܂��ˁB
���ƃ��{�}�� 2����̂�����ւ̂������ɂȂ��Ă܂���B
>����͌��킸�ɂƕ��������������܂��B�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�������̏ꍇ�ł��B
�T�C�Y���������P���ɔ�r�ł��܂���B�Z���T�[�̖ʐϔ������Ĕ�r���Ȃ���ł��B
�ЂƂ̉�f�Z���T�[���瓾����V�O�i���ɂ��ď������̂ł����B
���ƃ��{�}�� 2����ւ̕ԐM���Y���Ă��܂����A���������l�̏��������Ƃ�������Ɠǂ�ł���ԐM�ł��܂��H
>�≖�̎��͋Z�p�̐����Ő�ɓ����K�v������܂����A�{���͂����ł͂���܂���B
�t�B�����ŎB�e�E�����������Ƃ͂���܂��H
�I�o�ɂ��킹�Č��������A�ォ�犴�x�����킹�邱�Ƃ͕��ʂɂ��Ă��邱�Ƃł���B
�]�k�ł����B
�����ԍ��F10241156
![]() 4�_
4�_
�t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�́A�傫���Đ��ƁA�������Đ[�����̈Ⴂ�Ɠ����悤�Șb�ł��ˁB
�召��A��[�͏d�v�ł͂Ȃ��A�܂��͌��܂����ʂ̕Ă𐆂��Ȃ���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10241201
![]() 0�_
0�_
Tranquility����A
���x�͂����̋Z�p��i�ŁA�ʐ^�̖ړI�ł��Ȃ��A�]���̊�ł��Ȃ����Ƃł�����
��̋����F�����ł����Ǝv���܂��B
F�l�͂����̘I�o�v�Z�̓���ŁA���̃t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ȃǂ����Ȃ���A
�ʐ^������ł���ʂł͂���܂���B��p�ƌ��a�Ȃ�A�t�H�[�}�b�g�����Ȃ��ėǂ��ł��B
�����ԍ��F10241244
![]() 0�_
0�_
> ���鐯���߂炳�� 2009/09/27 16:41�@[10221959]
>
> �������ʘ_�ł����A4/3�̒����̓{�f�B����������������邱�Ƃł��B
> �Z���͓������a�̃����Y�́A35�~�����̂��̂���i�傫���d���Ȃ�܂��B
> ����͑���a�ł��Ȃ������̈�ŁA�o�ϐ����������ቺ���錴���ł�����܂��B
> ���̌����̌����A�܂�4/3�V�X�e���̖��_�́A�펯����v�ɂ���Ǝv���܂��B
�u�������a�̃����Y�́A35�~�����̂��̂���i�傫���d���Ȃ�܂��v���Ă��Ƃ́A�C���[�W�T�[�N�����傫��������Y�͏������y���Ȃ�A�C���[�W�T�[�N�����������Ȃ�����Y�͑傫���d���Ȃ�Ƃ������H
�o�L�ڂ��r�������B�k�ق̂͂��܂�B
�u�܂�4/3�V�X�e���̖��_�́A�펯����v�ɂ���Ǝv���܂��B�v�����v���������͉��ł����H
> ���鐯���߂炳��@2009/09/30 23:21�@[10239100]
>
> ��p�ƌ��a�������ł���A�œ_������F�l�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƊW������܂���B
�ȂA�����Ă邶���B�����Y�̑傫���A�d���́u��p�ƌ��a�v�ɂ���č��E����A�u�œ_������F�l�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƊW������܂���v�ɂ͓��ӁB
> ���鐯���߂炳�� 2009/09/29 01:52�@[10229766]
>
> �܂����ł��A4/3�̉掿�������̂��������Z���T�[�̓d�C���\���Ⴂ�Ǝv����������܂���
> ����͈Ⴂ�܂��B�P�ʖʐς̓d�C���\�́A�R���f�W�ł��AD3�ɕ����Ȃ��قǍ����ł��B
> �掿�̈Ⴂ�́A�P�ʖʐς̓d�C���\�ł͂Ȃ��A�P�ɏW���ʐς�����������ł��B
>
> ���̃V���b�g�m�C�Y�͘_���I�ɍ����ł��Ȃ����E�ł���A���̑O�ɉ�X�l�Ԃ͖��͂ł��B
> ����͉i�v�@�ւ�A�����E�G�l���M�[���Ȃ����琶������Ɠ�����Փx�̖�肾�Ǝv���܂��B
�u���̃V���b�g�m�C�Y�v�Ƃ́A1��f�P�ʁi�������͒P�ʖʐϓ�����j�Ō��ׂ��ۑ�ɑ��A��i�ł́u�P�ʖʐς̓d�C���\�ł͂Ȃ��A�P�ɏW���ʐς�����������ł��B�v�ƌ��_�t���Ă���B�S���_�_���قȂ鎖�ۂ��֘A�t�����悤�Ƃ��Ă��܂��B������k�ىƂ̏퓅��i�ł��ˁB
�ȏ�̂��Ƃ��͂��߁A���X�̃I�����p�X�X���ւ̓��e����A���鐯���߂炳��́A���܂��܂��k�ق���g����4/3���l�K�L���������������̃A���V�����Ɏv���ĂȂ�Ȃ��ł��B
�����ԍ��F10241260
![]() 7�_
7�_
> ���鐯���߂炳��@2009/09/27 16:22�@[10221874]
>
> �J�����͎ʐ^���B�铹��ł��̂ŁA�����܂ŎB��ꂽ�ʐ^�Ŕ��f���錋�ʘ_�ł��B
> �d�g�݂𗝉��ł��Ȃ����A���ʂƂ��Ă͑S�ē�i�̍��ɂȂ����킯�ł����A
>
> ���ʂ����āAF�l�������Ƃ��������Ă��Ӗ�������܂���B
>
> ���ʂ͓�i�̍��ł����A����ɑ��Ă̔��f�̓��[�U�[�����ꂼ�ꂵ�܂��B
> ���͔�ʊE�[�x�s���ɔY�܂���鎞���ǂ�����܂����i�掿�ƃg���[�h�I�t�ł��܂����j
> �Y��ɎB�ꂽ�ʐ^�ɂ킴�ƃm�C�Y�����ĕҏW����̂�����܂���B
��i�̈Ⴂ���ǂ̒��x���ʂɉe������̂ł��傤�H
��i�Â����ƂŌ����I�ɉ������Ȃ̂ł����H�@�[���Ȗ��邳���������ʑ̂ł���A���ʂɓ�i�Ƃ��l�i�Ƃ��i��ł���H�@����Ƃ��A���A���Ɏʐ^�B�e�̌o�����������Ȃ̂ł����H
�C���[�W�Z���T1��f������̎���ʐς��������Ə[���ȘI�o�������Ȃ��ꍇ�m�C�Y�������Ȃ�̂͊��o�B�����ے肷�����͂���܂���B
�[���ȘI�o�������Ȃ��ꍇ�A�X�g���{�Ȃǂ̕⏕�����g�p����Ηǂ������̘b�B
���Ȃ��������Ă���ʂ�A�w�����܂ŎB��ꂽ�ʐ^�Ŕ��f���錋�ʘ_�ł��B�x�ł���Γ�i�̍��Ȃǎ��ɑ���Ȃ��v���ł��ˁB
> ���鐯���߂炳��@2009/09/29 03:03�@[10229923]
>
> ��f���������̏ꍇ�͗������₷���Ǝv���܂����A
> ��f��������Ă���i�̍��͕ς�܂���B��f�P�ʂŌ���K�v������܂���B
>
>
> ���鐯���߂炳�� 2009/09/29 10:15�@[10230595]
>
>�i�O���j�W���ʐς����{�̓�i�̍��͉i�v�s�łł��B
�����]����i�̘I�o���Ɏv�����ꂪ������̂悤�ł��ˁB
�����x���Ȃ�������A�������Ȃ����i�̍��ŔY�܂��Ă���̂������Ă��������B
���������A�C���[�W�T�[�N����4����1�̖ʐς������i�̍��ɂȂ�Ƃ����̂́A�S�����ӂł��Ȃ����_�ł��B
������x�A�J�����̕�����b�����蒼���Ă݂Ă��������B
���Ԃ�A2�N��Ƃ��A���鐯����̏����ꂽ���e�������œǂݕԂ��ƁA�p���������Ȃ�Ǝv���܂���B
�����ԍ��F10241276
![]() 5�_
5�_
Tranquilit����I�͂���Ȉӌ����݂܂���B
���I�o�ɂ��킹�Č��������A�ォ�犴�x�����킹�邱�Ƃ͕��ʂɂ��Ă��邱�Ƃł���
�@20�N�߂��v�����{�ɂ����̂Ł@�����@�v�����g�̎��́@���ʂ̐l���@�m���Ă������ł��B
���������̂��Ƃ������Ă���̂���@�B�e�O��ISO���x�����߁@����ɍ��킹�Č�������͂��ł��B
���������������ƌ����܂���
[10226627]���@����Ή���Ǝv���܂���
�@�����ӌ��Ƃ��ā@2�i�×��_���́@�Z���T�[�̖��ł����ā@F�l�Ƃ͐藣���ā@�c�_���Ă��炢�����ł��B
�@
�����ԍ��F10241279
![]() 0�_
0�_
> ���s�̂������� 2009/09/28 01:33�@[10225138]
>
> �u�掿�͔�ʊE�[�x�Ō��܂�v�͐^���ł����A
> �掿�̂��߂Ɏʐ^�\�����̂Ă�͖̂{���]�|�B
>
> �u��͏������˂�v�ŁA�傫���t�H�[�}�b�g�ōi��Δ�ʊE�[�x��[���ł��܂����A�����ɂ������̂͂��������B
> ��ʊE�[�x���[���̂��D���Ȃ�R���f�W�������B
�w�u�掿�͔�ʊE�[�x�Ō��܂�v�͐^���ł����x���^���ł͂���܂���B�^���ƌ�����E�C�͔F�߂邪�A��͂�f�l�̔��z�B
�W���ʐ^�ŁA�őO��ɂ����s���g������Ȃ��悤�Ȕ�ʊE�[�x�̐ʐ^���B�ꂽ�ꍇ�u�掿���ǂ��v�Ƃ͌���Ȃ��B
��ʊE�[�x�́A�����Y���\�̈ꕔ�ł͂��邪�A��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�ʐ^���u�|�p�v�ƌ��邩�u�L�^�v�Ƃ��Č��邩�Ŕ�ʊE�[�x�̉��l���ς��B
����ɂ���ĉ��l���ς����̂��A���������̉��l�ς݂̂Łu�^���v�ƌ�����̂͗��\�ł��B
�����ԍ��F10241295
![]() 7�_
7�_
�펯����v�Ƃ͎��ӌ����̈Ӗ��ł����i����ZD14-54�̎��ӌ����͏��Ȃ��Ȃ��ł����j
���ʂ��瓯����p�E���a�̃����Y���ׂāA4/3�̕���������������ƕ�����Ǝv���܂��B
�ꕔ�i���\���������m��܂���H�j�̃��[�U�[�́A�������Z���T�[�̉掿���ǂ��Ȃ��̂��A
�d�C���\�̍��������ƌ������܂����A�����ł͂Ȃ��Ɛ������܂����B
�����ʐϔ�̍��͉i���I�Ɏ�菜�����Ƃ̂ł��Ȃ����ł��B
�d�C���\�̉��P�ő傫�ȃZ���T�[�ɒǂ��������C�����͕�����܂����A
����͑傫�ȃZ���T�[���������P���ł��Ȃ��ƌ����O��������K�v�ł��ˁB
����4/3�̉掿�͋Z�p�̍������ē�i�ȏ゠��Ǝv���܂����i�O�i�͗ǂ������܂��j�A
�撣���ē�i�܂łł���Ǝ��͎v���܂��B��������A������p�ƌ��a�̃����Y������A
35�~�����ɕ����邱�Ƃ�����܂���i���P�ʂ̍���f���ɂȂ�Ƒ����Ⴄ�����ł����j�B
��4/3�̐��\�Ή��i������āA35�~�����̋@�ނ��l�i���啪�����Ȃ��Ă܂�����A
�����܂Ŋ撣��邩�s��������܂��B
�܂��A�P�ʖʐς̓d�C���\�ł����A����͌������₷���\�������m��܂���B
���ۏ������Z���T�[�̕����P�ʖʐς̐��\�������ł��i�ʐςƊW�Ȃ����\�j�B
����ɂ��Đ[���@�肽���ł�����A�܂������b���܂��傤�B
�����ԍ��F10241338
![]() 0�_
0�_
���ƃ��{�}�� 2����
����ɂ��́B
�ǂ����ł����b�ɂȂ��Ă�����������܂���ˁB
>���������̂��Ƃ������Ă���̂���@�B�e�O��ISO���x�����߁@����ɍ��킹�Č�������͂��ł��B
�͂��A���ʂ͂����ł��ˁB�ł��A�B�e�Ώۂɂ���Ă͂������̐��������ɃV���b�^�[�X�s�[�h�ƍi�肪���߂��Ă��܂����Ƃ�����܂���ˁB���̂悤�ȏꍇ�͍Ō�ɕK�v�Ȋ��x�����܂��ł��B
4×5���̃|�W�Ȃǂł́A�e�X�g���������Ă���{�ԂŔ��������邱�Ƃ��悭����܂����B
���̂悤�ȑ�����u�ォ�犴�x�����킹��v�Ə����܂����B
����ȕ��͂Ő\���킯����܂���B
>2�i�Â����_�́@�Z���T�[�̖��ł����ā@F�l�Ƃ͐藣���ā@�c�_���Ă��炢�����ł��B
�����ł���܂��B
�����Ƃ��A�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ���u�Â��E���邢�v�ŕ\������̂���߂Ă��炢�����̂ł����B
�����ԍ��F10241360
![]() 3�_
3�_
������Ƃ����ʂ�܂��˂���A
�掿��i�̍�������̂������ł����A��i�̍��������Ă��\��Ȃ��Ƃ����ӌ��͔��_���܂���B
����̓��[�U�[���ꂼ��A������Ƃ����ʂ�܂��˂���Ȃ炲���g�Ō��߂邱�Ƃł�����B
�����g��4�`5�i�̍��̂���R���f�W���g���Ăč\��Ȃ��Ƃ������d���Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10241371
![]() 0�_
0�_
�� F�l�Ƃ͐藣���ā@�c�_���Ă��炢�����ł��B
���_���肫�łǂ��藣�����Ƃ͂���܂���B�œ_������F�l���ʐ^�̌��ʂ�����ׂ��ƌ����Ă܂��B
���ʂƂ��ē�i�Â��Ƃ��������܂���A����F�l�ł͓�i�Â��Ƃ����킯�ł��B
�t�ɎB��ꂽ�ʐ^�����炩�ɈႢ�܂��̂ɁAF�l������������ƌ������Ȃ�̈Ӗ�������ł��傤���H
�����ԍ��F10241395
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�w�掿��i�̍�������̂������ł����A�E�E�E�x�����������ł����B����Ɍ��ߕt���邩��A���V�ƌ����Ă�̂ł��B
�����āA���x�́u���邳�v�ł͂Ȃ��A�u�掿�v�ł����H
�����������k�ق͂�߂Ă��������ˁB
���邳�Ɖ掿���ǂ̂悤�ɊW����̂ł��傤�H
���������A���鐯����́u4/3�̃����Y�͓�i�Â��v�Ƃ̏����݂���������͖̂ڂɂ��Ă���܂��B
�������A��i�Â��Ȃ�Ɖ掿�������Ȃ闝�_�͔�߂��ł��B
�I�o���s�������Ɠx�ł̎B�e�́A�C���[�W�Z���T�[�̐��\�ɑ傫�����E�����̂͌����܂ł�����܂��A�[���ȏƓx��������ꍇ�A��i�́u�掿�v�̍����Ă���̂ł��傤���H
�i����i�i��A�V���b�^�[���x��x������B
�i����i�J�����A�V���b�^�[���x��Z������B
���āA���̏ꍇ�A�u�掿�v�ɂǂ�قǂ̍����ł�̂ł��傤���H
�U�X���o�ł����A��ʊE�[�x���掿�Ƃ����O��ł��b�����Ă��܂��B
����́u�掿�v�ł͂Ȃ��A�u�\�����@�v�ƌ����ׂ��ł���ˁB
�����ԍ��F10241443
![]() 7�_
7�_
> ���鐯���߂炳��@2009/10/01 13:37�@[10241338]
>
> �펯����v�Ƃ͎��ӌ����̈Ӗ��ł����i����ZD14-54�̎��ӌ����͏��Ȃ��Ȃ��ł����j
> ���ʂ��瓯����p�E���a�̃����Y���ׂāA4/3�̕���������������ƕ�����Ǝv���܂��B
> �i�ȉ����j
�Ȃ��A�w���ʂ��瓯����p�E���a�̃����Y���ׂāA4/3�̕���������������ƕ�����Ǝv���܂��B�x�ƌ������̂ł����H
�o�L�ڂ������Ȃ��ł��������B�o�L�ڂłȂ��̂ł���A�o�������Ă��������B
���ӌ��ʂ̒ጸ���́A���a�͊W����܂���B�����Y�̉�p�ƃt�����W�o�b�N���̃C���[�W�Z���T�[�ւ̎��ӕ��̓��ˊp�����ƂȂ�܂��B
�t�H�[�T�[�Y�V�X�e���ł́A�e���Z���g���b�N�������߂���{�v�ł��̂ŁA������p�̃t���T�C�Y�V�X�e���ɂ������Ƃ����ʐ��\�ƂȂ�͂��ł��B
����������A�t�H�[�T�[�Y�V�X�e���̃C���[�W�T�[�N�����������Ƃ����������A�e���Z���g���b�N�������߂���Ƃ��������ɂȂ�̂ł��B
���x�������܂����A�f�l�̎v�������k�ق�J����͎̂��߂Ă��������B
�����ԍ��F10241746
![]() 9�_
9�_
�t�H�[�T�[�Y�V�X�e�����A�Z���T�[�T�C�Y�����������䂦�ɁA�t���T�C�Y�ɏ�������B
http://www.four-thirds.org/jp/fourthirds/index.html
�����ԍ��F10241769
![]() 4�_
4�_
������Ƃ����ʂ�܂��˂���
�����Ԃ�O�@���̃T�C�g�\���������L��̂ł����@�����ɃX���[����܂����B
�@������@���낢��ȃT�C�g�Ł@2�i�Â��Ƃ����a�Œނ莅������Ă���l������ƂƎv���܂����@�����ނ��Ȃ��悤�ɂ������Ǝv���܂��B
�ł́@���̃T�C�g���炱��Ł@���炳���Ă��������܂��B
�����ԍ��F10241947
![]() 9�_
9�_
>���_���肫�łǂ��藣�����Ƃ͂���܂���B�œ_������F�l���ʐ^�̌��ʂ�
>����ׂ��ƌ����Ă܂��B
>���ʂƂ��ē�i�Â��Ƃ��������܂���A����F�l�ł͓�i�Â��Ƃ����킯�ł��B
����ς�Â���ł�����
�����ԍ��F10243028
![]() 0�_
0�_
�y4/3�z�Ƃ����͍̂�דI�ŃI�����p�X�̖��x�̖ڐ�̌떂�������Ǝv���܂��B
�y�S���̂P�z�ƕ\�L���Ă��炦�Ί��Ⴂ���čw�����鏉�S�҂�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F10244124
![]() 1�_
1�_
Tranquility���� �� [10239935] �ɂ��āB
�u�P�ʖʐς�����̐��\�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɖ��W�ŊF�����v
�Ƃ́A���� ���鐯���߂炳�� �ɂ���āA���ꂱ�����x�����x���J��Ԃ�������Ă������Ƃł��B
���ɂȂ��Ă���Ȃ��ƌ����Ă���悤�ł́A���Ȃ��͎��̌����Ă��邱�Ƃ������������Ă��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
[10229698] �ȍ~�̎��̏������݂�ǂ�ł݂āA�킩��Ȃ����ƁA�^��Ɏv�����Ƃ���������܂����₵�Ă݂Ă��������B
���ƁA��̕���
�u����f���̃t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�́A�t�H�[�T�[�Y�̌��ʂ� 1/4 �Ȃ̂œ�i���̃Q�C���A�b�v������ł��邩��m�C�Y�������v
�Ƃ�����|�̏������݂�����A�����ߋ��ɂ��������������݂��������Ƃ�����܂����A���͂��̐����͊ԈႢ�ł��B
�Q�C���A�b�v�ɂ���� S/N��͕ς��܂���B���ʂ����Ȃ����̂̌��V���b�g�m�C�Y�̑������m�C�Y�̑��������ł��B
�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l�����܂���B
�����ԍ��F10244233
![]() 0�_
0�_
>�@�t���T�C�Y�Ƀt���T�C�Y�p50mm F2��t���@�K���I�o�@ISO100�@1/60�@F5.6�̎�
>�@�t�H�[�T�C�Y�ɓ��������Y��t�� ISO100�@�P/60 �ɂ����ꍇ F�l�������ɂ���@�K���I�o�������܂����H
[10239977]
F5.6 �ł��傤�B���ꂪ�����H
�����ԍ��F10244255
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������A�����́B
�v���Ԃ�ɔ`���ɗ�����A�������^�C�����[�ȏ������݁B
�����u����f���̃t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�́A�t�H�[�T�[�Y�̌��ʂ� 1/4 �Ȃ̂œ�i���̃Q�C���A�b�v������ł��邩��m�C�Y�������v
�Ƃ�����|�̏������݂�����A�����ߋ��ɂ��������������݂��������Ƃ�����܂����A���͂��̐����͊ԈႢ�ł��B
����A���̏������݂ł��ˁB
���������́A���R������܂���ł������A�u���V���b�g�m�C�Y�v�ɂ��Ă��낢�뒲�ׂĂ��邤���ɁA�Ԉ���Ă����i�[���ċC�����Ă��܂����B
�{���I�ɂ́u���V���b�g�m�C�Y�v���������ƍ��ł͎v���܂��B
�u���ZF�l�v�Ɋ�Ȃɔ�������Ă���l���@�����܂��������Ȃ���u���V���b�g�m�C�Y�v�ɂ��Ĉ�x�A��������Ă݂�������ł��傤���B
���̐�̓W�J�Ƃ��āA
�u�Ȃ��A�t���T�C�Y�̃����Y�̓t�H�[�T�C�Y�̃����Y�ɔ��2�i�i��Ǝ�������ӌ��ʒቺ����a�H���قړ����ɂȂ�̂��H�v
�u�ʐ^���ӏ܂���T�C�Y���t�H�[�T�C�Y�̓t���T�C�Y��1/4�ɂ���Ɗ��Z�l�́A�����Ĕ�ʊE�[�x�͂ǂ��Ȃ�̂��H�v
�ȁ[��Ă��Ƃ��l���Ă܂��B
�����ԍ��F10244617
![]() 0�_
0�_
�u�Q�C���A�b�v�ɂ���� S/N��͕ς��Ȃ��v�ł��B�m�C�Y�������邯�ǁA�V�O�i���������邩��B
�ł��Q�C���A�b�v���邱�Ƃ� S/N�䂪�����̂��ꂿ�Ⴄ�i�悭�킩��悤�ɂȂ�j���Ă̂͂���܂��B
>�u�ʐ^���ӏ܂���T�C�Y���t�H�[�T�C�Y�̓t���T�C�Y��1/4�ɂ���Ɗ��Z�l�́A�����Ĕ�ʊE�[�x�͂ǂ��Ȃ�̂��H�v
���Z���Ă����̂͌��ǁu��r�v���邱�ƂȂ̂ŁB�T�C�Y�𑵂��Ȃ��Ɣ�r���悤���Ȃ��̂ł���ˁB�u���Z�����l�𑵂����Ƃ��̒l�v�ƌ����܂����B
�ł���ʊE�[�x���܂߂��ʐ^�̌������ɂ͋�������܂��B
�����ԍ��F10244670
![]() 0�_
0�_
�W���ʐς̍��A���V���b�g�m�C�Y�̏�Q�������ł�����A
�m�[�x���܂ƁA�M�ꓙ�����ˉԑ���͎O�N���A�ؑ��ɕ��q�܌ܔN�������������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10244683
![]() 0�_
0�_
��p�������AF�l�������̏ꍇ�A4/3��35�~�������K��
�@�� �����掿�i���x�掿�j�͓�i�����i��i�Â��j
�@�� ��ʊE�[�x�͓�i�[��
�@�� ��܃{�P�͓�i�傫���Ȃ�
�̎ʐ^���B��܂����AF�l�������̈Ӗ��́A�S�Ă���i�̍��ɂȂ�̂ł��ˁB
������Ɛ������āAF�l���i����������A�����ʐ^���B���Ƃ������P�Ȃ�ł����A
���̒�������F�l�́A����F�l�ƌ����܂��B�ǂ������炻��͌��a���Ӗ����Ă�ƕ�����܂��B
�q���̎�����A����a�E�����a�A���i��l�E��i��l�A�w�Nj�ʂȂ��g���Ă��܂������A
���߂Č�����A��p�������̏ꍇ�A���a���掿����A��ʊE�[�x�A��܃{�P�����߂܂����A
����̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƊW�Ȃ��������܂��B����͑�ϕ�����₷���ł��B
�t�ɍi��l�̓t�H�[�}�b�g���ς�����A�Ӗ��s���Ȃ��̂ɂȂ�܂�����A�J�����A�ʐ^��
�]�����鎞�ɁA�g���ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10244792
![]() 1�_
1�_
�t���T�C�Y����������i�i�邾���Ńt�H�[�T�[�Y�Ɠ����掿�̎ʐ^���B���Ȃ�ā`
�t�H�[�T�[�Y���ăR���p�N�g�Ŗ��ʂ������A���ɃR�X�g�p�t�H�[�}���X�̍����V�X�e�������Ă��Ƃ�����������ł��ˁI
�����ԍ��F10245631
![]() 5�_
5�_
����͋t�ł��B4/3�͔��Ɍ����̈����A���\�Ή��i�̒Ⴂ�V�X�e���ł��B
���^�y�ʉ��̓Z���^�[�T�C�Y�Ƃ���قNJW���Ȃ��A�Â������a���K�v�\�������ɋ߂��ł��B
�ł����A�Z���T�[������������������K�������Ȃ�ł͂���܂���B
����F�l��������A�Z���T�[�T�C�Y�͏d�v�ȗv�f�łȂ��ƕ�����Ǝv���܂��B
4/3�̌��������������́A�Z���T�[�T�C�Y�ȊO�ɂ���܂��B�v�v�z���Ԉ�����̂ł��B
�����ԍ��F10245668
![]() 0�_
0�_
��̓I�ȗ�́A�J�L�R[10225111]�ƁA[10225168]���Q�Ƃ��Ă��������B
�ǂ�Ȏ���ł������Y�̎d�l�A�i���ɑ��Ă̗v���������Ȃ��Ă����܂����A
���̂��ߑ����̑�^�d�ʂɂȂ��Ă��d���Ȃ��ʂ�����܂��B�ł����A4/3�͂�͂�ُ�ł��B
�����ԍ��F10245697
![]() 0�_
0�_
�ł����_�Ƃ��āA�����掿�̎ʐ^���B�����ď����Ă܂���ˁ`
�t���T�C�Y���i�i���ĎB�肽���l�ɂ̓t�H�[�T�[�Y���I�X�X���ł��ˁ�
���₠�t�H�[�T�[�Y�Ȃ��Ȃ����Ȃ��`
�����ԍ��F10245722
![]() 4�_
4�_
�����掿�ŎB���̂ł����A4/3�����Y�͏����a�Ȃ��̂�����ł�������p�͈͋����ł��B
�����掿�ŎB���@�ސݒ�́A4/3�@����펯�Ȃ܂ő傫���d���l�i�������Ȃ�܂��B
����͂����܂Ŏʐ^���B�邽�߂̍l�@�ŁA�ʐ^�ȊO�̂���4/3��I�ԂȂ�b���ς��܂��B
�����ԍ��F10245752
![]() 0�_
0�_
����ς蓯���掿�Ȃ�ł��ˁI
�l�̓t�H�[�T�[�Y���������܂����B
�{�f�B�̉��i�����R�{���炢����̂ɁI
�X�S�����t�H�[�T�[�Y�B
�����ԍ��F10245785
![]() 6�_
6�_
�@���̕����œ����掿�ɂ���Ȃ�A�S�^�R��ISO50���B�e�ł���悤�ɂ��Ă����Ȃ��ƁB
�@���ꂪ�ł��Ȃ��Ȃ�A�t���T�C�Y�łR�i�i���Ă̎B�e�Ɠ����E�E�E���I�ɂ́A����Ȋ����B
�����ԍ��F10245852
![]() 0�_
0�_
4/3�ō����E-3�̐��\�́A���Ђ̒����@�ɖ��炩�ɋy�Ȃ��ł����i���x���\�������Ă��ł��j�l�i�͓����ł��ˁB
4/3�̃����Y�͑�^�d�ʌ����̈������̂�����̂͂���܂ł̘b�ł�������Ǝv���܂��B
�����̌��_��4/3���L�Ȃ��̂ŁA��i�Â������ł͂����܂ň����Ȃ�K�v������܂���B
�� ��i�掿�̍����A
�� ��i��ʊE�[�x�̍����A
�� ��i��܃{�P�傫���Ȃ�̂��A
�������a�i��i�J���i��F�l�̏������j�����Y���g�������ł��܂��B
�Ȃ̂ŁA���X�͗��K�v������܂���B4/3�������������������Ȃ��������͕ʂɂ���܂��B
�����͂ǂ��ł���A4/3�ɗǂ����̂��Ȃ������ł�����A�I��������ς��������ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10245855
![]() 0�_
0�_
�s�����w����A
���Ԉ�ʓI�́A�̊��̍��͎O�i�ƌ����l�������݂����ł��ˁB
�p�i����̃Z���T�[���\�����P����āA�O�i�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�Õ��ȊO�͕ς�Ȃ��ł����AISO50������ΐ����ǂ�������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10245900
![]() 0�_
0�_
�� ����ς蓯���掿�Ȃ�ł��ˁI
�R���f�W�ł����Ɠ����掿�B��܂��i�R���f�W��ISO100�A����ISO1600�`3200�̔�r�j�B
�W�����v�����j���g�����A�n�ʂ��ꂷ���ԃ��V�Ɠ��������Ŕ�ׂ܂��B
�����ԍ��F10245939
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>Tranquility���� �� [10239935] �ɂ��āB
>�u�P�ʖʐς�����̐��\�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɖ��W�ŊF�����v
>�Ƃ́A���� ���鐯���߂炳�� �ɂ���āA���ꂱ�����x�����x���J��Ԃ�������Ă������Ƃ�
>���B���ɂȂ��Ă���Ȃ��ƌ����Ă���悤�ł́A���Ȃ��͎��̌����Ă��邱�Ƃ������������Ă�
>�Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B[10244233]
��������Ș_�_�ŏ����Ă܂����H
���Ȃ��̎���ɓ����āu�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v�Ƃ������Ƃ������Ă����͂��ł����B�����ǂ߂܂���ł������H
���鐯���߂炳��
>������Ɛ������āAF�l���i����������A�����ʐ^���B���Ƃ������P�Ȃ�ł����A
>���̒�������F�l�́A����F�l�ƌ����܂��B�ǂ������炻��͌��a���Ӗ����Ă�ƕ�����܂��B
>��p�������̏ꍇ�A���a���掿����A��ʊE�[�x�A��܃{�P�����߂܂����A
>����̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ƊW�Ȃ��������܂��B����͑�ϕ�����₷���ł��B
>�t�ɍi��l�̓t�H�[�}�b�g���ς�����A�Ӗ��s���Ȃ��̂ɂȂ�܂�����A�J�����A�ʐ^��
>�]�����鎞�ɁA�g���ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B[10244792]
���a�����������̂ł���A�ӂ��ɗL���a��\���uD�v�ŁuD=XXmm�v�ƌ��������̂ł́H
���������Ƃ���́u���ZF�l�i����F�l�H�j�v�ł́A�t�H�[�}�b�g���ς�邲�Ƃɂ��������v�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�u���ZF�l�v�����낦�邽�߂Ɋ��Z�i�����t�H�[�}�b�g���Ƃɂ��������v�Z���Ȃ���Ȃ�܂���ˁB
�z������ɁA�t�H�[�}�b�g���Ƃ̉掿�̈Ⴂ���ʊE�[�x���r����̂���̕��ɂ͕֗��Ɏg����̂�������܂��ǁB
���͕��ʂɎʐ^���B�鎞�ɁA�t�H�[�}�b�g�ɂ����w�n�̎�ނɂ��W�Ȃ��g�p�ł�����a��uF�l�v�̕����f�R�֗��ł��肪�����ł��B
�t�H�[�}�b�g���ς�邱�Ƃɂ���Đ������ʊE�[�x�̈Ⴂ�͖ڂŌ���킩��܂����A����������ʊE�[�x�͍ŏI�I�Ȏʐ^�̎g�p�T�C�Y�ŕς���Ă�����̂ł��B
>4/3�������������������Ȃ��������͕ʂɂ���܂��B
�Ƃ���4/3�����������Ƃ��v���܂��A����͉��ł����H
�����ԍ��F10246051
![]() 8�_
8�_
�����鐯���߂炳��
���낢��ƕ������Ă�����Ă܂��i��
�B�e���ɂ͑S�����ɗ����Ȃ�������������܂��A�������������
�ł̎ʐ^�����ʘ_�Ƃ��ė�������ɂ͖ʔ������ɗ��m���������ł��B
�����A��_�C�ɂȂ�̂ŋ����Ă��������B
>���Ԉ�ʓI�́A�̊��̍��͎O�i�ƌ����l�������݂����ł��ˁB
[10245900]
���̐��Ԉ�ʓI�Ƃ͂ǂ̕ӂ̐��Ԉ�ʂ���ł��傤���H
���̎���̐��Ԉ�ʂɂ́A����ȋ�̓I�Ȕ�r������i�m�C�Y������
�����Ƃ����l�͂��܂��l�B��������͔ے肵�܂���j�l�͂��܂���B
�����Ƃ�������ɂ͑���"��������̂ł��傤�ˁB
���ƁA[10241746]�̂�����Ƃ����ʂ�܂��˂���̈ȉ��̎���ɂ�
����������܂��̂ŋ����Ă��������B
>> �펯����v�Ƃ͎��ӌ����̈Ӗ��ł����i����ZD14-54�̎��ӌ����͏��Ȃ��Ȃ��ł����j
>> ���ʂ��瓯����p�E���a�̃����Y���ׂāA4/3�̕���������������ƕ�����Ǝv���܂��B
>> �i�ȉ����j
>�Ȃ��A�w���ʂ��瓯����p�E���a�̃����Y���ׂāA4/3�̕���������������ƕ�����Ǝv��>�܂��B�x�ƌ������̂ł����H
>�o�L�ڂ������Ȃ��ł��������B�o�L�ڂłȂ��̂ł���A�o�������Ă��������B
14-54�͎��̏�p�����Y�ł����A�u���ӌ����͏��Ȃ��Ȃ��v�Ɗ�������
�Ƃ͂���܂���B���ۂǂ��Ȃ̂ł��傤�ˁH�B�����ł͂Ȃ�����ŋ���
�Ă���������Ƃ��肪�����ł��B
�����ԍ��F10246519
![]() 4�_
4�_
���鐯���߂炳��
���������������߂܂���
�����ԍ��F10246671
![]() 4�_
4�_
���₢��A�Ƃ��Ă��킹�Ă��炢�܂����B
�J�����Ȃ�Ă��̂́A�����̎B�肽���ʐ^���B��邩�ǂ����A����őI�ׂ�����B
���̈Ӗ������ŁA����4/3��I�����܂����B
�����ԍ��F10248050
![]() 7�_
7�_
�Ƃ肠�����B
�e�t�H�[�}�b�g�̔�r
�E�{�P(��ʊE�[�x)
��ʊE�[�x�́A���e�����~�̒��a���B���ʂ̑Ίp����1/1400���ƂȂ��Ă��邽�߁A
��f���ɂ�炸�A�����~�̒��a�͎B����ʃT�C�Y�Ō��܂�܂��B
��ʊE�[�x�́A�T�ˋ��e�����~�̃T�C�Y�ɔ�Ⴕ�A�œ_�����̓��ɔ���Ⴕ�܂��B
���e�����~�A�œ_�������Œ肷��AF�l�ɔ�Ⴕ�܂��B
�܂��A������p�邽�߂̏œ_�����́A�Ίp���̔�ɂ�茈�܂�܂��B
���������āA������ʊE�[�x��F�l�́A�t���T�C�Y�ɑ���APS-C�@��1/1.5(Nikon)�A1/1.6(CANON)�A
�t�H�[�T�[�Y1/2�ƂȂ�܂��B����͒i�����Z����ƁA
APS-C(Nikon): 1.2�i�AAPS-C(CANON): 1.4�i�AFour Thirds: 2.0�i�ƂȂ�܂��B
(�����̌덷�͋C�ɂ��Ȃ��ł�������)
�E���i��{�P(��܂̉e��)
�_�����ɑ��鑜�́A1�_�ɏW�������A��܂ɂ��{�P�܂��B�啔���̃G�l���M�[��
�W������͈͂́A�G�A���[�f�B�X�N�ƌĂ�A�G�A���[�f�B�X�N�̔��a�́A�œ_������
�ˑ������AF�l�ɂ݈̂ˑ����܂�(1.22��F)�B���������āA���i��{�P�̉e��������邩
�ǂ����́A��f�s�b�`�ɂ݈̂ˑ����A��ʃT�C�Y�ɂ͈ˑ����܂���B(�𑜓x���Ⴏ���
�e�������Ȃ��͓̂��R���Ƃ����c�_�͑[���Ƃ���)�B
���̕����ɂ��āA���C���[�̊���̗p���āA�e���������F�l���v�Z���܂��B
�ȉ��Ɏ����܂��B(��=0.55��m�Ƃ���)�B(���C���[��ł͊Â���������܂���)
���ɒi�����Z�����܂��B
D3 / D700: F13 0 (�)
EOS-1Ds Mark III: F10 0.8
D3X: F9 1.0
D300s: F8 1.2
EOS 7D: F6 2.0
E-30 / E-620 etc.: F6 2.0
�o����A����F�l�͏��������܂���ˁB�x�C���[�z��{���[�p�X�t�B���^�ł́A
1��f���Ƃ̕���\�͓����Ȃ����肩�A2��f��藎����Ă��邩������܂���B
�E���x
1��f���W���ł�������͉�f�̖ʐςɔ�Ⴗ��ƍl���Ă悢�ł��傤�B���������āA
���p�ł�����˃G�l���M�[�́A��f�ʐςƘI�����ԂŌ��܂�܂��BISO���x��ݒ肵����
�I�����Ԃ����܂�A�������x�Ȃ�A���˃G�l���M�[�͉�f�ʐςɔ�Ⴕ�܂��B
�����Ă��̃f�W�J���͍Œኴ�x��ISO100�ɂȂ��Ă��܂��B(D3/D700�͒ʏ�ISO200)
���Ή�f�ʐς��ȉ��Ɏ����܂��B
D3 / D700: 1 (�)
EOS-1Ds Mark III: 0.58
D3X: 0.49
D300s: 0.43
EOS 7D: 0.26
E-30 / E-620 etc.: 0.26
���̖ʐϔ䂪���p���Ă�����˃G�l���M�[�̔�ɂȂ�܂��B(�������AD3/D700�͂���
������������Ȃ�)�B�B���f�q�Ŕ�������m�C�Y�͖ʐςɂ͔�Ⴕ�Ȃ��ł��傤�B
���������āA���p�G�l���M�[���������قǑ��ΓI�Ƀm�C�Y�Ɏア�Ɛ�������܂��B
���āA��L�̌��ʂ��F����͂ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F10248164
![]() 7�_
7�_
�������͂ǂ��ł���A4/3�ɗǂ����̂��Ȃ������ł�����A
���I��������ς��������ǂ��Ǝv���܂��B
���鐯���߂炳��ɒ�Ăł����A�����������Ƃ͒��ڃ��[�J�[�Ɍ�������ǂ��ł��傤���H
���Z�e�l�̕\�L���Ȃ����[�J�[�����Ȃ��̂��A�ɂ��Ă������Ŗ₢���킹����Ή����ł��邱�Ƃ��Ǝv���܂���B
�����������ȉ����̓w�͂����Ȃ��ŁA�����������̉��l�ς����������t����̂ōr���Ǝv���̂ŁA���Ў������g�Ń��[�J�[�ɖ₢���킹���Ċ��Z�e�l�ɂ��Ă̕s�����������Ă��������B
�����ԍ��F10248520
![]() 8�_
8�_
1-300����Ƌ��s�̂�������ƁACC��Tranquility����� ^^;
�����ƁA[10230406]����������ɂ�����ƌ��t������Ȃ��������Ȃ��A�Ǝv�����̂ł����A�`���b�g���o�|�����Ă܂��āA�����܂���ł����B
�܂��́A�u���V���b�g�m�C�Y�v���ăm�C�Y�ł��傤���B�Ƃ����b�B
���V���b�g�m�C�Y���āA���ʂ̕����T�O�̌[�֏������̕\���ŏ�����
�u���q�̐������Ȃ��Ȃ�Ɨh�炬�������ł��Ȃ��Ȃ�v
�Ƃ������ł��ˁB�u�m�C�Y��������v�ł͖����u�M���̎���������v�Ƒ�����l�̕��������Ǝv���܂��BS/N��Ƃ����T�O�ɓ��Ă͂߂��S�̎��������邩�AN�̑召���̈Ⴂ�ł��B
[10230406]�ł�N���L���̒l�̏ꍇ�A�Ƃ��܂������A���ʂ̈Ӗ��̃m�C�Y�������o����ꍇ�A�u���V���b�g�m�C�Y���c��v�Ƃ��邩�A�u�h�炬�������ł��Ȃ��v�Ƃ��邩�́A�ł��܂��A�債���Ⴂ�ł͖����ł��ˁB
���������킯�ŁA���V���b�g�m�C�Y�͓���̕����ł̓m�C�Y�Ƃ��Ēʂ�Ǝv���܂����A��ʂɃz�C�Əo���Ēʂ�����̂ł������Ǝv���܂����A���鐯���߂炳��̎n�߂���A�̃X���ł́A�m�C�Y�Ƃ��Ĉ����ėǂ��Ƃ��v���܂��B
�ƁA�������
���V���b�g�m�C�Y��F�l���Ăǂ��W�����ł����H
�Ƃ����̂����Ȃ�ł���B�u�Z���T�[�T�C�Y���傫���������V���b�g�m�C�Y���������ł���v�Ƃ��A�u���ʂ����Ȃ��ƌ��V���b�g�m�C�Y���傫���Ȃ�v�Ƃ����̂ł���Γ��ɖ��Ȃ��Ǝv���܂���B
���������u�Z���T�[�T�C�Y���傫���������_��̉掿�̌��E����v�Ƃ������Ƃɕ���̂���l�͂��Ȃ����A�uF�l���g���������̎d���v�����ȂƎv���܂���B
���V���b�g�m�C�Y�̑傫�������Ō��܂邩�ƌ����A��f������̌��q���Ƃ��ʎq�����Ƃ��͊W����Ǝv���܂����AF�l�͊W�����ł���ˁB
�����̑��ʂ��猩��ƁA���ʂƊ��x�𑵂���F�l��ς����ꍇ�i�܂�I�o���Ԃ�ς���j�Ɍ��V���b�g�m�C�Y�ɉe�����Ȃ���A���ʂ͌��V���b�g�m�C�Y��F�l�Ő������Ă͂����Ȃ��ł��ˁB�ׂ����b�ł����B
�i�ƁA�����Ɓu�V���b�^�[���x��ς���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����l���o�Ă���Ǝv���܂����A���̊��o���Ȋw�����̊�{�Ƒ��e��Ȃ��A�Ƃ������b�ł��B�ƂĂ����ׂȘb�ł��B�j
�����Ő\����܂���B
�����ԍ��F10249125
![]() 8�_
8�_
�� �B���f�q�Ŕ�������m�C�Y�͖ʐςɂ͔�Ⴕ�Ȃ��ł��傤�B
�� ���������āA���p�G�l���M�[���������قǑ��ΓI�Ƀm�C�Y�Ɏア�Ɛ�������܂��B
�ꉞ�������Ă�S�Ẵm�C�Y�̒P�ʖʐς̒l�i�����ʂ��j����x�͕���Ō��܂��B
����덷���傫���āA�m�C�Y�̊Ԃ̑������\�������ق��Y��ɐ���`���Ă܂���B
�܂��A�������Z���T�[�قǗL���̖ʂ�����܂�����i�����x�ɂȂ�ق�ISO�A���v�Ȍ��
��H���G�Ȃ��̂��g���Ă����\�ɂ��܂�e�����Ȃ��j�ǂ��Ȃ邩�́g�m�C�Y�h������
�Â��ėǂ������܂���B�������S�̂͌덷�͈͂ł��̂ŁA�C�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�ꕔ�J�����̍ō����x�͕ςȏ����������߂��A������ƈُ�ł��̂ŏ���ȊO�����肵�܂��B
http://www.dxomark.com/ �̋Ȑ��ōō����x�����̒l�̉�������ɂȂ��ꍇ�A���̎�O�܂ł�
�݂���Y��ɕ���ł܂��B�ō����x�͌v�Z�����ł����牄������ɂȂ��̂������ł��B
�t���T�C�Y��D3�ƃR���f�W��FX100���r���Ėʐϔ�̗\���ƍ����Ă�Ɗm�F���Ă��������B
�����ԍ��F10249392
![]() 0�_
0�_
�͂炽����@�����́B
������肪�Ƃ��������܂��B
�d�q�I�Ȃ��Ƃ͐��ƂłȂ��̂ŏڂ����͒m��Ȃ��̂ł����A���ۂ̂Ƃ�����V���b�g�m�C�Y�Ƃ��Č������q�̗h�炬�́A�ǂ̒��x�̃��x���Ō������̂Ȃ�ł��傤�H
�Ŗ�̃J���X���B�e����ɂ͉e�������邩������܂��A���ʂɓ����̎ʐ^���B�e����̂ɉe�����o��قǂ̌��q�̗h�炬���o��Ƃ͎v���Ȃ��̂ł����B
���s�̂�������͓������i�̃V���h�E���Ɍ��ꂽ�m�C�Y�����V���b�g�m�C�Y���ƌ������Ă��܂����A�����̃m�C�Y�͑��̌����̕��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�����ԍ��F10249430
![]() 0�_
0�_
�� �V���b�^�[���x��ς���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����l���o�Ă���Ǝv���܂����A
�� ���̊��o���Ȋw�����̊�{�Ƒ��e��Ȃ��A�Ƃ������b�ł��B�ƂĂ����ׂȘb�ł��B
�x���V���b�^�[���x�ŕ������ς�Ȃ��̂́A����Ȃ��ƘI�o��������̂ł��ˁB
����ł���B������ʂ���i�ł�����A�V���b�^�[����i�x���A1/4�̑��x���g��Ȃ���Αʖڂł��ˁB
�����ԍ��F10249577
![]() 0�_
0�_
�� �d�q�I�Ȃ��Ƃ͐��ƂłȂ��̂ŏڂ����͒m��Ȃ��̂ł����A���ۂ̂Ƃ���
�� ���V���b�g�m�C�Y�Ƃ��Č������q�̗h�炬�́A�ǂ̒��x�̃��x���Ō������̂Ȃ�ł��傤�H
�≖�̉��w���A�f�W�^���̓d�q�̒m���͂���܂���B
��i�����x�ݒ�Łi��i�I�o�ʂ������āj�ʐ^���B�����番����܂��B
�����Ō����܂��ƁAN �� ��S�ł�����ASNR �� S ÷ N �� S ÷ ��S �� ��S�ɂȂ�܂��B
��i�I�o����������AS�������ɂȂ�܂�����ASNR�͌���1/��2 �� 1/1.4�ɂȂ�܂��B
�����F�l�̈�i�Ɠ������l�ł�����A�o���₷���ł��B
�����ԍ��F10249625
![]() 0�_
0�_
�����ȊO�Ń����N���Љ�Ă���͂��ł����A�u���[�~���O�ƃX�~�A����̌��J���Ă���y�[�W�̃����N���܂ރR�����g�̃����N�ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=9987427/#10078120
��l�Ȗ��邳���B�e���Ă����K���z�̃q�X�g�O�����ɂȂ�A���̉������m�C�Y�Ƃ����A������u���V���b�g�m�C�Y�v�ɂ����̂��ƍl����悢�ł��傤�B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00501610453/SortID=6841288/#6850669
�����ŏЉ�Ă��郊���N���
http://homepage.mac.com/kuma_san/histogram/
�ŁA�i��J���ł͌��a�H�ɂ��q�X�g�O�����̕��z�������ɍL�����Ă��邪�AF5.6�ɍi������ł͗��z�I�ȕ��z�ƂȂ��Ă���B
�����ԍ��F10249651
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �� [10246051] �ɑ���ԓ��͂�͂�
>[10229698] �ȍ~�̎��̏������݂�ǂ�ł݂āA�킩��Ȃ����ƁA�^��Ɏv�����Ƃ���������܂����₵�Ă݂Ă��������B
�ɂȂ�܂��B[10229903] �ł��Ȃ��̕ԓ��͓r��Ă��܂��ˁB
�����g�̔����������g���������邽�߂̓w�͂͂����g�ł��Ă��������B�l�͕K���������e�𗝉����Ĕ������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��B
������̂ł���A�m�C�Y��萫�I�ɕ߂炦��ׂ��ł��傤�ˁB���Ȃ��̓m�C�Y��萫�I�ɕ߂炦�Ă���Ǝv���镔�����ꕔ����������܂��i�I�o���Ԃ̕����j�B����������͈�ʓI�ł͂���܂���B
������B��͂���ʌo���͏d�v�Ǝv���܂��B�}�l�Ȃ�Ȃ�����B�N�ł��ł���Ǝv����������@�͊��ɏЉ�ς݂Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10249661
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �� [10246051] �̌㔼�����ɂ��āB
>���a�����������̂ł���A�ӂ��ɗL���a��\���uD�v�ŁuD=XXmm�v�ƌ��������̂ł́H
����ł͉��̂��߂ɃJ�����ɁuF�l�v������̂��킩��Ȃ��ł���B���̈Ӗ��ł��Y�[�������Y�̉��l���l����ƌ������̂ł����E�E�E�B
���������J���������ɑ��݂��� F�l�̃����b�g���킴�킴���ċ��邱�Ƃ��Ȃ��ł��傤�ɁB
F�l�̈Ӗ��A�����b�g�A���݈Ӌ`�݂����Ȃ̂��l���Ă݂Ă��������B
>���������Ƃ���́u���ZF�l�i����F�l�H�j�v�ł́A�t�H�[�}�b�g���ς�邲�Ƃɂ��������v�Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�u���ZF�l�v�����낦�邽�߂Ɋ��Z�i�����t�H�[�}�b�g���Ƃɂ��������v�Z���Ȃ���Ȃ�܂���ˁB
���������������ł��Ă��܂���ˁB
�f�W�J���̉t���̏��\���ɁAF�l�̕ς��Ɂu���ZF�l�v��\������ςޘb�ł͂���܂����i���Ɓu���ZISO���x�v�Ɓj�B
���Z�œ_�����\�L�͎��̎����Ă���R���f�W�ł͂ł��Ă��܂��B
>�z������ɁA�t�H�[�}�b�g���Ƃ̉掿�̈Ⴂ���ʊE�[�x���r����̂���̕��ɂ͕֗��Ɏg����̂�������܂��ǁB
���̂Ƃ���ł���B
�������A����������O�ɂ��Ȃ��́uF�l�� S/N��͌��܂�v�ƌ����܂����ˁB���������ǂ��������̈ӌ����b��i�߂��ŏ�Q�ƂȂ�܂��i�������������X��₹�����̂��j�B
>���͕��ʂɎʐ^���B�鎞�ɁA�t�H�[�}�b�g�ɂ����w�n�̎�ނɂ��W�Ȃ��g�p�ł�����a��uF�l�v�̕����f�R�֗��ł��肪�����ł��B
���́[�AF�l�̃����b�g��ے肷����̂ł͂Ȃ��ł���H ���ɂǂ����ŏ������Ǝv���܂����A
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000027412/SortID=10096574/#10123437
�uISO���x�v�́A�u�摜�̖��邳�̋K��v�ɂȂ�Ƃ��������b�g������܂��B
���Ȃ̂́A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̈قȂ�J�������m���u����F�l�v�Ŕ�r����y�����邱�Ƃł��B
���邢�́u�g���~���O�ʼn掿�͂��Ȃ��v�Ƃ��ˁB
�قȂ�t�H�[�}�b�g�̉掿���r����Ƃ��ɂ͊��ZF�l�͕֗��Ȃ��̂ł��B
����A�X�e�B�b�`���Ă����Ƃ��́u����F�l�v���֗��Ɗ��ɏ����܂����ˁB�Ō�̔�r�̂Ƃ��ɂȂ��ď��߂Ċ��Z����̂��悢�ł��B
�����ԍ��F10249743
![]() 0�_
0�_
���K���z�����c���V���b�g�m�C�Y�c�������ۂ��u�펯�v�Ƃ��đ������邩�A�u�c�_�̑Ώہv���Ɗ����Ă��܂����������ꓹ�̂悤�Ɏv���܂��B
�����ԍ��F10249790
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
����͌��V���b�g�m�C�Y�������ł����H
���̌����͍l�����܂��H
����Ɏ��������������̂́u�ǂ̂��炢�̔�ʑ̖̂��邳�̃��x���Ō��V���b�g�m�C�Y�̉e�����o�Ă���̂��H�v��
�u�ǂꂭ�炢�̑傫���̃m�C�Y�Ȃ̂��H�v�ł͂���܂���B
����ƁA�������łȂ����̐l�����鐯�J��������̂��咣�Ɉӌ����q�ׂĂ����܂����A������ւ̕ԐM�����肢���܂��B
���s�̂�������
>���Ȃ��́uF�l�� S/N��͌��܂�v�ƌ����܂����ˁB
�ǂ��Ō����Ă܂������H
�����ԍ��F10249800
![]() 1�_
1�_
�� ����͌��V���b�g�m�C�Y�������ł����H
�I�o�ʂɊ֘A����m�C�Y�́A���V���b�g�m�C�Y�̒P�Ɣƍs�Ǝv���ėǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10249858
![]() 0�_
0�_
>�I�o�ʂɊ֘A����m�C�Y�́A���V���b�g�m�C�Y�̒P�Ɣƍs�Ǝv���ėǂ��Ǝv���܂��B
�����́H
�����ԍ��F10249888
![]() 0�_
0�_
����͌��V���b�g�m�C�Y�̒�`�ł�����B
�����ԍ��F10249913
![]() 0�_
0�_
>>���Ȃ��́uF�l�� S/N��͌��܂�v�ƌ����܂����ˁB
>
>�ǂ��Ō����Ă܂������H
>�ł�����A�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L�����Ə����܂����B
>���Ȃ��̎���ɓ����āu�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v�Ƃ������Ƃ������Ă����͂��ł����B�����ǂ߂܂���ł������H
�Ȃ����Ȃ��͐l�Ɏ��₷��̂ł��傤�H
�����ԍ��F10249924
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�l�͕K���������e�𗝉����Ĕ������Ă���킯�ł͂Ȃ��ł��B
�������������������Ȃ�A
>�����g�̔����������g���������邽�߂̓w�͂͂����g�ł��Ă��������B
>���Z�œ_�����\�L�͎��̎����Ă���R���f�W�ł͂ł��Ă��܂��B
����́u35mm���Ȃ牽mm�ɑ��������p���v��\���������ł��ˁB
F�l��ISO�܂Ŋ��Z���ĂȂ��Ǝv���܂����B
���̃J�����̓����Y�̌����ł��Ȃ��J������������p�セ��ŕs�ւ͂Ȃ��ł��傤���A�����Y�������ł���J�����Ŋ��Z�\���Ȃǂ��ꂽ��A�������邾���ł��B
�����ԍ��F10249941
![]() 3�_
3�_
[10249941]
�Ȃ�ł��̘b�ɂȂ�́H
�����ԍ��F10249949
![]() 0�_
0�_
>�Ȃ����Ȃ��͐l�Ɏ��₷��̂ł��傤�H
���Ȃ�������ɓ����Ȃ�����ł��B
�����ԍ��F10249950
![]() 1�_
1�_
�u�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v���uF�l�� S/N��͌��܂�v�Ƃ����Ӗ��ɓǂ߂�̂ł����H
�����ԍ��F10249980
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
>���Ȃ�������ɓ����Ȃ�����ł��B
���₢�₢��B��������ɓ����Ă����Ȃ��͂͂��炩����ł���B���邢�͕����ʐU�������Ƃ��B
�ŁA���Ȃ��ɂ����ƈӌ����q�ׂ�����Ɓu�����Ȃ�قǁA�������������Ȃȁv�Ƃ킩��B
������A���Ȃ����q�ׂ�����b���i�ނ̂ł��B
���Ȃ��̌���������
>�u�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v
���ꂪ�Ȃ��u���鐯���߂炳�� �̌����Ƃ���́A�P�ʖʐς̉掿�̓t�H�[�}�b�g���W�v�Ɠ����ɂȂ�̂��A�����g�ōl���Ă݂Ă��������A�Ǝ��͌����Ă܂��B
���邢�́A�u���鐯���߂炳�� �̈ӌ��v�ƈႤ�ƌ����̂Ȃ�A�Ȃ��Ⴄ�̂��A�ǂ��Ⴄ�̂����������b�B
���Ȃ��̗U���q��ɕt�������Ă�����A���܂ł��I���܂���B
�����ԍ��F10250002
![]() 0�_
0�_
>���₢�₢��B��������ɓ����Ă����Ȃ��͂͂��炩����ł���B���邢�͕����ʐU�������Ƃ��B
�����猩����A���Ȃ��₤�鐯���߂炳�����������ł���B����܂����ˁB
���邢�́A�������������Ƃ�S�R�Ⴄ�Ӗ��ɉ��߂��Ă���悤�ɂ��������Ă��܂��B
�u�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v��
�uF�l�� S/N��͌��܂�v�Ƃ����Ӗ��ɓǂ߂Ă���悤�ȂƂ���ȂǁB
���邢�͂����ƑO�́u���Z�œ_�����v�͕����ʂ��H�̌��ȂǁB
�U���q��Ȃǂ���C�͂Ȃ��̂ł����A����������Ă��邱�Ƃ��킩��Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F10250064
![]() 1�_
1�_
�� �m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L��
�O��������͂����蕪�����Ă���Ηǂ��Ǝv���܂��B
������p�ł͑���a�����Y���K�v�ł����A
�t�H�[�}�b�g�������łȂ���A����a�Ə��i��l�̔��W���������܂���B
�t�H�[�}�b�g���Ⴄ�ꍇ�A����a�ő�i��l�ɂȂ�\������܂��B
�܂�A�Ⴄ�t�H�[�}�b�g���r���鎞�ɁAF�l�����Č��a������Ηǂ��ł��B
���a���{���I�Ȃ��̂ƌ����܂��B
�t�ɁA�t�H�[�}�b�g�������̏ꍇ�AF�l���g�����v�Z�́A�œ_�����ƊW�Ȃ��K�p�ł��܂��B
F�l�̕����֗��Ŏg���₷���ł��B�P�ʖʐς̌v�Z�ł����A�t�H�[�}�b�g���ϐ��łȂ����
�S�̖ʐςƂ̔�Ⴊ���ł��̂ŁA�㗝�Ƃ��Ĉ�a���Ȃ��g���܂��B
���֗̕���F�l�Ɋ���Ă�l�������ł�����A���a�����a�Ƃ͌��킸�g����F�l�h�ƌ����܂��B
�����悤�ɉ�p����p�ł͂Ȃ��g�����œ_�����h�ƌ����Ă܂��B���������ꂽ�Ƃ͌����A
���ꂪ�{���Ɗ�����Ă͂����܂���B�ړI�Ə��������Ȃ���ł��B
�����ԍ��F10250076
![]() 1�_
1�_
���傤���Ȃ��ł��ˁB[10239935] �ɉ����܂��B
>>�u�m�C�Y�̏��Ȃ��M���v���ĉ��ł����H
>
>S/N��̑傫�ȐM���Ƃ����Ӗ��ł��B
>�V�O�i���ɔ�ׂăm�C�Y�̊������������Ƃ������Ƃł��B
�V�O�i����m�C�Y�̒P�ʂ�₤�Ă܂��B
�ʑS�̂ł��̂��A�P�ʖʐςł��̂��A�ɂ���ĕς��܂��ˁB
���邢�͓���f���̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�́u��f�����v�ł��̂��A����f�s�b�`�̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̉�f�����ł��̂��B
>F�l�������������Y�́A���邢�œ_�������т܂��B
>�����Ō����u���邢�v�Ƃ́A�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ������Ƃ������Ƃł��B
���������Ɓu�P�ʖʐρv�ł��Ɨ����ł��܂��B
>�l�Ԃ̖ڂ��A�t�B�������A�f�W�^���̃C���[�W�Z���T�[���A�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ��������Ƃ��u���邢�v�Ɗ����܂��B
>�ڂ̎��_�o�A�t�B�����̊����ޕ��q�A�C���[�W�Z���T�[�̃t�H�g�_�C�I�[�h�A�ǂ�������ɓ����������̋����i�ʂ̑����j���傫���قǁA�傫���������邩��ł��B
���̕ӂ�܂ł͂܂��悢�ł��傤�B
>�����āA�P�ʖʐϓ���̌��̗ʂ������قǁA���ΓI�Ƀm�C�Y�̊��������Ȃ��Ȃ�܂��B
���܂ł̕�������⑫����Ɓu���ΓI�Ɂg�P�ʖʐς�����́h�m�C�Y�̊��������Ȃ��Ȃ�܂��v�ɂȂ�܂��B
>�ł�����A�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L�����Ə����܂����B
������u�g�P�ʖʐς�����h�m�C�Y�̏��Ȃ��V�O�i���邽�߂ɂ́A������F�l�̃����Y�̕����L���v�ƂȂ�܂��B
����� ���鐯���߂炳�� �̈ӌ��Ɠ����ł��B
�u��f�s�b�`�����̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�v�̏ꍇ�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���W�Ɂu���f�� S/N��͓����v�ł��ˁB����F�l�A����SS�A����ISO���x�̏ꍇ�B
����܂��Ď��� [10229698] �ȍ~�̏������݂����Ă��܂��B
�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E
>�f�W�^���J�����ł́A�P��f�P��f���瓾����M���̏W���̂Ȃ̂ŁA���̂P��f�̐M���̎��iS/N��ASNR�j�����ł��B
�u�P��f�̐M���̎��v�Ɓu���̗ʁi��f���j�v�� S/N��͌��܂�܂��B
�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E�`�E
�ȍ~�̏������݂�ǂ߂킩��܂����A�u�t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̉�f���Ⴂ�̏ꍇ�A��f�������������Ȃ����ƈ�v����悤�ɏk�����T�C�Y����AS/N��͈ꏏ�ɂȂ�v�̈ӂł��B
���V���b�g�m�C�Y�Ȃ̂Łi����͗��_�̑O��j�A�u���f�v�����u���v�I�ɗL�ӂȉ�f���v���`���C�X����A���ς̎���Ƀ��x��������l�q���킩��܂��B
�����ԍ��F10250120
![]() 0�_
0�_
����B�Ō�̕��ł��B
>�t�H�[�}�b�g�Ⴂ�̉�f���Ⴂ�̏ꍇ�A��f�������������Ȃ����ƈ�v����悤�ɏk�����T�C�Y����AS/N��͈ꏏ�ɂȂ�v
�uS/N��́g�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̕������ɔ��h�v�ł��B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̕������ƌ����Ă��X��̘b�ŁA����̕W�������g�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̕��������̈�h�ɂȂ邪���m�Ȍ������ł��B
�����ԍ��F10250131
![]() 0�_
0�_
�����̕⑫�ɂȂ邩�킩��܂��B
���̎����Ă����f�s�b�` 1.69��m �̃R���f�W�� ISO100 �ł́A�v�Z����Ɓu8000��v�̐��̌��q����̉�f�ɍ~�蒍���܂��B
����������́u�O�a�M���M���̔��s�[�N���v�̌��q���ł��B�u�O���[�v�͂����� 2.5�i���ł��B�s�[�N��2�i���Ȃ�u2000�v�A3�i���Ȃ�u1000�v�ł��B
���N�̉��������������Y��܂������A�uPC fan�v�Ƃ��̎G���Ƀf�W�J���̃\�j�[�Z�p�҂̃C���^�r���[���ڂ��Ă��܂����B�T�C�o�[�V���b�g�̃R���f�W�ł����A�u��f��ɐ���̌��q���~�蒍���ł���v���čڂ��Ă܂����i�����O���[���͖��������j�B
�R���f�W�̌��q���͂܂�����ȂƂ���Ȃ̂ł��傤�B
�����ԍ��F10250140
![]() 0�_
0�_
>���鐯���߂炳��
>���������������߂܂���
�v�����H
�ǂ��Ǝv���܂���B���̎�̋c�_��
�����ԍ��F10250251
![]() 0�_
0�_
�����������ނ���́@���������̂ł����@�ʔ����u���O���������̂œ\���Ă����܂��B
�@http://mblog.excite.co.jp/user/zuiko/entry/detail/?id=10186662
�@�����������l���Ł@���̖��̓����Y�ł͂Ȃ��@�Z���T�[�̑召�ɂ���ċN������ł���t�H�[�T�C�Y�̃Z���T�[���t���T�C�Y�ɍ��킹��ׁ@�Q�C���A�b�v���@���̈׃m�C�Y�������Ȃ鎖���ƂƎv���Ă��܂��B
�@���̂悤�ȗ��R�Ł@2�i���邢�ł͂Ȃ��@�t���T�C�Y�̕����A�t�H�[�T�[�Y�Δ�Q�i���m�C�Y�����Ȃ��@�ƌ����Ē�����K���ł��B
�@���鐯���߂炳��@�M���̎��������Ă���݂����ł��̂Ł@����̓X���[���Ȃ��œǂ�ł݂Ă����������肢���܂��B
�@ps�@����Ŗ{���ɍŌ�ɂ��܂��B
�����ԍ��F10250253
![]() 4�_
4�_
�Â��Ƃ������t�ɑ��Ē�R��������Ƌ��܂����A
�Â��Ȃ��Ă��A���掿�Ńm�C�Y�������Ȃ��ł�����A����ȊO������肪����ł��傤���H
�Â��Ɖ掿�́A�������Ƃ��Ӗ�����̂��������ĂȂ��ł��ˁi���ꎫ���ׂĂ��������j�B
�����ԍ��F10250262
![]() 0�_
0�_
��ʊE�[�x�A���i��{�P�̈Ӗ��́A���鐯����͂Ȃ����������Ȃ������悤�ł����A
�t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y(D3/D700) �ɑ��Ċ��Z2�i�ł���̂́A�ʁX�̌����ɂ��
�̂ł���A��v���Ă���̂́A��f�����قړ����ł��邽�߂ł��BD3/D700�ł͂Ȃ�
D3X�Ɣ�r����A���ʂ��Ⴂ�܂��B
���������āA���̓_�ł��A�u����F�l�v�����܂�Ӗ��̂Ȃ��͖̂��炩�ł��B
�܂��A�m�C�Y�̌����A��f�s�b�`�Ɉˑ����Ă���̂ł���A�t�H�[�}�b�g�̖��ł�
����܂���B�t�H�[�}�b�g�S�̂ŗ��p����������t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y��1/4��
���邱�ƂƂ͒��ڊW����܂���B�֘A�����邽�߂ɂ́A���鐯���ʁX�̖���
�����Ă����A�掿�Ɋւ��āA��f���Ɖ�f���\�������N������K�v������܂��B
���������A1��f�̗��p������˃G�l���M�[��1/4�ł���Ƃ����̂��A������f���A
�������x�ݒ�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��O��ł��B
�܂��A�\���Ȍ��ʂ�����A�m�C�Y�����ƂȂ�Ȃ��A�����ł́A���p������˃G�l���M�[��
�ʂ��掿�Ɋւ��Č���I�ȗv���ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��͂��ł��B
���������A�J�����{�̂̐��\�������Y�ɉ������āu����F�l�v�Ŕ�r����c�_��
���������̂ł��B�u����F�l�v�����낦��Γ��������ɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�����ԍ��F10250283
![]() 8�_
8�_
�� ��v���Ă���̂́A��f�����قړ����ł��邽�߂ł��B
�� D3/D700�ł͂Ȃ�D3X�Ɣ�r����A���ʂ��Ⴂ�܂��B
��f�͎Q�l�ɂȂ�܂����A��f����ɂ��܂���̂ŁA�ς��Ă����ʂɉe��������܂���B
��́A�ʐ^���B��킯�ł�����A�ʐ^��ʑS�̂ł��B��̓I�ȃT�C�Y�Ɋւ�炸�A
��ʂ̑S���A�S���A�Ίp���Ƃ��ɑ��ē������̕����̔�r�ł���ł��B
�� �܂��A�\���Ȍ��ʂ�����A�m�C�Y�����ƂȂ�Ȃ��A�����ł́A���p������˃G�l���M�[��
�� �ʂ��掿�Ɋւ��Č���I�ȗv���ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��͂��ł��B
�ኴ�x�ʼn掿�������ꍇ�A�l�Ԃ̖ڂ��掿�̕ω��ɕq���ł͂���܂��A����͐l�Ԃ̖ڂ�
���Łi�������͖��Ȃ��j�q�ϓI�ɉ掿���肷��v�����ς����Ƃ��͊W�Ȃ��ł���B
�����ԍ��F10250300
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��́A�掿�������Ə����n�߂��Ă܂����A�O�ɂ������܂������A���_�Ɏ��M�����L��ȗl�Ȃ̂ŃI�����p�X�̔����ŏ�������EOS7D�̔�D90�̔ł��t���T�C�Y�@����i�����i�ȏ�Â��ׂ�܂���A��i�ȏ�掿�������ł���Ə������Ɨǂ��ł��傤�B
���́@������Ȃ�������������@���̂��Ɠ����͔����ė��܂��ˁB
�����ԍ��F10250716
![]() 13�_
13�_
�� �掿�������Ə����n�߂��Ă܂����A
�܂��͉掿�������ł��B���{�I�ɓ�i�̍�������܂�����B
�܂��A�掿�������̂́A�Â��ƈӖ��������ł��B
�ʐϔ�Ƃ����ȒP�ȃ��[���͂��ׂẴt�H�[�}�b�g�ɓK�p���܂��̂ŁA
4/3�����Ǝv������A������Ǝ����ꂵ�����ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10250769
![]() 0�_
0�_
������Ă���̂́A���鐯���߂炳��̕��ł��傤�ˁB
���鐯���߂炳��́A�t���T�C�Y�@�����g���Ė����������g�������������t�H�[�T�[�Y�@�̔ɂ���Ă���APS�@�̔ł́A���������o���Ȃ����_��W�J�����̂������ɂ͗���s�\�ł��B
APS�@�̔ł���̓I�Ɏ��_��W�J���ꂽ�甽�����傫���ċM���ɂƂ��Ă��L�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���H
���������Ɓ@�����ŏ����ׂ����̂ł͖����ł��傤�c
�����ԍ��F10250924
![]() 17�_
17�_
�͂炽����A���v���Ԃ�ł��B
���u�V���b�^�[���x��ς���Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����l���o�Ă���Ǝv���܂����A���̊��o���Ȋw�����̊�{�Ƒ��e��Ȃ��A�Ƃ������b�ł��B�ƂĂ����ׂȘb�ł��B
�@���ׂȘb��������܂��A�V���b�^�[���x��ς���Ɠ����ʐ^�͊�{�I�ɂ͎B��܂���B
��ʑ̂��J�������Î~���Ă���Ƃ�������I�ȏ����̎��ӊO�́B
�ƌ������A���̔�ʑ̂͐Î~���Ă��镨���ƂĂ����������肵�āE�E�E�E
�����ԍ��F10251142
![]() 1�_
1�_
tensor-tan����
�@���鐯���߂炳��́A��ʓI�ȃt�H�[�}�b�g�召�̖������Ƃ��ɂ́A�u���������ρv ���̗p���A�𑜂����܂�l�����Ȃ������Ō��܂��B
�@����Ƃ��Č���܂��A�u����ł��e�������قƂ�ǖ������z�I�ȃ����Y�������ꍇ�v �ŁA���A�u������Ɨ���Ďʐ^�������ꍇ�v �Ƃł������܂��傤���B
�@���̎��Ԃɍ��킹�Č����A�n�Y���̃����Y�킸�ɍςꍇ�ł��傤��w
�@�ʓr�A�R���p�N�g�f�W�J���̂悤�ɁA����ɏ�������f�����悤�ɂȂ�ȂǁA���{�I�ɉ𑜂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A���R�d�v�ȍ��ڂƂȂ��Č���܂� �i���鐯���߂炳��́A���X���̕��ӂɂ���Ă��̐ݒ肪�ς��̂ł����A�ˑR�������猩���l�ɂ͕�����ɂ����Ǝv���܂��j�B
�@����ɑ��āAtensor-tan����́A�𑜑��ɂ�����������������Ǝv���܂��B
�@�����ŁA�u�������O���C�J�[�h�������Ă���ʐ^�v ���B�e�����Ƃ��܂��傤�B
�@�c�O�Ȃ��� �u�O���C�J�[�h�v �̕��𒍖ڂ��Ă݂��ꍇ�E�E�E
�@�ʐ^�̒��ŁA��r�I�ɏ��Ȗʐς`������Ƃ��܂��B
�P�D�@�u�����f�`�v �̖ʐς��`�ŁA16bit �̏��ʂ�����A�O���C�J�[�h���ʂ����ꍇ
�Q�D�@�u�`�̂S���̂P�̖ʐς́A�����f�a�v ���S�W�܂�A12bit �̏��ʂŃO���C�J�[�h���ʂ����ꍇ
�@�u�����f�a�v ���A�����ƂQ×�Q�r�j���O���āA�P�� 16bit ���Ƃ����ꍇ�A�m�C�Y�̗ʂ͂`�Ɠ����ɂȂ邩�ǂ����B
�@���낢�뗝�z��Ԃ��l���������Ƃ��đ�����A�u�����f�`�v �� �u�����f�a×�S�v �́A�������������m�C�Y�ʂƌ������Ƃŗǂ��Ǝv���܂��B
�@���ɁA�\�����邢�����ŎB�e����m�C�Y�����Ȃ����Ȃ��ƌ���������������������ł��ˁB
�@���p��A��肪�Ȃ���Ηǂ��ł��傤�B
�@�������������Ӗ��ɂ����āA�S�^�R���A�R���f�W���g���܂��B
�@����������ł��A���邢�Ƃ���̏����A�傫����f�̕��������͎̂����ł���� �i����������f�̏W���ŁA�g�[�^���̓d�ׂ߂Ă����e�ʂ������̏ꍇ�������ƍl���܂��j�B
�@�ʐ^���B�e�����Ƃ��āA���̒��� �u���邢�����v �� �u�Â������v �������āE�E�E
�@�傫���t�H�[�}�b�g���L���Ȃ̂́A�ʐϔ�S�{�̏ꍇ �� �u�Â������v �� �������t�H�[�}�b�g�ɔ�ׁA�傫���t�H�[�}�b�g�͂S�{�̌�����荞�߂邩��A�Â������̍Č����ɗD���E�E�E�����܂łɗǂ����镶�ӂł���ˁB
�@�������A�u���邢�����v �̌����S�{������Ă���킯�ŁA���̐��m�� �i���̎��j �͂�荂���Ȃ�܂� �i���ʂ͋C�ɂ��Ȃ���������܂��j�B
�@���̂悤�ɂ��ē���ꂽ�ʐ^�́A��ɉ摜�����������Ȃ��Ƃ��A�ʐ^�����H����Ƃ��ȂǂɁA�u���H�ϐ�������v �ȂǂƌĂ�A�d��܂��B
�@�K�v�Ȃ��ł����H�@�����K�v�Ȃ��ł�w�@�E�E�E�Ƃ������A�K�v�ȏꍇ�́A�R���|�W�b�g�����Ȃǂ̕ʂȕ��@�ŏ��̐��m�����擾���܂��B
�����ԍ��F10251277
![]() 1�_
1�_
���鐯���߂炳��
>�Â��Ɖ掿�́A�������Ƃ��Ӗ�����̂��������ĂȂ��ł��ˁi���ꎫ���ׂĂ��������j�B
���̐l�͂ǂ��������炢���̂��킩��Ȃ��Ǝv���܂�����A�o�ŎЖ��E�������E���N�ł̉��y�[�W�ɏ����Ă���̂����L���Ă��������B�i�o�L�ڂ����炻��Ȏ����͂Ȃ��Ǝv���܂����j
��A�̑������������������Ŏ��������͕����邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��B�������ŋM���̍��܂ł̏������݂͂قƂ�Ǐo�L�ځi�{���̌��ۂƌ��Ǝv�����݂������፬���ɂȂ������́j�ł��������Ƃ�����܂����B
�o�L�ڂ������Ȃ����ƁB�r�炳�Ȃ����ƁI���������Ă��������B
����Ȃ��Ƃ���J��Ԃ��Ă���̂Ŏ��ɂ̓l�K�e�B�u�L�����y�[�����s���Ă���悤�ɂ����ʂ�Ȃ��̂ł���B
�����ԍ��F10252093
![]() 13�_
13�_
�� �u���������ρv ���̗p���A�𑜂����܂�l�����Ȃ������Ō��܂��B
����͌���ł��B�S������Ȃ��Ƃ͂���܂���B�𑜂͏d�v�ȗv�f�̈�ł��B
�������A�����掿���c�_���鎞�͉𑜂͊W���Ȃ��ł�����A���͏����Ƃ��Ă͂���܂���B
�����x�掿�Ƃ悭�����܂����A��f�T�C�Y�Ɩ��ڂȊ֘A��������Ɨǂ��������܂���
�������̂悤�Ȍ���ł�����A�����g�Ő������Ă����łȂ����Ƃ��m�F���Ă��������B
�����ԍ��F10253803
![]() 0�_
0�_
>���_�Ɏ��M�����L��ȗl�Ȃ̂ŃI�����p�X�̔�����
>��������EOS7D�̔�D90�̔ł��t���T�C�Y�@���
>��i�����i�ȏ�Â��ׂ�܂���A��i�ȏ�掿��
>�����ł���Ə������Ɨǂ��ł��傤�B
LE-8T����̂��ӌ���1000���^�����܂��A�l�������������Ƃ��������������̂ł��B
�t�H�[�T�[�Y�ɔ�ׂ�APS-C�̃��[�U�[�͗y���ɑ����̂ŁA���ZF�l�_���X�I�ɓW�J�������������L�v�Ȃ��ƂƂł͂Ȃ��ł��傤���H
����ł͊��ZF�l�_�҂̊F�l�A�����APS�̕��ł�낵�����肢�v���܂��B
�����ԍ��F10253816
![]() 10�_
10�_
�����x�掿�͉�f�T�C�Y�i����f�����j�ƑS���ƌ����ėǂ����炢�W������܂���B
�J�L�R[10177214]��ǂ�ł���������Ε�����Ǝv���܂��B
���ۂ͑������邩���m��܂��A���������ł͂Ȃ��A�ׂ����Z�p�ł����A�덷���x�ł��B
�Ȃ̂ŁA�Z���T�[�̊��x�掿���r���鎞�́A�S��ʂ���̉�f�Ƃ��Ĕ�r�������ł��B
�����ԍ��F10253889
![]() 0�_
0�_
�J������
�B�e���Ċy����
���������Ċy����
�������肽�����̂ł��B
���낻�낱�̋c�_���I���ɂ���
�B�e�ɏo�����܂��傤
�����ԍ��F10253915
![]() 9�_
9�_
�������x�掿�͉�f�T�C�Y�i����f�����j�ƑS���ƌ����ėǂ����炢�W������܂���B
�����ۂ͑������邩���m��܂��A�덷���x�ł��B
�����唻�ƃR���f�W�̉掿�̈Ⴂ�́A�S���ƌ����ėǂ����炢���Ȃ���������܂���Ǝv���܂��B
���ۂ͑������邩������܂��A�덷���x�ł��Ǝv���܂��B
���Ȃ��Ƃ��S�������ɎB���ʐς݂̂̔�r�ł�����A�唻�ƃR���f�W�̉掿�͊��S�Ɉ�v���܂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10255107
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�������掿���c�_���鎞�͉𑜂͊W���Ȃ��ł�����A���͏����Ƃ��Ă͂���܂���
�@�����ł��B
�@�����A�S�ʃO���[�J�[�h�̏����ɂ��Ă��܂��Ƃ��v���܂��B
�����ԍ��F10255203
![]() 0�_
0�_
������������A�J�L�R�ɊԈႢ���E�E�E �� 2009/10/03 11:36�@[10251277]
�E�E�E����̂ŁA�������܂� �� orz
�@�c�O�Ȃ��� �u�O���C�J�[�h�v �̕��𒍖ڂ��Ă݂��ꍇ�E�E�E
�@�ʐ^�̒��ŁA��r�I�ɏ��Ȗʐς`������Ƃ��܂��B
�P�D�@�u�����f�`�v �̖ʐς��`�ŁA16bit �̏��ʂ�����A�O���C�J�[�h���ʂ����ꍇ
�Q�D�@�u�`�̂S���̂P�̖ʐς́A�����f�a�v ���S�W�܂�A���ꂼ�� 14bit �̏��ʂŃO���C�J�[�h���ʂ����ꍇ
�@�u�����f�a�v ���A�����ƂQ×�Q�r�j���O���āA�P�� 16bit ���Ƃ����ꍇ�A�m�C�Y�̗ʂ͂`�Ɠ����ɂȂ邩�ǂ����B
�@���낢�뗝�z��Ԃ��l���������Ƃ��đ�����A�u�����f�`�v �� �u�����f�a×�S�v �́A�������������m�C�Y�ʂƌ������Ƃŗǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10255675
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
���܂��͉掿�������ł��B���{�I�ɓ�i�̍�������܂�����B
�_���؋��A��r�摜�������Ă���������ΊF����i�����j�[������Ǝv���܂��B
���ۂɌ��������Ȃ���i�̍��ȂǁA���ɂ͈Ӗ�������܂���B
�����ԍ��F10256229
![]() 2�_
2�_
Tranquility����
�����d�q�f�o�C�X�͐��ł͂Ȃ��ł����A�A�Akuma_san_A1����̏Љ�Ă���T�C�g�̐����ŗǂ��Ǝv���܂���B
�����̃f�W�J���ɂ�����h�炬�̉e���Ɨ��_�I���E�͕����čl����K�v������Ǝv���܂��B
�����̃R���f�W�ł͌��V���b�g�m�C�Y�̉e���͑傫���݂����ł����A���s�̂�������̃T���v���͂�����Ƒ傫�����̊��������܂��B(���V���b�g�m�C�Y�͌����I�Ȃ��̂ł�����A�V�����@�킪�o��x�Ƀm�C�Y�����P����悤�Ȏ����̋@��̃m�C�Y�̎x�z�I�v���Ƃ͎v���Ȃ��Ƃ����̂��ŏ��̔��z�ł��� ^^;)
���V���b�g�m�C�Y�ȊO�́u���l�̌^���̃m�C�Y�v���l����ƁA�������u�̂���Ƃ��A�J���[�t�B���^�[�̂���Ƃ��A��f���̗ʎq�����̂���Ƃ��A���낢��l�����܂����A�g�����Z���T�[���v���Ă݂Ȃ���Ε���Ȃ��A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ��ł��傤�˂��B
�����ԍ��F10256495
![]() 1�_
1�_
����͂����܂����B
�����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ɉˑ�����B���Ƃ�����Ȃ��Ƃ́B
��ʊE�[�x�́A�B���ʉ�f�T�C�Y�A���i��{�P�͉�f�T�C�Y�Ȃ�ł����ǁB
�����ԍ��F10256518
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
���Ȃ������������茾���ĂȂ��Ŏ����ł���Ă݂���B
���Ȃ��� Tranquility���� �����������ǁA��������点��Ɖ��̂��Ƃ͂Ȃ��́B�u�ŁH�v���Č��������Ȃ邱�Ƃ���B
����ł��Ⴀ���̌��������Ƃɑ��Ắu����͌��V���b�g�m�C�Y�̃T���v���ł͂���܂���v���ė������ւ���������Ȃ��B���������̂��u��排����v�ƌ����܂��B
���͌��V���b�g�m�C�Y�ɑ��Ă�����x�̒�ʓI�ȕ����Ă܂��B
�Ⴆ�� 1.69��m �̃R���f�W�i�����ȂƂ���ł̓L���m�� G10�j�� ISO100 �̃O���[�͌��q�����悻 1000���x�ƂȂ�܂��i���Ȃ蕝�����ς����āj�B�W������ 32�̌��q�B
����� 8bit �̃f�W�^���摜�Ƀ}�b�v����Ɓi�O���[�����x�� 125 �Ƀ}�b�v�����Ƃ��āj�W�����́u4�v�B
�܂�u�ŋ߂̃R���f�W�� ISO100 �͕��� 125 �𒆐S�ɁA±4 �͈̔͂Ɏ��܂��f�Ŗ�70% ���߂�v�ł��B
APS-C 1200����f������̃f�W�J�����ƁA��� 10�{���x�̉�f�ʐςƂȂ�܂��B��f�ʐ� 10�{�Ȃ̂Ō��q�� 10000�̕W���� 100�B
����� 8bit �摜�Ƀ}�b�v����ƕW������ 1.25�B
�܂�u�ŋ߂� APS-C �� ISO100 �͕��� 125 �𒆐S�ɁA±1 ���x�͈̔͂Ɏ��܂��f�Ŗ�70% ���߂�v�ł��B
������z���镔���͎B�e�����̈����i���C�e�B���O�A�O���[�J�[�h�j��A�f�W�J���Ɍ��X����m�C�Y�Ƃ������Ƃł��傤�B
�����ԍ��F10256836
![]() 0�_
0�_
�Ⴆ�O���[�J�[�h����Ȃ��ĕ��ʎ��i�R�s�[�p���j�̎B�e�����ǁA
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8512335/ImageID=139915/
��������̓i�ڂ̌��l�^��
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211147/SortID=8512335/ImageID=139927/
������j
�����ł��A������x�̌X���͂킩��܂��B
�t�H�[�T�[�Y�̐l���āA���������摜�o���Ă����ׂ邱�Ƃ��炵�Ȃ��ł���B
�����ԍ��F10256880
![]() 0�_
0�_
�y���v�Z���Ă݂܂����B
���̃����N��̋@��� DiMAGE A1 �Ƃ����@��B������ 8.89mm�A2560pixel �Ȃ̂ł��������f�s�b�`�����܂�A��f�ʐς����܂�B
��f�ʐς� 1.69��m �R���f�W�� 4�{���BISO100 �Ō��q�� 4000���A8bit �̃��x�� 150 �Ƀ}�b�s���O�A�ŋ��߂�ƁA
�u150 �𒆐S�� ±2.36 �͈̔͂ł���v�ƂȂ�܂��B
���ۂ̉摜���� ±4 ��͈̔͂ł���Ă��܂��B
�������k���ɂ���ĕW����������l�͂킩��܂��B
��f�ʐ� 4�{���ŕW�����́u4 �� 2.36�v�Ȃ̂ŁA40% �قnj���Ȃ���Ȃ�܂��A�摜�ł͂����܂ł͌����Ă��Ȃ��悤�ł��B
�c��̓f�W�J���̃m�C�Y�ł�������A�B�e���̈����ł������肵�܂����A����ł��v�Z����̗\�z�قǂ͕W�����͌����Ă��܂���B
�ƂˁB���o�́i����ړI�ł͂Ȃ��j�摜�ł��A�����܂ł͂킩��܂��B
�����ԍ��F10256968
![]() 0�_
0�_
�R���^�b�N�X�̃t���T�C�Y�J�����́A�Ȃ�ł���Ȃɉ掿�����������̂ł��傤���H
�����Y�͂��̗L���ȃJ�[���c�@�C�X�������̂ɁB
��ʖʐς���Y�����ʼn掿�̗ǂ����������܂�킯�ł͂Ȃ��̂ł́H
�Z���T�[�����Z�p�����[�J�[�ɂ���ėl�X�ł��傤�B
���_�l�ƌ����́A�ւ����肪�����ē��R�ł��傤�H
���_�l�����ł͐l�͓����܂���B
���[�U�[�������⊴���������邩�炱���A�����ɗւ����܂��̂ł��B
�t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y�ɔ�ׂăZ���T�[�����_��s���Ȃ݂̂͂�Ȓm���Ă��܂����A����ł��t�H�[�T�[�Y���D���Ȃ̂ŁA����͂��傤���Ȃ��ł��B
�J�����}�j�A�Ǝʐ^���D�Ƃ͕ʐl��ł��B
�}�j�A�̌��t�����݂̂ɂ��ċ@�ނ����낦��ƁA���僌���Y���炯�ɂȂ��Ă��܂��g�����ł��܂����ˁB
���D�Ƃ́A�����̃X�^�C���ɍ������̂����낦�Ċy�����B��邱�Ƃ���ɍl���܂��B
���͎R�x�n�тɃJ������S���œo��܂��B�o�R�������܂߂āA�U�b�N�̏d����20kg�ȏ�ɂȂ�܂��B
�t���T�C�Y��F2.8�Y�[���Ȃ�ďd�߂��Č����I�ł͂���܂���ˁB
�������������ԗŐ���Ń����Y�������������̂ŁA�S�~�����d�v�ł��B
�n�`��A�O�r���g���Ȃ��ꏊ�����X����̂ŁA����⒴�L�p�ł���u������L���Ȃ̂��K�{�@�\�ł��B
���̂悤�ȃt�H�[�T�[�Y�Ȃ�ł͂֗̕��@�\������킯�ŁA������l�����ăJ�����̐��\�Ƃ݂�ׂ��ł��傤�B
���̌f���́A�}�j�A�ƈ��D�Ƃɂ�鑊�e��Ȃ��b�ł��B
���_�l�����ł��ׂĂ��������Ȃ��̂��A�l��Ƃ������̂ł��B
������ǂ�ł���F�l�́A�}�j�A�ł����H���D�Ƃł����H
�������悭�l���ăJ������I��ŁA��������g�����Ȃ��Ă��������ˁB
�����ԍ��F10257277
![]() 9�_
9�_
tensor-tan����
�������x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ɉˑ��B
����ʊE�[�x�͎B���ʉ�f�T�C�Y�B
�����i��{�P�͉�f�T�C�Y�B
�@���ׂē��ӂł��B
�@�݂Ȃ���A����͕������Ęb���Ă���Ǝv���܂� �i�u�掿�v�́A�u�B���f�q���̓����v �� �u�𑜁v �̗��ւł��邱�Ƃ��j�B
�@���Ȃ݂Ɏ��͍����x�m�C�Y�ɂ��ď����A���̓��e�� tensor-tan���� �̈ӌ�����o����̂ł͂���܂��� �i�]�������I�Ȋ��o���炵�āj�B
�@���łɌ����ƁA���Z�e�l�̘b �i�������͑����e�l�E���l�j �� �u�����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�v�E�u��ʊE�[�x�͎B���ʉ�f�T�C�Y�v ���A������A����Ă��܂��B�@�t�H�[�}�b�g�Ԃʼn�f���������ꍇ�A �u���i��{�P�͉�f�T�C�Y�v ��������܂��B�@���A����ɂ��ẮA�����_�ɂ����ċC�ɂ��Ȃ������ǂ���������܂���B
�S���ʂȘb�ł����B
�@�ʏ��ɂ�����\��́A�u�B���f�q���召����ꍇ�̉掿�̘b �i�����e�l�̘b�͏��������j�v ���A�Ȃ��Ȃ��i�܂Ȃ��� orz
�@�����Atensor-tan���� �̃R���� �� 2009/10/02 21:26�@[10248164]
�ƂĂ��ǂ����ł��̂ŁA�Љ���Ă����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10257278
![]() 0�_
0�_
>�}�j�A�̌��t�����݂̂ɂ��ċ@�ނ����낦��ƁA���僌���Y���炯�ɂȂ��Ă��܂�
>�g�����ł��܂����ˁB
>�t���T�C�Y��F2.8�Y�[���Ȃ�ďd�߂��Č����I�ł͂���܂���ˁB
����͖����ł��傤(��)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10141193/#10225111
�����l�I�ɂ́������̗l�Ɏv���܂���
�����ԍ��F10257300
![]() 0�_
0�_
�����Y�{�l�B
������͖����ł��傤(��)
���ꂪ�}�j�A���z�Ȃ�ł���B
���̉��i�т̃����Y���w���ł��A�Ȃ��������^�т���ɂȂ�Ȃ��̂́A���Ȃ������}�j�A�����ł��B
�����ԍ��F10257326
![]() 6�_
6�_
�L���m����j�R���̍ŏ�ʋ@��̉��i��60���~�ȏ�B
�I�����p�X�̂����10���~���x�B
�������ׂĂ݂Ă��Ӗ��̂Ȃ����Ƃł��B
�t���T�C�Y�w�c�������������ׂ�����͒����f�W�^���ł��傤�H
�Ȃɂ����Ă���̂��E�E�E�B
�t�H�[�T�[�Y�̓j�b�`�ȕ���ŏ���ɓƎ��H���ł�������A����ł�����ł��B
�����ԍ��F10257491
![]() 7�_
7�_
���s�̂�������
���낢��v�Z���肪�Ƃ��������܂��B
�������A��������炸�l�̏��������Ƃ�������Ɠǂ�ł��������Ȃ��悤�ł��B
>����ł��Ⴀ���̌��������Ƃɑ��Ắu����͌��V���b�g�m�C�Y�̃T���v���ł͂���܂���v���ė������ւ���������Ȃ��B���������̂��u��排����v�ƌ����܂��B
����Ȃӂ��Ɍ����Ă܂����B�u���V���b�g�m�C�Y�ȊO�̌������l������̂ł͂���܂��H�v�Ə������̂ł����B�ǂ����Ă���������邱�Ƃ��D�ɗ����Ȃ��Ƃ��낪������̂ŁB
���̗��R�́A���V���b�g�m�C�Y�͌��ʂ̏��Ȃ��Ƃ��Ɍ����ɂȂ邱�Ƃ�A�I�����Ԃ������Ȃ�Ό��q�̗h�炬�����ω����ăm�C�Y�ʂ���������͂��ł��邱�ƂȂǂł��B
���s�̂����������摜�̂ЂƂ͓����̉��O�ł��邱�ƁA�����ЂƂ̃R�s�[�p���̃`���[�g�摜�i���܂�Ђǂ��m�C�Y�͌����܂��j��1/10�b�I�o�Ɣ�r�I�������Ƃ���A���̉摜�̃m�C�Y�͌��V���b�g�m�C�Y�ł͂Ȃ��ƑS�ے肷�����͂���܂��A����ȊO�̌������l�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������ł��B
�����͂����Ă��A���ɂ̓Z���T�[��摜���v�������i�͂���܂���̂ŁA�����܂ł��l�@���������ɉ߂��܂��A���̗����Ɍ�肪����̂�������܂���B���ڂ������̂��ӌ����������������Ƃ���ł��B
�����ԍ��F10258108
![]() 2�_
2�_
>���̉��i�т̃����Y���w���ł��A�Ȃ��������^�т���ɂȂ�Ȃ��̂́A���Ȃ���
>���}�j�A�����ł��B
�������������̂ɑ��Ă̕ԐM�ł����H
�����N��ǂ����ǂ��ł����
�����ԍ��F10259231
![]() 0�_
0�_
1-300����
�ǂ������J�ɂ��肪�Ƃ��������܂��B
>�@���ׂȘb��������܂��A�V���b�^�[���x��ς���Ɠ����ʐ^�͊�{�I�ɂ͎B��܂���B
���Ⴀ�A�ܒ��Ăł��������̂͂ǂ��ł��傤�B
�����̑��ʂ��猩��ƁA���x�ƃV���b�^�[���x�𑵂���F�l��ς����ꍇ�Ɍ��V���b�g�m�C�Y�ɉe�����Ȃ���A���ʂ͌��V���b�g�m�C�Y��F�l�Ő������Ă͂����Ȃ��ł��ˁB�I�o��K���ɂ��邽�߂ɂ̓X�^�W�I�B�e�����ďƖ��Œ������Ă݂܂��傤�B
�ϓ�������p�����^�����Ԃɕς���ƁA�m�C�Y�̌��������ł��邩������A�A�A�͓̂��R�ł��ˁB^^; �m�C�Y�̌����̐�����F�l�Ƃ���͕̂s�K�ł��B
35�~���t�B�����ł̎B�e�ɓ�ꂽ�l���t�H�[�T�[�Y�ŎB�e����ꍇ�A�i���2�i�J����Ηǂ��_�ɂ͒N���ّ��͖����ł��傤���A��������ZF�l�ƌĂԂȂ�ĂԂō\��Ȃ��Ǝv���܂��B
�����A��p��\���ׂɏœ_���������Z���Ă������Y�̏œ_�����͕ς��Ȃ��悤�ɁAF�l�����Z���Ă����邳���ς���ł͂Ȃ��_�����͖��L���Ă����ė~�����Ǝv���܂��B
�i���݂ɖ]���[300�~���̃����Y��600�~���]���Z�b�g�Ƃ��Ĕ̔����Ă����I�����p�X�͖��A�����Ǝv���܂��B�u���Z�v�Ȃ�����Ƒ傫�����L���Ȃ��ƗD�nj�F�ɂ�����Ǝv���܂��B�j
���s�̂�������
���������Ɍ����鏑�����݂���A���݂܂���l�F�B���Ƃ��Ă͕��ʂ̐l�ɂ�����悤�ɉ�����Ă������Ȃ�ł����B^^;
>���Ȃ������������茾���ĂȂ��Ŏ����ł���Ă݂���B
���_�I�ɂ� kuma_san_A1 �̏Љ�Ă���T�C�g�ɕ���͖�����ŁA���Ɏ������v�Z����K�v�͊����Ȃ�ł����ˁB^^;
�����u����������t���Ă���v�̂́A�������茾���A�m�C�Y�̑傫���̈Ⴂ��F�l�Ő������悤�Ƃ��Ă���_�u�����v�ł��B^^;
�����ԍ��F10259276
![]() 2�_
2�_
�����A���݂܂���B�h�́i�ƁA�u���v�j�������Ă��܂����Bm(_ _)m
��)
���_�I�ɂ� kuma_san_A1 �̏Љ�Ă���T�C�g�ɕ���͖�����ŁA���Ɏ������v�Z����K�v�͊����Ȃ�ł����ˁB^^;
��)
���_�I�ɂ� kuma_san_A1���� �̏Љ�Ă���T�C�g�ɕ���͖�����ŁA���Ɏ������v�Z����K�v�͊����Ȃ���ł����ˁB^^;
�����ԍ��F10259857
![]() 1�_
1�_
�@
�@�͂炽 ����A�����́B
�������u����������t���Ă���v�̂́A�������茾���A�m�C�Y�̑傫���̈Ⴂ��F�l�Ő������悤�Ƃ��Ă���_�u�����v�ł��B^^;
�@���Ƃ��Ă��uF�l�v�ɗ��Ƃ����݂����̂ł���B
���̕����u���Z�̖@���v�Ƃ��Ă��ꂢ�ɃX�b�L���܂Ƃ܂�܂�����B
�@�Ȋw�����̊�{�ł͌��V���b�g�m�C�Y�̑傫���̈Ⴂ�͌��ʂ̑召�Ő�������ׂ��ł��傤���B
���ʂ������ǂ�p�����[�^�́@�u�V���b�^�[�X�s�[�h�v�u���ĂĂ��郉�C�g�̋����v�uND�t�B���^�[�̃t�@�N�^�[�v�E�E�E�E�E�E�����āuF�l�v�Ƒ�R����̂ł����B
�@�ʐ^�̊�{�ł́i�Ȋw�����̊�{���炷��Ƃ����炪���肳�ꂽ�����ɂȂ�܂����j�������uF�l�v�ȊO�����ł���Ƃ��Đ����A��r���s����Ǝv���̂ł����B
�����l����A�u���ʁv�́uF�l�v�Ɠǂݑւ��Ă������ł����H
�@�{��Ƃ͊W�Ȃ��b�ł����A
���̓����Y��J�����̐v�҂ł͂���܂��A�܂��Ȃ낤�Ǝv���Ă��Ȃꂻ��������܂���B
�c�O�Ȃ���A���H�Ŋp���O���l�Ȃ�������@�������̎O�O�̊p�̕��i�͉����o���Ă��Ȃ��ʂ̂��������������킹�Ă��܂���B
�@����Ȏ��ł��A�Ȃ�Ƃ������̃C���[�W����A���邢�͂���ȏ�̉f�����B�e�������Ƃ����l���Ă��܂��B
�@����Ȏ��A�����⑼�̃X���b�h�Ō��킳���c�_�����A��q���g�ɂȂ鎖�����X����܂��B
�����g�����������C�̌��������Ƃ��������߂�����̂ł����E�E�E�E
�@�S�����炻���Ȏ��͌����Ȃ��ł����A�^���ɏ������܂�Ă�����X�Ɋ��ӂ��ēǂ܂��Ă�����Ă��܂��B
�����ԍ��F10260606
![]() 1�_
1�_
�� �����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ɉˑ��B
����͑S���̌���ł��������������l�������Ǝv���܂��B
4/3�@�ƃR���f�W������Ύ����ł��܂��̂Ŏ����Ă���Ă݂�
��f�T�C�Y�Ɩ��W�̂��Ƃ��m�F���Ă��������B
�����́i4/3�Ɠ����p�i����̃Z���T�[���g���jFX100���ɐ������܂��B
4/3�̊��Z�W����2�{�ł����AFX100��4.6�{�ł��B��̊Ԃ͖�2.3�{�̍�������܂��B
��̃J�����̃V���b�^�[�ƍi����ɍ��킵�܂��B�Z���T�[�̓����ʐς��r���܂��̂�
4/3�@�̕��͑Ίp����2.3�{�L���ʐ^���B���āAFX100�Ɠ����͈͂̕������o���܂��B
�iG1�̏ꍇ�A��220���A1710×1280��f�̎ʐ^�ɂȂ�܂��j�B
FX100��1200����f�ł������x�掿�͂���220���̎ʐ^�Ƃقړ����Ɗm�F�ł���Ǝv���܂��B
FX100��1200����f�̎ʐ^���A����200����f�̎ʐ^�ɏk�����Ĕ�ׂĂ݂�Ε�����܂��B
�܂�A�����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ƃ͊W�Ȃ��A�Z���T�[�ʐς������ł���Γ����ł��B
�i���̏ꍇ4/3�@�R���f�W�A��f�s�b�`�͖�2.3�{�A�ʐ�5.5�{������Ă��e�����y���ł��j
�����ԍ��F10260614
![]() 0�_
0�_
�� ����200����f�̎ʐ^�ɏk��
����220����f�̎ʐ^�ɏk�������瓙�{�Ŕ�r�ł��܂��B
�����ԍ��F10260660
![]() 0�_
0�_
>���V���b�g�m�C�Y�͌��ʂ̏��Ȃ��Ƃ��Ɍ����ɂȂ邱�Ƃ�A�I�����Ԃ������Ȃ�Ό��q�̗h�炬�����ω����ăm�C�Y�ʂ���������͂��ł��邱�ƂȂǂł�
����A�O�ɂ́u�I�����Ԃɉ����āi��Ⴕ�āH�j�m�C�Y��������v���f������Ă��܂���ł������H
���̗ނ̃m�C�Y�͔M�m�C�Y�ł��傤���B���W�͂킩��܂��A���܂�ėp���̂���m�C�Y���f���Ƃ͎v���܂��B�Ⴆ�uF5.6�A1/200sec�v�ɔ�ׁuF8�A1/100sec�v�̃m�C�Y�ʂ͓�{�ɂȂ邩��o���邾�������V���b�^�[�X�s�[�h��I�����ׂ��A�Ȃ�Ă��܂蕷���܂���B
�Ƃ�����A���V���b�g�m�C�Y�͌��ʂɉ�������������`�����̂Ȃ̂ŁA���ʂ����Ȃ��V���h�[���̓m�C�Y��������ł��傤�B
>�R�s�[�p���̃`���[�g�摜�i���܂�Ђǂ��m�C�Y�͌����܂��j��1/10�b�I�o�Ɣ�r�I�������Ƃ���A���̉摜�̃m�C�Y�͌��V���b�g�m�C�Y�ł͂Ȃ��ƑS�ے肷�����͂���܂��A����ȊO�̌������l�������������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������ł��B
�R�s�[�p���́u���x�� 150�v�ŘI�o�l�Ƃ��Ă͍����ł��i���ʂ������j�B����ł���r����ΈႢ�͂킩��܂����B
�܂��A���V���b�g�m�C�Y�ȊO�̃m�C�Y���������܂��B�Ⴆ��
http://www.imagegateway.net/p?p=Biu4wkfAsdH
����̈�ԏ��߂̉摜�́A��f�s�b�` 1.69��m �̂��̂ł��B�߃o���f�B���O�m�C�Y���m�F�ł��܂��B
������o�C�L���[�r�b�N�� 1/2 �k������ΕW�����̌������m�F�ł��܂����A���̌�g�債�Ă��o���f�B���O�͎c��܂��B
����͋ɒ[�ȗ�ł����A������ɂ��摼�̃m�C�Y�̑��݂��A���V���b�g�m�C�Y�̑��݂Ək���ɂ��m�C�Y�������ʂ�ے肷�邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂���B
�v�Z��̕W�����́A���̃��x���̉�f�s�b�`���l��f�������邱�ƂŁu±1�v�͗D�ɈႢ�܂�����A���ۂ̃t���T�C�Y�t�H�[�T�[�Y�̌����ڂ̍��ق͂����������肻���ł��B
������ɂ���A���̃m�C�Y�̑��݂͔ے肵�Ă��܂���B���w�Y�[�����i�i���Ċ��x���i�グ��A���̃m�C�Y�̕������掿�������Ȃ邱�Ƃ͊��ɏq�ׂĂ��܂��B
�ŁA�����g����s���������̂ł����A�u8bit �摜�̏k���v�ł́A�l��f�����قǂ̌��V���b�g�m�C�Y�ቺ�͓����܂���ˁB
���R�́uRAW �� 12bit ���� 8bit �փ}�b�v�������_�ŏ�����Ă���v����ł��B
��̓I�Ȍv�Z�@�͂킩��܂��A�u���� 125�A�W���� 4 �̐��K���z����C�ӂ̂S�����o���ĉ��Z����ƁA����͂ǂ�ȕ��z�ɂȂ邩�H�v�Ƃ������Ƃł��B
���� RAW �́u1000�� �� 4000�v�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
RAW �̒i�K�ʼn�f��������悢�̂ł��傤���A�������������\�t�g�͂�����ƒm��܂���B
���̈Ӗ��ł́A���̂����ɒ��f�@����肵�Ă����A�Ƃ����̂������I���ł͂Ȃ���������܂���B
�����ԍ��F10260664
![]() 0�_
0�_
>�� �����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ɉˑ��B
>
>����͑S���̌���ł��������������l�������Ǝv���܂��B
�����炱��́u�m�C�Y���f���ɂ��v�̂ł���B
�u�m�C�Y�̒萫��������v�ƌ����Ă��N�����Ȃ��ł���B������b���i�܂Ȃ��B
��ʓI�ɐ�������̂�
[�G�l���M�[�^�ʐ�]
���Z�p���x���ɂ���Č��܂郂�f���ł��傤�B
���̂�����u���w�Y�[���ƃg���~���O�Y�[���v�������B�S�������f�q���l�����ׂ�B
�V�O�i�����l�{�A�m�C�Y���l�{�A���ʂ� S/N��̓g���~���O����g���~���O���ꏏ�B�قȂ�̂́i�r�j���O�����ꍇ�́j���V���b�g�m�C�Y�����B
�����ԍ��F10260691
![]() 0�_
0�_
8�r�b�g�ł��o�J�͂ł��܂����B
�ኴ�x�ŎB�������掿�̎ʐ^�́ASNR�������ς��Ă��l�Ԃ̖ڂŔ��ʂ��ɂ����ł����A
4/3��ISO100�ł��ǂ�����ƌ��\�m�C�Y������܂�������ʂ���������܂��B
�����ԍ��F10260792
![]() 0�_
0�_
�� �S�������f�q���l�����ׂ�B�V�O�i�����l�{�A�m�C�Y���l�{�A
���������ł��B�l���ł��ƁA���ʂ��l�{�ł��ˁB�l�{�x���V���b�^�[�Ɠ������ʂł��B
�\�j�[�̐V�����Z�̖�i���������������ł��B�d�q��u����ł�����܂��B
�V�O�i�����l�{�ł����A�m�C�Y�͂��̕������̓�{�ł��B
�Ȃ��m�C�Y���l�{�ɂȂ�Ȃ��ƌ����܂��ƁA�قȂ�����̓��m�����ňꕔ���E����܂�����B
����͌��V���b�g�m�C�Y�����ł͂Ȃ��A�M�Ƃ���������̂��̂������ł��B
���w���v�������ł��B���w�A�����̊�{��������A���̕������͖Y��Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
����F�l�̂��Ƃ��ˁB
�����ԍ��F10260882
![]() 0�_
0�_
>����A�O�ɂ́u�I�����Ԃɉ����āi��Ⴕ�āH�j�m�C�Y��������v���f������Ă��܂���ł������H
����Ȃ��Ƃ��������L���͂���܂��c
�����ԍ��F10260966
![]() 1�_
1�_
�R���|�W�b�g�͉�f���炵�͂��Ă��Ȃ��̂ŁA��f������Ƃ͈قȂ�܂��B
�����ԍ��F10261147
![]() 0�_
0�_
���Ƃł��ˁB
�̎B���� 600����f APS-C �̃O���[�J�[�h�B�e�����Ă݂��̂ł����A[10256836] �ł�������_�l�ɋ߂��l���o�Ă��܂��B
��ł�����T�Z�̗��_�l���ƕW���� 0.9�A�����l�ŁiPhotoshop �́u�P�x�v�\���Łj�W���� 0.73 �ł��B
Photoshop �̕W���������������͂킩��܂��A�����ڂ��Y�킾�ȂƎv���ăO���[�J�[�h�𑪒肷��ƌ��ʂ͒����ė��Ă܂��A�o����B
�ŁA�ʐ� 1/4 �ɏk�����Ă��u��f�ʐώl�{�v�̗��_�l�͂�͂�o�܂���B�W�������������Ȃ邱�Ƃ͊m���ŁA�k���ɂ�� S/N ����͂���܂��B������ 8bit �ł͌��ʕs���ł��B
�����ԍ��F10261275
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
>4/3�̊��Z�W����2�{�ł����AFX100��4.6�{�ł��B��̊Ԃ͖�2.3�{�̍�������܂��B
>��̃J�����̃V���b�^�[�ƍi����ɍ��킵�܂��B�Z���T�[�̓����ʐς��r���܂��̂�
>4/3�@�̕��͑Ίp����2.3�{�L���ʐ^���B���āAFX100�Ɠ����͈͂̕������o���܂��B
�����œ_�����A�����V���b�^�[�X�s�[�h�A�����i��iF�l�j�ŎB�e����Ƃ������Ƃł��ˁB
>�iG1�̏ꍇ�A��220���A1710×1280��f�̎ʐ^�ɂȂ�܂��j�B
�Ȃ������œˑRG1���o�Ă���̂ł��傤���H
>FX100��1200����f�ł������x�掿�͂���220���̎ʐ^�Ƃقړ����Ɗm�F�ł���Ǝv���܂��B
>FX100��1200����f�̎ʐ^���A����220���i200��������j��f�̎ʐ^�ɏk�����Ĕ�ׂĂ݂�Ε�����܂��B
>�i���̏ꍇ4/3�@�R���f�W�A��f�s�b�`�͖�2.3�{�A�ʐ�5.5�{������Ă��e�����y���ł��j
�܂�g�p�J�����͂Ƃ������A��f���̈Ⴄ�����̃J�����ŁA�������邳�E�����{���̏œ_���̓�����p�������I�o�ŎB���āA�����摜�T�C�Y�ɏk������r����Ƃ������Ƃł��ˁB
�ŁA���̌��ʂǂ�����卷�Ȃ��摜�ɂȂ邩��A
>�܂�A�����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ƃ͊W�Ȃ��A�Z���T�[�ʐς������ł���Γ����ł��B
>����220����f�̎ʐ^�ɏk�������瓙�{�Ŕ�r�ł��܂��B
�Ƃ������Ƃł��ˁB
�����A�����ł��傤�B�k�����鎞�ɉ�f���Ƃɐ���������i�����x�m�C�Y�j���������ċς��Ă��܂����̂ł�����B
���s�̂��������4��f����1/4�T�C�Y�k������������ł���ˁB�ǂ����Ȃ�����ƍ�������1200����f��1��f�ɂ��Ă��܂��ǂ��ł��傤�B�������Ƃł���H
���ǁA���̑�������Ă킩�邱�Ƃ�
�u�œ_�����^�V���b�^�[�X�s�[�h�^�i����ɂ��ē�����ʑ̂��B�e����A�ǂ�ȃt�H�[�}�b�g�̃J�����ł��A�œ_�ʒP�ʖʐϓ���̖��邳�͂ǂ�������v
�Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł͂���܂��H
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̃J�����Ńm�C�Y���r����Ȃ�A�摜���k�����Ă̓_���ł��傤�B
�����ԍ��F10261658
![]() 3�_
3�_
�����āA��f�����T�C�Y�k���̑��삪���ZF�l�ɂǂ����т��̂ł��傤���H
�����ԍ��F10261663
![]() 3�_
3�_
���鐯�J��������́AD40�Ƃ��I���Ƃ�
��[���ł������߂�����邹������l�Ȃ�ł���B�݂��݂��B
�����ԍ��F10261703
![]() 6�_
6�_
>�� �����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ɉˑ��B
>
>����͑S���̌���ł��������������l�������Ǝv���܂��B
>
>4/3�@�ƃR���f�W������Ύ����ł��܂��̂Ŏ����Ă���Ă݂�
>��f�T�C�Y�Ɩ��W�̂��Ƃ��m�F���Ă��������B
>�����́i4/3�Ɠ����p�i����̃Z���T�[���g���jFX100���ɐ������܂��B
>
>4/3�̊��Z�W����2�{�ł����AFX100��4.6�{�ł��B��̊Ԃ͖�2.3�{�̍�������܂��B
>��̃J�����̃V���b�^�[�ƍi����ɍ��킵�܂��B�Z���T�[�̓����ʐς��r���܂��̂�
>4/3�@�̕��͑Ίp����2.3�{�L���ʐ^���B���āAFX100�Ɠ����͈͂̕������o���܂��B
>�iG1�̏ꍇ�A��220���A1710×1280��f�̎ʐ^�ɂȂ�܂��j�B
>
>FX100��1200����f�ł������x�掿�͂���220���̎ʐ^�Ƃقړ����Ɗm�F�ł���Ǝv���܂��B>
>FX100��1200����f�̎ʐ^���A����200����f�̎ʐ^�ɏk�����Ĕ�ׂĂ݂�Ε�����܂��B
>
>�܂�A�����x�m�C�Y�͉�f�T�C�Y�Ƃ͊W�Ȃ��A�Z���T�[�ʐς������ł���Γ����ł��B>
>�i���̏ꍇ4/3�@�R���f�W�A��f�s�b�`�͖�2.3�{�A�ʐ�5.5�{������Ă��e�����y���ł��j
����͑S���A�����ɂȂ��Ă��܂���B
FX100�Ƃ����̂́A�p�i�\�j�b�NDMC-FX100�̂��Ƃł�낵���ł��傤���H
����Ă݂�ƌ����Ă���Ă݂�A�ʐ�5.5�{�قǂ̍����x�m�C�Y�̍��͂Ȃ��̂�
���炩���Ǝv���܂��B
�������A�Ȃ������Ȃ�̂����鐯����͗��_�I�ɐ����ł���̂ł��傤���H
��f�ʐςłȂ��A�Z���T�[�ʐς̂������Ƃǂ����Č�����̂ł��傤���H
���������A��f�ʐς��������̂ƁA�u�Z���T�[�ʐρv���������̂́A������������
�v���܂����A�ǂ����āA�u�Z���T�[�ʐρv�̂����Ȃ�ł����H
�R���f�W�̃m�C�Y�͈�̑O�͂Ђǂ�����ł����B�Œኴ�x�ŁA�\�����ʂ�����
�ꍇ�ł��m�C�W�[�ł����B�C���[�W�Z���T�Z�p������قnj��サ���Ƃ͎v���Ȃ��̂�
���ł́A������摜���ł���悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��ł��傤���H
�R���f�W�̏ꍇ�ARAW���o�͂ł���@��͂ق�̈ꈬ��B������RAW���o�͂ł��Ă�
���łɉ��H���ꂽRAW�ł��B(1��ł����H����Ă���ł��傤��)
�����ԍ��F10261721
![]() 6�_
6�_
1-300����
�u���ʁv���uF�l�v�œǂݑւ���̂͂���ς薳��������Ǝv���܂����A�A�A^^;
�B�e�̃R�c�Ƃ������A�����������ƂȂ犷�ZF�l�ł��ǂ��Ǝv���܂����A���̃X���̂悤�ɃJ�����̐��\�̔�r������悤�ȏꍇ�́A������ƁA�����Ȃ������ǂ��Ǝv���܂���B
�u�t���T�C�Y�̃����Y���t�H�[�T�[�Y�ɕt����Əœ_������2�{�ɂȂ�v
�ƁA������
�u�ԈႢ�I�œ_�����͐L�тȂ��v
�ƁA�c�b�R�~������̂��l�b�g�̌f���Ƃ������̂ł��B�ُ�ɃX�����L�т܂��B
����ƁA���鐯���߂炳��̊��ZF�l���_�Ńt�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y���r����ꍇ�AF�l��2�i�AISO�l��2�i�̍��v4�i�ς�����Ⴄ��ł���ˁB�ŁA���������炽�߂ėǂ�����ƁA�m�C�Y��ISO�l��2�i�Ő������AF�l��2�i�̓{�P�̐����݂����Ȃ�ł���ˁB
���ႠF�l��2�i�ł͖��邳��ς��Ȃ��ŗ~�����Ǝv���܂��B�i�ׂ����Đ\����܂���j
�����ԍ��F10261977
![]() 4�_
4�_
1-300����
[10261977]�̏I���̕��́A���鐯���߂炳��̘b�@�Ƌ߂����̂�����Ǝv���܂��B^^;;;
�C���ēǂނƁA�X�b�Ɠǂ߂��Ⴄ�l�����邯�ǁA�ǂ��ǂނƁu�A���H�ς��Ȃ��v�ƂȂ�Ǝv���܂��B^^;
�����ԍ��F10262035
![]() 1�_
1�_
�r�m��́A�V�O�i���i�L�ӏ��j�ɑ���m�C�Y�i���ӏ��j�̊����ł��B
�L���Ӗ��ł�����A�����Y�̉𑜂͌����ɂ͑S���E�\�i�s���m�j�ł�����A�ʐ^�͑S���m�C�Y�Ƃ������������ł��܂��Ǝv���܂��B
�ł��A���{�x�@���R�j�~�m��M�p���ĖƋ��ʐ^�̎B�e�@�ނɓ������Ă���ȏ�A
�����I�Șb�Ƃ��đS�����m�C�Y�͌����߂���������܂���B
���Ⴀ�A�ǂ��܂ŃV�O�i���łǂ�����m�C�Y���B���̏����ݒ�͐l�Ԃ̎d���ł����A���ے��������܂���B
�����ŁA��ʉ��������Ȃ�l�ޓ��[�ł��傤�B
���̏ꍇ�A�����̐e���̂���������������A�g�уJ�����ŏ\���ȑ命���̕��X�͌����ɋy���A
�ʐ^���������Ƃ��J������G�������Ƃ��Ȃ����E���̐l�X�ɓ��[�������邱�Ƃ͌v�Z�ɓ���Ă����K�v������Ǝv���܂��B
�����炭�A���[���ʂ̓R���f�W���唻���m�C�Y���͌덷�͈̔͂Ƃ������ʂ��m���������ł��傤�B
�����A���{�̃J�������A�ʐ^���̑����ɑΏۂ����肵���m�x���啝�ɒႢ�~�j�~�j���[�ł�����A
���̉��i�R���̐m�`�Ȃ����Ґk������̗l�q���Q�l�ɂȂ邩������܂���B
����ł����p�Ґ��̔䗦����A�ĊO�t���T�C�Y����킷��ł͂Ɨ\�z����܂��B
�����܂Ŋӏ܉掿�ɂ�����肽���ł�����A�m�C�Y�]���Ƃ͂����������̂Ǝv���܂��B
�����Ȋw�̘b�i�d�q�f�[�^�j�ł�����A�m�C�Y�͐��l�Ɋ�Â����ʂ����߂�ꂻ���ł��B
�������A���ʂ̌��ߕ��i�����j���l�ޓ��[�Ŏx������闠�t���͑S�R�Ȃ��A
�ނ���ی��������Z�̂ق����傫�����Ƃ́A�z���ɓ����܂���B
���̏ꍇ�A�����͊Ԉ���Ă���A�����f�����s���m���Ƃ������Ƃ��Ӗ�����ł͂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10262081
![]() 2�_
2�_
������ƁA���鐯���߂炳��̊��ZF�l���_�Ńt�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y���r����ꍇ�AF�l��2�i�AISO�l��2�i�̍��v4�i�ς�����Ⴄ��ł���ˁB�ŁA���������炽�߂ėǂ�����ƁA�m�C�Y��ISO�l��2�i�Ő������AF�l��2�i�̓{�P�̐����݂����Ȃ�ł���ˁB
�����AISO��2�i�Œ��낪�����̂ł����B
�E���ZF�l�Łu�����p�ł̌��a=��荞�ގ��Ԃ��������(�G�l���M�[��)�v�����낦�čl����
�E���ZISO(���x)�ő��ʏƓx�̍������낦�čl����
�ł��̂ŁB
�܂��A�m�C�Y�Ƃ��������V���b�g�m�C�Y�Ɋ֘A���������́u���ZISO(���x)�v�Ő������������ǂ��Ǝv���̂ł����ǂˁB
�ŁA�𑜂Ɋւ��Ắu���ZF�l�v�ƕ����čl��������킩��₷���Ƃ����l������Ǝv���܂��B
�ł��A�����͓���I�ɂ܂Ƃ܂��Ă��܂��̂ŁA�ǂޕ��Ŏ����Ȃ�ɓǂ݉����Ƃ������Ƃŗǂ��Ǝv���܂���B
���łɂł����A����`��(�𑜊W�Ƃ��Ă��ǂ��ł�)��̂ɕK�v�ȁu��p�ƌ��a�v�����܂��Ă���Ƃ��܂��B
35mm���Z�Łuf35mm�AF8�v������̎v���o�L�^�Ƃ��܂��傤�B
�x�[�X���x��ISO100�Ɠ����ɂ����ꍇ�̃J�����t�H�[�}�b�g�Ⴂ���l�����
�E�唻�͂�蒷���I�����Ԃ��K�v->���V���b�g�m�C�Y���Ő��x������->��^�̃X���[�V�X�e��
�E���ł͂��Z���I�����Ԃōς�->���V���b�g�m�C�Y��Ő��x���Ⴂ->�R���p�N�g�ȃn�C�X�s�[�h�V�X�e��
�����ꂼ��\�ɂȂ�܂��B
�I���̎��R�Ƃ��̓������������ăJ�����V�X�e�����y����Ŏg���Ηǂ��̂ł����A�{���͗������Ă����������y����ŃV�X�e���I����B�e���s����ƍl���܂��B
����ɁARAW�o�͎��_�ʼn��H�͏k��RAW�t�H�[�}�b�g�ȊO�ł͍����I�ȗ��R�����ʂ��Ȃ��̂ōs���Ă��Ȃ��ƍl���Ă悢�ł���B
���x���グ�邽�߂ɍs���Ă����@�́u���H�v�ł͂Ȃ��ƌ����Ă悢�Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10262208
![]() 1�_
1�_
ISO�͊W�Ȃ��ł��ˁB�V���b�^�[�ƌ��a�Ō��ʂ����߂܂����A
ISO�͂��̌��߂�ꂽ���ʂŁA�ǂ��őP�Ɋ撣�邾���̘b�ł��B
�p�[�t�F�N�g�ł��A�^����ꂽ���ʈȏ�̉掿�͂ł��܂���B
�����ԍ��F10262227
![]() 1�_
1�_
�� ��f�����T�C�Y�k���̑��삪���ZF�l�ɂǂ����т��̂ł��傤���H
�ꕔ�̕��́A���͌��\�����Ǝv���܂����A��f�T�C�Y�ƊW������ƌ������܂����A
����F�l�̊��Z�ɂ́A��f���E��f�T�C�Y�Ƃ������͂��Ȃ��A�S���W�Ȃ����̂ł��B
�W������̂́A�Z���T�[�S�̂̃T�C�Y�ł��B
����ő��ʂ������܂�ł�����A��Ō��߂�ꂽ���ʂ����̉�f�ɕ����邩�͎��R�ł��B
�����ԍ��F10262268
![]() 0�_
0�_
>�ꕔ�̕��́A���͌��\�����Ǝv���܂����A��f�T�C�Y�ƊW������ƌ������܂����A
>����F�l�̊��Z�ɂ́A��f���E��f�T�C�Y�Ƃ������͂��Ȃ��A�S���W�Ȃ����̂ł��B
>
>�W������̂́A�Z���T�[�S�̂̃T�C�Y�ł��B
>����ő��ʂ������܂�ł�����A��Ō��߂�ꂽ���ʂ����̉�f�ɕ����邩�͎��R�ł��B
�u����F�l�v���Z�́A���鐯����̒�`�ł́A�m���Ɂu��f���E��f�T�C�Y�v���W���Ȃ�
�ł��傤���A���������u����F�l�v���̂ɈӖ��̂�����̂ł͂���܂���B
�u����F�l�v���`���Ă����āA���ꂪ�u��f���E��f�T�C�Y�v�ɊW�Ȃ��Ǝ咣����̂�
�z�_�@�ł��B
���鐯����́A�Ȃ��u����F�l�v���掿�ɉe������̂�������Ɛ������Ă����܂���B
�����ɁA�ϔO�I�A���o�I�ȋc�_�ɏI�n���Ă��܂��B
>����ɁARAW�o�͎��_�ʼn��H�͏k��RAW�t�H�[�}�b�g�ȊO�ł͍����I�ȗ��R�����ʂ��Ȃ��̂ōs���Ă��Ȃ��ƍl���Ă悢�ł���B
>���x���グ�邽�߂ɍs���Ă����@�́u���H�v�ł͂Ȃ��ƌ����Ă悢�Ǝv���܂����B
�����ɂ��悭�m��Ȃ��̂ŁA���m�ȂƂ���͐\���グ���܂��ARAW�������H���f�[�^
�ł���Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��Ǝv���܂��B
�B���f�q�̏o�͂́A���łɌŒ�p�^�[���m�C�Y��A�Ód���̕���s���Ă���͂��ł��B
�f�q�ɔ���`��������A������ł��傤���A������Ԃ��s���A�J���[�o�����X��
����(WB�̒����ł͂Ȃ�)���s���Ă���͂��ł��B���̂悤�ȏ����́A�n�[�h�E�F�A
���邢�̓t�@�[���E�F�A�A����ɂ͉摜�����G���W�����g�p���Ă��邩������܂���B
�����̉ߒ��ŁA�{���̃m�C�Y���ጸ��������Ă��Ă��s�v�c�͂���܂���B
�����ԍ��F10262395
![]() 2�_
2�_
���B���f�q�̏o�͂́A���łɌŒ�p�^�[���m�C�Y��A�Ód���̕���s���Ă���͂��ł��B
�f�q�ɔ���`��������A������ł��傤���A������Ԃ��s���A�J���[�o�����X��
����(WB�̒����ł͂Ȃ�)���s���Ă���͂��ł��B���̂悤�ȏ����́A�n�[�h�E�F�A
���邢�̓t�@�[���E�F�A�A����ɂ͉摜�����G���W�����g�p���Ă��邩������܂���B
�����̉ߒ��ŁA�{���̃m�C�Y���ጸ��������Ă��Ă��s�v�c�͂���܂���B
�����炻���́u���m�ɓǂݏo�����߂̎�@�v�ŁA������ʂ�����Ɂu���V���b�g�m�C�Y�v���c��̂ł��B
����͖{���I�A�����I�Ȍ��ۂɂ��Ă̘b�ł�����B
�����ԍ��F10262435
![]() 1�_
1�_
>�V���b�^�[�ƌ��a�Ō��ʂ����߂܂����A
>�W������̂́A�Z���T�[�S�̂̃T�C�Y�ł��B
�V���b�^�[�X�s�[�h�E���a�E�Z���T�[�T�C�Y�̂R�v�f�ŁA�C���[�W�Z���T�[������������ʂ����܂�̂͂�����܂��ł��B
���ZF�l�_�̂��Ƃ��Ƃ̎咣�́A�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ���炭��掿�i�m�C�Y�j�̈Ⴂ�𐮍������邽�߂̍l���ł͂Ȃ������ł����H
����܂Łu�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂�v�Ƃ����Ə�����Ă��܂����A�Ȃ������Ȃ�̂��A���܂��̒ʂ�������Ȃ���Ă���܂���B
����ɁA��f�T�C�Y���f���͊W�Ȃ��Ƃ��������B
���鐯�J��������͂����l���Ă���Ƃ������Ƃ����͂킩��܂������B
�u�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂�v
�@�@�@��
�u�Ȃ��Ȃ�m�C�Y�ɂ͉�f�T�C�Y���f���͊W�Ȃ����炾�v
�u���v�����̍����I�ŋ̒ʂ��������́A�܂��ǂ��ɂ�������Ă���܂���B
�����ԍ��F10262504
![]() 2�_
2�_
�u�m�C�Y�ɂ͉�f�T�C�Y���f���͊W�Ȃ��v
�@�@�@��
�u�Ȃ��Ȃ�A�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂邩�炾�v
�́u���v�ł������ł��B
�����ԍ��F10262515
![]() 0�_
0�_
[10261658] �Ȃ��̖��O���o�Ă��Ă܂����H
>���s�̂��������4��f����1/4�T�C�Y�k������������ł���ˁB�ǂ����Ȃ�����ƍ�������1200����f��1��f�ɂ��Ă��܂��ǂ��ł��傤�B�������Ƃł���H
���Ɠ����ʼn���b��ɂ��Ă���̂����͂킩��Ȃ��̂ł����E�E�E�B
��f��������Ό��V���b�g�m�C�Y�͌���܂��B
1200����f��1��f�ɂ��Ă�����܂��B���̏ꍇ�͑������x�̌���ł��ˁB�B���ʂ̌����������ł͎B���ʐςłقƂ�Ǎ����o�܂��A����ł����_�l�ǂ���̍��͏o��ł��傤�i������E�ȉ��ɂȂ�Ƃ��A�������������Łj�B
>���ǁA���̑�������Ă킩�邱�Ƃ�
>�u�œ_�����^�V���b�^�[�X�s�[�h�^�i����ɂ��ē�����ʑ̂��B�e����A�ǂ�ȃt�H�[�}�b�g�̃J�����ł��A�œ_�ʒP�ʖʐϓ���̖��邳�͂ǂ�������v
>�Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł͂���܂��H
��H
�ʂɉ摜�k����������Ȃ��Ƃ��A���̏������ł͒P�ʖʐς�����̖��邳�͓����ł����H
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̃J�����Ńm�C�Y���r����Ȃ�A�摜���k�����Ă̓_���ł��傤�B
�Ƃ������ƂŁA�b������Ă܂��B
Tranquility���� �̈ӌ��ɂ�����������̂́A���傹�̐l�͂ۂ��Əo�Ȃ�œǂނ̂��ʓ|������ł��B
[10261663]
>�����āA��f�����T�C�Y�k���̑��삪���ZF�l�ɂǂ����т��̂ł��傤���H
�����炠�B�u���Z�v���ē��{��𗝉����܂��傤�B
���x�������Ă��܂����A�t���T�C�Y���Z�œ_�����͉�p�Ƃ������l���������Ƃ��̃t���T�C�Y�̏œ_�����̂��ƁB
�t���T�C�Y���ZF�l�́A�u����\�v�u�����v�u��ʊE�[�x�v�̎O�i���ɂ����邩���j�̉��l���������Ƃ��̃t���T�C�Y��F�l�̂��ƁB
���ZF�l�͂���ŏI���ł��B
���̒��Łu�����v�̉��l�������ł��Ȃ����Ęb�ł���H
[10262504]
>�V���b�^�[�X�s�[�h�E���a�E�Z���T�[�T�C�Y�̂R�v�f�ŁA�C���[�W�Z���T�[������������ʂ����܂�̂͂�����܂��ł��B
>���ZF�l�_�̂��Ƃ��Ƃ̎咣�́A�Z���T�[�T�C�Y�̈Ⴂ���炭��掿�i�m�C�Y�j�̈Ⴂ�𐮍������邽�߂̍l���ł͂Ȃ������ł����H
��ɋ������悤�Ɂu��ʊE�[�x�v������܂����A��{�I�ɂ���ł����ł��B
Tranquility���� �́u����\�v�͔F�߂Ă��܂��ˁH ����Ɓu��ʊE�[�x�v���B�c��́u�����v�B
>����܂Łu�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂�v�Ƃ����Ə�����Ă��܂����A�Ȃ������Ȃ�̂��A���܂��̒ʂ�������Ȃ���Ă���܂���B
����ȁB�萫�I�Ȑ����ƁA����������ʓI�Ȑ��������܂������B
���̐����łǂ������ʂ��Ă��Ȃ����H
�����ԍ��F10262710
![]() 0�_
0�_
�͂炽���� �́uCIPA ISO���x�̋K��v��ǂ݂܂��傤�B
�����ԍ��F10262728
![]() 0�_
0�_
>�u�t���T�C�Y�̃����Y���t�H�[�T�[�Y�ɕt����Əœ_������2�{�ɂȂ�v
>
>�ƁA������
>
>�u�ԈႢ�I�œ_�����͐L�тȂ��v
>
>�ƁA�c�b�R�~������̂��l�b�g�̌f���Ƃ������̂ł��B�ُ�ɃX�����L�т܂��B
�œ_�������u���̑傫���v�Ƃ���ƁA��f�s�b�`�����z�I�ȏœ_���������肵�܂��i��f�s�b�`�����Ȃ�œ_������{�j�B
�œ_�������u��p�v�Ƃ���ƁA�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�����z�I�ȏœ_���������肵�܂��i�t�H�[�}�b�g�����Ȃ�œ_������{�j�B
�u���z�I�œ_�����v������Ȃ�A������߂āu����Z�œ_�����v�ł����ł��B���������œ_�����̘b�Ȃ�u�L�т܂��v�B
�����ԍ��F10262739
![]() 0�_
0�_
>�Ƃ������ƂŁA�b������Ă܂��B
����A�b�����ɖ߂��܂����B
>Tranquility���� �̈ӌ��ɂ�����������̂́A���傹�̐l�͂ۂ��Əo�Ȃ�œǂނ̂��ʓ|������ł��B
���̕��������Ɠǂ�ł�������Ⴂ�܂��B
�������̍l�������`���������Ȃ�A���Ђ��ǂ݂ɂȂ��Ă��Ԏ����B
>�t���T�C�Y���ZF�l�́A�u����\�v�u�����v�u��ʊE�[�x�v�̎O�i���ɂ����邩���j�̉��l���������Ƃ��̃t���T�C�Y��F�l�̂��ƁB
���ZF�l�͂���ŏI���ł��B
�m�C�Y�͊W�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�Ȃŏ��ƃY���Ă��Ă���悤�ȁc
>���̐����łǂ������ʂ��Ă��Ȃ����H
��͂�u���v�����̍����I�ŋ̒ʂ��������͂���Ă܂���B
�������ł킩�������Ƃ́A
��f��������ƃm�C�Y������Ƃ������ƁB
��f�������Ă�������������ʂ͕ς��Ȃ����ƁB
��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
�m�C�Y�̌����͑����ʂł͂Ȃ��āA
��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�ƂɌ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10262781
![]() 2�_
2�_
>�œ_�������u���̑傫���v�Ƃ���ƁA��f�s�b�`�����z�I�ȏœ_���������肵�܂��i��f�s�b�`�����Ȃ�œ_������{�j�B
�œ_�������u��p�v�Ƃ���ƁA�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�����z�I�ȏœ_���������肵�܂��i�t�H�[�}�b�g�����Ȃ�œ_������{�j�B
���Ȃ�4/3�ł�E-1�AE-3�AE-30�̂悤�ɉ�f�����ς��Ɗ��Z���K�v�ɁI
35mm�t���T�C�Y�ł���f�����ς�����犷�Z�I
����Ƀt�H�[�}�b�g�T�C�Y�����낢��ł����ł����Z�I
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̉�f���Ⴂ���r���悤�Ƃ���ƁA�ƂĂ��Ȃ������ւ�ł��ˁB
�����ԍ��F10262811
![]() 2�_
2�_
���S�ҁi�H�j�Ɍ����ď����Ă��镶�������ς��āA���`�㋉�� �iw�j �ւ̐������Ƃ��Ă݂܂����E�E�E��
�ʏ�́A�t�H�[�}�b�g�̖ʐς��S���̂P�̃J�����́A�掿���S���̂P�̘b
�@�S�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�ʓr�E�E�E
�@�Q�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�E�E�E���ɁA�ł�����ˁB
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A����f�q�̖ʐς͂S���̂P�ł��B�@���������āA
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A�P�s�N�Z��������̎�����̖ʐς��S���̂P�ł��B
�@���̂Q��̃J�����ŁA�����i��l�E�����V���b�^�[�X�s�[�h�E���� ISO �A�u�Q�^�R�̃J�����v �� �u�S�^�R�̃J�����v �̔����̏œ_�����ŎB�e�����Ƃ��܂��B
�@�u�S�^�R�̃J�����́A�P�s�N�Z���v �� 100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
���̏ꍇ�E�E�E
�@�u�Q�^�R�̃J�����́A�P�s�N�Z���v �ł́A25 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�P�s�N�Z�������� 10bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 10bit ×1200��
�@�E�E�E���������āA�u�S�^�R�̃J�����v �̏��ʁi���K���̐��m���ƌ����Ӗ��̉掿�j �́A �u�Q�^�R�̃J�����v �̂S�{�B
�t�H�[�}�b�g�̖ʐς��S���̂P�̃J�����ŁA���Z�e�l�����낦��ꍇ�̘b
������₷�����邽�߂ɁA��L�ƈقȂ�A�e�l�� ISO ��ݒ肵�܂��B
�@�S�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�ʓr�E�E�E
�@�Q�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�E�E�E���ɁA�ł�����ˁB
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A����f�q�̖ʐς͂S���̂P�ł��B�@���������āA
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A�P�s�N�Z��������̎�����̖ʐς��S���̂P�ł��B
�@���̂Q��̃J�����ŁA�u�Q�^�R�̃J�����v �� �u�S�^�R�̃J�����v �̔����̏œ_�����ŎB�e�����Ƃ��܂��B
�@�u�S�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�S�j �́A�P�s�N�Z���v �� 100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�p�^�[���P
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO50�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�p�^�[���Q
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A25 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�i�����ŁA�V���b�^�[�X�s�[�h�� �u�S�^�R�̃J�����v �̂S���̂P�ƂȂ� �i�����Ȃ�����ł�����ˁj �j
�@�P�s�N�Z�������� 10bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�B
�@���A�����ŁA�����łS�����B�e���č������A�P�s�N�Z�������� 10bit×�S ��12bit �̏��Ƃ���A
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@���́A�����ɂł��邾���̂��Ƃ������B�@��̂��Ƃ͔C����w
�@�i�܂����������ł���w�j
�@���������Ă��������ُ펖�Ԃ���A�u�����グ��X���b�h�ɗ��ė~�����Ȃ��v �Ə����܂����B�@���A���������ł��Ȃ��Ȃ����悤�ł����A�_�_���������Ă��܂����B�@���ɂȂ邩������܂��A�X���b�h�𗧂��グ����A�F����ɗ��Ă������������ł��B
�����ԍ��F10262815
![]() 1�_
1�_
>>���ZF�l�͂���ŏI���ł��B
>
>�m�C�Y�͊W�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
���ꂪ��͂��Ȃ�ł��B�u���l�v�����߂�̂́u�l�ԁv�ł��B
���́u�����v�����l�ɂ������H
�ʐ^�Ƃ͎B����O��Ƃ��܂��B�B������ƌ��ʂ̑��ǂ����V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ƂȂ��Ă�����܂��i����͂����ł��ˁH�j�B
�m�C�Y�̑������Ȃ����u���l�v������ł��B���Ȃ��ɂƂ��ĉ��l�ł͂Ȃ���������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͉��l�ł��B
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̉�f���Ⴂ���r���悤�Ƃ���ƁA�ƂĂ��Ȃ������ւ�ł��ˁB
������O�ɏ����܂������A�ʐ^�̏ꍇ�u��f���̊�v������܂���i�e���r�͂���j�B
�������f�������Z�œ_�����ɉ�������͈̂�ʓI�ł͂���܂���B
�ł��{���͊������Ă������ׂ��Ȃ�ł��B�Ȃ��Ȃ���ۂ̏œ_������L���̂ƑS���������ʂ������邩��ł��i���Ȃ��Ƃ��u����\�v�u�����v�u��ʊE�[�x�v�̎O�_�ɂ����āj�B
>��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
>�m�C�Y�̌����͑����ʂł͂Ȃ��āA
>��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�ƂɌ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�H�H�H
���ʂ������Ƃ���̕W�����̊����i���j�����適������m�C�Y���������ƌ����B
���q�̐U�镑�����m���I�ł���Ƃ������������ł��i���ꂪ���������j�B
���f�̌��ʂ̑��ǂ����߂���@�͐F�X����܂��ˁB�����Y�̍i��iF�l�j�A��ʑ̂̋P�x�A�V���b�^�[�X�s�[�h etc...
��f�s�b�`���������@�̂����̈�ł��B
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̉�f���Ⴂ���r���悤�Ƃ���ƁA�ƂĂ��Ȃ������ւ�ł��ˁB
�O�ɂ������܂������ʐ^�ɂ͉�f���̊������܂���i�e���r�͂���܂��j�̂ŁA��f�����œ_�����Ɋ��Z����͈̂�ʓI�ł͂���܂���B
��f���̊�����߂�ΐ������܂��B�������u��p�v�������邽�߂ɉ�f�s�b�`������������g���~���O���Ȃ�������܂���B
�u��f�����œ_�������Z�v�́u���ZF�l�v�̗��_�ƍ��킹�āA�u����\�v�u�����v�̓�_�ł͉��l�����Z�ł��܂��i�u��ʊE�[�x�v�����Ԃ�ł���j�B
�����ԍ��F10262853
![]() 0�_
0�_
����A
>�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̉�f���Ⴂ���r���悤�Ƃ���ƁA�ƂĂ��Ȃ������ւ�ł��ˁB
�������ςȕ��ɂ��Ԃ��Ă܂��ˁB�܂��K���ɓǂ�ǂ��Ă��������B
�����ԍ��F10262857
![]() 0�_
0�_
����A���t���炸�ł����B
>��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
>�m�C�Y�̌����͑����ʂł͂Ȃ��āA
>��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�ƂɌ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ł͂Ȃ��āA
�u��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
���̏ꍇ�̃m�C�Y�̌����͎���ʂ̑������Ȃ��ł͂Ȃ��āA
��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�Ƃɂ������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�v
�ł����B
�u��f�����̂��k���v�Ƃ�������Ńm�C�Y������̂�
1��f������̌��ʂ������邩��ł͂Ȃ���
�u��f���Ƃ̂�����ς��v����A�ł��ˁB
�����ԍ��F10263170
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
>�͂炽���� �́uCIPA ISO���x�̋K��v��ǂ݂܂��傤�B
�����ƁACIPA�̋K��̓h���t�g�Ȃ�啪�O�ɓǂ݂܂�����AISO�̊��x�̋K����ǂ��Ƃ���܂���B
�i�]�k�F�t�B�����̏ꍇ�ǂ����Ă�ASA���Č������Ⴄ���� ^^;�j
���s�̂�������͂��̃X���̍ŏ��̏������݂�ǂق����ǂ��Ǝv���܂���B���̃X���́u���V���b�g�m�C�Y���ĂȂ�ł��傤�v�Ƃ�������X���ł͖����̂ŁA���s�̂�������̏������݂̓X���̎�肩��́A����Ă���Ǝv���܂���B
�����ԍ��F10264307
![]() 6�_
6�_
�s�����w����@
�M���͎d�����ɂ��Ē��J�ɐ������Ă��������܂����B�M���̌����Ă��鑊��F�l�Ƃ����͎̂d�����𐔒l���������̂ł���ˁB�ł������炭�I�����p�X�̃��[�U�[�̕��̑����͂��̂��Ƃ����������Ǝv���܂��B�i�������Ď��₳����������������Ǝv���܂����j
�_�_�́u���̃t�H�[�T�[�Y���Â��A�Â��Ǝ��X�Ɍ���ꑱ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�v�ƌ������ƂȂ̂��Ǝv���܂��B
�������̒ʂ葊��F�l�Ƃ����͎̂d������\�����̂ł���u���邳�v��\�����̂ł͂���܂���B�����͂��ߔނ͓��{�ꂪ�s���R�Ȃ��ߌ����������Ƃ��\���ł��Ȃ��̂��Ǝv���܂����B�����ŊF����ɗ������Ă��炦��\���ɂ���悤�ɔނɂ̓A�h�o�C�X����������ł��B�ނ�����͗��������͂��ł��B����ł��̃X���͏I���܂����B
����ʼn��Ƃ��Ȃ�Ǝv���܂������A��ɂȂ��Ă܂������悤�ȃX���b�h�����X�Ƒ����Ă��邱�Ƃ�m��A����͉����ς��Ǝv�����̂ł��B
�����v���Ă���Ƃ��ɃA�I���[�X�e�n�[������̏������݂��ڂɓ���܂����B�u�ނ̓L���m���Ђ̃t���T�C�Y�ȊO�������������̂��v�ƌ����������݂ł����B�܂�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��낤�Ǝv���܂������A�ނ̏������݂�ǐՂ���Ƃ��̓��p�͔ے�ł��Ȃ����̂ł����B
�v���Ԃ��Ă݂�ƁA�L���m����APSC�̈���������������͎̂��ł��B�u���������Ĕނ͋؋�����̊ω����M�҂ŁA��A�̏������݂̓L���m���ȊO�̃J�������Ȃ߂�ׂ̂��́v�Ƃ����c�v��������ł����̂ł��B
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤�Ǝv���A�h�o�C�X�𑱂��܂����A�������݂����킷�����A���͔ނ͓��{�ꂪ���\�ł��邱�ƂɋC�Â��܂����B
�ނ́u�Ɠx�v���uF�l�v���u���邳�v���ǂ��������Ă��܂��B�Ȃ̂ɉ��ł��̂悤�ȏ������݂𑱂���̂ł��傤���H
�����_�ł̎��̍l���́u10252093�v�̒ʂ�ł��B
������������M���͔ނɂ܂�܂Ə悹���Ă��邾����������܂����B
���̍l���͂��܂�ɂ��Ό��ɖ��������̂Ȃ̂ō��܂ŏ����܂���ł����B�i���ł��������g�Ŋ��S�ɂ͐M���Ă��܂���j�������A��������ł��l�K�e�B�u�L�����y�[�����s�����悤�Ȃ̂Ŏ�肠���������Ă݂܂����B�i�܂��A�ނ͏�����Ă����傪�����Ȃ��قǂ��̔��r�炵�Ă���Ƃ͎v���܂����j
�������̕Ό����^���Ȃ�ނ̏������َ݂͖E����ȊO�ɂ���܂���B
���āA�^���̂قǂ͔@���ɁH
�����ԍ��F10264401
![]() 4�_
4�_
�@�͂炽����A
���B�e�̃R�c�Ƃ������A�����������ƂȂ犷�ZF�l�ł��ǂ��Ǝv���܂���
���܂��������܂��ˁB
���ɂƂ��ẮA��芸�����͂����������ƂȂ̂�������܂���B
�u�T�j�[16���[���v�Ƃ����I�o�̖@���������m���Ǝv���܂����A
ISO���x�ƃV���b�^�[�X�s�[�h�̕����\���̕���ɂ͖{���I�ɂ͉��̌q����������̂ł����A
���́i�A�o�E�g�ł͂��邯�ǁj�֗��Ȃ��̖@���ɂ�������������l�͋��Ȃ��ł��傤�B
�@�������A�{���I�ȗ����͂���ɂ��܂��ďd�v���Ǝv���܂��B
�����y�͂��݂Ȕ����͏����Ђ����āA���炭ROM���Ă܂��B
�܂��A�ǂ����Ă��������������o�Ă�����A���̎��͂�낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F10264565
![]() 0�_
0�_
1-300����
���݂܂���A���s�̂�������₤�鐯���߂炳��̎咣��1-300����̏������݂ɂ̓Y��������̂ŁA�Ȃ�1-300����ɂ͐\����Ȃ����������Ă��傤���Ȃ���ł��B
>ISO���x�ƃV���b�^�[�X�s�[�h�̕����\���̕���ɂ͖{���I�ɂ͉��̌q����������̂ł����A
>���́i�A�o�E�g�ł͂��邯�ǁj�֗��Ȃ��̖@���ɂ�������������l�͋��Ȃ��ł��傤�B
���₢��A����͂����Ȃ�悤��ISO���x�����߂��Ă���̂Ōq���肪����܂��B
���̘I�o�ɂ܂��q����̕����͂��鐯���߂炳��̒��Ă��闝�_�ł͖����āu���ʂ̗��_�v�ł��ˁB
���́A����������ƁA���Ƃ��T�j�[16�̒l��b����̓s����4�{�Ƃ�1/4�Ƃ��Ɋ��Z���āu�����Ă���l�Ƙb���ʂ��邩�v�Ƃ����Ƃ��납������܂���B
�����ԍ��F10265294
![]() 3�_
3�_
����F�l�́A����F�l��I�o�v�Z��ے肷����̂ł͂���܂���B
�Η����������Ȃ��A�������̂�����p�x���Ⴄ�����ł��B
�I�o�v�Z�͏]���ǂ���ʼn�����肪����܂���B
��肪����܂��A�I�o�v�Z�͒P�ʖʐς̃t�B�����ɑ��Ă̌v�Z�ŁA
�I�o�v�Z������������ƌ����āA35�~�����ƒ����̎ʐ^�������ʂ�ȃ��P������܂���B
�ʐ^�̎��_���猩����A����F�l�����ی������̂̐����ɂȂ�܂����A
F�l�͐����ł��܂���B�����犷�Z���K�v�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10265855
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� [10263170]
����͕����ʂ�u�m���E���v�̖��v�ł��B[10260664] �̍Ō�̕��̏������݂ɏ����Ă܂��B
Tranquility���� ���g���C���Ă݂Ă��������B
�Ɠx���̋�ԁA������ԕω��������̏����B
���� N�̌��q���������ݒ肾�ƕ�W�c�i��f�j�� 1/��N �ł���B
���f�̖ʐρi�܂��͎��ԁj�l�{���ƁA���� 4N �̂܂��� 1/2��N �ł���B
���͑O�҂̕�W�c����l���o���ĉ��Z����ƁA���ʂ��u���� 4N �̂܂��� 1/2��N �ł���v�ƂȂ邩�ǂ����A�ł��B
�����ԍ��F10265949
![]() 1�_
1�_
�� �Â��Ǝ��X�Ɍ���ꑱ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H
35�~������AAPS-C���͈Â��ł����A�R���f�W���͖��邢�ł���i2�`3�i�̍��j�B
�R���f�W��薾�邭�Ȃ��Ƌ����������m��܂��A����͈Ⴂ�܂��ˁB
�����ԍ��F10266399
![]() 0�_
0�_
>�I�o�v�Z������������ƌ����āA35�~�����ƒ����̎ʐ^�������ʂ�ȃ��P������܂���B
>�I�o�v�Z������������ƌ����āA35�~�����ƃt�H�[�T�[�Y�̎ʐ^�������ʂ�ȃ��P������܂���B
����͎��Ȗ����Ȃ̂ł́H���ZF�l�����낦��Γ����ʐ^���B���Ƃ������Ƃ������̂ł́H
���ʐ^�̎��_���猩����A����F�l�����ی������̂̐����ɂȂ�܂����A
��F�l�͐����ł��܂���B�����犷�Z���K�v�ɂȂ�܂��B
����͂��Ȃ��̎�ςł���B���Z���K�v�������łȂ����͂ЂƂ��ꂼ��ł��B
��ς̉����t���͂�߂܂��傤�B
�O�ɂ������܂������A�ǂ����Ă����ZF�l�_����ʘ_�Ƃ��ĉ����t�������̂Ȃ�A���[�J�[��F�l�̕\�L��ς���悤����������ׂ��ł́H
�����ԍ��F10269497
![]() 11�_
11�_
���ʐ^�̎��_���猩����A����F�l�����ی������̂̐����ɂȂ�܂����A
�ʐ^�̎��_���猩����A���̐l�̊�������A�u�Ԃ̂Ђ�߂��Ȃǂ���ԑ�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
����F�l���ʐ^�̐������A�Ȃǂƌ����̂͑S�������o���܂���B
����F�l��d�C�M���̎���ʁA�m�C�Y�Ȃǂ͏��������ł�����킴�Ƒ傫�Ȗ��̗l�Ɍ�����͎̂��ɂ�����Ȃ��Ǝv���܂��B�i�����܂Ŗl�̎�ςł��̂ő���F�l��ے肷�����ł͂���܂���j
�����ԍ��F10269641
![]() 9�_
9�_
������F�l��d�C�M���̎���ʁA�m�C�Y�Ȃǂ͏��������ł�����킴��
���傫�Ȗ��̗l�Ɍ�����͎̂��ɂ�����Ȃ��Ǝv���܂��B
������ƌ������邩������Ȃ��̂ŕ⑫�ł��B
���ZF�l��d�C�M���ɂ��Ă̋c�_��������Ȃ��Ƃ����Ӗ�����Ȃ��āA�ʐ^��F�l��d�C�M�������Ō��܂�A�Ƃ����ӌ���������Ȃ��ƌ����Ӗ��ł��B
�����ԍ��F10270050
![]() 9�_
9�_
�� ���ZF�l�����낦��Γ����ʐ^���B���Ƃ������Ƃ������̂ł́H
���̒ʂ�ł��B�P�ʖʐς̘I�o�v�Z�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
����F�l�͎ʐ^�̎��_����l�������ʂł����A
�� �ʐ^��F�l��d�C�M�������Ō��܂�A�Ƃ����ӌ���������Ȃ��ƌ����Ӗ��ł��B
����F�l�����ł͑ʖڂł��B����F�l�͂����܂ŏd�v�Q�l�l�̈�l�ɉ߂��܂���B
�����ԍ��F10270467
![]() 1�_
1�_
�����̒ʂ�ł��B�P�ʖʐς̘I�o�v�Z�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
������F�l�͎ʐ^�̎��_����l�������ʂł����A
�ł͊��ZF�l�_�͎��ۂ́u�B�e�v�ɂ͊W�����b�ƌ������Ƃł��ˁB
���ZF�l�𑵂��Ă��A35�~�����ƒ����̎ʐ^�������ʂ�ȃ��P������܂���B
�l���������������̂͂����������ƂŁA������35���������t�H�[�T�[�Y�����_��̏����𑵂����Ƃ��Ă��A���ۂ͓����Z�p�̃Z���T�[�i�t�B�����j����Y������킯�ł͂Ȃ��̂œ������ʂɂ͂Ȃ�Ȃ��ƌ������Ƃł��B
����35��������APS-C�̏ꍇ�Ɍ��肵���ꍇ�A�������[�J�[���Z���T�ƃt���T�C�Y�p�����Y�𗘗p����Ύ��ۂ̏����𑵂��邱�Ƃ��o���A���ZF�l�_�̎��H�ɂ҂�����̑g�ݍ��킹���Ǝv���܂��B
�ȏ�̗��R���獡��̓t���T�C�Y��APS-C�Ŋ��ZF�l�_���c�_���čs�����Ƃ����z�I�ł���A�܂����ۂ̃��[�U�[�ɂ��𗧂��ɂȂ�Ǝv���܂��B
������F�l�����ł͑ʖڂł��B����F�l�͂����܂ŏd�v�Q�l�l�̈�l�ɉ߂��܂���B
�����Ă邱�Ƃ��������Ă��܂���B��
���ʐ^�̎��_���猩����A����F�l�����ی������̂̐����ɂȂ�܂���
�����ԍ��F10270960
![]() 5�_
5�_
�����������Ƃ�������ɂ����Ȃ����̂ŁA�J��Ԃ��ɂȂ��Ă��܂��̂ł����B
1�A���[�J�[�̊��ZF�l�\�L�ɂ��Ĉًc��\�����Ă�������ǂ��ł��傤���H
2�A���㊷�ZF�l�ɂ��Ă̋c�_�̓t���T�C�Y��APS-C���ɂ���̂����z�I�ł́H
����ɂ��Ă��鐯���߂炳��͂ǂ��v���܂����H
�����ԍ��F10271158
![]() 0�_
0�_
�� ���ZF�l�𑵂��Ă��A35�~�����ƒ����̎ʐ^�������ʂ�ȃ��P������܂���B
�ʐ^�͕����̗v�f������܂����A���̒��ł́A���Ȃ��Ƃ��AF�l�Ɋ֘A����S�Ă̐����A
�����掿�A��ʊE�[�x�A��܃{�P�Ȃǂ́A�ʐ^�̎��_���猩��Ɠ����ł��ˁB
�t�̎��_����A4/3�͂̈�Ԃ̓����̓����Y�̌��a���������A35�~�����ȂǂƔ�r���܂���
�����ł���͈͂������̂�������Ǝv���܂��B
���^�y�ʂ������a�i���ʌ�����j�̗]�藘�v�Ƃ��ė����ł��܂��B
�����ԍ��F10271191
![]() 0�_
0�_
���ʐ^�͕����̗v�f������܂����A���̒��ł́A���Ȃ��Ƃ��AF�l�Ɋ֘A����S�Ă̐����A
�������掿�A��ʊE�[�x�A��܃{�P�Ȃǂ́A�ʐ^�̎��_���猩��Ɠ����ł��ˁB
�b�������ɂ���Ă�i���炵�Ă�H�j�����ł����A���Ȃ��Ƃ������ɂ�35�����ƒ����̎ʐ^���ɂ͓����ɂł��Ȃ��ƌ������Ƃɓ��ӂ���A�Ƃ������Ƃł���ˁH
���ł͊��ZF�l�_�͎��ۂ́u�B�e�v�ɂ͊W�����b�ƌ������Ƃł��ˁB�H
��������ӂł����ł����H
�܂��A���ZF�l�𑵂���ƁA35�~������APS-C�̎ʐ^���Ɏʂ���B�H
����͂ǂ��ł����H
�����ԍ��F10271274
![]() 0�_
0�_
�� ���[�J�[�̊��ZF�l�\�L�ɂ��Ĉًc��\�����Ă�������ǂ��ł��傤���H
F�l�̕\�L�́A�ʐ^�Ƃ��Ă̈Ӗ����������ł����A
�≖�̐̂���̒P�ʖʐς̈Ӗ����ς�Ȃ��L���ł��B��{�T�O��������͂���܂���B
���[�J�[�Ƃ��Ă͑���F�l�̕\�L���Ȃ����[�U�[��������Ă��ꂽ�����s�����ǂ��ł��傤��
���[�U�[���g�͊��Ⴂ������A�x���ꂽ�肢���܂���̂ŁA�����͕�����K�v������܂��B
�����ԍ��F10271277
![]() 1�_
1�_
�� �܂��A���ZF�l�𑵂���ƁA35�~������APS-C�̎ʐ^���Ɏʂ���B�H
F�l�Ɋ֘A������̂͑S�ē����ł��ˁB�Ȃ̂ŁA����F�l�̖��O�͂҂�����ł��B
�����ԍ��F10271301
![]() 0�_
0�_
���t�̎��_����A4/3�͂̈�Ԃ̓����̓����Y�̌��a���������A
��35�~�����ȂǂƔ�r���܂��Ƒ����ł���͈͂������̂�������Ǝv���܂��B
����͗������Ă܂���B4/3�̃C���[�W�T�[�N����22�����A�t���T�C�Y��43�����Ŗ��{�̈Ⴂ������܂��B
�ł�����̓f�����b�g�����łȂ������b�g������Ǝv���܂��B
�܂��J�����p�����Y��99���i�Ⴆ�ł��j��IC43�����Ȃ̂ŁAIC22�����͒����I�ȕ\�����o���郁���b�g������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10271359
![]() 0�_
0�_
�� �ł�����̓f�����b�g�����łȂ������b�g������Ǝv���܂��B
����F�l��������Z���T�[�T�C�Y��背���Y�̌��a���厖���Ă��Ƃ������ł���Ǝv���܂��B
�Z���T�[�T�C�Y�͓�{�i�ʐς͎l�{�j�̍�������܂����A�������a�i����F�l�j�̃����Y������A
�f�����b�g�������b�g�����Ȃ����Ƃ�������܂��B
�Â��Ƃ������t�ɋ�����R����l�����܂����A4/3�̑S�Ă̗��v�͈Â��������炵���̂ł��ˁB
�����ԍ��F10271386
![]() 0�_
0�_
��F�l�̕\�L�́A�ʐ^�Ƃ��Ă̈Ӗ����������ł����A
���≖�̐̂���̒P�ʖʐς̈Ӗ����ς�Ȃ��L���ł��B
����{�T�O��������͂���܂���B
����܂ł̎咣�Ɩ������Ă܂���A�P�ʖʐς̍l�������߂�����Ƃ������R�Ŋ��ZF�l���_���咣���Ă���킯�ł���ˁH�Ӗ������������炾�߂Ȃ�ł���ˁH
�����Ƀ��[�U�[�����܂���č������Ă���ƌ����咣�������͂��H
����܂ł̎咣�Ɩ������炯�ł���B
���ZF�l�͕K�v�Ȃ��悤�Ɋ���������̂ł����H
�����[�J�[�Ƃ��Ă͑���F�l�̕\�L���Ȃ����[�U�[��������Ă��ꂽ����
���s�����ǂ��ł��傤��
�����[�U�[���g�͊��Ⴂ������A�x���ꂽ�肢���܂���̂ŁA
�������͕�����K�v������܂��B
���[�J�[�ɂ��܂���Ȃ��l�Ɏ��ȐӔC�Ŕ��������A����͕��ʂ̂��Ƃł��ˁB
���_�͊��ZF�l�_�͎Q�l���x�ł悭�āA�{����F�l�̕\�L��ς���K�v���Ȃ��A���[�J�[�����[�U�����܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��ˁB
������Ƃ���܂ł̎咣�ƈႢ�������Ƃ������܂���B�H
�����ԍ��F10271505
![]() 5�_
5�_
�� �܂��A���ZF�l�𑵂���ƁA35�~������APS-C�̎ʐ^���Ɏʂ���B�H
��F�l�Ɋ֘A������̂͑S�ē����ł��ˁB�Ȃ̂ŁA����F�l�̖��O�͂҂�����ł��B
����͔[���̓����ł����B�O�O
�����ԍ��F10271514
![]() 1�_
1�_
������F�l��������Z���T�[�T�C�Y��背���Y�̌��a���厖
�����Ă��Ƃ������ł���Ǝv���܂��B
�������ς������Ă܂���A�u����F�l�Ȃ�����Ȃ����Ǒ���a���~�����v�ł��������A�u�����a�̃����Y�ł��܂Ăł��t���T�C�Y�������v�ł��ǂ��̂ł́B
���낢��Ȑl�����āA���낢��Ȍ��������Ă������̂ł́H
���Z���T�[�T�C�Y�͓�{�i�ʐς͎l�{�j�̍�������܂����A�������a�i����F�l�j
���̃����Y������A�f�����b�g�������b�g�����Ȃ����Ƃ�������܂��B
��������ߕt���ł���A�Ȃ�ł������ɂ���K�v�͂Ȃ��̂ł́A�����a�Ƒ���a�̌����y����ł������̂ł́H
���Â��Ƃ������t�ɋ�����R����l�����܂����A4/3�̑S�Ă̗��v�͈Â��������炵�����̂ł��ˁB
�����ł��B
�����ԍ��F10271568
![]() 1�_
1�_
�≖�̎��̓t�B�����͎����Ŕ����܂�����P�ʖʐς̌v�Z���K�v�ł����A
�f�W�^���ł͋≖�̏K���P���܂����A�I�o�v�Z�p��F�l�̈Ӗ������Ȃ��Ȃ�܂��B
�f�W�^���ł͂Ƃ��ɃR���f�W�������ł����A�œ_������AF�l�ł͕�����ɂ����ł��B
�����œ_�����A����F�l�̕������ꂵ��������₷���\�����Ǝv���܂��B
���������\������̂����[�J�[������I�͕W���ɂȂ��Ă܂����A����͉������ł��ˁB
�����ԍ��F10271576
![]() 0�_
0�_
�����̋c�_�́A�m�����߂́A�u4/3��F2.0�����Y��35mm�t���T�C�Y��F4.0����������A4/3��2�i�Â��v�Ƃ����b�������ƋL�����Ă��܂��B
���ꂪ���̊Ԃɂ��u4/3�̃Z���T�[��35mm�t���T�C�Y��1/4�̖ʐς����Ȃ�����2�i�Â��v�Ƃ����b�ɂȂ�܂����B
>�i4/3�́j35�~������AAPS-C���͈Â��ł����A�R���f�W���͖��邢�ł���[10266399]
���鐯���߂炳��̂��l���ł�
���鐰�ꂽ��������A�u�ʐς����Ɍ���1/4�̓����s�́A���Ɍ����2�i�Â��v�Ƃ������ƂɁB
�ǂ��������Ƃł��傤�H
�u�Â��v�Ƃ������t�̗p�@�����ł��邱�Ƃ������ł��B
>���[�J�[�Ƃ��Ă͑���F�l�̕\�L���Ȃ����[�U�[��������Ă��ꂽ�����s�����ǂ��ł��傤��
>���[�U�[���g�͊��Ⴂ������A�x���ꂽ�肢���܂���̂ŁA�����͕�����K�v������܂��B
>[10271277]
�̂���l�X�ȃt�H�[�}�b�g�̃J����������܂����i�����`�������`���������ג����̂��j���A�u���Z�i�����jF�l�v�̕\�L�Ȃǖ����Ă��A���Ⴂ�������������肷�郆�[�U�[�͂��܂���ł����B
�����ԍ��F10271577
![]() 7�_
7�_
F�l�����Z���Ȃ���Ȃ�Ȃ����R���F�ڌ������܂���B
�̐S�Ȃ��Ƃ́A���Ɣ�ׂĂǂ��Ȃ邩���l���邱�Ƃł͂Ȃ��A�����̃J�����łǂ̂悤�Ȏʐ^���B��邩��c�����邱�Ƃł��B
���������A�t�H�[�}�b�g���قȂ�ǂ����ǂ������낤�Ƃ��A�u�����ʐ^�v�Ȃǂ��肦�܂���B
���ꂱ��Y�ޑO�ɁA�����[�Y�{�^���������Ό��ʂ��ł܂��B
�����āA35�~���Ƃ����t�H�[�}�b�g���≖�ł����o�����Ă��Ȃ����ɂ́A�t���T�C�Y�Ƃ����Ă���f�W�^���J��������Ƃ������ZF�l�ȂǁA�܂��������Ӗ��ł��B
�����ԍ��F10271579
![]() 6�_
6�_
�� ���鐰�ꂽ��������A�u�ʐς����Ɍ���1/4�̓����s�́A���Ɍ����2�i�Â��v�Ƃ������ƂɁB
���Ɍ��Ɠ����s�̑S�悪�Z���T�[�ł���A�S�����̒ʂ�ł��B
�J�����̃Z���T�[�ɋ߂����z�d�r���l�����番����₷���Ǝv���܂��B
���d�ʂ��l�{�ł�����A���̓d�͂��g�����Ɩ����l�{���邢�ł��B
�����ԍ��F10271593
![]() 0�_
0�_
�� 35�~���Ƃ����t�H�[�}�b�g���≖�ł����o�����Ă��Ȃ����ɂ́A�t���T�C�Y�Ƃ�����
�� ����f�W�^���J��������Ƃ������ZF�l�ȂǁA�܂��������Ӗ��ł��B
����F�l�͋�̓I�ȋZ�p�Ɉˑ����܂���≖�ƃf�W�^���ɊW�Ȃ��K�p���܂��B
35�~���������g�킸�A4/3���S�����Ӗ��Ǝv���̂��l�̎��R�ł����A
4/3���g���A�������͌�������l�����܂�����A���Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10271607
![]() 0�_
0�_
>���d�ʂ��l�{�ł�����A���̓d�͂��g�����Ɩ����l�{���邢�ł��B
�L���������d�ʂ������͓̂�����O�ł��B�������A���d�ʂ��������Ƃ��u���邢�v�Ƃ͌����܂���B
�u�S�{�̓d�͂��g�����Ɩ����S�{���邢�v�́A�������u���邢�v�̎g�p���@�ł����A�u���Ɍ����S�{���邢�v�̏ؖ��ɂ͂Ȃ�܂���B
�����ԍ��F10271610
![]() 3�_
3�_
�� ���d�ʂ��������Ƃ��u���邢�v�Ƃ͌����܂���B
���d�ʂł�����A�l�{���邢�̂��A�l�{�����̂����R�Ɏg���܂����A
�ʐ^�ł͎l�{���邢���A�l�{�Â��������܂��ˁB���ꎫ���ɂ͂��������Ă܂��B
�����ԍ��F10271624
![]() 0�_
0�_
���f�W�^���ł͂Ƃ��ɃR���f�W�������ł����A�œ_������AF�l�ł͕�����ɂ����ł��B
�������œ_�����A����F�l�̕������ꂵ��������₷���\�����Ǝv���܂��B
�����������\������̂����[�J�[������I�͕W���ɂȂ��Ă܂����A
������͉������ł��ˁB
���̋^��ɂ��Ă̓��[�J�[�ɖ₢���킹�āA�Ȃ����ZF�l���g��Ȃ��̂������g�Ŋm�F�����ق����ǂ��ł���A���̂ق����������肷��̂ł́H
�l�Ƃ��Ă͊��ZF�l�̂��������~�߂Ă��炦��Ηǂ��̂ł��鐯���߂炳�����Ŕ[�����Ă��炢�����ł��B
�Ⴆ��wikipedia�Ɋ��ZF�l�_������ĕҏW���Ă݂�Ƃ��͂ǂ��ł����H
�����ԍ��F10271631
![]() 4�_
4�_
>�ʐ^�ł͎l�{���邢���A�l�{�Â��������܂��ˁB���ꎫ���ɂ͂��������Ă܂��B
���ꎫ�T�ɂǂ������Ă������̂��A�]�ڂ��ĉ������B
�������o�T�𖾂炩�ɂ��肢���܂��B
���܂܂łɂ�����Ȃ���肪���x���J��Ԃ���Ă��܂���
���܂܂ň�x�����炩�ɂ��ꂽ���Ƃ�����܂����ˁB
�����ԍ��F10271648
![]() 5�_
5�_
1�A���[�J�[�̊��ZF�l�\�L�ɂ��Ĉًc��\�����Ă�������ǂ��ł��傤���H
2�A���㊷�ZF�l�ɂ��Ă̋c�_�̓t���T�C�Y��APS-C���ɂ���̂����z�I�ł́H
�����̎咣����x�܂Ƃ߂܂��A1�A�ɂ��Ă͂����܂Ŋ��ZF�l�_�͈�ʘ_�ł͂Ȃ��A�\�L�̕ύX�����Ȃ��ėǂ������Ȃ̂ŁA���Ƃ͑��̃��[�U�[�Ɋ��ZF�l�_�������t���Ȃ��̂ł���Ηǂ��ł��B
2�A��FT��FS�̔�r���APS��FS�̔�r�̂ق��������I�ł���A���_�Ǝ��ۂ��s�b�^���ƈ�v���邻���Ȃ̂ō���͑�����APS���[�U�[�̂��߂ɂ��AAPS�ł̋c�_�������悤���肢���܂��B
�����ԍ��F10271668
![]() 3�_
3�_
��35�~���������g�킸�A4/3���S�����Ӗ��Ǝv���̂��l�̎��R�ł����A
����������Ȃ�A�u4/3�����g�킸�A35�~�������S�����Ӗ��Ǝv���̂��l�̎��R�ł����v
�����ɂ��������Ȃ������ς̂������Ȃ�ł���B
�r���܂Řb�������Ă����̂ɍŌ�̌��_�łЂ����肩�����ꂽ�����ł��B�O�O
�����ԍ��F10271685
![]() 5�_
5�_
�NjL
>���d�ʂł�����A�l�{���邢�̂��A�l�{�����̂����R�Ɏg���܂����A
���d�ʂł�����u�傫���E�������v���邢�́u�����E���Ȃ��v�ł��B
�u���邢�v���u�����v���g���܂���̂ł����ӂ��������B
����������ꎫ�T�ł��m�F���������B
�����ԍ��F10271694
![]() 5�_
5�_
���ꎫ���ł���ǂ���\���܂��AYahoo!�厫����������܂��ƁA
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%9A%97%E3%81%84&dtype=0&stype=0
�Â��F�@�������Ȃ��āi�����j�A�����悭�����Ȃ��i��j�B
���邢�F �����\���ɂ���A�܂��������������āi�����j�A�����悭�������Ԃł���i��j�B
�ʐ^�ł悭������Ƃ́ASNR�̂��Ƃł����A����͌��G�l���M�[�̗ʂɂ���ĕς��܂��B
�����Ɗ�͍��ꎫ���̒�`�Ɠ����ł��B���Ɍ����Z���T�[��������G�l���M�[�̗ʂ�
�l�{�ł�����A�����s���J��������i���邢�Ƃ͕�����܂��B
����F�l�قǕ��ՂɓK�p������̂͂Ȃ��Ȃ��Ȃ��ł��ˁB
�����ԍ��F10271701
![]() 2�_
2�_
��2�A��FT��FS�̔�r���APS��FS�̔�r�̂ق��������I�ł���A���_�Ǝ��ۂ��s�b�^���Ɓ���v���邻���Ȃ̂ō���͑�����APS���[�U�[�̂��߂ɂ��AAPS�ł̋c�_�������恄�����肢���܂��B
���ZF�l�_��APS�ł̓W�J�͂��Ђ��肢�������ł��A���̗��_�̏ڍׂɂ��Ă͖l�ɂ͐��������ė���������Ȃ��̂ŁA�M���ėǂ����̂���A�{���ɖ𗧂̂ł�������Ƃ������Q�����Ă��郁�W���[�Ȍf���ŋc�_���Ă�����āA�^�U��x�ɂ��Ă��m���Ȃ��̂ɂ��Ă��炢�����ł��B
�����������_�ł͏��S�ғ��ɂ�������͕̂ςȊԈႢ�̂��ƂɂȂ�v���܂��B
�����ԍ��F10271708
![]() 3�_
3�_
�� �^�U��x
����͊ȒP�Ɋm���߂�邱�Ƃ���Ȃ��ł����H
150/2.0��300/4�Ƃ���̐ݒ���g���Ċm�F�����璼��������ł��傤�B
�����ԍ��F10271719
![]() 1�_
1�_
��150/2.0��300/4�Ƃ���̐ݒ���g���Ċm�F�����璼��������ł��傤�B
FT��FS�ł̓����Y���Z���T���Ⴄ�̂Ŏ��ۂ̎ʐ^���ɏo���Ȃ��ł���ˁH
���������Ӗ���APS�ł̑����̌������҂��܂��B
�����ԍ��F10271742
![]() 5�_
5�_
���ꎫ�T�̏o�T�i�{���鐯���߂炳��̉��߁j���肪�Ƃ��������܂��B
>�Â��F�@�������Ȃ��āi�����j�A�����悭�����Ȃ��i��j�B
>���邢�F �����\���ɂ���A�܂��������������āi�����j�A�����悭�������Ԃł���i��j�B
���̂܂ܕ��ʂɉ��߂����
�u�Â��ʐ^�v�@�F�I���ʂ����Ȃ��Ĕ�ʑ̂��悭�����Ȃ��ʐ^
�u���邢�ʐ^�v�F�I���ʂ��\���Ŕ�ʑ̂��͂�����ƌ������Ԃł���
�Â�����Ɛ^�����ʼn��������Ȃ��ʐ^�ɂȂ�܂����A���邷����ƘI�o�I�[�o�[�̊K���������g�����ʐ^�ɂȂ�܂��B
���̂悤�ɁA�ʐ^�ł悭������Ƃ́A�K�����K���ł��邱�Ƃ������܂��B
>�ʐ^�ł悭������Ƃ́ASNR�̂��Ƃł����E�E�E
���������鐯���߂炳��́u�Â��v�̊ԈႢ�̍��{�ł��B
�m�C�Y�ł����ʐ^�����Ȃ����͂��܂肢�Ȃ��Ǝv���܂����A���̂悤�ȕ��́A�V�����\�����@��n������邱�Ƃ������߂��܂��B
�����łȂ��ƁA���̕��ʂ̐l�ɘb���ʂ��܂���̂ŁB
�����ԍ��F10271748
![]() 12�_
12�_
�NjL
���t�̗p�@���ԈႦ�����߂ɘb���H���Ⴂ�A�Ӗ����ʂ��Ȃ��̂́A���݂��ɂƂ��ĕs�K�ł��B
���������Ɛ푈�ɂ��Ȃ肩�˂܂���B
�������̂��l���𑼂̐l�ɓ`�������Ǝv������A�F�ɋ��ʂ̌��t�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂͐l�ނ̊�{�ł��B
�����ԍ��F10271763
![]() 8�_
8�_
���鐯�J��������A���ς�炸�ł��ˁB
�s�s���Ȏ����͖��������悤�Ȃ̂ŁA�m�F�����Ă��������B
�B���ʂł̕��ˏƓx�́A(���z���w�n�ł�)F�l�Ō��܂�B
�٘_������܂����H
�B���f�q��1��f�����p��������́A�J�����������Ȃ�A��f�ʐςɔ�Ⴗ��B
�٘_����܂����H
�B���f�q�̗��p������˃G�l���M�[��ISO���x�������Ȃ�A��f�ʐςɔ�Ⴗ��B
�٘_����܂����H
�m�C�Y�����́A��f�ʐςɈˑ�����B
�٘_����܂����H
�x�C���[�z��̐F���̐�����A�N�s������(�V���[�v�l�X)�A�m�C�Y�ጸ�����Ȃǂ�
�����āA�掿�͉𑜓x��������1��f�̓����Ō��܂�B
�٘_����܂����H
�B���ʂ̖ʐς́A��f���A�܂�𑜓x�݂̂��K�肵�A��f�̓����ɂ͊W�Ȃ��B
�٘_����܂����H
�u����F�l�v�͎B���ʂ̉�ʖʐς݂̂Ɉˑ�����B���������āA�𑜓x�������A�掿�ɂ�
�W�Ȃ��B
�٘_����܂����H
�����ԍ��F10272280
![]() 7�_
7�_
�� �掿�͉𑜓x��������1��f�̓����Ō��܂�B
����͊ԈႢ�ł��B��ɉ��x���������܂������A�ʐ^�͉�f�̏W���ł��B
�������s�Ƒ����ɖ���������܂����A�ǂ����ɌR�z�͈�̉�f�����ł͕�����܂���B
�� ���������āA�𑜓x�������A�掿�ɂ͊W�Ȃ��B
����F�l�͎ʐ^�S�̂̊����ʂ���ʐ^�S�̂̉掿��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�t�Ɍ���F�l�͒P�ʖʐς��������ł��܂���̂ŁA����F�l���K�v�ɂȂ�܂��B
����͋≖��f�W�^���A��f�z��Ƃ��ɂׂ͍����Z�p�ɊW�Ȃ��������܂��B
��b�m�����Ȃ��Ă��A�b�̑ΏۂƏ������Y��ɐ����ł���A
tensor-tan����̂悤�ɊT�O�̍��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10272471
![]() 0�_
0�_
�� FT��FS�ł̓����Y���Z���T���Ⴄ�̂Ŏ��ۂ̎ʐ^���ɏo���Ȃ��ł���ˁH
4/3�ł�35�~�����p�̃����Y���g���܂����A�R���f�W�ł����ł��܂��B
35�~������1/1.8"�̃R���f�W�̊Ԃł��A����F�l���������܂��B�덷�͂��قǂ���܂���B
�����ԍ��F10272495
![]() 0�_
0�_
�ł͂��̌��g�摜�h�������Ă��炦�Ȃ����낤���H
�M�a�̌����u��i�Â��v���̌��ۂ������̖ڂɂ͂ǂ̗l�Ɍ�����̂������ɋ���������B
�ʐ^�͖ڂŌ�����́B�@���o�ɑi����̂���ԑ����B
�����ԍ��F10272910
![]() 9�_
9�_
�@Sakura saku����ւ̂��Ԏ��Ƃ�
�@�T�[���X���v�]�̎��o�ɑi����ʐ^�Ƃ�
�@�����Ƃ��ɖZ�����A�ɂ��Ȃ����� �����G
�@���݂܂��� orz �Ƃ�����艳
�����ԍ��F10273417
![]() 0�_
0�_
>�� �掿�͉𑜓x��������1��f�̓����Ō��܂�B
>
>����͊ԈႢ�ł��B��ɉ��x���������܂������A�ʐ^�͉�f�̏W���ł��B
>�������s�Ƒ����ɖ���������܂����A�ǂ����ɌR�z�͈�̉�f�����ł͕�����܂���B
����܂��A�s���̂悢�悤�ɁA������g��������̂ł��ˁB
�掿�Ɖ�f���͕ʂ̖�肾�Ƃ���������Ă܂������B
�ŁA�����͉��Ȃ̂ł����H��̓I�Ɏ����Ɋ�Â��Đ������Ă��������B
>�� ���������āA�𑜓x�������A�掿�ɂ͊W�Ȃ��B
>
>����F�l�͎ʐ^�S�̂̊����ʂ���ʐ^�S�̂̉掿��������邱�Ƃ��ł��܂��B
>�t�Ɍ���F�l�͒P�ʖʐς��������ł��܂���̂ŁA����F�l���K�v�ɂȂ�܂��B
>����͋≖��f�W�^���A��f�z��Ƃ��ɂׂ͍����Z�p�ɊW�Ȃ��������܂��B
�u����F�l�v�ʼn掿���ǂ������ł��邩����Ă݂Ă��������B
�E�����Ȃ��ł��������ˁB
�����ԍ��F10273769
![]() 9�_
9�_
�@������Ǝ��Ԃ��o�����̂ł�������܂��B
�t�H�[�}�b�g�̖ʐς��S���̂P�̃J�����ŁA���̃t�H�[�}�b�g�Ɗ��Z�e�l�i�����e�l�E���l�H�j�����낦��ꍇ��
�@�i������₷�����邽�߂ɁA�e�l�� ISO ��ݒ�j
�@�S�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�ʓr�E�E�E
�@�Q�^�R�̃J�����ŁA1200����f�̃J�������������Ƃ��܂��B�@�E�E�E���ɁA�ł�����ˁB
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A����f�q�̖ʐς͂S���̂P�ł��B�@���������āA
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A�P�s�N�Z��������̎�����̖ʐς��S���̂P�ł��B
�@���̂Q��̃J�����ŁA�u�Q�^�R�̃J�����v �� �u�S�^�R�̃J�����v �̔����̏œ_�����ŎB�e�����Ƃ��܂��B
�@�u�S�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�S�j �́A�P�s�N�Z���v �� 100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�p�^�[���P
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO50�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�p�^�[���Q
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A25 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�i�����ŁA�V���b�^�[�X�s�[�h�� �u�S�^�R�̃J�����v �̂S���̂P�ƂȂ� �i�����Ȃ�����ł�����ˁj �j
�@�P�s�N�Z�������� 10bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�B
�@���A�����ŁA�����łS�����B�e���č������A�P�s�N�Z�������� 10bit×�S ��12bit �̏��Ƃ���A
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@���̏ꍇ�A�e�J�����Ԃ� �� ���a�������E��p�������E�掿�i�������ʁ����邳�H�j�������E�ڂ��̑傫���������ł��B�@�i����F�m�C�Y�����V���b�g�m�C�Y�݂̂Ƃ����ꍇ�j
�@����� �u���Z�e�l�v �́A���̔]���C���[�W�ł��B
�@���̕��� �i���̕����j �́A�͂炽���� �E Tranquility���� �E tensor-tan���� �Ɍ��Ă����������Ǝv�������܂����B�i�������F2009/10/05 13:30�@[10262815]�j
�͂炽����@���̍l�����͈̔͂ɂ����āA�Ԉ���ĂȂ��ł��傤���Hw
Tranquility����@�S���R���|�W�b�g������A���U�C�N���������肵�ĉ掿��ǂ�����b�ƁA���ނ̘b�ł��B
tensor-tan����@���i��{�P�̃T�C�Y�������������������Ƃ��v���̂ł����A�ǂ��v���܂��H
�����ԍ��F10273980
![]() 0�_
0�_
�@���Ȃ݂ɏ�̐ݒ�ŁE�E�E
�p�^�[���O
�@�u�S�^�R�́A1200����f�J�����́A�P�s�N�Z���v �� 100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit × 1200��
�p�^�[���R
�@�u�S�^�R�́A300����f�J�����́A�P�s�N�Z���v �� 400 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 14bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 14bit × 300��
�p�^�[���S
�@�u�S�^�R�́A4800����f�J�����́A�P�s�N�Z���v �� 25 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 10bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 10bit × 4800��
�E�E�E���Ȃ킿�A�ȉ��̂T�p�^�[���̌��ʁ��K�����̎�������
�@�@�@�@�p�^�[���O �F 12bit × 1200��
�@�@�@�@�p�^�[���P �F 12bit × 1200��
�@�@�@�@�p�^�[���Q �F 10bit × �S× 1200��
�@�@�@�@�p�^�[���R �F 14bit × 300��
�@�@�@�@�p�^�[���S �F 10bit × 4800��
tensor-tan����A���̌����������Ƃ�������܂��H
�����ԍ��F10274119
![]() 0�_
0�_
�s�����w����@
�������̒ʂ芷�Z�e�l�Łu���ʁv�͕\���܂����ˁB�i�����Č����Ȃ�������ȁj�]���āA�������͏��ʁ���ł��B�i�ٓ��̎l�������悤�ł��݂܂���j
�����ԍ��F10274356
![]() 0�_
0�_
Sakura saku����
�@�����Șb�Ȃ̂Œ����ɂ������̂ł����A�d�����Ȃ̂ŒZ���Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@��̘b �i���܂���Ă���Ƃ��A���Ȃ̂ł͂Ƃ��j�B
�@�����܂Ŏc���Ă���l�͑��v�ł��傤�B�@����҂Ƃ��āA���̂��炢�̘b�ɕt���Ă����l�Ȃ�A���܂���ăL���m�������Ƃ��Ȃ��̂ł́H
�@���鐯���߂炳��������Ȑl�́A�L���m�����D���ɂȂ�Ȃ��\�����傫�����ƁB
�@���Ȃ݂Ɏ��̓L���m���������ŁAX2 �� 50D �����͓̂��H�Ƃ����r�b�O�C�x���g������������A��ނ��ł��B
�@�ʓr�A���鐯����̌��� �u�L���m���̃}�E���g���D��Ă���b�v �́A���ƃy���^�������Y�����[�^�[�Ɉڍs�����������A�j�R���ƃy���^���i�胊���O�������������A�S�^�R�}�E���g���~�j�C�I�X�Ƃ����̂́A���������H�������� �i�n�߂���L���m���Ɠ����������̗p�j �Ƃ����Ӗ��ł��� �i�ƁA���������̂��Ǝv���j�B
�@�L���m���̃����Y�� �u�����\�v �ł��ǂ��ł����A�u�i���������v �ƌ�����Γ��ӂł���������������܂��B�@�ł�����̓L���m���̏���҂Ɍ����ׂ��A�ʂȘb�ł��B�@����͂���B�@����͂���B
�@���̘b�́A���̃X���b�h���܂߂ĂQ���������Ă��܂��A�ǂ�������͂�A�����邩�E������Ȃ��������̘b�ɂȂ��ď�������ł��܂��B�@���̒i�K�ŁA�f�l����ɉe��������Ƃ��āA�u�傫�ȃt�H�[�}�b�g�̕����掿�������v �Ƃ�����ʘ_�ł���ΊÎ邵���Ȃ��̂ł́H�@�ŁA�ǂ���̃X���b�h�ł��A���� ���s�̂������� ���A�R���f�W���g�����Ƃ������Ă���킯�ł��B�@
�@���������Ӗ��ɂ����āA�u����҂Ƃ��Ă����ƑI��ł��邩�H�v �Ƃ����̂͑厖�ȂƂ���ł���ˁB
�@��ɂ��o�܂����� �� http://www.four-thirds.org/jp/fourthirds/index.html
�@����́A�S�^�R���������A�t�B�����g�p�҂��S�^�R�ɂ�������Ⴂ�`���镶�ł��B�@���A�X����l�Ƃ��ꕔ�̐l�́A���݂̃f�W�^���i�c�R�E�T�c�U�j���S�^�R���`�ƁA�ǂ݊ԈႦ�Ă��܂��ˁH�@�ǂ݊ԈႦ�Ă��Ȃ���Ηǂ���ł��B
�@�ʓr�A�t���T�C�Y�����Ă����Ђ̃����Y�̑P�������͂���ł��傤�B
�@�t�H�[�}�b�g�Ō����A�傫���E�������̍��́A���邢�E�Â��Ǝv���Ă��܂��B�@�ɏ��ȖʐςȂ�A�u���v ���\���Ƃ����Ӗ��ŕ�����܂����B�@���̏ꍇ�A�����ɕK�v�Ȃ����� �u���邢�E�Â��v �Ə����Ȃ������ł��B
�@����͌����������̖��ŁA�c�_�̖{���ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@����ɑ��āA���낢�댾���Ă��A���͓����邾���ʓ|�Ȃ̂ŁA���͍l���Ă���`�̕\�������ɂ��܂��B
�@�����A�u���������l����������̂��v �ƌ�����́A������Ǝv���܂������E�E�E
�E�E�E���̃C���[�W���`���ʐ^���B�e�ł���Ǝv���܂����A���ʖ����ł��B�@�Q�鎞�Ԃ������Ȃ�܂�w�@���͎������Ă��d���Ȃ��ł��A�C���[�W�������Ȃ�����B�@UP�ł��������Ȃ��ł����AUP�ł�����A���Ă���Ă�������w�@�ܖ�������Ă邩���ł����B
�@�����I�@������I�@�d���̎��Ԃ������Ȃ�w
�����ԍ��F10274828
![]() 0�_
0�_
�@�ꉞ���M�B
�@���Z�E�����e�l�łȂ��Ă��A��� �u�p�^�[���O�`�Q�̔�r�v �ŁA�S�^�R �� 35mm�t�� �Ƃ̔�r�ɒu�������čl����ƁA�S�^�R�}�W�ł��Ə����I �i�t����j �Ƃ��v���܂��B
�@���̏ꍇ�A�u�V���b�^�[�V���b�N�v �����Ȃ���A�m���ɂf�P�������Ă܂����� �i����̑���� X2 �ɂȂ����́j�B
�@�Ȃ����A���鐯���߂炳��Ƃ��A�y���^�̃f�W�J���X�^�f�B����Ƃ��̍l���������������Ⴄ��ł��B�@���̒��̍\�����A�߂��̂���w
�����ԍ��F10275007
![]() 0�_
0�_
�i�P�j
�� ����܂��A�s���̂悢�悤�ɁA������g��������̂ł��ˁB
�P�ʖʐςƎʐ^�S�̂̈Ⴂ��������A���̂悤�ȃ��x���̘b�͏o�Ȃ��Ǝv���܂��B
�i�Q�j
�܂��ATranquility����̑O�̃J�L�R�ł����A
�� ��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
�� �m�C�Y�̌����͑����ʂł͂Ȃ��āA
�� ��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�ƂɌ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�S�Ẳ�f�́A�f�W�^���ł͐��l�ŁA�≖�ł͔��������g�G�̋�h���x�ł����A
���͈̔͂Ŋ������ꂽ�G�l���M�[��\�ɉ߂��܂���B����ɑ��Ă̑S�Ă̑���́A
���̊����������ʂ����ɂȂ�܂��B
�܂������ʂ����ł���A�ʐ^�̓��������ɓ�������������ł��̂Łi����������Ƃ��j�A
��f���Ƃ͊W������܂���B��f�Ɖ�f�͊�{�I�ɔ�r�ł��܂��A�������
�i��f���������j�̏ꍇ�́A�ʐ^�̓��������̔�r�ƔF�߂��܂��̂Ŕ�r�ł��܂��B
�i�R�j
�s�����w����֑̎��ł����A�掿�����ŁA��f����������A���f�̉掿������܂�
�i����Ȃ��ƑS�̂̉掿�������Ȃ�܂��j�B���ꂩ�獂��f���ƍ��掿���i�݂܂���
�t�@�C���T�C�Y�͓������ŋɒ[�ɂ͑����܂���B
�����ԍ��F10275193
![]() 0�_
0�_
�s�����w����
�t�H�[�}�b�g�Ō����A�傫���E�������̍��́A���邢�E�Â��Ǝv���Ă��܂��B�@
����͖��炩�ɊԈႢ�ł��B����������̂͌l�̎��R���Ǝv���܂����A�l�̌��Ă���Ƃ���ɏ������ނ̂͂ǂ����Ǝv���܂��B
����ɋɏ��ʐςłȂ��Ă��u���v�Ȃ̂ł��B�d�C�ł��Ƃ���ƁA���ʂ��d�͗ʁi�P�ʁF�W���[���E�E�d���A�G�l���M�[�j�ɂ��Ƃ����A�u�����i�P�Ɍ��̕����ǂ����ȁj�v�j���d�́i�P�ʁF���b�g�E�E�d�����j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����܂��H�@�u����F�l�v�������̂͌��ʂł͂Ȃ����́u�d�����v�ł��B
����F�l�ɂ��Ă��܂����̂ŗ������ɂ����Ȃ��Ă��܂����A�����Ō����u�d�����v�Ƃ́u���邳�v×�u�ʐρv�ł��B����F�l�̏o�����͋C�ɓ���܂��A����F�l���������Ɓu�d�����v�������ɂȂ�͎̂����ł��B�ڂ��ɂ��Ă̓f�[�^������܂���f���ł��܂��A�����炭�u����F�l������킷���́v�ŗǂ��̂ł͂Ɛ������Ă��܂��B�i�����ɂ͒f���ł��邾���̗��t��������܂���B���t���̂Ȃ��������݂����X�ɂ���Ƃ��̔��r�炵�Ă���N������Ɠ����ɂȂ��Ă��܂��܂��̂ŁA�ڂ��ɂ��Ă̓l�^�Ƃ������ƂŁE�E�E�j
�����ԍ��F10275410
![]() 2�_
2�_
>4/3�ł�35�~�����p�̃����Y���g���܂����A�R���f�W�ł����ł��܂��B
>35�~������1/1.8"�̃R���f�W�̊Ԃł��A����F�l���������܂��B
>�덷�͂��قǂ���܂���B
35mm���ɂ�4/3��R���f�W�̃����Y�͎g���Ȃ��̂Ŏ��͏o���܂����B
�� �܂��A���ZF�l�𑵂���ƁA35�~������APS-C�̎ʐ^���Ɏʂ���B�H
��F�l�Ɋ֘A������̂͑S�ē����ł��ˁB�Ȃ̂ŁA����F�l�̖��O�͂҂�����ł��B
35��������APS-C�ł�������Y���Z���T�������ɏo����̂Ŋ��ZF�l�_�̎�����̂Ƀs�b�^���̃��f���ł��A���鐯���߂炳��������ł��������Ă܂��ˁB
�t��4/3��R���f�W�ł͎����o���Ȃ����A�덷���傫���̂Ŕ�r�ΏƂƂ��Ă͖��炩�ɕs�����ł��B4/3�ɂ�����闝�R�͂Ȃ��Ƃ������܂����H
�����ԍ��F10275561
![]() 8�_
8�_
��FT��FS�̔�r���APS��FS�̔�r�̂ق��������I�ł���A���_�Ǝ��ۂ��s�b�^����
����v���邻���Ȃ̂ō���͑�����APS���[�U�[�̂��߂ɂ��AAPS�ł̋c�_�������恄�����肢���܂��B
���̌��ɂ��Ă�낵�����肢���܂��B
�����ԍ��F10275645
![]() 4�_
4�_
�𑜂���тr�m��͌����I�Ɋӏҁi����@��j�̔F���i����p�^�[���j�̖��ɋA�����܂��Ǝv���܂��B
�����Șb�ɂȂ�Ȃ�قǁA�l���i�̍��j��r���ł��Ȃ���������܂���B
��ʉ��������ł�����A�O�q�̒ʂ�A���M���̋c�_�͂��ׂČ덷�͈͓̔��ɖ��v���Ă��܂����ʂ��҂��Ă���ł͂Ǝv���܂��B
�ǂ�����ӂɉ���Ȃ�����A�o�E�g�ȓ��e�ō\��Ȃ��ł�����b�͑����āA
�@�ވȊO�̃p�����[�^�[�̂ق����B�e���ʂɏd�v�ȉe�����y�ڂ���������܂���B
�����ԍ��F10275733
![]() 3�_
3�_
�i�P�j
��{�I�ɃL���m���A�j�R���ƁA�I�����p�X�@�͑S�ăj�R���̃����Y���g���܂��B
���������Y���ƍi��l�iT�l�j������ł����A����ȏ�̈Ӗ��͂���܂���B
�V���b�^�[�̔����ȃY��������܂��B����͓���ł��B�ڂ����͊������܂����A
����@�ł�0.3�i�����̏ꍇ�������A�̂̋≖�������ł��̂Ŏ��p�ɂ͉e��������܂���B
�R���f�W�͊�{�I�ɊJ���i��ł��܂��̂ŁA���x�͐M���ł���Ǝv���܂��B
�ǂ̃J���������{�̃��[�J�[�̐��i�ł��B
�i�Q�j
������掿�̍��͊ȒP�Ɍv�Z�ł��܂����A�l�Ԃ��ǂ������邩�͊ȒP�ł͂���܂���B
35�~������APS-C�̍��͖�1.3�i�AAPS-H��APS-C��0.7�i�AAPS-C��4/3�͖�0.6�i�ł����A
���Ԉ�ʓI�ɂ͂ǂ���傫���Ǝv���܂��ˁB
���E����0.3�i��0.6�i�̊Ԃɂ���Ǝv���܂��B��i�̍����Ђǂ����ł��B
4/3�ƃR���f�W�̍��͖�2�`3�i������܂����A���ꂪ�덷�Ƌ��܂����H
�����ԍ��F10276889
![]() 0�_
0�_
Sakura saku����
�@���邢�E�Â��̘b�͒u���Ƃ���w
�@���� �u�d�����v �̘b�A���肪�Ƃ��������܂��B�@�Ȃ�قǂƎv���܂����B
�@������ɂ͂�����̊��o������܂����A���l�ɐ�������ɂ͍H�v������ƕ�����܂����B
�@���Ȃ킿��
25 ���x�̌� �E 100 ���x�̌� �E 400 ���x�̌� �́A�u�P��f�ɐi�������҂����A ���q�̐��̊��� �i�ŁA��Ƃ���傫���̉�f�� 100 �Ƃ���ꍇ�j�v �Ɛ�������A��蕪����₷���ł��ˁB
�@�u�����ł��� ���� �́A���q�̐����������Ȃ��ƌ����Ӗ��v �Ƃ����ꕶ����ꂽ�����ǂ��ł��ˁB
�@�t�H�[�}�b�g�̑傫�����Ⴄ�Ƃ��̐����́A�u���ʁv ���� �u�擾������q�̐��������E���Ȃ��v �Řb���������ǂ��̂�������܂���B
�@�m�b�{�P�B
�����ԍ��F10277430
![]() 1�_
1�_
�s�����w����
[10273980]�ł��w�������������̂ŁA�ԐM�ł��B
�����Â炢�Ȃ� ^^; �Ƃ������������Ⴄ��ł����A�A�A^^;;
>�t�H�[�}�b�g�̖ʐς��S���̂P�̃J�����ŁA���̃t�H�[�}�b�g�Ɗ��Z�e�l�i�����e�l�E���l�H�j�����낦��ꍇ��
�ƁA�����o���Ă��܂����A�A�A���̎��ɏ�����Ă����ł͊��ZF�l�������Ă��Ȃ��ł��ˁB
��F�l�������Ă��܂��B
�s�v�c�Ȃ̂͑��́u���ZF�l�Ő����ł���v�Ƃ��Ă�����X���A�����̕��́A�����ڍׂ������i�ɂȂ�ƁA�u���ZF�l�v���o�Ă��Ȃ���ł��B
�\����Ȃ���ł����A�S���w�I�A���邢�͕����l�ފw�I�������N���Ă��܂��B^^;;;
�����ԍ��F10278152
![]() 0�_
0�_
�s�����w����
>�擾������q�̐��������E���Ȃ��v �Ł`
�����������Ƃ͉���܂��B�����Ɠx�Ɗ��Ⴂ���Ă���Ƃ��v���Ȃ̂ł��傤�H
�Ɠx�ɖʐς������ċ��߂�̂��d�����ł�����P�ʖʐς͊W����܂���B
�d�����Ƃ������\���ƌ�������������܂����H
�������Ɠx�ɖʐς��������Ă����ʂƂȂ�Ȃ����Ƃ͂������ł���ˁI
�����ԍ��F10278287
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
�@���Ԏ����肪�Ƃ��������܂��B
�@���I�ɂ́A���������Đ����������Ǝv���܂��B
�@�����Ŋm�F�Ȃ̂ł����E�E�E
�p�^�[���O
�@�u�S�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�S�j �́A�P�s�N�Z���v �� 100 ���x�̌� �i����j ����邱�Ƃ��ł���\��������Ƃ��āA
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿������Ƃ���ƁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�p�^�[���P
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO50�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A100 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�P�s�N�Z�������� 12bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�̂ŁA
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�p�^�[���Q
�@�u�Q�^�R�̃J���� �iISO200�C�e�Q�j �́A�P�s�N�Z���v �ł́A25 ���x�̌�����邱�Ƃ��ł���\��������A
�@�i�����ŁA�V���b�^�[�X�s�[�h�� �u�S�^�R�̃J�����v �̂S���̂P�ƂȂ� �i�����Ȃ�����j �j
�@�P�s�N�Z�������� 10bit �K�� ���x�����鎿�����邱�ƂɂȂ�B
�@���A�����ŁA�����łS�����B�e���č������A�P�s�N�Z�������� 10bit×�S ��12bit �̏��Ƃ���A
�@�J�����S�̂̏��� �� 12bit ×1200��
�@�����ŁA100 ���x�̌� �E 25 ���x�̌� �́A�u�P��f�ɐi�������҂����A���q�̐��̊����v �ŁA��Ƃ���傫���̉�f�� 100 �Ƃ���ꍇ�B
�E�E�E�Ƃ����āA
�@�����e�l�������Ă��Ȃ��̂́A�u�p�^�[���Q�v �̎��ł��傤���H
�@�u�p�^�[���P�v �� �u�p�^�[���Q�v �̔�r�ŁA���e�������Ă���̂͂���Ƃ��āA
�@�u�p�^�[���O�v �� �u�p�^�[���Q�v �̔�r�ŁA�p�^�[���Q�̃J������ 10bit×�S �� 12bit�o�͂���@�\ �i�����e�l�Ή����[�h�Hw�j ��������J�����ł����Ă��A�����e�l�������Ă��Ȃ��Ǝv���܂��ł��傤���H
�@���������̃t�H�[�}�b�g�ł́A�u���q��ϊ������A�d�ׂ߂Ă��������̗e�ʁv ������ɔ����ď������Ȃ�ꍇ�������ł���ˁB
�@���Z�e�l�����낦�悤�Ǝv���A�傫������ ISO200 �� ISO100 �ŎB�e�����������A���������� ISO50 �� ISO25 �ŎB�e���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�ŁA���������� ISO25 ���������悤�Ǝv������A�i�Z���T�[�����ǂ���̂͑�ςȂ̂ŁA������Ƃ��āj ISO100 ���S��I�����āA�P�����Z����ΒB���ł��܂���� �i�����[���I��������܂��A�f�[�^��́j�B
�@���̕����ł͂Ȃ��āA�u�p�^�[���R�v �� �u�p�^�[���S�v �̏��ł��傤���H
�@���̏��ł�����A���鐯���߂炳�� �� tensor-tan���� ���A�����̃��[�v�i�H�j�����Ă���悤�Ȃ̂ŁA�������҂͓����������������̂��낤�ƌ������ƂŁA�p�^�[��������̂ł��B�@�����e�l�̘b�ł͂���܂���B
�@�����e�l�͓���ł����Ȃ��āA���Z���āA���������͂ǂ��������̂��A�傫�����͂ǂ�������̂��A�Ƃ������[�J�[�Ȃ胆�[�U�[�Ȃ�̑Ή����d�v�ł��傤�B
�@���̃o�b�N�{�[���͓V�̎ʐ^�B�e�ŁA�掿��ǂ����邽�߂̃R���|�W�b�g�����͓��풃�ю��ł��B�@�������������I�w�i�ł�w
�����ԍ��F10278517
![]() 0�_
0�_
>���E����0.3�i��0.6�i�̊Ԃɂ���Ǝv���܂��B��i�̍����Ђǂ����ł��B
�Z���T�[�Ɠ����ʐςɈ�����邱�Ƃ���ɍl���܂��B�ȑO�q�ׂĂ����Ƃ���u�t�H�[�T�[�Y�S�����ׂ�Ɠ����ɂȂ�v���M���̘_���B�]���ċt�ɍl����ƂS�{�傫���������Ɖ掿�����Ђǂ��Ȃ�ƌ������ƁB
���̂悤�ȃJ�����͍���������Ă��܂����B�m�����Â��ł��ˁB�i�M���̃J�����͂����Ȃ̂ł��傤����ǁE�E�E�≖�J�����Ȃ̂ł��傤���j
�M���̃J�����̉摜��A3���m�r�ȂɈ��������Â��āA�m�C�Y�������Ďg�����ɂȂ�܂���ˁB�i���ꂱ�����̂������Ђǂ����ł����̂ˁI�j����ȃJ�����͂����ɂ����������܂��傤�B���̃J�����͗ǂ��ł���B����Ȃ��Ƃ��C�ɂ��Ȃ��Ă��Y��Ȏʐ^���B��܂��B�d�������������Ă��������������̎B�e�łȂ����A3�m�r�܂��Y��ɏo���܂���I
�����ԍ��F10278544
![]() 3�_
3�_
�s�����w����
��ϐ\����܂���B�ǂ݊ԈႦ�Ă܂����Bm(_ _)m
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A����f�q�̖ʐς͂S���̂P�ł��B�@���������āA
�@�u�S�^�R�̃J�����v �ɑ��� �u�Q�^�R�̃J�����v �́A�P�s�N�Z��������̎�����̖ʐς��S���̂P�ł��B
����́A�O��ł��ˁA��r�Ώۂ͂���ȉ��ł��ˁB���݂܂���B
4/3�̃J������F4��2/3�̃J������F2�ł����犷�ZF�l�ł��ˁB
�ł́A���߂�
4/3�̃J������2/3�̃J�����̂ǂ��炪�u���邢�v�ł����H
2/3�̃J�����̕����Q�i���邢�̂����ʂ̗��_�B
�����u���邳�v�Ȃ�A���鐯���߂炳��̎n�߂����_�ł��B
�����ԍ��F10278621
![]() 0�_
0�_
�͂炽����
�@���݊G�ł��傤��w
�@���͔]���C���[�W���ʐ^�����Ă���ɂ�����܂���A������B�e�ł�����up���܂��B�@�d�����鎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ�̂ŁB�@�����������̖��ŁA�c�_�̖{���ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �� 10274828
�@�u�����̕������������v �̂Ɏז��Ȃ�A�u���邢�E�Â��v �͌���Ȃ��ł��ǂ��Ƃ��v���Ă܂��B
�@�����������������̂ɃP���J�ɂȂ�����A�Ӗ��̂Ȃ����[�v�����Ă��Ă��ǂ������Ǝv���̂ŁA�b�������̊�b�ɂȂ郂�f������肽�������ł��B�@�����ꂪ�A���ʂ̖ڕW�B
�����ԍ��F10278864
![]() 0�_
0�_
Sakura saku����
�@���́A�����͋��ŁA�S���������Ă��܂���B�@������Ε�����̂����ł����B�@���͌��t���Ȃ��݂܂���B
�@���������l�Ԃ����͂������ꍇ�A���ׂ� �u���q�̐��v �ɂ��Ă��܂��������A�ԈႢ�Ȃ��ł��傤���H
�@�u���̗ʂ�\���̂ɁA���q�̐���p����v �Ə����̂��܂�����ł��傤���H
�����ԍ��F10278893
![]() 0�_
0�_
�s�����w�����
���s���p������������ ^^; ����Ăď������Ⴂ�܂������B^^;;
�i�������ԐM�҂��Ă邵 ^^;;;)
���݊G�Ƃ������A�u���邢�E�Â��v�͂��̃X���̎��̈�ł��B
�u���邢�E�Â��v������Ȃ����ʂ̗��_�Ȃ�A�ʂɗǂ���ł����AF�l�����Z����ƁA������ɂ����Ȃ�܂���H
2/3��4/3���ǂ����F�l�𑵂��āA��f���ꏏ�Ȃ�A2/3�̉�f�ʐς�4/3��1/4������A��f�ӂ�̌��̗ʂ�1/4�ɂȂ���Č����������A�킩��₷���Ȃ��ł����H
���ZF�l�ōl��������������₷���Ƃ����̂ł���A�~�߂܂��A�u���邢�E�Â��v�̓z���g�A�����ł��肢���܂��Bm(_ _)m
�����ԍ��F10279063
![]() 1�_
1�_
�s�����w����
>�@���̏ꍇ�A�e�J�����Ԃ� �� ���a�������E��p�������E�掿�i�������ʁ����邳�H�j�������E�ڂ��̑傫���������ł��B�@�i����F�m�C�Y�����V���b�g�m�C�Y�݂̂Ƃ����ꍇ�j
>�@����� �u���Z�e�l�v �́A���̔]���C���[�W�ł��B
�܂��A���ʂƂ����̂͐������l���Ȃ��Ƃ܂����Ǝv���܂��B
�����I(���w�I)�ɍl����A�摜�̏��ʂ́A�e��f���Ɨ��ł���Ƃ���A
1��f�̏��ʂ́A��Ԃ̎�蓾��m��×��Ԃ̐��ł��B���������āA���r�b�g�����Ă��A
�����f�l�����m������������A2^�r�b�g���@�̉�f�l�m���Ŏ��ꍇ����
���ʂ͌���܂��B
�܂��A�ŏI�I��8�r�b�g�ɂȂ��Ă��܂��A���͂⌳�����r�b�g���͊W����܂���B
(�������ȗʎq��������ƁA�m���ɕ肪�����A���ʂ͌���܂���)�B
���ʂ͔�ʑ̂̔�������̋��x�̋�ԓI���z�ɂ���Č��܂�܂��B���������āA��ʑ̂�
�قȂ�A���ʂ͈قȂ�܂��B
��f�T�C�Y���������Ȃ�A1��f������̌���(���ˑ�)�͏������Ȃ�܂��B�������A
���ʂ��������Ȃ�킯�ł͂���܂���B���ʂ�����̂́A���͂��f�ɓ�����ʂ�
�ʎq�I�h�炬�����ƂȂ�قǏ������ꍇ�����ł��B�B���f�q�͒ʏ�A���̑��̃m�C�Y�̕���
���ɂȂ�܂��B���������āA��f�T�C�Y�����������Ƃɂ�鍪�{�I�Ȗ��́A
�V���b�g�m�C�Y�����ɂȂ�قǂ��肬��̍����x�ŎB�e����ꍇ�݂̂ł��B
���ʂ́A���̗ʂɂ͔�Ⴕ�܂���B���������āA��f�T�C�Y�Ɉˑ����܂���B
�����ŁA���������̂́A���̂悤�ȕ����I���ʂł͂Ȃ��ł���ˁH
�Ȃ��A�u�ڂ��v�̗ʂ̓����Y��F�l�ƎB����ʃT�C�Y�ŋ@�B�I�Ɍ��܂�ʂŁA
��f�T�C�Y�Ƃ͊W����܂���B���������ʂƂ��W����܂���B
>tensor-tan����@���i��{�P�̃T�C�Y�������������������Ƃ��v���̂ł����A�ǂ��v���܂��H
���i��{�P�́AF�l�ɂ���Č��܂�A���ꂪ�掿�ɕ\��邩�ǂ����͉�f�T�C�Y�Ɉˑ����܂��B
(���̗ʂɂ͈ˑ����܂���)
�����ԍ��F10279186
![]() 2�_
2�_
�s�����w����
����A����ς�Q�ĂĂ܂��ˁB�\����܂���B
�u���邢�E�Â��v�͏Ɠx�ȂǁiF�l�AT�l��OK�j�Ɏg���Ă��������B
�ł��B^^;
150mm F2.0�i�t�H�[�T�[�Y�p�j��300mm F2.8�i�t���T�C�Y�p�j���ׂ�300mm F2.8�̕����u���邢�v�Ȃǂƌ����ƁA�Ӗ����ʂ����X�����L�т܂��B
�����ԍ��F10279188
![]() 2�_
2�_
���鐯�J��������
>�i�P�j
>�� ����܂��A�s���̂悢�悤�ɁA������g��������̂ł��ˁB
>
>�P�ʖʐςƎʐ^�S�̂̈Ⴂ��������A���̂悤�ȃ��x���̘b�͏o�Ȃ��Ǝv���܂��B
�u���̂悤�ȃ��x���v�Ƃ͂ǂ��������x�����m��܂��A���Ȃ��̃��x���ł���ˁB
���Ȃ��́A�u�P�ʖʐςƎʐ^�S�̂̈Ⴂ�v���킩���Ă���̂ł���ˁB�����ł��܂����H
���Ƃ��A��̓I�Ɏ��₵�܂��B
�����B���ʃT�C�Y�����A��f���̈قȂ�B���f�q���������Ƃ��܂��B
��f�����قȂ�̂�����A��f�T�C�Y���Ⴂ�A�����x�m�C�Y�����A�_�C�i�~�b�N�����W��
�قȂ�͂��ł��B���āA�ǂ��炪�掿���悢�ł����H
���鐯���_�ɂ��A�B���ʃT�C�Y���������Ɖ掿�������ɂȂ�̂ł����H
����́A�Ȃ��A�����咣�ł���̂ł����H(�����Ńg�[�g���W�[�Ɋׂ�)
>�i�Q�j
>�܂��ATranquility����̑O�̃J�L�R�ł����A
>�� ��f����������m�C�Y���������Ƃ������Ƃ�
>�� �m�C�Y�̌����͑����ʂł͂Ȃ��āA
>�� ��f���ЂƂЂƂ�����Ă��邱�ƂɌ������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
>
>�S�Ẳ�f�́A�f�W�^���ł͐��l�ŁA�≖�ł͔��������g�G�̋�h���x�ł����A
>���͈̔͂Ŋ������ꂽ�G�l���M�[��\�ɉ߂��܂���B����ɑ��Ă̑S�Ă̑���́A
>���̊����������ʂ����ɂȂ�܂��B
>
>�܂������ʂ����ł���A�ʐ^�̓��������ɓ�������������ł��̂Łi����������Ƃ��j�A
>��f���Ƃ͊W������܂���B��f�Ɖ�f�͊�{�I�ɔ�r�ł��܂��A�������
>�i��f���������j�̏ꍇ�́A�ʐ^�̓��������̔�r�ƔF�߂��܂��̂Ŕ�r�ł��܂��B
���鐯����́A�������킩��Ȃ��悤�ł��ˁB���������Ă�����̂���������
�킩���Ă���̂ł����H�G�l���M�[�����������I�Ȏ��̂��Ǝv���Ă��܂��H
�掿������(���ˑ�)�ɔ�Ⴗ�邱�ƂɂȂ�̂ł����H�Ȃ��ł����H
���Ȃ݂ɁA����(���ˑ�)�͎d�����̒P�ʂł��B�G�l���M�[�͘I�����Ԃ����߂Ȃ���
���܂�܂���B��f�ʐς�2�{�ɂ���̂ƁA�I�o���Ԃ�2�{�ɂ���̂ł͈Ⴂ�������
�v���܂����H���Ȃ��Ƃ����p���Ă���G�l���M�[�͓����ł����B
>�i�R�j
>�s�����w����֑̎��ł����A�掿�����ŁA��f����������A���f�̉掿������܂�
>�i����Ȃ��ƑS�̂̉掿�������Ȃ�܂��j�B���ꂩ�獂��f���ƍ��掿���i�݂܂���
>�t�@�C���T�C�Y�͓������ŋɒ[�ɂ͑����܂���B
�掿�Ƃ͑������茸�����肷��̂ł����H�ǂ�����Čv��̂ł����H�����Ɛ��l���ł���̂ł���ˁH
����́A���鐯���A�ʐς������Ȃ�A��f���ɂ�炸�g�[�^���̉掿�������ł����
�v������ł��邽�߁A�掿����f���Ŋ���A1��f�̉掿�ɂȂ�Ǝv���Ă��邾���ł��B
���˂Ƀt�@�C���T�C�Y�̘b���o�Ă��܂����ˁB
�������������̂��v�̂܂��A��f���������Ă���f���ɔ�Ⴕ�ăt�@�C���T�C�Y��
�傫���Ȃ�Ȃ��ƌ��������̂ł��傤���H
���k���Ă��Ȃ���w�b�_��������Ⴗ�邩��A���k�����ꍇ�ł��傤�B
��������ƁA��f���������Ă����ʂ����邩��A���k���������Ȃ��f���ɔ�Ⴕ�Ȃ��Ȃ��
���������̂ł��傤�H
�������A����Ȃ��Ƃ�������ł��傤���H
�������Ƃ������Ă����܂��傤�B�t�@�C���T�C�Y��傫���������̂Ȃ�A�����_���m�C�Y�������邱�Ƃł��B
�����ԍ��F10279221
![]() 4�_
4�_
���鐯���߂炳��@������
����{�I�ɃL���m���A�j�R���ƁA�I�����p�X�@�͑S�ăj�R���̃����Y���g���܂��B
4/3��R���f�W�̃����Y���g��Ȃ��Ȃ�덷�����������Ď��ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����H
���ZF�l�_���̂��߂ɂ́A���ꃁ�[�J�[���t���T�C�Y��APSC�ł̔�r���œK�ł���B�i��Ŋm�F�ς݂ł����A����͎�ςł͂Ȃ����ʔF���ł��j
���̑O��A4/3�Ƃ̔�����Ȕ�r�ɂ�����闝�R�͉��ł��傤���H
�t�ɁA���ۂ̏����𑵂��Ăقڌ덷0�ŏؖ��ł���APSC�Ɣ�r���Ȃ����R�͉��ł��傤���H
�l�̎���͑��̕������Ƃ͈Ⴂ�P���Ȃ��Ƃł�����A�ȒP�ɓ�������͂��ł����H
����ł͂�낵�����肢�v���܂��B
�����ԍ��F10279340
![]() 7�_
7�_
>�i�Q�j
>������掿�̍��͊ȒP�Ɍv�Z�ł��܂����A�l�Ԃ��ǂ������邩�͊ȒP�ł͂���܂���B
>35�~������APS-C�̍��͖�1.3�i�AAPS-H��APS-C��0.7�i�AAPS-C��4/3�͖�0.6�i�ł����A
>���Ԉ�ʓI�ɂ͂ǂ���傫���Ǝv���܂��ˁB
>���E����0.3�i��0.6�i�̊Ԃɂ���Ǝv���܂��B��i�̍����Ђǂ����ł��B
>4/3�ƃR���f�W�̍��͖�2�`3�i������܂����A���ꂪ�덷�Ƌ��܂����H
�掿�̍����v�Z�ł���̂ł����H
�u����F�l�v�̍����掿�Ȃ�ł��ˁB
�悤�₭�킩��܂����B���鐯�J��������̓��̒�
�掿������F�l�|F�l(�)��2*log2(�Ίp��)-2*log2(�Ίp��(�))�@�@(�P�ʁFEV)
������u���鐯�J�����̖@���v�ƌĂт܂��傤�B�u�掿�v�͒l���������قLj����B
������̂��āu�Â��v�ƌ����B
���ۂɌv�Z���Č��܂��傤�B��͓��R�u35mm�t���T�C�Y�v�ł��B
6×9�t�B�����@2.4
6×4.5�t�B�����@1.4
645DF�@0.9
35mm�t���@0
APS-C(Nikon)�@-1.3
APS-C(CANON)�@-1.4
Four Thirds�@-2.0
1/1.7"�@-4.4
�����Ƃ��Ȃ�Ɓu�掿�v�������ł��ˁB�R���f�W�Ȃ͖��O�B
�y���Ӂz
1)�u�掿�v�l�́A�J�����̉掿��ۏ�����̂ł͂���܂���B
2)���̖@�����ɃJ�����̘I�o�ݒ�Ɏg�p���Ȃ��ł��������B
�����ԍ��F10279374
![]() 9�_
9�_
�s�����w����
�܂����Ǝv���܂��B�]�v����Ȃ��Ȃ�܂���B�M�����������Ƃ��Ă�����̂����ʂł͂Ȃ��d�������̂��̂Ȃ̂ł�����B���́u�����v����ԉ���₷���̂��ȁH�E�E�E
�����ԍ��F10279426
![]() 1�_
1�_
>�掿������F�l�|F�l(�)��2*log2(�Ίp��)-2*log2(�Ίp��(�))�@�@(�P�ʁFEV)
����͂������ł��ˁB
���̗��_�l�ɋߕt�����Ƃ��B���f�q�̐i�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10280254
![]() 0�_
0�_
��ʓI�ɂ͉掿�͉�f���������̎���SNR�̔�r�����ʂ��Ǝv���܂��B
��i�Ⴂ�܂��ƁASNR�͖�A3.0103�̍����o�܂��B����͖ʐϔ�ɂ҂������v���܂��B
�Ⴆ��4/3��35�~�����̏ꍇ�ASNR-EV�Ȑ��́A��5.8��������Ă܂��B
http://www.dxomark.com/�̑S�ẴJ������SNR�i����j���r���āA
SNR�掿�Ȑ��Ԃ̋������ʐϔ�̌v�Z�ƍ����Ă�̂��m�F���Ă��������B
���������R�ʔ������l���o�܂��B
SNR�̍� �� 1 �Ȃ�l�̖ڂ͂悭������A
SNR�̍� �� 1 �Ȃ�悭������Ȃ��i���ɒኴ�x�̏ꍇ�j
�����ԍ��F10280503
![]() 0�_
0�_
�掿�n������F�l�|F�l(�)��2*log2(�Ίp��)-2*log2(�Ίp��(�))�@�@(�P�ʁFEV)
>������u���鐯�J�����̖@���v�ƌĂт܂��傤�B�u�掿�v�͒l���������قLj����B
��Ă�\������܂��B
���̎��́u���s�n�̖@���v���Ǝv���܂��B
�u���鐯�J�����̖@���v�ɂ���ɂ́A
�掿�t���掿�n×��f��
�Ȕ��ł��B���Ȃ��Ƃ��A���܂܂ł̂��{�l�B�̘b���ˑR�b���Ȃ�����́B
���łɁu���邩�߂̖@���v����`���Ă����܂��B
���ۂɎʐ^�B��x���P�O�O�|�i�掿�t�܂��͉掿�n�����ɐM���Ă�%�j
�ł��B�ǂ��ł��傤�H
�����ԍ��F10280912
![]() 8�_
8�_
�������������ƂɂȂ��Ă��܂���
�v�Z���Ƃ��o�Ă��Ęb���{�����炸��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�l���v���ɂ́@
�P�A�T�C�Y���傫���ق����掿�ɑ��ėL���Ȃ͓̂�����O
�@�i�L���Ƃ������Ƃł���@�����Ƃ͌����Ă܂���@���ƒP���ȉ掿�ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ƃ����ӌ��ʂƂ����邯�ǂ܂��S�̂Ƃ��Ăˁj
�Q�A�����Y�̖��邳�������Ƃ����̂́A�Ȃ��Ȃ�����
�@���Ƃ��t���T�C�Y�ōl����Ƃ̂�������ʂ̒��S�����g���~���O�����̂�
�@�t�H�[�T�[�Y���ȁ@�������ɖʐς����������疾�邳�����������ǁ@�����A������
�@���邳�͓����@���̗��_�ł����Əœ_�������Z����Ζ��邳�������I�ɂ�����͂��Ȃ̂�
�@�����Y�̃��C���i�b�v�ł͂����ł��Ȃ����@�Ƃ��������ł��B
�R�A��ԏd�v�ȁA�o���オ���Ă����ʐ^�̉掿�́H
�@�m���Ƀt���T�C�Y�̂ق����傫������Ƃ����悤�ȁA�ł����̐l��
�@���≴�͂������̂ق����F���Y��ł����Ȃ��ƃt�H�[�T�[�Y
�@������V���[�v�Ńt�H�[�T�[�Y�̂ق��������Ȃ��Ƃ�
�@���܂ł̌o���ł����ƁA�ʐ^�������������Ă�l�́@�t���T�C�Y��I�ԌX��������
�@���ʂ̐l�Ȃ͋t�Ƀt�H�[�T�[�Y��I�Ԑl���������������܂��B
�@����ς�ʐ^����Ă�l�́A����ڂ�����Ȃ��Ǝv������
�@������Ƒ҂ā@�ʐ^���Ă��炤�͈̂�ʐl������E�E�E
�Ƃ��������ł��B
�@
�����ԍ��F10281339
![]() 5�_
5�_
�S�������Ƀt�H�[�}�b�g�̑召�������c�_�������ł�����i��P�i�K�j�A
�唻�T�C�Y����R���f�W�T�C�Y�܂ŁA�掿�i�d�q�f�[�^�j�͊��S�Ɉ�v���܂��B
5d2�ŎB�����ʐ^��aps-c�T�C�Y�Ő����Ă��A
aps-c���������̉掿�i�d�q�f�[�^�j�͐���O��ŕω����܂���B
���₢��A�ӏ܃T�C�Y�����낦��ׂ��ł͂Ȃ����A�Ƃ����͎̂��̒i�K�̘b�Ƃ��ė������܂����A
����������o���ł�����A�u�ӏ܁v�̋ᖡ�͍ŏI�I�ɐl�ޓ��[��҂�������܂���Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�l�ޓ��[�Ȃ�唻����R���f�W�܂ŁA�덷�͈̔͂̉\�����Z���ł��B
����������ꂽ�������łȂ�唻���������邩������܂���B
���̏ꍇ�A����ꂽ�����Ƃ͑唻�����悤�Ɏd�g�����łȂ��ۏ��ǂ��ɂ�����܂��B
���āA�P�Ƀt�H�[�}�b�g�̑召�����łȂ��V�X�e���S�̂Ƃ��Ẵt�H�[�}�b�g����肽���ł�����i��Q�i�K�j�A
�{�P����ӌ������m�C�Y�Ɋ��肷�邩�ǂ����ŕ]���������ł��傤�Ǝv���܂��B
�𑜂̊ϓ_�Ō����A�{�P����ӌ������m�C�Y�ɃJ�E���g����̂��S���Ó��łȂ��Ƃ܂ł͌����Ȃ��ł��傤�B
�����Ƀ{�P����ӌ����Ɂu���v��������̂��l��Ƃ��ė����ł��܂��B
�����ɂ͗D����܂���̂ŁA��ʘ_���v�Z���Ă����ʂ�������܂���B
�P�O�O�l���X�O�l�Ɍ����R�K���܂́A�c��P�O�l�Ɍ����܂���ł��傤�B
�c��P�O�l�̊��҂ɁA�ق��̂X�O�l�͌�������䖝���Ďg���ƌ������҂�����ł��傤���H
��R�i�K�Ƃ��ẮA�����̋@��̃��[�J�[�ԍ��A�@��ԍ�������܂��B
���ꂪ���\�厖�ł͂Ǝv���܂����A���_�̂��߂Ɍ������������l�����܂��B
dxomark�͌����ɂ��������Ă��܂��B
�����ȉ����p
This dxomark article evaluates only the selected camera�fs RAW sensor performance metrics, and should not be construed as a review of the camera�fs overall performance, as it does not address such other important criteria as image signal processing, mechanical robustness, ease of use, flexibility, optics, value for money, etc. While RAW sensor performance is critically important, it is not the only factor that should be taken into consideration when choosing a digital camera.
�Ȃ��Adxomark��raw�𑪒肵�Ă��邾���ŁA�I���`�b�v�m�q�ɂ��𑜗�����ɓ����Ă��܂���B
��õ��Ƃ����ׂ���������܂���B
�Ōオ�ӏҁi����@��j�̒i�K�ł��B
�l�̎��́A�ӏ܃T�C�Y�A�ӏ܋����A�ӏܑԓx�A�S�̏�ԁA���̑����낢��B
�������������O�i�K�܂ł̋@��ԍ������k�������܂��B�w�K�Q�l���ł͂Ȃ��ł����A���R���݂�������܂���B
�����ԍ��F10281567
![]() 3�_
3�_
�� �@��ԍ������k�������܂��B
�C�����͕�����܂����B�����͉��ł��傤���B�܂��k���̕��͊��ł���ł��傤���H
�j�R����A�\�j�[�@�̔���RAW�͊��m�̂��̂ł����A�������ꂽ���ǂ����͉掿���͂ł�������܂��B
�e�Ђ̃A���S���Y�����Ⴂ�܂�����{�͑�w�ł��������Ă܂��̂ŏ����̋����������x������܂��B
�t�Z��ł͌덷���傫���Ȃ�܂����A����RAW�̉e���ł��̌덷�ł��ˁB
����������DxO�̃f�[�^�������番����Ǝv���܂����A����Ȃ��Ă��덷������قǂ���܂���B
0.3�i�O��܂ł��w�ǂł��i�̂̃J�����Ɣ�ׂ���0.7�i�̍����o��̂�����܂����j�B
�t�ɋZ�p�̈Ⴂ��A�����̌떂�����Ŋ撣���Ă����̒��x�̂��̂ł�����A
�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȗv���ƕ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10281635
![]() 0�_
0�_
�������͉��ł��傤���B
�o���ł��B
���܂��k���̕��͊��ł���ł��傤���H
������ł��B�����I�ɑ���s�\�ł��傤�Ǝv���܂��B
�l�Ԃ̈ӎ��̐��ʉ��͂ǂ��܂Ő��m�ɉ\�ł��傤���H
�����ԍ��F10281650
![]() 0�_
0�_
�܂�A
�|���X�E�G�E�x�b�g���咣���Ă�̂́A
�|���X�E�G�E�x�b�g���ǂ�������Ȃ����̂ł��ˁB
���̗ǂ�������Ȃ��덷�������Ă�DxO�̃f�[�^�����ꂾ���Y��Ɉ�v����̂��ʔ�������Ȃ��ł����B
�����ԍ��F10281669
![]() 1�_
1�_
���ǂ�������Ȃ����̂ł���
�����l�Ԃ̔F���̋��X�܂Ő��m�ɐ��ʉ��ł��܂�����A�m�[�x���܂P�O�O������Ȃ��Ǝv���܂��B
���ǂ�������Ȃ��덷�������Ă�DxO�̃f�[�^�����ꂾ���Y��Ɉ�v����̂��ʔ���
DXOMARK�̃����W������������������܂���B
�l�̌ܓ�����[�����O�D�S���O�A�O�D�T�`�O�D�X�͂P�ł����ˁB
�����ԍ��F10281753
![]() 2�_
2�_
2009/10/09 00:39�@[10280254]
>>�掿������F�l�|F�l(�)��2*log2(�Ίp��)-2*log2(�Ίp��(�))�@�@(�P�ʁFEV)
>����͂������ł��ˁB
>���̗��_�l�ɋߕt�����Ƃ��B���f�q�̐i�����Ǝv���܂��B
�����i���ƌĂԂȂ�A�ʐςőS�Ẳ掿�����܂�̂ŋZ�p�҂͋����Ċ�т܂��ȁB�e�Ђ��̂����������ď����ł������\�̃Z���T�[���J������K�v���Ȃ��ʐς����m�ۂ��Ƃ��������́B�E�F�n�[�����萸���ɐ�o���Z�p�͖����K�v�����邩���B
�ȂA�ʐς�������A��f�s�b�`�����߂������������グ����A�ꐶ������������K�v�������Ȃ��āA�P�ɖʐς����m�ۂ��Ă����Ηǂ��Ƃ������Ƃ�ˁB�����Y���K���B
����Ӗ��i���ƌ����Ȃ����Ȃ����B�Z���T�[�J���҂ȂǂȂǑ�ʂ̐l���팸���\�ɂȂ�Ƃ����A�Z���T�[�����̍H���̐i���B�Ȃ掿����̂��߂̘J�͂��Ȃ������B
�ق�ƁH
�i���Ƃ����Ȃ�A�ʐς͏������̂ɑ傫���ʐς̃J�����ɔ���悤�ȃZ���T�[���J������A�܂���E��˔j���悤�Ƃ�������i���ƌ������Ȃ��낤���B
���Ȃ݂Ƀt�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�����D��Ă���Ƃ͑S���v���Ă��Ȃ��̂ł������炸�B����Ɉ�T�ɔ�肷��C�����Ȃ����B
�掿�I���Č����邩�炨��������ł����āA�w�t�H�[�}�b�g���̑�̂̉掿(�K���\����m�C�Y�̑����Ȃǁj�̖ڈ��x���Ă��������������������Ȃ��낤���Ǝv�����B
�Ⴆ��ISDN��ADSL��FTTH�̑��x�̑����̈Ⴂ�����������������A�݂����ȁA����Ȓ��x�̎g�����̃C���[�W�ŁAADSL�͊�n�ǂ���̋������e�����ăA�i���O�Ȃ݂̑��x�����邵�AFTTH���}���V�����^�C�v���ƒx�����A�������ɂ��S���͈قȂ邯�ǁA�w��{�I�ɂ�FTTH�͑����āAADSL�ł�ISDN���͑����ł���x�݂����ȁB
����Ȏg�����B����Ȃ�L��Ǝv���B
��������ȊT�O�I�Ȃ��Ƃ������Ȃ�t�H�[�T�[�Y��������Ȃ��đS�Ẵt�H�[�}�b�g�̃N�`�R�~�ł�������A���[�J�[�Ƃ����̑��̊W�c�̂ɒ�Ă�����������ۂǗ��v�������B
�M�d�Ȏ��Ԃ��g���ĐF�X�l���ď������݂�����̂ł���ΐ������̕����ǂ��̂ɁA�Ǝv��������B
�����ԍ��F10281806
![]() 6�_
6�_
���̓C���t���G���U�ɂ���������M�b�N�����ɂȂ�ƋC�����œ���܂��B
����ȂƂ��̓J�����̃m�C�Y�������낤�����Ȃ��낤���W����܂���B
�ł��̒����ǂ��Ƃ��ɂ͏��p����P�����T���Ԃ��U���Ԃ������ăj�����b�R���邩������܂���B
�ǂ�����{���̎��ł��B���ꂶ��ɒ[���ƌ���������������܂��A
�����̃o�C�I���Y���̕ϓ����X�R�̈�p���x����C�ʂ̉����Ƃ������Ƃ��炢�͗����ł��邩������܂���B
�ŋ߂�DXOMARK������ɂ߂���A���M���o���肷�邱�Ƃ�����ł��傤���B
DXOMARK�͓d���ω��ɑΉ��ł��Ă��A�l�Ԃ̊���R���g���[���\�͂͗c�����̂ł��B
�����ԍ��F10281811
![]() 0�_
0�_
�F�l
�@�S�̔� UP �ł���Ǝv����ƒ��ł����A�M�d�Șb�����Ă���������`�����X�Ȃ̂ŁA�����炭���P�\�������B
tensor-tan����
�@���̗���������Ȃ��̂ŁA�����Ă���������Ǝv���܂��B
�@���̋����ɂ��Ăł��B
����f�T�C�Y���������Ȃ�A1��f������̌���(���ˑ�)�͏������Ȃ�܂��B�������A
�����ʂ��������Ȃ�킯�ł͂���܂���B���ʂ�����̂́A���͂��f�ɓ�����ʂ�
���ʎq�I�h�炬�����ƂȂ�قǏ������ꍇ�����ł��B�B���f�q�͒ʏ�A���̑��̃m�C�Y�̕���
�����ɂȂ�܂��B
�@�܂��A���z��Ԃ����肵�Ă̘b�ł��̂ŁA�u���̑��̃m�C�Y�v �͏�������O���Ă��������B
�����I�w�i �� ��ʎB�e�̘b�ł́A���̎B�e�ł̓R���f�W�ŏ\���Ǝv���܂� �i�V���̖{�C�B�e�ȊO�̈�ʎB�e�̓����Ȃ̂œڒ����܂��� �E �ŋ� WX1 �Ƃ��������̂ŗV��ł݂悤�Ǝv���Ă��܂��j�B�@����͐l���ꂼ��ł��傤�B
�����̏��� �� �V���ł���Θb�͕ʂł��B�@32bit �܂łn�j�ł��B��http://www.astroarts.co.jp/products/stlimg6/spec/tone-j.shtml
�@�V���ł́A���̂�炬�ȊO�̗v�f����邽�߂ɁA�摜�f�q�̗�p�E�_�[�N�摜�ƃO���C�摜�̎擾�������Ȃ��܂��B
�@���̒��ɂ͗��z��Ԃɋ߂��B�����@������̂��Ƃ��������������A������̗��z��Ԃɂ��t����������������Ǝv���܂��B
�@���̏�Ł�
�p�P�D�@���́A�P�ʖʐϓ�����̌��q�̐���������Ɨh�炬���������Ȃ�悤�Ɍ�����̂ł��傤���H
�@���ɁA������葽����荞�߂�f�q�قǁA��萳�����K�������擾���₷���Ǝv���̂ł��B
�@���̂悤�ȍl���������Ă��܂����B
�@���q����������f�ɐi�� �� ��̓d�ׂɕϊ� �i������H�j �� �u�d�C�I�ɑ��������v�𑪒�ł���� +�Pbit�B
�@���� �Pbit ��ςݏグ��Ƃ��āA�d�ׂ߂Ă������̗e�ʂɂ�� 10bit �� 12bit �̊K���������Ɛݒ�B
�p�Q�D�@�u���܂��܁v 10bit �� �Q�^�R��1200����f�A12bit �� �S�^�R��1200����f �ƌ������Ƃɂ���A�K�����̐��m���� �i��ʓI�� �Wbit �ʐ^�ɂ͏o�Ȃ���������Ȃ����j ��҂̕�����B�@�ƌ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�� �i���邢�ꏊ�ł��j�B
�@���萔�ł�����낵�����肢�������܂��B
�����ԍ��F10282472
![]() 0�_
0�_
Sakura saku����
�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@�����������t�̒����ł����A�ȉ��͂ǂ��ł��傤���H
�@���q�̐��i�����E���Ȃ��j
�@���i�����E���Ȃ��j
�i�u���̗ʁv ���Ȃ������Ȃ��̂��A���o�I�ɑS��������Ȃ��̂ŁA��������̂��ӌ������肢�������̂ł��j
�����ԍ��F10283187
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳���
����3��͓������₵�Ă܂����H�����ł����H
�܂��܂��J��Ԃ��ł����A�d�n�r7�c�̔Ŋ��Z�e�l�_�̕��y���������ĉ������B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000041113/SortID=10159202/
������Ɠ���������ȒP�ł���H
�V�����̃J�������Ċ��ł���l�����ɁA���̃J������1.5�i���Â��āA�掿����������厸�s�ł����ˁ@�Ǝ��_�������Ă����܂��傤�B
�����ނ炩�炻��Ȃ͂��͂Ȃ��A�����Y�̂e�l�������͂����Ȃ��Ɣ��_���ꂽ�牽�x�ł��J��Ԃ����肪��������܂ŋ����Ă����܂��傤�B
�܂��d�e�r15-85�����@�e3.5-5.6�́@35�������Z�@24-136�����@�e5.6-8.9����
�łe�l�����Z���ĂƂĂ��Â������Y�ɂȂ邱�Ƃ��Y�ꂸ�ɁB
���E�ȏ�͂��邹�����̊��Z�e�l�_�ł��B�l�ɂ͗���s�\�Ȃ̂ňًc�̂�����͒��ڂ��邹������ɂ��肢���܂��B
�����ԍ��F10283720
![]() 9�_
9�_
���ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȗv���ƕ�����Ǝv���܂��B
�����ɂ���l�݂͂�Ȓm���Ă܂���A�Ȃ������Z�e�l�_�̂����͂�������Ȃ�H
�������ȑO�ʎq�͊w�Ƃ����ΐ����_�Ƃ��Ƃ�ł��Ȃ����ƌ����Ă�������������ǁH
�������b�̂��ƂɁA���ǂ����Ō�̂����́A�Z���T�̂ł������������Ƃ��������p�^�[���O�O
���܋C���������ǁA���������Ĕނ͂Ђ�����Ƃ茾�����������Ă��邾���Ȃ̂��H�����������Ƃ���A����܂ł̘b�̂��ݍ���Ȃ����킩�����悤�ȁH
�����ԍ��F10283874
![]() 8�_
8�_
�s�����w����
�@���i�������ǂ��E�����������j���ł��ǂ��\�����Ǝv���܂��B
�u����a�����Y���ƌ����悭�ʐ^���B���Ɓv�������\���Ȃ炵�����肵�܂����H
���ʂƂ��Ȃ��̂́A�_���Ă�����̂����̗ʂł͂Ȃ��̂���ł��B
�܂��A�������肭�錾�t���Ȃ��Ƃ������Ƃ́u�d�����v�͎ʐ^���B��Ƃ��ɂ��قǏd�v�ł͂Ȃ��ƌ������Ƃ��Ӗ����܂��B�i���邳�͏d�v�ł��j�������肱�Ȃ����́i�Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ����́j������邳�̒P�ʂŌ����A���邢�Â��ȂǂƂ����̂œǂ�ł���l�����������r���̂ł��B
�܂��A�d�����͏Ɠx×�ʐςł����畡�G�Ȍv�Z�����Ȃ��Ă��Z���T�[�ʐςʼn����Ă��܂��܂��B���l���������Ȃ�t���T�C�Y����ɂ�����Ō����Ηǂ��̂ł��B�i�ʐϔ䂻�̂��́j���̕��X�����G�Ȏ�������Ă��܂����A����Ɠ����ɂ������Ȃ�@���[�g�ʐϔ�@�Ƃ��邾���ł��B
�����ԍ��F10283938
![]() 3�_
3�_
�s�����w����A
�Z���T�[�ׂ̍����Z�p�f�[�^�����\�C�}�C�`�ǂ�������܂��A�Z�p�̍��������Ă�
����������_���i���x�ƌ����܂��B���̍��ƌ떂�����g�w�́h���덷�ƌ����邩�ǂ�����
�����ł����i�̂̃L���m�� vs ���̑��ُ͈펖�ԂƔF���j�A�R���f�W��FX100���f��
�t���T�C�Y�@��D3�̈��f�̐��\���債�ĕς�Ȃ��ł��ˁBDxO�̃f�[�^�ł��m�F�ł��܂��B
�掿�̍��͖w�ǏW���ʐρi�m�C�Y�j�̍��ŁA�V���b�g�m�C�Y�̈�l�ŋ��ł��B
FX100�̃Z���T�[���S������35�~�����܂ŐL�т邱�Ƃ��ł�����A�L����D3�ɓ���Ă�
����D3�̊��x�Ƒ債�ĕς�Ȃ��̂ł��i��_���i�̍��������j�B
mainoa����A
���ې��l�����̎d�l�Ƒ����Ⴄ�Ǝv���܂����A24-137mm f/5.6-9.0�����ȃ����Y�ł��ˁB
ZD14-54/2.8-3.5�Ɠ����ʈÂ������Y�ł��i�]���[�������������Â��Ȃ�Ɨ����ł��܂��j�B
�����ԍ��F10284025
![]() 0�_
0�_
�s�����w����A�����́B
�����A�摜�����̐��I�m���Ƃ����Ƃ���ł͑f�l�ł����A�V�̎ʐ^�̊�{�͗������Ă������ł��B
���V���b�g�m�C�Y�ƌ�������̗h�炬�ł����A���q�̊m���I�݂������ł��傤���A���ʂ̎B�e�ł͖��ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂܂������Ȃ��Ǝv���܂��B�O�ɂ������܂������A�����ԘI���ɂȂ�Ε݂��ς����̂ŁA�Ȃ�����ł��B
���������̓V�̎B�e�ł��A���V���b�g�m�C�Y�����ɂȂ����Ƃ����b�͂܂��������������Ƃ�����܂���B����A�������̈�b�I�o�Ƃ����������x�B�e�ł������܂���B
�m���I�݂Ƃ������Ƃł́A�J���~���Ă���Ƃ���Ɠ����悤�Ȃ��̂��ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��ɉJ�ʌv��~���l�߂āA�J�~��̎��Ɉ�ĂɊW���J���܂��B�͂��߂ɉJ�ʌv���p���p���ƔG�ꂾ�������ɂ͉J�H�̂�������邱�Ƃ��o����ł��傤���A�J��1mm�ɂ��Ȃ�A��������͂܂������킩��Ȃ��Ȃ�܂��B
�v���ɈӖ��̂���ʂ����܂鍠�ɂ́A����͂܂��������ɂȂ�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł́B
�����悤�ɁA���V���b�g�m�C�Y���B�e�Ŗ��ɂȂ�Ƃ���A���q���I�����Ԓ��ɂق�̐����炢�����͂��Ȃ��Ƃ����悤�ȏꍇ���炢���Ǝv���܂��B���Ԃ�Ŗ�̃J���X���^���ÂȂ̂ł́B
���s�̂�������₤�鐯���߂炳��́A���V���b�g�m�C�Y���f�W�^���ʐ^�̃m�C�Y�̌������Ƃ���������Ă��܂����A���͂����ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�B���f�q���H�̗�p�ŁA�m�C�Y��啝�ɒጸ�o���邱�Ƃ����̗��R�ł��B
�܂��A��ʓI�ȎB�e�Ō��V���b�g�m�C�Y���ʂ��Ė��ɂȂ邭�炢�Ȃ�A���ꂱ���Z���T�[�T�C�Y�̑召�ɂ�����炸���ɂȂ��Ă���͂��ł��B
�����ԍ��F10284030
![]() 6�_
6�_
>>�掿������F�l�|F�l(�)��2*log2(�Ίp��)-2*log2(�Ίp��(�))�@�@(�P�ʁFEV)
>����͂������ł��ˁB
>���̗��_�l�ɋߕt�����Ƃ��B���f�q�̐i�����Ǝv���܂��B
����̎��́Atensor-tan�����鐯���߂炳��⋞�s�̂����������Ă��邱�Ƃ��u���ɕ\�����炱���Ȃ�܂���v�ƌ����������ł��ˁB
���̎����Ӗ��̂��鐳�����������Ă��邩�ǂ����͕ʖ��ŁA���ZF�l�_�҂͂��̎����Ȃ��������邩�Ƃ������Ƃ��������K�v������̂ł́B
�����O�ɏ�����
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂�v
�@�@�@��
�u�Ȃ��Ȃ�m�C�Y�ɂ͉�f�T�C�Y���f���͊W�Ȃ����炾�v
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�u�m�C�Y�ɂ͉�f�T�C�Y���f���͊W�Ȃ��v
�@�@�@��
�u�Ȃ��Ȃ�A�C���[�W�Z���T�[���������ʂ��掿�����߂邩�炾�v
�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[
�́u���v�����̍����I�ŋ̒ʂ��������̂��Ƃł��B
���鐯���߂炳��
�Љ�ĉ��������T�C�g�̃f�[�^�x�[�X�������
OLYMPUS E-30 �� Nikon D3�ł́A�m���Ɋ��x�ɂ���2�i����SNR��������悤�ł����A
Nikon D3 �� D3x �ɂ�1�`1.5�i���̍�������܂��B
����͂ǂ����������̂ł����H
�����ԍ��F10284236
![]() 5�_
5�_
���鐯���߂炳��
�������肪�Ƃ��������܂��B�ł͒������܂��B
��
���܂��d�e�r15-85�����@�e3.5-5.6�́@35�������Z�@24-136�����@�e5.6-8.9����
���łe�l�����Z���ĂƂĂ��Â������Y�ɂȂ邱�Ƃ��Y�ꂸ�ɁB
��
���܂��d�e�r15-85�����@�e3.5-5.6�́@35�������Z�@24-137�����@�e5.6-9����
���łe�l�����Z���ĂƂĂ��Â������Y�ɂȂ邱�Ƃ��Y�ꂸ�ɁB
����ł͂��炽�߂āA
���ZF�l�_���̂��߂ɂ́A���ꃁ�[�J�[���t���T�C�Y��APSC�ł̔�r���œK�ł���B�i��Ŋm�F�ς݂ł����A����͎�ςł͂Ȃ����ʔF���ł��j
���̑O��A4/3�Ƃ̔�����Ȕ�r�ɂ�����闝�R�͉��ł��傤���H
�t�ɁA���ۂ̏����𑵂��Ăقڌ덷0�ŏؖ��ł���APSC�Ɣ�r���Ȃ����R�͉��ł��傤���H
���̎���ɓ����ĉ������B
�����ԍ��F10284245
![]() 5�_
5�_
�J������ISO���x�͌��\�C�}�C�`���m�ł͂���܂���̂Ŕ�r���鎞���ʓ|�ł����A
DxO�̃f�[�^���g���܂��ƁAFX100��5D�̉掿�́A��SNR �� 12�A��4�i�̍�������܂��B
�ʐϔ�Ōv�Z���܂��ƁA4.4�i�̍�������͂��ł����A�����f�[�^�������炻����
0.4�i���Ȃ��ł��ˁB����́A�R���f�W�̉ߓx�ȃm�C�Y�����ʼn��߂ł���Ǝv���܂��B
�ʐς͎���21�{���Ⴄ�J�����ł����A�ׂ�������Ȃ��Ă��덷��0.4�i�Ɏ~�܂�܂��B
�W���ʐς̍��Ŗ��Õ�����ƕ�����܂����A�����Ƃ��Ėʔ����Ƃ���́A
���G�l���M�[�A�V���b�g�m�C�Y�Ƃ����^�Ɛl��ߕ߂�����A��ʊE�[�x��
��܂܂ł̎������������Ă��܂��܂����B
�����ԍ��F10284309
![]() 0�_
0�_
���邹������@�ǂ�������ł����H
�����������H
�����ԍ��F10284629
![]() 1�_
1�_
Tranquility����
���V���b�g�m�C�Y���ʉ����܂������H
>���ʂ̎B�e�ł͖��ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂܂������Ȃ��Ǝv���܂�
�ʂɖ��ƂȂ�Ƃ͏����Ă܂��H
>���s�̂�������₤�鐯���߂炳��́A���V���b�g�m�C�Y���f�W�^���ʐ^�̃m�C�Y�̌������Ƃ���������Ă��܂���
���͌��V���b�g�m�C�Y�Ɍ��肵�Ă��܂��H
�����ԍ��F10284656
![]() 0�_
0�_
�������ł����H
���������̍l���Ɏ��M�������A���`������Ǝv���Ȃ炱�̎���ɂ܂��߂ɂ�������ׂ��ł��B�����č���͐M�O�ɂ��������đ��̌f���ł����Z�e�l�̕��y�����s���邩�A�܂��͉߂���F�ߍ���̍s�������߂�̂��A�Ȃ瑸�h���ĉ������܂���B
�������A��������ē������Ƃ��J��Ԃ��ȂȂ�A�m�����������������̔ڋ����Ƃ݂Ȃ��A�y�̂ɒl����l���Ƃ��āA������R�c�R�c�Ɠ˂����݂�����Ă�������ł��B
�����ԍ��F10284784
![]() 8�_
8�_
�� �������ł����H
������O�ł��傤�B�����o����Ď������Ă��������B
�����ԍ��F10284808
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
�܂�������Ă܂��ˁB
���͉�f�������Z�œ_�����Ɋ܂߂�ׂ����Ə����܂����B
�������������Z���āA�����g�嗦�ɂ��Ĕ�r����̂ł����B
�����ԍ��F10284812
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�f�q�Ƀm�C�Y�������Ƃ��A��̉�f�ɓ��Ă������ǂꂾ�����m�Ɏ������邩�͊m���̐��E�ł���A�i�Ⴆ�� n�̌��q����̉�f�ɓ��Ă��̂ł���j�������鐔�́u���� n�A�W��
�� ��n�v�̐��K���z�ŕ\����܂��B
2009/09/29 02:20�@[10229854]
>�f�q�̃m�C�Y�Ɋւ��đ傫���t�H�[�}�b�g�Ƀ����b�g�͖����Ƃ��A���q�̐��ɉ��������V���b�g�m�C�Y�Ɋւ��Ă͑傫���t�H�[�}�b�g�̃����b�g������Ƃ������Ƃł��B
2009/09/29 03:11�@[10229936]
>��{�I�Ɏ��̃A���o���ł̈Ⴂ�͌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ł��B
>2009/09/30 01:41�@[10234832]
>�Q�C���A�b�v�ɂ���� S/N��͕ς��܂���B���ʂ����Ȃ����̂̌��V���b�g�m�C�Y�̑�����
�m�C�Y�̑��������ł��B
�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l������
����B
2009/10/02 00:00�@[10244233]
>>���V���b�g�m�C�Y�͌��ʂ̏��Ȃ��Ƃ��Ɍ����ɂȂ邱�Ƃ�A�I�����Ԃ������Ȃ�Ό��q�̗h
>>�炬�����ω����ăm�C�Y�ʂ���������͂��ł��邱�ƂȂǂł�
>���̗ނ̃m�C�Y�͔M�m�C�Y�ł��傤���B���W�͂킩��܂��A���܂�ėp���̂���m�C�Y���f���Ƃ͎v���܂��B�Ⴆ�uF5.6�A1/200sec�v�ɔ�ׁuF8�A1/100sec�v�̃m�C�Y�ʂ͓�{�ɂȂ邩��o���邾�������V���b�^�[�X�s�[�h��I�����ׂ��A�Ȃ�Ă��܂蕷���܂���B
�Ƃ�����A���V���b�g�m�C�Y�͌��ʂɉ�������������`�����̂Ȃ̂ŁA���ʂ����Ȃ��V���h�[���̓m�C�Y��������ł��傤�B
�܂��A���V���b�g�m�C�Y�ȊO�̃m�C�Y���������܂��B�Ⴆ��
http://www.imagegateway.net/p?p=Biu4wkfAsdH
����̈�ԏ��߂̉摜�́A��f�s�b�` 1.69��m �̂��̂ł��B�߃o���f�B���O�m�C�Y���m�F�ł��܂��B������o�C�L���[�r�b�N�� 1/2 �k������ΕW�����̌������m�F�ł��܂����A���̌�g�債�Ă��o���f�B���O�͎c��܂��B
����͋ɒ[�ȗ�ł����A������ɂ��摼�̃m�C�Y�̑��݂��A���V���b�g�m�C�Y�̑��݂Ək���ɂ��m�C�Y�������ʂ�ے肷�邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂���B
>���̂�����u���w�Y�[���ƃg���~���O�Y�[���v�������B�S�������f�q���l�����ׂ�B
�V�O�i�����l�{�A�m�C�Y���l�{�A���ʂ� S/N��̓g���~���O����g���~���O���ꏏ�B�قȂ��
�́i�r�j���O�����ꍇ�́j���V���b�g�m�C�Y�����B
2009/10/04 23:29�@[10260691]
>��f��������Ό��V���b�g�m�C�Y�͌���܂��B
1200����f��1��f�ɂ��Ă�����܂��B���̏ꍇ�͑������x�̌���ł��ˁB�B���ʂ̌����������ł͎B���ʐςłقƂ�Ǎ����o�܂��A����ł����_�l�ǂ���̍��͏o��ł��傤�i������E�ȉ��ɂȂ�Ƃ��A�������������Łj�B
2009/10/05 13:00�@[10262710]
>�ʐ^�Ƃ͎B����O��Ƃ��܂��B�B������ƌ��ʂ̑��ǂ����V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ƂȂ��Ă�����܂��i����͂����ł��ˁH�j�B
�m�C�Y�̑������Ȃ����u���l�v������ł��B���Ȃ��ɂƂ��ĉ��l�ł͂Ȃ���������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͉��l�ł��B
���ʂ������Ƃ���̕W�����̊����i���j�����適������m�C�Y���������ƌ����B
���q�̐U�镑�����m���I�ł���Ƃ������������ł��i���ꂪ���������j�B
2009/10/05 13:43�@[10262853]
������ƐU��Ԃ��Ă݂܂������A
���Ȃ�͂�����ƌ��V���b�g�m�C�Y���m�C�Y�̌����Ƃ���������Ă��܂��B
�����ԍ��F10284831
![]() 3�_
3�_
��������O�ł��傤�B
�����ɐ��`������Ƃ������Ƃł��ˁB�ł͂��̎���ɓ����ĉ������B
���ZF�l�_���̂��߂ɂ́A���ꃁ�[�J�[���t���T�C�Y��APSC�ł̔�r���œK�ł���B�i��Ŋm�F�ς݂ł����A����͎�ςł͂Ȃ����ʔF���ł��j
���̑O��A4/3�Ƃ̔�����Ȕ�r�ɂ�����闝�R�͉��ł��傤���H
�t�ɁA���ۂ̏����𑵂��Ăقڌ덷0�ŏؖ��ł���APSC�Ɣ�r���Ȃ����R�͉��ł��傤���H
���肢�v���܂��B
�����ԍ��F10284834
![]() 8�_
8�_
Tranquility����
���̂��A���_�̘b�����Ă���̂ł����ǁB
���V���b�g�m�C�Y�������m�C�Y�̌����ȂǂƂ͌����Ă��܂����H
�����ԍ��F10284873
![]() 0�_
0�_
�]���p�ɂ���g���Ă݂܂��H
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/special/dsp/bbs/?mode=all&namber=1582&type=0&space=0&no=0#1650
�����ԍ��F10284893
![]() 0�_
0�_
���鐯�J��������
���Ȃ��͂���܂Ŏ����̎�ς����₪����X�ɉ����t���Ă����̂ł���B
�{�C�Ŏ��o���Ȃ��ƌ����Ȃ�A���̂��Ƃ����Ȃ��Ɏ������Ă��炢�����̂ł���B
���̂��߂ɂ͂d�n�r�f���ł��Ȃ�������܂ł���Ă������Z�e�l�̕��y���������Ă��炤���Ƃ���ԕ�����₷���̂ł��B
������������Ɏ����̂���܂ł̍s���ɂ��Ă̎����邱�Ƃ��ł���͂��ł��B
�i�Ȃ������܂Ŕ��������̂��j
�����������ƂŁA���ӂłȂ��A�M�O������̂Ȃ�^���ȋC�����Ŏ���ɂ��������������B
�����ԍ��F10284894
![]() 9�_
9�_
�� ���Ȃ�͂�����ƌ��V���b�g�m�C�Y���m�C�Y�̌����Ƃ���������Ă��܂��B
�V���b�g�m�C�Y�Ƒ��̌����́A���Ƃ̎��ɑ告�o�Ώ��w���ʂ��Ǝv���܂��B
����ȊO�́A�钷�b���I�o���̈Ód��������܂����A���ʂ̎B�e�͖w�NJW������܂���B
�i��f���ϘR���d�q����10�ɂȂ�I�o���Ԃ́A30�b�`1�����K�v�j�B
�����ԍ��F10284920
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>���V���b�g�m�C�Y�������m�C�Y�̌����ȂǂƂ͌����Ă��܂����H
>>��{�I�Ɏ��̃A���o���ł̈Ⴂ�͌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ł��B
>>2009/09/30 01:41�@[10234832]
>>�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l������
����B
>>2009/10/02 00:00�@[10244233]
�����Ă܂��H
���鐯���߂炳��
>�V���b�g�m�C�Y�Ƒ��̌����́A���Ƃ̎��ɑ告�o�Ώ��w���ʂ��Ǝv���܂��B
�ǂ������ǂ����ł����H
>����ȊO�́A�钷�b���I�o���̈Ód��������܂����A���ʂ̎B�e�͖w�NJW������܂���B
�ł́A��͂���V���b�g�m�C�Y���������ƁB
�ł���A�C���[�W�Z���T�[�T�C�Y�̑召�ɂ�����炸���l�Ɍ��V���b�g�m�C�Y�̉e��������͂��ł��ˁB
���q���z�̊m���I�ȕ݂ł���A�Z���T�[�̂ǂ��͈̔͂��ǂ̂悤�ȃT�C�Y�łƂ��Ă݂Ă��A�����悤�ɕ݂���͂��ł͂���܂��H
�܂�A�}�N���Ō��Ă��~�N���Ō��Ă��A���ׂĂ݂�Γ����悤�ȃ����i�m�C�Y�j���o��͂��B
����ƁA�����قǂ������܂������ANikon D3 �� D3x ��SNR�ɁA1�`1.5�i�̍����o����������Ă������������̂ł����B�����Ƃ�����35mm�t���T�C�Y�B
SNR�́A�Z���T�[�T�C�Y�ɂ݈̂ˑ�����͂��������̂ł͂���܂��H
�����ԍ��F10285054
![]() 3�_
3�_
���̔����ŁA
>��{�I�Ɏ��̃A���o���ł̈Ⴂ�͌��V���b�g�m�C�Y�̈Ⴂ�ł��B
����͌��ł��ˁB
����m�C�Y�����V���b�g�m�C�Y���A�������͑��̃m�C�Y���͏ؖ����ׂ���i�����͎����Ă��܂���B
�V���b�g�m�C�Y�̒�ʉ��������͖̂{�X���ɂ����Ăł����A�V���b�g�m�C�Y�� 1/��N �̊����ł�����̂Ȃ̂ŁA�ʐώl�{�Ȃ� 1/2*��N �̂���ɂȂ�܂��B�܂背�x���𑵂�����̂���̕��� 1/2 �ɂȂ�܂��B
�Ƃ��낪�i�������g�̗����̊Â���F�������悤�Ɂj�A�k���ł� 1/2 �ɂ͌���܂���B����͑��̉摜�ł������ł��B
�Ƃ������ƂŁA���̃A���o���́u���V���b�g�m�C�Y�ȉ��̉��P���v�ł��B
�ŁA�ߋ��ɎB�������낢��ȃf�W�J���̃O���[�J�[�h�B�e�摜��]�����Ă���̂ł����A�ǂ������_�l�ʂ�Ȃ�Ȃ���ł���ˁB
��̓I�ɂ̓R���f�W�͗��_�l���o���c�L�����Ȃ��A�f�W�^�����̓o���c�L����⑽���A�Ƃ����X���ɂ���܂��B
���̕ӂ��x�C���[�Z���T�[�i����̐����摜�j�ɂ����E�Ȃ̂��A�l�̓��o�ɊԈႢ������̂��킩��܂��B�덷�Ƃ������邩�ȁA�Ƃ��v���܂����B
���Y�^�B
��f�s�b�`�� p [��m] �Ƃ��āAISO100���̈��f������̃O���[�̌��q����
N = 0.4066 * p^2 * 10^3
���W���� �� 118/��N
�Ȃ�ł����A���ۂɂ͋t�K���}���������Ă��܂��̂ŁA
�W���� �� (0.692*118)/��N
�ƂȂ�܂��B
���ł�������f�s�b�`�A1.54��m �� ISO100 �́i��f1������́j���q�����v�Z����ƁA
N = 970
���W���� �� 2.62
�ƂȂ�܂��B
APS-C 600����f�i��f�s�b�` 6.4��m�j�ł�
�W���� �� 0.5 ���x
�ƂȂ�܂��B
���Ȃ݂Ɍo����ł́A�W������ 1 �� 2 �ł͂����Ԉ���Č����܂��B
����������𐔒l�Ƃ��Ĉ����Ɣ��ɏ����������ł��B
���V���b�g�m�C�Y�̌��̂��߂ɂ̓K���}�ϊ��O�̃��j�A�摜�̕����ǂ���������܂���B
�����ԍ��F10285057
![]() 0�_
0�_
>>�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l������
����B
>>2009/10/02 00:00�@[10244233]
����͂��̒ʂ�ł���B
���x���u�m�C�Y��萫������v���Č����Ă܂���ˁH
�����ԍ��F10285059
![]() 0�_
0�_
Tranquility����
���炾��X�������ĂĂ����傤���Ȃ��ł���B
�u��f�������Z�œ_�����Ɋ܂߂�ׂ��v
�������ł������͍l���Ă݂܂��傤�B����Ƃ��N���[�}�[�ł����H
�����ԍ��F10285064
![]() 0�_
0�_
>APS-C 600����f�i��f�s�b�` 6.4��m�j�ł�
�ԈႢ�ł��B
��f�s�b�` 8.0��m�A��f�ʐ� 64��m2 �ł��B
�����ԍ��F10285070
![]() 0�_
0�_
�� Nikon D3 �� D3x ��SNR�ɁA1�`1.5�i�̍����o����������Ă������������̂ł����B
�� �����Ƃ�����35mm�t���T�C�Y�B
Tranquility���������肵���~�X���Ǝv���܂����A����̓X�N���[�����{�̏ꍇ�ł��ˁB
��f������{����������܂��̂ŁA��f��SNR�͈�i�̈Ⴂ�͗\�z����܂��B����SNR�́A
�ʐ^�̉掿�̔�r�Ɏg���܂���̂ŁA������������SNR������K�v������܂��B
�X�N���[�����{�̏ꍇ�AD3��D3X�͉�f�Ή�f��1.2�i���̍�������܂����A����̏ꍇ��
��0.2���ɂȂ�܂��BD3�̖k���ܗ֎����X�|�[�c��p�@�̐��i���炱��0.2�i���̍���
�傫���������������_������Ǝv���܂����AD3X�̃����W�̍L���Ƃ����̐��\�Ƃ̃o�����X��
�l��������܂��B�܂��AD3�ґ�ȉ�H�v�Ɣ�ׂ܂��ƁAD3X���V���v���ɂȂ��Ă܂��̂�
���̊W�����邩���m��܂���iD3X�̕����R�X�g�������̃n�Y���Ǝv���܂��j�B
�ƌ����Ă��A0.2�i���̍��ł��ˁB
�����ԍ��F10285152
![]() 0�_
0�_
���鐯����
�Ȃ��A�d�n�r�f���Ŋ��Z�e�l�̕��y���������Ȃ��̂ł��傤���H�H�H
������肠��܂�����
�����ԍ��F10285182
![]() 11�_
11�_
�s�����w����
>�p�P�D�@���́A�P�ʖʐϓ�����̌��q�̐���������Ɨh�炬���������Ȃ�悤�Ɍ�����̂ł��傤���H
�V���b�g�m�C�Y�ɂ��Ă�Wikipedia��������Q�Ƃ��������B(���ɂ����Ƃ悢�T�C�g������
��������܂���)
SNR=N/��N=��N
N�͌��q�̐��ł��B�����ŁA���ӂ��Ă������������̂́A���q�̖��x�͊W�Ȃ��Ƃ�������
�ł��B�܂�A���ʂ����Ȃ��Ă��A�I�����Ԃ�L����S/N�͉��P���܂��B�Ƃ͂����A
�M�m�C�Y�͘I�����Ԃɔ�Ⴕ�đ����܂��̂ŁA���ɓV�̎ʐ^�̂悤�ɂ��Ƃ��ƒ����ԘI�o��
�K�v�ȏꍇ�́A�ł��邾������a�Ō��ʂ𑝂₵�����������̂͂������̂Ƃ���ł��B
�ʎq�͊w�̗L���ȓ�d�X���b�g�����ɂ����āA���q���ЂƂ����Ă��ꍇ�A�ŏ��́A
�����_���ȕ��z�ɂ��������Ȃ����̂��A���𑝂₵�Ă����ƁA���Ȃ��͂������
����Ă���̂ƌ����͓����ł��ˁB���Ԃ�B�]�k
>�@���ɁA������葽����荞�߂�f�q�قǁA��萳�����K�������擾���₷���Ǝv���̂ł��B
>�@���̂悤�ȍl���������Ă��܂����B
>
>�@���q����������f�ɐi�� �� ��̓d�ׂɕϊ� �i������H�j �� �u�d�C�I�ɑ��������v�𑪒�ł���� +�Pbit�B
>�@���� �Pbit ��ςݏグ��Ƃ��āA�d�ׂ߂Ă������̗e�ʂɂ�� 10bit �� 12bit �̊K���������Ɛݒ�B
CCD��CMOS�������t�H�g�_�C�I�[�h�̌��d�ϊ��𗘗p���Ă���킯�ł����A10�r�b�g��
1024�~���A12�r�b�g��4098�~���ł��̂ŁA���p���Ă�����q�̐��ɔ�ׂ�Ώ��Ȃ��킯�ŁA
���Ԃ�A����̉�f�T�C�Y�ł��A�V���b�g�m�C�Y��ʂɂ���A�\���ȗe�ʂ�����̂���
�v���܂��B���q�̐����\������A���ʂ̓A�i���O�Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂ŁA���ʂ�������1��
�Ȃ��Ă����ʂ����邱�Ƃ͂���܂���B
>�p�Q�D�@�u���܂��܁v 10bit �� �Q�^�R��1200����f�A12bit �� �S�^�R��1200����f �ƌ������Ƃɂ���A�K�����̐��m���� �i��ʓI�� �Wbit �ʐ^�ɂ͏o�Ȃ���������Ȃ����j ��҂̕�����B�@�ƌ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�� �i���邢�ꏊ�ł��j�B
�ǂ������ɂ͔��f�ł��Ȃ��̂ł����A�ʐ^��8�r�b�g�ł悢�̂������̂��B8�r�b�g�ł�
�\���\���͂̂���ʐ^�͂ł���̂ł����A�l�Ԃ̖ڂ�8�r�b�g�ǂ���ł͂Ȃ��L���
�_�C�i�~�b�N�����W�������Ă���̂͊m���ł��B���̂��߁A8�r�b�g�̉摜����邽�߂ɂ�
�����ƍL���_�C�i�~�b�N�����W���K�v�Ȃ̂��Ǝv���܂��B8�r�b�g���x�ł悯��A
�t�H�[�T�[�Y�͑������Ƃт��N����Ȃ�Ă�������邱�Ƃ�����܂���B
�����炭�A���̓m�C�Y�Ȃ̂��Ǝv���܂��B��m�C�Y�ɂ��邽�߂ɂ́A��f�T�C�Y��
�傫���قǂ悢�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�B���f�q�͂��̂��炢�̐��\�������Ă���
�Ƃ������Ƃł��傤�B
���邢�ꏊ�ł͂ǂ��Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃł����A�����炭��肪�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ�
�ł���̂��Ǝv���܂����A�B���f�q�́A�v�������荂���x���ɐU���ă`���[�j���O�����
����̂ŁA���邩�낤���A�Â��낤���A�B���f�q�̗��p������˃G�l���M�[�͏���������
�������Ă���̂��Ǝv���܂��B�܂藘�p�\�͌��ʂ��\�������Ă��A�킴�킴���ʂ�
���炵�Ďg���Ă���̂��Ǝv���܂��B
�����ł́A�V�̊ϑ���CCD�Z���T�Ȃ��ł͐��藧���Ȃ��悤�ł��ˁB�d�q�f�o�C�X�Ȃ̂ŁA
�������s�O���N����Ȃ��B�\���ȘI�����Ԃ��m�ۂł���A�l�Ԃ̖ڂ𗽉킷�銴�x��
������Ƃ������Ƃł��ˁB
�����A�̓V�̎ʐ^���B���Ă܂����B�ł��A�f�W�^������ɂȂ��Ă���͂���Ă܂���B
����ʐ^���B��ꍇ�ɂ́A�����ʂ�͈͂ŘI�o���l�߁A��������̉摜�����������
�悢�A�Ƃ����b���āA�Ȃ�قǂƎv���܂����B
�����ԍ��F10285222
![]() 1�_
1�_
���Ȃ��A�d�n�r�f���Ŋ��Z�e�l�̕��y���������Ȃ��̂ł��傤���H�H�H
������肠��܂�����
�\�j�[�E�T���X�����f���f�q��菬���ȃL���m�����f���f�q�ł�����L���m���D���ȕ��Ȃ̂ŏo���Ȃ��̂ł͂Ɛ������ċ��܂��B
�܂��A���_�����������Ŕ�r�ʐ^�𓊍e���ꂽ�������������Ȃ̂Ł@�f�W����������Ė����ăR���f�W�ŎB���Ă�\���Ⴕ���́A�J�����������ċ��Ȃ��\�����L�邩���B
�����ԍ��F10285408
![]() 13�_
13�_
DxOMark��SNR�����ł݂�ƁA�I�����p�X��E-520���L���m����50D�Ɨǂ������Ȃ�ł���ˁB
�i�������v�����x�ɂƂ�Ƒ�̓������ɏ��B�j
�_�C�i�~�b�N�����W�ł�50D���ǂ��āA�F�̎��ʂ�E-520�̕����ǂ��B
�Ƃ����킯�ŁASNR�����Ŕ��肷�邱�ƂɈًc����B
��������ł�50D�̃Z���T�[�̕�����ɂȂ�ً͈̂c�͖�������ǂˁB
����ƁA�Z���T�[�����̃e�X�g������A���炩��F�l�Ƃ͊W�����ł��ˁB
���ZF�l���D���Ȑl�́A���̒��Łu�Z���T�[�T�C�Y�̔�v�̎������ZF�l�̃L�����Ǝv���Ă���̂�������܂��AF�l���W�Ȃ��Ƃ����F�l�Ɩ��̕t�����̂��o���Ă��A�ǂ�ł���l�����������邾���ł��B
�����ԍ��F10286335
![]() 12�_
12�_
LE-8T����@������
�L���m���@�ȊO�̑����̃J�����ɂ��������Ă���Ƃ����͎̂����ł��BEOS�L�X���g�p���Ă���Ƃ̃l�^������܂��B
�ȉ��͂����̊��z�ł��E�E�E
�@�͂�����Ɩ{���������܂����ˁB����Ή���悤�ɔނ͓��{��͊��\�ł��B�͂��߂̍��̂��ǂ��ǂ����������͍폜������邽�߂̉��o�Ƃ��v���܂��B���̔��̃X���b�h�ɓn���Ď��X�ɍr�炵�������Ƃ����������l����Ɓ@�ނ̃��X�̍폜�Ɓ@�������֎~�@���K�p���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10287080
![]() 8�_
8�_
���鐯���߂炳��
>Tranquility���������肵���~�X���Ǝv���܂����A����̓X�N���[�����{�̏ꍇ�ł��ˁB
��f������{����������܂��̂ŁA��f��SNR�͈�i�̈Ⴂ�͗\�z����܂��B����SNR�́A
�ʐ^�̉掿�̔�r�Ɏg���܂���̂ŁA������������SNR������K�v������܂��B
�X�N���[�����{�̏ꍇ�AD3��D3X�͉�f�Ή�f��1.2�i���̍�������܂����A����̏ꍇ��
��0.2���ɂȂ�܂��B
�v�����g��SNR�́A8Mpix�ɂ��낦300dpi��8"×12"�Ƀv�����g�����摜���r���Ă���悤�ł����A�J�������Ƃ�SNR���r����̂ɂǂ�ȈӖ�������܂��傤�H
�v�����g�T�C�Y�����낦��Z���T�[�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������L���Ȃ͎̂����̂��Ƃł��B�≖135mm����6×9cm�����l��Ƀv�����g���Ĕ�r����悤�Ȃ��̂ł��傤�B
�����ŏo�Ă���킸����SNR���́A���[�J�[�̋Z�p�͂̍���������܂��A���邢�̓m�C�Y�Ɖ𑜓x���ǂ��������邩�̍l�����̍��Ȃ̂�������܂���B
�t�ɁA����f�@���g�p����ꍇ�͑�T�C�Y�����O��Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ������̂ŁA�X�N���[�����{�ł̔�r�̕�����ʓI�ƌ����邩������܂���ˁB
�i�����ɗ��Ă�����́A�����l���Ă�����������̂ł́H�j
���s�̂�������
>�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l������
����B
��ɏ������Ƃ���A���̗��R�͒P���Ƀv�����g���̊g�嗦������������ł��傤�B
�����܂ł����V���b�g�m�C�Y�Ƃ��������Ȃ�A���̗��R�������������������B
>�u��f�������Z�œ_�����Ɋ܂߂�ׂ��v
���Z�œ_�����ɂǂ��܂߂�̂��悭�킩��܂��A��͂��f�����掿�i�m�C�Y�H�j�ɊW����Ƃ������Ƃł��ˁB���̂ւ�́A���鐯���߂炳��Ƃ͈Ⴄ���l���̂悤�ł��B
�������A��ɂ������܂������A�Ȃ�����Ȃ߂�ǂ��������Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����H
�����������Z���Ȃ��Ă�
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����̃����Y�ʼn�p�������v
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�g�p�T�C�Y�Ŕ�ʊE�[�x��F�l��2�i���[���v
����ŏ\���ł��B
�����ԍ��F10287162
![]() 5�_
5�_
����
��u�≖135mm����6×9cm�����v
���u�≖35mm����6×9cm�����v
�ł����B
�����ԍ��F10287194
![]() 0�_
0�_
�Ȃ��Ȃ��������ł��ˁ@������e�������̕��͂�������Ȃ����炢�@���e����Ă܂���
���̓|���X�E�G�E�x�b�g����@�Ƃٓ����ӌ��Ȃ�ł�����
���������Ɓ@���n�@����@�B�����狣���ł������ȁA
���Ƃ������ʼnߋ��̃f�[�^�A�I��̉ߋ��̏��s�@�܂��J�Ïꏊ�����������ǁ@����Ƃ����
��f�[�^���R���s���[�^�[�ɂԂ����ނ킯�ˁB����ł��ď��������Č����Ɓ@�����Ă��܂�
�킯�@�ŏ������l�ɂȂ�łƕ����ƁA�o���Ɗ��Ɠ�����킯�@
�������̐l���ߋ��̃f�[�^��S�R�������Ă���킯�ł͂Ȃ��āA��͂莩���̓��̒���
�ߋ��̃f�[�^�͓����Ă���킯�ˁA��������̌o���Ȃ���
�������̐l�̓��ɂ́A������Ȃ��f�[�^�͓����Ă��Ȃ��킯�@���Ƃ����Ƃ���ɏW��
�����f�[�^�ˁB�l�����̃X�^�[�g���Ⴄ��ˁ@���Ƃ������Ƃ��͂��߂�̂�
�f�[�^����͂��߂�̂ł͂�
������ʐ^���A���炵���ʐ^���������B���̎ʐ^�͂ǂ��ŎB�����낤�@�ǂ�ȃJ������
�B�����낤�B�Ǝʐ^����͂��߂�̂ˁB�Ƃ��낪���̃J�����͂���Ȑ��\������A�掿��
�����Ƃ��A�J���������炢�����Ⴄ�Ɩ�킩��Ȃ��Ȃ�킯
�܂��Ⴞ���ǁ@���̎ʐ^���Y�킾�ˁ@���̓I�����p�X�̂d�|�R�O�O�ŎB�����B
�Ƃ��������ˁB���̐��D�����������ȕʂƂ��ā@E-300�̐�E-300�ł����o�Ȃ��킯��
��������Ɖ��͂��̐́A���̃J�����ł��o���邺�@�Ƃ��@��������ƍD�݂ɂȂ��Ă���킯
��{�I�ɂ̓T�C�Y����������A�����ɍ��Ή掿�͈����Ȃ�͓̂��R�@����͂��傤���Ȃ�
�Ƃ��낪�B���Ă݂���@�����@�T�C�Y���������̂ɂ������̂��掿�������Ȃ����Ă��Ƃ�
�ǂ�ǂ�킯�@������܂��ʐ^�͖ʔ������ǂˁ@����ʐώ����`�݂����̂����邯
�ǁ@����Ȃ̂킩���Ă�킯�ŁA������v�҂͍H�v���Ă���킯������
�ʔ����Ȃ��Ă���Ǝv�����ǁ@�܂�����Ȋ����ł��B
�����ԍ��F10287253
![]() 17�_
17�_
Sakura saku����
�@�����������E�E�E
�@�����V���b�^�[�X�s�[�h�������Ȃ��̂́A�����Ƃ��ē�����O������ł��B
�@�u�I�����Ԃ����낦�v �Ƃ��A�u���R�K���I���ŃO���C�J�[�h���B�e�v �Ƃ��A�����Ă����������ǂ������ł��ˁB�@���݂܂���A���s�ł����B
�@�p�^�[���Q�̏��ŏ����Ă������A�����ꂾ���ł͕�����ɂ���������������܂���B
���@�i�����ŁA�V���b�^�[�X�s�[�h�� �u�S�^�R�̃J�����v �̂S���̂P�ƂȂ� �i�����Ȃ�����ł�����ˁj �j
�@�d�C�̎��Ȃ�A���̋����ϑ��҂ɁA�B�e�@�ނ����W�ŋ����Ă���������Ƃ�����܂��āB
�@Sakura saku���� �ɋ����Ă��炤�̂ɁA�d�C�ɒu���������痝���ł��邩�H �Ƃ��v���čl������A���������Ď��Ԃ�����Ă��Ȃ��W�H�@�Ǝv�����B
�@���Ȃ݂ɁA12bit �� �Ƃ��́ARAW �t�@�C���̒��́A�P��f���̊K������z�肵�Ă��܂��B
�@�E�E�E������肵�āB�@�͂����āB
�����ԍ��F10287541
![]() 0�_
0�_
���ȕs���ł����B
>�v�����g�T�C�Y�����낦��Z���T�[�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������L���Ȃ͎̂����̂��Ƃł��B�≖135mm����6×9cm�����l��Ƀv�����g���Ĕ�r����悤�Ȃ��̂ł��傤�B
�����ŏo�Ă���킸����SNR���́A���[�J�[�̋Z�p�͂̍���������܂��A���邢�̓m�C�Y�Ɖ𑜓x���ǂ��������邩�̍l�����̍��Ȃ̂�������܂���B
��
�v�����g�T�C�Y�����낦��Z���T�[�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������L���Ȃ͎̂����̂��Ƃł��B�≖35mm����6×9cm�����l��Ƀv�����g���Ĕ�r����悤�Ȃ��̂ł��傤�B
���T�C�Y�C���[�W�Z���T�[�̋@����v�����g�Ŕ�r�������ɏo�Ă���킸����SNR���́A���[�J�[�̋Z�p�͂̍���������܂��A���邢�̓m�C�Y�Ɖ𑜓x���ǂ��������邩�̍l�����̍��Ȃ̂�������܂���B
�ł����B
�����ԍ��F10288045
![]() 0�_
0�_
tensor-tan���� �E Tranquility����
�@���肪�Ƃ��������܂��B
�@���������l��������̂��Ǝv���܂��B
�@�����A���̂܂܉������čl����ƁA�u���������ȏ�ɖ��邢�ꏊ�ŁA���傫�ȃt�H�[�}�b�g���g���̂́A�{�P�Ȃǂ̃����Y���̓��������ꍇ�̂� �i�J�������̖��t���������j�v �Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�{�f�B�[���̊W�͂قƂ�LjႢ���Ȃ� �i���邢�ꏊ�ł������j�A�Ƃ������Ƃł���A�Q�^�R�i�Ƃ��A�P�^1.7�Ƃ��j �Ȃǂ̍����R���f�W�g�p�҂́A�u35mm�t���T�C�Y�Ƒ債�Ĉ��Ȃ��v �Ƃ��Ċ�ׂ�Ǝv���܂��B
�@�i�����A�R�j�~�m�`�Q �i���Q�^�R�t�H�[�}�b�g�j ���g���Ă����W�ŁA����̌�p�@�킪�~�����Ǝv���Ă���̂ł���w�j
�@�����ɂ͂�͂�A�u�l�Ԃ̊��o�Ƃ��Ă킸���v �Ƃ� �u�Wbit�ɂ��Ă��܂��J�������̖��t���̕����傫���v �Ƃ���������邩������܂��ARAW �t�@�C���ɂ͂���Ȃ�ɈႢ������Ǝv���̂ł� �i35mm�t���T�C�Y vs �Q�^�R�j�B
�@�S�^�R���g���Ƃ������́A�ƂĂ��b�܂�Ă���A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@���ʂɎʐ^���B���Ă������A����ɕs���������Ȃ��ł��傤�B�@���������ł��B
�@�ł��A�S�^�R�ɔ�ׂ�`�ŃR���f�W���g������H
�@�R���f�W�����炱��ŗǂ��Ƃ����̂͂���܂� �i�ʐ^�Q�Ɓj�B
�@�S�^�R�ɑ��āA1�^2.4 �Ƃ��̏����������g���Ă݂Ȃ��ƁA�v�����Ȃ����Ȃ̂�������܂���B
�����ԍ��F10288081
![]() 0�_
0�_
��������orz
�^�������̃X���̃A�b�v�ɓ��������Ⴄ��
�X�N���[������̂����
�قƂ�Ljӌ��̂��ݍ���Ȃ��@�_�������܂ł���Ǝז�
�ǂ������݃����O����Ă���Ă您�肢������
�����ԍ��F10288102
![]() 5�_
5�_
�ڂ���ʐ^���ԈႦ�܂����B
�@�^���Â������̂ŁA�Ƃ肠�����P���B���� �i�O��UP�̎ʐ^�j�A���������������̕����ǂ��̂˂ƕ������C�������̂��A����̎ʐ^�ł����B
�@�R���f�W�ł��A�^���ÂȒ��A�����ʐ^���B���Ƃ����A�`�F�b�N�ŎB�e�������̂ł��B
Tranquility����
�@�����Ă�r���ŕ�����܂���ł������A��ʘ_�Ƃ��đ傫�������L���Ƃ���܂��ˁB
�@�C�����܂���ł����A���炵�܂����B
�����ԍ��F10288187
![]() 0�_
0�_
���v�����g��SNR�́A8Mpix�ɂ��낦300dpi��8"×12"�Ƀv�����g�����摜���r���Ă���悤�ł����A
���J�������Ƃ�SNR���r����̂ɂǂ�ȈӖ�������܂��傤�H
�l�ɂ͂��ꂼ��G�ꂽ���Ȃ�����������ł��傤����A��������ɐ������Ă��\���܂���ƌ����Ă��������B
���āA�ǂ�ȈӖ����ƌ����܂��ƁA����͏�L�̃v�����g�����ȊO�ł͖��ɗ����Ȃ�����Ȍ��ʂ��Ƃ����Ӗ��ł͂Ǝv���܂��B
����Ȋ��ʼn����꒼���ɕ��ڂ��ƁA����̓T�C�o�o�̏���Ȃ�ł���ƌ���������������܂���B
Dxomark���g���A���������ꈬ��̌��ʂ������������Ɉ�ʘ_�܂ōL������ƍ���ł��傤�Ǝv���܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�l���Ȃ��Ă������邱�Ƃł����ADxomark���p�����v�����^�[��C���N�A
��掆�A����@��ɂ́A���ꂼ�ꐫ�\�Ƃ������̂�����܂��B
���̐��\�́A�X�̊ӏ҂�{�A�c�o�d�����p����v�����^�[��C���N�A
��掆�̐��\����ъӏ҂̎��͂Ƃ̑��֊W���K�����������I�ł͂���܂���B
�Ƃ������قڕs���ł��B���ꂪ��P�_�B
���ɁADxomark�̃v�����g�T�C�Y�⑪�苗���ƁA
�X�̊ӏ҂̊ӏ܃T�C�Y����ъӏ܋��������łȂ����Ƃ͎����̗��ł��Ǝv���܂��B
�ӏ܁^����̑Ώہi�ʐ^�j���T�C�Y�E���e�Ƃ��Ɉَ��E�s�ψ�ŁA
���ӏ܁^���苗�������łȂ��ȏ�A�ӏ҂�Dxomark�Ɠ��l��
�m�C�Y���Ƃ炦�Ă���Ƃ����ؖ����������܂���B���ꂪ��Q�_�B
�ق��ɂ��l�Ԃ͑̒��⊴��A���_��ԁA�F���́A�v�����݁A�ӏܑԓx�A�ӗ~�A
���̑����܂��܂ȃo�C�A�X������Ȃ���ʐ^���ӏ܂��܂��B
���ɕs����ȑ��݂ł���A���������ϓ_���������@��Ɠ����悤��
�m�C�Y��F�����Ă���Ƃ����O���������������ł��傤�Ǝv���܂��B
�ł�����J��Ԃ��ɂȂ�܂����ADxomark������ȏ������œ���ȑ��u�ɂ�葪�肵�����ʂ�
���͈͓̔��ő��d���Ȃ��ł͂���܂��A��ʂɕ��Ղɒʗp����Ƃ����ؖ��͂ǂ��ɂ�����܂���B
�������u�ӏ܉掿�v�ɂ������A�����ȉȊw�̑ԓx�Řb���������ł�����A�X�^�[�g�n�_�͂��̂�����ł͂Ǝv���܂��B
�����Ƃ��A�d�q�f�[�^�i�f�W�^���掿�j�Ȃ�����ƊȒP�Ɍv�Z�ł��܂��B�S���p�\�R�����v�Z���Ă����ł��傤�B
�������A�p�\�R���͕]�������܂���B�]���͐l�Ԃ̎d���ł��B�u�ӏ܁v�ł��ˁB
�@�B���v�Z�����r�m�q���l�Ԃ̊ӏ܂ɂ��̂܂ܓK�p�ł���Ƃ����f�p�ȏ���́A
���ۂɂ͉Ȋw�̏ؖ�������܂���B�ł�����A�X�̊ӏ҂��ʂɔ��f���邵���Ȃ��̂ł��B
���͂�����l���ƌĂ�ł��܂��B
�ӏ܂͌l���ł��B�ӏ܂�����f�ƌ��������Ă�������������܂���B
�������l�����W�߂Ĉ�ʘ_����肽���ł�����A�ǂ����J�������̑������[�łȂ��A
���ЂƂ��l�ޓ��[�Ń��j�o�[�T���Ȍ��ʂ��ق����ł��B
���̂Ƃ��̕W���I�Ȋӏ܃T�C�Y�͑S���ł��傤���H�`�Q�ł��傤���H
���E�I�ȕ��y���猾���āA�������߂k���O��ȏ�Ɍ����ȃT�C�Y�͂Ȃ���������܂���B
�m�C�Y��������m��Ȃ��l�ɂ́A�m�C�Y�̂Ȃ邩��������ׂ��ł��傤���B
����Ƃ��m�点�Ȃ��̂��K���ł��傤���B
�{�P�̓m�C�Y��������܂���B���ӌ������m�C�Y�����Ă����ł��傤�B
�ǂ�����m�C�Y�łȂ��Ƃ����Ȋw�̏ؖ��͂Ȃ��ł��ˁB
�m�C�Y�������͊ӏ҂̋��O���ł��B
�����ԍ��F10288488
![]() 7�_
7�_
[10285057] �̔��Y�^�̒����B
>��f�s�b�`�� p [��m] �Ƃ��āAISO100���̈��f������̃O���[�̌��q����
>N = 0.4066 * p^2 * 10^3
����͂����ł��B
������ 555��m �̒P�g�����ł̌v�Z�i�����ɃY���͂��肻���j�B
���̌�̕W�����i@���x��118���j���S�ʓI�ɒ����B
18% �̃O���[�� 118 �ɍ����悤�ɂ����ƌv�Z����� 0.18354899 �ŁA����� x �Ƃ����B
x = 0.18354899
�W���� �� 255*(((1 -+ 1/��N)*x)^(1/2.2)) +- 118 �i���������j
118 �𒆐S�ɁA���͉��̕����傫���A��̕����������Ȃ�܂��B�t�K���}�J�[�u���Q�Ă��邽�߂ł����A���̈Ⴂ�͂ق�̂킸���i�R���}�������x�j�B
��f�s�b�` 1.67��m ���ƕW������ 1.7 ���x�B
2/3�^500����f�́A��f�s�b�` 3.5��m ���ƕW������ 0.8 ��B
APS-C600����f�́A��f�s�b�` 8��m ���ƕW������ 0.3 ���B
SILKYPIX �Ń��m�N���łȂ�ׂ������Ɍ������܂��B
�莝���̉摜�Ŏ������ƃR���f�W�͗��_�l�� 1�`2���������x�AAPS-C ���� 7�`8���������x���Ƃ肠�����o�Ă��܂��B
��̂���Ȋ����ł����Ǝv���̂ł����ǁB
���Ƃ� RAW �f�[�^�̃O���[���̃o���c�L�����̂܂ܕW��������\�t�g������A���悭�킩��ł��傤�B
�����ԍ��F10289993
![]() 0�_
0�_
�� �v�����g�T�C�Y�����낦��Z���T�[�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������L���Ȃ͎̂����̂��Ƃł��B
�����Ƌ��܂�����̓I�Ɍ����܂��ƏW���ʐςɂ�銴���G�l���M�[�̍��Ƃ��̍��ɂ��
���V���b�g�m�C�Y�̍��������ƌ����Ă邾���ł��ˁB����Œ萫�E��ʂƂ����߂ł��܂��B
�����ԍ��F10290222
![]() 0�_
0�_
�s�����w����@
���V���b�^�[�X�s�[�h�������Ȃ��̂́A�����Ƃ��ē�����O������ł��B
�]���āu�ٓ��̎l�������悤�ł��݂܂���v�Ƃ����O�̃��X�ƂȂ����̂ł��B
�����āA�u���v�Ȃ�킴�킴�I�����ԂƋL���K�p���Ȃ��̂ł��B�i�܂܂�Ă��邩��j
���肭���Ȑ����ōς݂܂���B
10277430�ŋM�����L���Ă���ʂ�A�l���Ă��邱�Ƃ�`����͓̂���ł��ˁB
�����ԍ��F10290530
![]() 0�_
0�_
���ӌ��������Ȃ��ƌ����܂����A���ۂǂ̈ʂ̍������邩�̂ł��ˁB
4/3������ԁAZD14-54/2.8-3.5�̃����Y�͕��ʂɎ��ӌ���������܂��ˁB
�����͂܂��𑜂��Â��Ƃ��Af/5.6�����ƈÂ��Ƃ����v��Ȃ������̂ł����A
AF�݂̓��ƂƂ��Ɂg�H�h�̕������Ǝv���܂��B
�����Y�̑傫���ƒl�i����́A���ӂ��ǂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��A
���ʂƂ��āA��������35�~�����̃����Y��蒆����������i�Â����ƂɂȂ��Ă܂��B
ZD14-35/2��AZD35-100/2�Ȃǂ�����Ε�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10291321
![]() 0�_
0�_
�ٓ��̎l���ɒ��ڂ������Ƃ�����A35�~���������Y�̕W�����f��������āA
�i�O�ʂ̕W�����S�~�H�e�����Y�͔���グ�{���̕��ρA�S�̂͊e�����Y�̎g�p���ŕ��ρH�j
ZD�Ɣ�r����Ǝv���܂����A�I�����p�X����̐�`���L�ۂ݂��đ�܂��ȗ\�z�����܂��ƁA
���ӓ̃G���A�ň�i�̉��P�ŗǂ��ł��傤���H
�ł�����P���v�Z�őS�̂�0.2�i�̗��v�ɂȂ�̂ł����A���p���͂��̔����ȉ��ł��傤���H
�����ԍ��F10291407
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
>>�v�����g�T�C�Y�����낦��Z���T�[�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������L���Ȃ͎̂����̂��Ƃł��B
>�����Ƌ��܂�����̓I�Ɍ����܂��ƏW���ʐςɂ�銴���G�l���M�[�̍��Ƃ��̍��ɂ��
>���V���b�g�m�C�Y�̍��������ƌ����Ă邾���ł��ˁB
�Ⴂ�܂���B
�Z���T�[�i�t�H�[�}�b�g�j�T�C�Y�̑傫�ȃJ�������v�����g�掿�ɗL���Ȃ̂́A�P�Ɉ����L���{��������������ł��B
�u�W���ʐςɂ�銴���G�l���M�[�̍��Ƃ��̍��ɂ����V���b�g�m�C�Y�̍��v�ƌ����Ȃ�A1��f�ɂ�����W���ʐςōl���Ȃ�������܂���B
�Z���T�[�S�̖̂ʐςŋς��čl���邱�Ƃ͊ԈႢ�ł��B�Ȃ��Ȃ�A�Z���T�[�ʐϑS�̂��ς����Ƃɂ���ăm�C�Y�ω����A�m�C�Y�̉e�������Ă��܂����ƂɂȂ邩��ł��B
�����āA1��f�ɂǂꂾ���̌����W�܂邩�̓����Y��F�l�ɂ���Č��܂�܂��B�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ͊W�Ȃ�F2.0��F2.0�ŏW���\�́i�����Y�́u���邳�v�ł��j�͓����ł��B
���鐯���߂炳��͂ǂ����ăZ���T�[�S�̖̂ʐς̘b�Ɏ����čs��������̂ł��傤�H
��̂Q�̏�������[10291321][10291407]�́A��������������Ă���̂��F�ڕ�����܂���B
���E�q��m�ɂ��肢���܂��B
�����ԍ��F10291669
![]() 1�_
1�_
�|���X�E�G�E�x�b�g����
�ڂ���������A���肪�Ƃ��������܂����B
�u�ӏ܁v�Ɋւ��邲�ӌ��A�܂��������ӂł���܂��B
�����ԍ��F10291703
![]() 0�_
0�_
�� �P�Ɉ����L���{��������������ł��B
����ł́A�����L���{�����ĉ��ł��傤�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
���̘I�����G�l���M�[�i�̑�\�A����L�^�����t�B������摜�t�@�C���j�������L���ꔖ��
�Â��Ȃ�̂ł��ˁB�P�ʖʐςł͈Â��Ȃ�̂ł��B����������P�ʖʐς̉掿�������Ȃ�܂��B
�S�̂̉掿�͕ς�Ȃ��̂ł����A�A�i���O�̏ꍇ������Ƃŋ͂��ɗ����邱�Ƃ�����܂��B
����͊�{�I�Ɉ����L���{���ɂ͊W���Ȃ��̂ł����A�����L���{�����傫���Ȃ��
�Ȃ�قǑ��������Ȃ��ƍl�����܂��i����͗]�k�j�B
�����ԍ��F10291715
![]() 0�_
0�_
>���̘I�����G�l���M�[�i�̑�\�A����L�^�����t�B������摜�t�@�C���j�������L���ꔖ��
>�Â��Ȃ�̂ł��ˁB
�Ⴂ�܂��B
�t�B�����Ȃ犴���������_�A�摜�t�@�C���Ȃ�I���f�[�^���擾�������_�ŁA���鐯���߂炳��̌����Ƃ���́u���̘I�����i���j�G�l���M�[�v�̎d���͏I���ł��B
���̌�́A�������ꂽ�t�B����������ꂽ�摜�t�@�C������̈����L���́A�B�e�Ƃ͂܂������ʂ̃v���Z�X�Ȃ̂ŁA���̃G�l���M�[�Ƃ͖��W�ł��B���������āA���̃G�l���M�[�������L���ꔖ���Ȃ�ƌ������Ƃ͏o���܂���B
�����ԍ��F10291792
![]() 4�_
4�_
�@�ŋߔ����Ȃ�A�ǂ̈��ł��ǂ��ł����A���ɂd�V���[�Y �i�S�^�R�j ��1200����f�ŁE�E�E
�@���ʂɏ\�����邢�Ƃ���ŁA�i�Ǝˌ��ʈ��ŁA�J�������猩��ƑS�ʁE���S�ɓ��K���ȁj �O���[�J�[�h��������B�e���āARAW �f�[�^���������擾�B
�@���������̊K����m�肽�������Ȃ�A���̒��̂P���́A�P��f������������o���Ώ\���ł��傤�B
�@�m�肽�����̐��x�ɂ���ẮA�Q�^�R��1200����f�̃J�����̂P��f��A�����Ə����ȃJ�����̂P��f�ł��ǂ���������܂���B
�@����Ƃ͕ʂɁA�P��f������ 12bit �̏����A���ӂ̉�f�Ƃ��S�W�߂� 14bit�i��12bit + 12bit + 12bit + 12bit �� 12bit * 4�j �̏��Ƃ���A�K�����̐��m���͍����Ȃ�܂��B�@�S���W�߂����̂��A����ɕʂɂR���p�ӂ��� 16bit �i�� 14bit * 4�j �Ƃ���A����ɊK�����̐��m���͍��܂�܂��B
�@�������B�e�������́A������f���������o���āA�P���̂P��f������ 12bit ���S���d�˂� 14bit �ɂ��Ă��������ł� �i�P�ɊK�����𐳊m�ɂ��悤�Ƃ����ꍇ�j�B�@�P�U���d�˂� 16bit �i�� 12bit * 16�j �Ƃ���A����ɊK�����̐��m���͍��܂�܂��B
�@�J�������̑f�q�ɑS���덷���Ȃ����z��ԂƂ���A���ӂ̉�f�̏����W�߂����̂̂S��f�E�P�U��f���̊K�����̐��m���́A�������d�˂��S��f�E�P�U��f�Ɠ����ł��B
�@���̔̏Z�l�̕��́A���ʂ̎ʐ^�̏ꍇ�A���̂P��f�̊K�����ŏ\���ł��傤����A�Õ��ʐ^���B��ꍇ�ł��A�������B�e���č�������l�͂��Ȃ��ł��傤�B
�@�������A�Z���Ƃ��čl�����ꍇ�A��� bit ���g�����v�Z�̂悤�ɁA��f�𑫂�����A�d�˂��肷��قǏ��̐��m���������Ȃ�܂��B�@������ؖ�����Ƃ�����Ȃ��ł��������ˁB�@�v�Z��͂��������Ęb�ł�����B
�@�ŁA35mm�t���T�C�Y �E �S�^�R �E �Q�^�R �́A���ꂼ��1200����f�̃J������p�ӂ����Ƃ��āA�債�ĉ掿�ɍ����Ȃ��Ƃ�����������ł��ˁB�@���́A���Ǝ�����Ȃ��ƁA�c�R�E�c�V�O�O�����l�����킢�����ȋC�����܂���w
�@���̍����A�����ȍ��Ȃ̂��A����Ȃ�ɑ傫���̂��́A���I�ɂ͂����Ō��_���o���Ȃ��Ă��ǂ��Ǝv���Ă��܂��B
�@�����������Ă����ȒP�Ȏ����܂Ƃ߂āA�S�̔�UP���Ă݂悤�Ǝv���Ă��邩��ł��B
�@�i���낢��Q�l�ɂȂ�b�́A�Q�Ƃ����Ă����������Ǝv���Ă��܂��j
�@�i�x�M�Ȃ��̂ŁA������Ɛ悩���ł� orz �j
�@�܂��A�ˑR�A�����{����up���Ă��A�u���R���H�H�H�v �ƂȂ��Ă��܂��\���������ł�����w
�@�ł́A�����ꂻ����Ł`
�����ԍ��F10292209
![]() 1�_
1�_
������
�Ȃ��Ȃ��A�������낢�ł��ˁB
�J�������Ƃ����ʔ����\�����o�Ă����̂ł�����g���āA�����b�����Ă݂����Ǝv���܂��B
�O��A�ʐ^�������@�J�����������Ƃ����b�����āA����ɃJ�����������Ƃ킯���킩��
�Ə������̂ł����@
���́@�����ōׂ��������̋c�_�����Ă���l�����́A���̓J�������Ƃ����d�Ԃɏ���Ă����
�ł��ˁB�����ʼn������Ă��邩�Ƃ����ƁA���̒��ŁA�ꐶ�������W�R���𑖂点�āA���̐��m
�ȃX�s�[�h���v���Ă��ł��ˁB���낢��Ȍv�Z�����g���āA���炵���@�B���g���ĂˁB
�ł��A���ꂪ���炵�����m�Ȃ�ł���B�݂Ȃ��炵���\�͂�(�����j�����Ă��܂���
��ˁB�Ƃɂ������������@���i���ā@�����ā@�����Ă�킯�ł��B
�Ƃ��낪�A�d�Ԃ͑����Ă�킯�ł���B�����A������d�Ԃ̒��Ő��m�Ɍv���Ă�
�d�Ԃ������Ă�킯�ł�����@�ł��d�ԁi�J�������j�ɂ���Ƃ���ɋC���t���Ȃ���ł����
����@�C���t���Ă邩������Ȃ��@�C���t���Ȃ��U������Ă�̂�������Ȃ�
�Ȃ@����Ȋ��������܂��B
�����ԍ��F10294288
![]() 4�_
4�_
�t�B�����̃t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ⴂ�̏ꍇ�́A�v�����g�𑜓x�������Ă������́u�v�����g�T�C�Y�Ɋւ�炸 S/N����v�ł��B[10229854] �Q�ƁB
Tranquility���� �� [10287162] ����B
>>�u�傫���t�H�[�}�b�g�� S/N��ɗD���v�̗��R�͌��V���b�g�m�C�Y�ȊO�Ɏ��ɂ͍l������
>����B
>
>��ɏ������Ƃ���A���̗��R�͒P���Ƀv�����g���̊g�嗦������������ł��傤�B
>�����܂ł����V���b�g�m�C�Y�Ƃ��������Ȃ�A���̗��R�������������������B
�t�B�����̏ꍇ�Ɠ��l�A��f�s�b�`����̃f�W�J���ł���u�v�����g���̊g�嗦�v�Ɩ��W�ɁuS/N����v�ł��B
Signal �� Noise ���u�G�l���M�[�̒P�ʁv�ł��B���̈Ӗ��� Tranquility���� ��
>�t�B�����Ȃ犴���������_�A�摜�t�@�C���Ȃ�I���f�[�^���擾�������_�ŁA���鐯���߂炳��̌����Ƃ���́u���̘I�����i���j�G�l���M�[�v�̎d���͏I���ł��B
����͐������ł��B
���Ắu���V���b�g�m�C�Y�v�ɂ��Ăł����A[10289993] �Ŏ������悤�ɁA
�E�u���V���b�g�m�C�Y�̑��݁v�́A�u�W��������f�s�b�`�ɔ��v���邱�Ƃ́u�\�������v
�ł��B
���̉ߋ��́i�����Ȃ���������Ȃ��j�o���ɂ��A�W��������f�s�b�`�ɔ�Ⴗ��X���͔F�߂��܂��B
�܂��A���́u�ʁv���u�v�������V���b�g�m�C�Y�ɋN������v�ƍl������ʂł��B
�u���������V���b�g�m�C�Y�ȊO�ł���v�Ƃ���ɂ́A���́i�W��������f�s�b�`�ɔ��́j�m�C�Y���f�����Ă��邾���ł͕s�[���ł��B
�u���V���b�g�m�C�Y�ɂ�郌�x���̃o���c�L�E���v�A�Ȃ����u���V���b�g�m�C�Y�Ɠ����̃��x���̃o���c�L�ށv�m�C�Y���f�����Ă���K�v������܂��B
�ӂ��́u���V���b�g�m�C�Y�͕W��������f�s�b�`�ɔ�Ⴗ�邱�Ƃ̏\�������v�������āu���x���̃o���c�L�������N���������͌��V���b�g�m�C�Y�ɂ���v�Ƃ��܂��ˁB
�����ł� [10289993] �݂����Ȃ̂��u���_�Ō��ۂ������ł����v�Ƃ���Ǝv���̂ł����B
�Ȃ��A[10289993] �͍l�@�Ƃ��ĊÂ������͂���܂��̂ŁA�����Ƃ悭�l���������悢�ł��傤�B
�����ԍ��F10294404
![]() 0�_
0�_
�v���̂ł���
�P�A���V���b�g�m�C�Y�͌��q�ʂɔ�Ⴗ��̂ŁA�������Ȃ�Z���T�[�ʐς��L���ق����L��
�Q�A�m�C�Y�i���ł̓m�C�Y�̌����͌��V���b�g�m�C�Y�����S�ł���B
���̌��͂���ł����ł�����Ȃ��ł���
�@�ł�����őS�̂������̂��Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ�
���낢�뗍�ނ킯�ł��B���Ⴀ�@�����Ƀt�H�g�_�C�I�[�h�Ɍ����m���ɓ��Ă邩�H
�Ȃ�Ă��Ƃ�����Ɓ@���₢��@4/3�̂ق����A�����Y�v�ɗ]�T������
�����������������܂���Ȃ�Ă��Ƃ�����@�ނށ@���q�ʂ��ς���Ă��邩�ȁH
�Ȃ�Ă��Ƃ�����킯�ł���
�Ƃɂ����t�@�N�^�[�͂��낢�날��킯�ł���@�A���ʏƎ˂Ƃ���
�����Ȃ�ƁA�ׂ����b�����@�S�̂ł����ā@�ǂ�CCD�@CMOS�����������Ęb�̂ق���
�킩��₷���Ǝv����ł���
���Ƃ����C�J�ɓ����Ă�R�_�b�N��1800����f��CCD�͎��ۂǂ��ȂƂ���
��������Ă݂Ă݂�Ɓ@���Ƃ��t�H�[�T�[�Y�Ȃ�ł�������
E300�Ȃ��]���ɂȂ�����@���ł����Ɓ@�x�m�̂T�o�q�n�@�Ȃ��ςɐl�C���ł��肷��
�킯��@�j�R���̂c�S�O�Ƃ��@�𑜓x�Ȃł�������V�O�}���������
�����炱���ɏ����Ă���l�Ȃ͎��Ȃ����S�R�ڂ����͂�������
�킩��₷���S�̓I�ȂƂ�����A�����Ă����Ɩ��ɗ��Ǝv�����ǂ�
�����玄�̂悤�Ȃ���Ȉӌ��Ƀi�C�X���P�S���t�����Ⴄ�킯��
�t�ɂ��̕ӂ�m�肽���Ǝv�����@�����ɏ����Ă���ڂ����l�Ɉӌ������Ă��������
�Ȃ��Ȃ����炵�����̂ɂȂ�Ǝv������
�ł�
�����ԍ��F10294986
![]() 4�_
4�_
�� ���̃G�l���M�[�������L���ꔖ���Ȃ�ƌ������Ƃ͏o���܂���B
�ʐ^�Ƃ͉����̊�{�I�ȔF���̖�肾�Ǝv���܂��B���ꎫ���ׂ������ǂ��ł���B
�ʐ^�͌��G�l���M�[�̋L�^�ł����A���̋L�^�ȊO�̂��́A�G��Ƃ��͕ʂ̘b�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10295407
![]() 0�_
0�_
�c�_�������[���q�����Ă��܂����B
���Z�p�̈Ⴂ��A�����̌떂�����Ŋ撣���Ă����̒��x�i0.3�i�O��j�̂��̂ł�����A
���ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȗv���ƕ�����Ǝv���܂��B
[10281635]
���鐯���߂炳��̎咣�̐M�ߐ���DxoMark�Ō����܂����B
���鐯���߂炳���������A����Ƃ��s���̗ǂ��f�[�^�������E���Ă���̂��A
�F����Q�l�ɂ��Ă��������B���͈����Ώ\�����Ǝv���܂��B
�܂��A�j�R���̗��R�@��iD2X�AD90�AD3�j�̖ʐς��j�R���̃T�C�g�Ŕ�ׂ܂����B
D2X�@23.7x15.7mm�i372.09mm2�j
D90�@23.6×15.8mm�i372.88mm2)
D3�@ 36.0×23.9mm(860.4mm2)
���Ȃ킿�A
D90��D2X��1.002�{
D3��D90��2.307�{�@�@�@�E�E�E�i�P�j
���ɁADxomark�́uSNR18%�v�ɂ��print�\����ISO800�̃m�C�Y�����܂����B
�J�����̋@�킲�Ƃɕ\����������ISO�A�\��ISO�iManufactulerISO�j��
D2X�@SNR��27.2dB
D90�@SNR��32.3dB
D3�@ SNR��35.8dB
�i1�i���̃m�C�Y�̈Ⴂ��3dB�̍��ɑ����j
�܂�AD90��D2X�ɔ��5.1dB�i��1.5�i�j�m�C�Y�����Ȃ��A
D3��D90�ɔ��3.5dB�i1�i���j�m�C�Y�����Ȃ��@�@�@�E�E�E�i�Q�j
����ɁADxomark�����ׂ��������x�imeasured ISO�j�̏ꍇ���v�Z�i�ő��0.7%�O��̌덷����j������A
D2X�@SNR��27.3dB
D90�@SNR��30.7dB
D3�@ SNR��34.6dB
�i������1�i���̃m�C�Y�̈Ⴂ��3dB�̍��ɑ����j
���������āA
D90��D2X�ɔ��3.4dB�i1�i���j�m�C�Y�����Ȃ��A
D3��D90�ɔ��3.9dB�i��1.3�i�j�m�C�Y�����Ȃ��@�@�@�E�E�E�i�R�j
���鐯���߂炳�����悤�ɁA�������u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v��������A
�i�P�j�̑O��ɑ��āA�i�Q�j�i�R�j�̌��ʂ��o�Ă��܂���B
�܂�A�ʐς�1.002�{�������Ȃ�D2X��D90��ISO800�̃�SNR�����̂�5.1dB�i��1.5�i�j�A������3.4dB�i�P�i���j������̂ɁA
2.307�{�̖ʐύ�������D3��D90�̃�SNR�����̂�3.5dB�i�P�i���j�A������3.9dB�i��1.3�i�j�����Ȃ��̂́A
�ʐς����Ő����ł��Ȃ��̂ł��B
���������āA�ʐς̓m�C�Y�́u�f�g�c��ԑ傫�ȗv���v�ł͂Ȃ��A�ق��ɂ����݂������̑傫�ȃt�@�N�^�[�̈�ɉ߂��܂���B
�ł́A���̑傫�ȃt�@�N�^�[�Ƃ͉����B
�������̒ʂ�A�R�@��̂���D2X������CCD�ŁAD90��D3��CMOS�ł��B
�i�Q�j�̌��ʂ�����ƁACCD����CMOS�ւ̑傫�ȋZ�p�ω����A
�m�C�Y�v���Ƃ��ĖʐςƓ����i��O�D�R�i���ȓ��j�̉e����^���Ă��邱�Ƃ�������܂��B
������O�̂��Ƃł����A��͂�Z�p�̍������������̂ł��B
�������ł͂���܂���B
�i�Q�j�̌��ʂƁi�R�j�̌��ʂ��ׂ�ƁA�������x�ƕ\�����x�̃Y�����A�@��ɂ���đS���Ⴄ���Ƃ��͂����肵�܂��B
D2X�͂킸��0.1dB�i�R�O���̂P�i���j�ł����AD90��1.6dB�i0.5�i�j�Ƒ傫���AD3��1.2dB(�O�D�R�i��)����܂��B
����̈Ӗ�����Ƃ���́A���Ƃ��Z�p�Ɩʐς������ł��A���[�J�[���ƁA
�@�킲�Ƃ̒����ɂ���ăm�C�Y�̑��ǂ�������傫�����E�����Ƃ������Ƃł��B
��ʃ��[�U�[���@�킲�ƂɎ������x�ƕ\�����x�̈Ⴂ���v������̂͗e�ՂłȂ��A
�قƂ�ǂ̏ꍇ�͋@��\���Ɉˑ����Ă���킯�ł�����A�������������̏d�v�x�����������܂��B
�Ȃ��A�Z�p�ƒ����Ƃ����Q�v�������Z����A�ʐς����m�C�Y�ɗ^����e�����͂邩�ɑ傫���P�[�X������Ƃ��������́A
�i�Q�j�̌��ʂ�����Ζ����ł��傤�B
�ȏォ��A�ʐς����Ńm�C�Y�̑��ǂ��قƂ�ǂ��ׂČ��܂�Ƃ����咣�͐^���ł͂���܂���B
�������A�ʐς��d�v�ȃm�C�Y�v���̈�ł��邱�Ƃ͘_��҂����A
���i.com�̃f�W�C�`�Ŕ���������X�̂قڋ��ʂ̔F���A���ʂ̌o���ƌ����ėǂ��ł��傤�B
�������������Ȏ咣�ł���A���̔����X����������A�r��Ȃ������͂��ł��B
�^���ƈقȂ�咣�ɊF�����������͓̂��R�ƌ�����ł��傤�B
������O�̌��_�͔��q�����ł����A���Ƃ��Ɛ^���Ƃ͂����������̂ł��B
�����ԍ��F10297253
![]() 9�_
9�_
����
���������̒ʂ�A�R�@��̂���D2X������CCD�ŁAD90��D3��CMOS�ł��B
�R�@��Ƃ�CMOS�ł����B
�S��CMOS�Ȃ̂ɋZ�p�̊i���͑傫���Ƃ����Ӗ��ŁA�����̎咣����i�ƕ⋭��������ł��B
�����ԍ��F10297293
![]() 3�_
3�_
���s�̂�������
���V���b�g�m�C�Y�Ƒ��̃m�C�Y���������邱�Ƃ��o�����̂ł��傤���H
���V���b�g�m�C�Y��S�ʓI�ɔے肷���ł͂���܂��A���̌����̕��������Ɖe�����傫���̂ł͂���܂��B
���鐯���߂炳��
>�ʐ^�Ƃ͉����̊�{�I�ȔF���̖�肾�Ǝv���܂��B���ꎫ���ׂ������ǂ��ł���B
�܂����������ł��ˁB�ł��A���ׂ�Ȃ�S�Ȏ��T�̕��������ł���B
�����A�����̈ӌ�������ɓ`���Ȃ����Ɂu�����ׂ�v�ōς܂��̂͂ǂ����Ǝv���܂��B
>�ʐ^�͌��G�l���M�[�̋L�^�ł����A���̋L�^�ȊO�̂��́A�G��Ƃ��͕ʂ̘b�ɂȂ�܂��B
���̂悤�Ȍ������ŕ\������A�ʐ^�Ƃ͌��G�l���M�[���L�^�����u���v�ł��B�G�l���M�[���̂��̂�ۑ����Ă����ł͂���܂���B
�ł�����A�����L���Ō��̃G�l���M�[�������Ȃ�Ƃ������Ƃ͂���܂���B���R�Â����Ȃ�܂���ˁB
�����ɗ��Ă���F����
���܂܂ł̘b�̓W�J�Łu�m�C�Y���ǂ��́v�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��܂������A���̘b��́u4/3�̃����Y�͈Â��̂��H�v�Ƃ������b�ł����B
�����Ŏ��̌����������Ƃ͂��ꂾ���ł��B
���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����B
���u���Z�œ_�����v�u���ZF�l�v�Ƃ����l�����A�\�����@�͍����������̂Ŗ]�܂����Ȃ��B
���t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ���l����Ȃ�A�����������Z���Ȃ��Ă�
�@�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����̃����Y�ʼn�p�������v
�@�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�g�p�T�C�Y�Ŕ�ʊE�[�x��F�l��2�i���[���v
�@���������\���ł��イ�Ԃ�B
���R�́A���X�����܂߁A����܂ł̏������݂�ǂ�ł���������킩��Ǝv���܂��i��ςł��傤���j�B
�ԈႦ���l������\�����@�Ɋ�Â��������݂ŁA���ꂩ��J������ʐ^�̂��Ƃ𗝉����悤�Ƃ��������������Ă���̂����������Ƃ��Ǝv���A�����܂ŏ������݂𑱂��Ă��܂��܂����B
����������I���ɂ������Ǝv���Ă���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��I���邱�Ƃ��o���܂���B�\����Ȃ��v���Ă��܂��B
�����ԍ��F10297369
![]() 12�_
12�_
D2X�͂���ډ߂��܂��ˁB��700�AD90�͑傫���i�����ăL���m���̃��x���ɒǂ����܂����B
����̋Z�p�ɑ傫�Ȓx����Ԃł����A�Z�p�̐i�����d�v�ȗv�f�ƕ�����܂��B
�������Z�p�̈Ⴂ�ƃt�H�[�}�b�g�̈Ⴂ�A�֘A���̓[���ł͂���܂��A�b���Ⴂ�܂��ˁB
�Z�p���͈ꎞ�̂��̂ŁA���̓L���m���ƃ\�j�[�͖w�Ǔ������x���ŁA�p�i���͍��ł��ˁB
�Z���T�[�T�C�Y�̍��͉i�v�s�łł�����B���Ȃ��Ƃ�4/3�K�i�����N�ŏ�����Ǝv���܂���B
���ꂩ������x���グ��]�n������܂����A���̋Z�p������T�C�Y�̃Z���T�[�ɓK�p�ł��A
����T�C�Y�̃Z���T�[�ɓK�p�ł��Ȃ����̂ł���A�ڂ����l�@����K�v������Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A1.5�ʂ��̏�������f�͐��\�������܂�����A���ʏƎ˂��g���ĉ��P���܂����A
���̃Z���T�[�͓����Z�p���g���Ă��A�������̉��P�������Ȃ��Ǝv���܂��B
����͌��X1�ʂ���̋ɏ���f�̐��\�����ς��Ⴂ�̂�����܂��B�S�̂�����Ƃ�͂�
�ꎞ�̕s����c�݂������Ă��i�≖���܂ށj�����̎��_����͈���ȊW������܂��ˁB
�����ԍ��F10297421
![]() 0�_
0�_
�� �������x�ƕ\�����x�̃Y�����A�@��ɂ���đS���Ⴄ���Ƃ��͂����肵�܂��B
����͔�r�̎��ɏ�����Ԃ�������܂����A����ȏ�̉e��������܂���B
�܂��Z�p�̍��͊��̃f�[�g���[�h��u�ԕ����̂悤�Ȃ��̂ł����A
D3�ƃ�700�Z���T�[�̈�i�̉��P�͍��܂Ŏj��ő�̐i�����Ǝv���܂��B
�� �������������Ȏ咣�ł���A���̔����X����������A�r��Ȃ������͂��ł��B
��ʂ�ł��ˁB����S�Ŋ�{������ł����A��i�Â��ĉ��������Ƃ��v���܂��B
�i�������a�̃����Y������Ή��������Ȃ��̂������̎咣�ł�����j
�����ԍ��F10297599
![]() 0�_
0�_
�������ꂳ��A
�Z�p�̍��̐����͂��܂������A��̃J�L�R��������x���Ă��������B
�ǒn�̍ő�u�ԕ����ł͂Ȃ��A�S�̂�����ΊԈ�������_�ɂȂ�܂���B
D2X��D90�̍��͈�i�ł����i1.1�i��A0.1�i�͌덷�j
����͓������ꂳ���������͂��ł�����A��1.5�i�̘b�͐S���₩�ł͂���܂���ˁB
��������̋Z�p���ׂ�A�ʐϔ�ƈ�v����̂��������ꂳ���������܂��ˁB
���������̂��S���₩�ł͂���܂���i������r���Ƌ��܂������j�B
���v�]��������������������܂����A�펯���x�ł�������n�Y�ł����炲�����ōl���Ă��������B
�����ԍ��F10297828
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��A
��D2X��D90�̍��͈�i�ł���
�P�i�̍��ŏ\�����ł����Aiso800��1.5�i�����炳��ɖ��ł��B
������ɂ���A�P�i�̍�����ʐς����ł͐����ł��܂���ˁH
�ł���Ȃ�q�����܂��B���X���X���������������B
���ǒn�̍ő�u�ԕ���
�����ł��Ȃ������������O��������̂́A���s����`�̓T�^�ł��ˁB
����������̋Z�p���ׂ�A�ʐϔ�ƈ�v����
�Ȃ�قǁB����������A�u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v�Ƃ����O���́A
�u��������̋Z�p�v�Ƃ����O�@�\���Ȃ��ƒʗp���Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
��������ŏ�����A����������Ȍ�������͂�������������Ă����ׂ��ł����ˁB
����I�ȃ~�X�ł��B
���v�]��������������������܂����A�펯���x�ŕ�����͂��ł��B
�����ԍ��F10297897
![]() 14�_
14�_
�@��������̋Z�p�Ƃ������Ƃł����@���₢��@���S�ȓ������@�����Z���T�[�@����Ȃ���
�O��ɂȂ�Ȃ��悤�ȋC�����܂���
�@
�������ꂳ�o�Ă��Ă��̘b�������ɂȂ肻���ł��ˁB
�@����ɂ����@�Z���T�[�i�����Ƃ����t�H�g�g�����W�X�^�j�����ł��̂܂܁@���ɓ������ł����ˁH
�����Y�����邵�@����������������Ǝv���̂ł���
�����ԍ��F10301367
![]() 1�_
1�_
>���V���b�g�m�C�Y�Ƒ��̃m�C�Y���������邱�Ƃ��o�����̂ł��傤���H
>���V���b�g�m�C�Y��S�ʓI�ɔے肷���ł͂���܂��A���̌����̕��������Ɖe�����傫���̂ł͂���܂��B
���ɏ������悤�ɁA�R���f�W�N���X�i��f�s�b�` 3.5��m �ȉ��j���ƁA�W�����͊T�ˉ�f�s�b�`�ɔ�Ⴕ�Ă��܂����B�ʂ͎����o�������_�l�̓葝�����x�ł��B
�������܂��l�@�ɊÂ�����������Ƃ͎v���Ă��܂��B
>���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����B
�u���ʏƓx�������v�ł��ˁB
���ʏƓx���u�����Y�ŗL�̌����̖��邳�v�ƌĂ̂̓t�B�����̊����������l���Ă̂��Ƃł��傤�B
>���u���Z�œ_�����v�u���ZF�l�v�Ƃ����l�����A�\�����@�͍����������̂Ŗ]�܂����Ȃ��B
������Ɨ������Ă���Ζ�肠��܂��A���̒��ɂ͊��Z�Ƃ����l�������o���Ȃ��l�͑����݂����ł��ˁB
>���t�H�[�}�b�g�̈Ⴂ���l����Ȃ�A�����������Z���Ȃ��Ă�
>�@�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����̃����Y�ʼn�p�������v
>�@�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�g�p�T�C�Y�Ŕ�ʊE�[�x��F�l��2�i���[���v
>�@���������\���ł��イ�Ԃ�B
����ɂ��Ă����x�������Ă܂����A
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�����W�{���ŁA������F�l��2�i�����Ȃ��v
��t��������Ƃ肠�����͏[���ł��B
�u���l��������ׂ��ʊW���Z�p���ŕ\���v�̂����Z�ł��ƁA���łɊo���Ă��炦�悢�ł��傤�B
>�ԈႦ���l������\�����@�Ɋ�Â��������݂ŁA���ꂩ��J������ʐ^�̂��Ƃ𗝉����悤�Ƃ��������������Ă���̂����������Ƃ��Ǝv���A�����܂ŏ������݂𑱂��Ă��܂��܂����B
�u�قȂ�t�H�[�}�b�g�Ԃ� F�l�͂��鉿�l�Ɋ�Â��Ċ��Z�ł���v�͊Ԉ���Ă��Ȃ��̂ŁA���Ȃ��̌����Ă��邱�Ƃ́u���_�ɑ����掁E�����v�ł��B
�����ԍ��F10301384
![]() 0�_
0�_
>>���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����B
>�u���ʏƓx�������v�ł��ˁB
>���ʏƓx���u�����Y�ŗL�̌����̖��邳�v�ƌĂ̂̓t�B�����̊����������l���Ă̂��Ƃł��傤�B
�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ�A���̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��Ă��A�t�B�����Ɋ��������Ă��A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő������Ă��A�������邳�Ɋ������܂��B
���������āAF�l���u�����Y�̖��邳�v�ƕ\�����邱�Ƃ͂���߂Ď��R�ŁA���̌��ʁu�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����v�ƂȂ�킯�ł��B
�t�B�������o����O���炻�̂��Ƃ͂킩���Ă����͂��ŁA�ׂɃt�B�����̊����������l������ł͂Ȃ��ł��傤�B
�����Łu�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸�v�Ƃ킴�킴�������̂́u�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���������ƃ����Y���Â��v�Ƃ����咣�i�������ԈႢ�ł��j������������ł��B
>������Ɨ������Ă���Ζ�肠��܂��A���̒��ɂ͊��Z�Ƃ����l�������o���Ȃ��l�͑����݂����ł��ˁB
���߂��珑���Ă��܂����u���Z�œ_�����v�Ƃ��u���ZF�l�v�Ƃ��������ʂ�����̂ł͂���܂���B
���炽�߂ď����܂����A�u���Z�œ_�����v�ƕX�I�Ɍ����Ă��邱�Ƃ́A�u����t�H�[�}�b�g�ŔC�ӂ̏œ_�����̃����Y���g�p�������A����Ɠ���̉�p��35mm���œ��邽�߂ɕK�v�ȃ����Y�̏œ_�����v�ł��B���ՂɎ����āu���Z�œ_�����́���mm�����v�ȂǂƂ����������������ɁA�P���Ɂu�t�H�[�T�[�Y����mm�̉�p��35mm���́���mm�����v�ƕ\�����ׂ��ł��B
F�l�Ŕ�ʊE�[�x���l����ꍇ�����l�ł��B
>�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�����W�{���ŁA������F�l��2�i�����Ȃ��v
��t��������Ƃ肠�����͏[���ł��B
�u�W�{���v�Ƃ͉��̂��Ƃł��傤���B
�܂��A���郌���Y�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌��̌o�H�������̂���ʓI�ł��傤�B
���������āA�����œ_�����E����F�l�Ȃ瓯���ʂɂȂ�܂��B�Z���T�[�̑Ίp���Ƃ͊W����܂���B
�u������F�l��2�i�����Ȃ��v�Ƃ����\���͌��ł��B
�Ίp���������̃Z���T�[�S�ʂɂ����鑍���ʂ����������̂ł���uF�l2�i�����Ȃ��v�Ƃ����������͂��������A���ʂɁu1/4�v�ƌ����Ό�����������Ƃ�����܂���B
>�u�قȂ�t�H�[�}�b�g�Ԃ� F�l�͂��鉿�l�Ɋ�Â��Ċ��Z�ł���v�͊Ԉ���Ă��Ȃ��̂ŁA
F�l�Ƃ́u�œ_����÷�����Y�̗L���a�v�Œ�`����A���Z�ł�����̂ł͂���܂���B
�u���鉿�l�v�ɂ��ƂÂ��ĉ����ʂ̂��Ƃ����������̂ł���A�����F�l�ŕ\���ׂ��ł͂���܂���B
>���Ȃ��̌����Ă��邱�Ƃ́u���_�ɑ����掁E�����v�ł��B
�ԈႦ�Ă��邱�Ƃ��u�Ⴂ�܂��v�Ƃ����̂́u��掁E�����v�ł����H
���l�̂��Ƃ��u��v�Ƃ��u�ڋ��̋ɂ݁v�Ƃ��u���Ȃ��ʖڂł���B���Ȃ����Ƃ��Ɋ��Z�œ_��������鎑�i�͖����v�Ȃǂƌ����̂͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�����ԍ��F10301636
![]() 9�_
9�_
���݂܂���A�����ł��B
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�g�p�T�C�Y�Ŕ�ʊE�[�x��F�l��2�i���[���v
�͊ԈႢ�ŁA
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A������p�̂Ƃ��A����F�l�E�g�p�T�C�Y�Ŕ�ʊE�[�x��F�l��2�i���[���v
�ł����B
�����ԍ��F10301662
![]() 0�_
0�_
����ł́A�����������܂��B
�� ����������A�u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v�Ƃ����O���́A
�� �u��������̋Z�p�v�Ƃ����O�@�\���Ȃ��ƒʗp���Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
�� ��������ŏ�����A����������Ȍ�������͂�������������Ă����ׂ��ł����ˁB
�� ����I�ȃ~�X�ł��B
�t�ɋZ�p���i�����Ȃ��Ƃ����O��͂��������Ǝv���܂��B�Z�p�̐i���͔g�̂悤�ł����A
���G�Ȕg�⒪�������Ă��K�����╽�ϊC�ʂƂ��̊�{������܂��B���{�ł�100�N�ȏ�O��
�ϑ����ꂽ���ʂ����ł��g���Ă܂��i�֓���k�Ђ̒n�Օω��ň�x����������j�B
�������ꂳ�w�E�����Z���T�[�A��700���ŏ��̐��i�ł����A�ނ��낻��܂�
���E�̎ז��ɂȂ��Ă��g�Z�p�̍��h���N���A���Č��̖{�����m�F�ł����Ǝv���܂��B
��700���o��܂ł́A�L���m������ΓI�ȋZ�p�D�ʂ������āi�ƌ����Ă���i�ʁj�A
4/3�@������Ă��A���Ђ�APS-C�@�Ɠ����ȏ�̐��\���ł���Ƃ����킯�ł����A
����ُ͈펖�ԂŒ��������Ȃ������ł��ˁB�Z�p�̍��͈ꎞ�I�Ȃ��̂ɉ߂��܂���B
�i�L���m���@�̐��\���Y��ɖʐϔ�Ⴕ�Ă܂��B��700�ƃ�900�������ł��j
��700�̐��\���ǂ��Ƃ������A����܂ł̃Z���T�[�̐��\���ُ�Ɉ����ƌ���������
�����������m��܂���BD2X��CMOS�Ȃ̂ɐv�̓\�j�[���ӂ�CCD�P���āA
���\����肭�����ł��Ȃ������̂ł��B��������͂�Z�p�̗����ꎞ�I�Ȃ��̂ł��B
����ŋZ�p�̍����قڂȂ��Ȃ�܂����iIMX021�̈ꕔ�̐��\�̓L���m�������ǂ��ł��j�B
���ł͉��i.COM��243�@�킪�o�^����Ă܂����A���ςƂ��Ċe�@�킪���̑O�̂��̂��
�ǂ̈ʉ��P�ł����ł��傤���H���͈ꕔ�������Ă܂��A����0.2�i���Ȃ��Ǝv���܂��B
���ۃZ���T�[�ׂ̍����Z�p���\�̌��܂��ƁA���\�F�X�H�v���ĉ��P���Ă܂����A
�F��ȓw�͂�ςݏd�˂Ă��A���ʂ͑債�ĕς�܂���B�Z���T�[���\�̉��P��ςł��B
DxOMark�ɂ͌Â�E-1��E-300�Ȃǐ��\�̒Ⴂ�@��f�[�^���Ȃ��c�O�ł����i�����������j�A
�p�i�����L10��G1��0.2�i�ł��ˁB�܂��L���m��40D��50D�̍���0.2�i���ł��B
7D�̃f�[�^�͂܂�����܂��A0.3�i�ʂ��ۂ��ł��B�ǂ���撣�������ʂł��B
�����ԍ��F10301834
![]() 0�_
0�_
�� F�l�Ƃ́u�œ_����÷�����Y�̗L���a�v�Œ�`����A���Z�ł�����̂ł͂���܂���B
�œ_����÷�L�����a�ł����A�œ_���������Z�ł��āAF�l���ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ��ł��傤�B
�ʂ�4/3�����Y��f/2.0�Ƃ���F�l�\�L���Ԉ�����Ƃ��A�����������Ƃł͂���܂���B
4/3��f/2.0�̃����Y�́A������p��35�~������f/4.0�̎d�������o���Ȃ��Ƃ����Ă܂��B
f/4.0�Ɋ֘A����S�Ă̎d����f/4.0�̒ʂ�ł��܂��B�K�v�\�������ł��B
�����ԍ��F10301884
![]() 3�_
3�_
���낻�남�ɂ����悤���Ǝv���܂��̂ŁA������Ɠ���b�����܂��ˁB�i�ȒP�Ȍ��t���g���܂����A���Ȃ�ʓ|�ȓ��e���܂݂܂��̂ŁA�R�����g����l�͒��ӂ��Ă��������l�B�j
�V�����ƒn�������Ă��邶��Ȃ��ł����B���z���n���̎�������̂��A�n�������z�̎��������Ă���̂��A�̈Ⴂ�ł��B
�ǂ��������������A�Ƃ����ƁA���ꂪ�����Șb�ł��āA�ǂ�����Ƃ��Ă��V�̂̉^�s�̐��m�ȋL�q���A���Ώo����A��ł���ˁB
���ZF�l������Ɠ����悤�Ȃ��̂ŁA���������������Ȃ����A�ƌ����A�܂��������ł��ǂ��Ǝv���܂��B
�������A����̂́A�݂�Ȃ��n�������̂��Ă���ꏊ�ɁA�����Ȃ�V��������������ŁA�낭�ȉ���������ɁA�u���������{�����v�ȂǂƏ������ƁA���ɍ������܂��B
�Ⴆ����́u�Â��v�̖��ł��B�u���Áv�̈Ӗ��̍����̉���͊���[10222160]�ł��܂����B���̌��ɂ��Č����A��{�I�ɂ͕\���̖��ŁA�u�Â��v�ł͂Ȃ��A�u���ʂ����Ȃ��v�ȂǂƂ���Α����̐l�������ł��傤�B
���Ⴀ�A�\���̖�肾�����Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��āu���ZF�l�Ő����ł���v�ƌ����A�����������n�߂�Ɗ��Z���Ă��Ȃ������肷��͍̂���܂��B�u�V�������������v�Ƃ��Ȃ���A�f���̋O���v�Z��n�����ł���悤�ȃ��m�ł��B
�Ⴆ�Ό��V���b�g�m�C�Y�̐��������ZF�l�ł���Ȃ�A�{���ȉ��̂悤�ɂȂ�n�Y�ł��B
�I�����p�XE-30�ƃj�R��D700���r����ƁA��f�T�C�Y�͊��Z�������āAF�l��2�i���Z�Â��̂ŁA��f������̌��ʂ�2�i�����Ȃ��Ȃ�A���V���b�g�m�C�Y��������B
���̂悤�Ȑ����Ŕ[���ł���̂ł���A�u���ZF�l�Ő����ł���v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł͖����ł��傤�B�t�Ɂu��f�ʐς��������̂Ō��V���b�g�m�C�Y��������v�ȂǂƂ��������ł���u���ZF�l�͊W�Ȃ��W�����v�Ƃ����ᔻ�ɂ͑ς��܂���B
�����܂ł������A�V�����ƒn�����ł͌��݈��|�I�ɒn�������x������Ă����ł����A�Ȃ����݁A�n�������̗p����Ă��邩�ƌ����A�n�����̕����ȒP������ł��ˁB���Ƃ��Ă͊��ZF�l���g���������̕������G�Ŗʓ|�Ȃ̂ŁA�����ł�����咣���邱�Ƃ͂��肦�܂��A����킵���\�������g��Ȃ���A�ʂɊ��ZF�l�ōl����̂��~�߂�قǂ̎��������Ƃ͎v���܂��B���ׁ̈A���̊��ZF�l�ᔻ�͕���킵���\���ɏW�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���ȍD���j�̓Ƃ茾�̂悤�ȃ����ł����A���Q�l�܂ŁB
�����ԍ��F10301895
![]() 6�_
6�_
���鐯�J��������
>�œ_����÷�L�����a�ł����A�œ_���������Z�ł��āAF�l���ł��Ȃ����Ƃ��Ȃ��ł��傤�B
>�ʂ�4/3�����Y��f/2.0�Ƃ���F�l�\�L���Ԉ�����Ƃ��A�����������Ƃł͂���܂���B
>4/3��f/2.0�̃����Y�́A������p��35�~������f/4.0�̎d�������o���Ȃ��Ƃ����Ă܂��B
>f/4.0�Ɋ֘A����S�Ă̎d����f/4.0�̒ʂ�ł��܂��B�K�v�\�������ł��B
���Ȃ��̎咣�ɂ͈�؍���������܂���B����w�E���Ă���Ă��邱�Ƃł��B
���Ȃ��͉掿�͎B���ʖʐςɔ�Ⴗ��ƃA�v���I���Ɍ��߂Ă����邾���ł��B
�����̏�ŁA������咣������̂͂�߂Ă��������B
�����A�{���ɂ����v���Ȃ獪���������Ă��������B
(�����ǂ������ɏ������Ƃ���������邩�A�����Ȃ��ɂ����������x���ɕt���������Ȃ�
�Ƃ���������邾�����Ǝv���܂���)�B
�{���ɐM���Ă���Ȃ�A�L���m�����[�U�̕��ɂ�EF�����Y�́AAPS-C�@�ɂ����
1.4�i�Â��Ȃ�A�j�R�����[�U�̕��ɂ�FX�����Y��DX�t�H�[�}�b�g�@�ɕt���Ă��A1.3�i
�Â��Ȃ�Ƃ������Ƌ����Ȃ����R�͉��ł��傤���H
�����ԍ��F10301913
![]() 9�_
9�_
>�I�����p�XE-30�ƃj�R��D700���r����ƁA��f�T�C�Y�͊��Z�������āAF�l��2�i���Z�Â��̂ŁA��f������̌��ʂ�2�i�����Ȃ��Ȃ�A���V���b�g�m�C�Y��������B
>
>���̂悤�Ȑ����Ŕ[���ł���̂ł���A�u���ZF�l�Ő����ł���v�Ƃ����̂��ԈႢ�ł͖����ł��傤�B�t�Ɂu��f�ʐς��������̂Ō��V���b�g�m�C�Y��������v�ȂǂƂ��������ł���u���ZF�l�͊W�Ȃ��W�����v�Ƃ����ᔻ�ɂ͑ς��܂���B
�ȂA�͂炽���� �͂����Ƃ킩���Ă��邶��Ȃ��i�O���͎��͐����Ƃ��Ă͐������Ȃ����ǁj�B
���ł��Ȃ������ZF�l�ւ̔�排���������̂��킩��܂���B
Tranquility���� �܂߁A�u���ő傫���𑵂���̂��킩��Ȃ��v�Ȃ�Ĉӌ����������̂ŏ����Ă݂܂��B
�i�ϐ��̑I�ѕ����Z���X�����ł����j���ł̉�ʂ̑傫�����u�G���v�A��ʂ̒P�ʑ傫��������ł̌������u�A�C�v�A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W�����uk�v�i�Ⴆ�t�H�[�T�[�Y���t���T�C�Y���Z����ꍇ�̃t�H�[�}�b�g�T�C�Y�W���́u2�v�j�Ƃ��܂��B
���Z�����������ŁA���Z���啶���ŕ\���܂��B
���̂Ƃ��A
M * I = (k^2) * m * i
�̊W������܂��B
�u�G���v�́A�B���O�Ȃ�Ⴆ�t�@�C���_�[�̑傫���A�B�����Ȃ��f���ł��B�B����̃v�����g�T�C�Y�͖��W�B
���̂Ƃ��u�A�C�v�͂��ꂼ��A�t�@�C���_�[�̏Ɠx�i�������U�x�j�A���f������̌����A�ƂȂ�܂��B
����������
�uF�l�Ŗ��邳�����܂�v
���A
�u�t�H�[�T�[�Y�͓�i�Â��v
���A
�����Ƃ�����ꂽ�����ł̔�r�Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
�u�ǂ��炪�ėp������́H�v���Č������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���A�ӂ��͉�ʃT�C�Y������ł��傤����u�t�H�[�T�[�Y�͓�i�Â��v�̕��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10302332
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��A
���Z�p�̍��͈ꎞ�I�Ȃ��̂ɉ߂��܂���
�u�ꎞ�I�v���ǂ����͊��S�Ɏ�ς̖��ł��ˁB����������A�Z��������B
�������A������ɂ���Z�p���̑��݂Ƃ����������͕̂s�ςł��B
�Z�p�����{���I�ȃm�C�Y�v�����ۂ��ɂ��āA���鐯���߂炳�ǂ��l����̂����R�ł��傤�B
�̐S�Ȃ̂́A���ʂƂ��āA�ǂꂾ����I�Ɍ���������ł��邩�ł��B
���̌���ɂ����āA�ǂ������l������ʓI�ŁA���ՓI�ŁA��I���f�����낵���B
���āAD90��D2X�ɂ͖ʐϔ��啝�ɒ��߂���قǑ傫�ȃm�C�Y��������A
���鐯���߂炳��́u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v�Ƃ����]���咣�͌����Ƃ̖����𗈂��Ă��܂��B
D90��D2X�ɂ�锽���u��O�v��u�덷�v�ƌĂсA��̂Ă�̂͏���ł����A
����ł͂��܂ł����Ă��������ł��Ȃ����A�u���X���X���������������v�Ƃ������̎���ɂ��ԓ��ł��Ȃ��ł��傤�B
�t�ɁA���̔����u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v�Ƃ����s���S�ȕ������̒��Ɏ�荞��ŁA
�ʐϗv���͕K�������f�g�c�łȂ��A���ɂ͋Z�p�v���̔䗦������P�[�X������ƏC�����Ă��Ηǂ��̂ł��B
�����ŏ��ɐ��������C���ł��B
����������A���ɂ̓[���ɂȂ�A���ɂ͑傫�Ȑ��l�ɂȂ�悤�ȕϐ��Ƃ��āA
�Z�p�v�������肷�邾���ŏ\���Ȃ̂ł��B
��������A���鐯���咣����Z�p���̈ꎞ���Ƃ����A�ǒn�̍ő�u�ԕ����Ƃ����A
�P�O�O�N�̔g�̓����Ƃ����A���ׂĂ��̕ϐ��̕ϓ��͈͂Ƃ��Đ����ł��܂��ˁB
�u��������̋Z�p�v�Ƃ́A�Z�p�ϐ����[���Ȃ����قڃ[���̏�Ԃ̂��Ƃ��w���Ă���ɑ��Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
���ہA���鐯���߂炳�g��
���Z�p���i�����Ȃ��Ƃ����O��͂��������Ǝv���܂��B
�Ɛi��Ŕ������Ă��܂��B
�Z�p�͐i������Ƃ����O��i�ϓ�����Z�p�v���j��������ɉ����Ȃ����R���S������܂���B
�����āA���Ȃ��Ƃ��u�ʐς̍��͒f�g�c��ԑ傫�ȁi�m�C�Y�j�v���v�Ƃ����O���ɂ́A
�ʐϗv�������Ƃ��đ傫������悤�ȉe�����s�g����Z�p�v�������S�Ɍ������Ă��܂��B
����I�ȃ~�X�Ƃ́A�����������Ƃł��B
���v�]���������ɐ������܂����A�����펯�ŕ�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10302907
![]() 6�_
6�_
���̊��Ɏ���܂ŁA����摜���o���Ȃ��������S�Ă���Ă���Ǝv���B
�{�����Z�Ƃ͕������ȗ������Ă킩��₷�����邽�߂̂��̂ł���A�������ōs�����ނ̂��̂��Ǝv���B
�������e�l���Z�͐����O������̔��肪�����A�����ʘ_�ɂ͐��蓾�Ȃ��Ǝv���B
����œ_�����i��p�j���Z�̓Z���T�[�̃X�y�b�N�Ɉ�؍��E���ꂸ���Z�ł���B�@���̍��͔��ɑ傫���Ǝv���B
�Z���T�[�̏o���s�o���������Y�̂e�l�ɒu�������鎖���̖���������Ǝv���B
�u���z�I�ȃZ���T�[�v�Ƃ��u�Z�p�i�����Ȃ��O��v�Ƃ��F�X�ƑO�u�����K�v�ȗl�ł��邪�A�O�u�����������قǔ��I�Ȃ��̂ƂȂ�A����̋�_�Ɖ����čs���B
�����ԍ��F10303809
![]() 11�_
11�_
�œ_����÷�L�����a��F�l�ŁA���Z�œ_����÷�L�����a�����ZF�l�Ȃ����œ���O��͂���܂���B
����ŘI�o�����F�l���g���s���㊷�ZISO���g�p����Γ���I�ɔ�ׂ���Ƃ��������̂��ƂŁA�K�v���������Ȃ��l�͂����l���Ȃ������̂��Ƃł��傤�B
�����ԍ��F10303847
![]() 4�_
4�_
�����̊��Ɏ���܂ŁA����摜���o���Ȃ��������S�Ă���Ă���Ǝv���B
�摜���o���K�v�����Ȃ����ƂȂ̂ł����ǂˁB
��Âɓǂ݉�����邱�Ƃ������߂��Ă����܂��B
�����ԍ��F10303864
![]() 2�_
2�_
>���������uF�l�Ŗ��邳�����܂�v���A�u�t�H�[�T�[�Y�͓�i�Â��v���A�����Ƃ�����ꂽ�����ł̔�r�Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
�u�ǂ��炪�ėp������́H�v���Č������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���A�ӂ��͉�ʃT�C�Y������ł��傤����u�t�H�[�T�[�Y�͓�i�Â��v�̕��ł��傤�ˁB
�ǂ����Ă�4/3���u2�i�Â��v�ƌ��������悤�ł��ˁB
�ėp���ōl����A�����Łu�Â��v�Ƃ������t�͎g���Ȃ��ł��傤�B�Ӗ����Ⴂ�܂�����B
��ɂ������܂������A���ʂɌ�����
�u4/3�̃Z���T�[�ʐς�35mm�t���T�C�Y��1/4�v
�u4/3�̃Z���T�[���鑍���ʂ�35mm�t���T�C�Y��1/4�v
�ɂȂ�ł��傤�B���̂ق��������ƃV���v�������킩��₷���B
�����Ƃ��u�ӂ��͉�ʃT�C�Y������v�ł��傤���H�@�^��ł��B
��������̂́A�掿���r���邱�Ƃ���̐l���炢����Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F10303899
![]() 7�_
7�_
>�摜���o���K�v�����Ȃ����ƂȂ̂ł����ǂˁB
�N�P�ʂł̓��X������I��������ɂ͂��ꂵ�����@�������Ǝv���B
���������Ӗ��ł͕K�v���͂���̂ł͂Ȃ����낤���B
�����ˋ�̃Z���T�[�ł̗��_�l�ł���ΐ��i�ł��b��ł��Ȃ��Ǝv���B
���̂͌��܂��ăt�H�[�T�[�Y�炵�����A�����܂ŗ���ƌ����点�Ƃ����v���Ȃ��B
>�K�v���������Ȃ��l�͂����l���Ȃ������̂��Ƃł��傤�B
���̒ʂ�ŁA�K�v�����邩�ǂ������킩��Ȃ��̂ɂ����Ȃ�u14-54��F4-F7�ł���v�Ƃ��u�t�H�[�T�[�Y�͓�i�Â��v�ȂǂƎa�荞��ŗ��邩��r���B
�����ԍ��F10303959
![]() 10�_
10�_
���s�̂�������
���`��A�u�V�����𐳂����Ƃ��Ȃ���f���̋O����n�����Ōv�Z����v�Ƃ���栂��͋��s�̂�������ׂ̈ɗp�ӂ�����ł����˂��B
���ZF�l���{���A���邢�͊ȒP�Ȃ�A���V���b�g�m�C�Y�̌v�Z������f�T�C�Y�ł͂Ȃ��āA���Z��f�T�C�Y���g���Ă�蒼���Ă��������B�i�{���ɂ��Ȃ��Ă��ǂ��ł��� ^^; �ł��A�������Ȃ点�߂ăJ���[�ɂ��Ă��������B^^;;�j
�u�Â��v���������邩�炻�̂܂g���Ă̓_���ł���B�ʐ^���B��l�͘I�o�̕��Ŋ��Ɂu���Áv���g���Ă܂�����B
�V�����ƒn������栂��͊��ZF�l���ő����e����栂��ł����A�܂��A�G���W�j�A�Ȃ犷�ZF�l���̗p���Ȃ��̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B
���ZF�l���g�����������ƁA���ۂ̌������ǂ��ɂ���̂����ȒP�ɕ\���ł��Ȃ��̂ŁA���ʂ̐����u��f�s�b�`���������ƌ��V���b�g�m�C�Y���傫���Ȃ�v�Ɣ�ׂāA��낵���Ȃ��ł��ˁB
�Ⴆ�Ό��V���b�g�m�C�Y�̌������u�����Y���Â��v�ł�������Y�𖾂邭����Ό��V���b�g�m�C�Y�͌���n�Y������ǁA���ۂɂ̓����Y�𖾂邭���Ă����V���b�g�m�C�Y�͌���Ȃ��ł��ˁB��f�s�b�`��傫������Ƃ��AISO���x�𗎂Ƃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�ܘ_�u���Z�v�Ƃ������t���g���Ă��̕ӂ������ł��Ȃ����������ǁA���G���̏�Ȃ��B
�v�Z�̎�Ԃ͖��炩�Ɂu���ʂ̗��_�v�̕����������B�����̌ꐔ�����ʂ̗��_�̕������Ȃ��čς݂܂��B���Ȃ��Ƃ��X���͂���ȂɐL�тȂ��ł��傤�B^^;
�����ԍ��F10304035
![]() 11�_
11�_
�� �摜���o���K�v�����Ȃ����ƂȂ̂ł����ǂˁB
�F�X�W�J���Đ������Ă܂����A����F�l���̂͋ɂ߂ĊȒP�ŃV���v���Ȃ��Ƃł��B
�ʐ^�̊�{�m������A�N�ł��m�F���ĕ�����ł��傤�B
�M�p���Ă���Ȃ�����ɏ؋����o���ƌ����Ă��A��a���������܂��B
������ȒP�Ȑ��w�╨��������Ă������{���܂ŕ����邱�Ƃł�����B
�t�ɍ��ꎫ����A���w�A�����̋��ȏ��ɁA�ǂ̂悤�ȏ؋�������ł��傤���H
�����͂���ȏ�ڂ������������Ǝv���܂����B
�����ԍ��F10304396
![]() 1�_
1�_
���鐯���߂炳��
> �F�X�W�J���Đ������Ă܂����A����F�l���̂͋ɂ߂ĊȒP�ŃV���v���Ȃ��Ƃł��B
> �ʐ^�̊�{�m������A�N�ł��m�F���ĕ�����ł��傤�B
�J�����̊�{�m��������A���ZF�l���́A�܂������Ӗ��̖������Ƃ͒N�ł�������ł��傤�B
�܂��A�ߋ��̃��X���炠�Ȃ��̍��{�I�Ȋ��Ⴂ�̌��́A
�u���邯��Ζ��邢�قlj掿���ǂ��v�Ƃ����_�ł��B
�Â�����̂��A���邷����̂��掿�Ɍq���邱�Ƃ��炢�A�ʐ^���B�����o���̂�����Ȃ�킩��͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����Ȃ��́w�Â��x���Ƃ���ɒ��ڂ���̂ł��傤���H
�ō��掿�͍œK�Ȕ�ʑ̏Ɠx�ƁA�œK�ȘI�����Ԃɂ���ē�����͂��ł��B
���邯��Ηǂ��ƌ������̂ł͂���܂���B
���̂��߂ɍi��H���������Y�ɕt���Ă��邩�l���Ă݂Ă��������B
�����ĉ掿�����������邽�߂ɍi��H�������Ă����ł͂Ȃ��̂ł��B
��������������A���鐯����́A��ɍi��J���ł����ʐ^���B���Ă��Ȃ��̂ł��傤���H
4/3�����Y�̗L�����a���A�t���T�C�Y��1/2�ŏ[���Ȃ̂́A����ŏ[���ȘI�o��������ɑ��Ȃ�Ȃ�����ł��B
�吨�̕����w�E���Ă���ʂ�A�t�H�[�T�[�Y�̃C���[�W�T�[�N���̓t���T�C�Y��1/4�̖ʐς�������܂���B
�]���āA�œK�ȘI�o�郌���Y�����Ȃ��̌����w���ZF�l�x�œ�i�Â��̂����x�ǂ��̂ł��B
�܂��A���́w���ZF�l�x�ł����A���鐯����̗��_���������ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�Ɨ����ł��܂��B
�E�J��F�l2.0��4/3�����Y���t���T�C�Y�̃J�����ɑ�������Ɓi�����Ȃ����ǁj�AF�l��4.0�ɂȂ�B
�E�t�ɁA�J��F�l2.0�̃t���T�C�Y�p�����Y����4/3�̃J�����ɃA�_�v�^����đ�������ƁA���Z���F�l��1.0�ɂȂ�B
��L�̗�͋ɒ[�ȗ�ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A���p�҂ɂƂ��ĉ��̏����������炵�܂���B�C���[�W�T�[�N���̑傫�����ς��Ɗ��Z���F�l���ς�邱�Ƃɉ��̈Ӗ�������̂ł��傤���H
���鐯���߂炳��A����ȏ�Ӗ��̖������ZF�l�̓`���ɘJ�͂𒍂����ނ��A�����ƃt�B�[���h�ɏo�đ����̎ʐ^���B���Ă��������B�ʐ^���B��y���݂������Ă��������B
�����ԍ��F10304851
![]() 10�_
10�_
�� ���̈Ӗ�������̂ł��傤���H
���Z��������F�l�������ł���i�܂�L�����a�������̎��j�ʐ^�̎��_�����
�Z���T�[�T�C�Y�Ɋւ�炸�AF�l�Ɋ֘A���鐫���A�I�o�̒��߂Ƃ���Ɋ֘A����掿�A
��ʊE�[�x�A��܌��E�Ȃǂ��ׂĂ��������ʂɂȂ�܂��B
�Ⴆ�AZD35-100/2.0�ƁAZD14-35/2.0���A���ꂼ��35�~�����Ɋ��Z���܂��ƁA
70-200/4.0�ƁA28-70/4.0�̃����Y�ɂȂ�܂����A���̓��ZD�����Y�́A
35�~�������A���炩�ɑ�^�d�ʂł��邱�Ƃ͕�����܂��B
����F�l���Ⴄ�ł��傤���A����F�l������Ă��A�������ʂɂȂ�ȏ�A�����ƔF�߂��܂��B
����͎ʐ^���B�鎞�ɋ@�ނ̑I�тƐݒ肪�e�ՂɂȂ�i�����܂�F�l�Ɋ֘A����v�f�ł����j
�܂��A�@�ނ��w������O�̔�r�����ɂ��𗧂Ǝv���܂��B
�������A����͂����܂Ō��a�̔�r�ŁA�����Y�̎�����A���ӂ̗���AAF���x��A
��舵���̂₷���Ȃǂƕ��s�������āA�g�[�^���Ō��߂�K�v������܂��B
���̏ꍇ�́A35�~�����Ɣ�ׂ�Ώ��^�y�ʂ��܂߂āA4/3�̗��_���Ȃ��Ǝv���܂����A
APS-C�ł�����A��Ԗ��邢f/2.8�Y�[���ł��Af/4.3�O��ɂȂ�܂�����A
4/3�̕����A0.3�i�̗D��������ƔF�߂��܂��B
�Z���T�[�Z�p���x���̍��ł��̗D�����Ȃ��Ȃ邩���m��܂��A
�����4/3�t�H�[�}�b�g�̂����ł͂���܂��A�����܂ł��������ƂƂ��v���܂���B
�����ԍ��F10305094
![]() 1�_
1�_
���鐯����A�܂��������Ƃ��J��Ԃ��Ă܂����l�̎���ɂ͂������Ă���܂����H
>�{���ɐM���Ă���Ȃ�A�L���m�����[�U�̕��ɂ�EF�����Y�́AAPS-C�@�ɂ����
>1.4�i�Â��Ȃ�A�j�R�����[�U�̕��ɂ�FX�����Y��DX�t�H�[�}�b�g�@�ɕt���Ă��A1.3�i
>�Â��Ȃ�Ƃ������Ƌ����Ȃ����R�͉��ł��傤���H
tensor-tan���������������Ă��܂����A�吨�̐l�����̎���̓�����҂��Ă���Ǝv���܂��̂œ������ɓ����ĉ������I
�J��Ԃ��ł����A�����t�H�[�T�[�Y��[�U�[�ɑ��Ẵl�K�L�����⌙���点�Ȃ���̂Ȃ�A���㊷�ZF�l���ς̂���������߂ĉ������B
�܂�������M�O�������Ċ��ZF�l�̕��y���l����Ȃ�i�����̗��v�Ǝv���Ȃ�j�������������A���X���X��EOS�f����NIKON�f���ȂǂŎ��_�̓W�J�����ĉ������B
�v����Ɂu������̂Ȃ����Ă݂�I�v�ƌ������Ƃł��B
�����ԍ��F10305585
![]() 14�_
14�_
>���Z��������F�l�������ł���i�܂�L�����a�������̎��j�ʐ^�̎��_�����
>�Z���T�[�T�C�Y�Ɋւ�炸�AF�l�Ɋ֘A���鐫���A�I�o�̒��߂Ƃ���Ɋ֘A����掿�A
>��ʊE�[�x�A��܌��E�Ȃǂ��ׂĂ��������ʂɂȂ�܂��B
�����ɂȂ�̂��ǂ������肩�ł͂Ȃ��B�@�܂艼���ɉ߂��Ȃ��̂ɁA
>�Ⴆ�AZD35-100/2.0�ƁAZD14-35/2.0���A���ꂼ��35�~�����Ɋ��Z���܂��ƁA
>70-200/4.0�ƁA28-70/4.0�̃����Y�ɂȂ�܂����A���̓��ZD�����Y�́A
>35�~�������A���炩�ɑ�^�d�ʂł��邱�Ƃ͕�����܂��B
�����̏�ɉ������d�˂Ă������͂��Ȃ��B�@�M�a�̘_���͑�̂������ł���B
>����F�l���Ⴄ�ł��傤���A����F�l������Ă��A�������ʂɂȂ�ȏ�A�����ƔF�߂��܂��B
����������B
�摜���o���Ȃ��̂͏o���Ȃ����R������Ƃ������ƁB�@�܂蓪�ōl���������ƌ����͈قȂ�Ƃ������ƁB
�����ԍ��F10305846
![]() 7�_
7�_
��̕���DXOmark�̔�r���������̂ňȑO�\�������ł����Q�l�܂ŁA�ʐςƐ��\�͕K����v����킯�ł͂Ȃ����Ƃ�������Ǝv���܂��B
FT��APS��K20�E50D�EE3�ł���Ă݂܂����B
�ꐢ��O��E3�ł�����������������Ă܂��A������������ƂقƂ�nj݊p�ɂ݂��܂��ˁB
�ł��܂��������ŁA����͗�O���Ƃ�����ȃP�[�X���Ƃ�������Ǝv��,�����ɓs���̈��������f�[�^�͖������s���̗ǂ����̂����������ƌ����咣�ł�����Borz
�����ԍ��F10306082
![]() 2�_
2�_
������Ƃ����ʂ�܂��˂���
>�J�����̊�{�m��������A���ZF�l���́A�܂������Ӗ��̖������Ƃ͒N�ł�������ł��傤�B
�܂������Ӗ��������A�Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��낪����Ƃ���ŁA�{�P�͌��a�Łi��́j���܂�̂ŁA35�~���t�C�����Ɋ��ꂽ�l�Ƃ��ŁA��p�����Z�œ_�����ōl����l�́A�{�P�����ZF�l�ōl����ƃV�b�N������Ǝv���܂��B
���ꂪ���X���ZF�l�ɈӖ���������l���o�鏊�Ȃł��ˁB
���邳�͎�F�l�A��p�����Z�œ_�����A�{�P�����ZF�l�łƂ����̂ł���A�債�Ė��͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���邳�����ZF�l�ŁA�Ƃ����̂ł���ΊԈႢ�ł��ˁB
�����Ƃ����w�̊�{�Ƃ������ł���Ί��Z�œ_�������炵�ďo�Ԃ͂���܂��B
�����ԍ��F10306160
![]() 5�_
5�_
�͂炽����
>���邳�����ZF�l�ŁA�Ƃ����̂ł���ΊԈႢ�ł��ˁB
����A�܂������߂����Ⴄ�́H
�ւ������ȕ����g�����������Ă݂Ă��������ˁB
M * I = (k^2) * m * i
���ƁA��Ŏ����������u��f�������Z�œ_�����Ɋ܂߂�ׂ��v�͂���ϊԈႢ�ł����B
���Z�œ_�����͉�p�Ɋւ��Ċ��Z�B�������摜�̑傫�����l�����Ă��Ȃ��B
���ZF�l�͂����̕����̕⊮�ɂȂ��Ă܂��i���ɂ����낢�날�邯�ǁj�B
�������f���͉�f���B�T���v�����O����\�����̂Ƃ���̂��悢�ł��傤�iLinePair/PictureHeight ���Ă悭�\����Ă����j�B
�ŁA[10304035] �͉������Ă邩�悭�킩��܂���i�O�������j�B
�㔼�����͂킩��̂Ŕ����B
>���ZF�l���g�����������ƁA���ۂ̌������ǂ��ɂ���̂����ȒP�ɕ\���ł��Ȃ��̂ŁA���ʂ̐����u��f�s�b�`���������ƌ��V���b�g�m�C�Y���傫���Ȃ�v�Ɣ�ׂāA��낵���Ȃ��ł��ˁB
�B����̘b�͕⏕�ƌ����Ε⏕�����A�K�v������Ƃ������邵�A�݂����ȂƂ���ł��B
�d�v�Ȃ̂͊��ɏ������u��ʂ̑傫���v���Ǝv���܂��B�Ȃ����H �t�@�C���_�[���ʐ^����ʂ̑傫����ς����邩��B
���邳�͉�ʂ̑傫���ɉ����ĕω��i���Ɏ��������j�B����ł͖��邢���̉����̕]���ł��Ȃ��B��ʂ̑傫���𑵂���̂͊�{�ł��B���ZF�l���u�P�ʖʐς� 1/4 �̌����i�t�H�[�T�[�Y�j�v�Ƃ���Γ�����̂ł���ł����̂ł��B
>�Ⴆ�Ό��V���b�g�m�C�Y�̌������u�����Y���Â��v�ł�������Y�𖾂邭����Ό��V���b�g�m�C�Y�͌���n�Y������ǁA���ۂɂ̓����Y�𖾂邭���Ă����V���b�g�m�C�Y�͌���Ȃ��ł��ˁB
����܂���B
>�v�Z�̎�Ԃ͖��炩�Ɂu���ʂ̗��_�v�̕����������B�����̌ꐔ�����ʂ̗��_�̕������Ȃ��čς݂܂��B
�v�Z�̎�Ԃǂ������ňӖ��������ƌ����̂Ȃ�A����͂�����ƈႢ�܂��ˁB
F�l�̎����E���l�݂����Ȃ��̂��l���Ă݂܂��傤�B���Z�̈Ӌ`�͂����ɂ���܂��B
�����ԍ��F10306514
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �� [10301636] �ɂ��āB
>�t�B�����Ɋ��������Ă��A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő������Ă��A�������邳�Ɋ������܂��B
�t�H�g�_�C�I�[�h�̏ꍇ�͑��ʏ�̖ʐςɂ���āu�������閾�邳�͈قȂ�v�܂��B
>���郌���Y�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌��̌o�H�������̂���ʓI�ł��傤�B
>���������āA�����œ_�����E����F�l�Ȃ瓯���ʂɂȂ�܂��B�Z���T�[�̑Ίp���Ƃ͊W����܂���B
����͈Ⴂ�܂��B
�܂��uF�l�v�̓��o�́u�Ɠx�v�����߂����ʂł��B��̕��͏Ɠx�ł͂Ȃ��u���x�v�ł��B
���x�̏ꍇ�́i���܂蕷���܂��j���a�i���̊p�j�Ō��܂�܂��B
>F�l�Ƃ́u�œ_����÷�����Y�̗L���a�v�Œ�`����A���Z�ł�����̂ł͂���܂���B
>�u���鉿�l�v�ɂ��ƂÂ��ĉ����ʂ̂��Ƃ����������̂ł���A�����F�l�ŕ\���ׂ��ł͂���܂���B
����͂�͂���{�ꂪ�킩���Ă��Ȃ��ł��B���Z�œ_�������u��p�Ƃ������l�v�Ɋ�Â��Ċ��Z���܂��i��f���͎��̊ԈႢ�j�B
�����ԍ��F10306556
![]() 0�_
0�_
�� �܂蓪�ōl���������ƌ����͈قȂ�Ƃ������ƁB
����F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�ŎB�����ʐ^�A4/3��35�~�����̉掿���卷������܂��H
�� mainoa����A
����URL��\���Ă���������A�o�����ǂ�������Ǝv���܂��i�R�s�y���g���Čq�����Ă��������j�B
http://www.dxomark.com/index.php/eng/Image-Quality-Database/Compare-cameras/(appareil1)/220%7C0/(appareil2)/213%7C0/(appareil3)/267%7C0/(onglet)/0/(brand)/Olympus/(brand2)/Pentax/(brand3)/Canon
�����SNR18%��Print�͎ʐ^�̉掿�ł��BNR�����̂������Ǝv���܂����AE-3��K20D��
�Ȑ����ςɋȂ��Ă܂��iE-3��NR�̋��������@�Ƃ��Ēm���܂��B�p�i���0.3�i���ł��j�B
�����K���ɐ��K�����܂��ƁAE-3��� �� 0�̎��ɁA
�@�@K20D�͂����� 0.4�i���掿���ǂ��i�ʐϔ�ł́A0.70�i�̗\���A�덷0.3�i��j
�@�@50D�͂����� 0.5�i���掿���ǂ��i�ʐϔ�ł́A0.56�i�̗\���A�덷�Ȃ��j
�ł��B
���w�E���ꂽ�悤�ɁADxOMark�́ANR�̌떂��������ʂ��Ȃ��ł����ו��̕`�ʂ����܂��ƁA
E-3���G1�̕����D��܂�����i����1010����f���̔�r�j�AE-3�̎��ۂ̊��x�͏���
�����C������K�v�Ǝv���܂��B�����P�ʖʐςł́AK20D��50D�̊Ԃł͂Ȃ��ł��傤���B
�i�����܂Ő����ł��B0.1�`0.2�i�ȉ��̐��x�͂ނ��������ł��j�B
E-3�ł͂���܂��A����1200����f��D300�AG1�ƁA50D�Ȃ�Z�p���x���͂��Ȃ�߂��ł��B
�ʐς̍�����������A�w��0.2�i�̌덷�͈͂ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10306567
![]() 0�_
0�_
�����A����Ȃ̂��������̂ł��ˁB
Tranquility���� [10303899]
��r�����ł͉�ʂ̑傫���͑����Ȃ���Ȃ�܂���B��ʂ̑傫���ɂ���Ė��邳���ς�邩��ł��B
�����ԍ��F10306596
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
���Ƃ��肵�Ȃ��ŁA�����ƕ��͂�ǂ�ʼn������ˁB
�����ԍ��F10306745
![]() 0�_
0�_
�ǂ��������Ɠǂ�ŗ~�����̂ł��傤���H
Tranquility���� �͂��т��т����������Ƃ������̂ō��f����̂ł����B
>�����Ƃ��u�ӂ��͉�ʃT�C�Y������v�ł��傤���H�@�^��ł��B
>��������̂́A�掿���r���邱�Ƃ���̐l���炢����Ȃ��ł��傤���B
�����ł��傤���H
�掿��r�]�X�͂Ƃ������Ƃ��āA�u�ӂ��͉�ʃT�C�Y������v�����ނ���u��ʃT�C�Y�𑵂��Ȃ���Ζ��邳�̔�r�͂ł��Ȃ��v�ł��B
�t�H�[�T�[�Y�̃t�@�C���_�[�ʐς� 1/4 �̏ꍇ�A���邳�̓t���T�C�Y�̃t�@�C���_�[�ƈꏏ�ł��B
�ŁA�u�t�@�C���_�[�ʐρi�傫���j�͂���ł����́H�v���ĂȂ����ꍇ�ł��ˁB����ł����̂Ȃ�t���T�C�Y�̃t�@�C���_�[������������t���T�C�Y�̕������邢�ƂȂ邵�A����ł͏������̂Ȃ�A�t�H�[�T�[�Y�̃t�@�C���_�[��傫�����Ă���͂�U��T�C�Y�̕������邢�ł��B
�K�ȉ�ʂ̑傫���Ɩ��邳�͗p�r�ňقȂ�܂��ˁB�ό��n�̓W�]��Ȃǂɂ���]�������l����킩��ł��傤�B
�Ȃ��A���t�̃t�@�C���_�[�œK�ȑ傫���Ɩ��邳�͂ǂꂭ�炢���H ���Ă͎̂��͂킩��܂���B�������Ŕ��f���������B
�����ԍ��F10306802
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��@�v���Ԃ�ɏ������݂��܂��B
�Ȃ��@�����ł́@��ԏd�v�ȃC���[�W�T�[�N���ɂ��ā@�������݂������̂ł��傤�H
�@�Z���T�[�T�C�Y���@�傫���Ȃ�@����ɍ�����F�l�̃C���[�W�T�[�N�����K�v�Ł@�C���[�W�T�[�N����傫������̂ɂ́@�L�����a��傫�����Ȃ���Ȃ�܂���B���̈׃����Y���傫���Ȃ�܂��B
�@���ꂪ�؋��ɂ͓���F�l�̃����Y�ł�6×4.5��6×7�Ȃǂ̃����Y��35mm�����L�����a���@�傫������ׁ@35mm�����a�̑傫�ȃ����Y���K�v�ő傫���d���Ȃ��Ă��܂��B
���̋t�Ńt�H�[�T�C�Y�̃����Y�́@�Z���T�[�����������C���[�W�T�[�N�����������o����ׁ@�L�����a���������o��35mm�����a�̏����ȃ����Y�ł��݁@�������Ė��邢�����Y���o����̂ł��B
�@�ł�����@�t�H�[�T�C�Y��F�l2.0�Ȃǖ��邭�E�����������Y������̂ł��B
���Ⴆ�AZD35-100/2.0�ƁAZD14-35/2.0���A���ꂼ��35�~�����Ɋ��Z���܂��ƁA
70-200/4.0�ƁA28-70/4.0�̃����Y�ɂȂ�܂����A���̓��ZD�����Y�́A
35�~�������A���炩�ɑ�^�d�ʂł��邱�Ƃ͕�����܂��B
�����̏��ł����@���鐯���߂炳��̍l���ł̓Z���T�[�T�C�Y���傫������ΐ���قǃ����Y�����������邭�o����̂ł��傤���H
�@
�����ԍ��F10306870
![]() 11�_
11�_
���s�̂�������
>�t�H�g�_�C�I�[�h�̏ꍇ�͑��ʏ�̖ʐςɂ���āu�������閾�邳�͈قȂ�v�܂��B
����Ⴛ���ł����A����Ȏ��͘_���Ă܂���B���͈ȉ��̂悤�ɏ����܂����B
�w�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ�A���̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��Ă��A�t�B�����Ɋ��������Ă��A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő������Ă��A�������邳�Ɋ������܂��B
���������āAF�l���u�����Y�̖��邳�v�ƕ\�����邱�Ƃ͂���߂Ď��R�ŁA���̌��ʁu�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����v�ƂȂ�킯�ł��B�x
�����Ă�Ӗ����킩��܂��H
>�܂��uF�l�v�̓��o�́u�Ɠx�v�����߂����ʂł��B��̕��͏Ɠx�ł͂Ȃ��u���x�v�ł��B
���x�̏ꍇ�́i���܂蕷���܂��j���a�i���̊p�j�Ō��܂�܂��B
�w���郌���Y�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌��̌o�H�������̂���ʓI�ł��傤�B
���������āA�����œ_�����E����F�l�Ȃ瓯���ʂɂȂ�܂��B�Z���T�[�̑Ίp���Ƃ͊W����܂���B�x
�Ə����܂������A�킩��Â炩�����ł��傤���H�@
�����ł́u�����v�ɂ��ď����Ă܂��B������ƏC�����Ă݂܂��B
�w������w�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌����̗ʂ������̂���ʓI�ł��傤�B
���������āA�����œ_�����E����F�l�Ȃ瓯���ʂɂȂ�܂��B�Z���T�[�̑Ίp���Ƃ͊W����܂���B�x
>����͂�͂���{�ꂪ�킩���Ă��Ȃ��ł��B���Z�œ_�������u��p�Ƃ������l�v�Ɋ�Â��Ċ��Z���܂��B
�wF�l�Ƃ́u�œ_����÷�����Y�̗L���a�v�Œ�`����A���Z�ł�����̂ł͂���܂���B
�u���鉿�l�v�ɂ��ƂÂ��ĉ����ʂ̂��Ƃ����������̂ł���A�����F�l�ŕ\���ׂ��ł͂���܂���B�x
�ɂ��Ă̕ԐM�ł��傤���A�����ł͊��Z�œ_�����ɂ���p�ɂ��܂������G��Ă܂���B���{��Ƃ��ĕςł����H
>��r�����ł͉�ʂ̑傫���͑����Ȃ���Ȃ�܂���B��ʂ̑傫���ɂ���Ė��邳���ς�邩��ł��B
�w��������̂́A�掿���r���邱�Ƃ���̐l���炢����Ȃ��ł��傤���B�x
�Ə����܂����A�掿��r�̂��߂Ȃ�K�v�ɉ����Ă����R�ɂǂ����B
�����A����܂ň�x�����邳�̔�r�Ƃ͌����Ă܂��A�t�@�C���_�[�̖��邳�Ȃǂ܂������b��ɂ��Ă܂����B
�����ʼn��̃t�@�C���_�[���H
�������̈ӌ��ɓs���̂����Ƃ��낾���i�������ȉ����āj�ǂ܂Ȃ��悤�ɂ��肢�������ł��B
�����ԍ��F10306908
![]() 5�_
5�_
���̂�
150mm÷37.5mm��F4
300mm÷75.0mm��F4
���Ď��Ȃ́B
����ȊO�̂Ȃ�ł��Ȃ��́B
������I�����p�X�̗ǂ������Y�͒l�i�������́B
����͎g��������Ȃ́B
�t�F���[���͗ǂ��Ԃł���B�����Lj��z���ו����^�Ԃɂ͌����Ȃ��ł���B
������̓}�~�������ĎR�o��̓L�c�C����E�V�X�e���Ȃ́B
�����ԍ��F10306988
![]() 11�_
11�_
���s�̂�������
[10304035]�̑O�������́A���s�̂�������͌����Ă��邱�Ƃ̂���ڂ́u���ZF�l�v������ǁA����Ă��邱�Ɓi���V���b�g�m�C�Y�̌v�Z�j�͂����ł͂Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��ł���B
���̎咣�Ƃ��ẮA
1. ���ZF�l�ɂ܂�闝�_�́A������w�ŏK�������w�Ƃ͈Ⴄ
2. ���ZF�l�ɂ܂�錾�t�ł́A�u���邳�v�ɓ��{��̎g�����Ƃ��Ė�肪����
�Ƃ����������ł��ˁB�܂����ʂ̕����Ɠ����l�������Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ����킯�ł������ł����A���ʂƈႤ�l����吨�ɔ��\����ꍇ�A�אS�̒��ӂ��K�v�ł���B
����̏ꍇ�T�^�I���́u���邳�v�ł��ˁB
���̌f���͎ʐ^���B��l�̗�����ύ����̂ŁA���������ꏊ�ɏ����ꍇ�A�u���Áv���Ɠx�ȊO�Ɏg�����Ƃ͖����ł��B�i�ʐ^���B��Ȃ��l�ɂ����ʂ͖������Ǝv������^^;)���t�͑���ɓ`���Ȃ�����܂�Ӗ�������܂���B
���s�̂�������̏ꍇ�A�I�o�v���ǂ̂悤�ɐv���邩�A�Ȃǂƍl����A�Ȃ�Ŏʐ^���B��l���Ɠx�𖾂邳�Ƃ��邩�������邩������܂���ˁB
�����ԍ��F10307165
![]() 5�_
5�_
����
�����{��͂ǂ��ł��ǂ��݂����ˁB
�u�掿�v���ĉ���B���̂��Ƃ������Ă��錾�t�Ȃ́H
�u�œ_�����v�Ɓu���a�v�������ŁuF�l�v���ς��Ȃ���u��p�v���u��ʑ̐[�x�v��
�u���邳�v�������ł���B���t��u�������������Ȃ́B
�z���������B
�Ȃ�Ńn���C�́u����]�����v�͂���Ȃɑ傫�������́H
�ȒP�ł���I�@�𑜓x���グ�邽�߂ł���I�@�������������������B
����A�Ȃ�ő傫������Ɖ𑜓x���グ����́H
�ȒP�ł���I�@�ʐ^�ɂ����Ƃ��̑傫�����ɂ�����A�����������Y���傫�������Y��
�����ʐς�����̍H�쐸�x���グ���邩��ł���B
���w���ł��\�������ł��镨���ł��B�����Z�A�����Z�A�|���Z�A����Z�����g��Ȃ�����B
������@�I�����p�X�̗ǂ������Y�͍����Ȃ�́B
������������A�݂�ȁA���O�Ŏʐ^�B���Ƃ��ŁI
�L���m���ł��A�j�R���ł��A�y���^�b�N�X�ł��A�������I�����p�X�ł�
���ꂢ�ɎB��邩��I
�����ԍ��F10307469
![]() 3�_
3�_
�c�_���M���A���ɐ\����Ȃ��̂ł����A���낻��u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�i���̂Q�j�v�Ƃ��ĕʃX���𗧂ĂĒ����Ȃ��ł��傤���H
���܂�ɃX�����������ău���E�U�\���ɔ��Ɏ��Ԃ��|����A���̘b��ɒm�����������Ȃ��{���҂ɂƂ��Ď��ɕs�ɂ܂�Ȃ��̂ł��B
�ǂ��������V�N���肢���܂��@m(__)m
�����ԍ��F10307495
![]() 4�_
4�_
������肷���ȃ}�j�A�̕��X�́A�O�ɏo�ďH�i���Ă��炢�����ł��B
�R�͍g�t���Ă܂���B��������܂�����B���c�ł͈�䂪�P���Ă܂���B
�������I�J�����ŁA�y�����B������ł�����ł��B
�g�ѓd�b�J�����Ŗ�������l������A�t���T�C�Y�ł������ł��Ȃ��l������ł��傤�B
���ꂼ��̃J�����̖������Ⴄ�����Ȃ̂ł���A�����ɂ͏�������Ȃ��ł��傤�B
�F����A�ŋߊy�����B��Ă܂����H
���̗͂��āA�ڂ��L���L���P�����ĎB��܂��傤��B
�ٓ��Ɛ����Ɖَq�������āA�Ԃ�Ԃ�Əo�����܂��傤�B
�����ԍ��F10307829
![]() 6�_
6�_
�� �ȒP�ł���I�@�ʐ^�ɂ����Ƃ��̑傫�����ɂ�����A�����������Y���傫�������Y��
�� �����ʐς�����̍H�쐸�x���グ���邩��ł���B
�ʐ^�Ƃ��Ă͂Ȃ��~�����{�̉𑜂ł�����R���f�W�ɏ��Ă��Ⴊ�Ȃ��ł��ˁB�W���J����f/2.8�ł����B
�ʐ^�Ƃ��Ă̌��ʂ�����Ȃ���Ή��̈Ӗ�������ł��傤�B�Â��Ȃ��ƌ����āA�������x����������B
�����ԍ��F10307837
![]() 0�_
0�_
����]��������d�q�������܂ŁA���{�̃J�����Z�p�͑f���炵���ł���!!
�n�C�r�W���������{�l�Ă̂��̂ł����A�����Ƀt�B�������[�J�[�����邵�A���ł��ؐ��Ô��̐������[�J�[���������邵�A
���������{�l�́A���E�ł����Ƃ��J�����̑I�������L�x�ōK���ł��ˁB
����ƁA
�X�[�p�[�J�~�I�J���f���f�W�J���̈��ł��傤���H
���Ƃ�����A���̒��a���\�Z���`�̋���ȓd���̂悤�Ȃ��̂����f�ɂȂ�̂ł��傤���H
�ڂɌ����Ȃ����q�̌����Ƃ炦��Ȃ�āA���ɂ̍����x�ł��ˁB
����ς���{�͑f���炵��!!
�������{!!
�����ԍ��F10308018
![]() 1�_
1�_
>����F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�ŎB�����ʐ^�A4/3��35�~�����̉掿���卷������܂��H
���͍����ǂ������Ƃ͈�،����Ă��Ȃ��B
�u��i�Â��v�Ȃ錻�ۂ����ɂ͂ǂ��������Ɍ�����̂��A�q���������ƌ����Ă��邾�����B
>�ʐ^�Ƃ��Ă̌��ʂ�����Ȃ���Ή��̈Ӗ�������ł��傤�B
���ʂƂ������ʂ��o���Ȃ������ɉ��̈Ӗ�������ł��傤�B
����̋�_���̂��̂ł͂Ȃ����B
�����ԍ��F10308054
![]() 8�_
8�_
���鐯���߂�l�B
���ʐ^�Ƃ��Ă̌��ʂ�����Ȃ���Ή��̈Ӗ�������ł��傤�B
�u�ʐ^�Ƃ��Ă̌��ʁv�Ƃ������̂Ɋ�Ȃ�Ă���܂����ˁB
���ʂ̓��e�͐l���ꂼ�ꂾ�Ǝv���܂���B
�����ԍ��F10308075
![]() 5�_
5�_
Tranquility���� [10306908]
�������ƌJ��Ԃ���Ă��A������Ƃ��Ă͊��ɓ��������ƂȂ̂ł����B�ׂ����Ƃ��͏Ȃ��āA�����̌������͂ƂĂ��ς��Ƃ��������ɓ������̂ł����B
>�w�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ�A���̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��Ă��A�t�B�����Ɋ��������Ă��A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő������Ă��A�������邳�Ɋ������܂��B
>�����Ă�Ӗ����킩��܂��H
�P�ʂ��g���ď����Ό������Ȃ��Ǝv���܂���B�u�����v�Ƃ����T�O���w��邱�Ƃ������߂��܂��B���Ђ�����܂��B
>�w������w�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌����̗ʂ������̂���ʓI�ł��傤�B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A����́u���x�v�ł��B
>���{��Ƃ��ĕςł����H
���Ȃ����u���Z�v�Ƃ������t�̈Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���Ӗ��Ȃ���������邽�߂ɂ́A�������Łu���Z�v���`���Ă݂Ă��������B
>�����A����܂ň�x�����邳�̔�r�Ƃ͌����Ă܂��A�t�@�C���_�[�̖��邳�Ȃǂ܂������b��ɂ��Ă܂����B
�u��ʂ̑傫���𑵂��Ĕ�r�v�ɂ��Ăł����A�u���邳�v�ȊO�� Tranquility���� �͔[�����ꂽ�̂ł��B�c����́u���邳�v�����̂͂��ł��B
�t�@�C���_�[�̑傫���𑵂���́u�B���O�v�̍l�@�̗�B
��f���𑵂���́u�B�����v�̍l�@�̗�B
�����ԍ��F10308548
![]() 0�_
0�_
�͂炽���� [10307165]
>1. ���ZF�l�ɂ܂�闝�_�́A������w�ŏK�������w�Ƃ͈Ⴄ
�u������w�ŏK�������w�v��N���m��܂���̂ŁB�N���m��Ȃ����[�J���Șb��������ɔ��_�Ƃ͏Ύ~�ł��B
>2. ���ZF�l�ɂ܂�錾�t�ł́A�u���邳�v�ɓ��{��̎g�����Ƃ��Ė�肪����
�ނ���uF�l�v�̕������{��̎g�����Ƃ��Ė�肪����̂ł����B�u150mm F2.0 �� 300mm F2.0 �Ɠ����v�Ȃ�ăt���T�C�Y��n���ɂ��Ă܂��B
>�I�o�v���ǂ̂悤�ɐv���邩�A�Ȃǂƍl����A�Ȃ�Ŏʐ^���B��l���Ɠx�𖾂邳�Ƃ��邩��
������Ɠx��ے�Ȃ��Ă��܂����H
ISO���x�ɂ́u�ʐ^�̖��邳�̋K��v�Ƃ������l������Ɖ��x�������Ă܂����H
�����ԍ��F10308562
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�ׂ����Ƃ��͏Ȃ��āA�����̌������͂ƂĂ��ς��Ƃ��������ɓ������̂ł����B
�P�ʂ��g���ď����Ό������Ȃ��Ǝv���܂���B�u�����v�Ƃ����T�O���w��邱�Ƃ������߂��܂��B���Ђ�����܂��B
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��ē������邳�Ɍ�����v
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�B�����Ɋ��������ē������邳�Ɏʂ�v
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő��������瓯�����邳�Ɍv���v
�ǂ����ςł����H
����F�l�̃����Y�Ȃ�A�œ_�����ɊW�Ȃ�������ʑ̂̏œ_���̖��邳�͂ǂ�������ɂȂ�ƌ����Ă�̂ł����B�P�ʂ͊W����܂���B
�����āA���ꂪF�l�������Y�́u���邳�v�ƌ������R�ł��B
>�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A����́u���x�v�ł��B
�w�E�B�L�y�f�B�A�x�ɂ��A
�u�����i���������Aluminous flux�j�v�Ƃ́A�������炠������ɕ��˂��ꂽ���ׂĂ̌��̖��邳��\���S���I�ȕ����ʂł���B
�u���x�i�����ǁj�v�́A�������炠������ɕ��˂��ꂽ�P�ʗ��̊p������̌��̖��邳��\���S���I�ȕ����ʂł���B�P�ʗ��̊p������̌����ŕ\�����B
���҂̈Ⴂ��
�u�����v�́u��������ɕ��˂��ꂽ���ׂĂ̌��v
�u���x�v�́u��������ɕ��˂��ꂽ�P�ʗ��̊p������̌��v
�����Ӗ����Ă���̂��A��������ς��Ă݂��
�u�����v�́u����������˂��ꂽ���̗ʁv
�u���x�v�́u�����̖��邳�v
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���������āA�����Y�ɓ��˂������̗ʂ������ꍇ�́u�����v���Ó����Ǝv���܂��B
�킽���͐����Ɍ��w���w��ł͂���܂��A���̂悤�ɗ������Ă��܂��B
�͂炽����͑�w�Ō��w���w�Ƃ̂��Ƃł����A����Ő������ł��傤���H
���Ƃ��Ƃ͋��s�̂�������
�u�Z���T�[�Ίp���������Ȃ�A�����œ_�����EF�l�E�����W�{���ŁA������F�l��2�i�����Ȃ��v
�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂������A���̕��͂̈Ӗ��Ɓu�W�{���E�����v�����������Ă���̂��킩��Ȃ������̂Ō��w�n�ɂ�����u�����v�ɂ��ď����܂����B
�����Ƃ��A���̂������Ƃ̕��͂Ŏ����u��p�v�Ə����Ƃ�����u�œ_�����v�Ə����Ă��܂����̂ō������������̂�������܂���B
>���Ȃ����u���Z�v�Ƃ������t�̈Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���Ӗ��Ȃ���������邽�߂ɂ́A�������Łu���Z�v���`���Ă݂Ă��������B
���͍ŏ�����u���Z�v�Ƃ������t������ƍ�������������g���ׂ��ł͂Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
>�c����́u���邳�v�����̂͂��ł��B
���ꂪ�t�@�C���_�[�̖��邳�̂��Ƃ�����������Ă���̂Ȃ�A���܂܂ł̉掿�Ɩ��邳�̊W�ɂ��Ă̋c�_�i�H�j�Ƃ͂܂������W�Ȃ��b�ł��ˁB
�u���邳�v�Ƃ����p��ɂ��Ăł�����A���܂܂ł������Ԃ��܂������A���̕������낢�돑������ł�������Ⴂ�܂��̂ŁA���������Ǐ��߂���ǂݒ����Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F10308717
![]() 8�_
8�_
>�N���m��Ȃ����[�J���Șb��������ɔ��_�Ƃ͏Ύ~�ł��B
��w�ł���Ă���w�͈�ʓI�Ȃ��̂��Ƒz�����܂����B
���ZF�l�_�̕�������ۂǃ��[�J���ł��傤�B
>�ނ���uF�l�v�̕������{��̎g�����Ƃ��Ė�肪����̂ł����B�u150mm F2.0 �� 300mm F2.0 �Ɠ����v�Ȃ�ăt���T�C�Y��n���ɂ��Ă܂��B
F�l�͕����I�ɒ�`����A���{��ȊO�ł����̖�������܂���B
�t�H�[�T�[�Y150mmF2.0 �� 35mm�t���T�C�Y300mmF2.0 ���������邳��������A�t���T�C�Y�͉������邱�Ƃ�����̂ł����H
�����ԍ��F10308759
![]() 16�_
16�_
�� �t�H�[�T�[�Y150mmF2.0 �� 35mm�t���T�C�Y300mmF2.0 ���������邳��������A
�g�������邳�h�ƌ����Ă��A35�~������300/4�̎d�������ł��Ȃ��ȏ�A���̈Ӗ�������ł��傤���B
�����ԍ��F10310689
![]() 0�_
0�_
�����ˁA�N���ǂ�ȍl���������ł����̂ŁA���͍Ō�̏������݂ɂ��܂��B
���͂����w�Z�T�N���̎Z���ŕ\�����܂��B
���t�H�[�T�[�Y�́@150mm�@�Ł�
150
��37.5mm�@�̌��a�́�
150�@37.5
��F�l���@�S�@�ł���
150÷37.5��4
���C���[�W�Z���T�[��̉�p�́A�t���T�C�Y�Z���T�[�́@300mm�@�Ɠ����Ł�
�i150÷37.5��4�j��300÷�w
��F�l�́@�t���T�C�Y�Z���T�[�́@300mm�@���a�@75mm�@�̃����Y�Ɠ����@F�S�@�ł���
�i150÷37.5��4�j���i300÷75��4�j
������ˁA�u300mm��F�W���I�v���Ď��Ȃ�A���a��37.5mm���ˁB
300÷8��37.5
300mm��37.5mm�̑O�ʂȂ�A�����Â���B�����Ԃ��������Y������B
�����ǂˁA��ԑ厖�Ȃ̂�
�u�t���T�C�Y�Z���T�[�̃J�����ɂ���������v����Ȃ���B
�u�t�H�[�T�[�Y�̃Z���T�[��Łv���Ă��ƂȂ́B�������`�̎n�߂���uF4���v���Č�����
����A�ς��̂́u���邳�v����Ȃ��Č��a�Ȃ́B
�������Ă鑊�肪�����̎q����Ȃ��Ă悩�����楥�
���I�@�������ˁ@���X�傳��̂��ƖY��Ă��B
�����ԍ��F10310707
![]() 8�_
8�_
Tranquility����
��w�ł͕����w�̈ꕪ��Ƃ��ďK�����̂Ń����Y������Ă���l�B�Ƃ̓m�����Ⴄ��������܂���^^; �����w�I�ȊT�O�Ƃ��ẮA���肷�闧�̊p���̌��̗ʂȂ�����A�P�ʗ��̊p�ӂ�̌������ƌ��x�ł��ˁB
���������āA
>��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌����̗�
�Ȃ�A�������K�ł��傤�B
�����ԍ��F10310759
![]() 6�_
6�_
�͂炽����
��{�A���̔F���ŊԈႢ�Ȃ��Ƃ킩����S���܂����B
���ԐM�A���肪�Ƃ��������܂����B
�����ԍ��F10311664
![]() 0�_
0�_
Tranquility���� �� [10308717]
�ŏ�����b���i��ł��Ȃ��̂ł����B
>�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��ē������邳�Ɍ�����v
�B���ʂړ���Ō���Ƃ������Ƃł��ˁB�Ⴆ�ΎB���ʂ����ɂ���Ƃ����āB����͂悢�ł��B
�������A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���Ⴄ�ꍇ�A������ƈقȂ�܂��i���A�Ƃ肠���������ł��傤�j�B
>�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�B�����Ɋ��������ē������邳�Ɏʂ�v
�u�t�B�����v�ƌ������ꍇ�A�u�����t�B�����v��O��Ƃ��Ă��܂��ˁA���݂��ɁB�t�H�[�}�b�g������Ă������t�B�����ł��i�ʐς��Ⴄ�����j�B
�����炱����悢�ł��B�u�������邳�̑傫���Ⴂ�v�ł��B
>�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő��������瓯�����邳�Ɍv���v
�ŏ����猾���Ă�悤�ɁA�t�H�g�_�C�I�[�h�̖ʐς�ς����瓯�����邳�ł͂���܂���B
�t�H�g�_�C�I�[�h�̖ʐς������Ȃ�A�u�������邳�̑傫���Ⴂ�v�ł��B
[10302332] �̌㔼�̎���p���������Q�ƁB�B�����͉�ʂ̑傫���ň��f������̌��ʂ��ω����܂��B
>�P�ʂ͊W����܂���B
>�����āA���ꂪF�l�������Y�́u���邳�v�ƌ������R�ł��B
����͖\�_�ł��BF�l�́u�Ɠx�v�����߂��ۂɏo�Ă���ϐ��ł��i���x���������Ƃ��j�B
���x�ɂ��ẮA���Ȃ����u��_����o�����v�ƌ������̂����̂܂��܂łł��B�_�����̏ꍇ�͌��x�ł��B
�E�B�L�y�f�B�A�͒m��܂��A����Ȃ���������ȏ��������Ă܂����H �u�P�ʂ͖��W�v�Ƃ������Ȃ��ɖ�肪���肻���ł����B�P�ʂ͕����̊�{�ł��B
���Ȃ��́u�����Ɠǂ�ł��������v��A�Ă��܂����A���������������Ɠǂ�ł��������ł���B
>���͍ŏ�����u���Z�v�Ƃ������t������ƍ�������������g���ׂ��ł͂Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
��l�̈ӌ��Ƃ��Ă͔F�߂܂����A�u���_�͈�l�̓����̂��߂ɑ��݂���̂ł͂Ȃ��v�ƌ����Ă����܂��i����A�O�ɏ��������t�ł����폜���ꂽ�̂Łj�B
>���ꂪ�t�@�C���_�[�̖��邳�̂��Ƃ�����������Ă���̂Ȃ�A���܂܂ł̉掿�Ɩ��邳�̊W�ɂ��Ă̋c�_�i�H�j�Ƃ͂܂������W�Ȃ��b�ł��ˁB
�t�@�C���_�[�̖��邳�i�Ɠx�E�������U�x�j�́u�B���O�v�B���f�̖��邳�i�����j�́u�B�����v�ł��B���҂Ƃ��u�傫������ΈÂ��Ȃ�A����������Ζ��邭�Ȃ�v�̊W������܂��B���̓_�ɂ����ė��҂͓��������̂��̂ł��B
[10308759] �ɂ��āB
>F�l�͕����I�ɒ�`����A���{��ȊO�ł����̖�������܂���B
���ZF�l�������I�ɒ�`�ł��܂����H
�u���Z�v���ĉp��Ō����ƂȂ�ł��傤�B�����܂ł͒m��܂���B
>�t�H�[�T�[�Y150mmF2.0 �� 35mm�t���T�C�Y300mmF2.0 ���������邳��������A�t���T�C�Y�͉������邱�Ƃ�����̂ł����H
�R�Q�W�̃����Y�����l��������Ȃ��ł��傤�ˁB
�ƌ��������A�傫���t�H�[�}�b�g�ɉ掿�ʂł̗D�ʐ��������Ȃ�܂��B�������玄�Ȃ�R���f�W����Ԃ����ł��B
�������u���邳�v�́u�P�ʃ��j�b�g������̌����v�ƒ�`���Ă��܂��B
�����ԍ��F10311822
![]() 0�_
0�_
[10306908]
>�w������w�n�ɂ�����u�����v�������ꍇ�A��ʑ̂̂P�_������˂��ꂽ���������Y��ʉ߂��P�_�ɏœ_�����Ԃ܂ł̌����̗ʂ������̂���ʓI�ł��傤�B
�G�A���[�f�B�X�N�̎���p���āA�u�_���̔��a�� F�l�ɔ��v�ƂȂ�܂��B���������ʂ͌��a���ł��B
�uF�l���̊ϑ��ŁA�_�����̖��邳�͌��a�ɔ��v�ł��ˁB
>���������āA�����œ_�����E����F�l�Ȃ瓯���ʂɂȂ�܂��B�Z���T�[�̑Ίp���Ƃ͊W����܂���B�x
�u�œ_�����v���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɔ�Ⴗ����̂Ȃ̂Łi���Z�œ_�����j�A�_�����̏ꍇ�́uF�l���̊ϑ��ŁA�_�����̖��邳�i�_�������̕��ϏƓx�j�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɔ��v�ł��ˁB
������O�ɁAF�l�̓��o�Ƃ��Ă���͈�ʓI�ł͂���܂���B
F�l�̓��o�́u�������̓���P�x�ʁv�������Ƃ��čs���܂��B
�ŁA���� [10301384] �ł�
>>���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�����炸����F�l�Ȃ烌���Y�̖��邳�͓����B
>�u���ʏƓx�������v�ł��ˁB
�ɂȂ�܂��i�_�����ɑ��Ă͐��藧���Ȃ����A����P�x�ʂɑ��Ă͐��藧�j�B
�B���ʂɑ������镔�����i�~���[�Ȃǂ���āj���ړ���Ō���ꍇ�ɂ͂���ł悢�ł��B�t���T�C�Y�Ƃ͖��邳�͓����ʼn�ʂ̑傫�����Ⴄ�����B
�ʐ^�̏ꍇ�A��ʂ̑傫���̊�Ƃ����̂͑��݂��܂���B�傫������ΈÂ��Ȃ邵�A����������Ζ��邭�Ȃ�B
�t�B�����̏ꍇ�́u�������́v�Ȃ̂ŁA�u���邳�������ő傫�����Ⴄ�v�̊W���������グ�邱�ƂɑÓ����͂���܂����B
�f�W�J���̏ꍇ�͉�f�s�b�`���قȂ�̂ŁA�uF�l���Ŗ��邳�������v�͕K�������������܂���i�s�������قƂ�ǁj�B
�������f�W�J���͉�f�s�b�`�� ISO���x�����܂�܂���I ���̂��Ƃ́u�t�B�����ƃf�W�J���ł� ISO���x�̈Ӗ��������قȂ�v���Ƃ��Ӗ����܂��B
�����ԍ��F10311946
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�R�Q�W�̃����Y�����l��������Ȃ��ł��傤�ˁB
>�ƌ��������A�傫���t�H�[�}�b�g�ɉ掿�ʂł̗D�ʐ��������Ȃ�܂��B�������玄�Ȃ�R���f�W����Ԃ����ł��B
�傫���Z���T�[�̃J�����Ƃ���p�����Y�����l�ɂ́A����Ȃ��u�Z���T�[�T�C�Y���傫���v�Ƃ����掿�ʂ̗D�ʐ����t���Ă��܂�����A�������Z���T�[�p�����Y�Ɩ��邳�������ł��\���������ł��傤�B
>�������u���邳�v�́u�P�ʃ��j�b�g������̌����v�ƒ�`���Ă��܂��B
�܂��V�����u���邳�v�ł��ˁB^^;
���������̃X�y�V������`���Ƙb���ʂ���̂����������ɂȂ����Ⴂ�܂���B
���Z�̈Ӌ`�A�˂��B(���ߑ�)
135���Ɋ��ꂽ�l�̎B�e���̕X�A�ł���B
�����ԍ��F10312142
![]() 10�_
10�_
�@�����ĕ�����l�ɂ��������܂��B
�@�u�ʐ^���B�e���悤�Ǝv�����v �Ƃ��A�ǂ�����H
�@���̖���ɑ��A�u�����Ă�J��������ɂ��A�B�e�Ɍ������v �Ƃ����̂͋ł��B
�@����� �i�l�j �͂܂��A�J�������Ƃ����Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B�@���낢��ȃJ�����������Ă���l�Ȃ�A�u�����̓R���������Ă������v �Ƃ������ƂɂȂ邩������܂���B
�@�l�͂��ꂼ��A�g���ėǂ����z �E ��p�Ό��� �E �t�@�b�V�������Ƃ����h�Ƃ�w �E �g�p�ړI�ɂ����Ă��邩 �E �����Ă������ʂ� �i�{�̑��̐��\�E�����Y���̐��\�j �Ȃǂ��l�����ăJ������I�ԂƎv���܂��B
�@���Ȃ킿�A�u�J������V�X�e����I�ԁv �Ƃ����̂́A�ʐ^���B�e����Ƃ������ɂ����� �u��ʓI�ȉۑ�v �ł��B
�@����ɑ��A�u�������Ă���J�������g���� �ǂ��B�e������ �ǂ��ʐ^���B��邩�v �Ƃ����̂� �u�p�v �̘b�ł����āA��ʓI�ȉۑ�ł͂���܂���B�@������肳��Ă���Ƃ����A�u����ȏ�Ԃɂ�����ۑ�v �ł��B
�@�ʂȘb�ł����A�u����ȏ�Ԃɂ�����ۑ�v �����������Ȃ��A�u��ʓI�ȉۑ�v �ɑ��āA���I�m�ɔ��f�ł���悤�ɂȂ�\���͍����ł��ˁB
�@�ł͂ł́`w
�����ԍ��F10312572
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������
���f�W�J���̏ꍇ�͉�f�s�b�`���قȂ�̂ŁA�uF�l���Ŗ��邳�������v�͕K�������������܂���i�s�������قƂ�ǁj�B
�@F�l�Ƃ͒P�ʖʐς�����̌��ʂł���@�t�B�����ł��t�H�g�Z���T�[�ł������C���[�W�T�[�N�����ł���ǂ���̎���ʂł��������邳�ɐ���͂��ł��B
�@�����Y��F�l�Ƃ́@�t�B������t�H�g�Z���T�[�̎���ʂɓ����������_�ł̌��ʂł���@���̌��f�s�b�`���قȂ낤�Ɓ@����̓t�H�g�Z���T�[�̖��ׁ̈@F�l�Ƃ͊W�����͂��ł��B
�܂��@�t�H�g�Z���T�[�Ɍ��������������_�Ł@������d�C�M���ɕς���Ă��܂��ׁ@�d�C�M�����@���邢�E�Â��ƌ����̂��ςȘb�ł͖����ł��傤���B
�����ԍ��F10312595
![]() 10�_
10�_
�t���T�C�Y�����`�҂̃f�W�^���]�̕��X�́A�ꌩ����Ɨ��_�I�ł����A�@
�������A���Z(�؋�)�Ɋ�Â��Ȃ��v�Z��̂��̂���Ɋ����܂��B
�����̌f���̎�|�̓����Y�ɂ��Ăł���A�Z���T�[���\�ł͂���܂����ˁB
�_�_�̂���ւ��̓_���ł���!!
���Ȏ咣�̗D�ʐ����������߂ɁA�_�_�̂���ւ��R�Ƃ����Ȃ��̂̓t���T�C�Y�����`�҂̓����ł����ˁB
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�͑��l�ł���A���ꂼ��Ɉ꒷��Z�����ē��R�ł��B�����ɂ͏����������܂����B
���̓t�B����35�~��������8×10���܂ł��܂����A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y���ς���Ă����邭���Ȃ�Ȃ����Â����Ȃ�܂���B
�T�C�Y���ς�邽�тɖ��邳���ω����Ă�����A�P�̘I���`�Ȃ�Ďg���܂����ˁB
4×5����6×7���z���_�[���g���Ɩ��邳���ς��!?
�t���T�C�Y��55�{�̖ʐς�8×10���͂Ƃ�ł��Ȃ����邭�Ȃ�!?�@�ł́A115�{��11×14���ł͂��������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂�!!
�f�W�^���]�̊F�l�́A�t�B���������蒼�����ق��������ł��ˁB�f�W�^���Ȃ��10�N�����ł��B
�t�B�������^�����^�܂ł�P�̘I���v�Ŗ��邳�������Ȃ���B��B�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɍ��킹�ă����Y��I�ԁB
��^�̏ꍇ�A�����œ_�����ł��C���[�W�T�[�N���̑傫���ɗl�X�Ȃ��̂�����B���a��170mm���炢����400mm���炢�܂ł���B
�ł��I�o�����邳�������B
���㗝�_����Ŏ��Z���Ȃ�����A���̂悤�ȃw���e�R���_���o������̂ł��傤�ˁB
���̌�����킩��܂���B
�����ԍ��F10312832
![]() 13�_
13�_
�t�B�����̘I�o�v�Z�ƁA�ʐ^�̖��Ái�����掿�j�����������̂ł��ˁB
�t�B�����̘I�o�v�Z�������ł��A�ʐ^�S�̂̊����掿�ƒ��ڌ��т܂���B
�t�H�[�}�b�g�̈Ⴄ�ʐ^�������番����͂��ł��B
�����ԍ��F10312881
![]() 0�_
0�_
�ʐς̘b�͌��������i���_���r�₦���j�悤�Ȃ̂ŁA�s�����w���������i�ƈ�ʓI�Șb�����܂��B
�ʐ^�̉掿�̗D��́A�ǂ̂悤�Ɍ��܂�ł��傤���B
���̏ꍇ�́u�掿�v�Ƃ́A�ő���I�ȁA���R�Ɨ����\�ȈӖ��ō\��Ȃ��Ǝv���܂��B
�J��������Y�Ȃǂ̎B�e�@�킳���D��Ă���A�K���D�G�ȉ掿�̎ʐ^���B���ł��傤���B
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB
�����@��ł��A�����Z�p�͂����B�e�҂̂ق�����ʓI�ɂ��ǂ��掿�邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�ł͍����Z�p�͂�������A�K���ǂ��掿����ł��傤���B
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB
�ǂ�ȂɋZ�p�����낤�ƁA�T�L���悩��R�X���X�P�ւ��L���C�ɎB�e����͕̂s�\�ł���A
�ԋ߂���R���p�N�g�J�����ŎB�e�����ق����͂邩�ɗǂ��掿�ɂȂ�Ɍ��܂��Ă��܂��B
�ł́A�D�G�ȋ@��ƍ����Z�p�ƗǍD�ȏ����������낦�A�K���D�G�ȉ掿�邱�Ƃ��ł���ł��傤���B
������Ȃ��ł��ˁB
�掿�̗D������߂�̂́A�J�����}���ł͂Ȃ��ʐ^������l�ł��B
�ʐ^�̌|�p�����i���Ƃ������]���ɂƂǂ܂炸�A�掿�̗D�����A����l����ł��B
�Ȃ��Ȃ�A�ʐ^�`�Ƃa���r����ۂ́A�`�Ƃa�̈Ⴄ�Ƃ���⓯���Ƃ�����ׂ��������グ��̂��Ȋw�ł����āA
���̗D��f�ł���̂͐l�Ԃ�����ł��B
�Ȋw�͌����I�ɗD��i���l�j��ł��܂���B�����Ȋw�Ŕ��f�ł���D����Ƃ���A
����́A�l�Ԃ����ӓI�ɗp�ӂ��������v���O�������^�p��������ɉ߂��܂���B
�����Ŗ����ׂ��͎�������̌��ʂł͂Ȃ��A�v���O�������̂̑Ó����ł��B
���܂œW�J���ꂽ�e�l��B���ʂ̘b�́A������݂���掿�v���̒��̂����ꕔ�A
�{���ɂق�̈ꕔ�݂̂Ɋւ���l�@�ł��B
����������A���̉掿�v�����̏ۂ����ꍇ�Ɍ���A�傫�ȈӖ�������܂��B
�����I�ɂ́ADxoMark��ImageResources�Ȃǂ̓���ȃe�X�g���ł����A�ł��L���ȉ��l�ł��B
���_�A���������l�@��ے肷��K�v�͂���܂���B
�����A���Ȃ��Ƃ������I�ɂ݂�A�B�e�̋Z�p�������я������A
�Ȃ�тɊӏ܂̋Z�p�������я��������X�̉掿�v���̕ϓ����̂ق����A
�B�e�@��ɂ��s�g�����掿�ւ̉e���̕ϓ�����傫�������Ă��邱�Ƃ́A�e�Ղɑz�������ł��傤�B
���������āA�@��̗D��ɂ��掿�̗D������ۂ́A���̂��Ƃ��̌��E���킫�܂��Ă����̂������ł��B
���������킫�܂�������A�k�J�Ƃ����ĂׂȂ�����͂Ȃ�������������܂���B
�����ԍ��F10312956
![]() 12�_
12�_
���鐯���߂�l�B
���t�B�����̘I�o�v�Z�ƁA�ʐ^�̖��Ái�����掿�j�����������̂ł��ˁB
���t�B�����̘I�o�v�Z�������ł��A�ʐ^�S�̂̊����掿�ƒ��ڌ��т܂���B
�u�ʐ^�S�̂̊����掿�v�Ƃ͂ǂ�Ȍ��ۂł��傤��!?�@�܂��V�����T�O�̓o��ł����H
�V�����T�O�ɂ͒��߂����Ă����Ȃ��ƍ���܂��B
�����ԍ��F10313802
![]() 8�_
8�_
���s�̂�������l�B
���R�Q�W�̃����Y�����l��������Ȃ��ł��傤�ˁB
���ƌ��������A�傫���t�H�[�}�b�g�ɉ掿�ʂł̗D�ʐ��������Ȃ�܂��B
��L�̎咣�ʂ�Ȃ�A�唻�j�b�R�[��300mmF8��A�唻�t�W�m��300mmF8.5�̉掿�͍ň��Ƃ������Ƃł��傤���H
�傫���t�H�[�}�b�g�ňÂ������Y���Ɖ掿�ʂł̗D�ʐ��������̂ł��傤���H
���̎咣�ʂ�Ȃ�A�≖���[�W�t�H�[�}�b�g160�N�̎��т����ׂăE�\�A�ڂ̍��o�A�C�̂����ɂȂ��Ă��܂��܂���!!
�����ԍ��F10313867
![]() 6�_
6�_
���낯�ނ�����
������ƑO�ɂ��̃X���Ŏ������鐯���߂炳��ɂ�������̉ł́A
�R���f�W�ł��t�H�[�T�[�Y�ł��t���T�C�Y�ł������u�掿�v�̎ʐ^���B��邻���ł���`
������ƍi����ISO���x������Έꏏ�Ȃ�ł����āB
�ˁ`
���鐯���߂炳���
�t���T�C�Y�����Ȃ�Ă������������Ȃ��ł��ˁ`�B
�����ԍ��F10314528
![]() 6�_
6�_
�r�r�X�X�X����
�@���Ȃ����ԈႢ�ł͂���܂���w
�@�������A35mm�t���T�C�Y���ŁA�u���ʂ��Ӗ����Ȃ����ʂɂ�������v �ōl����ł��B
�P�D�Y�[�������Y�Ɂ`
�Q�DND8 + ND4 �t�B���^�[�Q���d�� �܂��� ND8 + ND8 �t�B���^�[�Q���d�˂��ā`
�R�D���邢�Ƃ���ł� ISO3200 �ȏ�ŎB�e����`
�@�M���̂T�c�U���A�R���f�W���o����w
�����ԍ��F10314767
![]() 3�_
3�_
�R���f�W�`���[���A�b�v�̂T�c�U�I
�R���f�W���o�ŋC�y�Ɏ������������b����ꂻ���ł�(��)
�����ԍ��F10315015
![]() 5�_
5�_
�� �V�����T�O�ɂ͒��߂����Ă����Ȃ��ƍ���܂��B
�ʐ^�̉掿�Ƃ����ł��ǂ��̂ł����A�����Y�̎����Ȃǂł͂Ȃ��A
���ʂɊW����掿�i�g�����x�掿�h�̉掿�Ɠ����Ӗ��j�̂��Ƃ����肵�������ł��B
�≖�̎����A�����t�B�����A�����I�o�ݒ���g���Ďʐ^���B���Ă��A
�W���ʐς̑傫�����i�唻 �� ���� �� 135 �� 110�j���掿�������Ɨǂ��m���܂�����ˁB
�܂������Y�̎����ɂ��Ă̓I�����p�X����2000����f�ȏ�͌������Ƌ��Ă܂�����A
ZD�����Y�̐��\���������ς����Ă����E�������Ȃ��Ƃ̂��Ƃł��ˁB����͗]�k�ł����B
�����ԍ��F10315710
![]() 0�_
0�_
[10312142]
>�傫���Z���T�[�̃J�����Ƃ���p�����Y�����l�ɂ́A����Ȃ��u�Z���T�[�T�C�Y���傫���v�Ƃ����掿�ʂ̗D�ʐ����t���Ă��܂�����
������Ȋw���Ă����ł��傤�ɁB
>>�������u���邳�v�́u�P�ʃ��j�b�g������̌����v�ƒ�`���Ă��܂��B
>�܂��V�����u���邳�v�ł��ˁB^^;
�ȑO�ɏ��������Ƃł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9719097/#9914578
F�l�@�@:=�����Y�L���a�^�œ_����
���ZF�l:=�����Y�L���a�^���Z�œ_����
����Œ�`�A�ł�����ł����A�����܂ł� F�l�͑��ʏƓx�����߂��ۂɏo�Ă����ϐ��ł��B�{���́u�����̑傫���Ɋւ�炸���ʏƓx�ɂ����w�n�̖��邳��]�����悤�v�Ƃ����v�z���琶�܂ꂽ���̂��Ƃ������ƁB����ɂ��iF�l���Łj�Y�[���A�b�v���Ă��t�@�C���_�[���̖��邳���ς��Ȃ��A�Ȃǂ̃����b�g�����܂�܂��B
����ɑ����ZF�l�́A�t�H�[�}�b�g�ňقȂ郌���Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ��]�����Ȃ����A�Ƃ����̂����{�v�z�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�iF�l���Łj�����Y���̑傫���ɂ���ĕς����́A����́u�����v�ł��B�u�����������Y�̖��邳�Ƃ��ĕ]�����悤�v�Ƃ������{�v�z������Ƃ������Ƃł��B����ɂ���āA�قȂ�t�H�[�}�b�g�ł̌��V���b�g�m�C�Y������ɂȂ�A�Ƃ��������b�g�����܂�܂��B
�����ԍ��F10315920
![]() 0�_
0�_
[10312595]
>F�l�Ƃ͒P�ʖʐς�����̌��ʂł���
�ׂ������ƌ����u�����v�ł��ˁB
>�����Y��F�l�Ƃ́@�t�B������t�H�g�Z���T�[�̎���ʂɓ����������_�ł̌��ʂł���@���̌��f�s�b�`���قȂ낤�Ɓ@����̓t�H�g�Z���T�[�̖��ׁ̈@F�l�Ƃ͊W�����͂��ł��B
�u�����Y��F�l�Ƃ́@�t�B������t�H�g�Z���T�[�̎���ʂɓ����������_�ł́g�Ɠx�h�ł���v
�ł��ˁB
�㔼�͐��ɂ��̂Ƃ���ŁA�uF�l�ɂ͉�ʂ̑傫���̊T�O�����݂��Ȃ��v�ł��B
F�l�Ɂu�����Y���̑傫���̈Ⴂ���z��������v�T�O��t�����������̂��u���ZF�l�v�ƌ����܂��B
>�t�H�g�Z���T�[�Ɍ��������������_�Ł@������d�C�M���ɕς���Ă��܂��ׁ@�d�C�M�����@���邢�E�Â��ƌ����̂��ςȘb�ł͖����ł��傤��
�d�C�M���́u���G�l���M�[�̌v�����ʁv�ł��B���ZF�l�́i�P�ʃ��j�b�g������́j�����𖾂邢�Â��ƌ����B�I�o�̌��ʁA���ʂ̌v�����ʂ𖾂邢�Â��ƌ����B�ʂɕςƂ͎v���܂���B
�����ԍ��F10315975
![]() 0�_
0�_
[10313867]
>��L�̎咣�ʂ�Ȃ�A�唻�j�b�R�[��300mmF8��A�唻�t�W�m��300mmF8.5�̉掿�͍ň��Ƃ������Ƃł��傤���H
>�傫���t�H�[�}�b�g�ňÂ������Y���Ɖ掿�ʂł̗D�ʐ��������̂ł��傤���H
�傫���t�H�[�}�b�g�ňÂ������Y���ƁA�������t�H�[�}�b�g�Ŗ��邢�����Y�i���ZF�l�͓����j�ɑ��āA�掿�ʂł̗D�ʐ��͂���܂���B
���̑O�� [10312832]
>�����̌f���̎�|�̓����Y�ɂ��Ăł���A�Z���T�[���\�ł͂���܂����ˁB
�u���ZF�l�v�̓����Y�ɂ��Ă̂��̂ł��B�Z���T�[���\�͖{���͊W����܂���B
��́u�掿�ʂł̗D�ʐ��͂���܂���v�������Y�ɂ��Ă̂��̂ł��B
�i�������������Y�ŃC�[�u���ɂ����̂Ɂj���ۂ̎B���ɂ����Ă̓C�[�u���ȏ����ł͂Ȃ��ꍇ������̂ŁA���̌��ʂ͂��ꂼ��ł��B
�Ⴆ�A�t���T�C�Y�� ISO100 �͂���ǁA�t�H�[�T�[�Y�Ɋ��ZISO100 �͂���܂���B
�Ȃ��u�掿���ň��v���ǂ����͂����g�Ŕ��f���������B
�����ԍ��F10316014
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������l�B
���uF�l�ɂ͉�ʂ̑傫���̊T�O�����݂��Ȃ��v
�����͈Ⴂ�܂���B�@�e�l�̓C���[�W�T�[�N�����ň��ł����ăt���T�C�Y�̃Z���T�[�Ƀt�H�T�C�Y�̃����Y��t����Ǝ���ɂ͌��������炸�@�P�����Ă��܂��܂��B
�����ԍ��F10316203
![]() 1�_
1�_
�� �ŋ߂悭�A�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�͂Q�i�Â��v�u�Â�����掿�������v
�� �Ƃ����咣������A����ɑ��ċc�_���������邱�Ƃ�ڂɂ��Ă���܂����A
���_�́g�掿�������h�ł͂Ȃ��g�Â�����h�ł����A
�Â�����掿�������ƁA�Â��Ȃ�����掿�������ƌ��������ăX��������ȂɐL�тĂ��ʔ����ł��ˁB
�����ԍ��F10316299
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>�u���邳�v�́u�P�ʃ��j�b�g������̌����v�ƒ�`���Ă��܂��B
�P�ʃ��j�b�g�H�@�P�ʒP�ʁH�@�u���j�b�g���P�ʁv�ł��B�@
�ǂ��̉��̌����������Ă���̂��A�����`���Ă���̂��s���ł��B
>�t�H�[�}�b�g�ňقȂ郌���Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ��]�����Ȃ����A
�����Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ�Ƃ́H
���邳��F�l�������Ȃ�A���̑傫���ɂ�����炸�������邳�ɂȂ�̂ł����B
���̃T�C�Y���傫�����Ƃ��u���邢�v�Ƃ����̂͒N�ɂ��ʂ��܂���B
�N�ɂ��ʂ��Ȃ����[�J���ȍ����Ŕ��_���Ȃ��ł��������ˁB
>����ɂ��iF�l���Łj�Y�[���A�b�v���Ă��t�@�C���_�[���̖��邳���ς��Ȃ��A�Ȃǂ̃����b�g�����܂�܂��B
����������Ȃ�
�uF�l���ŃY�[���A�b�v���Ă��œ_���̖��邳�i���ʏƓx�j���ς��Ȃ��v�ł��傤�B
�ł��d�v�Ȃ̂͑��ʏƓx��m�邱�ƂŁA����͘I�o����Ɍ��������Ƃ��o���܂���B
�t�@�C���_�[�̖��邳���ς��Ȃ��͕̂����I�ȃ����b�g�ɂ��������܂���B
�i�t�@�C���_�[�̖��邳���ς���Ă�����قǍ���܂���j
�Ƃ���ŁA���s�̂�������͂ǂ�����ĘI�o���肵�Ă���̂ł����H
>�iF�l���Łj�����Y���̑傫���ɂ���ĕς����́A����́u�����v�ł��B�u�����������Y�̖��邳�Ƃ��ĕ]�����悤�v�Ƃ������{�v�z������Ƃ������Ƃł��B[10315920]
>>F�l�Ƃ͒P�ʖʐς�����̌��ʂł���
>�ׂ������ƌ����u�����v�ł��ˁB[10315975]
[10315920]�ł́AF�l���ł����̑傫���ɂ���Č������ς��A�ƌ����A
[10315975]�ł́AF�l�Ƃ͌����̂��ƁA�ƌ����Ă��܂��B
��������邱�Ƃɐ�����������܂���B
>���ZF�l�́A�t�H�[�}�b�g�ňقȂ郌���Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ��]�����Ȃ����A�Ƃ����̂����{�v�z�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�i�����j����ɂ���āA�قȂ�t�H�[�}�b�g�ł̌��V���b�g�m�C�Y������ɂȂ�A�Ƃ��������b�g�����܂�܂��B[10315920]
>�u���ZF�l�v�̓����Y�ɂ��Ă̂��̂ł��B�Z���T�[���\�͖{���͊W����܂���B[10316014]
���������������邱�Ƃɐ�����������܂���B
����ɏ�̕��̏������݂ɂ��A���낢�떵���_���U������܂����A�Ƃ肠�����ȗ��B
�����ԍ��F10316326
![]() 4�_
4�_
���鐯���߂�l
���W���ʐς̑傫�����i�唻 �� ���� �� 135 �� 110�j���掿�������Ɨǂ��m���܂������
�@����́@�����P�ɉ�ʃT�C�Y�̑傫���̈Ⴂ�ł͖����̂ł��傤���H
�����ԍ��F10316345
![]() 4�_
4�_
���鐯���߂炳��
>�t�B�����̘I�o�v�Z�ƁA�ʐ^�̖��Ái�����掿�j�����������̂ł��ˁB
2009/10/15 11:58�@[10312881]
�������Ă�̂͒N�ł����H
���鐯���߂炳��͂�����ꔲ���ŏ������̂ŁA��������邱�Ƃ��킩��Â炢�ł��B
>>�V�����T�O�ɂ͒��߂����Ă����Ȃ��ƍ���܂��B
>�ʐ^�̉掿�Ƃ����ł��ǂ��̂ł����A�����Y�̎����Ȃǂł͂Ȃ��A
>���ʂɊW����掿�i�g�����x�掿�h�̉掿�Ɠ����Ӗ��j�̂��Ƃ����肵�������ł��B
�����ł�����A�ŏ�����u�����x�掿�v�Ə��������̂ł́B
>�W���ʐς̑傫�����i�唻 �� ���� �� 135 �� 110�j���掿�������Ɨǂ��m���܂�����ˁB
�u�W���ʐρv�ł͂Ȃ��A�P�Ɂu�摜�̖ʐρv�ł��ˁB
�t�B�������W�����Ă���̂͂���܂���B
>���_�́g�掿�������h�ł͂Ȃ��g�Â�����h�ł����A
�Â�����掿�������ƁA�Â��Ȃ�����掿�������ƌ��������ăX��������ȂɐL�тĂ��ʔ����ł��ˁB
���l���̂悤�ł��˂��B
�����ԍ��F10316399
![]() 7�_
7�_
�����ʐςł��ǂ��Ǝv���܂����A�������W����̂���ڂł��ˁB
����͊��܂̓h�z�ʐςƋ�ʂ��邽�߂ł����A�����t�B�����E�Z���T�[�ł�
�������Ȃ������A�n�[�t�T�C�Y�͔��������������Ȃ��̂ł����A�͊W�Ȃ��ł��B
�t�B�������A�Z���T�[�������W���̂��߂̓���ł����A���̏W���ʐς��L�����̂́A
����EV�l�ł́A��葽���̌��G�l���M�[�����W�ł��A�掿���ǂ��킯�ł���܂��B
�ʐ^�͌��G�l���M�[�̋L�^�Ƃ�����{���m�肷��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10316468
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�W������������̂̓����Y�̖�ځB
�����������̏����L�^����A���邢�͋L�^�o����M���ɕϊ�����̂��t�B������Z���T�[�̖�ڂł��B
�t�B������Z���T�[���u�W������v�ƍl���邩��A�傫���t�H�[�}�b�g�̕����u���邢�v�Ǝv���Ă��܂��悤�ł��ˁB
�������Ԉ���Ă��܂��B
�܂������A���܂ł��s�тȂ������J��Ԃ������Ȃ��̂ł�����ǁc
�����ԍ��F10316483
![]() 8�_
8�_
�ܘ_�����Y�̌��a���厖�ł����A�Z���T�[�̖ʐς��厖�ł��B
�����Y�͕K���Z���T�[�̑傫�����l���Đv���܂����A
�Z���T�[�̑傫�����ς�����A�v�ʂ�̐��\�ɂȂ�܂���B
�ǂ������K�v�����ł��i�ǂ������\�������ł͂���܂���j�B
�����ԍ��F10316523
![]() 0�_
0�_
�ǂ��������Ԃ̂������Y�̎d���B
���̑������ɋL�^����̂��Z���T�[�ȍ~�̓d�q��H�̎d���B
�u���邳�v�͑O�ҁi�����Y�ł���j�̎d���̈ꕔ�ŁA
�m�C�Y�����͌�ҁi�Z���T�[�ȍ~�ł�����ˁj�̎d���̈ꕔ�ł��B
�������Ă͂����܂���B
�����ԍ��F10316541
![]() 5�_
5�_
>http://wwwsoc.nii.ac.jp/spstj2/syashin-teigi.htm
�ʐ^�̒�`�ł��ˁH
>�u�ʐ^�Ƃ́A���A���ː��A���q���A�M�Ȃǂ̃G�l���M�[�����w�I���邢�͕����I��@�ő����A���o�I�Ɏ��ʂł���摜�Ƃ��ċL�^�E�ۑ����\�������@����т��̉摜�ƒ�`����B�v
�������٘_�͂���܂���B
�u�W������������̂̓����Y�̖�ځB�����������̏����L�^����A���邢�͋L�^�o����M���ɕϊ�����̂��t�B������Z���T�[�̖�ځv
�u�ǂ��������Ԃ̂������Y�̎d���B���̑������ɋL�^����̂��Z���T�[�ȍ~�̓d�q��H�̎d���B�v
�����͖����Ǝv���܂����B
�u���A���ː��A���q���A�M�Ȃǂ̃G�l���M�[�����w�I���邢�͕����I��@�ő����A�v
�@�@�@�@�@��
�u�����Y����ʑ̂��t�B������Z���T�[�Ŏ������v
�u���o�I�Ɏ��ʂł���摜�Ƃ��ċL�^�E�ۑ����\������v
�@�@�@�@�@��
�u�t�B������Z���T�[������������̏����L�^����A���邢�͋L�^�o����M���ɕϊ�����v
�٘_������܂����H
�����ԍ��F10316573
![]() 2�_
2�_
���݂܂���A���ȕs���ł����B
�u���A���ː��A���q���A�M�Ȃǂ̃G�l���M�[�����w�I���邢�͕����I��@�ő����A�v
�@�@�@�@�@��
�u�����Y����ʑ̂��t�B������Z���T�[�\�ʂɌ������A����������v
�u���o�I�Ɏ��ʂł���摜�Ƃ��ċL�^�E�ۑ����\������v
�@�@�@�@�@��
�u�t�B������Z���T�[�������������̏����L�^����A���邢�͋L�^�o����M���ɕϊ����A�ۑ��E�\������v
�ɒ������܂��B
�����ԍ��F10316585
![]() 2�_
2�_
���鐯���߂�l
���Z���T�[�̑傫�����ς�����A�v�ʂ�̐��\�ɂȂ�܂���B
����́@�����Y�̖��ł͂Ȃ��@�t�H�g�Z���T�[�̖�肶��Ȃ��ł����H
�@�����C���[�W�T�[�N�����ł̃Z���T�[�̑傫���̈Ⴂ�ł��̂Ł@F�l�ς��Ȃ��͂��ł�����B
�����ԍ��F10316602
![]() 4�_
4�_
�� ����́@�����P�ɉ�ʃT�C�Y�̑傫���̈Ⴂ�ł͖����̂ł��傤���H
��ʃT�C�Y�i�����ʐρj�̑傫���̈Ⴂ�ł́A�ǂ��ʐ^�̉掿���e������̂��ł��ˁB
����������G�l���M�[�̗ʁA�G�̋�̗ʂ��Ⴄ����ƌ����܂����A���̈�̗v�f�ŁA
�����ʐςƉ掿��A�����L�����Ɖ掿�ȂǁA��������̌��ۂ��ȒP�ɐ����ł��܂��B
�����ԍ��F10316609
![]() 0�_
0�_
�� �����C���[�W�T�[�N�����ł̃Z���T�[�̑傫���̈Ⴂ�ł��̂Ł@F�l�ς��Ȃ��͂��ł�����B
�Z���T�[�̑傫�����ς��Ă��A�œ_�������AF�l���ς�܂���B
��������p���掿���ς�܂��B���̉�p�Ɖ掿���ǂ��ς邩�ƌ����܂��ƁE�E�E�ł��ˁB
�� ����́@�����Y�̖��ł͂Ȃ��@�t�H�g�Z���T�[�̖�肶��Ȃ��ł����H
����͌����������Ƃł��B�����Y�����ł��A�Z���T�[�����ł��ƍقł��܂���B
���R������V�c�ɂȂ�܂��A��������{���R�ɂȂ�܂���B
4/3�Z���T�[�͊m���ɖʐς��������ł����A�ʐς����ł͑S�Ă����߂邱�Ƃ��ł��܂���B
��iF�l�̑傫�ȃ����Y������A������4/3�ł��A35�~�����Ɛ��ʑΌ��ł��܂��B
��iF�l�̑傫�ȃ����Y�Ƃ́A���a�������ł�����A�����y�U�ŕ����鉽���͂��܂���B
�����ԍ��F10316615
![]() 0�_
0�_
�� ��iF�l�̑傫�ȃ����Y
���a���傫���AF�l���������ł��ˁB���i�I�j��
�����ԍ��F10316621
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂�l
���Z���T�[�̑傫�����ς��Ă��A�œ_�������AF�l���ς�܂���B
�@���ꂾ���@������������\�ł��B
��������́@�t�H�[�T�C�Y�ł��@�t���T�C�Y�ł�4×5�ł��@�����I�o�Ŏʐ^���B��܂��B
�@�掿�̕��́@�@�ނ̏d����@�@�������l���Ȃ���t�H�[�}�b�g�̃T�C�Y�i�掿�j�����߂�̂ŋC�ɂ��Ȃ��ʼn������B
�����ԍ��F10316645
![]() 11�_
11�_
���s�̂�������
>������Ȋw���Ă����ł��傤�ɁB
�͂��A�Ȋw�ł����B
�Ȋw�̃C���[�W�Ƃ����̂��l���ꂼ��ł����A���Ƃ��ẮA�V���v���Ɋ��Z�Ȃ��̕��ʂ̌��w��H�w�̐����̕����D���ł��ˁB�v�Z���ȒP�ɏo���܂����B
�����I�`���Ƃ��āu���Z�v�Ƃ����͖̂����ł��傤�B���w�n�̃T�C�Y���ς���Ă��܂��ƌ��̌��w�n�Ɠ��������ɂ͂Ȃ�܂���B���s�̂�������̋ߎ��͈̔͂ł͍����̂�������܂��A����͋ߎ����r���������Ǝv���܂���B
����ƁA���ZF�l���P�ʃ��j�b�g�E�Z��������̖��邳�̕ϐ��A�Ƃ����̂��ςȘb�ŁA����ł͎B���f�q�̉�f�s�b�`���ς��Ɗ��ZF�l���ς���Ă��܂��܂��B
���ZF�l�Ƃ͂�����Ɨ���āA��{�ɖ߂�ƁA
�掿�͕���N�����x�N�g���ŕ\�����̂ɑ��A���s�̂�������̓X�J���[�ʂŕ\�����Ƃ��Ă���̂ŁA�����̐l�ɗ�������Ȃ��B
�ȂǂƏ����ƉȊw�u���ۂ��v���Ȃ��B^^;
�����ԍ��F10316960
![]() 6�_
6�_
���Z���T�[�̑傫�����ς��Ă��A�œ_�������AF�l���ς�܂���B
���ʔF���ɂȂ�܂����ˁB
�≖����ɂ͂���Ș_�����炠��܂���ł������A���̐��̒��͕��G�ł��B
�����ԍ��F10317275
![]() 7�_
7�_
�� �@�ނ̏d����@�@�������l���Ȃ���
�ʐ^�̐��\�������^�y�ʂ��D�悳���ꍇ������܂��ˁB�R���f�W�͂����ł��B
�g���[�h�I�t���l������A�ǂ̃t�H�[�}�b�g���卷���Ȃ��Ƒ���F�l�������Ă���܂����A
4/3��������̂��߁i����̓Z���T�[������������ł͂Ȃ��A4/3�v�̖��j�A
ZD35-70/2.0��AZD14-35/2.0�̂悤�Ȕ��Ɍ������̈������̂������Ă��A
���^�y�ʂ̗��v�ȏ�A���\�̑������傫���Ƃ��v���܂��B
�����ԍ��F10317306
![]() 0�_
0�_
�͂炽�����Tranquility����̔S�苭�������ɒE�X�ł��B
�����Ԃ����l�ł����B
����ł�����x�Ɓu�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�̓t���T�C�Y���Â��v�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F10317328
![]() 6�_
6�_
�� ���ʔF���ɂȂ�܂����ˁB
�œ_�������AF�l���ς�܂���̂ɁA�B�����ʐ^���傫���ς�܂��B
�œ_������AF�l�ł͐����ł��Ȃ����ۂŁA���̌��E�̔F���ƁA�{���̌����ւ̋������Ȃ��ł��傤���H
F�l�Ƃ������l�������ł���A�ʐ^���ǂ��Ȃ邩�W�Ȃ���l�����܂����B
�����ԍ��F10317331
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
�ŋ߁A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�Ƃ��������Ĉ�ʃ��[�U�[�ɍD�]�ȃt�H�[�T�[�Y�w�c�������܂�����ł���ˁB
�킩��܂��B
�M���̗��_�ɂ��ƁA���ꂾ�����^�Ȃ̂ɉ掿���t���T�C�Y�̂Q�i�����ς��Ȃ���ł�����ˁB
�����ԍ��F10317363
![]() 5�_
5�_
���鐯���߂�l�B
����ʃT�C�Y�i�����ʐρj�̑傫���̈Ⴂ�ł́A�ǂ��ʐ^�̉掿���e������̂��ł��ˁB
������������G�l���M�[�̗ʁA�G�̋�̗ʂ��Ⴄ����ƌ����܂����A���̈�̗v�f�ŁA
�������ʐςƉ掿��A�����L�����Ɖ掿�ȂǁA��������̌��ۂ��ȒP�ɐ����ł��܂��B
�Ƃ���������Ă��܂����A�ȑOE-P1�ł̓����b��ł́A���L�̎咣������Ă��܂�����B
�����̃J������A�t�B�����̃T�C�Y�A�g�嗦�͈�،���K�v�Ȃ��A�����ʐ^�ɂ��Ĕ�r����Ηǂ��ł��B����ȊO�̘b�͂���܂���B�@�@2009/09/27�@17:55�m10222276�n
�����̓��e�ł��ˁB
�����ԍ��F10317398
![]() 4�_
4�_
�� �����̓��e�ł��ˁB
�ǂ����ł����H�g�����ʐ^�ɂ��Ĕ�r����Ηǂ��h�Ƃ͌��ʂł����A
�ŏI�I�Ɍ��ʂ��o���Ȃ���Αʖڂł��傤�BF�l���������ǂ����͕����܂���B
���̌��ʂ��Ⴄ���A���̐����̓G�l���M�[�ɂȂ�܂����B
�����ԍ��F10317481
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������l
�����@�t���T�C�Y�Ƀt���T�C�Y�p50mm F2��t���@�K���I�o�@ISO100�@1/60�@F5.6�̎�
�����@�t�H�[�T�C�Y�ɓ��������Y��t�� ISO100�@�P/60 �ɂ����ꍇ F�l�������ɂ���@�K���I�o�������܂����H
[10239977]
�@���̎��₵�����@
��F5.6 �ł��傤�B
[10244255]
�@�Ɠ����Ē����Ă��܂��̂Ł@�K���I�o�ɑ��Ă�F�l�́@�����l�����Ǝv���Ă��܂����@��낵�����ł��傤���H
�����ԍ��F10317506
![]() 4�_
4�_
���鐯���߂�l�B
�����^�y�ʂ̗��v�ȏ�A���\�̑������傫���Ƃ��v���܂��B
�@�掿�̐S�z���ĉ�����@���肪�Ƃ��������܂��B
�@�������@���@�f�P�ɃY�~�N����50����F�Q��t���@�g�p���Ă��܂���A4�܂łȂ�\����i�掿�Ƃ��Ďg�p�ł��܂��̂Ł@�����Ƃ��Ă��̉掿�͔[�����Ă��܂��B
�����ԍ��F10317540
![]() 7�_
7�_
�r�r�X�X�X����
���J�߂ɂ��������ċ��k�ł���
>����ł�����x�Ɓu�t�H�[�T�[�Y�̃����Y�̓t���T�C�Y���Â��v�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B
����A������ł��傤�B(���)
�������ZF�l�_�҂Ȃ�u�Â��v�Ɂu���Z�v�����āu���Z�Â��v�Ƃ���������Ŏ��ł��܂����A�ǂl���������ăX�����L�т�̂���Ԑl�����܂�����B
���Z�̖{���͎�ςɂ���܂����A���������Ȃ�^�_�ł����B
�����f������͗��_��m�C�Y�������Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��B ^^;
�����ԍ��F10317836
![]() 11�_
11�_
�R�c���`�� ���z�c�ꖇ�I
�����ԍ��F10318851
![]() 1�_
1�_
>�͂炽����
�����e�ł��B
�܂��A���̃X�^���X�ł������ZF�l�E�œ_�����̓{�P���p�Ȃǁu�摜�̐����v��
�ȒP�ɕ\���w�W�Ƃ��ĕ֗����ƍl���Ă��܂����A�u�Â��v�͕\���Ƃ��āu�H�v�ł��B
�ŁA�u���Z�Â��v��啪�O����\�������A�͂炽����ɓ��ӂ��Ă���܂��B
���̏�ł̋ꌾ�ł����A�A�A
���ZF�l�ɔ��̔����҂��������Q�`�R���O����̔������������\�ɐ����Ă܂��H
���ɁA[10317836]�ł�
�������f������͗��_��m�C�Y�������Ȃ�Ȃ��A�Ƃ��B ^^;
�ɂ͏����K�b�J�����܂����A�A�A
�����f�������炱���A�u����v�ɏ�炸�ɐa�m�I�Ȕ������J��Ԃ����Ŕ����҂̕i�i
���ۂ����̂ł́H
�ӌ��̑���͂����Ă��i�b�����ݍ���Ȃ��Ă��j�A�_���̑�����u�m�C�Y�v�Ȃǂƕ\��
���Ă��܂��ƁA�X���Ӗ��ɐL���u����v�Ƒ卷���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�܂��A����Ȃ��Ƃ������Ă��鎞�_�Ŏ����ǂ����Ǝv���Ă��܂����A�A�A
�����ԍ��F10319888
![]() 4�_
4�_
�� �K���I�o�ɑ��Ă�F�l�́@�����l�����Ǝv���Ă��܂����@��낵�����ł��傤���H
�g�K���I�o�h�ɂ͖�肪����܂��B�Ȃ��Ȃ�g�K���h�̑O��͐��ӂł���̂ł��B
�Ⴄ���x�̃t�B�������g�����Ɂg�K���h�ł��I�o���Ⴄ�ł��傤�B��ɂȂ�Ȃ��̂ł��B
�����t�B�������g������ǂ����ƌ����܂��ƁA����Ȃ�t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ�
����F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�œK���I�o�������܂��B���̏�Ԃł́A
4/3����i�Â��ƌ����܂��B�P�ʖʐς̌��ʂ������ł�����A�ʐϔ䂾���Â��Ȃ�܂��B
�ʐ^�̌��ʂ����Ă��A���̎���4/3�̉掿�́A35�~�����������V���b�^�[�X�s�[�h�ŁA
�i����i�i�����Ɠ����ɂȂ�܂��̂ŁA�����ƌ����܂��B�掿�����ł͂���܂���B
�ʐ^�Ƃ��ẮA��ʊE�[�x�i�{�P�j��A��܃{�P�������ɂȂ�܂��B
���̈Â��͌��t�̖{���̈Ӗ��ŁA�Â��ȊO���ł�����܂���B
�t�ɊF����ɂ������������̂ł����A�Â����ĉ��������ł����H�ǂ������Ȃ�̂ł����H
�����ԍ��F10320016
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��
>�œ_������AF�l�ł͐����ł��Ȃ����ۂŁA���̌��E�̔F���ƁA�{���̌����ւ̋������Ȃ��ł��傤���H
�u�{���́v�Ƃ����قǑ傰���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�P�ɎB���ʂ̖ʐς̈Ⴂ�ł��B
>�����t�B�������g������ǂ����ƌ����܂��ƁA����Ȃ�t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ�
����F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�œK���I�o�������܂��B���̏�Ԃł́A
4/3����i�Â��ƌ����܂��B�P�ʖʐς̌��ʂ������ł�����A�ʐϔ䂾���Â��Ȃ�܂��B
���̏�Ԃł�4/3�͓�i�Â��Ƃ͌����܂���B�P�ʖʐς̌��ʂ������ł�����A�ʐϔ�ɊW�Ȃ��������邳�ł��B
>���̈Â��͌��t�̖{���̈Ӗ��ŁA�Â��ȊO���ł�����܂���B
�Ⴂ�܂��B
�Ȃ��������邳�Ƃ����̂��A������x���̗��R�������܂��B
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ�A���̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��Ă��A�t�B�����Ɋ��������Ă��A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő������Ă��A�������邳�Ɋ������܂��B�v
�ЂƂЂƂ����ď����܂��B
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A���ړ���Ō��ē������邳�Ɍ�����v
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�B�����Ɋ��������ē������邳�Ɏʂ�v
�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő��������瓯�����邳�Ɍv���v
>�Â����ĉ��������ł����H�ǂ������Ȃ�̂ł����H
�u�Â��v�Ƃ������t�̎g�p�@���Ԉ���Ă���̂ł��B
�����ԍ��F10320270
![]() 6�_
6�_
�@�B�D�����n�l�Ԃ���
�������肳���Đ\����܂���B
�Ƃ������A���͐��l�N�q�ł͂���܂���̂ŁA�{��Ƃ��ɂ͓{��܂��B
���Ă��鐯���߂炳��Ɂu�Â��v�ɑւ��\�����˗������̂ł����A���̎��̂��鐯���߂炳��̉��u�K�N�v�ł����B�u�t�H�[�T�[�Y�̓t���T�C�Y�ɔ���K�N�v�Ȃ����ł��B
���͊킪�`�b�`���C�ł�����A�����{��܂���B^^;
������������A�{�点�悤�Ƃ��Ă���悤�Ȃ̂œ{���Č����Ă��邾���Ȃ̂����m��܂��ˁB^^;;
�����ԍ��F10320355
![]() 2�_
2�_
���B�܂��ڋ��� Tranquility���� �ł��ˁB
>�u�œ_�����ɂ�����炸����F�l�Ȃ炻�̃����Y�̍������́A�t�H�g�_�C�I�[�h�ő��������瓯�����邳�Ɍv���v
���̘b�� [10311822] �� [10311946] �Ō��������͂��ł��B
�����ԍ��F10320397
![]() 0�_
0�_
[10316203]
�C���[�W�T�[�N���̘b�͂��Ă��܂���B
�����ԍ��F10320419
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂�l�B
�t�H�[�}�b�g���傫�������掿���ǂ����́@�ے肵�Ă��܂���B
�@�����@�t�H�[�}�b�g�ɊW�Ȃ��@�V���b�^�[�ƍi��͓������ƌ�������������Ηǂ��Ǝv���Ă��܂��B
�@
�@�i��̉�܌��ۂ́@�R���f�W��t�H�T�C�Y�Ȃǃe�X�g���Č��܂����@�s�N�Z�����{�Ō���ƍi��قǏo�Ă��܂����@�����Ƃ��Ắ@A4��A3�Ƀv�����g�ɂ��Ă݂Ă����܂�C�ɂȂ�Ȃ����x�ł����B
�@��ʊE�[�x���@�t�H�[�T�C�Y��17mm��34mm�����̉�p�̃����Y�ł����@�����Y��17mm�̂܂ܔ�ʊE�[�x��17mm�̂܂܂ł��̂Ł@17mm�̃����Y�{�P�Ǝv���@����������Ƃ��Ă͋C�ɂȂ�܂���ł����B
�@�Ō�Ƀt�H�|�T�C�Y�̃Z���T�[�̓t�B�����Ō����Ɓ@110�T�C�Y�Ɠ����傫���Ȃ̂Ƀt���T�C�Y��APS�T�C�Y�ɑ��Ċ撣���Ă���Ǝv���܂��B
���낢�돑���܂���������͂���ōŌ�ɂ��܂��B
�����ԍ��F10320439
![]() 3�_
3�_
�c�O�Ȃ���A�����Y�̌��������Ō��Ă��d������܂���ˁB
�ʐ^���B���ł�����A�ʐ^�����Ȃ���Ύd���Ȃ��ł��傤�B
�ڂ̎d�g�݂͏����������Ă�Ǝv���܂����A�l�͐����ȍ�Ƃ����鎞�ɁA
��苭���Ɩ���K�v�Ƃ��܂��B�펯�ł��ˁB�܂薾�Â̊�͕ς��ł��B
��͂����܂ŁA���ꎫ���ɏ����Ă�悤�Ɂg�悭������h���ǂ����ł��B
�����Ɠx�ł���Ζ��邳�������Ǝv�����炻��͈Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F10320461
![]() 0�_
0�_
[10316326]
�P�ʃ��j�b�g�Ƃ́u�P�ʌn�̕ϊ��v�ł��B
>�����Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ�Ƃ́H
�����Y�����\����������̂��ƁB
>�uF�l���ŃY�[���A�b�v���Ă��œ_���̖��邳�i���ʏƓx�j���ς��Ȃ��v�ł��傤�B
����������Ȃ�ł����A���͌����ƏƓx�����������Ă���Ǝv���܂����B
�Ȃ��A�I�o������@�͂��ꂼ��ł��ˁB
>>>F�l�Ƃ͒P�ʖʐς�����̌��ʂł���
>>�ׂ������ƌ����u�����v�ł��ˁB[10315975]
����͗�����������
�ׂ������ƌ����uF�l�Ƃ͒P�ʖʐς�����̌����v�ł��ˁB
�ƂȂ�܂��B
>>���ZF�l�́A�t�H�[�}�b�g�ňقȂ郌���Y���T�C�Y�ɂ�閾�邳�̈Ⴂ��]�����Ȃ����A�Ƃ����̂����{�v�z�ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�i�����j����ɂ���āA�قȂ�t�H�[�}�b�g�ł̌��V���b�g�m�C�Y������ɂȂ�A�Ƃ��������b�g�����܂�܂��B[10315920]
>
>>�u���ZF�l�v�̓����Y�ɂ��Ă̂��̂ł��B�Z���T�[���\�͖{���͊W����܂���B[10316014]
�������͂���܂����H
���ZF�l�̓����Y�݂̂ł悢�̂ł��B
�u���ꂪ�掿�ɗ^����e���́H�v�ƕ������Ό��V���b�g�m�C�Y�̘b�ɂȂ�ƌ������ƁB
�ˍ��݂���Ŏ����ōl���Ȃ���Ή��ɂ��Ȃ�܂����B
�����ԍ��F10320479
![]() 0�_
0�_
1�̖��邳�Łu�Ƃ炳��Ă���v���̂�����4�����Ă����邳��4�{�ɂȂ�킯���Ȃ��B
�P��1�̖��邳�ŏƂ炳��Ă��镨�̂�4�ɑ����邾���ł���B
�\�[���[�p�l��1����4���ł͌�҂̕���4�{�̓d�͂����A����Ȃ��ɂ����4�{�̓d���������邪�A�c�O�Ȃ���t�B������Z���T�[�́g����h�Ȃ��Ȃ̂��B
���R�A�d���͕ω����Ȃ��B
���q���f�������͂��̗��q���f�������킯�ŁA1�l��炵��1���̔т�H�ׂĂ����Ƃ����4�l�ɑ�����4���̔т𐆂����Ƃ���ŁA1�l��4���H�ׂ���킯�ł͂Ȃ��̂Ɠ����ł���B
�����������̏��̊��Ⴂ�͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂��Ǝv���B
�����ԍ��F10320485
![]() 4�_
4�_
[10316960]
>�����I�`���Ƃ��āu���Z�v�Ƃ����͖̂����ł��傤�B���w�n�̃T�C�Y���ς���Ă��܂��ƌ��̌��w�n�Ɠ��������ɂ͂Ȃ�܂���B
��̓I�ɂǂ̓����ł��傤���H
���͑S�Ă̓�������v�Ƃ͎v���Ă��܂���B�����A����\�A���Ɣ�ʊE�[�x�ɂ��Ă͈�v���܂����B
>���ZF�l���P�ʃ��j�b�g�E�Z��������̖��邳�̕ϐ��A�Ƃ����̂��ςȘb�ŁA����ł͎B���f�q�̉�f�s�b�`���ς��Ɗ��ZF�l���ς���Ă��܂��܂��B
��f���ɂ��Ă͒������܂����B��f���͉�f���Ƃ����i���ZF�l�Ƃ͓Ɨ��́j�T�O�ł��B
�������u���̑傫���Ɩ��邳�̊W���v�͗��ғ��l�ɐ��藧���܂��B
�����ԍ��F10320515
![]() 0�_
0�_
�ʐ^�̔�r�͈�Έ�ł��B
�����ԍ��F10320533
![]() 0�_
0�_
[10317506]
���ƃ��{�}�� �Q���� �͓K���I�o�ɂ������܂��ˁB
�t�H�[�T�[�Y F4.0�ASS1/100�AISO100 ���K���I�o�Ƃ���A
�t���T�C�Y�@ F8.0�ASS1/100�AISO400 ���K���I�o�ł��B
�����ԍ��F10320550
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
>���̘b�� [10311822] �� [10311946] �Ō��������͂��ł��B
���Ă܂����B
��̏������݂Ŗ���������Ə������̂͂��̂��Ƃł��B
�����ɕԐM���Ȃ���������ڋ��҂Ȃ�ł����H
�������Ă���Ȃ�ɖZ�������̂ōς݂܂���ˁB
>�B���ʂɑ������镔�����i�~���[�Ȃǂ���āj���ړ���Ō���ꍇ�ɂ͂���ł悢�ł��B�t���T�C�Y�Ƃ͖��邳�͓����ʼn�ʂ̑傫�����Ⴄ�����B
�ʐ^�̏ꍇ�A��ʂ̑傫���̊�Ƃ����̂͑��݂��܂���B�傫������ΈÂ��Ȃ邵�A����������Ζ��邭�Ȃ�B
�t�B�����̏ꍇ�́u�������́v�Ȃ̂ŁA�u���邳�������ő傫�����Ⴄ�v�̊W���������グ�邱�ƂɑÓ����͂���܂����B
�f�W�J���̏ꍇ�͉�f�s�b�`���قȂ�̂ŁA�uF�l���Ŗ��邳�������v�͕K�������������܂���i�s�������قƂ�ǁj�B[10311946]
����ł́A���w�Z�Ŏ�������悤�ɃX���K���X�┒�����ɓ��e����킩��܂��ˁB
���l�̖ڂƔ�ׂ���킩��܂��A���Ȃ��Ƃ������̖ڂŌ���Ɠ������邳�Ɍ����܂��ˁB
���������悤�ɓ����t�B�������g���Γ������邳�Ŏʂ�܂��B
�������A���s�̂�������́A�Ȃ������Ńf�W�J��������f�s�b�`��ς���̂ł����H
�����Z���T�[���g���Γ������邳�Ɏʂ�͂��ł͂���܂��H
�f�W�J���łȂ��Ă��A�P�ɏƓx�v�ő������Ă������ł���H
���s�̂������A�f�W�J���̎������Z���T�[���Ⴄ���̂ɂ���̂��A�킩��܂���B
>�ʐ^�̏ꍇ�A��ʂ̑傫���̊�Ƃ����̂͑��݂��܂���B�傫������ΈÂ��Ȃ邵�A����������Ζ��邭�Ȃ�B
���������߂Ȃ���A�����������Ƃ͏o���܂���B
�Ⴆ�u�����Y�̗L���a��ς����ɏœ_������ς��鎞�v�Ƃ������悤�ɁB
���܂肻�̂悤�ȏ�ʂ͂Ȃ��Ǝv���܂����B
���鐯���߂炳��
>�����Ɠx�ł���Ζ��邳�������Ǝv�����炻��͈Ⴂ�܂��B
���̖ڂɂ́A�����Ɠx�ł���Γ������邳�Ɍ����܂��B
�����ԍ��F10320597
![]() 3�_
3�_
�� ���Ȃ��Ƃ������̖ڂŌ���Ɠ������邳�Ɍ����܂��ˁB
�� ���̖ڂɂ́A�����Ɠx�ł���Γ������邳�Ɍ����܂��B
����͏����I�ȃ~�X���Ǝv���܂����A4/3�̖ڂƁA35�~�����̖ځA�Ⴄ�ڂł��ˁB
�����Ɠx�ł��A�l�Ԃ��Èłʼn��������Ȃ��Ƃ���́A�L�����R���ݗV�ׂ܂��ˁB
�����ڂł��A����͈͂Ȃǂɂ���Ă͈Ⴂ�܂����A�Ǐ��ł��傫�Ȏ��ƍׂ������͈Ⴂ�܂��B
4/3�ׂ͍����ł����瓯���Ɠx�ł��ǂ������܂���B���ꎫ���ɎQ�Ƃ��܂��Ɛ��ɈÂ��ł��B
�����ԍ��F10320696
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂�l�B
�C�ɂȂ����̂Ł@�������������܂��B
���ڂ̎d�g�݂͏����������Ă�Ǝv���܂����A�l�͐����ȍ�Ƃ����鎞�ɁA
����苭���Ɩ���K�v�Ƃ��܂��B�펯�ł��ˁB�܂薾�Â̊�͕ς��ł��B
�������@�ڂɂ͓��E������@������������Ə������Ȃ�@�ア���̎��͊J���@�Ԗ��ɓ�����������ɂ��悤�Ƃ����ڂ�����Ǝv���܂��B
���s�̂�������
����́@����ISO���x��2�i�グ�����@�i���2�i�i���������ł���ˁB
�����ƃ��{�}�� �Q���� �͓K���I�o�ɂ������܂��ˁB
�@������O�ł��@�ʐ^���B��l�ł�����
�����ԍ��F10320748
![]() 6�_
6�_
���鐯���߂炳��
�������Ŏ������Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B
�����ԍ��F10320754
![]() 4�_
4�_
��̂ق������ǂ�ł܂��A�Ԃ��ʑ̂ɂ���Ȃ�R���f�W�ł��ǂ��Ǝv���܂��B
�t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̉掿���ׂ�Ȃ�A���i����Ȃ��Ɖ���Ȃ����������ł��B
���ɉԂł͈Ⴂ������ɂ����ł��B
���i�͖��������ł������҂̈Ⴂ������₷���ł��B
����ƁA�v�����^�[�ł͂Ȃ��A���j�^�[�Ŋg�債�Ă����E�E�E
�܂��ł��A�f�e�P�Ƃd�o�P�͂����ł��ˁB
���͓I�ȃJ�����ł��B
���A������B
�t���T�C�Y�̖��͂͐�ʊE�[�x���A�ȂǂƂ͑S���v���܂���B
�����͎��ہA�o���o���i��܂��B
�ꕔ�̃R�����g������ɁA�@�B�����Ȃǂ��Ďg���Ă�Ƃ͂����A�Ȃɂ����_���肫�I�ȕ��͋C�������܂��i�j
�����ԍ��F10320766
![]() 5�_
5�_
[10320597]
>�Ȃ������Ńf�W�J��������f�s�b�`��ς���̂ł����H
���邳��P�ʃ��j�b�g�̌����Ƃ��āA���邳�Ɖ�ʂ̑傫���ƃt�H�[�}�b�g�T�C�Y�̊W���o���܂�����ˁB�����ɒT���܂��B
�t�@�C���_�[�̏ꍇ�P�ʃ��j�b�g�Ƃ́i�~�����[�g���Ȃǂ̒P�ʂ�p�����j�P�ʖʐςł��B�f�W�J���摜�̏ꍇ�͒P�ʃ��j�b�g�͈��f�ł��B
�傫���̓t�@�C���_�[�̏ꍇ�t�@�C���_�[�ʐςł��i�~�����[�g���P�ʁj�B�f�W�J���摜�̏ꍇ�͉�f���ł��B
�傫������ΈÂ��Ȃ�A����������Ζ��邭�Ȃ�B�ǂ̑傫�����W���ȂǂƂ����K��͂���܂���B
�ʂɉ�f�s�b�`���t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɋւ�炸���ł������ł��B�L���m���� 5DMark�U �� E-1 �͓������邳�ł��ˁiE-1 �̕�������邢���j�B
>>�ʐ^�̏ꍇ�A��ʂ̑傫���̊�Ƃ����̂͑��݂��܂���B�傫������ΈÂ��Ȃ邵�A����������Ζ��邭�Ȃ�B
>���������߂Ȃ���A�����������Ƃ͏o���܂���B
���̘b�͌��X Tranquility���� �̕������o���ꂽ�A����F�l�̘b�ł��傤�B
�����ԍ��F10320830
![]() 0�_
0�_
[10320748]
�K���I�o�̒�`�������ق��������ł��B
�Ⴆ�uISO100 �ŃO���[�� 118 �̃��x���ɂȂ�v�Ƃ��B
�ŁA���X�́u���ZF�l�v�̘b�Ȃ̂ł�����A���̏�Ԃł̃t���T�C�Y�Ƃ̔�r�Ȃ�u��i�Â��v�ł��B�u���邳�v�͉��x�������悤�Ɂu�����v�ł��i�f�W�J���̘I���Ɋւ��Č����Ȃ�u���ʁv�j�B
�����ԍ��F10320844
![]() 0�_
0�_
�� �������Ŏ������Ă݂邱�Ƃ������߂��܂��B
���������Ȃ����Ƃ́A�������̃Z���t���Ǝv���܂��B
�ړI���Ȃ��A����Ȃ��A���ʂ����Ȃ��A����F�l�Ȃ瓯���i�����H�j�ςł��ˁB
�����ԍ��F10320851
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
��f�s�b�`�̘b�����Ă���̂ł͂���܂����B
���ʏƓx�̘b�����Ă���̂ł��B
�s���̂����悤�ɘb������ւ��Ȃ��ʼn������ˁB
�����Z���T�[���g���Γ������邳�Ɏʂ�͂��ł͂���܂��H
�f�W�J���łȂ��Ă��A�P�ɏƓx�v�ő������Ă������ł���H
���鐯���߂炳��
���s�̂�������
>���������Ȃ����Ƃ́A�������̃Z���t���Ǝv���܂��B
�u�Â��v�Ƃ������t�̎g����������l�i�����������瑼�ɂ��邩������܂��j�������ʂ̐l�ƈႢ�܂��B���̌��������Ă��������B
���t�́A�l�ɒʂ��Ȃ���ΈӖ��������܂���B
�����͑����̂ŁA�ڋ��Ǝv����������܂�����͂���ł����܂��ɂ��܂��B
�����̎d�����]���ɂ���킯�ɂ͂����܂���̂ŁB
�����ԍ��F10321031
![]() 4�_
4�_
Tranquility�l
�@�ʐ^���B��ƌ������Ƃ́@���˂�����Ǝ��ԂŌ��܂���̂ł���
�@���鐯���߂炳��⋞�s�̂��������́@�����P�ɓ��˂�������Z���T�[�ɓ����鎖�ɑ��ď������܂�Ă��邾���ׁ̈@�b������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�@����́@���˂�����Ǝ��ԁi�i��E�V���b�^�[�X�s�[�h�j�̎������͉����o�����Ǝv���܂��̂Ł@���̃X����莸�炳���Ă��������܂��B
�@���܂薳�������撣���Ă��������B
�@
�@�@
�����ԍ��F10321077
![]() 5�_
5�_
[10321031]
>�����Z���T�[���g���Γ������邳�Ɏʂ�͂��ł͂���܂��H
����͓��ӂ��Ă��܂����B�ǂ߂܂��H
>�u�Â��v�Ƃ������t�̎g����������l�i�����������瑼�ɂ��邩������܂��j�������ʂ̐l�ƈႢ�܂��B
����ɂ��Ă������Ə����Ă��܂����B
�����āA�킽���� Tranquility���� �́u�傫���𑵂������Ȃ��v�Ƃ̍l�������d���Ă��܂����B
�u�傫�������̂܂܁v���W���̈��ԁB�u�傫���𑵂���v���W���̈��ԁB�������������ł��܂��B
�����ԍ��F10321117
![]() 0�_
0�_
����ȗ��������邩��A����ȂɈÂ��A�̂悤�Șb������܂����A
�����Ȃ���4/3���Â��ł���ˁB�N�ł��m���Ă܂����A�Â����Ǝ��̂͑��_�Ƃ͎v���܂���B
�����āA4/3��ISO800�̉掿�́A35�~������3200��A6400�����Ƃ����ʂɌ����ł��傤�B
�l�ɕ�������A����O�i�̍�������ƌ����܂����A�܂�Ɉ�i�ƌ����l�����܂��B
���lj��i�ł����ƌ����܂��ƁA�����ʐς̍�����͓�i�Ǝ����������܂����A
�Â��Ȃ��Ƌ�l�ł��A�܂����[���i�Ƃ͌���Ȃ��ł��ˁB�����܂����H
�����ԍ��F10321263
![]() 0�_
0�_
���鐯����
���ǁA�ǂ��Ȃ���Ȃ��͖����Ȃ̂ł��傤���E�E�E�B
�����ԍ��F10321387
![]() 7�_
7�_
[10320515]
���s�̂�������
��̓I�ɁH
���Ƃ��A�����ƌĂ�郂�m�ł��ˁB
���s�̂�������͂��{�l�������I�ɏ����Ă��邯��ǁA���������Ă��܂��i������u�ߎ��͈̔͂ł͍����v�Ə����Ă��܂��̂ŁA�u�����̘b�͂��Ă܂���v�ȂǂƔ������Ȃ��ł��������ˁj
���������ߎ����A�ŏ��̒i�K�Ƃ��Ă͗ǂ�����ǁA���āA���̒i�K�Ƃ��āA�����Ǝ��R���ۂ��ׂ������ׂ悤�A������������悤���A�Ƃ���ƁA�͂��ƍ���B�͂��B������Z�����܂������l���Ă��ǂ��ł����A��ϖʓ|�ł��B�i�V�����ƈꏏ�ŁA�ϊ��ׂ̈̃p�����^���ׂ����������Ă����Ηǂ��j
�u���̒i�K�ɂ͍s���Ȃ����炩�܂Ȃ��v�Ƃ����ӌ������邩������܂��A�����ɂ͎����̖��������Y�͖����i�Ƃ�����茻���̌��ۂ̓��A�ȒP�Ɏ�舵���Ȃ������������ƌĂ�ł����ł����j�̂ŁA���i.COM�̂悤�ȏ��i�]���T�C�g�Ŏ��������̋ߎ��̗��_��U�������͔̂@���Ȃ��̂��Ǝv���܂���B
�Ⴆ�A�����̃����Y�ł���A300mmF2.8��300mm F4.0���ƁA�����w�͂ō������A�܂��ԈႢ����300mmF4.0�̕����ʂ肪�ǂ��ł��傤�B�u���邢�����̃����Y�v�Ȃ�Ă̂����X���邯��ǁA���������͈̂ꔭ�|�����獂���l�i�ł͔���Â炢�B
�ł������ɂ͖��邢�����Y�̕����ޗ���͍����Ȃ邩�獂���l�i�Ŕ��肽���B�ƂȂ�AF2.8�̕����㓙�ȍޗ��A�㓙�Ȑv�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��āA���邢�����Y�͍X�ɍ����Ȃ�킯�ł���ˁB
F�l�Ƀ����Y�̉掿����点�悤�Ƃ����͖̂����Șb�ł��B�s�̂���Ă��郌���Y�̉掿�ɂ͐l�ׂ����݂����Ă��܂��B
�����ԍ��F10322599
![]() 1�_
1�_
>�͂炽����
���Ƃ������A���͐��l�N�q�ł͂���܂���̂ŁA�{��Ƃ��ɂ͓{��܂��B
��������������A�{�点�悤�Ƃ��Ă���悤�Ȃ̂œ{���Č����Ă��邾���Ȃ̂����m��܂��ˁB^^;;
�܂��܂��S�ɗ]�T������\���Ȃ̂ň��S���܂����B
�����A�u�l�荇���v�ɔ��W����Ǝc�O���Ȃ��A�Ɗ����Ă��鎟��ł��B
�ŁA�{��ł����A
���ƃ��{�}�� �Q����[10321077]�Ŕ����Ȃ����Ă��܂����A
�W���\�͂̍��Łu���邢�v�u�Â��v��\�����邩�@�F���a�̑召�Ō��܂�i���ZF�l�j
�I�������̍��Łu���邢�v�u�Â��v��\�����邩�@�F�e�l�ő召�Ō��܂�
�œ����͕ς��܂���ˁB
�����g�́u�]���ϊ��v�œK���ɑΉ����Ă��܂��̂ŁA�����I�ɂ͑傫�Ȗ��͍݂�܂���B
�����A�����̐l���u������Ȃ��\���v�̕K�v���͊����Ă��܂��B
���[�J�[�ւ̗v���́A�t�H�[�}�b�g���Ⴆ�A�u�����Y�̏œ_�����EF�l�������ł��v�B���
�u�摜�̐����v���Ⴄ���Ƃ������Ɛ��m�ɕ\�����Ăق����Ǝv���܂��B
��������A�j�[�Y�ɍ��킹���t�H�[�}�b�g�̑I�����ȒP�ɂȂ邵�A�s�v�ȃt�H�[�}�b�g��
�̑Η��������Ȃ�̂ł́H�i�������A�����������Ė{���Ƀo�J�o�J�����ł���ˁB�j
���ZF�l���_�́A���[�J�[�����ڂ��Ă��镔����⊮���悤�ƍl���Ă̎����Ɗ����Ă��܂��B
���Ƃ́A�ǂݎ�̏�e���V�[����ł́H
�����ԍ��F10322779
![]() 0�_
0�_
�͂炽����A
���s�̂���Ă��郌���Y�̉掿�ɂ͐l�ׂ����݂����Ă��܂��B
�@���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
��F�l�Ƀ����Y�̉掿����点�悤�Ƃ����͖̂����Șb�ł��B
�@�����������āA�u�t�H�[�T�[�Y��14-35mm F2�̊J���ƃt���T�C�Y�� 24-70mm�� F4�ɍi�������́A���a�H����ӌ��ʒቺ�A�����͎��Ă���̂ł͂Ȃ����B�v�Ȃ�āE�E�E�E�B
�@�@�B�D�����n�l�� ����A
�����ZF�l���_�́A���[�J�[�����ڂ��Ă��镔����⊮���悤�ƍl���Ă̎����Ɗ����Ă��܂��B
�@���������C�����܂��B���[�J�[�Ƃ��ẮA�Ӑ}�I�ɂ����ɂ͐G�ꂽ���Ȃ��悤�Ȋ��������܂��B
�����ԍ��F10322946
![]() 0�_
0�_
�@�B�D�����n�l�Ԃ���
1-300����
���Z���֗��Ȃ̂͒m���Ă��܂��B
���Ȃ̂͋@�B�D�����n�l�Ԃ���̌����悤�ɕ\���̖�肾�Ƃ��v���܂��B
���ZF�l�ł͎ʐ^�p�̂Ȃ���F�l���g���Đ��������{�P�Ƃ���ʊE�[�x�Ƃ����낢��\���܂��B
����ǂ����Z�ɏ]��Ȃ�����������܂��B(F�l�ŕ\�����j�u���邳�v�͊��Z�ɂ͏]���܂���B���̏]��Ȃ��u���邳�v�ł킴�킴�\�����Â���Ƃ���ɋ����ӎu�������܂��B
���ꂪ
�u300�~��������F2.0�Ƃ�������傫�ȃ{�P�����҂���ZD150�~�������̂Ƀ{�P�Ȃ������v
�Ƃ����{��̓����Ȃ�ނ��냆�[�U�[��i�삷�邩���m��܂���B^^;
(�������A�œ_�����́u�����v�\�����폜������̂��AF�l�Ɂu�����v�\��������̂��͓����肾�Ǝv���܂��B���Ƃ��Ă͏œ_�����́u�����v���폜���邩�A���߂Ă����Ə��������ė~�����Ǝv���܂��B)
������x�n�����ƓV�����̗���o���܂����B�V�����Ɗ��ZF�l���_�́A���ɁA�u���ʂ̗��_�v���ϑ���̂̎�ςɏ]���ĕϊ����邾���œ�����̂ŁA�\���Ƃ��Ă͌��\���Ă��܂��B
���ZF�l���_�𐢊Ԃɒ����ۂ̔����́A�u�V�����𐳂����v�Ǝ咣�����ꍇ�Ɠ����������Ǝv���܂��B���Ԃ͌������ē��R�ł��B
�����u���z�͓����珸���Đ��ɒ��ށv�ƌ����Ă��N��������傪�o�Ȃ��悤�ɁA���ZF�l�֗̕��ȓ_������Ȃ�A�ʂ̕\���ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B
�Ԃ����Ⴏ�A�u���R�̐����v�Ɋ��ZF�l���g��Ȃ���Ηǂ���ł����ˁB
���ԓI�ɂ͊��Z�֗̕����͉�p�ɗ��p������x�Ɏ��܂��Ă��܂��B����ȏ�ׂ����������]�X��������Ε��ʂ̌��w���w�ׁA�Ƃ����̂����ʂȂ�Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F10323214
![]() 3�_
3�_
���lj��i�ł����A�ƌ����Q�i�ł����A���̗��R�͈Â�����ł͂Ȃ��A�Z���T�[������������ł��ˁB
�P�N�|���āA���������ꂾ���̂��Ƃ��ʂ��Ȃ��B
�������낻�남�ɂ��܂��ˁBm(_ _)m
�����ԍ��F10323484
![]() 5�_
5�_
�͂炽���� �ɂ́u��w�ŕ����v�̊Ŕ��~�낵�ė~�������̂ł��B�����Ă邱�������p���������Ȃ�̂ŁB
���邢�E�Â��ɂ��Ắu�����v�Ɖ��x�������Ă���̂ł����ˁB
�����ԍ��F10323541
![]() 2�_
2�_
1-300����
������������ǂ��ł��ǂ����Ƃ�������܂��A���a�H�͌ʐv�łƂĂ��ς�����Ⴄ����A���ZF�l�Œ��x�Ɍ������Ƃ�����A���R���A�v�҂����x�ɂ��킹�����̂ǂ��炩�ł��ˁB
���s�̂�������
���s�̂�������̏ꍇ�A���ʂ̐l�����邳�Ɗ����Ȃ����̂𖾂邳�Ǝ咣���Ă���_�ɓ��������܂��B�l�Ԃ̊����Ƃ̃Y���ł��ˁB
�����v����ő��肷��ꍇ�͑���l�́u�召�v�Ƃ��u����v�Ƃ������܂��ˁB�������ŕ\������X���̒����͐����k�܂�ł��傤�B
����ł́A���낻��{���ɂ��ɂ��܂��B���悤�Ȃ�B
�����ԍ��F10323703
![]() 8�_
8�_
�͂炽�����
�����ǂ�ŋ����Ȃ������m��܂��A
���u300�~��������F2.0�Ƃ�������傫�ȃ{�P�����҂���ZD150�~�������̂Ƀ{�P�Ȃ������v
���Ƃ����{��̓����Ȃ�ނ��냆�[�U�[��i�삷�邩���m��܂���B^^;
��(�������A�œ_�����́u�����v�\�����폜������̂��AF�l�Ɂu�����v�\��������̂��͓��
����肾�Ǝv���܂��B���Ƃ��Ă͏œ_�����́u�����v���폜���邩�A���߂Ă����Ə��������ė~�����Ǝv���܂��B)
�܂������A���ӂł��B
���������A�u��p�v���u�œ_�����v�ŕ\�������ɖ�肪����܂��B
�{���Ȃ�A�����u�����v�Ȃ�č폜���Ăق����ł��B
�����A�c�O�Ȃ���֗��Ȃ�ł���ˁA�A�A���̕\�L�Ɋ���Ă��܂��ƁB
�ł��A��ԗL�����p���Ă���̂̓��[�J�[�̐l���Ǝv���܂��B
�����ԓI�ɂ͊��Z�֗̕����͉�p�ɗ��p������x�Ɏ��܂��Ă��܂��B����ȏ�ׂ����������]�X���������
�����ʂ̌��w���w�ׁA�Ƃ����̂����ʂȂ�Ȃ��ł��傤���B
�≖�ʐ^�̂Ƃ��́A35mm�ȊO�̓}�C�m���e�B�[�Ȃ̂Łi�\�_�H�j��p�Ɏ~�܂��Ă����̂ł́H
�f�W�^���ƂȂ��ăt�H�[�}�b�g�������o�Ă��āA����͂��̑S�ĂɈ��䗦�̎s����������܂��B
�܂��AAPS-C�̓���@��t�H�[�T�[�Y�w�c�̌��тɂ��ʐ^���D�Ƃ��������Ă��܂��B
���ۂɎ��̎���ł������Y�������J�����i��肭�ǂ��ȁA�A�j�̈��D�Ƃ��������Ă��܂��B
�����̏��S�҂̋^��́A�t�H�[�}�b�g�Łu�����Ⴄ�́H�v���Ǝv���܂��H
���u300�~��������F2.0�Ƃ�������傫�ȃ{�P�����҂���ZD150�~�������̂Ƀ{�P�Ȃ������v
�����������������݂�A�u�t�H�[�}�b�g��ς�����s���g�̑O�オ�s���{�P�ł��B�v
�Ȃ�ď������݂����㑝���Ă�����������܂���B
�Ȃ̂Łu�V�����v�����m��܂��A�{������̘��������邩���m��܂��u���ZF�l�v���֗��ł��B
��ʏ���҂͂Ȃ��Ȃ��u���ʂ̌��w�v�͕~���������ł��B�i�ł����\�����̐l�������߂܂��B�j
�Ȃ̂ŁA���Ƃ��Ắu�J�������[�J�[�e�Ёv�ɂ��u�\���̓���v�����ė~�����̂ł��B
�u�ł��o�̏��Ɓv�͖������Ƃ����[�J�[�ɂ�����Ɛ������ė~�����̂ł��B
���P�N�|���āA���������ꂾ���̂��Ƃ��ʂ��Ȃ��B
���ꂾ���̃f�B�X�J�b�V����������Ώ\�����Ǝv���܂��B
�������ׂ̃X���b�h�Ŕ����̋^�`���������ꍇ�́A
�u[10141193] �t�H�[�T�[�Y�̃����Y�v��K���Ɏߓǂ݂��Ď����Ȃ�ɗ������Ă��������B
�ƃ��X����Α����̐l�ɂ͖𗧂Ǝv���܂���B
�����ԁA�����l�ł����B
�����ԍ��F10323999
![]() 2�_
2�_
�@�͂炽 ����A
�����a�H�͌ʐv�łƂĂ��ς�����Ⴄ����A���ZF�l�Œ��x�Ɍ������Ƃ�����A���R���A�v�҂����x�ɂ��킹�����̂ǂ��炩�ł��ˁB
�@�����Ō����ĂāA������Ɩ���������ȁ[�Ǝv���@
���ꂼ��̃t�H�[�}�b�g�ŁA�قړ����傫���A�d���A�l�i�œ�����p�̃����W�̃����Y��D�G�Ȑv�҂��蔲�������ɍ������A�܂���R�ł͂Ȃ��@�����Ȃ����̂����E�E�E�E�E
�@���̍���������܂���A�G�k�ł��B
�����ԍ��F10324491
![]() 0�_
0�_
�t���T�C�Y���g���~���O����`�o�r�|�b�ɁA����ɂ�����g���~���O����t�H�[�T�[�Y�ɂȂ�܂�����A�Z���T�[���������낤�ƎB�ꂽ�ʐ^�̘I�o�͓������邳�ɂȂ�܂��B
�܂�u�I�o�v�̈Ӗ��ł̖��邳�͓����Ƃ����̂͒N�ł�����܂��B
�����A�����Łu�Â��v�Ƌ�l�͐�ΓI�Ȍ��̗ʂ̈Ⴂ���]���Ă�̂ŁA�_�_���S���Ⴄ�Ƃ������ɂȂ�܂���ˁH
���������Ӗ��ł́A�ǂ�����Ԉ���ĂȂ��̂ł́H
�ŏ����猾�t�̈Ӗ����Ⴄ�̂ŋc�_�ɂȂ��Ė��������ł��傤�H�i�j
����b���o���悤�ȓ��e�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
���ƁA��̂ق��Ō��܂������A�R���f�W�����Q�C���A�b�v����̂́A�S���W�������̈Ⴄ�b���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10324784
![]() 1�_
1�_
�l�̖ڂɂ��āB
�Ԗ��ɂ͖��邢���Ɏd��������זE�i���́j�ƁA�Â����Ɏd��������זE�i�W�́j�̓��ނ�����ƌ����Ă��܂��B
�ʐ^�I�ɕ\������A���x�̈قȂ���ނ̍זE������炵���ł��B
���̋L�����m���Ȃ�A�Â��Ƃ��ɓ����זE�͐F�ɂ͓݊��炵���ł���B
���ZF�l�͂���ł���B
�ł��ˁA2�i�Â��Ƃ����\���ɂ͈�a���������ł��ˁB�����ăV���b�^�[���x�͂����ˁ[�����A�Ƃ����I�o�̕����łˁB
���I�ɂ́A������ăC���[�W���[���t���T�C�Y��4����1�̎d���������Ă��Ȃ��A�Ƃ����Ƃ������肭���ł���ˁB
���ꂩ��t�B�����̃t�H�[�}�b�g�Ⴂ�ɂ��Ăł����B
�t�B�����̏ꍇ�A�傫�ȃt�H�[�}�b�g�̉掿���Ȃ��ǂ��̂��Ƃ����ƁA�P���ɗ��q����������ł���ˁB
�t�B�������܂̗��q�Ƃ����̂́A�傫����ς����Ȃ���ł���B��������ƁA�ʐς��傫�������ɔ�Ⴕ�Ă�������̗��q������Ƃ������ƂŁA�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�Ɖ�f������Ⴕ�Ȃ��f�W�^���J�����Ƃ͔�r�ł��Ȃ���ł���B
����ɁA�O�ɂ��������s���z�[���J�����ł̗Ⴆ�Ȃ�ł����ǁA�s���z�[���J�������Ė��邯��Ηǂ��Ƃ������̂ł��Ȃ���ł���B
�ǂ̃t�H�[�}�b�g�Ńx�X�g�̃s���z�[���Ȃ̂��Ƃ������͂�����̂́A�قȂ�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�œ�����p��ꍇ�ł��A��{�I�ɂ͂���ς�傫���t�B�����̕����掿��ǂ����₷���Ƃ͎v����ł���ˁB
�����ԍ��F10325646
![]() 1�_
1�_
�� ���������Ӗ��ł́A�ǂ�����Ԉ���ĂȂ��̂ł́H
�Â��A�Â��Ȃ��Ɠ�̌��_������܂����A�S���������Ȃ��Ǝv���܂��B
�Â��ƌ����Ă�͎̂ʐ^���Â��̂ł����A����͎ʐ^�S�̘̂I���G�l���M�[�ɂ��܂��B
�Â��Ȃ��ƌ����Ă�̂͒P�ʖʐς̃t�B�����E�Z���T�[�ł����A����͎ʐ^�ł͂���܂���B
�P�ʖʐς̘I�o�������̏ꍇ�A�P�ʖʐς̉掿�������ł����A�Ⴆ�ΏW���ʐ^�̏ꍇ
35�~�����ň�l���ʂ��Ă�ʐςɁA4/3�ł͎l�l���ʂ��Ă܂��B
���̎l�l�̉掿�́A��l�̉掿�Ɠ����ƌ����āA�Ӗ������ł��傤���H
�P�ʖʐςł͖����ꒃ�ł��邱�Ƃ�������܂����A��r�́A�ꖇ�̎ʐ^�Έꖇ�̎ʐ^�A
��l�Έ�l�A�����ڂɖځA�@�ɕ@�̔�r�͎ʐ^�Ƃ��ėL�Ӌ`�̔�r�ł��B
�����ڂ̕����̘I���G�l���M�[�������ł���A�����ڂ��ʂ��掿�������ł��B
�����ԍ��F10326416
![]() 0�_
0�_
�ł���A�����t�H�[�}�b�g�ł��P�l���ʂ����Ƃ��ƂS�l���ʂ����Ƃ��͂S�l�̕�����i�Â��Ȃ�A�����J�����E�����Y�ł���ʑ̎���Ŋ��ZF�l���ϓ�����Ƃ������ɂȂ�B
���ZF�l�̓t�H�[�}�b�g�T�C�Y�����Ō���ł��Ȃ����ɂȂ�Ȃ����H
�����ԍ��F10328489
![]() 1�_
1�_
�t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ������ʐςɎl�l���ʂ������l�̏ꍇ����i�掿�������ł��B
������ʑ̂ɂ�����I���G�l���M�[���掿�����߂܂����A�����i��ƃV���b�^�[�̏ꍇ
�I���G�l���M�[�E�掿�̓Z���T�[�Ɍ���������ʑ̖̂ʐςɔ�Ⴕ�܂��B
��l������̉掿�ƌ����܂�����A�W���ʐ^�̓|�[�g���[�g���̉掿�ɂȂ�Ȃ��ł��傤�B
�ʐ^�S�̂̉掿�i�������̔сj���ς�܂��A��l������̉掿�i�H�ׂ�ʁj������܂��B
�l�l�̈�l���o���āA�����J�����̓����ݒ�ŎB�����|�[�g���[�g�Ɣ�ׂ���A
��i�Â��i�l���̈�̂��т����H�ׂȂ������䂪�q�H�j�Ȃ�܂��B
�����ԍ��F10328653
![]() 0�_
0�_
�Z�߂Č��܂��ƁA�����J�����̓����ݒ�ŎB�����ʐ^�́A
�ʐ^�̑S�̂̉掿�́A���l���B���Ă��ς�܂���i�������̔сj�B
��l������̉掿�́A�l������������܂��i�l�����̈�̔сj�B
�����ԍ��F10328690
![]() 0�_
0�_
�����X���b�h�ɂȂ�܂����ˁB
�������Ă���l�ɂƂ��Ă�
�u�Ȃ�ł���ȊȒP�Ȏ����킩��Ȃ��I�v
�Ƃ����C�������Ǝv���܂����A���ƌ����āA���S�҂�w�r�[���[�U�[�ł͂Ȃ������Ȑl�̃J�����w�����k�X���Ƃ��ŁA�ȒP�Ɍ������Ă��܂��̂͌���ގ��Ɍq����܂����A�l�K�e�B�u�L�����y�[�����ƌ�����\��������܂��B
�Ȃ̂ŁA���ڂ����m�肽���Ƃ����l�ɂ͓��X�����Љ�Ă���������ł����A�����ł͂Ȃ��l�ɂ́A���ꂼ��̃J�������g���Ă��郆�[�U�[���ǂ��_�A�����_�������Ă���������Ǝv���܂��B
���鐯�J��������͐e�ŋ����Ă����Ă���̂�������܂��A����ʌ���ޔ������������܂����A
�i��j�i���X���ł̔����j
>> �����Y�̖��邳�܂ŕω����ĈÂ��Ȃ�̂ł��ˁB
>�Â��Ȃ�܂��ˁB����������͒P�ʖʐςł͂Ȃ��A�ʐ^�S�̂��Â��Ȃ���Ӗ����܂��̂ŁA
>�g�����œ_�����h�Ɠ����悤�Ɂg�����Â��E�Â������h���������Ƃ����w�E������܂��B
>�P�ʖʐςł͕ς��܂��A�B�����ʐ^�A���ʂ͈Â��Ȃ�܂��B���ʘ_�ł͈Â��ł��B
>4/3�̓f�W�^���J�����ɑ��Ă̔F���̕s����o���s���ɂ����ꂽ���V�X�e���Ǝv���܂��B
���s�̂�������͋c�_������ɂ�����
�u���i���Ȃ��v
�u�ז����v
�u����������Y�v
�ȂǁA���l�ɑ����蔭�����ڗ����܂��B
���������A�E�ϋ�����Âȃ��X�����Ă���������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10328848
![]() 6�_
6�_
>�t�H�[�}�b�g�ƊW�Ȃ������ʐςɎl�l���ʂ������l�̏ꍇ����i�掿�������ł��B
�B��Ώۂ����ł��邩��F�l���ω�����킯���B
>�ʐ^�̑S�̂̉掿�́A���l���B���Ă��ς�܂���i�������̔сj�B
>��l������̉掿�́A�l������������܂��i�l�����̈�̔сj�B
���ՂŌ���ꍇ�Ƃ���ꏊ���Î�����ꍇ�ŁA�����P���̎ʐ^�ł����Ă�F�l���ω�����킯���B
�M�a�̕��̍l�����Ƃ�������ς��悤�₭�����ł����C������B�@����^���ł��Ȃ����D�D�D
�܂��ł�����ŁA14-54/2.8-3.5��F5.6-7�ł͌����Ă��蓾�Ȃ��̂͊m�M�����B
�����ԍ��F10331739
![]() 4�_
4�_
��ʂ̖ʐςɂ��ĕʂ̌f���������炦�܂����B
�I�����p�XE-P1�̏ꏊ�ł��B�m10331821�n
�F�l�̂��ӌ�����낵�����肢���܂��B(�����̑����̓_���ł���!!)
m(__)m
�����ԍ��F10332143
![]() 0�_
0�_
�� ���ՂŌ���ꍇ�Ƃ���ꏊ���Î�����ꍇ�ŁA�����P���̎ʐ^�ł����Ă�F�l���ω�����킯���B
�ǂ��������Ă܂��ˁB��ʂ�ł��B�Î��͈��̃g���~���O�ƍl��������Ȃ�܂��ˁB
����F�l�����ł͂���܂���B�����œ_�������ς�܂��B�ς�Ȃ��Ɖ����Ȃ�ł��傤�B
�����ԍ��F10332481
![]() 0�_
0�_
�͂炽���� �� [10323484] �Ȃ������Ȃ�ł����ǁE�E�E�B����{���͖ʐς���Ȃ���ł���ˁB
�܂��ʐςł��������ǂ��A�w�ʐς�����x���w���ʂ�����x�A����ł��������ǂ��B
���ꂾ�Ɓu���Z�v����Ȃ���ł���ˁB����u�����v���ƁB
�ʐς����遨��p�������Ȃ遨�œ_�������L�т��̂Ɠ������ʁ��ł����a�͂��̂܂܁����ۂɏœ_�����L���ē���F�l�̂Ɣ�ׂ�Ɠ�i�Â��B
�v����Ɂu��p�v�Ɓu���a�v�ŁB
300mm ���u600mm�v�Ƃ���������i����͂���ł������ǁj�uF5.6 �� F11 �ɂȂ邾��v���Ă��ƁB
��i�̍��̌����͖ʐςł͂Ȃ��u���a�v�ł��B
�����āu�t�H�[�T�[�Y�� 300mm�v�Ɓu�t���T�C�Y�� 600mm�v���ׂĂ���́B
����Ȃ� 300mm ���m��ׂĂ�̂Ȃ�u�ʐρv�ł��������ǁB
�����ԍ��F10332548
![]() 1�_
1�_
�� 4/3�̓f�W�^���J�����ɑ��Ă̔F���̕s����o���s���ɂ����ꂽ���V�X�e���Ǝv���܂��B
����̓I�����p�X������܂ދƊE�̋��ʔF�����Ǝv���܂��B
������p�i��������̂Ăă}�C�N��4/3�����܂����B
�I�����p�X����F�X���_������܂����A�I�����p�X����̕��͊F�v���ł�����A
�i�D�����ꂵ���ٖ��͌����{�l���M���ĂȂ��Ǝ����͓ǂ߂�Ǝv���܂��B
�ł����A����͓�i�Â��̘b�Ƃ͕ʂł��B��i�Â����}�C�i�X�ȃC���[�W�������
��l�������ł����A�����͒����I���Ǝv���܂��B��i�Â�������s���ł͂���܂���B
�����āA�������a�̃����Y������Z���T�[�T�C�Y�͊W�Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F10332628
![]() 1�_
1�_
���s�̂�������@
�Ԏ������Y�ꂽ�̂Ł@�Ō�ɏ��������܂��B
���C���[�W�T�[�N���̘b�͂��Ă��܂���B
[10320419]
�ł����@
���ʐς����遨��p�������Ȃ遨�œ_�������L�т��̂Ɠ������ʁ��ł����a�͂��̂܂܁�����
���ɏœ_�����L���ē���F�l�̂Ɣ�ׂ�Ɠ�i�Â��B
�@���ꎩ�́@�C���[�W�T�[�N���̎��Y��Ă��܂���B
�@���̘b�̓A�h�o�C�X���Ǝv���ā@�Ԏ��s�v�ł��肢���܂��B
�ł́@���炵�܂��B
�@
�@�@
�����ԍ��F10332677
![]() 0�_
0�_
[10332677]
�C���[�W�T�[�N���̘b�͂��Ă��܂���B
���ƃ��{�}�� �Q���� �����炩�̊W�����o�����̂ł���AF�l�ƃC���[�W�T�[�N���̊W��萫�����܂��傤�B���ꂪ�Ȋw�i�����j�ł��B
[10322599] �ɂ��Ă����l�B
�����������́u���a�v���p�ƊW������̂�����悤�ł��ˁB���������ނ̎����ɂ��Ă� F�l�Ŋ��Z�ł��܂��B
�����ԍ��F10332700
![]() 0�_
0�_
>���������ނ̎����ɂ��Ă� F�l�Ŋ��Z�ł��܂��B
���������ނ̎����ɂ��Ắu���ZF�l�v�Ɓu���Z�œ_�����v�ŕ\���܂��B�ɒ����B
�����ԍ��F10332709
![]() 0�_
0�_
���������œ_�����ƘI�o���ĊW����́H
70-200F2.8�̃����Y��100mm��200mm��F�l�͓�i�ς��́H
�����ԍ��F10332733
![]() 1�_
1�_
�� ���������œ_�����ƘI�o���ĊW����́H
�P�ʖʐς̘I�o�͎ʐ^�ł͂Ȃ��P�ʖʐς̉掿�����߂�̂ł����A
��������F�l�͂Ȃ�ł��傤���HF�l�̒�`���v���o���Ă��������B
�����ԍ��F10332792
![]() 1�_
1�_
����
70-200F2.8�̃����Y��
100mm��200mm�͂���Ȃɉ掿�ɍ����ł�̂��ȁH
�����ԍ��F10332840
![]() 0�_
0�_
���������t�H�[�}�b�g�̑O��ŁA�œ_�����E��p���Ⴄ�̘b���Ǝv���܂����A
����f/2.8�ł���A�掿�̍�������܂���B�ʐς������ł��̂ŁAF�l�̊��Z�������ł��B
����͍��܂ł̘b�Ɠ��e���������Ⴂ�܂����A�ʐ^�̊�{����A���G�l���M�[���l�����
���e��������ǂ��ς낤���A�������邱�Ƃ�����܂���B
��p���Ⴄ�ꍇ�ɓ������a�ł͏W�����\���Ⴂ�܂��̂Łi�����قǔ\�͂��Ⴍ�Ȃ�܂��j�A
�����W���\�͂�ۂ��ߌ��a���ς��܂��Bf/2.8�ʂ��Ƃ����̂͏œ_�����ɉ�����
�L�����a�������I�ɒ�������\��������Ƃ̈Ӗ��ł����A���̏ؖ��ɂȂ�Ӗ��͂���܂���B
�����ԍ��F10332856
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������@
�@�������Љ�܂��������̃X���ł͂�����Ƃ����ʂ�܂��˂��Љ�Ă��邱�̃T�C�g�����Ă��������B
[10241769]
�@http://www.four-thirds.org/jp/fourthirds/index.html
4/3�^�C���[�W�Z���T�[�̑Ίp���́A35mm���t�B�����̖�1/2�B
���������āA������p�邽�߂̏œ_������35mm���t�B�����J�����p�����Y��1/2�ōςނ��߁A���w�n�̑啝�ȏ��^�����\�ɂȂ�܂��B�������邳�ł���ΗL�����a�͏������Ȃ�܂����A��薾�邢�����Y����������\���������Ȃ�܂��B���^���Ƒ���a���̗����A�����Y�̐i���ւ̊��҂���������g����܂�
�܂�4/3�^�C���[�W�Z���T�[�̗̍p�ɂ��A�]���̃����Y�ł͂قƂ�ǒB���ł��Ȃ����������\�Ōg�ѐ��ɂ��D��Ă���Ƃ��������Y�������\�ƂȂ����킯�ł��B�Ⴆ�A35mm�����Z��300mm�̖]�������Y�́A�t�H�[�T�[�Y�V�X�e���ł�150mm�̏œ_�����ƂȂ�A�]���AF2.8�̖��邳���ő傾�����Ƃ�����A1�i�K���邢����aF2.0�̖��邳�Ŏ������邱�Ƃ��ł��܂����B
�����������܂������@���ꂪ�����Ɠ����l���ł��B
�����
���ʐς����遨��p�������Ȃ遨�œ_�������L�т��̂Ɠ������ʁ��ł����a�͂��̂܂�
���̍l�����Ɓ@�t�H�[�}�b�g���傫���Ȃ�قǗL�����a�������ł����邢�����Y���o���邱�Ƃɐ���͂��ł����@35mm���6×4.5�̃����Y�̂ق������a���傫���đS�̂̑傫�����@�傫���d���Ȃ��Ă��܂��B�i2��ځj
�������������̂́@�����������Ȃ��ׁ@�{���ɕԐM�͌��\�ł��B
�����ԍ��F10332860
![]() 0�_
0�_
�� �������������̂́@�����������Ȃ��ׁ@�{���ɕԐM�͌��\�ł��B
�������ƂƓ����b�́A�������x����������ł��ˁB
�I�����p�X����g���邳�h�͒P�ʖʐς̖��邳�ŁA�ʐ^�̖��邳�ł͂Ȃ��ł���B
�ʐ^�ƌ�������S���Ⴂ�܂��B������p�œ������邢�ʐ^���B�邽�߂ɂ́A�������a�A
�܂蓯���d���̃����Y���Ȃ���Ε����I�ɕs�\�ł��B�t�H�[�}�b�g���ǂ��ς낤�ƁB
�����ԍ��F10332863
![]() 0�_
0�_
�킩����
�t���T�C�Y�̃����Y300F4�ƃt�H�[�T�[�Y�̃����Y150F2�������掿�ɂȂ�Ƃ������Ƃł����H
�ł�F2��SS���g������ĕ֗����˃t�H�[�T�[�Y
�����ԍ��F10332922
![]() 5�_
5�_
�ł�F2��SS���g������ĕ֗����˃t�H�[�T�[�Y�B
�掿�Ƃ̃g���[�h�I�t�ŁA���ł������V���b�^�[���ėǂ��̂ł����A
�掿�������Ȃ̂́A35�~������f/4�����Ɠ����V���b�^�[�X�s�[�h�ł��ˁB
�����瑊���ƌ����Ă邶�Ⴀ��܂���H
�����ԍ��F10333573
![]() 0�_
0�_
�掿�������Ȃ̂́A35�~������f/4�����Ɠ����V���b�^�[�X�s�[�h�ł��ˁB
SS�����ɂ����甒��т��Ďg���Ȃ��Ȃ�Ȃ��H
���Ă�F4�܂ł����g���Ȃ������Y���
F2�܂ł���������֗������
�����ԍ��F10333743
![]() 3�_
3�_
[10332860]
�C���[�W�T�[�N���̘b�͂ǂ��֍s�����̂ł��傤�H �l�̌��������ƂɂƂɂ����P�`�������������̂ŁA�Ƃ肠�����C���[�W�T�[�N�����^�p�����Ƃ������Ƃł��傤���H
�ŁA���ƃ��{�}�� �Q���� �̍l�����͊Ԉ���Ă��܂��B
>���^���Ƒ���a���̗���
>����aF2.0
F�l�̒�`���v���o���܂��傤�B
>���ʐς����遨��p�������Ȃ遨�œ_�������L�т��̂Ɠ������ʁ��ł����a�͂��̂܂�
>
>���̍l�����Ɓ@�t�H�[�}�b�g���傫���Ȃ�قǗL�����a�������ł����邢�����Y���o���邱�Ƃɐ���͂��ł����@
�����킩�����B�������u�C���[�W�T�[�N���v�ł��ˁB
���́u�t�H�[�}�b�g��傫������b�v�͂��Ă��܂���B
�ŁA���ƃ��{�}�� �Q���� �́u�t�H�[�}�b�g��傫������ƃC���[�W�T�[�N��������Ȃ��Ȃ�v���Ďv���Ă��ł���ˁH
�C���[�W�T�[�N��������Ȃ���܂Ƃ��ȎB�e�ɂȂ�܂���ˁB�܂Ƃ��ȎB�e���ł��Ȃ���Ԃ� ���ƃ��{�}�� �Q���� �͂���Ɏv�l�𑱂���̂ł����H
�����ԍ��F10333920
![]() 0�_
0�_
���I�I
SS�����ɂ���̂�ISO�ς��������
�܂�
�K�i���t����̫�����
mm��300��150
F�l��F4��F2
SS��1/50��1/50
ISO��400��100
���ZF�l���ĉ]����芷�ZISO���Ă����ق���
�掿������ł͂ӂ��킵���C�����邯��
�����ԍ��F10334016
![]() 2�_
2�_
�V���b�^�[�X�s�[�h���҂��Ȃ���A
�掿�̗ǂ���ISO�ŁA
��ʊE�[�x�̐[���ʐ^����肽���B
�Ƃ����P�[�X�ɂ����ẮA�t�H�[�T�[�Y���L�����Ă����������o���܂��ˁB
������u�Â��v�ƕ\������̂̓C�}�C�`�[���ł��܂��A�����Y�̖��邳�͓����ƍ��ӂł����悤�ł����A���̃X���̖�ڂ��I���ł����ˁB
�����ԍ��F10335740
![]() 2�_
2�_
�E�𑜓x���Ⴂ
�ES/N�䂪�Ⴂ
�E�{�P�ɂ���
�����͑S���u�Â��v�ƌ����̂��������B
�܂��A����t�H�[�}�b�g�ł���ʑ̂̌`�Ŗ��邳���ϓ����A�ł����������ʐ^�̑S�̂߂�Ƃ��͖��邢���A�ꕔ�𒍎�����Ƃ��͈Â��Ȃ邻�����B
���ɂƂ��Ă̖��Â͂����������ۂ��w���̂ŁA����͂������������Ȃ��Ǝv���B
�b�����ݍ����Ƃ͓���v���Ȃ��̂ŁD�D�D
���ǁA���ꊴ�o�̑���ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�����ԍ��F10336335
![]() 7�_
7�_
���V���b�^�[�X�s�[�h���҂��Ȃ���A
���掿�̗ǂ���ISO�ŁA
����ʊE�[�x�̐[���ʐ^����肽���B
���Ƃ����P�[�X�ɂ����ẮA�t�H�[�T�[�Y���L�����Ă���������
��
��ʊE�[�x�͍i��t���T�C�Y�ł���[���܂�����A���̘b�͓��Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���܂��B
����ƁA�u�掿�̗ǂ���ISO�v�Ƃ������Ȃ�A�Ӗ��Ƃ��Ă͍�ISO�ł��掿�̗ǂ��t���T�C�Y�̂ق����L���ɂȂ�܂��B��ISO�Ȃ�Ȃ��X�̎��ł��B
�܂�A�u�掿�v�Ƃ������̂��e�[�}�ɂ����Ƃ��́A�K���f�q�T�C�Y���傫���t���T�C�Y�̂ق����L���ł��B
����͂����܂ł���ΓI�ȃ��m�Ȃ̂ŋc�_�̗]�n�͂���܂���B
�������A�Z���T�[���������t�H�[�T�[�Y������Ə������R���f�W�́A�t���T�C�Y�̕����ł���A�Ɖ]���܂��̂Ŕ�ʊE�[�x�Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ŁA�s���g�̍����Ă��镔���ƍ����Ă��Ȃ������̈Ⴂ���B���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�܂�A�����ŗL�邪�̂ɁA��������̓p���t�H�[�J�X�̂悤�ȏ�Ԃɂ�����܂���B
�ǂ��������������ׂɃV���[�v�l�X�������鎖�ɂ���āA�������肵����ʂ��o���Ă���悤�ł��B
�V���[�v�l�X�������Ȃ���ΗB�̖����摜�ɂȂ�ł��傤�B
�v�����g�A�E�g�������m��吨�Ɍ����Ăǂ������L���C�Ȃ̂��E�E�E
���������F���ŃJ�������ׂ�A�Ƃ����Ȃ�R���f�W�̂ق����ǂ��Ƃ����܂��B
�܂�A�t�H�[�T�[�Y�ł����I�[�o�[�L���p�V�e�B�[�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F10336394
![]() 0�_
0�_
�d�����ς珑�����Ǝv���Ă������Ƃ���������ł����A���炭���Ȃ������ɑ��̕����������Ƃ���������ł��������܂����B
����܂ł����x������Ԃ��ꂽ���ƂŁA�����܂��������Ƃ������Ă��d���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�����܂ł��Ă������ς���Ă��Ȃ��̂ŁA���鐯���߂炳������s�̂�������l�Ƃ��A�������̂��l�����l�������Ă݂�C�͂��炳�疳���Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂����B
��������炸�A�������Ƃ�����Ԃ���Ă�������Ⴂ�܂��B
���́A�܂��������ʂȂ��ƂɎ��Ԃ��g���Ă��܂����悤�ȋC�����Ă��܂��B
�u���Z�œ_�����v�Ɏn�܂�u���ZF�l�v�Ƃ��u4/3�͂Q�i�Â��v�ȂǂƂ������ӌ����A���܂�ɂ������̐l�����������Ă���̂ŁA������Ȃ�Ƃ��������Ǝv���Ă����̂ł����B
���Ƃ���
�u4/3�{�f�B��OM�����Y���g������œ_������2�{�ɂȂ��ł���B�v
�u4/3��OM�����Y���g�����Ƃ��A�i��F2.8����F5.6���Ă��Ƃ���ˁH�v
�u4/3��6×7�p�̃����Y���g������œ_�����͂ǂ��Ȃ�́H�v
�u4/3��6×7�p�̃����Y���g���Ƃ��A�i��̐����͂ǂ����Z����́H�v
�u4/3�J������V�̖]�����Ŏg���Ƃ��̏œ_�����̌v�Z�͂ǂ�����́H�v
�u4/3�J������F6�̓V�̖]�����Ŏg���Ƃ����ۂ̌��a��̌v�Z�͂ǂ�����́H�v
�u4/3��F2.0��2�i�Â��炵������I�o���Ԃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ˁv
�u4/3�̎�Ԃ��̏œ_�����蓮���͂͊��Z�œ_�����ł����́H�v
�ǂ���������ۂɐu���ꂽ��A�e���Ŗڂɂ�������ł��B
�u4/3��25mm�����Y�̉�p��35m����50mm�̉�p�ɑ����v��
�u4/3��25mm��35mm�����Z�œ_����50mm�v�ƕ\������̂��ԈႢ�̂��Ƃ̂悤�ȋC�����܂��B
�u���Z�œ_�����v�Ƃ������ۂ̐��l������悤�Ɏv���Ă��܂�����ł��B
�����̃t�H�[�}�b�g�����݂��钆��35mm�����ΓI�Ȋ�Ƃ��闝�R�͂Ȃ��A�t�B��������ɂ͖��������u���Z�œ_�����v�₻������h�������i�H�j�u���ZF�l�v�Ȃ���̂�����Ă����̂́A�����̃��[�U�[��35mm�t�B���������g��Ȃ������̂��A�f�W�^���J�����e���[�J�[�����ꂼ��̍l���ɂ���Ă��낢��ȃT�C�Y�̃C���[�W�Z���T�[���̗p�������߂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
35mm���̏œ_�����ʼn�p�𗝉����Ă��������K�������������߁A���͍������ɂ��邩������܂���ˁB�������A���ꂾ���Ɂu�œ_�����v�u���邳�v�u��p�v�����t�ŕ\������Ƃ��́A�N�ł��ԈႢ�Ȃ������ł���悤�ȕ\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��i�����g���C�����Ȃ���j�B
���Ƃ��A���[�J�[�ɂ��Ă������Y�ɏœ_������F�l�����łȂ��A��p���p�x�ŕ\������̂�������������܂���B
�ł��A���V�X�e�����ɕ����̃t�H�[�}�b�g�������������ł��ˁB�������l���Ă����ZF�l�_�҂�4/3�ȊO�̃��[�J�[�̌f���Ŋ��������̂��Ӌ`������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
4/3�V�X�e�����ł�����A�Ⴄ�J�������g���Ă����Z�̕K�v������܂��B
�킽�������낻�낱���ւ̏������݂͏I���ɂ��悤�Ǝv���܂��B
���s�̂���������ɂ́A�܂����Z�œ_��������鎑�i�͖����ƌ���ꂻ���ł��ˁB
�܂��A�킽���͊��Z�N���u�ɓ����C�͂���܂���̂ŁA���i�͗v��܂��ǁB
����́A������Ă������Ȏ���⏑�����݂������������ɂ́A���ڂ��̐l�ɐ�������悤�ɂ���Ƃ��܂��傤�B
�����Ŏ��̌����Ă邱�Ƃ��Ԉ���Ă�����A���w�E������������K���ł��B
�l�̘b�����Ƌq�ϓI�ɍl����p�������͎����Ă������Ǝv���܂��B
�ǂ������X�Ǝ��炢�����܂����B
�����ԍ��F10336443
![]() 12�_
12�_
�� �Ƃ����P�[�X�ɂ����ẮA�t�H�[�T�[�Y���L�����Ă����������o���܂��ˁB
�������Ƃł́A4/3�͉���L���Ȃ��Ƃ�����܂���B�������A����F�l�̎��_����
���̏ꍇ�͉���s���Ȃ��Ƃ�����܂���B�������a�̃����Y������ł��B
�������Z���T�[�̗L���Ȃ��Ƃ͐��Y�����������ł��B�����ȉ��H�Z�p���K�v�ł���
��4/3�Z���T�[�ł��Ő�[�Ȕ����̋Z�p��K�v�Ƃ��܂���B�X�ɍ���f���i�ނƁA
�}�C�N�������Y�Ƃ��̉��H������Ȃ�܂����A���ʏƎ˂�����܂����A�Z�p���i�݂܂��B
���Ӊ�f���߂ɂ���Ƃ��ʔ�������������łɂ���܂��i������4/3�����n�ł����j�B
���͂�����A�������a�̃����Y�����邩�ǂ����ł��B
�������a�̃����Y���Ȃ��ƁA�\���ǂ܂肾�Ǝv���܂����A
�������a�̃����Y������A���j�ł����ł͂���܂���i�t�@�C���_�[�����Ȃ��ł��j�B
�����ԍ��F10337117
![]() 0�_
0�_
�� �\���ǂ܂�
E-1��E-3�͖����\���ɂ��܂��傤�B
E-3�ɓ������a�̃����Y������A��f���ƍŒኴ�x�ȊO�̓�900�Ƒ卷�Ȃ����Ǝv���܂��B
�������a�̃����Y�Ƃ����̂́A8-17/1.4�A12-35/1.4�ƁA35-100/1.4�Ȃǂł��B
���ꂮ�炢���Ȃ��ƁA�y�U�ɏオ���Ă�����ɕЎ�ŕЕt�����܂��B
�����ԍ��F10337210
![]() 0�_
0�_
[10336443]
Tranquility���� �Ƃ̂����̒��� [10320830] ��
>�L���m���� 5DMark�U �� E-1 �͓������邳�ł���
���̘b���r���Ő܂ꂽ�܂܂Ȃ̂ł����ˁB
�͂炽���� �������Ȃ̂ł����u�������閾�邳�͖ʐςɈˑ�����v�Ƃ������Ƃ��킩���ĂȂ���ł���ˁB
1 lx [���b�N�X] �� 1/1000000 lm/mm2 [���[�����^�����~�����[�g��]
�����ԍ��F10337407
![]() 0�_
0�_
2��������œǂ݂܂����B
A700���g���Ă��āA�R�o����n�߂����߂Ɍy�ʂȃV�X�e�����K�v���Ȃ��Ȃǂƍl���Ă�
�܂��B
���̗������Ă���Ƃ���͈ȉ��̊����Ȃ̂ł����A�Ԉ���Ă��邱�Ƃ������������
�������B
�u�t�H�[�T�[�Y�̃����Y��2�i�Â��v�ƌ����̂͌��ǂ̂Ƃ���AA4�̎���A2�̎����ׁA
A2�̎������邢�ƌ����Ă���悤�ɕ������Ă��ł����B
������Ċ��Ƀ����Y�̘b����Ȃ��ł��ˁB
�唻�p�����Y���}�E���g�A�_�v�^�[�Ŋe�t�H�[�}�b�g�Ƀ}�E���g���Ď��ʂ��Ă݂��
�����킩��悤�ȋC�������ł����B
���邳�͉����ς��v�f�������Ǝv���܂����ǂˁB
�ς��͎̂���ʐςł����āA�����Y��ʉ߂��Ă�����̗ʂ͉����ω����Ȃ��ł���ˁB
�����Y�͉����ς��Ȃ��̂ł����āA����ʐςɂ���ē����i��l�ł��A��ʊE�[�x��
�ω�(�t�H�[�}�b�g���偨��)����ɂ�đ��ΓI�ɑ傫���Ȃ邾���B
�Ȃ������āH
���̃V�X�e���̓t�����W�o�b�N���ω����Ă��܂��B
�傫���t�H�[�}�b�g�͂��ꂾ�������Y�������̂�����āA�������t�H�[�}�b�g�̓���
�Y�ɋ߂��Ȃ��Ă��܂���ˁB
A4�ł��AA2�ł����S�ɒ��a10cm�̊ۂ�`������ʊE�[�x
���Č�����������Ȃ���ł����H
���̂Ƃ��ɁA���ꂼ��̎��ɂ������Ă�����̗ʂ͂��ĕ����������A2�̂ق�����
���ł��B
���Ⴀ���邳�́H���Ă����Ɖ����ω����Ȃ��ł��B�����Â��Ȃ��ł��傤���B
�t�ɒ��S�ɕ`�������a10cm�̊ۂ͑傫���t�H�[�}�b�g(A2)�ł́A�債�đ傫���Ȃ�
(�[�x����)
�������t�H�[�}�b�g(A4)�ł͂��������傫���Ȃ��Ă��܂�(�[�x���[��)
�Ȃ̂ŁA��ʊE�[�x��35mm�ł̃t�H�[�}�b�g�ɔ�ׂĐ[���Ȃ��Ă��܂��B
�t�H�[�}�b�g(����ʐ�)���Ⴄ�t�B�����ɑ��āA�ς��̂̓t�����W�o�b�N���ω�
���邱�Ƃł��킹�ĕω����Ă��܂���p�ł����āA���̂ق��͉����ς���ł����H
�ǂȂ��������Ă���������ƍK���ł��B
�����ԍ��F10337949
![]() 5�_
5�_
���݂܂���A��̏������݂ŁA�ԈႢ���B(�ꊾ)
> �t�H�[�}�b�g(����ʐ�)���Ⴄ�t�B�����ɑ��āA�ς��̂̓t�����W�o�b�N���ω�
> ���邱�Ƃł��킹�ĕω����Ă��܂���p�ł����āA���̂ق��͉����ς���ł����H
�唻�����Y�g�p�Ƃ��鎖��O��ɂ���ƁA��̏������݂͕s�K���ł��B
�}�E���g�A�_�v�^�[�Ńt�����W�o�b�N�͂��킹�Ă��܂��B
�����Y�t�����W�o�b�N����肾�����Ƃ��ɕω�����v�f�́A����̂̃T�C�Y�ω��ɂ��
��p�ȊO�ʼn�������܂����H
�Ə���������ł����Bm(__)m
�����ԍ��F10337999
![]() 3�_
3�_
[10337949]
>�����Y��ʉ߂��Ă�����̗ʂ͉����ω����Ȃ��ł����
�ƁA
>���ꂼ��̎��ɂ������Ă�����̗ʂ͂��ĕ����������A2�̂ق�����
���ł��B
>���Ⴀ���邳�́H���Ă����Ɖ����ω����Ȃ��ł��B
�̓�̕��͂ɖ���������܂��B
��p�͍��킹�Ȃ��Ƒʖڂł��B�u���Z�v�ł�����B
>�t�H�[�}�b�g(����ʐ�)���Ⴄ�t�B����
�t�B�����͓������邳�ł��B[10337407] �Ŏ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă܂��B
�����ԍ��F10338211
![]() 0�_
0�_
���s�̂�������
���ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
>>�����Y��ʉ߂��Ă�����̗ʂ͉����ω����Ȃ��ł����
>
>�ƁA
>
>>���ꂼ��̎��ɂ������Ă�����̗ʂ͂��ĕ����������A2�̂ق�����
>���ł��B
>>���Ⴀ���邳�́H���Ă����Ɖ����ω����Ȃ��ł��B
>
>�̓�̕��͂ɖ���������܂��B
>
>
>��p�͍��킹�Ȃ��Ƒʖڂł��B�u���Z�v�ł�����B
��[�����������Ă���̂��A�����킩��܂���B
10cm�̊ۂ�`�����Ƃ���ɘI�o�v�ĂāA�o�Ă��鐔�l������Ă���Ȃ�
�܂��킩��̂ł����ˁB
������Ă��閾�邳���ƌ����������ق����悩�����ł����ˁB
����ƁA�����Y�������ƑO�Ă���̂ŁA���Z�O�̊m�F�Ǝv���Ă��������ȁB
�ȏ�
�����ԍ��F10338327
![]() 2�_
2�_
[10338327]
>��[�����������Ă���̂��A�����킩��܂���B
��s�J���Ă���̂�ǂݎ���Ă��������B
>���̗ʂ͉����ω����Ȃ��ł����
�ƁA
>���̗ʂ͂��ĕ����������A2�̂ق�����
>���ł��B
�Ō����Ă邱�Ƃ��������Ă܂��B
>>��p�͍��킹�Ȃ��Ƒʖڂł��B�u���Z�v�ł�����B
>�����Y�������ƑO�Ă���̂ŁA���Z�O�̊m�F�Ǝv���Ă��������ȁB
�u�����Y�������v�̏ꍇ�́u�g���~���O�v�ɂȂ�܂��B�u�g���~���O�͊��Z�œ_������{�v���i���Z�̍l�����́j��{�ł��B
�u���Z�œ_��������{�Ȃ̂Ɍ��a�͈��Ȃ̂ŁA���ZF�l�͓�{�v���u���ZF�l�v�̍l�����i�ƌ�������`�j�ł��B
�g���~���O�̏ꍇ�́A�u�g���~���O�����ɃG�N�X�e���_�[�����܂��v�ꍇ�ƈꏏ�ł��i��������f���͈قȂ�j�B
��{�̃G�N�X�e���_�[�̏ꍇ�� F�l����{�A����ƃg���~���O�͓����B
��f���͎����r���ԈႦ�܂������A�u��f���͉摜�̃X�y�b�N�̈�v�Ƃ��Čォ��l�����܂��B�u��f���Ƃ͉�ʁi���̏ꍇ�͉摜�j�̑傫���̂��Ɓv�ł���A�Ⴆ�u500����f����v�Ȃǂƒ�߂�u2000����f�͊g�嗦��{�v�ȂǂƂ������������\�ł��B
�u���Z�œ_�����E���ZF�l�E���ZISO���x�v�̎O���Z�b�g�ŁA����Ƀv���X�Łu��f���i�g�嗦�j�v�Ƃ����X�y�b�N�����݂��܂��B
�����ԍ��F10338386
![]() 0�_
0�_
�����R�[�h�M���M������
���ZF�l�_�ɂ�����v�Z�œ��������ꂽ�ЂƂ̌��_
�K�i=�t���T�C�Y=�t�H�[�T�[�Y
mm=300=150
F�l=F4=F2
ISO=400=100
���Ɠ����u�掿�v�̎ʐ^���B���
�Ƃ������鐯���߂炳��̎咣���������Ɖ��肵���ꍇ�́A�����̂ЂƂƂ��l���������B
���������������Ƃ́A�t���T�C�Y�́u�掿�v���t�H�[�T�[�Y�Ƃ�����ۂ����̈Ⴂ�ł����̂ł����H
�Ƃ������Ƃł��B
���ZF�l�_�́A�t�H�[�T�[�Y���Â��ƒ@�����Ƃ��邱�ƂŁA�t�Ƀt���T�C�Y�̉��l���Ȃ߂Ă��܂��ˁH
���鐯���߂炳��
�R���f�W�ł��t�H�[�T�[�Y�ł��t���T�C�Y�ł������u�掿�v�̎ʐ^���B���Ǝ咣�����̂͒N�ł����H
���������Y�̘b�͂����ł��B
�����ԍ��F10338647
![]() 3�_
3�_
�����̂���A�i��ƃV���b�^�[�X�s�[�h�̘I�o������������܂����A
�������������A��������𑝂₹�ΒP�ʖʐς̘I���ʂ��ۂ�����A��������ƌ����܂��B
����F�l�̊��Z�́A�����ʐ^���B�邽�߂ɓ�����p�A�������a���K�v�ƌ����킯�ł����A
�Z���T�[�ʐς������Ă��P�ʖʐς̘I���𑝂₹�Ή�ʑS�̘̂I���ʂ��ۂ�����܂�����
������������ƌ����܂��B
���̑������͘I�������������ŁA��ʊE�[�x���܂Ȃǂ͑������܂��A�ʐϔ��
���Z����F�l�̑����́A�I���G�l���M�[�ʂ���A��ʊE�[�x���܂܂Ŋ����ɑ������܂��B
���̑������͒P�ʖʐρA����F�l�͎ʐ^�S�̂ƑΏۂ̈Ⴂ�ɂ����ڂ��Ă��炢�����ł��B
�Η��▵�����Ȃ��A���������̊�{���瓾��ꂽ���_�̈Ⴄ���ł��B
�����ԍ��F10338762
![]() 0�_
0�_
���̘_���̃|�C���g��
�u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂邩�ۂ��v���Ǝv���܂��B
�����e�l�܂��͊��Z�e�l�͂��̖��肪�������Ƃ̑O��ŏo�Ă���T�O�ł��B
�Ȃ��u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�̂�
�X�g���[�g�Ȑ����������Ǝv���܂��B
�����ōl���ĂƂ��A���̃J�L�R�����ĂƂ������̂͌��\�ł��B
�ߋ��̃J�L�R�⑼�̃J�L�R�����܂������A�X�g���[�g�Ȑ����͂���܂���ł����B
�i�}�t�̘b�̐����͂�������܂������j
���́u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�ƍl�����
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�̈Ⴂ�ɂ���ʊE�[�x�⍂���x�m�C�Y���̍��ɂ���
���܂��������ł���Ƃ����������邢�͌o�����ƍl���邱�Ƃ��K�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10338872
![]() 3�_
3�_
�����ʂ�������Ή掿���オ��A���Ȃ���Ή掿�������Ȃ�B
��
�S���̑f�l�̔��z���ˁB
���ʁi���ʂƂ��Ă��ǂ��j���������Ă��掿�����邱�Ƃ��炢�A��������o���Œm���Ă���͂��Ȃ��ǂˁB
�ʐ^�Ō����Δ��h�r�Ƃ��O�a�Ƃ��B
��ʌo���ł��A�Â��Ƃ��납�疾�邢�Ƃ���֏o���Ƃ���ڂ�ῂށA�ȂǁB
�ō��掿�͍œK�ȏ��ʂœ�����B
���ʂ̉ߏ��݂̂Ȃ炸�A�ߑ�����v�I
�����ԍ��F10339226
![]() 3�_
3�_
���[�v�E���[�v����
�@�O�a�܂ŁA14bit �̊K�� �i16384 �K���j �����������\���ł��� �u��f�`�v ���������Ƃ��܂��B
�@���ꂪ1200����f�W�܂����̂��A�J�����`�B
�@����̂S���̂P�̖ʐςŁA
�@�O�a�܂ŁA12bit �̊K�� �i4096 �K���j �����������\���ł��� �u��f�a�v ���������Ƃ��܂��B
�@���ꂪ1200����f�W�܂����̂��A�J�����a�B
�@���҂������Ă���J�����ŁA�������i�� �i�����ł̓O���[�J�[�h�Ƃ��܂����j�A���ʂɑ������ĎB�e����H
�@�K���̐��m������萳�����\���ł������Ȃ̂́A�u��f�`�v �u�J�����`�v ���Ǝv���܂��H
�@�O���[�J�[�h���B�e�����悤�ȏꍇ�A�u��f�a�v �� 12bit ���� �i�߂��̑��̉�f�R�ƍ��킹�āj �S������ 14bit �ɂ���A�u��f�`�v �Ɠ����ȏ��ƌ��邱�Ƃ��ł��܂� �i�����I���o���炷��j�B
�@�������� 12bit �ŏ\��������A14bit �̕����ǂ��Ȃ�Ęb�����Ă����� �ƌ����Ȃ�A����͂���ŕ�����̂ł����A�S�^�R�i��h(�H)�̐l�̒��ɂ́A�ǂ����������������ł͂Ȃ��l�������悤�Ȃ̂ł��B
�����ԍ��F10339464
![]() 1�_
1�_
�s�����w����
���������ʂ̂��𑽂̂����ʁi14bit �̊K���j�ŋL�^�����ꍇ�ƁA���Ȃ����ʁi12bit �̊K���j�ŋL�^�����ꍇ�A�������ʁi14bit �̊K���j�������掿�Ƃ̐����ł��B
�Ȃ��u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�̂�
�X�g���[�g�ȁi�{���I�ȁj�����ɂȂ��Ă��܂���B
���̂悤�ȉɂ��āA����܂ł��̐S�Șb�ɂȂ�Ƙ_�_���Y�����ƌ����Ă����l��
���܂������A�c�O�Ȃ��玄�������v���ł��B
���������u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�Ƃ̖����
�Ȋw�I�������ꂽ���_�ł͂���܂���B
���`��B���Ɏ����ꂽ�Ƃ��Ă��A�����w���w��ł������o���Ȃ��l������Ƃ�����
���ΐ����_�Ȃ݂ɓ���ȗ��_�ɂȂ肻���ł��ˁB
�������������̂́A�������邢�͌o�����ɂ����Ȃ����̂�藝�̂��Ƃ�������̂ŁA
���p�̔������̂��Ƃ������Ƃł��B
�f���ɉ����Ƃ��Ē���A�u���̍l���ʔ����ˁv�ƗL�Ӌ`�ȃX���ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10339667
![]() 1�_
1�_
�ǂݕԂ��ƊȌ��������̂ŕ⑫�ł��B
14bit �̊K���A1200����f�̃J�����`��
�S���̂P�̖ʐςŁA14bit �̊K���A1200����f�̃J�����a�Ŏʐ^���B�����Ƃ��A
�Ȃ����H�J�����`�̂ق������掿�ƂȂ邱�Ƃ�������邱�Ƃ��A
�Ȃ��u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v���̐����ł��B
�����ԍ��F10339720
![]() 0�_
0�_
���[�v�E���[�v����
�@�����s���Ȃ̂����H
�@�u��f�`�v �u�J�����`�v �́A���ꂼ�� �u��f�a�v �u�J�����a�v �ɑ��A���ʂS�{�ł��B
�@���R�A�����ʂ� �u�J�����`�v �� �u�J�����a�v×�S �ł��B
�@����ł������ɍ���Ȃ��ł��傤���H
�����ԍ��F10339724
![]() 1�_
1�_
�s�����w����
��̃X���ɏ����܂����悤�ɃJ�����`�ƃJ�����a��bit�������킹�Ȃ���
�Ȃ��u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v���̐�����
�Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����Z�p���x���Ő�������Ɖ�f�a�̂ق�����f�s�b�`���������߁A���ʂ��Ⴍ�Ȃ�A
�u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�̉��������藧����
�ʔ����Ƃ̂��Ƃł�����^�����܂��B
�܂��A�O�̂��߁A���̓t�H�[�T�[�Y�ƃt���T�C�Y�̉掿���ς��Ȃ��Ǝ咣���Ă���킯�ł�
����܂���B����f���ƍ����x�m�C�Y�ł͖��炩�Ƀt���T�C�Y���D�ʂ��ƍl���Ă��܂��B
�����ԍ��F10339860
![]() 4�_
4�_
���[�v�E���[�v����
�@���S�Ҍ����̐��������������Ǝv���Ă���̂ł����A�S���M���i�݂܂���B
�@�d��������̂ŁA�ȒP�Ƀl�^�����炷�ƁE�E�E
�@Tranquility���� �ɒ������������@�ł����A�J�ɂ��Ƃ��悤�Ǝv���܂��B
�@�u���������v ��ݒ聫�@�i���z�Q�^�R�H�j
�@��ӂ� 10cm × 10cm�A�����͂�����̓s���� 10.24cm �ɂ���Ƃ��v���܂��B
�@�u���������v�� 1024g �i��10bit ���j ����� �i���J�̂Pcc���C�Pg �Ɛݒ�j�B
�@�u�� �� ���v ��ݒ聫�@�i���z�S�^�R�H�j
�@��ӂ� 20cm × 20cm�A�����͓����� 10.24cm �ł��B
�@�u�� �� ���v�� 4096g �i��12bit ���j ������B
�@�u�傫�����v ��ݒ聫�@�i���z�W�^�R �F 35mm�t���T�C�Y�����H�j
�@��ӂ� 40cm × 40cm�A�����͓����� 10.24cm �ł��B
�@�u�傫�����v��16384g �i��14bit ���j ������B
�@�V�C�\��ŁA�J�ʂ����������z�肳���킯�ł��ˁB
�@���邢�́A���̉J���~�葱���Ƃ��A�s���̗ǂ��ݒ������킯�ł���w
�@���R�A�I�[�o�[�t���[�����Ă͈Ӗ����Ȃ��킯�ł����A�����ł� �u���́A���Ԓ��x�Ɏ��߂� �i���O���[�J�[�h�B�ew�j �\�I���� �i���I������w�j�v ��ݒ肵�āA�R��ނ̏��ő��肵�܂��B
�@�R��ނ̏����A���ʂPg �̂͂���ő��肷��ƁA�����J�𑪒肵�Ă��āA�J�ʂ���萳�m�ɑ��肷��̂́A�ǂ�H
�@�����A���͈�ԏ������̂��A��Ԗڂłŏ\���ł�w �i�V�̎ʐ^�������j
�@�ڂ����m�肽���l�́A�u�傫�����v ���g���Ɨǂ��Ǝv���܂�w
�@���������Ƃ͂���̓ǂ݂����āA����������Ȃ� �i���M�m�C�Y�����H�j �Ƃ��A
�@���̍����� 10.24cm �� ISO100 �Ƃ���ƁA�����̍����� ISO200 ���H�@�Ƃ��l����ƁA���\�y�����ł��B
�@���A��A�炵�����������w
�����ԍ��F10340184
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���A���������C�ɗx�炳��Ă܂��ˁB
�����l�ł��B
�ނ��������l����Ђ悤�Ȃ�ĂȂ���ł���H
���́A�����Ȋ��Z�ŁA�S�Ă̖ʂ�u�������Đ����ł���A�ƌ����̂ł�����A���Z�O�̏�Ԃ����ꂱ��l����K�v�͖����̂ł��B
"���Z�ゾ��"���l����悢�̂ł���B"�����Ȋ��Z"�Ȃ�ł�����B
����ȊO��"������Ɍ��������"�͑S���A�b�����Ɋ������߂̃t�F�C�N�ł��B
�Ƃ�����ŁA���Z��̘b�������Ȍ��ɂ܂Ƃ߂�ƁA
�uEF70-200F4LIS�́AEF70-200F2.8LIS���掿�̗��A���s���̃N�Y�����Y�ł���B���[�U�[�����܂����߂����ɗL�郌���Y�ŁA���j�Ə\���قǂ̎��͍��ł���B�v
���Č����Ă邾���ł���B
��L�͔ނ玩�g�̌��t���E���ĂȂ��������ł��̂ŁA�ԈႢ�Ȃ��͂��ł��B
�����ԍ��F10340860
![]() 12�_
12�_
���邩�߂���
�͂��A�䖝�����ꂸ�x�肾���Ă��܂��܂���(^_^;)
�s�����w����
���萔���������悤�ŋ��k�ł��B
bit���̍��͑����ʂ̈Ⴂ�ɂ����ʂ̍���\�����������_�͗������܂����B
�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�ɂ�葍���ʂ��Ȃ킿�A���ʂɍ����ł��A���̂��Ƃ��掿�ɉe����^���Ă���ɈႢ���Ȃ��B���̂��Ƃ��l���邱�Ƃ͖ʔ����Ǝv���܂����A
���́A���ꂪ�L�ӂȂ̂��i�����̎��ۂɂ����ĈႢ������̂��j�ł��B
�d�R�O�Ƃc�V�O�O�̂悤�Ȃقړ���f���̃t�H�[�T�[�Y�@�ƃt���T�C�Y�@��ISO200�ŎB���ׂ�B�i��f�����Ⴆ�Ή𑜓x�ɍ����o��͓̂�����O�����A�����x�m�C�Y�̍��͒N�����F�߂Ă���j
�}�E���g�A�_�v�^�[���g���Γ��ꃌ���Y�ł̔�r���\�����A�X�ɃY�[�������Y�Ȃ��p�����낦�Ă̔�r���\�ł��傤�B
���̏ꍇ�ɒN�����c�V�O�O�̉掿�A�𑜓x�̂ق����D��Ă���ƔF�߂邩�H
�c�O�Ȃ���掿�ɍ��͂Ȃ��Ƃ���l���唼�ł��B
��������_�ł̔�r�ł��菫���A�𑜓x�͂Ƃ������Ƃ��āA�Ⴆ�_�C�i�~�b�N�����W�A���g�r�⍕�Ԃ�A�Õ��̔S��Ȃǂɖ��炩�ȈႢ������ƒN�����F�߂�悤�ɂȂ邩������܂���B
���̂悤�ɂȂ��āu�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�Ƃ̖���̕]������܂�܂ŁA�����Ƃ��Ĕ�������ׂ��Ȃ̂ł́H
�ŏ��ɉ������������l�̐挩�����쐫�̕]���ɕς��͂���܂���B
�����ԍ��F10341275
![]() 3�_
3�_
�r�r�X�X�X����B
�����鐯���߂炳��̎咣���������Ɖ��肵���ꍇ�́A�����̂ЂƂƂ��l���������B
���t���T�C�Y�́u�掿�v���t�H�[�T�[�Y�Ƃ�����ۂ����̈Ⴂ�ł����̂ł����H
��
���́u�掿�v�̈Ӗ����R�����g�ɂ���ĕς���Ă܂�����ˁE�E�E
��������ۂ����̈Ⴂ
��
���ۂ̋@��Ƃ����Ӗ��ł͉���܂��B
�����ɂ̓t���T�C�Y�ƃt�H�[�T�[�Y�ł͋@����K�͂��Ⴄ�̂ɓ����掿�͂ǂ�����Ă������܂���ˁB
�����ʼn]���u�掿�v�́u��p��F�l�Ƃh�r�n�����킹��v�Ƃ����Ӗ��ɖ���ւ���Ă��܂��Ă��܂��B
�Ȃ̂ŕ��ʂɈӖ����ʂ��Ȃ��ē��R�ł��B
���̃X���̖w�ǂ͍ŏ�����c�_�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł��i�j
�u�t�H�[�T�[�Y���Â��v�Ɖ]���̂����t�Ƃ��Č����^���Ă܂����B
���R�̎��Ƃ��āA�Z���T�[���������Ă��I�o�͈Â��͂Ȃ�܂���B
�J�����͎ʐ^���B��ׂ̓���Ȃ̂ŁA�I�o���K���Ȃ�Â��Ƃ͌���Ȃ��̂����ʂł��B
���Z�����l�Ȃ̂��A���t�̑I�ѕ��ɂ͊S�������̂�����܂��E�E�E
�܂��ɒ[�Șb�A�R���f�W�̉掿���D�����Ƃ����l������ł��傤���A����͔ے肳���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����A�D������Ă��܂����ꍇ�ɂ͂����͍s���Ȃ��A�Ƃ����̂�����܂��B
�R���f�W�t�H�[�T�[�Y�t���T�C�Y�Ȃ�ď������݂��Ă��܂��B
�ł����i�Ƃ��Ă̖��͂Ƃ����̂͑S�������̈Ⴄ�b�ł��B
�������肵�đN�₩�Ȏʐ^��ǂ��Ƃ���l�ɂ̓R���f�W���ł����͓I�ł��傤�B
���������l���猩��t���T�C�Y��t�H�[�T�[�Y�Ȃ�Ă��������Â炢�����̕��ɂȂ�܂��B
�t���T�C�Y�Ő�ʊE�[�x����������悤�Ȏʐ^�������Ȃ��ŁA�t�H�[�T�[�Y�͓Ǝ��H���Ŗ��͓I���Ǝv���܂���B
����Ɍ����A�����̓t���T�C�Y�̖��͔͂�ʊE�[�x�̐����ł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă܂��B
�I���̋Z�p�҂������Ă܂����t�H�[�T�[�Y�͌v�Z���ꂽ���ʏo���T�C�Y���Ƃ������Ƃł����B
�R���f�W���y���ɑ傫���Z���T�[�ł���Ȃ��爵���₷���Ƃ����ǂ����Ƃ��ǂ���������������̂��Ǝv���܂��B
�t�H�[�}�b�g�ԂŗD�������Ƃ����A���������u�y�U�v�ɏオ��Ȃ�A����Ȃ�̎������e�[�}�ɂ�����܂���B
�����ԍ��F10341317
![]() 5�_
5�_
���s�̂�������
�u���Z�v�O�̊m�F�ł��̂ŁA�u���Z�v�͂ЂƂ܂������ł��肢���܂��B
>>���̗ʂ͉����ω����Ȃ��ł����
�����Y��ʂ���̗ʂ��đO�u�����Ă܂��B
���̐����ł́A�O�����Y�̏����͕ω����Ȃ��B
�����Y��ʂ���̗ʂ͕ω����Ȃ����Ƃ�������Ă��镔���ł��B
>>���̗ʂ͂��ĕ����������A2�̂ق�����
>>���ł��B
>
>�Ō����Ă邱�Ƃ��������Ă܂��B
����ʐς̈Ⴄ��(A2,A4)��������̗ʂ̘b�ł���ˁB
�ʐψႤ�̂Ŏ�����̗ʂ��Ⴄ�ƌ������Ƃ��m�F���Ă���̂ł����B
�����I�Ɉ��p�����ƈӖ����ʂ�Ȃ��Ȃ�̂ŁA���͂̐擪����ł����
��Ǔ_�u�B�v�ŋ���Ĉ��p���Ă���������ƌ�����������Ǝv���܂��B
���ꂼ��ʂ̘b�����Ă���̂ňꂭ����ɂ��ꂽ��Ӗ����ʂ�܂���B
�ǂ����������Ă���̂ł��傤���H
�����ԍ��F10341322
![]() 2�_
2�_
>�s�����w����
�Z���T�[�ɍ~�蒍�����̗ʁu�̂݁v���掿�����߂�̂ł���A���̎���i�����ǂ������Ƃ��j�͈�؊W�Ȃ��͂��ł���ˁB
12bit��4/3�Z���T�[��8bit��135�Z���T�[�̑Ό��ł�135���K�������ɂȂ�܂����A�������ɂ���͖���������܂��B
�ł����Ȃ����͂����咣���Ă���̂ł��B
���ǁA�Z���T�[�ʐς��L���قǍ���f�ɂ��₷�����A�����f���Ȃ��f�s�b�`���L������Ƃ����A�̂��猾���s������Ă���������O�̌��_�ɗ��������̂ł͂Ȃ��ł����B
>�ʑLj�t����
�����Y��ʂ���̗ʂ������Ȃ�AA4��A2������̗ʂ͓����ł��B
�����ǂ����ŏ������葝�����肷�鎖�͂Ȃ��̂ł�����B
�����AA2�̕������̖��x���Ⴍ�Ȃ�Ԃ�Â��Ȃ�܂��B
�Ǝ˔͈͂������ł�������d���Ŏ�������Έꔭ�ł킩��܂���B
�ǂ܂ł̋����͈��A�d���̖��邳�����A�Ⴄ�̂͏Ƃ炵�Ă���ʐς����ł�����B
�����ԍ��F10341898
![]() 0�_
0�_
�������AA2�̕������̖��x���Ⴍ�Ȃ�Ԃ�Â��Ȃ�܂��B
���Ǝ˔͈͂������ł�������d���Ŏ�������Έꔭ�ł킩��܂���B
���ǂ܂ł̋����͈��A�d���̖��邳�����A�Ⴄ�̂͏Ƃ炵�Ă���ʐς����ł�����B
��
����͑S���Ⴂ�܂���B
�Z���T�[�T�C�Y���������낤���������낤���A�I�o�͈Â��͂Ȃ�܂���B
�����̖��x���Ⴍ�Ȃ�
��
����Ȏ��͂���܂���A����ł͘I�o���Â��Ȃ��Ă��܂��܂��B
�t�ɏ������Z���T�[�͏Ă��Ă��܂��܂���B
����Șb�A�ǂ��ŕ������̂ł����H
�J������͉��N�ł����H
�����ԍ��F10342152
![]() 2�_
2�_
XJR1250����
>�����Y��ʂ���̗ʂ������Ȃ�AA4��A2������̗ʂ͓����ł��B
>�����ǂ����ŏ������葝�����肷�鎖�͂Ȃ��̂ł�����B
>�����AA2�̕������̖��x���Ⴍ�Ȃ�Ԃ�Â��Ȃ�܂��B
>�Ǝ˔͈͂������ł�������d���Ŏ�������Έꔭ�ł킩��܂���B
>�܂ł̋����͈��A�d���̖��邳�����A�Ⴄ�̂͏Ƃ炵�Ă���ʐς����ł�����B
��[�Ǝ˔͈͂�������̂́A����̓����Y���ς���Ă��邱�ƂƓ��ӂł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F10342211
![]() 0�_
0�_
�������݂Ɏ��s�����悤�Ȃ̂ŁB
ISO���x�̕��ˏƓx�ɑΉ��t������`�͌�������܂��A
�ܓV����F8�ŃV���b�^�[���x1/���x�Ƃ����ڈ�����T�Z���܂��ƁA
ISO100�ŁA1��f��������q��10�����x�ɂȂ�܂��B
����́A14�r�b�g�̊K�����ꌅ�����̂ŁA14�r�b�g�ŗʎq�����Ă�12�r�b�g�ŗʎq�����Ă�
�ς��Ȃ��ł��傤�B
�V���b�g�m�C�Y�����ɂȂ�Ȃ����x�ł��B
4�{���x�̉�f�ʐς̈Ⴂ�Ȃǂ��킢�����̂ł��B�R���f�W�����Ă����Ǝʂ�܂�����B
�����I���w�I���E�ɂ͂܂��B���Ă��Ȃ��B
�����A�掿�̈Ⴂ������Ƃ���A����̓Z���T�����̂����ł��B
TRNDYnet��D3s�͌�������Ŏ莝���ŎB���A�Ȃ�Č��o���ł������A
ISO 10���ɂȂ�A���q��100���x�ł��B����ł́A�m�C�Y�܂݂�ɂȂ�A���̓m�C�Y
���_�N�V�����ŃV�O�i�����̂Ƃ��m�C�Y������āA����\�܂ŗ��Ƃ��Ȃ��ƁA������
�����ʂ��Ă���̂����ʂł��Ȃ��摜�ɂȂ�ł��傤�B
ISO 10���Ƃ����͕̂����I���E�܂ŁA�摜�ɂ��܂��A�Ƃ����Ӗ��ł����ˁB
���������0.2���N�X���炢�H�莝���B�e�͖����ł��傤�B
�����ԍ��F10342219
![]() 1�_
1�_
�@���[�v�E���[�v ����A���������悤�Ȏ����l���Ȃ��牽�ł��ȁ[�Ǝv���Ă����̂ł����E�E�E�E
�v���������������Ă݂܂��B�@�܂��A������O�̂��ƂȂ̂ł����A���͍ŏ��@���̎��ɋC���t���܂���ł����B
�@�����̃q���g�ɂȂ�E�E�E�E�E
���d�R�O�Ƃc�V�O�O�̂悤�Ȃقړ���f���̃t�H�[�T�[�Y�@�ƃt���T�C�Y�@��ISO200�ŎB���ׂ�B�i��f�����Ⴆ�Ή𑜓x�ɍ����o��͓̂�����O�����A�����x�m�C�Y�̍��͒N�����F�߂Ă���j
�}�E���g�A�_�v�^�[���g���Γ��ꃌ���Y�ł̔�r���\�����A�X�ɃY�[�������Y�Ȃ��p�����낦�Ă̔�r���\�ł��傤�B
���̏ꍇ�ɒN�����c�V�O�O�̉掿�A�𑜓x�̂ق����D��Ă���ƔF�߂邩�H
�c�O�Ȃ���掿�ɍ��͂Ȃ��Ƃ���l���唼�ł��B
�@����͋ɒ[�ȃ��^�b�`�����Ă��Ȃ����A3�v�����g��20�C���`�ʂ̃��j�^�[�Ŕ�ׂ�Ƃ����ł���ˁB
�@�قƂ�ǂ̐l�����ʂɍs���Ă���ӏܕ��@�Ȃ̂Ł@��r���鎞�̊��Ƃ��Ă͈Ӗ�������Ǝv���܂����A
���ɂ�-6EV�A���_�[�̈Õ���4�i��������悤�ȃ��^�b�`��������A�S���̃|�X�^�[�p�̎ʐ^���B��l�����܂��B
�{���I�ɂ�ISO200�ł��掿�̍��͂������Ǝv���܂��B
�@���Ε����Ō����AISO3200�̉�ł��J�����ɂ��Ă�3�C���`�t�����j�^�[�Ō����瓯���悤�ȉ掿�Ɍ����Ă��܂��H
���c�O�Ȃ���掿�ɍ��͂Ȃ��Ƃ���l���唼�ł��B
�c�O�Ƃ������@�ǂ��炩�ƌ����ƍK�^�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B
���܂���E-1���g���Ă��鎄�Ƃ��ẮB
�����ԍ��F10342547
![]() 2�_
2�_
[10341322]
���Ȃ������ւ̉� [10338386] �ŏ����Ă��܂��B����ɂ��Ă킩��Ȃ����ƁA�^��Ɏv�����Ƃ�����܂��ǂ����B
�u�g���~���O���Ă����邳�͕ς��Ȃ��v�́u�g���~���O���Ă��掿�͕ς��Ȃ��v�Ƃ����_�@�ƈꏏ�ł��B
����ƁA�����̐l�����藐��Ă�̂ŁA���X�A���J�[�i���X�ԍ��j���Ă��炦��Ɣ�т₷���ł��B
�����ԍ��F10342721
![]() 1�_
1�_
[10342219]
��f�s�b�`�ƌ��q���̊W�ɂ��Ă� [10289993] �ɂ܂Ƃ߂Ă���܂��i�v�Z�Ⴂ���邩������Ȃ��̂ŁA���̂�������������ł����j�B
�����������̎��𐳂����Ƃ���ƁAD3s �� ISO102400 �̈��f�̌��q���́u29�v�ł��B
8bit�摜�ɂ����� 18%�O���[�́i�K���}��O�̌��́j���x���� 46 ���炢���������ȁH ����Ȃ���ł��i���Y�^�ɂ��鎮�Ōv�Z�ł��܂��j�B
�܂� D3s �� ISO102400 �́u�K�v���x����菭�Ȃ����q���ʼn摜�����Ă���v�킯�ŁB������Ɩ�������Ȃ����Ǝv���킯�ł��B
�L���m���� 1DMark�W �� ISO102400 �����l�Ɍv�Z����Ɓu���q�� 12.9�v�ł��i����͂����Ɩ����j�B
���̏ꍇ�͎��̌v�Z����p�����Ƃ��A�t�H�[�}�b�g�T�C�Y�䁁1.29 ��p���āA
(3/4)*29*(1/1.29^2) = 13
�Ƃ��Ă������͏o�܂��B3/4 �͉�f���� 12M/16M �̂��Ƃł��B
�Ȃ��t�H�[�T�[�Y 12M�@�̏ꍇ�́i���ZISO���x���g���ājISO25600���Ɍ��q���u29�v�Ɓi�v�Z���Ȃ��Ă��j�킩��܂��i�A�X�y�N�g��̈Ⴂ�ɂ��덷�����j�B
ISO102400���ł���i1/4�{�ɂ��āj�u7.25�v�Ƃ킩��܂��B
�����ԍ��F10342911
![]() 0�_
0�_
����ʂ̖ʐςɂ���ē����錋�ʂ��Ⴄ�Ƃ����̂͂킩��܂����A
���ꂪ���Ȃ킿�����Y���Â��ƌ����͈̂Ⴄ�Ǝv����ł����ˁB
�����̊m�F�������������̂ł����A�킩��Ȃ����Ȃ��������Ȃǂ�
����ꂻ���Ȃ̂őގU�������܂��B
#�킩��Ȃ����������ł��Ȃ��̂͌��ǁA�������Ă���{�l�����܂�
#�����ł��Ă��Ȃ����Đ̂̉��t�ɋ����܂������A�����������܂����B
�ł͂ł�
�����ԍ��F10343027
![]() 4�_
4�_
�ʑLj�t����
�Ǝ˔͈͂̓C���[�W�T�[�N���ƍl���Ă��������B
�����Y�ɑ�������̂́A���̏ꍇ�d���ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F10343072
![]() 0�_
0�_
[10343027]
>�����Y���Â��ƌ����͈̂Ⴄ�Ǝv����ł�����
�u�����Y���Â��v�ł͂Ȃ��A�u�����Y�X�y�b�N�����Z�����ꍇ F�l�͓�{�ɂȂ�v�ł��B
�u�t�H�[�T�[�Y25mm F1.4�v���t���T�C�Y���Z����Ɓu50mm F2.8�v�ł��B
����Ȍ�����������u�œ_�����͓�{�ɐL�сAF�l�͓�i�Â��Ȃ�v�݂����Ȋ����ł��B
�����ԍ��F10343131
![]() 1�_
1�_
�� EF70-200F4LIS�́AEF70-200F2.8LIS���掿�̗��A���s���̃N�Y�����Y�ł���B
�� ���[�U�[�����܂����߂����ɗL�郌���Y�ŁA���j�Ə\���قǂ̎��͍��ł���B
EF70-200/4LIS�̌��a�A�d���A�l�i�Ƃ��Af/2.8����i���i�����j�ł��̂ŁA
���^�y�ʂ≿�i�d���̂��q������I�����₷���ł��B���̃��x���̃��[�U�i���S�`�����j��
���^�y�ʂ≿�i�d���ł�����A4/3��I�Ȃ������ǂ��ł��傤�B
�������A35�~�����ɂ́A�J��f/5.6��Af/7�Af/8�̃����Y������܂���A
4/3��f/2.8�Af/3.5�Af/4�Ɠ����g���邢�h�����Y���d������Ȃ�
4/3�Ƃ����I��������܂��B�}�C�N��4/3�̓o�ꂩ���4/3�̈Ӗ����w�ǂȂ��Ȃ�܂����B
����Ă���Ȃ��ł����A35�~������f/5.6-7�̃����Y���������A
ZD14-54/2.8-3.5���͏��^�y�ʂł���Ɛ������܂��B
�����ԍ��F10343138
![]() 0�_
0�_
�P���Ɍv�Z���܂��ƁA12�r�b�g�ŁA�m�C�Y�Ȃ��i0.5��菬�����j�̏����́A
��(���d�q��) �� 2^13 �Ȃ킯�ł����A���d�q����6700���ȏ� �{ �����ȏ������K�v�ł��B
JPEG��8�r�b�g�ł��ƁA26���܂Œl�������Ă���܂����AD3�̖O�a�d�q����6.5����ł��B
�t�Ɍv�Z���܂��ƁAD3���m�C�Y�Ȃ��̎ʐ^���B�������́A
JPEG �� 300����f�A12�r�b�g �� 1.2����f�A14�r�b�g �� 740��f�ł��B
E-300��E-400��2.5���ʂŁA�R���f�W�͈ꖜ�����������Ǝv���܂��B�����͕K�v���܂���B
�Ȃ��Ȃ畽��5�i�̍�������܂�����A�R���f�W��ISO100�ł��AISO3200�����ɂȂ�܂��̂�
����ȂɌ��d�q���W�߂�킯������܂���B
�����ԍ��F10343254
![]() 0�_
0�_
1-300������
�����ʂ̍������炩�̌`�ʼn掿�ɉe����^���Ă���Ƃ̍l�����͖̂ʔ����Ǝv���܂����A
�u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�Ƃ̖���ɂ͔��̗���ł��B�o����A�����ł��Ȃ�����ł��B
���͂��̃X���ɏW���l�X�́A���Ԉ�ʂł̓J�����܂��͎ʐ^����Ƃ������Ȑl�B�ł���A�i���q�J���̑䓪�łق̂��ɗ���̉��P�������܂����E�E�E)�A
������S�����Ɠ����x���ƍl����ׂ��ł��傤�B
���̓��D�̎m�ǂ����ōl���̎咣�̎d���ŕs�тȂ������������Ȃ����ǂ��̂ł͂Ǝv���܂��B
���鐯���߂炳��
���[���A�܂��B
���Ȃ��̃J�L�R�͂��Ȃ��̍l���錋�_�݂̂��q�ׂāA�������ȗ�����X��������܂��B
�u�����ʂ��邢�͑��G�l���M�[���ʐ^�̉掿�A�𑜓x�����߂�v�Ƃ̎咣�ɂ͓��ӂł��܂��A���Ȃ�����J�L�R�������ł��B
���������咣�̎d�����l���܂��H
�����ԍ��F10343271
![]() 5�_
5�_
�� �o����A�����ł��Ȃ�����ł��B
�ǂ�Ȍo�����ꂽ���Ǝv���܂����A���̎������ĉ��ł��傤�B
�� �咣�ɂ͓��ӂł��܂���
��������������ł��ˁB���O�̌������͕ʂɋC�ɂ��܂���B
�ꐶ���������Ă���ł��A�{���͕������Ă���Ă�ƌ����S������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F10343411
![]() 0�_
0�_
�܂����鐯���������Ȃ��Ƃ������Ă܂��ˁB
������ł��܂���B
�����ԍ��F10343426
![]() 15�_
15�_
�V���b�g�m�C�Y�ȊO�A�d�C�Ȃǂ̌������傫���Ǝ咣����������܂��B
��������i����������掿�̍����w�ǎc���Ă܂���B����̓V���b�g�m�C�Y�ȊO��
�S�Ă̌����̑��v�ɂȂ�܂����A�ǂꂪ�傫���̂��ȒP�ɕ�����ł��傤�B
���Ȃ݂ɁA1�`2�b�ȏ�̒��b���I�o�ȊO�̃m�C�Y�̖w�ǂ͓Ǐo�m�C�Y�ł����A
���d�q�P�ʂŌ����܂��ƁA��b���x�̎��ɁAAPS-C��10�`20�O��A35�~������20�`30���
4/3��10�O��Ǝv���܂��B10�̓d�q�ƌ����A�l�I�����q����ł��B
�����ԍ��F10343448
![]() 0�_
0�_
�����Y�����邭�Ȃ�������Ȃ��ƐM�����Ă��鎞�_�ŁA�����ˁA���S�Ɋ�Ƃ̎v�f�Ƀn�}���Ă����ł���B
���ł������邢�i�����j�����Y������Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ������ǁA�Â������Y�̓A�N���o�e�B�b�N�Ȑv�Ȃǂ��Ȃ��Ă��A�����������Ɉ��肵�����w���\����ɓ�����܂��B
�n�܂�́A���[�J�[���}�X�R�~�ɍL������Ăł����グ�����l�ςƂ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
���Â��G���g���[�ł���A���݂ł͂��������l�ς��ς���Ă��Ă��邯��ǁA���LURL�̃u���O�̓��e�́A�ʐ^�Ƃ͂Ȃ�Ƃ����Ƃ�����A�u�����Ɓv�ʐ^���B���Ă����l�������ɕ\�����Ă���̂ŁA���ɋ≖�J�����̒m����o�������Ȃ��l�ɂ͓ǂ�ł��炢�����B
http://alao.cocolog-nifty.com/the_eye_forget/2005/09/post_96fb.html
�����ԍ��F10348291
![]() 3�_
3�_
���邹���J��������ɂ�������������ł�����
���V���b�g�m�C�Y���Ă����̂́A����̂ł̌���߂炦������̗ǂ������ɂ����
��������݂�������
�Ǝv���̂ł����@����̂Ɍ����W�߂�@�����Y��@���[�p�X�t�B���^�[�Ȃǂ�
�����ɉe���͂���̂ł��傤���H
�����ԍ��F10357900
![]() 0�_
0�_
�� �Â������Y�̓A�N���o�e�B�b�N�Ȑv�Ȃǂ��Ȃ��Ă��A�����������Ɉ��肵�����w���\����ɓ�����܂��B
���X35�~�����ł������a�����Y�������ł��i�A�o�E�g�ň�i�Â��A��i�����j�B
ZD�̏ꍇ�A��i�Â��A��i�����ł��̂ŁA�������\��35�~���������Y����i�����Ȃ��Ă܂��B
�� �n�܂�́A���[�J�[���}�X�R�~�ɍL������Ăł����グ�����l�ςƂ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
���ہAE-P1�ł��AGF1�ł��听���ł��ˁB�������ʘ_�ł����A�������Ă�ȏ�ǂ������ƌ�����������܂���B
�����ԍ��F10358000
![]() 0�_
0�_
�� ����̂ł̌���߂炦������̗ǂ������ɂ���Ĕ�������݂������̂Ǝv���̂ł����A
�����ł͂Ȃ����X������̂ł��B�������g����߂炦������h�̉e�����傫���ł��B
�����Y�̏ꍇ�Ɍ��a�ȊO�́AF�l��T�l���������𑽏��e�����܂����A����T�l���w��
�g���Ă܂���̂ŁAF�l�ł��\�����p�ł���ƌ������P�ł��B
�Z���T�[�̏ꍇ��QE���ƌ����̂�����܂����A����͐����d�v�ł��B
�������A����̓Z���T�[���[�J�[�̋Z�p�\�̖͂��ŁA�t�H�[�}�b�g�Ƃ͕ʂł��B
�P���̌��d�q�ϊ��ƁA���̑O�̃}�C�N�������Y�܂łƁA���̌�̓d�C�����̈ꕔ���܂߂�
����QE��������Ǝv���܂��B�}�C�N�������Y�̉��P���痠�ʏƎ˂͂��̑O�̕����ŁA
�e��p�^�[���m�C�Y�͂��̌�̕����ł����A���ۉ摜���番����̂��A�����̕��ł��B
�L���m���̐�`�ł́A50D���A7D�����P�ł����ƌ����܂��B
���[�J�[�̋Z�p���x���͔g������܂����A���ϐ����̍������Ȃ��ł��B
���Ȃ��Ƃ����̓L���m���A�\�j�[�A�p�i�̌�O�ƁH���قړ������x�����Ǝv���܂��B
�������Z���T�[�ق�QE���������i�܂�4/3���s���j�ƌ����܂����A���ۂ͂���قǂ�
��������܂���B�����Ȃ��Ǝv���Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�R���f�W�̃m�C�Y�]����
����i�m�C�Y�������x�����j�Ǝv���܂����A�ܒi�i�O�\�{�j���Ⴄ�J�����ł�����
�����́g�s�O�h���o��ł��傤�B
�����ԍ��F10358054
![]() 0�_
0�_
�@
���鐯���߂炳��̃��X���
��ZD150/2.0�́A300/4�����ȃ����Y�ŁA328����i�Â��Ȃ�܂��B
��f/2.0�ł���̂́A�ԈႢ�܂��A�B�����ʐ^��������A
��35�~������f/4�Ɠ������ʂ��������܂���Af/4�����ƌ����܂��B
���J�����͎ʐ^���B�铹��ł��̂ŁA�����܂ŎB��ꂽ�ʐ^�Ŕ��f���錋�ʘ_�ł��B
�@------------------------
�{����ZD150/2.0�ŎB�����ʐ^�Ɠ������̂�300/4�ŎB���ł��傤���H
�����X�|�[�c���̂��Ղ�A�o���G���\��A�Â��������œ��������B��Ƃ��܂��B
F2.0�AISO3200�ł��肬��~�߂�ꂽ��ʂŁA�V���b�^�[���x��2�i���x��F4.0�Ŏ~�߂���ł��傤���B
��ʑ̃u���������܂��ˁB
���k���̎B�e�ł��A2�i�x���Ɛ��̗����͓����Ɍ����Ȃ��ł��ˁB
�܂蓯���ʐ^�͎B��Ȃ��B�������ʂ͓����Ȃ��̂ł��B
�J�����͎ʐ^���B�铹��B�����܂ŎB��ꂽ�ʐ^�̌��ʂŔ��f����Ƃ������Ƃł�����
�t�H�[�T�[�Y��F2.0�̓t���T�C�Y��F4.0�ɑ������Ȃ��Ƃ������_�ł��B
�����ԍ��F10359839
![]() 3�_
3�_
�� F2.0�AISO3200�ł��肬��~�߂�ꂽ��ʂŁA
�� �V���b�^�[���x��2�i���x��F4.0�Ŏ~�߂���ł��傤���B
�� ��ʑ̃u���������܂��ˁB
����͈Ⴂ�܂��BM���[�h�œ�������F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�ŎB��̂ł��B
����ɍ����āAISO�͎����Ƃ��K���ł���Ηǂ��ł��B�f�W�J����ISO�̓C�}�C�`
�M�p�ł��܂��A4/3��3200�̉掿�́A35�~������12800�̉掿�Ɠ����Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F10359872
![]() 0�_
0�_
���鐯���߂炳��A���肪�Ƃ��������܂��B
�\�z�ʂ�̂��Ԏ������������܂��āA���ꂵ���v���܂��B
�܂�F�l�����������A���x���グ��ƌ������Ƃł��ˁB�@(*^^)v
�����ԍ��F10360051
![]() 3�_
3�_
�≖�ł������ł����AF�l�ƃV���b�^�[�ŒP�ʖʐς̘I�o�ʂ����߂܂��B
�Ⴆ�A�X�|�[�c���B�鎞�Ɏ��O�ɕK�v�ȃV���b�^�[�ȂǘI�o�ʂ�������܂�����
���̘I�o�ʂɉ����ăt�B�����̊��x��I�Ԃ킯�ł����A���������t�B�����̊��x���ς��Ă�
�I�o�ʂ��ς�킯�ł͂���܂���B�����܂ŗ^����ꂽ�I�o�����ōőP�Ȋ��x��I�Ԃ̂ł��B
�≖�ł͋Z�p�̐����ŁA��Ƀt�B�����U���Ă���ʐ^���B��葱��������܂����A
�ʐ^�̍l���Ƃ��ẮA���x����ɂ���킯�ł͂���܂���B
�����ԍ��F10360248
![]() 0�_
0�_
>���ہAE-P1�ł��AGF1�ł��听���ł��ˁB�������ʘ_�ł����A�������Ă�ȏ�ǂ������ƌ�����������܂���B
���ɔے�͂��܂��A�������_�ŁA�t���T�C�Y�Ƃ������i���܂�܂Ə悹���Ă���̂ł��B
�����ԍ��F10361023
![]() 5�_
5�_
�N���w�E���܂���̂Łc
>> F2.0�AISO3200�ł��肬��~�߂�ꂽ��ʂŁA
>> �V���b�^�[���x��2�i���x��F4.0�Ŏ~�߂���ł��傤���B
>> ��ʑ̃u���������܂��ˁB
>����͈Ⴂ�܂��BM���[�h�œ�������F�l�A�����V���b�^�[�X�s�[�h�ŎB��̂ł��B
>����ɍ����āAISO�͎����Ƃ��K���ł���Ηǂ��ł��B�f�W�J����ISO�̓C�}�C�`
>�M�p�ł��܂��A4/3��3200�̉掿�́A35�~������12800�̉掿�Ɠ����Ȃ̂ŁB
�掿�̍������鐯���߂炳��̌����Ƃ��肾�Ƃ��āc
4/3��F2.0�iF4.0�����H�jISO3200�œ����掿�ɂȂ�̂Ɠ����V���b�^�[�X�s�[�h�邽�߂ɂ́A35mm�t���T�C�Y�ł�F4.0�Ŋ��x��ISO12800�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB
���x���グ�Ȃ�������Ȃ��̂ŁA��͂�uF4.0��F2.0���Â��v�ƌ������Ƃ��ł����ł��B
���͂̑g�ݕ��ŁA�����悤�ɂ��������Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ̏ؖ��ł��B
�u���邢�E�Â��v�Ƃ������t�̊Ԉ�����g�����A�����������߂܂��H
����Ɓu����F�l�v�Ƃ������������B�u2�i���Ⴄ�v�ł����̂ł́B
�����ԍ��F10363097
![]() 3�_
3�_
�ςȕ��͂ł����B���݂܂���A�C���ł��B
4/3��F2.0�iF4.0�����H�jISO3200�Ɠ����V���b�^�[�X�s�[�h�邽�߂ɂ́A35mm�t���T�C�Y��F4.0�ł͊��x��ISO12800�ɂ���K�v�������āA����ł���Ɠ����掿�ɂȂ�Ƃ����킯�ł��ˁB
���x���グ�Ȃ�������Ȃ��̂ŁA��͂�uF4.0��F2.0���Â��v�ƌ������Ƃ��ł����ł��B
�����ԍ��F10363448
![]() 4�_
4�_
��4/3��F2.0�iF4.0�����H�jISO3200�Ɠ����V���b�^�[�X�s�[�h�邽�߂ɂ́A35mm�t���T�C�Y��F4.0�ł͊��x��ISO12800�ɂ���K�v�������āA����ł���Ɠ����掿�ɂȂ�Ƃ����킯�ł��ˁB
���Z���x�̏��o�ł��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490811103/SortID=9469167/#9511752
�����ԍ��F10363539
![]() 0�_
0�_
���ƁA���̑O����ǂ�ł����Ƃ����Ǝv���܂��B
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9514873/#9515266
�����ԍ��F10363563
![]() 0�_
0�_
�� ��͂�uF4.0��F2.0���Â��v�ƌ������Ƃ��ł����ł��B
�ʐ^�����ĒP�ʖʐς������������ʂ�ł��ˁB
�����ԍ��F10364956
![]() 0�_
0�_
���������A
���l�u�r��_��ŁA
���l�̉����c���A��_���̊O��ɏ�荞��ŁA
�����̑I��̔N���4�{�Ⴄ����A��͂�2�i�Ⴄ�B
�Ƃ�邩�炱��ȂɃX�����L�т�Ǝv���܂��B
�ŏ����玩�R�̉����ȂŁA������2�i����͂�����ƌ����A
�������ˁA�ŏI���b�B
�܂��A�͂Ȃ���X�|�[�c���ϐ킷��i�ʐ^���B��j����ł͂Ȃ�
�쎟�����̂��ړI�Ȃ�A�听���Ȃ�ł��傤���ǁB
�����ԍ��F10375389
![]() 3�_
3�_
�s�����w����
������EP-1�̃X���ł���ȏセ�̑��ʂ͂���̂ł́H
�����炢��ʔ�������ʂ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�Ȃ�A���t�J�������ׂĂ̔ŁA
�S�t�H�[�}�b�g��Ώۂɂ����ق����A
�w�p�I�ɂ��傢�ɉ��l������Ǝv���܂����H
���������̍ۂ̓t�H�[�}�b�g�Ȃ̂��A�����Y�Ȃ̂��_�_���i�����ق����A
��艿�l��������̂ɂȂ�Ǝv���܂��B
���l�t�H�[�T�[�Y����ʊE�[�x���[���A�����x�m�C�Y����������
�ʂɈ٘_�͂���܂���̂ŁB
�����ԍ��F10376002
![]() 5�_
5�_
�����@EP-1���I�����p�X
�����ԍ��F10376023
![]() 0�_
0�_
�ő�KID����
�@����������̂ƁA���̂������͕̂ʂ��Ǝv���̂ŁA���̕ӂ͍l���Ă������������ł��B
�@���鐯���߂炳�ǂ������Ă��A�����c�̑������̏�������ẮA�����c�̕i�i������܂��B
�@�S�s�ڈȌ������ƁA�ő�KID���� �Ǝ��͂قƂ�Ǔ����l���Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�@�����A���������������Ƃ� �w�p�I���l �Ȃ�Ă���܂���B�@��ʏ펯�ł��B
�@��{�I�ȂƂ���ŁA�u�����̏����v�H�v �Ƃ��v�����Ƃ����邾���ł��B
�����ԍ��F10376097
![]() 0�_
0�_
���́E�E�E������ǂ�œ��̒��œW�J����̂��h����ł����A�����Ă��邱�Ƃn�I�ɏ����Ƒ�̂���Ȋ����ł��傤���H
�E�f�q���傫�������掿�������͓̂�����O�A������v���݂͂�ȃt���T�C�Y�ł���B
�E�t���T�C�Y�͐F�X�ȖʂŗZ�ʂ������̂Ŗ��\�A�����������Ăł����B
�E�t�H�[�T�[�Y�̓����Y�̐��\���������߁A�o�ė����͊��Ɨǂ��Ă܂�ł��Ȃ��B
�����ԍ��F10385204
![]() 3�_
3�_
�� �f�q���傫�������掿�������͓̂�����O
�f�q�̃T�C�Y���A�����Y�̌��a�ł��ˁB
�� �t�H�[�T�[�Y�̓����Y�̐��\���������߁A
4/3�����Y�̐��\���������ǂ����͕�����܂���B������R���f�W�̃����Y���ǂ��ł��B
�����a�ł���Έꕔ�̎��������Ȃ��Ȃ�܂��B�I�o�Ɋ֘A����掿�͌������Ȃ�܂����B
�����ԍ��F10385229
![]() 0�_
0�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�f�W�^�����J���� > �I�����p�X�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 7 | 2025/11/24 12:14:56 | |
| 3 | 2025/11/22 23:15:07 | |
| 6 | 2025/11/22 21:33:33 | |
| 0 | 2025/11/06 18:38:03 | |
| 11 | 2025/10/21 21:21:58 | |
| 7 | 2025/10/19 17:57:13 | |
| 8 | 2025/10/11 14:18:49 | |
| 2 | 2025/09/25 10:14:53 | |
| 22 | 2025/09/23 22:17:25 | |
| 30 | 2025/09/04 23:02:11 |
�u�f�W�^�����J���� > �I�����p�X�v�̃N�`�R�~������(�S 366901��)
�N�`�R�~�f������
�œK�Ȑ��i�I�т��T�|�[�g�I
[�f�W�^�����J����]
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�������߃��X�g�z�ьN�������ߗpPC���X�g
-
�yMy�R���N�V�����zwindows11�ɑΉ��ōw��
-
�y���̑��z���_�p�H
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�J�����j
�f�W�^�����J����
�i�ŋ�3�N�ȓ��̔����E�o�^�j