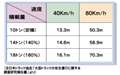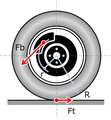96km/h����t���u���[�L�B1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B
https://youtu.be/MRxr757Q9nk?t=211
����͌��̉d�����ŁA���A�^�C���ƃu���[�L�̎d���ʂ�����������H�Ȃ��ӊO�Ȍ��ʂł���ˁB
�����ԍ��F25923955�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ʂ͉^���G�l���M�[�͑��x�ɔ�Ⴕ�đ�����̂Ő������������������Ȃ����ǁA�ς��Ȃ��Ȃ�āA�u���[�L����̉��b�Ȃ�ł��傤���ˁH
�����ԍ��F25923965�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
EBD�i�d�q���䐧���͔z���V�X�e���j�̂������ł��傤
�����ԍ��F25924006
![]() 4�_
4�_
�����ł��A�d�ʂɔ��A���x��2��ɔ��ł����B
���炵�܂����B
�����ԍ��F25924043�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���R�z�@���Y����
���������̊ȈՌv�Z���ɏd�ʂ̕ϐ��͊܂܂�܂���̂ŗ��_��͉d�Ɩ��W�ł��B
https://mathwords.net/teisikyori
ABS��쓮�A�߉d�Ŗ����ꍇ�̎��ۂ̐��������ϓ�(�Ώ�����E�ו���)��5�|10%���x�Ƃ���܂��B
�����ԍ��F25924063
![]() 2�_
2�_
���R�z�@���Y����
���C�͂́A���C�W���Ɖd�ɔ�Ⴕ�܂��B
https://wakariyasui.sakura.ne.jp/p/mech/masatu/masaturyoku.html
���C�W���������Ȃ�A�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA���_�I�ɂ͎ԏd���ς���Ă����������͓����ł��B
�^�C���̏ꍇ�̓S������ꂽ�肷��̂ŁA������ƈႤ�悤�ȋC�����܂����B
�����ԍ��F25924117
![]() 2�_
2�_
���R�z�@���Y����
����Ԑl���������Ă����������͓���
��^�g���b�N�ł͋�E��i�d�ʁE1.3�{�d�ʂł͑啝�ɈႢ�܂�
���ʎԂŃu���[�L���}�j���A���Ȃ�ΈႢ�͂���̂ł�
�����ԍ��F25924131
![]() 1�_
1�_
�m���ɉݕ��Ԃł͑����Ⴄ��ˁB
�y�g�������ċ�ׂ̂Ƃ��ƁA�ו��ύڎ����ᐧ�������͈Ⴄ���B
�����ԍ��F25924148
![]() 1�_
1�_
�����́i���x�E�d�ʁj�Ɛ����́i�u���[�L���\�j�Ɩ��C�́i�d�E�^�C�����\�E�H�ʁj�̃o�����X�ŕς���Ă��邩�ƁB
�����ԍ��F25924230�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��BREWHEART����
������̃T�C�g�ʼn��������܂����B
�u���͂���ǂ����邽�߁A��������������������ʓ��i���f���z�F1.5�`2%�j�ŁA���ꂾ���̐������܂�̂́A�����̑�J�̂Ƃ��ł��傤�B
�Ȃ�����Ȃɂ����I�ȏ�ԂŎ����������ƌ����A���ꂮ�炢���Ȃ��Ɛ��������ɍ����o�Ȃ���������ł��B
�����āA�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɂ��ꂾ���������荞�߂A���������ɍ����o��͓̂��R�̎��ł��傤�B
���̂Ȃ�A�^�C���ƘH�ʂ̊ԂɈقȂ镨�������݂���̂ł�����A���C�͉͂d�ɔ�Ⴗ��Ƃ����W������邩��ł��B�v
https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette
�����ԍ��F25924241�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
1. ���������̌���
��������d��(�ȗ���)
d=v^2/ 2��g
v: �����x
��: ���C�W��
g: �d�͉����x
���������͑��x�ƘH�ʏ�ԂɈˑ����邪���ʂɂ͒��ڈˑ����Ȃ��B
2. �ԗ����ʂƐ�������
�u���[�L�́F�d��������Ǝԗ��̑����ʂ����������ɖ@���́i�^�C����H�ʂɉ����t����́j��������̂Ő����͎͂��ʂɉ����đ������A���������������ێ�����悤�ɓ����B
�����F�ԗ����d���Ɗ������傫���Ȃ��~����̂ɕK�v�ȃG�l���M�[���傫���Ȃ�B �������u���[�L�V�X�e���͐������ŗl�X�ȉd�ɑΉ��ł���悤�ɐv����Ă��Ĉ�ʓI�ȉd�����ł͐��������ւ̉e�����ʏ�قƂ�ǖ����B
3. �d�̎��ۂ̉e��
�d�̑����F�����̏ꍇ��q�̐l���𑝂₵�Ă����C���������邽�ߐ��������ւ̉e���͔�r�I�������B �����̑����ɂ�萧���������킸���ɐL�т�ꍇ�ł��W���I�ȕ��ׂȂ猀�I�ȉe���͂Ȃ��B
�ɒ[�ȕ��ׁF �ԗ����v���E���ĉߐύڂ���Ă���ꍇ�̓u���[�L�V�X�e�����\���ȗ͂��������������������啝�ɐL�т�\��������B �܂��ߐύڎԂ̓u���[�L�t�F�[�h���������u���[�L�������ቺ����\��������B
�����悻�̕ω�: �u���[�L�V�X�e���̓t���ύڎԂ̓T�^�I�ȏd�ʔ͈͂ɑΉ�����悤�ɐv����Ă���̂ŁA��ʓI�ȏ�Ԓ���̏ꍇ�Ƀu���[�L�V�X�e�����K�ɋ@�\���Ă���Ȃ琧�������̑�����5�`10%���x�ɂƂǂ܂�B
�T�X�y���V�����ƃo�����X�F �d���d�͎ԗ��̃o�����X�ƃT�X�y���V�����ɉe�����A�^�C�����H�ʂƂ̌��ʓI�ڐG�ێ��ɉe������~�����������Ȃ�\��������B
�^�C�����\�F ���ׂ�������ƃ^�C���̈��͂������Ȃ�H�ʂƂ̐ڒn�ʂɉe����^����\�������邪�A�ʏ핉�ׂł̉e���͌y���B
�����ԍ��F25924255
![]() 2�_
2�_
���������̒Z�k��ǂ��l�߂�ƎԂ�F1��o�C�N��MotoGP�݂����ɁA
�n�C�O���b�v�^�C���i�ƒǂ����u���[�L�V�X�e���j�ƁA�G�A���p�[�c�ł̃_�E���t�H�[�X�ł��ˁB
F1�͂������ł��傤���A�ߔN�̃o�C�N���E�C���O�������ď]�����y���ɑ̂ɑ傫�ȕ��S��������悤�ł��B
������O�̎��ł����A���ʂ̐l�����ʂɎg����蕨�͓������x��ڎw���č���Ă���ƌ��������ƁB
�����ԍ��F25924285
![]() 1�_
1�_
�^�C�����{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�
�{�͑��u���{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�
�p�b�h�A�f�B�X�N�@���{�g���l�b�N�ɂȂ�̂��@���Ď��ł��傤
����^�C�����{�g���l�b�N�ɂȂ��Ă����Ȃ�
�d�����Ł@���̌��ʂɂȂ����̂ł��傤
�}�X�^�[�o�b�N�s����������
�p�b�h�A�f�B�X�N�e�ʕs���Ȃ��������ʁ@�@�g���b�N�̃t���ו��ŐL�т�
�ɂȂ����ł��傤
�����ԍ��F25924291
![]() 2�_
2�_
����MOON����
����^�g���b�N�ł͋�E��i�d�ʁE1.3�{�d�ʂł͑啝�ɈႢ�܂�
100%(���)�A140%�A180%�̐ύڗʂł��Ȃ�ς��܂��ˁB0%�A50%�łǂꂾ���ω����邩�C�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25924662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���R�z�@���Y����
��̕��̐l�̗����ł́A0����100���ł��A���������قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�����ǁA��Ȃ������Ȃ��悤�ȁB
�����ԍ��F25924925�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��������������d=v0^2/2��g�͕����@���Ȃ̂Œn����̒N�������ł���Ă������B���Z�����B
���̕������ŏ����x�����܂�Ύc��ϐ��͖��C�W���̂݁B
���̎��͎ԗ��d�ʕω��Ő����������ω����闝�R�͖��C�W�����ω����邽�߂Ǝ����Ă��āA�ω��̒��x�͂��̎Ԃ̐����n�̐v����B
�S�d�ʔ͈͂ɑ��ēK���ɐv���ꂽ�����n�i�������d�ʕω��ɂ��^�C���̕ό`�Ȃǂ��܂ށj�ł���ΐ������̖��C�W���̕ϓ������Ȃ��̂ŁA����Đ��������̕ω����������B
1. ��{�I�Ȓ�`�Ɖ���
- ���������id�j�F �u���[�L����������A�ԗ������S�ɒ�~����܂ł̋����B
- �����x�iv0�j�F �u���[�L�������钼�O�̎ԗ��̑��x�B
- �ŏI���x�iv�j�F �ԗ�����~�����Ƃ��̑��x��v=0�ƂȂ�B
- �����x�ia�j�F �u���[�L�ɂ�錸���x�i���̉����x�j�B
- ���C�W���i�ʁj�F �^�C���ƘH�ʂ̖��C�B
- �d�͉����x�ig�j�F �d�͂ɂ������x�Ŗ�9.8m/s2�B
��C��R�₻�̑��̗v���͖����ł����H�͕��R�ł���Ɖ���B
2. �j���[�g���̑��@���F
�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂��Ԃ�����������B �j���[�g���̑��@���ɂ���
;F=ma
������F�͗́Am�͎Ԃ̎��ʁAa�͉����x�i���̏ꍇ�͌����x�j�B
���C�͂́F
Ff=��N
�����Ńʂ͖��C�W���AN�͖@���́B
���R�ʂł�N=mg��m�͎ԗ��̎��ʁAg�͏d�͉����x�B
���������āA���C��Ff��
Ff=��mg
���C�͂��j���[�g���̖@���iF=ma�j�̌����͂Ɠ����������
ma=��mg
������
a=��g
����́A������a���^�C���ƘH�ʂ̖��C�Əd�͉����x�Ɉˑ����邱�Ƃ������B
3. ���������̉^���������F
�������������߂�ɂ́A�����A�I���A�����x�A�������W�t����^�����������g�p�F
v^2=v0^2+2ad
�ԗ��͒�~����̂�v=0�����琧������d��:
0=v0^2+2ad
d=-v0^2/2a
a=-��g�Ȃ̂�
d=v0^2/2��g
���̎��͗��z�I�ȏ����i���̌����x�A�^�C���̃X���b�v���Ȃ��Ȃǁj�Ȃ̂ŁA���ۂ̌��ʂ̓^�C���̏�ԁA�u���[�L�����A�H�ʁA�d�ʔz���Ȃǂ̗v���ɂ���ĈقȂ�ꍇ������B
https://yama-taku.science/physics/linear-motion/motion-of-uniform-acceleration/
�ȏ�A�ׂ��ȓW�J�Ń~�X�^�C�v�Ȃǂ�����߂�B�ŏI���W�J���@�͐������B
�����ԍ��F25924998
![]() 3�_
3�_
��SMLO&R����
�����ł�����Ƌ^��Ȃ�ł����A
ma=��mg�ŁAa��g�����ɏd�͂̉����x�ł��̒l��9.8�ł͂Ȃ��̂ł��傤���H
���Ƃ���A���̎��ł̓ʂ̒l�͏��1�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁH
�����ԍ��F25925059�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��a��g�����ɏd�͂̉����x
�������Aa �͎ԗ��̌����x�A�܂萅�������̉����x�ł���B
���ꂪ�u���[�L�ɂ�門�C�͂����C�W���ʂƎԏd�A�܂莿��m�Əd�͉����xg�Ōq�����Ă��邯�ǁA�d�͉����x���̂͐��������ł���ˁB
�����ԍ��F25925074�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�܂��A�}�����ɂ�����^�C���̖��C�W�����A�h���C�� 0.7 �E�G�b�g�� 0.3 ���x�ƌ����Ă��܂��ˁB
���i�A�����ЂƂ肾���Ōy�����Ԃ��^�]���Ă��āA�e�ʂ��Q�l���}�����Ƃ��́A�����ɂ��댸���ɂ���A���i�ʂ肾�Ɓu�~�܂�ɂ����v�������܂����B
�z�[���Z���^�[�Ōy�g������ăR���N���[�g�ޗ��� 200kg ���炢�����o�������ȂǁA���M���ɂȂ�~�܂낤�Ƃ�����A��납��u�����o����銴���v�����Ď~�܂�ɂ����̂ɂ͏ł�܂����B
�����ԍ��F25925096�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�ǂ����{�g���l�b�N�ɂȂ��Đ����������L�тĂ邩��������
�ǂ�ȂɎ��W�J���Ă�
�Ȋw�I�ł͂���܂���B
�����ԍ��F25925099
![]() 1�_
1�_
�u��Ԑl���������Ă����������͓����v�ƕ����ƈӊO�Ɏv����������܂��A��~�����������{���������ŁA�ǂ�������x�Ƃ̊W���o�����͂��ł����A�ԏd�͊W�Ȃ������ł���ˁB
�����ԍ��F25925112�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���R�z�@���Y����
�����A�ŏ��ɁA���瓚�����o����Ă����܂���
�t���u���[�L�𐔉�J��Ԃ��Ă��A�����͈͂��肵�Ă��āA����̂ق����A���b�N���Ȃ��A��肭����Ă���̂ŁA�H�ʏ��ǂ��Ƃ�������������܂����A�ŋ߂̎Ԃ́A�ق�Ɨǂ��Ȃ�܂�����
�������A�H�ʏ������Ȃ�A�^�C���̃O���b�v���E��������A���b�N���������A���Ԃ�P���ɂ͐Ö��C�W���⓮���C�W���̘b�Ȃǂ���n�܂��āA���̑����������S���ς��A���������͎ԗ����d�ʂɉe������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��傤
�����ԍ��F25925137
![]() 0�_
0�_
���`�r������
�^�C���̖��C�͂����łȂ��A�u���[�L�p�b�h�ƃf�B�X�N�̖��C�͂�����܂��ˁB
���C�W���������ł��A�ԏd��2�{�ɂȂ�����A�p�b�h�̉����t���͂�2�{�ɂ��Ȃ��Ɛ����������L�т܂��B
�t���u���[�L���O�łȂ��A�u���[�L�̓��ݕ������Ȃ�A�~�܂�ɂ����Ɗ�����ł��傤�B
�����ԍ��F25925159
![]() 2�_
2�_
�������Ƃ���
��ʂ�ł��B�����������i�͋}�u���[�L�ł͖����A���i�ʂ�ɂ��邩��d���Ȃ�Ǝ~�܂�ɂ����Ɗ����邾���ł��B
ABS ��������Ă���u�Ԃ͈��u���[�L���ɂ߂Ă��܂��̂ł��܂��̂ŁA�����I�ɂ͎ԏd�Ɛ��������͖��W�ł��A���ۂɂ̓P�[�X�o�C�P�[�X�ł��傤���ǁB
�܂� 60km/h �ɂ����鐧�������� 27m �Ƃ����b���A0.5G �������x�Ō����ɑ����Ȃ����ł����B
�����ԍ��F25925197�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����ˁA�G�l���M�[�ōl����킩��₷���悤�ȁB
���̂������Ă��鎞�͂��̕��̂̏d���Ɠ����Ă��鑬�x�̂Q��ɔ�Ⴗ��^���G�l���M�[��L���Ă��܂��B
�ŁA���̕��̂̓������~�߂�ɂ́A���̉^���G�l���M�[����苎���ă[���ɂ���K�v������킯�ł��B
�ł�����A�Ԃ̏ꍇ�͉u���[�L�͔��d�����Ȃ̂ł�����ƈႤ���ǁA���ʂ̓u���[�L�M�i���[�^�[�ƃp�b�h�Ԃ̖��C�M�j�ƘH�ʂƃ^�C���Ƃ̖��C�M�ł��̉^���G�l���M�[��M�Ƃ��ĕ��o���邱�ƂŎ~�܂邱�Ƃ��o�����ł���ˁB
�ŁA�~�߂邽�߂̔M���o(������)�́A�H�ʂ̖��C�ɂ��Ă͘H�ʂ̏�ԂƂ��^�C�����\�ɂ�邾�낤���A�ԑ��ł̓u���[�L���\�̍��ɂ���ĕς���Ă��邩�ƁB
�Ŗ{��́A�������H�ŁA�����^�C���ŁA�����u���[�L���\�̎ԂŁA�������x�ŁA��Ԑl����������������A��l�̑̏d���U�T�L���Ƃ����ꍇ�A�S�l��ԂȂ�A�^�]�肾���̎����P�X�T�L�����d�ʂ�������̂ŁA����ɔ�Ⴕ�ĉ^���G�l���M�[��������̂ŁA��l��Ԃ̎��Ɠ��l�̋}�u���[�L���v�������蓥���̂S�l��Ԃ̐��������͓��R�L�т��Ȃ��ł��傤���ˁB
���ꂩ��R�z�@���Y���A�b�v���ꂽ�ߐύڃg���b�N�̐��������̕\�ł��A�\�ɂ͏o�Ă��Ȃ����ǁA�����������A�ύڗʃ[������P�O�O���܂ł̓t���b�g�ň��ŁA�P�O�O���I�[�o�[���琧���������L�юn�߂�Ƃ͍l�����炭�A�ςׂ݉��[�����瑝����ɏ]�������������L�т��Ȃ����ȂƁB
�����ԍ��F25925222
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�ق�
�ł͂Ȃ���^�g���b�N��
�������H�ł̐������x���Ⴉ������
���~�b�^�[���x���Ⴉ�����肷��̂ł��傤��
��^�g���b�N�ɐ������L��ό��o�X�ɖ����̂�
�����ڂ̃T�C�Y�͋߂��Ă��ό��o�X�͏d�����������炢
������Ȃ�ĕ��������L��܂���
�@
�����ԍ��F25925310
![]() 0�_
0�_
�������Ƃ���
�����C�W���������ł��A�ԏd��2�{�ɂȂ�����A�p�b�h�̉����t���͂�2�{�ɂ��Ȃ��Ɛ����������L�т܂�
�����Ƃ������܂����B
SMLO&R����̎��ɂ���悤�ɍő吧���͂̓^�C���̃ʂŌ��܂�܂��B
�^�C�������b�N��������Ȃ�A�p�b�h�̉����t���͂������ł����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���i�C�g�G���W�F������
����Ⴕ�ĉ^���G�l���M�[��������̂ŁA��l��Ԃ̎��Ɠ��l�̋}�u���[�L���v�������蓥���̂S�l��Ԃ̐��������͓��R�L�т��Ȃ��ł��傤���ˁB
���x���J��Ԃ��Ȃ�Ƃ������A��x�̋}�u���[�L�ō����o��悤�ȃM���M���̔M�e�ʂł͐v����Ă��Ȃ��ł��傤�B
�����ԍ��F25925314�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���Ȃ�ق�
���ł͂Ȃ���^�g���b�N��
���������H�ł̐������x���Ⴉ������
�����~�b�^�[���x���Ⴉ�����肷��̂ł��傤��
��͂�d�ʂ��傫���̂ő��x�𗎂Ƃ��ĉ^���G�l���M�[��}���邽�߂ł��傤�B
�^���G�l���M�[�͑��x�̂Q��ɔ�Ⴗ��̂ő��x�𗎂Ƃ��͉̂^���G�l���M�[������������̂ɂ߂�����L���ł��B
�����ԍ��F25925320
![]() 0�_
0�_
���^�C�������b�N��������Ȃ�A�p�b�h�̉����t���͂������ł����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����x���J��Ԃ��Ȃ�Ƃ������A��x�̋}�u���[�L�ō����o��悤�ȃM���M���̔M�e�ʂł͐v����Ă��Ȃ��ł��傤�B
�^�C�������b�N�����Ă��܂�����u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h�̊Ԃ̖��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��u���[�L�������Ȃ��Ȃ�܂���B
���z�̓��b�N���O�Ń��[�^�[�Ƀp�b�h���v�������艟�������Ă����Ԃ��ƁB
�܂����̎Ԃ͂`�a�r���W�������Ȃ̂ŋً}���ɂ͍\�킸�v�������蓥�߂������ǂˁB
�u���[�L�̔M�e�ʂ��[���ł��A�����Ă���Ԃ��~�߂�̂ɁA�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�A���ʁA�����������L�т�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB
�����ԍ��F25925340
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
��̃Z���t�E�E�E����c���́E�E�E���Ă����̂́A�������ɁASMLO&R����ɂ͌����܂��E�E�E
���i�C�g�G���W�F������
���^�C�������b�N�����Ă��܂�����u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h�̊Ԃ̖��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��u���[�L�������Ȃ��Ȃ�܂���
�H�H�H�@���b�N���́A���[�^�[�ƃp�b�h�͐Ö��C�̊W�ƂȂ��āA�u���[�L�͂͂������Ȃ��ł����H
�܂��A�^�C�������b�N���āA�^�C���ƘH�ʂ̊W���A�����C�ɂȂ邩��A�����������L�т�Ǝv���܂�
ABS�̖����}�u���[�L�́A�d�ړ�����O�ɁA�u���[�L�͂������A�^�C�������b�N�����Ă��܂��̂ŁA���銴���Ő����������L�т�
���̎��́A���ʂɂ��^���G�l���M�[�ƁA�^�C���ƘH�ʂɂ��M�G�l���M�[�̊W�ɂȂ�Ǝv���܂�
�����ԍ��F25925376
![]() 0�_
0�_
���˂��݂���B����
�u���[�L�����b�N�����ă^�C���̉�]���~�߂Ă��܂�����A�u���[�L���[�^�[�ƃu���[�L�p�b�h�Ԃ̐������C���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�u���[�L�͌����Ȃ��Ȃ�Ȃ�Ƌ��ɁA�X�e�A�����O�R���g���[���������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�����͂͘H�ʂƃ^�C���̖��C�݂̂ɂȂ�A�Ԃ܂����ōs�������Ƃ��܂ōs���݂����ȁA�ƂĂ��댯�ȏ�ԂɂȂ�̂ł́H
�����ԍ��F25925393�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G�l���M�[�ōl�����
�ԏd��������Ή^���G�l���M�[���傫���Ȃ邩��A�����ɂ���ɂ���A����Ȃ�̔\�͂��K�v�ɂȂ邾���̘b�ŁA�ǂ݂̂��^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂ƁA���̏u�Ԃ̑��x�̐ρi���o�́j�ȏ�̔\�͔͂����ł��Ȃ����ƁB
�����ԍ��F25925426�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�ǂ����ŁA�킽�����̊��Ⴂ�����邩������܂��E�E�E
���b�N������A�~�܂炸�A�X�e�A�����O�������Ȃ��Ȃ�A�Ԃ܂����̊댯�ȏ�ԂɂȂ�Ƃ����̂́A�悭������܂�
���[�X�V�[���̃X�g���[�g�G���h�ŁA�悭������i�ł����
�ł��̂ŁA�Ȃ��̂��ƁASMLO&R����́A������s�Ő����̘b���I����Ă��܂��̂��s�v�c�ŁE�E�E
�����ԍ��F25925429
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�����A���݂܂���B
�^�C�������b�N��������Ȃ�A�Ƃ����̂́A�^�C�����\�ɑ��ău���[�L�̐��\���\���ł���A�Ƃ����Ӗ��ł��B
���b�N���O���ő吧���͂Ƃ��čl����̂ŁA���ۂɃ��b�N������Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�i���̓^�C���̃ʂ͏��������Ă����Ԃōő�ƂȂ�̂ł����j
�t�ɂǂ�Ȃɑ傫�ȃu���[�L���t���Ă��Ă��^�C���̐��\�ȏ�̐����͂͏o���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�i�n�ʂƐڂ��Ă���̂̓^�C�������Ȃ̂œ�����O�ł���ˁj
���u���[�L�̔M�e�ʂ��[���ł��A�����Ă���Ԃ��~�߂�̂ɁA�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�A���ʁA�����������L�т�Ƃ������Ƃ̂悤�ȁB
�ԏd���y�������d�����̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ������Ȃ�̂͂��̒ʂ�ł����A��x�̋}�u���[�L�ł������ɑ��ď\���ȔM�e�ʂŐv����Ă���ł��傤�A�ƌ����Ă��܂��B
�����ԍ��F25925432�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��use_dakaetu_saherok����
���˂��݂���B����
�������܂����B
�����ԍ��F25925489�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
YouTube�Ń|���V�F�̓G���W���p���[���u���[�L�p���[�i�ϊ����Ă�j���������v�ɂ��āA�ߍ��Ȏ��ԃe�X�g�����Ă�ƌ��܂����B
�J�[�{���Z���~�b�N�f�B�X�N�u���[�L�̓I�v�V�����ŕS���~�z���ł����B
ABS�͗��q�@�ɍ̗p���ꂽ���̂��N���}�ɍ~��Ă����A�������Ɋ����H�Ƀh���ƃ����f�B���O����̂́A�^�C���̉��x���グ�邽�߂��Ƃ��i�W�F�b�g�@�͋t���˂��܂����j
�����ԍ��F25925539
![]() 0�_
0�_
����c���́E�E�E���Ă����̂́A�������ɁASMLO&R����ɂ͌����܂��E�E�E
�����āA���_�l��@��(���܂�)�Ƃ������(��c��)�b������Ȃ�
�^�U�͂Ƃ����������l(����)�̘b���ł���
�v�Z�łǂ��̂��ĕ������邯��
�܂�Ȃ����˂����ނ�
�����ԍ��F25925652
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
�܂�Ȃ����˂�����ŁA���݂܂���ł���
�����������ƁA���́A�������Ɍ���̎����l�̘b�ł����E�E�E
���v�Z�łǂ��̂��Ă������E�E�E�̘b���A�����ɂ���c���Ƃ������A���{�ɂ̌����ʂ�A�����Z�����E�E�E�̋����̘b�������̂ŁE�E�E
�����ԍ��F25925669
![]() 1�_
1�_
�X����l�̂���������́A�t���u���[�L���O�̎��̂��̂Ȃ̂ŁA�����͂̓^�C���̖��C�͂Ɉˑ����܂��B
���C�W�������ʼnd���ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴕ�A���������͎ԏd�ɂ�����炷���ł��B
JAF�̓���ł́A�u���[�L���ݗ͈��Ń^�C������]���Ă���̂ŁA�����͂̓u���[�L�p�b�h�̖��C�͂Ɉˑ����܂��B
���C�W�������ʼnd�����Ȃ̂ŁA�����͂����ƂȂ�A�ԏd���d����ΐ��������͐L�т܂��B
���Z�ŏK�������@���ł��A���퐶���ŋN���錻�ۂ͂���ɏ]���܂��B
�Ⴄ���ۂ����������ɐ��������߂���A�ʂɕs�v�c�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25925763
![]() 1�_
1�_
�������Ƃ���
�����Ȃ̂ł����H
JAF�̃e�X�g�́A�����ď�������₱�������āA���ʂ��A�d����Ԃł͎~�܂�ɂ����E�E�E�ɂ��āA��ʃh���C�o�[�ɒ��ӊ��N���铮��ł����
�ŏ��̓���ł́A���̎Ԃ�ABS��u���[�L�A�V�X�g���D�G���Ƃ������Ƃ�������܂����A���ʂ́i�D�G����Ȃ��j�ԂȂ�A�t���u���[�L�ł́A�^�C�������b�N����Ǝv���܂�
�����ɕs�v�c���������A�P�ɁA�ύڂɂ�����炸�������������E�E�E���ƌ����Ă��܂��̂��A�ق�Ƃɕ������ۂ̐��������߂Ȃ̂��A�����|�����Ă��܂�
�����ԍ��F25925820
![]() 0�_
0�_
�r���C�W�������ʼnd���ԏd�ɔ�Ⴗ��̂ŁA�����͎͂ԏd�ɔ�Ⴕ�A���������͎ԏd�ɂ�����炷���ł��B
��^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ
��ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂��
���Ď��ł�낵���̂ł��傤��
�����ԍ��F25925824
![]() 1�_
1�_
�^�C�������b�N���Ă��A�����C�W�������Ȃ瓯�����Ƃł��B
�����ԍ��F25925962
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
����^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ
����ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂��
�����Ď��ł�낵���̂ł��傤��
���x���o�Ă��Ă���ʂ�A�ő吧���͂̓^�C���̃ʂŌ��܂�܂��B
�������A���Z�����ƈႤ�̂̓^�C���̃ʂ����ł͂Ȃ��A�����R�́i�d�j�ɂ���ĕω�����Ƃ����_�ł��B
�g���b�N�̏ꍇ�͑z�肷��d�ʂ̕������ɑ傫���̂ň�T�ɂ͌����Ȃ��̂ł����A��ׂł̓^�C���̃ʂ��������Ȃ邽�߁A�����������L�т邱�Ƃ�����܂��B
���������́A�v�͈͂̒��̂���ύڗʁi��ρj�ōŒZ�ƂȂ�A�ύڗʂ��v�͈͂���i�ߐύځj�Ƃ܂��L�т܂��B
�����ԍ��F25926076�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�g���b�N�̏ꍇ��
�^�C���̔\�͂ł͂Ȃ�
�u���[�L�i�Ɣ{�͑��u�j�̔\�͂��{�g���l�b�N�ɂȂ�̂�
�d���@�Ɓ@���������@����Ⴕ�ĐL�т܂�
��p�Ԃ̎����Ƃ͈���Ă��܂�
�����ԍ��F25926082
![]() 2�_
2�_
����A�g���[���[��ABS���`���Â����Ă������10�N�ɂȂ�܂����A�������ɂ���ABS�������Ă���O��̘b�ł�����Ȃ��ł����H
���ǂ���x�̋}�u���[�L�Ń^�C���ȊO���{�g���l�b�N�ɂȂ�悤�Ȑv���Ȃ��Ǝv���܂����ǁB
�����ԍ��F25926105�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>��^�g���b�N���t���u���[�L�|�����ꍇ�@��ׂł��ו����ڂł����������Ŏ~�܂����Ď��ł�낵���̂ł��傤��
�C�G�X�A���h�m�[�ł����ˁB
���_�I�ɂ͂����ł��B���������̂悤�Ȑ��\�̐������u��ς�^�Ԃ��������邩�͋^��ł��B���͑�^�ԂƂ͑S�������ł�������Ԃ͑����܂��A�����g���b�N���[�J�[�̌o�c�҂Ȃ炻�̂悤�ȎԂ͑����o�ύ����������������Ȃ̂ō��Ȃ��ł��傤�B
�܂���^�g���b�N�ƈ�ʂ̏�p��(SUV�A�~�j�o���A�Z�_���Ȃ�)�Ƃ͎ԗ��d�ʕω������S���Ⴄ�̂œ����y�U�ł̋c�_�ɂȂ�܂���B
������x�����܂����A���z�����Ɋ�Â����������������ɏd�ʂ͊܂܂ꂸ�A�d�ʂƐ��������̊Ԃɗ��_��͒��ړI�ȊW������܂���B
���Z�������A���������Ȃǝ������悤���A����͕����w�̐^���Ȃ̂ŁA���̗��������̋c�_�̏o���_�ł��B
�����E�ł́uABS��쓮�A�߉d�Ŗ����ꍇ�̎��ۂ̐��������ϓ�(�Ώ�����E�ו���)��5�|10%���x�Ƃ���܂��B�v�Ɩ`���Ɋ��q�����ʂ�i��ʓI�ȏ�p�Ԃ̏ꍇ�j�d�ʑ召�Ő��������ɈႢ������܂��B���_�ƌ����̍��̑�v�͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�@ ���Ƃ���7�l����p�Ԃɂ��ď�����ɂ��d�ʂ̕ω����݂�ƁA���Ɏԗ��d�ʂ�1,500kg�Ƒz�肷���1�l(55kg�j��Ԃ�1,555kg�A7�l��Ԃ�1,885kg�Ȃ̂ŁA�����ɂ��d�ʕω�����21%�B2�g���̎ԗ��Ȃ�16%�ł��B�ȒP�̂��ߐωׂȂǂ͏ȗ����܂��B
����A�ԗ��d��5�g���A�ύڗ�6.5�g���̑�^�ԁi�����u10�g���ԁv�A���������ݒ�Ő������H�j�̏ꍇ�͋�ׂȂ�5,055kg�A���ڂȂ�11,555kg�ł�����A���̕ω�����229%�ł��B
�����n���\�v���ɑ���p�Ԃ�0.2�{���x�̕ω��͈͂Ȃ琧�������̍����������悤�Ȑv���\�Ō��ɋL�q�ʂ�5�|10�����x�ƌ����܂��B��������^�Ԃ̂悤�ɂQ�{�̕ω�������ꍇ�A���������ω���10�����x�܂łɗ}����v�Ɍo�ύ����������邩�^��ł��B
�A ���������������������ŒZ���������Œ�~����ɂ̓^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���ʂ𐧓��J�n�����~�܂őS���x��ōő�l�ɕۂ������Ȃ���Ȃ�܂���(�Î~���C���)�B����̓^�C�������b�N���O�Ń��b�N���Ȃ���Ԃ��O��ł��B���ۂ̉^�]�Ō����A�Ⴆ�A�h���C�̃A�X�t�@���g�H�ʂ�ABS���쓮���鐡�O��Ԃ̃u���[�L���O���ŏ�����Ō�܂ňێ�����Ƃ������ł��B��Ɏ����\�Ƃ͌���܂���B
�B ���_��̓^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�W���ʂ͑��x�Ɉˑ����Ȃ��ƍl���܂��B�������������E�ł͑��x�ˑ������w�E�E�m�F����Ă��܂��B�������Ƀʂ��ς��ΐ����������ω����܂��B�ڍׂ͊������܂����ȉ��̂悤�ȗv��������A���f����̈ˑ����A�^�s��Ԉˑ���������܂��B
a �^�C���ƘH�ʂ̑��ݍ�p
���M�ɂ��^�C�������ω��A�^�C���ό`�A�^�C���a�̘H�ʊ��݁i�ᑬ���j
b ���̗͊w���ʁi�G��ʁj
�����A�n�C�h���v���[�j���O�A�S�����C
c �^�C���̃R���p�E���h�E�v
�����\�^�C���A�[���g���b�h�E����p�^�[��
d ��͂ƃ_�E���t�H�[�X
�����ԍ��F25926113
![]() 1�_
1�_
���Ď��ۊX�ł̋}�u���[�L����
��Ԑl���������Ă����������͓���
�Ȃ�ł��傤����
�����ԍ��F25926248
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�@
�����Ď��ۊX�ł̋}�u���[�L����
����Ԑl���������Ă����������͓���
���Ȃ�ł��傤����
�@
���L�̃T�C�g�ŏڂ����l�@������Ă���A��r�I�킩��Ղ����ƁB
https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette
�@
���̃T�C�g�̉���Ɋ�Â��A�ȉ��̑O��ɂ����Ắu��Ԑl���������Ă����������͂قړ����v�ƌ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B
�E�H�ʂ��������Ă��ċɒ[�ȉ���(�������)���Ȃ�
�E�����傫�������Ȃ�(=�u���[�L���\�v�͈͓̔�)
�E���d�ʂ��������Ă��O��̏d�ʃo�����X���ς��Ȃ�
�@
�����A���ۂɂ͈�l��ԂƔ�ׂđ��l����Ԏ��ɂ͂ǂ����Ă��㕔�d�������������邽�߁A���̕����������Ȃ�Ƃ��e�����o��̂ł́B���Ɍ㕔���Ȃɂ������l��������Ă�����A���ɏd�ʕ����ڂ��Ă���ꍇ�ɂ͂��傫�ȉe�����o����̂Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25926344
![]() 0�_
0�_
�́A�����悤�Ȏ�����������Ƃ�����܂��B�u���[�L�̐��\�����������ꍇ�́A�d���Ă����̕��^�C���̖��C�͂�������̂ɁA�ǂ����Čy�����������~�܂��̂��A�ƁB
���̎���������́A�u���C�͂��d���ɔ�Ⴗ��͍̂��̂̏ꍇ�ŁA�^�C���̂悤�ɏ_�炩���ĕό`������̂͏d���ɑ��ĕ��G�ȃJ�[�u��`���A�P���ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��v�Ƃ������̂ł����B
�����Ōv��������ł͂Ȃ��̂ŕ�����܂��A�����͂ց[�Ɣ[�������L��������܂��B
�����ԍ��F25926360�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�ԏd�������Ă���̂ɁA�����ς��Ȃ��͂����Ȃ��A�Ƃ����̂��݂Ȃ�����D�ɗ����Ȃ��Ƃ���ł��傤���B
����ł����ƕω��͂�������āA�ԏd��������A�^�C�������b�N������iABS�������j���߂ɕK�v�ȃy�_���̃X�g���[�N�ƃy�_���ޗ͂������܂��B
�����������ς��Ȃ��ƌ����Ă���̂́A�X�g���[�N��͂ɂ�炸������ABS�������Ƃ���܂œ��ݐ邱�Ƃ��O����ł��B
���̂���JAF�̓���̂悤�ɁA���������Ńu���[�L�y�_���ނƂ��������ł���A���������̕����ς��܂��B
�����A�ŋ߂̓u���[�L�o�C���C���̎Ԃ������̂ŁA�����������Ԃł���y�_���ɂ��ω��͋N���܂���B
�����ԍ��F25926371�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��������@�Ȃ��₳��
>�����A���ۂɂ͈�l��ԂƔ�ׂđ��l����Ԏ��ɂ͂ǂ����Ă��㕔�d�������������邽�߁A���̕����������Ȃ�Ƃ��e�����o��̂ł́B
���̃T�C�g�ł͌�։d���傫�������L�����ĂȂ��Ă��܂���
�u���[�L���\�ɂ͗]�͂����蓯�����͂Ō����Ȃ��Ɗ����Ă�
��苭�����߂Ύ~�܂����ĈӖ������͔���܂�
���̎Ԃ������Ԃł̐ύڂł͂Ȃ��ʁX�̎Ԃł̏d�ʂōl�@���Ă��܂�����
�b�̃X�^�[�g�m�o���c�L���傫�����܂�
�g���b�N�̉ߐύڂ̋L�q�ł��S���������u���[�L�̐��\������Ȃ��݂����ɂȂ��Ă��܂���
�ύڂ��l�������ł��i�ԗ��d�ʂ�����̂Łj�ԗ����d�ʂ͂��������Q����R���������炢���Ǝv���܂�
������ꔭ�̃u���[�L�Ő��\�s���ƂȂ�u���[�L�Ƃ͎v���܂���i�]�͂Ȃ��j
�m���Ɏ����l�����ɂ��Ă��܂���
���g�̍l�@�ɓs���̂悢�f�[�^�[��E�܂�ŏW��
�s���̈����f�[�^�͑̍ق悭�ے肵
���̏�őg�ݍ��킹�������L�肫�̘_���̂悤�Ɋ����Ȃ�������܂���
�����Ȃ������Ȃ��ƌ����ĂȂ��ŕK�v�Ȏ��͋������߈ĊO������
���ĈӖ������̋��P�ɂ͗ǂ���������܂���
���̏�ɏo�Ă��Ȃ������͖�����ł�����
�ԍD���̖l�Ƃ��Ă̓C�j�V�����c�̂b�f�A�j����
�Ԃ̓����͖ʔ������ǂȂɂ��R����������������
�悭�l���Ă݂���
�b�f�ł͘H�ʂ̂��˂肪���f����Ă����ԑ̂�^�C���̏オ���Ȃ��n���h���C�����Ȃ����ׂĂ̓������X���[�Y�ȑ���Ȃ�ł����
�i���ۂɂ͘H�ʂ̂��˂�≚�ʁA�O���b�v�̕ω���e�ԗւ̉d�ω��Ƃ��^�[�}�b�N�����[�̃��[�`���[�u�Ƃ�����ƃ��A�������S�R�Ⴄ�j
���̏�i�v�Z�◝�_�j�ɂ͂Ȃ����ۂ̎Ԃ⓹�H�̏�i���ۂ̑��s�j�ɏo�Ă��鉽��������ł�����
�����Ȃ����Ǝ��ۂ͂����Ɠ��߂��ĈӖ����������ł��܂���
���������͓����ƌ����Ă�
�܂��P�O�O���M�����܂���
�P�ɓ��̌ł��W�W�C�Ȃ�����������܂���
�����ԍ��F25926419
![]() 1�_
1�_
�^�C���������ƘH�ʂ��Ƃ炦�ăX���b�v���Ȃ��A�u���[�L�@�\���ԗ�(�^�C��)�������E��~�����鐫�\���[���ł���A
�h���C�o�[�̔������x�A�둀��Ȃǂ������A
������́A�d�ʂɊW�ɊW�Ȃ��~�܂�܂����B
���ۂɂ͏d�ʂ��傫����A�}�������ɃX���b�v���������A�]�v�ɐ��������������܂��B
�܂��̓u���[�L���\���ԗ�(�d��)�����̐��\�ɂȂ���A�Z�������ł̐����ł��܂��A�u���[�L�@�\���j�����܂��B
�܂�A
��96km/h����t���u���[�L�B1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B
���@������̓u���[�L���\���ŁA���X���b�v���������Ȃ��̂Ő����������قړ������ʂƂȂ�܂����B
�g���b�N�̖��ڎ��A�܂��͉ߐύڎ��́A�}�����̍ۂɏd�ʂ̑傫�����炭��X���b�v���������₷���Ȃ�A�����������L�т܂��B(�ň��A����s�\�ʼn��]�Ȃ�)
���邢�̓h���C�o�[�̑����ABS�Ȃǎԍڋ@�\�Ŏԗւ̃��b�N������āA���̕��̐����������L�т܂��B
���Ƀg���b�N�̉ߏd�ʂ⍂�����́A�u���[�L���\�����̏�Ԃɒǂ������A
�u���[�L�̐��\�s����A�u���[�L�j���Ɍq����܂��B
�����ԍ��F25926455�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�@
�����̃T�C�g�ł͌�։d���傫�������L�����ĂȂ��Ă��܂���
�@
�m���ɂ����ł��ˁB�u���[�L���|�������ɂ͂ǂ����Ă��Ԃ̑O�������ނ̂ŁA����̉d���傫�������O��ւ̉d�o�����X�ω����������A���ʓI�Ƀu���[�L���̐����G�l���M�[�̑O��փo�����X�̕ω����������Ȃ�܂��ˁB�ł���ΑO�q�́u�e���v�͂ނ���|�W�e�B�u�ȕ����ł��ˁB
�@
�@
�����������͓����ƌ����Ă��܂��P�O�O���M�����܂���
�@
�S�������ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��ʓI�Ɏv���Ă���قǂɂ͏�Ԑl����d�ʑ��ɂ��e���͑傫���Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邩�ƁB
�����ԍ��F25926467
![]() 1�_
1�_
��SMLO&R����
���������Ɋւ��āA�V���v���ȏ����ŁA�����I�ɂ�������������A���肪�Ƃ��������܂���
��������Ε��G�ɂȂ鎖�ۂ��A�V���v���Ȑ����ɂ���̂́A���z�I
�ł��E�E�E
����̘b��ŁA�q���̍��A�������ɂȂ������X���闝�R�̈���v���o���܂���
�����̃C���[�W�ƁA���ȏ��̘����ɂ��āE�E�E
�������V���v���ɂ���ƁA�Ȃ������\�Ԃ̃^�C������a�Ȃ̂��A���L�Ȃ̂��A�G���Ȃ̂��E�E�E�������Ă��܂�
�q���S�ɂ́A�����ڂ̃C���p�N�g���傫���^�C���̑��݂����Ă܂ŁA�V���v���ɂ����ƁA�C���[�W�N�����A�ʔ����Ȃ��Ȃ�A�������i�܂Ȃ��A�����i���ł͉�c���j�����̘b�ɂȂ��Ă��܂����̂ł�
�����ς�炸�A�d���������ł��Ȃ��A�����̃I�b�T���̌�����ł���
�����ԍ��F25926483
![]() 0�_
0�_
>���Ƀg���b�N�̉ߏd�ʂ⍂�����́A�u���[�L���\�����̏�Ԃɒǂ������A
�u���[�L�̐��\�s����A�u���[�L�j���Ɍq����܂��B
���̕ӂ����̏�̘b���ȂƎv����ł����
���Ƃ��T�������̐ύڂł����b�N�������邵�u���[�L�j�������Ȃ��Ǝv���܂����ǂ�
>�S�������ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A��ʓI�Ɏv���Ă���قǂɂ͏�Ԑl����d�ʑ��ɂ��e���͑傫���Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����邩�ƁB
����Ȋ����ł�
�H�ʂ����đS������ق��肪�������Ď��͂Ȃ���
�i�`�e�̈Ⴄ���Ď����݂�����
�������Ď������ړI�ɂ����������ł͂Ȃ�Ď߂Ɍ��Ă��܂��܂�
�����ԍ��F25926522
![]() 0�_
0�_
�����Ƃ��T�������̐ύڂł����b�N�������邵�u���[�L�j�������Ȃ��Ǝv���܂����ǂ�
�������g���b�N(���̏�)�̋K�́E���\�ɂ����܂����A
���b�N���Ă��܂��ƃX���b�v���Đ��������������܂����A
�}�u���[�L������A���ՁE�����ׂ�������A�j���Ɍq����͓̂��R���Ǝv���܂��B
�}�u���[�L�P�������A���̓s�x�A�j������Ƃ͌����Ă���܂���B
�����ԍ��F25926542�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>���b�N���Ă��܂��ƃX���b�v���Đ��������������܂����A
�A�����̃X���ɔ�����
>�}�u���[�L������A���ՁE�����ׂ�������A�j���Ɍq����͓̂��R���Ǝv���܂��B
���b�N��̃u���[�L�̕��ׂ͕ς��Ȃ���ԑ̑S�̂Ƃ��Ă͌������������邯��
�����͐��������X���������
�����������ς�邩������
���Ď~�܂�Ȃ��ȕ����邯��
���̃X���ł�
���b�N�����鐫�\�������ł����ςł��ߐύڂł����������͕ς��Ȃ����Ď��ɂȂ�܂���
�u���[�L���ĊȒP�ɂ͉��Ȃ��扷�x�ȊO�̉ߕ��ׂ̓^�C���ɓ����邩��
�ȑO�O�X���ł̃o�X���̂����ău���[�L�������Ȃ��Ȃ��������Ńu���[�L����ꂽ��Ȃ���
�����ԍ��F25926557
![]() 0�_
0�_
���A�����̃X���ɔ�����
����Ȃ���͖ѓ�����܂����B��
�^�C�����H�ʂ��Ƃ炦�Ďԗւ̌����ɂ���ԂƁA
�^�C�����b�N���ăX���b�v���Ē�ԂƂ́A
���(���C)�������������Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B
�ᑬ�ł́A�ԗւ̌����ɂ���ԂƁA�^�C�����b�N�̃X���b�v��Ԃł́A
�قƂ�Ǎ��ق͂Ȃ��ł��傤�B
����100�L���O��⍂�����H�ł̂��̍��ق͈���Ă��܂��B
���̂Ȃ��ŁA�X���b�v(���琶���鍷��)�Ɋւ��Ď��̈ӌ����q�ׂĂ�̂ł����āA
�ʂɔ����Ƃ�����Ȃ���͂���܂���B
�����A�٘_�E���_���������ʂ͂���܂����A
���ꂱ���A���_�������萔��G�ɉ��낤�ȂƎv���A�����Ă܂��B
�����ԍ��F25926576�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ڂȂ烍�b�N���Ȃ���ł́@
�����ԍ��F25926578
![]() 0�_
0�_
�����ڂȂ烍�b�N���Ȃ���ł�
�g���b�N�h���C�o�[�̈ӎ��̘b�ł����H
�g���b�N�̋@�\�ŏ���ɂ����Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł���ˁB
�����ԍ��F25926588�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����_�ł��܂����l���̕����u�H�H�H�v�Ƃ������ł��낤���͑z���ɓ����܂���B���̂Ȃ�^���G�l���M�[k��
k=1/2 m v^2
�Ƃ����L���Ȍ��������ɒ@�����܂�Ă��āA�u�^���G�l���M�[�������������������������ē��R���v�ƒN���������I�Ɋ����邩��ł��B�������^���G�l���M�[�͂��̉^���̂̎��ʂɔ�Ⴕ�܂��B
�����������Ԃ̏ꍇ�͎ԗ��̎��ʂ��ω�����ƘH�ʂƎԗ��̊Ԃ̖��C�͂��^���G�l���M�[�Ɠ��������ʕω��ɔ�Ⴕ�������܂��̂ŁA�o���̎��ʂ̑����̉e���͂��݂��ɃL�����Z�����A���Ǘ��_�I�ɂ͎��ʑ����Ɛ��������͖��W�ł��B�������E�ł̘����ɂ��Ă͋L�q�ʂ�ł��B
�ʂ̕\��������Ə�L�̌����͕��̂����^���G�l���M�[�ʁi�W���[�����邢�̓��b�g�b�j���������̂ŁA���Y�G�l���M�[�ʂ����Ԃ��~����ɂ͖��C�u���[�L�i�̏ꍇ�j�ł��̑S�^���G�l���M�[��M�ɕϊ�����K�v������A�ƌ����Ă��邾���ł��B�܂肱�̌����͕��̂̉^���ɂ��Ă͉��������Ă��܂���B�ǂ̒��x�̎��Ԃ�������������ĎԂ����S�^���G�l���M�[��M�G�l���M�[�ɕϊ����邩�͒�`�O�ł��B
�����������`����ɂ͐�q�̉^���i���x�A�����x�A�����j�ɂ��Ắu�^���������F�ψʂƑ��x�̊W���v���K�v�ł��B
�b��߂��܂��B
���̗��_�ɂ́u���ꐧ��������ۂꍇ�ɕK�v�Ȑ����͎��͎̂ԑ̏d�ʂ̑����ŕω��v�Ƃ����O�Î�����Ă��܂��B�u�S�Ă̎��ʂɂ����ĘH�ʂƂ̖��C�W�����ő偁����o�����O���ێ��v���O����ł��B
�u�^���G�l���M�[���������琧�������������ē��R���v�̑���Ɂu�^���G�l���M�[�����������������͂Ȑ������u���K�v���v�ł��B�Ԃ̃u���[�L���u�Ƃ��Ă͑O�҂���҂̕����g���Ղ�����ł��B�Ƃ͌��������̐��E�ł͋Z�p�I�E�o�ϓI����100���B���Ƃ�����ɂ͂Ȃ�܂���B
���鎿�ʂŖ��C�W���ő�ɏo����u���[�L�\�͂̐v���������A����ȉ��̎��ʂł͌������̏�Ԃ����o����ł��傤����A���̎��̎��ʂɍ��킹�čő喀�C�W���̓_�Ő����������鎖���o�����Ȃ琧�������͈��ł��B���������̐v�l�ȏ�̎��ʂł͍ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���܂���̂Ő��������͐L�т܂��B�d�ϓ����傫�ȎԂł͌�҂̏ɂȂ�ꍇ���������낤�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25926599
![]() 3�_
3�_
���˂��݂���B����
���������V���v���ɂ���ƁA�Ȃ������\�Ԃ̃^�C������a�Ȃ̂��A���L�Ȃ̂��A�G���Ȃ̂��E�E�E�������Ă��܂�
�X�����ƊO��܂����炲���ȒP�ɁB���̓^�C���n�͕s�ē��ł����̎���ł��B����Ă������ƂȂ����B
��a�^�C���́A�]������������邱�ƂŃR�[�i�����O�̈��萫�A�Ռ��z�����A�g�b�v�G���h�X�s�[�h�����コ����B
�g���b�h�����L���^�C���͐ڒn�ʐς��L���A�g���N�V�����A�n���h�����O�A�u���[�L���O���\�����サ�A���M���ʂ�����B
���[�v���t�@�C���E�^�C���́A�T�C�h�E�H�[���̂���݂�ό`��}���邱�ƂŁA�������s���̉������A���萫�A�n���h�����O�����コ����B
�ł͂��߂ł��傤���B����Ƃ������u�V���v���ɂ���ƁE�E�E�����Ă��܂��v�̉��߂��ԈႦ�Ă��邩���B
�����ԍ��F25926624
![]() 0�_
0�_
���b�N���₷���́���ׁ@�Ȃ̂͌o�����ł�
�ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���
�����ԍ��F25926632
![]() 0�_
0�_
���������́A�H�ʂƃ^�C���̐Ö��C�͂��ő剻����ߒ��i���b�N���钼�O�j�܂ł̓u���[�L���\�Ɉˑ����A�����͂��u���[�L���\���Ö��C�͂̂ǂ��炩������Əd�ʑ�������������L���v���̈�ɂȂ�A�Ƃ��������ł́H
�Ö��C�͂̓^�C���̈Ⴂ��ό`�E�ގ���A�d�i�Ƃ��̕ω��j��T�X���\�E�H�ʏɂ��ˑ�����̂œ���Ȃ�܂����B
�m��ǁB
�����ԍ��F25926648�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����b�N���₷���́���ׁ@�Ȃ̂͌o�����ł�
���ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���
�����������Ƃł����B�킩��܂����B
���ڂ̃g���b�N�����b�N���Ȃ�(����)�́A���͖��o���Ȃ̂ŁA
�o�����ꂽ���̈ӌ��͏d�݂�����܂��B
�����ԍ��F25926662�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SMLO&R����
�lj��̂������A���肪�Ƃ��������܂���
�^�C���Ɋւ��Ă��A�R�����g���������A��ϋ��k�ł�
���肾�ƌ����Ă����܂����A�g���b�h���̂Ƃ���ŁA�ڒn�ʐς��L���A�g���N�V�����A�u���[�L���\�����シ��Ƃ̔F���́A�킽��������ʘ_�Ƃ��Ď����Ă���܂��āE�E�E
�t�Ƀ^�C���̔\�͂��A�u���[�L���\�ɁA�ǂꂭ�炢�e����^����̂��E�E�E�Ƃ��E�E�E
�^�C���Ɖd�Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ낤���E�E�E�Ƃ��A�[�݂ɂ͂܂��Ă��܂��܂���
�V���v���ɂ́A���C�́i���g���N�V�����j�͐ڒn�ʐςƊW�Ȃ��Ȃ����肵�܂�����E�E�E
�����ԍ��F25926669
![]() 0�_
0�_
���ԗ����d�ʂ��傫����Ί����͂Ń^�C��������������ł���
�Ԃł���ȏ�A�ԗւ����Ă���A
�ԗւœ]�����Ĉȏ�A�]���薀�C(�]����W��)�͏������A
�����炱���Ԃ͓����̂ł���A
�Ԃ̃u���[�L(�s��)�Ƃ́A�܂��]����ԗւ��~�߂�s�ׂł��B
�����ł܂��A�u���[�L�f�B�X�N��h�����ɂ����C�̘͂b�ɂ��Ȃ�܂����A
�n�ʂƂ̓]���薀�C(�]����W��)���������ȏ�A
�傫���ԏd����̊�������]����ԗւ���(���邢�͎~�߂悤)�Ƃ���g���N�̗͂ƂȂ�A
�~�߂�ɂ͋����u���[�L���K�v�ƌl�I�ɂ͎v���܂��B
�����ԍ��F25926692�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����
×�]���薀�C�@���@���]�����R
�����ԍ��F25926701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����_���ɂ����̂Ȃ��Ă��܂�����
�^�����o����Ȃ�
�����̐���������
����ʂ�
���������͓������Ď��ŗǂ��̂ł��傤��
�����ԍ��F25926727
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�����A�܂����������ɂ��I
�����́A�����ύڂ������Ă��A���������͕ς��Ȃ����H
�Ԃƃ^�C���ƘH�ʂɂ��E�E�E�Ƃ������Ƃł��傤
��ʓI�ɂ́E�E�E
https://www.nissan.co.jp/COMPASS/ISF/SS/MESSAGE/distance.html
���ƁA����̐���u���[�L���́A���ɏ����ύځA���Əd�S���Ȃǂɂ����ӂ��K�v���ƁE�E�E
������A���������̃_���_���u���[�L���A���l���A���ύڎ��́A���ӂ��K�v�����E�E�E
�����ԍ��F25926752
![]() 0�_
0�_
���˂��݂���B����
���V���v���ɂ́A���C�́i���g���N�V�����j�͐ڒn�ʐςƊW�Ȃ��Ȃ����肵�܂�����E�E�E
�Ȃ�قǁA�u�����Ă��܂��v�Ƃ͂��������Ӗ��ł������B
�������\�Ƃ������W����ł����班�������ł����A�X���傳��A���X���������B
�ēx����Ŋȗ��ł��B
���������ʂ薀�C���_�ł͖��C�͂͐ڐG�ʐςɂ͈ˑ������A�@���͂Ɩ��C�W���Ō��܂�܂��B
�����������̐��E�ł̓^�C���̐ڒn�ʐς�傫�����邱�ƂŃO���b�v�́A���M���A�g���N�V���������サ�A�^�C���̐��\�����シ�邱�Ƃ��ł��܂��B
����͖��C�͎��̂��^�C���ƘH�ʂ��ǂ̂悤�ɑ��ݍ�p���邩�Ƃ������Ƃɑ傫���ˑ�����Ƃ���܂��B
�����̃^�C���ƘH�ʂ̑��ݍ�p�ɂ̓^�C���̕ό`�A�M�A�H�ʂ̑e���ȂǕ��G�ȗv�f���܂܂�邽�߁A�ڐG�ʐς����C�ɋy�ڂ��e���ɂ��ĒP���Ȍ����͑��݂��܂���B
�����ԍ��F25926753
![]() 0�_
0�_
��SMLO&R����
�ق�ƁA�����J�ɁA�킽�����̋^��ɂ��������������A�ǂ������肪�Ƃ��������܂���
�킽�����̏��Ȃ����ł��A�Ȃ�ƂȂ��C���[�W�N���Ă��܂���
�����ԍ��F25926763
![]() 0�_
0�_
���˂��݂���B����
���Y�͉ו������������N���}�قǐ����������L�т܂��B
��
�P�ɐL�т�Ƃ��������ɂ��i���͋C�j�I�C�����邪
���_�l�łȂ�
���ۂ̓��H�ł͂ǂ��Ȃ낤
���_�l�ɕt��������t�@�N�^�[�����肻��ɑ傫�����E����ĐL�т�_���o���肵�Ă��Ȃ��̂��낤��
�����ԍ��F25926802
![]() 1�_
1�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���g���b�N�̖��ڎ��A�܂��͉ߐύڎ��́A�}�����̍ۂɏd�ʂ̑傫�����炭��X���b�v���������₷���Ȃ�A�����������L�т܂��B
���������ԏd�������Ă����������͓����A�Ƃ����̂́A�^�C�������b�N���鐡�O�Ńu���[�L��ێ�����A��������ABS���쓮����A�Ƃ����������̂��Ƃ������Ă���̂ŁA�^�C�������b�N�����琧�������������ē��R�ł��B
��p�Ԃł��g���b�N�ł����ǂ�ABS�̂��Ă��Ȃ��Ԃ͂قڂȂ��Ǝv���̂ł����A�Ȃ��^�C�������b�N����O��Ȃ̂ł��傤���B
�܂��A�����ɂ����Ă͏d�ʂ��傫���ƃX���b�v���������₷���Ȃ�A�Ƃ������Ƃ͂���܂���B
�ނ���A�X���b�v����������܂ł̃y�_���̃X�g���[�N�ƃy�_���ޗ͂͏d�ʂ��傫�����������܂��B�i�܂�A�u���[�L�������ɂ����Ɗ����A��胍�b�N���ɂ����Ȃ�j
�Ȃ��Ȃ炲���g�ŏ����Ă���������悤�ɁA���傫���������~�߂�ɂ͂�苭���u���[�L���K�v������ł��B
��SMLO��R����
�����������̐v�l�ȏ�̎��ʂł͍ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���܂���̂Ő��������͐L�т܂��B
�����A�����ł��܂���ł����B�ł�����������������������ƁB
���͎ԏd�������������^�C���̖��C�W���͑傫���Ȃ�Ƃ����F���ł����A�����ł͂Ȃ��Ƃ̂��l���ł��傤���B
�^�C���̖��C�W���ł͂Ȃ��u���[�L�̖��C�W���̂��Ƃ����Ă���Ƃ������Ƃł��Ȃ������ł����A�ő喀�C�W���ɒH�蒅���A�Ƃ����\�����悭������܂���ł����B
�i�^�C���̖��C�W���͎ԏd�ɂ��e�����܂����A�u���[�L�̖��C�W���͎ԏd��u���[�L�͂̑傫���ɉe�����Ȃ��Ƃ����F���ł��j
���Ȃ݂ɁA�����������悤�Ɏԏd�������邱�ƂŃ^�C���̖��C�W�����傫���Ȃ�̂ł���A���������͂���ɒZ���Ȃ肻���ł����A�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B
���˂��݂���B����
��https://www.nissan.co.jp/COMPASS/ISF/SS/MESSAGE/distance.html
�T�j�[1500�X�[�p�[�T���[���Ƃ͂܂����������Ԃł��ˁB
���̎���ł�ABS�̓O���[�h�ɂ��t���Ă����肢�Ȃ������肾�Ǝv���܂����A���̕��͂�ABS����������i�^�C���̐��\�����E�܂Ŏg���j�܂œ��ނ̂ł͂Ȃ��A���̎�O�̗̈�ŗ��ғ����悤�Ƀy�_����A�Ƃ����O��ŏ�����Ă���悤�Ɍ����܂��ˁB
�����ԍ��F25927226�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�u���C�W���v�Ɓu���C�́v��������Ǝg�������Ă���Ȃ��ƁA������Ȃ��ˁB
�����ԍ��F25927276
![]() 2�_
2�_
�����B�Ȃ�قǁB
�_�����Ⴀ��܂����A�lj��ɏ_�������܂���ł����B
�����ԍ��F25927291�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
>�ԏd�������������^�C���̖��C�W���͑傫���Ȃ�Ƃ����F���ł����A�����ł͂Ȃ��Ƃ̂��l���ł��傤���B
������Ƃ������Ⴂ���Ǝv���܂����A���C�W���ʂ��̂��̂͏d�ʂɂ���ĕω����܂���B�ʂ͖��C�ʂ̍ޗ��̑g�ݍ��킹(�A�X�t�@���g�ƃS���Ȃ�)�ƕ\�ʂ̏�ԂŌ��܂�܂��B�܂�d�ʂ������Ɩ@���͂������܂����疀�C�͂͑������܂����ʎ��͓̂����ł��B�����m�̒ʂ薀�C�͂͊���o��(�ԗւŌ����ƃ��b�N���)�ƒቺ���܂��B
�^�C���̕ό`�A�M�A�\�ʏ�ԂȂǂ͎��ۂ̐������̐��\�ɉe����^���܂����A��ʓI�ȏ������ł́A�����ɂ���Ă��ʎ��̂��ω����邱�Ƃ͖����Ƃ���܂��B
>�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B
�����F���ł��B
�������u�̐��\�ɂ��Ắu���H�^���ԗ��̕ۈ���v�ɋK�肪����܂��B�ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł��̂ł��S������܂�����ǂ����B
���́g���\�h�ɂ��Ă͓ǂݍ���ł��܂���B�܂������ԍH�w�̐��Ƃł���܂���̂œǂݍ���ł������o���Ȃ��Ƃ��낪���肻���ł��B
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S015.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S093.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S171.pdf
�g���b�N�y�уo�X�̐������u�̋Z�p�
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B010.pdf
��p�Ԃ̐������u�̋Z�p�
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B012.pdf
�A���`���b�N�u���[�L�V�X�e���̋Z�p�
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/B011.pdf
����K����13��(�ŐV�ł����m�F�A�Â��\������A�����Ȃ͍����V�����|��ł��J�����Ȃ��Ȃ������悤)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/un/UN_R013_01.pdf
Regulation No. 13 (�ŐV��)
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r013r6e.pdf
�Ԏ�̒�`��
M Power-driven vehicles having at least four wheels and used for the carriage of passengers
N Power-driven vehicles having at least four wheels and used for the carriage of goods
O Trailers (including semi–trailers)
�����ԍ��F25927450
![]() 0�_
0�_
�v>�ߐύڂŐ������������т�̂́AABS�������Ƃ���܂Ńu���[�L�͂��グ��̂Ɏ��Ԃ�������A�������́A�u���[�L�͂�����Ȃ��Ȃ�ABS�������Ƃ���܂Ŏ���Ȃ�����A�Ƃ����F���ł��B
�r�����F���ł��B
����
��ׂƖ��ύ�(��i�ύ�)�ł͂ǂ��ł��傤
�����ԍ��F25927466
![]() 0�_
0�_
����ȁ@�킴�Ɠ�����Ȃ��Ă�
���̂̂��G�l���M�́@�P�^�Q����������
���C�ɏ����G�l���M�́@�ʁ���������
�@���@���P�^�Q����������/�i�ʁ������j���P�^�Q������/�i�ʁ����j
����Ă����傫�Ȃ��f�Ɋ������Ƃ��Ă��@���@�ɉe�����Ȃ��@q.e.d
�����ԍ��F25927474
![]() 0�_
0�_
��SMLO&R����
���肪�Ƃ��������܂��B
�ő喀�C�W���܂ŒH�蒅���Ȃ��A
�͌�L�ŁA
�ő喀�C�͂܂ŒH�蒅���Ȃ��A
���������Ƃ������Ƃł��ˁB
���Ȃ݂ɍ��Z�����Ƃ͈Ⴂ�A�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω����܂���B
�������A���������͎ԏd�ɂ���ĕς��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������̂ɂ͕K�v�Ȃ����ƂȂ̂ŁA����ȏ�͏q�ׂ܂���B
��gda_hisashi����
����ׂƖ��ύ�(��i�ύ�)�ł͂ǂ��ł��傤
���_��͂���ύڗʁi��ρj�ł̐����������ŒZ�ƂȂ�A��ׂł͂�������L�т܂��B
�������Ȃ���A���̍��͒�ςƉߐύڂ̍��قǑ傫���Ȃ����߁A�e�X�g���Ă��o���c�L�̒��Ɋ܂܂�Ă��܂������ȋC�����܂��B
�i�G�ꂽ�H�ʂ⍂�����x�ł����������������܂���j
�����ԍ��F25927527�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
>���_���
�ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��
��͂蓯���ł�����
��̓��Y�͉R���Ȃ̂ł��傤��
�����ԍ��F25927574
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
>���Ȃ݂ɍ��Z�����Ƃ͈Ⴂ�A�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω����܂���B
��肪�Ƃ��������܂��B
�c�O�Ȃ��玄�̍��Z�����̒m���͈͓̔��ł́u�g��ʓI�ȏ������g�ł͖@���͂�����Ԃ̏d�ʕω����^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�W���ڕω������鎖�͖����v�ł��B
���C�W�����d�ŕω�����ƌ��������E�_���������ƒT���Ă݂܂�����������܂���ł����B�l�b�g��ɖ����A���������x���̎����ɂ͂���̂����m��܂���B
����Ď��͍��̂Ƃ���A���_��A���C�W���́g��ʓI�ȏ������g�ł͏d�ʂɂ���ĕω����Ȃ��Ɨ������Ă��܂��B ���C�W���̓^�C���ƘH�ʂ̍ޗ������̑g�����ł�����ł��B
���������ۂɂ́A�^�C���̕ό`�A�M�̒~�ρA�H�ʂ̏�ԁA���I�d�̕ω��ȂǁA�Ԃ̏d�ʂɂ�� �Ĉ����N������邠���̊ԐړI�ȉe�����A�^�C���̌��ʓI�Ȗ��C��O���b�v�� �e����^���ꌩ�����Ƃ��떀�C�W�����ω������悤�Ɍ����鐫�\�̕ω��ɂȂ���A�ƌ�����|�̐����͌�����܂��B
1. �^�C���̕ό`�ƃR���^�N�g�p�b�`�̕ω�
2. ���M�Ɖ��x����
3. �H�ʏ��
4. �^�C���̃R���p�E���h�ƍ\��
5. �^�C���̖���
6. �T�X�y���V�����Ɖd�ړ�
�u��ʓI�ȏ����v�Ƃ͓K�ȋ�C���̃^�C���A�K�x�ȑ��x�A�o�����X�̎�ꂽ�d�A�������������ꂽ���H�𑖍s����ʏ�̏��w���܂��B
�u��ʓI�łȂ������v�Ƃ͋ɒ[�ȓV��i�G�ꂽ�H�ʁA���������H�ʁA�����̘H�ʁj�A�ԗ��̉ߐύځA�����\���s�i���[�X�A�����R�[�i�����O�j�A�H�ʂ̉��ʂȂǁA�����͎������C�ɑ傫�ȉe����^���܂��B��ʓI�ɖ��C�W�����̂��̂͗^����ꂽ�ޗ��Ə����̑g�ɑ��Ĉ��ł����A�����̔��^�I�ȏ̓^�C���A�H�ʁA���Ԃ̓��I���ݍ�p�ɂ���ĊԐړI�Ɏ������C��ω������錴���ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F25927600
![]() 0�_
0�_
�X���`���̓��悪�A���ۂŌ����̎����ł͂Ȃ��̂��ȁB
�X���ŕς��v�f�����邩�ˁB
�����ԍ��F25927602
![]() 1�_
1�_
�g���b�N�̘b�ł́E�E�E
��ʓI�Ȋ����Ԃ̎ԗ��d�ʂŁA�u���[�L���\�̔F���ĂāE�E�E
�L�����s���O�J�[�ȂǁA�ꕔ�̓���Ȏԗ��ŁA���炩�̎���ɂ���āA���ޏ�̎ԗ��d�ʂ������Ă��܂��ƁE�E�E
�u���[�L���\�̔F�؊����O��A�Ԍ��ɒʂ�Ȃ��Ȃ�Ƃ����A�\�b�����������Ƃ�����܂�
����́A����������ƁA�ԗ����y���Ȃ�A�v�Z�������̏������ς��A�����������L�т鑤�̌��ʂɂȂ邩�炩���H
��gda_hisashi����
���Y����̘b�́A������Ɖ��������Ԃ��o�ꂷ�邭�炢�ł��̂ŁA�����̂`�a�r�����u���[�L�A�^�C���̐��\���A���قǂł͂Ȃ������̂�����̂�������܂��E�E�E
���_�I�ȁA��ΐ��\�̉R���z���g�̘b�ł͂Ȃ��A��ʃh���C�o�[�́A�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ����AJAF����Ɠ������ӊ��N�����āE�E�E
���ɁA���̘b�ł́A�ԊԂ��܂��傤�Ƃ������Ƃ����ƂȂ��Ă��܂�
�����ԍ��F25927621
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�ǂ�����������]�Ȃ̂�������܂��A���ۂɃe�X�g������ǂ��Ȃ邩�܂Ő��@���Ă��������܂�����B
����̓��Y�͉R���Ȃ̂ł��傤��
���Y�̎����ɂ͑O�������������Ă��Ȃ��̂ŁA��������ł͋U�ł���A��������ł͐^�ł��B
���̏����Ƃ͐�ɏ������ʂ�A�S���ABS����������悤�ɓ��ޏꍇ�͋U�ł���A���������O�̗̈�ň��̃X�g���[�N�ƈ��̗͂�ۂ悤�Ƀy�_���ޏꍇ�ɂ͐^�ł��B
�����ԍ��F25927628�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>��ʃh���C�o�[�́A�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ����AJAF����Ɠ������ӊ��N�����āE�E�E
�ׂ̈̍��b�i�s���悭�r�F�j���Ď���
�Ԃ��d���Ȃ�ƁA�~�߂ɂ����Ȃ�Ƃ���
�ƌ������͖����̂�
�i�`�e�����Y�����[�U�[�ɈӖ��Ȃ������������Ă����ł��傤��
�����ԍ��F25927633
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
���Ȃ��^�C�������b�N����O��Ȃ̂ł��傤���B
�n�ʂƂ̖��C��(���C�W��)���g�����l�@�ł́A�^�C�����b�N��Ԃ����C��(���C�W��)�ł��邩��ł��B
��L�ł������܂������A�ԗւ����ĉ���Ă�ȏ�͍l����ׂ��́A�]�����R(�]����W��)�ł��B
�����ɍׂ��������ł́A�����⌸�����~�ŏ������X���b�v�Ƃ������n�ʂƂ̎C�ꂪ�J��Ԃ���Ă܂����A����͖�������Ƃ��āA
����ABS�Ń^�C�����b�N���Ȃ��̂��X�^���_�[�h�ɂȂ����A
�̊�����ɂ���A���Ȃ��ɂ���A�ׂ����^�C�����b�N�������ɂȂ�ƃ^�C�������̂��J��Ԃ�ABS���l����ƁA
���C��(���C�W��)�ł͌v��Ȃ��̂͊�������Ǝv���܂��B
�������Ƃ���
���X���`���̓��悪�A���ۂŌ����̎����ł͂Ȃ��̂��ȁB
����̎���98km����38m�Œ�~�́A�l�b�g��̒�~�����̒ʐ�����ˏo���āA
���Ȃ荂���\�̃u���[�L���\�ł��B
ABS�̋@�B�I�e�N�j�b�N���D��ĒZ������~�Ȃ̂��킩��܂��A
��͂�ʐ��̌�����T�O�����Ă܂�܂���B
�����ԍ��F25927651�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�Ȃ���������̂�
�l���d�ʂƐ����������W�Ȃ����ė��_�����ێԂ����h���C�o�[�Ƃ��Ăɂ킩�ɐM�����Ȃ�����ł�
���g�ŏd�ʂɂ�鐧�������̎������s������ł͖����̂ŃG�r�f���X�͖����ł�
�ŐV�`�a�r�͂���������܂���
�l�̎Ԃ͂`�a�r���������u�Ԑ����������~�܂�Ȃ������o�܂��i���������L�т܂��j
��p�Ԃł����P�l��2�l�ł͕ς�������o�͂قږ����ł���
�R�l�ȏゾ�ƒʏ�ł������Ȃ������������܂������ێ~�܂�̂ɋ����͑����܂�
����ɂ��Ă͂����܂Łh���h�ł�����̃X��������߂����
�y������Ńu���[�L���邩��ŏd�ʂ�]���ϊ����ŏ����狭�����߂Ή������ĈӖ������͗����ł��܂�
�ł��������ނƂ`�a�r�����������d�ʂɂ�門�C�W���t�o�Řd���Ă���Ƃ͊������Ȃ�
�͍̂��o�Ȃ̂�
�u���[�L�̈������������̂�
�����ɋC�ɂȂ鏊�ł�
�����ԍ��F25927653
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
���ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��
����͂蓯���ł�����
���ۂ̊X���ł̃u���[�L�ƁA����́u�����e�X�g�v�ł͓��ݕ����S���Ⴂ�܂��B
���̐����e�X�g�ł̓��[�C�h���I�Ńu���[�L���h�J���Ɠ��݂܂��i���ABS�C���Łj
��ɃX���傳���Љ�Ă��ꂽ���N���}���d���Ȃ��Ă����������͕ς��Ȃ���
https://vehicle-cafeteria.com/braking.html#google_vignette
�̖`�������̎ʐ^���グ�܂����B
�����ŏ��Ƀp�b�ƌ������́u���₢��A�u�����{�̂ق����c�v�Ǝv���܂������A
�m�[�}���u���[�L�ł��h�J���Ɠ��߂Ƃ肠�������ʂɃ��b�N���鐫�\�͂���킯�ŁA
�u�����{���̗ǂ��͏��������Ƃ��R���g���[�����Ƃ��́A�e�X�g�ŋ��߂���̂Ƃ͈Ⴄ�ǂ��ŁA
�ł��̂œ��Y�̋L���Ƃ�����̊X���Ƃ��́u�����Ɠ������ݕ����Ǝv�������~�܂�Ȃ��v�ƌ��������ƁB
�܂�JAF�̋L�����u���[�L���\�̌��E�ȑO�ɁA�E�G�b�g�H�ʂŃ^�C������Ɍ��E����悤�ɂ������̂ŁA
�����܂ł����ӊ��N�̈��ƌ��������Ǝv���܂��B
�܂����͍��Z���������S���킩��܂��A��̇��N���}���d���Ȃ��Ă����������͕ς��Ȃ����̋L���́A
�����P���Ȃ̂ŕ��ʂɓǂ�Ŕ[�����܂����B
�����ԍ��F25927674
![]() 2�_
2�_
�����_��́@�@�ł͂Ȃ����ۂ̊X�i���H�j�ł͂ǂ��ł��傤��
�l�o��܂��˂��B
���Z�������x���̓��i���j�ł͂������������낤�Ɨ������Ă��܂��B���m�ɂ̓l�b�g���ł����[�����Ă���̂Ŏ��̒m���ł�����܂��B
��^�Ԃ̏ꍇ�ɉd�����ɂ�鐧�������̕ω����傫�����R�͂������̗v�f���֘A���Ă��āA�����̗v�f�����݂ɉe�����܂��B���ɖ��ڎ��̏d�ʑ����͐��������ɑ傫�ȉe����^���鎖������܂��B
1. �d�ʂ̑傫��
��^�Ԃ͊�{�I�ɑ傫�Ȏ��ʂ������A��i�ݕ��ڂ����ۂɋ�Ԏ��Ɣ���ʂ��啝�ɑ������܂��B�ԗ��̉^���G�l���M�[�͎��ʂɔ�Ⴗ�邽�߁A���ʂ���������ƒ�~����̂ɕK�v�ȗ͂Ǝ��Ԃ��傫���Ȃ�܂��B��^�g���b�N�ł͂��̏d�ʕω��������ʼnd�ω��̉e���͑傫���ł��B
2. �u���[�L�V�X�e���̕���
��^�Ԃ̃u���[�L�V�X�e���͕��L���d�����ɑΉ�����悤�v����Ă��܂��B���������ڎ��ɂ̓u���[�L�V�X�e���ɂ����镉�ׂ��������A���ɒ����Ԃ̃u���[�L���O��}�u���[�L���ɉߔM���������₷���Ȃ�܂��B�ߔM�����u���[�L�͐����͂��������ߐ��������������Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
�i���F ���{�̑�^�g���b�N�̐����n�͒�i�ݕ��ڂ����ꍇ�ɂ��^�C�������b�N�����邩ABS�쓮���O�܂ł̐����͂����悤�v����Ă���A�ƕ����B�v����ɐ�q�����ۈ���ŋK�肷��ȏ�̐��\�j
3. �^�C���Ɛڒn�ʐ�
��^�Ԃł͉d�ɂ��ԗ��d�ʂ̑����ɂ��^�C���ւ̕��ׂ����������ɁA�^�C���̐ڒn�ʂ̌`��ω�����p�ԂȂǂ��傫���^�C���ƘH�ʂ̖��C���s�ψ�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
��^�Ԃ̃^�C���͏�p�Ԃɔ�ׂčd����C�����������߉d�̑����ɂ���Đڒn�ʐς��������ω����A���ɋ}���ȃu���[�L���O���Ɍ����I�ɗ͂�`����̂�����Ȃ�܂��B
4. �ԗ��d�S�̍���
��^�Ԃ͎ԗ����̂̏d�S����p�Ԃ����������Ƃ���ʓI�ŁA�d�S�������ƃu���[�L���O���ɑO��̉d�ړ����傫���Ȃ�A�t�����g�^�C���ɕ��ׂ��W�����₷�����A�^�C���ƘH�ʂƂ̐ڐG�������������I�ȃu���[�L�͂������ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���ɖ��ڏ�Ԃł͂��̉d�ړ��������ɂȂ�܂��B
5. �T�X�y���V�����V�X�e���̉e��
��^�Ԃ̃T�X�y���V�����V�X�e���͉d���~�߂邽�߂Ɋ��ɍ���Ă��܂����A�d�����ɂ��T�X�y���V���������ݍ��݂�����Ǝԗ��̈��萫���ቺ���A�^�C�����������H�ʂɐڐG���ɂ����Ȃ�܂��B������u���[�L���\�̒ቺ�Ɛ��������̉����Ɋ�^����v���ł��B
6. ���C�W���Ɖd�̊W
���_�I�ɖ��C�W���͎ԗ��̏d�ʂɈˑ����Ȃ����ߏd���Ȃ��Ă����C�͂���Ⴕ�đ������܂��B���������ۂɂ̓^�C���̖��Ղ�H�ʏɂ���Ė��C�͂��œK�ɔ�������Ȃ����Ƃ�����܂��B���ɑ�^�Ԃ͖��ڎ��ɘH�ʂɑ��鈳�͂��傫���Ȃ�A�^�C���̊���₷���������Ė��C�͂��\���ɔ�������Ȃ��\��������܂��B
�������ۂ̋�̗�͐獷���ʂ̏ꍇ�������A����玖�Ⴊ���_�ƊT�ˈ�v���Ă���Η��_�Řb���Ηǂ������̎����Ǝv���܂��B�ʏ����ɍ��E���ꂽ���ʂ��ڍׂȃf�[�^�����ɂ������������ƒNj����Ă����܂�Ӗ�������Ƃ͎v���܂���B����͊T�ˁg�덷�h���邢�́g�펯�I�����g�ł��B
���_����ɂ����Ċϑ���Ŋm�F����ꍇ�Ƒ����̊ϑ��l�������Ă��̌��ʂꂷ�闝�_���\�z����ꍇ������܂����A�ǂ���������l�͓��v�I���z�����Ă��Ă��̕��U���召���܂��܂ł��B�������݂̗��_�Ƒ啝�ɈقȂ铝�v�I�ɗL�ӂȌ��ۂ���������V���_���\�z�ł��܂��B
�����ԍ��F25927681
![]() 0�_
0�_
�t����������^�C���̓��b�N����ABS���쓮���܂��B
���̎��_�Ń^�C���̕��ה\�͂��Ă܂��B
ABS���L���Ă������Ă����ۓI�ɂ͓����B
�m���Ƀ^�C���d��������^�C���̖��C�~�͑傫���Ȃ�܂��B�������A�����͂͂��������܂��B
��ׂł��낤�ƃt���ύڂł��낤�ƁA�t�������Ń^�C���̌��E����̂ŁA�����͂��傫���قǐ��������͐L�т܂��B
�t�Ɍ����A�^�C�����E�����鐧���͂ƂȂ�悤�ɃN���}�͏o���Ă��܂��B
�����Ŗ�����Ί댯�ł��B
�w��I�m�����S���������ŁA�悭���l���ɂȂ�����l�b�g�������Ă���̂͑f���炵���Ǝv���܂����A�����̊�{��N���}�ɂ��Ă̑�O�R���Ɛ����ɒH�蒅�������������������������B
�����ԍ��F25927701�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
> �t����������^�C���̓��b�N����ABS���쓮���܂��B
�ŋ߂�ABS�̓^�C�������b�N�������A���������b�N���O�̏�Ԃ��ێ����œK�ȃu���[�L���\���m�ۂ���悤�p���I�Ƀu���[�L�͂����Ă��܂��B
�����ԍ��F25927714
![]() 0�_
0�_
�������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�A������c�_���Ă����ʂł��ˁB
���Ӗ��ȃX���ɂȂ��Ă��܂��܂����ˁB
�����ԍ��F25927723
![]() 1�_
1�_
���������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�
���_�͂Ƃ������A
���s��1��̎������I舂ɐM�����Ⴄ�����ǂ������Ă�B
�{�C�ł��Ȃ�A
�C�����u���[�L�p�b�h�̉��x���s�x�s�x���肵�āA
�������s���Ď����l�̕����Ƃ��āA
�Ō����Ă����X�����琄�_��W�J�����_�Ɏ���B
���炢�͂��Ȃ��ƁB
���Ȃ݂Ɏ��͏d���Ȃ�ΐ��������͐L�т�h�B
���ۂ͈���Ă��Ă��\��Ȃ��B
���ۂ͂��Z�������Ŏ~�܂ꂽ�Ƃ��Ă��A
�����������L�т�Ǝv���Ă����ĕs���v�͂Ȃ��B
�l�𑽂��悹��A�ו��𑽂��悹��A
�����������L�т�Ǝv���Ă��T�d�ɉ^�]����B
�h���C�o�[�̐S�\���Ƃ��Ă͂��ꂪ�����B
�����ԍ��F25927745
![]() 0�_
0�_
������A�u�^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω��v�̌��ł����A�������ۂ̔����܂߂����v���܂��B
ABS���y�ȑO�̃o�C�N���Ȃ番����܂����A
�O�^�C���ɉd���|����Ȃ���Ԃ���t���u���[�L���Ă������Ƀ��b�N���邾���Ŏ~�܂�Ȃ�����Ȃ����ŁA
�܂��̓W���b�ƈ����đO�^�C����ׂ��Ă���t���u���[�L���܂��B
�d��������قǁA�^�C���̐��\�͈͓��ŃO���b�v���܂��i�^�C���ő含�\�������o���܂��j
����ȏ�ɐ����������k�߂悤�Ƃ��܂��ƃn�C�O���b�v�̃^�C���ɕς�����A
�u���[�L���\��R���g���[���������߂ău���[�L�V�X�e�������ւ����肵�܂��B
����10/13�Ƀo�C�N���[�X��MotoGP�Ň��G�A���p�[�c�g�p�Ń_�E���t�H�[�X���Ƃ̏������݂����܂����B
���ہA�{�f�B�J�E���ɃE�C���O��t���āA���^�C���ɉd��������u���[�L���\�i�^�C���O���b�v�j����������܂����B
���̓s���A����G�Ƃ������オ��ŁA�u���[�L������Ȃ���2�{�̘r�ő̂��x����̂̓g���f���ȏ�Ԃ��ƁB
�܂����[�X�̂����200km/h��300km/h�̘b�Ŗ{�肩��͗]�v�Șb����ł����A
���ǁu�d�̓O���b�v�Ɍq����v�ƁA���͎v���Ă��܂��B
�����ԍ��F25927753
![]() 0�_
0�_
���������ʂ����_���M���Ȃ��ƌ����Ȃ�A������c�_���Ă����ʂł��ˁB
���ǁA�l������M���邩�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
�d�����S���Ƃ��傫�ȐƂ����ł������ł����A
�n�ʂɂ�������Ԃʼn����@���@����d�����A�n�ʂƂ̖��C�͂���p
��Ԃɏ悹�ĉ����@���@����O�҂ɔ�y���͂ōς݁A�n�ʂƂ̖��C�͂͂Ȃ��A�ԗւ̓]�����R����p
����͂�����x�̔N��ɒB����ΒN�����o���������Ƃ���͂��ł����A�����Y��A
�ԂŒn�ʂƂ̖��C�͂��X�^�[�g�ɍl���Ă��܂��܂�����B
�����Ƃ炵�����������͂ŁA�l�͊ȒP�ɐM���Ă��܂��܂��B
�l�b�g�̐^�ʖڂɏ����Ă镶�͂��������Ƃ͌���܂���B
�ʂɁA�����S�Đ������Ƃ������Ă�킯�ł͂���܂���B
�����ԍ��F25927755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
SCM 416����
�̃R�����g�����������ǂ����łȂ�
�����悤�ɐF�X�Ȋp�x���炠�蓾��A�\�����l��������
�`�a�r�������Ă�����Ď��͂�����ɂ��Ă��^�C�����E�t�߂ł����
���ꂪ���̎Ԃ̎~�߂鐫�\���E���Ď��ł����
���̌��E�l���d���Əオ����Ď���
SCM 416����̌������������}�����ނ��ė��_�Ȃ�ł����
�i�d�������^�C���̌��E�l�������A�ǂꂾ�������A�����̖@�����͂˕Ԃ���j
�����ԍ��F25927764
![]() 0�_
0�_
����̎ԂŃu���[�L���\�������A�^�C����H�ʏ������Ȃ�A�}�u���[�L�����������A�ԏd���d���Ȃ�ΐ����������L�т�͓̂�����O�̂��Ƃł��傤�B
�d���Ȃ�u���[�L�ŕ��M���ׂ����M�ʂ������Ȃ�A�u���[�L���O���Ԃ������K�v�ɂȂ邩��B
�R�z�@���Y����A�b�v�̃g���b�N�ߐύڂ̐��������̕\�̒ʂ肩�ƁB
�\�ɂ͂Ȃ����ǁA�ߐύڂłȂ���ׂ�100�p�[�Z���g�ύڂ̔�r�ł����������͐L�тĂ���͂��B
�����A���������ǒ�ʐύ�(100��)�̎��̐������������̃g���b�N�ŗL�̐��������Ƃ������Ƃł����āA��ʖ����Ȃ瓖�R�����萧�������͒Z���Ȃ�ł��傤�B
��^�ݕ��Ȃǂ́A���ԂƖ��ڏ�Ԃł͑̊��I�ɂ��~�܂肩�����S�R�Ⴄ����ˁB
�����ԍ��F25927774�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���^�C���̖��C�W���͉d�ɂ���ĕω�
���ۂɂ͉��x�Ƃ��ׂ�i�����I�Ȗ����x�j�Ƃ��Ŋ��o�I�ȈႢ�͏o���ł��傤���ǁA������v�Z�ɑg�ݍ��ނ��ǂ��������̋C�����܂��B
���`�a�r�������Ă�����Ď��͂�����ɂ��Ă��^�C�����E�t�߂ł����
ABS�̐���i�^�C���̋�]���ǂ̂悤�ɏE���ǂ̂悤�ɐ�����������̂��j���ւ��̂�ABS�O�ƌ����ɂ����Ȃ邩�ƁB
�H�ʂ̂Ƃ̖��C������^�C���̌��E�͒Ⴍ�Ȃ�܂�����A��芵���͂��x�z�I�ɂȂ�܂��B�t�ɍl����A�O���b�v���ǂ��H�ʂȂ�d�ʂɂ�鍷���o�ɂ����Ȃ�͎̂��R���ƁB
�����ԍ��F25927779�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�����ς��Ȃ��ł���
���Ċ���ŗ��_�I�ɏؖ��������ăX��
�݂����ł�
���o�I�ɂ͓��ӂȂ�ł���
����͂Ȃ�����
�グ���Ă��闝�_�Ɖ����Ⴄ�̂����Ȃ��̂�
�������������Ă��łȂ�
�^���A�������m�肽��
�����ԍ��F25927781
![]() 0�_
0�_
�t���N�V����(���C)�ƃO���b�v�͈قȂ���̂ł��B
���m�Ɏg��Ȃ��Ƃ��咣�̈Ӗ����s���m�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25927791�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����̌��E�l���d���Əオ����Ď���
��SCM 416����̌������������}�����ނ��ė��_�Ȃ�ł����
���E�l���d���Əオ��Ƃ����̂����邩������܂��A
�S��Ƃ�ABS�������Ă��āAABS�̌������Ő��\�̃L���p���Ȃ̂��Ǝv���܂���B
���Ԃ�S��Ƃ�ABS�������Ă�͂������A
�S��ڂɃh���C�o�[���uABS�������Ă�v�ƁA�O3����h���C�o�[���̊����ĂȂ������ŁA
�������Ƃɒi�K�I��ABS�������������Ȃ��Ă�͂��ł��B
�����ԍ��F25927794�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��SMLO&R����
���t���N�V����(���C)�ƃO���b�v�͈قȂ���̂ł��B
���܂肻������ʂ���Ӗ��͂Ȃ����ƁB�v�Z��́u���C�́v�A�����I�ɂ́u�O���b�v�v�B���E�t�߂ł͊�����������Ă��邾�낤���B
�ύڂ����g���b�N�̐����������L�т�̂̓u���[�L�̓��͂�\���W���邾�낤���A�O���b�v�̌��E�t�߂܂œ��ݍ��߂i���R���̓��͂͋�ׂ̎��Ƃ͈قȂ邵�A�����܂Ō������ǂ����͊����͂�H�ʂ̖��C�͂ɑ���u���[�L���\�ɂ��ˑ��j�A�u���C�͂ƃu���[�L���\�������͂��x�z�I�ł������v�͐��������ɍ��͏o�Ȃ����ƁB
�����ԍ��F25927806�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
JAF�����Y���A�������gda_hisashi����̔����o���A�R��ԈႢ�ł͂���܂����
���߂ł́A�������`�����������Ă���ʂ�A���ۂ̘H��ł́A��[���h���Ńt���u���[�L�ȂL�蓾���E�E�E
���Ƃ��R���}���b���̘b�ł��A�u���[�L�y�_���̃X�g���[�N�⑫�̋ؓ��̔������Ԃ��K�v�ŁA�D�G�ȃu���[�L�A�V�X�g���������Ƃ��Ă��A�����ύڂ������Ă���ƁAABS�쓮�̈�܂ł̎��Ԃ������Ă��܂��܂�
���̃R���}���b�����A�����[�g���̍��ƂȂ�A���ʁA�������邱�Ƃ����邩������܂���
���Ƃ́A���Ƃ����b�N���Ȃ��D�G��ABS���������Ƃ��Ă��E�E�E
���ʑ�����A����ɔ����d�S���㏸�́E�E�E
�^�C����H�ʏ̈����A�ԗ������Ȃǂ̏����ɂ���āE�E�E
������������萫�ɂ́A�m���ɕs���ɓ����܂�
�댯�ɑ�����S�̍l�����̈�Ƃ��āE�E�E
�G�l���M�[���オ��A���Ӂ@�ł�
�^���A�M�i�Ⴍ�Ă��j�A�ʒu�A���͓��X�E�E�E
���i�C�g�G���W�F������
�g���b�N�́A��ׂ��ƁA�}�u���[�L���A�ɒ[�ɑO�։d�����������āA�O�փV���O���Ȃ̂ŁA�^�C���̐��\���Ă��܂��݂����ł�
�܂��A���ۂ̘H��ł́A��ׂ��ƌ��̃o�l���A�⏕�o�l�܂Ŏg��Ȃ��Ă��d���A�_���p�[���L���Ă������Ă����˂āA���肵���O���b�v�m�ۂ�����̂ŁA���ʁA��ׂ̋}�����ł́A�ӊO�Ɛ����������L�тĂ��܂��݂����ł�
����ƁA�G�A�u���[�L�ł��̂ŁAABS������A�܂����ǂ��̏�p�ԕ��݂Ƃ͌����Ȃ��݂����ł�
���Ȃ݂Ƀh�����u���[�L�́A���M���������ł����A�ꔭ�̐����͂́A�f�B�X�N�u���[�L��苭�͂炵���ł�
�����ԍ��F25927823
![]() 2�_
2�_
���O���b�v���ǂ��H�ʂȂ�d�ʂɂ�鍷���o�ɂ����Ȃ�͎̂��R���ƁB
��^�g���b�N�ł�ABS�����Ȃ�}�u���[�L�[���݂ŗe�ՂɃ^�C�����b�N����͂��ŁA
���ǂ́A�^�C�����n�ʂ��Ƃ炦��(���O���b�v�H)���ǂ����̖��ł���A
������̎咣�͐������Ǝv���܂��ˁB
�^�C���̕����C�ɂȂ�Ƃ���ł����B
�����ԍ��F25927824�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���C�W���Ɩ��C�͂���������ɂȂ��āA�����^����ł��ˁB
���C�́����C�W���������t����d
�ł��B���C�W�����ÂƓ��ȊO�ɂǂ��ω�����͂��Ȃ荂�x�Șb�Ȃ̂ň�U�u���Ă����āA
�ԏd��1.2�{�ɂȂ�A�^���G�l���M�[��1.2�{
�ԏd��1.2�{�ɂȂ�A�^�C�������ޖ��C�͂�1.2�{
�u���[�L���ǂ�ȑ��x����ł��t�����b�N�ł���قNj���Ȃ��̂ł������ꍇ�A���Z�����I�ɒP���Ɍ����A�u���������͕ς��Ȃ��v�ɂȂ邩�Ǝv���܂��B(����������ĕςȂ��ƌ����Ă���l���܂���)
�ߐύڂ̑�^�g���b�N���A���肪�������Ƃ��Ɏ~�܂�Ȃ��̂̓^�C���̖��C�͂ł͂Ȃ��A�u���[�L���M�e�ʂ��Ė��C�͂��s�����Ă��܂�����ł��ˁB
�����Ă���Ƃ��̎��ۂ̃^�C���͓����C�ƐÖ��C�̊Ԃɂ���ł��傤���A�u���[�L���\�Ɠ��͂Ɨe�ʁA�O�q�̕ό`������̖̂��C�͉͂d�ɑ��ĒP����Ⴕ�Ȃ��\���A�����̍���o���c�L�A�ȂǂȂǂ��낢��ȗv�f�������āA���������͕ς��Ȃ����A������ƐL�т邩�̊Ԃŕω�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����c�B
�����ԍ��F25927917
![]() 2�_
2�_
��gda_hisashi����
>���o�I�ɂ͓��ӂȂ�ł���
����͂Ȃ�����
��p�ԂɈ�l��Ԃ̎��ƁA�t����Ԃ̎��ƂŁA�R��ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�t���u���[�L���O�ł̐��������͕ς��Ȃ����낤���ǁA��������Ȃ��ł���B
�t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B
���̑������������������ɂ�����邩�ƁB
�����ԍ��F25927923�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����������ɂ����錋�ʁ@���Ă���
���������͂��܂��ܓ������낤���^���G�l���M�[�͑S�R�Ⴄ�i���R�^���ʂ��j
�����ԍ��F25927931
![]() 0�_
0�_
���t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B
���̑������������������ɂ�����邩�ƁB
�����͂Ɩ��C�͂��u���[�L�̌��E���Ȃ��͈͂ł���A������Ȃ����ƁB���̏ꍇ�A�������ɔR����]�v�ɐ����̂Ɠ��l�ɁA�u���[�L�ŕ��̉����x��]�v�ɗ^���Ă��i�������ݍ��ށj�����B
�O��̉d�o�����X���ǂ����i������x�d�����������j����ׂŌ�ւ̉d����������Z�߂Ŏ~�܂ꂻ���B�o�C�N�̌�փu���[�L��z������ƕ�����₷���B
�����ԍ��F25927945�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���t����Ԃœ������R��(����)��������A������~�߂邽�߂̃u���[�L���O(�o��)�����l�ɑ����邩��B
�������u���[�L�̔M�ʁi�d���ʁj�͑����܂����A
���ʂ̏�p�ԂȂ�u���[�L���\�̌��E�����^�C���O���b�v�̌��E����ɂ��܂��B
���������̂Ŋ��o�I�ȏ������ɂȂ�܂����A�^�C���O���b�v�̌��E����l��ԂŁu���C��100�v���Ƃ��āA
�u���[�L�͌J��Ԃ��̎g�p���܂߁A���X���Ȃ葽�߂́i���C��150�Ƃ�200�Ƃ��j�L���p������Ǝv���܂��B
�Ԃ̏d�ʂ�1.2�{�ɂȂ��ă^�C���O���b�v�̖��C�͂�1.2�{��120�ɂȂ������ŁA
�܂��܂��u���[�L�̐��\�͈͓��ł��̂ŁA��Ƀ^�C����������ABS���쓮���܂��B
����ău���[�L���\�̃L���p����Ƃ�ł��Ȃ��ߐύڂł����Ȃ��ƁA�����͐L�тȂ��ł��傤�B
���̎���ABS����������ɏd�ʂɕ����āA�O���b�v�̂܂܃Y���Y���Ɖ����o������Ԃ��ƁB
�����ԍ��F25927953
![]() 0�_
0�_
�l�����������
�ǂݕԂ��Ă݂�
SMLO&R �����
�������o�����_�Ċ����͌y��������
�܂�����
���̊����͉^���G�l���M�[�Ƃ��ēo�ꂷ�邪
���_(����)�ɂ͈����Ȃ�
�^���G�l���M�[���Ȏ҂�
���������藧�̂͏d���Ŗ��C�͂�������ƂȂ��Ă��邪
�^���G�l���M�[�������邠���肪�����Ă��Ȃ�
���C�͂͑����~�߂�͂������Ă�
�^���G�l���M�[�̑����ɂ͏��ĂȂ��̂�
�����ԍ��F25928006
![]() 1�_
1�_
�����C�͂͑����~�߂�͂������Ă�
�^���G�l���M�[�̑����ɂ͏��ĂȂ��̂�
���X����ł����ǁA�^���G�l���M�[�̑������̓u���[�L���i���C�͂̌��E�͈̔͂Łj�������ނ��Ƃ��A�����Ă���C�����܂��B
�y����Ԃł͖��C�͂����Ȃ��̂Ńu���[�L�̓��b�N���Ղ��A�d���������Ԃł̓��b�N����܂ł�苭�����ݍ��߂�͂��ł��B
�����ԍ��F25928025�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>�^���G�l���M�[�̑������̓u���[�L���i���C�͂̌��E�͈̔͂Łj�������ނ��Ƃ��A�����Ă���C�����܂��B
�X���̗��ꂩ��u���[�L���\���̂͊�{�I�ɑ����
�`�a�r�t�߁i�^�C���̖��C�͂l�`�w�t�߁j���O��ł͂Ȃ��ł���
�����ԍ��F25928080
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
> �������o�����_�Ċ����͌y�������Ă܂�����
>���̊����͉^���G�l���M�[�Ƃ��ēo�ꂷ�邪���_(����)�ɂ͈����Ȃ�
�G�l���M�[������̗L���Ȍ������������������Ƃ̊W�ɂ��ĐG��܂����B�@�����ԍ��@25926599
����ŐF�X�ƃo���o���Ə����܂����̂œ��ꐫ�Ɍ����A��є�тł܂Ƃ܂肪�Ȃ��\����Ȃ��ł����A��{�I�ɏ��������e�͎����Ŋm�F���Ă��܂��B
���x���J��Ԃ��܂����A���_��A���������͎ԏd�Ɩ��W�ł��BWEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/TeisiKyori.html
���������ۂɂ͎ԏd��������Ɛ�����������������ꍇ������܂��B
����̓A�i���O�̐��E�ł͗��_���f���i�P�������Ă���j�ƕ��G�Ȏ��ۂ͈Ⴄ����ł��B���Ƀt���N�V�����ƃO���b�v�͈Ⴂ�A���ۂ̎Ԃō�p����̂̓O���b�v�ł����A���_���������Ă���̂̓t���N�V�����ł��B�t���N�V�������O���b�v���͎��Ă��܂������̋��ڂɂ͞B���ȗ̈悪����܂�����{�I�ɕʊT�O�ł��B
������ƌ����ė��_���f�������ɗ����Ȃ��킯�ł͂���܂���B���_���f�����o���_�ł��B���̃X�����u�w��Ԑl���������Ă����������͓����x���ăz���g�H�v����n�܂��Ă���Ƃ��������ł��B�����玄���܂߉��l���́u���_�I�ɂ͂��ꂪ�������v�Ɠ�������\���グ�Ă��܂��B
�����ČʃP�[�X�ŗ��_�Ǝ��ۂƂ͉����Ⴄ���͗l�X�ł�����A�������̂ǂ��Ⴄ�̂��̋c�_�ɂ͉��l������܂��B���̒萫�I�Ⴂ�̈������X�g�A�b�v���܂����̂ŎQ�l�ɂȋ����Ă݂Ă��������B
�u�w��I�m�����S���������ŁA�悭���l���ɂȂ�����l�b�g�������Ă���̂͑f���炵���Ǝv���܂����A�����̊�{��N���}�ɂ��Ă̑�O�R���Ɛ����ɒH�蒅�������������������������B�v�Ƃ̂��w�E�͌����Ɏ~�߂����Ē����܂����A�R�o�L�ڂ𓊍e��������͂���܂���B
�Ȃ��ŋ߂�ABS�̓��b�N���Ȃ��M���M���Ő��䂵�Ă��܂�����A�t���u���[�L���O���Ă���Ό������b�N��Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ݔ����C�����Ŏv���蓥�߂ΒN�ł��قڍő喀�C�͂����鎖���ł��܂��B�Ƃ͌������̌����͔����ȃX���b�v�����o����1�b�Ԃ�10-20��̃I���I�t�����鐧��ł�����A����������ɂ͋������L�т܂��B
�����ԍ��F25928107
![]() 1�_
1�_
�u���[�L�́A�ǂ���̏ꍇ���AABS�����Ŗڈ�t��������ł��āA�^�C�����b�N���Ă��Ȃ��̂́A�O������ł̔�r������B
�d�����������������L�т�͎̂����̗��ł���B
�����ԍ��F25928113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B
�������L�邩��ԈႢ�Ȃ����ĕ������܂�
�Ԉ���Ă���Ƃ����Ă����ł͖���
���o�Ɣ�ח����ł��Ȃ������ł�
���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�
�t�Ɂi�g���b�N�Ō����j���ɂP�O���i��j�Q�O���i���ځj�e�X�P�O�O����/������̉^���G�l���M�[���O�i�~�߂�j
�����������ɂȂ�̂ł��傤��
�����ԍ��F25928134
![]() 1�_
1�_
>WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B
�������L�邩��ԈႢ�Ȃ����ĕ������܂�
�Ԉ���Ă���Ƃ����Ă����ł͖���
���o�Ɣ�ח����ł��Ȃ������ł�
���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�
�t�Ɂi�g���b�N�Ō����j���ɂP�O���i��j�Q�O���i���ځj�e�X�P�O�O����/������̉^���G�l���M�[���O�i�~�߂�j
�����������ɂȂ�̂ł��傤��
�����ԍ��F25928144
![]() 1�_
1�_
���������ł��Ă��Ȃ����𗝉����܂����B
���C�W�������Ō�������Ƃ��A������^���G�l���M�[���ԏd�ɔ�Ⴗ�邱�Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F25928151
![]() 2�_
2�_
ABS�͉�]�������m���ē����̂ŁA���ɖ��C�͂̌��E���Ă��܂��ˁB���̏�Ԃł͐Ö��C�����߂��ɂ͊����͂����Ȃ������L���ɂȂ肻���ł��B
�����̗v��������ŋN���鎖�ۂȂ̂ŁA�u�d�����������������L�шՂ��v�Ǝv���Ă����Ηǂ��Ǝv���܂��B�H�ʂ�������ԂɂȂ�قǂ��̌X���͋��܂�͂��Ȃ̂ŁA���S�^�]�Ɋ�^����������Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25928156�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
> �t�Ɍ����A�^�C�����E�����鐧���͂ƂȂ�悤�ɃN���}�͏o���Ă��܂��B
> �����Ŗ�����Ί댯�ł��B
�댯�ł����A�^�C���̔\�͂����ė]���Ă����Ԃł��������Ȃ����Ƃł�
�N���}�̉^�����\�����߂�ł��V���v���ȕ��@���^�C�����O���[�h�A�b�v���邱�ƂŊԈ���Ă��Ȃ��ł��傤
F1�ł��^�C�����\������Ƃ��������ꂿ�Ⴂ�܂�����
�����ԍ��F25928297
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
���� WEB�̌v�Z�T�C�g�Ȃǂł���~�����v�Z�ɃG�l���M�[���d�ʂ������܂���B�ԑ��Ɩ��C�W�������ł��B
�� ���ꂪ�Ȃ��K�v�����������������ł�
SMLO&R����̌����鎮�ɁA�d�ʂ�^���G�l���M�[�������ĂȂ��̂́A�S���W�Ȃ�����ł͂Ȃ��A�P�����_�ɂ����Ă͑ł����������ď����邩��ł��傤�B
���q�ƕ���ɓ��������|����ƁA�l�͕ς�炸���̂܂܂ł���ˁB
�d�ʂ��������̂�����A�^���G�l���M�[���������B(�~�܂�ɂ����Ȃ�)
�d�ʂ��������̂�����A�^�C���̖��C�͂��������B(�~�܂�₷���Ȃ�)
�ǂ������x�z�I�Ȃ́H�͎��ۂɂ͂��낢�날�邯��ǁA�u���[�L�����G�̋����ŁA�����̒P�����������ōl����A�ǂ����2��Ƃ��͓����ĂȂ��āu�d�ʂɔ��v�Ȃ̂ŁA1.2�{����1.2�Ŋ��邩�猳�̂܂܁A������(�P��)�v�Z������͏������Ƃ��ł���A�Ƃ����Ӗ��ł���ˁB
�����ԍ��F25928324
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���n�ʂƂ̖��C�́i���C�W���j���g�����l�@�ł́A�^�C�����b�N��Ԃ����C�́i���C�W���j�ł��邩��ł��B
���݂܂���B���̓lj�͂ł͋��Ă��邱�Ƃ�������܂���B
�}�Ɏ��͓��{�ꂪ�ǂ߂Ȃ��Ȃ������̂悤�ł��B
�w���̍l�@�ɂ�����^�C���ƒn�ʂƂ̖��C�͂Ƃ́A�^�C�����b�N��Ԃ̖��C�͂ł���x�Ƃ������Ƃ����Ă��܂����H
�^�C��������Ă��Ă��n�ʂƃ^�C���Ƃ̊Ԃɖ��C�͔͂������Ă��܂���B��������Ȃ��Ɖ������������ł��܂���B
�w���Ԃɍڂ��ĉ����ƒn�ʂƂ̖��C�͂��Ȃ��Ȃ�x�Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���B��Ԃ̃^�C���ƒn�ʂ̊Ԃɖ��C�͂����邩��A��Ԃ̃^�C���͓]����̂ł��B
�����̕�������܂łɏ�����Ă���^�C���̖��C�W���Ƃ́A���b�N���Ă����Ԃł̖��C�W���ł͂Ȃ��A�]�����Ă����Ԃł̖��C�W���̂��Ƃł���B
���Ȃ��Ƃ����͂��̂���ŏ����Ă��܂��B
�ԏd�������Ă����������͕ς��Ȃ��A�Ƃ����͎̂��ɂƂ��Ă͓�����O�̂��Ƃ������̂ŁA�݂Ȃ��܂����Ɉ����������Ă���������̂����ɂ͐����悭������܂���B
�ԏd�������Ă��u���[�L�̌����͕ς��Ȃ��A�ƌ����Ă���̂ł͂���܂���B
���R�A�ԏd��������A���������y�_�����̃u���[�L�����͎キ�Ȃ�܂��B
�ł��A���̕�����Ƀy�_�����������߂Ες��Ȃ������Œ�܂邱�Ƃ��ł��邵�A�����狭������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�A�Ƃ��������̘b�Ȃ̂ł����B
�����ԍ��F25928482�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
Copilot�ɕ����Ă݂܂���
Q �ԏd�������Ă����������͕ς��܂��H
-----------------------
A �ԏd��������Ɛ��������������Ȃ邱�Ƃ���ʓI�ł��B�d���Ԃ͓����Ă��銵�����傫���Ȃ邽�߁A�����u���[�L�͂ł͒�~����܂ł̋����������Ȃ�܂��B
�|�C���g�́w�����u���[�L�͂ł́x�Ƃ����Ƃ���
��苭���y�_���ޓ����ău���[�L�͂𑝂₹�悢�̂ł��i�^�C���̃O���b�v���E���Ȃ��͈͂Łj
�t�Ɍ����Ύԏd���y���Ƃ��y���͂Œ�~�ł���Ƃ�������
�t����Ԃł͎~�܂�ɂ�����ۂ�����̂͏�L�����R����Ȃ��ł�����
�����ԍ��F25928536
![]() 3�_
3�_
��use_dakaetu_saherok����
���̏������݂ɋ����������Ă��炢�A���肪�Ƃ��������܂��B
���S��������āA�����ւ���Ă����ʂ��Ǝv���Ă܂����B
���̐}������P�ԂĂ��Ƃ葁���Ǝv���܂��B
�Q�l�摜
https://www.try-it.jp/chapters-8001/sections-8111/lessons-8121/
https://clicccar.com/2021/03/10/1063298/#google_vignette
���
���^�C��������Ă��Ă��n�ʂƃ^�C���Ƃ̊Ԃɖ��C�͔͂������Ă��܂���B��������Ȃ��Ɖ������������ł��܂���B
�^�C���̐ڒn�ʂƂ��������I���_�ł́A
���C�͂���������ԗւ��n�ʂ��Ƃ炦�đ��邱�Ƃ��ł��A���������ʂ�ł��B
�ԗւƂ����@�\���g�����Ƃɂ��A���̑��̐ڒn�ʂ��ړ������邱�ƂŁA
�]�����R�Ƃ����A���C�͂�菬������R�ŁA���������Ƃ��ł��܂��B
�Ȃ̂ŁA�^�C���̐ڒn�ʂƂ��������I����������Γ��R�u���C�́v�ŁA
�ԗցA�ԂƂ����@�\������A�u�]�����R�v�ƂȂ��Ă���킯�ł��B
�����āA�ԗւ���炸�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă�^�C�����b�N��Ԃ��A
�ԗւ�ԑ̂Ƃ����@�\�̖��C�͂ƌ�����Ǝv���܂��B
�{��̌��_�������ƁA�X���b�v(�^�C�����b�N)���Ă��܂��A
�d�ʂ̑����ɔ���������������������Ǝv���܂��B
ABS�ŃX���b�v(�^�C�����b�N)���邱�ƂȂ��^�C�����n�ʂɂƂ炦�A
�܂�ABS�����x�ɂ���ċ���Ƃ������p�x���ω�����̂ŁA
�ŏ��̓���̂悤�Ȍ��ʂɂȂ����̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25928562�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�[�I�ɂ����A
�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă適���C��
�ԗւȂǐڒn�ʂ��ړ����適�]�����R
�ƕ\������킩��₷���ł��傤���H
�����ԍ��F25928569�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���́[�A�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ɠ]�����R�͑S���ʂ̒l�ł���H
�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ƃ�2�ڂ̃����N��ŃO���b�v�ƕ\������Ă���l�̂��Ƃł���A�]�����R�̓^�C���̕ό`���Ɏg����G�l���M�[���X�̂��Ƃ��w���܂��B
�m���ɁA�]�����Ă����Ԃł̖��C�W���������Ȃ�A�]�����R�W���������Ȃ�X���͂���܂����A�����͂ƍ��R��̃g���[�h�I�t��l�X�ȍH�v�ŗ��������Ă���̂��ߔN�̃G�R�^�C���ł��B
�����͂ɊW����̂̓^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�W���ł����āA�]�����R�W���͊W�Ȃ��Ǝv���̂ł����A������������肽���̂ł��傤���H
�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�W���ƃ^�C�������b�N���Ă����Ԃł̖��C�W�����������ɂ�1�ڂ̃����N�����ŏ\���ł���A�O�҂��Ö��C�W���A��҂������C�W���ł��B
�Ö��C�W����蓮���C�W���̕������������߁A�ő吧���͂̓^�C�����]�����Ă����Ԃœ����A�^�C�������b�N����Ɛ����͂͏������Ȃ�܂��B
�����ԍ��F25928604�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���������_�ł����A
��d=v0^2/2��g
����͐F�X�ȂƂ���ł���͌�������̂ŁA�ʂ�SMLO&R�����ᔻ���Ă����łȂ��̂ł����A���̎����̂��^��Ȃ̂ł��B
�Ƃ����̂́A
W = (1/2) m v^2
�̉^���G�l���M�[�ƁA
W = F d
�̈ړ��G�l���M�[�Ƃ��������Ƃ���������A
(1/2) m v^2 = F d
(1/2) m v^2 = ��mg d
(1/2) v^2 = ��mg d
d = v^2 / (2��g)
�ƂȂ��Ă���̂ł����A
���ہA���������Ă���̂̓u���[�L�@�\�ł���A�^�C���͒P���ɘH�ʂƂ̐ڐG��ۂ��Ă��邾���Ȃ̂ŁA�^���G�l���M�[��M�֒u������Ώۂł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����͗L���҂̎���ŁA�m���ɂ����l����Ώd�ʑ��Ő��������������Ȃ���̌��Ƃ͒��낪���������Ƃ���������A�������l���܂����B
���߂ē����Ƃ���Ȃ�A
(1/2) m v^2 = F d
(1/2) m v^2 = B S (2 �� r) N
�iB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρA�F�~�����Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�AN�F��]���j
�̂悤�Ȍ`�ɂȂ낤���Ǝv���܂��B
N = m v^2 / (4 �� r B S)
�ƂȂ��āA
d = N x �^�C���O�a
�Ő����������o�鎖�ɂȂ�Ǝv���܂��B
��͂�d�ʂ̕ω��ł��A�����������ς��Ȃ��Ƃ����͎̂ߑR�Ƃ��Ȃ���ł���ˁB
�����ԍ��F25928617
![]() 1�_
1�_
�����́[�A�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ɠ]�����R�͑S���ʂ̒l�ł���H
�킩���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA
�ڒn�ʂ����܂��Ă��܂��Ă適���C��
�ԗւȂǐڒn�ʂ��ړ����適�]�����R
�Ə����Ă��܂��B
�]�����R�Ƃ́A���̂��ʏ��]����Ƃ��ɐi�s�����Ƃ͋t�����ɐ������R�͂̂��Ƃł���A
��R���ƂȂ����͓̂��R���X�����ł��傤�B
���C�W���Ƃ�2�̕��̂��ڂ��Ă���ʂ̖��C�x������\�����̂ŁA
�^�C�����H�ʂɂ͕����I�ɖʂŐڂ��Ă���A�ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԗւ��Ă��܂��B
���̂ƘH�ʂ̊ԂɎԗւ����ݓ]�������Ƃɂ��A
���̂ƘH�ʂ�(�ԗւȂ�)�̏�Ԃ�蕨�̂̓���������Ă��܂��B
��������肽���̂͂����������Ƃł��B
�ԗւ�]�����̂͂������n�ʂƂ̖��C�͂��K�v�Ȃ�ł����A
�n�ʁ@�@�ԂƂ����@�\�@�̖��C�͂Ƃ͂܂��ʕ��Ȃ�ł����B
���C�Ő��܂��ԗ֎��̂̓����ƎԂ̓������Ⴄ�ł���B�ƌ����Ă��A
���̕\���͂������ē`���܂����ˁB�B�B
�����ԍ��F25928630�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����
×�ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԗւ��Ă��܂��B
�@��
���ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԑ̂����Ă��܂��B
���̑��ɂ��뎚��\���̑���Ȃ�����������܂����A
�w�E�͎܂����A�����̕ςȕ\���͎@���Ă��������B
�����ԍ��F25928636�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�r��������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�A
�C�ɂȂ�
�����ԍ��F25928656
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
>>��������ł�����Ȃ��قǎԏd��������ΎԂ���܂鋗���͐L�т�
�m���ɁA����鑫��Ȃ��͈Ӗ��s�������ǁA�u���[�L���\�̂��Ƃ������Ă�̂��ȁH
�ł��A�����ł͓����u���[�L���\�̎ԂŁA��Ԑl�����������ƁA���Ȃ����ɁA�����͂Ŗڈ�t�̋}�u���[�L�����������̐����������ǂ������Ă�����r�Ȃ�ˁB
������ABS���Ń^�C�����b�N�͖������O��ŁB
�����ԍ��F25928666�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G�����J����
���Ȃ��̌v�Z�́A�uB�F�u���[�L���́v�����̎��̂��́B
�u�t���u���[�L���O�v�ɂ��邽�߂ɂ́AB���ԏd�ɔ�Ⴕ�đ��₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ԍ��F25928670
![]() 0�_
0�_
������ƌ������Ă݂���A�ԏd��������ΐ���������������Ƃ����펯���A�����ĕ����悤�ȁA��̕�����Ȃ��L�����A�ł��炵���A�b�v���Ă���̂�����悤�ȁB
���������L����^�ɎĂ��܂��l����萔����̂��ۂ߂Ȃ����ǁB
�����ԍ��F25928690�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���̍l�������̂̓G�����J����ɋ߂������ł��B
��������m�ň��p�����Ă��炢�܂����B
��W = (1/2) m v^2
���̉^���G�l���M�[�ƁA
��W = F d
���̈ړ��G�l���M�[�Ƃ��������Ƃ�����
(����)
��d = v^2 / (2��g)
���ƂȂ��Ă���
����́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB
�}A(https://www.try-it.jp/chapters-8001/sections-8111/lessons-8121/)
�����ԍ��F25928707�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB
����@ABS���ғ����Ă�Ȃ�ꏏ��
�����W�����Î~���C�W���ɂȂ�̂Ŏ��U�ꂷ�邪
�����ԍ��F25928711
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�E�l�Ɖו��ŏd�ʂ�1.5�{�ɂȂ����ꍇ
�E���x��1.22�{�ɂȂ����ꍇ
����A�ǂ�����^���G�l���M�[�͌���1.5�{�ł��B
�ǂ�����u���[�L���A����1.5�{�������ޕK�v������܂����A�O�҂̕����Z�������Ŏ~�܂�܂��B
���o�ł����AABS�̓u���[�L�̖��C�͂��^�C���̖��C�͂��������u�Ԃɉ�݂��ė͂����������܂��B�O�҂̕����A�^�C���̖��C�͂��傫�����A���̉�݂���̂��x���Ȃ��ł��B
���ʂ̎Ԃ͂���Ȃɋ���Ȍ����̃u���[�L��ς�łȂ��ł����A�ʏ�^�]����ABS�������قǓ��݂܂���A�u����[�A�����͐l�Ɖו����ڂŎ~�܂�ˁ[�v���Ċ����܂���ˁB
�����ԍ��F25928721�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
�����C�Ő��܂��ԗ֎��̂̓����ƎԂ̓������Ⴄ�ł���B�ƌ����Ă��A
�����̕\���͂������ē`���܂����ˁB�B�B
�����B�����肽���̂������ς蕪����܂���B
������́A��ł��\��܂������ԗւ����ĂȂ����̂����ɐڂ��Ă��Ԃ̂��̂ł��B���邢�̓^�C�����b�N��ԁB
�����A�ԗւ����Ă����Ԃł��������Ƃł��B
����u�Ԃ�����čl���Ă݂��ẮB
�^�C�����]�����Ă��遁�����Ă��Ȃ���Ԃł�����A�����ł͂Ȃ��͂��l����A�����̂ł��낤�Ɖ~���i�ԗցj�ł��낤�Ɠ������Ƃł��B
���G�����J����
����͂�d�ʂ̕ω��ł��A�����������ς��Ȃ��Ƃ����͎̂ߑR�Ƃ��Ȃ���ł����
���W�J���ꂽ���ł͘H�ʂ��ω����Ă������������ς��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̕������͎ߑR�Ƃ��܂���B
��gda_hisashi����
���C�ɂȂ�
�ł�����ߐύڂŐ��������������邱�Ƃ�ے肵�Ă���l�͂ЂƂ�����Ȃ��Ǝv���܂����B
�����ԍ��F25928723�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���܂ł���ł��傤�H
�����ԍ��F25928726�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��ABS���ғ����Ă�Ȃ�ꏏ��
ABS�ғ��ł��ԗւ���]���Ă鎞�_�ňႤ�Ǝv���܂��B
ABS�ғ��́A�@�B�����̎��̏�ԂŒ����Ƃ��̉�����̂ŁA
�����̂P�ߒ��ɂ����Ď��R���ۂ̕����@��(�H)���牓�̂��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25928735�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�r�ߐύڂŐ��������������邱�Ƃ�ے肵�Ă���l�͂ЂƂ�����Ȃ��Ǝv���܂����B
�ߐύڂ���Ȃ��ł���
�ύڂł�
�ύ�100%�Ȃ琬�藧��(�L�тȂ�)����110%����130%����150%����
�ƂȂ�܂���(�ߐύڂɌ��艄�т��)
�G�r�f���X�͖����ł���150%�ł��]�T�Ńu���[�L���b�N(ABS�쓮)����Ǝv���܂���
�ł���Ό������藧���܂���
�Ⴆ�^�C���̖��C�͉͂d�𑝂₵�Ă������ɑ傫���Ȃ��łȂ�
���C��up�̏�����L��Ƃ�
��ɂ��R�����g���Ă��܂���
�����ے�ł͂Ȃ��ʂ̃t�@�N�^�[���L�邩�����Ċ����ł�
�����ԍ��F25928740
![]() 1�_
1�_
�q���̍��ɂ���Ă݂�����������Ǝv���܂����A�����S�����g�������C�͂̎����ł��B
�@ ��̐}�Ńe�[�u���ɒu���������S�����A�^������w�ʼn����܂��B
�@�@���ʂ͌y�������܂��B
�A ���Ɏw�������S���̏�ʂɒu���āA�����悤�ɉ������Ƃ���ƁB
�@�@���ʁA�߉��ɉ������^�Łi�w�̏d�����j�d���Ȃ�܂��B
�B �������͇A�̈����ŁA�Ў�Ōy�������S�����ォ�牟�����A�Ў�Ő^�����牟���Ă��������d���Ȃ�܂��B
���ꂪ�u�d�ʂ�������Ɩ��C�͂��傫���Ȃ�v�ƌ��������ƁB
����̃e�X�g�̏ꍇ��ABS�Ń^�C�����b�N���Ă���̂�����A�u���[�L�͂Ƃ�������ӂ�ɂȂ肪���ł����A
ABS�̓O���b�v�ƃ��b�N�̋��E��ŃR���g���[�����Ă��܂��̂ŁA����Ӗ��i�قځj���b�N��Ԃł��B
�u���[�L���|�������A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�Ŏ~�܂낤�Ƃ��܂����A
�ԑ̂͘H�ʁi�O���b�v�ʁj�ɑ��Ċ����Ō�납�牟�����^�ɂȂ�܂��B
����̇������S�����Ō����ƁA��납��w�ʼn����̂��u�u���[�L�́v�ł��B
�����S���d�ʂƏォ�牟�������d���ő�O���b�v�́i�^�C�����C�́j�ƂȂ�܂����A
�ʏ�͎w�ʼn����́i�u���[�L�́j�̂ق����]�T������A�^�C���O���b�v�̌��E���Ă��܂��܂��B
���̗]���Ă��܂����̃u���[�L�͂�ABS�œ�������āA����ȏ�̗͂ɂȂ�܂���B
�s���A�����S���d��100�Ǝw�d20��120�̊����d�ʂ��|�����Ă��A
�����S�����̂̃O���b�v���d����120�ɑ����Ă���̂ŁA�u���[�L�����͓������A�ƂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25928742
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
�������B�����肽���̂������ς蕪����܂���B
�������A�ԗւ����Ă����Ԃł��������Ƃł��B
�͂��A���̂����u����Ԃ̐}A�ƁA�ԗւ����ē]�����ԂƂ����@�\�̋�ʂ��ł��Ă��Ȃ���l�q�ł��B
���̐������������܂����A����ł͉i�v�ɗ�������Ȃ����Ƃł��傤�B
�d�������̂�����(���邢�͈�������)�̂ƁA��Ԃɏ悹�Ĉړ�������̂́A
�͂̉��������������Ⴄ�Ƃ����o�������������̂ł��傤���B
�����ԍ��F25928745�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�ł�����ߐύڂłȂ��Ƃ���ׂ�100���ύڂ��ᐧ�������Ⴂ�܂����āA�����̖�Ȃ��ł���B
����������̏Z�l�����́A���C���ǂ��̂����̂ƌ����āA���������͕ς��Ȃ����Č����Ă��ˁB
�����ԍ��F25928753�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���^�C�����]�����Ă��遁�����Ă��Ȃ���Ԃł�����A�����ł͂Ȃ��͂��l����A�����̂ł��낤�Ɖ~���i�ԗցj�ł��낤�Ɠ������Ƃł��B
�����̂̊����Ă��Ȃ���Ԃ͒�R(���C)�ƂȂ�A�����Ȃ��A
���邢�͕��ׂƂȂ�܂��B
�~���i�ԗցj�̊����Ă��Ȃ���Ԃ͋�]�����A�]�����Ă����܂��B
���ꂾ����������͂��Ⴂ�܂��B
������A�������������̂��킩��Ȃ��ƈ�R���ꂻ���ł����A
�ԗւƂ����@�\���A���u���ƈႤ��ʂ̂��������ɂ��Ȃ�B
�����ԍ��F25928765�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�������̖�Ȃ��ł���B
���_���肫�Ȃ�c�_����͖̂��ʂł́H
�����ԍ��F25928766�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
>�ł�����ߐύڂłȂ��Ƃ���ׂ�100���ύڂ��ᐧ�������Ⴂ�܂����āA�����̖�Ȃ��ł���B
�v���͂����Ȃ�ł���
�m���ɒʏ�̊X�ł̃u���[�L���O�ł͌��X�]�͂����邩��ŏ����瓥�͂���������Ă͕̂���
�����̖@���œ������Č�����Ƃ��Ⴀ�Ȃ����ۂ͎~�܂�Ȃ��̂�
����~�܂�܂���
��������
���Ċ����Ȃ�ł���
�����ԍ��F25928775
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�c�_�Ȃ�Ă���C�͂Ȃ���B
�ŏ���Ԑl���ő����Ă��鎞�A�v��������}�u���[�L���������ƁA�����t�œ����X�s�[�h�ő����Ă��鎞�A�����悤�ɋ}�u���[�L���������̐����������������ƐM����l�͂����v���ĉ^�]����������A�l�̂悤�ɓ����Ȃ��A�ƍl����l�͂����v���ĉ^�]������������Ȃ�Ȃ��́B
�����ԍ��F25928779�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�������悤�ɋ}�u���[�L
�����Ȃ�d�������������͐L�т�ł��傤���A�����͂ɉ����ē��͂𑝂�����������I�ł͂Ȃ��ł��傤�B�����猻���͐L�т�����ɂ����Ǝv���܂��B
����ŁA�����𑵂���ΐL�тȂ��P�[�X�����邱�Ƃ��u����ςŁv�ے肵������̂��ǂ����ƁB
�����ԍ��F25928825�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�u�^�C���̐Ö��C�͂ƃu���[�L���\���A�����͂̑������x�z�I�ȏꍇ�ɂ����āv���������͐L�тȂ��B
�Ƃ��������̂��Ƃł��B
�����ԍ��F25928830�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��
�u���[�L�̐����́A�^�C�������b�N���鐡�O�܂ōs���ꍇ�ɂ����āi�d����������ɉ����Ă�苭�͂Ȑ��������͂��K�v�j�Ƃ������Ƃł��B
�����̏ꍇ�A�l�Ԃ�������o���Ȃ����琧���������L�т�̂ł��傤�B
�����ԍ��F25928838�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�ŋߎ��Ԗ�����Ōy���ǂ�ł邾���ł����A���S�Ɏv�l��~����̂͂ǂ����Ǝv���܂���B
�������i�C�g�G���W�F������͔�ѐX���Ő̓^�C���̉�]�ł͌���ɔ�Ȃ��Ƃ̈ӌ��̐l�������ƋL�����Ă��܂����A����C���[�W�Ƃ��Ă�100km/h�ő����Ă�ƌ����100km/h�Ŕ��ł����ł���ˁH
�ł����ۂ̓^�C���̉�]�R���ł͂����Ȃ�Ȃ��B
�C���[�W�A��ۂƎ��ۂ͈Ⴄ�ꍇ���L��ƌ����͈̂ꉞ�l���Ă����������ǂ��ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25928840
![]() 2�_
2�_
���������`����
�킽�������A����̗��_�Ń^�C�������ɂ́A�����S�����ȁE�E�E���Ďv���Ă���܂���
�ł��A�ŋ߂́A����ł��p�\�R���嗬�ŁA�����S���̑��݊����A�����Ȃ��Ă��܂��܂�����
�ȉ��̘b�́A�������A�u���[�L�̔\�͂��\���ȏꍇ�ł�
���ʑ�����A�u���[�L�V�X�e���ɂ����ׂ�������̂́A���R�̘b�ł�
�����S���ŊԈ�������������Ƃ��A�͂����Ȃ���i�d���|���Ȃ���j�����ė]�v�ɍ����Ȃ��āA�����Ă���܂���@�i�܂��A���p�ł́A���������Z�@������܂����j
������u���[�L�������Ȃ���Ԃƈꏏ
������x�A�͂�����Ɓi�d��������Ɓj����ɂ����Ȃ�A���肾�����O�̒Z�����Ԃ͐Î~���āA���̉d�ɂ�����ő�̒�R�ƂȂ�܂�
������Ö��C�͂ŁA����d�ɑ��A��ԃu���[�L���������
���肾������A�����C�Ɉڂ�A��R�͏�����܂�A�����S���̓K�x�ȍ����Ȃ���A���������Ă���܂�
�ł��A����̓^�C�����b�N�̃X���b�v���
�X�L�[������炵�Ȃ���A�u���b�N�}�[�N���c�����
F-1�Ȃ�A�^�C���X���[�N�o���āA�t���b�g�X�|�b�g������Ă��܂����
��R�͎�܂�̂ŁA�u���[�L�͌����Ȃ����
���x�́A���`���N�`���͂�����Ɓi�d������������Ɓj���炸�A�����S���͐�Ă��܂��܂�
�^�C���Ȃ�o�[�X�g�Ȃǂ̊댯���o�Ă�����
�����S���̃J�h��A�؏����̓���葫�A�X�[�p�[�J�[�����S���̃^�C���ȂǁA�ڐG�ʐς����Ȃ���A�����ɂ������̂ŁA���e�����d�͏��Ȃ��Ȃ�܂�
�ł��A�������͈͂�������ɂ́A�J�h�g���A�����ȗ͉������K�v�ȁA�e�N�j�b�N�̂ЂƂE�E�E
�v�̓^�C���ɂƂ��ẮA�K���d���d�v
�y�ɂ͌y�́A�g���b�N�ɂ̓g���b�N�̃^�C���ŁA�K���Ȕ͈͂Ŏg�����Ƃł�
���ƁA�����S���J�X�������ƁA����ɏ�������Ċ����Ă��܂��܂�
���p�̎��ƂŁA6B�Ƃ��̉��M�g���āA�^�����ɂ������������ꂢ�ɏ����Ƃ��A�����ď����S�����^�����ɂȂ�A���ꂢ�ɏ����̂�����Ȃ�܂�
���~���̉���������S���ŏ������Ƃ���A���Ƃ͈�������G�ɂȂ�܂�
���ł��t���悤���̂Ȃ�A����Ɗ����Ă��܂��܂�
�����́A������H�ʏɂ��E�E�E�Ƃ�����Ԃł�
�܂��A�����S���̏�������ď����͓̂���A�Ȃ�ׂ��������Ə����₷���Ȃǂ��A�o�����Ƃ��āA����ʂł͝G���^�C���̗L�p���������ł����ʂ�����܂�
���ɁA�d�����������S���͊����ď����ɂ������A���炩�̗ŁA�˂�����������S���͊��炸�g���ɂ����Ƃ��A�I���W�̊��̈����o���ɂ��鍻�����́A������ƕ~���������ȂǁA�q���̍��̌o���̔����o�͑�ł�
�X�[�p�[�J�[�����S���Ƀx�r�[�p�E�_�[��t����͔̂����ł����A�t�ɓ���Ȃ�A�����痎���Ă��܂��܂�
�{�[���y���̃o�l����������L���Ă��A���܂���ʂ͂���܂���ł������E�E�E
�ǂ����ɂ���A�d�������S���́A���܂�i��ł���܂���
����A�u���[�L���ǂ������̂��A����Ƃ��t�ɁA�~�܂��Ă镨�������ɂ����Ȃ�A�����Ă镨�͎~�܂�ɂ����̂��E�E�E
�ł��A�d�������S���́A�y�������S�����A�ȒP�ɒe������Ă���܂�
����ς�A���ʂ̎��G�l���M�[���傫���ł�
�b���Ă��݂܂��A����ł��A�V��ł���̎q���ł��A�����Ƌz���ł��܂�
�ł��A����Ő^�ʖڂɎ���W�J�������́A���X�y�N�g�������܂�
�����ԍ��F25928847
![]() 2�_
2�_
�X���̗���Ń^�C�������b�N���Ȃ���Ƃ����b�N������ĉ��o�Ă��邯��
���b�N���Ă����Ȃ��Ă����݂������i���b�N��j�Ȃ�
���C��R�̌����͕ς��Ȃ����瓯�����Ď��ɂȂ�܂����
���b�N����ƐL�т邵�Ȃ�����ăR�����g���L��܂���
��̃X���b�v�ɂ�鑬�x�v�Z�\��������b�N���Ă��L�тȂ��i�����j
������
�����ȕX�̏�Ɂi�Ⴆ�j�����K�����炵���l�ȏ����Ń����K�Ƀ����K���d�ˁi�Q�i�ɂ��Ă��R�i�ɂ��Ă��j�Ċ��点�Ă�
�~�܂�܂ł̋����͓������Ď��Ȃ̂ł��傤��
�����ԍ��F25928852
![]() 0�_
0�_
�������K�����炵
�H�ʂƂ̖��C���Ȃ���Ԃ͋c�_�̊O�ł����c�A
���̏ꍇ�͏d�͉����x�Ɠ����ł���ˁB��C��R������A���ʂ͊W�Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F25928862�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���b�N�Ƃ��������p���Ă܂����A�����ԓ����ׂ��ł����H
����Ƃ����̕��̈ӌ��҂��ł����H
���́A�ԗ�(�^�C��)�̋@�\�ƁA���u��(�Ƃ������z�ŕ����@���E����)�́A�Ⴂ�܂���Ə����Ă܂����A
�ȂɌ����Ă�̂��킩��Ȃ������Ȃ̂ŁA���������̎d�l������܂���B
�����������͑ΏۊO�Ȃ�A�ł�����Ď��炵�܂����B
�����^�C�����b�N�̌��t�𑽗p���Ă��̂ŁA�����ȂƎv���B�B�B
�����ԍ��F25928871�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����A���łɏ�����Ă܂��ˁB���炵�܂����B�ł����܂����B
�����ԍ��F25928887�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>�H�ʂƂ̖��C���Ȃ���Ԃ͋c�_�̊O�ł����c�A
���C�͗L��܂����C�������������ł��R�{�͂R�{�A�T�{�͂T�{�ł�
���_�͓����i�����j�ł����
>���̏ꍇ�͏d�͉����x�Ɠ����ł���ˁB��C��R������A���ʂ͊W�Ȃ��Ȃ�܂��B
���������Ŏ~�܂���Ď��ł��傤��
�����ԍ��F25928892
![]() 1�_
1�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
�ǂȂ������Ęb�ł͂Ȃ�
���b�N���Ă����Ȃ��Ă��`�a�r�������Ă������Ȃ��Ă�
������ԂȂ瓯�����_���������Ȃ����ȂƎv�������̂�
�O���b�v���Ă���Ƃ����b�N����Ƃ������͔������o�I�ɂ��Ȃ���
�i�ᔻ�ł͂Ȃ��ł����̂��������Ȃ�Ƃ̖l�̎v�������o�ł�����j
�����ԍ��F25928895
![]() 1�_
1�_
���R�z�@���Y����
�f�������Ă��āA�^�C���ƃu���[�L���\�ɗ]�T������̂��ȂƎv���܂����B
�����ƍ����Ȃ獷���o�Ă��邩������Ȃ������
���Ȃ��Ƃ��e�X�g�Ԃ́A����96kg�Ńt����ԃt���ύڂŃt���u���[�L���s���Ă��傫�Ȗ�肪�Ȃ��l��
ABS���܂߂����ƍ�肱�܂�Ă���̂ł��傤�B
�����ɗ]�T���Ȃ��ƁA���x�Ȃ萧�����ԂȂ�d�Ȃ�ŁA�u���[�L���t�F�[�h���Ē�~�������L�т₷���Ƒz�����܂��B
�t���u���[�L���s�����Ƃ͂܂�ŁA
�ʏ�̃u���[�L�̓u���[�L�ƃp�b�h���ɂ߂ɐڐG���Ă����Ԃ�����A
��Ԑl������������ו���������Ɛ��������͐L�т���́B
�����ԍ��F25928900
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
�������ȕX�̏�ɁE�E�E���āA���������肷�邩��A�����̐��E�Ƃ̃C���[�W���A�ǂ�ǂ̒��ŃY���Ă���Ǝv���܂���
�������铹��ł��A�X�̏������X�P�[�g�C�ƁA��̏������X�L�[�ł́A�S�R�Ⴄ�ł���
�����ԗւł��A�l�X�ȏ����ɑΉ����Ȃ�������Ȃ��Ԃ̃^�C���ƁA����Ӗ����z�I�ȏ����ɋ߂Â����S���̎ԗւ́A�S�R�Ⴄ���E�E�E
�J�[�����O�̃X�g�[���ɁA��]��^����Ɛi�H���ς�錻�ۂ́A�Ȋw�I�ȍ����́A���܂����m�ɉ𖾂���Ă��܂��E�E�E
�ł��A�e�N�j�b�N�Ƃ��ẮA�݂�ȁA������O�Ɏg���Ă邵�E�E�E
����ς�A�����o�Ƃ��āA���ʂ�������A���ꂾ���댯�͑�����Ǝv���Ă����A������Ȃ��ł��傤��
���Ȃ��Ƃ��A�d�S���͏オ��A����͎キ�Ȃ邵�A���낢�땉�ׂ������āA�Փˎ��̃_���[�W�͑�����̂ł�����E�E�E
���������A���̕��A�a�����Ă��閽���������ł�����E�E�E
���S���ɍl���܂��傤
�����ԍ��F25928912
![]() 0�_
0�_
�������o�Ƃ��āA���ʂ�������A���ꂾ���댯�͑�����Ǝv���Ă����A������Ȃ��ł��傤��
�ł��ˁB�H�ʂ̏E�^�C�����\�E�u���[�L���͂̌������l����B
�����ԍ��F25928923�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ƁA������ƁA�����������Ƃ����������Ă��������܂�
�N�������Ă����^�C���̃O���b�v�~��A�킽�������A�����������Ă���A������ɂ���ďd�S�����㏸����b�Ȃǂ́A���܂�b��ɂȂ�܂��E�E�E
�\��̃����N�f�����A�P���ɒ�����̐��������Ȃ̂ŁA���ɉ������b�肪�D�悳���͎̂d������܂��E�E�E
�}�u���[�L�ޏ�ʂƂ��āA�{�l�̒��ӕs���̏ꍇ�i��̏a��ԐM���Ȃǁj�́A���i�̃t���u���[�L�ł��傤
�ł��A���ہA�}�u���[�L�̏�ʂƂ��ẮA�J�ȂǂŎ��E���������ł̋}�Ȕ�яo����A���ɂ�����̉����A�ȂǁA�����Ă��H�ʂ��������ŋ}�n���h���ɂ���𑀍�������A���ɏ����Ƃ��ẮA�������Ƃ������Ȃ�܂�
�Ԃ̊댯���\�͂Ƃ��āA���ʂ̑�����d�S���̏㏸�́A��ΓI�ɕs���ȕ����ɓ����܂�
���ɑ��l����Ԃ��\�ȃ~�j�o���Ȃǂ́A���Ƃ��Ǝԏd�͏d���A�d�S�������A�^�C���͕��ʂŁE�E�E
�����7�l��8�l�����A�����s���ɂȂ�͂��ł����c
�Ȃ̂ɁA�d���⍂�������������Ȃ��A���K�ȑf���炵���Z�b�e�B���O�ŁE�E�E
�u���[�L�����v�ȂE�E�E���āA�v���Ă��܂�����E�E�E
�{�����ӂ��ׂ���ʂł��A���ʂɉ^�]����l�����������ŁA�|��
�����ԍ��F25928979
![]() 3�_
3�_
���Ⴀ�A���������������Ƃ��������Ă��������܂��B
�ԏd�������I�Ȉ��S���ɉe������͓̂�����܂��̘b�ŁA�����炱���@���ʼnߐύڂ��K�����Ă��܂��B
�ԏd���d����u���[�L�̌����������Ȃ�A���߂ɓ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�h���C�o�[�Ȃ犴�o�I�ɕ�����ł��傤�B
�X���`���̓���́A���������ɂ�����Ŏԏd������ς��Ď����������̂ł��B
���̌��ʂ��������Ƃ������Ƃ́A�ԏd�������瑝���Ă����S�ɉe�����Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�댯�����炻�̌��ʂ͐������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��Z�p�I�Șb�ł͂���܂���B
�����ԍ��F25929018
![]() 4�_
4�_
�������Ƃ���
���댯�����炻�̌��ʂ͐������Ȃ��E�E�E
��
�����܂ŒN�������Ă܂������H
���́@�����@���ʂ͐������Ă��A���ہ@�댯�͊댯�E�E�E�Ƃ����_�����A�����Ƃ�����A�킽�������܂߁A�قƂ�ǂ������Ǝv���܂����E�E�E
�����̌��ʁA����Ԃ́A1�l����7�l+200kg�͈̔͂܂ŁA�h���C�H�ʂŁA96km/h��36m�ł���
�����ԍ��F25929099
![]() 0�_
0�_
�������Ƃ���
���������ʂ����_���M���Ȃ��Ƃ����Ȃ�A������c�_���Ă����ʂł��ˁB
�܂��ɂ���ł��B
���Ƃ͕ʂ̉F���̕��������݂��邩�̂悤�ł��B
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���d�������̂������i���邢�͈�������j�̂ƁA��Ԃɍڂ��Ĉړ�������̂́A�͂̉��������������Ⴄ�Ƃ����o�������������̂ł��傤���B
�����͎d�����Ă܂���ŁA�^�C�����[�Ƀ��X�ł��Ȃ��Ă��݂܂���B
�ŁA���߂ĉ�����������肽���̂ł����H
���̂u���ň�������͂́A���̂̍ڂ�����Ԃ������͂����傫���A�Ƃ������Ƃł����H
���̔�r������̂ł���A���̂u���ň�������͂ƁA�Ԏ��Ƀu���[�L�̂���������Ԃ���������͂��r���Ȃ��Ƃ�����������܂��H
�����O�҂���҂��傫����A���̂u���ň������遁�^�C�������b�N������������͂͑傫���Ȃ�A�^�C�������b�N�����������������͒Z���Ȃ�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����Ȃ��Ƃ͂���܂����ˁB
�ǂ�����Î~���Ă����Ԃł���A���҂������ł��邱�Ƃ͖��m���Ǝv���̂ł����A�^�C�����]�����Ă����Ԃ��ƂȂ������v���Ȃ��̂ł��傤���B
�^�C�������b�N���Ċ����Ă����ԁ����u���Ŋ����Ă����Ԃł��邱�Ƃ͖��m���Ǝv���̂ł����A�^�C�����]�����Ă����ԁ����u���Î~��Ԃł��邱�Ƃ�����������Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��傤���B
������x�A���u���̕��̂������ē����n�߂�Ƃ��̗͂ƁA�u���[�L����������Ԃ������ē]����n�߂�Ƃ��̗͂��l���Ă݂Ă��������B
�i��Ԏ��̂̏d����]�����R�͖������܂��j
�u���[�L���ク��A��Ԃ͒��������y���͂œ]����n�߂܂��B
�u���[�L���K���ł���A��Ԃ͒������Ɠ����͂œ]����n�߂܂��B���ꂪ�ő吧���͂����Ă����Ԃł��B
�u���[�L�������苭����A��Ԃ͒������Ɠ����͂Ŋ���n�߂܂��B���ꂪ�^�C�����b�N��Ԃł��B
�����ɕK�v�ȕ����@���� �w���C�͂͐����R�͂ɔ�Ⴗ��x �w�Ö��C�W���͓����C�W�����傫���x ��2�����ł��B
�����܂ł̘b�̂ǂ��ɋ@�\�̈Ⴂ�╨���@���E�����̈Ⴂ������̂ł��傤���B
�����ԍ��F25929608�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����͐��������Lj�ʓI�ȉ^�]�����Ƃ͈Ⴄ�̂������ȏ�
��ʓI�ɂ�1�l��Ԃœ��ލŒ���K�v�ȃu���[�L�̗͂Ƒ��l���œ��ރu���[�L�̗͂̓C�R�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ�
�ł����悾�ƍő�ύڎ��ɓ��ޗ͂ōŏ��ύڎ��ɂ����l�ɉ����Ă܂�����A�u���[�L�ƃ^�C���ƘH�ʂ��瓾����ő含�\�l�͈͓̔��ł͐��������ɍ��͂Ȃ��B���x���オ��Ώオ��قǐ��\�l���Ɏ��܂炸�I�[�o�[���������������o�܂��B����̃e�X�g�͂��̑��x�ł͖����S�Ă̏d�ʂŎ��܂��Ă��������B
����Ɉ�ʓI�ȉ^�]�肪�펞�K�b�N���u���[�LMAX�Ńu���[�L�Ȃ�Ė����B�����Ă��ɂ₩�ȉ����œ��ޗ͂��A�b�v�����Ă����܂�����K�v�ȗ͂ɒB����܂ł̎��Ԃ͐L�тĂ��̕���~�����͐L�т܂��B��ً̋}���ɑS�͂œ��ݍ��߂�l���Ȃ����烁�[�J�[���⏕�@�\����Ă邮�炢���߂ĂȂ��l����B
����͓���Ŋy���߂܂����A��ʓ��ł͑��l����ԁA�ύڂ������ꍇ�͎Ԋԋ����𑽂߂Ɏ�������������̕��̏ꍇ���S�ł��ˁB
�����ԍ��F25929652
![]() 0�_
0�_
�@�������Ƃ���
�����Ȃ��̌v�Z�́A�uB�F�u���[�L���́v�����̎��̂��́B
�ܘ_���ł��B
�łȂ���A�ԏd�ω��Ő����������ω����Ȃ������ؖ��ł��܂���B
�����̂��������ς��A���������ς����Ĕ�r���Ă��ẮA���������������ȂǏؖ��ł��܂����B
���Ƃ����̂́A�����̈������ω������A���̑O����r���čl�@������̂ł��B
�ꉞ�u���[�L���͂́A�t���u���[�L��z�肵�Ă��܂��B
�������A�����ɂ̓ʂ�����ׂ����������ȂƂ����C�͂��Ă��܂��B
�����ԍ��F25929738
![]() 1�_
1�_
���G�����J����
���ꉞ�u���[�L���͂́A�t���u���[�L��z�肵�Ă��܂��B
�ԏd��������A�^�C�����X���b�v������E�̐����͂��オ��܂��B
ABS���쓮����̂��t���u���[�L�Ƃ���Ȃ�A�ԏd�������ău���[�L���͂������Ȃ�A�t���u���[�L�ɂ͂Ȃ�܂���B
JAF�̎����Ɠ����ŁA�����������L�т邱�ƂɂȂ�܂��B
�ԏd���ς������A�t���u���[�L�ƃu���[�L���͈��͗������܂���B
�����ԍ��F25929802
![]() 3�_
3�_
��use_dakaetu_saherok����
���ŁA���߂ĉ�����������肽���̂ł����H
��������肽�����Ƃ͏����܂����B
������A�������������Ȃ�(�����|�[�W���O����)�A�������悤�Ƃ��Ȃ��l�ɂ�������������͂���܂���B
�������ɕK�v�ȕ����@���� �[(����)�[ ��2�����ł��B
�����Ƃ͕ʂ̉F���̕��������݂��邩�̂悤�ł��B
���Ԃ�A������͕��ʂ̒n���ɂł��Z��ł����������ł��傤�B
�̂͂���ȕ��͂����ς���������Ⴂ�܂����B
�����ԍ��F25929822�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
aABS�����삵�悤�����܂����A�Ƃɂ��������X�s�[�h�ŋ}�u���[�L���ɁA�ԏd�̑����ɂ�鐧�������̔�r�ł���ˁB
�����ł����}�u���[�L�Ƃ́A�ǂ���̏ꍇ�������^�]�肪�͈�t�v��������u���[�L�ނ��Ƃł��B
�����ABS���������ǂ����͘H�ʏ�^�C�����\�Ȃǂ��낢��L�邾�낤���ǁA�Ƃɂ��������Ԃł̔�r�Ȃ̂�ABS�̓���ɊW�Ȃ��A�d�ʕω��Ő��������̈Ⴂ�����邩�ǂ����A�����_�ł��傤�B
�����ԍ��F25929827�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����Ɍ����}�u���[�L����ABS�ɂ��Ă͎���4�̏ꍇ���z��ł��܂��B
1�A�ԏd���y�������d�����Ƃ���ABS�����삵���B
2�A�d�ʂ��y�������d��������ABS�͓��삵�Ȃ������B
3�ԏd���y��������ABS���������B
4�A�ԏd���d����������ABS���������B
1�`4�̂�����ł����Ă��A�����Ԃł����Ȃ����Ȃ�A���̎��̐����������������̔�r���ǂ����H
�Ƃ������Ƃł�����B
�����ԍ��F25929838�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���[��B�ʂɔے肵�����̂ł͂Ȃ��āA�{���ɂ��Ȃ���������������肽���̂����������������Ȃ�ł����ǁB
�Ίۍ\���ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă�������Ⴂ�܂����H
���Ȃ�:A��B�͈Ⴂ�܂�
�킽��:������Ƃ悭������Ȃ�������ł����ǁAa��b���Ⴄ�Ƃ������Ƃł����H�����Ⴄ��ł����H
���Ȃ�:�����������܂���
�����̂ƘH�ʂ̊ԂɎԗւ����ݓ]�������Ƃɂ��A
�����̂ƘH�ʂ�(�ԗւȂ�)�̏�Ԃ�蕨�̂̓���������Ă��܂��B
����������肽���̂͂����������Ƃł��B
���ꂪ����̉ɂȂ��Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͂�������ɂȂ�܂����H
������������肽����ł����H�Ƃ����̂́A����炪�Ⴄ���ƂƐ����������ǂ��W�����ł����H�Ƃ�������ł��B
�����ԍ��F25929842�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
ABS�̓���ɊW�Ȃ��ł�����A������Ƀu���[�L�A�V�X�g�Ȃ������Ŏ����̌��ʂ�����܂��B
��������悹��ƁA�ǂ��ς��H���������Ɛ��\���r�yJAF���[�U�[�e�X�g�z
https://youtu.be/-dw1avumTpI?si
�\�������܂��A��L�̓���͐����O�ɒm���Č��܂����B
���R�A���������Ⴄ�A�������Ⴄ�ƁA�����E��Ԃ̈Ⴂ�����邱�ƂɂȂ�A
�����̈Ⴂ�ʼn����ς���Ă��邩�l���Ă܂����B
�����ԍ��F25929861�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
��������������肷�������Ȃ��ł��B
�ł����A�u�Ίۍ\���ɂȂ��Ă���v�ƈӖ��͒m��܂��A
�Ȃ��Ԃŝ����Ɏg���Ă錾�t�������ꂽ�̂ŁA�����͔��_���܂��B
�����Ȃ�:A��B�͈Ⴂ�܂�
�@��
A��B�͈Ⴄ���ƂƁA���̈Ⴂ�������܂����B
���킽��:������Ƃ悭������Ȃ�������ł����ǁAa��b���Ⴄ�Ƃ������Ƃł����H�����Ⴄ��ł����H
�@��
�킩��Ȃ���A���̉ӏ��������Ă��������B
�u������������肽���̂��킩��Ȃ��v�ł́A�����S�̓I�ɂ킩��Ȃ�(�킩��Ȃ��Ƃ��낪�킩��Ȃ�)�l�q�ŁA
���������������グ�ł��B
�܂��A�}�X�R�~���J��Ԃ������̂́A�����{�炷(�ʔ����\����B��)�Ӑ}����ł��B
�����Ȃ�:�����������܂���
�@��
�J��Ԃ����́A��ނ���闧��Ƃ��Ă͎��Ԃ̖��ʂł��B
�ēx�J��Ԃ�(���Ԃ̖���)�ł����A��������肽�����͏����܂����B�������킩��Ȃ��̂́A���̐������������̂ł��傤�B
�M������M���Ȃ��l�̏���ł��B�����R�ɂǂ����B
�����ԍ��F25929879�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
�i�`�e�̃f�[�^�S���������ǂ�������܂��O�o�ł���
>ABS�̓���ɊW�Ȃ��ł�����A������Ƀu���[�L�A�V�X�g�Ȃ������Ŏ����̌��ʂ�����܂��B
�������͂��Əd���ɂ���ă^�C���̖��C�͂������Ă��u���[�L�̌����G�l���M�[�𑝂₵�Ė�������L�т�͓̂��R�ł����
�t�Ɍ������ꂾ�����������i�d���j���Ă��~�܂�Ȃ��������Ɣ�ׂP�����x�̂̐L�т��Ȃ�Ďv��Ȃ����Ȃ��ł�
�����̃X���͏d����������Ζ��C�̒�R�͂������邩�疀�C�i�^�C���j�����ł̒�R�ρi��~�����j���ς��Ȃ����ăX���ł�
�����ԍ��F25929913
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
���i�`�e�̃f�[�^�S���������ǂ�������܂��O�o�ł���
�{���ł��ˁB�m�F���܂����B��ώ��炵�܂����B
�����Ƃ��Ă܂����B
�����ԍ��F25929930�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���킩��Ȃ���A���̉ӏ��������Ă��������B
���u������������肽���̂��킩��Ȃ��v�ł́A�����S�̓I�ɂ킩��Ȃ�(�킩��Ȃ��Ƃ��낪�킩��Ȃ�)�l�q�ŁA
�����������������グ�ł��B
���͓s�x�A��������肽���̂͂����������Ƃł����H�ł�����͂��������Ȃ��ł����H�Ƃ����q�˕������Ă�������ł��B
�������Ȃ��玄�̐����ɑ��Ă͂��l�@�����������A�����̎咣���J��Ԃ������肾�������Ƃ��c�O�Ɏv���܂��B
���̐q�˕������Ȃ������̂悤�Ɏ��ꂽ�̂Ɠ������A���Ȃ��̎咣�����̂悤�Ɏ�����l�Ԃ�����Ƃ������Ƃł��B
�q�˕��ɂ��Ă͔��Ȓv���܂������̎��ɂ͂���ȏ�̐������ł��܂���̂Ō��r�v���܂��B
�������������Ă����������������Ȃ����Ƃ͎v���܂����A���͈Ⴄ�����@��������̂Ȃ炻���m�肽�����������ł��B
���̂�������̂ƁA��Ԃɍڂ��ĉ����̂Ƃł́A�ǂ̂悤�ȕ����@���̈Ⴂ�������āA���ꂪ�ǂ̂悤�ɐ��������ɊW����̂ł����H
�Ƃ����̂����̐\���グ�����������Ƃł��B
���Ȃ݂Ɂw���������x�͑��h��ł��̂ŁA�������̔����ɑ��Ă͌�����́w�\���グ��x�����g���ɂȂ�������ǂ����Ǝv���܂���B
�����ԍ��F25930682�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
���������Ȃ��玄�̐����ɑ��Ă͂��l�@�����������A�����̎咣���J��Ԃ������肾�������Ƃ��c�O�Ɏv���܂��B
������(�^��ɑ���ԓ�)���Ă��܂����H
�����w���̍l�@�ɂ�����^�C���ƒn�ʂƂ̖��C�͂Ƃ́A�^�C�����b�N��Ԃ̖��C�͂ł���x�Ƃ������Ƃ����Ă��܂����H
�����^�C��������Ă��Ă��n�ʂƃ^�C���Ƃ̊Ԃɖ��C�͔͂������Ă��܂���B��������Ȃ��Ɖ������������ł��܂���B
�@���ԓ�
�����̐}������P�ԂĂ��Ƃ葁���Ǝv���܂��B
���^�C���̐ڒn�ʂƂ��������I����������Γ��R�u���C�́v�ŁA
���ԗցA�ԂƂ����@�\������A�u�]�����R�v�ƂȂ��Ă���킯�ł��B
�����ԍ��F25928562
�������́[�A�^�C�����]�����Ă����Ԃł̖��C�͂Ɠ]�����R�͑S���ʂ̒l�ł���H
�@���ԓ�
���킩���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA�`�`�`
���]�����R�Ƃ́A�[(����)�[�ڒn�ʂ̖��C�𗘗p���Ďԗւ��Ă��܂��B
�����ԍ��F25928630
���������A�ԗւ����Ă����Ԃł��������Ƃł��B
�@���ԓ�
�����̂����u����Ԃ̐}A�ƁA�ԗւ����ē]�����ԂƂ����@�\�̋�ʂ��ł��Ă��Ȃ���l�q�ł��B
���d�������̂�����(���邢�͈�������)�̂ƁA��Ԃɏ悹�Ĉړ�������̂́A�͂̉��������������Ⴄ�Ƃ����o�������������̂ł��傤���B
�����ԍ��F25928745
�����^�C�����]�����Ă��遁�����Ă��Ȃ���Ԃł�����A�����ł͂Ȃ��͂��l����A�����̂ł��낤�Ɖ~���i�ԗցj�ł��낤�Ɠ������Ƃł��B
�@���ԓ�
�������̂̊����Ă��Ȃ���Ԃ͒�R(���C)�ƂȂ�A�����Ȃ��A���邢�͕��ׂƂȂ�܂��B
���~���i�ԗցj�̊����Ă��Ȃ���Ԃ͋�]�����A�]�����Ă����܂��B
�����ꂾ����������͂��Ⴂ�܂��B
���ԗւƂ����@�\���A���u���ƈႤ��ʂ̂��������ɂ��Ȃ�B
�����ԍ��F25928765
�����ŁA���߂ĉ�����������肽���̂ł����H
�@���ԓ�
����������肽�����Ƃ͏����܂����B
�����ԍ��F25929822
�J��Ԃ��ɕ�������̂́A�ԗւ����Ă��ꂪ�]�����Ă遨�]�����R�@�Ƃ���
�����E�����@������X�^�[�g�ł��Ă��Ȃ�����ł��B
�ʂɐ����Ă���ł�����Ȃ��ł��傤���A���̍l�������v���������܂���B
���Ȃ݂Ɂw��������肽���x�́A�����炪�����ꂽ�\��(���)�����p�̑�(�Ă�)�Ŏg���Ă邾���ŁA
���h�〉���Ƃ��Ӑ}�Ŏg���Ă܂���B
�����ԍ��F25930810�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�@�������Ƃ���
�ԏd��������A�^�C�����X���b�v������E�̐����͂��オ��܂��B
ABS���쓮����̂��t���u���[�L�Ƃ���Ȃ�A�ԏd�������ău���[�L���͂������Ȃ�A�t���u���[�L�ɂ͂Ȃ�܂���B
JAF�̎����Ɠ����ŁA�����������L�т邱�ƂɂȂ�܂��B
�ԏd���ς������A�t���u���[�L�ƃu���[�L���͈��͗������܂���B
���ԏd��������A�^�C�����X���b�v������E�̐����͂��オ��܂��B
��ABS���쓮����̂��t���u���[�L�Ƃ���Ȃ�A�ԏd�������ău���[�L���͂������Ȃ�A�t���u���[�L�ɂ͂Ȃ�܂���B
���ԏd���ς������A�t���u���[�L�ƃu���[�L���͈��͗������܂���B
����͂������o������A�u���[�L�@�\���S�������ł��B
�ԏd�����Ń^�C���̖��C�͂��オ���Ă��A�������������u���[�L�̖��C�͂͒ቺ���܂��B
���ꂱ���A�ԏd���W�Ȃ��Ƃ������_�̕����A���{�I�ɑ傫������܂��B
��JAF�̎����Ɠ����ŁA�����������L�т邱�ƂɂȂ�܂��B
JAF�̎����̂ǂ�������Ă���̂�������܂��A���ꂱ�����̒��_���������Əؖ����Ă���̂ł͂���܂��H
(1/2) m v^2 = F d
(1/2) m v^2 = ��B S (2 �� r) N
�i�ʁF�u���[�L���C�W���AB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρA�F�~�����Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�AN�F��]���j
���A
N = m v^2 / (4 �� r�� B S)
d = N x �^�C���O�a
�����ԍ��F25930828
![]() 1�_
1�_
���G�����J����
���ԏd�����Ń^�C���̖��C�͂��オ���Ă��A�������������u���[�L�̖��C�͂͒ቺ���܂��B
�����ꂱ���A�ԏd���W�Ȃ��Ƃ������_�̕����A���{�I�ɑ傫������܂��B
�Ӗ���������܂���B�u���[�L�̖��C�͂��ቺ���邱�Ƃ��A�����ӂ̐����Ő��������肢���܂��B
�Ȃ��A�u���[�L�����i�u���[�L���ݗʈ��j�ŁA�ԏd�ɂ�萧���������ς�邱�Ƃ́A���_�I�ɂ������I�ɂ��m�F����Ă��܂��B
�X���̎n�߂̕����䗗���������B
�����ԍ��F25930887
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
�����J�ɂ����̂ڂ��Ă��������A���肪�Ƃ��������܂��B
���������܂Łw���������������Ă��Ȃ��^�����܂����x�̃M���b�v���ǂ��Ɋ����Ă���̂��������邱�Ƃ��ł��܂����B
���ǎ��ɂ́w���ꂪ�ǂ̂悤�ɐ��������ɊW����̂��x�̂Ƃ���̂������������ł��Ă��܂���ł������A���������ł��B
�����Ƃ����������ۂɑ��ċ�C��R������̂Ɠ����悤�ɁA���͓]�����R�����čl���Ă��܂������A���Ȃ��͓]�����R�������A�Ƃ������Ƃ���������Ă���킯�ł��ˁB
�ԏd��������Ƃ������]�����R��������킯�ł����A���ꂪ���������ɉe����^����قǂ̍��ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���ꂱ���ԗւƂ����@�\�̌��ʂł��B
�]�����R�܂ōl������Ƃ������Ƃł���A�^�C���̓]�����R�͂قڃ^�C���̕ό`�ɂ���ċN����܂�����A�w���C�͂͐����R�͂ɔ�Ⴗ��x�����ł͂Ȃ��w���C�W���͒萔�ł͂Ȃ������R�͂ɂ���ĕω�����x�Ƃ����m���ɍ��Z�����͈̔͂��������@���܂ōl������K�v������܂��ˁB
�����ԍ��F25930897�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���������������u���[�L�̖��C�͂͒ቺ���܂��B
�����̒��_��������
�܂������̂��o�Ă����B
�����ԍ��F25930917�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���G�����J����
���W�J���ꂽ���́A�H�ʂ��畂�������Ԏ��Ƀu���[�L���������ł͐������Ǝv���܂����A�H�ʂ̏�𑖂�Ԃ̐���������\���Ă͂��܂���B
�i�O�҂�m�͎Ԏ�����̊����ł���A��҂�m�͎ԏd�ł��j
�u���[�L�̃T�C�Y��u���[�L�p�b�h�̃ʂ�I�ԏ�ł͍l�����Ȃ�������Ȃ����ł����A��ώԏd�̋}�������ɑ��Ă͏\�Ȏd�l�Őv����܂�����A���ӂƉE�ӂ͓����ł͂Ȃ��A�E�ӂ̕��������Ƒ傫���ł��B
�i�����łȂ���ΌJ��Ԃ��u���[�L��⓹������悤�ȃu���[�L�ɑΉ��ł��܂���j
�ԏd��������u���[�L�̖��C�͂��ቺ����A�Ƃ���������Ă���̂́A�u���[�L���u�̖��C�͂��ቺ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�ԗ��̐����͂��ቺ����Ƃ������Ƃł��傤���B
���̋}�����ł���A�u���[�L���u�̖��C�W���͎ԏd�ɂ�炸�قڈ��ƍl�����(��)�A�ԏd���������ABS���������邽�߂ɕK�v�ȃu���[�L���͂͑����܂��B
�i���F�����ɂ͑��x�ɂ���Ă��ω����܂��j
�ԏd���������炻�̕������y�_���܂Ȃ��ƌ����܂���B
�u���[�L�����ł͐��������������ē��R�ł��B
�����ԍ��F25930952�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���݂܂���
�ԗւ��L���Ă��^�C���̕����̖��C
���x�A�����O���ł̖��C
���L����
���Z���Ă����Ȃ菬���Ȗ��C�͂��Ƃ͎v���܂����@
�����̐��E��
��̉d��������Δ�Ⴕ�Ė��C�͂���������Ă��
���藧���Ȃ���ł���
�����ԍ��F25930985
![]() 0�_
0�_
�l�@�ɖ��������邩�ƁA�u���[�L�̐��\�ƘH�ʏ�ݒ肵�Ȃ��Ə����ɂ��Ⴄ�̂ł́H
1)�^�C���ƒn�ʂ̐ݒu�ʂ͎ԏd�ɂ���ĉe��������B
2)�u���[�L�@�\�͐��\���E��������̌��E�l���z����A��]���~�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ肻�̒l�ɂ͎ԏd�͊W���Ȃ��B
�]����^�C���łȂ��l�p�����̒�ɃS��������t���Ēu����Ă���ƍl����A���̏�ԂőS�̂��y����Όy���قǂ悭����B
�Ԃ̏ꍇ�u���[�L�̂���^�C��������l�p�����̒�ɔ��Ɉ��ȏ�̉����͂ʼn�]���n�߂�S��������Ɠ����B
�u���[�L�@�\�̐��\����ŏ��ω�����̂ŁA��]���Ȃ��S�����������Ɖ�]����S���̂��������Œ肷��͂�
�����ȉ��Ȃ�d�ʑ������邾�����������͐L�т�B
��������ɂȂ�Ȃ�قǂɏd�ʑ����Ő����������Z���Ȃ�B
�e�X�g����Ԃ̃u���[�L���\�ƘH�ʂ̊�������B
����₷���]����₷�����͏d�͂̉e�����ł�����ɋ߂Â��Ă�̂ƈꏏ������A��͕��̂̎��^���G�l���M�[�̍��ɂȂ�B
������JAF����������carwow��������
�����ԍ��F25931039
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����
���܂������̂��o�Ă����B
���ꂾ���X�����L�т�Ɛ����S���ǂ߂�͂��������ł����A���E�����Ȃ��̂���ނȂ����ƁB
�e�X�g���̃u���[�L�̈��͂Ȃ蓥�݉����̑������������ȕ��ł��ꂼ��o���o���ł���ˁB
���x���������������܂����A�u���[�L�́u���ݕ��v�����Ɗ|����u���́v����肩�͂�������ň���āA
JAF�̃e�X�g�ł́A�����������b�N���Ȃ����x���̓������͂ł̃e�X�g�ł��B
����ł��Ƒ������d�ʂɃu���[�L���ǂ����Ȃ��͓̂��R�ŁA�����͐L�т܂��BJAF�e�X�g�̒ʂ�ł��B
�����A�X���`���̃e�X�g�͓��ݕ����ƌ����Ă��u�S�́v���A�������͂���ɏ����鋭�����ݕ��ł��B
�����Ň�ABS��������ł��܂��B
�Ⴆ�Ύԏd1�g���̓����ԂŎ���50km/h�Ƃ��̏����ŁA
�@ �ؚ��ȏ������S�͂œ��ꍇ�B
�A �̏d150kg���炢�̃v�����X���[���S�͂œ��ꍇ�B
�ǂ�����S�͂œ��߂����炭�^�C�����b�N�ɕK�v�ȕ��܂Ńu���[�L�������B���A
����ȏ��ABS�����b�N���O�ň��͂��܂��̂ŁA�v�����X���[���ǂꂾ�����͂��傫���Ă����ʂɂȂ�܂��B
��̇@�A�͏���̑̏d���A���d�ʂ��Ⴂ�܂��̂ł�����b�N���O�iABS����j�܂łɕK�v�ȃu���[�L���͕ς��܂��B
�����������͏o���܂���̂Łw�����܂ł��C���[�W�x�Ƃ��Ăł����A
�@�̏�������Ԃ̏ꍇ�A�Ⴆ��20kgf�܂œ����_��ABS����������Ƃ��܂��B
�@�{�l�͊撣����30kgf�ł����Ɠ���ł��܂����A20�ȏ�̕���ABS�������Ă��܂��B
�A�̏ꍇ�A�̏d����1���A���d���̂ŁAABS����܂łɂ͖�22kgf�̓��͂��K�v�ł��B
�@���X���[�͎���100kgf�œ��ݑ����Ă��܂����A���ۂɂ�22�ȏ�̕��͖��ʓ��݂ł��B
�i���͂ƃu���[�L���͂͐���Ⴕ�Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�����܂ł��C���[�W�ł��j
���ǁA�d�ʑ������̓^�C�����C�̓A�b�v�Ńu���[�L�����s�ł��鈳�͂����܂�ׁA��~�����͂قړ������ƂȂ�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25931100
![]() 2�_
2�_
��Mr.Z.����
��1)�^�C���ƒn�ʂ̐ݒu�ʂ͎ԏd�ɂ���ĉe��������B
��2)�u���[�L�@�\�͐��\���E��������̌��E�l���z����A��]���~�߂邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ肻�̒l�ɂ͎ԏd�͊W���Ȃ��B
1)�͂��̒ʂ�ł����A�e���͔��ɏ��Ȃ��A�X����̎��ۂ��������̂ɕK�v���Ƃ͎v���܂���B
2)�͌��ł��B�u���[�L�@�\�̐��\���E�ɂ͎ԏd���傫���W���܂��B�ԏd�ȊO�̏����������ς��Ȃ��Ă��A�ԏd���v�l���ďd���Ȃ�ƁA��]���~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
��]���Ȃ��S�����������Ɖ�]����S���̂������̘b�ɂ��ẮA���������ʂ肩�Ǝv���܂��B
�֑��Ȃ���A1)�ɂ��Ă��������������܂��B
�ԏd��������ƃ^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂��傫���Ȃ邱�ƁiF=��N��N�������傫���Ȃ邱�Ɓj�ƁA�ԏd��������ƃ^�C���ƘH�ʂ̖��C�W�����傫���Ȃ邱�ƁiF=��N�̃ʂ�N���傫���Ȃ邱�Ɓj����������Ă�����������������悤�Ɏv���܂��B
�悭�o�Ă���^�C���̃O���b�v�~�͂��̂قƂ�ǂ��O�҂����̂��b�ł��B
�ԏd�������Ă������������ς��Ȃ��̂́A�ԏd�ɂ���Ė��C�͂͑����Ă����C�W������肾����ł��B
�ԏd��������Ɩ��C�W����������Ƃ������Ƃ́A�ԏd��������Ɛ����������k�݁A�t�Ɏԏd������Ɛ����������L�т�Ƃ������Ƃł��B
����͔��ɏ��Ȃ��ω��Ȃ̂ŁA�ʏ�̊��ł͎����̃o���c�L�ɕ���Ă��܂��܂��B
��ʘH�⍂���Ƃ����������ł�������ł邱�Ƃ�����܂��B
�����ԍ��F25931254�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���e�X�g���̃u���[�L�̈��͂Ȃ蓥�݉����̑������������ȕ��ł��ꂼ��o���o���ł���ˁB
�ł��ȁB���_��ς��āA�u���[�L�̐��\���Ԏ�ɂ���ĈႤ����A�d���قǐ����������L�т�Ƃ����������Ȃ��B
�o�C�N�̑�^�i�ԏd�{�̏d��300kg�E�t�����g�_�u���f�B�X�N�Ό�4�|�b�g�L�����p�[�E�c�[�����O���W�A���^�C���j�ƌ���i����180kg�E�t�����g�V���O���f�B�X�N�Љ���1�|�b�g�E�o�C�A�X�u���b�N�^�C���j�ŁA�O�҂̕����m���ɐ��������͒Z���B��������Ȃ��Ƒ��ΓI�ɑ��x�������c�[�����O���y���߂܂ւ�B�������A�H�ʂ��d�̑������~�߂Ċ���Ȃ��ꍇ�ł����B
���������������u���[�L�̖��C�͂͒ቺ���܂��B
������H���Ċ����B
�����ԍ��F25931269�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��use_dakaetu_saherok����
�u���[�L�@�\�����P�̂ōl���Ă���������Ηǂ����ƁB
�����u���[�L�^�����V���O���s�X�g���ƍ����i�̑��d�R�s�X�g��
�O�҂ɂ�����d���������Ƃ���ŔM�G�l���M�[�ɕϊ��ł���ő�l�͌��肪���荂���i�ɂ͂��Ȃ��܂���B
�Ԃ��~�߂�Ƃ����s�ׂ�P�������čl����u���[�L�ŔM�G�l���M�[�ϊ����ĉ^���G�l���M�[��������Ă���
(�{���̓^�C���̓]�����R�����ȂǂŊ����ɕϓ�������܂����A�ɘ_�Ŗ���)
�Ⴆ��1�b��100�̗͂ŔM�G�l���M�[�ϊ��ł���u���[�L���������Ƃ���
1�l�̏d���ł̓^�C����10�̗͂ŃX���b�v����̂ŁA�u���[�L�̐��\�͊�������1�b��10�̗͂ŔM�G�l���M�[�ϊ�����B���̎��̎Ԃ̉^���G�l���M�[��200�Ȃ�20�b�������Ď~�܂�B
5�l�̏d���ł̓^�C����100�̗͂ŃX���b�v����̂ŁA�u���[�L�̐��\��1�b��100�̗͂ŔM�G�l���M�[�ϊ�����B���̎��̎Ԃ̉^���G�l���M�[��2000�Ȃ�20�b�������Ď~�܂�B
10�l�̏d���ł�200�̗͂ŃX���b�v���邪�A�u���[�L�̐��\���E��100�̗͂ŔM�G�l���M�[�ϊ�����B���̎��̎Ԃ̉^���G�l���M�[��4000�Ȃ�40�b�������Ď~�܂�B
�H�ʏ������A�S�Ă̐l����10�̗͂ŃX���b�v����H�ʂȂ�^���G�l���M�[�������ԂقǁA�M�G�l���M�[�ɕϊ����鎞�Ԃ�������~�܂�܂Ŏ��Ԃ�������B
���ۂɂ͂���ɗl�X�ȓ]�����R�̏d�ʑ��ɂ�鑝���l�������P���ȐL�тɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����A��Ƀu���[�L�ŎԂ͎~�߂Ă�̂ŒP�������čl���Ă݂܂����B
�����ԍ��F25931608
![]() 0�_
0�_
���G�����J����
��(1/2) m v^2 = F d
��(1/2) m v^2 = ��B S (2 �� r) N
�i�ʁF�u���[�L���C�W���AB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρA�F�~�����Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�AN�F��]���j
���A
��N = m v^2 / (4 �� r�� B S)
��d = N x �^�C���O�a
�������邽�߂ɏ����L���̕\�L��ς���̂ƁA�������L����lj������Ă��������B
(1/2)�Em�Ev0^2 = Ft�Ed �c(1)
�im�F�ԏd�Av0�F�u���[�L�J�n���̑��x�AFt�F�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɓ������C�́Ad�F���������j
(1/2)�Em�Ev0^2 = ��b�EB�ES�E(2��r)�EN �c(2)
�i��b�F�u���[�L���C�W���AB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρA�F�~�����Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�AN�F��]���j
N = m�Ev0^2 / [(4��r)�E��b�EB�ES] �c(2')
d = N�E(2��R) �c(3)
�iR�F�^�C���O�a�j
(3)��(2')����
d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�E��b�EB�ES) �c(4)
�����܂ł͓��������������������������ł��B
��������(4)�̎��������݂�A���q�̃^�C���aR�E�ԏdm�E���xv0���傫���Ȃ邩�A����̃u���[�L���C�W����b�E�u���[�L�ar�E�u���[�L����B�E�u���[�L�ڐG�ʐ�S���������Ȃ�A��������d��������悤�Ɍ����܂��B
�������A�Ⴆ�Ύԏdm���傫���Ȃ��Ă��u���[�L����B�����̕��傫������ΐ�������d�͑����܂���B
�ő吧���͂����Ă����ԂƂ����̂͂���������Ԃł��B
��Ɏw�E�����悤�ɁA�����܂ł̎��ɂ́A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W�����o�ꂵ�܂���B
�����ŁA�摜�̂悤�ɎԎ�����̃��[�����g���l����ƁA���L�̂悤�Ȏ��������܂��B
R�EFt = r�EFb �c(5)
�iFb�F�u���[�L�̖��C�́j
Ft = ��t�E(mg) �c(6)
�i��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���j
Fb = ��b�EB�ES �c(7)
(5)��(6)(7)��������ƁA
R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
����(8)���̍��ӂ��傫���Ȃ�A�E�ӂ��傫�����Ȃ��Ƃ肠�����Ƃ�܂���B
�Ⴆ�Ύԏdm���傫���Ȃ��Ă��u���[�L����B�����̕��傫������A�Ƃ������̂͂��̂��Ƃł��B
���������悤�Ȏԏd�����Ń^�C���̖��C�́i��t�E(mg) �j���オ���Ă��A�������������u���[�L�̖��C�́i��b�EB�ES�j�͒ቺ����Ƃ������ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ͂�������ɂȂ�܂��ł��傤���B
�����(8)����ό`���A
��b = [R�E��t�E(mg)] / (r�EB�ES) �c(8')
(8')��(4)�ɑ������ƁA
d = (1/2)�E(R�Em�Ev0^2) / (r�EB�ES) �E(r�EB�ES) / [R�E��t�E(mg)] �c(9)
����(9)��������ƁA
d = v0^2 / (2�E��t�Eg) �c(9')
�ƂȂ�A�ԏdm���u���[�L�̍��������āA�������猾���Ă��鎮�Ɠ����ɂȂ�܂��B
���Ȃ킿��������d�͑��xv0���傫����Β����Ȃ�A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W����t���傫����ΒZ���Ȃ�܂��B
�����ԍ��F25931647�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��Mr.Z.����
���������Ӗ��ł������B
�ԗ��Ƃ��ău���[�L�ŕϊ����K�v�ȔM�G�l���M�[�̗ʂ͎ԗ��̎ԏd�Ƒ��x�ɂ���Č��܂�܂�����A��̏������݂ɂ������ԏd�͊W���Ȃ��Ƃ����̂͌��ł͂���܂��H�Ə����܂����B
�ԗ��Ƃ͊W�Ȃ��u���[�L�@�\�P�̂ōl����̂ł���A�u���[�L�@�\���ϊ��ł���M�G�l���M�[�̗ʂ́A�m���ɂ��̃u���[�L�@�\�̎d�l�����Ō��܂�܂��B
���̕����ɂ��Ă͊Ԉ���Ă���Ƃ͎v���܂���B
�����ԍ��F25931687�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�@��use_dakaetu_saherok����
���������A�Ⴆ�Ύԏdm���傫���Ȃ��Ă��u���[�L����B�����̕��傫������ΐ�������d�͑����܂���B
���ő吧���͂����Ă����ԂƂ����̂͂���������Ԃł��B
�������A�z��̓t���u���[�L���O�Ȃ̂ŁA���͈͂��ł��B
�܂��u���[�L�@�\�́A���[�^�[�̉�]�͂ډ����Ԃ��͂ł͂Ȃ��A�������Ă��̖��C�ɂ���Ĕ��͂֕ϊ����Ă��܂��B
�����P���ȃx�N�g���ōl���Ă݂�ƁA���s�����̃x�N�g�����P�{����A����ɑ������̃x�N�g���ō��E���牟�������鎖�ɂ�鐧���i�f�B�X�N�u���[�L�̏ꍇ�j�ƍl������̂ŁA���̗͂̍������l����A�����́i�d�ʕω��j���傫���֗^���鎖��������܂��B
�܂芵���͂���������A�t���u���[�L���O�̈��Ȑ������͂ł̉��������ł́A�����͈͂ȑO��菟���ē˂������鎖�ƂȂ萧���͂͒ቺ���܂��B
���ꂪ�����͂ɂ���Ė��C���ω�����Ɛ\���Ă��鍪���̂��闝�R�ł��B
�܂������܂߁A�ԗ��d�ʂ̕ω��ɂ���Đ����������ω�����Ɛ\���Ă�����X�́A�ԗ��d�ʂ̕ω��ŕK�v�Ƃ����u���[�L���͂��ω���v������Ă��܂������A���̌��Ƃ��Ď�����Ă�����X���Ǝv���܂��B
���������̋�_����������Ă��A���̌��ɏ�����̂͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���ۂɔ����������𗝋��ʼn𖾂���A���̌��ʂ��l�X�ȕ������_�Ƃ��ĔF�m����Ă����ł�����A�܂����_���肫�ł͂Ȃ��̂ŁA���ۂɔ������Ă��錻�ۂ�����Ă��c�_�͕��s���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����ԍ��F25931694
![]() 0�_
0�_
���G�����J����
���z��̓t���u���[�L���O�Ȃ̂ŁA���͈͂��ł��B
�t���u���[�L���O�Ƃ�ABS���쓮����u���[�L�̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł����H
�ԏd���������ABS���쓮����ۂ̃u���[�L���͂͑����܂��B
�������l��ו�����������ڂ�����A������苭���y�_���܂Ȃ��ƁA�����Ɠ��������������Ȃ��A�Ƃ����̂����̎��̌��ł��B
�����ԍ��F25931709�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
����������ƃV���v���ɍl������ǂ��ł��傤�B
�܂��H�ʂƃ^�C���̖��C�ɂ�錸�������ǁA�^�C���Ɠ����S���ō�����A�����O�`���@�Ŕ�d���Ⴄ���̂�p�ӂ��āA���̂Q�̕��̂��A�����̓��͂łT�O�jm�^���܂ʼn����������_�Ńp�b�Ɠ��͂�藣���ĘH�ʂ����点�����A�d�����ƌy�����̂ǂ��炪��܂ōs���Ď~�܂邩�H
����͌y�������ۗL�^���G�l���M�[�͏��������njy�������C�����Ȃ��A�d�����͉^���G�l���M�[�͑傫�����Ǐd�������C���傫���A�����痼���Ƃ������ʒu�Ŏ~�܂�Ƃ������Ƃł����ˁB
���̎�����ꂽ���������悤�ȁB
�ŁA���ۂɎԂ��~�߂邽�߂ɂ͑����Ă���Ԃ̉^���G�l���M�[���[���ɂ���K�v������A����ɂ́A���̘H�ʂƃ^�C���̖��C�͂ƎԂ̃u���[�L�ɂ�門�C�M�̗������K�v�ɂȂ�܂��B
�ł�����A�H�ʂƃ^�C���̖��C�M���ς��Ȃ��Ȃ�A��l��Ԃ̂Ƃ����A�������Ԃ̕����d�����^���G�l���M�[���傫���̂ŁA�u���[�L�Ŕ������ׂ��M�ʂ������K�v�ɂȂ�܂��B
���̎ԏd�����ɂ�鐧�������̔�r�ł́A�������\�A�\�͂̃u���[�L�̎ԂŁA�����u���[�L���ݗ́i�����͂Ŏv�������蓥�ށj�Ȃ̂ŁA���M���ׂ��u���[�L�M�ʂ������K�v�ȏd���Ԃ̂ق�����~�܂ł̃u���[�L���O���Ԃ������Ȃ镪�A�����������L�т�ł��傤�ƁB
�t�ɋ}�u���[�L���_�ŁA�y�������d���������^�C�����b�N�����Ȃ�A�����͂��H�ʂƂ̖��C�݂̂ɂȂ�̂Ő��������͓����ɂȂ邩���A�����������������̂��̂͑����L�т�̂ł́B
�Ƃ������ƁA�ł��̃X���`���̃��[�`���[�u����́A�g���b�N���W���[�N���A�������͂`�a�r�����̎ԂŃ^�C�������b�N�����Ă����̂��Ǝv���A�i�`�e�̃e�X�g���ʂ̕����M������B
�����ԍ��F25931710
![]() 1�_
1�_
�������u���[�L���ݗ́i�����͂Ŏv�������蓥�ށj�Ȃ̂�
��������ƁA�y���Ԃ͑���ABS���쓮����A�d���Ԃ͐����R�͂��傫������ABS���쓮�i���b�N�j���ɂ����A�ƂȂ��ł���ˁB������E�ӂƍ��ӂ�m�͏����o����Ƃ������_�ɍ��v���A���b�N�����ɔM�G�l���M�[����o�o����͈͂ɂ����Đ��������͐L�тȂ��A�ƂȂ邩�ƁB
�����ԍ��F25931716�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���ʂ��ς��ƁAABS���쓮���n�߂�u���[�L���i�u���[�L���݈��j���ς���Ă��邱�Ƃ��A�����ł��Ȃ��悤�ł��ˁB
ABS���쓮����̂́A�^�C�����X���b�v���n�߂�Ƃ��B
���Ȃ킿�A�^�C���ɂ����鐧���͂��A�Ö��C�́i�ԏd�Ɩ��C�W���̐ρj�ɒB�����Ƃ��ł��B
�����ԍ��F25931727
![]() 3�_
3�_
JAF�̃e�X�g��ABS�����������ǂ����͕�����Ȃ����ǁA�ǂ����ɂ��Ă��A���ꂪ�e�X�g���ʁB
���Ƌ}�u���[�L���ގ��A��Ԑl���œ��݂����ς��Ȃ���ˁB�N�ł��v��������ӂނ̂ł́B
���Ƃ̓u���[�L�V�X�e�����ǂ����䂷�邩�݂����ȁB
�����ԍ��F25931734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��use_dakaetu_saherok����
�����ǎ��ɂ́w���ꂪ�ǂ̂悤�ɐ��������ɊW����̂��x�̂Ƃ���̂������������ł��Ă��܂���ł������A���������ł��B
���̍ŏ��̏������݂ɏ������Ă��������܂����B
���^�C���������ƘH�ʂ��Ƃ炦�ăX���b�v���Ȃ��A�u���[�L�@�\���ԗ�(�^�C��)�������E��~�����鐫�\���[���ł���A
���h���C�o�[�̔������x�A�둀��Ȃǂ������A������́A�d�ʂɊW�ɊW�Ȃ��~�܂�܂����B
�����ۂɂ͏d�ʂ��傫����A�}�������ɃX���b�v���������A�]�v�ɐ��������������܂��B
���܂��̓u���[�L���\���ԗ�(�d��)�����̐��\�ɂȂ���A�Z�������ł̐����ł��܂��A�u���[�L�@�\���j�����܂��B
�������ԍ��F25926455
�������o�ŏ������̂ŁA���m�łȂ��A�ڍׂł��Ȃ��̂ŁA
�ǂ��͂�͂�u�Ӂ[��A�悭�킩���v�Ǝv�������Ƃł��傤�B
���̕\���ł͂��܂������ł��Ȃ��̂ŁA�T���ďo�Ă����T�C�g����}�ƕ��͂����p���܂��B
�Q�l�摜�Ȃ�тɕ��͉��L���
https://www.jari.or.jp/research-database/detail/?slug=45597
����ʂ̏�p�Ԃł́A�u���[�L�y�_���ޗ́i�y�_�����́j�̓u���[�L�t�̉t���ɕϊ�����A�u���[�L�@�\�ɓ`�B����܂��B�`�B���ꂽ�͂ɂ���āA�f�B�X�N�u���[�L�̏ꍇ�ɂ̓p�b�h���f�B�X�N�ɁA�h�����u���[�L�̏ꍇ�ɂ̓u���[�L�V���[���h�����ɉ����t�����܂��B���̂Ƃ��A�p�b�h�ƃf�B�X�N�̊ԁA���邢�̓V���[�ƃh�����̊Ԃɂ��ׂ薀�C�������A���̖��C�͂ɂ���Ďԗւ̉�]���x��������܂��B����ƁA���x�̓^�C���ƘH�ʂƂ̊Ԃɂ��ׂ���A���̂��ׂ�ɂ���ă^�C���ƘH�ʂƂ̊Ԃɗ́i�����́j���������A�Ԃ͑��x�𗎂Ƃ��~�܂�̂ł��B
�����̂悤�Ƀu���[�L���u�́A�^�C���ƘH�ʂƂ̊Ԃɐ����͂������ĎԂ��~�߂�킯�ł����A�����ɁA���s����Ԃ̎��^���G�l���M�i���͔R���G�l���M�j��M�ɕϊ�����C���ɕ��U����������������Ă��܂��B�u���[�L���������Ƃ��A�ԗւ���]���Ă���A�M�̂قƂ�ǂ̓u���[�L�@�\�Ŕ������܂��B�������A�ԗւ̉�]����~���ă��b�N��ԂɂȂ�ƁA�u���[�L�@�\�ł͂��ׂ肪�Ȃ����ߔM�͔��������A�M�̑S�Ă��^�C���ƘH�ʂƂ̊ԂŔ������܂��B���̂��߁A�^�C���͋Ǖ��I�ɖ��Ղ��邱�ƂɂȂ�܂��B�������Č���ƁA�u���[�L�̎g���߂��̓^�C����u���[�L�̖��Ղ𑁂߂邾���łȂ��A�G�l���M�̖��ʌ����ɂȂ��邱�Ƃ������ł���ł��傤�B
��L���͂̌J��Ԃ��ɂȂ��Ă��܂��܂����A���C�͂̓u���[�L�@�\�̃p�b�g�ƃ��[�^�[�ԂŔ������A
�ԏd�ɊW���銵���̓p�b�g(�����R��)�łȂ��A���[�^�[�̉�]�̕��Ɋ֗^���A
�ڒn��(�u���[�L�ƃp�b�g)�̐��������ɓ����܂��B
�����ɏ�����Ă��鐧����(�^�C���ƒn�ʂ̐ڒn��)�ɂ��������ԏd��������A
��������͂ɂ��u���C�́v���W���Ă��܂����A
����o�����}�P�̖��C�͂ƈႤ�Ƌ�ʂ��čl���Ȃ��ƁA��ʂ��ł��Ȃ����A���������܂��B
�Ȃ̂ŁA��ɉ�~����̂łȂ��A�܂��}�P�̒��u���Ǝԗ@�\���Ⴄ���Ƃ𗝉����Ă��炢���������̂ł����A
�ԗ@�\���A�Ӑ}���`��炸�c�O�ł��B
�����ԍ��F25931941�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���_��͐��������Əd�ʖ��W�B����͕����̖@���ŒN�������Ȃ������̗����ɔ��_���Ă��S���̖��ʁB
���ۂ̐������������_�ƈقȂ鎖���́A���_�ʂ�쓮���鐧���n�����ɋZ�p�ł͍��Ȃ��A���邢�͍�ꂽ�Ƃ��Ă��o�ύ������������A���ꂾ���̎��B
�v����ɊF����̑̌��͂��̎Ԃ̐����n�ւ̋��̊|��������ł��B
�����ԍ��F25931948
![]() 1�_
1�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�����ԁi�{�́j�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2025/11/17 15:19:54 | |
| 0 | 2025/11/17 14:38:25 | |
| 2 | 2025/11/17 15:30:36 | |
| 8 | 2025/11/17 15:39:02 | |
| 8 | 2025/11/17 15:29:15 | |
| 3 | 2025/11/17 10:24:44 | |
| 2 | 2025/11/17 7:52:10 | |
| 0 | 2025/11/17 0:06:15 | |
| 10 | 2025/11/17 12:55:35 | |
| 10 | 2025/11/17 14:09:42 |
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�����ԁj
�����ԁi�{�́j
�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j