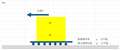https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/
�̂Â��ɂȂ�܂��B
��Ԑl���������Ă����������͓���
�Ƃ������Ƃ��ǂȂ��ɂł�������悤�ɐ������鎎�݂ł��B
�Ɠ����ɑ��ɂ������@��������̂Ȃ炻���m�肽���Ƃ������̍D��S�ł��B
�����ԍ��F25932232�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�d�������ڂ�����u���[�L�������ɂ����Ɗ�����
�y�_�����������߂u���[�L����������
�����܂ł݂͂Ȃ��܂̋��ʑ̌��Ƃ������Ƃł����ł���ˁH
���Ⴀ�A
�d�������ڂ��Ă��A���̕������u���[�L�߂Γ���������������
����������������Ȃ瓯�����������Ŏ~�܂��
�ƂȂ�܂��H
�{�͑��u��ABS�����邩�番����ɂ����̂ł��傤���B
ABS�̓^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂ƃu���[�L�͂��肠���悤�Ɂi�ő吧���͂��ł���悤�Ɂj�u���[�L���͂����鑕�u�ł��B
�l�������������u�ʼn������悤�������@���͕ς��܂���B
�����ԍ��F25932235�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���G�����J����
���܂芵���͂���������A�t���u���[�L���O�̈��Ȑ������͂ł̉��������ł́A�����͈͂ȑO��菟���ē˂������鎖�ƂȂ萧���͂͒ቺ���܂��B
�����ꂪ�����͂ɂ���Ė��C���ω�����Ɛ\���Ă��鍪���̂��闝�R�ł��B
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
���̎�������m�Ɛ�������B�̊W��\���Ă��邱�Ƃ͂�������ɂȂ�܂����H
�E�ӂ𐧓��͂ƕ\������Ă���悤�ł����A���ӂ������͂ł��邱�Ƃ͂�������ɂȂ�܂����H
���ӂ͎Ԃ������o���Ă��܂��Έ��ł��B�i�H�ʂ̃ʂ��r���ŕς��̂͂Ȃ��Łj
���ꂪ���̎Ԃ̔����ł���ő吧���͂ł��B
����A�E�ӂ̓u���[�L�ޗ͂�ABS��������͂ł���A�ϓ����܂��B
��ʂ̂��߂Ɉȉ��A�E�ӂ��u�Ԑ����͂ƋL�ڂ��܂��B
�E�ӂ̕����������Ƃ������Ƃ̓^�C���ɂ܂��]�T�������Ԃł���A�E�ӂ̕����傫���Ƃ������Ƃ̓^�C�������b�N�����Ԃł��B
ABS�̓^�C�����b�N�t�߂ʼn����������J��Ԃ����u�ł�����AABS���쓮���Ă���Ƃ������Ƃ́A���ӂƉE�ӂ��قړ�������Ԃł��B
���������ʂ芵��m�������Ă�����B�����Ȃ�E�ӂ̕����������Ȃ�A�u�Ԑ����͂͑��ΓI�ɏ������Ȃ�܂��B
�������Ȃ���A����m��������ƍ��ӂ̍ő吧���͂͑傫���Ȃ�܂��B�^�C�����b�N�܂łɂ͗]�T�����܂�܂�����AABS�͂���ɉ������Ĉ���B���傫���Ȃ�܂��B
����ȊO�Ɋ���m�Ɛ�������B�̊W��\����������A�����Ă��������B
�����ԍ��F25932242�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
���Ȃ̂ŁA��ɉ�~����̂łȂ��A�܂��}�P�̒��u���Ǝԗ@�\���Ⴄ���Ƃ𗝉����Ă��炢���������̂ł����A
���ԗ@�\���A�Ӑ}���`��炸�c�O�ł��B
�������W�n�ōl���邩��]���W�n�ōl���邩�A�Ƃ������Ƃł��傤���H
�P�ʂ�mm�ł�rad�ł������@���͕ς��܂��A���Ԃ������Ӑ}�ł��Ȃ���ł��傤�ˁB
���u���Ǝԗ@�\�Ő����͂ɑ���l�������ǂ��ς��̂��A����ς莄�ɂ͂悭������܂���B
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
���ɂƂ��Ē��u���Ǝԗ@�\�ňႤ�̂́A���̎���R��r�������Ƃ��炢�ł��B
�����ԍ��F25932309�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���[�[�@�f�l�l�́@�������������ς�
�����ԍ��F25932326
![]() 10�_
10�_
�S�֓Ɨ�ABS���ő���\�͂������
�Î~���C�W���ɂȂ�̂Ł@����M��������
�u���[�L�̗e�ʂ�����Ȃ���
�ő吧���́@F����܂����ꍇ�@��M����
���������x�́@����M�ɔ���Ⴗ��
�ȏ�@�@Q.E.D
�����ԍ��F25932339
![]() 5�_
5�_
��use_dakaetu_saherok����
�H�ʂ�����₷���ƁA�d���قǐ��������͐L�т₷����ˁ[�B
�H�ʂ�����ɂ����قǁA�u���[�L���\���ǂ��قǁA�T�X�y���V�����Ɛl�Ԃ��悭�����قǁA�d���̉e���͎ɂ�����ˁ[�B
�ŗǂ��̂ł́B
�����ԍ��F25932340�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�v�́A�ŏ��̃X���̖`���̃��[�`���[�o�[�̎ԏd������Ă����������͕ς��Ȃ��Ƃ��������M���邩�A�펯�I�œ�����O�̎ԏd���ς��ΐ����������ς��Ƃ���JAF�̃e�X�g��M���邩�Ƃ����b���ŁA�������ʂ͗D�G�ȕ����w�҂Ȃ痝�_�Â��o����͂��B
�c�O�Ȃ���l�b�g���ɂ͖����̂悤�ȁB
�����ԍ��F25932355�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
���H�ʂ�����₷���ƁA�d���قǐ��������͐L�т₷����ˁ[�B
���o�Ō���Ă��@�Ԉ���Ă܂�
�d����@�������Ă�͂������Ȃ��ā@���Ǐd��M�������������
���������͕ς��Ȃ����Ă̂��@�ŏ��̓���ł��B
�����ԍ��F25932364
![]() 1�_
1�_
���ƂЂƂ厖�Ȃ��Ƃ́A�����̑匴���ł���G�l���M�[�s�ł̖@��(�G�l���M�[�ۑ��̖@��)����A�����u���[�L���\�̎ԂŁA�d��������ω���������^���G�l���M�[�͏d���ɔ�Ⴗ��̂ŁA�d���Ԃ̕�����~����̂ɗ]�v�����̔M����o���Ȃ�������Ȃ��B
����́A�Ȃɂ��ǂ����������ˌJ��܂킵�Ă��A�ς��Ȃ�����B
�����ԍ��F25932368�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���Ђ�N�Ђ�N����
���d����@�������Ă�͂������Ȃ��ā@���Ǐd��M������������� ���������͕ς��Ȃ�
����₷���H�ʌ���ŏ����Ă��ł����ǁB�����ł́A�y����ABS�������쓮���܂����ǁB�H�ʂ̖��C��u���[�L���\�ɑ��Ċ����͂��x�z�I�ɂȂ�قǁA�L�т�ł���H
�����ԍ��F25932370�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���d���Ԃ̕�����~����̂ɗ]�v�����̔M����o���Ȃ�������Ȃ��B
���̎��̓C�G�X�ł������������Ƃ͖��W�ł��B
�G�l���M�[�ʂƐ��������́i���_�I�ɂ́j���W���Ƃ������Ƃ͑O�̃X���ŕ�����������ؖ��ς݂ł��B
�G�l���M�[�ʂ����������ɊW����Ƃ��咣�Ȃ炻�̎�����������������ďؖ��Ȃ���̂������ł��B
�����ԍ��F25932402
![]() 6�_
6�_
��use_dakaetu_saherok����
�X�����Ă��肪�Ƃ��������܂��B
�܂��́A�������ʂ�O�X������]�ڂ��܂��B
96km/h����t���u���[�L�B
1�l�A4�l�A7�l�A7�l��200kg�̉ו��ŁA���ꂼ�ꐧ�������������B
https://youtu.be/MRxr757Q9nk?t=211
�u���[�L���ݗʂ����ɂ���JAF�̃e�X�g����B
�P����Ԃɔ�ׂĒ����Ԃ͐����������L�т�B
https://www.youtube.com/watch?v=-dw1avumTpI
�����ԍ��F25932423
![]() 5�_
5�_
��use_dakaetu_saherok����
�u���[�L�@�\�̖��C�́@F'=��'N'
��'�@�p�b�h�ƃ��[�^�[�ږʂ̖��C�W��
N'�@�u���[�L���͂̐����R�͂ŏd��(�d�͉����xg)�W�Ȃ��B���ݍ��ݗ͈��Ȃ���B
���̃u���[�L�@�\�̖��C�͂ł́A�����R�͂ɏd�ʂ͊W����܂���B
���ݍ��݂ƃu���[�L�@�\�̐��\����ł��B
���ݍ��݈�(�p�b�h�̈���)�����Ȃ�A
���傫�������ō���(�͋���)�ʼn���Ă��郍�[�^�[�ɓ��ĂĂ�
���[�^�[(�^�C��)���~�܂�ɂ����̂́A�z�����Ǝv���܂��B
��������ŕ\���Ƃ܂����Ȃ�߂�ǂ������̂Ŋ������܂��B
�]�����R(�]���薀�C�H���\���Ƃ��Đ������̂����f�s�\�ɂȂ��Ă��܂���)������������ƁA
��]��X���b�v���������A�^�C�����H�ʂ��Ƃ炦�ĂȂ��ɂȂ�܂��B
���̒��u��(���C�͂̐})�ł́A���̂̊����ɏd�ʂ̗v�f�������Ă��A
�����R��(�����Ă͖��C��)���d�ʂɉ����đ傫���Ȃ�܂����A
�ԗ@�\(�u���[�L�@�\)�ł́A�u���[�L�@�\�̐����R��(���C��)�ɂ͏d��(�ԏd)�̗v�f������܂���B
�����ō����łĂ��܂��B
�����͂����ŕ\�킻������ƁA�u���[�L�@�\�̖��C�͂��g���N�Ƃ��ĕϊ�(�t�ϊ�)�����āA
�]�����R(������͏d�ʂɊW����)�Ƃ̘a�ł��o���ł��傤���H
���̐��_��Ԃł͌v�Z����ӗ~���o�܂���B
�����ԍ��F25932511�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�������u���[�L���\�̎ԂŁA�d��������ω���������^���G�l���M�[�͏d���ɔ�Ⴗ��̂ŁA�d���Ԃ̕�����~����̂ɗ]�v�����̔M����o���Ȃ�������Ȃ��B
�N��������ے肵�Ă��܂����B
7�l���̎Ԃ�7�l����ĔM�̕��o�ʂ�����Ȃ��Ȃ�悤�ȃu���[�L�͕t���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�t�ɍl����A�M�̕��o�ʂ�������Ă���A���������͕ς��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��H
�����ԍ��F25932561�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
���R�s�X�^�X�t�O����
���H�ʂ̖��C��u���[�L���\�ɑ��Ċ����͂��x�z�I�ɂȂ�قǁA�i���������́j�L�т�ł���H
�m���Ɋ����ł͂Ȃ������͂̐������ł��Ă���܂���ł����B
�Î~��Ԃ̗͂̂荇���ōl����Ί����͂̓[���ł��̂ŏȂ��Ă���܂������A�^���������Ő������Ă݂܂��傤�B
ma = F
�im�F���ʁAa�F�����x�AF�F�́j
�Ƃ����j���[�g���̉^���������́A�݂Ȃ����m���Ǝv���܂����A���̎��ɂ͑���������܂��āA
ma + dv + ��N = F
�id�F�S���W���Av�F���x�A�ʁF���C�W���AN�F�����R�́j
�ƂȂ�܂��B
�S���͍�������Ƃ��āA������ԗ��ɓ��Ă͂߂�ƁA���L�̎��������܂��B
m�Ea + ��t�Em�Eg = Ft
�im�F�ԏd�Aa�F�ԗ������x�A��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���Ag�F�d�͉����x�AFt�F�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɍ�p����́j
m�������͂̍��Ɩ��C�͂̍��̗����ɓ��{�ł������Ă��邱�Ƃ�������܂��ł��傤���H
�܂�Am�������Ă��A�H�ʂ̖��C�ɑ��Ċ����͂��x�z�I�ɂ͂Ȃ�܂���B
�������A��t���������Ȃ�Ɗ����͂��x�z�I�ɂȂ�Ƃ����̂͂��������ʂ�ł��B
�܂��A���������Ƃ̊W�͑O�X����
��(1/2)�Em�Ev0^2 = Ft�Ed �c(1)
�id�F���������j
����A
Ft = (1/2)�Em�Ev0^2 / d
��������̎��ɑ�����āA
m�Ea + ��t�Em�Eg = (1/2)�Em�Ev0^2 / d
��������āA
d = (1/2)�E(m�Ev0^2) / (m�Ea + ��t�Em�Eg )
�ƂȂ�܂��B
���q�ƕ���̗�����m�����邽�߁A��͂萧�������Ɏԏd�͊W���Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25932574�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
��(�]���薀�C�H���\���Ƃ��Đ������̂����f�s�\�ɂȂ��Ă��܂���)
��͂肱���ɃM���b�v������悤�ȋC�����܂��B
�]�����Ă���^�C���̖��C�͐Ö��C�ł��B
�����Ă���^�C���̖��C�͓����C�ł��B
�]���薀�C�H�Ƃ��ĕ\�����ꂽ�����ۂ͐Ö��C�i���u���j�ōl���Ė��Ȃ��͂��ł��B
�������͂����ŕ\�킻������ƁA�u���[�L�@�\�̖��C�͂��g���N�Ƃ��ĕϊ�(�t�ϊ�)�����āA
���]�����R(������͏d�ʂɊW����)�Ƃ̘a�ł��o���ł��傤���H
��҂̓]�����R�ɂ��Ă͏ȗ����Ă��܂��܂������A�O�҂̃g���N�i�����[�����g�j�ɂ��ẮA�G�����J����ւ̐����œW�J�������ł��̂ŁA�]�T�̂��鎞�ɂł����Q�Ƃ��������B
�����ԍ��F25932595�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��m�Ea + ��t�Em�Eg = Ft
���im�F�ԏd�Aa�F�ԗ������x�A��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���Ag�F�d�͉����x�AFt�F�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɍ�p����́j
��j a�F�ԗ������x
���j a�F�ԗ����������x
�ł����B
m/s�̌����x���g�����Ƃ��قڂȂ��̂ŁAm/s^2�̌��������x�̂��Ƃ������x���Č������Ⴂ�����Ȃ́A�������ł����ˁB
�����ԍ��F25932614�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���]�����Ă���^�C���̖��C�͐Ö��C�ł��B
�������Ă���^�C���̖��C�͓����C�ł��B
����͔F�����Ă���A�ے肵�܂���B
�^�C���̖��C�͐Ö��C�@+�@�ԗւ���~�@���@�Ԃ���~
�^�C���̖��C�͐Ö��C�@+�@�ԗւ���]�@���@�Ԃ������Ă�
��L�́u�ԗւ��Î~�v�Ɓu�ԗւ���]�v�̍����A�]�����R(�]���薀�C)�̍��B
�ƕ\������Γ`���ł��傤���B
���Ƀ^�C���ƒn�ʂ̖��C�͐Ö��C�ł��B
�ŁA�����Ă�Ԃ��~�߂�s�ׂ́A��]����^�C�����~�߂�s�ׂł��B
(�X���b�v�E��]������)
�����ԍ��F25932623�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���͍����͂܂Ƃ��ɍl�����Ԃł͂Ȃ�(�n�C�e���V����)�A
���j�ȍ~�Ɉ����Â肽���Ȃ��̂ŁA�����܂��B
������Ă��������B�������H�������H�����N�H�����F�肵�Ă܂��B
�����ԍ��F25932643�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
.>�G�l���M�[�ʂƐ��������́i���_�I�ɂ́j���W���Ƃ������Ƃ͑O�̃X���ŕ�����������ؖ��ς݂ł��B
����Ȃ��Ƃ͂���܂���
�ő喀�C�W�������҂ł���@�l�֓Ɨ�ABS�ғ��ł�
L�@�i�Ƃ��̋z���G�l���M�[��
L��MG�@�ł��B
�g���b�N���~�܂��Ȃ��ߐύڏ�Ԃł�
�ő喀�C�W�������҂ł��܂���̂�
F��M���@����
���������x���@���S�̎��ʂl�ɔ���Ⴕ�܂�
�����ԍ��F25932653
![]() 1�_
1�_
�^�]��P�l��������Ă鎞��60�L���̎����Ԃ�����60���[�g���Œ�~�����鐧���͂ŁA�^�]����܂�5�l��Ԃ��Ă鎩���Ԃ��~�����悤�Ƃ���Β�~�܂ł̋�����60���[�g������̂͊ԈႢ�����ł��傤�ˁB
�܂����ꂼ��̎����Ԃ�����60�L������j���[�g�����ɃV�t�g���đĐ����s�����5�l��Ԃ̎����Ԃ̕�����~�܂ł̋����������̂��ԈႢ�����ł��傤�B
�����ԍ��F25932675�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�u�t���u���[�L�v�̂Ƃ��̓���ł́A��Ԑl����d��̗ʂɂ�����炸�AABS���쓮���Ă���Ǝv���܂��B
��p�Ԃ�ABS�����Ă���A�u���[�L�\�͂��Ȃ���ABS���쓮�������Ȃ����Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B
��^�g���b�N�ʼnו���ςꍇ�́A�u���[�L�\�͂�����Ȃ��P�[�X������܂��B
���������P�[�X�ł́A�ԏd���d���قǐ����������L�т܂��ˁB
�����ԍ��F25932702
![]() 2�_
2�_
�l�b�g��AI�̉ŁA�������肭��ʔ������̂�����܂����B�u���[�L�̐����d���ʁA���������M�ʂ́A
���������������������M��(�����d����)
�Ƃ������́B
�����Ő����͂Ƃ͎ԌŗL�̂��̂ŁA����l�ȏ�łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ���������邻���ł�
�u���[�L���\�������ԂقǁA���̒l�͍����Ȃ�悤�ł��B
�ŁA���������͂̎Ԃŏd�ʂ��ς��A�Ԃ��~�߂邽�߂ɕK�v�Ȑ����M�ʂ͏d���ɔ�Ⴕ�ĕς��̂ŁA��̎��ŕ�����悤�ɁA���������������Ȃ���ΐ����M�ʂ͑��₹�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�䂦�ɁA�����u���[�L���\�̎Ԃł́A�d�ʂ�������A����������������悤�ȁB
�����ԍ��F25932731�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���֓d�ӂ���
�m���ɑO�i�͓��ӂł����A��i�͂��̃X���Q���ҒB�̗��_�Řf�킳�ꂽ�̂��A�l�ɂ͗ǂ��킩��܂ւ�B
�����ԍ��F25932745�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�l�H�I�Ȑ������u���g�킸�����͂̋�C��R�����̐����͂Ō�������A�d�ʂ��d�������Ԃ̕�����~�܂ł̋����͒����Ȃ�ƌ������B
���ꂾ���ł����������͂Ȃ�d���Ԃ̕������������������Ȃ�̂��킩��܂��B
���[�`���[�u�ł��ꂼ��قȂ����d���̎ԂȂ̂ɒ�~�܂ł̋����������Ȃ̂́A�قȂ����͂Ő������s�����ƌ������ł��傤�B
����͉^�]�肪�S�ԑS�͂Ńu���[�L�y�_���̂Ƃ͕ʖ�肾�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25932762
![]() 3�_
3�_
���i�C�g�G���W�F������
�������Ő����͂Ƃ͎ԌŗL�̂��̂ŁA����l�ȏ�łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ���������邻���ł�
�����[���b�ł����A���̍����͂ǂ��ł��傤���B
�����͂Ƃ́A�u�Ԃ�����������́v�Ƃ����Ӗ��ł�낵���ł��傤���B
�����ԍ��F25932773
![]() 1�_
1�_
�������Ƃ���
�l�b�g�Ő����͂Ƃ��Ō�������A����o�ė��邩�ƁB
�����ԍ��F25932793�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�`���ɖ߂�܂���
�y�_�����������߂u���[�L����������
�Ƃ����̂����ʑ̌��ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����ˁH
���i�C�g�G���W�F������
�����������������������M��(�����d����)
���̒ʂ�ł���H
�����͂������Ȃ琧���������L�т�̂Ɠ����悤�ɁA���������������ɂȂ�悤�ɐ����͂�傫����������A�Ƃ������Ƃ������Ă��邾���ł��B
�Ȃ������͂������ƍl������̂ł��傤���H
�y�_�����������߂������ނقǐ����͂͑傫���Ȃ�܂���H
�������Ԃ��ꂼ��Ɍ��E������܂����A7�l���̎Ԃ�7�l����Ă����E�ł͂���܂���B
�����ԍ��F25932818�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���l�b�g�Ő����͂Ƃ��Ō�������A����o�ė��邩�ƁB
�u�����͂Ƃ͎ԌŗL�̂��́v�Ɓu����l�ȏ�łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ����������v�͌�����܂���ˁB
�����N��\���Ă��������܂��B
�����ԍ��F25932824
![]() 1�_
1�_
�u�����͎͂Ԃɂ���ĈႤ�v�Ō������Ă݂���B
����ȏ�͎����Œ��ׂĂˁB
�����ԍ��F25932843�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���u�����͎͂Ԃɂ���ĈႤ�v�Ō������Ă݂���B
�u�����͂Ƃ͎ԌŗL�̂��́v�Ƃ����������ɁA�����͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤���B
�����ԍ��F25932851
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
�}�������������ꍇ�́A�Ԃ̐����͂��ő�ɂȂ�悤�ɎԂ̃u���[�L�V�X�e���������̂ŁA�ԏd���y�������d�������A���������͂̂悤�ȁB
���̕ӂ�̂��Ƃ��l�b�g�ɂ��낢��o�Ă���悤�ȁB
�����ԍ��F25932854�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
MAX�̐��\�g�p�Ő�������10m�B�J�b�N���u���[�L����
�d�ʂ�����t�@�W�[�u���[�L���O�Ő�������10m�B
�J�b�N���u���[�L�ł����Ȃ狗���͒Z���čςށB
�Ȃ�œ����Ǝv�����s�v�c����B
�����Ȃ킯�Ȃ��B
�����ԍ��F25932860�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
����ς܂����B
���䃍�W�b�N���D�G�B�ȏ�B
�����]�X��胍�W�b�N��͂��Ȃ��ƈӖ��Ȃ��b�肾�ȁB
�����ԍ��F25932872�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���}�������������ꍇ�́A�Ԃ̐����͂��ő�ɂȂ�悤�ɎԂ̃u���[�L�V�X�e���������̂ŁA�ԏd���y�������d�������A���������͂̂悤�ȁB
�u���[�L�V�X�e���͍ő吧���͂ƂȂ�悤�ɐ����͂�����
�Ƃ������Ƃ͂�������ɂȂ�܂����H
�ԏd���d���Ȃ�ƍő吧���͂��傫���Ȃ�
�Ƃ������Ƃ͂�������ɂȂ�܂����H
�ǂȂ���������������Ă����悤��
�����S�������������t����Ə����S��������ɂ����Ȃ�
�Ƃ������ƂƓ������ƂȂ̂ł����B
�����ԍ��F25932881�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�N�[�������C�������藧�Ƃ�������̌��ł���A�X����l�̎咣�̒ʂ�ł��B�����Ȃ�Ƃ��܂Ƃ��ɗ͊w�𗝉����Ă���l�ɂƂ��Ă͋^���]�n�͂���܂���B
����ŃN�[�������C���͒P�Ȃ�o�����ł���A���ۂɊϑ�����門�C���ۂ��G�c�ɋߎ������������ɉ߂��܂���B���ہA���C�͂͐����R�͂ɔ�Ⴗ��̂ł͂Ȃ��A�����R�͂���ɂȂ�ɂ�A���̔��萔�ł��門�C�W���͏������Ȃ�܂��BJAF���������J���Ă��邩�͒m��܂��A�ԏd���d������Ɛ����������L�т�Ƃ����������ʂ�����Ƃ�����A���̂��߂ł��B
�^�C���͑��������O���b�v�������A�O�ւ̃��[�����������߂�A���_�[�X�e�A�X���������Ȃ�A�������N�[�������C���ɑ���Ȃ����ۂł��B
�����ԍ��F25932933�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��Ԑl�������Ȃ��ĎԂ��y�����ł��A��Ԑl���������ĎԂ��d�����ł��A�h���C�o�[���댯���@�m���ċ}����(�p�j�b�N�u���[�L)���������Ƃ��A�Ԃ̃u���[�L�V�X�e���͐����͂��ő�(���̎Ԃ��������͂�100��)�ɂȂ�悤�Ɏ������䂷��͂��B
�t�ɏd�ʂ��������͋}�����Ńu���[�L�\�͂�100���o���āA�d�ʂ������̎��̋}�����ł̓u���[�L�\�͂�50�������������Ȃ��悤�ȃu���[�L�̎�������Ȃ�A���[�U�[�͓{��ł��傤�B
�ԏd���y�����ł��A�}�����̎��͎ԏd���d�����̂悤�ɁA�ɂ��܂������͂�100����������悤�Ȑ���ɂ��Ă�����āB
�����ԍ��F25933024�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���ԏd���y�����ł��A�}�����̎��͎ԏd���d�����̂悤�ɁA�ɂ��܂������͂�100����������悤�Ȑ���ɂ��Ă�����āB
����A����A�^�C�������b�N���邾���ňӖ��Ȃ��ǂ��납�A�t�ɐ������������܂�����B
�����ԍ��F25933085�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������Ⴂ���ĂȂ��H
�����͂��P�O�O�p�[�Z���g�ɂ����A���b�N�����Đ����͂��[���ɂ����Ȃ���B
�Ԃ̃u���[�L�V�X�e���̓��b�N���O�̈�ԃu���[�L��������ԂɂȂ�悤�������䂷�邩��ˁB
�댯���@�m���ċ}�����������h���C�o�[�͎Ԃ���~����܂ŗ͂����ς��u���[�L�ݑ����Ă�����������ŁA�ׂ�������͎Ԃ̃u���[�L�V�X�e�����œK�Ȏ������䂷��̂ŁB
�����ԍ��F25933109
![]() 2�_
2�_
���m�n����
���N�[�������C�������藧�Ƃ�������̌��ł����
�͂��B���̒ʂ�ŁA����̓N�[�������C�������藧�Ƃ�������̌��ɂ��b���Ă��܂��B
�����ہA���C�͂͐����R�͂ɔ�Ⴗ��̂ł͂Ȃ��A�����R�͂���ɂȂ�ɂ�A���̔��萔�ł��門�C�W���͏������Ȃ�܂��B
���ۂ͖��C�͂������R�͂ɔ�Ⴕ�Ȃ��Ƃ����b�́A�O�X���ŋ�ׂ̕������������������邱�Ƃ�����Ƃ����b�������ۂɏ����G��Ă���̂ł����A����̃X����Ɋւ��Ă̓N�[�������C�������Ő����ł���Ǝv���Ă��܂��B
��L�̐����ɂ����āA���͒ᕉ�ח̈�Ő����R�͂��������Ȃ�ɂꖀ�C�W�����������Ȃ�Ƃ����t�̘b�����܂������A�����ח̈�ł͂��������Ƃ��萂���R�͂��傫���Ȃ�ɂꖀ�C�W���͏������Ȃ�܂��ˁB
�����ԍ��F25933124�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
������x�����܂����A
�@ �u���[�L�V�X�e���͍ő吧���͂ƂȂ�悤�ɐ����͂�����
�A �ԏd���d���Ȃ�ƍő吧���͂��傫���Ȃ�
�@�͂��������������Ă���悤�ł����A
�@�ɕt�������ƁA
�@' �u���[�L�V�X�e���̓^�C�����b�N���O�̍ő吧���͂��Ȃ��悤�ɐ����͂�����
�@'������������ƁA
�@'' �u���[�L�V�X�e���̐����͂��ő吧���͂���ƃ^�C�����b�N����i�̂Œ����Ȃ��悤�ɒ�������j
�ɂȂ邱�Ƃ͂��������������܂����H
�ł́A�A�͂�������ɂȂ�܂����H
��������łȂ���A�������݂������̂ڂ��Ă��������B
�A�ɕt��������
�A' �ԏd���d���Ȃ�ƃ^�C�����b�N���O�̍ő吧���͂��傫���Ȃ�
�A'�Ƈ@'�����킹��ƁA
�B �ԏd���d���Ȃ�ƁA�^�C�����b�N���Ȃ��悤�ɒ�������u���[�L�V�X�e���̐����͂��傫���Ȃ�
�ƂȂ�܂��B
�B�̋t�́A
�B' �ԏd���y���Ȃ�ƁA�^�C�����b�N���Ȃ��悤�ɒ�������u���[�L�V�X�e���̐����͂��������Ă���
�ƂȂ�܂��B
�B'�Ƈ@''�����킹���
�C �ԏd���y���Ȃ��Ă��A�u���[�L�V�X�e���̐����͂��d�����Ɠ����ɂ��Ă��܂��ƁA�u���[�L�V�X�e���̐����͂��ő吧���͂��ă^�C�����b�N����
�ƂȂ�܂��B
�������Ⴂ���Ă�������Ⴂ�܂��H
�����ԍ��F25933160�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�ԏd�ɂ�銵���͂��傫���قǃ^�C����O�ɓ]�����͂��傫���Ȃ�̂ł�胍�b�N���ɂ����Ȃ�A���傫�Ȑ����͂��������܂�
�i���E�u���[�L���̐����͕͂ς��Ȃ��Ƃ������咣�ɑ��āj
�����ԍ��F25933243
![]() 2�_
2�_
���͂����ς��u���[�L�ݑ����Ă������������
�Ԍ��́u�����͂̑��a�v�@�܂œ��B������@�������瑝���Ȃ��̂��C���[�W�ł��Ȃ���ł���
�����ԍ��F25933248
![]() 1�_
1�_
�d�ʑ����Ńu���[�L���O�̒���������̂��l�Ԃł��A�ł��Ȃ��l�͕������ɂ��܂��傤�B
�ڂ����ς��u���[�L�|����͉̂^�]�x�����炢�ł��i�쓮�������Ƃ͂Ȃ��j
�����ԍ��F25933255
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�܂������������Ƃ͗����ł���B
�����V�X�e���łȂ�d�ʌy���ق��������������Z���Ȃ�̂���ʓI���ˁB�t���u���[�L�Ȃ��琧�������Z�������D�܂����B�d�ʂɌ��炸�����Ȃ̂͒����Ȃ��B
�t�ɁA�l������ő吧�������ɑ����Ă���Ƃ������W�b�N��������Ȃ��ˁB
�����������䃍�W�b�N�Ƃ����d�v�ȃt�@�N�^�[�����Ō��̂��������Șb�����ǁB�����o��킯�Ȃ��B
�����ԍ��F25933280�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�J��Ԃ��ɂȂ邯�ǁA�l�����������̂́A���݂̃u���[�L�V�X�e���������Ԃł́A��Ԑl�����������ł����Ȃ����ł��A�ً}���ɋ}�����������鎞�A�h���C�o�[�����ׂ��́A�f�����A�͈�t�u���[�L���A�Ԃ��~�܂�܂ŁA���������邱�Ƃł���܂��B
�h���C�o�[�ɏo����̂͂����܂łŁA���Ƃ͎Ԃ̃u���[�L�V�X�e�������^�C�����b�N�����Ȃ����ōő�̐����͂�����悤�Ɏ������䂷��Ƃ����ƁB
�����������Ŏԏd�ω��ɂ�鐧�������̒��Z���o���Ƃ���JAF�̃e�X�g��M���āA�l�͎x������Ƃ������ƁB
�����ԍ��F25933310�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���ǂȂ��ɂł�������悤�ɐ������鎎�݂ł��B
�����ł����B
�����ԍ��F25933386�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
��use_dakaetu_saherok����
>�]�����Ă���^�C���̖��C�͐Ö��C�ł��B
>�����Ă���^�C���̖��C�͓����C�ł��B
>�@' �u���[�L�V�X�e���̓^�C�����b�N���O�̍ő吧���͂��Ȃ��悤�ɐ����͂�����
�͐Ö��C�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��������C�Ȃ�ł���
�����ԍ��F25933412
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
�Ö��C�ł���
�����ԍ��F25933415�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>�Ö��C�ł���
�]�����Ă����ł����
�����ԍ��F25933427
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
�O�X���r���ŁA�]�����R�E�E�E�Ƃ������t�����āA����̃X����l�ł���use_dakaetu_saherok����Ƃ̂������A�ǂ��Ȃ�̂��ƁAROM���Ă���܂���
���X�Ȃ���A��ڂ̃X���ɓ���A�悤�₭�R�}���^���u�u�u�u�[����̌����Ă��邱�Ƃ��A�������Ă��������ł�
�����A�킽�������g�A�����Ă��邱�Ƃ�ǂݎ������A�����������Ƃ�`�����肷��̂́A����Ǝv���܂�
���ǁA�u���[�L���|����Ƃ́A�]�����R��傫�����āA����������E�E�E�Ƃ����A������O�̂��Ƃł���
�l�ނ́A�d�����̂��^��A�n��������悭�ړ����邽�߂ɁA�ۂ����̂�]�����Ηǂ����Ƃ����A�]�����R�����炷���߁A�ۑ�����ԗււƐi�������E�E�E
���x�́A���̓��������̂��A�ϋɓI�Ɏ~�߂Ȃ�������Ȃ��Ȃ����E�E�E
�]�����R�ƌ�����Ƃ��́A�u���[�L�p�b�h�ƃ��[�^�[�������C�A�^�C���ƘH�ʂ͐Ö��C�E�E�E�̊W�ŁE�E�E
�^�C���ƘH�ʂ̖��C�͂̂ق����傫�����
�^�C�������b�N������Ԃ́A�]�����R�ł͂Ȃ��A�p�b�h�ƃ��[�^�[�͐Ö��C�A�^�C���ƘH�ʂ������C�E�E�E�̊W�ŁE�E�E
�p�b�h�ƃ��[�^�[�̖��C�͂̂ق����傫����ԂŁE�E�E�����̏d�Ɠ����ɂȂ�E�E�E
�Ƃ����A������O�̘b�ł���
�u���[�L�́A�^�C���̓]����ɁA�u���[�L���|���鑕�u�E�E�E
�����ԍ��F25933430
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�������������Ŏԏd�ω��ɂ�鐧�������̒��Z���o���Ƃ���JAF�̃e�X�g��M���āA�l�͎x������Ƃ������ƁB
�u�����������Łv�ƌ����܂����AJAF�̃e�X�g�ł͈͗�t�u���[�L�������Ă͂��܂����ˁB
�����Ɠ�������Ă��܂����B
�ǂ�������������̂ŁA���t�̒�`�m�ɂ��Ă����܂��傤���B
�u�����́v
�@�@�����I�ɂ́A�u���[�L�����������ɎԂ�����������́A���R�u���[�L�̓��ݕ��ŕς��
�u�u���[�L�̐����́v
�@�@�ۈ���ł́A�e�u���[�L����������ő�̐����͂̈Ӗ��ŁA�ԂɌŗL�̓���
�@�@��ʎԗ��̕ۈ���ł́A�S�ւ̑��a�����d�ʂ�50���i4.90N/kg�j�ȏ�A��ԗւ̘a���㎲�d��10���i0.98N/kg�j�ȏ�
�u�u���[�L�\�́v
�@�@���̃X���ł́A�u�u���[�L�̐����́v�Ɠ����Ӗ�
�����́u�����́v�ƕۈ���́u�u���[�L�̐����́v�͍������₷���̂ŁA���m�Ȏg���������K�v�ł��B
�����ԍ��F25933445
![]() 2�_
2�_
��̕����̖@����
�^�C���������Ă��Ȃ����ɂȂ肽��
�^�C�����Œ�i���b�N�j����Ă��鎞�ɂȂ肽��
>�u���[�L�V�X�e���͍ő吧���͂ƂȂ�悤�ɐ����͂����鎞�����Ȃ肽��
�ǂ��Ȃ�ł��傤
�����ԍ��F25933448
![]() 2�_
2�_
���R�}���^���u�u�u�u�[����
����L�́u�ԗւ��Î~�v�Ɓu�ԗւ���]�v�̍����A�]�����R(�]���薀�C)�̍��B
�^�����Ă��镨�̂��������̂ɁA�Î~��Ԃ̂荇���Ő�������̂͂��������Ȃ��H�A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�m���ɂ����͔����Ă���܂����B
���傤�ǎԗւ̉^����������W�J���Ă��������������Ⴂ�܂����̂ň��p�������܂��B
���낪�鍄�̂Ɩ��C��(�ŏ�)
https://kopi.hatenadiary.jp/entry/2016/11/06/112317
���낪�鍄�̂Ɩ��C��(d)
https://kopi.hatenadiary.jp/entry/2016/11/07/203543
2�߂̃����N��
�Ԏ��ɍ�p����i�s�����̗�F�Ǝԗւƒn�ʂ̊Ԃɍ�p�����f
�����
�Ԏ����甼�a�̗��ꂽ�ʒu�ɍ�p�����F�ƒn�ʂ̊Ԃɍ�p�����f
�̊W�o����Ă��܂��̂ŁA
�O�҂��ԗ��Ɛ����́A��҂��u���[�L�͂Ɛ�����
�ōl�������̎��ۂɓ��Ă͂܂�Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25933480�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��gda_hisashi����
���]�����Ă����ł����
�͂��B�]�����Ă���Ƃ������Ƃ͊����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���^�C���������Ă��Ȃ����ɂȂ肽�� �c[1]
���^�C�����Œ�i���b�N�j����Ă��鎞�ɂȂ肽�� �c[2]
��>�u���[�L�V�X�e���͍ő吧���͂ƂȂ�悤�ɐ����͂����鎞�����Ȃ肽�� �c[3]
��̕����@���Ƃ����̂́A
d = (1/2)�Em�Ev0^2 / (��t�Em�Eg)
�ł�낵���ł����H
���̕����@�����̂͂�����ɂ����Ă͂܂�܂��B
[1]�c ��t�͐Ö��C�W��
[2]�c ��t�͓����C�W��
[3]�c ��t�͐Ö��C�W��
�ƂȂ邾���ł��B
[1]�̐����͂�[3]�̍ő吧���͂Ɠ����ł���A
R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES
�ł���A
d1 = (1/2)�Em�Ev0^2 / [(r / R)�E��b�EB�ES]
�ł�����A
d1 = d �ƂȂ�A���������͓����ɂȂ�܂��B
[1]�̐����͂�[3]�̍ő吧���͂��Ⴂ���Ƃ����Ӗ��ł�����A
R�E��t�E(mg) > r�E��b�EB�ES
�ƂȂ邽�߁A
d1 > d �ƂȂ�A���������͐L�т܂��B
�����ԍ��F25933508�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
��use_dakaetu_saherok����
�Ȃ�ق�
�ǂ�ł������ł�����b�N��Ԃ��덷�������Ȃ��i�Z���~�܂�ł͂Ȃ��~�܂鋗�����ׂ�̂Ɂj
��ԓ��ꊴ�����Ă�i�C���[�W���₷���j��Ԃł���
�����ł���
�ł͑O�X���̕X�̏�̃����K��
��Ԃ̃x�A�����O���̓]�����R��
�d�𑝂₵�Ă�
�~�܂鋗���͓������Ď��ł���
����Ƃ����C��R�����̓_���ʼn����u���[�L�i�����s��)���K�v�Ȃ̂ł��傤��
���Ɩ��C��R�͉d�ɑ��āi�����ł́j�����I�ɑ����܂������E�͂Ȃ��̂ł��傤��
�d�͂Q�{�ɂȂ邪���C�̕�ނ��Q�{�̖��C��R���ł��Ȃ��Ƃ�
�����ԍ��F25933520
![]() 3�_
3�_
����Ԃ̃x�A�����O���̓]�����R��
���d�𑝂₵�Ă�
�q�ɂȂǂŁ@��Ԃ������o���ĖړI�ۊǏꏊ�܂�
�����o���Ă�o�����炷���
�i�����܂ł��d���ł��@�V��ł���킯�ł͂Ȃ��j
�����������Ȃ�
��Ԃɑ�R����Ă鎞���@������Ƃ�������ĂȂ�����
�قڂقځ@���������܂Ŋ������܂�
�i��@�d���ق����@�����܂ł����j
�����ԍ��F25933547
![]() 3�_
3�_
��gda_hisashi����
������Ƃ����C��R�����̓_���ʼn����u���[�L�i�����s��)���K�v�Ȃ̂ł��傤��
�����B���������@���͓����ł��B
�u���[�L���Ȃ����Ԏ���^�C���̓]�����R�̂� �ł���A�����͂��㉺���܂���A���ʂ�������Β�~�����������܂��B
�����Ɩ��C��R�͉d�ɑ��āi�����ł́j�����I�ɑ����܂������E�͂Ȃ��̂ł��傤��
���d�͂Q�{�ɂȂ邪���C�̕�ނ��Q�{�̖��C��R���ł��Ȃ��Ƃ�
�͂��B���ۂɂ͖��C�W�������ł͂���܂���B
�^�C���Ɋւ��Č����A�����ח̈�ł͉d��������Ɩ��C�W�����������Ȃ�A�d��2�{�ƂȂ��Ă��ő吧���͂�2�{�ƂȂ�Ȃ����Ƃ�����܂��B
�������Ȃ���A��ׂ����ς͈̔͂ł���A�قڈ��ƍl�����邭�炢�̍��ł���Ǝv���܂��B
�����ԍ��F25933560�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��gda_hisashi����
�����Ɩ��C��R�͉d�ɑ��āi�����ł́j�����I�ɑ����܂������E�͂Ȃ��̂ł��傤��
���d�͂Q�{�ɂȂ邪���C�̕�ނ��Q�{�̖��C��R���ł��Ȃ��Ƃ�
�����̃^�C���ł͌��E������悤�ł��ˁB
http://www.carphys.net/tire/tirewidth.html
�]�T�̂���^�C�����g���Ă��Ȃ��Ɗ댯�ł��傤�B
�����ԍ��F25933572
![]() 1�_
1�_
���Ђ�N�Ђ�N����
>�����������Ȃ�
>��Ԃɑ�R����Ă鎞���@������Ƃ�������ĂȂ�����
>�قڂقځ@���������܂Ŋ������܂�
���肪�Ƃ��������܂�
��use_dakaetu_saherok����
>�u���[�L���Ȃ����Ԏ���^�C���̓]�����R�̂� �ł���A�����͂��㉺���܂���A���ʂ�������Β�~�����������܂��B
�����ł���
�덷�Ȃ̂������̖@���ȊO�̉��������ނ̂�
�����ԍ��F25933584
![]() 2�_
2�_
��use_dakaetu_saherok����
>�͂��B���ۂɂ͖��C�W�������ł͂���܂���B
�^�C���Ɋւ��Č����A�����ח̈�ł͉d��������Ɩ��C�W�����������Ȃ�A�d��2�{�ƂȂ��Ă��ő吧���͂�2�{�ƂȂ�Ȃ����Ƃ�����܂��B
�Ⴆ��
���ۂ̃^�C���͎g�p����ɔ����肪���肶��Ȃ��ł���
�葬���s��ʏ�̎ア�u���[�L�ł͖����ł���͈͂�������܂���
���Z��}�u���[�L�ł̓��b�N�łȂ��Ă�������������킯�ł���
���̊��鎞���ă^�C���\�ʂł̓S�������ʂ͍�ꂽ�肵�ă��[�X�p�^�C���Ƃ����Ɨn�����肷����
�������͂��̍�ꂽ��n�����肷�鎖�i�\�ʕω��j�Ŗ��C��R������Ƃ������ł�����
�����̌�����ے肷�����͂Ȃ��ł���
���������i��~�����j�͐L�т�Ƃ̎v���͔����o�Ƃ��Ă���̂�
�����Ƃ���̃^�C�����i�ڒn�ʐρj�̌����܂�
�@���ƕʂ̉����������Ă���Ǝv����ł���
�i���ۂ͐L�т�j
�����ԍ��F25933592
![]() 2�_
2�_
�ԑ̂̃u���[�L�V�X�e�����i�����Ă��āA�\���Ȑ��\�ƁA�D�G�Ȑ��䂪����Ă�Ȃ�E�E�E���Ƃ̓^�C����
�^�C�����āA��ʎԂł��A�T�}�[�^�C���A�X�^�b�h���X�A�X�^�b�h�A�}�b�h���X�m�[�A�f�U�[�g�Ƃ��F�X�����āA���ꂼ��A�����ɓ���s���肪����
�����[�Ȃ��A�^�[�}�b�N�A�_�[�g/�O���x���A�X�m�[/�A�C�X�o�[���Ǝg���^�C���͑S�R�Ⴄ���A�P�ɕ��L�������Ƃ����킯�ł͂Ȃ�
��ʎԂ̃X�����[���i�E�E�E�ŋ߂̓W���J�[�i���j�ł��A�m�[�}���A�Z�~�X���b�N�A�X���b�N�ƃ^�C�����Ⴄ
�g���b�h�̍a�ł��A�R���p�E���h�ł��ς��
�̂�F-1��Q�^�C���́A�K���^�C���Ƃ������邭�炢�A�l�`���l�`���������炵���A���C�Ƃ������A�S���E�E�E
�S���̐��E���ƁA�ڒn�ʐς��W���Ă���
���̃T�[�L�b�g�ł��A�����^�C���ŁA��C����ς��邾���ŁA�^�C����������肷��
��ʓ��ł́A��C�������ƃu���[�L�����Ȃ������ƌ����Ă���
�܂��A�X�g���[�g�G���h�Ńu���[�L���b�N�����Ԃ́A�꒼���ŃR�[�X�A�E�g����V�[���́A�悭����
F-1�ł́A�X�^�[�g�ŏ����ł��z�C�[���X�s������悤�Ȃ�A�o�x��āA�����ڐÂ��Ȃ��̂����A�A�����J�̃h���b�O���[�X�́A����Ȃ\���Ȃ��ŁA�^�C�����c�ɕό`���邭�炢�āA���������đ����Ă���
�����͒m��Ȃ��Ă��A���ۂ̈Ⴂ��A�����ڂ̈Ⴂ�͕�����
����Ȓ��ŁA�^�����\�Ƃ��ẮA�y���ق��������Ƃ����Œ�ϔO���A���t�����Ă���
�ł��A�y���͎m���A�d���͎m�������o����̂́A���t�������A����̑̏d�������p���āA�����̖��C�͂��オ�邩�炩�E�E�E
�E�E�E�x���ŗ�ȒE�����炵�܂���
�����ԍ��F25933670
![]() 2�_
2�_
���˂��݂���B����
����͓��d�ʂł̃u���[�L���\��������^�C���̖��C�i�O���b�v�j�̘͂b�ł����
�����ł̘b��̓^�C���ɂ�����d�ʂ������Ă�
�u���[�L���\���d���ɏ\���ɑ���Ă����
�d���Ń^�C���̃O���b�v�����������������ς��Ȃ����Ęb�ł�
�����ԍ��F25933677
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
�����A�����Ă܂������E�E�E
�ԗ��^�����\�ƃh���C�o�[�̋Z�ʂŋ����A���[�^�[�X�|�[�c�ł́A�y���ق�����ΗL���@�i�Ƃ����C���[�W�j
�����A�����A�R�[�i�[�����O�A�^�C�����C�t�A�R��ȂǂȂ�
�ł��E�E�E
��͂Ń_�E���t�H�[�X�t���āA��������d�����āA�ڒn�������߂āA�R�[�i�����O���x���グ�Ă���
��ʎԂ́A�ԑ̌`�ʌ^�Ȃ̂ŁA��s�@�̗��Ɠ����ŁA�t�Ƀ��t�g�͂������A�����ł̕s���萫�ƂƂ��ɁA�����͂̒ቺ���E�E�E
�����ԍ��F25933739
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����
���[�X�ő����ł͂Ȃ�
>�d���Ń^�C���̃O���b�v�����������������ς��Ȃ����Ęb�ł�
���ăX���ł�
��͂����܂���҂ł��Ȃ����Z�ł��y�������Z�������o����C���[�W�͖l������܂�
�ł������̖@���ł͏d���Ă���Ɍ������X�g�b�s���O�p���[���u���[�L�ɗL��Β�~�����͓���
���Đ��̃X���ł�
�����ԍ��F25933750
![]() 1�_
1�_
��ŃC���[�W�E�E�E�ƕt�������܂������A
���ہA�X�[�p�[GT�ł��A���E�}���ł��A�i���n�ł��j�A�E�G�C�g�n���f�����݂��邵�A�卷�͂Ȃ��Ă��A���s���邭�炢�̏����͂���ł��傤
���[�X�ϐ�⎋���ł��A�E�G�C�g�̏d���𗘗p���ău���[�L���O�����ŏ������E�E�E�Ȃ�ăV�[���͎v���o���܂��E�E�E
�i�O�㍶�E�̃o�����X��Ƀn���f�E�G�C�g�g���āA�n���h�����O���P�Ȃǂ̘b�́A���܂ɂ���j
���Ƃ��Ƃ̎ԏd��A�n���f�A�R���Ƃ��ŏd���������ŁA�u���[�L���O�����ɕ������E�E�E�Ƃ����b�Ȃ�A��������
�u���[�L���O�����ŁA���|�I�ȍ����o����A���ꂱ�������@���ɉ���Ȃ��ł��傤���A���E�߂��ł́A�������锼�Ԑg���x�̍��́A���C�̕����@���ȊO�̏��ŁA�o�Ă���̂ł��傤
��̏�ł�������Ə����܂������A�^�C���͖��C�����łȂ��A�M��S���A�ό`�̘b�����肵�܂�����A����ŁA�ق�̐����[�g���ŁA�������������Ȃ�A�܂������A�ق�̐����[�g�����������邱�ƂɂȂ邩������܂���
�����ԍ��F25933781
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����
�l�̎v���������ł���
>���ہA�X�[�p�[GT�ł��A���E�}���ł��A�i���n�ł��j�A�E�G�C�g�n���f�����݂��邵�A�卷�͂Ȃ��Ă��A���s���邭�炢�̏����͂���ł��傤
����͉����Ƃ��R�[�i�[�����O�Ƃ������̗v�f���܂܂�Ă��邶��Ȃ�
�����̃u���[�L���O�����ɑ��Ă̒�~�����̂������̖@���ŏd�����d���Ȃ��
���C��R�������邩�瓯���Ȃ���
���o�ł͂Ȃ������w��
�����ԍ��F25933792
![]() 2�_
2�_
���̋}�����ƃ��[�X�Ƃł͘b�͕ς���Ă��܂���B
���x���o�ꂵ�Ă���悤�ɁA�ԏd��������ƕ��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��M�G�l���M�[�͑����܂��B
���̋}�����ł���Ώ\���ȃu���[�L�ł����Ă��A���[�X�̂悤�ɉ��x���}�������J��Ԃ��A�M�̕��o���ǂ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
���̂��߂ɂ����Ƒ傫���u���[�L������Ƃ܂��ԏd���オ���Ă��܂��܂��B
�܂��A���[�X�ԗ��ɂ�ABS�͂��Ă��܂��A�J�e�S���[�ɂ���Ă͔{�͑��u������Ă��܂���B
�}�����̓x�ɁA��p�Ԃ̉��{���̗͂Ńy�_���݁A�^�C�������b�N���邩���Ȃ����̂Ƃ���ł��̓��݉��������Ȃ�������Ȃ��킯�ł��B
�ԏd���y������̕����ޗ͂����Ȃ��Ă��݂܂����A��͂�y���͐��`�ł��B
�����ԍ��F25933814�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��use_dakaetu_saherok����
��gda_hisashi����
���[�X���āA�X�s�[�h���Ȃǂ̃C���[�W����s���܂����A�{���́A�����Nj��̃P�`�P�`�Q�[���������肵�܂�
�����A���[�X�J�[�ɍ����\ABS���t���ĂĂ��A�d�ʍ�������A�^�C�����C�t�Ɍ����Ă��āA���Ղ����^�C���́A���ǃO���b�v�������Ă�̂ŁA���������͐L�т�ł��傤
�܂��A���̌�̃R�[�i�[�̂��߂ɁA�]���Ɍ������K�v�ŁA�K�v�Ȑ����������̂��A�����ł���
��ʎԂł��A�}�u���[�L�ɉ�삪�����Ȃ�A�d���ق�����Εs���ł����
�����ԍ��F25933987�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�������Ƃ���
���u�����́v
�@�@�����I�ɂ́A�u���[�L�����������ɎԂ�����������́A���R�u���[�L�̓��ݕ��ŕς��
���u�u���[�L�̐����́v
�@�@�ۈ���ł́A�e�u���[�L����������ő�̐����͂̈Ӗ��ŁA�ԂɌŗL�̓���
�@�@��ʎԗ��̕ۈ���ł́A�S�ւ̑��a�����d�ʂ�50���i4.90N/kg�j�ȏ�A��ԗւ̘a���㎲�d��10���i0.98N/kg�j�ȏ�
���u�u���[�L�\�́v
�@�@���̃X���ł́A�u�u���[�L�̐����́v�Ɠ����Ӗ�
�����ł��傤�ˁB
�ōŏ��ɖl�����������ɖ߂邯�ǁA
������×���������������M�ʁ@(���P)�@�Ȃ̂ŁA
���������������M�ʁ^������(���Q)�@�@�ɂȂ��ˁB
�����ԂŁA�������x�ő����Ă�ԂȂ炻�̉^���G�l���M�[�͏d�ʂɔ�Ⴗ���ˁA�ł��̎Ԃ��~�߂�ɂ́A���̉^���G�l���M�[���[���ɂ���K�v������̂ŁA���̉^���G�l���M�[�Ə�̎��̔M�G�l���M�[�͓��ʂɂȂ�܂��B
�ŁA���������悤�ɐ����͓͂��ݕ��ŕς��܂����A�i�`�e�̃e�X�g�ł͓��͌v��t���ē����͂Ńu���[�L��ł���̂ŁA�����͓͂����ł��B
�ŁA�d�����̎Ԃ̐����M�ʂ��`�A�y�����̐����M�ʂ��a�A�����͂��b�Ƃ��āA���Q�ɂ��Ă͂߂Ă݂�ƁA
�d�����̐����������`�^�b
�y�����̐����������a�^�b
�ƂȂ�@�`���a�@�Ȃ̂Ł@�d�����̐��������̕����傫���Ȃ�܂��B
������i�`�e�̃e�X�g�͏ؖ����Ă���̂��ƁB
�ŋً}���ɋ}�u���[�L�ގ��́A�̂̂`�a�r�Ȃ��̎Ԃł͎v�������苭�����ނ����ł́A�^�C�����b�N���ău���[�L�͌����Ȃ��Ȃ���肩�R���g���[���������A�ɂ���Ă̓X�s���Ȃǂ��N���邱�Ƃ�����̂ŁA���b�N�����Ȃ����߃|���s���O�u���[�L�Ȃǂ̃e�N�j�b�N���K�v���������ǁA�ً}���̋}�u���[�L�őf�l�ɂ͂���ȃe�N�j�b�N�͓���āA���������o������̂ł͂Ȃ��������ǂˁB
�ł��Z�p�̐i���̉��b�ŁA����̂`�a�r�����̎Ԃł́A�Ԃ̃u���[�L�V�X�e�������l�̃|���s���O���A�����ƍ��x���k���Ȑ���������ł���Ă����̂ŁA�ً}���̋}�u���[�L���S�O�Ȃ��A�f�����A�͂����ς����ނ̂��A��ԋ��������͂������āA�����������ŒZ�ɂȂ�킯�ł��B
�ŁA���̎��͂��̎Ԃ̃u���[�L�\�͂̍ő�����܂��B
�ł�����A�ً}���̋}�u���[�L�̎��ł��A���̎Ԃ̃u���[�L�\�͂̂����ς������ς����A���̎��̐����͂ɂȂ�̂ŁA����ς蓯���Ԃł̔�r�Ȃ�A�d�������̕����y������萧�������͐L�т�͂��ł��B
�����ԍ��F25934273
![]() 1�_
1�_
�r�ł�����A�ً}���̋}�u���[�L�̎��ł��A���̎Ԃ̃u���[�L�\�͂̂����ς������ς����A���̎��̐����͂ɂȂ�̂ŁA����ς蓯���Ԃł̔�r�Ȃ�A�d�������̕����y������萧�������͐L�т�͂��ł��B
���ꂪ�����w��͕ς��Ȃ��炵���ł���
�����ԍ��F25934293
![]() 1�_
1�_
������
�{�g���l�b�N��
�^�C���̐ڒn�\�́@�Ȃ̂��@
�u���[�L�V�X�e���̗e�ʁ@�Ȃ̂�
�錾���Ă��玮�W�J���悤�ˁ@
�����ԍ��F25934306
![]() 2�_
2�_
>�{�g���l�b�N��
���[�X�ő������邨�肶��Ȃ�
�P�ɋ}�u���[�L�|������
�^�C���̃O���b�v�͂͏d���Ȃ�Ɩ��C��R�������邩��
�u���[�L���\�]�X����Ȃ��������|�������
�^�C���̖��C�ɂ���~�����͓����ɂȂ����ĕ����̖@��
�ɑ���
�l�͎��ۂ̓��H�Ŗ{���ɐL�тȂ��̂��Ďv����
���̎Ԃ͂����ꔭ�̎������蓥�߂u���[�L�̓��b�N������i�`�a�r����������j
���炻�����O�̓u���[�L�̐��\����Ȃ��h���C�o�[�̎g�����i���ݕ��j
�������C�R�[�������ɂ��ďd���Ă����������Ŏ~�܂���ĕ���
�l�͉��т�Ǝv����(�v�������j
�����ԍ��F25934340
![]() 1�_
1�_
��gda_hisashi����
�l�b�g���́A�ɂ킩�����w�ł͉𖾂͖������Ă��Ƃ��ƁB
�����ԍ��F25934341�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���ً}���̋}�u���[�L�̎��ł��A���̎Ԃ̃u���[�L�\�͂̂����ς������ς����A���̎��̐����͂ɂȂ�̂ŁA
����Ɍ��t�̒�`��ς��Ȃ��悤�ɁB
�u�u���[�L�\�́v=�u�u���[�L�̐����́v�́A�ۈ���ł͎ԗ����d�ʁi�����ԁj�ő��肵���Ƃ��̍ő吧���͂ł��B
�ԏd���ς������g���܂���B
�܂��AJAF�̓���͌����悤������A�i���͂��Ă��܂����ǂˁB
�����ԍ��F25934347
![]() 2�_
2�_
����ł����AABS�͎Ԃ��y�����������쓮���₷������A�u�y�����瑁���~�܂�v�Ƌt�̌��ʂ����蓾��̂ł́H�ƃu������ł݂�B
�����ԍ��F25934356�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���ً}���̋}�u���[�L�̎��ł��A���̎Ԃ̃u���[�L�\�͂̂����ς������ς����A���̎��̐����͂ɂȂ�̂ŁA
�u���[�L�����̃��J�Ō��邩������~������s�בS�̂Ō��邩������
��ɂ������������b�N�������Ȃ����J�I�u���[�L���\�͂܂������i���Ȃ��j�Ǝv������
�~�߂�͂̓^�C���̃O���b�N�͂���
�����ԍ��F25934361
![]() 1�_
1�_
�R�s�X�^�X�t�O����́�ABS�͎Ԃ��y�����������쓮���₷��
�Ђ�N�Ђ�N����́��錾���Ă���E�E�E�Ƃ����b�ŁA�������ł́A�u���[�L�e�ʁ��^�C���\�́@�Ƃ��āE�E�E
��L�A�R�s�X�^�X�t�O����́A�^�C�����E�܂ł́A�@�B�I��ABS�쓮�J�n�܂ł̎��ԁE�E�E�̑O�i�K�Ƃ��āE�E�E
�l�̓��ݍ��ݑ��x�ⓥ�ݍ��ݗ͂ɂ��AABS�ɓ͂����܂ł̎��ԁE�E�E�����Z�����
ABS�ɓ͂����܂ł̎��Ԃ��A�d���Ȃ�A���̕���������A�����������L�т�
����90�L���́A�b��25���[���ł��̂ŁA�R���}���b���Ⴆ�A�����[�g���͕ς��
���̐����[�g�����A�R���ǂ���s�Ԃ��V�l�q���Ȃǂ̑��݂ŁA�^�����ς��
���������l�́A���i�̃u���[�L������f���P�[�g�ɍs���Ă���̂ŁA�p�j�b�N�u���[�L�Ɋ���Ă��Ȃ��AABS�ɓ͂����܂Ŏ��Ԃ́A�u���[�L�A�V�X�g�������Ă��A�ӊO�Ƃ�����Ǝv����
�ύڂ������ɂ��AABS�ɓ͂������߂́A���Ɖ��������̃u���[�L���͂̍����A�^������
�����̓V���v���ɍl�����{
�V���v���ȏ����ł́A�ς��Ȃ��Ă��E�E�E
���ۂ̘H��́A�l���Ԃ��H�ʁA�C�ۂ��A���G�ȏ����@�Ȃ̂ŁA�d�ʑ��́A�V���v���ɒ��ӂ������
����Ƀv���X���āA�d�S�����オ��Ƃ��A�n���h������ɂ��댯����������̂ŁA�����ƒ��ӂ��K�v�ƂȂ�
�����ԍ��F25934399
![]() 1�_
1�_
�u���[�L�e�ʁ��^�C���\��
�Ł@�L���Ȏl�֓Ɨ�ABS���ғ����Ă���Ȃ�
�ʁ��Î~���C�W���ƌ��Ȃ��ā@
�Î~����L�@�����߂�Ƃ��̎���M�������܂��B
�i�n���h����ƃT�C�h�t�H�[�X�Ƃ̎O�p�藝�ɂȂ�܂��j
�����ԍ��F25934424
![]() 2�_
2�_
�������Ƃ���
>��ł͎ԗ����d�ʁi�����ԁj�ő��肵���Ƃ��̍ő吧���͂ł��B
������O�ł��傤�B
�d�������u���[�L�ɂƂ��ĉߍ������A�~�܂�ɂ����Ȃ邩��ł���B
�ő�d�ʂŊ���߂�̂́A���S�̂��ߓ��R�̂��ƁB
����ōő�ߏd�����Ȃ�A���̊�Ŗ��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����ˁB
�Ōy�����ł��d�����ł��}�����ł́A�u���[�L�͍ő�\�͂œ����悤���䂳���̂����R�̂��Ƃł��傤�B
�����܂ł́A�����펯�I�Șb���Ȃ̂ŁB
�����ԍ��F25934481�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��ABS�ɓ͂����܂ł̎��Ԃ��A�d���Ȃ�A���̕���������A�����������L�т�
�Ȃ�ŁH
�@ABS�ɓ͂����܂ł̎��Ԃ��A�d���Ȃ�A���̕���������A
�����Ԃ������قǐÖ��C�͂Ő����������Ă���Ƃ������Ƃł́H
�A�����������L�т�
���t�ł́H
�����ԍ��F25934495�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���Ђ�N�Ђ�N����
�������Ŏ���M�������āA�D�����ł́A����͈͓��̎����Ŏ����ꂽ�͔̂F���ς݂ł����E�E�E
���Ƃ��A�g��H�Ȃǂł́A�^�C���̉d�ϓ����炭��A�d�ɑ��門�C�͂̔���`�����e�����A���C�͂���������Ƃ��E�E�E
�T�X�y���V�����X�g���[�N���A�o�l��d�ʑ����ɂ���Č������A�H�ʒǏ]������������Ƃ��E�E�E
���n���h����ƃT�C�h�t�H�[�X�Ƃ̎O�p�藝�E�E�E���A���C�~�͑ȉ~�`�Ƃ��E�E�E
����ς�A���ۂ͕̏��G�ɂȂ�A����M�̑����́A�����ɂ��s���ɓ������Ƃ������ƍl���Ă����ق����A����ł��傤��
�����ԍ��F25934502
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�l���AABS�����Ƃ���܂ŁA�Ō�܂œ��ݍ��ނ܂łɁA���Ԃ�������̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ƃ������Ƃł�
��ɂ������܂������A����90km�́A�b��25m�ł�
���Ԃ�������A���̕��A�i��ł��܂��܂��@���@�����������A�L�т܂�
�����ԍ��F25934506
![]() 1�_
1�_
�ꕔ�̕��́A�u���[�L�͂ɂ͌��E������̂ŏd�ʑ����Œ�~�����͐L�т�Ƃ̈ӌ����Ǝv���܂��B
�������u���ɑS�d�ʂ��~�߂�قǂ̃u���[�L�͂������ł��傤���A����ł���ɕ�����̂̓^�C���ł��B
���a�̎��ォ��u���[�L�͎v�������蓥�߂��b�N����̂ŁA
���������ő����v���X�����̏d�ʒ��x�̓J�o�[�ł��鐫�\�ō\������Ă��܂��B
�u���[�L�͎͂ԏd��50%�Ƃ�������܂����A����͔�����]����������[���[�̏�ł̎����ŁA
���[���[�������Ȃ̂�����܂����X���b�v���Ă���ȏ㐔�l���オ��Ȃ��̂����ʂł��B
���̎�����Ƀ^�C���������Ă��ł��B
�܂������ł���Ă݂���ł͖����ł����A�����炭���̃e�X�g�ł�1����Ԏ������l����Ԏ��ł��A
�ǂ�����^�C������Ɍ��E���}����ABS������A�Ԏ�Ȃ�̃L�b�N�o�b�N���������Ă�����Ǝv���܂��B
�ŋ߂̎Ԃ́u�u���[�L�A�V�X�g�v�ƌ������S���u���t���Ă��܂��B
����͈��ȏ�̋}�u���[�L�ƎԂ����f����@�B���u���[�L���������Ă���܂��B
���̃e�X�g�̏ꍇ���u�p���I�v�Ɠ��߂@�B���A�V�X�g�A�����u���[�L�͂��������܂��B
�^�C���͏d�ʑ������A���̌��E�l�����܂�̂͋��ʔF�����Ǝv���܂��̂ŁA
�u���[�L�\�͂ɗ]�T������Ȃ�Ί�{�I�ɒ�~�����́A���肱�����Ȃ������L�тȂ����������ƁB
�����ԍ��F25934511
![]() 2�_
2�_
���˂��݂���B����
>�l���AABS�����Ƃ���܂ŁA�Ō�܂œ��ݍ��ނ܂łɁA���Ԃ�������̂ł͂Ȃ����E�E�E�Ƃ������Ƃł�
������������܂���B
�����Ԃ�������A���̕��A�i��ł��܂��܂�
ABS����������͐����͂͗����܂���ˁH�������Ȃ��M���M�����ł��H�ʂƂ̖��C�͂���͂��ł����H�Ȃ�Ήd���傫�������A���̏�Ԃ��ۂĂ�͂��ł����H
�����ԍ��F25934535�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�ԗ����d�ʂƒ�~�����̊W�ɂ��āA���^���p�o�����g���ו��d�ʂƐύڈʒu��ς��čs�����������ʂ�����܂��B
�y�o�T�z
https://www.researchgate.net/publication/339539314_The_influence_of_the_cargo_weight_and_its_position_on_the_braking_characteristics_of_light_commercial_vehicles
�@
�����̊T�v�́A
1.�h���C�o�[�݂̂̏ꍇ (�ԗ����d�� 2,480kg) �����
2.�ו��̏d�ʂ��ȉ��̂Ƃ���ς�
�E250kg (�� 2,730kg)
�E500kg (�� 2,980kg)
�E750kg (�� 3,230kg)
�E1,000kg (�� 3,480kg)
3.�ו��̐ύڈʒu���ȉ��̂Ƃ���ς����ꍇ��
�E���O�� (���őO������ו��̏d�S�܂ł̋��� 455mm)
�E������ (�� 1,600mm)
�E����� (�� 2,690mm)
4.����75km/h����̃t���u���[�L���O�ɂ�����ȉ��̐��l�����ꂼ�ꑪ�襎Z�o�B
�EMFDD (���ϊ��S�쓮�����x) ��
�E��~����
�E�O�Ԏ��d (�Î~��)
�E�O�Ԏ��d (�u���[�L���O��)
�E������
�@
�����������ɂ����āA�����J�n������ԗ�����~����܂ł̐�������������ԥ�u�����x��ړ�������o�ߎ��ԥ��Ԍ����x�Ȃǂ��v���������ʂ���Z�o�����l�ŁA�ԗ��̈��S���\�]����ABS�]���ȂǂɎg�p�����
�@
�{�X���̖{��ł����~�����ɂ��Ă͈ȉ��̌��ʂƂȂ��Ă܂��B(�ڍׂ͏�Ɏ����������N��ɂ���PDF���Q�Ƃ��ĉ�����)
1.�h���C�o�[�݂̂̏ꍇ�̒�~���� 29.28m�ɑ��A
2.�ύڈʒu�����O���̏ꍇ �� ������̃P�[�X�Ƃ���~�����͐L�т�
�E250kg�F30.32m (+0.74m)
�E500kg�F30.80m (+1.52m)
�E750kg�F31.05m (+1.77m)
�E1,000kg�FN/A
3.�ύڈʒu���������ɂ����ꍇ �� ��ׂɔ�ג�~�����͐L�т邪���O���ɔ�גZ�k
�E250kg�F29.64m (+0.36m)
�E500kg�F30.52m (+1.24m)
�E750kg�F30.51m (+1.23m)
�E1,000kg�F30.05m (+0.77m)
4.�ύڈʒu��������ɂ����ꍇ �� ��~�����͋�ׂƂقړ�����
�E250kg�F30.12m (+0.84m)
�E500kg�F30.00m (+0.72m)
�E750kg�F29.75m (+0.47m)
�E1,000kg�F29.33m (+0.05m)
�@
���^���p�o�����g���������̂��߁A
�E�T�X�`����Z�b�e�B���O��u���[�L���\�Ȃǂ͏�p�ԂƂ͈قȂ邱��
�E�ԗ����d��2.5�g���̃N���}�ɂ����1�g���܂ł̉d���|���������ł��邱�Ɠ�
�����p�Ԃł����l�̌��ʂ������邩�ǂ����킩��܂��A�����̖@�����K�p�ł���̂����ǂ�����m���ł͏\�����ƁB
�@
�Ȃ�JAF�̎����ɂ��Ă͊��������H�ʂł̌��ʂ������藝�����₷���̂ł����A�����炭�`���̓���̂悤�ɒ�~�����ɂ͂قƂ�Ǎ��͂Ȃ��A�Ƃ������ʂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B
�@
�܂薀�C�W���������قǏd�ʍ��ɂ���~�����̍��͏������A�Ⴆ�ΕX�̏�̂悤�Ȓ��������C�W�����Ⴂ�H�ʂł͂��̍��͍ő�ɂȂ�͂��ł��B
�����ԍ��F25934536
![]() 4�_
4�_
���R�s�X�^�X�t�O����
���Ԃ�AABS�ɂ��āA�킽�����ƃR�s�X�^�X�t�O����ƂŁA�F�����Ⴄ�Ǝv���܂�
�O�X���`���̓���A����͂��ׂ�ABS�������Ă��Ԃ��Ƃ������Ƃł�
���Ȃ킿�A���ǂ���ABS�́A���b�N�����Ȃ��M���M���𐧌�ł���Ƃ̔F���ł�
��ABS����������͐����͂͗����܂���ˁH
���ꂪ�A�������ɁA�ő吧���͂ɋ߂���Ԃ��ێ��ł���Ƃ����F���ł�
��������������܂���
�܂��A�^�C���d�ɂ���āAABS�������|�C���g���Ⴂ�A�d����A���̕��u���[�L�ݍ��܂Ȃ�������܂���
�R�s�X�^�X�t�O�����g�ŁA���͂�ς��ău���[�L���܂��ƕ�����Ǝv���܂�
�X�g���[�N���ς��A�����͂ł́A���ݏI���܂Ŏ��Ԃ������邱�Ƃł��傤
�������́A���v�̃X�g�b�v�E�H�b�`�@�\�ŁA�J�`�J�`�ƁA�����Z���Ԃ��o���Ƃ��A�ア�͂ƁA�����͂Ŕ�ׂ�A�����͂̕������Ԃ�������͂��ł�
�l�̋ؓ��́A�����͂��o�����߂ɂ́A������x���Ԃ�������܂�
���łɌ����ƁA�ق�Ƃ͐���������ق��������A�f�����������܂�
�Ȃ̂ŁA�������Ă���A�G�Ȃ������ƁA���[�̂��I�Ńh�J���ƃu���[�L���߂�̂ł����A���������͂����܂���
�J��Ԃ��܂����A�R���}���b�����d�v�ł�
�����ԍ��F25934564
![]() 2�_
2�_
��������@�Ȃ��₳��
���܂薀�C�W���������قǏd�ʍ��ɂ���~�����̍��͏������A�Ⴆ�ΕX�̏�̂悤�Ȓ��������C�W�����Ⴂ�H�ʂł͂��̍��͍ő�ɂȂ�͂��ł��B
�ł��ˁB
�O�d�ŐL�т�̂́A�O�֑��̃u���[�L�E�H�ʂƂ̃R���^�N�g�̕��ׂ��������i�����ꂩ�̌��E�_�����j���ƁA��ւ͉d�������Đ����͂��ł��Ȃ��������ƁA�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25934565�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����
�����Ԃ�AABS�ɂ��āA�킽�����ƃR�s�X�^�X�t�O����ƂŁA�F�����Ⴄ�Ǝv���܂�
���̂悤�ł��B
�����ǂ���ABS�́A���b�N�����Ȃ��M���M���𐧌�ł���Ƃ̔F���ł�
ABS�͐Ö��C�͂̌��E���u�������v���Ƃ����m����i��]����ω������E���j�킯�ł����A�d����i�d���傫����j�H�ʂƂ̐Ö��C�͂̌��E�͍����Ȃ�܂��B�܂�AABS�̍쓮�i�����A���b�N�����m�j��x�点�錋�ʂƂȂ�͂��ł��BABS�͂ǂ��܂ōs���Ă��u���b�N�i��]���E�ω����j�����m���ău���[�L�̐����͂���߁A�H�ʂƂ̐Ö��C�͂���������|�C���g��T��v��ƂȂ̂ŁA�S�����b�N�����Ɏ~�܂�ꍇ��萧���������Z���Ȃ邱�Ƃ͂���܂���B
�l�Ԃ̔������x�͕����@���Ƃ͂܂��ʂ̘b�ł��ˁB
�F�X�g�[�^�����āA������@�Ȃ��₳��̂����_���ƁB
�����ԍ��F25934574�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
������@�Ȃ��₳��
�̏��͌��ʂ��Y��ȕ��тɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��Ȃ^���g������܂���
�F�����͂Ȃ��Ă��܂���
�P�O�O�O�����lj��ł����̒��x�̍��Ȃ�
��ɂ��R�����g�L��悤��
���̉d�Ɍ����������͂�������܂ł̃u���[�L�x���Ƃ����L�肻������
��͂�ς��Ȃ��̂�
����ł͏d���Ɠ��͂��K�v�ɂȂ邩������Ȃ��������邪
�p�j�b�N�u���[�L�i�u���ɋ������ݍ��߂j�ԏd���R���ȏ㑝���Ă����傢�L�т��炢��2���R���Ƃ��͉��тȂ���������
�����ԍ��F25934585
![]() 2�_
2�_
���ȃ��X�ł��B
��ABS�͐Ö��C�͂̌��E���u�������v���Ƃ����m����i��]����ω������E���j�킯�ł����A
�����x�E�p���x�Z���T�[�Ƒg�ݍ��킳��Ă���ꍇ�͂�荂���x�ɂ͂Ȃ�܂��ˁB�o�C�N�ɂ�6��IMU�Ȃ�ĕt���Ă���̂�����܂����B
�����ԍ��F25934590�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���̎�̋c�_�ŏd�v�Ȃ̂�
�����ł�
�u���[�L�͖�����̐��\�������Ă���A��]���u���Ɏ~�߂鐫�\������B
�^�C���͘H�ʂ̉^�����C�͂͏d�ʂ̑����ɑ��Ĕ�Ⴕ�Ė�����Ŕ�ᑝ������B
�H�ʂ͎ԗ����Î~�o����Î~���C�͂�L���Ă���B
�����R�͂̒l���ω����Ȃ������ʂł���B
�ԗ��̑��x�͑��F�����x�����Ƃ���B
�����̏������łȂ�d�ʑ����ł��ς��Ȃ��B
�����̎Ԋ��ł͑S�Ă̏�����������͓̂���A�H�ʏƘH�ʂ̌X�Ε����͓��ɍ����Ԃł������ł��Ȃ��B
�����瓮��͗����Ƃ��������A�������ۂ̐����Ŗ��ɗ��\�h��͏d�ʑ������ɂ͎ԊԂɂ�Ƃ��
����̗��_�͒m���Ƃ��Ėʔ���
�����ԍ��F25934616
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���Ōy�����ł��d�����ł��}�����ł́A�u���[�L�͍ő�\�͂œ����悤���䂳���̂����R�̂��Ƃł��傤�B
���R�ł͂���܂����B
�u���[�L��ڈ�t���Ƃ��Ă��A�^�C���̖��C�͈ȏ�̐����͂͏o���܂���ˁB
�^�C���̖��C�͂́A�y�����Əd�����ł͈Ⴄ�̂ł����āA�������ƌ����Ă܂����ǂˁB
���˂��݂���B����
���������Ă���A�G�Ȃ������ƁA���[�̂��I�Ńh�J���ƃu���[�L���߂�̂ł����A���������͂����܂���
�����ł́A�u���[�L��������n�_�����܂��Ă���̂ʼn\�ł��B
����������Ȃ̂ŁA�����ƈႤ���Ƃ͕���������ł̘b�����Ă��܂��B
�����ԍ��F25934618
![]() 5�_
5�_
��Mr.Z.����
>�^�C���͘H�ʂ̉^�����C�͂͏d�ʂ̑����ɑ��Ĕ�Ⴕ�Ė�����Ŕ�ᑝ������B
����ȊO�̓x�X�g�łȂ��Ă������������Ȃ�s���ĕ��ϒl�o���Ύ����Ƃ��Ă͏o������
�������ǂ����͕ʂɁi�����I�͈͓��ł́j�d�ʂ����������̃^�C���̖��C�W���ɕω��������Ȃ��̂��͋C�ɂȂ�܂�
�����ԍ��F25934623
![]() 3�_
3�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�O�X���`���̓��������ꂽ�����z���A���Ђ������������̂ł����E�E�E
������āA������t�B�[�h�t�H���[�h���䂩�A����ɋ߂����炢�̉�����Ǝv���܂�
�ȂO��t�@�~���[�J�[���A96km/h����36m�Œ�~�ł��鎞��ł�
�|���V�F911GT3��100km/h����ƁA5m�̍��ł���@�i�召�ɂ͌��y���܂��E�E�E�j
�i���Ȃ݂ɁA��̎��́A���ʂ͂������A�^�C�������W����܂���̂ŁA���̍�������ł���̂́A�^�C���̃ʂ����H�j
�E�F�b�g��A�C�X�o�[���͒m��܂��A���̃h���C�H�ʂł́A���u���b�N�i��]���E�ω����j�����m���āE�E�E�v�E�E�E���Ă��Ƃ���Ă��悤�ɂ͌����Ȃ������ł��@�i�܂��A���A�^�C������Ă܂��E�E�E�j
�������Ƃ���
�������A�������Ȃ̂ŁA�����ƈႤ���Ƃ͕���������ł̘b�E�E�E���āA�킽�������A�قڊF��������ӂ��Ă���b���Ǝv���Ă܂����E�E�E
���̂����ŁA�������A�����͈����ق��ɈႢ�₷���̂ŁA���ӂ��܂��傤�ƁA���̎肱�̎�g���Č����Ă邾���ł�
�����ԍ��F25934681
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����
���t�B�[�h�t�H���[�h���䂩�A����ɋ߂����炢�̉��
�����x�E�p���x�Z���T�[�Ƃ��n���h���E�u���[�L�̑��쑬�x�E�ʂȂǂ��E���Ă��Ȃ�ׂ����f��������͂��Ă����ł��傤�ˁB�ł��A�H�ʂƃ^�C���̐ڐG�ڏE���Ă���킯�ł͂���܂��AABS�̃A�N�`���G�[�^�̍쓮�̎d���ɂ����E����A���E�͂��邩�ƁB
������ɂ��Ă��e�����̌��ʂ͎������Ǝv���܂����A���ʂɈ�a���͂���܂���B���ۂ̓��H���⎩�g�̔������x�������̂悤�ɂ͂����Ȃ����Ƃ��A������܂��B
�����ԍ��F25934714�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�d�����̐ς炻�̕��������܂Ȃ��Ǝ~�܂�Ȃ��B
������Ĉ����ق��ɍl���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�����ԍ��F25935098�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�ł��邾�������̌��t�Ő����Ƀ`�������W���܂�
�����Ƃ̓^�C����O�ɓ]���������̊����́@VS�@�u���[�L�V�X�e���ɂ��^�C���̉�]���~�߂�����̐�����
�̂��߂������̌��ʁA��҂��ł������Ďԑ��������Ă�������
�����������ŒZ�ɂ��邽�߂ɂ͐����͂����̃V�X�e����������ő�ɂ������Ƃ���ł����A�����͂��ł�����������ƃ^�C���̓��b�N���܂��̂ŁA���̐��O�܂ł̂Ƃ���Ő����͂�}���ăR���g���[�����Ă��K�v������܂�
���̎�i��ABS�������肷��킯�ł��i�l��ABS�܂ށj
���Ȃ݂ɁA���̃��b�N���O�̐����͈͂��ł͂Ȃ��A�����ɂ���đ傫�����邱�Ƃ��ł��܂�
���Ƃ��Ďv�����̂�
�E�ԏd��傫������
���傫�Ȋ����͂�^���邱�ƂŃ^�C����O�ɓ]�����͂�������̂Ő����͂�傫���ł��܂�
�E�^�C���̃O���b�v�͂����߂�
�n�C�O���b�v�^�C���ɕύX����ȊO�ɂ��A�����d��傫�����Ă�苭���H�ʂɉ����t���铙����O���b�v�����債�ă��b�N���E�����܂�A�����͂�傫���ł��܂�
��Ԑl����������A�����͂̑���Ƃ����}�C�i�X�ʂ��肪���ڂ���܂����A��L�̂悤�ȃ����b�g�����͂���̂ł�
F=ma�ł�����Am�i�ԏd�j���傫���Ȃ��Ă�F�i�����́j���悤�ɑ傫���ł���Γ��������x�i�����ɂ����錸���x�j�ɂȂ�܂�
���������x�Ƃ������Ƃ͐��������������Ƃ������ƂɂȂ�܂�
�����ԍ��F25935124
![]() 2�_
2�_
�ԏd�ω��ɂ��^�C���̖��C�͂̋c�_�����M���Ă�悤�����ǁA
����Ȃ��l��Ԃ̎��ƁA����t����Ԃ̎��ɓ������x����A�u���[�L���b�N(�^�C�����b�N)�����Đ��������̑��������A�u���[�L�͊W�Ȃ��^�C���̖��C�݂̂̔�r�ɂȂ�̂ŁA�͂����肵�������ˁB
�Ⴆ�Ύ���40�L���Ńu���[�L���b�N(�^�C�����b�N)���������A��l��Ԃƃt����ԁA�ʂ����Ăǂ���̕����Z�������łƂ܂��ł��傤���H
�����ԍ��F25935248�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�����ł��B
�i�X��̂悤�ȋɒ[�Ȓ�ʘH�͏����j
�����ԍ��F25935260�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����������ƂȂ�ƁA�ԏd�̕ω��Ő��������ɕω��������炷�̂̓u���[�L�̔��M�ʂ̈Ⴂ�Ƃ������ƂɂȂ�A
������������~�̂��߂̏��p���M��/������
�Ƃ����u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h�̖��C�M�ɁA�s�������悤�ȁB
�����ԍ��F25935290�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
��������������~�̂��߂̏��p���M��/������
�͂��B�ł�����A
���q���傫���Ȃ镪�A������傫���Ȃ�
�Ƃ��b���Ă��܂��B
�d�ʂ�������Ɩ��C�͂��傫���Ȃ�Ƃ������Ƃ��ǂ����Ă��������肢�������Ȃ��悤�ŁB
�����ԍ��F25935304�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�����������A�ԏd���d���Ƃ����y�������A�}�������̓��[�^�[�Ƀp�b�h�����b�N���O�̗͂ʼn����t�����ő唭�M�ɂȂ�悤���䂳���̂ŁA�ۗL�G�l���M�[�̑����d�����̂ق����A�ۗL�G�l���M�[����苎�邽�߂̔��M���Ԃ�����������̂ŁA���̕����������������Ȃ�Ƃ������ƂŁA�O�̎��Ɨ����͓��������ǂˁB
�����ԍ��F25935305�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�������������A�ԏd���d���Ƃ����y�������A�}�������̓��[�^�[�Ƀp�b�h�����b�N���O�̗͂ʼn����t�����ő唭�M�ɂȂ�悤���䂳���̂ŁA
�ԏd���d�����͌y�������M�ʂ������܂��B
�d�����̔M�ʂł����Ă����o�\�ȍő�M�ʂ��͏������ł��B
�����ԍ��F25935310�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25935353�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���ԏd���d���Ƃ����y�������A�}�������̓��[�^�[�Ƀp�b�h�����b�N���O�̗͂ʼn����t�����ő唭�M�ɂȂ�悤���䂳���̂�
�u���b�N���O�̗́v�́A�ԏd���d���Ƃ��قǑ傫�ȗ͂ɂȂ�̂ŁA�ő唭�M�������܂��ˁB
�ԏd���d���قǁA�^�C���̓��b�N���ɂ����Ȃ�̂ł��āA������J��Ԃ��ł����B
�����ԍ��F25935378
![]() 2�_
2�_
����Ǝ����悤�Șb�ł��ˁB
https://www.manabinoba.com/science/9720.html
�����ԍ��F25935383�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�v�����݂�A�@���i����𗘗p���錠�́j�Ȃǂɂ���l�X�̎v�f�ŁA�����Ȃ��Ȃ�����A�Ȃ����Ă��܂����Ƃɂ́A�킽�������܂߁A�݂�Ȓ��ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł���
���킽�����́A�卷�łȂ������͈̔͂ŁA�d�ɂ��^�C���̎d���ʂ̕ω����C�ɂȂ��Ă��܂�
�^�C���̑�G�c�ȁA�d�ɂ�門�C�͂̕ω��́A�r���܂Ŕ��ŁA����d�������`�ɂȂ��āA�����ɂ����A�Ƃ����O���t�͌����̂ł����E�E�E
���炩���ߓ����Ă����C���̊W�Ƃ��A���x�̊W�Ƃ��A���C�ƔS���A�\�ʕό`�ɂ��A�����ь��ʂƂ��A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃɂ��镨�̂̉e���Ƃ��E�E�E
���x�̓��b�N�����Ƃ��̕\�ʔj��̉e���Ƃ��E�E�E
�^�C��������ɂƂ�A���S�ғ���ҏ������x�ł��傤���A�C�ɂȂ�܂��@�i��������ŕ\����Ă��͗����ł��܂��E�E�E�j
�����ԍ��F25935427
![]() 1�_
1�_
���˂��݂���B����
���d�ɂ��^�C���̎d���ʂ̕ω�
��Ⴕ�Ȃ����Ă��Ƃł����ˁB�^�C���\�ʂ�n�����đ��郌�[�X�Ȃł͌����ɂ����ł��傤�ˁB
���ۂ̘H�ʂ̓U���U���A�d���ĐH���������ނ���悭�~�܂肻�������A�����͂̑�����ł��������ƂɈ�a���͂Ȃ��B
�����ԍ��F25935545�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O����
����Ⴕ�Ȃ����Ă��Ƃł����ˁE�E�E�͂��A����ȃC���[�W�ł�
���d���ĐH���������ނ���悭�~�܂肻�������A�����͂̑�����ł��������ƂɈ�a���͂Ȃ��B
���[�V���O�J�[��~�b�h�V�b�v�̃X�|�[�c�J�[�ȂǁA�ύڕ��̉e�������Ȃ��A�d�S���Z���^�[����������ŒႢ�Ԃł������A�t�����g�u���[�L�̂ق������|�I�ɑ傫���A���ꂾ���������͑O�ւɉd��������Ƒz���ł��܂�
�t�����g�͋}�������A�ق�ƂɘH�ʂɐH�����ނ��炢�̃C���[�W�ł����
���p�o���̎������ʂł́A�O���ɏd�葝�₹�A�t�����g�̋��e���Ă��܂��̂ł��傤
���ɔw���~�j�o���Ȃǂ́A�d�ړ����傫���Ȃ�����ł��̂ŁA����܂�����
�ł��E�E�E
�z�C�[���x�[�X�Z���A�w�������A��z�Ƃ��̏��^�g���b�N�E�E�E�ŋ߂͖Ƌ����x�ɑΉ����āA�ԗ��d�ʂ��y���Ԏ�������Ȃ��Ă��܂������E�E�E
����́A��ׂł��A�d�S�͍����A�}�������̓t�����g�Ɋ|���肷���āA���e�����āA���A�͋t�ɉd�����āA�Ȃ�Ȃ����ȃC���[�W
�^�C�����A�ϋv���d�����ۂ��A�O���b�v�セ���ŁA��C���������A������X���b�v�T�C�����肬��܂Ŏg���Ă��������E�E�E
�ŁA���̎Ԃ̉^�]��́A�Ƌ��I�ɂ͌o���̐l���������ŁE�E�E
�܂��A���ʂ̃g���b�N�ł��A���̑O���ɉו������߂Ă�ƁA����ς��Ȃ���
���A�G�A�T�X�Ȃ�A�܂������A�o�l�͖\�ꂻ���ȃC���[�W�E�E�E
�����܂ŃC���[�W�ł�
�����ԍ��F25935646
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
���́[�A������킹�Ē����܂��B
�ԏd(��Ԑl��)�������A�قȂ葼�͑S�ē����Ԃł̔�r�ł��B
�y�������A�d���������A������]���ʼn���Ă���u���[�L���[�^�[���A�����͂Ńu���[�L�p�b�h�������̖��C�M�͓����ł��傤�B
�������[�^�[�ۗ̕L�M��(�^���G�l���M�[)���Ⴄ�̂ŁA�y���ĕۗL�M�ʂ����Ȃ������A������������ł��傤�ƁB
����̓t���C�z�C�[���ɂ��Ƃ���Ε�����₷�����ƁB
�d���̈Ⴄ��̃t���C�z�C�[���͂œ�����]���܂ʼn���A���͂���藣���āA�ӂ��̃t���C�z�C�[�����Đ��ʼn���Ă���̂��u���[�L�Ŏ~�߂邱�Ƃ��l���܂��B
���̓�̃t���C�z�C�[�����A���ꂼ�ꓯ���u���[�L�p�b�h���͂ʼn����t���ău���[�L���������Ƃ����A���ꂼ��̃t���C�z�C�[���̎~�܂���͂ǂ����H
���������̃u���[�L���������Ȃ�A�ۗL�M��(�^���G�l���M�[)�̑����A�d���t���C�z�C�[���̕����~�܂�̂Ɏ��Ԃ�������܂��B
�v����ɓ���������(�u���[�L��)�Ȃ�A�����͂��������ł��ア���ł��A�~�܂�܂ł̎��Ԃ͕ς�邯�ǁA������̏ꍇ���A���������͂Ȃ�A�y�����������~�܂�Ƃ������Ƃł��B
�Ԃ̐��������̖����A���̃t���C�z�C�[���Ɠ��������Ȃ̂ł́H
�����ԍ��F25935936�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���́[�A������킹�Ē����܂��B
�ԏd�i��Ԑl���j�������قȂ�A���͂��ׂē����Ԃł̔�r�ł��B
�y���u���[�L���[�^�[�Əd���u���[�L���[�^�[��������]���ʼn���Ă���ꍇ�A�d�����[�^�[���y�����[�^�[���������͂ŋ��ނƁA���̕������̖��C�M����������ł��傤�B
�����瑽���̔M����o���悤�ƁA�d�����[�^�[�������Ă����M�ʁi�^���G�l���M�[�j�̕����傫���킯�ł����A���ޗ͂ɂ���Ă͌y�������d�������~�܂�܂ł̎��Ԃ͓����ɂȂ�ł��傤�ƁB
���������͂Ȃ�y�����������~�܂�܂����A�d���Ă����̕������͂���������Γ����ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�����ԍ��F25936126�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�����ł��ˁB
�ł́A���ɒ��ޑ��x�͏d�����̂ƌy�����̂łǂ��ς��H�Ƃ����₢�ɐ�������������l�͈ĊO���Ȃ��Ǝv���܂��B
���R�����̑O������Ƒ��x�������ɂȂ闝�R�𗝉����Ă���A���������ł͑��x���قȂ闝�R����������͂��Ȃ̂ł����B
�����������́A�Ŏv�l��~���Ă��܂���ł��傤���B
�����ԍ��F25936139�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���̕���������Ă܂������A���Z�����̐��E���ƃ^�C�������������O���b�v����Ƃ����b�͐��藧���Ȃ���ł���ˁB�����Đڒn�ʐς��L��������A�P�ʖʐϓ�����̈��͂�����̂Ńg�[�^���̖��C�͂͒P���v�Z��͓����ł���˂Ƃ����c�B
����ƁA�g���N�V�����R���g���[���̐����ɂ悭�łĂ��܂����A���s���̃^�C���͐₦�������Ɋ����Ă���̂ŁA�^�C�������b�N���Ȃ��Ă��A��~���̐Ö��C�W�����͖��C�W�����������Ȃ��ł���ˁB��x�����b�N���������Ƃ��Ȃ��l�̎Ԃł��A����^�C���͖��Ղ��Ă����܂����c�B
ABS�̂Ȃ��ԂŃ��b�N�����Ă��܂��Ă��AABS�������ė͂����Ă��A�㋉�҂��M���M�����b�N�����Ȃ��悤�ɋ������Ƃ��ł��A���������͎v�����قǑ傫���͈��Ȃ��Ƃ����������ʂ������Ō����悤�ȋL��������܂��B
�Ö��C�W���Ɠ����C�W���͈�ʓI�ɂ͑傫���Ⴄ��ł����A���b�N�����Ȃ��悤�ɉ������邱�Ƃōő吧���͂������ĂȂ�������A���b�N���Ȃ��Ă������ɂ͊����Ă���Ƃ���2�̗v���ɂ����̂ł��傤�B
��������]�k�ł����c�B
�����ԍ��F25936210
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���ԏd(��Ԑl��)�������A�قȂ葼�͑S�ē����Ԃł̔�r�ł��B
���y�������A�d���������A������]���ʼn���Ă���u���[�L���[�^�[��
�����܂ł͐ݒ�̒ʂ�ł��B
�������͂Ńu���[�L�p�b�h�������̖��C�M�͓����ł��傤�B
���́A�u�����͂Ńu���[�L�p�b�h�������v�ł����A��̃u���[�L�e�X�g�ł̋��ޗ͇͂������͇�����Ȃ��ł��B
�����Łw�������d�ʕ��ɔ�Ⴕ�ă^�C���O���b�v�i���C�́j���オ��x������ł��܂��B
����̊X���ł̓t���u���[�L�ȂǓ��݂܂���̂ŁA���������悤�Ɂu������ƐL�т��v�����ʂ��Ǝv���܂��B
�����A����̌��̓t���u���[�L�ł̐��������e�X�g�ł��B
�e�X�g�ł�����u���[�L�J�n�|�C���g�����܂��Ă��āA�����Łu�h���v�ƃu���[�L�݂܂��B
����������܂������A�����̎Ԃ͇��u���[�L�A�V�X�g���ƌ������S���u���t���Ă��܂��B
����͉^�]�肪���ȏ�̐����i�����j�Ńu���[�L�߂@�B�͇��t���u���[�L���K�v�ȏ��Ɣ��f���A
�����^�]�肪��͂ȏ����ł��A��͋@�B���L��]�邾���u���[�L���������Ă���܂��B
�ł��A���ۇ��L��]�釁�قǂ̃u���[�L�͕͂K�v�Ȃ����낤�H�ƂȂ�܂����A�]��������ABS���J�b�g���܂��B
ABS�̓^�C�����O���b�v���������O�́i�قځj�ő喀�C��Ńu���[�L�����R���g���[���i�������j���܂��B
�^�C���̃O���b�v�͂́A�d�ʂ���������Γ��������ő����܂��B
�Ⴆ��1����Ԏ���ABS�ɃR���g���[�����ꂽ�A�^�C�����b�N��O�̃u���[�L�������P���Ƃ��܂��B
��������ԂŎԏd��1.2�{�ɂȂ����ꍇ�A�u���[�L�������P���ł͂܂��܂��O���b�v�ɗ]�T������A
ABS�͂܂��u���[�L�������A������1.2���ɂȂ������ɃO���b�v���E�Ńu���[�L�����܂��B
��́w�u���[�L�p�b�h�ŋ��ޗ́x��1.2�{�ɂȂ�܂����̂ŁA���_��ł͓��������Ŏ~�܂�A�ƂȂ�܂��B
�i�� �u���[�L���̑����ƃp�b�h�̖��C�͂̑����͕K�������C�R�[���ł������Ǝv���܂����A�܂����̑������A�ƌ������ł��l���������B�j
�����ԍ��F25936225
![]() 2�_
2�_
���������@������ł���
�ÓT�����̎��W�J�����Ȃ�@�d���X�L�[���[�@�Ɓ@�y���X�L�[���[�ł�
�������x�ɂȂ�܂���
���Z�X�L�[�ł́@�d���I��̂ق����^�C���������ł�
�����ԍ��F25936243
![]() 2�_
2�_
��cbr_600f����
���͎����O�X���̎傳���ꂽ�u���O�́A�ʂ̋L���@��
https://vehicle-cafeteria.com/T15TorqueHorsePower.html
��ǂ�Łi�܂�����ǂ݂ŁA�V���[�Y�̕ʃy�[�W�܂ߑS�Ă͓ǂ�ł��܂��j
�u�C���C���A���w�I�ɂ͂�����������Ȃ����A���ۂ͑����ق����c�v�Ǝv����ł��B
���������̌��ɂ��Ă͊T�˓��ӂł��B
�ł��R�[�i�����O���E���ŁA�ڒn�ʐς�����̈��͂Ƃ��A������܂ł͗������܂����A
��͂苆�ɓI�ɂ̓^�C���������ق����L���ŁA��̐������������͍����o��Ǝv���Ă��܂����ł��B
�ǂȂ����A���̃u���O��_�j�ł���A�������͊��S�Ɏ^������ƌ������A
���АV�X���𗧂��グ�Ē�����c �Ə���Ȃ��肢�����鎟��ł��B
�����ԍ��F25936269
![]() 3�_
3�_
�����ɓI�ɂ̓^�C���������ق����L��
�������@�G���Ȃق����@�����\�ȃC���[�W������܂���
���́@�h���b�N���[�X�̃^�C���͈�����肵�܂�
�T�C�h�t�H�[�X�̃p�t�H�[�}���X�Ɓ@�쓮�����̃p�t�H�[�}���X�͈Ⴄ��ł���
�����ԍ��F25936273
![]() 2�_
2�_
���������`����
���Ⴆ��1����Ԏ���ABS�ɃR���g���[�����ꂽ�A�^�C�����b�N��O�̃u���[�L�������P���Ƃ��܂��B
��������ԂŎԏd��1.2�{�ɂȂ����ꍇ�A�u���[�L�������P���ł͂܂��܂��O���b�v�ɗ]�T������A
ABS�͂܂��u���[�L�������A������1.2���ɂȂ������ɃO���b�v���E�Ńu���[�L�����܂��B
���ꂪ�l�̍l�������ƈႤ�̂ŁA�`���b�Ƌ^��Ȃ�ł���ˁB
�}�u���\�L���ɓ��삷��`�a�r�̓^�C���̏����m���āA���b�N������i���b�N�������ɂȂ�����j��u�����u���[�L���ɂ߂ă��b�N��h���A�Ăуu���[�L��������Ƃ���������u���ɌJ��Ԃ��A���S�Ɍ����o����悤�ɂ������̂ł���ˁB
������`�a�r�V�X�e�����A�ԏd�̈Ⴂ�Ńu���[�L����ς���̂ł͂Ȃ��A�P����Ԏ����t����Ԏ����A�ő喀�C��������u���[�L������������ŁA�Z���T�[���^�C���̉�]���ƃX�s�[�h���r���āA���b�N�����o������u���[�L�����ɂ߁A���b�N�������狭�߂�Ƃ����������u�̂����ɌJ��Ԃ����ƂŁA���₩�ɉ^���G�l���M�[��M�Ƃ��ĕ��o���铮�������̂��ƁB
���̃u���[�L����ŎԂ��~�߂邽�߂ɂ́A�g�[�^���Ƃ��ĕ��o�����ׂ��M�ʂ͂P����Ԃ�葽�l����Ԃ̕��������Ȃ�܂��B
�ŁA�}�u���[�L���ɂ�����A�`�a�r�̈�A�̃u���[�L����̂Ȃ��ŁA�ꖼ��Ԃ̎��Ƒ��l����Ԃ̎��̐��������̈Ⴂ�͂ǂ��Ȃ̂��H
����ς葽�l����Ԃ̕����u���[�L�ŕ��o���ׂ��M�ʂ��������u���[�L���O���Ԃ��L�т�̂ŁA�����������L�т�낤�Ȃ��āB
�����ԍ��F25936434
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���}�u���[�L���ɂ�����A�`�a�r�̈�A�̃u���[�L����̂Ȃ��ŁA�ꖼ��Ԃ̎��Ƒ��l����Ԃ̎��̐��������̈Ⴂ�͂ǂ��Ȃ̂��H
���̓������O�X���`���̓���ł���ˁB
ABS�͓����Ă���悤�Ɍ����Ȃ������œ����Ă���B�O��։d�̃o�����X����r�I�ǂ������ȃ~�j�o���i�d�̔����₷����ւ���������d��������j�����A�u���[�L�ɂ��]�͂������ł��傤�B���̗]�͂ɔ�ׂ���u���[�L�̔M�ʂȂ�Ĕ��X������̂ł��傤�B����ȒZ���Ԃ̋}�����ʼn��������Ă���������̉����ŁA�����Ȃ��B
���ʂɈ�a���͂���܂���i�u36m�v�̌덷�͐��\cm���肻���ł����ǁj�B
���܂ł��́H
�����ԍ��F25936446�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
���ő喀�C��������u���[�L�������������
���x�������Ă��܂����A�ԏd���d���Ȃ�ő喀�C��������u���[�L���͑傫���Ȃ�܂��B
��͂�d�ʂ�������Ɩ��C�͂��傫���Ȃ�Ƃ������Ƃ��ǂ�����Ă��������肢�������Ȃ��悤�ŁB
�����ԍ��F25936463�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�������������Ȏ����ŏo�Ă���Zkm/h�̎��̒�~�����Zm���Đ����Ɏԗ��d�ʂŕω����܂��A���Ē��߂��t���Ă�̂͌����L���������ł���ˁB
�Ȃ̂ŁA�܂������������Ȃ낤���Ďv���Ă܂��B
�u���[�L�y�_�����̊��G�͐��������L�тĂ�[�A���Ċ����Ȃ�ł����ǂˁB
�����ԍ��F25936466
![]() 1�_
1�_
���R������
(1/2)�Em�Ev^2 = m�Eg�Eh
���ӂ�m������̂ŁAm�ɂ�炸�������x
����������
(1/2)�Em�Ev0^2 = ��t�Em�Eg�Ed
���ӂ�m������̂ŁAm�ɂ�炸������������
�R�s�^�X�t�O����̂��������ʂ�A���R�����̎������ʂ͎�����邯�ǐ��������̎������ʂ͎�����Ȃ��Ƃ����̂́A�A���X�g�e���X�̎��ォ��K�����I���O�̎���܂ł͏d�����̂̕�������������Ǝv���Ă����̂Ɠ������ƂȂ�ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25936473�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
��use_dakaetu_saherok����
�������_�����Ē����܂��B
�����x�������Ă��܂����A�ԏd���d���Ȃ�ő喀�C��������u���[�L���͑傫���Ȃ�܂��B
����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł́H
�u���[�L���������Ȃ���b�N���O�ōő喀�C��������̂͊m���ł��傤���A�ԏd�ɂ���ău���[�L�����ς�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA
�}�����ł`�a�r�������������A��Ƀu���[�L���̓��b�N���O�̃u���[�L���̂Ȃ��ŁA�Z���T�[�����b�N�����m������u���[�L������߂܂��u���[�L����߂��Ƃ������Ƃ��u���ɌJ��Ԃ��Ă��āA�ő喀�C�ʂ��ŏ����������ɂȂ�悤���䂳���̂ŁB
���Ȃ݂ɂ`�a�r�ɂ͎ԏd�����o���ău���[�L����ς���悤�ȃZ���T�[�͖����̂ł́B
�܂��A�l�Ԃ��ً}���̋}�u���[�L�Ŏv��������u���[�L���́A�`�a�r�����b�N���O�̍ő喀�C��������悤�u���[�L�����������䂷��̂ŁB
����͂�d�ʂ�������Ɩ��C�͂��傫���Ȃ�Ƃ������Ƃ��ǂ�����Ă��������肢�������Ȃ��悤�ŁB
������A�d�ʂ�������Ɩ��C���傫���Ȃ�Ƃ������^���G�l���M�[��ł��������߂̖��C�ʁi���C�M�ʁj��������ƌ������ƂȂ̂ł́B
���������`�a�r�͏d�ʂ��������Ƃ����C�͂�傫�����鐧��͂���Ă��Ȃ��̂ł́A����ȃZ���T�[���Ȃ����낤���B
�ŁA����͎��ȗ��̍l���������ǁA�u���[�L�������������u�Ԃ̖��C���W���[���^�b�Ƃ����P�ʂ̕��M���Ƒ�����ƁA�Ԃ��~�܂�܂ł̑S���M�ʂ́A
�@�@���M��(�W���[���^�b)�@×�@�u���[�L���ԁi�b�j�@���@���M��(�W���[��)�@�@�@�@�ɂȂ�悤�ȁB
�Ȃ̂ŎԂ��y�����ł��v�����ł��`�a�r�́A���̎Ԃ̃u���[�L�������Ă���ő�̖��C�M��������ׂ����������̂ŁA�d�����A�y�����A������̏ꍇ�����M���͂قړ����i�`�a�r�̓���Ŏ�ς���Ă��j�Ȃ̂ŁA�d���ĕ��M�ʂ̑傫���Ԃ̓u���[�L���Ԃ�������A�����������L�т�̂��ƁB
��L��A�̑O��Ƃ��āA
�P�A�u���[�L�̖��C�M�̓u���[�L���̋����ŕς���ˁB
�Q�A�`�a�r�������Ȃ����ʂ̃u���[�L���O�ł̓u���[�L���͓��ݕ�(���݂̋���)�ł����܂��ˁB
��L�̂P�A�Q�A�͏�������ς���Ă��A��������������܂���ˁB
�Ȃ̂ŁA�`�a�r�����삵�Ȃ��ʏ�̃u���[�L�ł��A�����u���[�L�̓��ݕ��Ȃ�A�d�����̕����A�y���������M���Ԃ��������̕������������L�т�̂��ƁB
�����ԍ��F25936673
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�d�ʂ�������Ɓu�^�C���ƘH�ʂƂ́v���C�͂��傫���Ȃ�
�Ɠǂݑւ��Ă݂ẮH
�����ԍ��F25936683�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
2��ڂł�
�ԏd�ɂ�銵���͂��傫���قǃ^�C����O�ɓ]�����͂��傫���Ȃ�̂ł�胍�b�N���ɂ����Ȃ�A���傫�Ȑ����͂��������܂�
�i���E�u���[�L���̐����͕͂ς��Ȃ��Ƃ������咣�ɑ��āj
ABS�ł����Ă��Ȃ��Ă��W�Ȃ��ł�
���M�ʂ͂�������܂���
�����ԍ��F25936750
![]() 0�_
0�_
���R�s�X�^�X�t�O����
�ȂO�̕��ŁA�F���H�ʂ̖��C�ŏd�ʕω��ɂ�鐧�������͕ς��Ȃ��Ƃ����b�����������悤�ȁB
�Ȃ̂Ńu���[�L�̔M���o�̊W�ŏd�ʕω��ɂ�鐧�������͂ǂ������čl���Ă���ǁB
�d�ʕω��ŘH�ʂ̖��C��u���[�L�M�W���ς��Ȃ��Ȃ�A�����������ς��Ȃ��낤���ǂˁB
�����ԍ��F25936755�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���u���[�L�̔M���o�̊W�ŏd�ʕω��ɂ�鐧�������͂ǂ������čl���Ă�
�u�d���Ɛ����������L�т�v�Ƃ�������ς����邩��A����Ȃ��Ƃ��l����H�ڂɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł����H
�����ԍ��F25936759
![]() 0�_
0�_
�����������������ł��܂�
���b�N���n�߂鐧���͓͂����ԗ��ł����ł͂Ȃ��A�ŕω����܂�
�v���ł����Ă������ԃ��[�X���Ƀ^�C�������b�N�A�b�v�����Ă��܂��̂͂����������ƂȂ̂ł��傤
���b�N���n�߂鐧���͂�
�E������z�ł͑傫���Ȃ�
�E�����z�ł͏������Ȃ�
�E�H�ʂ������Ă���Ƒ傫���Ȃ�
�E�H�ʂ��G��Ă���Ə������Ȃ�
�E�^�C���̃O���b�v�͂��傫���Ƒ傫���Ȃ�
�E�^�C���̃O���b�v�͂��������Ə������Ȃ�
�����āA����̂���ł́A
�E�ԏd���傫���قǑ傫���Ȃ�
�ƂȂ�̂ł�
�����ԍ��F25936772
![]() 0�_
0�_
�������������B
��Ԑl����l�̎Ԃ��T�O�j���^�g�܂ʼn�������G�l���M�[����͂`
�t����Ԃ̎Ԃ��T�O�j���^�g�܂ʼn�������G�l���M�[����͂a
��Ԑl����l�łT�O�j���^�g�ő����Ă���Ԃ��~�߂邽�ߎ�苎��G�l���M�[�̓^�C���̖��C�M�b�{�u���[�L�̔��M�ʂc���o�̓G�l���M�[�d
�t����ԂłT�O�j���^�g�ő����Ă�Ԃ��~�߂�̂Ɏ�苎��G�l���M�[�̓^�C���̖��C�M�e�{�u���[�L�̔��M�ʂf���o�̓G�l���M�[�g
�Ƃ���ƁA
�y���Ԃł͂`���b�{�c���d
�d���Ԃł͂a���e�{�f���g
�ŎԂ͎~�܂�܂���ˁB
�ŁA�`���a�Ȃ̂ŁA�@�b���e�@�c���f�@�Ȃ�`�|�a�̃G�l���M�[�̍��͂ǂ��ɍs������ł��傤���H
�����ԍ��F25936796
![]() 0�_
0�_
�ʃ�M���@���k�@����Ԑl���̍����ł�
�����ԍ��F25936798
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���`�a�r�����삵�Ȃ��ʏ�̃u���[�L�ł��A�����u���[�L�̓��ݕ��Ȃ�A�d�����̕����A�y���������M���Ԃ��������̕������������L�т�̂��ƁB
�J��Ԃ��ł����A�u�����u���[�L�̓��ݕ��v��ABS���쓮�����A�^�C�������b�N���Ȃ��Ȃ�AJAF�̎����Ɠ����ɂȂ�܂��B
ABS���쓮����Ȃ�A�u���[�L�̓��ݕ��������ł��A�u���[�L����ABS�����䂵�����͂ɂȂ�̂ŕς��܂��B
�^�C�������b�N����Ȃ�A�����C�W���������Ȃ̂Ŗ��C�͎͂ԏd�ɔ�Ⴕ�܂��B
�����ԍ��F25936799
![]() 0�_
0�_
ABS�쓮�|�C���g�̂���Ł@
�ʃ�M���@���k�@���@�f�[D�@�ł�
�����ԍ��F25936802
![]() 1�_
1�_
����A�b���e�A�c���f�ł���H
���M��������Ȃ��āA�g�D�̕���i�^�C���E�H�ʁE�p�b�h�E�f�B�X�N�̏��Ձj������B
�����ԍ��F25936806
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�`���b���c���d
�a���e���f���g
�`���a
�ł���@���Ԃ�
�����ԍ��F25936814
![]() 2�_
2�_
���˂��݂���B����
�ł��ˁB�ԈႦ�܂����B
�����ԍ��F25936822
![]() 0�_
0�_
���炵�܂���
B>A�ł��ˁB
�d���Ԃ̕����ۗL�G�l���M�[���������̂ŁB
�����ԍ��F25936884�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�@��use_dakaetu_saherok����
�d�����Z�����A�{���ł��Ȃ������ɂ��̂Q���ł��Ă����悤�ł��ˁB
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
R�At�Ar�Ab�́A�����w���Ă��܂����H
���̋��ʌ��ꂪ�����ƁA�����ł��܂���̂ŁB
�����ԍ��F25937090
![]() 1�_
1�_
���̃X���ɎQ������Ă��鑽���̕��́A�l�b�g�L���������āA������L�ۂ݂ɂ��Ă��邾���ŁA�����̌��t�ŁA���ۂ𗝉����Č���l���A�قƂ�ǂ���������Ȃ��̂��Q���킵���悤�ȁB
�����ԍ��F25937114�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������������炢�ł�����
���肪�Ƃ��������܂��B
�l�͂�����������D���ł��B
>2��ڂł�
�܂��܂�200�܂ŗ]�T������̂ŁA����ł��D���Ȃ����A�ǂ�������������ĉ������B
�����ԍ��F25937153�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
����Ⴂ�������܂��ˁB
�����������ς��Ȃ��Ƃ����b�́A�u���[�L���\������ŁA�ǂ�ȑ��x����ł��x���Ȃ��Ƀ��b�N�ł���A������^�C���̖��C�͂��x�z�I�Ƃ����O��ł��B
�i�C�g�G���W�F���������Ă���̂̓u���[�L���v�A�ŁA��������ł��Ȃ��Ȃ����b�N����Ƃ���܂ł����Ȃ��Ƃ����P�[�X�ł��傤�B
���̎��ɐ����������L�т�Ƃ����̂́A�L�тȂ��ƌ����Ă���F���F�߂Ă��邱�Ƃł���B
�����ԍ��F25937160�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 5�_
5�_
> ���̃X���ɎQ������Ă��鑽���̕��́A�l�b�g�L���������āA������L�ۂ݂ɂ��Ă��邾���ŁA�����̌��t�ŁA���ۂ𗝉����Č���l���A�قƂ�ǂ���������Ȃ��̂��Q���킵���悤�ȁB
���[��A�����ł̐����͕~�����������������Ƃ���������Ǝv�����̂ŁA�����̌��t�ŃC���[�W��������Ă݂�����Ȃ�ł�����
�قƂ�Nj����Ȃ������悤�ł���
���������ł�
�����ԍ��F25937205
![]() 4�_
4�_
���i�C�g�G���W�F������
�����ƃV���v���ɍl���Ă��������B
����~�ՃT�C�Y�̃u���[�L�f�X�N�̉�]�������ł��~�߂�u���[�L�̎d���ʂ������Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�^�C���̐ݒu�d�ʼn�]�g���N���傫���ς��܂��B
�u���[�L���~�Ղ̃R�}�A�ԏd�����݂Ƒ������
�����炢���̒��a1M�̉~�Ղ�����10��]�ʼn���Ă܂��B
����10cm�̋����̒��a1M�̉~�Ղ�����10��]�ʼn���Ă܂��B
�ǂ����5�b�Ŏ~�߂Ă��������ƂȂ�A��]�g���N���傫���~�Ղ͂�苭�����݂��ނ����ł��B
�u���[�L�ɗ]�͂�����ԏd�ɉ�]�g���N����ᑝ���������u���[�L�̎d���ʂ͂��ꂼ��ς��܂����A�����Ƃ�����^�C�~���O�ʼn�]���~�߂��܂��B
��O�͓��̖��C�W������ᑝ�����������R�͂��キ�Ȃ�i�������ւ̉��X�␅�A�X���Ȃǂ̈�舳�ȏ�ŌW�����Ⴍ�Ȃ��ԂȂǂł��B
���̏ꍇ�ԏd�ɉ�]�g���N����ᑝ�����Ȃ����߃u���[�L�d���ʂ����肸�A���̕���~�Ɏ��Ԃ�������܂��B
�����ԍ��F25937239
![]() 0�_
0�_
���G�����J����
������́A
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/#25931694
�ɑ��郌�X�ƂȂ�܂��B
���̎��́A
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/#25931647
�ɋL�ڂ������ł��B
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
�iR�F�^�C���O�a�A��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���Am�F�ԏd�Ag�F�d�͉����x�Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�A��b�F�u���[�L���C�W���AB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρj
�����ԍ��F25937266�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���y���Ԃł͂`���b�{�c���d
���d���Ԃł͂a���e�{�f���g
���ŎԂ͎~�܂�܂���ˁB
���ŁA�`���a�Ȃ̂ŁA�@�b���e�@�c���f�@�Ȃ�`�|�a�̃G�l���M�[�̍��͂ǂ��ɍs������ł��傤���H
A = C = D = E
B = F = G = H
A < B, C < F, D < G, E < H
�ł��邱�Ƃ͂���������܂������H
A - B �� �G�l���M�[���́A�u�ԓI�ɂ̓p�b�h�ƃ��[�^�[�̕\�ʉ��x�̍��ƂȂ�܂����A�����ɕ��i�S�̂Ŋ��炳��A���̌�A��C���ɕ��o����܂��B
���l�b�g�L���������āA������L�ۂ݂ɂ��Ă��邾���ŁA�����̌��t�ŁA���ۂ𗝉����Č���l���A�قƂ�ǂ���������Ȃ��̂��Q���킵���悤�ȁB
���������ǂ������������X�ɑ��āA���܂�Ɏ���ł́H
�Q���킵���ł��B
�����ԍ��F25937322�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���ƁA�w�ԏd���d���Ȃ�ő喀�C��������u���[�L���͑傫���Ȃ�x�Ƃ������Ƃɑ��āA���_�����������Ă����悤�Ȃ̂ŁB
�����Ȃ݂ɂ`�a�r�ɂ͎ԏd�����o���ău���[�L����ς���悤�ȃZ���T�[�͖����̂ł́B
�͂��B�t���Ă��܂���B
ABS������Ɏg���͎̂ԗ֑��Z���T�[�� Yow-G�Z���T�[�ł��B
4�ւ����ꂩ�̎ԗ֑����[���A��������4�ւ��ׂĂ̎ԗ֑����[���Ȃ̂Ɍ��������x�iG�j���o�Ă���ꍇ�A�^�C�������b�N���Ă���Ɣ��肵�A���̎ԗւ̃u���[�L���ɂ߂܂��B
�ł�����AABS���쓮���Ă��遁�^�C�����b�N�O��̃u���[�L���ł��B�����܂ł͂��������ʂ�ł��B
�������A��L�̂悤��ABS�̓^�C�������b�N���Ă���쓮���܂��̂ŁAABS���쓮������ɂ́A�܂��^�C�������b�N����܂Ńu���[�L�y�_���܂Ȃ���Ȃ�܂���B
�ԏd���d������̕��������܂Ȃ���ABS�͍쓮���Ȃ��̂ł��B
�����������`�a�r�͏d�ʂ��������Ƃ����C�͂�傫�����鐧��͂���Ă��Ȃ��̂ł́A����ȃZ���T�[���Ȃ����낤���B
���x�������Ă���悤�ɁA���C�͂͐����R�͂ɔ�Ⴕ�đ傫���Ȃ�܂��B
���R�H�̏ꍇ�A�����R�͂Ƃ͎ԏd�ł�����A�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͎͂ԏd��������قǑ傫���Ȃ�܂��B
����A�^�C�������b�N����Ƃ������Ƃ́A
�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�� �� �u���[�L�̖��C��
�ł��邱�Ƃ͂�������ɂȂ�܂��ł��傤���B
�܂�AABS���쓮���Ă����ԁA���Ȃ킿�^�C�������b�N���Ȃ��M���M���̏�ԂƂ́A
�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�� �� �u���[�L�̖��C��
�ł���A���ꂪ�ő喀�C�͂ł��B
����āA�ԏd��������ƁA�^�C���ƘH�ʂ̊Ԃ̖��C�͂������AABS���쓮����Ƃ��̃u���[�L���C�͂������A�ő喀�C�͂�������u���[�L���͑傫���Ȃ�̂ł��B
�����ԍ��F25937400�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����ꂪ�ő喀�C�͂ł��B
�t�������܂��ƁA
���ꂪ�i���̎ԏd�ɂ�����j�ő喀�C�͂ł��B
�ԏd��������Ζ��C�͂̍ő�l�������܂��B
�����ԍ��F25937404�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���傤���Ȃ��ȁ[�[
�ȉ��̗��K���������Ă���������Η���͂��g�ɒ������������܂���B
�Ȃ��d�͉����x�͂��Ƃ���
��P
�����C�W���ʁ@�̕��ʂ�
���ʂl�@�̕��̂�����
�������ɏ���V������������
��~����܂ł̊��������k�P�����߂�B�i�z�_�R�O�j
��Q
�����C�W���ʁ@�̕��ʂ�
���ʂQ�l�@�̕��̂�����
�������ɏ���V������������
��~����܂ł̊��������k�Q�����߂�B�i�z�_�R�O�j
��R
�����C�W���ʁ@�̕��ʂ�
���ʂl�@�̗��z�I�Ȏԗւ���������R��Ԃ�����
�E���ŕR�ɘA�����ꂽ���ʂ��@�̕��̂�����B
���R��Ԃƕ��͕̂R�Őڍ�����Ă���
�ړ��ɔ����Ĉ�����������̂Ƃ���
���̎����R��Ԃɍ������ɏ���V������������
��~����܂ł̊��������k�R�����߂�B�i�z�_�S�O�j
�����ԍ��F25937527
![]() 1�_
1�_
��use_dakaetu_saherok����
����R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8�j
�iR�F�^�C���O�a�A��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���Am�F�ԏd�Ag�F�d�͉����x�Ar�F���[�^�[�ʂ�h�����ʂ̕��ϔ��a�A��b�F�u���[�L���C�W���AB�F�u���[�L���́AS�F�u���[�L�ڐG�ʐρj
�����ԂȂ̂œ��R�����u���[�L�A�����^�C���A�����H�ʏA�Ȃ̂ŁA�����̌W���͏d�ʈȊO�S�ē������l�Ȃ̂ŏd�ʕω��ɂ�鐧�������̔�r�ɂ͊W�Ȃ����̂ł��傤�B
����
�P�A�u���[�L�̖��C�M�̓u���[�L���̋����ŕς���ˁB
�Q�A�`�a�r�������Ȃ����ʂ̃u���[�L���O�ł̓u���[�L���͓��ݕ�(���݂̋���)�ł����܂��ˁB
��L�̂P�A�Q�A�͏�������ς���Ă��A��������������܂���ˁB
�Ȃ̂ŁA�`�a�r�����삵�Ȃ��ʏ�̃u���[�L�ŁA�����u���[�L�̓��ݕ��Ȃ�A�d�����̕����A�y�������Ԃ��~�߂�܂ł̃u���[�L�̍�p���ԁi���C���M�y�ѕ��M���ԁj���������̕������������L�т�Ƃ������ƁB
����́A�i�`�e�̃e�X�g���ʂ𗠕t���ł�����̂ł�
�����������o�����i�`�e�̎������ʂ��A�M�����Ȃ��A�˂����t�F�C�N���Ƃ����Ȃ�A����ȏ�Ȃɂ������Ă��͂��܂�Ȃ����ǂˁB
�ŁA���Ⴀ���ꂪ�}�u���[�L���Ȃ�ǂ��Ȃ�Ƃ����b�����ǁA����������ނˌ��ʂ͓����͂��ł��B
�}�u���[�L���͂`�a�r�����삵�āA�ݒ肳�ꂽ�u���[�L���i�p�b�h�����[�^�[�ɉ�������́j��������܂��B
����́A�d�ʂ̑召�ɊW�Ȃ����ł��B
�ł����炨�Ȃ����x�œ����Ă���y�����̂��d�������̂ق����ۗL�G�l���M�[���傫�����߁A�~�܂�܂łɎ��Ԃ������萧���������L�т�ł��傤�ƁB
���������̃u���[�L����������Ȃ��ŁA�`�a�r�V�X�e�������b�N��h�����ߐ_�ƓI�ȃ|��s���O���s���̂Ŏ�̍��͂��邾�낤���ǁA�`�a�r�������Ȃ����ƂقƂ�Ǖς��Ȃ����ƁB
�����ԍ��F25937536
![]() 0�_
0�_
��S
�����C�W���ʁ@�Î~���C�W���ʁf�̕��ʂ�
���ʂl�@�̕��̂�����
�����C�W����Î~���C�W���ɕς��閂�@���O�~�ɏ���Ă���Ƃ���B
�������ɏ���V������������
��~����܂ł̊��������k�S�����߂�B�i�{�[�i�X�Q�O�j
��Q
�����C�W���ʁ@�Î~���C�W���ʁf�̕��ʂ�
���ʂQ�l�@�̕��̂�����
�����C�W����Î~���C�W���ɕς��閂�@���O�~�ɏ���Ă���Ƃ���B
�������ɏ���V������������
��~����܂ł̊��������k�T�����߂�B�i�{�[�i�X�Q�O�j
�����ԍ��F25937541
![]() 1�_
1�_
���_�Ђ���Ɠ��������ɂȂ��Ă��܂����ˁc�B
�^�C�����傫���ău���[�L�f�B�X�N�����ɏ������A�{�͑��u���Ȃ��I�t�Ԃ̃o�C�N�ɏ���Ă����Ȃ�A��l������l���̕������������͐L�т܂��ˁB
�����ԍ��F25937545�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���J���̃u���[�L�f�B�X�N�ɑ��s���Ƀs�����h���āA���C�͖����ɋ�����~�����ꍇ(���ʂ͎Ԃ����܂����j����l����Ə����C���[�W�ł������Ɏv���܂����A�܂������ł��傤�ˁB
�l�͋t������Ƃ��́A�u�Ȃ�ŊF�t�����Ă�낤�v���Ďv�������ł����B
�����ԍ��F25937555�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
���}�u���[�L���͂`�a�r�����삵�āA�ݒ肳�ꂽ�u���[�L���i�p�b�h�����[�^�[�ɉ�������́j��������܂��B
������́A�d�ʂ̑召�ɊW�Ȃ����ł��B
��
�����̔F�����A�킽�����Ƃ͈Ⴂ�܂���
ABS�Ő��䂳���u���[�L���́A�d�ʂ̑召�ɂ���āA�ς��Ǝv���Ă��܂�
�����ԍ��F25937558
![]() 2�_
2�_
> �}�u���[�L���͂`�a�r�����삵�āA�ݒ肳�ꂽ�u���[�L���i�p�b�h�����[�^�[�ɉ�������́j��������܂��B
> ����́A�d�ʂ̑召�ɊW�Ȃ����ł��B
����������I�ɔF�����Ȃ�ł���
���炩���ߐݒ肳�ꂽ�u���[�L���Ƃ��Ȃ���ł�����
�����ԍ��F25937565
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
��R�E��t�E(mg) = r�E��b�EB�ES �c(8)
���������Ƃ̊W�͂���������m�F���������B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25923955/#25931647
d = (1/2)�E(m�Ev0^2) / (��t�Em�Eg)
d1 = (1/2)�E(R / r)�E(m�Ev0^2) / (��b�EB�ES)
�id�F���������A��t�F�^�C���ƘH�ʂ̖��C�W���Ad1�F�u���[�L��B�̎��̐��������j
��L(8)�̎����������鎞�Ad = d1 �ƂȂ�A�ő吧���͂ƂȂ�܂��B
���P�A�u���[�L�̖��C�M�̓u���[�L���̋����ŕς���ˁB
���Q�A�`�a�r�������Ȃ����ʂ̃u���[�L���O�ł̓u���[�L���͓��ݕ�(���݂̋���)�ł����܂��ˁB
����L�̂P�A�Q�A�͏�������ς���Ă��A��������������܂���ˁB
�͂��B�����ł��B
���}�u���[�L���͂`�a�r�����삵�āA�ݒ肳�ꂽ�u���[�L���i�p�b�h�����[�^�[�ɉ�������́j��������܂��B
������́A�d�ʂ̑召�ɊW�Ȃ����ł��B
�������B�Ⴂ�܂��B
�d�ʂ��d������ABS�쓮���̃u���[�L���͑傫���Ȃ�܂��B
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25932232/#25937400
���̗��R��������邽�߂̌��t�͂����ɏ������ȏ�̂��̂��������킹�Ă���܂���B
�\�������܂���B
�����ԍ��F25937566�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�W�Ȃ��b�ł����E�E�E
�́A�z���_��ALB�i�A���`�E���b�N�E�u���[�L�j�ƌ����Ă�
�ł��A��ʓI�ȉf���ł́A��ʘH�ŁA���b�N�ƊJ�����J��Ԃ��Ă����̂ŁA�ǂ����A���`�E���b�N��˂�E�E�E�ƃc�b�R�~�����������E�E�E
���ʂ�ABS�ƌ����Ă��Ƃ�����A�J�^�J�i�ǂ݂ł́A�A���`���b�N�u���[�L�V�X�e���Ȃ̂��A�A���`�X�L�b�h�u���[�L�V�X�e���Ȃ̂��A����ӂ₾����
�O�X���`���̓���ŁA�h���C�H�ʂ����ǁA��������A���`���b�N�ɂȂ��ĂāA30�N�̎��Ԃ́A�����߂�����������Ȃ��ȁE�E�E�ƁA�����̔F�����A�b�v�f�[�g�����Ă��������܂���
�����ԍ��F25937576
![]() 1�_
1�_
> �}�u���[�L���͂`�a�r�����삵�āA�ݒ肳�ꂽ�u���[�L���i�p�b�h�����[�^�[�ɉ�������́j��������܂��B
> ����́A�d�ʂ̑召�ɊW�Ȃ����ł��B
���������̂悤��ABS�̐v��������A��~���[�H�ł͂����Ƀ��b�N�A�b�v���邵�A�n�C�O���b�v�^�C���𗚂��Ă����������ɐ��������͕ς��Ȃ����ƂɂȂ�܂����A���������悤�ɉו���ς߂ΐςނقǐ��������͐L�т����ł�
���b�N�A�b�v����܂ł͈������߂Ă����A���b�N�A�b�v�����o����Ίɂ߂�Ƃ����t�B�[�h�o�b�N���䂾���炱���A������ɉ������u���[�L�œK�Ȑ��䂪�ł��Ă���̂ł���
�����ԍ��F25937615
![]() 2�_
2�_
���������������炢�ł�����
ABS�́A�ݒ肳�ꂽ���̋����Ńp�b�h�������t���A���b�N������A�ɂ߁A���b�N������A�܂����������Ńp�b�h�������t����Ƃ���������u���ɌJ��Ԃ��Ă���Ă���Ɨ������Ă܂����A�����ł͂Ȃ��A���̉ߒ��ʼn����t���������̂��̂�ς��Ă���Ƃ����A�Ȃɂ��؋��ɂȂ镶��������܂�����A�������Ē�������[���ł���̂ł����B
�����ԍ��F25937648�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�����̉ߒ��ʼn����t���������̂��̂�ς��Ă���Ƃ����A�Ȃɂ��؋��ɂȂ镶��������܂�����A�������Ē�������[���ł���̂ł����B
���y��ʏȂ̎����ł��B
�u�Z���T�[�����m���ău���[�L�����œK�ɂ���B�v�Ƃ̂��Ƃł��B
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/02safetydevice/abs.html
�����ԍ��F25937660
![]() 2�_
2�_
�`�a�r�ɂ��F�X���邩������Ȃ�����
��{�̓��b�N������ɂ߂�O���b�v������ɂ߂�̂���߂���Ďd�g�݂��Ǝv���܂�
�������Ƃ���
�̎Q�Ɛ�ł�
�}�u���[�L�����������ȂǂɃ^�C�������b�N�i��]���~�܂邱�Ɓj����̂�h�����Ƃɂ��A�ԗ��̐i�s�����̈��萫��ۂ��A�܂��A�n���h������ŏ�Q��������ł���\�������߂鑕�u�ł�
�݂����ł�
����
�ŋ߂̃��b�N�������O�ŁE�E�E�����ۂ͔����b�N�i���傢����j�̌��m���Ǝv���܂�
�����ԍ��F25937667
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���v�]�̓��e�����邩������܂��A�Q�l�C���[�W�Ƃ��āE�E�E
https://www.honda.co.jp/factbook/motor/technology/19950900/006.html
�����܂ŁA�킽�����l�I�ɂ́A�Ȃ�ƂȂ��̃C���[�W�����₷�����ŁE�E�E
���ꂪ�_���Ƃ��ɂȂ�ƁA�킽�����A�����T�b�p���Ȃ̂ŁA���[�J�[�̃y�[�W�ɂ��܂������A�T���A����Ȃ�ɐF�X���肻���ł�
�O�ɂ����������܂������A����ς菃���ȃt�B�[�h�o�b�N����ł͂Ȃ��A���O�}�b�s���O�����ĂāA�\�����������Ă�݂����ł���
�����ԍ��F25937674
![]() 0�_
0�_
��
30�N�O�̘b�ł���
�����ԍ��F25937676
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
> ABS�́A�ݒ肳�ꂽ���̋����Ńp�b�h�������t���A
�w�ݒ肳�ꂽ���̋����Łx�Ƃ����̂��M���l�̎v�����݂Ȃ�ł���
����������̂̓u���[�L�y�_���ރh���C�o�[�i��ABS�ł͂Ȃ��j
�������̂�ABS
���������������S�ł�
�h���C�o�[���ł���̂̓u���[�L�y�_�����������ݑ����邱�Ƃ���
���Ƃ�ABS���K�Ɋɂ߂Ă����̂ł�
�����ԍ��F25937680
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
ABS�i�A���`�X�L�b�h�u���[�L�V�X�e���j�̑S�Ă��i��̂��R���g���[�����j�b�g�ŁA�\���m�C�h�o���u���ɐ��䂵�A�t���[�h��������B
https://www.goo-net.com/magazine/carmaintenance/repair/216657/
�Ƃ������ƂȂ̂ŁA�����t���������̂��̂�ς��Ă��܂��ˁB
�����ԍ��F25937687
![]() 0�_
0�_
���́A�z���_��ALB�i�A���`�E���b�N�E�u���[�L�j�ƌ����Ă�
�́@�h�}�[�j�SWDABS�S���҇E���k�C���e�X�g�R�[�X��
�A���`�@�u���[�L�@�V�X�e���@�ɂȂ����Əł��Ă��B
�������ʂ����ςɂȂ����炵��
�����ԍ��F25937709
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�������̂́A�z���_�̓�ւł���
�l�ւł́A�Ȃ��Ȃ�������Ă����؋��݂����Ȃ̂́A�o�Ă��Ȃ��ł���
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/yamaha-motor-life/2011/11/post-89.html
������A���}�n�̓�ւł����E�E�E
�����ɁA���u�����I���v�u�����I�t�v��2���[�h�I���̏]��������A���i�K�ɖ����������\�ȃ��j�A����ABS�𓋍ځE�E�E�Ƃ���܂��̂ŁA�����炭�A���ǂ��́A�l�ւł����ʂɍ̗p����Ă���ƁA�����������܂�
�܂���ւł́A���b�N���Ă��܂��ƁA�Z���Ԃł��]�|�̊댯���傫���Ȃ�܂�����E�E�E
�����ԍ��F25937712
![]() 0�_
0�_
���Ђ�N�Ђ�N����
�y�����l�^�A���肪�Ƃ��������܂�
�����ԍ��F25937714
![]() 0�_
0�_
�������Ƃ���
���[��B
���̎����ł́A�c�O�Ȃ���AABS���u���[�L�̃I���I�t���u���ɌJ��Ԃ��Ȃ��ŁA������ς��Ă�����̂��́A�s���̂悤�ȁB
�����ԍ��F25937716�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���������������炢�ł�����
���₢��A�}�����߂Ό��ABS�̎�������Ɉς˂邱�ƂɂȂ�AABS�͂��̃u���[�L�\�͂��ő�Ɏg���A�ŏ��̐��������ɂȂ�悤�ɐ��䂵�܂���ˁB
�����܂ł́A������O�̘b���B
�ŁAABS���쒆�Ƀp�b�h�����t���͂������ŕς��Ă���Ƃ��������́H�H�H
�����ԍ��F25937723�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�������Ƃ���
�Q�l�T�C�g�ł�
���b�N���ԗ֑��Z���T�[�Ō��m���A���b�N���Ă���ԗւ̃u���[�L�t������߁A�H�ʂƂ̃O���b�v��������Ƃ����̂���{�������B���̍쓮�͈��݂̂ł͂Ȃ��A�d�q����ɂ���āA���b�N�����������܂ōs����B
�Ƃ̋L�ڂ�����܂�
��{�̓��b�N���ɂ߂�߂��̌J��Ԃ��Ŋɂ߂��������������ł������ɂ��ǂ邾���Ō���苭���͂��Ȃ��ł��傤��
�����ԍ��F25937725
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
�Ƃ������Ƃ͋����͈��Ƃ����ƂȂ�ł����ˁB
�����ԍ��F25937734�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�i�C�g�G���W�F������̒m�肽�����͂��ꂩ�ȁH
https://www.denso-ten.com/jp/technicalreview/jp_pdf/19/19-5J.pdf
�X���b�v����10-20%�ɃR���g���[������悤�ɐ��䂵�Ă��邻���ł�������ł͖����ł��傤�ˁB
�����ԍ��F25937745
![]() 0�_
0�_
ABS�̓Z���T�[�Ŏԑ��ƃ^�C����]���ɂ���āA���A���^�C������Ń��b�N������u���[�L����߁A���b�N��������A�܂����̋����Ńu���[�L�������邱�Ƃ��u��(���A���^�C��)�ŌJ��Ԃ��Ă���ɉ߂����A�u���[�L�̋����܂ŕς��Ă͂��Ȃ��ł���B
�Ƃ����̂��l�̎咣�B
���₻������Ȃ��A�|���s���O�����łȂ��u���[�L�̋������ς��Ă���Ƃ����Ȃ�A���̍����������ĉ������ƌ����Ă��܂��B
�����ԍ��F25937753�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����R��EVO����
�X���b�v��10�`20���ɐݒ�Ƃ����̂́A�����Ȃ�Z���T�[�̊��x�ł���ˁB
ABS�����쒆�Ƀu���[�L��(�p�b�h�������t�����)��ς��Ă��邩�ǂ����͕s���̂悤�ȁB
�����ԍ��F25937763�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�̂�ABS�R���s���[�^�[�͔\�͂��Ⴍ��
�I�v�V������ABS��I������Ɓ@���A���f�B�X�N������܂����i�l�i�������j
���̓}�C�R�����͂́@�T���v�����O���[�g���グ����悤�ɂȂ���
�h�����̂܂܂ł�ABS���ł���悤�ɂȂ�܂���
�������ʎq���r�b�g�͏グ�Ă��Ȃ��̂�
���Ԓl���䂵�Ă邩�Ƃ�����Ɓ@�ہ@�Ȃ���
��������
�\���m�C�h�Ŗ������@�����ɐ��䂷���PWM�I�ȕ��ω������̂�
�ʂׁ[�[�[�Ɓ@�u���[�L�����ቺ���܂�
�����ԍ��F25937767
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
��ABS�����쒆�Ƀu���[�L��(�p�b�h�������t�����)��ς��Ă��邩�ǂ����͕s���̂悤�ȁB
�u���X�ɖ������グ�Đ����͂��ő�ɂȂ�X���b�v���փR���g���[������B�v
�Ƃ����L�q�����邩��A�u���[�L��(�p�b�h�������t�����)��ς��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
�s���̈����Ƃ���͖������āA���X�������œ��������ł��傤���B
�����ԍ��F25937783
![]() 1�_
1�_
�����b�N������u���[�L����߁A���b�N��������A�܂����̋����Ńu���[�L��������
���b�N�Ɏ��鈳���Ⴄ���Ƃ����ɂȂ����痝���ł���̂ł��傤���˂��B
�����ԍ��F25937784�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
>ABS�����쒆�Ƀu���[�L��(�p�b�h�������t�����)��ς��Ă��邩�ǂ����͕s���̂悤�ȁB
���ꂪ�`�a�r�̎d���Ŋɂ߂Ȃ��ƃ��b�N������
�ɂ߂Ă���̂͑��i�u���[�L�y��فj�łȂ��`�a�r���j�b�g
>���b�N�Ɏ��鈳���Ⴄ���Ƃ����ɂȂ����痝���ł���̂ł��傤���˂��B
����͂`�a�r�̎d������Ȃ���{���i�h���C�o�[�j�̎d��
�`�a�r�͓��͂̈������m����̂ł͂Ȃ��^�C���̃��b�N������m
�����ԍ��F25937798
![]() 1�_
1�_
������Ɓ@�S�ւ̗�͌�����܂���ł�����
�o�C�N�̗�݂͂���܂���
�|���v�͋��ʂȂ̂Ł@��ւ��Ƃ̈��͂ɍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B
�\���m�C�h�̊J���Ԃ͐���ł��܂��B
�����ԍ��F25937817
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
��̂Ђ�����̏�ɍڂ��āA�y�����Ă��ꍇ�i�y���ԁj�Ƌ����������Ă��ꍇ�i�d���ԁj�ŁA�ǂ��炪����₷���i���^�C�������b�N���₷���j�ł����H
�����ԍ��F25937824�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
> �ŁAABS���쒆�Ƀp�b�h�����t���͂������ŕς��Ă���Ƃ��������́H�H�H
�p�b�h�������t����̂�ABS�ł͂Ȃ��h���C�o�[�ł�����A�u���[�L�y�_���߂Γ��ނ����p�b�h�����t���͂͑����܂�
�������E������b�N�A�b�v
�Ȃ��A���E�͈��ł͂Ȃ��A�������ŕω����邱�Ƃ͑O�ɂ������܂���
�����h���̂�ABS�A�t���[�h�������ĉ����t���͂������܂�
ABS�̓u���[�L�{�̂ł͂Ȃ��ł��A�u���[�L���ɂ߂鑕�u�ł�
�����ăp�b�h�����t���͂̕ω��̓u���[�L�ޗ́i�l�ԁj�Ɗɂ߂�́iABS�j�̈����Z�̌��ʂł�
�����ԍ��F25937828
![]() 0�_
0�_
���� �ŁAABS���쒆�Ƀp�b�h�����t���͂������ŕς��Ă���Ƃ��������́H�H�H
���p�b�h�������t����̂�ABS�ł͂Ȃ��h���C�o�[�ł�����A�u���[�L�y�_���߂Γ��ނ����p�b�h�����t���͂͑����܂�
���������E������b�N�A�b�v
���Ȃ��A���E�͈��ł͂Ȃ��A�������ŕω����邱�Ƃ͑O�ɂ������܂���
�������h���̂�ABS�A�t���[�h�������ĉ����t���͂������܂�
��ABS�̓u���[�L�{�̂ł͂Ȃ��ł��A�u���[�L���ɂ߂鑕�u�ł�
�������ăp�b�h�����t���͂̕ω��̓u���[�L�ޗ́i�l�ԁj�Ɗɂ߂�́iABS�j�̈����Z�̌��ʂł�
�����ɂȂ��Ă��܂���ˁB
�p�j�b�N�u���[�L�i�}�u���[�L�j���́A�����ł����X���[�ł��A�v�������蓥���_�ŁA�����x�ȏ�̓��ݗ͂Ȃ�A�h���C�o�[�͂��̂܂ܓ��ݑ����邾���ŁA�Ԃ��~�߂铭��������̂͂`�a�r�̎d���ɂȂ�̂ŁA�����炻��ȏ�u���[�L��ł��p�b�h�̉������͕͂ς����܂���B
�ł`�a�r�͒�߂�ꂽ���̃u���[�L���Ń|���s���O���Ċɂ߂錳�̋����ɖ߂����A�Z���T�[�ɂ�胊�A���^�C���ōs���܂��B
�Ř_�_�͂`�a�r�̃|���s���O�Ŋɂ߂Ė߂����A���̋����ɖ߂��̂łȂ��A�`�a�r���u���[�L���������Œ�������Ƃ����̂��M���l�̎咣�ł���ˁB
������x�������܂��B
�P�A�`�a�r�쓮���ɃV�X�e�����u���[�L����ς��Ă���Ƃ��������́H
�Q�A�܂��A�ǂ̂悤�Ȑ���Ńu���[�L����ς��Ă���̂������������������B
�����ԍ��F25937875
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
���`�a�r�͒�߂�ꂽ���̃u���[�L���Ń|���s���O���Ċɂ߂錳�̋����ɖ߂����A�Z���T�[�ɂ�胊�A���^�C���ōs���܂��B
���̃u���[�L���Ń|���s���O����Ȃ�A�Z���T�[�́u�����v���m����̂ł����H
��̂Ђ�����̏�ɍڂ��āA�y�����Ă��ꍇ�i�y���ԁj�Ƌ����������Ă��ꍇ�i�d���ԁj�ŁA�ǂ��炪����₷���i���^�C�������b�N���₷���j�ł����H
�����ԍ��F25937891�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���i�C�g�G���W�F������
�킽�����A�Ȃ�̂�������H�E�E�E�ƁA�ǂ�Łi����A�ǂ߂��A�������������Łj���S������������܂��A�����̂��Q�l�ɂȂ�E�E�E
https://patents.google.com/patent/JP2007038764A/ja
�����ԍ��F25937896
![]() 0�_
0�_
�Z���T�[�͉�]�p�Z���T�[�����Ȃ��ł�
�����ԍ��F25937969
![]() 3�_
3�_
�������炢�̋����œ���ł���̏�ł͑��߂�ABS�������ė͂��A�������H�ʂł͍쓮���Ȃ��B
����͂܂�A�^�C���ƘH�ʂ̖��C�ɉ�����(�d���▀�C�W���ȂLj�،��o���Ȃ��Ă�)ABS���u���[�L�̋��������Ă���̂Ɠ����ȂƂ������Ƃ��A�i�v�ɕ�����Ȃ���ł��傤�˂��c�B
�����ԍ��F25937996�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 2�_
2�_
�̂́@�p���x���O�@�ŐU�����N�����܂�����
���݂�
��]�p�Z���T�[����@
�p���x��
�p�����x���v�Z��
�^�C���̍ō����C�͂��z����
�p�����x�����o�����ꍇ
�U�������܂��B
��ɕ���^�]���Z���T�[���ғ�����
�^�C����ʁi�ē~�j�ɂ�苖�e�����p�����x�l��
�X�V���Ă��܂��B�i�w�K�j
�����ԍ��F25938022
![]() 0�_
0�_
>�ł`�a�r�͒�߂�ꂽ���̃u���[�L���Ń|���s���O���Ċɂ߂錳�̋����ɖ߂�
�i�C�g�G���W�F�������ABS�t�����̓���̋L�����甲�����Ȃ��Ǝv���B
�m���ɑ�̂͂��ꂾ�����Ǝv�����ǁA���̃��X���������̒ʂ荡�͐��䂪�t�Ȃ�ł���B
�ɂ߂���A�i�K�I�ɋ������čs���̂ł��B
�u���b�N�X�������o����ƃA�N�`���G�[�^�[���쓮�����ăz�C�[���V�����_�[�̖�����������B���̌��ʁA�ԗ֑��x�����X���b�v������������B���̌�Ăя��X�ɖ������グ�Đ����͂��ő�ɂȂ�X���b�v���փR���g���[������B�v
�ƁA���̗l�ɏ����Ă���܂��B
���X�ɖ������グ��̂ł��B
�����ԍ��F25938023
![]() 0�_
0�_
���i�C�g�G���W�F������
�rABS�̓Z���T�[�Ŏԑ��ƃ^�C����]���ɂ���āA���A���^�C������Ń��b�N������u���[�L����߁A���b�N��������A�܂����̋����Ńu���[�L�������邱�Ƃ��u��(���A���^�C��)�ŌJ��Ԃ��Ă���ɉ߂����A
�u���[�L����߂��Ă킩���Ă��邶���
��肶��Ȃ���
���ޗ͈͂��ł��ɂ߂���x�����Ă���
���R��EVO����
�����グ����߂�(������)���_���猩������Ȃ���
���炵������߂����������猳���͏グ�Ȃ�����
��������ł��铥�͂�葝�₷���u�Ȃ�
ABS�ƃu���[�L�A�V�X�g���������u����
�����ԍ��F25938050
![]() 0�_
0�_
�\���m�C�h�Ŕ����ꂽ���͂́@
���̃V�[�P���X�Ń|���v�ɂ���[����܂��B
���̂Ƃ��̔��͂����ɓ`���܂��B
�����ԍ��F25938052
![]() 0�_
0�_
�݂Ȃ���@�����O�~��������@�Ȃ�����
�u�����������炢���ȁv����Ȃ���
�\���v���������ƌ��܂��傤
�����ԍ��F25938056
![]() 0�_
0�_
��gda_hisashi����
>�����グ����߂�(������)���_���猩������Ȃ���
>���炵������߂����������猳���͏グ�Ȃ�����
���A���^�C������ł�����A�H�ʂ̃ʂʼn����܂ŏオ�邩�͈Ⴄ�Ǝv���܂��B
�����܂�Ŋɂ�A������Ċ��������ɏo�Ă������オ��Ȃ�������_���ł�����B
�����ԍ��F25938057
![]() 1�_
1�_
> �����炻��ȏ�u���[�L��ł��p�b�h�̉������͕͂ς����܂���B
���ꂪ�i�ԑ��A�ԏd�A�H�ʏ�etc�j�ŕς����Ă̂��킽��������Ԍ����������Ƃ���
�i�C�g�G���W�F�����s�ςƂ��������p�b�h�̉����t���͉͂��Ō��܂�̂ł��傤���H
���������ē��Y�ԗ��̐v�Ƃ��Č��܂��Ă�����̂Ƃ��l���ł͂Ȃ��ł����H
�����^�C���ɑւ����琧���������ς��̂̓^�C�����[�J�[��CM�Ő�`����܂����A�Ȃ��Ȃ̂��������������Ă܂��H
�O���b�v���オ��Ɖ����悭�Ȃ�̂��H
> �Ř_�_�͂`�a�r�̃|���s���O�Ŋɂ߂Ė߂����A���̋����ɖ߂��̂łȂ��A�`�a�r���u���[�L���������Œ�������Ƃ����̂��M���l�̎咣�ł���ˁB
�ǂ����ꗂ��N�����̂��A�Ȃ����ɈႢ�܂����A�ꉞ���������܂��傤
> �P�A�`�a�r�쓮���ɃV�X�e�����u���[�L����ς��Ă���Ƃ��������́H
> �Q�A�܂��A�ǂ̂悤�Ȑ���Ńu���[�L����ς��Ă���̂������������������B
�����F�������Ă܂����A�������茾���܂���
�u���[�L���������Łi�h���C�o�[�̃R���g���[���Ȃ��Ɂj�ς���̂�ABS�Ƃ������̂ŁA���b�N���Z���T�[�Ō��o���Ĉ����ɂ߂Ă���
�Ƃ��������ł�
�����ԍ��F25938074
![]() 0�_
0�_
�����R��EVO����
>�u���b�N�X�������o����ƃA�N�`���G�[�^�[���쓮�����ăz�C�[���V�����_�[�̖�����������B���̌��ʁA�ԗ֑��x�����X���b�v������������B���̌�Ăя��X�ɖ������グ�Đ����͂��ő�ɂȂ�X���b�v���փR���g���[������B�v
ABS�̓�������ł��傤����A�����͗����ł��܂��B
�ł�����́A��l��Ԃ̎����t����Ԃ̎����A��������ɂȂ�̂ł́B
�����ł́A�����̐����͂��ő�ɂȂ�u���[�L�����ԏd�ɂ���ĕς�邩�ǂ������A���_�Ȃ�ł��B
ABS���u���[�L�������߂����߂�����J��Ԃ����A�ԏd���ς���Ă����̃u���[�L���ɖ߂��̂��l�̔F���ŁA�ԏd���ς��u���[�L�����̂��ς���Ƃ����ӌ��ɑ��āA���̍����ƁA���̐�����@��₤�Ă��܂��B
�����ԍ��F25938084�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>>�u���[�L�����ԏd�ɂ���ĕς�邩�ǂ������A���_�Ȃ�ł��B
��Ԑl���ɂ��X���b�v�̏��ς��̂�
�p���x�@�̔����@���p���x���ɂ₩�ɂȂ���
�����u���[�L�͂܂Ł@�U�����������܂���i���͂������Ȃ��j
�����ԍ��F25938085
![]() 0�_
0�_
×�@�����܂�Ŋɂ�A������Ċ��������ɏo�Ă������オ��Ȃ�������_���ł�����B
�Z�@�����܂�Ńu���[�L���ABS���쓮������A������Ċ��������ɏo�Ă������オ��Ȃ�������_���ł�����B
�����ԍ��F25938086
![]() 0�_
0�_
�Ȃ�ABS�̎d�g�݂̘b�Ɉڂ��Ă��܂��Ă܂����A�{���͂����ł͂���܂���
�ԏd���d�������������u���[�L����������Ƃ����_�ɂ�����ABS�����낤���Ȃ��낤���A���܂�W�Ȃ����Ƃł�
�����ԍ��F25938093
![]() 2�_
2�_
���i�C�g�G���W�F������
����l��Ԃ̎����t����Ԃ̎����A��������ɂȂ�̂ł́B
�������ł́A�����̐����͂��ő�ɂȂ�u���[�L�����ԏd�ɂ���ĕς�邩�ǂ������A���_
���ݍ������A��̃P�[�X�Ƃ���ABS���쓮���鈳������Ƃ���ƁA
��l��Ԃ̎����t����Ԃ̎��̕����u���[�L���͍����iABS�̍쓮�J�n���x���j�ł��傤�ˁB�Ȃ�����ABS���ő�Ɉ�������Ԃ̈����A�t����Ԏ��̕��������ł��傤�B����́A�u�d������v�ł��B
��̂Ђ�����̏�ɍڂ��āA�y�����Ă��ꍇ�i�y���ԁj�Ƌ����������Ă��ꍇ�i�d���ԁj�ŁA�ǂ��炪����₷���i���^�C�������b�N���₷���j�ł����H
�����ԍ��F25938098�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�����ԁi�{�́j�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2025/11/17 19:13:09 | |
| 0 | 2025/11/17 18:52:28 | |
| 0 | 2025/11/17 16:57:31 | |
| 1 | 2025/11/17 19:01:40 | |
| 1 | 2025/11/17 17:53:49 | |
| 2 | 2025/11/17 15:30:36 | |
| 13 | 2025/11/17 18:34:23 | |
| 14 | 2025/11/17 19:06:07 | |
| 3 | 2025/11/17 10:24:44 | |
| 2 | 2025/11/17 7:52:10 |
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�y�~�������̃��X�g�z200V�E�ߏ��g�[
-
�y�~�������̃��X�g�z����PC2025
-
�y�~�������̃��X�g�z�J�����{�����Y
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White CL Hydroshift II build
-
�y�~�������̃��X�g�zO11D mini v2 White SL no LCD build
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �m�[�g�p�\�R����������9�I�I �p�r�ʂ̃R�X�p�ŋ����f���y2025�N10���z

�m�[�g�p�\�R��
- �p�i�\�j�b�N �u���[���C���R�[�_�[�̂�������5�I�I ���S�Ҍ����̑I�ѕ�������y2025�N10���z

�u���[���C�EDVD���R�[�_�[
- �r���[�J�[�h �X�^���_�[�h��JRE CARD�̈Ⴂ�͉��H ��ׂĂ킩�����u���܂��g�����v

�N���W�b�g�J�[�h
�i�����ԁj
�����ԁi�{�́j
�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j