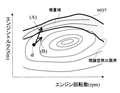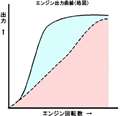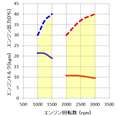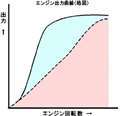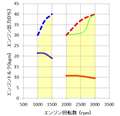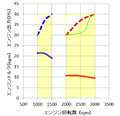�����ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B
�@(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)
�ȑO�A�����͂�ō����ɉe�����傫���̂̓G���W���̃g���N���o�͂��H�Ƃ����c�_������܂����B
�ǂ̂悤�Ɏ�������Ă����̂��q�����Ă���܂������A���������_�ɒH�蒅�����悤�ɂ́A���ɂ͌����܂���ł����B
�命���̕��X�͂���������Ă���悤�ł����A�������Ă����������������悤�ł��B
�@(�ǂ����ďo�͂��ƒf��ł���́H�ƕ����ꂽ��A���ɓI�ɂ́u�o�͂Ƃ́A���̂��Ƃ�\���P�ʂ�����v�ɂȂ��Ă��܂��̂ł����B)
�������A�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��B
�ł��̂ŁA�G���W������������g���N�̑召���ڈ��ƂȂ�ꍇ�u���v���X����܂��B
�@(���p����Ă���JAF�̃R�����g���A��ʓI�ȃh���C�o�[�ɑ��Ă͍����Ă��܂��B)
�ŋ߂͂��܂茩��@��Ȃ��Ȃ�܂������A�h���s���\�Ȑ��h����Ԕ���₷���Ǝv���܂��B
�@(�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��̂��Ƃł͂���܂���B�̂̓J�^���O�̌��̕��ɍڂ��Ă��܂����B�O�O��Ώo�Ă���Ǝv���܂��B)
�����͎ԑ��ŁA�e�M�����Ƃ̋쓮�̓J�[�u�A�e�M�����Ƃ̃G���W����]���A�e���z���Ƃ̑��s��R�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���}�ł��B
�ׂ̃M���Ƌ쓮�̓J�[�u���d�Ȃ��Ă��镔���ŁA�쓮�͂��傫�����̃M����I�����Ă����A���̎Ԃōō��̉����ƂȂ�܂��B
�@(�{���̌����́A�G���W���g���N�̉ߓn�����A�C�i�[�V���A���̑����낢��Ȃ��Ƃ��e�����܂����A�����ł͏ȗ����܂��B)
�쓮�̓J�[�u�́A�G���W���̃g���N�J�[�u�Ƒ����`�ł����A�M����ɂ��c�ɐL�т���A���ɐL�т��肵�܂��B
�ǂ̎ԑ�(�G���W����]��)�Ŏ��̃M���Ɉڂ�쓮�͂��傫���̂��́A���̃M����Ƃ̊W�Ō��܂�܂��B
���낢��ȑ��s���\�Ȑ��������Ŋm�F���Ă݂�Δ���܂����A�ō��o�͉�]������O�ŃV�t�g�A�b�v�ƂȂ邱�Ƃ͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�A���̎ԑ��ōő�̋쓮�͂���̂́A�G���W�����ō��o�͂����Ă����Ԃ�����ł��B
CVT�Ȃ�A�G���W�����ō��o�͉�]���ɃL�[�v�����܂ԑ���ω��������܂����A
�L�i�ϑ��ł́u�������Ȃ��v�ō��o�͉�]���O��̏o�͂̒Ⴂ�G���W����]�����g���Ă���̂ł��B
�܂��A���������������Ȃ����̂Ȃ��ɂ́A�u�쓮�͂�1�ԍ����̂̓G���W�����ő�g���N���o���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ����H�v��
�����邩���m��܂���B(�m���ɓ����M����ł͂����Ȃ�܂��B)
����₷����������܂��B
A�G
�G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm
B�G
�G���W����]��=3000rpm�A�G���W���̃g���N=5kgm�@(�o�́�21PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=3
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=15kgm
�o�͂������a�̕����A�����ԑ��ł͋쓮�͂������Ȃ�܂��B(�ǂ̑��x��z�肵�Ă��A���R�����ł��B)
�Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B
�M����ɂ���āA�G���W���g���N�̋쓮�́A�G���W����]���̎ԑ��@�̊W���ω����܂��B(������𗧂Ă�A�����炪������)
�����Ƃ����Ă悤�Ƃ���A�G���W���g���N�ƃG���W����]�����|�����킹�����l(���o��)����������K�v������܂��B
���Ȃ킿�A�u�o�͂Ƃ́A���̂��Ƃ�\���P�ʁv�ł��B
�G���W���̍ő�g���N��]���̕����A�ō��o�͉�]���������͂������̂́A
�����M���ŁA
�G���W���̍ő�g���N��]���t�߂̉����͂ƁA�ō��o�͉�]���t��(���R�A�ԑ��͈Ⴄ)�̉����͂��A��r�����ꍇ�ł��B
(����ɉ��̈Ӗ�������̂��A���ɂ͔���܂��B)
����́A�u�G���W���̍ő�g���N�̍��������A�������x������������瑬���v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B
�]�k�ł����A�ǂ����āA
�G���W����]��(rpm)×�G���W���̃g���N(kgm)�^716.2�ŁA"�o�r"�Ƃ����P�ʂ̐��l���v�Z�ł���̂ł��傤���H
�@(�����Ă���l�Ȃ�A�����Ɛ����ł��锤�ł���B)
redswift����Akami.it.����A�����̂�������A����Ȃ���ł�낵���ł��傤���B
�@(���Ȃ����͂��̌��Ɋւ��āA�}�g���Ȓm�������������Ɣq���������܂����B)
�������炢�����܂����B
���i.com�̃N�`�R�~�̎�|�ɍ������ǂ�������܂��A���e�����Ă��������܂����B
�����ԍ��F19872641
![]() 14�_
14�_
�A�^�}�ǂ���ł���
���́A
�X�y�b�N�Ȃ��
������Ɖ����āA
�J�l�Ŕ������̂��Ǝv���Ă��B
�����ԍ��F19872708�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�Ȃ�قǁA�킩���I�I
�����ԍ��F19872750�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 4�_
4�_
�g���N�^�[�w�b�h�ŋ����H
�����ԍ��F19872846�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 3�_
3�_
�A�N�Z���S�J�ŘA���I�ɓ���������͂ƁA
�S�������̓p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ���������͂Ƃł�
�b���S�R�Ⴄ�Ǝv���̂ł����B
�O�҂͍ō��o�͂Ɉˑ����A��҂͍ő�g���N�Ɉˑ�����B�����I�ɂ͗��҂̃~�b�N�X�B
�������ꂾ���̘b�ł́H
�����ԍ��F19872884
![]() 11�_
11�_
���O�[�X350����
�i�C�X����Ƃ��܂����B
������̍�������������������Ə�����̂ł����E�E�E
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19856796/#tab
�����ԍ��F19872970
![]() 6�_
6�_
��LUCARIO����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�h�S�������̓p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ���������́h�ƌ����܂��̂́A
�M����̕ύX�Ȃ��ŁA�Ƃ������ł��傤���H
����Ȃ�A�쓮�ւ̃g���N���傫���̂́A�������G���W���g���N���傫�����ł��B
�u���ɃV�t�g�_�E�����ĉ�]�����グ���Ƃ��Ă��A�Ƃ������ł��傤���H
�V�t�g�_�E��������̉�]���ł̏o�͂̕���������A������̕����쓮�ւ̃g���N�͑傫���Ȃ�܂��B
�o�͂̓G���W���o���ł��A�쓮�ւł������ł��B(�`�B���X�������ꍇ)
�o�͂������Ƃ������́A�����ԑ�(�쓮�ւ̉�]��������)�Ȃ�A�쓮�͍͂����Ƃ������ł��B
�����ԍ��F19872984
![]() 3�_
3�_
>�p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃɓ����������
>��҂͍ő�g���N�Ɉˑ�����B
����A�p�[�V��������S�J�ɂ����u�Ԃ̃g���N�Ɉˑ����邾���ŁA���̎��ő�g���N�������邩�ǂ����͉�]�����悾�ˁB
���Ǎ���]�ō��g���N��������Α�p���[�Ȃ��B
�����ԍ��F19873037
![]() 1�_
1�_
�������v����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�����N�̃X���́A�^�[�{�����̕����u�����Ȃ�Ɨǂ��̂ɂȂ��`�v�Ɗ���Ă���X���ł���ˁB
���_���猾���܂��ƁA�u�J���҂łȂ���Δ���܂���B�v
�^�[�{���A�����łȂ����A�͎�i�ł����ĖړI�ł͂Ȃ�����ł��B
�ڕW�Ƃ���(���߂��Ă���)�A�������A�R��A���K���A�ϋv���A�������A�R�X�g�A�[���A���X��
�ǂ̂悤�Ȏd�l�Ȃ��ԓs���悭�B���ł���̂��H�Ƃ������ł��B
�^�[�{�ANA�o���Ō������Ă���Z�p�荞�߂A���������܂łɂ͂����Ȃ锤���A
�����炱�̃p�b�P�[�W�ōs�����I�ƁA���̒i�K�Ō��f����̂��H�ł����A
���̉�Ђ̌������ǂ̃��x���܂Ői��ł���̂��A
���̎Ԃ̔�����������t�Z���āA���J���X�y�b�N���i�荞�܂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂��A
����Ȃ̃}���钆�̃}����Ȃ̂ŁE�E�E�B
�܂��A����Ȏ��������܂��Ɩ��C�Ȃ��̂ŁA�I���͂����v���I����I���͂������I�Ƌc�_����̂́A�������낢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
(�����܂ŋc�_�ł���B�l�肠���ł͂Ȃ��āB)
�o�́E�g���N�̘b�͋c�_����b�ł͂Ȃ��ł����E�E�E�B
�����ԍ��F19873078
![]() 1�_
1�_
�O�[�X350����̓T�[�L�b�g�ł��������Ȃ�ł����ˁH
�T�[�L�b�g�����Ȃ�Ƃ������A��p�ԂɕK�v�Ȃ̂͏��q���ɒ��]�ő����Ă��Ԃ���X���[�Y�ɉ����ł��邩���d�������B
�����獂��]�ł̍ō��o�͂Ȃ���Ȃ��A���ᑬ�ł̃g���N���d�v�Ȃ�ȁB
�o���̈����^�[�{�Ȃ��ƁA�^�C�����O�����邩�猙����B
�����ԍ��F19873121�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 12�_
12�_
���O�[�X350����
���o�́E�g���N�̘b�͋c�_����b�ł͂Ȃ��ł����E�E�E�B
���̒ʂ�ł��ˁO�O
���L�̍��z�c����
�����ȏ������ł��ˁO�O
�o�͓����̖�肪�����肻���Ȃ̂ŁA���łɃ��X�͔@���ł��傤���H
�����ԍ��F19873133
![]() 2�_
2�_
��RGM079����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�Ⴆ�T�[�L�b�g�𑖂�����A�[������������A�S�͉�������ꍇ�͂Ƃ����Ӗ��ł��B
�u�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��v�̂ŁA
�������A�o�͂���������Ηǂ��Ƃ����C�̓T���T������܂���B
�����ԍ��F19873150
![]() 1�_
1�_
���O�[�X350����
�펞�A�N�Z���S�J�A�펞�p���[�o���h�L�[�v�Ȃ炻���Ȃ�ł��傤�ˁB�����Ɉ٘_�͂Ȃ��ł���B
�ł������ɂ́A�i�����͂������̂��ƃT�[�L�b�g�ł������j����ȖȂ��ł��傤�H�ƁB
�X���b�g��������Ԃ��瓥�ݍ��ރV�[�����K������B�Ƃ���������ȏ���ł��B
���̎��A�u�����́v�����E����͉̂����H
���̎��̉�]���ɂ�����ő�g���N(��)�ƁA���ݔ����Ă���g���N�Ƃ̍����A�����]�T�g���N�ł��ˁB
�������M����ŕς��b�ł����A�����ł͓��ꁕ�Œ聕�ƌ��ĉ������B
�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����
�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B
�����L�̍��z�c����
��ł͑�G�c�ɍő�g���N�Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂��܂������A���m�ɂ͌X�̉�]���ɂ�����WOT(wide open throttle)
�g���N�̈Ӗ��ŁA��܂��ɂ̓G���W�����̂̍ő�g���N�l�ɘA�����Ēl�̑召�����܂邾�낤�Ƃ����O��ł��B
����͑����傫���͊O���Ă��Ȃ��Ǝv���܂���B
�ȉ��͂��Q�l�ł��B
�Y�t�͓��Y�����Ԃ̓�������̈��p�ł��B
�}�����v�����ɗ]�T�g���N�̑召�ɂ���ĔR�Đ�����H�v���R������_�������̂ł����A�]�T�g���N���傫���ꍇ�ɂ�
�g���N�̗����オ�肪�����Ȃ�悤���䂳��Ă��܂��B
���̓_�̂ݐ�o�����ꍇ���u�ő�g���N���傫�������A�����͂������v�P�[�X�ɊY������̂ł́B
���Ƃ������Ԃ����Ⴏ�A�O�������������ƌ��߂Ęb������Ζ������鎖���Ȃ��i���nj��߂��ɂ�邩��O�_�O�_������j�̂ł́H
���Ƃ����������������킯�ł����B�u�������Ĉ���Ɍ������ǂ����v�A�Ƃ����b�ł��B
�����ԍ��F19873252
![]() 3�_
3�_
��LUCARIO����
�����Ԃ���A�M���Œ�ŃA�N�Z���S�J�ɂ���A
���̃G���W����]���ł̑S���׃g���N�ɂȂ�A
�]�肵�����̋쓮�͂ʼn������Ă����A�Ƃ������ł���ˁH
�������ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����
���ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B
�����쓮�n�Ƃ������́A���̎ԑ��ł͓����G���W����]���Ƃ������ł��ˁH
����Ȃ�A�A�N�Z���ݍ��Ƃ��ɏo����G���W���̃g���N�����������A�쓮�͂������Ɍ��܂��Ă��܂��B
(���R�A������̕����o�͂������ł��B)
�h�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W���h�Ȃ�A�����ԑ��Ȃ�A1�����N�傫�ȃM�����I���ł��܂���ˁH
�ł��̂ŁA�G���W����]���ƃG���W���g���N�̐ςł���o�͂̒l�ŁA�쓮��(������)�͌��܂�A�Ɛ\���グ�Ă���̂ł��B
�M����������A�G���W����]���������Ȃ�A���R�A�G���W���g���N�����������A�쓮��(������)�͍����ł��B�o�͂������ł��B
�����ԍ��F19873280
![]() 0�_
0�_
�F�������̂ł��������N���Ă�̂ł��傤���H
1.���@��:�^���̕ω��i�����x�j��F=ma�@by�j���[�g���i���w�������j
2.1.�̓G���W���̃g���N��o�͂ł͖����A�쓮�ւ̃^�C���ɓ`���g���N����ˁ@by�O�[�X350����
3.�����g���NTa�mN�Em�n�́A�p�[�V��������L�������̃g���N������ˁ@�L�̍��z�c����
4.�A�N�Z���J�x�ŕς������g���N�̕ϓ��͏o���̈����^�[�{���ƃt�B�[�����O������ˁ@RGM079����
5.���x�ێ��͑S�J�ł͖����A�p�[�V�����i�K���J�x)�ʼn����x��0����ˁ@byLUCARIO����
�i6.���������@by���̑��̕��@�����s���j
�S�X���ʼn������������Ȍ��ɋ����Ă���������Ə�����܂�^^;
�����ԍ��F19873334
![]() 0�_
0�_
�������v����
�܂Ƃ߁A���肪�Ƃ��������܂��B
�S�͉����łȂ��ꍇ(�X���[�Y�ɉ�������ꍇ)�̓g���N���ƁA
LUCARIO����ARGM079����͂���������Ă���̂ł��傤���H
�������������悤���A�S�͂ʼn������悤���A�Ԃ̉����͂̑召�͏o�͂Ƃ������l�̑召�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
(�h�ō��o�́h�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A���̂Ƃ��ɃG���W�����o���Ă���o�́A�Ƃ����Ӗ��ł��B)
�G���W���͓����Ă���ȏ�A�����]���ʼn���Ă��܂��B
�����āA�g���N���������u�ԂɁA�o�͂����������Ă��܂��B
�ԑ����猩�܂��ƁA����ԏd�̕��̂��A����ԑ�����A�Ⴄ�ԑ��ɕω�������Ƃ������́A
�͂Ǝ��Ԃ̃t�@�N�^�[��ς���Ƃ������ł��̂ŁA���Ȃ킿�A�o�͂�ς���Ƃ������ł��B
�l�Ԃ̊��o���炵�܂��ƁA�g���N�̏o���Ƃ����܂����A����オ�肩���Ƃ����܂����A�A�N�Z���ւ̃c�L�Ƃ����܂����A
�\��������̂ł����A�����́h�A�N�Z���Ƃ��́A�o�͂̕ω��h�Ƃ������ɏW��܂��B
���鑬�x�ŃN���[�W���O���Ă����Ԃ���A��������������Ƃ�����ʂ��l���Ă݂܂��傤���B
�g�b�v�M�����낤���A���ԃM�����낤���A���̎Ԃ̎���͈͂ł���A�N�Z���̓��ݕ��ł����������������܂���ˁH
�h���鑬�x�ŃN���[�W���O���Ă����ԁh���g�b�v�M�����ƁA�G���W����1000rpm×5kgm���Ƃ��܂��ƁA
���ԃM���ł͗Ⴆ�A2000rpm×2.5kgm�ő����Ă���Ƃ������ł��B
�܂�A�G���W���g���N�̐��l�̑召�ł͂Ȃ��̂ł��B
�Ԃ𑖂点�Ă���̂́A���̂Ƃ��̏o�͂̐��l�̑召�Ȃ̂ł��B
�Ԃ̑��x���R���g���[������Ƃ������́A�쓮�ւ̏o��(���Ȃ킿�A�`�B���X���Ȃ��Ƃ���G���W���̏o��)��
�A�N�Z���ƕϑ��@���g���ăR���g���[������A�Ƃ������ł��B
(�ŋ߂͕ϑ��@�͂قƂ�ǎ����ł����E�E�E�B)
�����ԍ��F19873479
![]() 0�_
0�_
�������ĉ����咣�������̂�������ɂ����ł��B�K���͒����̑����ƊW������Ǝv���Ă���̂��ȁH
�����ԍ��F19873513
![]() 2�_
2�_
���S�͉����łȂ��ꍇ(�X���[�Y�ɉ�������ꍇ)�̓g���N���ƁA
��LUCARIO����ARGM079����͂���������Ă���̂ł��傤���H
�����A���������Ă�̂͑S��p�[�V��������̑S�͉����ł���B
�G���W���́A�����]���ʼn���Ă��鎞�ɕK���g���N�J�[�u����̃g���N���o���Ă���킯�łȂ��͎̂����ł���ˁB
����͂����܂ōő�l�ł�����B
�S��p�[�V��������WOT�g���N�Ɏ���܂ł̗����オ��̎��ԁA����Ɍ����Ȃ炻�̏u�Ԃɉ�]�����ˏオ�鑬�x�A
���ꂪ�����x�̎x�z�v���ɂȂ�Ƃ��������ł��B
����M����ł���A�G���W����]���̏㏸���x�i�N�����N���̊p�����x�j���N���}�̉����x�ɔ�Ⴗ��̂��܂������ł��̂ŁB
�����ԍ��F19873514
![]() 1�_
1�_
���~�X�^�[�H������
�K���́A�L���� [yen?] × ���荇�� [rpm] �A���Ȃ��B ���͉�]���ʼn҂��h�ł��i�j
�����ԍ��F19873559
![]() 1�_
1�_
��LUCARIO����
�����ł��ˁB
���{���̌����́A�G���W���g���N�̉ߓn�����A�C�i�[�V���A���̑����낢��Ȃ��Ƃ��e�����܂�
�̂ŁA
���S��p�[�V��������WOT�g���N�Ɏ���܂ł̗����オ��̎��ԁA����Ɍ����Ȃ炻�̏u�Ԃɉ�]�����ˏオ�鑬�x
�́A����Ԃő��肳�ꂽ�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��̃f�[�^�������Ă���A���s���\�Ȑ�����͔���܂���B
�����\���グ���������̂́A����������܂��Șb�ł��B
�u�����̓G���W���g���N�̐��l�Ō��܂�̂������������B�v�Ƃ��A
�uCVT�ōő�g���N��]�����ێ����ĉ���������A������Max���B�v�Ƃ����ӂ��Ɍ������Ă���������܂����̂ŁE�E�E�B
�����ԍ��F19873567
![]() 2�_
2�_
�������ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B
��(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)
���́u�����́v���ĕ\�����B�������疈���₱�����Ȃ�B
�E�O�|�P�O�O�ł͏��Ă邪�O�|�S�O�O�ł͕�����A��
�E�O�|�P�O�O�ł͕����邪�O�|�S�O�O�ł͏���B��
�����������ꍇ�ǂ����������͂��L��́H���ĂȂ�B
�����ĉ���蓖�Y��]���ɂ�����A�g���N�̔����ʂɂ���ďo�͂����E�����̂�����A�u�g���N���傫������������ǂ��v�Ƃ̕\���͕ʂɍ\��Ȃ��Ǝv����I�i���̂Ȃ��]������̏o�͂��オ��̂�����j
��������ȂɁA�u�o�͂��I�v�Ə���Ȃ����炨�������Ȃ�B
�����ԍ��F19873584
![]() 3�_
3�_
F�����u1��1���]�܂ł�������I�v
�����ԍ��F19873605�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��eoffice����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
�G���W����]���������ł���A
���g���N�̔����ʂɂ���ďo�͂����E�����̂�����A�u�g���N���傫������������ǂ��v�Ƃ̕\���͕ʂɍ\��Ȃ��Ǝv����I
�͂��A�\���I�ɂ͂���ł��ǂ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19873636
![]() 0�_
0�_
�������\���グ���������̂́A����������܂��Șb�ł��B
���u�����̓G���W���g���N�̐��l�Ō��܂�̂������������B�v�Ƃ��A
���uCVT�ōő�g���N��]�����ێ����ĉ���������A������Max���B�v�Ƃ����ӂ��Ɍ������Ă���������܂����̂ŁE�E�E�B
�Ȃ�قǁB���̃X���ł��̘_�ɌŎ����Ă���l�͒N�����܂���ˁB�������A�����܂߂āB
�������̕�������������̂ł�����A������Ă˂Ƃ��������悤���Ȃ��ł��B
�����ꂽ�玄������܂���B�Ԃ����Ⴏ���肵�Ă��Ȃ��̂ŁB
�����ԍ��F19873649
![]() 5�_
5�_
��LUCARIO����
�����ł��邾���ւ�肽���͂���܂���B
���̕��̔M�فH�ɘf�킳�ꂽ�������Ȃ���n�j�ł��B
�����ԍ��F19873682
![]() 4�_
4�_
>�����ɂ́A�����́A�ō����x�̗D��̓G���W���o�͂̑召�Ō��܂�܂��B
>(�������A�ԏd�Ȃǂ͓����Ƃ���)
���w�Z�ŋ�������悤�ȋC���E�E�E
�������x�ő����Ă��鎩�]�ԁB�i���x������������o�͓͂����j
�ᑬ�M�A�ő����ƃy�_�����y���B�i���Ȃ��g���N�ōςށj
�����M�A�ő����ƃy�_�����d���B�i�����g���N���K�v�j
����O�̘b���Ǝv�����ǂˁB
�y���y�_���i��g���N�j�ł��A
�����𑝂₹�i��]�����グ��j�A
�d���y�_���i���g���N�j�Ɠ����d���ʂɂȂ�B
�@��
�g���N�����ł͉������܂�Ȃ��B
�����ԍ��F19873987
![]() 5�_
5�_
>�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����
>�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B
�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W�����ڂ���Ȃ畁�ʂ͍ŏI�����䂭�炢�ς���̂Ŕ��I�ȃ��f���ł��ˁB
�Ⴆ�ő�g���N������20N��4000rpm�Ŕ�������G���W����5000rpm�Ŕ�������G���W�����ׂ�ƁA5000rpm�̕��������J�[�u�łQ���Ⴂ�M�����g���܂�����A�G���W���̃g���N�͓����ł��]�T�쓮�͂͂Q���傫���Ȃ�܂��B
���ǂ��ꂪ��o�͂��Ď��ł��ˁB
�ʏ�͂Q���o�͂��傫����P�����x�͍ō�����L�������Ɏg���̂ł���قǍ��������ɂ͂Ȃ�܂��A�o�͂��傫�������������L���Ȃȓ_�͓����܂���B
�����ԍ��F19874023
![]() 2�_
2�_
>�����ԏd�A�����쓮�n�̎ԗ��ɁA�g���N����������܂ʼn��Ȃ��G���W���ƁA�g���N�ׂ͍�����܂ʼn��G���W����
>�ڂ���ׂ��P�[�X��z�肵�ĖႦ��K���ł��B���łɌ����ƃV�t�g�`�F���W�ł��Ȃ��B
�����M�A�ŁA����]��z�肷�邩�Ō��ʂ��ς��܂���B
���ʂɍl���Ă݁B
�@1���̃[�����i�Ȃ�E�E�E
����]�܂ʼn��G���W���Ȃ��C�ɉ�������B
��܂ʼn��Ȃ��G���W���Ȃ�A���������Ƃ���ʼn����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
���������ɂȂ�Ȃ��ł��B
�A4���̃[�����i�Ȃ�E�E�E�i����Ȃ��Ƃ��Ȃ����ǁj
����]�܂ʼn��G���W���ł��A�{�̂������]���܂Ŏ����čs���Ȃ��̂ŁA
�������������ł��Ȃ��B
���i����ׂɂ́A���N���ŋ����ɉ�]�����グ�邵�����@�������B
�ᑬ�^�G���W���̕����A�܂����i���₷���ł��傤�ˁB
����������ɂȂ�Ȃ��ł��B
���āA
�����I�Ȃ̂́A�ǂ����ł��傤�H�i��
�����̎����Ԃ́A
�h���C�o�[�̈ӎv�œK�ȃM�A��I�ׂ�̂ŁA
�ō��o�͂������G���W���̕����������ǂ��Ȃ�܂��B
����O�̂��Ƃ����ǁE�E�E
�����ԍ��F19874096
![]() 3�_
3�_
����Ȏ��A�p�[�V�����A�n�[�t�X���b�g���Ȃ�Č����n�߂��猋�_�o����̂��B
���ŁA�ő�g���N��]�����A���̃M�A�ōő�g���N���ő���Ɏg�����߂��B
���ɂ́A�ő�o�͉�]���܂ʼnȂ������������ǂ��ꍇ���L��́B
���]�Ԃ����āA�M�A���グ�ďd����������A���������������������낤�B
�n���ȗ����悪�L��݂��������ǔ������낤�B
�����ԍ��F19874151
![]() 2�_
2�_
���A���̗���Ȃ�ł��˥��
�����͓���̂ŁA�Z�������Ƃ��܂�(^�^)�~~
��kakkurakin����
�ڍׂȒ������X�������҂�������܂����^^
���L�̍��z�c����
�A�X���[�g��2.0T��3.5�͔��I�ȃ��f���H
���ۂ�ۂ� �D����
S2000�͏����^�̕��������̂ł����H
�����ԍ��F19874238
![]() 1�_
1�_
���炵���X�����肪�Ƃ��������܂��B
�����͂��ߑ����̕����s�����Ȏv�������Ă��܂����̂œI�m��
�����Ă������������Ɗ��ӂ������܂��B
���߂Č������ɂ����ꂪ�킩��悤��
���̃X���̂��ƂɂȂ����̂�
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19833544/#tab
�M�����̂͂����ł���
�������t�i�n���A�z��A���j�͏����Ȃ��悤���肢�������܂�m(_ _)m
�����ԍ��F19874271
![]() 2�_
2�_
>�����v����
>S2000�͏����^�̕��������̂ł����H
�����P���ɂ͂����܂���B
AP2 �́AAP1 �̃f�B�`���[���łł͂Ȃ��āA
���ǔłł�����ˁB�r�C�ʂ��Ⴄ���B
���������A
�ǂ�����������B�E�E�E�ł����ˁB�i��
�����ԍ��F19874276
![]() 1�_
1�_
���ۂ�ۂ� �D����
���肪�Ƃ��������܂��B�ǂ����������̂ł���^^
pop5555����A�o�܂��킩��܂����B������܂��B
�N�`�R�~������HP�̂悤�ȕ��B������ʑ��l�͐킢�������ȊO�A���@�������̂ł��傤��^^
�����ԍ��F19874329
![]() 1�_
1�_
kakkurakin����
>�����ɉe�����傫���̓g���N���o�͂�
>���̓g���N���Ǝv���Ă��܂��B
2016/04/30 19:05�@[19833544]
�@
>�����o�͂ł��g���N�����������G���W����]�㏸���x�������̂ʼn����͗ǂ��B
2016/05/04 12:24�@[19844747]
�����͕ς��Ă��Ȃ��Ԃ��Ă͂��܂����A���e�Ƃ��Ắ��̃p�N���ɕϐ߂��Ă܂��ˁB
�ԏd�������x�̎ԓ��m�ʼn����ɐ�ΓI�ɉe�����傫���̂͏o�͂ł��B(�d���ʁ��o�͂͋`������ŏK������ˁH)
�g���N�͏o�͂������x�ł���Ήe��������x�ł��ˁB(�G���W���A�쓮�n�̊������[�����g�̉e���Ō����䂪�傫���Ɗ������[�����g���傫������Ղ��B)
2016/04/30 20:59�@[19833897]
�����ԍ��F19874354
![]() 1�_
1�_
�������ɁA��̃X������Ȃ��̂ɁA�邵�グ�͂ǂ����Ǝv���E�E�E�E
�X���傳��I�ɂ́A���̏ǂ��Ȃ́H
�����ԍ��F19874497
![]() 1�_
1�_
��eoffice����
�d���Ȃ���A�����܂Ŏ����o���Ȃ���Ύv�l�ł��Ȃ������A�`������ŏ\���Ƌ��Ă���ʁX�ł�����A���H���R�Ɣ��_�ł���킯���Ȃ��B
�����Ȃ�ƁA���̌f�������ӂ̊���Ă������āA��排��������J��Ԃ��ƌ����ᑭ�ȑR��i�ɑi����B
�����炨�����ȗ�����ꂪ��绂���B
�o�͂Ƃ̘_���I�A���͑S���Ȃ��ɂ�������炸�A�ӐM�I�ɂ����M���Ăċ^��Ȃ��Ƃ̊�Ȃȑԓx�͂ǂ����痈��̂��s�v�c�ł��B
�͂�������Ή����ł���킯���Ȃ��A�͊w�ȑO�̏펯�����ǂˁB
�|�������A�{���ɊԈ���Ă��B
�����ԍ��F19874726
![]() 2�_
2�_
�܂��`���������̔��[���A�u�p���[�E�F�C�g���V�I�ʼn������\�͌��܂邩�H�v���Ď��������悤�ȋC�����܂����ˁi���j
�����Ŏ������������L�̗l�Ȏ���
�E�O�|�P�O�O�ł͏��Ă邪�O�|�S�O�O�ł͕�����A��
�E�O�|�P�O�O�ł͕����邪�O�|�S�O�O�ł͏���B��
�uA�ԁF�ō��o�͂͗�邪�A�ő�g���N�͏�v
�uB�ԁF�ō��o�͂͏�A�ő�g���N�͗��v
�O�|�P�O�O�����Ō����A�Ԃ��D��Ă��邪�A�O�|�S�O�O�Ō����B�Ԃ��D��Ă���Ȃ�Ď�������A���ǂǂ������D��Ă���́H�ƂȂ����B
�E�݂���͍ŏI�I�ȏ��҂́AB�Ԃ�����u�ō��o�͂��傫��������]�^�v�̕����������ǂ��I�ƌ����B
�E�݂���͂O�|�P�O�O�܂łȂ�AA�Ԃ̕��������̂�����u�ő�g���N���傫�������g���N�^�v�̕��������͂��L��I�ƌ����B
����Ȏ��_�̑���ƌ��������܂ł̎��āB
�i���ꂪ���̔��[�j
�����ԍ��F19874783
![]() 1�_
1�_
�܂���Q���E���h�͎��Ԑ�ŁA�g���N�h�̎咣�ŏI����Ă��܂��܂�������ˁB
�g���N�h�́A�g���N���傫����ΒႢ��]���ł��\���ȁu�o�́v���o�邩��������ǂ������Ȃ̂ɁA�o�͂���]�����������ăg���N���Ǝ咣���A���̂��u�ő�o�́v�̘b�ƃS�`�������ɂ��邵�c
�p���[�h�́A�g���N���������Ă�����]�ŏ\���ȁu�o�́v������A�M���ʼn�]���ƃg���N���������ĕK�v�ȃg���N����������A�����G���W���P�̂̍ő�g���N�����Ō��܂��ł͖����Ɣ��_���Ă���̂Ɂc
����ς� Do-Do ���[�v�ł���B
�����ԍ��F19874852�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
���O�[�X350����
�ʔ����X���ł��ˁB
�����͐���������₷���[�������Ⴂ�܂����B
�Ȃ̂ɁA�ڂ������͗ǂ��킩��܂��A�����I�ɂ͉����ƍō����͏o�͂ɕK�������W���Ȃ��Ǝv����ł����ǂˁB
�Ȃ����H
���낢��ȏ�蕨�ɏ�������z�ł��B
���o�Ȃ̂ŁA�����ł̋�_��c�ɎQ���o���Ȃ��̂��c�O�ł����ǁB
�����ԍ��F19874917�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
��A�G
���G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1
���܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm
��B�G
���G���W����]��=3000rpm�A�G���W���̃g���N=5kgm�@(�o�́�21PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=3
���܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=15kgm
A�AB�ǂ���̉�����(�o���)�������̂ł��傤���H
���łɁA�lj��̂���ł����A
�a�̏�Ԃ����̃G���W���̍ō��o�͓_���Ƃ��܂��ƁA���̗�(�M���䁁3)�ȊO�ŁA
�쓮��1000rpm���̋쓮�͂�15kgm��荂������\�ł��傤���H
3000�������ȊO�̍ő�g���N�͂�����ł��\���܂���(�`���������Ă�OK)���A�ō��o�͂�3000�������Ƃ��܂��B
���̎�������A�h�ō��̉�����(�쓮��)�悤�Ƃ���̂ɁA�ō��o�͂��g��Ȃ���͂Ȃ��h�Ƃ�����������Ǝv���܂��B
�������M���ŁA
���G���W���̍ő�g���N��]���t�߂̉����͂ƁA�ō��o�͉�]���t��(���R�A�ԑ��͈Ⴄ)�̉�����
���r���悤�Ȃ�āA���Ă��܂���B
���ŗ����ł��Ȃ��̂Ȃ�A
�����낢��ȑ��s���\�Ȑ��������Ŋm�F���Ă݂��
�ǂ̉�]���ŃV�t�g�A�b�v����A���̎Ԃŋ쓮�͂���荂�����C���ŁA�Ȃ��Ă�����̂�����܂��B
�����ԍ��F19875012
![]() 0�_
0�_
>eoffice����
>�܂��`�ߋ��̂���肪�A���Ȃ̂ŁA���C�����͉���܂��B
�g���N�ʼn����x���v�Z����Ƃ������Ƃ́A
�G���W���g���N�����R������ G �Ɠ������ƍl���Ă����ł��傤�B�����ƁB
�G���W���g���N�͗͂ł�����A
���]�ԂŌ����A
�y�_���𑆂�1�̗͂ł����Ȃ��̂ŁA
�y�_���𑆂����|�����킹�Ȃ����Ƃɂ͈Ӗ��𐬂��Ȃ��ł��B
�y�_��������������ŁA
�d�͂̂悤�ɁA���`���Ɠ����́i�g���N�j���|���葱����̂Ȃ�A
����႟�g���N�����ʼn����x���v�Z�ł��܂����ǂˁB�i��
�����ԍ��F19875047
![]() 1�_
1�_
�����[�����[����
�ԐM���肪�Ƃ��������܂��B
���t���炸�Ő\����܂���B
�X�y�b�N�ōō��o�͂̒l�������G���W���Ȃ�A�ǂ�ȏꍇ�ł������͂������A�ƌ����Ă����ł͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�A��ɍō��o�͂��o���Ă����Ԃł��葱���邱�Ƃ́ACVT�����̂悤�ɐ���ł����Ȃ�����s�\������ł��B
�ō��o�͂̒l�������ۗ����č���(���ɂ����s�[�L�[��)�G���W���ł��ƁA��茰���ł��B
�����̏ꍇ�A���X�ō��o�͂��Ⴉ�낤���A�e�M���̎���͈͂̃g���N�������������X�|���X���ǂ��āA
�Ђ��Ă͉������ǂ�����������܂��B
��LUCARIO����A��eoffice������������e�̂��w�E�����������A�������Ă��������܂����B
�����ԍ��F19875074
![]() 2�_
2�_
�o�͂��̃g���N���̂��āA��r��P���ɂ���ׂɁA
�ԑ̂��ɂ��āA��C��R�A�]�����R�ȂǓ����ɂ��āA
�^�C���i�쓮���j�a�����ɂ���ƃ^�C���̏o�́��g���N����]���^�肪�����͂̍��B
��]���^�萔�͂ǂ���������A
������A�S�O�����^���˂W�O�����^���Ȃǂ��l������A
�o�͂��傫�����̃g���N�傫�����̂����Ȃ�_�c�łȂ��A
���g���N����]�^�G���W���Ƒ�g���N���]�^�G���W���̔�r
���̏o�́i�g���N�j���ǂꂾ���ێ��ł��邩�Ƃ��������݂��J�o�[����Ƃ��ł́H
����ɂ́A�M�A��A�M�A�i���A���i�����A�g���N�R���o�[�^�[��A���͓`�B�������ǂ��l���邩�ł�����A
�G���W���ɑ��āA�~�b�V�����`���i�{�f�t�j���ǂ��I�肷�邩�ɂȂ�̂��Ȃ�
�s�̎Ԃ́A�R�X�g�A���p�����傫���e�����܂����B
���ꂪ�A�[���˂S�O�O���ł��A�P�l�h�k�d�ł������������������߂邩�ƁB
�����ԍ��F19875293
![]() 0�_
0�_
�F����
���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B
(���̃G���W���̍ō��o�͂̐��l�ł͂Ȃ��A�g�p���Ă��邻�̂Ƃ��̏o��)
�E�쓮�ւ��n�ʂ��R���āA�Ԃ͑O�ɐi�ށB
�E�G���W������쓮�ւɗ͂�`�B����̂ɂ́A�e�R�̌����������B
�E�o�͂Ƃ́A��]���ƃg���N�̐ςł���B
����3�̎���m���Ă���A���̂��Ƃ����Ȃ�܂��B
�ł��̂ŁA�u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H
�Ƃ������Ƃɂ��ċc�_����Ă��A�H�w�I�ȗ������[�܂邾���ł��B
(����ȂƂ���ł��[�����[���������A�H�w����ǂ��������Ɨ��_���ĂāA�L�`���Ə����Ă���Ǝv���܂��B)
���������A�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��B
���ł��̂ŁA�G���W������������g���N�̑召���ڈ��ƂȂ�ꍇ�u���v���X����܂��B
��(���p����Ă���JAF�̃R�����g���A��ʓI�ȃh���C�o�[�ɑ��Ă͍����Ă��܂��B)
�����̎ԂŁA
�Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H
�Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H
�A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H
���X���c�_���鎖�́A�����̎Ԃւ̗�����[�߂邽�߂ɂ͈Ӗ�������Ǝv���܂��B
���A�u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B
�����ԍ��F19876260
![]() 1�_
1�_
���Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H
�e�X�̎Ԃ̋@�B�����y�э\����A�ł��傫�ȉ������s����̈�ŕϑ����Ă��邩��ł���A�S�Ăɂ����āu���_�̍œK�v���u�����̍ŏ�v�Ƃ͌���Ȃ��ׂɋN���蓾�錻�ہB�i�ϑ��Ƃ͎��̉������s�����߂̓��삾����j
���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H
�u�ō��o�́v�Ƃ̓N���}�̑����������w�W�ł���A�u�ő�g���N�v�̓N���}�̉����́A�Ƃ�킯�d�ʂ̂����ރN���}�����S��~��Ԃ��������Ԃɂ����Ă������߂̒�́i���G���W���o�͎��̉�]�́j�������w�W�ł�����̂ł��Bby JAF
��ʓI�ɎԂ��w������ꍇ�A���r�C�ʂ̕����������Ă����ꍇ��L�̂Q���傫�������A���\���ǂ��X��������ׁu�w�W�v�ɂȂ�ƌ������Ӗ������ł��B
���Ȃ݂Ɂu�����́������v�ƌ��������_�Ō��Ă��Ȃ��_������A��ʓI�ɂ��H�w�I�����I�ɂ��������������Ǝv���܂��B
���A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H
�E���_�ƌ����̋��Ԍ��ۂł��傤���ˁH
�����l���ē���̏������ł̒l�Ȃ̂ŁA���̏������ω�����Γ�����錋�ʂ��ς��܂��B
�̗̂l�ɃG���W���̕��ׂ����āA�@�B�I�ɋ쓮����Εω��͏��Ȃ��ł����A���s�Ԃ̖w�ǂ��d�q�������iMT�Ȃ̂Ɏ����u���b�s���O�܂ł���j�Ȃ̂ŁA������ӂ̐���̉���ɂ���Ă��ς��܂��B
�i���Z�n�Ԏ킾�ƃJ�b�g�A�E�g���������[�h���L��j
�����ԍ��F19876793
![]() 2�_
2�_
��eoffice����
���낢��ȗ��R�A���肪�Ƃ��������܂��B
���͂����ƒP���ɍl���Ă���܂����B
���Ȃ��ACVT�ԂőS�J��������ꍇ�A��ɍō��o�͂�����悤�ɂ͂ł��Ă��Ȃ��̂��H
�A�N�Z���S�J�ɂ����Ƃ��ɁA���̎�(�R���p�N�g�J�[�Ƃ��A�X�|�[�c�ԂƂ�)�ɋ��߂�������͂ɕK�v�ȏo�͂��o���A
�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă��邽�߂��Ǝv���Ă��܂��B
�����A���[�J�[���x�X�g�o�����X���Ǝv���Ă���̂ƁA�X�̏���҂Ƃ̍l���͈Ⴂ�܂��̂ŁA
���������������ǂ��ق����E�E�E�Ƃ��A����Ȃɉ����͂͂���Ȃ���������ƔR����E�E�E�Ƃ��́A�ǂ�ȎԂɂł�����Ǝv���܂��B
�����̗v���ɃW���X�g�t�B�b�g�̎Ԃ́A�Ȃ��Ȃ�����܂���˂��B
���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H
���]�Ńg���N��������������₷���Ƃ́A�F����������Ă�����Ǝv���܂��B
�����ɂ͏o�͂��K�v�Ȃ̂ŁA���̏o�͂��ǂ̃G���W����]�Ŕ���������̂��H�Ƃ������Ƃł����A
��]����ς����ɍs��(�A�N�Z�������A�g���N��������)�̂��A��ԃ��X�|���X���ǂ����炾�Ǝv���Ă��܂��B
������Ɖ��������������Ȃ̂ɁA��������1�����Ƃ��ĂȂ�Ėʓ|(������A/T�ł��ACVT�ł��u���ɂ͏o���Ȃ�)�Ȏ������Ȃ��Ă��A
���̃G���W����]���ŕK�v�ȋ쓮�͂�������Ȃ�A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����ɁA�쓮�͂����߂���̂͏o�͂����������Ƃ��Ă��A�M�����������ł��傫�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ŁA
���ɔ��i���ɂ̓G���W���g���N�̑召�����m���������ɂȂ�܂��B
���A�N�Z���ݍ���ł���A���ۂɑ��s���\�Ȑ��̋쓮�͂�������̂��x���Ԃ́A�Ȃ������Ȃ̂��H
�̂ɂ͂悭�����܂����h�^�[�{���O�h�́A���̓T�^�ł͂Ȃ��ł��傤���B
���͔R��̗D�揇�ʂ������������̂ŁA�t�@�~���[�J�[�Ȃǐ�ΓI�ȉ����͂�X�|���X�����߂��Ă��Ȃ��Ԏ�ł́A
�h���C�o�[���A�N�Z���ʂɓ������Ă��A�G���W���͊����ĉ������Ȃ�(���X�|���X�I�ɂ͈���)�悤�ɂ��Ă���̂ł�
�Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�����ԍ��F19876976
![]() 1�_
1�_
���Ȃ��AJAF�������Ă���悤�ȓ��e���A�h��ʓI�h�Ȃ̂��H
��ʓI�Ȏs�̎Ԃ̃G���W���̋��e��]���Ȃ�Ăǂ�������悤�Ȃ��̂ł�����A���̒��Ŕ�r����@�g���N���傫�����o�͂��傫���@�ƌ����Ă��قڊԈႢ����܂���ˁB
���{�̃��[�^�[�X�|�[�c�����c�̂Ƃ��Ă݂�ƁA���Ȃ�p���������ԈႢ�ł����B
�����ԍ��F19877064
![]() 1�_
1�_
���O�[�X350����
���A�N�Z���S�J�ɂ����Ƃ��ɁA���̎�(�R���p�N�g�J�[�Ƃ��A�X�|�[�c�ԂƂ�)�ɋ��߂�������͂ɕK�v�ȏo�͂��o���A
�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă��邽�߂��Ǝv���Ă��܂��B
����͂��A����Ǝv���܂���I
���ɃR���p�N�g�J�[�Ȃ́A�X�y�b�N�ł͍������Ă���̂ɂ��S�炸�A�O�|�P�O�Okm/h�����Ȃł͑�̂P�Q�b��ɂȂ��Ă܂�����ˁi�j
�v�͂��̒��x�̉���������A�����̓��H����͖��Ȃ��Ƃ������l���ł��ˁI
���Ȃ݂Ɏ����u�@�B�����y�э\����v�ƌ������Ӗ��̒��ŁA�����₷���̂������ł��ˁB
CVT�̏ꍇ�A���ɖ����Ǘ�������ō��o�͂܂ʼn��A��������P�O�O�Orpm���x�ŕϑ������邩�̈Ⴂ�ɂ��A��������M�ʂ͑傫���قȂ�܂��̂ŁA���̓_�̑Ë����L��܂��B�i���_�l�ōs���������ǁA��p�����p�̈׃n�[�h�������Ȃ��j
�s�̎Ԃō��������Đ����オ���Ă��钆�ŁA�L�b�N�_�E������x�ɖ����グ�Ă�����A�����I�Ɍ������ł�����ˁB
�܂��`���������������v��ƁA�u�o�ϐ��A�������A���K���A�R�X�g�Ȃǂ��ŗǂɂ��Ă���v�ɒʂ���̂�������܂���ˁi�j
�����ԍ��F19877135
![]() 1�_
1�_
��eoffice����
���肪�Ƃ��������܂��B
���ۂ�CVT�̃E�B�[�N�|�C���g���ɂ��ẮA�S�R�ڂ����Ȃ��̂ŕ��ɂȂ�܂��B
���܂���M/T�Ԃɏ���Ă���܂����A���̎�(�܂�������̘b�ł���)��CVT���Ȃ��`�Ɣ��R�ƍl���Ă���܂��̂ŁA
CVT�̎����A��������������[�߂����Ɗ����Ă��鍡�����̂���ł��B(��)
�����ԍ��F19877357
![]() 1�_
1�_
���O�[�X350����
CVT�͖������v�Ȃ̂ŁA������ӎs�̂���ɂ������ċC���g���Ă��܂��ˁB
�X�e�b�vAT���Ƒ����M�N�V���N���邾���ł����ACVT���ƃx���g������ł���v�[��������ł��Ȃ��Ȃ�܂�����B
�^�Ă̍������H��NA�y�ŁA�����������Ă���Ə��X�ɗ͂������Ȃ��Ă���ƌ�����������̂́A�������オ��S�����ቺ���鎖�Ńv�[���̋��ݍ��݂��Â��Ȃ�̂������ł��B
�����̎�(�܂�������̘b�ł���)��CVT���Ȃ��`�Ɣ��R�ƍl���Ă���܂��̂�
�ł��O�Ԃ�MT�Ԃ̕��́A���iAT��DCT����Ȃ��Ɩ����ł��Ȃ������ł��B
��������Ńt�@�[�X�g�J�[�́A�W���X�|�[�cAT�ł��i�j
�����ԍ��F19877821
![]() 1�_
1�_
���O�[�X350����
�̉���O���i�⓮�̓e�X�g�ǂ͂��̒ʂ�
������n�͂Ō��܂�
�S�����̒ʂ�
�e�|�P�ł��h���C�o�[�́h���A�p���[�h���Č����܂����
�g���N�h�̕������̕ӂ͏��m�ł��̏ꍇ�ł��n�͂��������Ă��g���N��������Α���
�Ȃ�Ďv���Ă�����͂قƂ�ǂ��Ȃ���Ȃ���
�F�����m�̒ʂ�g���N����]���ʼn҂��n�͂ɂȂ�܂����
�g���N���������͑������Ȃ��Ƃ����]���𑝂₵�n�͂��������ł����
������g���N�����Ȃ��n�͂������d�^�f�͍���]�Ŕn�͂��o����
�M���������ɂ���Ηǂ��ł����^����ꂽ�T�Ƃ��U�Ƃ��i�V�ł��ǂ����ǁj
�Ŏ���͈͂����荂��]�^�̂d�^�f�̕����ō��o�͂��M����ύX������
���̃M���ł̉�]�������݂��傫���e�M�������������g���N���������肾���Ȃ�����
���̕��������Ēx���i�����Ȃ��j�ƌ����̂ł͂Ȃ��ł��傤��
�����P�P�T�g�o�ł�
�l�̂s�d�|�V�P�͗F�l�̂c�a�^�t�@�~���A�^�[�{�Ɖ���O�|�S�O�O�i���i�����j�̋��������Ă�
�Ԃ��������Ă��܂���
�s�d�|�V�P�@�@�P�P�T�����F�P�S�D�T����/��
�c�a�@�@�@�@�@�P�P�T�����F�P�X����/��
�ܘ_�M����A�ԏd�A�쓮�������Ⴂ�͂���܂���
�S�����������Ȃ������L��������܂�
�ō��o�͎��ȊO�̒��Ԓn�_�ƃg���N�������ɂ͂��Ȃ�d�v���Ǝv���܂�
�f�b�C���v���b�T��G�{�Q�C�R�C�S���炢�̎�������ۂ̍��������[��W���J�[�i�[�i���̌�̂r�ς��H�j
�ō��o�͂�ԏd���߂����҂ł����ԃg���N�����������G�{�̕������₷��
���ʂ��c���Ă����悤�ȁE�E�E
�n�͔h�ƃg���N�h�ł͐��\�̌����̐��肪�Ⴄ��Ȃ����ȂƎv���܂�
�����ԍ��F19879385
![]() 0�_
0�_
>gda_hisashi����
>�����P�P�T�g�o�ł�
>�l�̂s�d�|�V�P�͗F�l�̂c�a�^�t�@�~���A�^�[�{�Ɖ���O�|�S�O�O�i���i�����j�̋��������Ă��Ԃ��������Ă��܂���
���ꂱ��
�o�͂��Ⴄ��ł���B
�ō��o�͂́A�����܂œ����]���ł̏o�͂ł��B
�ō��o�͂��������Ă��Ȃ���]��ł́A
�ߋ���t�G���W���̏o�͂������Ȃ��ł��B
�ܘ_�A�g���N�������Ȃ��Ă��܂���B
�o�͂̓g���N�Ɖ�]�����|�����킹�����̂ł�����ˁB
�Ⴆ�A
���\�Ȑ��̏o�͂������o���āi�g���N�Ȑ��͏����āj
2000��]��6000��]�̈ʒu�ɏc���������Ă݂�B
��������ƁA
�Ȑ��Əc���̓����̖ʐς����ۂ̐��\�ɂȂ�܂��B
�G�ŕ`���Ȃ��ƕ�����h�����ǁE�E�E�i��
�g���N���������Ă��Ӗ��������̂ŁA
�������̂��ƌ���̂��~�߂�C�C��ł���B
�o�͌v�Z�̒��Ƀg���N�������Ă��܂�����ˁB
�����ԍ��F19879492
![]() 1�_
1�_
>�ō��o�͂́A�����܂œ����]���ł̏o�͂ł��B
>�ō��o�͂��������Ă��Ȃ���]��ł́A
>�ߋ���t�G���W���̏o�͂������Ȃ��ł��B
>�ܘ_�A�g���N�������Ȃ��Ă��܂���B
>�o�͂̓g���N�Ɖ�]�����|�����킹�����̂ł�����ˁB
�p���[�i�n�́j�Ȑ��͂ǂ̂悤�ȃG���W���ł������̈Ⴂ�͂����Ă���]���ɂ�蒼���I�ɐL�т܂����
�i�ܘ_�����I�������葽���ӂ���݂��������肵�܂����j
���Ԃł̈Ⴂ�̓g���N�̕����傫���ł����
�g���N�h�̕��͂��̕ӂ������Ă���̂��Ǝv���܂���
�O�̔ł�
�n�͂��傫����������
�n�͂������Ȃ瓯��
�n�͂���������Βx��
�������ƂƎv���܂�
�n�͂��ō��n�͂Ǝg�����i���j�̔n�͂Ō������ς��̂ł��傤
�ō��n�͉͂�]���ʼn҂��܂������Ԉ�Ō�����
�g���N�̑傫�������̔n�͂��傫���ƂȂ��Ă��܂��Ǝv���܂�
�n�͂��傫���Ƃ͂��Ȃ�s���|�C���g�̃s�[�N�̏ꍇ������
�g���N���傫���Ƃ͂��̃s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�ɑ傫���ꍇ������
�i�t���b�g�n�͂̃G���W���Ȃ�Č����܂����ˁj
���̈Ⴂ���n�͔h�ƃg���N�h�ł̌����̈Ⴂ�ł�����Ǝv���܂�
�G���W���ȊO�̈Ⴂ��������
�s�d�|�V�P�Ƃ`�d�|�W�U
�P�P�T�����F�P�S�D�T����/��
�P�R�O�����F�P�T����/��
��
�g���N���O�D�T����/���傫���`�d�|�W�U�̕���
�������̃g���N���͏��Ȃ��i�����H�j�ł�
���ۑ���Ƃ`�d�|�W�U�̕������͐��\�I�ɂ���������
�i�ԏd���Ⴂ�͂���܂�����͂�n�͂������H�j
�́`���
�����ԍ��F19879538
![]() 0�_
0�_
>�n�͂��傫���Ƃ͂��Ȃ�s���|�C���g�̃s�[�N�̏ꍇ������
>�g���N���傫���Ƃ͂��̃s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�ɑ傫���ꍇ������
���A����A
�����������ۓI�Ȃ��Ƃ����������ƃL���������̂ŁA
�g���N��S�ďo�͂ɕϊ����Ă��܂��A
��ڗđR�A���ڔ�r���o�����ł����āB
�g���N�^�G���W���́A�s�[�N�O��̉�]���ł�����Ȃ�Ƀg���N���傫���B
�E�E�E�Ȃ�Č���Ȃ��ł����A
���̎��̃g���N×0.0014×�G���W����]���Ōv�Z����ς݂܂���B
���̃g���N�����ɂ����v�Z���ʂ��O���t�ɗ��Ƃ�����ł�����
�o�͋Ȑ��ɂȂ�܂��B
�������\�́A���̋Ȑ��̓����̖ʐςɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19879576
![]() 2�_
2�_
�y�̃^�[�{��NA���ׂ�ƁA
�ō��o�͂͑卷�������Ă��A
���ۂ̉����͂͑�Ⴂ�������肵�܂���ˁB
�g���N�����Ɍv�Z�����o�͋Ȑ�����������Ε�����Ղ��Ǝv���܂��B
�g���N�Ȃ�ĖY��Ă��܂��Ă����C�ł��B
�o�͂̒��Ƀg���N�������Ă��܂�����ˁB
���̃O���t����
�s���N�F�̖ʐς�NA�G���W���̐��\�ŁA
�s���N�F�̖ʐςɗΐF�̖ʐς𑫂������̂��A�^�[�{�̐��\�ɂȂ�܂��B
��������Ղ��l�ɋɒ[�ɏ����Ă���܂��B�O�̂��߁E�E�E
�ō��o�͂́A�^�[�{���`���b�ƍ��������Ȃ̂ɁA
�����ƍ����\�ɂȂ��Ă���̂����Ď���͂��ł��B
���̂悤��
�o�͋Ȑ������ŃO���t�Ə��������ĖʐςŔ�ׂ�ƁA
�ᑬ�g���N�^�ƍ��o�͌^�̓������킩��Ղ��Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19879625
![]() 3�_
3�_
���ۂ�ۂ� �D����
���̒ʂ�ł���
���̐��\�Ȑ��̏ꍇ�g���N�l���������Ńt���b�g�ɂȂ��Ă�����
�g���N�h�̕��͂��̂悤�Ȃd/�f�̏ꍇ�g���N���L��ƌ���
���R�n�͂�����
���Ҍ��Ǔ�������]�������ŁE�E�E
�g���N���傫���Ȃ�Ȃ��Ɣn�͂��傫���Ȃ�Ȃ�
�n�͂��傫���ƌ������̓g���N���L����Ď��ł���
���ΓI�ɉ�]���Ŕn�͂��҂��ł���d�^�f��
���̍���]��̔n�͕��������ɗL�����Ď��̂悤�ł�
�����ԍ��F19879672
![]() 0�_
0�_
>�g���N���傫���Ȃ�Ȃ��Ɣn�͂��傫���Ȃ�Ȃ�
>�n�͂��傫���ƌ������̓g���N���L����Ď��ł���
EG��]���������ꍇ�Ȃ�B�ł����ǂˁB
���ۂɂ�
�g���N�������Ă�����]�܂ʼn��Ȃ��G���W�������݂��A
�g���N���Ⴍ�Ă�����]�܂ʼn��G���W�������݂���B
����Ȃ̂�
�g���N�������݂� �u �ǂ��������� �v �͖��Ӗ��ł��B
��]�����|���ďo�͂Ɋ��Z���āA���߂Ĕ�r�ΏۂɂȂ�B
��������A
�ŏ�����o�͂Ŕ�r����C�C�����̘b�ł��B
�����
�G���W���g���N�����������d�͂̂悤�Ɏv���Ă���l�����\����݂����ł��B
�G���W���g���N�ʼn������\���v�Z���Ă���T�C�g���L��܂�����ˁB
�����ԍ��F19879749
![]() 2�_
2�_
���̘b��A���X�Ƒ����Ă���܂��ˁB
�X�l�̉��l�ςȂǂō��E�����b��ł͂Ȃ��A�ÓT�͊w�͈͓̔��Ŗ��m�ɐ����ł��邱�ƂȂ̂ŁA�X����l���L�ڂ���Ă���ʂ�A
���u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B
�Ȃ̂ł����B
�ʂ̐��������݂܂��B
����ԗ�������������ہA���̉����͂́A�^�C���ɉ�����쓮�g���N�Ō��܂�܂��B
�i�^�C������]����Ƃ������l���Ȃ�����A�����͂ǂȂ����٘_�������Ǝv���܂��B�j
�u�^�C���쓮�g���N�v�́A�u��������i�ϑ��@�ƃf�t�ɂ��j�v×�u�G���W�������g���N�v�A�ƂȂ�܂��B
����ŁA�u��������v���u�G���W����]���i��]���x�j�v÷�u�^�C����]���i��]���x�j�v�ł��B
�����ŁA�Q�ڂ̎����P�ڂ̎��ɑ������ƁA
�u�^�C���쓮�g���N�v���u�G���W����]���i��]���x�j�v×�u�G���W�������g���N�v÷�u�^�C����]���i��]���x�j�v
�ƂȂ�܂��B�i����������A�Ɋ܂\�L�ƂȂ�܂��B�j
���鑬�x�ő��s���Ă����ԂŁA���̎ԗ����t�����������邱�Ƃ��l���܂��B
�^�C����]���́A�^�C���̋�]��������A�ԗ��̑��s���x�Ɉˑ�����Œ�l�ƂȂ�܂��B�i����s�\�ł��B�j
�h���C�o�[�i����юԗ�����n�j���ł��邱�Ƃ́A�X���b�g���S�J�ɂ��ăG���W�������g���N���ő�ɍ��߂�Ɠ����ɁA
�ϑ��@��K�ɕϑ����삷�邱�Ƃɂ��A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v���ő剻���邱�Ƃł��B
���́A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v�́A�G���W���o�́i�p���[�A�n�́A�d�����j�Ƃ��������ʂł�����A
�Ȃ�ׂ������G���W���o�͂�������悤�ɕϑ��@�𑀍삷��A�ƌ��������Ă��������Ƃł��B
�O�|�S�O�O���Ƃ��O�|�P�O�O�L���Ƃ��A�L�����x�͈͂ōő������ꍇ�ɂ��ẮA
���i�ϑ��@�ł���A�G���W���o�͂��ő�ƂȂ�G���W����]����ۂ悤�A���X���X�̕ϑ����I�肷��Ηǂ����A
�L�i�ϑ��@�ł���A�ő�o�͉�]������܂ň�������A�������o�͂ƃV�t�g�A�b�v�������̏o�͂��h�R�����Ƃ���ŃV�t�g�A�b�v����̂��ł��L���ƂȂ�܂��B
�i�ۂ�ۂ� �D���o�͋Ȑ��Ő�������Ă���ʂ�ł����B�j
�����ԍ��F19879824
![]() 0�_
0�_
>�m�n����
>���́A�u�G���W����]���v×�u�G���W�������g���N�v�́A�G���W���o�́i�p���[�A�n�́A�d�����j�Ƃ��������ʂł�����A
>�Ȃ�ׂ������G���W���o�͂�������悤�ɕϑ��@�𑀍삷��A�ƌ��������Ă��������Ƃł��B
�����Ȃ�܂��ˁB
>�O�|�S�O�O���Ƃ��O�|�P�O�O�L���Ƃ��A�L�����x�͈͂ōő������ꍇ�ɂ��ẮA
>���i�ϑ��@�ł���A�G���W���o�͂��ő�ƂȂ�G���W����]����ۂ悤�A���X���X�̕ϑ����I�肷��Ηǂ����A
>�L�i�ϑ��@�ł���A�ő�o�͉�]������܂ň�������A�������o�͂ƃV�t�g�A�b�v�������̏o�͂��h�R�����Ƃ���ŃV�t�g�A�b�v����̂��ł��L���ƂȂ�܂��B
�����Ȃ�܂��ˁB
���ʂɍl����ƁA�����Ȃ�n�Y�Ȃ�ł����A
�Ȃ����w���e�R�����Ȍv�Z��������āA
�ő�g���N�����ʼn����x���v�Z�ł����ƌ����o���B
�i����ȃA�z�ȁj
��������
�[�����i����N���}�́A�ŏ��͎~�܂��Ă���̂ŁA
�ő�g���N�Ȃ�Đ�ɔ������Ă��Ȃ��B
�����x�����߂�Ȃ�A
���X�ƕω�����g���N�Ɖ�]����
���X�Əo�͂ɕϊ����Ȃ��Ɩ����ł��B
�����ԍ��F19879891
![]() 0�_
0�_
������Ƌ^�₪����܂��B
���������܂����H
���L�Ԃ̍ő�����͂͂ǂ̎�
�ɂȂ�܂����H
�ō��o�́@185 ps/6500 rpm
�ő�g���N�@23.4 kgm/4500 rpm
6��MT
1���@3.818
2���@2.353
3���@1.571
4���@1.146
5���@0.943
6���@0.861
�ŏI������@4.176
�����̍ő�n�͂̎��Ƃ�
�����̍ő�g���N�̎��œ����Ă���������ΗL���ł��B
�����ԍ��F19880695�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��DEND�C�ۂ���
�ő�����͂��l���鎞�́A���x�����m�T�V�ɂ��Ȃ��ƁA���܂�Ӗ��̂Ȃ���r�ɂȂ�܂��B
���̗�ōs���A�ő�����x��������̂�1����4500rpm�̎��ł����A��������̃M�A�̍ő�o�͎��̉����x�Ɣ�r���Ă��A�����牽�H�Ƃ������x���̋c�_�ɂ����Ȃ�܂���B
�Ƃ����̂́A��ʂɁA���x�������قǁA���x���グ��̂ɂ��傫�ȉ^���G�l���M�[��K�v�Ƃ��邩��ł��B
�����ԍ��F19880771�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�������̂�������
���肪�Ƃ��������܂��B
�悭�킩��܂����B
�����ԍ��F19880911�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
��̌�m�ւ̂��Ή��A����ꂳ�܂ł��B
���炩�ȊԈႢ�����܂�Ɏ��M���X�Ɍ�����̂ŁA�ŏ��͖ʔ�������(����Ȓ��\�[�X�A�悭�T���Ă���Ȃ��`)�̂ł����A
���܂��ɂ́A�u���̐��ɏ]���A�S�ăc�W�c�}�������v�݂����ȁA�������ȐV���@���̂悤�Ȏ���������悤�ɂȂ��Ă��܂��A
�䖝�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B(�v�́A�ނ��Ă��܂��܂���(��))
�ނ̎��͂ǂ��ł��悢�̂ł����A��_�C�ɂȂ�܂����B
�u�G���W���P�̂̐��\���}�́A�o�̓J�[�u�̖ʐρv�Ƃ����̂́A�C���[�W�͍����Ă���Ǝv���܂����A������ƈႤ�Ǝv���܂��B
�����ō��o�͂ŁA������]����5000rpm�̃G���W���ƁA8000rpm�̃G���W�����r���܂��B
�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B
�Ⴆ�A5000rpm�G���W���ŁA4000rpm����4400rpm�܂ʼn�������̂ƁA
8000rpm�G���W���ŁA6400rpm����7040rpm�܂ʼn�������͓̂����ł��B
�g�p����G���W����]���̕����A400rpm��640rpm�̍�������܂��B
����ł͖ʐς͓����ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�����Ƌɒ[�ȗ�ł��ƁA�G���W����]���Œ�̂܂܁ACVT�ʼn��������ꍇ�ł́A�ʐρ��[���ł��B
�ʐςł����Ȃ�A�u���s���\���}�́A�쓮�̓J�[�u�̖ʐρv�̕����A���C���[�W�ɋ߂��Ǝv���܂��B
�h�߂��h�ƌ����܂��̂́A���x�ɂ���āh�ʐρh�ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��悤�ȋC�����邩��ł��B(�h�C������h�ł��݂܂���B)
0-50km/h�ł͕����邯�ǁA0-100km/h�ł͓����Ƃ����ꍇ�A
0-50km/h�ł͖ʐς��������A50-100km/h�ł͑傫���Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂����A
0-100km/h�̖ʐςœ����ɂȂ�̂��H�ƌ����܂��ƁA�ᑬ�̕����e�������Ȃ�(�ʐς����������ɂ̓^�C�����͏��Ȃ�)�悤�ȁA
�C������̂ł��B
�͊w���L�`���Ɗw���Ȃ���������Ǝv���܂��B
�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ��b�Ő\�������܂���B
�����ԍ��F19881111
![]() 0�_
0�_
�������̂�������
�K�Ȃ����肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F19881116
![]() 0�_
0�_
�Q�킵���Ⴈ�����ȁH
�ԂȂ���A�����I�Ȗ�肾�B
�ЂƂY��Ă���̂��A�r�K�X�A�X���b�O����B�����āA�R���� ���Q�� �T���U�炷�����ł�����B
�R�����ǂꂾ���g�����A�ǂꂾ�����邩�Ƒ��������������Ȃ��R������ʂő���邩�A������ �r�o�K�X�ɂǂꂾ���̊댯�������܂�ł��邩�H
�����͂��A��R�l��������� �ǂ��Ȃ�B
�܂�A��]���̒�R�l���ɗ͉������B
����� �R��ɂ������B
����]�ł����A�o�͂��o���ɂ����A�K�\�����G���W���ł� �~�b�V�����̖������d�v���ȁI
�^�C���A�{�f�B�[�A�T�X�y���V�����ɂ���Ă��A�쓮�͂�`���ɂ��������肷��B
�G���W���̉�]gs�X���[�Y�ɉ��悤�ɁA�t���C�z�C�[���̏d�ʂ�o�����X�� ��������Ă���B
�ꏏ�� ���d�@���āA��R�ɂȂ��Ă���B
���݂̎Ԃł́A�z�C�[���ɔ��d�@�� ����āA�G���W���p���[�� �H��Ȃ��悤�ɂ��Ă��镨�� �łĂ��Ă���B
�܂�A�G���W���P�̘̂b�����Ă��A�S�����Ӗ��ȂB
�z���_�̂e�P�G���W�������ĂȂ����R����B
�����ԍ��F19881919
![]() 0�_
0�_
�X����l�A
���ʐςł����Ȃ�A�u���s���\���}�́A�쓮�̓J�[�u�̖ʐρv�̕����A���C���[�W�ɋ߂��Ǝv���܂��B
���h�߂��h�ƌ����܂��̂́A���x�ɂ���āh�ʐρh�ɂ͔�Ⴕ�Ȃ��悤�ȋC�����邩��ł��B(�h�C������h�ł��݂܂���B)
�c�O�Ȃ���A���s���\���}�̐ϕ����A�Ӗ��̂��镨���ʂɂ͂Ȃ炸�A�C���[�W�ɂƂǂ܂�܂��B
���������ԁA�c�����쓮�́i�m�j�ł���AN x dt�̐ϕ��͗͐ςɂȂ�܂��̂ŁA
�i���O�ɋ�͒�R��s��R�������������Ă����j�^���ʕω��ɍ��v���܂��B
���邢�́A���������B�����ł���A�@N x dm�̐ϕ��͎d���ɂȂ�܂��̂ŁA�^���d�ƔM�d�̑����ɍ��v���܂��B
���s���\���}�ɂ����āAN x d(m/sec)���v�Z���Ă��A���Ӗ����ƁB
�ł��Q�̎Ԏ�̉^�����\���r���ăC���[�W����̂ɂ͑傢�ɖ𗧂��܂��ˁB
�i�ŋ߂̓J�^���O���ɂ��f�ڂ���Ă��炸�A�c�O�ł����B�j
�����R�O�N�ȏ���O�ł����A���͂Ȃ����ǎ��Ԃ͂���ԍD���w������������A
��̃O���t�p���ɕ����Ԏ�̐��}���d�ˏ������A��X�Ƒz����c��܂��Ă���������v���o���܂��B
�o�n�߂̃p�\�R�����g���ăy���g���R�C�h�Ȑ���`��������B�q�w�|�V���~�����������ǁA���I�Ȗ��ł�������B
������v���A�����ȕϑԂł��ˁB�i�j
�����ԍ��F19882418
![]() 3�_
3�_
���ۂ�ۂ�100����
�Q�킢���ł��˂�^^
F1�A�撣���ė~�����ł��B
�O�H�֘A�̋ɒ[�ȗi��҂̑���͂��������ł��傗
���s��R�ƃ^�C���ɓ`���g���N�Ō��܂邩��A���_�͏o�Ȃ��Ɨ\�����Ă܂����A�ʔ����b��ł����^^
�����ԍ��F19882697
![]() 1�_
1�_
���m�n����
������肪�Ƃ��������܂��B
�����ł���ˁB���ɂȂ�܂��B
���Ȃ��̂悤�ȕ�������������Ə�����܂��B
���i�ŋ߂̓J�^���O���ɂ��f�ڂ���Ă��炸�A�c�O�ł����B�j
�����ł��ˁBM/T�𑀍삷��̂ɂ̓C���[�W���N���̂ł����A�قƂ�ǂ�CVT���܂�A/T�ŁA���G�ȕϑ�������s���Ă��錻��ł�
���s���\�Ȑ������Ă����傤���Ȃ��ł��B������Ǝ₵���ł����B
��������v���A�����ȕϑԂł��ˁB�i�j
�ł��A��������Ď����̎�����Ċm�F�������Ƃ͐g�ɕt���܂���ˁB
���ł́A�A�N�Z���J�x���C���v�b�g����A���͂��A�E�g�v�b�g�����A�u���b�N�{�b�N�X�����i�݉߂��Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B
�����Ə�̐���̕��X����́A�u���܂��炪�Ⴂ���ɂ́A���������Ȃ��Ƃ����킢�I�v�ƌ����邩���m��܂��ǁB(��)
�����ԍ��F19883320
![]() 1�_
1�_
LUCARIO������₷�����B
���͈Ӗ��s�������B
�����ԍ��F19883455
![]() 3�_
3�_
>�O�[�X350����
>�g�p����G���W����]���̕����A400rpm��640rpm�̍�������܂��B
>����ł͖ʐς͓����ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
���]�^���ƁA400��]������
����]���ƁA640��]������
640��]�����������A�ʐς��L���Ȃ�̂ł́H
�E�E�E���Ă��Ƃł���ˁB
���ۂ̃G���W���ŏo�͋Ȑ��������ƁA
���]�^�́A�Ȃ��炩�ȎR�ɂȂ�A
����]�^�́A�}�ȎR�ɂȂ�܂���ˁB
�R���}������A��]�����L�����Ȃ��Ɠ����ʐςɂȂ�Ȃ���ł���B
���ꂩ��A
CVT�ʼn�]�������ɂ���Ȃ�A
�ʐςŔ�r����K�v�͂���܂���B
���̂܂܃_�C���N�g�ŏo�͔�r������C�C�����ł�����ˁB
CVT�Ŏ��ۂ̉����͂ɍ����o��̂Ȃ�A
����̓G���W�����\�̈Ⴂ�ł͖����āA
�ϑ��@�̐��\�̈Ⴂ�Ƃ������ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19885113
![]() 0�_
0�_
�X���傳���
��̐������ƕ�����h����������Ȃ��̂�
��������ς���ƁE�E�E
�����������\�������A
�t���N�V�������X���C��R�Ȃǂ������Ȃ�A
�ʐς������ɂȂ�悤�ɏo�͋Ȑ����`����Ă���n�Y�B
�����łȂ��ƒ��낪�����܂���ˁB
�����ԍ��F19885257
![]() 0�_
0�_
�b�u�s���čl�����i���_�l�H�j�͂����`��������
���ۏ��ƂȂ��b�T�����čD���ɂȂ�Ȃ�
�Ȃ�ł��낤
���ۂ͂��Ȃ芊���Ă���̂�
����Ƃ��v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������̂��E�E�E
�����ԍ��F19885311
![]() 0�_
0�_
>���ۂ͂��Ȃ芊���Ă���̂�
>����Ƃ��v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������̂��E�E�E
CVT�Ȃ�A
�G���W���͍ō��o�͉�]���ŌŒ肳���̂ŁA
�o�͂͏[���ɏo�Ă��܂��ˁB
�������A
�������邽�߂ɂ́A
�u �͂��� �v �ŃM�A���ς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂ŁA
���� �u �͂Â� �v �ɏo�͂�H��ꂿ�Ⴂ�܂��ˁB
�L�i�M�A�Ȃ�A
�ϑ�������̗͋Z�͕K�v����܂���A
���̈Ⴂ�ł��傤�B
�����ԍ��F19885414
![]() 0�_
0�_
>�u �͂��� �v �ŃM�A���ς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂ŁA
>���� �u �͂Â� �v �ɏo�͂�H��ꂿ�Ⴂ�܂��ˁB
�Ƃ�
�v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������
�Ƃ̉��߂ŗǂ��̂ł��傤����
�����g���R���̃L�b�N�_�E���̕������C���������čD�������Ă�
�i���ۂ̑����͉���Ȃ��������ς������Ƃ����邩������Ȃ����j
�c�b�s��`�l�s�̕������҂����Ă�C������
���݂܂���E�������Ă��܂��܂���
�����ԍ��F19885509
![]() 0�_
0�_
>�v�[���[��ύX�Ɏ��Ԃ�������
>�Ƃ̉��߂ŗǂ��̂ł��傤����
���Ԃ��|����ƌ����̂͂ǂ��ł��傤�ˁB
�A�N�Z���S�J�ʼn�]���i�o�́j���Œ肳��Ă���̂Ȃ�A
�ϑ����� �� �������\�@�ɂȂ�܂�����A
�ϑ����Ԃ��̂��̂��A�������\�ɂȂ����Ⴂ�܂��B
�A�N�Z���S�J�ł͂Ȃ��X���ł̕��ʂ̉����Ȃ�A
�����̃t�B�[�����O�̖��ł��ˁB
�����ԍ��F19885532
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
�����ۂ̃G���W���ŏo�͋Ȑ��������ƁA
�����]�^�́A�Ȃ��炩�ȎR�ɂȂ�A
������]�^�́A�}�ȎR�ɂȂ�܂���ˁB
�������t�ɂȂ�܂��B
�o�͓͂����Ȃ̂ł���B
�Ƃ������Ƃ́A�c�����o�́A�������G���W����]���̏ꍇ�A���]�^�̕����낪�����`�ɂȂ�܂��B
�ł����A�R�̌`�͑債�Ė��ł͂���܂���B
�Ȃ��Ȃ�A���s���\�Ȑ��̋쓮�͂������Ȃ�A���̂Ƃ��̏o�͓͂����A
�܂�A���ꂼ��̃G���W���P�̂̏c���̒����͓����ł��̂ŁB
��������������������̂ɁA�g���G���W����]���̕����Ⴄ�̂Ŗʐς͈Ⴂ�܂��B
CVT�ł̏ꍇ�����R�����ł����A
���������\�́A���̋Ȑ��̓����̖ʐςɂȂ�܂��B
�Ƃ����̂͊ԈႢ���Ɛ\���Ă���̂ł��B
���ʐς������ɂȂ�悤�ɏo�͋Ȑ����`����Ă���n�Y�B
����M����Ȃ炻�����Ǝv���܂��B
�����ԍ��F19885990
![]() 1�_
1�_
�R������A���� �V���[�V�_�C�i����� �����Ă��邩��A�����s�Ƙ���������B
���ۂ̎Ԃ� �V���[�V�_�C�i����� ����Ƃ��ɂ́A���s��R�̌v�Z��̕��ׂ������Ă��邪�A��C��R�͂������Ȃ��B
��C���x�� �ĂƓ~�ł� �Ⴄ���ˁB
�T�����炢�͕ς���Ă���̂��ȁH
�G���W���� �p���[�܂�A�n�͂� �ɒ[�ɂ�����ƁA�g���N�� �������B
�g���N���ɒ[�ɏo���ƁA�n�͂�������B
�G���W��������Ȃ��� �킩��˂����낤���ǂˁH
�����ԍ��F19886895
![]() 0�_
0�_
���G���W���� �p���[�܂�A�n�͂� �ɒ[�ɂ�����ƁA�g���N�� �������B
���g���N���ɒ[�ɏo���ƁA�n�͂�������B
�u�{�A�X�g���[�N��v�֘A�H
�����ԍ��F19886910
![]() 0�_
0�_
>�ł����A�R�̌`�͑債�Ė��ł͂���܂���B
>�Ȃ��Ȃ�A���s���\�Ȑ��̋쓮�͂������Ȃ�A���̂Ƃ��̏o�͓͂����A
�l�������t�����āB
�o�͋Ȑ��́A
�G���W�����\��\�����O���t�Ȃ̂ŁA
�G���W�����\����ɂ���܂��B
�ō��o�͂��������Ƃ��Ă��A
�S���ʂ̃G���W���Ȃ�o�͋Ȑ�������Ă��܂��B
�o�͋Ȑ����Ⴄ�̂ŁA�쓮�͂̕ω��i�쓮�͋Ȑ��j���Ⴂ�܂��B
�ʂ̃G���W�����ڂ����N���}�i�Ⴄ���\�Ȑ��̃N���}�j�����ۂɑ��s�����āA
���܂��ܓ��������^�C���ɂȂ����̂Ȃ�A
�o�͋Ȑ��̖ʐς��A���܂��ܓ������������Ă��Ƃł���B
�Ⴆ�A
�ϑ������� 40�`100km/h �����^�C���������Ȃ�A
�����������\���ƌ����܂����A
�����x���ו�������ƁA�e�Z�N�V�������Ƃœ������Ƃ͌���܂���B
�����āA�o�͋Ȑ����Ⴄ�̂ŁA�o�͂̍��܂�������R�Ⴄ�ł���B
�Ȃ̂ŁA
�o�͋Ȑ��̈Ⴄ�N���}�ǂ����ĉ����^�C���������A
40�`100km/h ���^�C���I
80�`120km/h ����
20�`40km/h ����
�E�E�E���Ă��Ƃ����蓾�܂��B
�ō��o�͂��������ƌ��������ŁA
�ō��o�͂����Ă��Ȃ����̏o�͂������Ƃ͌���܂���ˁB
�����ԍ��F19887849
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
������A
���M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B
���̂悤�ȃG���W���̔�r�ł���B
�h���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������h�Ȃ�A���͐��\�͓����ł���ˁH
�������A�g�p����G���W����]���̕����Ⴄ�ƌ����Ă���̂ł��B
�M���䂪�Ⴄ�̂ɁA���͐��\�������ꍇ�́A�G���W���P�̂̏o�̓J�[�u���t�Z���Ă݂ĉ������B
�����ԍ��F19887887
![]() 1�_
1�_
���ۂ�ۂ� �D����
�}���������������B
�j�����o�́A�������g���N�ł��B�@�ƐԂ̃G���W�����r���܂��B
�{�M����1.5�A�ԁ{�M����3�A�őS�������쓮�̓J�[�u�ɂȂ�܂��B
��1000rpm����1500rpm�܂ʼn�������ƁA�Ԃ�2000rpm����3000rpm�܂ʼn�������̂́A�����������\�ł���ˁH
�ǂ����Ă��Ԃ̕��̖ʐς��L���ł��B
���l�������t�����āB
�ǂ���������������܂���B
�ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)�Ƌ쓮�͂���o�͂�����A
�M��������߂�A���̏o�͂��A�ǂ̃G���W����]��×�G���W���g���N�Ŕ��������Ă���̂�������܂��B
�S�������쓮�̓J�[�u�ŁA�M���䂪�Ⴄ�Ԃ��������ꍇ�A�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��͂ǂ�����Ă���̂��H�Ƃ������ł��B
�S�������쓮�̓J�[�u�Ȃ�����͓͂����A����͗ǂ��ł���ˁH
���Ȃ��̐����ł́A�����͂́u�G���W���P�̂̏o�̓J�[�u�̖ʐρv�Ȃ̂ł�����A
���ꂼ��̃G���W���Ŏg�p�����]�[���̖ʐς́A�����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��̂ł����H
�����ԍ��F19888718
![]() 2�_
2�_
�X���傳���
�쓮�͂��o�͂ɂ��Ȃ��ƈӖ��������̂ŁA
�쓮�g���N���l����K�v�͖����ł��B
�쓮�o�͂��l����C�C��ł����A
�G���W���o�͂Ƌ쓮�o�͓͂����Ȃ̂ŁA
�쓮�o�͂��l����K�v�������ł��B
���̃O���t���ƁA
�����^�C���������ɂȂ�܂����B
�Ԃ̕����^�C�����ǂ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F19890422
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
���{�M����1.5�A�ԁ{�M����3
�ł���B
�G
�G���W����]����1000rpm�A�o�́�30PS�A�܂�G���W���g���N��21.5kgm�@���쓮�։�]����667rpm�A�쓮�́�32.2kgm
�G���W����]����1500rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��19.1kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm
�ԁG
�G���W����]����2000rpm�A�o�́�30PS�A�܂�G���W���g���N��10.7kgm�@���쓮�։�]����667rpm�A�쓮�́�32.2kgm
�G���W����]����3000rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��9.5kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm
�ǂ����ĐԂ̕����������ǂ��̂ł����H
������肢�v���܂��B
�����ԍ��F19890487
![]() 2�_
2�_
�X���傳���
���[�ƁA
���������ŃC�C��ł���ˁH
�Ⴆ�A
20-80km/h �̃^�C���������Ƃ��āA
�� 1000��]�� 20km/h �ŁA
�Ԃ� 2000��]�� 20km/h �ŁA
��ĂɃX�^�[�g�I
�� 1500��]�� 80km/h ���B�ŁA
�Ԃ� 3000��]�� 80km/h ���B�ŁA
���ꂼ�ꂪ�S�[���I
���M�A�䂪�Ⴄ�̂�EG��]��������Ă����x�͓����B
���̎��A
���v���Ԃ��Z����A
�^�C�����ǂ� �� �������ǂ�
�E�E�E�ŃC�C��ł���ˁH
���������A
���ꂪ �u �������ǂ� �v ���Ă��Ƃł���ˁB
�����ԍ��F19890601
![]() 0�_
0�_
���[�ƁA�ǂ��Ƃ��đ�����ƁE�E�E
�� 1000��]�� 20km/h �ŁA
�Ԃ� 2000��]�� 20km/h �łȂ̂ŁA
�������Ԃœ���������i�݂܂����A
���x�̓^�_�̗��Ȃ̂ŁA
���x�����ł͋����̓[���ł��ˁB
����Ɠ����悤��
�G���W����]����1000rpm�A�o�́�30PS ���A
�G���W����]����2000rpm�A�o�́�30PS ���A
���ԓ�����̎d���ʂ͓����ł����A
�^�_�̗��Ȃ̂ŁA�܂��d���͂��Ă��܂���ˁB
������C���[�W�ł����E�E�E
�ŏ���1000�`100�P��]��30�n��
���̎���1001�`1002��]��30.01�n��
���̎���1002�`1003��]��30.02�n��
���̎��́���]����Z��]�ŁZ�n�́@�Ǝd�������Ă����A
�Ō�́A1500��]��40�n�͂ɂȂ��ł���ˁB
���̌��ʂ��O���t�ɗ��Ƃ������̂��A
�X���傳�������o�͋Ȑ��ł���ˁB
����Ȃ͈̂�X�S�Čv�Z�Ȃ�ďo���Ȃ��̂ŁA
�O���t�ɂ�����ł���ˁB
����Ȃ�A
����1000��]����A1500��]�܂ł̊ԂŁA
���������ǂꂾ���̎d���������������߂�ׂɂ́A
�S�Ă̎d���ʂ𑫂��K�v������ł��傤�B
�ŏ���1000�`100�P��]��30�n��
���̎���1001�`1002��]��30.01�n��
���̎���1002�`1003��]��30.02�n��
���̎��́���]����Z��]�ŁZ�n�́@�Ǝd�������Ă����A
�Ō�́A1500��]��40�n�͂ɂȂ�B
�����S�ĐώZ�������Ȃ�A
�o�͋Ȑ��̖ʐςɂȂ�͂��ł��B
�ŏ��ƍŌ�̑��x�͓����B
�d���ʂł���ʐς��L���̂Ȃ�A
�ړI�̑��x�ɒB����܂ł̏��v���Ԃ��Z���Ȃ�n�Y�ł��B
����ʼnɂȂ��Ă邩�ȁH
�����ԍ��F19891056
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
�܂��A
���� 1000��]�� 20km/h �ŁA
���Ԃ� 2000��]�� 20km/h �ŁA
�Ƃ���Ȃ�A
�� 1500��]�� 30km/h
�Ԃ� 3000��]�� 30km/h
�ł��B
20km/h����30km/h�ɉ�������̂ɁA�Ȃ����ԍ�������̂ł����H�Ƃ�������ł��B
�G���W���P�̂̐��\�Ȑ��͉�����rpm�ł���B
���������ԂȂ炻���ł��傤�B
���x�������܂����A�h���s���\�Ȑ��́h�쓮�̓J�[�u�͓����Ȃ̂ł���B
���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�͓����Ȃ̂ɁA���͐��\�͈Ⴄ�A�Ƃ��Ȃ��͎咣����Ă��܂����A
����͂Ȃ��ł����H�Ǝ��₵�Ă���̂ł��B
�����ԍ��F19891249
![]() 2�_
2�_
�쓮�̓J�[�u������Ȃ�A�������\���ꏏ����Ȃ��́H
�����ĒP�ʎ��ԓ�����́A�^�C���̉�]���͈ꏏ�Ȃ���B
�����ԍ��F19891296
![]() 0�_
0�_
��̎Ԃ̈Ⴂ���A�o�͋Ȑ��Ɖ�]�����r����ׂɃf�t�̌������ς��������Ȃ�A
1000�`1500�̃G���W���̏o�͋Ȑ��̕��݂̂�{�ɂ��āA2000�`3000�̏o�͋Ȑ��ɏd�˂āA
�s�b�^���d�Ȃ�Ȃ�A�����͓����B
�d�Ȃ�Ȃ��Ȃ�A��ɗL��Ԃ��������ǂ��B
�㉺������ւ��Ȃ�A�ϕ����Ă������ƂɂȂ�̂��ȁH
�����ԍ��F19891401
![]() 0�_
0�_
�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B
�����͂���/��2�A��/��2�����B
���x�������ԂŊ���Ȃ��ƁA���ω����x�͏o�Ȃ����B
�����ԍ��F19891405
![]() 2�_
2�_
>�X���傳���
>20km/h����30km/h�ɉ�������̂ɁA�Ȃ����ԍ�������̂ł����H�Ƃ�������ł��B
20km/h �������ŁA
30km/h ���ŏI�I�ȑ��x�ł��ˁB
�ŏ��ƍŌ�̏o�͂�g���N�A�쓮�͂������ł��A
�r���̏o�͂�g���N��쓮�͂������łȂ��ƁA
���ԍ��͓����ɂȂ�܂����B
�X���傳��̌v�Z���@���ƁA
�Ԃ̃G���W���ɉߋ���ƃu�[�X�g�R���g���[���[����t���āA
2000��]�� 30�n��
2100��]�� 40�n��
2500��]�� 40�n��
3000��]�� 40�n��
�E�E�E�ƃp���[�A�b�v�����Ă�
�����^�C���ɂȂ�܂��H
�����ԍ��F19893072
![]() 0�_
0�_
>�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B
>�����͂���/��2�A��/��2�����B
>���x�������ԂŊ���Ȃ��ƁA���ω����x�͏o�Ȃ����B
����Ⴛ�������B
�����x�����߂Ă����Ȃ����āA
�ǂ���̉����x���傫���������߂Ă����ł����炳�B
�����ԍ��F19893085
![]() 0�_
0�_
�ʂ̌������̕����C�C���Ȃ��B
�Ⴆ�A
0 �� 40km/h �̉��������������Ƃ���B
�������͖ʓ|�L���̂Ń[���ɂ��܂���
�ʓ|�L���̂ŃN���b�`�̖������������ǁA���̂܂܉����ł�����Ă��Ƃɂ��܂��傤�B
�����x���[�����ƃG���X�g���邾��I���Ă͎̂捇���������ŁB�i��
�G���W�����ԃG���W����
40km/h ���_�̏o�͂́A����40PS�ł����B
�@���i�����������ł��j
�G���W����]����1500rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��19.1kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm
�ԃG���W����]����3000rpm�A�o�́�40PS�A�܂�G���W���g���N��9.5kgm�@���쓮�։�]����1000rpm�A�쓮�́�28.6kgm
��������I��ק�I�@���Ă��H
����Ȃ͓̂�����O�ł��B
�������x�܂ʼn��������悤�Ƃ��鋣���ł�����A
�S�[���ł̑��x���쓮�͂������Ɍ��܂��Ă��܂��B
�����A���ꂾ���̘b�ł��B
�������A
���ꂾ���ł͉����x�Ȃ�ĕ�����܂����B
40km/h �ɒB����܂ł������ł�����A
�G���W�����A�[����]����1500rpm�ɒB����܂łɍ��o�����o�͂ƁA
�ԃG���W�����A�[����]����3000rpm�ɒB����܂łɍ��o�����o�͂��ׂȂ��ƈӖ��������ł��B
�ǂ����Ă��쓮�g���N�Ɋ��Z�������̂Ȃ�A���̍��v�o�͂�ϊ����Ȃ��ƈӖ��������ł��B
�����Ȃ�1500rpm�ʼn�]������A
�����Ȃ�3000�������ʼn�]������͂��܂����B
�[����]����A�i�X�Ɖ�]�������Ȃ��ł���B
�����Ȃ�ƁA
�́A�[����]����1500rpm�ɒB����܂ł̑S�Ẳ�]��ł̏o�͍��v���K�v�ł��傤�B
�Ԃ́A�[����]����3000rpm�ɒB����܂ł̑S�Ẳ�]��ł̏o�͍��v���K�v�ł��傤�B
��NA�ŁA0�`1500rpm�܂ʼn�]�㏸�Ƌ��ɏ��X�ɏo�͂������Ȃ��Ă��āA
�Ԃɂ̓^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āA
1000�`3000rpm �̊ԁA��Ƀh�J���ƃt���p���[�i40PS�j�����Ă��邩���m��܂����B
�����A�ǂ����܂���B
���������͂ł����H
�����ԍ��F19893262
![]() 0�_
0�_
�ۂ�ۂ� �D����
�����ꂵ���l�ȋC�����܂���H
�O�[�X350����́u�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B�v�ƌ����Ă��܂�����A�u�^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āv�Ȃ�Ęb�͖������Ǝv���B
�O�[�X350�������A�ƐԂ̓����}���������ł́u�h�J���ƃt���p���[�v���A��������Ă���悤�ɂ͌����܂��ǁE�E�E�E
�����ԍ��F19894048
![]() 2�_
2�_
>eoffice����
>�O�[�X350����́u�M������A5��8�ɂ����ꍇ�ɁA���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ȃG���W���ł̔�r�ł��B�v�ƌ���>�Ă��܂�����A�u�^�[�{�ƃu�[�R�����t���Ă��āv�Ȃ�Ęb�͖������Ǝv���B
�Ⴂ�܂��B
�O���t�ɂ͏o�͂ƃg���N�����ڂ��Ă��܂���B
�O�[�X350���A�쓮�̓J�[�u�ƌĂ�ł�����̂́A
�G���W���g���N�����ɋ쓮�͂̃g���N���v�Z���������ł��B
�܂�A
�o�͊��Z����Ă��Ȃ��̂ŁA
�G���W���g���N�Ɠ����ł��B
�ł�����A
�쓮�͂ōl�������̂Ȃ�A
�쓮�͂��o�͂Ɋ��Z����K�v�������ł���B
���ǂ܂��A
�g���N���ᖳ���ďo�͂���B���Ęb�ɖ߂��Ă��܂��̂��B
�߂������ȁB���ꂪ�������ȁB
�����ԍ��F19894100
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
���Ԃ̃G���W���ɉߋ���ƃu�[�X�g�R���g���[���[����t���āA
��2000��]�� 30�n��
��2100��]�� 40�n��
��2500��]�� 40�n��
��3000��]�� 40�n��
���E�E�E�ƃp���[�A�b�v�����Ă�
�������^�C���ɂȂ�܂��H
�����������Ԃ̔j���͂����ł��B(�M����3�ŁA�G���W����]��2000rpm��20km/h�Ƃ���)
2000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm
2100��]�� 31.5�n�́@��21km/h�A�쓮�́�32.2kgm
2500��]�� 37�n�́@��25km/h�A�쓮�́�31.8kgm
3000��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm
���̋쓮�̓J�[�u�̃G���W�����A
�Ȃ��A
2000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm
2100��]�� 40�n�́@��21km/h�A�쓮�́�40.9kgm
2500��]�� 40�n�́@��25km/h�A�쓮�́�34.4kgm
3000��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm
�̎Ԃɏ��Ă��ł����H
�����ԑ��ɑ��āA�쓮�͂��������������͑����ł��B
�����������̔j���͂����ł���B(�M����1.5�ŁA�G���W����]��1000rpm��20km/h�ƂȂ�Ƃ���)
1000��]�� 30�n�́@��20km/h�A�쓮�́�32.2kgm
1050��]�� 31.5�n�́@��21km/h�A�쓮�́�32.2kgm
1250��]�� 37�n�́@��25km/h�A�쓮�́�31.8kgm
1500��]�� 40�n�́@��30km/h�A�쓮�́�28.6kgm
�ԃG���W���ԂƁA�ԑ��ɑ�����쓮�͓͂����ł��B(���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������Ȃ̂ŁA���R�ł��B)
��0 �� 40km/h �̉��������������Ƃ���B
���x�́A40km/h�̂Ƃ��̃G���W����]�����A��1500rpm�A�ԁ�3000rpm�Ɖ��肷��̂ł��ˁH
�Ƃ������Ƃ́A
��1000rpm�A��2000rpm�̂Ƃ��̎ԑ��́A27km/h�ƂȂ�܂��B
�[���X�^�[�g�Ƃ������Ƃ́A����܂Ō��߂Ă��Ȃ��G���W����]�����g���Ƃ������ł��̂ŁA
���̉�]��̃g���N�A�o�͂����߂܂��B
����ȉ��̃G���W����]�����g�p�����ꍇ���A���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�������ɂȂ�悤�ɂ��܂��B
�܂��A�쓮�̓J�[�u�������Ȃ�Ȃ�ł��ǂ��̂ŁA�ʓ|�������̂ŁA
�́A�G���W����]��0�`1000rpm�܂œ����G���W���g���N(21.5kgm)
�Ԃ́A�G���W����]��0�`2000rpm�܂œ����G���W���g���N(10.7kgm)�@�Ƃ��܂��B
(�ł��̂ŁA0rpm����A��30PS/1000rpm�܂ŁA�Ԃ�30PS/2000rpm�܂ŁA��]���ɔ�Ⴕ�ďo�͂͑�������Ƃ������Ƃł��B)
�Ƃ����ꍇ�A
�ǂ���̎Ԃ��A�ԑ�0����27km/h�܂ŁA�ǂ̑��x�ł��쓮�́�32.2kgm�ƂȂ�܂��B(�̃M����1.5�A�Ԃ̃M����3�Ƃ���)
�܂�A0����40km/h�܂ŁA���`���Ƃǂ̎ԑ��ł��A�쓮�͓͂����ł��B
����ŁA�^�C���ɍ�������̂ł��傤���H
�G���W���P�̂̐��\���}(������rpm)�ł́A�o�̓J�[�u�̖ʐς͔{���炢�Ⴄ�悤�ł����E�E�E�B
�����ԍ��F19894128
![]() 1�_
1�_
�O�[�X350����͗�̐ƐԂ̐}���Q�Ƃɂ��āA�v�Z�����Ă���݂����Ȃ̂ŁA���̐}���������ۂ�ۂ� �D�������A�u�Ƀh�J���ƃt���p���[�v�Ȃ�ăG���W���ł͖����l�ł����ƌ����Ӗ��ł��B
��̐}������ɂ��Ă��Ȃ��Ȃ�b�͕ʂł����i���j
�����ԍ��F19894150
![]() 0�_
0�_
�������x�����߂Ă����Ȃ����āA
���ǂ���̉����x���傫���������߂Ă����ł����炳�B
�����x���o���Ȃ��ŁA�ǂ����������x���傫�������邸�炩�H
���������B
���̐}�ŁA�����x���o�邸�炩�H
����ς�A�Ӗ��s�������B
�����ԍ��F19894169
![]() 1�_
1�_
���ۂ�ۂ� �D����
���O���t�ɂ͏o�͂ƃg���N�����ڂ��Ă��܂���B
���O�[�X350���A�쓮�̓J�[�u�ƌĂ�ł�����̂́A
���G���W���g���N�����ɋ쓮�͂̃g���N���v�Z���������ł��B
���x�������܂����A
���{�M����1.5�A�ԁ{�M����3
�ł���B
�ƐԂ̃M����̔��1�F2�ɂ���A�����F�ԑ��A�c���F�쓮�͂̃O���t�͑S���d�Ȃ�܂��B
���쓮�͂ōl�������̂Ȃ�A
���쓮�͂��o�͂Ɋ��Z����K�v�������ł���B
�����ł���B
�쓮��×�ԑ����o�͂ł��B(�M����ɂ���āA���̂Ƃ��̃G���W����]��×�G���W���g���N���ς��܂��B)
������A�����ԑ��̏ꍇ�A�쓮�͂��������o�͂������������͂��ǂ��A�ł��B
0��40km/h���낤�ƁA20��30km/h���낤�ƁA�ǂ�������Ă��o�͂́A�ƐԂœ����Ȃ̂ł���B
���Ȃ��͋C�����Ă��Ȃ��̂����m��܂��A
���Ȃ��́A�u�����͂́A���̂Ƃ��̏o�͂ł͌��܂�Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł���B
�����ԍ��F19894201
![]() 0�_
0�_
��l�Ƃ��A���������ԂŖ����O���t�łȂɝ��߂Ă�邸�炩�H
�����x�͂���/��2�A��/��2�����B
���x�����ԂŊ���Ȃ�������A�����x�ł͖��������B
�����Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B
�����ԍ��F19894416
![]() 2�_
2�_
�u���������̊ȒP�Ȏd���ł��v�Ȃ̂��H
���_�ɓs���̗ǂ��v�Z�͊ԈႢ�ňӖ��͂Ȃ��B
����ł͂Ȃ������ɕ��ׂ̂����Ԃōl����̂��K�v����Ȃ��́H
�����ԍ��F19894487
![]() 1�_
1�_
�����t�g�^�[������
�������Ɏ��Ԃ��o�ĂȂ��O���t�ʼn����̘b�����Ă鎖���ԈႢ�����B
�����ł��B
�����F���ԁA�c���F�o�́@�̃O���t�Ȃ炻�̖ʐςł��傤�B
�����Frpm�ł͈Ⴄ�ꍇ������ł��傤�H�Ɨ���o���Ă���̂ł����A�����Ă��������Ȃ��悤�ł��B
�ł͂ǂ�����A�����F���ԂɂȂ�̂��H�ł����A
����ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)����A���̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B
(�ł��̂ŁA�����͂Ƃ͏o��(�쓮�ւ̉�]��×�쓮�ւ̃g���N)�ƂȂ�܂��B)
�܂�A��r����2�Ԃ́A�ԑ��ɑ���쓮�͂��A�O���t�̂ǂ��ł������ꍇ�A�ǂ̎ԑ��Ŕ�r���Ă������͓͂����ł��B
(�u�����́v�Ƃ́A���܂������ԓ��ɁA�ԑ�����km/h�㏸�������H�ł���ˁB�G���W����]������rpm�㏸�������H�ł͂Ȃ��āB)
�����ԍ��F19894647
![]() 1�_
1�_
������ԑ�(�쓮�ւ̉�]��)����A���̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B
�Ӗ��s�������B
�g���N���オ��قǁA�������x���Ȃ�̂Ȃ�A�X�^�[�g���オ�ő�ŁA�ő�g���N��]���܂ő��������������鎖�ɐ����Ă��܂����B
�����ԍ��F19895145
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���g���N���オ��قǁA�������x���Ȃ�̂Ȃ�A�X�^�[�g���オ�ő�ŁA�ő�g���N��]���܂ő��������������鎖�ɐ����Ă��܂����B
�t�ł��B
�����̏�̎ԑ��ɑ������鎞�Ԃ́A�쓮��(�쓮�ւ̃g���N)�ɔ���Ⴕ�܂��B
�쓮�͂��傫�������Ԃ��Z����������ł��B
�쓮�͂��傫���قǁA�h���ԁh�͒Z���Ȃ�̂ŁA�����ł��B
������Ǝ����\���I�ɖ������̂ł����A�h�����h�Ƃ��h�X�s�[�h�h�Ȃ�A���R���ł��B
(����ɂ����Đ\�������܂���B)
�ł��̂ŁA�ő�g���N��]�����A���̏u�Ԃ̉����͂Ƃ��Ă͍ő�ł��B
(��������́A�����̂�������[19880771]�Ō����Ă���Ƃ���A���܂�Ӗ��̂Ȃ������͂ł����B)
�����ԍ��F19895190
![]() 0�_
0�_
���쓮�͂��傫�������Ԃ��Z����������ł��B
���ő�g���N��]�����A���̏u�Ԃ̉����͂Ƃ��Ă͍ő�ł��B
���_�o����B
��(��������́A�����̂�������[19880771]�Ō����Ă���Ƃ���A���܂�Ӗ��̂Ȃ������͂ł����B)
�Ӗ��s�������B
���႟�A�������������Ă��邸�炩�H
�����ԍ��F19895226
![]() 1�_
1�_
�����t�g�^�[������
�����႟�A�������������Ă��邸�炩�H
�Ԃ�����������̂́A�쓮�͂ł��B
�����A�P���Ɂu���႟�A�G���W���g���N�̑傫���������͂����߂�v�Ƃ�����ł͂���܂���B
���܂����M����̂Ȃ��ł͂����ł����A�����ԑ��̂Ƃ��ɁA�����Əo�͂������G���W����]���ɂȂ�悤�ȃM����ɂ���A
������̕����쓮�͍͂����Ȃ�܂��B
(���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�̗�)
�����ԍ��F19895259
![]() 0�_
0�_
�����܂����M����̂Ȃ��ł͂����ł����A�����ԑ��̂Ƃ��ɁA�����Əo�͂������G���W����]���ɂȂ�悤�ȃM����ɂ���A
������̕����쓮�͍͂����Ȃ�܂��B
�ő�g���N��]���ȏ�̉�]���Ȃ�쓮�́i�g���N�j�������Ă��܂��̂ő����͒x���Ȃ邸��B
����ȉ��Ȃ�P�ɃM�A��������邾�������B
�����ԍ��F19895276
![]() 0�_
0�_
���ő�g���N��]���ȏ�̉�]���Ȃ�쓮�́i�g���N�j�������Ă��܂��̂ő����͒x���Ȃ邸��B
�M������Œ肵�Ă���ȏ�A�����ł��B
������ȉ��Ȃ�P�ɃM�A��������邾�������B
�h���̎ԑ��Łh�쓮�͂������ł���M�����I���ł���Ȃ�A������̕��������͗ǂ��ł��B
�����ԍ��F19895308
![]() 0�_
0�_
>�M������Œ肵�Ă���ȏ�A�����ł��B
�Œ肾�낤�ƁA�ϑ����悤�ƍő�g���N��]������쓮�͂�������͕̂ς��Ȃ����B
���h���̎ԑ��Łh�쓮�͂������ł���M�����I���ł���Ȃ�A������̕��������͗ǂ��ł��B
������������䂵�Ă���̂��b�u�s����B
�����ԍ��F19895391
![]() 0�_
0�_
���Œ肾�낤�ƁA�ϑ����悤�ƍő�g���N��]������쓮�͂�������͕̂ς��Ȃ����B
�ϑ����悤�ƍő�g���N��]���ŋ쓮�͂��ő�ɂȂ�̂ł���A�ő�g���N��]�����L�[�v����̂��ő��ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�ő�g���N��]�����Ă��쓮�͂������Ȃ�̂́A���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�̏ꍇ�Ő����ς݂ł��B
�h�����ԑ��Łh�쓮�͂��������������͗ǂ��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F19895421
![]() 0�_
0�_
���Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B
�쓮�́��́��g���N����B
�N�����N�V���t�g���́i�g���N�j���Ԃ��쓮���Ă��邸��B
����͕s�ς����ׁB
���@�ł��g��Ȃ�����A�����@�A�ϑ��@�ł�������ł��Ȃ����B
�G���W��������������g���N�i�́j���쓮�͂Ŗ����̂Ȃ�A�����Ԃ����Ă��邸��H
�����ԍ��F19895472
![]() 0�_
0�_
���G���W��������������g���N�i�́j���쓮�͂Ŗ����̂Ȃ�A�����Ԃ����Ă��邸��H
�͂Ƃ��Ă݂�ꍇ�́u�쓮�́��́��g���N�v�ő�g�͂����Ă��܂��B
�����ĎԂ����Ă���̂��g���N�ł��B
�������̏ꍇ�P�Ȃ�͂������������i�N�����N�����]����������j�ŁA�d���ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł����ŏI���ɂȂ�܂��A�����ƌ����T�O����鎖�͏o���܂���B
���t�g�^�[������́A�u�����x�v�u�G���W���g���N�v�������Ǝv���Ⴂ���Ă���̂ł́H
�b�����݂����Ă��Ȃ��ƌ������A�����ł��Ă��Ȃ��l�ȋC�����܂��E�E�E
�����ԍ��F19895671
![]() 1�_
1�_
>�������̏ꍇ�P�Ȃ�͂������������i�N�����N�����]����������j�ŁA�d���ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł����ŏI���ɂȂ�܂��A�����ƌ����T�O����鎖�͏o���܂���B
��G�c��
�d���ʁ��ԑ�×�ԏd
�ԑ����d����/�ԏd
���̎�
�d���ʁ���]��*�g���N*�W��
�Ȃ̂�
�i�ԑ�-�ԑ��j/���ԁ������x
��
�o�i��]��*�g���N*�W���j-�i��]��*�g���N*�W���j�p/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x
���������
�i��]��*�g���N*�W���j/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x
�ƂȂ�B
�����ŁA�����Ɋ|�������Ԃ�����Δn�͂Ɛ��邪�A�g���N���傫���ꍇ�͑����Ɋ|�������Ԃ��Z���čςނ̂Ńg���N���傫�����������ǂ��Ȃ邸��B
�ő�o�͎��̃g���N�͍ő�g���N���Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��A��T�ɔn�͂��傫������������ǂ��Ƃ͌����Ȃ������B
�����ԍ��F19895892
![]() 0�_
0�_
���i��]��*�g���N*�W���j/�d��/�����Ɋ|�������ԁ������x
�������ŁA�����Ɋ|�������Ԃ�����Δn�͂Ɛ��邪�A�g���N���傫���ꍇ�͑����Ɋ|�������Ԃ��Z���čςނ̂Ńg���N���傫�����������ǂ��Ȃ邸��B
�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v
��L�̎��̒ʂ�A�g���N�l�����傷��Ώo�́i�n�́j���オ���ł����H
���ő�o�͎��̃g���N�͍ő�g���N���Ⴍ�Ȃ��Ă��邩��A��T�ɔn�͂��傫������������ǂ��Ƃ͌����Ȃ������B
�ǂ�Ȏԗ��Ȃ̂��m�ɂ��Ȃ��ƁA���̘_�͐��藧���܂����B
�����āu��T�Ɂv�ƕt�����Ď��͋t����F�߂�ƌ������ł��B
�����ĂȂ��b���A����ւ��Ă���悤�ȋC������̂́A�C�̂����ł����ȁH
�����ԍ��F19895988
![]() 1�_
1�_
�ō������o�͂ɂ��Ƃ���Ȃ̂͐������Ǝv���B
�������A�������E�ɂ͏d�͂▀�C�E��C��R�Ƃ��������ׂ����݂���B
���ׂ�Ŕj����̂̓g���N�ł����ďo�́i�d�����j�ł͂Ȃ��B
�l�b�g�ŎU������o�͔h�̗��_�ɂ̓R���������Ă���B
���̉�]�ɂ��o�͂����ōl����ƁA0-400m�ǂ��납0-800m�ł����F�C������H2R�ɕ����闝�R�������ł��Ȃ��B
�o�C�N�ƎԂ��r���Ă��H�Ƃ����ӌ��ɂ́A�O�����܂��Ȍv�Z���ŋ��߂Ă��H�Ɖ��܂��B
�����ԍ��F19895998
![]() 0�_
0�_
>�u��T�Ɂv�ƕt�����Ď��͋t����F�߂�ƌ������ł��B
�����́A�������Ԃ̑��ʂƃg���N�ቺ��×��]���ʂƂ̔�ɂ�茈�肷�邸��B
���ꂱ���A�c�����x�A�������Ԃ̃O���t��������A���Ƃ������Ȃ����B
������A������]���̃O���t�ł͉����x�͌��Ȃ��ƌ����Ă邸���B
�����ԍ��F19896062
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�d���ʂƂ������t�́A�d�����w���̂��d�������w���̂��A�����܂��Ȃ̂Ŏg��Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B
���d���ʁ���]��*�g���N*�W��
�Ƌ��Ă���̂ŁA���Ȃ��̌����u�d���ʁv�͎d�����ł��ˁH
���ԑ����d����/�ԏd
�Ȃ�A��L�̎��͕����I�Ɍ��ł���B
�ԑ��̒P�ʂ� m/s
�d�����i���Ȃ��̌����d���ʁj�̒P�ʂ� W �ł����A�g�ݗ��ĒP�ʂŌ����� J/s �܂� kgm2/s3 �Ȃ̂ŁA�ԏd�� kg �Ŋ����Ă����x�ɂ͂Ȃ�܂���B
�P�ʂƂ��ẮA���x�Ɨ́i��R�j�̐ς��o�́i��R�ɂ���Ď�����o�́j�ɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19896082�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�d���ʂł͖����A�d�����i���ԓ�����j�ɒ������邸��B
�d���i�ʁj���d��*�����i���E�����j
�d�������d��/���ԁi���E����/���j���d��*���x�i���E����/���j
�ő��͒������ׂ��Ƃ���͖��������B
�����ԍ��F19896218
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�������A�d���͗͂Ƌ����̐ρi�����I�ɂ̓g���N�Ƃ������Ӗ������j�ł���A���ʂƋ����̐ςł͂���܂����B
�S�������āA�d�͂ɋt����Ďd��������Ȃ�A���ʁiKg�j�Əd�͉����x�im/s2�j�Ƌ����im�j����d�������߂鎖���ł��܂����A�P�g���͒P�� 1000kg �Ƃ������ʂ̒P�ʂł�����A���ʂƋ����̐� kgm �͎d���� W �ɂ͂Ȃ�܂���B
�����ԍ��F19896254�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�A�����炵�܂�m(__)m
�܂��A���ʂ̒P�ʂł���L���O�����ikg�j�ƁA�͂̒P�ʂ̈��ł���L���O�����d�ikg-f�j���A�S�`�������ɂȂ��Ă���C�����܂��B
���ƁA��L����
�y��z
���ʂƋ����̐� kgm �͎d���� W �ɂ͂Ȃ�܂���
�y���z
���ʂƋ����̐� kgm �͎d�� J �ɂ͂Ȃ�܂���
�����ԍ��F19896306�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�����������Ɠǂނ̂�����ł��˂���
������Q���Ȃ�����̗\�K�p
http://macasakr.sakura.ne.jp/T05TorqueHorsePower.html
����̗���̗\���p
http://macasakr.sakura.ne.jp/T21TorqueHorsePower.html
���w���ł�������g���N�Ɣn�̘͂b�i�g�b�v�y�[�W�j
http://macasakr.sakura.ne.jp/index.html
�����ԍ��F19896327
![]() 0�_
0�_
���́`
�܂��b���A�����͂́A�G���W���g���N�̍����Ō��܂�̂��A�o�͂̍����Ō��܂�̂��H
�Ƃ����c�_�ɂȂ��Ă��Ȃ��ł��傤���H
���̎ԑ��ł̉�����(����R�ɑł������ĎԂ�O�ɐi�߂��)�́A�쓮�͂̍����Ō��܂�A�Ƃ����̂͂�낵���ł���ˁH
�쓮�͂̌��͓��R�A�G���W���g���N�ł����A�G���W���g���N��T/M�ɂ���āA�쓮�͂Ƃ��đ傫�������������o���܂��B
�������A�쓮�͂�傫������A���̕������ԑ��͒x���Ȃ�܂��B
(�쓮�́��쓮�ւ̃g���N���G���W���g���N×�M����A�ԑ����쓮�ւ̉�]�����G���W����]��÷�M����)
�G���W���g���N���Ⴍ�Ă��A����]�܂ʼn�G���W���Ȃ�A�M�����傫�����āA�쓮�͂�傫���o���܂��B
����́A�쓮�ւ̃g���N(�쓮��)×�쓮�ւ̉�]��(�ԑ�)���G���W���g���N×�G���W����]�����o�́A�������Ƃ����Ӗ��ł��B
��̓I�ȎԂł́A�����F�ԑ��A�c���F�쓮�͂̃J�[�u�́A�G���W���P�̐��\�̉����Frpm�A�c���F�g���N�̌`�̑����`�ł��B
�܂�A�ő�g���N��]���ł̋쓮�͂��ő�ƂȂ�̂ŁA���������̂����m��܂���B
�ł́A���̍ő�g���N��]���ł̎ԑ��ŁA�ō��o�͉�]�����g���悤�ȃM����̐ݒ��������A�쓮�͂͂ǂ��Ȃ�ł��傤�H
�K���A�ō��o�͉�]�����g�������쓮�͍͂����Ȃ�܂��B
(�����A�G���W����]��×�G���W���g���N�@�̒l����ԍ����̂ł�����B)
���႟�A�܂����̃M����ł́A�ő�g���N��]���ł̋쓮�͂́A�����ƍ����Ȃ��Ă����ˁA�Ƃ������Ƃł����A
�܂��M�����ύX���āE�E�E�ƉʂĂ��Ȃ��o����̂�CVT�Ƃ������ł��B
���E�쓮�ւ��n�ʂ��R���āA�Ԃ͑O�ɐi�ށB
���E�G���W������쓮�ւɗ͂�`�B����̂ɂ́A�e�R�̌����������B
���E�o�͂Ƃ́A��]���ƃg���N�̐ςł���B
���M����ɂ���āA�G���W���g���N�̋쓮�́A�G���W����]���̎ԑ��@�̊W���ω����܂��B(������𗧂Ă�A�����炪������)
�������Ƃ����Ă悤�Ƃ���A�G���W���g���N�ƃG���W����]�����|�����킹�����l(���o��)����������K�v������܂��B
���u���������̘b�Ƃ��āA�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�v�Ƃ����͖̂{�����H�Ƃ����c�_�͕s�v�ł��B
�����ԍ��F19896529
![]() 2�_
2�_
���G���W���g���N���Ⴍ�Ă��A����]�܂ʼn�G���W���Ȃ�A�M�����傫�����āA�쓮�͂�傫���o���܂��B
����́A�쓮�ւ̃g���N(�쓮��)×�쓮�ւ̉�]��(�ԑ�)���G���W���g���N×�G���W����]�����o�́A�������Ƃ����Ӗ��ł��B
�M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B
���Ǘ]�v���ɐ���A���ʂ͕ς��Ȃ������B
�g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B
�����ԍ��F19896569
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B
������A���̕��A�i�ނ悤�ȉ�]���܂ʼnȂ��Ƃ����܂���B
���g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B
�쓮�ւ̃g���N���ˁB
�ł́A���̃X���̍ŏ��̂`�Ƃa�ł́A�G���W���g���N�̍����`�̕����������ǂ��̂ł��ˁH
�����ԍ��F19896647
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ�
�G���W����]���������Ȃ�A�����ł��ˁB
�G���W����]�����Q�{�ɂ��Ă��g���N�������ȏ゠��A�M������Q�{�ɂ��Ă��^�C���̉�]�����i�ދ������ς��Ȃ����A�����ȏオ�Q�{�Ȃ猳�̃g���N���傫���Ȃ邩��A������]���Ńg���N���傫���i�܂�o�͂��傫���j�����������ǂ��Ȃ�n�Y�ł���ˁB
�ǂ����ăR�R�܂ŋc�_���t�߂肷�邩�ȁH
�����ԍ��F19896654�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���M�����傫��������i�ދ��������Ȃ��Ȃ邸��B
�����Ǘ]�v���ɐ���A���ʂ͕ς��Ȃ������B
���`�ƁA�����炻��������]�����Ȃĉ҂���ł����ǁE�E�E
�i�����܂Ŕ���ȃg���N���͂Ȃ��ł���j
���g���N���グ�Ȃ���������͑�������Ȃ������B
�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v
�g���N���グ��A��]������̏o�͂��㏸���鎖�ɂ��A�����Ȃ�͎̂����ł��B
�������A�g���N�l���Ⴂ�ꍇ�ł��A��]���ł��̍����U�ł��܂��i�o�͏㏸�j�B
���̈׃g���N�������A����������ƌ������_�͌��ł��B
�i��]���𐧌�����Εʂł����E�E�E�j
�����ԍ��F19896677
![]() 0�_
0�_
�쓮�́��́��g���N����B
�Ȃ�A�A�N�Z���ݔ����𑝂₵�A�g���N���グ�鎖����]���グ�邱�Ƃ���B
�g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����B
���@�ł��g��Ȃ�����A�����@�A�ϑ��@�ł�������ł��Ȃ����B
�����ԍ��F19896747
![]() 0�_
0�_
���Ȃ�A�A�N�Z���ݔ����𑝂₵�A�g���N���グ�鎖����]���グ�邱�Ƃ���B
��]�����㏸����ɂ�āA�s�X�g���^���������Ȃ邩��@�B�I�ύt�������A�ő�g���N�����l���߂���ƃg���N�͌������܂��B
���g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����B
���₢��A�g���N�l���ꏏ�ʼn�]�������{�ɂ����Ȃ�A�o�͂͌��サ�i�ދ����������Ȃ�܂�����`�i�j
�����ԍ��F19896781
![]() 1�_
1�_
�����t�g�^�[������
���쓮�́��́��g���N����B
�M���䁁2��T/M���g���ƁA
�G���W���g���N��2�{�̋쓮�g���N��������A�쓮�ւ̉�]���̓G���W����]����1/2�ɂȂ�A
�Ƃ��������������Ȃ��悤�ł�����A�����A���Ȃ��ɉ��������Ă����ʂł��B
���Ȃ��́A
�uCVT�ŁA�ō��̉��������邽�߂ɂ́A�ő�g���N��]�����L�[�v���鎖���B�v
�u�L�i�ϑ��ŁA�ō��̉��������邽�߂ɂ́A�ő�g���N��]���t�߂��g�p���鎖���B�v
�ƁA��̌�m�̂悤�Ȏ��������Ă���̂ł���B
�����@�ł��g��Ȃ�����A
�e�R�̌����͖��@�ł͂���܂���B
�����ԍ��F19896822
![]() 2�_
2�_
�����t�g�^�[������
�G���W����]���� 3000rpm �g���N�� 100N�Em �Ƃ��܂��傤�B���̎��̏o�͖͂� 31kW �ɂȂ�܂��B
�ϑ��@�őI�������M���̃M���䂪 2.5 �Ńt�@�C�i���̃M���䂪 4 �Ȃ�A�S�̂̃M����͗��҂̐ςł��� 10 �ɂȂ�܂��B
�܂�^�C���̉�]���� 300rpm �ɂȂ�̂ł����A�u���Ɂv�^�C���̃g���N�� 100N�Em �ŕς��Ȃ��Ƃ�����A�^�C������̏o�͖͂� 3.1kW �ɂȂ�܂��B
31-3.1=27.9kW �́A��̃h�R�ɏ����Ă��܂��̂ł����H�܂����`�B���X���Ƌ�܂��܂��H
���ƁA��]������̃g���N�Ƃ́A�����I�ɉ����Ӗ����Ă���̂��A�������肦�܂��H
�����ԍ��F19896931�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
>���₢��A�g���N�l���ꏏ�ʼn�]�������{�ɂ����Ȃ�A�o�͂͌��サ�i�ދ����������Ȃ�܂�����`�i�j
���ǁA�������ς��Ȃ���A�쓮�ւ̈��]�̃g���N��1/2�ɂȂ邩��A���Ԃ��{�|�����Ă��܂����猋�lj����x�͕ς��Ȃ�����B
�o�͂��オ��̂ɁA�g���N�������Ȃ�����͓����ƂȂ�A��͂�����̓g���N�ˑ����Ă��邸��B
�����ԍ��F19896986
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���Ȃ��́Akakkurakin ����ł��傤���H
���̃X���̍ŏ��̂`�A�a�ǂ��炪�����͂������̂��������肢�܂��B
�����ԍ��F19897065
![]() 5�_
5�_
���o�͂��オ��̂ɁA�g���N�������Ȃ�����͓����ƂȂ�A��͂�����̓g���N�ˑ����Ă��邸��B
���������āA�u�G���W�������g���N�v�Ɓu�쓮�ււ̏o�̓g���N�v���������Ă��܂��H
�G���W���g���N�����ʼn�]�����{�ɂȂ�A�~�b�V�����ւ̓��͂��{�ɂȂ��Ă���̂�����A�~�b�V��������̓o�͂��{�ɂȂ�̂ł���B
�����ԍ��F19897074
![]() 0�_
0�_
���킟...�A�܂������Ă��B
�g���N�e���̋������x���ꂽ���X��...�B
���ō������o�͂ɂ��Ƃ���Ȃ̂͐������Ǝv���B
�������A�������E�ɂ͏d�͂▀�C�E��C��R�Ƃ��������ׂ����݂���B
���ׂ�Ŕj����̂̓g���N�ł����ďo�́i�d�����j�ł͂Ȃ��B
����͕����邪�A�g���N�h�̃g���N�Ƃ������t�͂����Ӗ��������R���R���ς�邩��M�p�o����B
�����Ō����Ƃ���̃g���N�Ƃ̓^�C���̋쓮�͂ł���A�����ăG���W���g���N�̎����w���Ă͂��Ȃ��B
�G���W���g���N��������ł��������Ă��A�����@��g�ݍ��ނ��Ƃŋ쓮�͂͏グ����B
�G���W���g���N�������Ă��g�����X�~�b�V������������܂Ƃ��ɓ����Ȃ���B
�o�͂��������������̂͐^���B
�ő�o�͂��������������Ƃ����Ɨ�O�����邪�A
�ᑬ�g���N���������ᑬ����o�͂�����
�Ƃ������ƂȂ̂Ō��NJW���Ă���̂͏o�́B
�����ԍ��F19897334�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
�P����r����Ȃ�A�M�A�䂪�ǂ��ł���A�����ԑ̂ŁA�G���W���ƃ~�b�V�����A�f�t���Ⴄ�����̔�r���l������V���v���ł��傤�B
�A�N�Z���ׂ����蓥��ł��鎞�́A�^�C���Ԏ��̏o�́i���g���N���Ԏ���]���^�萔�j�ōl������A�A�A�A�B
�g���N���傫���A�A�A�o�͂��傫���A�A�A�ǂ��Ⴄ�́H�H
�o�́��g���N����]���^�萔
����Ƃ��A�g���N�A�o�͂̒�`�Ⴄ�́H�@�݂Ȃ�����`�A������r�H�H�H
�l���ꂼ�ꏟ��Ȓ�`�A������������ł���ł��傤�B
���Ȃ��Ƃ��A
���@�d���i�ʁj���d��*�����i���E�����j
�G���W���ɂ��d���Ɖ]���ɂ͖���������B
����C���̓��ŃA�N�Z���n�e�e�ł����x�ێ�����ꍇ�����邵�A���x�A�b�v�����邵�B
�����ԍ��F19897647
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���g���N���ς��Ȃ���A��]��{�ɂ����Ƃ���ŁA��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��i�ދ�����1/2�ɂ����Ȃ�Ȃ�����
�܂��A�ϑ��@��p����ꍇ�A�G���W�����ƃ^�C�����ŁA��]���ƃg���N�Əo�͂��A�M����ʼn����ω����ĉ����ۑ������̂��A���̒��Ő������Ă��������B
�g���N�������ɂȂ�Ίp�����x�������ɂȂ�̂ŁA�u�������Ԃł���Ίp���x�i��]���j�̑����������ɂȂ�܂��v���c
��ӂ����������ƁA���ۂɃN���}���������������ŁA�G���W����]���̏㏸���͓����ł��傤���A�Ⴄ�ł��傤���B�Ⴄ�Ȃ�Ή������̌����ł��傤���H
�^�C���̉�]�����Q�{�Ȃ�A�P��]�̎��Ԃ͔����ɂȂ邵�A�������ԂȂ�Q�{�̋�����i�݂܂���B�G���W�����ƃ^�C�������A�S�`�������ɂ��Ă��܂��H
�����ԍ��F19897968�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���G���W���g���N�����ʼn�]�����{�ɂȂ�A�~�b�V�����ւ̓��͂��{�ɂȂ��Ă���̂�����A�~�b�V��������̓o�͂��{�ɂȂ�̂ł���B
����́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��B
�g���N�͓����ƌ����Ă��邸��B
�^���ʁE�G�l���M�[�ۑ��̖@��
�G���W���Ŕ��������^���ʂ̓��J�j�J�����X�������^�C���쓮�̉^���ʂƓ�������B
���@�ȊO���̖@����j�鎖�͏o���Ȃ����B
�����ԍ��F19898055
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
������́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��
�������A�Ⴂ�܂��B
�G���W�������������Ă���g���N�������ŁA�G���W���̉�]�����Q�{�ɂȂ�A�G���W�������������Ă���o�͂��Q�{�ɂȂ��Ă���̂ł���B
�ϑ��@���g�����ŁA�Ⴆ�M���䂪�Q��������A�o�͂̉�]���͓��͂̉�]���̔����ɂȂ�ς��ɁA�o�͂̃g���N�͓��͂̃g���N�̂Q�{�ɂȂ�܂��B
�`�B���X�������A���͂��ꂽ�G�l���M�[�i���͑��̉�]���ƃg���N�Ǝ��Ԃ̐ρj�ƁA�o�͂����G�l���M�[�i�o�͑��̉�]���ƃg���N�Ǝ��Ԃ̐ρj�́A��ʂ�ۑ�����Ă��܂��̂ŁA���@�ł����ł�����܂���B
�����ԍ��F19898113�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
������́A�g���N��2�{�ɐ����Ă��邸��B
���g���N�͓����ƌ����Ă��邸��B
�������Ȃ��Ă��܂����I
�G���W���g���N�́A���ƌ����Ă���ł͂���܂��B
���G���W���Ŕ��������^���ʂ̓��J�j�J�����X�������^�C���쓮�̉^���ʂƓ�������B
�u�o�́i�n�́j����]��×�g���N×�W���v
�G���W���g���N���ω����Ȃ��Ă��A��L�̌v�Z��G���W����]����{�ɂ���A�o�͂��㏸���܂���I
�G���W���Ŕ��������^���ʁ��o�́i�n�́j
���g�Ō��_�ɒB�����悤�ł��ˁI
�����ĉ^���ʂƋK�肵���Ȃ�A�g���N�͊Y�����܂���i�g���N�͉^���ł͂Ȃ��j�B
���Ȃ݂Ƀ��t�g�^�[���������Ă���A�u�g���N�v�͉��̃g���N�Ȃ̂ł����H
���͏�y�ї��_����u�G���W���g���N�v�u�쓮�փg���N�v�Ƃ��قȂ��Ă��܂����H
�����ԍ��F19898121
![]() 0�_
0�_
���t�g�^�[���������Ă邱�Ƃ̓g���N�e���ƑS���������ƁB
�͂����茾���ĊԈႢ�B
�G�l���M�[�ۑ����������o����Ȃ畁�ʂ͗����o������ǂ��B
CVT�����������z�I�ȃ��X�̖����g�����X�~�b�V�����ł���P�ԗ������₷�����f���ɂȂ�B
�ő�g���N������]���ŕϑ�������A�ő�o�͔�����]���ŕϑ����������M�A�䂪�����A�쓮�͂������Ȃ�̂ʼn����͑����B
�L�i���ϑ��@�̏ꍇ�̓G���W����]�����ϓ����邩���₱�������ǁA���z�I��CVT�ł���l����]�n����Ȃ��B
�����ԍ��F19898164�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
>���t�g�^�[���������Ă邱�Ƃ̓g���N�e���ƑS���������ƁB
>�͂����茾���ĊԈႢ�B
���̗l�ł��ˁB
20 �� 60km/h �����̂悤�ȏꍇ�A
�X�^�[�g���ƃS�[�����̑��x�����܂��Ă���̂ŁA
�X�^�[�g���ƃS�[�����̑��x�͓����Ɍ��܂��Ă���B
2�̃N���}�̃X�^�[�g���ƃS�[�����̏o�͂������Ȃ�A
���̎��̃G���W���g���N���쓮�g���N�������Ɍ��܂��Ă���B
�����āA�����ݒ肵������B
�r���ŕϑ����Ȃ��̂Ȃ�A�^�C������鑬�x�������Ɍ��܂��Ă��邵�A
2�̃N���}�̃M�A������Ă���̂�����A
����̉�]���ő��x���r���Ă������Ɍ��܂��Ă���B
�����āA�����ݒ肵������B
�o�͂̃g�[�^���ɂ���ĕς��̂́A
���̉�]���ɒB����܂ł̎��Ԃł��B
���Ԃ��ς邩������x�ɈႢ���o���ł��B
�g�[�^���o�͂��傫���Ⴄ�̂ɁA
���x�������x�������Ȃ�A
�G�l���M�[�ۑ��̖@������ꂿ�Ⴂ�܂��B
�����ԍ��F19898366
![]() 0�_
0�_
>�O�[�X350����
>�h�����ԑ��Łh�쓮�͂��������������͗ǂ��Ȃ�܂��B
���{�I�ɁA�������Ⴂ�܂��B
���ꂪ���Ⴂ�̌��ł́H
�쓮�͂́A�^�C���̓����]���ł̗͂ł�����A
�ԏd���R�������ŁA
���x�i�^�C���̉�]���j�܂œ����Ȃ�A
���̎��̋쓮�͕͂K�������ɂȂ�܂��B
�Ⴂ������̂Ȃ�A�������x�ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B
�쓮�͂�������A
�쓮�͂��Ⴂ�N���}�����A
�����Ƒ����� ���̓����]���ɒB���邾���̘b�ł���B
�����x���ׂ�̂Ȃ�A
�́i�g���N�j����Ȃ����āA
�d���i�o�́j�Ŕ�ׂȂ��ƈӖ��������ł��B
�����]���̃g���N���o�͂Ɋ��Z���āA
��]�����Ƃ̏o�͂�S�č��Z����K�v������܂��B
����ł��ʂ��Ȃ��낤���H�H�H
�����ԍ��F19898403
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
���o�͂̃g�[�^���ɂ���ĕς��̂́A
�����̉�]���ɒB����܂ł̎��Ԃł��B
�u�Ԃ̉����͂������ꍇ�ł��A�����Frpm�̃O���t�̖ʐς͈Ⴄ�ꍇ������v�Ƃ��������A���������悤�ŁA�����ł��B
�����ԍ��F19898415
![]() 0�_
0�_
>�u�Ԃ̉����͂������ꍇ�ł��A�����Frpm�̃O���t�̖ʐς͈Ⴄ�ꍇ������v�Ƃ��������A���������悤�ŁA�����ł��B
�Ӗ��s���ł���B
����ρA�ʂ��Ă��Ȃ��Ȃ��B
�������x�ɒB����܂ł̎��Ԃ��Ⴄ��ł���B
�����x���Ⴄ��ł���B
�^�C�������Ⴄ��ł���B
��������
�G���W���o�͂́A�G���W�������o�����p���[�ł��B
�쓮���邽�߂̃p���[�́A�t���N�V�������X�������A
�G���W�������o�����p���[�Ɠ����ł��B
�u�����ɂ́A�����͂�ō����x�̓G���W���̏o�͂Ō��܂�܂��B�i����j�v
�E�E�E���Č����̂Ȃ�A
�u�����ɂ́A�����͂�ō����x�͋쓮�͂̋쓮�o�͂Ō��܂�܂��B�v
�E�E�E�ƂȂ�͂��ł����A
���́A�g���N�A�g���N�ƘA�Ă���̂ł��傤���H
�G���W���o�͂̍��v���v�Z����ςނ�ł��B
�G���W���o�͂̍��v���v�Z����ƖʐςɂȂ�܂��B
�����ԍ��F19898433
![]() 1�_
1�_
���ۂ�ۂ� �D����
���쓮�͂�������A
���쓮�͂��Ⴂ�N���}�����A
�������Ƒ����� ���̓����]���ɒB���邾���̘b�ł���B
����������͂��ǂ��A�Ƃ����܂��B
�������x���ׂ�̂Ȃ�A
���́i�g���N�j����Ȃ����āA
���d���i�o�́j�Ŕ�ׂȂ��ƈӖ��������ł��B
�܂��A���t�̊ԈႢ�B
�o�́��d����
�́��d���@�ł��B
�����͖{���I�ȕ����ł͂Ȃ��Ƃ��āA
�����͏o�͂Ŕ�ׂ�̂ł��傤�H
�쓮�ւ̉�]��×�쓮�ւ̃g���N�@�����h�ȏo�͂ł���B
�����ԑ�(�������쓮�ւ̉�]��)�ŁA�쓮�ւ̃g���N(���쓮��)�����������A�o�͍͂����ł��B
�����ԑ�����S�J��������̂ɁA���̂Ƃ��̑S�J�ł̋쓮�͂������Ȃ̂ɁA�����͂��Ⴄ�Ƃ����̂��A�����ł��Ȃ��̂ł��B
�����ԍ��F19898475
![]() 0�_
0�_
���݂܂���B
�u�́��d���v�ł͂Ȃ��ł��B
�u�o�́��d�����v�͂����ł��B
�����ԍ��F19898537
![]() 0�_
0�_
�X���傳���
�܂��ŏ���
�������̌v�Z���@���Ⴄ�Ƃ������ɋC�Â��Ă��������B
�����`���b�ƕς����B���ĂˁB
�X���傳������O���t�i�E�ԁj��
���܂��ܐƓ����^�C���ɂȂ�悤��
�ƊT�˓����ʐςɂȂ�悤�ȗ������Č��܂����B
�Ɗ�{�G���W���Ƃ��܂��傤�B
�́A�ō��o�͂��o�͖ʐς��Ɠ����ł�����A
�r�C�ʂ������ȍ���]�^�G���W���ɂȂ�܂��B
�X���傳��̌v�Z�ł��A
���Ɠ����^�C���ɂȂ�܂��ˁB
����]�^�Ŏg���h���G���W���ł����A
�捇�������^�C���ł����B
����
�ɉߋ��@��t���Ē��ᑬ���p���[�A�b�v������A
�Ԃ̃O���t�ɂȂ�܂����B
����ł�
�X���傳��̌v�Z�ł́A
���`��ԁA�����^�C���ɂȂ��ł���H
�ς��Ǝv���܂��H
����ŕς��Ǝv��Ȃ��悤���ƁA
�b���i�܂Ȃ����ǁE�E�E�E�i��
�E�E�E�Ŗ{��
>�쓮�ւ̉�]��×�쓮�ւ̃g���N�@�����h�ȏo�͂ł���B
�쓮�ւ̌v�Z���Ԉ���Ă���̂ł́H
�������Ԉ���Ă���̂͑z���ł����E�E�E
�@���i�z���j
�쓮�ւ̏o�͂ƃG���W���o�͂̓C�R�[���Ȃ̂ŁA
�쓮�ւ̓����]���ł̋쓮�o�͂����߂�ɂ�
�܂��ŏ��ɂ��̎��̎ԗւ̉�]������A
���̎��̃G���W����]�����t�Z����K�v������܂��B
�G���W����]�������߂�ꂽ��A
���̎��̃G���W���o�͂��쓮�ւ̏o�͂ł�����A
���̎��̃G���W���o�͂����ԗւ̉�]���Ŋ���K�v������܂��B
��������Ă܂����H
�����ԍ��F19898573
![]() 0�_
0�_
�G���W���o�� �� �쓮�͏o�͂�����A
���̎��̃G���W���o�͂��ԗ։�]���Ŋ��邾���ŃC�C�̂ł́H
�ԗւ̉~���͈��Ȃ̂ŁA
�ԗւ̉�]���Ƒ��x�͔�Ⴕ�܂��ˁB
�Ȃ̂ŁA
�ԗւP��]�ł̏o�͂��v�Z����ςނƁB
50�n�͂̃G���W�����낤���A
1,000�n�͂̃G���W�����낤���A
�ԗւP��]�œ���������i�ނ̂ŁA
�n�͂��傫���ق�1��]�ɕK�v�Ȏ��Ԃ��Z�k�����B
�@��
�������ǂ��I
�����ԍ��F19898639
![]() 0�_
0�_
���̃X���̗�������Ă���ƁA�����悻�N��������̒��Ԃ������Ă����̂������Ă��܂��ˁ`�i�j
����܂ŕς��āA���������������̂��낤�ˁH
�N�Ƃ͌����܂��A�}�b�`�|���v�I�ȏL��������E�E�E�E
�����ԍ��F19898741
![]() 0�_
0�_
�����A���C�t�����B
�ʐςƌ����̂́A
���F�ň͂����ł���B
�́A1000�`1500��]�܂ʼn����A
�ԂƗ́A2000�`3000��]�܂ʼn����A
���ꂼ��̉����^�C����\�������Ȃ̂ŁA
�o�̖͂ʐς���]���͈͓̔��ł��B
�b���ʂ��Ȃ��̂́A
���̕������H
�����ԍ��F19898749
![]() 0�_
0�_
>eoffice����
>����܂ŕς��āA���������������̂��낤�ˁH
>�N�Ƃ͌����܂��A�}�b�`�|���v�I�ȏL��������E�E�E�E
�����I
�N�H�N�H
�����āB
�����ԍ��F19898805
![]() 0�_
0�_
���A���ꂩ��A
����30�n�͂̎��̋쓮�o�͂�
�^�C���P��]���Ōv�Z�����Ƃ��Ă��A
����͉����ׂ̈̋쓮�o�͂���Ȃ��ł�����ˁB�O�̂��߁B
�����x�͂܂��������Ă��Ȃ��̂ŁA
�����̂��߂̏o�͂��܂��g���Ă��܂���B
�����ׂ̈Ɏg����
�^�C���P��]���̏o�͂̊T�Z���o�������̂Ȃ�A
2��]�ڂ̏��߂̏o�͂���A
1��]�ڂ̏��߂̏o�͂������āA
�T�� 0.5 ���|�������̂ɂȂ�܂��ˁB
�Ⴆ�A
1��]�ڂ̍ŏ��� 1.0PS �ŁA
2��]�ڂ̍ŏ��� 1.2PS �Ȃ�A
���̍��� 0.2PS �� 1/2 ��0.1PS �������Ɏg��ꂽ���Ă��Ƃł��B
�����l�͓K���ł��B�l���������ˁB
�����ԍ��F19898921
![]() 0�_
0�_
�����꒚���łɁE�E�E
�i�A�����߂�j
�쓮�͋Ȑ��Ƃ́A
�e�M�A�̋쓮�͂�\���O���t�̂��Ƃ������Ă���̂��ȁH
�����������c
�@��
http://www.weblio.jp/content/%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%9B%B2%E7%B7%9A%E5%9B%B3
����́A
���z�̊p�x�ɂ���ēo��邩�ǂ���������O���t�ł���B
���̃O���t�Ō����A
���z 15% �̏ꍇ�A
2����1���ł����o��Ȃ��B
3���ȏゾ�ƃg���N���s�����Ă��ēo��܂��`��B
���ĈӖ��Ȃ��ǁE�E�E
�����ԍ��F19898975
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
���ƊT�˓����ʐςɂȂ�悤�ȗ������Č��܂����B
�S�R�A�Ɠ����ʐςɂ͌����܂��ǁH�H�H
�Ђ���Ƃ���30PS�ȏ�̖ʐς̂��ƁH�@(30PS�ɉ��̈Ӗ�������̂�����Ȃ��ł����E�E�E�B)
���X���傳��̌v�Z�ł��A
�����Ɠ����^�C���ɂȂ�܂��ˁB
�Ȃ��Ȃ��ł���B
�������Ă�r���ŏo��(�쓮��)���Ⴍ�Ȃ��Ă���̂�����B
�����ԑ��A�F1250rpm��37PS�A�F2500rpm��31PS���炢�H
(�̃M���䁁1.5�A�̃M���䁁3�A�Ƃ����ꍇ)
���捇�������^�C���ł����B
�ǂ����ǂ��v�Z������A�����^�C���ɂȂ�̂ł����H
�����`��ԁA�����^�C���ɂȂ��ł���H
�ƐԂ͓����ł����A�͒x���Ɍ��܂��Ă�ł���B
�ǂ����āA�X�^�[�g�ƃS�[���̏o�͂��������Ȃ�A�����^�C���ɂȂ�́H
(�́A���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u���ǂ���������ďd�Ȃ�Ȃ��ł���B�@�Ђ���Ƃ��āA�h���s���\�Ȑ��h������Ȃ��H)
���쓮�ւ̓����]���ł̋쓮�o�͂����߂�ɂ�
���܂��ŏ��ɂ��̎��̎ԗւ̉�]������A
�����̎��̃G���W����]�����t�Z����K�v������܂��B
���G���W����]�������߂�ꂽ��A
�����̎��̃G���W���o�͂��쓮�ւ̏o�͂ł�����A
�����̎��̃G���W���o�͂����ԗւ̉�]���Ŋ���K�v������܂��B
������`�A
�̃M���䁁1.5�A�Ԃ̃M���䁁3�A�Ɖ��x�������Ă܂���ˁH
�Ƃ������́A
�F�G���W����]����1000��1250��1500rpm�@(�쓮�։�]����667��833��1000rpm)
�ԁF�G���W����]����2000��2500��3000rpm�@(�쓮�։�]����667��833��1000rpm)
(�F�G���W����]����2000��2500��3000rpm�A�M���䁁3�Ƃ��āA�쓮�։�]����667��833��1000rpm)
�F�o�́�30��37��40PS�@(�쓮�փg���N��32.2��31.8��28.6kgm)
�ԁF�o�́�30��37��40PS�@(�쓮�փg���N��32.2��31.8��28.6kgm)
(�F�o�́�30��31��40PS�A�M���䁁3�Ȃ�A�쓮�փg���N��32.2��26.6��28.6kgm)
�����̎��̃G���W���o�͂��ԗ։�]���Ŋ��邾���ŃC�C�̂ł́H
������`�A
���s���\�Ȑ��̋쓮�̓J�[�u�͓����ɂȂ���āA��������x�������Ă܂���ˁH
�ƐԂ́A�G���W���o�͂��쓮�։�]���Ŋ������l���A�ǂ̎ԑ��ł������ł����āB
(�Ⴆ�A30PS�A667rpm�̂Ƃ��ɁA�g���N��32.2kgm�ɂȂ���Čv�Z�͏o�����ˁH)
���ԗւP��]�ł̏o�͂��v�Z����ςނƁB
������`�A
�ƐԂł̓M���䂪�Ⴄ�̂�����A�ԗւ�1��]�̂��邤���ɁA�G���W��������]���邩�́A�Ⴄ���āB
�ԗ�1��]����̂ɁA�Ԃ͔{�A�G���W�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���B
�܂�A�ɑ��ĐԂ́h�����F�G���W��rpm�̏ꍇ�h�A�{�̖ʐςƂȂ�̂ł���B
���e�M�A�̋쓮�͂�\���O���t�̂��Ƃ������Ă���̂��ȁH
�������������c
����ς�A���܂Łh���s���\�Ȑ��h�̎��������m�Ȃ������̂ł��ˁB
�����z�̊p�x�ɂ���ēo��邩�ǂ���������O���t�ł���B
�����ƁA��̂ق��ɁA�u�ԑ��ɑ���쓮�͂Ƒ��s��R�̊W��m��A���̍�(�]�T�쓮��)����������\�A�E�E�E�v
�ƁA�����Ă���܂���B
���̋쓮�̓J�[�u���҂����蓯����������A�������\�͓������Ǝv���܂���H
(�����ŁA�v��Ȃ����Č�����ƁA�ǂ����悤������܂��B)
���̋쓮�̓J�[�u���҂����蓯�������ǁA�M���䂪�Ⴄ�ꍇ�́A�G���W�����\��ƐԂƂ��Ď����Ă��邾���ł��B
�܂�A�ƐԂ͉������\�������Ȃ̂ɁA���F�̖ʐς͈Ⴄ�Ɛ\���Ă���̂ł��B
���Ȃ����ʐς��Ǝ咣����Ă���̂́A�����M����̏ꍇ�Ɍ��邨�b�ł͂���܂��H
�u�����͂́A�G���W���P�̐��\�Ȑ�(�����Frpm�A�c���F�o��)�̖ʐςƔ�Ⴗ��B�@�A���A�M���䂪�����ꍇ�B�v
�ƁA�������Ȃ�[���ł����E�E�E�B
�����ԍ��F19899163
![]() 1�_
1�_
>�O�[�X350����
>�S�R�A�Ɠ����ʐςɂ͌����܂��ǁH�H�H
>�Ђ���Ƃ���30PS�ȏ�̖ʐς̂��ƁH�@(30PS�ɉ��̈Ӗ�������̂�����Ȃ��ł����E�E�E�B)
30PS�ȏ�̖ʐςɌ��܂��Ă邶��B
����ρA�����Ŋ��Ⴂ���Ă����ȁB
30PS ����̉������v�Z�������̂ŁA
30PS ��肵���͌v�Z����K�v�͂���܂���B
>������`�A
>�ƐԂł̓M���䂪�Ⴄ�̂�����A�ԗւ�1��]�̂��邤���ɁA�G���W��������]���邩�́A�Ⴄ���āB
>�ԗ�1��]����̂ɁA�Ԃ͔{�A�G���W�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł���B
�G���W��������]���Ă悤���A
�G���W���o�� �� �쓮�o�� �ł��B
�Ԃ��A�{�̃G���W����]���ʼn���Ă������A
�o�͂́A�����Ōv�Z����K�v������B
���႟�R����������I
�@��
�G���W���o�� �� �쓮�o��
����ŃC�C�ł����H
�����ԍ��F19899190
![]() 0�_
0�_
>���̋쓮�̓J�[�u���҂����蓯����������A�������\�͓������Ǝv���܂���H
>(�����ŁA�v��Ȃ����Č�����ƁA�ǂ����悤������܂��B)
���z��o��邩�ǂ����̐��\�ł��B
�����ԍ��F19899207
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
�����z��o��邩�ǂ����̐��\�ł��B
�ۂ�ۂ� �D����́A���̋쓮�̓J�[�u���҂����蓯���ł��A�������\�͓������Ƃ͎v��Ȃ��̂ł��ˁH
�����ԍ��F19899295
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
�����A�E�オ��̋Ȑ������z�Ƒ��s��R�������Ă���A�O���̐��͍�����邩�ۂ��ł͂���܂���B
�e�M���̎R�^�̐����쓮�͂ł���A�i���z�Ɓj���s��R�Ƃ̍����A�����͂ł��傤�H
�����ԍ��F19899311�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
�g���N�������ŁA�Е��̉�]����2�{�ɂ��A���͕ς��Ȃ��ꍇ�A2�{�ɂ������̃^�C���̈��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��A���R1��]���鎞�Ԃ�2�{�ɂȂ�B
���ɁA�A�C�h�����O�����A�g���N�Ɖ�]������Ⴕ�đ����Ă����ꍇ�A2�{�ɂ������́A������1/2�ɂȂ�A�����g���N�ɒB����ɂ�2�{�̎��Ԃ�K�v�Ƃ��邸��B
�ۑ��̖@���ɏ]���A���������Ȃ�Ȃ����B
�����Ɏ��ԂłȂ��O���t�ł͉����͉���Ȃ����B
�����x�̒P�ʂ͂���/��2�A��/��2����A���x�������ԂŊ���Ȃ���������x�Ƃ͐���Ȃ����B
�����ԍ��F19899445
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���g���N�������ŁA�Е��̉�]����2�{�ɂ��A���͕ς��Ȃ��ꍇ�A2�{�ɂ������̃^�C���̈��]������̃g���N��1/2�ɂȂ邩��A���R1��]���鎞�Ԃ�2�{�ɂȂ�B
���́`�A�m�F�����Ă��������B
��L�̕��͂̂Ȃ��ŁA
�h�g���N�h�Ƃ̓G���W���g���N�̎��ł��傤���H
�h��]���h�Ƃ̓G���W����]���̂��Ƃł��傤���H
���ƁA���낻��A�` or �a�̂��l���������������������B
�����ԍ��F19899502
![]() 1�_
1�_
Lesson1
��{�I�ɎԂ́A�R�Ď��ł̔����͂𐄐i�͂Ƃ��Ă���B
���̔����͂ɂ��N�����N�̃��[�����g���g���N�Ƃ��ĕ\������Ă���B
������A�����@�A�M�A����ă^�C������]�����Ă���B
�e���ł̑���������A����́��Ō����B
�����łȂ���A�G�l���M�[�ۑ��̖@���ɔ����Ă��܂��B
�����B
�����ԍ��F19899534
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���̎���͖����Ȃ��邨����ł����H
������́��Ō����B
�e�R�̌����́A�G�l���M�[�ۑ��̖@���ɔ�����A�Ƃ������咣�ł�낵���̂ł��ˁH
�����ԍ��F19899561
![]() 0�_
0�_
�������x�̒P�ʂ͂���/��2�A��/��2����A���x�������ԂŊ���Ȃ���������x�Ƃ͐���Ȃ����B
�����x�Ȃ́H
�����Ȃ́H
�����x�Ȃ瓯��M�A��Ȃ�ő�g���N������]������B
�����ōő�����߂�Ȃ�ő�o�͂���B
���̈Ⴂ��������H
���t�g�^�[�����g���N�e���H
�������̊Ԃɂ��X����������Ă���悤�����B
�����ԍ��F19899669�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 1�_
1�_
����{�I�ɎԂ́A�R�Ď��ł̔����͂𐄐i�͂Ƃ��Ă���B
���̔����͂ɂ��N�����N�̃��[�����g���g���N�Ƃ��ĕ\������Ă���B
���ƁA�ׂ����������ǁA�R�Ď��Ƃ������̒ʂ�R�Ă�����ˁB
�����������炻��ُ͈�R�Ă�����B
�G���W���͖җ�Ȑ����ʼn���Ă邩�甚���̕����C���[�W�����₷���낤���ǁB
�����ԍ��F19899680�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
Lesson2
�x�_��蓯�������̃V�[�\�[�ɓ����̏d�̐l�����Βނ荇���B
�Е��̒[�ɑ̏d�������̐l���ڂ��Ēނ荇�킹��ɂ͑̏d�����̐l���������x�_���2�{�̒����Ƃ���Ηǂ��B
���ꂪ�Ă��̌����B
�����Ēނ荇�������G�l���M�[�ۑ��̖@���ɂ���ďؖ�����Ă���B
�e���̃��X������A�G���W�����ƃ^�C�����̃G�l���M�[�͓���ɂȂ�B
�Ȃ�^�C�����̃g���N��2�{�ɂ����̂Ȃ�A��]��1/2�Ȃ�͓̂��R�����B
�����ԍ��F19899828
![]() 0�_
0�_
�܂��܂����₳���ĉ������B
�X���傳�܂̍ŏ��̂���
A�����
�G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgfm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgfm
���̃G���W���̃g���N����2�{�ɁA�܂�g���N��20kgfm�ɂ���Ɖ����ς�肩�H
�o�͂�2�{�A�쓮�ւ̃g���N��2�{�ɂȂ�Ƃ���
���̎Ԃ͂ǂ��ς��܂����H
�����ԍ��F19899849�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
��DEND�C�ۂ���
�����̃G���W���̃g���N����2�{�ɁA�܂�g���N��20kgfm�ɂ���Ɖ����ς�肩�H
�G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=20kgm�@(�o�́�28PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=20kgm
�ƂȂ�܂��B
�a���o�͂������Ȃ�܂��̂ŁA������̕����쓮�͂������Ȃ�A�����͂������Ȃ�܂��B
�����ԍ��F19899881
![]() 0�_
0�_
���X���傳��
���肪�Ƃ��������܂��B
���̏ꍇ�A�o�͂��オ��������Ƃ�����
�ō����x���オ��Ȃ�Ď��͂Ȃ��ł����
�M�A��������ċ쓮�ւ̉�]�����グ�Ȃ�����́A���x�͕ω����Ȃ�
���ɁA�M�A��������ĉ�]�����グ���ꍇ�A�M�A����������������쓮�ւ̋쓮�͂�������A�����͓݂͂邪�ō����x�͏オ��B
�̍l�����ŊԈ���ĂȂ��ł���ˁB���s��R�ȂǍl�����Ȃ��O���
�����ԍ��F19899926�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 0�_
0�_
���ۂ�ۂ� �D����
���������ł��B
���ʐςƌ����̂́A
�����F�ň͂����ł���B
�Ƃ������́A2000�������E10PS����A3000rpm�E20PS�܂ł����o�Ȃ��G���W����ςԂ��A
��������������Ƃ������ł�낵���̂ł��ˁH
�����ԍ��F19899941
![]() 0�_
0�_
��DEND�C�ۂ���
���������Ƃ���A�ԑ����o���Ƃ������́A�쓮�ւ̉�]�����グ�āA����ɋ쓮�͂������Ă����A�Ƃ����M�����
�ǂ��܂őI���ł��邩�H�Ƃ������ł��B
(�t�ɂ����A�ԑ����L�[�v�o����쓮�͂��m�ۂ��A�쓮�ւ̉�]�����ǂ��܂ŐL���邩�H)
�����ԑ����o���Ă���Ƃ��ɁA�쓮�͂���ԍ����ł���̂́A�ō��o�͂��o���Ă����Ԃł��̂ŁA
�o�͂��オ��A�ԑ����X�ɐL�������ł��܂��B
���s��R�ɑ���]��쓮�͂������͂ł��̂ŁA��{�I�ɑ��x���オ��قǁA�����͓݂͂��Ȃ�܂��B
�����ԍ��F19899982
![]() 0�_
0�_
�O�[�X350�����
���{�I�Ȏ����
�G���W���o�� �� �쓮�o��
�E�E�E�̓����͂ǂ��Ȃ�ł���H
���̓����Ȃ��́H
�����ԍ��F19900588
![]() 0�_
0�_
>�`�r������
>�����A�E�オ��̋Ȑ������z�Ƒ��s��R�������Ă���A�O���̐��͍�����邩�ۂ��ł͂���܂���B
>�e�M���̎R�^�̐����쓮�͂ł���A�i���z�Ɓj���s��R�Ƃ̍����A�����͂ł��傤�H
�`�r������炵���Ȃ��ł��ˁB
�쓮�͕͂����ʂ�͂Ȃ̂ŁA
��R�ɑł������Ďԗւ���邩�ǂ����ł��B
�����͂����߂����̂Ȃ�A
�o�͂Ɋ��Z���Ȃ��Ɩ����ł���B
�����ԍ��F19900594
![]() 0�_
0�_
>�O�[�X350����
>���������ł��B
>�Ƃ������́A2000�������E10PS����A3000rpm�E20PS�܂ł����o�Ȃ��G���W����ςԂ��A
>��������������Ƃ������ł�낵���̂ł��ˁH
���̎���͈Ӗ��𐬂��܂���B
��������
�X�^�[�g���̏o�͂��Ⴂ�܂�����A
�X�^�[�g���̑��x�������ɂ͂Ȃ�܂���B
�������������ׂ�����ł��傤�H�H�H
�����ԍ��F19900615
![]() 1�_
1�_
�ȂA�����Ɏア�҂ƍ���Ɏア�҂��݂��̎�_��@���������Ă邾���̍\�}�Ɍ����ė����B
�ア�҂���������Ɏア�҂�@���Ă��A��������̂̓u���[�X���炢�Ȃ���ł���B
�����ԍ��F19900635�@�X�}�[�g�t�H���T�C�g����̏�������
![]() 6�_
6�_
>LUCARIO����
>�ア�҂���������Ɏア�҂�@���Ă��A��������̂̓u���[�X���炢�Ȃ���ł���B
���� �u ����Ɏア�� �v ��@���Ă��� �u �ア�� �v ���Ă̂�LUCARIO����ł����H
����ł����āA�u���[�X����������ƁB
����ŋX�������ƁB
�����ԍ��F19900644
![]() 1�_
1�_
����������Ǝv���Ă�����A�܂������Ă����̂ł��ˁB�B�B
�}�t���߂ł����A
���ۂ�ۂ� �D����
�������͂����߂����̂Ȃ�A
���o�͂Ɋ��Z���Ȃ��Ɩ����ł���B
�쓮�͂��瑖�s��R���������l�i�]�T�쓮�́j���A�ԏd�Ŋ���ƁA���̑��x�ɂ�����������Z�o����܂��B
�Ⴆ�A���p����Ă��鑖�s���\�Ȑ�����K���ɓǂݎ��ƁA�R���W�O�L���ł̋쓮�͂͂Q�O�O�O�m���炢�A���z�[���̑��s��R�͂T�O�O�m���炢�ł��傤���B
���̎ԗ��̎ԏd���P�T�O�OKg�Ɖ��肷��ƁA�R���W�O�L���ł̑S�J�����������̉����x�́A
�P�T�O�ON�^�P�T�O�OKg�@���@�Pm/sec2
�ƌv�Z�ł��܂��B�O�D�P�f���炢�ł��ˁB�i�r�h�P�ʌn��p����A���Z�W�����s�v�ł��B�j
�����Ɍ����A�^�C���Ƃ��h���C�u�V���t�g�Ƃ��̉�]�n�̊������[�����g���v�Z���A�������ʂɊ��Z������Ŏԏd�ɉ����Ȃ���Ȃ�܂��A�܂��傫�Ȍ덷�ɂ͂Ȃ�܂���B
�ۂ�ۂ� �D���L�ڂ��ꂽ�ʂ�A�o�͂ł����_�v�Z�͂ł��܂����A���傢�Ɩʓ|���Ǝv���܂��B
�G���W���o�͂���A���s��R�ɐH����d�����������Z����ƁA�c�肪�����Ɏg����d�����ł��B
�i���s��R�ɐH����d�����́A�O���t����ǂݎ�������s��R�́i�m�j�ƁA���̎��̑��x�im/sec)�̏�Z�Ōv�Z�\�ł��B�j
�����Ɏg����d�����́A�^���G�l���M�[�i1/2mv2)�̑����A���Ȃ킿���Ԕ����Ɉ�v���܂��̂ŁA�ȉ��̕������������܂��B
�i�����Ɏg����d�����v�j�@���@�i�ԏd�j���j�@×�@�i���xm/sec�j�@×�@�i�����xm/sec2�j
��L���������A�����x�̎Z�o���\�ł��B
�����ɂ͉�]�n�������[�����g�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��̕��@�Ɠ����ł��B
�܂��A�G���W���o�͂ƋL�ڂ��܂������A�G���W������^�C���܂ł̑������Öق̓��ɖ������Ă܂��̂ŁA�^�C���o�͂������l�ƂȂ�܂��B
�ȏ�̒ʂ�A���s���\�Ȑ�������A���X���X�̉����x�͎Z�o�\�ł��B
���̎��X���X�̉����x�𐔒l�I�Ɏ��Ԑϕ�����A���X���X�̑��x�������܂��B
�܂�A�c���͋쓮�́A���������Ԃ̃O���t������A���̃J�[�u���̖ʐς́A���̎Ԃ��L�������̔\�͂�\���ƌ����ėǂ��ł��傤�B�i�͊w�p��ł͗͐ςɂȂ�܂��B�j
�c�����G���W���o�́i�d�����j�A���������Ԃł��A���̃J�[�u���̖ʐς́A�G���W�����o�͂����g�[�^���̎d���ƂȂ�܂��̂ŁA������������l�����ŗL���ȕ����ʂł��B
�����A�������G���W����]���ł���ƁA���̖ʐς͈Ӗ��̂��镨���ʂɂ͂Ȃ�܂���B
���́A�X����l����Ɍf�ڂ����ԂƐ̃O���t�ƂȂ�܂��B�i�g���N�Q�{�A��]�������̂Q�̃G���W����r�̂��̂ł��B�j
���̂Q�̃G���W�����ڎԂ́A�����x�͈�v���܂����A�O���t��̖ʐς͔{�E�����̊W�ƂȂ�܂��B
�����ԍ��F19900832
![]() 4�_
4�_
���ۂ�ۂ� �D����
�ǂ���2�Ԃ��ׂ悤�Ƃ��Ă���̃C���[�W���Ⴄ�悤�ł��ˁB
�@1)�@�F�M���䁁1.5�A�ԁF�M���䁁3
�@2)�@�F1000rpm�A�ԁF2000rpm�A�܂蓯���ԑ��ŁA��푖�s���Ă���B(�A�N�Z���S�J�ł͂Ȃ�)
�@3)�@�����ɃA�N�Z���S�J
�@4)�@2�ԂƂ�30PS���A�����Ďԑ��̏㏸�Ƌ��ɏo�͂��������Ă����B
�@5)�@�A�N�Z���S�J�̂܂܁A�F1500rpm�A�ԁF3000rpm�A(�܂�A�ŏ���1.5�{�̎ԑ�)�ɁA���B�B
�@6)�@3)�`5)�Ɋ|���������Ԃ͂ǂ��炪�Z���̂��H
�Ƃ����A������(���ԉ����Ƃ��A���������̃C���[�W)�̔�r�ł��B
�G���W���o�́��쓮�֏o�͂ł�����A�쓮�ւ�����A�쓮�։�]��×�쓮�փg���N�́A
3)�`5)�̊Ԃ̂ǂ��ŐƐԂ��r���Ă������ł��B
���̂Ƃ��A�^�C���͓����ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł����H�@�Ɛ\���Ă���̂ł��B
�������܂����ł��傤���H
���m�n����
�x�X�̂�����A���肪�Ƃ��������܂��B
�����ԍ��F19900857
![]() 0�_
0�_
Lesson3
���Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B
���m�n����
���܂��A�G���W���o�͂ƋL�ڂ��܂������A�G���W������^�C���܂ł̑������Öق̓��ɖ������Ă܂��̂ŁA�^�C���o�͂������l�ƂȂ�܂��B
���̈Ⴂ���d�v����B
�������|���āA�^�C�����̃g���N���グ���Ƃ���ŁA���̕��^�C���̉�]�����Ȃ��Ȃ邾���̘b�����B
���ǁA�R�Ď��ł̔����ȏ�̃G�l���M�[�͐����Ȃ��̂�����A�G���W�����A�^�C�����ƕ����ĈႢ���L��ƍl���邩��ԈႤ����B
�����ԍ��F19901691
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�����ǁA�R�Ď��ł̔����ȏ�̃G�l���M�[�͐����Ȃ��̂�����A�G���W�����A�^�C�����ƕ����ĈႢ���L��ƍl���邩��ԈႤ����B
�G���W���o�́��^�C���̏o�́@�ƁA���Ȃ��ȊO�S���̕��X������������Ă���܂����E�E�E�B
�����ԍ��F19901726
![]() 0�_
0�_
���݂ɁA�ǂ����Ă������ɉ�]�����g�������̂Ȃ�A�c���͂��̉�]���̎��ɐi�ދ���������������B
��]����1000��]/���i������A�O�̂��߁j������A1000��]�ɗv���鎞�Ԃ�1���ƌ��܂��Ă��邩��A1000��1���Ƃ��Ċ���Ε������o�邵�A���̍���1000��]�Ŋ��Z�������Ă��Ή����x�͋��߂鎖���\����B
���R�A���ԓ�����ɐi�ދ����������������͗ǂ��Ɛ�����B
�����ԍ��F19901740
![]() 0�_
0�_
���O�[�X350����
���Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B
����B
�����ԍ��F19901746
![]() 0�_
0�_
Lesson1
��{�I�ɎԂ́A�R�Ď��ł̔����͂𐄐i�͂Ƃ��Ă���B
���̔����͂ɂ��N�����N�̃��[�����g���g���N�Ƃ��ĕ\������Ă���B
������A�����@�A�M�A����ă^�C������]�����Ă���B
�e���ł̑���������A����́��Ō����B
�����łȂ���A�G�l���M�[�ۑ��̖@���ɔ����Ă��܂��B
�����B
����B
�����ԍ��F19901750
![]() 0�_
0�_
���ǁA�����͔n�͂ł͌��܂�Ȃ��ƌ����������B
�����ԍ��F19901755
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�Ƃ��Ƃ�A�e�R�̌������Ȃ��邨����ł��ˁH
���ƁAA or �a�͂ǂ���ł��傤���H
�����ԍ��F19901809
![]() 0�_
0�_
�Ⴆ�A��n�͓��m�̉��������Ŕn�͂����������ǂ��L�^���o��ꍇ�����邪�A����́A�r���ʼn������I����Ă��܂��A�o���ō����ɒB�����ꍇ�ɋN���邱�Ƃ���B
0�`100����/���͍��g���N�̕��������A0�`400���ł͍��n�͂̕����ǂ��ƌ����̂����̈�Ⴞ���B
�����ƌ����̂Ȃ�A�ō����ɒB������ɑ��������͍��������̂�������O�����B
�u���x�͔n�͂Ō��܂�B�v
�����B
�����ԍ��F19901815
![]() 0�_
0�_
���Ƃ��Ƃ�A�e�R�̌������Ȃ��邨����ł��ˁH
Lesson2
�x�_��蓯�������̃V�[�\�[�ɓ����̏d�̐l�����Βނ荇���B
�Е��̒[�ɑ̏d�������̐l���ڂ��Ēނ荇�킹��ɂ͑̏d�����̐l���������x�_���2�{�̒����Ƃ���Ηǂ��B
���ꂪ�Ă��̌����B
�����Ēނ荇�������G�l���M�[�ۑ��̖@���ɂ���ďؖ�����Ă���B
�e���̃��X������A�G���W�����ƃ^�C�����̃G�l���M�[�͓���ɂȂ�B
����B
�����ԍ��F19901822
![]() 0�_
0�_
���܂��A�G���W���o�͂ƋL�ڂ��܂������A�G���W������^�C���܂ł̑������Öق̓��ɖ������Ă܂��̂ŁA�^�C���o�͂������l�ƂȂ�܂��B
�����m�n����
����B
�����ԍ��F19901827
![]() 0�_
0�_
Lesson-1
�����x�͂���/��2�A��/��2�����B
���x�����ԂŊ���Ȃ�������A�����x�ł͖��������B
�����ԍ��F19901847
![]() 0�_
0�_
��A�G
�G���W����]��=1000rpm�A�G���W���̃g���N=10kgm�@(�o�́�14PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm
B�G
�G���W����]��=3000rpm�A�G���W���̃g���N=5kgm�@(�o�́�21PS)�A�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=3
�܂�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=15kgm
�o�͂������a�̕����A�����ԑ��ł͋쓮�͂������Ȃ�܂��B(�ǂ̑��x��z�肵�Ă��A���R�����ł��B)
�Ԃ����̂́A�G���W���̃g���N��T/M�ŕω��������쓮�͂ł��B�G���W��������������g���N���̂��̂ł͂���܂���B
�M�A�Ō����̂Ȃ�A2���A4�����x�̌Œ�ł̘b����B
�������ǂ��̂�2���Ɍ��܂��Ă��邸��B
���݂ɁA�`��������]�ނ̂ł���A�V�t�g�_�E������̂��킸��B
���R�`���������ǂ��Ɍ��܂��Ă��邾���B
�����ԍ��F19901900
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
�����R�`���������ǂ��Ɍ��܂��Ă��邾���B
�^�C�����͂����Ȃ��`�̕����������ǂ��̂ł��ˁH
���̗��R�����������������B
�V�t�g�_�E�����ċ쓮�͂𑝂₷����A�ƌ����̂Ȃ�A�a�����̕��V�t�g�_�E�����܂���B
�����A���Ƃ��M�����������烀���A�Ƃ��w���Ȍ�����͂Ȃ��ł���B
�����ԍ��F19901969
![]() 1�_
1�_
�����t�g�^�[������
�c�O
A�̓{���S�f�B�[�[���AB�̓X�|�[�c�o�C�N�ł�����
�����ԍ��F19902064
![]() 0�_
0�_
���V�t�g�_�E�����ċ쓮�͂𑝂₷����A�ƌ����̂Ȃ�A�a�����̕��V�t�g�_�E�����܂���B
�����A���Ƃ��M�����������烀���A�Ƃ��w���Ȍ�����͂Ȃ��ł���B
�a�͉����܂ŗ��Ƃ����炩�H
0.5���A005���A0.0001���H
�����Ƃ����ԂɃg���N���g�����Ă��܂�����B
���������ۂ��Ă��鑀������Ă����āA�����������ƌ������Ă��H����B
�����̍�������4���Œ�ł��邸�炩�H
�����\�Ԃ͕ʂƂ��āA����2���܂ŗ��Ƃ��ĉ��������č������邸��B
�M�A��3�A������������1���ł��������炢�̃M�A�䂸��A����ŌŒ�Ȃ��Ȃ��č����ɍ�������ł��Ȃ�����B
���I�ȏ�ʂ�z�肵�Ă����āA����ňႤ�ƌ����Ă��A������0�����B
�X����������������Ǝv�������ɃV�t�g�_�E�������Ă���B
�����ԍ��F19902074
![]() 0�_
0�_
�����t�g�^�[������
���a�͉����܂ŗ��Ƃ����炩�H
�`�Ɠ����ԑ��܂łł��B
�������̍�������4���Œ�ł��邸�炩�H
�Ȃ��A�����ō��������̘b���o�Ă���̂ł��傤�H
���������A�����̎Ԃł́A�R��A�����A�ϋv���A�������A�R�X�g�E�E�E�E���낢��Ȑ�����܂��B
���ł��̂ŁA�G���W������������g���N�̑召���ڈ��ƂȂ�ꍇ�u���v���X����܂��B
���A�O�̃X���Łu���������̘b�v�Ƃ���������Ă����̂́A���Ȃ���kakkurakin ����ł���B
�����ԍ��F19902126
![]() 3�_
3�_
�����ɘb�����B
�A�N�Z�����ݍ��u�Ԃ̗]��g���N�̂łȂ����B
4��1000��]�ʼn�����]�ꍇ�ɃV�t�g�_�E�����Ȃ��Ȃ�Ĕ��ȊO�̉����ł��Ȃ����A�M�A��3��1�`2�����x�Ȃ�V�t�g�_�E�����Ă�1�i�����x�A���ɃM�A��4�Ƃ���A4000��]���x�ɐ����Ă��܂��A����4000��]�ʂ��ő�g���N�Ȃ̂̂ŁA�V�t�g�_�E�����Ă��A������2���ɃV�t�g�A�b�v���邵���Ȃ�����B
�a�̂ǂ����������ǂ����炩�H
�����ԍ��F19902134
![]() 1�_
1�_
�c�O�A�ԏd�͓������āA�˂����݂��疳�������G�G
�ǂ����{�X���ł͌������ƂȂ�܂��B���߂āA�����Ȃǂ̊�{��`�����ł��s���Ă͂������ł����H
�����ԍ��F19902158
![]() 1�_
1�_
�G�A����̋�_�̗ނ̘b�łȂȂ������B
������������ł���O�ɂ���Ȃ�Ȃ������B
��������̂ɁA�V�t�g�`�F���W���Ȃ��A�M�A��͔��ȂقǍ��߂�Ȃ�Ĕn���Șb�ȂȂ�����B
�������Ɍ����A�^�C���Ƃ��h���C�u�V���t�g�Ƃ��̉�]�n�̊������[�����g���v�Z���A�������ʂɊ��Z������Ŏԏd�ɉ����Ȃ���Ȃ�܂��A�܂��傫�Ȍ덷�ɂ͂Ȃ�܂���B
�������ɂ͉�]�n�������[�����g�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��̕��@�Ɠ����ł��B
���X�A���������̐����ׂ̈ɁA�����̈ꕔ���Ȃ��ƌ����̂͗L�肾���A�����ɗL��Ȃ���z�肵�Ă�����͔F�߂��Ȃ����B
�����ԍ��F19902181
![]() 1�_
1�_
�����t�g�^�[������
���a�̂ǂ����������ǂ����炩�H
�`�Ɠ����ԑ��̎��ɁA�쓮�͂������o���邩��ł��B
�L�i�ϑ��ŗ����ł��Ȃ��Ȃ�ACVT�Ȃ�C���[�W���₷���Ǝv���܂���B
���G�A����̋�_�̗ނ̘b�łȂȂ������B
���Ȃ����h���s���\�Ȑ��h�����������Ȃ� or �Ӗ�������Ȃ��̂ł��傤���H
�����ɕ`����Ă���̂́A�G�Ȃł͂���܂���B
�����ԍ��F19902237
![]() 1�_
1�_
�ݒ�����𗝉����Ă���́H�H�H�@�ǂ���ŋc�_���Ă���́H�H
�ŏ��̐ݒ�́A19872641
A�ԁF�G���W������쓮�ւ܂ł̃M����=1�A�쓮�ւ̉�]��=1000rpm�A�쓮�ւ̃g���N=10kgm
����Ȃ�A�ǂ���̉������ǂ����͖��炩�B
�����ǁA19888718�ŁA�O�[�X����̐ݒ�́A�M����P�D�T
���̏ꍇ�A��r���Ă���ݒ��]����Ȃ瓯�������̃G���W���Ȃ̂ŁA�����͓����͂��B
�`�B���X�͓����Ƃ��āB
�ŁA�c�_�́A�ݒ��]�������̃g���N�������l�����āA��ʓI�ɁA����]�^�G���W���L���ƌ����Ă���́H�H
�ݒ��]��ł̃G���W���o�͓͂����ŁA�g���N���������ƃf�t�̃M�A��݈̂قȂ��r���c�_�H�H
�J���Ⴂ��A�ݒ�����𐳂����������Ă��Ȃ��̂͂����܂ւ�ŁA�A�A�A�A�B
�����ԍ��F19902251
![]() 1�_
1�_
�������v����
�]�T���Ȃ��Đ\����Ȃ�����E
�\���Ă�������A�����N������Ζ��炩�Ȏ������ǁA���N�ɂ킽��M���Ă������Ƃ��̂Ă���Ȃ����̂���B
���܂�A�u�ō��o�́v�Ƃ̓N���}�̑����������w�W�ł���A�u�ő�g���N�v�̓N���}�̉����́A�Ƃ�킯�d�ʂ̂����ރN���}�����S��~��Ԃ��������Ԃɂ����Ă������߂̒�́i���G���W���o�͎��̉�]�́j�������w�W�ł�����̂ł��B
�����i�`�e
���G���W���o�͂ƋL�ڂ��܂������A�G���W������^�C���܂ł̑������Öق̓��ɖ������Ă܂��̂ŁA�^�C���o�͂������l�ƂȂ�܂��B
�����m�n����
���炾���������Ă��鎖����Ȃ�����B
�ȏ�
�����ԍ��F19902257
![]() 1�_
1�_
�����Ȃ����h���s���\�Ȑ��h�����������Ȃ� or �Ӗ�������Ȃ��̂ł��傤���H
�����ɕ`����Ă���̂́A�G�Ȃł͂���܂���B
������A���s�Ȑ���ے肵�ĂȂ�����A���̐ݒ肪���ƌ����Ă邸��B
�G�Ƃ͂��������ݒ�̂��Ƃ����B
�����ԍ��F19902266
![]() 1�_
1�_
�ꕔ�̗�O�������A�����̓g���N�ɂ�茈�肳��A�n�͂͑��x��\���w�W���ƌ��������͂����肵������B
�����͔n�͂Ō��܂�Ƃ����̂͗������A�l�b�g�̃f�}����B
�����ԍ��F19902283
![]() 1�_
1�_
���������A200�ł��B
���M���X�ɉ����̓g���N���A�����Ă�����ɘf�킳�ꂽ���͂��Ȃ��悤�ŁA���S���܂����B
(�{�l�͖����ɁA�������낢������������Ă�����悤�ł����B)
�����ꌏ�A����オ�������e�ɂ��܂��Ă��A
�m�n�����[19900832]�ŁA���_���o���Ǝv���Ă���܂��B
�Ō�ɁA
�����t�g�^�[������
���G���W���o�͂ƋL�ڂ��܂������A�G���W������^�C���܂ł̑������Öق̓��ɖ������Ă܂��̂ŁA�^�C���o�͂������l�ƂȂ�܂��B
�������m�n����
����Ɉ��p����Ă��܂����A
�����ƁA�G���W���o�́��^�C���o�́@�Ə�����Ă��܂���B
�G���W���g���N���^�C���g���N�@�Ƃ͂ǂ��ɂ������Ă܂����B
�����ԍ��F19902284
![]() 3�_
3�_
���̃X���b�h�ɏ������܂�Ă���L�[���[�h
�u�����ԁi�{�́j�v�̐V���N�`�R�~
| ���e�E�^�C�g�� | �ԐM�� | �ŏI���e���� |
|---|---|---|
| 0 | 2025/12/26 14:40:54 | |
| 1 | 2025/12/26 13:41:51 | |
| 4 | 2025/12/26 14:49:17 | |
| 11 | 2025/12/26 14:47:59 | |
| 6 | 2025/12/26 10:40:53 | |
| 2 | 2025/12/26 14:35:10 | |
| 4 | 2025/12/26 10:12:17 | |
| 5 | 2025/12/26 6:35:59 | |
| 6 | 2025/12/25 22:24:50 | |
| 1 | 2025/12/26 1:36:52 |
�N�`�R�~�f������
�V���s�b�N�A�b�v���X�g
-
�yMy�R���N�V�����z���C���A�b�v�O���[�h�ŏI�e
-
�yMy�R���N�V�����z����p�\�R��
-
�yMy�R���N�V�����zSUBPC 2025 WHITE
-
�y�~�������̃��X�g�za
-
�y�������߃��X�g�z���N�̂����ɂ���őg�ߓI�Ȏ���Q�[�~���OPC��
���i.com�}�K�W��
���ڃg�s�b�N�X
- �t���e���r�̂�������11�I�I �l�C���[�J�[�̍��掿���f���⍂�R�X�p���f�������I�y2026�N1���z

�t���e���r�E�L�@EL�e���r
- iPad�̂������߃��f���I Pro�AAir�A����Amini�̈Ⴂ�ƑI�ѕ���O�����y2025�N12���z

�^�u���b�gPC
- �g�уL�����A�̃N���W�b�g�J�[�h���r�I �������߂̍��Ҍ��J�[�h���Љ�y2025�N12���z

�N���W�b�g�J�[�h
�i�����ԁj
�����ԁi�{�́j
�i�ŋ߂P�N�ȓ��̓��[�j